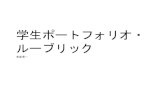ライティングラボの活用ƒ©イティングラボの... · 今日学ぶこと 1. 文章をよりよくするための方法としてルーブリックを活用してみよう!
「より良い授業を目指して」l4015/dcmt/pr5.pdf「より良い教育」は教員にとって永遠のテーマである。入学...
Transcript of 「より良い授業を目指して」l4015/dcmt/pr5.pdf「より良い教育」は教員にとって永遠のテーマである。入学...
「より良い授業を目指して」 「より良い授業を目指して」 《目次》 ●「授業改善のための討論会」特集にあたって ●より良い授業を目指して ●授業改善の第一歩
《目次》 ●「授業改善のための討論会」特集にあたって ●より良い授業を目指して ●授業改善の第一歩
特 集
「より良い教育」は教員にとって永遠のテーマである。入学
してくる学生の資質も年々変化している。そのような学生に
対応するために教育も柔軟に変容させていくことが求められ
る。そのための1つのよりどころは「学生による授業アンケー
ト」である。平成12年度に、いくつかのアンケート項目を対
象に、学生の評価が高かった教員による討論会を開催したと
ころ、「大変参考になった」という声が多かった。特に本学の
教員になって年数の浅い教員に好評であった。そこで今年度、
同様な企画による討論会を再度開催することになった。今回
選ばれた教員たちの授業に対する取り組みも前回同様興味深
く、参考になるものが多かった。学生との対話を心がける、
配布資料をカラー印刷の利点を生かし中身を色分けする、製
品企画やマーケッティングの手法を取り入れる、視聴覚機器
を活用する、自前の大きな声を利用する、など各自授業を理
解させるための試みが紹介された。この「教育開発センタ
ー・ニュース」は今回の討論会でパネラーになられた教員の
特集である。今後の授業改善に役立たせていただけたら幸い
である。
2 Center News No. 5
「授業改善のための討論会」特集にあたって
教育開発センター 所長
石 井 博 章
●Ishii hiroaki
「よい授業をする」、この言葉は教員にとって永遠の課題かもしれない。毎年変わる学生に接し
「昨年はうまくいったけど今年はいま少し」とか「昨年まで学生が分かりづらかったところに、
たとえ話を入れてみたら理解してくれた」等、授業の度ごとに様々な感想を教員はもつものであ
る。同時に「どんな授業がよい授業なのだろうか」という意識を多くの教員は持っているのでは
ないだろうか。科目により、受講生の数により、教室の形により授業の進め方は異なるので「こ
れがベストの授業だ」といったものはないのであろう。
小学校から高等学校までの教員になるためには教育実習が義務付けられている。しかし、大学
教員にはそのような経験がない。10年以上前までは、その必要が無かったというのが正しいので
あろう。どんな授業をしても学生がなんとかついて来てくれるであろうと思い、実際そのとおり
であった。しかし、その後の進学率上昇、入学方法の多様化、高校教育内容の多様化等と共に
様々なバックグランドを持つ学生が入学するようになった。大学のユニバーサル化(進学率が
50%以上)と共に、これまでと同じ教育方法では学生の理解が進まなくなってきている。教員の
戸惑いも生じている。この戸惑いを解消する方法はないものであろうか。もっと良い授業方法は
ないものであろうか。
教育開発センターでは毎年実施している「学生による授業アンケート」結果をもとに討論会
「より良い授業をめざして」を平成16年9月に開催した。討論会で話題を提供していただく先生と
授業アンケート項目(1.先生の声は聞こえましたか 2.黒板の字はよく読めましたか 3.先生は
学生の理解度を確かめながら授業を進めていたと思いますか 4.説明の仕方は分かりやすかった
ですか 5.OHPやビデオ、パワーポイント等の視聴覚機器は授業の理解に役立ちましたか 6.プリ
ント等の配布資料は授業に役立ちましたか 7.授業の目標は明確でしたか 8.先生の授業の準備
は良く出来ていたとおもいますか 9.授業内容は理解できましたか 10.授業内容に刺激を受け
たり、新たな興味がわいてきましたか 11.総合的に判断して、この授業に満足しましたか)の
結果から特徴ある授業をされている方を学部、学科、年齢等を考慮して次ページ以下に示す6名
の先生にお願いした。討論会では「自分の授業の進め方、工夫している点等」をお話いただいた
後、参加者を交えて意見交換を行った。
今回のセンターニュース特集は,その時、話題を提供していただいた先生方に当日話された内
容を原稿にしていただいたものである。自分の授業をより良いものにするための参考になれば幸
いである。
3Center News No. 5
健康科学論授業は、知識・情報の教授ととも
に問題発見・問題解決学習を重視して授業を実
施しています。授業形態については、多様化し
た授業形態を取り入れています。1つは、一方的
な講義中心の授業ばかりでなく実習授業を組み
入れ、13回授業の中で2~3回は教室から離れ体
育館・トレーニング場において実習を行ってい
ます。実習の内容は学生自身の「体脂肪率はど
のくらいあるのだろう?」「健康との関係は?」
という事で、学生に問題提起をして測定を実施
し、そして測定結果から体脂肪率を出し評価を
行い、学生自身が健康とのかかわりについて考
察することを学習させています。学生の反応は
良く、友達とコミュニケーションを取りながら
検者になったり被験者になったりして楽しく実
習しています。
2つ目は視聴覚機器を利用した授業です。授業
のスタイルもプリント・板書・講義も大切です
が、現代の学生は情報の時代そして映像の時代
に育ってきている訳ですから、映像を通しての
情報伝達の方が文字を通しての伝達より効果が
ある場合がありますので、講義内容によっては
ビデオを利用し授業(エイズ)を実施していま
す。
3つ目は、授業時間中において、授業コメント
とか小レポートを書かせています。これらにつ
いては、毎回の授業で実施したいのですが、現
在は2回~3回で1回の割合で授業コメントとか
講義内容について小レポートを書かせています。
これらは、私自身授業に対しての学生の反応を
認識するとともに授業内容の理解度を確認し、
今後の授業に生かしています。
次に授業の取り組み方についてですが、私自
身この「健康科学論」というのは学生が生涯の
健康を自分自身で考え、実践する「健康学」を
学ばせることを目標としています。この授業を
より良い授業にする為には、まず学生に対して
いかに「学習意欲」を刺激し、そして「学習意
欲を持続」させる為には「動機づけ」が非常に
大事になってくる訳です。よって、授業の最初
は動機づけにポイントを置き、健康科学論の必
要性等を説明し理解を求めています。そして、
学生とのキャッチボール。これらは非常に大切
だと考えるのですが、なにしろ相手がいること
で学生がその気にならないと、うまくキャッチ
ボールができません。投げるボールも最初は優
しいボール(やさし講義)を投げることを意識
し、段階をおって難しいボールを投げる様心が
けています。具体的には、一方通行にならない
様、学生に質問を投げかけたり、また実習の時
は私の方から積極的に学生の中に飛び込んでい
くよう努力しています。学生は嫌がります
が・・・
以上の結果、私自身授業のさまざまな目標を
効果的に実現する為には、これまでの形式にと
らわれることなく、多様化した取り組みが必要
であると思われる。また、授業の取り組み方に
ついても、一方的な教授にとどまる事のないよ
う、留意している。
4 Center News No. 5
「総合評価」「刺激・興味」で評価が高い
一般科 教授
泉 川 喬 一 ●Izumikawa kyouichi
健康科学論
今回アンケート調査を実施したのは、分類Ⅲ
の必修科目で、一度単位を落とした学生のため
に、正規の開講時期(1年後期)から半年遅れで開
講している授業でした。受講者約100名全員が
再履修者で、学生の方は、今回は何としても合
格したいという気持ちで臨んでいただろうし、
こちらとしても全員に合格点を取らせたいとい
う思いで授業を行いました。双方の気持ちがう
まくかみ合ったのか、アンケート結果はこれま
で私が実施した他の科目と比較して各項目で高
い評価を得ることができました。
本科目は演習のコマが付いていないので、ほ
ぼ毎回、講義時間の後半の20分程を使って演習
を行いました。A4用紙1枚に2、3問を用意し、
時間内に終わらなかった場合は宿題とし、提出
させ、これらは演習点として評価の対象としま
した。演習点と試験との評価の割合は3:7です。
また、第1回目の授業のとき合格するための指
針を示しますが、「全回出席して、全回きちんと
ノートを取り、全回演習問題を自分の力でやっ
て提出すれば、必ず試験で合格点が取れる。」と
話しました。「それでも単位を落とした場合は、
全講義分のノートとチェック済みの全ての演習
問題を持って抗議に来て下さい。」とも言いまし
た。幸いにも、前期成績が配布されてからかな
り経ちますが、抗議に来た学生はいません。私
が担当している他の科目で、残念ながら、上記
を実行しても必ず単位を落とす学生が出てくる
科目もあります。しかし、この科目に限っては、
電子工学の基礎ということで、これまでの学生
個人の知識の差が影響しにくく、試験で難しい
計算を必要としないため、また、過去何年かの
実績から見ても、大丈夫だろうと予想がつきま
した。必修科目を落として不安だった学生は、
多分これで安心して授業を受けることができた
と思います。
5Center News No. 5
特集●より良い授業をめざして
「内容の理解」「黒板の文字」で評価が高い
電気電子工学科 教授
奥 村 万規子 ●Okumura makiko
基礎電子工学Ⅰ
授業のやり方としては、第2回目以降の授業で、
座席を指定しました。講義は前の方で聞きたい
という学生もいるので、第1回目の授業で前列
を希望する学生を尋ねたところ、約1割にあた
る10名が前列を希望しました。座席指定の第1
の目的は演習問題の返却を短時間で行うためで
した。私は以前他の科目で自由に座らせた140
名程のクラスで、毎回演習問題を返却するのに
時間がかかり私語が多くなり授業の雰囲気を損
ねる失敗をしたことがありました。その反省か
ら来たものです。返却は次の回の演習問題実施
中に行いますが、予め席順に並べておけば2、3
分で済み、残りの時間は学生の質問に答えるこ
とができました。自分の学生時代を思えば、大
学の授業は自由に座って聞くのが当たり前です
から、高校生じゃあるまいしと、多少違和感を
覚えたのですが、同じ学科の先生が座席を指定
していることを聞き、今の学生にとっては、そ
れほど違和感は無いのかも知れないと思い実行
しました。席を指定したことによる利点は既に
実施している先生から伺っていましたが、私も
幾つか実感することができました。学生がいつ
も同じ席に座っていれば、顔は覚えられますし、
出欠状況を含めその学生がどんな態度で授業を
受けているかがわかります。この様な情報は学
生に質問をしたり、注意するときに役に立ちま
す。また、学生に緊張感を与えることができま
した。
学生アンケートは現在、1科目を教員が選んで
実施しますが、公開され冊子にもなるので、私
はどうしても「なるべく高得点が取れそうな科
目」で実施してしまいます。しかし、昨年の後
期科目には「高得点が取れそうな科目」が無く、
結果はやはり殆どの項目で平均点以下という厳
しいものでした。
今年度実施した科目をA、昨年度実施した科
目をBとして、2科目を比較すると表のようにな
ります。科目Aは「基礎電子工学Ⅰ」で、内容
は電子デバイスのほんのさわりと論理回路の基
礎です。科目Bは「アナログ電子回路」で、2年
後期の選択必修科目で、ほぼ全員が履修します
が、1年次の幾つかの専門基礎科目をベースとし
た応用科目で学生にとっては少し難しい内容で
す。科目Bは、いつも試験や合格率が悪いので、
演習の採点、添削などを丁寧に行うなど、新し
い試みをしたのですが、学生の評価は得られま
せんでした。反省点としては、テキストが難し
すぎた、席を自由とし私語を注意しきれなかっ
たなどがありました。現在、後期の授業が始ま
りましたが、今年度は新しいテキストとパワー
ポイントを使って、昨年度とはガラリと変わっ
た授業を行っています。
私は科目Bのような科目を沢山抱えていて、
このような科目を如何に学生に分かり易く説明
するかが大きな課題です。少なくともやる気が
あって全回出席した学生は合格できるような授
業を目指して、今後も試行錯誤でやっていこう
と思います。
6 Center News No. 5
科目 科目 A 科目 B
必選別 分類Ⅲ・必修 分類Ⅲ・選択必修
履修者 107名 144名
内容 基礎科目 応用科目
難易度 比較的簡単 比較的難しい
試験平均点 69.0点 54.7点
仕事の補助 TA:1名 なし
学生評価 良かった 悪かった
(表)科目A, Bの比較
本講義は1年生の選択必修科目です。高校で
化学をほとんどやっていない学生も少し含んで
います。また、演習の時間を講義後に併設し、
内容の理解に重点をおいた授業となっています。
第一回の授業では、授業方針を説明し、化学の
基礎的事項から説明します。有機化学の共通言
語(英語でいえば、アルファベットとスペルで
しょうか)である化学式、構造式を理解しても
らうことが、必要不可欠です。しかし、これが
なかなか、難しい。これができるようにならな
いと、学生との間の会話が成り立たないという
ことになります。そこで、できる限り、理解し
やすいように、配布資料を工夫しました。でき
る限り見やすい資料にするべく、化学構造式を
描くソフトフェアであるChemDrawを利用し
て、資料を作成しました。有機化学では、結合
の切断、連結など物質が変化することを扱いま
す。わずかな違いを見分ける必要があるので、
どこがどのように変わったか、わかりやすいよ
うに、変わった部分をカラーで表示するように
しました。配布資料として、カラー印刷したも
のを配ることに多少ためらいもありましたが、1
年生ということもあり、少しでもわかりやすい
ものにすべくカラー版のプリントを配っていま
す。学生が、「カラーだ!」と言っていたことが
印象として残っています。配布資料の評価が高
かった理由は、カラー印刷したことでわかりや
すいプリントになったと言うことかもしれません。
わかりやすいプリントと評価されたので、授
業の理解に配付資料が役にたったということな
のでしょうが、本来の目標である内容の理解が
高い評価を得られず、逆に、本授業の評価項目
の中では最も低い評価値となってしまいました。
合格率も、半分以下となっています。併設した
演習の授業では、学生の皆さんの出来が良かっ
たので、理解できていると勘違いして授業を進
めていました。演習の授業では、教科書やノー
トを参考にしたり、多少周りの学生と相談して
もよいことにしていたので、理解しながら演習
問題をやるというよりは、教科書を見ながら、
機械的にやっていただけだったようです。でき
た学生に答えを聞いていただけで、理解してい
なかったということかもしれません。本試験で
は、持ち込み不可なため、授業内容が身につい
ていなければ点は取れません。この点が、学生
にしっかりと伝わっていなかったようです。覚
えなければならない部分と類推できる部分の違
いがわからず、すべてを覚えようとするため、
知識が断片化してしまっています。これらの点
を改善すべく努力したいと思います。また、こ
の授業はJABEE対応の科目であり、後期の有機
化学Ⅱに続ける必要があるため、内容が多くな
り、学生には負担と感じる面もあったと思いま
す。入ってきたばかりの多様な学生に対してど
のように対応すべきか、難しいところです。反
省が多い授業評価でしたが、いろいろ工夫して
いきたいと思います。
7Center News No. 5
特集●より良い授業をめざして
「配布資料」で評価が高い
応用化学科 助教授
野 田 毅 ●Noda tuyoshi
有機化学ⅠA
この授業の目的は、マーケティングとは営業
やものを売る立場の人たちのためではなく、む
しろものを作る立場にいる技術者がしっかり把
握していなければならない領域であり、その重
要性と効果の認識を植え付けることにあります。
従って、特に技術者の視点に立った内容に力点
を置いて進めております。
この授業を通して学生達に教えたいことは、
第一にプロダクトを、技術オリエンテッドにな
らずに多角的な視野で捉える能力を身に付けて
もらいたいといことです。第二として、自分の
目で問題を捉え、自分の頭で考え、自分独自の
答を導き出す習慣を付けさせることにあります。
すなわち、計算式のように決められた正解ばか
りではなく、自分で答を発見するものだという
意識を持たせること。そして第三に培ってもら
いたいこととして、自分のコンセプトを正確に
相手に伝えるプレゼンテーション能力です。も
のを作る、特に工業製品の場合は、自分一人だ
けでは事は進められません。必ず何らかの組織
があるはずです。そのためには第三者に自分の
考えを的確に伝える能力が社会に出て絶対に必
要になります。
この授業は演習を取り混ぜながら講義を中心
に行なっており、講義は凡そ7割程度になりま
す。指定の教科書は使用せずにオリジナルの講
義ノートを毎回配布しています。講義の場合は
どうしても眠くなりがちになってしまいますの
で、OHPを使用しビジュアルを多く活用するこ
とで、判り易く興味を持たせる工夫をするよう
に努めております。
特にこの授業の性格からすると、最近の世の
中の出来事や技術・製品トレンドを例にとって
話すことで興味や内容理解がより深まりますの
で、話題になった事象の成功・失敗例を含めた
実例を解説しながら進め、その要因は何かを考
えさせるようにしています。できるだけその授
業を行なう一週間の中で起こった新鮮な事象を
話題に挙げることで学生に刺激を持たせるよう
にしています。更に、私自身も長年商品開発の
現場におりましたので、そこでの体験や実例も
交えながら行なうことで、ともすると絵空事に
なりがちな内容に臨場感を持たせるように工夫
しています。現実的な話題は学生にはインパク
トが強いようで、非常に興味を持って聞いてお
ります。
ものを開発するエンジニアの基本的な姿勢と
して「誰のために、どのような条件や技術を踏
まえて、どのような目的のものを作るのか?」
すなわち、プロダクトアウトの発想ではなくマ
ーケットインの発想が重要です。そのためには、
常に人々の暮らしぶりについての深い洞察力を
持たなければなりません。ターゲットが見えな
い中で的確なものは作れないし、どんなハイテ
クな技術であってもそれは手段であって目的で
はありません。
そのために、学生には世の中の最新の動きや
トレンドをチェックするように、少なくともTV
のニュース番組くらいは見る癖をつけて欲しい
と言っています。特に、技術者を目指したいの
8 Center News No. 5
「説明の仕方」「目標の明確さ」で評価が高い
システムデザイン工学科 教授
森 勇 輔 ●Mori yuusuke
製品企画・マーケティング
ならば東京12チャンネルで毎夜放送している
「WBS」やNHKの「こどもニュース」は大変有
効な情報源になるから見るように常に宣伝して
います。
自分の嗜好に合わせるように、ものや情報選
択が自由に(身勝手に)できる時代に育った学
生は、反ってものや情報が見えなくなっている
ように強く感じます。
演習課題は、身近な事象を捉えてそこから新
しい提案をさせる形でグループ単位で実施して
います。また、演習には中間・期末試験の役割
も持たせております。
課題を解くということでは、その結果も大切
ですが、むしろどのような視点で考えたのか、
その発想やプロセスを重視しなければならない
と思います。そのために、グループの討議に加
わり木目細かいフォローや的確なヒントを与え
ることが大切です。時には楽しく、時には真剣
に、時には論理的に進めさせ、最後にプレゼン
テーションを通して達成感を味わあせるように
しています。そのためには学生が興味を引きそ
うな課題を設定することが重要です。
知識だけでは答は出ない。知恵を出さないこ
とには自分の答は見つからない。知識の詰め込
みだけではなく、それをどのように応用するか
を考えさせることが実社会に出ていかに大切か
を今知ってもらいたいということでしょうか。
演習を通して、学生には「見て、感じて、考
える」という習慣を是非身に付けてもらいたい
ということです。私はこれを「野次馬的好奇心
の大切さ」と言っておりますが、毎回の結果か
ら見ると、講義中はただ「フンフン」と聴いて
いればよかったものが、いざ演習課題になると
能動的に動く(動かざるを得ない)学生が多く見
られることに現れているように感じております。
しかし、この授業を実施して感じることは、
自分で考えることができなくなっている学生が
多いということです。判らないことは、何かマ
ニュアルのようなものに頼らないと解決できな
い習慣が身に付いてしまっている。与えられた
コースの外側のことは想像できない。創意工夫、
創造力を高めるための仕掛け作りが今後の授業
設計の大きな課題です。
最後に、この授業を通しての成果らしきもの
があるとするならば、単に技術的力量だけでは
なく、情報に対する理解力と構築力の大切さと
難しさを体感できたこと、明確な目的意識と知
的柔軟性の醸成、すなわち「クリエイティブ」
の面白さと大切さを何らかの形で知ることがで
きたのではないかと思います。そして、社会に
出て有為な仕事をやってみたいというキッカケ
の足がかりになってもらえたのであれば目的の
何割かは達成できたのではないかと思います。
9Center News No. 5
特集●より良い授業をめざして
私の場合、「声が大きい」ということで授業の
評価がよかったものですから、どうして声が大
きいのかということに関しましては、特に多く
書くことはでません。声が大きいのは地声であ
って、特にボイストレーニングしたわけではあ
りません。そこで、私なりに勝手な解釈をいた
しますと、「声が大きい」ということは、相手に
対して「聞きやすい」、「わかりやすい」という
意味が含まれていて、その結果の評価だと考え
たいと思います。本来ならばここで終わりなの
ですが、多少私が行った授業の方法などを記し
たいと思います。
アンケート対象となった授業は、「運動機能加
齢学」という講義方式の授業です。科目の目的
上、多くのデータを示すことで、加齢に伴う身
体機能の変化を学ぶことになります。私は、身
体機能をテーマごとに区分し、最近示されてい
るデータおよび私が行った測定結果などを資料
としてまとめ、学生に配布いたします。その上
で、パワーポイントを用いて配布した資料の内
容を解説し、必要事項を資料に記入させる方式
を取っています。学生へは、授業の初回にノー
トを取る重要性を伝えています。記憶は薄れる
が、記録は残るからです。
資料を説明する上で最も苦慮することは、い
かに現実感を持たせるかということです。本学
科の場合、福祉機器・用品開発のためのエンジ
ニアの育成になりますから、学生は、単に機器
開発の技術習得だけではなく、それを利用する
人間とのかかわりを理解しなければならない必
要があります。授業の内容を理解させるために
は、暗記ではなく理解型の授業でなければなら
なく、そのためには授業内容に興味を持たせる
必要があります。そのためのひとつの方法とし
て、現実的な話をする必要がありそれなりに私
も勉強しなければならないことが多かったとい
うことです。
授業内容からして、知識の押し売り的なこと
でよいとは思うのですが、実際にはそれでは学
生は興味を示さない気がします。授業では、な
るべく学生に問題(テスト問題のようなもので
はありません)を問いかけ、考えさせるように
しています。考えることが興味を持たせること
であり、理解するための第一歩と思っているか
らです。なんとなくでも良いから「多少わかっ
た」、「なるほど」と思う学生を一人でも多く増
やしていきたいと考えています。とはいうもの
の、なかなかそうはうまくはいかないものです
が。
授業の内容によっていろいろな形式の授業方
法があると思います。それでも私が考えている
のは、授業に出たことで何か知識が得られたと
学生に感じさせることができたらと考えていま
す。そう思うと、ここは知っていて欲しいとい
うところはついつい声が大きくなってしまうの
かもしれません。
10 Center News No. 5
「声の大きさ」「視聴覚機器」で評価が高い
福祉システム工学科 助教授
高 橋 勝 美 ●Takahashi katsumi
運動機能加齢学
アンケート対象科目は「計算機概論」(情報メ
ディア学科1年・前期・必修)です。この科目
は、コンピュータのハード、ソフト全体の導入
的な基礎を教える科目で、情報学部の共通科目
となっています。特に、情報メディア学科では
母体の学科である情報工学科と共通の教材を使
用して講義しています。その教材は、両学科共
通の科目主査である情報工学科の陳先生を中心
に、両学科2名、合計4名の教員が共同で作成し
ています。その教材(パワーポイント資料)を
プロジェクターで投影して講義し、また配布資
料としています。従いまして、評価が良かった
項目は私だけへの評価でなく、陳先生をはじめ
とする4名の教員に対する評価といえます。今
回、この科目をアンケート対象にしたのは私だ
けのようですので、私が代表して話題提供者と
なったようです。
共通教材を使用しても、講義の方法には各教
員の個性がでると思います。ここでは、「配布資
料」、「視聴覚機器」の話題に限定せず、私の講
義に対する姿勢・取り組みをお話しします。こ
れは、アンケートの対象となった科目だけでなく
私が担当するすべての科目に共通したことです。
まず、私の講義に対する基本方針は、「大学生の
場合、内容の理解は(学生の)自己責任」とし
ています。ここでの比喩として適切ではないか
もしれませんが、「水場へ連れて行くことは容易
だが、無理やり飲ませることは容易ではない」
とよく言われますね。この比喩を用いるとすれ
ば、静かな水場、おいしい水を用意し、その水
はおいしいことを納得させて、飲んでもらうよ
うに努めています。
講義を真剣に聴きたい学生のために、教室を
静かにしておく、つまり私語は絶対に許さない
11Center News No. 5
特集●より良い授業をめざして
「授業の準備」「配布資料」で評価が高い
情報メディア学科 教授
速 水 治 夫 ●Hayami haruo
計算機概論
12 Center News No. 5
としております。私語がでた場合は、その都度
注意しますし、なかなか収まらないときは、私
が話すのを止めます。そうすると、必ず私語は
止まります。また、現在の常識に照らし合わせ
て、教室内で帽子等のかぶり物はとってもらっ
ています。このように注意すると、この教員は
厳しい先生だなと認識されて、ある程度の緊張
感を保って授業が進むのではないかと思います。
また、説明の声がよく通るように、大教室で
はワイヤレスマイクを使いますが、その際ネッ
クホルダーを使用しております。これを使用す
るとマイクが口元の一定の距離に固定されます
ので、常に一定の音量で説明できます。また、
両手が空くというメリットもあります。
おいしい水を用意するために、授業の準備に
は充分時間をかけます。パワーポイント資料は
時間をかけて作成しますし、見直しにも時間を
かけます。他の担当科目においてですが、授業
準備の積み重ねに基づいた教科書を出版して使
用しております。本学のレベルにあわせた教科
書ですので学生の評判も良いようです。同程度
のレベルの大学は多いようですので、2冊の教科
書はほぼ毎年増刷されております。
学期の始まりにはその科目の位置づけ、重要
性を充分に説明しています。また、各章や節の
始まりにおきましては、対象技術の必要性・意
義を話すようにしています。つまり、水がおい
しいことを説明しているつもりです。
授業中の話し方として、壁に向かって話すご
とくではなく、しっかり聴いてくれるグループ
に語りかけるようにしています。うなずいて欲
しいときにうなずいてくれる学生がいることは
うれしいものです。また、質問には丁寧に回答
しています。つまり、次に話します「挨拶」も
含めてですが、対面授業として双方向のコミュ
ニケーションが働くようにしているつもりです。
以上、学生に対して厳しい面を強調しました
が、実は学生に対してフレンドリーに接するよ
うにしているつもりです(あくまでも、私の
「つもり」であって、学生がどう受け取ってくれ
ているかは定かではありません?)その具体策
の一つとして、授業の開始時に、「おはようござ
います」と挨拶しています。しかも、私がつぶ
やくだけではなく、教室の大多数が「おはよう
ございます」と応えてくれるまで、挨拶を繰り
返します。(応えてくれることを期待して、お茶
目な仕草もします。)学期の始めに繰り返しをす
れば、次回からはすぐ応えてくれるようになり
ます。なお、学生達の年代では、「おはようござ
います」はオールマイティの挨拶のようですの
で、午後の授業でもそのように挨拶しています。
そして、授業の終了時は「お疲れ様」と言って
います。
「フレンドリーな間柄で、緊張感が漂った授業」
が私の理想で、そのようになるように努めてい
るつもりです。
「授業改善」には二つの意味がある。一つは「授業内容の改善」であり、古くなった内容を更新したり、
難しい表現をより分かりやすい表現にする。また、学生に授業に対する興味を抱かせ、「もっと勉強したい」
という意欲をわかせるような内容に改善することなどである。これは科目によって内容が異なるため担当
教員の改善意欲に依存する。
もう一つは教育技術、すなわち「教え方」の改善である。「先生の声が良く聞こえる」「黒板の字が読み
やすい」「配布資料が分かりやすい」等である。これは大多数の科目に共通するものであり他の教員の教え
方が大いに参考になるし、教員が相互に意見を交換し、さらに知恵を出し合えばより良い改善が得られる。
ここでは授業において最も基本的な「教員の声の大きさ」「黒板の字の読みやすさ」について考えてみる。
この二つは授業の第一歩であり、原点であり、授業の成否がかかっていると言える。
(1)教員の声の大きさ
次の表・グラフは2003年度(後期)と2004年度(前期)に本学で実施した学生による授業アンケート設問
(1)の結果を比較したものである。
(1)先生の声(マイクを含めて)は聞こえましたか
授業時に「先生の声が聞こえる」かどうかは授業の根幹である。たとえ教室の条件が悪いにしても、教
員の声が聞こえないのでは授業内容を理解することを望むべくもない。2年間の比較においてほとんど変化
はないといってよい。
85%の学生は聞きやすいか、普通と答えている。問題はないであろう。しかし、約15%の学生が「聞きづ
らい」と答えている。先ず、ここを0%にする必要がある。考えられる改善策をいくつか挙げてみよう。
① 学生に正面から向かって話そう。学生に背を向け板書しながらしゃべる、横や下を向いてしゃべると
学生には聞きづらい。
② 教室の一番後ろの学生に「聞こえますか」とたずねてみよう。自分では大きい声を出しているつもり
でも、必ずしも学生が聞こえているとは限らない。また、最初は大きい声で話していても、いつの間
にか小さくなっていることもある。
③「聞きづらいときは聞こえませんと言ってください」と学生に言おう。学生は聞こえなくても「聞こえ
ません」とはなかなか言わない。何も言わないから聞こえていると思って授業を進めると、アンケー
ト結果で驚くことになる。
④ 声の出しづらい教員はマイクを使おう。風邪で声が出しづらい、体調が悪い、もともと声が小さいと
いう方は積極的にマイクを使う。
⑤ マイクの使い方としては授業のはじめに使い始めたら終わりまでマイクを同じ位置に保ち、途中は学
生にマイクを使っていると感じさせないよう注意する。マイクの位置がずれ声の調子が変わると学生
は集中力がきれるといわれている。マイクの位置を保つために本学では平成16年後期より首にかける
2003年
2004年
0 25 50% カテゴリ 2003年 2004年
1.非常に聞きづらい 378 3.2% 486 3.4%
2.やや聞きづらい 1396 11.7% 1670 11.7%
3.普通 4385 36.8% 5466 38.3%
4.聞きやすい 3613 30.3% 4270 29.9%
5.非常に聞きやすい 2142 18.0% 2378 16.7%
サンプル数(%ベース) 11914 100.0% 14270 100.0%
13Center News No. 5
特集●より良い授業をめざして
マイク保持器(ネックホルダー)が準備されている。
クラスのサイズによりマイクの使用はほとんど決まるといってよい。50人以下はマイクなし。100人以
上はマイクを使用する。50人から100人の間は部屋の大きさ、形によりマイクを使うかどうかを決める。
(2)黒板の字の読みやすさ
次の表・グラフも上記(1)と同じ2003年度(後期)と2004年度(前期)に本学で実施した学生による
授業アンケートの結果を比較したもので設問(2)である。
(2)黒板の字はよく読めましたか
学生にとって「授業をする先生の声が聞こえる」「先生の書いた黒板の字が読める」ことは最低限の要求
である。教育者として必ず備えておくべき必要条件である。この二つが揃わないと授業は成立しない。ア
ンケート結果は「読みやすい」が約22%に対し、「字が読みづらい」という学生が25%強いる。4人に1人
は字を読むのに苦労している。
学生は小学校以来、黒板には授業の要点が書かれている、先生はもっとも大事なことを精選して書いて
いると思っている。一方、教員は学生に「聞きながら要点を掴んでノートを取って欲しい」と望んでいな
いだろうか。教える教員は内容を熟知しておりポイントがどこか十分に知っているが、学生にとって初め
て学ぶ科目の要点を聞きながらノートにまとめるのは並大抵のことではない。学生が正確に黒板の文字を
写せば授業内容の要点の70%近くはそこにあるというのが望ましい板書であろう。「字が読みづらい」の
25%を0%にする必要がある。改善策をあげて見よう。
① 黒板には要点を楷書で書こう。要点を書くことは上記したが、文字は分かりやすく楷書で書く。崩し
字や略字、草書体は多くの学生が読めないと思ったほうが良い。うますぎる字は授業に必要はなく、
丁寧な字の方が良い。また難しい漢字は平仮名で書くか、ルビを打つ。
② 一番後ろの学生に「字は読めますか、小さくないですか」とたずねよう。いくら楷書で丁寧に書いて
も、字が小さすぎては読めない。字の大きさをどれくらいにするかは教室の大きさと学生数に由る。
50人程度の教室なら横書き黒板で7, 8行は書ける。しかし、200人以上になると4, 5行になり大きな字
が要求される。
③ 黒板、白板とチョークの色の組み合わせも考える必要がある。黒板といっても実際は濃い緑、深緑板
である。チョークの色として見やすい色、見づらい色がある。最も見やすい色がオレンジ色であり、
教室の一番後ろからでもくっきりとみえる。2番目が白と黄色であり、4番目が赤である。青と緑は非
常に見にくい。大事な事を赤で書く場合がある。ノートなどでは目立つが黒板では意外に見づらい。
白板の場合は黒、赤、青は後ろからでも同じようによく見える。
以上、授業に際し、最も基本となる「声」と「板書」についての改善点、注意点を書いた。多くの先生
方にとって、これらはこれまで実行してきたことであり当たり前のことで不必要なことであろう。しかし、
15~20%の学生はこの二点で困っているのも事実である。参考にして頂ければ幸いである。
(教育開発センター 遠山紘司)
2003年
2004年
0 25 50%
2003年
2004年
カテゴリ 2003年 2004年
1.非常に読みづらい 605 5.2% 769 5.5%
2.読みづらい 2556 21.9% 2914 20.9%
3.普通 5605 48.1% 6850 49.0%
4.かなり読みやすい 1730 14.8% 2077 14.9%
5.非常に読みやすい 847 7.3% 1050 7.5%
6.黒板は使用しなかった 307 2.6% 312 2.2%
サンプル数(%ベース) 11650 100.0% 13972 100.0%
14 Center News No. 5
15Center News No. 5
学生の授業アンケート結果から学生が変えて欲しいと望む点がわかっていても、なか
なか変わらないというのが数年の結果を並べてみると分かる。
アンケート結果からそれぞれの項目で高い評価を受けられる先生がおられる。学生に
勉強の楽しみを理解してもらえるよう、教員各自が持っている特徴を出し合い討論でき
る場をまた持ちたいものである。
編集 後記
月 日 活動6日 プレイスメントテスト実施1日1日
第1回 教育開発センター運営委員会基礎教育支援センター開所式
29日 第2回 教育開発センター運営委員会7日~8日 大学教育学会第25回大会(大阪薬科大学)
14日平成15年度工学教育連合講演会ーJABEE認定プログラムの事例紹介を中心としてー(早稲田大学)
26日 第3回 教育開発センター運営委員会7日~9日 「日本語表現」資料収集と問題点の討論(高知大学)
18日学習支援室(一般科化学)・基礎教育支援センター(化学)との懇談会学習支援室(一般科数学)・基礎教育支援センター(数学)との懇談会
22日 第1回 教育評価WG24日~25日 「学生による授業評価」事例研究会(名古屋)29日 第1回 教養教育・導入教育WG
第4回 教育開発センター運営委員会
31日
31日学習支援室(一般科英語)・基礎教育支援センター(英語)との懇談会学習支援室(一般科物理)・基礎教育支援センター(物理)との懇談会
3日~5日日本工学教育協会第51回年次大会ー変革の時代における工学教育と産学連携ー(北海道大学・工学部)
10日 第2回 教養教育・導入教育WG24日 第1回 創成教育WG25日 第5回 教育開発センター運営委員会7日 第3回 教養教育・導入教育WG22日 第1回 日本語表現WG23日 第6回 教育開発センター運営委員会5日 第2回 創成教育WG11日 第4回 教養教育・導入教育WG20日 第7回 教育開発センター運営委員会26日 第2回 日本語表現WG
29日~30日大学教育学会2003年度課題研究集会 ―大学新時代における教養教育の再考と創造―(中京女子大学)
8日 「学生による授業アンケート」実施9日 第5回 教養教育・導入教育WG
12日FD講演会「学生による授業評価は教員の教育評価に何処まで使えるか」講師:小笠原 正明教授(北海道大学高等教育機能センター)
17日17日
第3回 創成教育WG第3回 日本語表現WG
18日 第8回 教育開発センター運営委員会13日 第6回 教養教育・導入教育WG22日 第9回 教育開発センター運営委員会23日 第4回 日本語表現WG30日 第5回 日本語表現WG26日 第10回 教育開発センター運営委員会28日~29日 第9回FDフォーラム,第1回高大連携教育フォーラム(龍谷大学)18日 第11回 教育開発センター運営委員会
2月
10月
1月
3月
4月
5月
6月
7月
12月
11月
9月
教育開発センター活動記録(平成15年4月1日~平成16年3月)