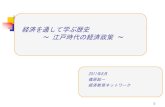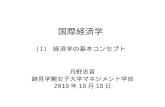循環経済ビジョン2020(概要)...2020 年5月 経済産業省 循環経済とは • 線形経済:大量生産・大量消費・大量廃棄の一方通行 ※ の経済
日本の経済成長 1945 55togo/articles/日本の経済成長1945...Musashi University Working...
Transcript of 日本の経済成長 1945 55togo/articles/日本の経済成長1945...Musashi University Working...

Musashi University Working Paper
No.17 (J-9)
日本の経済成長 1945-55年:
ガバナンス、援助、貿易、外交政策
2013年 3月
武蔵大学
東郷 賢※
<要旨>
本稿の目的は、開発経済学の分野で経済成長の要因として近年重要視されているガバナ
ンスが、日本の 1945年から 55年にかけての戦後復興において、どの程度の重要性を持っ
ていたかを検証するものである。また、ガバナンスの相対的重要性を検証するために、援
助、貿易、外交政策の重要性も併せて検討する。外交政策の重要性については、経済成長
分析において今まで殆ど検討されてきていない。しかし、本稿では重要な要因であること
が明示される。
Keywords:日本、経済成長、制度、民主化、ガバナンス、援助、外交政策、特需
※ email: [email protected]. 本研究の一部は科学研究費補助金(C No.22530282)お
よび武蔵大学総合研究所の支援を受けて行われた。ここに記して感謝いたします。

1
1. はじめに
開発経済学の分野では、経済成長の要因として、近年ガバナンスの重要性が指摘されて
いる。しかしながら、「ガバナンス(Governance. 日本語では統治と訳されることが多い)」
の定義は研究者によって異なり、具体的に「法の支配(rule of law)」であるのか、「民主主
義(Democracy)」であるのか、それとも「制度(institution)」であるのかはっきりしな
い1。
但し、「ガバナンスが良ければ、経済成長率も高くなる」という仮説自身は、開発経済学
の重要な検証仮説と考えられ、十分な研究がなされる必要があるだろう。例えば、民主主
義であると経済成長しやすいとか、法の支配が効いていると高成長になるとか、官僚制度
がしっかりしていると成長しやすいとか、具体的なケース・スタディの積み上げによって、
ガバナンスのどの要素が重要であるのか検証することが必要である2。
このような観点に立つと、日本の 1945年から 1955年にかけての戦後復興は大変興味深
いケースとなる。なぜならば、日本は 1945年から 1952年までの約 7年間、連合国軍によ
り占領されていながら経済成長を遂げ、独立回復 3年後の 1955年には戦前の経済水準まで
到達することが出来たからである。
占領時代は、連合国軍による間接統治であった。日本政府は存在していたが、連合国軍
あるいはアメリカ政府の意思が強く反映された政策が実施され、公職追放なども行われた。
外国の間接統治の下で、経済成長を達成したという事実は、ガバナンスと経済成長の関係
について重要な判断材料を提供してくれると考えられる。
ガバナンスの相対的な重要性を検証するために、成長要因としてしばしば指摘される「援
助」と「貿易」についても同時に考察していくこととする。更に、本稿では「外交政策」
の重要性も取り上げたい。
占領時の日本のように、他国の影響が如実に反映される状況では、他国の外交政策がそ
の国の将来を決めかねない。実際、連合国軍を代表する米国の占領政策は、冷戦をきっか
けに途中で大きく変化しており、この意味で当研究は大国の外交政策が小国の経済成長に
与える影響についても考察する。このような大国の外交政策は、占領という特殊な形態を
とらなくても、小国の経済パフォーマンスに現代でも日々影響を与えているのではないだ
ろうか。
1 経済成長要因としての制度に着目した既存実証研究のサーベイについては、東郷(2009)
を参考にしていただきたい。 2 クロス・カントリー・データを使った経済成長の実証研究の問題点については Togo(2011)
を参考にしていただきたい。

2
本稿では、このような視点から日本の 1945年-55年の間にどのような事実があり、経
済成長の要因として「ガバナンス」、「援助」、「貿易」、「外交政策」それぞれの相対的重要
性について分析していきたい。今回、様々な歴史に関する文献を参考としたが、文献によ
って事実の認識が異なったり、経済データの値が異なったりと、改めて歴史的事実の把握
の難しさを実感した。筆者は経済史家ではないので、重要な事実や文献が抜けていたり、
認識の誤りがあるかもしれない。読者諸兄の厳しいご批判を頂けたらと願う次第である。
2. 1945年~1955年の日本
(1) 主な出来事(Annex表1 1945-55年の出来事 参考)
1945年 7月 26日に発表されたポツダム宣言の受諾、および 9月 2日の降伏文書への調
印により、日本は連合国軍に占領されることとなった 。連合国最高司令官(Supreme
Commander for the Allied Powers, SCAP)であるマッカーサー元帥が統治を行うことにな
り、1952年 4月 28日に独立が回復されるまでの 6年 8か月の間、最高司令官の指令・勧
告に基づき日本政府が統治するという間接統治の方法がとられた。
しかし、9月 2日の時点では、直接軍政の可能性があったとされる。鈴木(1973, p.27)
によれば、参謀次長マーシャル少将より三布告の文章を渡され、公表の手続きを取ってほ
しいと言われたという。その三布告とは、①直接軍政(英語を公用語とする)、②日本の司
法権は GHQに属し、GHQの指令に違反するものは軍事裁判にかけられる、③日本円を廃
しアメリカ軍軍票を使用、の3つであった。翌 3日に重光外務大臣は急遽マッカーサー元
帥に面会を要望し、三布告の中止を要請した。結果的には、重光大臣の説得が成功し、こ
の三布告の公布は中止となったとされる。
この直接統治の可能性については、米国国務省が作成し、国務・陸・海軍三省調整委員
会(The State-War-Navy Coordinating Committee, SWNCCと略す)に提出された「初
期対日政策の基本文書(SWNCC150と呼ばれる)」の変遷を見ると、異なる解釈が可能で
ある。1945年 4月の SWNCC150では、直接統治が想定されていたものの、7月のポツダ
ム宣言を受け修正された SWNCC150/1では間接統治の意味合いが含まれ、その後大幅な修
正が加えられた SWNCC150/3では間接統治の方針が明確になったとされる。この文書は 8
月 31日の SWNCC会議には提出されているので、現実的には直接軍政の可能性は低かった
と考えられる3。
ただし、GHQ労働課長であったコーエン(Theodore Cohen)によれば、SWNCC150/4
3 国立国会図書館HP(http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/022shoshi.html)より。
SWNCC150/4も、このサイトからダウンロードできる。

3
はあくまでも指針(ガイダンス)であり、軍人のマッカーサーはこれを本気で守る気がな
かったとの意見が述べられている(コーエン 1983、p.33)。この意見を受け入れれば、9月
2日時点で、マッカーサーが日本の直接軍政を考えていても不思議ではない。
他方、同じ敗戦国ドイツでは連合国軍による直接軍政が布かれたわけだが、連合国軍の
エコノミストであったエレノア・ハードレー(Eleanor M. Hadley)は、連合国軍の中に日
本語を話せる人間が少なかったので、ドイツと違い間接統治にならざるを得なかった、と
の意見を述べている(ハードレー1973、p.81)。
いずれにせよ、米国の対日占領方針は、初めは直接統治であったが、のちに間接統治に
変更され、実施されたということである。
上記 SWNCC文書は、9月 6日にトルーマン大統領の承認を経て、22日に「降伏後にお
ける米国の初期対日方針(United States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan、
SWNCC 150/4/A)」として公表された。この文書は占領の究極目的として、平和的で責任
ある政府の樹立と自由な国民の意思による政治形態の確立を挙げている。わかりやすく言
えば、日本の「民主化」と「非軍事化」が占領の目的であったと言える。この文書の中で、
財閥解体を支持することも明示されている(第 4章「経済」、第 2節「民主主義勢力の助長」、
B項)。
連合国軍は、この目的の実現のために、早速 1945年 10月 11日に 5大改革(婦人解放、
労働組合結成、学校教育民主化、司法制度改革、経済機構民主化)の指令を出し、11月 16
日は財閥解体指令も出している。
連合国軍の占領政策を定義した文書としてもう 1つ重要なものがある。それは、1945年
11月 1日に国務・陸・海軍三省調整委員会(SWNCC)が承認し、3日に統合参謀本部(Joint
Chiefs of Staff, JCS)が承認した日本占領に関するマッカーサーへの正式指令である「日
本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期基本的指令
(Basicdirective for Post‐Surrender Military Government in Japan Proepr,
JCS1380/15=SWNCC52/7)」という文書である4。
コーエンによれば、マッカーサーは軍人なので、マッカーサーを拘束したのは、この統
合参謀本部からの指令 JCS1380/15であったとされる(コーエン 1983、p.33)。この
JCS1380/15は、公職追放(第 1部「政治」、第 5節「政治および行政的枠組み」、B項)の
条項を含んでいる。
そのような中、1945年 11月 5日にはポーレー(Edwin W. Pauley)を委員長とする賠償
4 この文書も国会図書館のサイト
(http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/036shoshi.html) から入手できる。

4
委員会が来日し、日本が負うべき賠償について調査を行った。アメリカの賠償政策は、第
一次大戦後の対独賠償問題の教訓を生かし、現金の賠償は避け、取り立ての中心を軍需工
場の過剰既存設備におき、賠償総額を支払国の経済的自立を損なわない程度に抑えるもの
であった。そこで、彼らは日本で 100以上の工業施設を踏査し、12月 6日には「日本から
の賠償即時実施計画(Reparations from Japan, Immediate Program)」(通称「ポーレー
中間報告」)を作成し、大統領に提出した。
ポーレーの報告書では、日本国民に許容される生活水準は、日本が占領したアジアの
他の諸国を上回らない水準とされ、平和経済維持のための最低必要水準を上回る過剰な重
工業プラントおよび在外資産は、主に日本の軍事行動によって被害を蒙ったアジア諸国に
引き渡されるとされた。具体的には、鉄鋼生産許容能力は、満州事変直前の 1930年と同じ
水準とされた(大蔵省財政史室編 1976, p.197)。しかし、この報告書の内容は、後のアメ
リカの政策転換によって、そのまま実現されることはなかった。この報告書の内容が、そ
のまま実施されていれば、日本人の生活水準はかなり低いものとなったのは想像に難くな
い。
1945年 12月に入って、婦人参政権成立(17日)、労働組合法公布(22日)、第 1次農地
改革(29日)と立て続けに連合国軍による改革が実現されていく。
憲法改正について、GHQは日本政府に草案を作成させたものの、出てきた草案を気に入
らず、1946年 2月 1日に自ら作成したものを憲法草案として吉田外務大臣に渡した。日本
政府は、これにわずかな修正を加えたのち日本国憲法として 1947年 11月 3日に公布した。
従って、現在の日本国憲法はマッカーサー元帥のアイデアが強く影響されたものと考える
ことが出来る。この憲法第 9条は戦争放棄を掲げている。この戦争放棄の条項は、のちに
吉田首相の吉田ドクトリンと呼ばれる政策に利用されることとなる。
1946年 8月には、内閣総理大臣を総裁とする経済安定本部が設置され、12月 27日には
閣議で、当時の基幹産業である石炭と鉄鋼に資源、資金を集中的に投入し、両者の生産拡
大によって日本経済全体の生産拡大を図る傾斜生産方式を実施することが決定された。
1947年 1月には復興金融金庫が開業し、日本の生産力を回復するための制度が準備された。
1947年 4月 14日には独占禁止法が公布され、同年 12月 18日には過度経済力集中排除
法(Law for the Elimination of Excessive Concentration of Economic Power,
Deconcentration Lawとも呼ばれる。)が施行された。集中排除の指定企業としては 325社
が指定され、調査されることとなった。このように財閥解体の準備も着々と進められてい
った。

5
しかし、このような中、米国政府内で外交政策の大きな方針転換が図られる。1946年に
中国で国共内戦が始まり、フィリピンやベトナムで共産活動が活発化する。戦時中から芽
生えていたソ連と米国の間の不信感が激しくなり、「冷戦」へと進展していく。これを受け
て米国政府の対日政策も転換していく。
1947年に米国の外交官ジョージ・ケナン(George F. Kennan)は雑誌『フォーリン・ア
フェアーズ(Foreign Affairs)』に「ソビエト対外行動の源泉(The Sources of Soviet
Conduct)」という論文を Xという著者名で寄稿した。この論文はX論文と呼ばれる。1948
年 1月 6日には、ロイヤル(Kenneth C. Royall)陸軍将軍が日本への政策転換を表明する
演説をおこなった。1948年 10月 7日、「アメリカの対日政策に関する諸勧告
(Recommendations with Respect to United States Policy toward Japan, NSC13/2)」で、
この政策転換が明文化された5。これを受け、いわゆる「逆コース(reverse course)」が実
施されていく。この「逆コース」とは具体的には、財閥解体の規模の大幅な縮小や賠償条
件の緩和などである。
1948年 12月 19日には、経済安定九原則(予算の均衡、徴税強化、資金貸出制限、賃金
安定、物価統制、貿易改善、物資割当改善、増産、食糧集荷改善)が、連合国最高司令官
の吉田首相宛の書簡の形で指令された。1949年 2月にはドッジ公使が来日し、3月 7日か
ら、いわゆるドッジラインが実施された。具体的には、緊縮財政、復興金融金庫融資の廃
止、日銀借入金返済などの需要の抑制政策である。これは、当時の日本経済においてイン
フレが激しかったことを反映したものである。ドッジは当時の日本経済を米国援助と国内
の補助金に頼った経済であることから、竹馬経済と呼び、この状況からの脱却が必要であ
るとした。
1949年 5月には、商工省が改組されて通商産業省が設置される。その目的は産業経済の
行政方向を「他力依存」から「自力再建」へと持っていくことであった。
このような中、1950年 6月には、朝鮮戦争が勃発する。この朝鮮特需で日本経済は救わ
れた。連合国軍による資材の調達、修理サービスなどの直接の支出だけでなく、駐日米軍
家族の支出など日本の生産に対し、大きな需要が創出された。
1952年 4月 28日には、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本の独立が回復される。
この後、立て続けに日本経済の国際化が進展する。具体的には、1952年 5月 29日、IMF
と世界銀行が日本の加盟を承認する。1953年 4月 2日には日米友好通商航海条約が調印さ
れ、日本に対して最恵国待遇が与えられることとなった。
5 この文書も国立国会図書館のサイトよりダウンロード可能。
(http://www.ndl.go.jp/modern/cha5/description10.html)

6
このような中、1953年 7月 27日には朝鮮戦争の停戦が合意された。その後も、日本は
成長を続け、1955年 9月 10日には GATTにも加盟し、これで IMF、世界銀行、GATTと
いう西側諸国の主要な国際制度に日本は組み込まれることとなった。
1956年の経済白書では、敗戦からの復興が終了したとして、「もはや戦後ではない」との
記述がなされた。
(2) 経済成長の軌跡
生産・GDP
鉱工業生産データに関しては、連合国軍総司令部経済科学局が作成したものや、経済安
定本部、通商産業省が作成したものなど、様々なものが存在し、データの値も少しずつ異
なっている。ここでは、最も長期にわたってデータが入手可能な通商産業省の鉱工業生産
指数(1955年=100とする)を使用して、1945年から 55年にかけての鉱工業の生産拡大
の経緯を見て行く。
出所:大蔵省財政室編(1978)、p.94.
鉱工業生産の全体(産業総合)について、戦前の最も高い指数は 1944年の 98.2である。
これが敗戦後の 1946年になると、19.2と 5分の 1以下に低下する。同時期、産業の分類
でみていくと、鉄鋼業は 84.2から 9.9へと、10分の 1近に低下している。産業総合指数は、
1955年に 100の水準に到達しているので、1955年に戦前の鉱工業生産水準を回復したこ
とがわかる。その後、鉱工業生産は順調に伸び続け、1960年には 224.8と 5年間で倍以上
になっている。
次に国内総支出(=総生産、GNP)の実質値(1934~36年価格基準)を見てみる。戦前
は 1938年頃より GNPが殆ど増えないなか、個人消費が毎年縮小していき、他方で資本形
成と政府支出が拡大していった。このことは戦時中の国民の耐乏生活を示している。戦後
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
193
0
193
2
193
4
193
6
193
8
194
0
194
2
194
4
194
6
194
8
195
0
195
2
195
4
195
6
195
8
196
0
1955=100
グラフ1:鉱工業生産(産業総合)

7
の 1945年のデータは取れないが、1946年の実質 GNPは 116億円と 1944年の 56%とな
った。鉱工業生産に比べればまだ良いが、それでも GNPは戦前の半分近くに低下したとい
うことである。1944年の水準を超えるのは、鉱工業生産より少し早く 1953年である。1955
年までは、GNP成長への寄与度は消費が一番高く、消費主導の成長であったと言える。
出所:大蔵省財政史室編(1978), p.28.
インフレ
インフレに関しては、1947年~1949年の間に急騰したことがわかる。1947年は、卸売
物価指数と消費者物価指数(東京)が、それぞれ対前年比 196%と 116%の上昇となった。
消費者物価の方は 1950年には 7%近く低下するが、翌年には再び 16%の伸びを示し、52
年から 59年の平均で 3%の増加となる。他方、卸売物価指数は 1951年以降安定する。
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
193
0
193
3
193
6
193
9
194
2
194
8
195
1
195
4
195
7
196
0
196
3百万円(1934~
36年価格基準)
グラフ2:実質国内総支出
国民総支出
個人消費支出
国内民間総資本形成
政府の財貨サービス購
入
経常海外余剰

8
出所:大蔵省財政史室編(1978)、p.40 & p.52.
援助・貿易・特需
下の表は 1946年から 1955年までの国際収支表から重要と思われる項目のデータを抜き
取ったものである。日本の輸出は 1946年の僅か 65百万ドルから始まり、1955年にはその
31倍である 20億ドルに達した。これは毎年 46%ずつ輸出額が増加したことになる。他方、
輸入は 1946年に 3億ドルにのぼり、1955年にはその 7倍の 20.6億ドルに達した。こちら
は輸出の約半分の毎年 24%成長したことになる。
占領期間中、日本は 1946年を除いて経常取引では黒字を達成していることが興味深い。
これは、外貨制約により、資金が手当てできる限りにおいて輸入を行ってきたことを示し
ている。独立後の 1953年、1954年は経常赤字を記録したものの、1955年には再び黒字に
変換した。
表1:日本の輸出入等:1946~1955 (単位:百万ドル)
出所:大蔵省財政史室編(1978)pp.120-123.
例えば、1946年の政府贈与 193百万ドルは米国からのものである。米国からの贈与は食
料や工業原料などの物資で供給されたので、この輸入代金がそのまま輸入と贈与双方に計
0
100
200
300
400
5001934~3
6年平均=1
グラフ3: 物価指数
卸売物価指数 消費者物価指数(東京)
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955商品の輸出 65.3 181.6 262.3 533.3 920.3 1,353.5 1,288.6 1,257.8 1,611.2 2,006.4商品の輸入 303.3 449.0 546.6 728.1 885.9 1,645.3 1,701.3 2,049.6 2,040.5 2,060.8差引出入 -238.0 -267.4 -284.3 -194.8 34.4 -291.8 -412.7 -791.8 -429.3 -54.4 軍関係消費及び払下げ財産 0.0 0.0 18.8 48.6 62.6 624.2 787.7 803.2 602.3 505.1 政府贈与 192.9 404.4 461.0 531.9 360.3 155.3 5.4 0.0 -0.1 12.6経常取引合計 -78.1 46.4 74.8 207.1 476.3 329.4 224.7 -205.1 -50.9 226.5

9
上される。また、この表には出ていないが、1946年には米国から綿花借款 108.7百万ドル
も供与されており、これも米国からの綿花の輸入に充てられたので、同じように輸入金額
に計上される。この両者を合計すると 301.6百万ドルになり、日本の商品輸入額にほぼ匹
敵する。
1946年から 1952年の占領期間中の輸入総額は 63億ドルで、その間に日本が得た政府贈
与は21億ドルであるから、日本は輸入の3分の1の金額を贈与で賄ったということになる。
軍関係消費及び払下げ財産の収入は 1948年から発生しているが、1950年の朝鮮動乱に
よる朝鮮特需によって、その金額が急増する。1953年の 8億ドルがピークで、1950年か
ら 1955年までの 6年間で、軍関係消費の累計金額は 34億ドルにのぼった。政府贈与が減
少したときに、朝鮮特需が発生したことで、外貨調達という点では日本は幸運だったとい
える。
3. 経済成長の要因分析
(1) ガバナンス
1945年~1952年まで日本は連合国軍により間接統治されていた。この状況を「ガバナン
ス」としてどう考えるべきか?日本人によって構成される日本政府は存在し、総選挙も 1946
年には行われた。ただし、連合国軍のイニシアチブで政策が実施されていったのも事実で
ある。「ガバナンス」を構成する要素と考えられる「民主主義」、「法の統治」、「制度」の観
点から占領時代に生じた具体的な出来事を考察していく。
公職追放
占領期間中、多くの者が公職追放に処せられた。しかし、公職追放の権威である増田弘
によれば、占領期の経済復興において公職追放が果たした役割は今日まで解明されていな
い、とのことである(増田 1996、p.i)。政策に関わる人物が公職追放に処せられれば、当
然その政策の実現は阻まれるであろうし、その結果経済パフォーマンスにも影響が出てく
る。また、「民主主義」や「法の統治」を超えて、公職追放がなされれば、それは「ガバナ
ンス」を低めていることにもなろう。
公職追放者の数は増田によれば 21万人とされるが、増田はその大半は公平に実施された
と主張している。しかし、鳩山一郎、石橋湛山のケースに関してはそうではないとしてい
る6。
6 増田(1996)は三大政治パージとして平野力三のケースも取り上げているが、ここでは

10
日本自由党総裁鳩山一郎は 1946年 5月 4日に公職追放に処せられた。4月 10日に実施
された戦後初の総選挙で彼が率いる自由党が第 1党となったことを受けて、内閣組閣に着
手していた矢先であった。つまり、日本国国民が民主的なプロセスで選んだ首相が、就任
前に GHQによってパージされたということである。
鳩山の追放の理由は、田中義一内閣の書記官長時代の治安維持法の改正や、田中内閣の
世界政策の礼賛などであるが、増田(1996、p.57)によれば、このような追放理由は明ら
かに根拠が薄弱であるとのことである。
鳩山がパージされ、その結果として吉田茂が首相となるわけだが、この点について
Saunavaara (2009)は、GHQが戦前の政党政治家(party politician)よりも非政党の政治
家(non-party-affiliated political actor)を好んでいたからと主張している。増田はこ
のパージを、敗者意識の薄い鳩山に対する、多分に見せしめ的“恐喝”という政治性を持
ったものであったとする(増田 1996, p.iii)。
第一次吉田内閣の大蔵大臣であった石橋湛山は、1947年 5月 16日付で公職追放に処せ
られた。追放の理由はジャーナリストであった石橋の戦前の言論であるが、石橋はリベラ
ルな言論人として軍部を批判していたのであるから、この理由は矛盾している。実際、増
田によれば日本側の中央公職適否審査委員会が石橋を「追放非該当者」と認定したにもか
かわらず、GHQの民政局(Government Section, GS)が容認せず、一方的に「追放該当」
とし、日本政府に追放指令を出したとのことである(増田 1996、p.67)。増田は、石橋追放
の真の理由を、GHQに対して終戦処理費(連合国軍の駐留費のうち日本が出す部分のこと)
の削減を要求したりする反占領軍的姿勢を持つ石橋が、自由党内で急速に力を増したこと
に GHQが懸念したためと主張している(増田 1996、p.68)。
上記の2つのケースは、敗者意識の薄い、強力な政治家が、薄弱な根拠で公職追放にあ
ったというものである。「法の統治」という観点からは、明らかに逸脱した状態と言えよう。
また、占領状態とはそういうものだともいえるが、選挙で選ばれた首相が追放されたとい
う点では、「民主主義」も存在していなかった、と解釈できる。
公職追放は、政治家、官僚、右翼団体幹部、国策会社の重役などが主な対象者だが、「制
度」という観点で見ていくと、興味深い特徴があったことがわかる。
中村(2012)によれば、政治家に関しては、進歩党 274名中 262名、日本自由党 45名
中 30名、協同党 23名中 11名と多くの政治家が追放された。戦前の政党政治家の多くが追
放されたことがわかる。
紙幅の関係で割愛した。

11
しかし、官僚について言うと、1800名の文民官僚の追放者のうち、70パーセントは警察
を中心とした内務省からで、商工省、軍需省、大蔵省などの経済官僚からの追放はごくわ
ずかであったとされる(ジョンソン 1982、p.51)。
つまり、戦前に強大な権力を持っていた政治家と内務省官僚が公職追放にあい、経済官
僚は殆ど手付かず残ったということである。このことにより、経済運営に関しては戦前か
らの制度と人が維持され、支障が生じなかったといえる。つまり、公職追放にもかかわら
ず、経済運営の「制度」は維持されたということである。
まとめると、占領期の日本において、「ガバナンス」を構成する要素については「民主主
義」と「法の統治」は弱かったが、経済運営の「制度」としての官僚組織は維持されたと
いうことができよう。
(2) 援助・米国向け輸出・特需
日本の戦後復興は、飢えた国民に食料を提供するとともに、国内生産を拡大し雇用を生
み出すことによって成し遂げられた。この点で、米国からの援助、米国向け輸出、朝鮮特
需は非常に重要な役割を果たした。
占領期の日本は国民の食糧を確保するための輸入が必要であったものの、日本の輸出品
である製造業品を生産する原材料が不足していたため輸出が滞っていた。これを救ったの
が米国からの食料と原材料の現物援助であり、米国の援助は日本国民の生活水準を決定し
たという意味でとても重要であった。
1946年から 1952年の占領期間中の輸入総額は 63億ドルで、その間に日本が得た政府贈
与は 21億ドルであるから、日本は輸入の 3分の 1の金額を贈与で賄ったということになる
(表 1)。
それでは、具体的にどのような品目に米国からの援助がつけられていたのか?占領後初
期の方が輸入に占める援助比率は高いが、具体的なデータが利用できるのは 1950年からで
ある(表2)。輸入の 37%は米国からの援助により可能になったものであるが、金額でみる
と綿花が最も援助額が多い。当時、綿製品は日本の主要輸出品であったので、この綿花の
輸入により日本の綿製品輸出が可能になり、その外貨で食料品の輸入が可能になったと言
える。次に、食料品そのものの援助も大きく、穀物と豆の援助依存度が高い。また、国内
農業生産の増加に必要な化学肥料も米国からの援助に頼っていたことがわかる。

12
表2:1950年の輸入における米国援助の比率 (単位:ドル)
出所:Economic Stabilization Board 1950、No.49 pp.21-22 & 1951, No.53, pp.19-21
次に、日本の輸出入における米国向けのシェアを考えてみたい。表 2は 1945年 9月から
48 年にかけての日本の総輸出入と米国向け輸出入のデータを示したものだが、これを見て
わかるとおり、占領の初期においては日本の輸入は殆どが米国からのものであるが、その
輸入に占めるシェアは急激に低下していく。輸出における米国のシェアも 1945年 9月から
1946年末までには 75%と高かったものの、急激に縮小していく。日本の貿易における米国
の存在は占領期の初期において重要であったと言える。
表 3:輸出入に占める米国シェア (単位:千ドル)
出所:Economic Stabilization Board、No.32, p.72 and p.74.
朝鮮特需を中心とした連合国軍の消費は、1950年から 55年までの間に 34億ドルに及ん
だ。特需には狭義の特需と広義の特需(駐留米軍家族の支出なども含んだもの)があり、
ここでの 34 億ドルは狭義の特需の方であり、広義では 52 億ドルに及んだとされる(中村
1982, p.285)。他方、米国からの援助総額は 21億ドルであるから、金額的に朝鮮特需の影
響は非常に大きかった。
朝鮮特需は金額だけでなく、その質的な内容でも日本の経済成長に大きな影響を与えた。
それは、日本の工場が直接米軍の利用に供せられ、そこで技術移転が行われたと考えられ
1950 Total American Aid %Total 949,076,085 354,152,224 0.37Food and Beverage 329,580,146 115,170,661 0.35 Cereals and products 250,159,567 97,333,350 0.39 Legunas 26,291,134 17,207,020 0.65
Fibers and Textiles 367,808,663 167,725,935 0.46 Cotton 276,685,480 163,548,897 0.59
Chemicals 57,138,312 29,841,129 0.52 Chemical Fertilizers 47,781,899 28,494,101 0.60
Total Import From USA % Total Export To USA %Sep.1945 toDec.1946
303,393 297,688 98 103,292 77,437 75
1947 526,130 483,511 92 173,567 20,090 121948 682,130 441,381 65 258,621 65,758 25

13
るからである。中村によれば、1951年当時、米軍の需要にこたえる(Procurement Demand)
工場が 20余りあり、そのなかにはトヨタ自動車、日産自動車、日野ディーゼルなどの工場
が含まれ、自動車や重機甲車の修理が行われた(中村 1982 , p.284)。工場での労働者の技
術習得が行われるだけでなく、米軍の最新自動車、重機甲車の技術が日本の技術者に示さ
れたと考えられる。
(3) 外交政策
ここでいう外交政策とは大国(米国)の小国(日本)に対する外交政策のことである。
上で述べたように、戦争に勝利した米国は当初日本に対して非常に厳しい姿勢で挑んだ。
「非軍事化」と「民主化」が大きな目的であったにせよ、日本の賠償に関する「ポーレー
中間報告」は、日本に許容されるべき生活水準は、日本が占領したアジア諸国を上回らな
い水準とされ、当時のアジア諸国の所得を考えれば、日本に対しかなり厳しいものであっ
たと言わざるを得ない。また、財閥解体の一環として行われた過度経済力集中排除法の対
象企業として調査された企業数は 325社にも及んだ。
しかし、冷戦の激化により、1947年以降いわゆる「逆コース」が実施され、日本をアジ
アの反共の砦とすべく、賠償条件は緩和、財閥解体は規模を大幅に縮小、様々な支援が実
施された。この政策の転換が無ければ、日本の経済発展の軌跡は今よりずっと緩やかなも
のになっていただろうことは想像に難くない。
このような米国の外交政策の変化は、米国社会のなかでの様々なプレイヤー達の抗争の
結果であった。まず GHQの中にニュー・ディーラー(New Dealer)と呼ばれるグループ
がいたことが知られている。ニュー・ディーラーとはルーズベルト大統領のニュー・ディ
ール政策を経験した、あるいは信奉する左派的な思想の持ち主たちである。代表格は、反
トラスト・カルテル課長のウェルシュ(Welsh)、民政局(GS)次長のケージスであった。
ウェルシュは経済力集中排除法の法案を作成し、三井物産、三菱商事の解体を行った(中
村 2012, p.531)。マッカーサーは共和党の保守主義に属する人であったことを考えると、
ニュー・ディーラーの政策をマッカーサーが良く受け入れたと思うが、日本の民主化、非
軍事化が進む限り、彼らニュー・ディーラーの政策には反対しないという姿勢であったの
であろう。
米国本土では、民主党のトルーマン大統領が 1947年 3月に共産主義に抵抗する政府の支
援を行うというトルーマン・ドクトリンを発表した。同年 7月には、モスクワにも勤務経
験のある外交官ジョージ・ケナンが X論文を書き、対ソ連戦略を公にした。このように GHQ

14
が日本で「非軍事化」と「民主化」の名の下に改革を実行しているとき、米国本土では太
平洋戦争の相手の改革よりも、新たな「冷戦」の対策の方が重要な課題となっていた。
1947年 12月には『ニューズ・ウィーク』でジェイムズ・リー・カウフマン(James Lee
Kaufmann)が、日本では GHQの下、かなり左寄りの改革が実施されており、この改革が
進むなら日本はアメリカの投資先としては魅力のない国になるであろう、との記事を著し
た(ハードレー1973、p.159)。ウォール街の投資銀行の役員でもあった陸軍次官ドレイパ
ー(William H. Draper Jr.)は、1948年 3月にケミカル銀行の頭取であるジョンストン
(Percy H. Johnston)と日本を訪れ、「ジョンストン報告書」を発表した。この報告書は、
日本の問題は経済復興であり、日本の賠償額は縮小されるべきとして、ポーレー案の 4分
の 1が提案されている(ハードレー1973, pp.172-173)。その後、「対日政策に関する勧告
(NSC13/2)」が 1948年 10月に採択され、日本に対する政策は正式に転換する。この影響
を受け、1949年、最終的に過度経済力集中排除法に基づいて処理された企業は僅か 19社
のみとなった。
日本を「民主化」及び「非軍事化」するという目標のもと計画された賠償や財閥解体は、
日本を「冷戦」におけるアジアの反共の砦にするという新たな目標のもと大幅に縮小され
た。米国のこのような政策の転換が、日本の経済制度を温存し、独立回復後の経済成長を
容易にしたのである。
4. まとめ
1945年から 1955年までの 10年間、インフレなどの問題はあったものの日本経済は着実
に復興を遂げた。1953年に実質 GDPは戦前の水準に達し、1955年には鉱工業生産も戦前
の水準に達している。その間、ドル建て輸出額は毎年 20%近い成長を遂げている。
しかし、1945年 9月から 1952年 4月までの約 7年間、日本は連合国軍によって間接統
治され、戦後第 1回目の選挙で選ばれ首相になる予定であった鳩山一郎はその直前にパー
ジされ、大蔵大臣であった石橋湛山もパージされている。両者のパージの理由は、公職追
放の研究者によれば薄弱あるいは根拠のないものであり、この意味で当時の日本は「法の
統治」や「民主主義」が実現されていたとは言い難い。その一方で、公職追放にあった官
僚の多くは内務省出身者で、大蔵省や商工省などの経済官僚の多くは戦後もそのまま働き
続けることが可能であった。つまり、経済を運営する官僚機構という「制度」は維持され
た。この意味で、「ガバナンス」を構成する様々な要素のうち、経済官僚機構という「制度」
は機能したということが出来るであろう。

15
敗戦後、日本が米国から多額の援助を受け、このことによって日本国民の飢えが緩和さ
れ、綿製品を中心とする製造業品の生産および輸出の拡大につながったことは非常に大き
な事であった。戦後初期には、米国が市場を提供し、日本の輸出品の多くを購入たことも
重要であった。日本は輸出が拡大するにつれ、米国市場への依存を弱めたが、それは日本
の製品の国際競争力が高かったことによるものと解釈できる。
朝鮮特需は米国の援助に比べて、より重要であった。それは金額的にも大きかったが、
質的にも重要であった。その理由は、米軍から乗用車や重機甲車の修理などが日本の工場
に発注され、日本の企業が米国の最新の技術を習得することが可能になったからである。
このことがその後の日本の生産技術の向上につながった。
最後に、この間の日本の成長を決定づけた最も重要な要素として、米国の外交政策の転
換を挙げたい。それは、「冷戦」が始まったことにより、日本をアジアの反共の砦とすべく、
賠償額が縮小され、財閥解体も規模が大幅に縮小された。「ポーレー中間報告」がそのまま
実施されていたら、あるいは財閥解体が当初 GHQのニュー・ディーラーが計画していた通
りに実現されていたら、日本経済の成長過程は現在よりもずっと低いものとなったであろ
う。
このことは、大国の外交政策が小国の経済パフォーマンスに大きな影響を与えることを
示している。もちろん、小国自身の努力があってこそ成長が可能になるが、小国を取り巻
く経済環境も重要で、その経済環境は大国の外交政策によって決定づけられるところが大
きいということを、日本の 1945年から 1955年の経験は示している。

16
<参考文献>
大蔵省財政史室編(1976)、『昭和財政史 終戦から講和まで 第 15巻 国際金融・貿易』、
東洋経済新報社。
大蔵省財政史室編(1978)、『昭和財政史 終戦から講和まで 第 19 巻 統計』、東洋経
済新報社。
コーエン、セオドア(1983)、『日本占領革命 GHQからの証言』、TBSブリタニカ.
ジョンソン、チャーマーズ(1982)『通産省と日本の奇跡‐産業政策の発展』、TBSブリ
タニカ.
鈴木九萬(1973)、『日本外交史 第 26巻 終戦から講和まで』、鹿島平和研究所
東郷賢(2009)、「制度と経済成長:既存実証研究のサーベイ」、『武蔵大学論集』、第 57
巻、第 2号、pp.265-296、2009年 12月.
中村隆英(1982)、「日米「経済協力」関係の形成」、『年報・近代日本研究-四-太平洋
戦争-開戦から講和まで-』、1982年 10月 20日、pp. 279-302, 山川出版社.
中村隆英(1989)、「概説 1937-54年」、『「計画化」と「民主化」』、岩波書店
中村隆英(2012)、『昭和史下 1945-89』、東洋経済新報社。
西川博史、石堂哲也 解説訳(1999)、『GHQ日本占領史 第 52巻 外国貿易』、竹前 栄
治, 中村 隆英監修、日本図書センター
橋本寿朗(1989)、「1955年」、『高度成長 日本経済史8』、安場保吉、猪木武徳編集、
岩波書店.
ハードレー、エレノア M(1973)『日本財閥の解体と再編成』、小原敬士・有賀美智子監
訳、東洋経済新報社.
増田弘(1996)、『公職追放 三大政治パージの研究』、東京大学出版会。
Economic Stabilization Board, Japanese Economic Statistics, November 1951~
General Headquarters, Japanese Economic Statistics, 1947~1951
Saunavaara, Juha (2009), “Occupation Authorities, the Hatoyama Purge and the
Making of Japan’s Postwar Political Order,” The Asia-Pacific Journal, Vol.39-2-09,
September 28, 2009.
Togo, Ken (2011), “Should PPP GDP Per capita data be used with or without
Reservation?” The Empirical Economics Letters, 10(10):1037-1045, October 2011.

Annex 表1 1945-1955年の出来事
年 首相 主要大臣 出来事 外国での出来事
1945 鈴木貫太郎(4/7~、軍人)トルーマン大統領就任(4/12)
ポツダム宣言(7/26)
東久邇宮稔彦王(8/17~、皇族)
外務大臣:重光葵(8/17~、外務官僚)
昭和天皇が「戦争終結の詔書」を読み上げる(8/15)。
外務大臣:吉田茂(9/17~、外務官僚)
降伏文書調印(9/2)「初期対日方針(SWNCC150/4)」発表(9/22)。
幣原喜重郎(10/9~、外務官僚)
外務大臣:吉田茂(10/9~)
GHQ、5大改革(婦人解放、労働組合結成、学校教育民主化、司法制度改革、経済機構民主化)を要求(10/11)。GHQ,財閥解体指令(11/16)
婦人参政権成立(12/17)
労働組合法公布(12/22)
第1次農地改革(12/29)
1946戦後初の総選挙(4/10)で日本自由党が第一党に。幣原内閣は総辞職し、自由党総裁の鳩山一郎を後継首班に奏請。GHQ、鳩山を公職追放にする(5/4)。
吉田茂(5/22~、外務大臣を兼務)
大蔵大臣:石橋湛山(5/22~、ジャーナリスト)
経済安定本部設置(8)
第2次農地改革(10/21)
日本国憲法公布(11/3、翌年5/3施行)
傾斜生産方式閣議決定(12/27)
1947 復興金融金庫開業(1)全官公庁労組共闘委員会、2月1日からの無期限スト宣言(1/18)
ジョージ・マーシャル米国国務長官に就任(1/21)
マッカーサー、ゼネスト中止を指令(1/31)片山哲(5/22~、弁護士、日本社会党)
外務大臣:芦田均(6/1~、外務官僚)
石橋湛山公職追放(5)
ジョージ・ケナン、対ソ封じ込め政策のX論文を
フォーリンアフェアーズに過度経済力集中排除法施行(12/18)
1948ロイヤル陸軍長官の演説(1/6)
芦田均(3/10~、外務大臣を兼務)吉田茂(10/15~、外務大臣を兼務)
昭和電工事件で芦田内閣総辞職(10/7)「対日政策に関する勧告(NSC13/2)」採択
マッカーサー、経済安定9原則の実行を指示(12/19)東条英機ら7人の絞首刑(12/23)、GHQ、A級戦犯釈放を指令(12/24)。
1949吉田茂(2/16~、外務大臣を兼務)
大蔵大臣:池田勇人(2/16~、大蔵官
ドッジ公使来日(2/1)
$1=360円の為替レート設定(4/23)
通商産業省設置(5)下山事件(7/6)、三鷹事件(7/15)、松川事件(8/17)が続く。GHQ, 税制改革案(シャウプ勧告)を発表(9/15)。
1950 朝鮮戦争始まる(6/25)
1951マッカーサー、GHQ最高司令官を解任される(4/11)石橋湛山ら2,958名の追放解除(第1次追放解除)(6/20)GHQ, 持株会社整理委員会解散に関する覚書公布、財閥再建はじまる(6/21)鳩山一郎ら、13,940名の追放解除(第2次追放解除)(8/6)サンフランシスコ平和条約、日米安全保障条約調印(9/8)
1952平和条約、安保条約発効。GHQ廃止(独立の回復)(4/28)国際通貨基金、世界銀行、日本の加盟を承認(5/29)。
吉田茂(10/30~)通商産業大臣:池田勇人(10/30~)
1953アイゼンハワー大統領就任(1)スターリン死去(3)
朝鮮休戦協定成立(7/27)
日米友好通商航海条約発効(10/30)
1954 日米相互防衛援助協定締結(MSA協定、3/8)
防衛庁設置法、自衛隊法公布(6/9)鳩山一郎(12/10~、政治家)
外務大臣:重光葵(12/10~)通商産業大臣:石橋湛山(12/10~)
1955 GATT加盟(9)自由党と日本民主党が合同し、自由民主党が結成される(11/15)。
出所:首相官邸HP(http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/kakuryo/showa20.htmlなど)注:( )内は月日。例えば、(4/17)は4月17日、(5)は5月。主要大臣は重要と思われる人物を取り上げた。

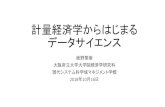






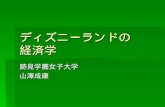



![理論経済学―マルクス経済学入門 - 法政大学 [HOSEI UNIVERSITY] · 2012-12-25 · 223 【経済学研究のしおり】 理論経済学―マルクス経済学入門](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5e50c53b646db20d687de839/cecoeaffcoee-hosei-university.jpg)