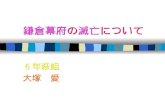各府省の取組において作成...
Transcript of 各府省の取組において作成...

各府省の取組において作成されたロジックモデルの例
(令和元年度)
内閣官房
行政改革推進本部事務局
令和2年5月
参考資料1

目次【人事院】 国家公務員の職務に係る倫理の保持に関する事業 … p.2
【内閣府】 安全・安心分野におけるニーズ・シーズの把握とマッチング … p.3
DV被害者等セーフティネット強化支援パイロット事業 … p.4
地域の課題解決に資する交通安全計画推進に関する調査 … p.5
【宮内庁】 京都御所等における見学学習プログラムの提供 … p.6
【公正取引委員会】 ASEAN加盟国向け競争法・政策研修等の実施に必要な経費 … p.7
【警察庁】 安全かつ効果的・効率的な救助活動 … p.8
【個人情報保護委員会】 独自利用事務の情報連携の届出手続のシステム化 … p.9
【金融庁】 金融経済教育の推進(学校教育関連等の取組み) … p.11
【消費者庁】 若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム … p.12
【復興庁】 伴走型人材確保・育成支援モデル事業 … p.15
【総務省】 公衆無線LAN環境整備支援事業 … p.17
関係人口創出・拡大事業 … p.18
新たな広域連携促進事業 … p.19
【法務省】 地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施を通じた医療観察対象の社会復帰の促進 … p.20
SNS(LINE等)を活用した周知・広報 … p.21
【財務省】 財政教育プログラム … p.22
【文部科学省】 幅広いアプローチ(BA)活動等 … p.23
【厚生労働省】 一般介護予防事業 … p.26
【農林水産省】 農山漁村振興交付金 … p.27
【経済産業省】 省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費 … p.28
【国土交通省】 地域防災力の強化 … p.29
【環境省】 山岳環境保全対策事業 … p.30
【原子力規制委員会】 緊急時対策通信設備等整備事業 … p.31
【防衛省】 情報発信の強化 … p.32 1

【人事院】国家公務員の職務に係る倫理の保持に関する事業
活動/アウトプット 最終アウトカム(上位目標)
(円滑な行政運営のため)
公務に対する国民の信頼を確保
中間アウトカム
職員の倫理感のかん養
倫理的な組織風土・環境の構築
公務員不祥事の減少
初期アウトカム
定期的・継続的な倫理研修の受講
相談・通報窓口の整備、利用促進
職員の倫理制度に係る理解度向上
倫理制度に関する意見聴取
倫理研修の実施支援(教材の作成や講師派遣)
公務員倫理セミナーや講演会の開催
国家公務員倫理週間(月間)の実施
事業者等への周知・啓発
国民の理解促進
・外部窓口設置状況・違反を見聞きした場合の対応
ヒト・カネの投入(インプット)
・国家公務員自身の肯定的な印象の割合
事務局職員16人
事務局予算17百万円
安心して相談できる職場環境づくり
倫理に関する制度説明会の開催
国家公務員倫理審査会事務局
設定困難
設定困難
・国家公務員への肯定的な印象の割合
・窓口設置状況・窓口の認知度
・説明会やセミナー等の理解度・満足度
・最後に倫理研修を受講してからの期間・倫理研修受講率
凡例:指標、エビデンス:審査会事業に限られないもの
・研修講師派遣数・教材配布数
・開催数及び参加者数
・要請事項への取組状況
・PR記事を掲載した団体数
注)「 」は、因果関係を証明するためのエビデンス設定やその評価方法の構築が困難
国民目線の行政運営
本事業は、一般職国家公務員の職務執行の公正さに対する国民の疑惑・不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する信頼を確保するために実施している。1990年代に続発した幹部公務員の不祥事を受けて制定されて国家公務員倫理法令は、制定から約20年が経過し、ルールとしては概ね浸透してきている。しかしながら、
昨今、複数の幹部職員が高額の供応接待を受けるなどの事態が生じ、倫理制度の在り方そのものが問われる残念な状況となっており、個々の職員一人ひとりの倫理感を高めること及びそのような事態が生じにくい組織風土・環境づくりが喫緊の課題となっている。
事業の目的、背景・課題
2

インプット(予算)
アクティビティ(事業概要)
アウトプット(活動実績)
インパクト(社会的な影響)その他の関連事業、施策
初期(※)アウトカムマッチングによって特定された重要技術について、研究開発を行う。
・研究開発実施件数
中長期(※)アウトカムマッチングにより特定された重要技術について、社会実装を行う。
・社会実装に至った件数
調査・検討の結果に基づいて、マッチングの仕組みを構築。
・マッチングの仕組みの有無
アウトカム(活動実績がもたらす状況の変化、人の行動変容、その他成果)
事業により直接コントロールできない部分
(※)時間軸で初期→中長期で設定。
解決すべき問題・課題
安全・安心分野における、それぞれの単一分野における研究開発を実施する際、ニーズを解決する技術シーズを有する企業や研究機関等を公募し、応募、審査を行い、技術シーズの収集が図られている状況。技術シーズの収集対象範囲がニーズに関連の深い分野に限定されがちになり、ニーズ解決のためのより適切な技術シーズが入手できる環境となっていない。
上記問題・課題と事業との関係
安全・安心に関わるニーズに対応した具体的な技術シーズについて、政府内で一元的に集約・共有し、政策に結び付ける必要がある。分野横断的な視点を有した目利き人材を活用することで、広い分野における技術シーズの探索が可能となり、ニーズを解決するためのより優れた技術シーズが選定される(マッチング)。本件は、上記を実現するためのマッチングの仕組みについて、調査・検討を行うものである。
(注1)アウトプット及びアウトカムの点線枠内には、何をもってアウトプット及びアウトカムを測るのかを記載する。(注2)アウトカムを定量的に測ることが困難な場合には、代替となる事項をもってアウトカムを測ることの相当な理由も同枠内に記載する。
【R2年度】28(単位:百万円)
目利き人材を活用したマッチングの仕組みについての調査・検討。
安全・安心分野における将来の活用が期待される技術や適切に管理すべき分野の早期発掘、特定に繋げ、国及び国民の安全・安心を実現。
○官民研究開発投資拡大プログラム (PRISM)「革新的建設・インフラ維持管理技術/革新的防災・減災技術」
○戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」
【内閣府】安全・安心分野におけるニーズ・シーズの把握とマッチング 担当:科学技術・イノベーション担当
3

インプット(予算)
アクティビティ(事業概要)
アウトプット(活動実績)
インパクト(社会的な影響)
・民間シェルター等の先進的な取組を促進するパイロット事業を実施
・パイロット事業の効果検証及び事例調査の実施
・令和2年度(2.5億)
・地域におけるDV被害者等の支援の充実(DV被害者等の保護・自立)・自治体による財政援助(特別交付税措置含む)
・他省庁による財政援助(婦人保護事業等) 等
その他の関連事業、施策
初期(※)アウトカム①・民間シェルター等の活動基盤の強化(活動強化)
・パイロット事業に参加した民間シェルター等の数、事業の実施数等
・民間シェルター等に対するアンケート調査(支援者数、利用者数等)
中長期(※)アウトカム・民間シェルター等における先進的な取組の普及(対応力向上)
・パイロット事業により支援につながった人数や自立した人数
・民間シェルターに対するアンケート調査(利用者数等の経年変化、支援内容の充実の状況)
・各地方公共団体において、民間シェルターへの支援を実施
・パイロット事業に参加した地方公共団体数
・地方公共団体による民間シェルターに対する支援内容等
・民間シェルター等のニーズや効果検証、課題の把握
・先進的な取組を含むノウハウの蓄積
・パイロット事業に関する調査報告書
初期(※)アウトカム②・パイロット事業に参加する地方公共団体・民間シェルタ―等の広がり・好事例の展開
・パイロット事業の参加を希望する地方公共団体・民間シェルター等の数
アウトカム(活動実績がもたらす状況の変化、人の行動変容、その他成果)
事業により直接コントロールできない部分
(※)時間軸で初期→中長期で設定。
解決すべき問題・課題
配偶者からの暴力(以下、「DV」という)の被害者等に対する支援については、民間シェルター等の団体が、地域において重要な役割を担っているものの、財政面、人的基盤などにおいて厳しい状況にある。
上記問題・課題と事業との関係
民間シェルター等が官民連携の下で行う先進的な取組を促進するパイロット事業を実施することで、民間シェルター等の活動強化と対応力向上につながり、DV被害者等に対するニーズに沿った支援を行うことが可能となる。
(注1)アウトプット及びアウトカムの点線枠内には、何をもってアウトプット及びアウトカムを測るのかを記載する。(注2)アウトカムを定量的に測ることが困難な場合には、代替となる事項をもってアウトカムを測ることの相当な理由も同枠内に記載する。
【内閣府】DV被害者等セーフティネット強化支援パイロット事業 担当:男女共同参画局
4

インプット(予算)
アクティビティ(事業概要)
アウトプット(活動実績)
インパクト(社会的な影響)
交通安全対策の成果等を客観的に地方公共団体間で比較できる指標の検討
交通安全対策の成果を上げている地方公共団体における対策等のベストプラクティスを分析の上、共有
15百万円
道路交通事故死者数、死傷者数等の削減・交通安全の普及・啓発
・道路交通環境の整備・車両の安全性の確保 等
その他の関連事業、施策
初期(※)アウトカム①データに基づく地域の交通事情の正確な把握
地方公共団体における指標の確認の割合
中長期(※)アウトカム交通安全計画や交通安全対策への反映、予算要求等の実施
地方公共団体における対策等のベストプラクティスの活用の割合
交通安全対策の成果等を客観的に他の地方公共団体と比較できる指標
指標の数
交通安全対策の成果を上げている地方公共団体における対策等のベストプラクティス
対策等のベストプラクティスの数
アウトカム(活動実績がもたらす状況の変化、人の行動変容、その他成果)
事業により直接コントロールできない部分
(※)時間軸で初期→中長期で設定。
解決すべき問題・課題
道路交通事故死者数、死傷者数等の削減
上記問題・課題と事業との関係
各地方公共団体における交通安全対策を推進させる
(注1)アウトプット及びアウトカムの点線枠内には、何をもってアウトプット及びアウトカムを測るのかを記載する。(注2)アウトカムを定量的に測ることが困難な場合には、代替となる事項をもってアウトカムを測ることの相当な理由も同枠内に記載する。
【内閣府】地域の課題解決に資する交通安全計画推進に関する調査 担当:共生社会政策担当
5

【宮内庁】京都御所等における見学学習プログラムの提供 ロジックモデル
インプット(資源)
アクティビティ(事業概要)
事業の目的 京都御所等を題材とする学習プログラムを提供することにより,皇室とその歴史・文化について,学生等の興味・関心と理解を深める。
予算措置
↓特段の予算措置はない
必要性と背景皇室とその歴史・文化の学習については,従来,文献・インターネットによる調査といった自主的な調査にゆだねら
れていた。
人的資源文化財管理担当職員(2名)
・見学学習プログラの作成・学校との打ち合わせ・説明パネル,資料の作成・説明者の訓練
これまでの参加者へのアンケートの結果
職員の気づき
参加校の募集京都市教育委員会を通じ,市内の学校へ働きかけ
アウトプット(活動実績)
①参観前学習
②参観学習
<アンケート等を通じた改善>(令和元年度の取組例)・紫宸殿の屋根の檜皮や竹釘等のサンプルに触れることのできる体験学習の取り入れ・わかりやすい資料の作成例)京都御所で行われていた儀式の写真パネルの使用・本プログラムの担当者以外のベテラン職員による解説等
アウトカム(成果目標)
改善
プログラム参加者の皇室施設への理解が深まる
アウトカム(インパクト)
事業の目的の達成
皇室とその歴史・文化への,学生等の興味・関心と理解を深める
参加した学生等個々の興味・関心と理解の向上=縦の広がり
充実した受入れによる参加希望校の増加=横の広がり
宮内庁職員の解説のもと,施設を見学
測定指標①皇室の歴史・文化への理解の向上(参加者へのアンケート調査を実施)②参加校,参加者数
宮内庁職員が学校に出向き,参観前に題材となる施設について解説。
等・・・
③参観後学習
プログラム終了後アンケートを実施
参観学習実施後,各学校の授業等において生徒が,見学で学んだことをポスター等を用いて発表。宮内庁職員が発表会に出向き,解説・講評
見学学習プログラム提供
アウトカム(第一段階)
参観後学習による,理解の更なる促進
アウトカム(第二段階)
アンケート実施等による見学学習プログラムの改善
アンケート結果のプログラムへの反映
6

政府方針
現状
・昨今のグローバル化の進展を受け,中小企業を含む多くの日本企業等がASEAN加盟国・地域への事業展開を行っているところ,日本の経済界から,海外の法執行の予見可能性の担保や,進出先の競争環境の整備を求める声が寄せられている。
・ASEAN加盟国からも,アジアにおいて最も長い競争法の執行の歴史を有する日本に対し,競争法の整備・施行に関する技術支援への強い期待が寄せられている。
【公正取引委員会】ASEAN加盟国向け競争法・政策研修等の実施に必要な経費
(小事項名)海外競争当局等との連携強化に必要な経費
●「経済財政運営と改革の基本方針2019」(いわゆる「骨太の方針」/令和元年6月21日閣議決定)第2章 Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり
4.グローバル経済社会との連携(2)経済連携の推進,TPP等の21世紀型ルールの国際標準化
「自由で公正な経済圏の拡大による効果を享受できるようにするため,…海外展開先における現地人材の育成支援…を実施する」
●「自由で開かれたインド太平洋」(令和元年7月12日付け外務省HP)“ASEAN地域の連結性を向上させることで,質の高いインフラ整備,貿易・投資の促進,ビジネス環境整備,人材育成強化を図る。”
●「日本・ASEAN包括的経済連携協定」(平成20年4月署名)第8章 経済的協力 第53条 経済的協力の分野
1 全締約国は,相互の利益に基づいて,次の分野の経済的協力に関する活動を検討し,及び実施する。(b) ビジネス環境, (f) 人材養成, (l) 競争政策
インプット(投入資源)
アクティビティ(活動)
アウトプット(活動による産出物)
初期・中間アウトカム(政策効果)
最終アウトカム(政策効果)
予算
25,930千円
・ASEAN加盟国競争当局の職員・関係者の競争法に対する理解の深化
・公正取引委員会職員等による各国の競争当局職員等に対する知見の提供
・競争当局間の協力関係の強化
・訪日研修(各国の競争当局職員等を日本に招へいし,公取委の職員等が独占禁止法及び競争政策に関する研修を実施)
・現地ワークショップ(競争政策に係る様々な議題について,公取委の職員等が相手国に出張して,プレゼンテーションや議論等を実施)
・現地コンサルテーション(各国の競争当局の特定の活動について,公取委の職員等が相手国に出張して相談・協議を実施)
・各国における競争法・制度の日本の独禁法と親和的な形での整備
・中小企業を含む日本企業等の海外展開の後押し
・我が国とASEAN加盟国との経済関係の深化
・各国における競争法執行活動及び制度運用の適正化・ASEAN加盟国のビジネス環境の整備・海外の法執行の予見可能性担保による競争法リスクの低減・日本企業等の参入障壁の低減
(初期) (中間)
内 容カンボジア,ラオス,ミャンマー及びベトナム(CLMV)の各国の競争当局職員や関係者等を日本に招へいし,訪日研修を行うほか,現地に有識者・公取委職員等を派遣して現地ワークショップ及び現地コンサルテーションを行うもの。
目 的 ・ 目 標ASEAN加盟国の中で,とりわけ競争法の整備が遅れているとされるCLMVにおける競争法・政策が我が国のものと親和的なものとなるよう,その整備・施行を積極的に支援することにより,ASEAN地域で事業活動を行う日本企業にとっての競争法リスクの低減及びASEAN加盟国との経済関係の深化に資する。
7

【警察庁】安全かつ効果的・効率的な救助活動現状把握・課題
【現状】
インプット
【予算】○ 平成30年度(補正) 4,422,478千円○ 平成31年度 32,117千円
災害警備訓練施設 17,296千円広域緊急援助隊訓練 14,821千円
○ 令和元年度(補正) 590,363千円○ 令和2年度 92,703千円
災害救助用装備 64,558千円災害警備訓練施設 17,349千円広域緊急援助隊訓練 10,796千円
アクティビティ
○ 効果的・効率的な訓練による救助技能の早期修得
アウトプット
アウトカム
○ 指揮官の能力向上広域技能指導官等、質の高い指導員による基礎技術指導を行い、部隊指
揮官に訓練ノウハウを修得させることによって、自所属における訓練の質が向上
インパクト
【課題設定】
管区警察局の定める年間訓練計画に基づき、県別訓練、集合訓練(エリア、大隊ごと)、管区合同訓練(関係機関も参加)を段階的に実施。実施状況は、管区ごとに集約、管理。
救助活動に必要な技術を部隊の種別・配備資機材を基に分類・項目化した「訓練基準」に従って実施
○ 訓練内容
○ 装備資機材の整備とその効果を最大限発揮するための救助技術の修得効果的な装備資機材の整備とその特性を理解し、そ
の効果を最大限に発揮できる技術の修得が課題。
○ 救助技能の維持、強化救助部隊の大半を占める機動隊、管区機動隊の人事
異動で、一時的に部隊の技術力が大きく低下し得る。また、警備実施もあり、限られた人員及び時間で効
率的な訓練を行う必要がある。
⇒ 「基礎の確立」、「安全管理の徹底」を明示した訓練の実施
⇒ 計画的な訓練指導員の育成と訓練方法の検証
⇒ 質の高い指導員による基礎技術の指導
⇒ 訓練施設の優位性を生かした効率的な技術訓練
⇒ 合同訓練の機会を活用した訓練効果の検証
⇒ 検証結果を踏まえた効果的活動への反映
○ 訓練効果の検証災害現場における
「安全かつ効果的・効率的な救助活動」に資する訓練
【平成30年度】<指導員育成>専科教養 5回 106人警視庁派遣(1年) 2回 6人<指導員派遣>県別訓練 13回集合訓練 23回管区合同訓練 6回※大雨に伴う警備対応により1回中止
<訓練施設の利用>近畿管区 95回 8,682人警視庁・東日本 221回 4,509人
<訓練効果の検証>各訓練項目に定める実施状況の調査広域技能指導官による技術練度の検証
災害現場における
「安全かつ効果的・効率的な救助活動」
◎ 現場における「二次災害防止」
◎ 一人でも多くの要救助者の「救出・救助」
・ 現場の安全管理 ・ 隊員の安全管理 ・ 要救助者の安全管理
○ 訓練状況
○ 救助技能の格差訓練環境(指導員、訓練時間、訓練施設の確保状況
等)の差により、都道府県ごとの救助技能に格差が生じ得る。⇒ 指導員の派遣や訓練施設の活用が有効
⇒ 救出救助技術検討会で主要装備資機材の性能、使用方法について検討。救助技法を資料化し、周知
⇒ 装備資機材の特性を生かした救助技法を用いた訓練
○ 装備資機材の効果的活用方法の周知と救助技術の修得
○ 広域技能指導官による訓練効果の検証
○ 救助技術の効率的な修得知識・技術の豊富な指導員の派遣による訓練指導により、効果的・効率的に救助技術を習得
訓練時間の長短のみならず、広域技能指導官等を招聘するなど効果的・効率的に訓練を実施しているかどうかについても考慮して取組を検証する。
訓練頻度
活動能力
<装備品の有効活用による効率的な救助事案例>平成30年7月豪雨において、土石流等により大型の重機が入れず救助活動に支障
を来していたところ、警察が保有する小型バックホウを活用し、効率的に救助活動を実施。(平成30年度補正予算により全国に増強配置)
管区等広域技能指導官
等派遣訓練広域技能指導官在籍数
北海道 1回 0東北 7回 1
警視庁 1回 4関東 11回 2(1警察庁)中部 3回 0近畿 7回 0中国 1回 1四国 0回 1九州 5回 0全国 36回 9北海道 東北 警視庁 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 全国
【広域技能指導官等派遣訓練】【平成30年訓練実施状況】時間※
※1人当たりの訓練実施時間
<救助技能を生かした安全かつ効果的な救助事案例>平成30年北海道胆振東部地震において、倒壊家屋の捜索時、特別救助班指揮専
科等において修得した安定化措置を念頭に置いた救助活動を実施し、約280名の体制の中、一人の受傷者も出すことなく安全に救助活動を実施。
【災害現場における効果】
○ 救助部隊の構成等
近年、長期の対応を要する災害が続発していることに加え、南海トラフ地震及び首都直下地震については、甚大な被害が想定されており、平時の訓練を通じた一層の災害対処能力の向上が必要。
検証の結果、不足している項目について翌年の訓練計画等に反映
管区等項 目
総合評価初動活動 安全管理 救助全般 要救活動 指揮支援 ロジ関係 装備資機材
北海道 ● ● ● ● ● ● ●
東北 ● ● ● ● ● ● ●
警視庁 ● ● ● ● ● ● ●
関東 ● ● ● ● ● ● ●
中部 ● ● ● ● ● ● ●
近畿 ● ● ● ● ● ● ●
中国四国 中 止
九州 ● ● ● ● ● ● ●
【平成30年度検証結果】「優」「良」「可」の3段階による評価
※令和元年度から主要装備資機材の特性を生かした救助技法についても検証※検証項目については、継続的に精査・検討
8

【個人情報保護委員会】独自利用事務の情報連携の届出手続のシステム化
直接アウトカムインプット 中間アウトカム最終
アウトカム
ロジックモデル
アクティビティ アウトプット
独自利用事務の情報連携業務のシステム化の要件定義に係る予算※39.0百万円(令和2年度新規要求)
地方公共団体におけるマイナンバー利活用が一層進み、添付書類の削減等により、社会全体の利便性が向上
情報連携の届出手続に係る行政コスト削減により、地方公共団体において独自利用事務の情報連携の活用が進むとともに、マイナンバー制度の信頼性を確保
作業時間の短縮(業務の効率化)一連の独自利用事務の情報連携の届出手続を全てシステム化
・郵送・電子メールでの届出、不備連絡等の廃止
・データ標準レイアウト関連様式の作成・確認作業の削減
独自利用事務の情報連携の届出手続に係る業務システムの構築※
○地方公共団体からの届出(参考「①」)は、紙媒体(郵送)と電子データ(メール又は郵送)・市区町村の届出は都道府県がとりまとめて提出・不備・連絡事項はメールによる連絡
○データ標準レイアウト関連様式の作成・確認(参考「④」)は、職員の手作業に依存
○紙媒体と電子媒体での提出コストの発生○不備等のメール連絡のコストの発生
○手作業による、人為的ミスの発生
⇒・情報連携できないことにより、地方公共団体の業務に支障が出るリスク・特定個人情報の取扱いが不適切となるリスク
○届出手続に係る行政コストの削減(行政の利便性向上)
○的確な情報連携による、マイナンバー制度の信頼性確保
〇マイナンバー利活用の一層の促進(社会全体の利便性向上)
現状と課題 課題解決による目標
独自利用事務の情報連携の届出手続をシステム化(令和4年度から運用開始)
※令和4年度からシステムを運用開始業務の正確な実施
①国の年間の業務処理期間約41日間×3回(総業務処理日数から、委員会報告等のシステム化により効率化が見込めない日数を除いた日数)
②地方公共団体の年間の業務処理確保期間約34日間×3回(業務処理期間の詳細は不明)
届出1件あたりの不備・連絡事項件数2.4件(令和元年2回目募集時)
①情報連携を行う独自利用事務の届出件数
<参考>R2年2月現在:8,561件
②独自利用事務の情報連携を行う地方公共団体数<参考>R2年2月現在:1,213団体
(うち、市町村1,166団体)
データ
データ データ
今後の検討課題等○令和2年度からの要件定義に当たり、事業の効果を検証できるデータ(直接アウトカム関係)の把握可能性を検討○業務効率化の観点に関しては、「業務見直し」においても取り組み、効果を検証 9

(参考)委員会規則で定める要件① 独自利用事務の趣旨又は目的が、
法定事務の根拠となる法令の趣旨又は目的と同一であること。
② その事務の内容が、法定事務の内容と類似していること。
独自利用事務の情報連携について
〇 マイナンバーの利用は、原則として番号法に定められた事務に限定されているが、地域の自主性の観点から、地方公共団体が条例で定める事務についてもマイナンバーを利用することができる(独自利用事務)。
(番号法第9条第2項)〇 独自利用事務のうち一定の要件を満たす事務は、委員会規則で定める届出を行うことにより、情報提供ネット
ワークシステムを使用して他機関との情報連携ができる。 (番号法第19条第8号)➣ 提出する添付書類の大幅な削減、職員の事務の効率化が実現。
〇 個人情報保護委員会では、届出に関する事務及びデータ標準レイアウト関連様式(情報提供ネットワークシステムに権限設定するための様式)の作成を行う。
A市B町
A市
準ずる
≒
法定事務の情報連携
独自利用事務の情報連携
添付書類の提出
情報連携
申請
添付書類の取得
個人情報保護委員会
申請者(B町からA市へ転入)
情報連携
情報提供ネットワークシステム
①届出
④データ標準レイアウト関連様式作成
(情報連携の権限設定)
(②届出内容の要件該当性を確認)(③要件を満たす届出を公表)
情報連携によるバックオフィス連携
国民の利便性向上(添付書類の削減)
(参考)届出の状況(令和2年2月26日現在)・届出数:8,561件・届出団体:1,213団体
参 考
10

各個人がライフステージに応じた様々なニーズに見合う金融サービスを適切に選択し、最適なポートフォリオを構築できるようにすること。
ライフプランニング、金融の役割、基本的な金融商品の知識等について、学生のうちに、少なくとも一度は、基本的な知識が身に付ける機会が得られるようにする。(主に、高校生の授業において、新学習指導要領に基づく教材が広く活用され、適切な内容の授業・指導等が行われること)
<測定指標>金融広報中央委員会実施の「金融リテラシー調査」• 正誤問題(金融知識・判断力)の全体及び学生(18‐24歳)の正答率(2019年:全体56.6%、学生:42.6%)
• 学生(18‐24歳)の「学校等において金融教育を受けた人の割合」(2019年:17.0%)
●出張授業●子ども霞が関・チームラボ等の、親子向けイベントの実施●イベントを活用した教材・指導法の作成
小学生計640万教員42万約2万校
●出張授業●新学習指導要領に関する情報提供
中学生計320万教員25万約1万校
●出張授業●全国の家庭科教員との連携強化(研究授業の実施、勉強会等への参加)●家庭科教師と連携した共通教材作成●金融経済教育に関するイベント(教師向けつみップ等)
高校生計320万教員23万約5千校
●出張授業●大学連携講座への協力●教員養成大学でのモデル授業●投資サークルとの連携
大学生計300万教員23万約1千校
インパクトアウトカム
アウトプット
個々人の生活の多様性に十分留意しながら、各個人が、金融リテラシーを、関係する情報リテラシーとともに向上させ、ライフステージに応じた様々なニーズに見合う金融サービスを適切に選択し、最適なポートフォリオを構築できるような環境を総合的に整備していくことが重要な課題となっている。
金融経済教育推進会議(メンバー:有識者、金融関係団体、金融広報中央委員会、関係省庁)において策定された金融リテラシーマップを踏まえ、「家計管理」「生活設計」「金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択(詐欺やローン・クレジットの仕組み等を含む)」「トラブルへの対処」などを内容とする出張授業等の取組みを実施(高校生以下で年約3千件、27万人(回数は増加基調))。
こうした取組みを通じ、各団体の連携体制は構築されてきたが、各団体とも新学習指導要領への準備はこれからであり、学校現場へのより効果的なアプローチが課題。 広く国民の金融・情報リテラシーの向上に取り組んでいくためには、金融庁・財務局が共同で行うべき重要な行政テーマとの認識の下、様々な関係者との連携体制の構築やイベント間の連携強化が必要である。
【金融庁】金融経済教育の推進(学校教育関連等の取組み) G20福岡において承認された「G20福岡ポリシー・プライオリティ」において、デジタル化されていく金融サービスを誰もが活用できるようにするための金融・情報リテラシーの向上、高齢者を狙う投資詐欺等に対する啓発活動や消費者保護、そして、生涯を通じたライフプランを設計できるようにするための情報提供などの重要性を指摘。
また、多様な個人が資産形成を行うという点でも、投資に対する抵抗感や金融機関に対する不信感が強く残っているとの指摘や、資産形成の必要性を感じていても、必ずしも関連する知識が十分でなく、適切な金融サービスの選択ができていないとの指摘もある。
背景
現状認識・課題
(インプット)予算22百万(2019年度)
(アクティビティ)①出張授業等 ②教材の検討・策定 ③ガイドブック等の配布
上記の「金融経済教育の推進(学校教育関連等の取組み)」のほか、「つみたてNISAを通じた長期・積立・分散投資の普及」、「販売会社による顧客本位の業務運営の推進」、「アセットオーナーの機能発揮」、「資産運用業の高度化」、「金融・資本市場の機能・魅力向上」、「コーポレートガバナンス改革の推進」に向けた取組みを実施。他事業
教育機関や地方公共団体等においてガイドブック等や新た
に作成した共通教材を配布(出張授業等や説明会でも活
用)
国民の金融・情報リテラシーの向上を通じて、国民一人一人がより良い暮らしを送ることが可能となること。
日銀・日証協等の関係団体が連携して学校を支援する体制
の構築
教育庁(教育委員会)や教員を含む教育関係者とのリレー
ションの構築
金融・情報リテラシーの現状についての知見を得るとと
もに教育現場における金融経済教育のニーズを把握
11

【消費者庁】若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム (担当課: 消費者教育推進課)
【背景】・平成30年6月13日、成年年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる民法改正法案が可決・成立。平成34年4月施行予定。【必要性】・民法の成年年齢引下げを見据え、若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、自主的かつ合理的に社会の一員として行動する自立した消費者の育成のための効果的な消費者教育の方策として、実践的な消費者教育の実施が喫緊の課題となっている。(平成30年2月20日 若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議決定より引用)
【政策課題(大項目)】 実践的な消費者教育の推進【政策課題(中項目)】 消費者教育教材の開発、手法の高度化
【現状】データ消費者教育の推進に関する基本的な方針 平成30年3月20日に閣議決定により変更された基本方針においては、成年年齢の引
下げを見据え、「若年者への消費者教育」を当面の重点事項として位置づけ地方公共団体における「消費者教育推進計画」の策定(平成30年4月1日時点)
47都道府県、18政令市策定
地方公共団体における「消費者教育推進地域協議会」の設置(平成30年4月1日時点)
47都道府県、18政令市策定
教育委員会が消費生活センターと連携して実施する取組の状況 都道府県、政令指定都市、市・区では、学校への情報提供や専門家の派遣等の取組を実施している割合が高いが(30%~60%)、町・村では10%未満であり、未実施が50%超(※1)
教育委員会が消費生活センターに期待する役割 「学校や社会教育施設等への情報・教材の提供」が67.0%、「学校や社会教育施設等への専門家の派遣」が47.8%。
地方消費者行政推進交付金を活用して消費者教育を行ったことがある教育委員会の割合
10%未満にとどまる(平成28年度値:8.3%) (※2)
成年年齢の引下げを踏まえ、新たに取組を新規・拡充した又は実施する予定がある教育委員会の割合
約4%(※3)(実施することとした取組がある:0.8%、今後実施予定:3.7%)
(※1)文部科学省「平成28年度消費者教育に関する取組状況調査」 図11 (※3)同上調査 図22(※2)同上調査 図13 12

【現状】データ成年年齢引下げを踏まえ、新規・拡充して実施することとなった取組はないと回答した教育委員会の割合
94.2%(※4)
消費者教育コーディネーターの設置 19府県・13政令市に設置(※5)消費者教育のコーディネートを行う人材・機関等がいる・あると回答した教育委員会の割合
都道府県、政令指定都市では5割程度であるのに対し、町・村は10%未満(※6)(都道府県:55.6%、政令指定都市:44.4%、市:20.5%、区:38.5%、町:9.5%、村:3.3%)
教職員対象の研修において消費者教育に関する内容を扱っている教育委員会の割合
10.5%(「今後実施予定」と回答した教育委員会は1.1%)(※7)
消費者教育に関する研修について、他機関が主催する研修に教職員を派遣している教育委員会の割合
平成28年度は37.1%。22年度は26.8%、25年度は31.4%であり、他機関の研修への派遣が増える傾向にある。(※8)
消費者教育に特化した教職員向け研修の対象の割合 小学校(71.4)、中学校(71.4%)の教職員が最も多く、高等学校の教職員向けの研修は5割に達しない(46.4%)(※9)
高校生向け消費者教育教材「社会への扉」を活用した授業の実施 平成30年度には、全国の2144の高校等(全国の約38%)で実施。※平成29年度には、徳島県内の全ての高校等(全56校、約6,900人)において実施
スマートフォンを利用してインターネットでニュースを見る若年者(20歳代以下の割合)
20歳代で70.7%、15~19歳で54.8% (50歳代は38.0%、60歳台は14.0%)(※10)
消費者ホットライン188の認知度 消費者ホットライン「188」を知っていたと回答した割合は、15~19歳で4.9%、20~24歳で4.3%(全体で6.6%)(※11)
(※4)文部科学省「平成28年度消費者教育に関する取組状況調査」 図34 (※10)平成29年版消費者白書 図表Ⅰ-3-1-17(※5)消費者庁「平成30年度 地方消費者行政の現況調査」 (※11)消費者庁「消費者意識基本調査」(平成29年11月実施)(※6)文部科学省「平成28年度消費者教育に関する取組状況調査」 図13(※7)同上調査 図37(※8)同上調査 図38(※9)同上調査 図40
⇒【課題】①教育委員会と消費生活センターとの連携の促進 ②地方公共団体における地方消費者行政強化交付金の消費者教育への活用③地方公共団体における消費者教育コーディネーターの育成・配置 ④学校における実践的な消費者教育の実施⑤地方公共団体(教育委員会を含む。)における教員の指導力向上のための取組の促進 ⑥インターネット情報を活用した若年者への情報発信
13

【エピソードベース】 (政策課題(大項目)) 実践的な消費者教育の推進→(政策課題(中項目)) 消費者教育教材の開発、手法の高度化→(政策手法) 高校生向け消費者教育教材「社会への扉」等を活用した実践的な消費者教育の実施、消費者教育教材の開発、実務経験者の学校教育現場での活用、教員の養成・研修等
【エビデンスベース】 (政策課題(大項目)) 被害に遭わない、合理的意思決定のできる自立した消費者の育成→(政策課題(中項目))全国の高校での(「社会への扉」等を活用した)実践的な授業の実施→(政策手法)①地方公共団体における消費者行政部局と教育委員会との連携、②教員の指導力向上、③学校教育現場で
の外部人材の活用、④消費者ホットライン188の認知度向上
【エビデンス(国内)】・地方公共団体における消費者行政部局(消費生活センター)と教育委員会の連携が不十分・国からの交付金の消費者教育に関する活用度が低い・成年年齢引下げを見据え特に消費者教育に取り組む教育委員会が少ない・消費者教育コーディネーターを配置している地方公共団体が少ない・地方公共団体における教員の指導力向上のための取組(消費者教育に関する内容の研修実施等)が少ない・若年者への情報発信として、インターネットによる情報発信が有効
消費者庁HP、政府広報などインターネットを活用した消費者ホットライン188の周知
「社会への扉」等の活用について地方公共団体(教育委員会を含む。)への働き掛け
被害に遭わない、合理的意思決定のできる自立した消費者の育成
(若年者における消費者被害の防止・減少)消費者教育コーディ
ネーターの育成・配置について地方公共団体への働き掛け
地方公共団体における消費者行政部局と教育委員会との連携(全県的な学校における消費者教育の推進に係る取組の推進)
授業成果の提供(ヒアリングやアンケートの実施)
関係省庁への提言
消費者教育コーディネーターの要件の検討・提示
消費者行政強化交付金の活用促進
地方公共団体職員向けコーディネート機能強化研修の実施
消費者教育コーディネーターの活用に関する事例の提供
授業実施手法の改善
全国の高校で「社会への扉」等を活用
各省庁における提言を踏まえた対応
地方公共団体におけるコーディネート機能強化
消費者行政強化交付金の交付【予算】20億円(令和2年度)
全国の高校での「社会への扉」等を活用した実践的な授業の実施
【47都道府県】
教員の指導力向上
学校教育現場での外部人材の活用
消費者ホットライン188の認知度向上
「若年者への消費者教育分科会」における教員の指導力向上のための方策の検討
消費者教育推進会議(若年者への消費者教育分科会を含
む)の運営
「社会への扉」の作成(作成済み)
消費者ホットライン188の運用
「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」の推進
消費者庁と文部科学省との連携による地方公共団体等への働き掛け(通知発出、校長会など説明会の活用)
消費者ホットライン188の啓発媒体の普及
(2020年度)
【予算】(※注)20.3億円(令和2年度予算案)、28.3億円(令和2年度要求額)、22.2億円(令和元年度予算)
アウトプット 初期アウトカムアクティビティ 中期アウトカムインプット
最終アウトカム
特別支援学校での実施手法の検討・確立
コーディネーター会議の開催
効果的な実施手法の検証・確立
(※注)本事業に係る予算額は、正確には【予算】に記載する金額の内数となる。 14

【復興庁】伴走型人材確保・育成支援モデル事業 ロジックモデル
インプット アクティビティ アウトプットアウトカム(短期)
アウトカム(長期)
インパクト
【課題】東日本大震災の被害の大きい地域では、被災や人口流出により人口が減少している中、十分な労働力が確保できず復興の妨げになっている地域や産業がある。
伴走型人材確保・育成支援モデル事業
平成29年度:3.1億円
平成30年度:3.2億円
平成31年度:3.0億円
○学生が被災地企業の経営課題に経営者と協働して解決に取り組む「長期滞在・課題解決型インターンシップ」の実施
○被災地企業の課題解決のために定期的に訪問する者を増加させるためのワークショップ等(関係人口増加プロジェクト)の実施
左記アクティビティを踏まえた事業の実施。
長期滞在・課題解決型インターンシップ
参加学生平成29年度:198名平成30年度:265名平成31年度:318名
関係人口増加プロジェクト
平成30年度実施回数:6回参加者数:102名
令和元年度実施回数:7回参加者数:148名
受入企業、学生参加者の課題解決への習熟・理解
【指標】・課題解決に係る受入企業、学生の理解度
・人材確保手法に係る受入企業の理解度
・事業における課題解決を踏まえたインターンシップに係る学生の満足度
地域のNPO団体等(復興・創生インターンシップにおける地域コーディネート機関等に従事)の育成
【指標】・学生及び企業における地域団体への評価
ノウハウの獲得による課題解決の自走化
【指標】・事業終了後における受入企業のノウハウの活用度、満足度
複数の企業が雇用管理や経営改善の切磋琢磨を行い、地域における先進グループを形成・拡大しながら当該地域全体の人材力を強化し、「人と企業が集い、育ち、地域が活性化するモデル」を実現
【指標】・地域における先進グループの形成状況
地域企業等への就職
【指標】・事業終了後における学生・参加者の地域企業等への 就労状況
地域への訪問
【指標】・事業終了後における参加者の被災地への訪問又は関わりの状況
・参加者の地域への満足度
地域支援事業の自走化
【指標】・事業終了後におけるNPO団体の地域支援事業のフォローアップ状況
・自走化された地域支援事業の満足度
15

設定指標に対する調査方法
指 標 調査対象 調査内容 調査時期
課題解決に係る受入企業、学生の理解度受入企業 「インターンシップ・プログラムは適切なものだったと思いますか?」 実施中
学生 「受入企業が持つ課題について理解できたか」 実施予定(単年度)
人材確保手法に係る受入企業の理解度 学生 「本事業を踏まえ、人材確保手法を理解できたか」 実施予定(単年度)
事業における課題解決を踏まえたインターンシップに係る学生の満足度
受入企業、学生 「課題の解決を前提としたインターンシップに満足できたか」 実施予定(単年度)
学生及び企業における地域団体への評価 受入企業、学生 「地域コーディネート機関のフォローアップに対し評価できたか」 実施予定(単年度)
事業終了後における受入企業のノウハウの活用度、満足度
受入企業 「成果発表会等で得た課題解決に係るノウハウを利用しているか」 実施予定(本事業終了後)
事業終了後における学生・参加者の地域企業等への就労状況
学生「事業終了後、被災地企業、地域コーディネート機関へ就職した者、あるいは関係人口となった者がどれくらいいるか」
実施予定(本事業終了後)
事業終了後における参加者の被災地への訪問又は関わりの状況
学生、関係人口増加PJ参加者
「事業終了後、被災地へ訪問したか」 実施予定(本事業終了後)
参加者の地域への満足度関係人口増加PJ参加者
「被災地域(企業)の取組みについて満足しているか」 実施予定(単年度)
事業終了後におけるNPO団体等の地域支援事業のフォローアップ状況
地域コーディネート機関
「事業終了後も本事業、あるいは類似の事業を継続して取り組んでいるか」 実施予定(本事業終了後)
自走化された地域支援事業の満足度地域コーディネート機関
「本事業について、事業内容に満足しているか」 実施予定(本事業終了後)
地域における先進グループの形成状況地方公共団体、商工会
「人材確保に向けた地域グループが形成されているか」「地域全体の企業のうち、その地域グループに参加している企業はどれくらいか」
実施予定(本事業終了後)
16

0【総務省】公衆無線LAN環境支援整備事業現状把握 政策目標 初期アウトカムアウトプット(実績) 中期アウトカムインプット/アクティビティ
○災害時、電話回線が輻輳等のため、利用できない場合、住民や旅行客が災害情報を受発信できないおそれ(例:東日本大震災は輻輳が2日間続いた)
○ 旧 規 格 ( 2.4GHz帯)のWi-Fiは周波数帯の逼迫が発生しており、新規格(5GHz帯)のWi-Fiによる電波の有効活用の必要
○電波政策2020懇談会報告書(総務省)利便性の高いWi-Fi環境の整備のため、電波利用料で支援することが妥当と結論○「日本再興戦略」20162020年までに、主要な観光・防災拠点における重点整備箇所について、国が作成する整備計画に基づき、無料Wi-Fi環境の整備を推進
【公衆無線LAN環境整備支援事業】○概要避難所等の防災拠点や被災場所として想定され災害対応の強化が必要な公的拠点におけるWi-Fi環境の整備を行う地方公共団体に対し補助
○予算(当初予算額・億円)
○事業主体普通地方公共団体・第三セクター
○補助率1/2(財政力指数0.8以下又は条件不利地域)2/3(財政力指数0.4以下かつ条件不利地域)
○補助対象無線アクセス装置、制御装置、伝送路設備、非常用電源等
H29年度 H30年度 R元年度
31.9 14.3 11.8
○整備箇所数H29年度 849箇所H30年度 1,196箇所
○情報交換会・補助金説明会回数H29年度 2回H30年度 7回
○事例集の作成H29年度 6事例H30年度 13事例
○調査研究・「熊本地震における被災地のWi-Fi利用状況等に係る調査研究」(H29)・平成30年に発生した各種災害での活用状況を調査(H30)
【防災時の利活用】熊本県の事例(H29)○くまもとフリーWi-Fのアクセスは震災後急増・約5,000回(4/16本震発生時)※震災前は約1,800回○災害時の情報収集や通信手段として「役立った」との回答が約9割を超える。
平成30年度に発生した災害で避難所等で開放されたWi-Fi環境が有効活用された事例(北海道苫小牧市、広島県大崎上島町、愛媛県大洲市)・市町担当者から、災害時のWi-Fiの開放状況やアクセスログ数の増加状況、携帯キャリアの通信障害の有無等について紹介
○防災拠点等におけるWi-Fi環境の整備済み箇所数(実績)H29年度 20,980箇所H30年度 23,896箇所(目標)R元年度 30,000箇所
○防災拠点等におけるWi-Fi環境の新規整備箇所数(実績)H29年度 2,860箇所H30年度 3,100箇所(目標)R元年度 6,000箇所
【文部科学省】学習指導要領改正(H29.3)小学校において、プログラミング教育が必修化されるなど、今後の学校活動での積極的なICT活用を推進【目標:普通教室の無線LAN整備率100%】
教育ICT化に向けた環境整備5か年計画(2018~2022年度)普通教室での無線LAN整備を含め学校のICT環境整備に必要な経費について地方財政措置
○防災等に資するWi-Fi環境の整備計画(総務省)平成31年度までに約3万箇所の整備目標数を設定
【H28公開プロセス】観光・防災Wi-Fiステーション事業について、「事業目的を防災、観光の二つに明確に分けて制度設計すべき」との有識者の指摘
【観光庁】・訪日外国人旅行者数3,119万人(2018年)と増加・スマートフォンを活用した旅行スタイルへの変化が顕著であり、公衆無線LANの設置が一定の効果あり
・観光振興事業(国際観光旅客税財源)・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業(両事業 令和元年度~)観光地の公衆無線LAN等を整備
【00000JAPAN】(ファイブゼロジャパン) (無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)が主導)大規模災害時、災害情報の収集やメール・SNS等を活用した安否確認などを支援するために、ドコモ、au、softbank等の被災地のアクセスポイントを災害用統一SSID「00000JAPAN」を追加し、さらにID、パスワードの入力(認証)を不要とすることで、契約者以外でも公衆無線LANを利用できる取組 17

○2000年から2015年の15年間で、地方(東京圏以外)の若者人口(15~29歳)が約3割(532万人)減少。出生数も約2割(17万人)減少
地方圏においては、人口減少や高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題に直面
○都市住民の多くの者が、移住以外の方法で農山漁村地域と関わりを持ちたいと考えており、観光やイベント参加等に関心がある者のほか、地域活動(農作業や祭り等)への参加や地元の人との交流のための滞在、二地域居住を希望する者もそれぞれ1割程度存在
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる「関係人口」が地域づくりの担い手となることに期待できる。
●「関係人口」が持つ、地域づくりに対して貢献したいという気持ちを受け止めるため、地方公共団体は自らの「関係人口」の認識及び地域と継続的なつながりを持つ機会の提供が重要だが、「関係人口」と継続的につながる機会を構築する手法は未確立
●国は、上記の背景を踏まえ、地方にとって緊急性が高い取組である「関係人口」の創出・拡大に向け、地域外の者が地域と継続的につながる機会を構築する手法を検証・確立し、全国へ情報発信することが必要
●市町村は「関係人口」を募り、その取組に賛同する者との関わりを継続する仕組みを構築する必要
●都道府県は、情報提供等の支援や、広域的な観点から「関係人口」を創出する取組を行う必要
現状・課題
【総務省】関係人口の創出・拡大
○全国各地において、地域と多様に関わる「関係人口」が地域課題の解決や地域経済の活性化に貢献
インパクト
○関係人口の創出・拡大に取り組む地方公共団体数:409団体(H29.12.1)○目標値:第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に向けて検討中
アウトカム
○「関係人口」と継続的なつながりを持つ機会の提供等を行う自治体をモデル団体として採択し、事例創出
○地方公共団体向けフォーラム等による関係人口の取組の周知 等
○モデル事業実施団体数(重複含む)(実績)H30年度:30団体、R元年度:44団体○地方公共団体向けフォーラム参加地方公共団体数(予定)R元年度:調査中
アウトプット
関係人口創出・拡大事業(H30年度予算額:約2.5億円、R元年度予算額:約5.1億円)
インプット
アクティビティ
18

現状と課題
インパクト人口減少・少子高齢社会における地方行政体制の確立
◎人口減少社会において、高齢化や人口の低密度化等により行政コストが増大する一方で資源が限られる中で、行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供するためには、あらゆる行政サービスを単独の市町村だけで提供する発想は現実的ではなく、各市町村の資源を有効に活用する観点からも、地方公共団体間の連携により提供することを、より柔軟かつ積極的に進めていく必要。
◎このため、連携中枢都市圏の形成、条件不利地域等における都道府県と市町村の連携、三大都市圏における水平・相互補完的、双務的な連携等、地域の実情に応じた多様な広域連携が重要。
◎全国において多様な広域連携の取組を促進するとともに、国において全国各地の先進事例の知見を収集するため、「新たな広域連携促進事業」を実施。当該事業で得られた知見についての情報提供を通じ、取組の横展開を促進。
◎当該事業の成果として、広域連携に取り組む地方公共団体の数は着実に増加。一方で、現時点では、各地域における取組は、中心市の施設の広域的な利用等の比較的連携しやすい取組が中心となっているほか、市町村との連携に積極的に取り組む都道府県や三大都市圏において広域連携に取り組む自治体は少数。
◎今後、人口減少・少子高齢化は、三大都市圏も含めて全国的にかつ加速度的に進行。こうした中でも持続可能な形で行政サービスを提供していくためには、行政需要や経営資源の長期的な変化の見通しの把握、地方公共団体間での資源の共有、こうした取組の全国展開が必要。
インプット新たな広域連携促進事業
(令和元年度予算額:約2.0億円)
◎新たな広域連携促進事業の実施(H26年度~)
「連携中枢都市圏の形成等に向けた取組」(43件)「都道府県と市区町村との連携に向けた取組」(17件)「三大都市圏における水平・相互補完的、双務的な役割分担の取組」(10件)
◎各取組により得られた知見についての情報提供(連携中枢都市圏の取組団体等に対する個別の働きかけ、連携中枢都市連絡会議や総務省のHP等における情報提供)
アクティビティ
アウトプット
直接アウトカム
【総務省】新たな広域連携促進事業
◎行政需要や経営資源の長期的な変化の見通しの地域(首長、議員、住民等)における共有
◎専門人材の広域的な確保・育成・共有等の地方公共団体間で資源を共有する取組の全国展開
◎連携中枢都市圏等における利害調整を伴うため合意形成が難しい行政課題の解決
◎都道府県と市区町村との連携、三大都市圏における広域連携の取組の拡大
◎連携中枢都市圏の形成の進捗⇒32圏域が形成済み(H31.4.1時点)
◎地域の実情に応じた多様な広域連携の展開
最終アウトカム持続可能な行政サービス提供体制の構築
19

【法務省】地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施を通じた医療観察対象者の社会復帰の促進
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰の促進
R1年度政府予算
総額329百万円
インプット(資源) アクティビティ(活動) 中期アウトカム
(成果目標)初期アウトカム(成果目標)
インパクト(社会への影響)
ケア会議を通じた関係機関相互間の連携等により,医療観察対象者(以下「対象者」という。)に対する地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施を確保し,その者の社会復帰の促進を図る。
測定指標
処遇終了後も継続的な援助等を受けることのできる環境の整備
対象者の病状の改善,社会生活能力の向上等
精神保健観察の適切な実施・生活状況等の見守り・必要な指導等
ケア会議の実施・処遇実施計画の作成・見直し
障害福祉サービス事業者等への説明の実施・対象者やその援助の実情に関する理解の促進
対象者が指定通院医療機関による手厚く専門的な医療を受けることができる
対象者が障害福祉サービス事業者等による必要な援助を受けることができる
KPI③
KPI④
精神保健観察事件年間取扱人員に占める再他害行為があった者の数の割合
アウトプット(活動目標)
ケア会議における情報共有,処遇方針の統一・障害福祉サービス事業者等の関係機関による連携した援助の実施
年末現在係属中の対象者(開始から1年以上経過している者に限る。)に対する地域の関係機関による援助に関する評価が良好である又は以前より改善した割合
障害福祉サービス事業者等の受入れに向けた不安の解消・医療観察制度に協力する障害福祉サービス事業者等の増加
継続的な通院の確保・指定通院医療機関による必要な医療の実施
KPI①
KPI②
KPI①
KPI②
障害福祉サービス事業者等に対する説明の実施回数
新たに医療観察制度に協力することとなった障害福祉サービス事業者等の数
KPI③
KPI⑤
KPI⑤
年末現在係属中の対象者(開始から1年以上経過している者に限る。)に対する通院状況に関する評価が良好である又は以前より改善した割合
KPI⑥
KPI⑦
KPI⑥
精神保健観察終了者に対する病状・社会生活能力等に関する評価が終了時に良好である又は以前より改善した割合
KPI⑦
精神保健観察終了者に対する処遇終了後の環境の整備に関する評価が終了時に良好である又は以前より改善した割合
KPI④
20

【法務省】SNS(LINE等)を活用した周知・広報
国の人権擁護活動を含む人権に関する情報への接触機会の増加
・SNS利用者における国の人権擁護活動の認知度向上
・人権関係キーワードによる検索数の増加
・人権関係HPのアクセス件数の増加
等
対象者に理解されやすい投稿(内容の平易さや適切な画像の使用等)の実施
国の人権擁護活動に対する認知・理解が促進されるとともに,人権問題についての国民の関心が高まる。
R元年度政府予算
14,007千円人権関係イベント,相談窓口等に関する投稿内容の充実
インプット(資源)
アクティビティ(活動)
アウトプット(活動目標)
アウトカム(成果目標) インパクト(社会的な影響)中間アウトカム
20代から40代において,SNS(LINE等)への接触時間が増加傾向にあるが,これを広報媒体として十分活用できておらず,SNSの普及度に比して,SNSを通じて人権相談窓口を認知したものが少ない。そこで,SNSを活用した広報活動を実施し,人権相談窓口や人権関係イベント等の取組の周知を図ることにより,国の人権擁護活動等に対する接触機会を増加させ,認知度の向上を図るとともに,人権問題についての関心を喚起する。
・投稿形式別インプレッション(リーチ)数(twitter,facebook)KPI①
・twitterフォロワー数・facebookフォロワー数・LINEお友達数
KPI⑥
・SNSアカウントの認知度KPI⑦参考
測定指標
SNSアカウントの周知・広報の実施(スタンプの配付,HP等による周知)
○国の人権擁護活動等の認知度は,年代別に見ると20代~40代において低くなる傾向。○20代~40代が接触するメディアの上位はテレビとスマートフォンが突出(メディア定点調査2019・博報堂DYメディアパートナーズ)。○スマートフォンでの主要な利用形態はSNSであり,スマートフォンの普及とともにSNSの利用も増加。国民の代表的SNSの利用率は71.2% (H29情報通信白書) 。
SNSアカウントにおける効果的なトップページ,背景(キャラクターの使用や適切な色使い)等の作成 人権擁護局SNSアカウ
ントの認知度の向上
効果的に到達させる投稿手法(適切な投稿形式や投稿の時間等)の確立
投稿が閲覧される可能性の向上
・リツィート数・シェア数(facebook)・シェア数(LINE)
KPI⑤・投稿形式別の高評価数(twitter,facebook)・投稿形式別のリンクのクリック数(LINE)
KPI②
KPI➀
初期アウトカム
リツイート,シェア等を通じた人権擁護局SNSユーザー以外への投稿内容の拡散
人権擁護局SNSユーザーの増加
KPI④
・スタンプダウンロード数・スタンプ利用回数・SNSアカウント周知用HPへのアクセス件数 ・累計インプレッション数(twitter)
・累計リーチ数(facebook)・人権擁護局HPへのアクセス件数・人権関係キーワードの検索動向
KPI⑧
・国の人権擁護活動の認知度・国の人権擁護活動の理解度(P)・人権相談窓口の認知度
KPI⑨
KPI②
KPI⑤
KPI⑦
KPI⑥
KPI⑧ KPI⑨
SNSアカウントへの接触機会の増加
SNSアカウントの誘因力の向上
・SNSアカウントの好感度KPI③
KPI③
KPI④
21

【財務省】財政教育プログラムのロジックモデル
インプット/活動
受益と負担の両面性(トレード・オフ)を理解し、多面的な見方の重要であることを感じる。
中間アウトカム 最終アウトカム
公共サービスと集めるお金(税金)、足りないお金(借金)との関係を理
解する
財政教育プログラムに満足する
多様な意見の集約のための民主主義的過程の重要
性を認識する
教材
運営カリキュラム
講師・財務局職員・学校の教員
学校による指導案作成
学校による事前学習
財政/税制パンフレット
動画教材
グループワーク教材・タブレット端末・ワークシート
座学教材
アドバイザーの支援
身近な公共サービスや公共施設にどういったものがあるのかを理解する
日本の財政の現状を理解する
アウトプット
日本の財政に興味を持つ
財政教育プログラムの実施
財政教育プログラムで学んだことを周囲に伝える
社会の課題を自ら考えなくてはならない問題だと
感じる
財政教育プログラムをきっかけに、日本の将来について考え、判断する知識が育まれる
22

・原型炉の核融合運転による発電が行われ、経済的実現性が検証される。
・核融合発電が社会に受け入れられるに足る安全性・信頼性を得る。
・核融合発電の導入を前提としたエネルギーミックスの将来像が示される。
・実用段階の核融合炉の建設プロジェクトが民間主導の形で企画される。
幅広いアプローチ(BA)活動等ロジックモデル
○社会経済活動の基盤として、持続可能な開発目標に資する安定的かつ大規模なエネルギー供給源が求められる。
○地球温暖化等の気候変動対策として、脱炭素型のエネルギー転換が必要。
○安全性の面にも配慮した、原子力発電の代替エネルギー源が要求されている。
(現状)
「幅広いアプローチ(BA)活動(フェーズII)の推進」
R2年度概算要求額 7,292百万円(参考資料1)
(インプット)
(1)先進超伝導トカマク装置JT-60SA の建設と利用・JT-60SAで、高圧力プラズマの生成及び制御のための研究開発を実施し、安全性・信頼性・経済性を追求。また、ITERの稼働に向けた大型超伝導トカマクの制御技術を先んじて開発。そのために加熱装置やダイバータ等の所要機器を整備。・ITERの運転を先導する人材を育成。大学等のオンサイトラボを整備予定。
(2) 核融合中性子源用原型加速器の建設と実証(IFMIF/EVEDA)・構造材料の開発に向けて、核融合炉で発生する中性子照射と同等の照射が可能な試験施設の整備が必要であるため、その前提となる工学実証・工学設計活動を実施。
(3)国際核融合エネルギー研究センター(IFERC)事業等・ブランケットを用いて三重水素を十分に生産するため、中性子増倍材、三重水素増殖材等の研究開発を実施。・ITERの機器製作やJT-60SAの建設で培った技術を核融合原型炉に向けて維持・発展させるため、概念設計活動を実施。・ITERやJT-60SAの効率的な運転等のため、スパコンを用いてプラズマの挙動、材料特性の変化等のシミュレーションを実施。・日本でITERの実験が可能な遠隔実験センターに必要なシステム開発等を実施。
(アクティビティ)
○核融合プラズマの制御:超高温プラズマを長時間安定に制御することが必要。また、経済性を高めるためには、プラズマの高圧力化が必要。○構造材料:構造材料は、DT反応により発生する高い中性子照射への耐久性、低放射化特性を有する構造材料の開発・評価が不可欠。○ブランケット:三重水素の生産性を向上し、炉の稼働及び反応の維持に必要な三重水素を確保。また、三重水素の取扱い技術の開発も必要。○人材確保:ITER機構における日本人数が加盟極中下位層に位置。核融合炉というプラント機器の製作及び建設・運用をする技術・ノウハウを産業界が維持できるようにすることが必要。
(課題)
・ITERや核融合原型炉建設に資するデータ・技術の取得及び試験機器の建設
経済・社会等の変化(誰が/何が、どう変化することを目指しているか)
・ITERがプラズマ運転を開始する。
・ JT-60SAでITERの運転シナリオ{高閉じ込め(Hモード)運転、ディスラプション回避等}が開発される。
・原型炉の工学設計に向けた国際社会の方針(国際協調or競争等)が定まる。
・原型炉に求められる規制に関する議論を行う枠組みが作られる。
・核融合中性子源の建設が開始される。
・ITERで核融合反応を人類が初めて制御する。
・原型炉の建設に取りかかる。
・JT-60SAによる安全性・信頼性・経済性の検証が完了する。
・原型炉に必要な材料の開発・評価が完了する。
・海水からの燃料回収技術が確立する。
(中期アウトカム)2030年代
(アウトプット)
(長期アウトカム)21世紀中葉
(初期アウトカム)2025年から数年以内
・持続可能な開発目標に資する安定的な脱炭素型エネルギー供給源の獲得及びエネルギー自給率の向上。→エネルギー輸入コストの低減(-176億US$2000/yr)
・温室効果ガスの排出量削減による気候変動対策や有限資源である化石燃料使用量の削減により、日本の国際的地位の確立に貢献。→温暖化緩和対策費用の低減(-56~+14億US$2000/yr)
⇒電力価格の低下(-10%)
※環境対策の進捗については他国との比較も必要※電力価格については様々な外的要因にも影響されるため要検討
(出典:RITE「世界のエネルギーシナリオにおける核融合エネルギー導入ポテンシャル評価」成果報告書)
(インパクト)
直接コントロールできる部分
○JT-60SAの運転時間・放電回数・加熱パワー・加熱維持時間○原型加速器の運転回数(重陽子ビームパルス発生回数)○スパコンの稼働率○材料開発のアクティビティ(試験期間、サンプル数、測定項目等)
○JT-60SA、シミュレーション活動等に係る査読付論文数、受託タスク等
○原型加速器による重陽子ビームのエネルギー、電流、持続時間
○JT-60SAの実験に参加するITER機構や大学等からの共同研究者数
○ITER機構の日本人職員数
○原型炉による発電単価と、実証炉or商用炉におけるブレークイーブン価格見込み
○核融合発電の理解に対する国民へのアンケート調査結果
○エネルギーミックスに占める核融合発電の構成比見通し
○民間企業等から実用段階の核融合炉への投資額
○ITERで核融合運転前に達成したQ値(プラズマ温度及び閉じ込め性能(プラズマ密度・閉じ込め時間))、β値(プラズマ圧力/磁場圧力)とそれらの維持時間
○JT-60SAのQ値、β値とそれらの維持時間
○構造材料の耐久性(中性子照射量に対する材料強度等)
○TBMにおける中性子照射量と三重水素生産量の比
○海水からのリチウム6回収速度、コスト
○ITER機構の日本人職員数
○CO2排出量の推移
○温暖化緩和対策費用の推移
○エネルギー輸入コストの推移
○エネルギー自給率の推移
○電力価格の推移
【政府の取組】核融合発電の実用化に向けた研究開発に係る費用を負担する。
核融合発電
【政府の取組】実証炉or商用炉の建設等に係る費用の補助を行う。
※赤字は主にBA活動等のみで達成を目指すもの
【文部科学省】幅広いアプローチ(BA)活動等ロジックモデル※ロードマップ
23

・ITERでトカマク本体の組立・据付を開始する。
・ JT-60SAのトカマク本体の組立が完了する。
・国際核融合エネルギー研究センターが六ヶ所村に整備される。
・原型炉の基礎的な概念設計が行われる。
・核融合中性子源の原型加速器で大電流重陽子ビームを発生させる。
参考(フェーズⅠアウトカム)
2020年
○JT-60SAのトカマク本体の組立工事の進捗
○国際核融合エネルギー研究センターで行われるシミュレーション活動等に係る査読付論文数等
○原型加速器による重陽子ビームのエネルギー、電流、持続時間
○ITER機構の日本人数
要素技術 我が国の研究開発概況 他極の研究開発概況 我が国が取るべき戦略
(1)炉設計・ITERのCDA,EDAの頃から設計に取り組む。IFERCでは原型炉設計活動として、基礎的な原型炉の概念設計を実施し、原型炉に向けた各機器のR&Dの方向性を提示。
・欧州は日本とともにIFERCで基礎的な原型炉の概念設計を実施。
・中国は独自に核融合工学試験炉の工学設計に着手。
・早期の発電実証に向けてITER及びBAの成果と既存技術を最大限活用した経済的実現性の高い原型炉プラントの概念設計を完了する。
(2)超伝導コイル・ITERではTFコイルとCSコイル導体を、JT-60SAではEFコイル及びCSコイルを製作することで主要3種のコイルを網羅。
・超伝導コイルのための高強度の構造材開発をNIMSと共同で実施。
・ITERのTFコイルは日本、欧州、EFコイルは欧州、中国、ロシア、CSコイルは米国が調達。
・JT-60SAのTFコイルは欧州が調達。・原型炉までは国内に需要がないため、蓄積した技術が原型炉の建設に引き継がれるようにする。
(3)ブランケット
・ITERのTBM計画では2つあるポートの片方のポートマスターを務めるべく調整中。WCCBでの実施に向けて、工学試験棟の建設等を推進中。
・IFERCでは原型炉に向け、ブランケット設計検討、構造材料、中性子増倍材、トリチウム増殖材等の研究開発を実施。
・資源確保に向けた新たなBe精製技術を開発。
・TBM計画には、欧州、中国、韓国、インドがそれぞれ異なる方式のTBMを検討中。(ポート減少に伴い調整中)
・欧州はIFERC等でブランケット材料の開発、資源状況の調査を実施。
・原型炉に向けてTBM計画の着実な実施。・核融合炉材料資源 (Be,Nb,W,Li)確保への道筋を付ける。
(4)ダイバータ・ITERではフルタングステンの外側ターゲットを製作、JT-60SAではカーボンダイバータを製作予定。
・IFERCでは米国HFIRを利用して原型炉用ダイバータ材料研究を実施。
・ITERでは日本、欧州、ロシアがダイバータを調達。・欧州のWEST装置でタングステンダイバータの実機試験を実施・欧州、米国、中国で原型炉用ダイバータ材料開発を活発に推進。
・ITER及びJT-60SAのダイバータを計画的に製作。・原型炉用ダイバータ開発の推進。
(5)加熱・電流駆動システム
・ITER、JT-60SAともに、高周波加熱装置、中性粒子入射加熱装置の両方を調達。
・中性粒子入射加熱装置は、原型炉に向けてイオン源の改良、中性化効率の向上に向けた研究を実施。
・高周波加熱装置は、原型炉に向けて更なる高周波数化、複数周波数化の研究を実施。
・ITER-NBIは日本と欧州のみ調達。・ITER-ECRFは日本、欧州、ロシアがジャイロトロンを、欧印が電源を、日欧がランチャーを、米国が伝送系を調達。
・JT-60SAのNBIは日本のみ、ECRFは日本と欧州で調達。
・NBTFでの試験の実施、ITER-NBI、ECRFの調達、JT-60SAのNBI、ECRFの調達を実施。
・原型炉に向けた改良を継続。
(6)理論・シミュレーション
・IFERC-CSCのJFRS-1でシミュレーションコードの開発・利用・改善を継続中。
・欧州は独自の計算機資源を確保。今後、日本との協働調達も視野。米国は、SciDACプロジェクトにより核融合シミュレーション研究を推進。
・JFRS-1後継機の導入とITER実験データベース構築。・ITER及び原型炉のためのシミュレーション研究と機械学習等を用いた大規模データ解析技術開発の推進。
(7)炉心プラズマ・JT-60SAの組立完了により、Lモードでのプラズマ制御が可能になり、フェーズⅡ及びその後の機器整備を通して、ITERの運転期及び原型炉を見据え、Hモードプラズマ制御実現を目指す。
・欧州はJET、WEST、ASDEX-U等、米国はDIII-D、中国はEAST、韓国はKSTAR、インドはSST-1、ロシアはT-10でそれぞれプラズマ運転を実施。
・JT-60SAで大学等との連携によりITERに貢献出来る実験と人材育成を実施。
(8)燃料システム・三重水素取扱技術を、ITERのDS開発及びIFERCのJETダスト分析等を通して開発。
・海水等からのリチウム回収に向けた研究開発が進展。
・ITERの燃料処理設備は、プラズマ排ガスからの燃料精製は米国、燃料の同位体分離精製は欧州、燃料貯蔵は韓国が担当。
・欧州はリチウム6の濃縮法に関する既往技術の調査に着手。
・ITERのDS調達の計画的な実施。・原型炉規模の三重水素取扱技術開発にむけた大型トリチウム取り扱い施設の設計・開発を推進。
・外部資金も活用したリチウム回収の研究開発を推進。
(9)核融合炉材料
・IFMIF/EVEDAを通して、核融合中性子源A-FNSに向けた技術基盤を確立し、材料に対する中性子の影響評価への道筋をつける。
・IFERCでは米国HFIRを利用した中性子照射試験を着実に実施。
・欧州はスペインに核融合中性子源IFMIF-DONESの建設を計画。
・ 欧州、中国では、独自材料の照射データベース拡充に向け各国材料試験炉を利用した中性子照射試験を大規模に実施。
・IFMIF/EVEDAの着実な実施。・A-FNS構想に向けた政策論、財源論の検討。・日本の材料開発の優位性確保にむけ、既存炉(米国HFIR等)を利用した中性子照射試験による照射データベース拡充を推進。
(10)トカマク組立
・JT-60SAを通して大型超伝導トカマクの組立・据付技術を蓄積。当該技術でITERの組立・据付にも貢献予定。
・ITERの組立は、イタリアの企業を中心としたコンソーシアムと、中国の企業を中心としたコンソーシアムが実施。 ・ITERの組立・据付に貢献することを通じた技術の獲得。
要素技術戦略核融合炉に必要となる要素技術ごとに、その研究開発の概況と今後の研究開発戦略を整理した。
要素技術戦略表
24

幅広いアプローチ(BA)活動等について
BA活動等の位置付け幅広いアプローチ(BA)活動とはITER計画を補完・支援するとともに、核融合原型炉に必要な技術基盤を確立するための先進的研究開発を実施する、国会承認条約に基づく日欧の国際科学技術協力プロジェクト
実施極 : 日、欧協定 : 2007年6月1日発効(日欧いずれかが終了を提起しない限り自動延長)実施地 : 青森県六ヶ所村、茨城県那珂市事業期間:2020年(R2)3月 フェーズⅠ完了
2020年(R2)4月~フェーズⅡ(詳細は日欧協議中)
各拠点における具体的取組内容
3
2,452百万円(2,525百万円)
【青森】○ 核融合原型炉に向けた総合的取組として、以下の研究開発を実施。
(3)国際核融合エネルギー研究センター事業等
➢核融合原型炉の概念設計や技術検討➢シミュレーション研究➢ITER等の遠隔実験解析 等
スパコン 六ちゃん-Ⅱ
(2)核融合中性子源用原型加速器の建設と実証等 【青森】
全長36m
原型加速器
○ 原型炉に必要な材料の開発を行う施設の設計・建設に係る知見を獲得するため、主要機器となる原型加速器の性能実証及びターゲット系の研究開発を実施。
622百万円(536百万円)(1)先進超伝導トカマク装置JT-60SAの建設と利用
○ JT-60SA研究計画※1を踏まえ、運転・装置整備を段階的に進め、以下の目標に向け研究開発を実施。
JT-60SA
【茨城】
➢ITERではできない、経済性に優れた高圧力プラズマを追求するため、高加熱実験を実施し、原型炉に求められる安全性・信頼性のデータを獲得。
➢ITERに先立ち様々な実験データを取得し、ITERの運転開始や技術目標達成を支援。
4,217百万円(4,231百万円)
○ 平成30年度は、超伝導トロイダル磁場コイルと上側平衡磁場コイルの据付作業を完了。令和元年度は、超伝導トカマク本体の完成に向けて、本体組立及び周辺機器の製作を進める予定。
○平成30年度は、新たなスパコンの本格運用を開始。令和元年度は、原型炉における燃料供給に不可欠なベリリウムを、従来の1/100以下のエネルギーで精製する技術を開発。
○ 平成30年度は、世界初となる8系統高周波によるビーム加速に成功。令和元年度は、7月に世界最高強度の5MeV、125mAの重陽子ビーム加速に成功(従来記録は2MeV、45mA)。今後、全ての機器を完成予定。
令和2年度要求・要望額:7,292百万円令和元年度予算額 :7,292百万円
核融合原型炉・発電実証・経済性見通し
(科学的・技術的実現性) (技術的実証・経済的実現性)
実用化段階
ITER計画(実験炉)・燃焼プラズマの達成・長時間燃焼の実現 等
BA活動等・ITER運転シナリオの検討・核融合原型炉に向けた技術基盤の構築 等
BAフェーズⅡ(5年間)の目標・JT-60SAのプラズマ加熱運転・核融合中性子源の技術基盤確立・原型炉の概念設計完了等
組立てが進むJT-60SA
参考資料
25

令和元年度予算額
1,941億円の内数
市町村で行われる以下の事業について、交付する。■介護予防把握事業地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。
■介護予防普及啓発事業介護予防活動の普及・啓発を行う。
■地域介護予防活動支援事業市町村が介護予防に資すると判断する地域における住民主体の通いの場等の介護予防活動の育成・支援を行う
■一般介護予防事業評価事業介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。
■地域リハビリテーション活動支援事業地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。
【現状把握のエビデンス】
◆「健康寿命延伸プラン」において、わが国の健康寿命を2040年までに75歳以上にする目標を掲げている。2016年時点で、健康寿命は以下のとおりであり、健康寿命の延伸が必要。男性:72.14年女性:74.79年(2016年)
◆健康寿命延伸に向け、一部の科学的な実証研究では「通いの場」の必要性が指摘されている。
しかし2018年度時点で参加率は5.7%に留まっている。経済財政諮問会議において「通いの場」への参加率を2040年度までに15%にすることが明示されており、介護予防・健康づくりの推進の観点から、「通いの場」の拡充・強化が課題である。
(インプット) (アクティビティ) (アウトプット) (短期アウトカム)(長期アウトカム)事業実施市町村数
令和元年度■介護予防把握事業XXXX市町村
■介護予防普及啓発事業XXXX市町村
■地域介護予防活動支援事業XXXX市町村
■地域リハビリテーション活動支援事業XXXX市町村
※ 令和元年度の数値については、まとまり次第公表予定
○通いの場の参加率
2020年度末までに6%
2040年度末までに15%
参考:平成30年度
5.7%
健康寿命の延伸
2040年までに男女ともに3年以上延伸し、75歳以上にする。
【厚生労働省】一般介護予防事業のロジックモデル
・ 一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会⇒一般介護事業等に今後求められる機能やPDCAサイクルに沿った更なる推進方策等の検討を集中的に実施し、介護保険部会の議論に資するため、検討会を開催。エビデンスや効果検証の仕組みや考え方等についても議論。 令和元年12月13日に取りまとめを公表。
(現状・課題)
■必要性について 高齢者の筋肉は毎年1%程度減少。筋力低下が要介護につながるため、継続的に運動ができる身近な場が必要(※研究参考:葛谷雅文「老年医学における Sarcopenia & Frailty の重要性」日本老年医学会雑誌 2009; 46: 279―285)
高齢者の虚弱への入り口は「社会性」の低下にある。虚弱の予防には社会参加機会が必要(※研究参考:虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防プログラムの考案および検証を目的とした調査研究 : 平成24年度-平成26年度総合研究報告書 : 厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合研究事業)
わが国の介護予防の推進に係る評価やPDCAについては、「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」で議論され、取りまとめにおいて、今後エビデンスを構築することが求められた。
2
エビデンス■効果について 「通いの場」への参加が虚弱(フレイル)の発症リスクを半減させた研究事例(※出典:厚生労働省「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」(第3回:令和元年7月19日)
多様な予防サービスと「通いの場」等の組み合わせて実施することが参加率を高める先行事例(※H25年度 厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進事業分 「介護予防を推進する地域づくりの効果的手法に関する調査研究事業」 ※H25年度老健補助事業データを元に今年度のEBPM推進事業において行った分析)
関連する研究データ
1
26

【農林水産省】農山漁村振興交付金
アクティビティ(事業概要)
事業を行う背景(現状)解決すべき問題・課題
インプット(予算)
アウトプット(活動実績)
地域活性化対策
農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した地域の活動計画づくりや実践活動を支援。
地域資源を活用した活動計画づくりや実証活動等の取組を実施した地区数(H30実績:132地域)
アウトカム(成果目標)
予算額(百万円) R2:9,805、R元:9,809、H30:10,070
インパクト(政策評価目標との関連)
農林水産業に関わる地域のコミュニティを維持するとともに、都市と農山漁村の交流人口の増加(令和2年度までに1,450万人)及び農村部における人口減を抑制(令和7年度に2,151万人)することにより、農山漁村の活性化及び自立化の実現に寄与。
農福連携対策
障害者等の雇用・就労を目的とした農園等を整備する取組に加え、障害者等が働きやすくなるために実施する農業技術習得の研修等を支援。
農泊推進対策
「農泊」をビジネスとして実施できる体制の整備、観光コンテンツの磨き上げや宿泊施設の整備等を一体的に支援。
農山漁村活性化整備対策
市町村等が作成する活性化計画に基づき、農山漁村における定住、所得の向上や雇用の増大を図るために必要な生産施設等の整備を支援。
農泊を推進するための体制の整備や観光コンテンツの開発等を実施した地域数(H30実績:349地域)
整備した宿泊施設数(H30実績:76施設)
障害者等の雇用・就労を目的とした農園等(農業生産施設、加工・販売施設等)の整備や障害者の農業技術の習得等の取組を実施した地区数
(H30実績:66地区)
農山漁村における雇用を創出する施設整備を実施した地区数(H30実績:59地区)
供用開始した施設数(H30実績:46施設)
【短期】取組が事業完了後も続く見込みの地区の割合
(目標:令和●年度までに●割)
【短期】整備した宿泊施設の稼働率の向上
(目標:令和5年度に27.3%)
【短期】取組地区で雇用・就労する障害者等の人数の増加
(目標:令和2年度までに710人)
【短期】整備した施設における雇用者数の増加
(目標:令和5年度までに300人)
【中期】旅行者数増加の実感がある取組地域の割合の増加
都市農業機能発揮対策
都市部における農業体験や交流の場の提供等、都市住民の農山漁村への関心の喚起等都市農業の多様な機能について、広く国民の理解及び関心の増進を図る取組を支援。
農山漁村の価値が再認識されるなかで、農山漁村の活性化、自立及び維持発展を図ることが重要となっている。しかし、農山漁村においては、人口の減少・高齢化に伴い、地域のコミュニティの活力が低下し、地域経済が低迷している。このため、都市部での農業への理解醸成や都市と農山漁村の交流及び農山漁村への定住の促進により、農林漁業に関わる地域コミュニティの維持発展、農山漁村の活性化及び自立化を推進することが重要である。本事業は、地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大
に結び付ける取組等を総合的に支援する。
都市部と農村部の交流人口※【H28:1,126万人、H29:1,187万人、H30:1,212万人】※出典 農林水産省農村振興局資料(国内の交流人口)及び観光庁資料(訪日外国人旅行者数)を基に農林水産省農村振興局が算出農村部の人口※【2016 : 23,538千人、2017 : 23,263千人、2018 : 22,978千人】※出典 総務省資料(住民基本台帳人口)を参考に農林水産省農村振興局が集計
スタートアップ
山村活性化対策
山村の所得の向上や雇用の増大に向け、山菜や薪炭等の山村の特色ある地域資源等の潜在力を活用するため、地域資源の商品化や販売促進等の取組を支援。
中山間地農業推進対策
中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画を深化させる取組の支援及び農業者等の更なる発展や継承に向けた課題の把握、対策の検討や実施に必要な取組を支援。
具体的なエリア 具体的なツール ハードの充実 都市部での取組
山村の活性化に向けた取組を実施した地区数
(H30実績:100地区)
地域別農業振興計画の実現に向けた取組を実施した地区数
参考(R1実績(中山間地農業ルネッサンス推進事業):89地区)
【短期】取組地域において、販売額、雇用者数等の目標を達成した地区の割合
(目標:令和2年度までに8割)
【短期】取組地域が定めた事業目標を達成した地区の割合
(目標:令和2年度までに8割)
【中期】取組地域における販売額、雇用数等の維持・増加
【中期】取組地域が属する市町村将来ビジョンの構想を達成した地区の割合
(目標:令和7年度までに8割)
都市農業機能の発揮に向けた取組を実施した主体数(H30実績:9主体)
【短期】都市農業への肯定的評価や都市農業を通じて農山漁村を訪れたいと感じた都市住民の割合の増加(目標:令和4年度に70%)
【中期】取組地域において都市住民の都市農業機能への理解が深まったと実感した取組主体の割合の増加
【中期】農福連携に取り組む主体の創出
(目標:令和6年度までに3,000創出)
【長期】取組地域におけるコミュニティの維持に関する肯定的評価の割合の増加
【中期】事後評価時における事業目標を達成した地区の割合
(目標:令和7年度に7
割)
27

【経済産業省】省エネルギー等に関する国際標準の獲得普及促進事業委託費
予算[R02要求] 2600[H31当初] 2625[H30補正] -[H30当初] 2700(単位︓百万円)
協力企業等・日本規格協会・国研・大学・シンクタンク・民間団体・企業
等
国際標準原案の開発・関連技術情報・試験データの収集・国際標準原案の開発・試験・認証基盤の構築 等
国際標準の提案[測定指標]国際標準化機関に提案した国際標準素案件数(件)
[R02見込]50[H31見込]50[H30実績]61
我が国の国際標準化体制構築・重点分野のルール形成に関する調査研究・国際標準化機関等対策・標準化の戦略的活用に係る啓発・情報提供・次世代標準化人材育 成等 ※二重線囲いは、レビューシート上の指標。
国際標準に関する会議への参画[測定指標]国際標準化機関の国際会議に派遣したエキスパート数(人)
[R02見込]130[H31見込]130[H30実績]151
国際標準化の実現[測定指標]国際標準の発行件数(件)[R07目標] (350)[R04目標] (250)[H30実績] 42(123)
※括弧内は累計
開発した国際標準の活用
開発した国際標準の活用実績-国際ルールにおける引用-他国の規制・調達基準等への導入
-認証制度の創設・運用-国内規制・政府調達基準等への導入
等
アウトプットの達成が、アウトカムの発現につながることを示すエビデンス・当省の標準化事業において国際標準提案を行いこれまでに発行された国際標準の活用状況について、事業実施者に対してアンケート調査を行ったところ、活用実績あり/活用に向けて活動中の標準が9割以上(うち、他国/国内の規制・調達基準等への導入、認証制度の創設・運用が図られている標準は約4割)との結果を得ている。
直接コントロールできる部分 経済・社会等の変化(誰が/何が、どう変化することを目指しているか)
(インプット) (アクティビティ) (アウトプット) (短期アウトカム) (中期アウトカム) (インパクト)エネルギー分野における我が国の産業競争力強化
省エネルギー社会の実現や、再生可能エネルギーの普及拡大への貢献
28

(アウトプット)
(インプット)
【国土交通省】地域防災力の強化
昨今の平成29年7月九州北部豪雨や平成30年7月豪雨等の災害において、気象庁は防災気象情報の発表や緊急記者会見をするなど重大な災害の起こるおそれを事前に広く伝え、また、多くの被災地では自治体から避難勧告が発令されるなど、避難行動を促す情報が出されたものの、自宅に留まる等により、多くの犠牲者が出た。
「地域防災力向上に向けた市町村支援のための体制強化等」(増員)
(アクティビティ)
(短期アウトカム)
(解決すべき課題)
気象庁では、「地域における気象防災業務のあり方検討会」報告書(平成29年8月)(別添1)を受けて、これまでの都道府県を窓口にした間接的な支援を、防災の最前線に立つ市町村に対しても、防災気象情報を緊急時の防災対応判断に「理解・活用」(読み解き)いただけるよう取り組む。また、「防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組」報告書(平成31年3月)(別添2)におけるアンケートや現地での聞き取り結果から防災気象情報が必ずしも住民等に理解・活用されていないことが明らかになった。このことから、平時・災害時・災害後の取組を一層推進するとともに、住民に対しても、気象台等の持つ危機感を効果的に伝え、住民の主体的な避難を促す取組をより強力に支援する必要がある。
(把握している現状)
(課題認識)
(最終アウトカム)
「地域防災支援強化のための予報警報業務の強化」(増員)
予算 「JETT(気象庁防災対応支援チーム)の体制強化による自治体の防災対応支援」(令和元年度66百万円)
自治体との連携強化・市町村等の防災行動を支援
市町村の迅速な防災行動を支援するために、予報警報の適時適切な発表が必要
気象災害時に自治体に派遣して気象解説を行うJETTの体制強化をし、地域の実情に応じた防災対応支援を強化
地域防災支援を担当する専任者を配置し、「あなたの町の予報官」が効果的な地域防災支援の取組に関する企画立案、自治体等との連絡調整を行う。
各官署が独自で収集・整理していた地域の自然特性や過去の災害等の資料(市町村カルテ)について、気象庁全体で質と量を一定以上に保ち、気象庁職員全員が全国の資料を同じ手順で参照できるよう気象防災データベースを整備し、市町村と共有する。
災害時や冬季の悪路でも市町村を訪問し、市町村長との「顔の見える関係」構築や現地での気象解説等を実施可能となるように官用車の機動力を強化して更新を行う。
地域の自然特性や過去の災害等を集約、データベース化し、地域の実情に応じた防災対応支援を強化
予報業務の体制変更を実施し、気象観測データ等の詳細な解析を行う要員の配置による防災気象情報作成発表の効率化を行う。迅速な気象警報等の防災気象情報の発表
災害時の市町村への職員の派遣の迅速化、平時の研修や演習の強化
市町村の防災気象情報の理解・活用、住民の主体的な避難を促す取組を強化
市町村における避難情報発表の的確な判断のための知識の向上災害時に市町村における的確な防災判断
住民が災害時に避難など適切な防災行動をとることができる
災害後に共同で「振り返り」を実施し、市町村及び気象台の防災対応を改善平時の取組も含め、気象台が実施した地域防災力強化の取組が災害時の市町村の防災対応等に貢献したかについて、振り返りやアンケートで確認することで、平時・災害時の取組の成果を検証振り返りにより市町村の地域防災計画等の見直しがあるなど、市町村の防災に関する取組状況を把握することで検証
激化する気象現象に対し、行政は住民が適切な避難行動をとれるよう全力で支援するとともに、住民一人ひとりが「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で行動する社会の構築
防災気象情報に基づく地方公共団体の防災対応を疑似体験していただく気象防災ワークショップや、住民向け普及啓発の担い手となる専門家の育成についての施策を企画・立案
気象防災ワークショップ単年度で600市町村、令和元年度から令和3年度までに全市町村の職員が参加できるように開催状況を定期的に集計し検証
市町村訪問市町村訪問の実施状況を、定期的に集計し回数や災害リスク等も参考に検証
気象防災データベース各官署が保有する市町村カルテの情報を気象防災データベースに登録できたか実際の登録データについて検証気象防災データベースによって全国の情報が統一的に取得できるようになったか庁内の利用者による振り返りで検証
予報業務体制の変更気象台の危機感を伝える防災気象情報の発表が適時的確に実施できたかどうか気象庁職員の振り返りにより検証
住民向け普及啓発住民向け普及啓発の担い手となる専門家の育成状況について定期的に集計し検証
住民が防災の知識や関心を持つようになる
災害時に気象台の危機感を市町村と共有する
気象特性や災害時の防災対応を気象台と市町村で共有する
振り返りで総合的・継続的に検証
29

・国立公園内の登山利用者の増加に伴い、し尿、廃棄物等の対応を民間山小屋が担い、トイレ利用など公共的に果たす役割が増大・山岳トイレの整備は整備コストが高く、民間だけではハードルが高いため支援が必要・山小屋の中には土壌浸透、斜面放流等(垂れ流し)トイレは依然として残存
【環境省】山岳環境保全対策事業(自然環境局国立公園課)令和元年12月27日時点
・環境配慮型トイレの未整備でし尿が直接外部に廃棄され、自然環境への悪影響が続いている。・新たなカテゴリーの登山者からの要請(外国人の増加、若者の増加)
課題/目的
・国立公園等の山岳地域において、山岳環境が保全され、登山者が快適に利用できる環境を生み出す。
・未整備山小屋件数ゼロ・整備済老朽化施設の減少・登山者の満足度向上
インパクト
【予算】R1年度: 54,155千円、H30年度: 60,002千円H29年度: 86,598千円
【補助率】対象事業経費の1/2【補助先】民間山小屋事業者など
1施設当たりのコスト(執行額/整備数)
30年度 20百万円環境配慮型トイレ未整備山小屋約40施設
インプット
○山岳環境保全施設の整備の拡大・民間山小屋における公共的機能を発揮するため、トイレ、廃棄物処理施設および給水施設の整備費用を補助し、整備の拡大○利用者負担による維持・整備施設の利用に当たって、利用者から負担金を得て、維持管理等への充当○地域協力による環境保全の推進・地域協議会(地域団体、自治体(県・市町村))が参画し、地域の協力体制の中で環境保全の推進○利用者増加に伴う対応・様々な利用者の増加に伴う今後の山岳環境保全の在り方の検討
・整備普及→年度毎整備件数3~5施設・補助事業と直轄整備→補助事業の場合、直轄整備と比較し、国費負担が約1/4程度抑制。維持管理も山小屋で実施のためメリットも大きい・地域協力の環境保全→地域ほか県、市町村行政機関も参画し、一体となった取り組み
アクティビティ
・H23~H30で7か所の国立公園等において32施設整備(H11~H30で140施設整備)
・ H23~H30で発足、参画した協議会数 11協議会
・事業実績(H23~H30)補助件数 32施設補助合計 610百万円
アウトプット
○山岳環境の改善、利用者の利便性や快適性等の向上○地域団体や自治体との山岳保全におけるネットワーク形成
・実施事業者へのアンケート結果【集計中】
アウトカム
30

【原子力規制委員会】原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業 ロジックモデル
平成30年度
予算
3,525百万円
※うち当初予算3,251百万円※うち補正予算369百万円(全額翌年度へ繰越)※うち前年度からの繰越し予算274百万円
(執行額3,375百万円)執行率96%
(百万円)
(インプット) (アクティビティ) (アウトプット) (アウトカム)
原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業
1 緊急時の対応拠点となる「緊急時対応センター(ERC:規制庁内)」、「原子力災害対策本部(官邸)」、「オフサイトセンター(OFC)」、「地方公共団体」、「原子力事業者」等の間を専用回線、衛星回線を使用し、テレビ会議、情報共有を行うネットワークを整備、維持管理。
2 上記ネットワークを利用し、原子炉施設等から送られてくるパラメータ情報(温度、圧力、水位、注水量)をリアルタイムで模式的に表示するシステム(ERSS)を整備、維持管理。
3 上記のシステムの脆弱性を抽出するためリスク評価(ストレステスト)を実施(平成29年度)。
1 統合原子力防災ネットワークシステム 及び
2 緊急時対策支援システム
【活動指標】平成29年度に行ったリスク評価(ストレステスト)において、改善課題があるものとして57項目を抽出。うちオフサイトセンターの電源確保など本事業の対象ではないものを除き、本事業内で対象とする25項目の改善の進捗。【活動実績】平成30年度 18/25個(72%達成)
3 リスク評価
(上位政策・施策)
施策:放射線防護対策及び危機管理体制の充実・強化
政策:原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守ること
年度 執行額
H26FY 3,879
H27FY 3,063
H28FY 3,054
H29FY 3,188
H30FY 3,375
○訓練を行うことによる継続的改善
○実際に使用することによる情報システムへの信頼性の向上
○緊急時対応の正確性・迅速性の向上
○情報システムとしての信頼性の向上
【活動指標】稼働時間【活動実績】平成30年度 8,760時間
(24時間365日運用)
過去5年間の実働実績・警戒事態(所在市町村6弱以上/大津波警報) 2回・情報収集事態(所在市町村5弱/5強) 6回・連絡体制強化(全国6弱以上※、宇宙飛翔体、核実験等) 14回※警戒事態や情報収集事態に該当する場合を除く。
30年度中の訓練実績・総合防災訓練及びその段階的訓練 年間 14日・事業者防災訓練 年間 39日・緊急時通信訓練(各自治体等との接続訓練) 年間 16日・事業者との接続訓練 年間 96日・EMC訓練(各EMCとのシナリオ訓練) 年間 12日・宿日直勤務者に対する月例研修(訓練) 年間 18日(宿日直勤務者による毎日のシステム確認訓練 年間 365日)
【不具合の例】TV会議システムの音声が途切れることがあった。→システムの再起動で復帰。音声が途切れた場合の対処を訓練項目に導入。
【改善の例】三段階の事態の遷移が明らかとなるよう緑、黄、赤の表示灯をERC内に設置。ホワイトボードの内容をストリーミングで共有。
31

インプット(予算)事業に投じられたリソー
ス
アクティビティ(事業概要)
事業の具体的内容
アウトプット(活動実績)
活動に基づく産出物
当初・中間アウトカム(当初・中間成果目標)活動に基づく当初成果
長期アウトカム(長期成果目標)活動に基づく長期的
な成果
インパクト(上位政策・施策
目標)
【防衛省】情報発信の強化(ロジックモデル)
現 状
◎政策目標安全保障協力の強化
◎施策目標様々な媒体やメディアからの情報発信により、国際社会及び広く国民に理解と協力を得られる環境を構築
○国際社会における防衛省・自衛隊についての理解を通じて、我が国の「積極的平和主義」や「自由で開かれたインド太平洋」等に向けた取組みを広めることにより、同盟国・友好国との協力を維持・強化するとともに、国際社会における我が国の信頼を高める。
○防衛省のみではなく、在京・在外公館等と連携して情報を発信することで、国際社会における防衛省・自衛隊についての理解を促進。
○同盟国・友好国との情報発信における協力関係を構築(Twitterのフォロワー14か国・31機関)。
○海外メディア約0.1百万円 ・海外メディア対応の実施
○英語版のホームページとTwitter約52百万円
(※国内外の予算の区分なし)
・英語版ホームページによる情報発信・英語版Twitterを運用(平成31年1月開始)
・16カ国、46人の海外メディアに対応
・英語版ホームページアクセス数は、年間約500万件・英語版Twitterで、年間約280ツイート
○防衛白書(英語、ロシア語、中国語、韓国語、フランス語)約5百万円
・英語版防衛白書及び英露中韓仏語の防衛白書ダイジェスト版を作成
・英語版防衛白書3,000部、英露中韓仏防衛白書ダイジェスト版を計5,400部を在外公館等に配布
○在京外国大使館等向け英語版ニュース約15百万円
・JDF(英文広報パンフレット)を作成・JDFニュースレター(電子版)の配信
・毎月4,100部のJDFを発行し、在京、在外公館等に送付するとともに、JDFニュースレターを延べ約8,200件配信
○報道記事の翻訳約11百万円
・広報資料等を多言語に翻訳
・16カ国語、85件の広報資料等を翻訳し、在外公館に送付
令和2年度内局広報予算案 約312百万円
課 題国内に対しては、世論調査の結果が示すとおり、高い評価を得ているが、国際社会においては、防衛省の発信による効果や反応等の収集・分析が未実施
※世論調査(30.1実施)自衛隊に良い印象を
持っている 89.7%
・国際社会(特にインド太平洋諸国)の情報を収集し、発信効果等を分析・短編動画をTwitter等により発信
・国際社会の反応等の情報収集・分析を実施・海外発信向けの短編動画を作成
○情報発信の強化(国外情報発信基盤の強化)約36百万円
○防衛省・自衛隊に対する国民の関心を高め理解と支持を得るため、防衛政策や自衛隊の現状について分かりやすい広報活動を積極的に実施。
○国民及び国際社会に向けてソーシャルネットワークを活用した情報発信を実施。
●広報体制の整備約122百万円
●印刷物広報 約114百万円
●行事広報 約68百万円●視聴覚広報 約7百万円
32