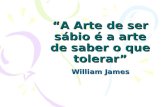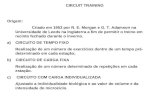末梢神経生検法と組織処理 - NeuroMuscular...
Transcript of 末梢神経生検法と組織処理 - NeuroMuscular...

2016年 8月 7日(日)
ハンズオンセミナー「神経・筋生検」
Neuromuscular Conference共催 (NMC educational 85)
末梢神経生検法と組織処理 東京大学神経内科
清水潤
Ⅰ 末梢神経生検法
1)適応の判断にあたって
2)生検病理で認める直接的所見、間接的所見
3)末梢神経生検の適応疾患
4)生検部位の選択
5)同時、短腓骨筋生検の意義
6)神経所見、電気生理検査との対応
7)生検手技の実際
8)生検後の処理を迅速に
Ⅱ 末梢神経組織の採取後の分割方法
1)臨床施設での末梢神経組織の処理
2)きれいな組織を得るためのポイント
図 分割の仕方の例
Ⅲ 採取された末梢神経組織の処理方法
1)末梢神経観察のために必要な固定と処理の特徴
2)固定後の処理の実際(観察できるまで) 3)必要物品
参考 実際の処理の状況

Ⅰ 末梢神経生検法
はじめに
神経生検は侵襲的な検査であり、病歴、神経所見、電気生理検査、血清免疫学的検
査で診断が出来る場合は基本的には生検は不要である。例えば、現在、糖尿病性末梢神経
障害、ギラン・バレー症候群で生検がなされることはその他の合併病態が疑われない限り
ほとんどない。一方、頻度の多いものとして、血管炎による末梢神経障害は、その他の臓
器で診断困難な場合はよい適応となる。アミロイドーシスに伴う末梢神経障害が疑われる
が遺伝子検査が容易ではない場合も多く適応となる。原因が不明な末梢神経障害の場合は、
炎症性の機序が関与しているか、どのような障害機序が背景にあるか、治療のヒントにな
る所見がないか、などの目的で生検の適応が考慮される。末梢神経障害が患者の主の病態
であり診断の不確実な場合には生検を考慮してよいであろう。
1)適応の判断にあたって
生検を行う場合には、あらかじめ精査をした上で「~の病気が疑われ病理診断を
つけたい。」「~~の病態を考えるが、治療可能な炎症性因子の程度や病勢を知りたい。」な
ど、生検の目的をはっきりさせておくのが望ましい。末梢神経障害があるからといって、
漠然と生検をしても、たまたま特異的な所見が得られる場合もあるが、その可能性は必ず
しも高くない。また病理所見を読むのは、神経内科医であり、診療情報を考慮して病理所
見を読んでいる。丁寧な臨床情報がないと、どうしても病理所見の読み込みは甘くなる。(わ
ずかな所見があった場合、それをどのように重み付けるかどうかということ)また、複数
因子が病態に関与している場合には、病理所見が出たあとに病理診断医とディスカッショ
ンすることにより、生検からの病理情報をより有効に活用できる。 一方、仮に病理所見
で診断の確定が期待できる病態でも、血管炎やアミロイドーシスによる末梢神経障害のよ
うに病変の存在が patchyである場合には、採取組織内に診断的所見が入っていない場合も
あるし、採取部位の病理所見が患者さん全体の病勢を直接示すものとは言えない。生検の
適応がある場合もその限界を知っておく必要がある。
2)生検病理で認める直接的所見、間接的所見
末梢神経生検は、後根神経節に細胞体がある末梢神経細胞の末端の一部を採取して診断に
役立てようというわけである。腓腹神経生検の病理所見には主に以下の2種類に分けられ
ることを知っておく。
①直接的な所見(採取部位に診断的所見がある場合)
脱髄、血管炎、腫瘍細胞浸潤、サルコイド、アミロイド沈着、DM性血管変化
IgM沈着

②間接的所見(採取部位の近位の所見の結果としての主に軸索変化)
軸索脱落の程度、急性軸索変性の頻度、再生の程度
・これらの所見は生検部位での病勢を反映してはいるが,より近位にある病変が
どのようものかは判断できない。
・ただし、軸索障害が神経束ごとに程度が異なる。⇒炎症性?
軸索障害と浮腫がある。⇒炎症性、ただし beriberiなどは注意。
軸索障害所見の相がそろっていない。⇒中毒ではない。炎症性?
3)末梢神経生検の適応疾患
生検の適応疾患は以下のようにおおまかに分けることができる。
①末梢神経内に特異的な所見があり生検が有用である場合
・アミロイド―シス
・ライによる末梢神経障害
・サルコイドニューロパチ―
・悪性リンパ腫の末梢神経浸潤
・壊死性血管炎に伴う末梢神経障害
②末梢神経での病変プロセスが想定可能で、診断的価値がある場合
・炎症性か遺伝性か?
(浮腫、炎症細胞浸潤、神経束ごとの所見差)
・選択的障害か?
sensory ataxic neuropathy、無髄と有髄の障害の程度の解離
small fiber neuropathy
③末梢神経障害の病態・重症度・予後の判定に役立つ
・患者の病態の説明(病勢の把握)
⇒脱落の程度(重症度)、再生・再髄鞘化の程度(回復の勢いはどうか?)
・病態がひとつではないことが予想されるとき(糖尿病、アルコール性)
⇒何が、最も悪い要因となっているか?
④特徴的な所見はあるがその他の方法でも診断が可能な疾患
原因が不明な末梢神経障害で病理所見から、さらなる精査のヒントが得られることを期待
(末梢神経障害の原因はさまざまであり、すべてのスクリーニングは不可能なので)
・遺伝性末梢神経障害

CMT1A, HMSN3(Dejerine-Sottas)、遺伝性脆弱性ニューロパチー、
Hereditary sensory autonomic neuropathy、
・Fabry病、Krabbe病
・CIDP(非典型例)
・IgM paraproteinemiaに伴う neuropathy
・クリオグロブリン血症による末梢神経障害
・n-hexane 中毒による neuropathy
4)生検部位の選択
末梢神経生検部位としては、一般的には腓腹神経(sural nerve)が選択される。腓腹神
経以外に浅腓骨神経、伏在神経などを生検部位とされる場合もあるが筆者はした経験がな
い、これらの神経にのみ病変が限局していると考えられる症例を除いては積極的に選択す
る理由に乏しい。また、手技に慣れていないため採取をする場合は形成外科医の助けを借
りる方が無難であろうし、コントロールデータが乏しいなどの理由で解釈ができない所見
が出てきた場合には困る場合があるかもしれない。腓腹神経で生検を行う理由は以下のと
おりである。
(1) ヒトでは運動成分を含まない(正確には機能障害をおこす運動成分は少数)
生検後に運動麻痺をきたさない 。
* Deep accessry nerveの有無の検討は末梢神経伝導検査で行っておくことが望まれる
(2)下肢遠位端にあるため、各種ニューロパチーで病理学的変化をつかまえやすい。
(3)過去に多くの症例の蓄積があり、それらとの対比が可能。
(4)ルチーンに感覚神経伝導検査を行う神経で電気生理学的情報との対比が可能。
(5)高位の腓腹神経生検では同時に短腓骨筋生検が可能で、1カ所の切開で神経・筋
の生検ができる。
5)同時、短腓骨筋生検の意義
腓腹神経生検は外踝の後方およびその遠位でとる場合もあるが、その位置より近位に
切開をおくことで同時に短腓骨筋を採取することができる。短腓骨筋を同時生検すること
により以下の利点が期待できる。
①炎症性疾患の場合(特に血管炎)、筋組織内の血管炎・浮腫、筋内神経の軸索障害の所
見が得られることがある。
②筋病理所見より運動神経の障害の有無、障害の程度、経過(慢性か急性か)の所見を
得ることができる。
③まれで幸運な場合には、筋組織内を走る筋内神経の脱髄性所見を確認できる。
④免疫染色を筋組織に加えることで炎症性の機序の有無が確認できる。

ただし、神経原性変化が強い場合、切開部位によっては短腓骨筋の筋萎縮が強く、筋の
位置が深い場合がある。その場合は、手術前に採取を予定していても、術野の状況で中止
を判断する場合もある。
6)神経所見、電気生理検査との対応
腓腹神経生検で有意な所見を得るためには、感覚障害の所見の強い下肢、両側の腓腹
神経の伝導速度検査をおこない振幅の低い側で生検することがよい。ただし、筆者は血管
炎症例の初期例で伝導速度の低下がない場合にも典型的な血管所見を認めた経験はある。
障害の軽い神経を採取した場合にはあとから切断端の疼痛が生じる可能性があるので説明
と配慮が必要である。また、血管炎の場合には局所の熱感や浮腫の程度から炎症の強さを
判断して生検サイドを決める場合もある。
なお、腓腹神経病理との対応から、特に生検腓腹神経の支配領域の温痛覚、触覚、お
よび同側下肢遠位での振動感覚、位置感覚は丁寧に所見をとっておくのが望ましい。
7)生検手技の実際
手術室を利用するのが理想的であるが、ベッドサイドや処置室でも決して不可能な手
技ではない。従って、緊急に神経生検が必要な状況下(たとえば急性に進行する血管炎性
ニューロパチーが疑われるような症例)では、手術室の確保に固執することなく生検をす
すめて欲しい。患者の体位はうつ伏せ、あるいは手術肢側を上にした斜め 45°仰臥位また
は側臥位で手術肢を膝で 90°屈曲した形、のいずれかがとられる。どちらの体位でも腓腹
神経が術者に直視できる格好になる。呼吸状態に問題がなければ、患者さんにとってはう
つ伏せが楽なようである。(山口大学神経内科 神田先生の施設の場合)
補足: 患者の体位は手術肢側を上にした側臥位または斜め側臥位で、手術肢を膝で
屈曲して術野が真上にくるように,両足を重ねた体位をとる。手術肢の下に硬く丸めたタ
オルや枕をおくなどして,手術肢をベッドに対して水平に近く安定して保持できるように
する。また、手術時間が 30分以上かかる場合も多いため、患者の無理なく同じ姿勢を保持
できるか確認しながら体位を決めることも大事である。腓腹神経生検をスムースに行うた
めには、手術体位を決めた上で、切開線を腓腹神経の走行に沿って、おくことが最も大事
である。 (東大神経内科の場合)
採取部位は腓腹神経の走行で外踝から遠位の部分とる場合もあるが、ここでは、
高位の生検法を紹介する。この方法では、短腓骨筋の採取も可能である(後述)。外踝後方
で外踝上縁より約 2 横指上方、アキレス腱との間の部位を中心に十分な消毒を行う。静脈
確保は必須である。十分な局所麻酔の後、腓骨とアキレス腱の中間(こころもちアキレス
腱寄りがよい)に、アキレス腱と平行に 3-4cm 程度の切開を入れる(図 1)。結合組織を鈍
的に剥離していくと、切開創と平行に走行する直径 2-3mm の 2 本の管状ないし平板状構造

物が認められるようになる。この 2 本が小伏在静脈と腓腹神経に相当する。多くの場合、
小伏在静脈は腓腹神経よりも表面に近いところを走行するが、この 2 者の区別は思ったほ
ど簡単ではない。とくに、高齢者では静脈壁の fibrosisが進行するし、若年者でも一見し
て血管には見えないケースにときどき遭遇する。静脈と神経を鑑別するポイントは、(1)
神経はよくみると絹のような光沢があり、数本の縦に走行する数本の神経束の“束”とし
て認められる、(2)血管は直角に分岐するが、神経は直角に枝を出すことはない、などで
ある。ここまでのプロセスで血管などが腓腹神経上を横走しているような場合は、確実に
結紮して無用な出血を避けることが重要である。出血するとますます両者の弁別は難しく
なる。腓腹神経を確認したら、小伏在静脈を十分に剥離し、採取する神経全体が直視下に
入るようにする(図 3,4)。ここで気をつけるべきことは、決して神経をつまんだり引っ張
ったりしない(末梢神経は preparation artifactの極めて出やすい組織である)ことであ
る。位置覚・振動覚の強く障害された患者さんでは、生検中、とくに痛み刺激を与えた際
に下肢が動いて清潔操作を不可能にすることがしばしば経験される。このような場合、介
助者に下肢を保持してもらうことが必要になる。近位端に軽く浸潤麻酔を施した後、軽く
糸をかけて(強く結ばないこと)神経束を少し浮かせ、鋭いメスないし剪刀で一気に切断
する。言うまでもないことであるが、神経の切断は必ず近位端から行う。切断の瞬間には
患者さんは“電気が走ったような”強いしびれ感あるいは痛みを感じるので、必ず直前に
これから切離する旨を告げる必要がある。続いて遠位端を切離し、腓腹神経の採取は終了
する。遠位端と近位端で切除の角度を変えておけば、生検後も材料の遠位端、近位端の区
別ができ、便利である。筋生検と異なり筋膜縫合の必要はない。止血を十分に確認したら
皮膚縫合を行う。
上記の方法は腓腹神経の“total biopsy”、すなわち、全腓腹神経を採取してくる方法であ
るが、このほかに、腓腹神経を短冊状に切り取ってくる“fascicular biopsy”という方法
がある。腓腹神経は 5-14 本位の神経束 nerve fascicle からなっており、この一部だけを
採取してくるのであれば、当然、生検後の hypesthesia の領域は狭くなる、ということが
期待される。ただし、短冊状に切り取ってくることに若干の技術的修練が必要で
preparation artifact の可能性が大になることや、fascicular biopsy によってむしろ生
検後の不快な dysesthesia, paresthesiaの頻度が高くなるなどの意見もあり、筆者はこの
方法を最近は用いていない。Fascicular biopsy の弱点はもう 1 つある。血管炎に基づく
neuropathy は神経生検の適応となる最も重要な疾患の一つであるが、観察面積を限定する
ことでその診断に重要な神経上膜(epineurium)の情報や、各神経束毎の病変の程度の差
異を検出しにくくなるデメリットは看過し得ない。したがって、これから腓腹神経生検を
始めようという先生方には total biopsy をお勧めする。
腓腹神経生検後にさらに短腓骨筋生検を行いたい場合は、神経生検後の止血を確
認した後、さらに結合組織を鈍的に剥離して深部へと進む。腓腹神経が腓骨・アキレス腱
の中間よりもややアキレス腱寄りに位置するのに対し、短腓骨筋はやや腓骨寄りにあるこ

とに留意する。筋膜を見つけたらメスで切開し、通常の筋生検と同じ方法で筋肉標本を切
除する。一般に行われる筋生検の部位と違って短腓骨筋は深い位置にあるため、切除後の
筋膜縫合がしばしば困難となる。筋膜切開前に筋膜に糸を通しておくなどの工夫が必要で
ある。
生検施行後は 2-3 日は術肢に体重をかけないよう指導し、基本的に移動は車椅子
で行う。とくに、短腓骨筋の同時生検を行った場合には注意が必要である。術後数日間~
数週間の間は生検部位の圧迫や足首を曲げた際の電撃痛などを訴える場合が多いが、これ
らの症状は時間とともに軽減していくことが多い。一時的なものであること、原疾患の悪
化によるものではないことなどをよく説明する必要がある。術後 7-10日で抜糸可能である。
生検後は切除した腓腹神経の支配領域に hypesthesia, paresthesiaが残存するが、正常末
梢神経には軸索再生能力があり(1 日最大で約 1mm 弱と言われている)、時間とともに徐々
に回復することが多い。ただし、ニューロパチーの基礎疾患によっては回復プロセスに若
干の variationがあることもよく説明する必要がある。(山口大学神経内科 神田先生の施
設の場合)
8)生検後の処理を迅速に
末梢神経は小さいだけに乾燥しやすい。超微形態の保持のためには組織の乾燥は
もっとも避けるべきことである。手術の術者が検体処理もしなければならない場合は、ガ
ーゼを生食で濡らしよく湿らせたあとに一度よく絞り(生食が多いと組織がふやけ形態が
変化する)採取した腓腹神経が折れ曲がらないようにくるみ密閉容器に入れておく。手術
終了後になるべく早期に処理を行うようにする。

Ⅱ 末梢神経組織の採取後の分割方法
1)臨床施設での末梢神経組織の処理
末梢神経の病理診断にはトレーニングが必要であると同時に、時に電子顕微鏡を
用いた超微形態観察が必要である。そのため、すべての施設で診断までおこなうことは困
難であろう。
したがって、末梢神経生検に関連して臨床施設でおこなうことは、
①生検適応がある症例の決定
②手術時に牽引、圧挫などのアーチファクトなく末梢神経を採取
③採取後の末梢神経の分割と固定をして病理診断の専門施設に送る
の 3つとなる。
①②に関しては、第一項「Ⅰ 末梢神経生検法」で説明した。
臨床施設で行うのは③の採取後の末梢神経の分割と固定開始(分割した神経組織を固定液
に入れるまで)となる。
末梢神経は 5-6cm程度採取できると処理がしやすい。
採取した末梢神経は、電顕固定用(グルタールアルデヒド固定)、ホルマリン固定用、凍結
ブロック用の 3 つに分けて処理する。 充分な長さの神経が採取できなかった場合には、
電顕固定用、ホルマリン固定用のみを作製する。各固定および処理には、それぞれの特徴
があるため、疑う病態によっては、分割する組織量が異なってくる。
2)きれいな組織を得るためのポイント
(1)分割までの注意点
分割して固定液に入れるまで、採取後の神経を乾燥させないことが最も大事である。
(採取後、分割処理までに待ち時間が必要なら、よくしぼった生食ガーゼにつつみ、冷所
に保存しなるべく早く処理する。)
注意:容器の中に組織が生のまま入っていて、直接容器が氷に接すると、組織が固定液に
入れる前に凍ってしまう場合がある。組織をよくしぼった生食ガーゼにくるむか、容器を
ガーゼにくるむなど直接に氷に触れないように工夫する。
(2)電顕用固定(グルタールアルデヒド固定)(組成は別紙参照)
①エポン包埋ブロック用
末梢神経の病理観察の基本となる固定である。固定液は自前で作製もできるが、病理
診断施設のものを取り寄せて用いる方が安全である。(固定液の組成の微妙な違いによる浸

透圧によるアーチダクトは最も多く認めるものである。)
・採取された神経の真ん中のいちばん挫滅の少ないところを電顕用の固定液に入れる。
・よりよい超微形態像を得るためには、組織採取後になるべく早期に固定液に入れる。
・一度、長いまま(1.5~2.5cm の長さ)電顕固定液に入れて、半固定できてから細切断す
る。
・ブロックを小さく細切(2~3mm 程度の長さ)した方が、固定液が早期に深部まで浸透す
るので形態が保持される。また、周囲に脂肪組織があると固定液の浸透が悪くなるので、
ピンセットや剪刀で丁寧に脂肪をはずす(特にオスミウムによる後固定)。
・細切時には、両刃のカミソリを縦にわり、すりあわせるように切る。このとき圧挫に最
も注意する。
・細切時にメカニカルアーチファクトが生じやすいので自信がなければ、病理処理施設に
長いまま送るのが無難。輸送は 4度~常温でかまわない。
・細切時には、切断する台(デンタルワックスなど)に載せた組織に直接電顕固定液を少
量かけることで乾燥をさける。
・移動させるときは、ピンセットで直接に把持するのではなく、ピンセットの先を少しひ
ろげ、そこに固定液と組織を表面張力でくっつけて移動させるのがよい。
②ときほぐし標本用
ときほぐし標本は、電顕固定液の段階では①のエポン包埋標本用と同じである。
細切の段階で、5-7mmの長さのものを電顕固定液と同時に別の容器に分ける。
細切に自信がないときは、長いまま(1.5~2.5cm の長さ)電顕固定液に入れて、組織処理
施設に 4度~常温で郵送する。
③電顕用ブロック
電顕用ブロックとエポン包埋ブロックは同じです。
エポン包埋ブロックからエポン包埋トルイジンブルー染色と電顕用の超薄切片を作製する。
(ここは処理施設で処理します。)
(3)ホルマリン固定
ホルマリンは固定液の組織浸透もよく、脂肪や結合組織もしっかり固定できる。特に炎
症性の病態や腫瘍性の病態を疑う場合には、神経束を含むようにまわりの組織も含め大き
いまま組織をホルマリン固定液に入れる。グルタールアルデヒド固定と異なり神経束以外
の組織を外す必要はなく細切の必要はない。固定液は市販の中性バッファーホルマリンで
充分である。
・採取組織の端(5-7mm)を中性ホルマリンに入れる。

・炎症像やアミロイド沈着には病理所見の組織内部位差がある可能性がある。診断の可能
性を高めるためには、このような疾患が疑われる場合には、採取神経組織のやや離れた異
なる部位が含まれるようにするとよい。特に血管炎が疑われ場合は、ホルマリン固定用の
標本にまわす分を優先する。
(4)凍結標本
凍結標本は形態保持が悪く、血管変化や炎症像の観察は可能であるが、神経線維の
評価には役立たない。そのため、現在のところ診断のために必須とはいえず採取された腓
腹神経の長さが充分でなければ必ずしも作製しない。しかし、他の固定で作製する切片が
観察できるまでに数日以上時間がかかるが、凍結切片はその場で作製し HE染色を行うこと
で観察可能なので、特に血管炎の迅速診断には有用である。また凍結切片は、免疫染色に
おいてパラフィン包埋切片より使用出来る抗体の数が多い、また in situ hybridization
手技を用いた検討も可能であり特殊な症例の診断目的や研究目的のために、組織量に余裕
がある場合には作製する方がよい。
末梢神経生検の各処理法の有用性 (表1)
切片の名前 パラフィン切片 エポン包埋超薄切片
(電顕切片)ときほぐし 凍結切片
固定方法 10% 中性ホルマリン
切片の厚さ 4μm 1~0.5μm 約70nm 8~10μm
染色HE・Masson
Trichrome・コンゴレッド・Methyl violet
トルイジンブルー染色
オスミウム・ウラン・鉛
オスミウムHE・Gomori-Trichrome
特徴炎症、間質、腫瘍の
観察、免疫染色光学顕微鏡レベルの超微形態
超微形態有髄線維髄鞘・脱髄評価
免疫染色
血管炎 ◎ ◯ △☓ △ ◎
アミロイド ◎ ◯ ◯ △ △☓
CIDP △ ◯ ◯ ◎ △(◯)
IgMparaproteinemi
a△ ◯ ◎ ◯ ◎
CMT △ ◎ ◎ ◯ △
糖尿病 △ ◯ ◯ △ △☓
アルコール性 △ ◯ ◯ △ △☓
自律神経障害性 ◯ ◯ ◎ ☓ △☓
グルタールアルデヒドを含む固定液


Ⅲ 採取された末梢神経組織の処理方法 1)末梢神経観察のために必要な固定と特徴 採取した末梢神経は、電顕固定用(グルタールアルデヒド固定)、ホルマリン固定用、
凍結ブロック用の 3 つに分けて処理する。 充分な長さの神経が採取できなかった場合に
は、電顕固定用、ホルマリン固定用のみを作製する。 各固定および処理には、それぞれの特徴があるため、疑う病態によっては、分割する組織
量が異なってくる場合もある。固定および処理の特徴に関して以下に簡単に説明を加える。 ①電顕用固定(グルタールアルデヒド固定) 末梢神経の病理観察の基本となる固定である。組織はグルタールアルデヒドを含む固
定液で前固定、オスミウムを含む固定液で後固定し、脱水後にエポン樹脂に包埋し、1μmの厚さのエポン包埋切片を作製しトルイジンブルー染色をして光顕観察する。また、同じ
ブロックから電顕用の超薄切片を作製し超微形態観察を行う。グルタールアルデヒドを用
いた固定は超微形態の保持には優れるが免疫染色性は低下する。 エポン包埋ブロックが出来上がるまで、グルタールアルデヒドを含む固定液での固定に1
日、オスミウム固定後脱水しエポン樹脂になじませるまで1日、エポン樹脂に包埋しエポ
ンが固まるまで2日、合計約4日かかる。 電顕固定液の組成は施設により異なる。当科では、2.5%濃度のグルタールアルデヒド
に加え paraformaldehydeが入った half Karnovsky液を用いるが、paraformaldehyde を含まない 2.5%のグルタールアルデヒド液のみを用いる施設もある。固定液の組成で固定後
の組織のサイズが影響をうけるため、施設ごとに一定した固定液を継続して用いるのが望
ましい。(各施設の病理部門でも電子顕微鏡観察用の固定液があるが、必ずしも末梢神経の
固定に適さない可能性がある。また、固定液の作製や洗浄に用いるバッファー(緩衝液)
には、リン酸バッファーとカコジル酸バッファーの 2 つがある点にも注意。) 固定および固定後のバッファーでの処理では、浸透圧アーチファクトがおきやすく、
他施設に固定後の処理を依頼する場合には、依頼先の施設の固定液を用いるのがよい。ま
た、よい固定を得るためには固定液は新鮮な方がよい。使用前に作製するか、固定液は凍
結保存が可能なため、一度に作り分注保存し(1 検体 5ml 程度あればよい)、使用時に解凍
して用いるのもよい。なお、解凍して用いる場合には、しっかりと常温に戻してから使用
する。 <ときほぐし用標本> 特に脱髄性疾患を疑う場合の解析に必要であるが、標本量が許す限りルーチンに作製
するのがよい。電顕用固定液で 15~30 分固定したのちに、約 5-7mm の長さの神経を切り

分け、別の容器に移して処理する。長時間にわたり電顕用固定液で固定すると、ときほぐ
しにくくなるため数時間~overnight の固定後、バッファーに移す。 ②ホルマリン用固定 ホルマリン固定切片は、炎症細胞の種類、血管変化、および間質の変化を観察するの
に適する。しかし、神経束内の浮腫や有髄線維のおおまかな密度(神経束ごとの密度の差
も)はわかるが、軸索障害の程度の評価は正確には困難であり、脱髄線維の確認や無髄線
維の評価は不可能である。一方、アミロイド沈着の検出のための特殊染色や炎症細胞の染
め分けなどの免疫染色はホルマリン固定切片でおこなう。また、時に炎症性や腫瘍性疾患、
また特殊な形態変化を認めた場合、一般病理の先生に相談する必要が生じるが、一般病理
の先生はエポン包埋切片や凍結切片での観察に慣れていないことが多く、パラフィン切片
でコンサルトすることになる。。固定液は市販の中性緩衝ホルマリンで充分である。 ③凍結標本 凍結標本は形態保持が悪く、血管変化や炎症像の観察は可能であるが、神経線維の評
価には役立たない。そのため、現在のところ診断のために必須とはいえず採取された腓腹
神経の長さが充分でなければ必ずしも作製しない。しかし、他の固定では作製する切片が
観察できるまでに数日以上時間がかかるが、凍結切片はその場で作製し HE 染色を行うこ
とで観察可能なので、特に血管炎の迅速診断には有用である。また凍結切片は、免疫染色
においてパラフィン包埋切片より使用出来る抗体の数が多い、また in situ hybridization手技を用いた検討も可能であり特殊な症例の診断目的や研究目的のために、組織量に余裕
がある場合には作製する方がよい。 組織から DNA や mRNA の抽出が可能である。DNA に関しては生検時に別個に DNA用採血をしておく方がよいが、mRNA などの発現解析には凍結標本用の検体はのちに述べ
る O.C.T.コンパウンドなどの余分な成分が入るので、もし、検討の必要性が考えられるな
らば、腓腹神経の一部をそのままエッペンドルフチューブなどの容器に入れ迅速凍結保存
するのがよい。特に、リンパ腫に伴う末梢神経障害の診断に凍結組織を用いた IgH clonalityの検討が有用である。この場合、組織内に含まれる浸潤細胞の量により検出感度が異なる
ので凍結にまわす組織の長さは長い方がよい(できれば 3cm 以上)。最初から長めに神経を
採取し、その一部を解析まで凍結保存しておく。

2)固定後の処理の実際(観察できるまで) 以下に組織固定後、標本ブロック作成までの処理について示す。 ホルマリン固定標本の処理は、他の組織標本の処理と同様である。 処理開始前の固定液での固定時間は、末梢神経は組織が小さいため over night の固定がな
されれば充分である。 ホルマリン固定パラフィン包埋標本の作製法 10% 中性緩衝ホルマリン内でovernight 固定70% エタノール 1.5時間80% エタノール 1.5時間90% エタノール 1.5時間95% エタノール 1.5時間100% エタノール 1.5時間 x 2キシレン 1.5時間 x 3パラフィン 1.5時間 x 2包埋
電顕標本の作製法 half Karnovsky 固定液 over night0.1M cacodylate buffer 内洗浄 10分ごと3回
1% オスミウム 30分1% uranyl acetate 30分50% エタノール 10分70% エタノール 10分80% エタノール 10分90% エタノール 10分95% エタノール 10分100% エタノール 10分 x 3100% propylene oxide 10分 x 3half and half デシケーター内でover night(Epoxy resin 50% and propylene oxide 50% )
濾紙の上で拭き取り、新しいeponにて包埋Epon 100% 48時間
(60度のオーブン内で)

ときほぐし標本の作製法
half Karnovsky 固定液 over nightcacodylate buffer 内洗浄 10分ごと3回この段階で、神経外膜、周膜をなるべくはがし神経束が露出するようにときほぐしておくとosmificationがよくなり所見がとりやすくなる。
4% オスミウム 4時間cacodylate buffer 2分 x 350% エタノール 10分70% エタノール 10分80% エタノール 10分90% エタノール 10分95% エタノール 10分100% エタノール 10分 x 3Ceder oil over night
神経ときほぐし標本ができあがったら、実体顕微鏡下でときほぐす。この場合落射光
の方が観察が容易である。まず、大まかにときほぐして明らかに神経線維の集団である部
分をいくつか取り出す。それらをさらに、電顕用ピンセット直 2 本を使ってときほぐす。
スライドグラスを 2 枚左右に並べ、左のほうのプレパラートでときほぐしていく.次いで,ときほぐしたものの端を,電顕用ピンセット曲を用いて横に垂直に引っ張っていき、右のスラ
イドグラスの端から順にスライドグラスの方向に垂直に並べていく。 並べ終わったら、60℃のオーブンで overnight 加熱し、Ceder oil が十分に乾燥したことを
確認した後、カバーグラスをかけて包埋する。

3)処理物品 <採取後の分割時に必要な物品> パラフィンワックス(SHOFU) (発泡スチロールの板でもよいが、組織を置く前に固定液やバッファーでよく表面をぬら
しておかないと、組織と癒着する。) 先の細めのピンセット 2本(時計ピンセットなど) 両刃のカミソリ(フェザーのカミソリがよい) ホルマリン組織用容器(スチロール棒ビン) 電顕組織用容器(エポン包埋用、ときほぐし用) 2本(スクリュー管) コルク(またはクリオモルド) ティシュー・テック O.C.T.コンパウンド(Sakura) ときほぐし用ピンセット(ビガー5 型など) <必要試薬> Sodium Cacodylate TAAB 100G (TAAB) GLUTARALDEHYDE 25 % Solution, EM, Grade 10x10ml (Electron Microscopy Sciences) 8% Paraformaldehyde (Paraformaldehyde(粉末)8g を 100ml の distilled water に溶かし、温めながら撹拌し、
必要に応じて、1N の NaOH を数滴加え、透明になるのを待つ。) 10%中性緩衝ホルマリン (Wako) <電顕固定液> 施設により各種のものが用いられる。 half Karnovsky 固定液 (当施設で用いているもの) 0.2 mol cacodylate buffer 25ml glutar aldehyde 25% 10ml 8% paraformaldehyde 6.25ml Distilled water 58.75ml 2.5% グルタールアルデヒド液 固定液 0.2 mol cacodylate buffer 50 ml Glutar aldehyde 25% 10ml Distilled water 40 ml 洗浄バッファー 0.1M cacodylate buffer

0.2M カコジル酸バッファー カコジル酸ナトリウム(Na(CH3)2AsO2) 4.28gに distilled water 80ml をくわえて溶か
し、次いで 0.1N HCl を加え、pH が 7.4 になるように調整する(およそ 5.4ml)。次いで、
distilled water を追加して全体量が 100ml になるようにする。 0.1M cacodylate buffer は、0.2M 溶液を distilled water で稀釈して作製する。 1% Osmiun 固定液 0.2M cacodylate buffer 2ml 4% オスミウム 1ml Distilled water 1ml (30 分以上 stirrer で撹拌する) エポンブロック エポック 812 8.5ml DDSA 4.0ml MNA 5.3ml DMP-30 0.27ml (MNA 量が多いほど、DMP-30 量が多いほど樹脂は固くかつ脆くなり、DDSA の量が多い
ほど柔らかくなる。)