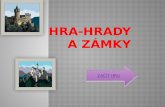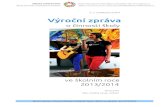NRRC研究ロードマップHRAの運用事例の調査...
Transcript of NRRC研究ロードマップHRAの運用事例の調査...

NRRC研究ロードマップ
原⼦⼒リスク研究センター (NRRC)
2020年7⽉
1

安全性向上を⽀えるリスク研究開発• 低頻度だが⼤きな被害をもたらし得る事象のさらなる解明と対策⽴案• 従来の決定論的な⼿法に加えてリスク情報を活⽤する⼿法を適⽤
2 リスク評価技術
1 事象評価技術研究開発項⽬
応
⽤
フィードバック
成果の実務適⽤⽀援
フィードバック
① 新規制基準への適合(対策追加・改良⼯事等)
② リスク評価(PRA実施)
継続的安全性向上の取り組み
③ リスク低減/深層防護(安全性確保策の強化)
④リスク情報活⽤(リスクマネジメント)
⑤リスクコミュニケーション
<東電福島第⼀事故・規制基準⾒直し>
<再稼動>
<安定運転>
*炉⼼の著しい損傷を伴う重⼤事故
様々なステークホルダー
↔組織内部↔
1) シビアアクシデント(SA)*
2) 活断層3) 地震動4) 断層変位5) 地盤・斜⾯・⼟⽊構造物耐震6) 建屋・機器耐震7) 津波8) ⽕⼭9) ⻯巻等極端気象10) 内部⽕災・内部溢⽔
1) PRA⼿法(内的・外的事象)2)⼈間信頼性(HRA)3)環境放出時影響
3 リスクコミュニケーション
<継続的安全性向上>
*番号①〜⑤は、後述のロードマップの「成果の適⽤先」の番号に対応
2

PRA技術の改良開発状況専⽤研究は不要 研究開発開始予定 研究開発中 モデル
プロジェクト実施中
出⼒運転時PRA
停⽌時PRA
地震PRA
津波PRA
内的事象
外的事象
上記以外の外部事象(⻯巻・強⾵、⽕⼭)
レベル1 レベル2 レベル3
⽕災・溢⽔PRA2017年 溢⽔PRA実施ガイド2019年〜 モデルプラント試⾏2019年 ⽕災PRA実施ガイド2020年 ⽕災モデル・発⽣頻度整備2021年〜 モデルプラント試⾏
2017〜2020年 津波PRAモデルプラント
2019年 過酷状況下HRAガイド2019年 FCVSモデル⾼度化MAAP2021年 最適FP放出評価法2021年〜 レベル2PRA試⾏
(モデルプラント)2024年 レベル2PRA実施ガイド
2020年 SSHACプロセス導⼊2019年〜 地震PRAモデルプラント(随時)ハザード・フラジリティ評価⾼度化
2020年〜 強⾵PRAモデルプラント(計画中)2021年〜 ⽕⼭灰PRAモデルプラント(計画中)
2017年 内的事象HRAガイド2019年 ピアレビューガイド2019年 MUPRA* ケーススタディ2021年 PRA実施ガイド2021年 ピアレビュー実施
* マルチユニットPRA
3
2019年 WinMACCS利⽤ガイド2021年〜 仮想モデルプラント試⾏2023年 WinMACCS利⽤ガイド改訂

PRA技術の改良開発スケジュール
PRA項⽬ 年度研究項⽬
2018以前 2019 2020 2021 2022 2023
以降
出⼒運転時
内的レベル1PRA⼿法改良⼈間信頼性評価(HRA)⼿法⾼度化過酷状況下HRA⼿法開発マルチユニットPRA⼿法開発放射性物質放出リスク評価⼿法⾼度化(レベル2)環境影響リスク評価⼿法開発(レベル3)
内部⽕災 内部⽕災リスク評価⼿法整備(レベル1)内部溢⽔ 内部溢⽔リスク評価⼿法整備(レベル1)
地震
地震リスク評価⼿法⾼度化(レベル1-2)SSHACプロセス確⽴ハザード評価⼿法⾼度化フラジリティ評価⼿法⾼度化
津波津波リスク評価⼿法⾼度化(レベル1-2)ハザード評価⼿法⾼度化フラジリティ評価⼿法⾼度化
⻯巻・強⾵ ハザード評価⼿法⾼度化、フラジリティ評価⼿法開発⽕⼭ ハザード評価⼿法⾼度化、フラジリティ評価⼿法開発
リスクコミュニケーション 内部・外部コミュニケーション⽅法改善策策定
研究開発 モデル 実務適⽤ 要素技術毎に随時実務適⽤凡例︓ ⇒ ⇒
4

1. 内的レベル1PRA⼿法改良項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023〜
(国の検査制度⾒直しのスケジュール)
パイロットプロジェクト支援
国内PRAが国際レベルに達していない
↓• パイロットプラントの海
外エキスパートレビューによる国内PRA技術の向上• 各社がパイロット等の知
見を反映できるようにガイド等を整備
PRAピアレビュー実施方法の確立
PRAの品質維持向上方策が十分でない
↓• PRAピアレビューの実施
方法の確立
信頼性データベース構築
PRA用パラメータ整備
品質の高いパラメータの整備が十分でない
↓• データ収集ガイドの整備• 国内一般パラメータ評価
(機器故障、CCF、他)
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
検討・整備 試運用 最終確認
信頼性データシステム構築
一般機器故障率推定手法の検討、整備
▽データ収集ガイド②
過去データ収集
電⼒各社【凡例】 NRRC*NEI:⽶国原⼦⼒エネルギー協会
パラメータ評価 更新
システム改良
データ収集(新たな運転実績、重大事故対処設備等)
ピアレビューガイド② ▽
NEI*ピアレビューガイドの調査国内版ガイドの策定 ガイドの改良
ピアレビュー実施方法の構築
米国PRA標準、NEIガイドを参考にレビューを実施
ピアレビュー実施
海外ピアレビュー現地調査
ピアレビュー体制の構築
伊方3/柏崎刈羽7を対象に、海外エキスパートレビューの実施
パイロットの知見をガイド化、個別R&D活動とPRA標準・ガイド類との連携(レベル1から順次)
適宜パイロットの知見を反映
PRA実施ガイド② ▽
5
一般パラメータ評価
信頼性DBシステム②▽ 信頼性DB運用②▽
▽データ収集ガイド公刊②
▽一般パラメータ公刊②
CCF事例判定手法まとめ▽CCF判定ガイド②
定量化対象機器選定/事象抽出 データ・定量化 更新▽CCFガイド・パラメータ公刊②

2. 人間信頼性解析手法の拡充及びその高度化技術の開発6
項 ⽬ ギャップ/解決 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023〜
電気事業におけるHRA研究の活用
HRA分析モデルの整備・
HRAガイドの拡充
定性分析手法の改善・外的事象に用いる現実に即したHRA分析モデル及び、高ストレス下における定量化手法の改善が必要
↓• HRAガイド適用拡大• 外的事象HRA分析モ
デル開発・適用事例
新定量化手法の開発
文脈、業態を反映する定量化手法が不十分
↓• 国外最新手法調査• 行動影響因子構造モ
デル提案• HRAへVR活用検討
ハルデン炉プロジェクトへの
国際協力
• MTOで得られる先進的知見をの取込み、電力各社に利用可能な研究成果の提供
人間信頼性データベース
の開発
人的過誤情報の不足↓
• 国内データベース整備
• 国内傾向を反映した人的過誤確率(HEP)評価
HRA運用促進策の開発
人的パフォーマンス向上のためのHRA運用に際し、ヒューマンファクタの知見や技術の活用が不十分
↓• HRA運用促進策開発
パイロットプラント津波PRAのHRA高度化
ハンドブック1(インタビュー方法)②▽
国内DBフレームワーク構築
HRAガイドの定性分析手法によるPRA高度化
最新定量化手法の調査・適用性検討
HRAの運用の要件②▽
適用評価事例の作成
HRAの運用事例の調査
分析モデルの反映、適用事例の拡大によるHRAガイドの充実
HRAの運用要件の解明
叙事知と標準定量化手法の組合せによるHRAガイド
過酷状況下分析モデルの整備
ガイド改定(随時)②▽
改訂版HRAガイドを用いたHRAの応用拡大 (訓練・手順書改善 含)
実績データに基づくHEP更新
知見反映
人間信頼性データ収集の国際連携の動向把握(NRC、EPRI、KAERI、等)
▽国内用DB枠組の開発②
HRAの運用促進策の開発
ハンドブック2(訓練観察方法)②▽
高度化された手法に対応したデータ収集方法およびノミナル値更新方法②▽ 拡張版データベース②▽
知見反映
▽ガイドの事例提供②
動向検討・反映
開発済み人間信頼性データベースの運用支援
高度化されたHRA手法に対応可能なデータ収集方法およびノミナル値更新方法の確立
各社データ収集と活用
~2020(燃料材料研究のもとで実施)
知見反映
行動影響因子の構造モデル、コードの開発、新定量化手法の提案
実績反映
分析モデルの整備②▽
知見反映
分析モデルの整備②▽
HRAガイド改訂版同 英語版②▽
PIF検討調査結果②▽ 新定量化手法ガイド②▽
国内DB仕様の検討
人的過誤率(HEP)推定・更新手法 検討
拡張版データベースの開発
外的事象PRAに係る人間特性データの抽出(VR)
HRA分析モデルの拡充
中操放棄に係る人間特性データの抽出(VR)
分析モデルに適用
ハルデン炉プロジェクト MTO共同研究への参画
知見反映
影響因子等の知見反映
知見反映
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)

3. マルチユニットPRA(MUPRA)
項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023〜
MUPRA手法の開発
複数ユニット同時発災時の文脈を考慮したGood PRAを導入するための標準的な実施方法が未整備
↓• 外部ハザード(地震)レベル1
MUPRA手法の開発• モデルプラント評価(レベル2)への
反映
▽ 内的事象レベル1MUPRA手法提示②
レベル2PRAへ知⾒反映
内的事象レベル1 MUPRA⼿法の開発
(ケーススタディ含む)
7
地震MU起因事象分析②▽
地震レベル1MUPRA⼿法の提案
IAEA MUPRAプロジェクトへの参画
地震レベル1MUPRA手法案② ▽
PRAの要素評価による傾向・影響分析
地震による機器同時損傷の影響分析②▽
地震レベル1MUPRAケーススタディの実施
地震レベル1MUPRA手法提示②▽
知⾒反映
知⾒反映
レベル2MUPRAに向けた先⾏研究等調査
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)

4. 放射性物質放出リスク評価⼿法⾼度化(レベル2)▽:R&D成果(①-⑤:成果の適用先)
項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023〜
SA時の事故進展評価
(原子炉~格納容器~原子
炉建屋)
現実的な格納容器破損挙動評価及び機能喪失頻度(CFF)評価手法、ソースターム評価手法の整備が不十分
↓• 代表核種(Cs)の挙動解明• 格納容器/建屋内でのFP付
着/移行挙動の評価と分析• MAAPコードのモデル検証
と高度化• 現実的なFP移行挙動評価
のための手法開発• 緩和システム(FCVS)のモ
デル開発• 格納容器内温度評価及び
破損部位特定手法の整備• 重要事故シナリオの評価手
法整備
SA時の事故進展評価
(使用済燃料貯蔵施設:
SFP)
SA時のSFP内での熱的挙動や燃料破損、臨界についての評価及びモデル検証が不十分
↓• SA時のSFP内気相の自然
循環、スプレイ冷却効果、燃料被覆管の破裂形態の解明とMAAPモデル検証、高度化• SA時のSFP内臨界評価手
法の構築
モデルプラント評価
重要事故シナリオの評価手法整備
FPの現実的挙動の解明とモデル構築(エアロゾル成長、貫通部FP除去、スクラビングFP除去)
MAAPコードの入力データ高精度化② ▽
SFP内臨界シナリオ評価
臨界シナリオ②▽
原子炉の再臨界評価手法②▽
エアロゾルパラメータ最適化② ▽
コード特性把握②▽
貫通部DFデータ②▽
MAAPによるFPの建屋沈着/移行挙動評価とモデルの妥当性確認
建屋DF見込み(概略)②▽建屋モデリングのノウハウ②▽
SFP内気相の自然循環流量評価モデルの検証と高度化
簡易流量評価ツール②▽
SFPスプレイ冷却モデルの検証と高度化(可視化試験)
モデルプラントを対象としたレベル2PRAの試行
8
SFPを対象とした停止時PRA手法の開発
格納容器破損部位特定手法②▽
建屋DF見込み(詳細)②▽
実機適用性②▽
被覆管破裂評価モデル②▽
スプレイ冷却モデル②▽
▽冷却後の機械特性データ②
SFPスプレイ冷却モデルの検証と高度化(伝熱特性試験)
SFP内燃料被覆管破裂評価試験( Zry-2、Zry-4、高燃焼度条件、バンドル体系)
燃料被覆管破裂評価モデルの開発
実現象に即した格納容器温度評価手法の構築(MAAP、CFD、GOTHICの適用性評価)
SA時の現実的なSFP熱流動評価手法の構築
破裂条件②▽
スプレイ時伝熱特性データ②▽
最新知見を反映したGoodレベル2PRA手法の開発(CFF、ソースタームPRD、ダイナミックPRA、EDF共研、国際プロジェクト)
SFP内燃料被覆管破裂評価試験(Zry-2)
破裂挙動データ②▽
FP挙動評価モデル② ▽
レベル2マルチユニットPRAに向けた先行研究等調査
格納容器破損部位特定のための評価手法の開発(温度評価、構造評価)
今後の研究課題②▽
MAAPコードのモデル検証、改良と高度化
現実的なFP移行挙動評価手法の開発
FPの現実的挙動評価モデルの高度化(建屋沈着/移行、貫通部FP
除去、スクラビングFP除去)

5. 環境影響リスク評価⼿法開発(レベル3)▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
9
項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023〜
レベル3PRA技術の検討
電気事業者が最新のレベル3PRAコードを利用するための知見が不足
↓• 米国の既存モデル(WinMAC
CS)導入と特性把握、我が国への適用性評価• ソースターム入力(MAAP出
力からWinMACCSへの入力)手法の整備• 国内におけるデータの収集、
パラメータ化
仮想モデルプラント評価
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
仮想のモデルプラントを対象としたレベル3PRAの検討
WinMACCS利用ガイド改訂②▽
WinMACCS特性把握・早期被ばく評価技術の確立
防護措置の影響②▽
パラメータの影響解析 ツール試運用
国内におけるパラメータの情報収集、検討、評価
レベル2/3PRAインターフェースツール②▽
ソースタームの入力手法・不確実さの解析手法の整備
中長期被ばくを含めたパラメータの総合的検討・解析
環境中のセシウムの減衰挙動モニタリング
防護措置等影響評価② ▽
WinMACCS利用▽ガイド②
WinMACCSのパラメータ評価② ▽
△地域データ入力手法②
△ 防災等データ入力手法②
地形等の影響把握

10
6. 内部⽕災リスク評価⼿法整備(レベル1)・⽕災防護
項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023〜
内部火災PRA技術の構築
内部火災PRA実務に適したガイドが整備されておらず、国内火災事例データも不十分また、地震誘因火災PRAの知見が不足
↓• 米国最新知見を踏まえた火災PRAガ
イドの整備• 国内火災発生事例に基づく火災発生
頻度の提示• 地震誘因火災PRA手法の整備
内部火災PRAプロジェクト
ガイドの実機評価適用性が未確認↓
モデルプラントを対象とした試評価とガイドへのフィードバック
火災進展評価技術の高度化
新知見(HEAF:電気盤の高エネルギーアーク損傷)に対する火災発生防止・影響軽減対策が不明確また、現実的な煤煙と熱の伝播挙動を再現可能な火災進展解析手法やターゲット損傷基準が未整備
↓• 低高圧電源盤***やバスダクトを用いた
HEAF火災実証試験による知見の蓄積• 火災進展解析に必要な火災モデルの
整備• 国際共同研究や海外機関との連携に
よる最新知見の導入・活用
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
ガイドドラフト版②▽
ガイド改訂②△
知見反映
電源盤・バスダクトHEAF⽕災試験
高圧M/C・低圧P/C***
電源盤HEAF火災実証試験①△
OECD国際共同研究(電源盤⽕災HEAF2・複数区画⽕災PRISME3)への参画
⽕災進展モデルの整備ゾーンモデル*
整備②△
ソーンモデル改良・フィールドモデル**整備② △
知見反映
知見反映
* 上下二層の空気層(ゾーン)の形成を前提とした計算負荷の小さい実用モデル** 精緻な空気温度の空間分布が評価可能な数値流体力学モデルで計算負荷が高い*** M/C:メタルクラッドスイッチギア、P/C:パワーセンター、MCC:モーターコントロールセンター
国内プラント⽕災発⽣頻度評価
内部⽕災PRA⼿法の整備
△火災発生頻度②
内部⽕災パイロットPRAの調査・計画
モデルプラントを対象とした内部⽕災PRAの試⾏
ガイド改訂に向けた事例蓄積
DG用M/C・低圧MCC***
電源盤HEAF火災実証試験①△
電源盤ZOI評価・バスダクトHEAF実証試験①△
△HEAF火災総合報告①
ガイド公開版②▽
海外機関(EDF, INL)との連携
地震誘因⽕災PRA⼿法の調査
10
ゾーンモデル△総合報告②

7. 内部溢⽔リスク評価⼿法整備(レベル1)▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
11
項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
内部溢水PRA技術の
構築
内部溢水PRA実務に適したガイドが未整備また、地震誘因溢水PRAの知見が不足
↓• 米国電力研究所(EPRI)の溢水
PRAガイドを補完(例えば、被水影響評価等)した評価ガイドの整備• 地震誘因溢水PRA評価手法の
整備
内部溢水PRA
プロジェクト
内部溢水PRAガイドの実機評価適用性の確認・向上が必要
↓• モデルプラン評価を通じたガイド
の実機評価への適用性及びガイドへの知見のフィードバック
内部溢⽔PRA⼿法の整備
▽ガイド制定②(2017)
地震誘因溢⽔PRA⼿法の調査
モデルプラントを対象とした内部溢⽔RAの試⾏
内部溢⽔PRAガイドの改定
▽概略評価② ▽詳細評価② ▽最終評価②
ガイド改定②▽
海外最新知⾒の反映
知⾒のフィードバック
国内プラント溢⽔発⽣頻度評価
△溢水発生頻度②
海外機関(INL)との連携知見反映
知見反映
知見反映

8. 地震/耐震【ハザード/フラジリティ】(全体概要)項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
地震ハザード評価
-活断層-地震動
地震動評価における不確かさが大きい日本において不確かさを,より現実的に評価する手法がない
↓• 地震動評価の不確かさ
をより現実的に評価する手法を構築
地震PRAプロジェクト
地震フラジリティ評価
-機器-建物-地盤・斜面-地中土木構造物
耐力とフラジリティの評価が保守的な評価に留まっている
↓• 実現象をより正確に捉
えられる応答解析手法に基づくフラジリティ評価手法の構築
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
基礎地盤への実用化(二次元)①,② △
【地震動】
【機器】
【機器】
【建物】
【地盤・斜面】
【地中土木構造物】
第1ステップ
▽実岩盤への実用化(二次元)①,②
SSHACプロセス国内適用②▽確率論的地震ハザード解析⾼度化のための要素技術の⾼度化
震源パラメータの定量評価
活断層の連動性・端部の定量的な評価指標の開発
PRAのための定式化②▽▽連動性評価指標提案①,②【活断層】
▽震源パラメータの提案①,②
第2ステップ
震源近傍強震動と深部地盤構造の評価
地震・津波重畳等のマルチハザード評価
新たな指標を踏まえたセグメンテーション評価⼿法の開発
震源近傍GMPEの⾼度化
地盤・斜⾯の⼆次元, 三次元⾮線形解析⼿法の開発/実⽤化
地中⼟⽊構造物の耐震性能照査⼿法の標準化/⾼度化/実⽤化
大入力時の建屋挙動評価手法①,②▽
地震損傷データに基づく現実的フラジリティ評価⼿法構築地震損傷データに基づくフラジリティ評価法構築①,②▽
機器・配管系の弾塑性評価法の構築
弾塑性応答評価の許容基準値提案①,② ▽
▽終局耐震性検討手法構築①,②
△岩盤構成モデル開発(三次元)①,②
*SSHAC:地震ハザード解析専⾨家委員会
SSHAC*技術⽀援
▽弾塑性解析法提案①,②
⼤⼊⼒に対する建屋挙動評価(三次元モデル・地盤-建屋相互作⽤など)大入力時の建屋挙動評価手法高度化①,②▽
確率論的地震ハザード解析⼿法の⾼度化
△断層モデルも考慮した確率論的地震ハザード解析手法開発②
▽三次元地震応答解析手法実用化①,②
弾塑性応答を考慮した配管系フラジリティ
▽評価法構築①,②
12

8-1. 地震/耐震【地震ハザード(活断層)】
項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
活断層の震源断層評価
地震規模評価において、活断層の連動区間・端部に関する評価基準に関する知見の補強が必要。また、活構造の認定において、地域性の不確実さが大。
↓• 実地震の破壊停止要因
に基づく連動性評価指標の提示• 活断層が認めにくい要
因の分析とそれに応じた認定手法の蓄積
近年発生した地震を対象にした断層調査
活断層が未確認の地域における地表地震断層の出現事例の増加。
↓• 当該断層の分布・出現
形態、破砕性状や活動性の調査に基づき、事前に評価しうる可能性を明確化
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
PRAのための定式化②▽
地域性を考慮した震源断層評価⼿法の構築
連動性・端部の定量的な評価指標の開発
▽連動性評価指標提案①,②
活断層の未成熟な地域の認定手法提案①▽
火山地域の認定手法提案①▽
事前評価の可能性に関する検討
総合的な事前評価手法の提案①△
震源を特定しにくい地域における活構造認定⼿法の開発
知見反映
知見反映
破砕性状・活動性 知見反映
新たな指標を踏まえたセグメンテーション評価⼿法の開発
活断層として認識されていなかった地表地震断層の調査
リモートセンシングデータを組み込んだ国内外の地表地震断層の調査
分布・出現形態
近年の地表地震断層の特性提示①▽
新知⾒を踏まえた総合的な事前評価法の検討
13

8-2. 地震/耐震【地震ハザード(地震動)】項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
震源を特定して策定する地震動の評価
既往被害地震の震源モデルが質・量とも少ない、地下深部の速度構造モデル化手法の高度化が必要
↓• 統一した手法を用いた
震源モデル化• 観測データに基づく地
下構造評価法の確立
震源を特定せず策定する地震動の評価
M6級の中規模地震の際に震源近傍で稀に得られる大加速度記録の発生要因に関する知見の補強が必要
↓• 強震記録の取得地点で
の詳細調査に基づく発生要因の解明• 地盤増幅の影響を除去
した基盤地震動の評価
確率論的地震ハザード評価
SSHACの国内適用方法が未確立
↓• 確率論的地震ハザード
評価における認識論的不確実さ考慮を目的としたSSHACレベル3手法の国内適用方法確立• 確率論的地震ハザード
解析で用いる要素技術の高度化
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
インバージョン⼿法による震源パラメータの定量評価
地震観測・微動観測に基づく地下構造把握・モデル化⼿法の体系化
防災科学技術研究所の強震観測点における⼤加速度観測記録の①地下構造調査による
発⽣要因解明と基盤地震動推定
②鉛直アレイ地震観測の実施による検証(同研究所との共同研究)
非線形サイト特性・地形サイト特性・3次元サイト特性モデル構築①②▽
震源近傍強震動と深部地盤構造の評価
サイト特性予測モデルの構築とGMPEへの取り込み
震源を特定せず策定する地震動▽に資する地震動評価①
ばらつき評価への反映
サイト特性モデル構築への反映
震源近傍記録の共通事項、サイト固有事項の解明と新知見創出① ▽
近年の被害地震、計器観測初期の▽地震の震源パラメータの提案①②
伊⽅SSHACプロジェクトの技術⽀援 全社展開/地震・津波重畳等のマルチハザード評価
確率論的地震ハザード解析⾼度化のための要素技術の⾼度化(フェーズ1)
プロジェクト報告書作成支援② ▽
△地震予測モデルの定量的選択方法高度化②
▽SSHAC Level 3に基づく確率論的地震ハザード解析の課題抽出②
△断層モデルも考慮した確率論的地震ハザード解析手法開発②
IAEA TECDOC︓確率論的地震ハザード解析の検証・更新⽅法開発
▽ SSHACプロセス国内適用②
震源近傍GMPEの⾼度化
Diffuse seismicity評価法の構築
確率論的地震ハザード解析⼿法の⾼度化
地震PRAへの反映
取り込み
確率論的地震ハザード解析⾼度化のための要素技術の⾼度化(フェーズ2)
地下構造モデル化法の体系化① ▽
14

8-3. 地震/耐震【地震フラジリティ(機器)】
項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
機器・配管の加振試験
大加速度時の破壊挙動や機能維持に関する知見の補強が必要
↓• 20Gまでの加振による
限界耐力・機能維持限界の把握
機器・配管の現実的耐力・
応答評価
耐力とフラジリティの評価が保守的な評価に留まっている可搬機器等のフラジリティの評価等の整備が必要
↓• 従来の弾性範囲の評価
を置き換える塑性変形能力・疲労・弾塑性応答を考慮した現実的な評価法を整備• 可搬機器等のフラジリ
ティ評価法等を整備
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
弁の加振試験・機能維持限界評価
・加振試験による機器・配管系(配管サポート等)の限界耐⼒評価・機器・配管系の弾塑性評価法の整備と⾼度化・規格化・配管系簡易弾塑性評価法の構築
・安全係数法に基づく機器フラジリティ評価⼿法の⾼度化・可搬設備等のフラジリティ評価⼿法構築・地震損傷データに基づく現実的フラジリティ評価⼿法構築
機能維持確認済加速度確認①,②▽
弾塑性応答評価の許容基準値・疲労評価法提案①,② ▽
機器・配管系の弾塑性解析法提案①,②▽
損傷モードに応じた許容値・地震動指標・累積疲労評価法の整備
現実的な機器・配管系の▽耐震評価法構築①
動的機器の現実的機能維持限界評価法構築①,② ▽
高度化された係数評価法、可搬設備等のフラジリティ評価法構築①,②▽
配管系簡易弾塑性評価法構築①,② ▽
新規制基準を踏まえた機器・配管系評価法の整備
知見反映
知見反映
⾼振動数領域の取扱い・3⽅向地震動の組合せに関する評価法の構築
既設蒸気発⽣器伝熱管耐震設計合理化
高振動数領域の取扱い・3方向地震動組合せ評価法構築① ▽
蒸気発生器伝熱管耐震設計法構築① ▽
配管系フラジリティ評価法の⾼度化弾塑性応答を考慮した配管系フラジリティ評価法構築①,②▽
△機器・配管系の弾塑性評価法の規格化案①,②
△機器・配管系の弾塑性評価法の精緻化①,②
地震損傷データに基づく現実的フラジリティ評価法構築①,② △
15

8-4. 地震/耐震【地震フラジリティ(建屋)】項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
合理的な耐震設計手法及び耐震安全性評
価手法
大入力に対する建屋の3次元挙動に関する知見の補強が必要RC部材の地震経験依存性に関する知見の補強が必要
↓• 建屋3次元FEM解析による建屋挙動に関する知見の蓄積• 建屋の3次元振動特性評価法の提案• 地震後剛性低下を考慮した地震荷重評価法の整備
免震構造の極限荷重設計法
免震建屋の耐震設計限界が線形までとなっている
↓• 線形限界を超える免震建屋の応答評価法の提案
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
免震建屋の終局挙動評価⼿法の構築△現行設計限界を超える
免震応答評価法①、②
3次元耐震性能評価法の提案①,②△
実建屋の地震観測による3次元振動特性同定法開発
RC部材の高加速度試験法の整備①,② △
地震経験を考慮した地震荷重評価法の開発
地震後剛性低下を考慮したRC部材の地震荷重評価法整備①,② ▽
建屋の3次元応答特性評価手法提案①,② ▽
⼤⼊⼒に対する建屋挙動評価(3次元モデル・地盤-建屋相互作⽤など)
知見反映
知見反映
次フェーズ︓免震建屋フラジリティ評価⼿法開発
フェイルセーフ機構を含む冗長性評価技術①、②▽
次フェーズ︓既設建屋の安全性評価⽀援技術
知見反映
大入力時の建屋挙動評価法、影響評価法高度化①,②△大入力時の建屋挙動評価法、影響評価法①,②△
16

8-5. 地震/耐震【地震フラジリティ(地盤、斜⾯、⼟⽊構造物)】
項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~地盤・斜面
評価
基準地震動の増大に伴って,二次元等価線形に基づく照査及びリスク評価,液状化評価では厳しい場合があるため,より現実的な解析手法の開発と合理的なリスク評価の導入が必要
↓• 2D及び3D時刻歴非線
形解析の実用化• 非線形解析及び不連続
体解析を用いたリスク評価手法の確立• 合理的な液状化予測手
法の開発
土木構造物評価
基準地震動の増大に伴って,二次元解析による安全側の照査では厳しい場合があるため,より現実的な解析手法や合理的な照査指標の導入が必要
↓• 地盤構造物連成系の三
次元非線形解析および変形・ひずみに基づく性能照査手法を構築• 詳細な崩壊機構、機器
境界部、補修効果が耐震性に及ぼす影響評価方法の提案
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
次フェーズ(構造健全性評価)
評価⼿法の⾼度化,実⽤化など
影響評価手法確立①,② ▽
三次元時刻歴⾮線形解析⼿法の開発
基礎地盤への実用化①,② ▽
斜⾯崩落/基礎地盤のリスク評価
⼆次元時刻歴⾮線形解析⼿法の開発
地中構造物の三次元⾮線形解析RC構造物の三次元解析ベンチマーク実験
地中⼟⽊構造物の耐震性能照査⼿法の標準化/⾼度化/実⽤化
鉄筋コンクリート構造物の崩壊挙動評価
構造物と機器の境界部の解析的検討補修・修復されたコンクリートの耐候性検討
三次元地震応答解析手法実用化①,② ▽
終局耐震性検討▽手法構築①,②
合理的な液状化予測⼿法開発
▽実岩盤への実用化①,②
3Dすべり安全率の評価手法確立①,② ▽
PRA手順書作成② ▽
不連続体解析による斜面崩壊解析手法確立①,② △
三次元時刻歴⾮線形解析⼿法の実⽤化
地盤物性のバラツキの合理的な評価⼿法
リスク評価(斜⾯崩落,断層変位)
液状化予測手法確立①,② ▽
岩盤構成モデル開発①,②▽
岩盤物性の合理的評価法確立② ▽
調査・観測法の⾼度化
17

9-1. 敷地直下断層評価【活断層の判定】項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
基盤岩内の断層破砕性状に基づく活動性
評価
評価基準となる上載層の年代が不明、あるいは欠如している場合、断層活動性評価が困難
↓• 断層破砕性状に基づく
活動性評価手法の構築• 従来手法では測定でき
ない地層に適用可能な年代測定手法の構築
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
活断層と⾮活断層の⽐較調査・分析、既往知⾒も踏まえた調査・評価⼿法の体系化・確⽴
断層破砕帯の詳細構造・構成物質分析
断層破砕性状に基づく活動性評価手法の提案①,② ▽
調査・評価手法の体系化①,② ▽
断層破砕帯の現地調査(活断層/⾮活断層)
新たな年代測定⼿法の開発年代測定手法確立①,② △
知見反映
比較
試料
知見反映
NRRC共研とタイアップ
断層破砕帯試料の▽処理方法の構築①
△断層破砕装置及び
試験法の構築①,②
岩⽯せん断実験による断層破砕過程の再現
断層破砕性状の定量的評価法構築①,② ▽
年代測定装置及び測定手法の構築①,② △
18

項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~断層変位評価 不確実さの幅が広い断層
変位量の予測手法が未確立。実際のデータも少数。
↓• 衛星画像データの活用
によるDBの拡充• 数値解析手法の確立
断層変位に対する設計を行ううえで、変位に対する構造物の許容値等を含む設計基準自体が未整備
↓• 実験及び数値解析によ
り、変位応答評価手法、許容値を含む設計基準を策定
定量的なリスク評価を行う上で、断層変位に対するPRA評価手法自体が未整備
↓• フラジリティ評価手法の
確立、事故シーケンス評価を実施し、PRA手法を確立
9-2. 敷地直下断層評価【断層変位評価】▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
動⼒学的モデル/HPCによる断層変位評価の構築
▽断層変位ハザード評価手法構築②
▽断層変位評価手法提案①,②
入力条件▽地震動との重畳を考慮した評価手法構築①,②
建屋・構造物や機器・配管系の断層変位に対するフラジリティ評価⼿法、断層変位に対する事故シナリオ検討による、PRA⼿法構築
▽地震動との重畳を考慮した評価手法提案①,②
断層変位に対する損傷評価手法提案①,② ▽
▽地震動との重畳を考慮したPRA手法構築②
断層変位に対するPRA手法提案② ▽
地震動との重畳を考慮した解析手法提案①,② ▽
断層変位で被害を受けた構造物周辺の地盤変形量のDB化
衛星画像解析に基づく地表地震断層の定量評価(DB拡充)
屋外重要⼟⽊構造物の断層変位に対する評価⼿法の確⽴
確率論的断層変位ハザード評価の⾼度化
主断層/副断層の認定⼿法開発
原⼦炉建屋の断層変位に対する評価⼿法の確⽴(フェーズ2)
フェーズ2
検証
変位と地震動の重畳の検討
経験式の改良
19

10. 津波【ハザード/フラジリティ】項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
津波ハザード評価
古津波による,信頼できる被害津波記録は少なく,津波規模推定の不確実性大.非地震性津波評価手法に関する知見の補強が必要
↓• 地質学的調査で古津波
の知見を増やし,不確実性の定量化精度向上• 数値解析手法や確率論
的評価手法の確立により非地震性津波のリスク評価法確立
津波PRAプロジェクト
津波フラジリティ・耐力評価
様々な津波影響を考慮した津波PRAの手法および手順に関する知見の補強必要また、津波影響評価技術に関する新知見の検証が必要
↓• 津波PRAにおけるフラ
ジリティ評価の試行を通して、評価手法および手順を提案• 新知見を収集すると共
に、それを踏まえた津波影響評価手法の検証および高度化
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
津波堆積物に関する現地採取堆積物分析、堆積物⽣成過程模擬実験、評価⼿順確⽴
△ ハザードレベルに応じた津波フラジリティ評価手法提案②
▽ 配管・機器の対津波設計手法整備①,②
津波影響評価⼿法の⾼度化(溢⽔/津波荷重/漂流物影響/浮遊砂影響)
概略評価 詳細評価
津波PRAにおけるハザード評価〜フラジリティ評価の試⾏
△ ハザードレベルに応じたスクリーニング概念提案②
△ 浮遊砂影響評価手法整備①,②
溢水評価手法整備①,② ▽
▽国内適用③,④
⾮地震性波源(地すべり)の考慮による確率論的津波ハザード評価⼿法の拡張
▽非地震性の波源を考慮した確率論的津波評価手法試行①
津波以外のイベントを考慮したイベント堆積物の評価⼿順確⽴
△イベント堆積物に基づく津波判定模評価手法確立①,②
小型船舶を対象とした漂流物▽ 影響価手法提案①,②
陸上及び海底の地すべり等に起因する津波の評価⼿法の構築(数値解析⼿法)▽火山現象(カルデラ陥没)による津波評価手法確立①②
▽堆積物分析に基づく津波の判定評価手法提案①,②
地震動起因の海底地すべり)を▽考慮した確率論的津波評価手法提案②
⾮地震性波源(地すべり以外含む)の考慮による確率論的津波ハザード評価⼿法の拡張
イベント堆積物の判定における不確実さ評価⼿法
20

11. ⻯巻等極端気象【ハザード/フラジリティ】項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
極端気象ハザード評価、飛来物影響
評価
台風ハザード,竜巻ハザードに対する地形影響,地域特性,飛来物影響に関する合理的な評価方法の開発や最新知見の補強が必要
↓• 台風影響評価法の開発• 日本の竜巻強度指数や
気象・地形条件を適切に考慮できる合理的な設計竜巻評価法の開発• 日本の発電所条件に適
した確率論的竜巻飛来物影響評価モデルや変動風速評価法の確立
強風PRAプロジェクト
竜巻等極端気象に対する対策工評価と固縛対策支援技
術
竜巻飛来物のリスクを定量化する方法が整備されておらず,過剰な対策を避けるための合理的な対策設計法が必要
↓• フラジリティ評価やリス
ク論に基づく合理的な対策工評価の提案• 竜巻の検知・予測など、
ソフト的な固縛対策支援策の開発
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
ハザード評価モデルTOWLAの改良⾶来物速度評価コードTONBOSの改良
⾶来物対策⼯評価に関するバックデータ蓄積/数値解析⼿法の確⽴
▽竜巻飛来物に対する合理的な対策工や評価法確立①
確率論的⾶来物評価法の構築とその数値解析コードTOMAXIの開発
▽日本の諸条件に適合する竜巻影響評価法確立①,②
台⾵ハザード評価法と台⾵影響評価法の開発
リアルタイム⻯巻検知・予測システムの構築
台風影響評価法確立①,②▽
▽固縛対策支援策確立①
損傷リスク情報に基づく対策設計⼿法の開発
⽇本版改良藤⽥スケールに適合した⻯巻影響評価法の開発
計画中
建物影響を考慮した変動⾵荷重評価法の構築
強風リスク検知・予測ツールの開発・実サイト適用性評価
健全性評価に関する数値解析⼿法の確⽴
▽確率論的な飛来物影響評価手法確立②
21

12. ⽕⼭【ハザード/フラジリティ】項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023~
降灰ハザード評価
降灰荷重ハザードについては決定論的評価が行われている。機器脆弱性評価と関連が深い噴煙・降灰の数値解析では、適切な計算条件の設定が課題となっている。
↓• 降灰履歴に基づくハ
ザード曲線を新たに策定• 降灰ハザード評価のた
めの再現計算を実施,高精度予測のための降下火砕物輸送の素過程を評価
降灰PRAプロジェクト
降灰に対する脆弱性評価
火山灰に対する機器脆弱性について、定量データが不足。効率的な対策の選択肢も乏しい。
↓• 火山灰に対する機器脆
弱性試験を実施• 火山灰用プレフィルタを
提案
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
ハザード曲線
▽火山灰用プレフィルタ提案①
▽除灰システム提案①
マグマ特性と降灰の特性を関連づけるモデル構築・検証
⽕⼭噴⽕履歴データの拡充(降灰量・年代)
▽文献ベースのハザード曲線提案②
ハザード曲線の改善
⽕⼭灰⽤プレフィルタの性能・再⽣試験
ディーゼル発電機吸気⼝に侵⼊する粒⼦量評価(試験・数値解析)
重⼒沈降式除灰システムの提案(試験・数値解析)
▽ハザード曲線改良②
計画中
PRA評価に追加すべき試験を実施
降灰ハザード評価のための⻑期気象データに基づく再現計算代表的気象条件の選定・定常⾵向場でのFall3D解析⼿法整備
巨⼤噴⽕の噴煙・降灰評価
代表的降灰粒径の評価⼿法開発▽粒径評価手法提案②
知見反映
知見反映
降下⽕砕物輸送の素過程の⾼精度予測(噴煙柱・地形影響)
ハザード曲線改良/高精度予測手法②▽
▽風向頻度評価提案②
22

2020
項 ⽬ ギャップ/解決⽅策 〜2018 2019 2020 2021 2022 2023〜
1. リスク情報活用に関する理解向上に向けた社内RCの要点分析
部門間に亘るリスク情報活用に対する共通理解の醸成が求められている。
↓• 安全管理、運転、保守及び
地域対応に関わる部門間のRCにおける要点表出
2. 事業者のRC戦略の妥当性評価のための調査手法開発
新たにUPZに入った地域の情報提供ニーズ及び公衆から得られた意見と、RC戦略にギャップが生じている。
↓• RC戦略の妥当性評価に資
する調査手法の開発
3. 一般公衆がリスクと考える情報に関する対話技法の開発
事業者責任範囲で回答できる地域ニーズに限りがある。
↓• 地域住民が知りたい情報に
関する適切な発信者(事業者、国、自治体等)とその内容の明示
4. SNS等を活用した地域対話活動の新たな場
の構築
若者層及び女性層等との接点が不足している。
↓• SNS等を活用した地域対話
活動の新たな場の提供
リスク情報を活⽤した⾃主的安全性向上を⽀援するRC⽅策の提案
各社聞き取りによる、部⾨間のリスク情報に対する捉え⽅の違い(乖離)等の同定
乖離の要因分析乖離を埋める⽅策
の検討
リスク情報に対する捉え方の違い ▽⑤
社内RCにおける乖離の要因分析結果 ▽⑤
社内RCにおける乖離を埋める方策の提案▽⑤
パイロットサイトでの調査⼿法開発
事業者のRC戦略の妥当性に関する調査・分析結果 ▽⑤ ▽⑤
事業者のRC戦略の妥当性評価に資する調査手法 ▽⑤
実験的地域コミュニティの構築・課題抽出 運⽤⼿法の整理
地域コミュニティの構築 ▽⑤
原子力に係る情報提供の試行結果 ▽⑤
原子力の話題を扱える信頼感が醸成された地域コミュニティの構築方策 ▽⑤
パイロットサイトでのRC設計・実施・分析 他サイト適⽤・評価
オフサイト情報を含めた地域住民が求めるリスク情報の発信に関する調査・分析結果
▽⑤ ▽⑤
一般公衆がリスクと考える情報に関する対話技法の提案
▽⑤
他サイト適⽤・評価
【項目(~2020)】電気事業者内部/外部におけるRC方策
【項目(~2020)】立地地域におけるRC方策
国外良好事例 ▽⑤
リスクマネジメントにおけるRC方策 ▽⑤
リスク情報に基づく双方向対話方策▽⑤
RC実施における要点及びコンテンツ等の提案
▽⑤ ▽⑤
良好事例▽⑤
13.リスクマネジメントを⽀援するリスクコミュニケ-ション技術の開発
RC:リスクコミュニケーション SNS: Social Networking Service
▽︓R&D成果(①-⑤︓成果の適⽤先)
実務現場ニーズに基づくRC調査実験と良好事例の蓄積
23