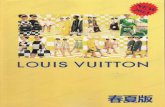News Release...News Release 今年の夏休みは、「映画ドラえもん のび太の宝島」と東急ハンズがコラボ 夏休み限定「ドラえもんとひみつ探しに出発だ!」開催!
NEWS LETTER global ver. 2014 ( 平成 26) 年夏号 NEWS ...µ·外NL2014...NEWS LETTER global ver....
Transcript of NEWS LETTER global ver. 2014 ( 平成 26) 年夏号 NEWS ...µ·外NL2014...NEWS LETTER global ver....

NEWS LETTER global ver. 2014 (平成 26) 年夏号
- 1 -
NEWS LETTER 2014 年夏号(2014 年 7 月 15 日発刊)
本号の目次 ニュース
<トップニュース>
・海外勤務者の社会保険の報酬取扱い… 1
・海外勤務者の社会保険の報酬取扱い
(トップニュースの解説)… 2
・韓国をはじめアジア各国で定年引上げ… 3
・中国・上海市の邦人数が約 1 万人減少… 3
・中国 2014 年度の平均昇給率は 8.8%とな
る見込み… 4
中国人事労務コラム
中国の労働裁判に対する企業の心積もり… 5
海外赴任コラム
海外赴任規程とは何か ~海外赴任規程 を構成する要素~ … 6
外国人雇用コラム
健康保険 海外にいる家族の扶養可否… 7
世界各国の労働法制
香港(中華人民共和国香港特別行政区華人 民共和国)… 8
<トップニュース>
海外勤務者の社会保険の報酬取扱い
海外勤務者に支払われる給与等については、社会保険制度において、保険料などの算定を行う際の
報酬の取扱いが具体的に言及されていないことから、その判断に迷うことがあります。特に海外法人から支
給される報酬については、それが算入の対象とならなければ、将来の年金額が減少してしまうため、その
取扱いの判断は重要といえます。そのような中で今回、日本年金機構より、海外勤務者の報酬の取扱いに
ついてまとめられたリーフレットが公開されました。リーフレットでは、海外勤務者の報酬に関する基本的な
考え方が示されており、要点は以下のとおりとなります。
(1)海外勤務者の社会保険加入の取扱い
国内の厚生年金保険適用事業所での雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、出向元から給
与の一部(全部)が支払われているときは、原則として、健康保険・厚生年金保険の加入は継続します。
(2)国内および海外双方から給与等の支給がある場合の取扱い
海外の事業所から支給されている給与等であっても、適用事業所(国内企業)の給与規定や出向規
定等により、実質的に適用事業所(国内企業)から支払われていることが確認できる場合には、その給
与等も社会保険制度において「報酬等」に算入することになります。
■日本年金機構 リーフレットのダウンロードページ
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000020022FUlxbluFis.pdf
出典:日本年金機構ホームページ
海外労務版

2014 (平成 26) 年夏号 NEWS LETTER global ver.
- 2 -
海外勤務者の社会保険の報酬取扱い
(トップニュースの解説)
海外勤務者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格が、海外勤務後も継続するか否
かについては、その出向形態によって取扱いが異なり、具体的には、以下のとおり区分されます。
(1)在籍出向の場合
在籍出向の場合は、出向元である日本国内の適用事業所との雇用関係が継続しているため、出向元
から給与の一部が支払われているときは、原則として、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格が継
続します。
(2)移籍出向(転籍)の場合
移籍出向(転籍)の場合は、出向元である日本国内の適用事業所との雇用関係が消滅するため、健康
保険・厚生年金保険の被保険者資格は喪失します。
その上で、海外勤務後も被保険者資格が継続する場合、従業員に対する手当や旅費などの各種の
支払いが、保険料の算定対象となる「報酬等」の範囲は、基本的に、被保険者が労働の対償として受け
るすべてのものが対象であると規定されています。報酬等の一般的な対象判断を一覧にすると下表のと
おりとなります。
<報酬等の一般的な対象判断>
支払区分 支払例 報酬に
労働の対償として経常的かつ実
質に受けるもので、給与明細等
に記載があるもの
賃金、給与、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手
当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、海外勤
務手当、ハードシップ手当、留守宅手当 等
該当
労働の対償でないもの 傷病手当金、内職収入、労災法に基づく休業補償、解雇予告
手当、適用事業所以外(海外事業所等)から受ける収入 等 非該当
事業主が負担すべきものを立て
替え、その実費弁償であるもの 出張旅費、赴任旅費、渡航費用 等 非該当
恩恵的に支給するもので、常態
的な報酬でないもの 見舞金、結婚祝い金、餞別金、大入袋 等 非該当
海外事業所から支払われているが実質的に国内事業所の負担であると規程等で確認できるもの 該当
国内事業所の規程に定めがなく、海外事業所の労働の対償として直接支払われているもの 非該当 参考:日本年金機構ホームページ
なお、上記判断はあくまで一般的な場合を想定したものとなります。名称だけではなく、個別の実態
に合わせて、対象であるか否かの判断がなされますので、判断が難しい場合は、社会保険労務士等の
専門家や管轄の年金事務所に確認し、正しい取扱いを行うようにしましょう。

NEWS LETTER global ver. 2014 (平成 26) 年夏号
- 3 -
韓国をはじめアジア各国で定年引上げ
2014 年 5 月、韓国では、「雇用上の年齢差別禁止および高齢者雇用促進に関する法律」の改正法が
施行されました。今回の改正においては、これまで努力義務であった 60 歳以上の定年制が、2016 年 1 月
から、まずは 300 人以上の事業場から義務化されることとなり、2017 年 1 月にはそれ以外の企業にも義務
化の範囲が拡大される予定となっています。
定年の引上げが行われているのは、韓国だけでありません。マレーシアでは、2013 年 7 月に 低定年法
が施行され、定年の 低年齢が 60 歳とされたほか、タイやシンガポールにおいても、定年引上げの議論
がなされています。
このようにアジア各国では、定年引上げの動きが加速していますが、その背景としては、日本だけでなく
アジア各国で生じている労働力不足が一因であるとみられます。
<アジア各国の定年制度状況>
国名 定年制度の状況
日本 低定年年齢 60 歳。さらに、65 歳までの雇用確保が必要。
韓国 2016 年 1 月より 低定年年齢を順次 60 歳に引上げ。
マレーシア 2013 年 7 月より 低定年年齢は 60 歳。
中国 男性 60 歳、女性 50 歳、女性幹部 55 歳(引上げが議論されている)。
タイ 60 歳(65 歳への引上げが議論されている)。
シンガポール 法定年齢 62 歳、希望者 65 歳まで再雇用(67 歳への引上げが議論されている)。 参考:日本貿易振興機構(ジェトロ)ホームページ等
中国・上海市の邦人数が約 1 万人減少
日本企業のアジア進出が加速することに伴い、アジア各国には日本企業から赴任した駐在員やその家
族が多数在留しています。その中で も在留邦人数が多い都市は中国・上海市ですが、今回、その上海
市の在留邦人数に大幅な変化がみられました。2014 年 5 月 23 日、中国・上海市の日本総領事館が発表
した統計によると、2013 年 10 月 1 日時点での上海市の在留邦人数は約 47,700 人であり、前年同時期の
約 57,000 人から約 1 万人減少したことがわかりました。上海市の在留邦人数が前年対比で減少したのは、
日本総領事館が統計を取り始めた 1994 年以来、初めてのことです。
上海市の邦人数が減少に転じた理由としては、PM2.5 がもたらす大気汚染による健康被害への不安等
いくつかの要因が考えられます。 近では、日本企業からの赴任者が帯同家族を日本に帰国させたり、新
たに赴任する際には単身赴任の形態を採るようになっており、その結果が顕著に表れているといえます。
参考:レコードチャイナ
<参考:アジア各国の邦人数(上位 10 国)> ※表中、( )内は 2010 年 10 月 1 日時点の人数
国名 邦人数(人) 国名 邦人数(人)
中国 150,399 (131,534) フィリピン 17,822 (18,202)
タイ 55,634 (47,251) 台湾 15,870 (21,559)
韓国 33,846 (29,064) インドネシア 14,720 (11,701)
シンガポール 27,525 (24,548) ベトナム 11,194 (8,543)
マレーシア 20,444 (9,705) インド 7,132 (4,501) 出典:外務省領事局政策課「海外在留邦人数調査統計 2013 年要約版(2012 年 10 月 1 日現在)」

2014 (平成 26) 年夏号 NEWS LETTER global ver.
- 4 -
中国 2014 年度の平均昇給率は 8.8%となる見込み
ニューヨークに本社を置くコンサルティング会社、Towers Watson が中国の 515 社に向け、「2014 年
新の人的資源動向」についての調査を行ったところ、88%の企業が 2014 年に増員する計画があり、増員
率は平均で約 10%という結果が出ました。2013 年の実質賃金の上げ幅は平均 8.5%、賞与は平均 3.4 ヶ
月分という結果でありましたが、調査に回答した企業の 2014 年度の昇給、賞与の計画予想よると 2014 年
の賃上げ率は平均 8.8%に達する見込みで、昨年に比べ小幅の上昇が見られ、賞与も平均 3.6 ヶ月に増
額する様相を呈しています。
業界別では、2013 年の平均賃上げ幅はハイテク企業(9.6%)が首位に立ちましたが、2014 年は 9.5%
になる見通しであり、この点から見れば 2014 年も賃上げの勢いは続くものと思われます。また、不動産業
の人材競争において近年、住宅市場の不況の影響はほとんど見られず、2014 年の賃上げ幅は 9.9%にな
る見込みです。Towers Watson の中国総代表である許文宗氏は、「大規模不動産として 近は商業施設
が大きな注目を浴びているが、不動産業界全体としては人材の獲得競争が更に激しくなってきており、高
給を提示して優秀な人材を確保しなければならないという現状から見れば、賃金の高い上げ幅が示してい
る結果は納得できる。不動産業界の 2014 年の賃金の平均上げ幅は 10.6%にも達する可能性もあり、不動
産業界は絶対的なトップランナーとなっている。」とコメントしています。
地域別の賃上げデータでは、北京市・上海市・広州市・深セン市などの大都市では上げ幅に大きな違
いは見られません。広州市(8.3%)がやや低いことを除くと他の地域の上げ幅は 8.5%以上に達していま
す。また、蘇州市の 2014 年の賃上げ幅は 9.4%に達する見込みです。蘇州市は 2013 年の実質賃金の上
昇率は平均で 10%に達しました。これは多くの製造業が蘇州市に集積していることと関係があり、ここ数年
の労働力不足の影響によって、企業が労働力不足に直面しており、賃金の上昇が全体的に後押しされた
形となっています。
また今回の調査では、調査参加企業の 2013 年の離職率について正確なデータが提供されています。
全国平均では企業全体の離職率は平均 23.8%に達し、都市別では深セン市の離職率が他都市を上回り
33.3%に達しています。従業員の職務別では作業者全体の平均離職率が依然として他の職務を遥かに
上回っており、36.1%に達しています。
出所:2014 年 4 月 3 日『新聞早晨』 翻訳:プレシード

NEWS LETTER global ver. 2014 (平成 26) 年夏号
- 5 -
中国人事労務コラム
中国の労働裁判に対する企業の心積もり
2008 年 1 月、それ以降の中国の労働法制のす
べてを牛耳ると言っても過言ではない「中国労働
契約法」が施行されました。これを境に、中国現地
法人と従業員との間の労働裁判はうなぎ上りの一
途を辿っており、2008 年の労働裁判件数は上海
市で前年の約 2 倍、広東省では 3 倍以上の急激
な増加を示しています。10 年以上前、私が上海に
初めて足を踏み入れた時代は、企業、従業員とも
にまだ情を持って話し合おうという風潮が強く残っ
ておりましたが、今は法の後方支援を盾に争うとい
う、まったくもって殺伐とした労使関係になってしま
いました。
中国の司法制度は二審制を採っておりますが、
労働裁判となりますと一足飛びに司法に訴案を委
ねることはせず、まず準司法という位置づけである
「労働仲裁委員会」に不服申し立てを行うことにな
ります。この労働仲裁委員会は、企業を管轄して
いる地域の労働局の外局であり、主には従業員か
ら企業に対する仲裁申立によって審議が開かれる
ことになります。昨今、この仲裁件数自体が爆発的
に増加しており、おそらくどこの企業であっても仲
裁のひとつやふたつは経験していることでしょう。と
ころが被告である企業の、特にその本社サイドの
概ねの認識としましては、「争いごとはできるだけ
避け、穏便に済ますことはできないのか」というもの
が圧倒的に多く、「仲裁」と聞いただけで腰が引け
てしまうケースが大半を占めているのではないでし
ょうか。
この「穏便に済ます」というのが実は曲者でして、
それはすなわち「金で解決できないのか」ということ
とほとんど同意語になってしまうのです。金銭で片
づけようとすればそれは青天井の交渉になってし
まい、運よく双方の合意が取れたとしても、隠し事
のできない中国では、多額の金銭を払ったという
事実を他の従業員たちは瞬く間に知ってしまい、
それが企業のスタンダードになってしまうのです。
つまりこの某従業員だけの問題ではなく、今後企
業に残り続ける従業員に対する示しもつかなくなっ
てしまうのです。
私は常々、「企業は法律以下のことをしてもいけ
ません。でも法律以上のことをしてもいけません」と
いう持論をあらゆる機会に訴えてきました。従業員
に対しては法律どおりのことを行い、それで相手が
不服であれば、躊躇することなく労働仲裁を活用
すればよいのです。労働仲裁委員会はまず、双方
の主張を聞き、事実を確認し、証拠を提出させ、
終的に和解を勧めてきます。肝心なのは従業員に、
主張がそのまま通るとは限らないということを理解さ
せることなのです。それに加え、直接交渉の中で
は折り合いがつかないのが通常ですので、それを
第三者であり、公的な機関でもある仲裁委員会に
委ね、判断してもらう。この企業としての姿勢こそが、
欧米企業に肩を並べられるほどの強いマネジメン
トの姿勢でもあるのです。
(執筆:プレシード 中国人事労務コンサルタント 清原学)

2014 (平成 26) 年夏号 NEWS LETTER global ver.
- 6 -
海外赴任コラム
海外赴任規程とは何か ~海外赴任規程を構成する要素~
「海外赴任規程を
整備したい」と考える
海外進出企業は少な
くありません。しかし、
この規程の中にどの
ようなことを網羅すれ
ばよいのかわからず、
インターネット上のサ
ンプル規程をダウンロ
ードしてみてもそこに
記載された内容が自
社の運用等とまったく
異なる内容であることによって、結局、作成に向け
ての着手がまったく進まないというケースも多くみら
れます。
そもそも「海外赴任規程」とは、海外赴任者に関
するルール全般をまとめた規程となりますが、様々
な角度からみてみると、そのルールは実に多岐に
亘っていることがわかります。例えば、海外赴任者
の賃金のルールはどのように設定されるのかという
内容もあれば、赴任や帰任にあたっての休暇、服
務規律等のルールはどうするのかという点もありま
す。更には、海外赴任者が現地に赴任中に帯同
家族や日本国内に残された家族の慶弔時にどうい
った取扱いをしなければならないのかという実際に
現地に行って事態が起きないとわからないような問
題もあります。
こうしたルールを紐解き始めると、膨大なルール
設定をどうまとめていくのかという点で困惑してしま
い、通常の日常業務よりも優先順位が下がり、結
局、なかなか作成が進まなくなってしまいます。そ
のような場合は、日本の通常の就業規則や諸規程
と同じものを海外版として作成をしていくと考えると
よいでしょう。例えば、日本国内の慶弔見舞金規
程については、海外赴任者を対象とした「海外赴
任者慶弔見舞金規程」と考えることができますし、
出張旅費規程については、海外赴任者が現地に
おいて、現地や第三国への出張にあたってのルー
ルとして「海外赴任者出張旅費規程」としてまとめ
ることができます。
もっとも、海外赴任者数が企業全体でわずか数
名程度しかいないにも関わらず、大袈裟に細かい
ルールを整備する必要があるのかという問題もあり
ます。確かに、ルールとしては整備をした方がよい
のは間違いないのですが、そもそも海外赴任規程
を整備する目的は、海外赴任者が一定のルール
に従って安心して現地で働いてもらうことにありま
す。よって、自社の規模や実態に合わせて 低限
のルールをまずは整備し、滞在期間が長くなるに
したがって、こうした規程も徐々に内容の追加等を
行っていってもよいでしょう。

NEWS LETTER global ver. 2014 (平成 26) 年夏号
- 7 -
外国人雇用コラム
健康保険 海外にいる家族の扶養可否
外国人従業員の中には、母国に家族を残して、
単身赴任で日本に働きに来ており、その家族に仕
送りをして養っているという場合があります。時折、
そのような外国人従業員から、「母国にいる家族を
健康保険の被扶養者にできないか」という要望を
受けることがあります。
この点について、健康保険の制度ではどのよう
な取扱いがされているのでしょうか。そもそも被扶
養者の加入基準について、日本国内に在住して
いなければならなないという要件はありません。そ
のため、海外に住んでいる家族であっても、主とし
て被保険者(その従業員)の収入で生計を維持し
ているということが確認できるのであれば、日本人
と同様の要件のもと、健康保険の被扶養者となる
ことは不可能ではありません。例えば、日本人の
場合であっても、大学生の子が海外留学をしてい
るといった場合は同様の扱いとなるわけです。
別居している家族が被扶養者となれる要件
海外に住んでいる(=別居している)家族が被
扶養者となるための要件は、次の 2 つです。
<要件①>被扶養者となる家族の範囲
被保険者と別居していてもよい者
○配偶者(内縁関係でも可)
○子、孫および弟妹
○父母、祖父母などの直系尊属
<要件②>被扶養者となる収入要件
被保険者と別居している場合の必須要件
○年収 130 万円未満(60 歳以上や一定の障害者
の場合は 180 万円未満)
○年収が被保険者からの仕送額より少ない
よって、要件①に該当する家族の収入(日本円
換算した金額)が要件②を満たしているのであれ
ば、被扶養者となれる可能性があるのです。
被扶養者にするための手続
要件を満たす家族を被扶養者にする手続きとし
ては、国内在住者と同様に、「健康保険被扶養者
(異動)届」に必要事項を記載して管轄の年金事
務所へ届け出ることが必要となります。その際、海
外に住んでいる家族ということで特別に添付が必
要となるのが次の 2 つの書類です(対象の書類が
外国語で記載されている場合には、日本語訳を
添付する必要があります)。
要件①の確認書類
被保険者と対象家族の続柄がわかる証明書等
要件②の確認書類
被保険者が対象家族に送金を行っている事実がわか
るもの(通帳の送金記録等)
※必要となる書類は年金事務所によって異なる場合があります。
実際に海外にいる家族に傷病が発生し、医療
機関において診療を受ける場合、海外では日本
の健康保険証を使用することができないため、一
旦、現地において医療費の全額を立替払いした
上で、日本で健康保険の保険者にその診療内容
の明細書や領収書を日本語に翻訳した文書ととも
に提出し、療養費の請求を行うことになります。
以上のとおり、海外にいる家族については、海
外にいることのみをもって被扶養者となれないわ
けではありませんが、その加入・給付申請の手続
きが煩雑であることに加え、昨年、海外療養費の
不正請求事案が複数明らかとなったことを受けて、
審査が強化されており、現実的には被扶養者にな
ることが難しい状況であります。よって、一般的に
は、家族自身で自国の医療保険に加入し、そちら
で給付を受けるということとなります。
(注)保険者が健康保険組合等である場合は、独自の基準を設
けている場合がありますので、保険者にご確認ください。

2014 (平成 26) 年夏号 NEWS LETTER global ver.
- 8 -
世界各国の労働法制
香港(中華人民共和国香港特別行政区)
1.概況
香港の労働関係の取扱いについては、基本的
に「雇用条例」において定めがされています。「雇
用条例」とは、使用者が従業員に保障すべき各種
の労働条件が規定されたものです。労使間で特段
の約束がない場合には、雇用条例の取扱いに従う
こととなります。
この雇用条例に定められた権益を享受できる従
業員は、「継続的契約」に該当する者です。継続
的契約とは、①連続して 4 週間あるいはそれ以上
の期間、かつ、②1 週間における労働時間が少な
くとも 18 時間以上の雇用を、同一の企業から受け
ている場合をいいます。企業と従業員との関係が
継続的契約とみなされた場合、当該従業員は、休
日、年次有給休暇及び傷病手当等の権益を享受
することができるのです。
2.祝日
香港の祝日は、以下のとおりです。なお、祝日の
具体的な日付は毎年異なります。
<2014 年の場合>
日付 祝日の名称
1 月 1 日 元日
1 月 31 日 旧暦正月
2 月 1 日 旧暦正月の 2 日目
2 月 3 日 旧暦正月の 3 日目(4 日目)
4 月 5 日 清明節
4 月 18 日 グッド・フライデイ★
4 月 19 日 グッド・フライデイの翌日★
4 月 21 日 イースター・マンデイ★
5 月 1 日 労働節
5 月 6 日 釈迦生誕節★
6 月 2 日 端午節
7 月 1 日 香港特別行政区設立記念日
9 月 9 日 中秋節の翌日
10 月 1 日 国慶節
10 月 2 日 重陽節
12 月 22 日
12 月 25 日
冬節またはクリスマス(どちらを
法定休日とするかは任意選択)
12 月 26 日 クリスマス後の 初の平日★
※★印は、雇用条例以外に設定された法定休日以外の公休日。法定休
日以外の公休日を休みとするかどうかは、企業が自由に決定できます。
3.雇用契約と就業規則
香港の雇用条例おいて、雇用契約は書面ある
いは口頭形式のどちらでも成立するとされていま
す。また、就業規則の作成義務もありません。しか
しながら雇用契約を口頭で済ましてしまうことは、
労働トラブルを招くもとであり、雇用契約書を交わ
し、就業規則において自社の就業ルールを明確
にしておくことは重要です。
このコーナーでは毎回 1つの国を取り上げ、
その国の労働法制について紹介します。
今回は、香港(中華人民共和国香港特別行
政区)です。
国 名:中華人民共和国香港特別行政区
(Hong Kong Special Administrative Region of the
People’s Republic of China)
通 称:香港(Hong Kong)
面 積:1,104.4 平方キロメートル(東京都の約半分)
人 口:711 万人(2011 年末時点/出所:ジェトロ調べ)
言 語:中国語(一般には広東語が多い)・英語
公用語:中国語(北京語:繁体字)・英語

NEWS LETTER global ver. 2014 (平成 26) 年夏号
- 9 -
4.試用期間
香港の雇用条例上、試用期間の長さについて
は定めがありません。よって、試用期間の長さ
は、試用期間を設けないということを含め、自
由に設定ができますが、実態としては 3 ヶ月と
しているところが多いようです。
なお、試用期間中は、次表のとおり、労使双
方より契約の解除を行うことができます。
試用期間中 雇用契約の解除
最初の 1 ヶ月 労使双方即日解除可能。
2 ヶ月目以降、
試用期間満了
まで
労使双方 7 日以上の予告期
間を設けること、または解
雇予告手当を支払うことに
より解除可能。
5.労働時間・休日
香港においては法律上、労働時間の上限時間
等は設けられていません。そのため、労使で自由
に所定労働時間の設定を行うことができます。た
だし、休日については、7 日ごとに少なくとも 1 日
与えなければならないとされているため、週 1 日以
上の休日は必要となります。
6.割増賃金
香港の雇用条例において、割増賃金率につい
ては特段の定めがありません。そのため、時間外
労働を行う際などの割増率については、労使間で
自由に設定をすることができます。
7.年次有給休暇
年次有給休暇は、12 ヶ月以上の期間雇用され
た場合に、次表の付与日数に基づく取得権利を
有することとなります。具体的な年次有給休暇の
付与日数は、次のとおりです。
勤続年数 付与日数
1年 7日
2年 7日
3年 8日
4年 9日
5年 10日
6年 11日
7年 12日
8年 13日
9年以上 14日
8.傷病手当
香港では、従業員が医師の証明に基づく傷病
により、連続して 4 日以上休業する場合には、企
業は傷病手当を支払う必要があります。その際に
支払いを要する補償額は、その従業員の 1 日あた
りの平均日給の 80%となっています。
また、傷病手当の支払いを要する日数は、入社
1 年目は 1 ヶ月の勤務につき 2 日ずつ、入社 2 年
目以降は 1 ヶ月の勤務につき 4 日ずつ権利が発
生し、 大 120 日まで累計することができます。

2014 (平成 26) 年夏号 NEWS LETTER global ver.
- 10 -
9.解雇補償金・長期服務金
解雇補償金・長期服務金は、従業員が一定の
条件の下、解雇や退職した場合に企業が支払わ
なければならないものです。それぞれ雇用期間
による条件があり、次表のとおりとなっていま
す。なお、この 2 つを同時に受給することはで
きません。
解雇補償金 継続的契約に基づく2年以上の雇
用期間が必要。
長期服務金 継続的契約に基づく5年以上の雇
用期間が必要。
また、解雇補償金・長期服務金の計算方法は、
以下のとおりとなっています。
月給の従業員
(前月の給料もしくはHK$22,500の
いずれか少ない額)×2/3×雇用期
間の対象年数
その他の
従業員
(前30日の通常労働日のうち従業
員が選択した18日分の給料もしく
はHK$22,500のいずれか少ない額)
×2/3×雇用期間の対象年数 ※HK$1=約 13 円(2014 年 7 月現在)
10.年末手当(ダブルペイ)
香港の特徴的な賃金支払いの習慣として、年
末手当(ダブルペイ)があります。一般的には、
旧暦の正月(2014 年は 1 月 31 日)前に、1 ヶ
月分の給与額と同額以上を支給するものです。
ダブルペイは「13 ヶ月目の給与」と呼ばれてお
り、その制度を導入している場合には、賞与の
ように個人の評価や企業の業績等により支給
額を引き下げることはできず、1 ヶ月分以上の
支給を確約しなければなりません。
11.社会保障制度
香港において、企業に加入の強制がある公的な
社会保障制度は、次表のとおり、強制積立退職金
制度(MPF)と労災保険の 2 種類となっています。
香港では、強制加入の医療保険がありませんので、
一般的には、リスク対策として、民間の医療保険に
加入をすることがあります。
<社会保障制度>
制度 内容
強制積立
退職金制度
<MPF>
(確定拠出年金)
労使双方が支出をして積立
を行う確定拠出年金。原則と
して 65 歳から支給開始。
労災保険
(労災保険)
労災が発生した際には、一
旦企業が従業員への補償を
行い、労災認定がされた場
合には、労災保険より企業
に支給。
※( )内は日本の制度に例えた場合のイメージ。
12.台風・豪雨警報時の就業制限
香港は台風の進路となることが多く、台風や
豪雨の場合には、企業は基本的に労工処(日本
でいう労働局)のガイドラインに従い、次のよ
うな取扱いを行うことが一般的です。
始業時刻前に警報発令 出勤不要
警報解除 2時間以内に出勤
就業時間中に警報発令 原則帰宅
※出勤不要とした時間には、基本的に賃金支払いを行う。
参考:日本貿易振興機構(ジェトロ)ホームページ等
次号予告
次号(2014 年秋号)は、2014 年 10 月 15 日
発刊予定です。「世界各国の労働法制」の
コーナーでは、ベトナムを取り上げる予定です。
<免責事項>
当ニュースレターの掲載内容につきましては、細心の注意を払っておりますが、掲
載内容の正確性、有用性、確実性について当事務所が一切を保証するものではあり
ません。また、当ニュースレターに関連して損害等が生じた場合であっても、その理由
の如何に関わらず、当事務所は一切の責任を負うものではありません。