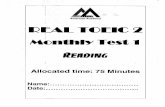Monthly No 31Microsoft Word - Monthly_No_31.docx Author 加藤 靖恵 Created Date 4/27/2012...
Transcript of Monthly No 31Microsoft Word - Monthly_No_31.docx Author 加藤 靖恵 Created Date 4/27/2012...

第 31号 発行:名古屋大学文学部
広報体制委員会 [email protected]
教員コラム―No.30
夜のルーヴルでアリマタヤのヨセフと会う 木俣 元一(美学美術史学)
短期間パリに調査に行くときには、美術館に行く時間がなかなか取れ
ないため、昼間に図書館で調べ物などをしてから、ルーヴル美術館の夜
間開館を利用して美術作品を見るようにしている。もちろん日中よりも
値段が安いこともあるが、何よりも夜の美術館のひっそりとした気分に
惹かれるところが大きい。とくに中世の工芸を集めた展示室はほとんど
私ひとりになってしまうことが多く、小さな工芸品と静かに向かい合っ
ていると、そこがルーヴルであることも忘れて、自分がどこにいるのか
わからなくなってしまうような不思議な感覚に襲われる。 ルーヴルが所蔵する中世の工芸品のなかでいちばん好きな彫像が、13
世紀後半にパリで制作された《十字架降下》の群像を構成するアリマタ
ヤのヨセフである。群像の中央でキリストの遺骸を十字架から降ろして
肩に担いでいるのだが、その重さにもかかわらず、すっと立っているそ
の姿全体の美しさがまず目を引きつける。聖母マリア、キリスト、そし
て右にひざまずくニコデモと考えられる男性像がいずれも顔を下に向けているのに対して、ヨセフは斜
め上に視線を向け、キリストを負いながらゆっくりと歩き出そうとしている。他の人物とは異なり、そ
の高貴な顔だちには悲しみなどの感情が表れておらず、淡々としていながらも内に秘めた強い意志を感
じさせる。 キリストやマリアさえも脇役としてしまうようなヨセフのこうした存在感は、この作品を当時所有し
ていた人物が自身を彼に重ねようとしていたことに由来するのかもしれない。そうだとしたら、死せる
キリストを背負って歩み出そうとするその想いはどのようなものだったのだろうか。夜のルーヴルはこ
んなことを考えるのにぴったりである。 授業紹介―File37 作品解釈の面白さ
専攻:ドイツ文学(文学・言語学コース)
授業名:ドイツ写実主義文学(2011 年度開講)
時代順にドイツ文学の代表的な作品をいくつか取り上げ、
それについての解釈の講義の授業です。今年の前期は写実主
義を扱い、シュティフター『晩夏』、ヘッベル『ユーディット』、
ラーベ『ライラックの花』、シュトルム『みずうみ』などの作
品を扱いました。 この授業は、ドイツ文学の専門科目であると同時に開放科
目にもなっています。従って、もちろんドイツ文学の専門生もいますが、なかには理系であっても興味
をもって受講に来る学生もいます。そのため、授業は予備知識がなくても十分にわかる内容ですが、専
門生でも興味深く感じる内容です。まずはあらすじ・一般的な作品解釈の説明があり、その後、先生ご
自身の解釈を紹介してくださいます。一見美しく見える作品でも、批判的な視点をもって読めば、意外
な解釈も可能となります。作品の中に隠された、作品成立の背景や作者の意図などが見えてきて、表面
とは全く違う内容が明らかになることもあります。

2012年 5月 10日
例えば、シュトルムの『みずうみ』を取り上げてみましょう。これは永遠の青春文学と呼ばれるほど
に甘く切ない作品です。穏やかなヒロイン、エリーザベトですが、彼女には主体性のなさという欠点が
浮かび上がってきます。シュトルムはこの作品で何が言いたかったのか。
シュトルムの妻コンスタンツェは情熱に欠ける女性で、彼は不倫のそし
りを恐れずに、別の女性ドロテーアを愛しました。エリーザベトのもと
を去る主人公ラインハルトには、そうした作者シュトルムの姿が重なっ
て見えてくるのです。 私自身、作品解釈の面白さを先生の授業で感じ、現在ドイツ文学研究
室に所属しています。ただ文学作品を読む以上に、より深く読み込んで
考察することの楽しさを知っていただければと思います。 [伊東 麻衣(博士課程前期課程2年)]
授業紹介―File38 古代ギリシア史の史料と解釈をめぐる諸問題
専攻:西洋史学(歴史学・文化史学コース)
授業名:古代ギリシア史の史料と解釈をめぐる諸問題 この授業は英語で発表された古代ギリシア史に関する最新の論文から最低でも 1人 1つの論文を読んで、その内容を 1回の授業で 2人の学生が発表するという形式で進んでいきます。先生の講義を聞くだけのような受身な授業ではなく、学生 1人 1人が主役となります。1つの論文は13~20ページほど。発表をしなければならないので、予習は必須です!勿論わからないところは先生や大学院生の先輩が教
えてくれます。 西洋史学の舞台の中心となるのはヨーロッパやアメ
リカを中心とする国々です。当然、先行研究も日本語で
なされたものより、英語やその他の言語で書かれたもの
の方が多いです。そのため、西洋史の研究をするのに外
国語は必須です。この授業では英語をただ単純に読むだ
けではなく、この論文が何を伝えたいのかを考えなけれ
ばなりません。西洋史の研究をする上で、しなければな
らない基本的なことが学べます。 確かに、英語の研究論文を 1人で読み進めるのは中々大変です。しかし読み進めていくうちに自分の知らなか
った歴史の側面が見えてきます。高校の時の教科書では、2~3行でさらりとしか書かれていなかったことの中に、これだけの背景とドラマがあったのか、ということが実感できます。例えば、私はアレク
サンドロス大王の死後におこったディアドコイ戦争についての論文を読みました。教科書では 3行で終わってしまう内容ですが、その中には何十人もの人々の物語がつまっていたのです。発表を終えた今で
は、そのたった 3行に対する見方がまったく違ったものになっています。そしてそれを自分で読み解いていくことはとてもやりがいのある、楽しい作業です。また、自分で発表をするだけではなく他の皆の
発表を聞くのも、とてもおもしろいですよ! [四井 美早紀(学部 3年)] 最近の文学部
新年度スタート いよいよ新学期が始まりました。この時期はあちらこちらに行列が… 私の研究室のある文学部本館2階は,237大講義室があるので、休み時間のお手洗いはフレッシュな1年生の列でにぎやか。文学部棟近くの南部食堂ではお昼に数十メートルの列ができ、みなさんご飯はちゃんと食べられるのかなと不安になります。(加藤)
*本紙では,名大文学部の多彩な内容を順に紹介していきますが,それまで待てない人は… 名大文学部のWEBサイト http://www.lit.nagoya-u.ac.jp/ まで(『月刊名大文学部』のバックナンバーもあります)