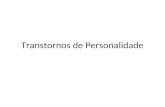MITS Design Pro CAM-TP - mitspcb.com · 1 Ⅰ.CAM-TPとは 加工機「FP-21T...
Transcript of MITS Design Pro CAM-TP - mitspcb.com · 1 Ⅰ.CAM-TPとは 加工機「FP-21T...
1
Ⅰ.CAM-TPとは
加工機「FP-21T Precision」の制御プログラムです。
CONVERTER や EASY CAD で作成した基板のデータを加工します。
[アプリケーション]から[CAM-TP]をクリックしてください。
2
Ⅱ.加工機の準備
1.各部の名称と働き
1 スピンドルモータ
工具を回転させるモータです。
2 吸塵ホース
ゴミを吸い取るためのホースです。この先に吸塵機を取り付けてください。
加工時には基板の削りかすが出ますので、吸塵機でゴミを吸い取ってください。
3 ベーク下敷き
加工テーブルの上にベーク下敷きを敷いて加工します。
3
4 基板
ベーク下敷きの上に基板を固定して加工します。
基板の固定方法にはテープまたはスプレー糊を使用します。
5 加工テーブル
加工ステージです。
加工テーブル保護のため、この上にベーク下敷を敷き、基板はベーク下敷きの上にのせて
加工します。
6 プレッシャーフット(基板押え)
プレッシャーフットで基板を押さえながら加工します。
FP-21T Precision のプレッシャーフットはHPタイプ(エア浮上型)が標準です。
プレッシャーフット自体は基板を上から押さえますが、プレッシャーフットの下の面から
エアを突出して空気の膜を作り、プレッシャーフットと基板が接触していない状態で加工
します。
オプションで、接触型のプレッシャーフットもあります。
7 深さ調節ネジ
このネジを回すと、工具の深さを調節できます。
上から見て、時計方向に回すと深く、反対方向に回すと浅くなります。
深さ調節ネジを1周回すと 0.5mm 上下します。1ノッチでは約3ミクロン上下します。
工具の深さは、まずミリングカッタの深さを調節し、その位置を加工の基準とします。
8 エアチューブ(HPタイプのみ)
エアプレッシャーフットにエアを供給するチューブです。
9 コントローラ
加工機の制御ユニットです。
10 パワースイッチ
FP-21Tのスイッチです。電源を投入するにはこのスイッチを押してください。
加工機のスイッチは、Design Pro を起動してから入れてください。
4
11 RS-232C接続ポート
RS-232Cケーブル(ストレート)でパソコンと接続してください。
12 ディップスイッチ
コントローラ内のプログラムを書き換えるときに使用します。
通常、ユーザーは使用しないスイッチです。
13 USB接続ポート
14 インターロック用コネクタ
インターロック付き安全カバー(オプション)を接続します。
5
15 ヒューズ
2Aヒューズをセットしてください。
(購入時に予備ヒューズが付属しています)
16 AC OUT
吸塵機(掃除機)の電源ケーブルは加工機に接続し、吸塵機のスイッチを ON にしてください。
17 AC IN
電源コードを接続してください。
18 スピンドルモータコネクタ
スピンドルモータとコントローラの接続コネクタです。
19 コントローラ接続コネクタ
加工機本体とコントローラの接続コネクタです。
20 AIR IN(HPタイプのみ)
エアレギュレータからのエアホースを接続してください。
21 エアレギュレータ(HPタイプのみ)
エア圧力の設定を行います。エア圧力は、0.4~0.45Mpaに設定してください。
22 エアバルブ(HPタイプのみ)
エア浮上用のエアバルブです。通常は操作する必要はありません。
23 アース
6
2.準備するもの
◇吸塵機
スピンドルモータに連動し、加工中に発生するゴミを吸い取ります。
◇基板
一般的な基板は、厚さ 1.6mm 銅はく厚は 35 ミクロンです。
0.2mm より細い高周波ミリングカッタを使用する場合は、銅はく厚 18 ミクロン以下のものを
使用します。スルーホールメッキを行う場合、銅はく厚 18 ミクロンのものを使用します。
◇工具
工具は大きく分けてミリングカッタ・ドリル・フォーミングカッタ(ルータ)の 3種類あります。
ミリングカッタには先端に角度がついた通常のミリングカッタと、高周波用のミリングカッタがあります。
ミリングカッタ
基板の表面を加工する工具です。
工具の先端に角度がついており、加工時に深さを調節することにより切削幅を変えることが
できます。加工するときはまずこの工具を取り付けて 深さの調節を行います。
<参考>
工具径(溝幅)によるミリングカッタの使い分け
ミリングカッタ 60°:0.15mm~0.2mm/18μm 銅箔基板加工
ミリングカッタ 90°:0.2mm~/18μm 銅箔基板加工
ミリングカッタ 60°:0.2mm~0.3mm/35μm 銅箔基板加工
ミリングカッタ 90°:0.25mm~0.4mm/35μm 銅箔基板加工
ミリングカッタ 120°:0.4mm~0.7mm/35μm 銅箔基板加工
高周波ミリングカッタ
基板の表面を加工する工具です。
工具の先端がストレートになっており、加工溝の断面が垂直に加工できます。
ドリル
穴あけ加工を行う工具です
フォーミングカッタ
外形の切り落とし加工や基板のくり抜き加工を行う工具です。
7
◇リング
必要に応じて工具に取り付けます。
リングの取り付け位置とリングの取り付け方は、次のページを参照してください
◇ルーペ
切削りした基板面の確認に使用します。
◇テープ
基板を固定するのに使用します。
◇スプレー糊
基板やベーク下敷きを固定するのに使用します。
◇スチールたわし
切削した基板面をみがくのに使用します。小さなゴミやバリを取り除くのに便利です。
◇エアコンプレッサ
FP-21T Precision はHPタイプ(エア浮上型)が標準です。
HPタイプの機種ではエアコンプレッサが必要です。
8
2-1 リングの取り付けについて
スピンドルモータのコレットの奥行きは 22mmです。
工具を突き当たるまで差し込んで取り付けてください。
加工する基板の厚さや、工具の長さによっては、工具にリングを取り付けます。
◇薄い基板を加工するとき(厚さ 1.0mm 未満の基板)
リングをつけずに、工具をスピンドルモータの奥まで差し込みます。
ただし、36mmのミリングカッタを使用する場合は、図のようにリングをつけます。
穴あけのときは、深さ調節ねじを回して基板を貫通するように刃先を出します。
深さ調節ネジは 1周 0.5mm、1クリックで約 3ミクロン上下します。
深さ調節ネジには目印を付けていますので、調節する目安にしてください。
9
◇一般的な基板を加工するとき(厚さ 1.0mm 以上の基板)
38mmのミリングカッタはリングをつけずに、工具をスピンドルモータの奥まで差し込みます。
ドリルや 36mmのミリングカッタには、図のようにリングをつけます。
ミリングカッタで深さ調節しておけば、厚さ 1.6mmの基板でもドリルの穴が貫通します。
加工深さの微調節は、深さ調節ネジを回して行ってください。
深さ調節ネジは 1周 0.5mm、1クリックで約 3ミクロン上下します。
深さ調節ネジには目印を付けていますので、調節する目安にしてください。
◇リングの付け方
付属のリング取り付けジグを使って取り付けます。
ジグに、リング→筒→工具(刃先が下向き)の順に入れて、木槌などで上から押さえ込みます。
※リングを取り付ける道具は、この他に、オプションの精密型リングセッタがあります。
10
3.接 続
基板加工機とパソコンは、RS-232Cケーブル、または、USBケーブルで接続します。
吸塵機(掃除機)の電源ケーブルは加工機に接続し、吸塵機のスイッチを ON にしてください。
ケース1
パソコンのシリアルポートに付属のRS-232Cケーブルを接続し、加工機に接続してください。
ケース2
1.お客様にてA-BコネクタタイプのUSBケーブルをご用意戴き、図のように接続して下さい。
2.加工機の電源をオンにすると、加工機が 原点復帰し、パソコン画面の右下に、
“新しいハードウェアが見つかりました”と表示されます。
3.新しいハードウェアの検出ウィザード 画面が起動されたら“一覧または特定 の場所から
インストールする”を選択し、 次へボタンをクリックします。
11
4.CD ドライブに Design Pro の CD を入れ、CD 内のフォルダ Drivers を選択し、
次へボタンをクリックします。
5.ドライバのインストールが終わったら、 完了ボタンをクリックします。
6.Design Pro を起動して、メニュー [条件]/[加工機条件]で、通信手段を“USB” に
設定します。ソフトを再起動して下さい
* 詳しくは、インストールマニュアルをご覧下さい。
12
Ⅲ.加工の流れ
Design Pro CAM-TP 起動
↓
加工データを開く
↓
エアコンプレッサの準備を行う
↓
加工機の準備を行う
↓
加工の条件を設定する
↓
[P3点読み込み]を行う
↓
加工アイコンをクリックする
↓
加工枚数・加工順序を決める
↓
加工基準点(P1点)を設定し、加工範囲を確認する(P1・P2点 Revised 方式の場合)
加工範囲を確認する(P3・P4点方式の場合)
↓
ミリングカッタで加工深さを調節し、切削溝幅を確認する
↓
基準穴あけを行う(P1・P2点 Revised 方式の場合)
↓
表の加工を開始する(画面のメッセージに従い工具を交換する)
↓
加工が終了したら加工の状態を確認する
↓
基板を裏返す
↓
裏の位置合わせを行う(P1・P2点 Revised 方式の場合)
↓
裏の加工を開始する(画面のメッセージに従い工具を交換する)
↓
加工が終了したら加工の状態を確認する
↓
基板を取り外す
13
Ⅳ.加工条件の設定
加工機を制御するために必要な各設定を行います。
1 加工機の基本動作環境を設定します。
2 加工時のスピンドルモータの回転数や加工速度を設定します。
3 登録されている加工条件の読み込み、また 1~2の設定内容をファイルに登録します。
4 登録されているP3点の読み込み、また P3点の登録を行います。
1.加工条件
[加工機種別]
FP-21TPを選択してください。
[分解能]
0.001 固定です。
14
[円加工法]
円・円弧の加工を設定します。
円・八角形どちらかを選択できますが、通常は円を選択して下さい。
[INK加工]
ON固定です。
[基準穴加工法]
P1・P2方式で基準ピンを立てて加工する場合にはP1・P2Revised を選択してください。
P3・P4方式で加工する場合は、垂直点を選択してください。
教示原点方式で加工をする場合には教示原点を選択してください。
一般的な基板の場合は、P1・P2Revised を選択してください。
※関連事項・・・・・参照
[加工速度]
手操作時の加工速度を設定します。
推奨値は 2~8mm/sec です。
[空送速度]
ヘッドがUPしているときのX・Y軸の移動速度を設定します。
推奨値は 20~30mm/sec です。
[下降速度1]
ヘッドが基板上空5mm の位置までDOWNするときの下降速度を入力します。
推奨値は 12~15mm/sec です。
[下降速度2]
ヘッドが基板上空5mm から基板面までDOWNするときの下降速度を入力します。
推奨値は 1~2mm/sec です。
[基板厚さ]
加工する基板の厚さを入力します。
[下敷き厚さ]
ベーク下敷きの厚さを入力します。
[基板押え深さ]
加工するときの基板を押さえ込む強さを表示しています。
[シミュレーション深さ]
シミュレーションを行う際の深さを設定します。
[ドリルウェイト]
穴あけ加工時のヘッドの待ち時間(ヘッドがDOWNしてUPするまでの時間)を設定します。
[切削前ドゥエル]
切削前の待ち時間(ヘッドがDOWNしてからX・Y軸が動き始めるまでの時間)を
設定します。
[切削後ドゥエル]
切削後の待ち時間(加工後ヘッドがUPしてからX・Y軸が動き始めるまでの時間)を設定
します。
15
[塗布前ドゥエル]
プラスSオプションの塗布前の待ち時間を設定します。
[塗布後ドゥエル]
プラスSオプションの塗布後の待ち時間を設定します。
[通信手段]
加工機とパソコンの接続により、COM*ポート、または、USB ポートを設定します。
[通信速度]
9600 を設定します。
[カメラ有無]
カメラオプションの有無を設定します。
2.輪郭加工条件・ハッチング加工条件・穴加工条件・外形加工条件
[加工速度]
それぞれの工具に対して、加工速度を設定してください。
単位は、mm/sec です。(ドリルにはこの項目はありません)
加工機の 空送り速度の適正値・加工速度の目安は次の通りです。
空 送 り ‥‥20~30mm/sec
ミリング加工 ‥‥2~8mm/sec
これは 高周波ミリングカッタを使用して加工する場合です。
種類の異なるカッタを使用する場合はカッタに適した加工速度を入力して
ください
外形加工 ‥‥ 1~ 2mm/sec
フォーミングカッタで加工する場合は、これより速く加工すると工具が
折れてしまう恐れがありますので注意してください)
[回転数]
それぞれの工具に対して、スピンドルモータの回転数を設定してください。
単位は、1000rpm です。基板加工の場合、標準値は 30~40(×1000rpm)です。
回転数の適正値は、加工対象物の材質と工具の種類によって変わります。
特殊な材質を加工する場合はお問い合わせください。
16
3.加工条件読込・加工条件登録
[加工条件読込]
ファイル登録されている条件情報を読み込みます。
ファイル名を選択し、開くをクリックしてください。
条件ファイルを読み込むと、それまで使用していた各条件の情報は上書きされてしまいます
ので、ご注意ください
[加工条件登録]
現在設定している各加工条件の情報をファイルとして登録します。
ファイル名を入力し、OKをクリックしてください。
特に指定がないときには、拡張子 prc で登録されます。
登録される情報:加工条件
輪郭加工条件
ハッチング加工条件
穴加工条件
外形加工条件
ホールハンダ条件
チップハンダ条件
4.P3点読込・P3点登録
※関連項目 Ⅶ.加工の準備 基準ピン立て-P3点登録 参照
[P3点読込]/[P3点登録]
加工の準備として、両面加工の位置合わせのために基準ピン穴をあけ、
その位置をP3点として登録しておきます。→[P3点登録]
[P3点読込]では、ファイル登録されているP3点情報(****.p3i)を読み込みます。
加工を行うときには必ずP3点情報を読み込んでください。
17
Ⅴ.加工機を動かしてみましょう
1.基本動作
エアホースを接続し、エアコンプレッサの準備を行ってください。
加工機とパソコンを接続し、Design Pro CAM-TP を起動してください
次に、加工機の電源を投入して下さい。
自動的に原点復帰(ヘッドが奥の機械原点まで移動する)します。
※ 原点復帰を行わない時は機械的なトラブルが考えられますのでご連絡ください。
マニュアル操作のアイコンをクリックしてください
ヘッドが手前(P3点またはP1点)に移動し、マニュアル運転のダイアログが表示されます。
画面の各ボタンをクリックすると加工機が動作します。
加工機の電源を投入せずにマニュアル運転のアイコンをクリックすると マークが表示されます。
その場合、SHIFT+ESC キーを押すと は解除できます。
Design Pro は、一旦終了して、再度起動してください。
加工機の電源を投入してから再度マニュアル運転を行ってください。
18
前後左右に移動している最中に、加工範囲より外側まで移動すると、「リッミトエラー」と表示されます。
リミットエラーが表示されたら、それ以上同方向の移動ボタンはクリックせず、原点 をクリックして
下さい。加工機が原点復帰を行い、マニュアル運転動作を再開できる状態になります。
スピンドル ON スピンドル OFF
スピンドルモーターを回転・停止させます。
UP DOWN
ヘッドの上げ下ろしを行います。
ハンダ
ペースト塗布を行います。プラスSオプションのみ有効です。
原点
ヘッドの原点復帰を行います。
手前 奥 左移動 右移動
ヘッドを前後左右に移動します。
P1 P2 P3 P4
ヘッドをそれぞれ、P1・P2・P3・P4点に移動します。
ヘッド待避
ヘッド待避点に移動します。
刃先測定
オプションの刃先測定治具を使用するためのボタンです。
基板面検出
刃先が基板面に触れる位置を測定する機能です。
単位移動距離
1ステップ(ヘッドの移動ボタンを 1回クリックしたとき)の移動距離を入力します。
ドリルウェイト
穴あけ加工時の待ち時間(ヘッドがDOWNしている時間)を入力します。
19
空送速度
ヘッドがUPしているときのX・Y軸の移動速度を入力します。
加工速度
ヘッドがDOWNしているときのX・Y軸の移動速度を入力します。
待避位置設定
ヘッド待避点を設定します。
ヘッド待避点・・・・加工した基板全面を確認するときや、基板を裏返したり工具を交換したりする
ときなどのために、ヘッドを端の方へ移動させる位置のことです。
ヘッド待避点は任意の位置に設定することができます。
設定方法 ・・・・・・ 待避点にしたい位置までヘッドを移動し、待避位置設定をクリックして下さい。
その位置がヘッド待避点となります。
一度設定した待避点は、加工機、パソコンの電源を切っても記憶しています。
ヘッド待避点を変更する場合は、新たな位置までヘッドを動かし、
改めて待避位置設定 をクリックして下さい。
基板厚さ
加工する基板の厚さを入力します。
下敷き厚さ
ベーク下敷きの厚さを入力します。
基板押え深さ
加工するときの基板を押さえ込む強さを表示しています。
下降速度1
ヘッドが基板上空5mm の位置までDOWNするときの下降速度を入力します。
下降速度2
ヘッドが基板上空5mm から基板面までDOWNするときの下降速度を入力します。
スピンドル回転数
スピンドルモータの回転数を設定します。単位はX1000rpm です。
ショット回数
ペースト塗布回数を入力します。プラスSオプションのみ有効です。
X座標 Y座標
ヘッドの位置(X・Y座標)を表示します。
20
2.試し切り(テストカット)
加工機の動きに慣れたら試し切りをしてみましょう
① スピンドルモータにミリングカッタを取り付けてください。(工具交換方法の項目をご覧ください)
ミリングカッタの先がプレッシャーフットよりも極端に下に出ていないように深さ調節ネジを回して
おきます。深さ調節ネジは上から見て右(時計回り)に回すと深くなります。
② 手前 奥 右移動 左移動 ボタンを操作して、基板の端の方までヘッドを移動してください。
③ 単位移動距離を5~10 ミリにしてください。
④ スピンドル ON をクリックし スピンドルモータを回転させてください。
⑤ DOWNをクリックしてヘッドを下げたあと、UPをクリックしてヘッドを上げ、
スピンドル OFF をクリックしてください。
この時に基板に深く刺さるようでしたら深さ調節ねじを回して浅くして、ミリングカッタの先が
基板面に軽く触れる程度にしてください。
⑥ もう一度スピンドル ON をクリックし、DOWNをクリックしてください。
⑦ スピンドルモータが回転し、ヘッドがDOWNした状態で移動キーを1回押すと、
試し切りができます。
⑧ UPをクリックしてヘッドを上げ、 スピンドル OFF をクリックしてください。
切削溝の幅を確認して下さい。
切削幅が 0.3mm 程度になるように深さ調節ネジでミリングカッタの深さを調節してください。
21
* 工具交換方法*
<model 40 の場合>
モータが回転していないこと、ヘッドがUPしていることを確認してください。
付属のピンセットで工具をつかみ、工具着脱レバーを下図のように静かに回し、
工具を抜いてください。
工具を突き当たりまで差し込み、工具着脱レバーを静かに回してください。
工具装着時 工具脱着時
***重要!***
・工具着脱レバーは、しっかり 回さなかったり(途中でとめたり)、はじくよう に回すと、
故障の原因になります。
・スピンドルモータは高精度を保つために工具脱着時でもチャック部はきつくなっています。
工具の抜き差しは十分注意してください。
<model 60 の場合>
モータが回転していないこと、ヘッドがUPしていることを確認してください。
付属のピンセットで工具をつかみ、工具着脱ノブがはまり込むまで押し下げてまわし、
工具を抜いてください。
工具を突き当たりまで差し込み、工具着脱ノブをまわしてください。
最後に必ずノブを引き上げてください。ノブを引き上げていないと、スピンドルモータが
回転しません。
※ノブを引き上げていないと、モーターの故障の原因になりますのでご注意ください。
22
(注:写真は FP-21T)
*** 注 意 ***
加工機を使用しないときは必ずダミーツールを取り付けておいてください。
スピンドルモータに何もつけていない状態で長時間放置すると、スピンドルモータのコレット
内が変形し工具を取り付けることができなくなってしまう恐れがあります。
23
Ⅵ.加工について
CAM-TPでは、加工するデータに対して図のようにP1点・P2点の基準点情報をもっています。
基板を加工するときは、基準ピンを立てて基板を固定することによって、両面の位置合わせが簡単に
できます。
Y軸上の 2点に基準ピンを立てて基板を取り付け、裏面の加工は左右反対になるように裏返します。
加工の位置あわせ方法は、P1・P2点 Revised 方式、P3P4点方式(垂直点方式)、
教示原点方式があります。
それぞれの説明の項目を見て、行いたい基板加工に適した方法を選択してください。
通常はP1P2点 Revised 方式で加工します。
加工方式は[加工機条件]-[加工条件]画面で設定できます。
24
Ⅶ.加工の準備 基準ピン立て-P3点登録
両面加工の位置合わせを容易に行うために、Y軸上の 2点に基準ピンを立て、基板は基準ピンに合わせて
取り付けます。裏面の加工は基板が左右反対になるように裏返します。
基準ピン立てコマに基準ピンを立てる穴(3mm)を作成して下さい。
手前の基準ピン位置をP3点と呼びます。もう一点は、P3点のY軸方向の延長線上に立てます。
P3点は登録しておきます。
また、基板にもピン立て用の下穴をあけてください。
このとき、基準ピン2穴間の距離と基板の2穴間の距離が同じになるように穴をあけて下さい。
(注:写真は FP-21T)
①[加工機条件]-[加工条件]画面で、基準穴加工法を「P1P2 Revised」を選択してください。
25
②基準ピン立てコマを加工テーブルの溝にしっかりとはめ込んでください。
1つはテーブルの手前に、もう1つは奥に取り付けます。
基準ピン2つの間隔は 140~150mm に設定しますので、それを考慮してピン立てコマを
取り付けます。
③基準ピン立てコマを取り付けたら、ベーク下敷を置き、その上に基板を置いてください。
(注:写真は FP-21T)
④メニュー[ファイル]/[開く]で、任意のファイル(例 Mdemo.PCB)を開きます。
[加工]のアイコンをクリックし、位置合わせ 画面まで進んでください。
この画面で穴あけとP3点の決定を行います。
* マニュアル操作のアイコンではP3点の設定はできませんのでご注意ください。
⑤ミリングカッタ 90 度を取り付け、基板上で試し削りを行い、切削溝が 0.3mm になるように
調整します。(詳しくは加工機を動かしてみましょうの試し切りを参照してください。)
⑥基板を取り除きます(下敷きはそのまま)
付属の基準ピン穴あけ用3mm ドリルを使用し 基準ピン立てコマに穴をあけます。
基準ピン穴あけ用のドリルを使用すると、深さ5mm 程度の穴があけられます。
(1)原点ををクリックしてください
(2)150mm 手前 75mm 右に移動してください。
(3)ドリルが基準ピン立てコマのちょうど上に来るように左右方向のみ
左移動・右移動ボタンをクリックして位置を微調整してください。
26
(注:写真は FP-21T)
⑦下降速度2の値を2mm/sec に変更してください。
スピンドルモータをON にし、ヘッドをDOWN するとコマに穴があけられます。
穴があきましたら、UPをクリックしてください。
手前のピン穴をあけた位置で P3 位置設定 をクリックして下さい。
以後この点がP3点となります。
⑧ヘッドをまっすぐ奥に移動してもうひとつピン穴をあけます。
このとき2つのピン穴間の距離を記憶しておいてください。
加工範囲に注意し、最大距離 150mm までの間(140~150mm)で穴を開けてください。
27
⑨通常の3mm ドリルに交換し、加工する基板にも穴をあけて下さい。
基準ピン2穴間の距離と基板の2穴間の距離が同じになるように穴をあけて下さい
(注:写真は FP-21T)
⑩穴あけが終わったら、OKをクリックしてください。
加工の表裏変更メッセージのダイアログに戻りますので、中断をクリックしてください。
⑪[加工機条件]―[P3点登録]で、今設定したP3点の位置を登録してください。
ファイル名は任意の名前でかまいません。この点が今後の加工の基準点になります。
28
Ⅷ.加工 P1・P2 Revised 方式
CONVERTER や EASY CAD で作成したデータを加工します。
Ⅶ.加工の準備 基準ピン立て-P3点登録に従って、Y軸上の 2 点に基準ピンを立て、
P3点を登録してください。
また、基板にもピン立て用の下穴をあけて、加工機のテーブルに取り付けてください。
加工するときには、取り付けた基板の任意の位置に加工できます。
加工データのP1点を基板上の任意の位置に設定します。
裏面の加工は基板が左右反対になるように裏返すとそのまま加工できます。
基準ピンを立てたときの「あそび」さえも裏面の位置合わせに影響するほど精密な加工をする場合は、
裏面の加工時に位置合わせを微調節することができます。
応用編として、記載していますので参照してください。
1.加工データ表示
画面に加工するデータを読み込んで下さい。
[ファイル]-[開く]でデータリストの中から加工するデータを選択し、開くをクリックすると
画面に表示します。
29
2.加工機準備
加工機本体のスイッチを入れてください。
スイッチを入れると、ヘッドが自動的に機械原点まで移動し停止します。(この動作を原点復帰といいます)
機械原点は、加工機に向かって左奥です。
次に、基板を取り付けてください。
(片面の基板加工を行う場合はピンで固定する必要はありません。ですが、ピンで固定しておくと、
加工機から外してしまった基板の再加工を行う場合に便利です)
最後に、基板の4辺をテープできちんととめて下さい。
*基板に反りがあった場合は、手でなおしてから取り付けてください。
3.P3点読込み
両面加工の位置合わせを簡単に行うために、基準ピンの位置をP3点として加工します。
あらかじめ 設定し、登録しておいたP3点(基準ピン)の位置情報を読み込みます。
加工をはじめる前にまず、[加工機条件]-[P3点読込]で、P3点情報(****.p3i)を
読み込んでください。
30
4.加工順位の設定
加工のアイコンをクリックしてください。
加工順位の設定が表示されます。
ここでは加工枚数と加工順序を設定します。
[加工順位リスト]
加工対象リストから、加工するレイヤを加工する順番に選択して下さい。
加工対象リストから加工するレイヤをクリックします。
>> をクリックすると、選択したレイヤが加工順位リストに登録されます。
通常 両面加工の場合、
ドリル加工(表)→輪郭加工(表)→輪郭加工(裏)→外形加工(裏)の順で加工します。
また、片面基板の場合、
ドリル加工(裏)→輪郭加工(裏)→外形加工(裏)の順で加工します。
設定したら、OK ボタンをクリックしてください。
ヘッドが任意の位置に移動して基板の表/裏変更メッセージが表示されます。
31
基板の表/裏変更メッセージでは、まず位置合せボタンをクリックしてください。
位置合わせの画面に切り替わります。
この画面では、
・ミリングカッタでの深さ調節(切削溝幅調節)
・P1点の設定とP2点の位置確認
・基準穴あけ を必ず行ってください。
ミリングカッタでの深さ調節
Ⅴ.加工機を動かしてみましょうの2.試し切りをご参照ください。
[加工種別]
加工するレイヤを表示しています。
[再加工]
任意の位置からの再加工を行います。
[続行]
次のダイアログに進みます。
[スキップ]
加工種別に表示されているレイヤの加工を
とばして、次のレイヤを表示します。
[位置合せ]
加工基準点の設定と、加工の位置合わせを行います。
[中断]
加工を中断します。
32
P1点の設定とP2点の位置確認
1.はじめに、加工基準点(P1点)を設定します。
P1点は任意の位置に設定できますが、基板を有効活用するために、取り付けた基板の
左手前方向に設定するといいでしょう。
左・右・手前・奥のボタンをクリックしてヘッドを動かしてください。
<重要>
移動中に“警告:ハードリミット検出”画面が表示されたら、原点ボタンを押してください。
加工機が原点復帰を行った後、やり直してください。
※“警告:ハードリミット検出”は、基板加工機のヘッドが、移動可能範囲をこえた時に
表示されます。
2.HOME をクリックすると、その点がP1点となります。
P2点の位置調整を行いますか?とメッセージがでますので、いいえをクリックして下さい。
(P2点の位置調整は、両面加工のように一度基板を取りはずしたあと位置合わせをするときに
行います)
3. P1点が決まったら、P2点の位置を確認しておいて下さい。P2をクリックすると、
加工機のヘッドはP2点まで移動します。
(加工範囲の確認のため忘れずに行ってください。)
※P1点を変更する場合は、再度ヘッドを動かし HOME をクリックして下さい。
その位置が新たなP1点になります。
加工範囲とP1・P2点の関係は次のとおりです。
33
基準穴あけ
基準点を設定した後にP1・P2点に基準穴をあけます。
穴あけ用のドリルを取り付けてください。0.8mm 程度のドリルが適しています。
基準穴作成 をクリックすると、ヘッドがP2点に移動し、
基準穴加工を行いますか?とメッセージが表示されます。はいをクリックすると穴あけを
行います。(スピンドルモーターの ON/OFF は自動で行います)
基準点設定と基準穴あけが終わったら、OKをクリックして下さい。
5.ドリル加工
位置合わせの画面でOKをクリックすると基板の表裏変更メッセージの画面に戻ります。
続行ボタンをクリックしてください。
工具交換メッセージが表示されます。
[工具番号]に表示されている工具を取り付けて下さい。
スピンドルモーターの回転数[回転速度]を確認して下さい。
続行をクリックすると穴あけ加工を開始します。
スピンドルモーターと吸塵機の ON/OFF は、自動的に行います。
多面取り加工の場合、何枚目を加工しているかは画面下に表示します。
ESCキーを押すと、加工を一時停止できます。
[続行]
加工を開始します。
[スキップ]
表示されている工具番号の加工をとばして、
次の加工対象の工具を表示します。
[戻る]
スキップの逆で、一手順ずつ前に戻ります。
[手操作]
マニュアル操作画面が表示され、ヘッドの
移動やスピンドルモータの ON/OFF などが
手操作できますます。
[再加工]
任意の位置からの再加工を行います。
[中断]
加工を中断します。
34
!! 警告 !!
加工中、スピンドルモーター(ドリル)に触れたり、顔を近づけたりしないでください。
どうしても近くで見る必要があるときは、ゴーグルなど保護眼鏡を着用して下さい。
6.パターン(輪郭線)加工・表
ドリルの加工が終了すると、加工機の動きが止まり 工具交換のメッセージが表示されます。
まず、ミリングカッタに交換して、手操作をクリックしてください。
試し切りを行って、[工具径]に表示されている切削幅になるように加工深さを調節して下さい。
切削幅の調整ができたら、OKをクリックしてください。
続行をクリックすると加工を開始します。
*重要*
高周波ミリングカッタを使用する場合はステップ加工を行います。
ステップ加工の項目をご参照ください
途中で加工を一時停止するときは、キーボードのESCキーを押してください。
スピンドルモータとX・Y軸の動きが止まって次の画面が表示されます。
ESCキーを押した時点で すでに加工機に送信されたデータまでは加工しますので、ESCキーを押し
た瞬間には止まりませんが、加工機やソフトウェアの異常ではありません。
続行をクリックすると、加工を再開します。
35
加工が終了したら、ヘッド待避点にヘッドが移動して基板の表/裏交換メッセージが表示されます。
基板を取り外す前に、加工の状態を確認してください。
7.再加工
再加工の方法は2種類あります。
・ 任意位置からの再加工
・ 中断位置からの再加工
任意位置からの再加工
加工中ドリルやミリングカッタが折れてしまった場合、削り残した部分があった場合などのために
任意の部分だけを再加工することができます。
工具交換メッセージや加工中断メッセージのダイアログで再加工をクリックしてください。
[再加工]
ダイアログが表示されますので、X・Y方向それぞれ何枚目から再加工するのか入力して下さい。
(加工枚数が一枚のときもこのダイアログは表示されます)
36
画面左下に<要素を選んでください>とメッセージが表示されます。
再加工を始める要素をクリックしてください。
加工の対象となるデータは黄色で表示され、加工の再開確認のダイアログが表示されます。
いいえをクリックすると、加工開始要素を指定しなおすことができます。
はいをクリックすると、工具交換メッセージが表示されますので、メッセージにしたがって工具を
交換して下さい。
続行をクリックすると加工を始めます。
再加工を一時停止するときは、ESCキーを押してください。
中断位置からの再加工
加工途中に加工を中断した場合、ソフトウェアはその位置を記憶しています。再加工の機能で中断位置
からの再加工を行うことができます。
再加工のアイコンをクリックしてください。工具交換メッセージが表示されます。
続行をクリックすると、自動的に中断位置からの再加工を開始します。
37
8.パターン(輪郭線)加工・裏
表の加工が終了したら、ヘッド待避点にヘッドが移動して基板の表/裏交換メッセージが表示されます。
加工の状態を確認して 問題がなければ基板を裏返してください。
基板は左右が反対になるように裏返して、テープで止めてください。
このとき、基板と下敷きの間にごみが挟まらないようにしてください。
通常の基板はこのまま続行をクリックします。
基準ピンを立てたときの「あそび」さえも裏面の位置合わせに影響するほど精密な加工をする場合は、
裏面の加工時に位置合わせを微調節することができます。
応用編として、記載していますので参照してください。
続行をクリックすると、工具交換のメッセージが表示されます。
38
表の加工と同様に、切削幅の調整を行い、OKをクリックしてください。
続行をクリックすると加工を開始します。
切削幅の調整は、手操作をクリックして表示される手操作画面で行うことができます。
9.外形加工
輪郭加工とハッチング加工が終了したら、基板の表裏変更メッセージに外形加工(裏)と表示されます。
特に再加工などが必要ない場合は、続行をクリックしてください。
工具交換メッセージが表示されます。
画面の指示に従って フォーミングカッタ(ルータ)に交換してください。
加工する前に、必ず加工速度を確認してください。(加工速度1~2mm/sec)
加工スピードが速すぎると工具が折れてしまいます。
加工スピードは手操作で変更できます。
次に、工具の深さ調節を行います。下の説明のように少し浅く加工するように調節します。
このようにしておけば、切り抜いた基板が飛び出ることもなくきれいに加工できます。
深さの調節方法は、次の通りです。
① 手操作をクリックしてください。
② 移動ボタンを操作して、図のような位置にヘッドを移動します。
*プレッシャーフットの一部分は基板の上にのっていて、
フォーミングカッタは下敷きの上にある。
39
③ 深さ調節ネジを浅くなる方に 1回転程度回しておきます。
④ DOWNをクリックし、ヘッドを下げます。深さ調節ネジを浅くなる方にさらにまわし、
フォーミングカッタの先が下敷きから少し浮き上がったところで止めます。
UPをクリックしヘッドを上げてください。
⑤ 深さ調節ネジを、フォーミングカッタが深くなる方向に少し回してください。
スピンドルONをクリックし、DOWNをクリックします。
一旦UPをクリックし、スピンドルOFFをクリックします。
下敷きにあとがついているかどうかを見てください。
⑥ ⑤の操作を何度か繰り返して、下敷きに丸くフォーミングカッタの歯のあとがつくくらい
の深さにしてください。
⑦ その深さから 15~20 ノッチ程度浅くします。
このように調節をしておけば、両面基板であれば、下の面の銅箔が残る程度の深さで加工
できます。
* できれば、加工を始める前に 基板の端の方でテストカットするとよりよいでしょう
外形加工が終了したら、加工終了確認ダイアログが表示されます。
加工の状態を確認して、問題がなければ終了をクリックしてください。
40
Ⅸ.加工 P3・P4(垂直点)方式
CONVERTER や EASY CAD で作成したデータを加工します.
位置合わせの方法がP1・P2Revised 方式と異なるだけで、加工方法は同じです。
ここでは、位置合わせ方法のみ記載します。
P3・P4点方式では、P3点を設定すると、自動的に加工データの加工位置が決まります。
裏面の加工は、基板が左右反対になるように裏返すとそのまま加工できます。
多面取り加工の場合、P3点と基板の加工位置は次のようになります。
あらかじめ 設定し、登録しておいたP3点(基準ピン)の位置情報を読み込みます。
41
加工のアイコン→加工順位の設定→基板の表/裏変更メッセージ→位置合せまで進みます。
「P3点まで移動してHOMEボタンをピックしてください」とメッセージがでますが、
すでに登録しているP3点を読み込んでいるので、HOMEはクリックしないでください。
この画面では、
・P1点とP2点の位置確認
・ミリングカッタでの深さ調節(切削溝幅調節) を必ず行ってください。
加工の手順は、P1・P2 Revised 方式と同様に行ってください。
42
Ⅹ.加工 対角点方式
CONVERTER や EASY CAD で作成したデータを加工します.
位置合わせの方法が異なるだけで、加工方法は同じです。ここでは、位置合わせ方法のみ記載します。
対角点方式は、P1・P2点 Revised 方式、と似ており、P1・P2点 Revised 方式との相違点は、
基準ピンを使わないところです。
対角点方式での位置合わせは、オプションのカメラモニタシステムを合わせて使います。
かなり精密な加工をする場合、裏面を一部分加工してから位置合わせを微調節することができます。
応用編として、記載していますので参照してください。
加工条件の設定で、「対角点」を選択してください。
まず、カメラドリルのオフセット量を測定します。
カメラのアイコンをクリックしてください。
基板を取り付けてください。(使い残しの基板で結構でも構いません)
ドリルを取り付けて、基板にドリルが貫通するように深さ調節をしてください。
加工テーブルの中央より左側の領域に、1ヶ所穴をあけてください。
スピンドルモータを「ON」にして「DOWN」を押すと穴があけられます。
穴をあけた位置で基準位置を押してください。
43
次にカメラで穴が見える位置までヘッドを移動してください。
カメラで穴の中心まで移動してカメラ位置を押してください。
これでカメラとドリルのオフセット位置が記録されます。
加工のアイコンをクリックしてください。
教示原点を合わせるのですが、このとき、カメラ視点で合わせます。
画面のCAMERAを押してください。カメラ視点で位置合わせができます。
44
位置合わせ画面で、P1点を設定します。
加工データのP1点を、これから加工する基板のどこにするのか・・・という設定の仕方をします。
P1点の設定はドリル視点で行ってください。
この画面では、
・ミリングカッタでの深さ調節(切削溝幅調節)
・P1点の設定とP2点の位置確認
・基準穴あけ を必ず行ってください。
46
カメラ視点で、P1点の穴の位置を合わせ、HOMEを押します。
自動的に基板が置かれている角度を計算します。
裏面の加工を行ってください。
この角度補正は、CAM-TPを終了しても次にP1点の設定を行うまでは保たれます。
47
ⅩⅠ.加工 教示原点方式
CONVERTER や EASY CAD で作成したデータを加工します.
位置合わせの方法が異なるだけで、加工方法は同じです。ここでは、位置合わせ方法のみ記載します。
教示原点方式での加工は、オプションのカメラモニタシステムを合わせて使います。
P1・P2Revised 方式やP3・P4方式と異なって、すでにでき上がっている基板に対して、
追加で加工するときに便利な方法です。(一般的に「パターンカット」と言われる加工など)
CADデータの原点を基準とし、基板中の目印になる点2ヶ所を利用して位置合わせを行います。
条件設定画面で、「教示原点」を選択してください
48
まず、カメラドリルのオフセット量を測定します。
カメラのアイコンをクリックしてください。
基板を取り付けてください。(使い残しの基板で結構でも構いません)
ドリルを取り付けて、基板にドリルが貫通するように深さ調節をしてください。
加工テーブルの中央より左側の領域に、1ヶ所穴をあけてください。
スピンドルモータを「ON」にして「DOWN」を押すと穴があけられます。
穴をあけた位置で基準位置を押してください。
次にカメラで穴が見える位置までヘッドを移動してください。
カメラで穴の中心まで移動してカメラ位置を押してください。
49
これでカメラとドリルのオフセット位置が記録されます。
加工のアイコンをクリックしてください。
教示原点を合わせるのですが、このとき、カメラ視点で合わせます。
画面のCAMERAを押してください。カメラ視点で位置合わせができます。
画面のCAMERAを押してください。教示原点まで移動して教示設定を押します。
50
「角度補正を行いますか?」と表示されるので、はいを押してください。
加工する基板上から、“水平な直線”または“水平な直線上にある点”を見つけてください。
“垂直な直線”または“垂直な直線上にある点”でも構いません。
位置合わせのための基板上の 1点めを合わせて教示設定を押してください。
52
ⅩⅡ.ステップ加工
微細加工を行うときは、一度に銅箔厚さ分を切削するのではなく、何度かに分けて徐々に深く加工します。
この方法をステップ加工といいます。
加工するときにはまずプレッシャーフット基板に接地し、基板面をある程度の圧力で押さえ込みます。
カッタの刃先はその後基板に接触します。
ステップ加工では、基板面から加工深さの値まで設定された切り込み量ずつ深く加工します。
設定された内容で加工し、プレッシャーフットから突出している刃先分が最終的な加工深さになります。
輪郭加工の工具交換メッセージダイアログのステップ加工の項目にチェックすると
ステップ加工を行うことができます。
ステップ詳細ボタンをクリックして設定を行います。
開始オフセット:この後の説明に従って基板厚さ(=刃先が基板に触れる位置)を確認し、
オフセット量を設定してください。目安は-4~-10 ミクロンです。
基板厚さに対して若干上空から加工開始することはツールの破損を防ぐために有効です。
基板面に対して上空から加工開始するには、-値で入力してください。
53
繰り返し回数 :ステップ加工を何回行うか入力します。
切り込み量 :1 ステップの切削深さを入力します。
加工深さ設定
まず、プレッシャーフットからどれだけ刃先を突出するか設定します。
最終的な加工深さ=プレッシャーフットからどれだけ刃先を突出するか の設定は
オプションの刃先測定治具で設定します。
<刃先突出量測定治具>
1.刃先突出量測定治具の 0点を合わせます。
付属のプリズムを刃先感知部分の上に置き、
刃先感知部分の真ん中に上から力がかかるように押さえます。
54
2.押さえた状態でダイヤルゲージの目盛りを 0に合わせます。
何度か繰り返して、正確に合わせて下さい。
3.工具を取り付けます。
このとき、プレッシャーフットから刃先が突出しないように深さ調節ネジを回します。
4.刃先量測定は位置合わせ画面、またはマニュアル運転画面で操作します。
下降速度 2 の値を 2mm/sec に変更します。
*下降速度 2 の数値が大きいと正しく測定できないことがありますのでご注意下さい*
画面の刃先測定ボタンを押します。
プレッシャーフットから刃先が突出していないことを再度確認して下さい。
55
5.治具をプレッシャーフットの下に置きます。
治具は基板の上ではなく、下敷きの上に置いてください。
6.治具の高さを確認し、DOWN をクリックするとヘッドが下がります。
(治具の高さはデフォルト値 25mm です)
スピンドルモータは回転しません。
エア浮上タイプの加工機の場合は、エアが突出します。
7.この状態で深さ調節ネジを回していき、目盛りを見ながら刃先の突出量を合わせます。
56
8.UP を押してヘッドを上げてから OK を押して下さい。
<刃先突出量測定冶具調整方法>
治具の 0 点が合わせづらくなったら、次のように調整して下さい。
1.治具側面のネジを緩めます。
2.ダイヤルゲージを少しずつ持ち上げて針がふれるようになったらネジを締めて下さい。
3 つのネジはそれぞれ少しずつ徐々に締めて下さい。
57
基板面検出
加工する基板の厚さが入力されていれば、ヘッドがDOWNすると基板面に刃先がちょうど接触するはず
ですが、工具の取り付け方、工具長の公差、基板厚さの公差などの要素によって、実際にカッタの刃先が
ちょうど接触する位置は微妙に異なります。
微細加工を行うときは少しの値も加工に影響しますので、ステップ加工の詳細設定を行う前に、
実際に刃先が基板面に接触する位置をオプションの基板面検出用冶具で検出します。
<基板面検出用冶具>
電極 1 ツールに取り付けます。
電極 2-a 通常の基板加工のときに使用します。基板にのせます。
電極 2-b 金属以外の対象物を加工するときに使用します。
<操作方法>
1. 加工する基板をセットし、加工に使用するツールを取り付けます。
2.基板面検出用の冶具を取り付けてください。
58
電極 1 をツールに取り付け、電極 2-b を基板にのせます。
電極 1 はプレッシャーフットの開口部から差し込みます。
3.基板面検出ボタンをクリックします。
4.OKをクリックすると基板面検出動作を行います。
ヘッドが下降し、スピンドルモータが回転します。
刃先が基板に触れると自動的にヘッドが上昇します。
59
画面に基板厚さが表示されます。
*加工する基板は反っていたり、暑さが均一ではないこともありますので、
ヘッドを移動し、加工範囲の側近数ヶ所で測定し、基板厚さを確認してください。
5.基板面検出用の冶具を取り外してください。
*加工するものが金属以外の素材の場合は、次のようにしてください。
1.加工するものの上に電極 2-b をのせます。
2.基板面検機能では、この電極の上に刃先が触れるようにします。
3.基板面検出機能で表示された基板厚さから電極の厚さ(4.0mm)を引いた数値を基板厚さの欄に
入力します。念のため、電極 2-b の厚さをノギス等で正確に測定してください。
または、
1.基板の上に加工するものをのせ、基板の部分で通常の基板と同様に基板面検出を行います。
2.基板面検出機能で表示された基板厚さに加工するものの厚さを足した数値を基板厚さの欄に
入力します。加工するものの厚さはあらかじめノギス等で正確に測定しておいてください。
60
ⅩⅢ.応用編 角度補正
加工するときは、基準ピンに合わせて基板を取り付けることで、裏面の加工は、基板を裏返すとそのまま
できるようになっています。
精密加工で、基準ピンを立てたときの「あそび」さえも裏面の位置合わせに影響するほど精密な基板加工
する場合は、裏面の加工時に位置合わせを微調節することができます。
P1・P2 Revised 方式を選択してください。
1.微調節のための準備
微調節ができるように、あらかじめデータを作成しておきます。
位置合わせ用部品「awase」 「awase」配置位置
①加工する基板のデータができあがったら、EASY CAD で位置合わせ用の部品「awase」を、
P1点付近と P2点付近に配置してください。
②裏面加工の時は まず位置合わせランドを先に加工してください。
③位置合わせランドの加工を見た上で、必要であれば P1,P2点の位置合わせを微調節します。
◇データの作成方法
部品配置をします。
62
次に、配置する角度を 180 と入力してOKをクリックし、
P2点付近に配置します。
部品「awase」は、図のようにランドごとに輪郭線 No.を変えていますので、
一つ目のランドを加工したところで、加工機は一時停止します。
そこで、加工した結果を観察して、微調節が必要であれば次の項目の説明に従って微調節を行います。
63
2.合わせ方
位置合わせのランドは、「ドリルの穴に対して、ランドの丸をどちらに移動したらぴったり合うか」という
見方をします。
加工例1:P1点はそのままで、P2点を 0.1mm 左に動かすとき
加工例2:P1点もP2点も 0.1mm 左に動かすとき
P1をクリックするとヘッドがP1点まで移動します
ので、HOME2 をクリックしてください。
P2点の位置調整を行いますか? のメッセージで、
はい をクリックしてください。
P2点までヘッドが移動しますので、そこから 0.1mm
左移動して HOME をクリックしてください。
P1をクリックするとヘッドがP1点まで移動します
ので、そこから 0.1mm 左移動して HOME2 をクリック
してください。
P2点の位置調整を行いますか? のメッセージで、
いいえ をクリックしてください。
裏
裏
64
加工例3:P1点を 0.1mm 左に動かし、P2点はそのままのとき
P1をクリックするとヘッドがP1点まで移動します
ので、そこから 0.1mm 左移動して HOME2 をクリックして
ください。
P2点の位置調整を行いますか? のメッセージで、
はい をクリックしてください。
P2点までヘッドが移動します。角度補正は保たれていま
すが、P1点の位置を移動したため その距離の分だけ
P2も移動していますので、そこから 0.1mm 右移動して
HOME をクリックしてください。
裏
65
ⅩⅣ. FP-21TP使用上の注意
◆ 電源電圧について
FP-21T Precision の許容電源電圧は、85V~264Vです。
この範囲を逸脱する電源の地域でご使用される場合は、必ず自動電圧調整器を通してお使い
下さい。
◆ 加工範囲
加工は、FP-21T Precision の最大加工範囲内で行ってください。
加工前には、加工する基板のサイズ・P1,P2点の位置を十分に確認してください。
加工中またはマニュアル運転中に、最大加工範囲をはずれる(リッミトエラーになる)と、画面に
「加工範囲を超えました」というメッセージが表示されます。
マニュアル運転の場合
リッミトエラーになったら、それ以上同方向の移動ボタンは絶対にクリックしないでください。
反対方向の移動ボタンをクリックして ヘッドを一旦加工範囲内に戻してください。
その後 原点 をクリックして下さい。加工機が原点復帰を行い、加工動作を再開できる状態に
なります。
加工中の場合
リミットエラーになったら、一旦加工機の電源を切って下さい。
パソコン側は、中断をクリックしてダイアログを抜けて下さい。
画面に が表示されたままになりましたら、SHIFT+ESC キーを押して下さい。
その後、再度加工機の電源を入れて下さい。
◆ 脱調
加工中またはマニュアル運転中に 加工速度が速すぎたり、加工テーブルが何かにぶつかったり
すると、脱調してしまうことがあります。脱調は ソフトウェアの指令通りに加工機が動作でき
なかった場合に起きます。脱調すると、基準点の位置情報がずれてしまいます。
脱調した場合は、一度加工機の原点復帰動作を行って下さい。
マニュアル運転画面の 原点 をクリックすると加工機が原点復帰動作を行います。
66
◆ 工具の深さについて
加工深さが深すぎると加工機のテーブルを損傷しますのでご注意下さい。
◆ 加工条件の確認
加工は、[加工機条件]-[輪郭加工条件]・[ハッチング加工条件]・[外形加工条件]・[穴加工条件]で
設定されている内容に従って行います。
加工条件の設定が抜けていたり、間違えていたりすると、加工中にドリルが折れたり、加工
エラーが起きてしまったりすることがあります。
加工に入る前に、再度 各加工条件の設定内容を確認してください。
◆ 吸塵機の使用
加工中 ゴミがたまると、基板がきれいに加工できないばかりでなく、加工機のヘッド周辺の
故障の原因にもなります。
加工時には、ゴミを吸い取るために必ず吸塵機をつけておいて下さい。
◆ 他のソフトとの共存
他社のCADソフトなどで、セキュリティボックスを使用しているものと共存する場合、
基板加工時には、必ず他社ソフトのセキュリティボックスをはずしてください。
加工機動作エラーが出ることがあります。
◆ 加工中の注意
加工中は加工機に近づかないでください。特にヘッド部分に注意して下さい。
ヘッド部分は絶えず動いていますので、顔をぶつけたり手をはさんだりすることのないよう、
十分に注意して下さい。
また、加工機の動作中は保護眼鏡を着用して下さい。
◆ 工具と回転数について
基板加工の時は 回転数 30~40 にして下さい。単位はx1000rpm です。
また、微細加工の時は ヘッドの下降速度を遅くしてください。
下降速度2の値を1~2mm/sec にしてください。
67
◆ 空送り・加工速度について
FP-21T Precision の 空送り・加工 の適正速度は次の通りです。
これより速く動作させないでください。
空 送 り ‥‥ 20~30mm/sec
ミリング加工 ‥‥ 12~18mm/sec
微細加工(高周波ミリングカッタ)
‥‥ 2~ 8mm/sec
ルータ加工
フォーミングカッタ2mm‥‥ 1~ 2mm/sec
◆ 輸送について
FP-21T Precision は、精密機械ですので、輸送を行う場合は、弊社が納入時使用した箱を
ご使用ください。
また、社外輸送のため、外部業者に委託される場合は、貨物の取扱が丁寧な業者をご指定ください。
FP-21TPを持ち上げるときには、各軸のガイドやリードスクリュー、ヘッドには力をかけな
いでください。精度が狂う恐れがあります。
◆ メンテナンスについて
プリント基板加工機の保証期間は、正常に使用し、メンテナンスを行っていた場合に 1年です。
それ以降については、保守契約、メンテナンス契約をご用意しております。
この保証には、スピンドルモータ・消耗品は含まれません。
保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
誤使用、不適切な組み立て、不注意による破損、天災、摩耗、装置の改造、メーカー純正部品以外の使用、
指定電圧以外での使用等。
特に、トレーニング無しで基板加工機を購入の場合には、誤使用にご注意ください。
・リニアガイド、リードスクリュー
加工機の使用中、X軸Y軸移動時に異音が出た場合は、音のする軸に注油を行ってください。
注油は頻繁に行う必要はありません。異音がする時に適宜注油してください。
X軸は、カバーの隙間からリニアガイド・リードスクリューに注油します。
少量のミシン油を塗布した後、油がまんべんなくいきわたるように、マニュアル運転で
ヘッドを左右に移動してください。