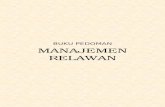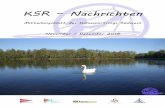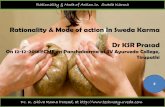KSR v. TELEFLEX 連邦最高裁判決 2007 年4 月30 日」
Transcript of KSR v. TELEFLEX 連邦最高裁判決 2007 年4 月30 日」

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
1
「KSR v. TELEFLEX 連邦最高裁判決 2007 年 4 月 30 日」
弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記) 友野 英三
本稿のご案内
合衆国において連邦最高裁判所で取り上げる事件は極めて限定され、いずれも社会的或い
は法律的に大きな意義を有するもののみである。特許分野でも、近年連邦最高裁で取り上
げられたものは、均等論と禁反言の問題を取り上げたフェスト事件(Festo Corp. v. Shoketsu
Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 525 U.S. 722, 62 USPQ2d 1705 (2002))や、侵害成立と差止認
容の関係を取り上げたイーベイ事件(eBay Inc. v. MercExchange LLC, 126 S. Ct. 1837, 78
USPQ2d 1577 (2006))など、数えるほどしかない。本事件は、非自明性に係る論点につい
て連邦最高裁が判断を示したものであり、今後の特許実務者にとって大きな影響を持つも
のと考えられる。本稿は、この合衆国連邦最高裁判所による「KSR v. TELEFLEX」事件判
決(KSR International Co. v. Teleflex Inc., U.S., No. 04-1350,4/30/07)の全文訳と、その評釈
である。 判決文全文訳
合衆国連邦最高裁判所
No. 04-1350
KSR INTERNATIONAL CO., 上告人 v.
TELEFLEX INC. et al.
連邦巡回控訴裁判所判決に対する裁量的上訴申立事件
[2007 年 4 月 30 日]
Kennedy 判事が当裁判所の見解を以下に表明する。
Teleflex Incorporated 及びその子会社の Technology Holding Company(本稿においては両者を
Teleflex と呼ぶ。)は、KSR International Company に対して特許権侵害を原因として訴訟を提起した。
問題になっている特許は、合衆国特許第 6,237,565 B1 号であり、「電子スロットル制御を備えた調節
可能式ペダル・アセンブリ(Adjustable Pedal Assembly With Electronic Throttle Control)」と題する
ものである。 Supplemental App. 1. 特許権者は Steven J. Engelgau であることから、本特許は
「Engelgau 特許」と称される。Teleflex は本特許についての独占的実施権を保持している。

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
2
Engelgau 特許のクレーム4は、調節可能な自動車用ペダル及び電子センサを組み合わせることで、こ
の車輌のエンジンにあるスロットルを制御しているコンピュータに対して当該ペダルの位置を送信する
ことができるようになっているメカニズム(a mechanism for combining an electronic sensor with an
adjustable automobile pedal so the pedal's position can be transmitted to a computer that
controls the throttle in the vehicle's engine)を記述するものであった。KSR で以前から設計されてい
たペダルの一つに電子センサを取り付けることは Engelgau 特許を侵害するものであるとして、
Teleflex が KSR を訴えると、KSR は、クレーム4は、その対象が自明なものであることから、特許法す
なわち合衆国第 35 法典第 103 条の規定により無効なものであると反論した。
第 103 条は、「特許権付与を請求される対象が、従来技術との間で、当該発明がなされた時点におい
て、当該対象内容が関係する技術分野における通常の技量を有する者にとって、当該対象は全体とし
て自明であったろうと考えられる程度の差異しか有していない場合」には、特許の発行を禁ずる規定で
ある。
Graham v. John Deere Co. of Kansas City( 383 U. S. 1 (1966))事件において、裁判所は制定法た
るこの第 103 条の文言を適用するための枠組みを提示したが、当該条項の文言自体は、それより以
前の Hotchkiss v. Greenwood(11 How. 248 (1851))事件判決及びその後継的事件判決の論法に基
づいている。 383 U. S., at 15-17 参照。 この分析は、客観的なものであって、次のように記される。
「第 103 条規定下では、従来技術の範囲および内容が決定されねばならず;当該従来技術と
争点に係る諸クレームとの差異が確認されねばならず;関連する技術分野における通常の技
量水準が決定されねばならない。こうした背景に照らした上で、当該対象の自明性もしくは非自
明性が決定されることになる。商業的な成功、久しく渇望されてはいたものの未解決であったニ
ーズ、他者の失敗といった二次的考察事項は、特許権による保護が請求される対象の原点を
取り巻く状況に光を当てるために利用することも許されよう。」 同上、 at 17-18.
これらの諸論点の順序は、具体的事件によっては再順序付けされる可能性があるものの、これらの諸
要因は依然として、支配的な審理事項を規定するものである。もし裁判所または特許審査官がこの分
析を実行して、クレームに係る対象が自明であったとの結論を出す場合には、当該クレームは第 103
条の規定により無効である。
もっと統一性および首尾一貫性をもって自明性の問題を解決しようと模索した連邦巡回控訴裁判所は、
当事者が「教示―示唆―動機づけ」テスト(TSM テスト)と呼ぶ方法を採用してきたが、このテストによ
れば、特許クレームは、「従来技術の複数の教示事項を組み合わせることの何らかの動機づけもしく
は示唆」が従来技術、課題の性質、或いは当該技術分野における通常の技量を有する者の知識の中
に、見出し得る場合にのみ、自明であるとされるものである。たとえば、Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc.,
174 F. 3d 1308, 1323-1324 (CA Fed. 1999)参照。 KSR は、当該テストそのものに対し、また

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
3
は少なくとも本件に対してそれを適用することに対し、疑問を呈しているものである。 119
Fed. Appx. 282, 286-290 (CA Fed. 2005)参照。 連邦巡回控訴裁判所が第 103 条および我々の先
例に反する方法で自明性の問題に取り組んでいたことから、当裁判所は裁量的上訴申立を許可したも
のである。 547 U. S ___ (2006). 当裁判所は、原審を破棄する。
I
A
コンピュータ制御式スロットルのない自動車エンジンにおいては、アクセルはケーブルその他の機械的
連結を介してスロットルと相互作用する。該アクセル・ペダルのアームは、枢軸点を中心に回転するレ
バーとして作用する。ケーブル作動式スロットル制御においては、ペダルを押し下げることで生じる回
転によってケーブルが引っ張られると、これが今度はキャブレタまたは燃料噴射装置中の開放弁を引
き開く働きをする。開放弁が広く開けば開くほど、燃料および空気の放出量が多くなり、これにより燃焼
度が増大し車が加速されることになる。運転者がペダルから足を取り除けば、これと正反対のことが起
こって、ケーブルがゆるめられ、弁が摺動して閉じる。
1990 年代になって、車にコンピュータを搭載してエンジンの動作を制御することが、より一般的になっ
た。コンピュータ制御式スロットルは、弁の開閉を、ペダルから機械的連結によって伝達される力を通し
てではなく、電気信号に応答することで行う。空気と燃料の混合ガスについての安定的で微妙な調整
が可能である。ペダル位置以上の諸要素をコンピュータで迅速に処理することで、燃料効率およびエン
ジン性能が向上する。
コンピュータ制御式スロットルが運転者の自動車運転動作に反応するためには、コンピュータはペダル
に起こっていることがわからなければならない。ケーブル或いは機械的連結は、このために十分ではな
い。つまり、なんらかの点において、機械的動作をコンピュータが理解することができるデジタルデータ
に変換するための電子的なセンサが必要である。
センサについて更に議論を進める前に、ペダル自体の機械的デザインに目を向ける。従前のデザイン
では、ペダルを押し下げたり解放したりすることができるものの、これを足元の空間内で前方や後方に
スライドさせてその位置を調整することはできない。その結果、ペダルにもっと接近したり或いはペダル
からもっと離れることを望む運転者は、運転席中での自分の位置付けをし直すか、もしくは何らかの方
法で当該座席を移動させなければならない。足元の空間が深い車の場合、これらの解決策では、身長
の比較的低い運転者にとっては不完全である。1970 年代初めに、本発明者は、この課題を解決する
ために、足下の空間内で位置を変更するように調整可能なペダルを設計した。本件にとって重要なの

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
4
は、合衆国特許第 5,010,782 号(1989 年 7 月 28 日出願)(Asano 特許)および同 5,460,061 号(1993
年 9 月 17 日出願)(Redding 特許)において開示される 2 つの調節可能ペダルである。Asano 特許の
開示するペダルを収納する支持構造では、ペダルの運転者との相対的位置が調整される場合であっ
ても、ペダルの諸枢軸点のうちの 1 つが固定されるようになっている。そのペダルを押し下げるのに必
要な力は、その位置調整に関係なく一定であるようにペダルは設計されてもいる。Redding 特許は、こ
れとは異なった、ペダルおよび枢軸点の両方が調整される摺動メカニズムを開示している。
ここで、センサに話を戻す。Engelgau がこの争点に係る特許を出願するはるか以前から、発明者の中
には、コンピュータ制御式スロットルのための電子的ペダル・センサを含む特許を獲得していた者もあ
った。こういった諸発明、例えば合衆国特許第 5,241,936 号(1991 年 9 月 9 日出願)('936 特許)中で
開示される装置においては、ペダルの位置を、エンジン内ではなくペダル・アセンブリ内で検出すること
が好ましい旨が教示されていた。'936特許は、ペダル・アセンブリ内の枢軸点上にある電子センサを有
するペダルを開示していた。合衆国特許第 5,063,811 号(1990 年 7 月 9 日出願)(Smith 特許)は、セ
ンサとコンピュータとを接続するワイヤーがすり減って磨耗するのを予防し、運転者の足から汚された
り損傷を受けたりするのを回避するために、センサはペダルの脚パッドの中や上ではなく、ペダル・ア
センブリの固定箇所上に設置されるべきである旨を教示していた。
統合型センサを備えたペダルに関する特許に加えて、発明者たちは内蔵型モジュール式センサに関
する特許を取得した。モジュール式センサは、所定のペダルとは独立に設計されることで、既製品を用
いつつさまざまな種類の機械式ペダルに取り付け可能とすることができ、これにより、当該ペダルはコ
ンピュータ制御式スロットルを備えた自動車で使用することが可能となるものであった。 そのようなセ
ンサの一つは、合衆国特許第 5,385,068 号(1992 年 12 月 18 日出願)('068 特許)において開示され
ていた。1994 年、Chevrolet はモジュール式センサであって「ペダル支持ブランケットに取り付けられ、
当該ペダルと隣接し、動作中にペダルが回転する際の枢支軸に係合されるもの」を用いる一連のトラッ
クを製造した。 298 F. Supp. 2d 581, 589 (ED Mich. 2003).
従来技術は、調節可能式ペダルの上にセンサを配置する技術に関する特許も含むものであった。例え
ば、合衆国特許第 5,819,593 号(1995 年 8 月 17 日出願)(Rixon 特許)は、ペダルの位置を検出する
ための電子センサを備えた調節可能式ペダル・アセンブリを開示している。Rixon のペダルでは、セン
サは脚パッドの中に位置していた。 Rixon のペダルは、ペダルが押し下げられ解放される際に、ワイ
ヤがすり減るという欠点を持つことが知られていた。
このペダルおよびセンサ技術の不足性が、本案件への橋渡しをすることとなった。
B

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
5
カナダの企業である KSR は自動車の諸部分を製造し供給するものであったが、この中には
ペダル・システムが含まれていた。Ford Motor 社は 1998 年に KSR を採用し、ケーブル作動式
スロットル制御部を備えた様々な系統の自動車用の調節可能式ペダル・システムを供給させた。KSR
は、Ford のために調節可能型機械式ペダルを開発し、そのデザインに対して合衆国特許第
6,151,976 号(1999 年 7 月 16 日出願)('976 特許)を獲得した。2000 年に、KSR は General Motors
社(GMC または GM)に採用され、コンピュータ制御式スロットルを備えたエンジンを使用する
Chevrolet および GMC 小型トラック用の調節可能式ペダル・システムを供給した。'976 特許のペダル
を当該トラックと互換性を持たせるべく、KSR は単にそのデザインのみを使用し、モジュール式センサ
を付加した。
Teleflex は、調節可能式ペダルの設計および製造分野での KSR の競争相手である。前述のように、
Teleflex は、Engelgau 特許の独占的実施権者である。Engelgau は 2000 年 8 月 22 日に特許を出願
したが、これは合衆国特許第 6,109,241 号となった出願で、1999 年 1 月 26 日に出願されたものの継
続出願としてなされたものであった。Engelgau は、1998 年 2 月 14 日に当該特許の対象を発明してい
たことを宣誓した。Engelgau 特許は調節可能式電子ペダルを開示していたが、これは明細書では、
「より廉価で簡略化された車両制御ペダル・アセンブリであって、使用部品点数はより少数であり車両
内部にパッケージし易いもの」と記述されていた。 Engelgau, col. 2, lines 2-5, Supplemental App. 6.
本件での争点に係る本件特許のクレーム4は、次のように記載されている。
「車両制御ペダル装置であって、
車両構造に取り付けられるのに適合したサポートと;
前記サポートに対して前方及び後方に移動可能なペダル・アームを有する調節可能式ペダ
ル・アセンブリと;
前記調節可能式ペダル・アセンブリを前記サポートに対して枢支し枢支軸を規定するための
枢軸と;
前記サポートに取り付けられて車両システムを制御するための電子制御部と
を具備し、
前記枢軸に呼応する前記電子制御部は、前記ペダル・アームが休止位置及び印加位置の間
で前記枢軸を軸に旋回する際にペダルのアーム位置に対応する信号を供給するためのもの
であり、前記ペダル・アームが前記枢軸に対して前方及び後方に移動する間前記枢軸の位置

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
6
が一定に維持されることを特徴とする装置。」 同上、 col. 6, lines 17-36, Supplemental App.
8 (図の番号は省略)。
当裁判所は、このクレームが「位置調整可能なペダル・アセンブリであって、該ペダル・アセンブリの支
持部材に取り付けられた電子ペダル位置センサを備えたものを開示している。当該センサを支持部材
に取り付けることで、運転者がペダルを調整しても、センサは一定位置にとどまることが可能となる。」
とする地方裁判所に同意する。 298 F. Supp. 2d, at 586-587.
合衆国特許商標庁(PTO)は Engelgau 特許を発行する前に、現在のクレーム4に類似しているがそれ
よりも広い範囲を持った特許クレームのうちの 1 つを拒絶していた。当該クレームは、当該センサが固
定された枢軸点上に配置されねばならないという要件を含んでいなかった。PTO は、当該クレームが
Redding特許およびSmith特許で開示された従来技術の自明な組合せであると結論づけ、次のように
説明した。
「『従来技術引用例がこの目的を持った活動分野からのものであることから、ここで開示され
る目的は...Redding 特許に関連する技術分野では認識されていたものであろう。したがっ
て、...Redding 特許の装置に対して Smith 特許が教示するような支持部材に取り付けられる
当該...手段を供給することは、自明であったであろう。』」 同上、 at 595.
換言すれば、Redding 特許では調節可能式ペダルの一例が与えられ、Smith 特許はセンサをペダル
の支持構造に取り付ける方法を説明するものであり、当該拒絶された特許クレームは単にこれら 2 つ
の教示事項を組み合わせたものにすぎなかった。
このより幅広い範囲を持ったクレームは拒絶された一方でクレーム 4 は後に特許許可されたが、それ
は、固定された枢軸点という限定要件を含むことでRedding特許のデザインとは区別されるという理由
からであった。 同上前記箇所。 Engelgau 特許は従来技術引用文献中に Asano 特許を含んでおら
ず、また、Asano 特許は本件特許の権利化手続過程において言及されてもいなかった。したがって、
PTO はその記録中に固定枢軸点を有する調節可能式ペダルを有していなかった。本件特許は 2001
年 5 月 29 日に発行され、Teleflex に譲渡された。
TeleflexはKSRがGMのために設計を行っていることを知るとすぐに、KSRに対して警告書を送付し、
同社の提案は Engelgau 特許を侵害するものである旨を通告した。「『Teleflex の信ずるところでは、調
節可能式ペダルを電子スロットル制御と組み合わせる製品のいかなる供給者も、Teleflex の特許の一
またはそれ以上で包摂される技術を必然的に使用することになる』」。 同上、 at 585。 KSR は、
Teleflex との使用料支払の和解に入ることを拒否したため、Teleflex は特許権侵害を原因とし
た訴訟を提起し、KSR のペダルが Engelgau 特許および他の 2 つの特許を侵害するものであると主張
した。同上前記箇所。後になって Teleflex は、当該その他の特許に関する主張を取下げ、その特許に
ついては公衆の共有財産とした。残った論争は、KSR が GM 用に設計したペダル・システムが

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
7
Engelgau 特許のクレーム4を侵害したとするものであった。Teleflex は、KSR のペダルが当該特許の
その他の三つのクレームを侵害するとの主張をすることはなかったし、Teleflex はまた、KSR が Ford
用に設計した機械式調節可能ペダルが自身のいずれかの特許を侵害するとの主張をすることもなか
った。
C
地方裁判所は、KSR に有利な正式事実審理省略判決を出した。ペダル・デザインの関連する歴史、
Engelgau 特許の範囲、関連性のある従来技術を検討した後に、同裁判所は、争点に係るクレームの
有効性について吟味した。合衆国第 35 法典第 282 条の命ずるところにより、発行された特許は、有効
であるとの推定を受ける。同地方裁判所は Graham 判例法の枠組みを適用して、正式事実審理省略
判決基準の下で、KSR が当該推定を克服できていたか否か、クレームに係る対象が発明された時点
において、クレーム4が実存する従来技術に照らして自明であったことを立証することができていたか
否かについて判断した。第 102 条(a)参照。
地方裁判所は、専門家証言および両当事者の訴訟上の合意に照らし、ペダル・デザイン分野における
通常の技量水準は、「『機械工学学部卒業程度(または同等量の業界経験)[及び]車両のためのペダ
ル制御システムについての精通度』」であると決定した。 298 F. Supp. 2d, at 590. 同裁判所はそれ
に続いて関連する従来技術を説明したが、ここには、当該特許および上記したペダル・デザインが含ま
れていた。
Graham 事件判例法の指令事項に従い、同裁判所は Engelgau 特許のクレームと従来技術の教示事
項とを比較した。同裁判所は「両者の違いはほとんどない」と認定した。 298 F. Supp. 2d, at 590.
Asano 特許は、センサを用いてペダル位置を検出し、スロットルを制御しているコンピュータにこの検
出信号を送信することを除き、クレーム4において含まれるすべてを教示していた。その追加的な側面
は、'068 特許や Chevrolet の用いたセンサといった出典において示されていた。
しかし、連邦巡回控訴裁判所による支配的な諸判例法の下、同地方裁判所は、そこで止まることが許
されなかった。同裁判所は、TSM テストを適用することを要求された。地方裁判所は、KSR が同テスト
の条件を満たしたと判断した。同裁判所は、(1) 業界の水準からすれば、電子センサおよび調節可能
式ペダルの組合せは必然的に導かれるであろう、(2)Rixon 特許はこれらの開発のための基礎を提供
するものである、(3)Smith 特許は Rixon 特許におけるワイヤーの磨耗という課題に対する解決策、す
なわちペダル上の固定された構造上にセンサを設置するという思想を教示するものである、と論じた。
これにより、Asano 特許或いはそれに類似するペダルと、ペダル位置センサとの組合せが導かれ得る
だろうとされた。

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
8
地方裁判所の見解では、Engelgau のデザインが自明なものにすぎないとの結論を支持するのは、
PTO が当該クレーム4のより幅広い版について拒絶したという事実であった。もし Engelgau 特許が自
身の明細書中に Asano 特許への言及を含んでいたとしたならば、PTO は、これよりも広いクレームを
Redding特許及びSmith特許に基づく自明な組合せであると認定していたという事実からすれば、クレ
ーム4についても Asano 特許及び Smith 特許に基づく自明な組合せであると認定していたであろう、と
同裁判所は論じた。最終的な問題として、地方裁判所は、Engelgau のデザインに基づくペダルでの
Teleflex の商業的成功という二次的要因は、その結論を変えるものではない、と判示した。同地方裁
判所は、KSR の主張を認めた正式事実審理省略判決を下した。
連邦巡回控訴裁判所は、主にTSMテストに依存することで、逆転判決を下した。同控訴裁判所の判決
によれば、地方裁判所は十分厳密にこのテストを適用することなく、「『熟練職人の知識の範囲内で、
[当該]発明の知識を有しない者に対して、..Asano 特許のアセンブリの支持ブランケットに電子制御部
を取り付けるという動機づけを与えたであろうと考えられる具体的な解釈もしくは原則に関する認定』を
行っていなかった。 119 Fed. Appx., at 288 (括弧はオリジナルによる) (In re Kotzab, 217 F. 3d
1365, 1371 (CA Fed. 2000)を引用している)。 連邦巡回控訴裁判所は、本発明の解決すべき課題の
性質によりこの要件が充足されるとした地方裁判所は誤ったものであると判示し、その理由として、当
該「従来技術の引例が特許権者が解決しようとするその正味の問題に取り組む」ものでない限り、当該
課題は発明者にそれら引例に眼を向けさせる動機付けとはならないであろうという点を挙げた。 119
Fed. Appx., at 288.
本件においては、連邦巡回控訴裁判所の認定によれば、Asano 特許のペダルは「『一定割合という課
題』」、すなわち、ペダルを押し下げるために必要な力は、ペダルがいかに調整されようとも一定のもの
であることを保証するという課題、を解決すべく設計されていたものであったが、Engelgau 特許は、よ
り単純、小型かつ安価な調節可能式電子ペダルを供給しようとするものであった。同上前記箇所。
Rixon特許に関しては、そのペダルがワイヤー摩耗問題を欠点として持っていたにも拘らずこれを解決
することを目的としていなかったものであると、同裁判所は説明した。同裁判所の見解では、Rixon 特
許は、Engelgau 特許の目的に役立つものを何も教示していなかった。これに対して Smith 特許は、調
節可能式ペダルに関係するものではなく、「ペダル・アセンブリの支持ブランケット上に電子制御部を取
り付けるという動機づけの問題に必ずしも踏み込む」ものではなかった。同上前記箇所。これらの特許
をこの方法で解釈した場合、これらは、いわゆる当業者を、Asano 特許中で記述される種類のペダル
にセンサを載せるように導くものとはいえなかったであろう[とされた]。
同裁判所の見解によれば、Asano 特許及びセンサの組合せを試みることは自明といえたかもしれない
という点は同様に無関係であるとされ、その理由として、「『「試すのが自明であること」は、自明性[の
根拠]を構成するものではないと、長い間判示されてきた』」ことが挙げられた。 同上、 at 289 (In re
Deuel, 51 F. 3d 1552, 1559 (CA Fed. 1995)を引用している)。

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
9
同控訴裁判所はまた、PTO がクレーム4のより幅広い版について拒絶したことを地方裁判所が斟酌し
た点を非難した。地方裁判所の役割は、もし Engelgau 特許が Asano 特許について言及していたとし
たならば PTO がどのような行動をとったであろうかに関して推測することではない、と連邦巡回控訴裁
判所は説明した。地方裁判所はむしろ、まず発行済みの特許が有効であるとの推定に立った上で、当
該従来技術の再検討に基づいた独自の自明性判断をなすことが義務付けられるものである、と同裁
判所は判示した。 PTO がクレーム4のより幅広い版を拒絶したという事実は、その分析中に入る余地
がない、と同控訴裁判所は述べた。
連邦巡回控訴裁判所は更に、純粋な要件事実論からすれば、この正式事実審理省略判決は排除され
て然るべきであると判示した。 Teleflex は、クレーム 4 は Rixon 特許と比較すれば「『諸特徴点の単純、
簡潔かつ新規の組合せである』」(119 Fed. Appx., at 290)とする一人の専門家からの陳述書、及び、
Rixon 特許と異なり、当該センサはペダル自体にではなく支持ブランケット上に取り付けられていること
から、クレーム4は非自明なものであるとする別の専門家からの陳述書を提出した。この証拠は公判を
必要とするための十分な理由である、と同裁判所は結論づけた。
II
A
当裁判所はまず、連邦巡回控訴裁判所のこの厳格なアプローチを否定することから始めたい。 当裁
判所の自明性問題との関わり全体を通して、我々の判例法が一貫して示してきたのは、拡張的かつ弾
力的なアプローチであって、これは連邦巡回控訴裁判所が本事件において TSM テストを適用したやり
方とは適合しないものである。 たしかに、Graham 事件判決は「統一的かつ明確な」ものの必要性を
認めたものである。 383 U. S., at 18. しかし、Graham 事件判決で提示された原則は、Hotchkiss 判
例法(11 How. 248. See 383 U. S., at 12)の「機能的アプローチ」を再確認したものである。 この目的
を達成するために、Graham 事件判決は幅広い審理を示した上で、裁判所が必要に応じて、有益性が
あろうと考える二次的考察事項があればいかなるものにでも眼を向けることを奨励するものであった。
同上、 at 17。
従来技術中に見出される要素の組合せに基づく特許を付与する際に注意が必要である点に関して、
当裁判所が以前から発している指令事項は、第 103 条の立法によろうとも Graham 事件判決の分析
によろうとも、妨げられるものではない。半世紀以上にわたり、裁判所は、「旧来の諸要素を結び付け
ているのみでそれぞれの機能に関しては何の変更もない組合せに対して与えられる特許は、…すでに
既知のものを市場独占の領域に引き込み、熟練者の利用できる資源を減らしてしまうものであることは
明らかである」と判示してきた。 Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.,

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
10
340 U. S. 147, 152 (1950). これが、自明なものに対して特許を付与することを拒否する主要な理由
である。ありふれた要素を既知の方法に従って組み合わせるものは、それが予測可能な結果を生むに
すぎない場合、自明であるとされる可能性が高い。Graham 事件の後に判決が下された次の 3 つの事
件が、この法理の適用を例示するものである。
Graham 事件の類例でもある United States v. Adams 事件(383 U. S. 39, 40 (1966))においては、
裁判所は「湿式電池」についての自明性の問題を考察したが、これは従来のデザインとは2つの点で
異なるものであった。そこには、従来、蓄電池で採用されていた酸ではなく水が含まれており、その電
極は亜鉛および塩化銀ではなく、マグネシウムおよび塩化第一銅であった。特許のクレーム対象が、
従来技術においてすでに知られている構造であってその 1 つの要素を当該分野で公知の別の要素で
単に置き換えるという変更を加えたにすぎないものである場合には、当該組合せは予測可能な結果を
生む以上のことをするものでなければならない、と裁判所は認定した。 383 U. S., at 50-51. それにも
かかわらず同裁判所は、Adams の電池は自明であるとする行政側の主張を退けた。 同裁判所は、
従来技術が特定の公知要素を組み合わせることと反することを教示する場合に、それらの組み合わせ
を行う手段であって奏功するものの発見は、非自明となる可能性が高いとする、必然的帰結たる原則
に依拠していた。同上、 at 51-52。 Adams が自分の電池を設計した際に、そこで採用された種類の
電極を使用する場合には危険が伴うことを従来技術は警告していた。 これら諸要素が予想外であり
ながら有意義な方法によって協働したという事実は、Adams の構想がいわゆる当業者にとって自明な
ものではないという結論を支持するものであった。
Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.事件(396 U. S. 57 (1969))において、裁判
所はこのアプローチについて詳述した。 法廷に上げられた当該特許の対象は、2 つの既存の要素で
ある放射熱バーナーおよび舗装機械を組み合わせた装置であった。裁判所が出した結論によれば、こ
の装置は、なんらかの新しい共働効果を生み出すものではなく、当該放射熱バーナーは普通のバーナ
ーに期待される機能をそのまま発揮するものであり、当該舗装機械についても同様であった。 これら
二つが組み合わされたものは、それぞれの要素が別々に、連続した動作で行うこと以上のことをするも
のではなかった。 同上、at 60-62。 こうした状況においては、「旧来の諸要素の組合せが実用的な機
能を果たしはするものの、それはすでに特許された放射熱バーナーの性質及び品質に対して何物も追
加していない」として、当該特許は第 103 条の規定により特許性を否定されたものである。 同上、at
62 (脚注省略)。
最後に Sakraida v. AG Pro, Inc.事件(425 U. S. 273 (1976))において、裁判所は、これら諸先例から、
ある特許が「単に古い諸要素を並べ、その各要素が実行する機能がそれまでに当該要素が実行する
として知られていた機能と同じであ」り、この種の配列から期待できるであろう以上のものを生み出さな
い場合には、当該組合せは自明なものである、という結論を導き出した。同上、at 282。

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
11
従来技術の諸要素の組合せを権利請求している特許が自明なものであるかどうかが争点の場合に、
これらの事件の基礎をなす諸原則は教訓的なものである。ある作品が一つの目的活動分野で利用可
能な場合、同じ分野或いは異なる分野のいずれにおけるものであろうとも、デザイン誘因およびその他
の市場実勢がその作品の幾つかの変形版の出現を促すことはあり得る。通常の技量を持った人間が
予測可能な変形版を実施することができる場合、第 103 条によってその特許性が妨げられる可能性が
高い。同じ理由から、ある技術が用いられることで装置が改良され、しかもいわゆる当業者であれば、
同じ方法により類似の装置が改良されるであろうことを認識するだろうと考えられる場合には、当該技
術を用いることは、その実際の適用が当事者の技量を超えるものでない限り、自明となる。 Sakraida
事件及び Anderson's-Black Rock 事件が例示的であるが、裁判所は、当該改良が、従来技術の諸
要素についてのそれらの確立された方法による予測可能な利用を超えるものであるかどうか、につい
て問いを発しなければならない。
これらの原則に従うことは、他の事件の場合には本件における場合よりも困難性を増す可能性がある
が、それは、特許クレームに係る対象が関連するのが、一つの公知要素を別の要素に単に置換させる
こと、或いは改良態勢にある従来技術の一遍に対して単に公知技術を適用することを超えるものであ
る場合があるからである。往々にして、裁判所が目を向ける必要があるものとしては、多数の特許の相
互に密接な関係のある教示事項;設計の世界に公知な、或いは、市場に存在する需要の影響;従来
技術分野における通常の技量を有する者が備える背景知識であり、これらは総て、争点の特許が権
利請求する方法で公知の諸要素を組み合わせるための明瞭な根拠が存在するか否かを決定するた
めのものである。 再審理を容易にするために、この分析は、明示的なものとされるべきである。 In re
Kahn, 441 F. 3d 977, 988 (CA Fed. 2006)参照 (「自明性を根拠とする拒絶は、単なる推論的声明
のみではこれを支持し得ず、自明であるという法的結論を支える何らかの論拠であって、何らかの合
理的基盤を持ち明瞭に表現されたものがなければならない」)。 しかしながら、我々の先例が明らかに
しているように、この分析においては、当該問題とされるクレームの具体的対象に向けられた厳密な教
示事項を追求する必要はない。というのは、裁判所は、当業者であれば採用するであろうと考えられる
推論結果および創造的手段を考慮に入れることができるからである。
B
組合せが自明であることを示すためには公知の諸要素を組み合わせるための教示、示唆、或いは動
機づけを立証しなければならないとする要件を連邦巡回控訴裁判所が最初に定立した際、同裁判所
は役に立つ洞察を表現していた。 Application of Bergel, 292 F. 2d 955, 956-957 (1961)参照。
Adams 事件のような諸判例から明らかなように、複数要素からなる特許であっても、これらの各要素
が別々に、従来技術において公知であったことを示すのみでは、自明であることは立証されることには

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
12
ならない。2つの公知装置をそれぞれに確立された機能にしたがって組み合わせたものを新考案とし
て権利請求する特許出願に対して、慎重な眼を向けるべきことを良識が命じるとはいえ、当該関連分
野における通常の技量を有する者に対して、当該権利請求に係る発明が組み合わせる方法で当該諸
要素を組み合わせることを促したであろうと考えられる根拠を発見することが重要となり得るのである。
このことがいえるのは、全てではないにしてもほとんどの場合に発明というのは、ずっと以前に発見さ
れた積み木の上に成り立っているようなものであって、権利主張される発見物は必然的にそのほとん
どが、ある意味では、すでに知られていることの組合せにすぎないからである。
しかしながらいかに有用な洞察であろうと、必ずしも厳格かつ強制力を持った公式となる必要はなく、
TSM テストがそのようなやり方で適用されている場合には、これは我々の先例とは相容れないもので
ある。自明性分析は、教示、示唆、および動機づけという文言からなる過剰形式主義的概念によって
は、或いはまた、出版された論文の重要性や発行された特許の明示的内容を過度に強調することによ
っては、限定し得ないものである。発明行為及び最新技術の多様性は、このような方法で分析を限定
しないように勧告するものである。多くの分野において、自明な技術もしくは組合せについての議論が
ほとんどないということもあり得るし、多くの場合、科学文献よりむしろ市場の需要が設計動向を駆りた
てるということは真実であるかもしれない。 通常の過程において起こり得、真の革新の伴わない進歩
に対して特許権による保護を与えることは、発展を阻害するものであり、以前から公知の要素を組み
合わせている特許の場合には、従来発明からそれらの価値或いは有用性を奪う可能性がある。
関税特許控訴裁判所が TSM テストの本質を明らかにして以来何年もの間、控訴裁判所が多くの場合
に、これらの諸原則に従ってこのテストを適用してきたのは疑いないことである。TSM テストの根拠を
なしている考え方と Graham 分析との間には、必然的な不整合はない。しかし、連邦巡回控訴裁判所
が本件でしたように、裁判所がこの一般的原則を、自明性審理を制限する厳格な規則に変形する場合
には、それは誤っていることになる。
C
連邦巡回控訴裁判所の分析の欠点は、その大部分が、その TSM テストの適用に反映される、同裁判
所が自明性審理に関して有している狭い概念に関するものである。特許クレームの対象が自明である
かどうかを決定するに当たっては、特許権者側の特定の動機づけも公然の目的も、支配的要因とはい
えない。重要なのは、当該クレームの客観的な範囲である。もしそのクレーム[の射程範囲]が自明で
あるものにまで及ぶ場合には、第 103 条の規定により無効となる。特許の対象についての自明性を立
証し得る方法の一つは、当該発明の時点において公知の課題が存在しており、この課題に対しては、
本願特許クレームで包摂される自明の解決手段が存在していたことを示すことによるものである。

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
13
本案件における同控訴裁判所の最初の誤りは、裁判所及び特許審査官は特許権者が解決しようとし
ていた課題のみに目を向けるべきであると判断することで、この論証を排除したことである。119 Fed.
Appx., at 288. 特許権者に動機付けする課題は、当該特許対象が取り組んでいる多くの課題のうち
の一つにすぎないということがあり得るという点を、同控訴裁判所は認識していなかった。問題は、当
該組合せが特許権者にとって自明だったかどうかではなく、同組合せが当該技術分野における通常の
技量をもつ者にとって自明であったかどうかである。正しい分析の下では、発明の時点における目的
活動分野で知られた必要性もしくは課題であって特許が取り組んでいるものはいかなるものであっても、
当該諸要素をクレームに係る方法で組み合わせるための根拠を提供する可能性がある。
同控訴裁判所の第二の誤りは、当該技術分野での通常の技量を持った人間であって課題を解決しよ
うと試みる者は、その同じ課題を解決するのを目的とした従来技術上の諸要素のみに導かれるもので
あるとする、その前提にある。同上前記箇所。Asano 特許の主要な目的は、一定割合問題を解決する
ことにあった。したがって、同裁判所の結論によれば、調節可能式ペダル上にセンサをのせる方法に
ついて熟考している発明者であるならば、当該 Asano 特許に係るペダル上にこれをのせることを考え
付く根拠を有しないであろう、とするものである。同上前記箇所。しかしながら、ありふれた部品がそれ
らの主要目的以上の自明な用途を有する場合があり、多くの場合、通常の技量を持った者が、パズル
の多数のピースのように、多数の特許の教示事項を組み合わせることが可能であることは常識が教え
ることでもある。Asano 特許の主要目的に関係なく、当該デザインは固定枢軸点を備えた調節可能式
ペダルの自明な例を提供するものであるといえる。さらに、従来技術中に含まれる多数の特許では、
固定枢軸点がセンサのための理想的な取付台であることが示されていた。Asano 特許が一定割合問
題を解決することを目的としていたからとして、調節可能式電子ペダルを製作することを望む設計者で
あれば Asano 特許を無視するだろうという考え方は、ほとんど意味をなさない。通常の技量を持った者
は、通常の創造力を持った人間でもあり、ロボットではないのである。
この同じ制約的分析が、同控訴裁判所を、諸要素の組み合わせを「試みることが自明」であることを単
に示すだけでは特許クレームについての自明性の立証とはなり得ないという誤った結論に導いたもの
である。同上、at 289 (中にある引用符は省略)。 課題を解決するための設計上の必要性或いは市場
からのプレッシャーがあり、かつ、予測可能であってこれだと特定できる諸解決手段が存在する場合、
通常の技量を持った人間が自分の技術的な理解力の範囲内でその知られていたオプションを追求す
るということには十分の合理性がある。もしこれにより予想された成功が導かれるのであれば、それは
おそらく、革新からの製品ではなく、通常の技量および常識からの製品である。その場合において、組
合せはそれを試みることが自明であったという事実は、それが第 103 条の規定により自明であることを
立証するものともいえよう。
最後に、連邦巡回控訴裁判所は、裁判所および特許審査官があと知恵の先入観の犠牲になるという
リスクから間違った結論を引き出した。当然のことながら事実認定者は、あと知恵の先入観によって生
じる歪曲を認識しておくべきで、事後的な推論に依存しての議論には慎重でなければならない。

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
14
Graham, 383 U. S., at 36((Monroe Auto Equipment Co. v. Heckethorn Mfg. & Supply Co.事件判
決( 332 F. 2d 406, 412 (CA6 1964))を引用しつつ)参照「従来技術中に争点に係る発明の教示事項
を読み込もうとする誘惑」に対して警告を発し、裁判所に対してあと知恵の利用に陥ることに対し注意
を喚起している)。しかしながら、事実認定者が常識に頼るのを否定する厳格な防止的規則は、我々の
判例法に照らして必要ともいえないし、それと整合するともいえない。
当裁判所は、同控訴裁判所がそれ以来、現事件に適用されたものよりも幅広い TSM テストの概念を
念入りに作り上げてきたことに注目する。たとえば、DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland
KG v. C. H. Patrick Co., 464 F. 3d 1356, 1367 (2006)参照 (「我々の示唆テストは実際上、非常に
弾力的なものであって、常識および分別に考慮を払うことを許容するだけでなく、そのことを要求もして
いる」); Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464 F. 3d 1286, 1291 (2006) (「従来技術中の動機づけが
暗黙的にしか認められないことがあることから、我々の自明性法理には融通性が存在する。我々は、
実際の教示事項が…組み合わせるものでなければならないとする厳格なテストを行うものではない」)。
もちろん、それらの判決は、現在当裁判所の俎上にあるものではなく、本件について同控訴裁判所が
犯した法律的誤りを正すものではない。彼らが説明する分析について、当裁判所の以前の諸先例およ
び判決とどこまで整合させるのかという程度は、連邦巡回控訴裁判所がその将来の案件において考
察すべき問題である。 我々が判示するのは、前述した基本的な誤解が原因となって、連邦巡回控訴
裁判所が本件において、当裁判所の特許法関連諸判決と整合しないテストを適用することとなった、と
いうことである。
III
我々がこれまでに説明した基準を現在の諸事実に適用する場合、クレーム4は自明であると認定され
なければならない。当裁判所は、関連従来技術に関する地方裁判所の詳説および当該技術分野にお
ける通常の技量水準についての同裁判所の決定に同意し、これを採用する。地方裁判所がそうであっ
たように、当裁判所も、Asano 特許および Smith 特許を結合させた教示事項と、当該 Engelgau 特許
のクレーム4に開示される調節可能式電子ペダルとの間の差異をほとんど認めることができない。い
わゆる当業者であれば、Asano 特許とペダル位置センサとを、クレーム4によって包含される方法で組
み合わせることができたであろうし、かつ、そうすることの利益も理解していたことであろう。
A
因みにTeleflexは、Asano特許の枢軸機構のデザインからすれば、Asano特許のペダルはクレーム4

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
15
記載の方法によってはセンサと組み合わせることができないと主張している。被上告人弁論趣意書
48-49, n. 17 参照。 したがって Teleflex は、たとえ Asano 特許にセンサを付加することが自明だった
としても、そのことが、クレーム4が自明な対象を含むということを成立させることにはならない、と主張
する。 しかしながら、地方裁判所ではこの議論は提起されなかった。地方裁判所においては Teleflex
は、Engelgau 特許が権利請求する発明に対して動機付けを与えている当該課題によっては、Asano
特許をセンサと組み合わせるという解決手段が導かれるものとは考えられないとする主張を行うのみ
で満足していた。KSRの特許無効の旨の正式事実審理省略判決申立てに対するTeleflexの答弁(No.
02-74586 (ED Mich.), pp. 18-20, App. 144a-146a)参照。連邦巡回控訴裁判所において、Teleflex
は、Asano 特許をセンサと組み合わせてもクレーム4の限定要件を充足することにはならないであろう
とする、具体的事実に基づかない、推論的主張を提示したが、上記の論点が提起されたか否かについ
ては明確でない。No. 04-1152 (CA Fed.), pp. 42-44 中の原告-控訴人弁論趣意書参照。その上、
Teleflex 自身の専門家宣誓供述書も、Teleflex が現在持ち出している論点を支持するものでない。
Declaration of Clark J. Radcliffe, Ph.D., Supplemental App. 204-207; Declaration of Timothy L.
Andresen, 同上、at 208-210 参照。 いずれの宣誓供述書においてもこの議論に影響を持ちうる唯一
の陳述は、次の Radcliffe 宣誓供述書中に見ることができる:
「Asano 特許...及び Rixon 特許...は、複雑な機械式連結を基礎とする装置であるため、生産・組
み立てが高価につき、パッケージングが難しい。[Engelgau 特許が]解決しようとするのは、まさに
従来技術の設計についてのこれらの難点なのである。ペダル位置を表す単一枢軸を持った調節
可能式ペダルを、当該支持部と該枢軸上の調整アセンブリとの間に載置される電子制御部と組
み合わせて用いたことは、Engelgau の'565 特許の諸特徴点についての単純、簡潔かつ新規の
組合せである。」 同上、at 206, ¶16。
この宣誓供述を全体としての文脈で読めば、「Engelgau の'565 特許が取り組んだ、廉価で、組み立て
が迅速にでき、パッケージングが小さくて済む、電子制御部を備えた調整可能式ペダル・アセンブリを
提供するという課題」を解決するために Asano 特許を用いることは不可能であった旨を意味するものと
解釈するのが最も適している。同上、at 205, ¶10。
地方裁判所は、Asano 特許を枢軸搭載型ペダル位置センサと組み合わせたものはクレーム4の範囲
内にあると認定した。 298 F. Supp. 2d, at 592-593. この認定が同地方裁判所判決に対して持つ重
要性を考えるとき、もし Teleflex がこのクレームを保持することを意図していたとしたならば、同社はも
っと明確な形で異義申立を行っていたであろうことは明瞭である。 Teleflex がこの論点を明確な形で
提起しなかった点、及び連邦巡回控訴裁判所がこの論点について沈黙している点に照らせば、当裁判
所としては、この点に関する同地方裁判所判決は正当なものであると考える。
B

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
16
Engelgau がクレーム4の対象物を設計した時点において、いわゆる当業者が Asano 特許を枢軸載置
式ペダル位置センサと組み合わせることは自明であった、と地方裁判所が結論付けたのは正しかった。
その時点において存在していた市場が、機械式ペダルを電子ペダルに変換するための強い誘因を創
り出しており、当該従来技術がこの進歩を達成するための多くの方法を教示していたといえる。連邦巡
回控訴裁判所が、白紙状態で書き込みを行うペダル設計者であれば、Asano 特許と、Chevrolet のト
ラック群で用いられ'068 特許中に開示されるのと類似するモジュール式センサとの両者を選択してい
たであろうといえるであろうか、との問いを実質的に発したことは、本論点についての考察としては狭き
に過ぎるものである。同地方裁判所では、同じように、この狭窄的審理を採用したのであるが、それに
もかかわらず正しい結果に到達した。尋ねるべきであった本当の問いは、通常の技量を持ったペダル
設計者であれば、本目的対象分野における開発によって生み出された広範囲のニーズに直面した場
合に、センサを用いて Asano 特許に改良を加えるということに利点を見出したであろうかどうかというこ
とであった。
自動車デザインにおいて、その他多くの分野と同様に、多数の構成要素の相互作用は、1 つの構成要
素を変更すれば多くの場合他の構成要素も同様に変更することを余儀なくされる、ということを意味す
る。技術開発は、コンピュータ制御式スロットルを使用するエンジンが標準となるであろうということを明
らかにした。その結果として、設計者はゼロから新規ペダルを設計することに決定した可能性もある一
方で、既存のペダルをこの新規エンジンと共に動作させようとすることにも、同様に合理性が認められ
たことであろう。実際に、自身の既存モデルに改良を加えるということによって、KSR は、Engelgau 特
許を侵害するものとして現在訴えられているペダルの設計に至ったものである。
Asano 特許を出発点とする設計者にとっては、問題はセンサをどこに取り付けるべきかということであ
った。次に結果として生じる法的問題は、Asano 特許を出発点とし、通常の技量を有するペダル設計
者であれば、固定枢軸点上にセンサを配置するということが自明なことであると認定したであろうという
ことがいえるか否かということである。上記で論じた従来技術は、KSR および Engelgau が配置した場
所にセンサを取り付けることは通常の技量を有する者にとっては自明なことであったであろうとの結論
に我々を導くものである。
'936 特許は、センサをエンジンの中にではなくペダル装置上に載せることの有用性を教示していた。対
して Smith 特許は、センサをペダルの脚パッド上ではなくその支持構造上に載置させることを説明して
いた。そして、Rixon 特許の公知のワイヤ磨耗問題と Smith 特許の「ペダル・アセンブリは、接続ワイヤ
の動作をいささかも引き起こすものであってはならない」(Smith, col. 1, lines 35-37, Supplemental
App. 274)なる教示事項からすれば、設計者であればセンサをペダル構造の非可動部分に配置する
という思想を知っていたであろう。センサがペダル位置の感知を容易に行うことができる構造上の非可
動部分として最も明らかな箇所は、枢軸点である。したがって、設計者であれば、Smith 特許に従って

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
17
センサを枢軸に載置することで、クレーム4で包摂される調節可能式電子ペダルを設計することだろ
う。
Asano 特許をコンピュータ制御式スロットルで動作させるように改善するという目的を出発点とすること
が可能であったのと同様に、Rixon 特許のような調節可能式電子ペダルを採用し、ワイヤー摩耗問題
を防止し得る改良を追求することも可能であった。まさにここに説明したものに準ずる段階を踏めば、
設計者ならば、センサの動きを防止すべきことをSmith特許から学んだ上で、これによりAsano特許に
至ることだろう。というのは、Asano 特許は、固定枢軸を持った調節可能式ペダルを開示していたから
である。
Teleflex は、従来技術の開示事項が Asano 特許にセンサを取り付けることと反することを教示するも
のである旨を間接的に主張し、その根拠として、Asano 特許は、同社の見解によれば巨大で、複雑か
つ不経済であることを挙げている。しかしながら、Teleflex がこの議論を支持すべく提示する唯一の証
拠は Radcliffe 宣誓供述書であり、それは、Asano 特許は、小型、単純かつ安価なペダルを製作すると
いう Engelgau 特許の課題を解決するものではなかったであろう、ということを単に示したものである。
当該宣誓供述は、Asano 特許が、当該ペダルもしくはそれに類似するペダルを改良して現代エンジン
と適合させることには合理性がない、といえるほどの何らかの欠陥を有しているものであることを示唆
するものではない。実際に、Teleflex 自身の宣誓供述が、この結論を論破している。Radcliffe 博士は、
Asano と同様の大きさおよび複雑さの問題を、Rixon 特許も欠点として持っていたと述べている。 同
上、at 206 参照。 しかしながら、Teleflex の他の専門家は、Rixo 特許自体、既存の機械式ペダルにセ
ンサを付け加えることによって設計されたものであると説明した。 同上、at 209 参照。 Rixon 特許の
基礎ペダルが欠陥があまりにあり過ぎて改良することができないというのでない限り、Radcliffe 博士の
宣誓供述は Asano 特許も同様であることを示してはいないことになる。 Asano 特許は Engelgau 特許
の好適な実施形態と比較して非効率的である、というもっともらしい主張を Teleflex は行ったのかもし
れない。しかし Asano 特許を Engelgau 特許に照らして判断するということは、あと知恵の先入観で縛
られることになり、これはまさに、Teleflex が防止されなければならないこととして強く主張している対象
に他ならない。したがって、Teleflex は、Asano 特許を用いるということと反する旨を教示する事項を従
来技術中から何も示さなかったことになる。
最後に、地方裁判所と同様に当裁判所は、クレーム4が自明であるという決定を排斥する二次的要因
を Teleflex は提示していないと結論する。以上より、Graham 判例法及びその他の先例をこれらの事
実に対して適正に適用することで、当該クレーム4は自明な対象を含むものであるとの結論が導かれ
る。結果的に、当該クレームは第 103 条の要件を充足していないことになる。
Engelgau 特許についての権利化手続過程において Asano 特許を開示しなかったことが、既発行特許
に対して与えられる有効性の推定を覆すものであるか否かという問題には、我々は取り組む必要を認
めない。というのは、クレーム4は、この推定如何に拘らず自明であるからである。そうはいいつつも、

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
18
「特許商標庁がその専門的知識において、当該クレームを許可したものである」という、当該推定を正
当付ける理論的根拠は、本件では大いに減弱したように思われる、との注釈を付すのが当裁判所とし
ては適切と考えるものである。
IV
連邦巡回控訴裁判所が正式事実審理省略判決を覆すために与えた別の根拠は、要件事実という論
点についての論争が存在することであった。当裁判所はこの点についても、同控訴裁判所に同意しな
い。同裁判所が、専門家が自明性の問題に取り組む推論的宣誓供述書を提示する場合の正式事実
審理省略判決の可能性を排除するためのものであるとして、Graham アプローチを理解する限度にお
いて、同裁判所は、当該分析において専門家証言の果たす役割を誤解しているといえる。この論点に
関する正式事実審理省略判決を考慮するに当たっては、地方裁判所は専門家証言を考慮に入れるこ
とができるし、考慮にいれるべきである。この専門家証言は、特定の事実問題を解決したり、或いは、
明らかにしたりする可能性を持つものである。しかしながら、これが当該論点の終結点となるわけでは
ない。自明性に関する最終的な判断は、法的決定事項である。 Graham, 383 U. S., at 17. 本件のよ
うに、従来技術の内容、特許クレームの範囲、当該技術分野における通常の技量水準が要件事実に
おける争点となっていない場合、および、これらの諸事実に照らせば当該クレームの自明性が明らか
である場合、正式事実審理省略判決は適切なものといえる。Teleflex によって差し出された宣誓供述
書のいずれも、同地方裁判所が、本件における正式事実審理省略判決の付与の基礎をなす慎重な結
論に至ることを妨げるものではなかった。
* * *
我々は、身の回りの形を持った明白な現実に立ち戻ることで新たな作品を構築し創設するものだが、こ
の作品は、本能、純然たる論理、通常の推論、特別な着想、さらに時には才能にさえも基づくものであ
る。これらの進歩は、一旦我々の共有知識の一部となるとすぐに、再度の革新の出発点を画する新た
な閾値を規定するものとなる。より高いレベルの到達物を出発点とする進歩が期待されることが通常と
なるのにつれて、通常的革新の成果は特許法制に規定される独占権の対象にはなじまないものとなる。
もしそれと逆であったとしたならば、特許は有用な技術の発展を抑圧しこそすれ、促進するものとはな
らないであろう。 U. S. Const., Art. I, §8, cl. 8 参照。 こういった前提があって、自明な対象を権利請
求する特許を禁ずる思想が導かれ、これが Hotchkiss 事件判例法で樹立され、第 103 条中に成文化

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
19
されたものなのである。この禁止条項の適用は、その本来の趣旨を全うできないほど拘束的なテスト
或いは公式化の中の、制限的なものであってはならない。
KSRは、モジュール式センサをAsano特許のペダルの固定枢軸点上に載置することは、当該関連技術
分野における通常の技量を持つ者が十分理解できる範囲内にある設計の一段階にすぎない、とする
説得力ある証拠を提示した。その主張に係る諸事項および記録は、Engelgau 特許のクレーム4は自
明であることを証明するものである。地方裁判所の判決を退けるに当たって同控訴裁判所が本論点を
分析した方法は、狭窄的で厳格なものであり、これは第 103 条および我々の諸先例と整合するもので
はない。連邦巡回控訴裁判所の当該判決を破棄し、本件を、当見解と整合した更なる訴訟手続に付す
べく差し戻すものとする。
よって主文のように判決する。
評釈 恐らく、特許出願についての特許性、有効性の議論において実務上最も重要であり最も
頻繁に議論される点は、日本においては進歩性、合衆国においては非自明性であろう。こ
れまで、合衆国連邦最高裁は、自明性は、 (1)従来技術の範囲および内容; (2) 権利請求に
係る発明および従来技術の違い; (3)いわゆる当業者の技量水準; (4) 商業的成功、長きに亘
って感得されてきたものの解決されなかったニーズ、他者の失敗...を含むあらゆる関連二次
的考察事項、に依拠して判断される、とする判例法を打ち立ててきた。これを受ける形で
合衆国特許商標庁では、合衆国において非自明性を立証するためには、prima facie case of obviousness(一見して自明性を推認できるとする程度の事実に基づく立論)が打ち立てら
れねばならず、この prima facie case of obviousness の樹立は、次の諸点が事実として存在
することをいわねばならないとされてきた。 1一以上の先行技術、 2これらの先行技術が当該発明者にとって利用可能であったこと、 3これらの先行技術が具体的な教示事項を有していること、 4この教示事項の中には、先行技術を組合せ、もしくは改良することを示唆する旨が含
まれること、 5これらの組合せもしくは改良は、いわゆる当業者にとって当該クレームに係る発明を
自明なものにするのに十分なものであろうと考えられること。 これらのそれぞれに対して、たとえば何が先行技術となり得て何がなり得ないのか、と
か、どういった場合に発明者にとって利用可能といえるのか等につき、多くの判例法が存
在する。本件は、狭義には、連邦巡回控訴裁判所(及び前身の関税特許控訴裁判所)の用
いてきた非自明性判断に対するアプローチの正当性が問われたものだが、本質的には、先
行諸技術の組合せにおける「組合せ」という事実の立証性、日本的に言い換えるのであれ

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
20
ば「組合せ」の要件事実論が論点となったものと捉えることも可能であろう。 本件は一義的には、合衆国の(非)自明性判断について連邦最高裁が、prima facie case of
obviousness という枠組みに必ずしもとらわれずに、非自明性という本義に立ち戻り、これ
まで基準となって運営されていた連邦巡回控訴裁判所(及び前身の関税特許控訴裁判所)
の考え方に修正を加えたものという理解もできる事件である。本件に関する事実関係の経
緯は次のように纏めることができる。 本件はもともと、調節可能ペダル・アセンブリに関する特許(U.S. Patent 6,237,565;
「‘565 号特許」)に関する権利を保有していた Teleflex 社が、KSR 社に対して、KSR 社
の調節可能ペダル・アセンブリが‘565 号特許のクレーム4を侵害することを原因として、
ミシガン州東部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起したものである。 同連邦地裁は、このクレーム4は自明であるとして特許を無効とするサマリー・ジャッ
ジメント(正式事実審理省略の判決)を言い渡した。同地裁の判決の論拠は、当該クレー
ム4は先行技術である Asano 特許と、いわゆる当業者の(当時の)知識とからすれば自明
なものにすぎない、というものであった。地裁によれば、この Asano 特許にはクレーム4
に掲げられている構造的な構成要件は、電子的制御を除き、総て開示されていたものであ
り、電子的な制御については、当該技術(自動車用のペダル・アセンブリ技術)分野にお
いてよく知られていたものであった。 このことから同連邦地裁は、解決すべき課題の性質に基づけば、Asano 特許と電子制御
とを組み合わせるための動機付けは存在していたと見るべきであると判断した。より具体
的には、別の先行技術である Rixon 特許では‘565 号特許の取り組んでいた課題を問題点
として抱えていたものであり、いわゆる当業者であれば、これらの問題を克服するために
Asano 特許と電子制御とを組み合わせるということに想到するであろうと考えられるとし
た上で、第3の先行技術である Smith 特許にはペダル・アセンブリに電子制御を用いるこ
とが教示されている、とした。 控訴審において連邦巡回控訴裁判所は、連邦地裁の判決を覆した。同控訴裁判所は次の
ように述べている。諸先行技術文献の組合せに基づいて特許を無効とするためには、当該
組合せを教示し、示唆し、もしくは動機付けるものが存在していなければならない、と地
裁が考えたのは正しい。組合せの動機付けが、本件特許が取り組んでいる課題の性質中に
発見される可能性がある、としたことも正しい。しかし、同地裁は、この TSM テストの適
用を誤ったものである。 同控訴裁判所は次のように考えを述べている。争点に係る特許がクレームしている特定
の方法によって先行技術文献を組み合わせることを動機付けること、に関する具体的な事
実が認定されなければならない。組合せの動機付け基準が満たされているとされるのは、
その組合せというのが、「特許権者が解決しようとする、まさにその正味の課題に取り組ん
でいる複数の先行技術文献」に基づいている場合のみである。この分析手法は、後知恵に
よる評定という弊害を防止するものである。地裁は、「いわゆる当業者であれば、‘565 号特

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
21
許の取り組む課題を解決すべく、Asano 特許に開示される構造に電子制御を付加するとい
うことが具体的に動機付けられたであろう」ということがなぜいえるのかについての事実
を提示していない。すなわち、Asano 特許は‘565 号特許の取り組んでいる課題と同じ課
題に取り組むことを目的としておらず、Smith 特許も同じく、‘565 号特許の取り組む課題
とは異なるワイヤー磨耗問題に取り組むものであり、Rixon 特許は‘565 号特許の取り組む
課題と同じ問題を問題点として有していたが、解決手段を提供するものではなかった。 本件はその後、連邦最高裁に裁量的上訴申立てされたが、2006 年 6 月 26 日、連邦最高
裁はこの申立てを許可した。ここでの争点は、いわゆる当業者であったとすればこの者を、
クレームに係る方法で、関連従来技術の諸開示事項を組み合わせることに導くであろう「教
示、示唆、もしくは動機付け」が存在していたことを何らかの形で立証するものがない場
合には、当該クレームに係る発明を自明として合衆国第 35 法典第 103 条規定により特許性
を有しないとしてはならないと連邦巡回控訴裁判所が判断したのは誤っていたか否か、と
いう点である。 合衆国司法省の訟務大臣は、連邦最高裁が本件の裁量的上訴申立てを許可し、自明性基
準を明確化することを働きかけた上で、具体的に次の点を述べた。第 103 条(a)規定の自明
性テストは柔軟性を持つものであることが意図されたものである一方で、連邦巡回控訴裁
判所の「教示―示唆―動機付け」テストは厳格なものである。連邦巡回控訴裁判所の TSMテストでは、先行技術事項をクレームに係る特定方法で組み合わせることを教示し、示唆
し、もしくは動機付けることを示した具体的検証事実及び積極的証拠が必要であるとして
いる。このテストによれば、既存の技術を非革新的に組み合わせることを開示するにすぎ
ないものであって、本来万人が利用可能なはずの知識の利用から競業者を締め出すような
特許であってもこれを許すことになる。連邦巡回控訴裁判所のテストではまた、訴訟が増
加することになる。というのは、組み合わせるための「動機付け」が果たして存在するの
かどうかという点についての争いが誘発されるからである。 本判決は、このような経緯、背景のもので、全米で、そして恐らくは全世界的な注目の
もとで、下されたものである。 本件の審理に当たり、連邦最高裁判所が取り組んでいた論点としては、狭義のものとし
ては「クレームに係る組合せをなすための具体的な動機付けがない場合に、特許は無効で
ある(或いは、特許出願は拒絶される)とすることができるか」というものであり、より
広義のものとしては「要素の組合せに係るクレームにおいて、各要素がそれぞれの要素と
して既知の機能しか果たしていない場合に、かかる『組合せ』特許は有効(或いは特許出
願は登録適格性を有する)といえるのか」、「あらゆるものは『組合せ』ではないのか」と
いうものであった。 本判決でも言及される Graham v. Deere テストでは次のような判示がなされている。
「1952 年法は、Hotchkiss v. Greenwood 事件判決の原則…を包含する判決例を成文化する
ことを意図してなされたものである。」「特許性を維持するために必要な進歩の一般的水準

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
22
は、同じものにとどまっている。」「議会は、公有財産領域から現存の知識を除去し、或い
はすでに利用可能な素材に対する自由なアクセスを制限するという効果しかもたらさない
特許の発行を正当と認めることができない。」 Graham v. Deere 事件の自明性テストとは、(1)従来技術の範囲および内容; (2) いわゆる
当業者の技量水準; (3) 権利請求に係る発明および従来技術の教示事項の違い; (4)非自明性
についてのあらゆる客観的証拠の程度または、例えば商業的成功、模倣行為、他者の失敗...といった二次的考察事項、といった点を明示したものであった。 これら二つの判例法を受け、連邦巡回控訴裁判所が非自明性の判断基準として「TSM テ
スト(教示―示唆―動機付けテスト)」を打ち立てこれに沿って幾多の係争についての審理
を行い、これを受ける形で合衆国特許商標庁での特許付与基準(第 103 条充足性判断基準)
にまでなってきていたものであった。 本判決では、TSM テストが不適当といっているのではないことにまず注意したい。本最
高裁判決が繰り返し言明しているのは、連邦巡回控訴裁判所の「厳格なアプローチ」、すな
わち、非自明性を否定する側(特許性を否定する側)は、クレームに係る組合せをなすた
めの具体的な動機付けが存在することを証明できない限り特許性付与を否定できない、と
する程度まで、厳格・制限的に TSM テストを運用するアプローチは、否定されねばならな
い、ということである。TSM テストそのものを積極的に否定していない文脈から読めるの
は、結局、日本で言う要件事実論の立証責任の転換に似ていると考えられる。 すなわち、これまでは、非自明性(日本でいう進歩性に対応すると思われる)を否定す
る場合、合衆国の審査官は、prima facie case of obviousness(一見して自明性を推認でき
るとする程度の事実に基づく立論)を打ち立てねばならないとされてきた。これが打ち立
てられないときには、「疑わしきは罰せず」ではないが、疑わしくとも特許を付与せねばな
らない。同じような考え方は日本国特許法第 51 条にもある。すなわち、「審査官は、特許
出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならな
い。」とされる。たとえ審査官が自分独自でどんなに疑わしい感じを抱いたとしても、拒絶
の理由を立証できないときには特許を付与しなければならない。これは後知恵の弊害にさ
らされる危険を常に有している出願人・権利者の不利を救う趣旨とも理解できる。ここで
の問題は、では、いかなる事実が、この「拒絶の理由」を形成する事実となり得るものか、
ということである。 連邦巡回控訴裁判所は、これを極めて厳格に、すなわち特許権者にとって有利なように
解釈し、クレームに係る組合せを具体的に教示、示唆、或いは動機付ける先行技術等の事
実が積極的に存在していない限りは「拒絶の理由」は形成されない、としてきたものであ
る。たとえば具体的に、あるクレームの構成要件が、A、B、C、D、E を具備する X とい
うもので、A、B、C、D、が先行技術 Y に開示され、E が先行技術 Z に開示されていたも
のとしよう。連邦巡回控訴裁判所のこれまでの厳格アプローチでは、単にこの Y、Z の開示
事項が存在することを示すだけでは自明性を立証したことにならない。「A、B、C、D」+

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
23
「E」の「+」(組み合わせること)が教示され、示唆され、或いは動機付けられることが
積極的に証明されねばならない。この「積極的証明」とは、先行技術文献中に記載されて
いること、業界における技術常識であること、業界・市場でのニーズが存在すること、な
どが事実として証明されることを意味するものとして、これまでは理解されてきたもので
ある。たとえば、これまでの連邦巡回控訴裁判所の事件を紐解けば、この「教示」に包含
できるものとして、先行技術中の代替物の提示(In re Fulton)等、「教示」に包含できな
いものとされてきたのが、組合せが提示されてはいるものの動作不可能なこと(Tec Air, Inc. v. Denso Manufacturing Michigan Inc.)、先行技術が実施可能でないこと(In re Kumar)等があり、「示唆」に包含できるものとして、トレンド(In re Gartside)、「示唆」に包含
できないものとされてきたのが、先行技術同士が一般的関係のみ有すること(In re Alhamad)、高レベルの技量(In re Rouffet)、旧来もしくは公知の要素が別の問題を解決
するものであること(Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. American Hoist & Derrick Co.)、先行技術要素が関連性を有しない分野からのものであること(In re Oeticker)等が
ある。また、「動機付け」に包含できるものとして、取り組んでいる課題自体が動機付けを
与えていること(In re Greene)等、「動機付け」に包含できないものとされてきたのが、
第一の先行技術が第二の先行技術との組合せに反することを教示していること(In re Rudko)、単なるトレード・オフ(Winner International Royalty Corp v. Wang)、良識も
しくは常識(In re Lee)等がある。 今回の判決によって、これらの中の「厳格なアプローチ」が否定された。ということは、
特許についての自明性は今後、より認定が柔軟になされる可能性が高まったことになる。
ただ、「厳格」なアプローチでないものを否定してはいないので、これまでの判例法のうち、
非自明性を否定してきた論拠は失われるものではなく、「教示」「示唆」「動機付け」に含ま
れないと(厳格に)解されてきたものの一部について、判断を修正することが必要となる
ものであろう。 我々実務家、特に合衆国において権利取得・活用する場面に携わる者は、これまでの諸
判例から、どういう場合なら特許性が肯定的に推認され、どういう場合なら否かを推量し、
可能な範囲で現実的指針を抽出してきたわけであるが、今回の判決によって、少なくとも
合衆国における特許戦略には一定の修正が必要となるものと考える。ただし、冒頭に述べ
たように、TSM テストそのものが否定されたわけではなく、「厳格な」アプローチが否定さ
れたわけである。何が「厳格」で何が「厳格とはいえない」のかについては、必ずしも判
断基準が明示されてはおらず、今後この判断について争いが生ずることにもなろうが、次
の判示文言にこのための手がかりを見出すことの可能なように思える。 ①「たしかに、Graham 事件判決は「統一的かつ明確な」ものの必要性を認めたものである。 ・・・ しか
し、Graham 事件判決で提示された原則は、Hotchkiss 判例法・・・の「機能的アプローチ」を再確認した
ものである。・・・Graham 事件判決は幅広い審理を示した上で、裁判所が必要に応じて、有益性があ
ろうと考える二次的考察事項があればいかなるものにでも眼を向けることを奨励するものであった。」

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
24
②「従来技術中に見出される要素の組合せに基づく特許を付与する際に注意が必要である点に関して、
当裁判所が以前から発している指令事項は、第 103 条の立法によろうとも Graham 事件判決の分析
によろうとも、妨げられるものではない。半世紀以上にわたり、裁判所は、『旧来の諸要素を結び付け
ているのみでそれぞれの機能に関しては何の変更もない組合せに対して与えられる特許は、…すでに
既知のものを市場独占の領域に引き込み、熟練者の利用できる資源を減らしてしまうものであることは
明らかである』と判示してきた。 ・・・これが、自明なものに対して特許を付与することを拒否する主要な
理由である。ありふれた要素を既知の方法に従って組み合わせるものは、それが予測可能な結果を生
むにすぎない場合、自明であるとされる可能性が高い。」
③「連邦巡回控訴裁判所が、白紙状態で書き込みを行うペダル設計者であれば、Asano 特許と、
Chevrolet のトラック群で用いられ'068 特許中に開示されるのと類似するモジュール式センサとの両者
を選択していたであろうといえるであろうか、との問いを実質的に発したことは、本論点についての考察
としては狭きに過ぎるものである。・・・尋ねるべきであった本当の問いは、通常の技量を持ったペダル
設計者であれば、本目的対象分野における開発によって生み出された広範囲のニーズに直面した場
合に、センサを用いて Asano 特許に改良を加えるということに利点を見出したであろうかどうかというこ
とであった。」
④「・・・進歩は、一旦我々の共有知識の一部となるとすぐに、再度の革新の出発点を画する新たな閾
値を規定するものとなる。より高いレベルの到達物を出発点とする進歩が期待されることが通常となる
のにつれて、通常的革新の成果は特許法制に規定される独占権の対象にはなじまないものとな
る。・・・こういった前提があって、自明な対象を権利請求する特許を禁ずる思想が導かれ、これが
Hotchkiss 事件判例法で樹立され、第 103 条中に成文化されたものなのである。この禁止条項の適用
は、その本来の趣旨を全うできないほど拘束的なテスト・・・、制限的なものであってはならない。」 更に、実務上の指針を打ち立てるには、本件の詳細な分析を踏まえた上で今後の判例の
趨勢の観察が必要となるかもしれない。しかし、次の判示文言には少なくともそのヒント
が埋め込まれているように思える。 ①「特許のクレーム対象が、従来技術においてすでに知られている構造であってその 1 つの要素を当
該分野で公知の別の要素で単に置き換えるという変更を加えたにすぎないものである場合には、当該
組合せは予測可能な結果を生む以上のことをするものでなければならない・・・。従来技術が特定の公
知要素を組み合わせることと反することを教示する場合に、それらの組み合わせを行う手段であって
奏功するものの発見は、非自明となる可能性が高い・・・。」 ②「ある特許が『単に古い諸要素を並べ、その各要素が実行する機能がそれまでに当該要素が実行
するとして知られていた機能と同じであ』り、この種の配列から期待できるであろう以上のものを生み出
さない場合には、当該組合せは自明なものである・・・。」 ③「ある技術が用いられることで装置が改良され、しかもいわゆる当業者であれば、同じ方法により類
似の装置が改良されるであろうことを認識するだろうと考えられる場合には、当該技術を用いることは、
その実際の適用が当事者の技量を超えるものでない限り、自明となる。・・・裁判所は、当該改良が、
従来技術の諸要素についてのそれらの確立された方法による予測可能な利用を超えるものであるか

KSR v. TELEFLEX 判決翻訳及び評釈 070520
25
どうか、について問いを発しなければならない。」 ④「Teleflex が・・・提示する・・・Radcliffe 宣誓供述書・・・は、Asano 特許が、当該ペダルもしくはそれ
に類似するペダルを改良して現代エンジンと適合させることには合理性がない、といえるほどの何らか
の欠陥を有しているものであることを示唆するものではない。」 本件によってある部分の非自明性判断基準は組合せの教示、示唆、動機付けの存在を認
知する上での厳格性が緩和されるという効果を奏するものの、たとえば先行技術としての
成立性、発明者にとっての先行技術の利用可能性、二次的要素等、「組合せの教示、示唆、
動機付け」以外の非自明性判断要素について過去 200 年余りの判例法が培ってきたものは
その大部分がそのまま有効であると考えられる。 結論として、本件は合衆国の連邦巡回控訴裁判所の厳格アプローチ自体を否定した以上
でも以下でもないものであるが、非自明性判断全体に波及するのは必至であると思われる。
ある意味、合衆国でも、日本の特許庁によって採用されている考え方に結果的に近い判断
の方向にあるものと理解でき、日米に亘って事件に携わる実務家にとっては両者の乖離が
少なくなる意味においては好ましいともいえるが、権利者にとっては権利化、権利維持化
についての障害が一つ増えたような感じにも写るだろう。しかし、今回の直接の議論の対
象はあくまで、連邦巡回控訴裁判所の厳格なアプローチであって、それ以外のものを否定
したわけでもない。ましてや、日本の特許法制に近づけたという単純な理解は、これまで
の 200 年余りの蓄積の判例法をご破算にして考えるものであって、正鵠を得ていないだけ
でなく、合衆国で非自明性を肯定的に推認せしめるにあたっての有効な武器の構築から外
れることとなろう。たとえば、宣誓供述、反教示、prima facie case など、日本には必ずし
も存在しない要素でありながら、合衆国では往々にして効力を持った要素が依然として重
要性を失うものではないことを意識しておくべきであろう。 (2007.5.20)