化腐朽為神奇 環保酵素運用心得分享 · 指導製作神奇環保清潔酵素。 ... 4. 洗滌衣物:將酵素加上洗衣精,放 入洗衣機內清洗衣物;先將衣服稍
Izumi Art Laboratory Home pege J - 位階と服色衣服令のこと • 衣服令の変遷 –...
Transcript of Izumi Art Laboratory Home pege J - 位階と服色衣服令のこと • 衣服令の変遷 –...

位階と服色
• 160613 • S.Izumi

衣服令のこと • 衣服令の変遷
– 位階を冠や衣服の色によって差異を付ける制度(衣服令)は飛鳥時代から奈良時代にかけて幾度か変遷を経ている
• 推古十一年(604)聖徳太子の「冠位十二階制」 • 大化三年(647)「七色十三階制」 • 天智三年(664)「七色二六階制」 • 天武十四年(685)「四十八階制」 • 大宝元年(701) 『大宝律令』親王四階・諸王一四階・諸臣三十階の位階制度
– 「衣服令」は『大宝律令』で定まったとされるが、『大宝律令』は今日失われている
• 天平宝字元年(757)『養老律令』の「衣服令」 – 我々が確認できるものとしては、淳和天皇(在位823年~833年)が勅して『養老律令』の解釈に基準を設けるために撰述させた『令義解』(
りょうのぎげ)の「衣服令」によってである

聖徳太子の「冠位十二階制」
• 十二月戊辰朔壬申(604年1月11日)に、始て冠位を行う • 大徳(師説云今之四位)、小徳、大仁(五位)、小仁、大禮(六位)、小禮、大信(七位)、小信、大義(八位)、小義、大智(初位)、小智、あわせて十二階、並に、當色の絁(あしぎぬ)を以て、之を縫へり。
• 『日本書紀』巻二十二・推古十一年(604) • 徳・仁・礼・信・義・智をそれぞれ大小に分けて十二階制とした
– 五行の五常(仁・礼・信・義・智)に徳を加えた – 徳を紫とし、以下を五色(青・赤・黄・白・黒)としそれぞれ濃淡で大小に分けたとする説がある
• 江戸時代の国学者、谷川士清(たにかわことすが) – しかし、 『日本書紀』に色彩の記述はなく、「當色の絁を以て、之を縫へり」についてはわからない。谷川説には以下の疑問がある
• 徳を紫では、中国での至上の色が四位以下になる • 天皇の色と考えられる白が下位の役人の色となる

「七色十三階制」 • 大化三年(647年)、大化改新以後の新政府は「七色十三階制」を施行した – 「冠位十二階制」の徳・仁・礼・信・義・智を大小に分けて十二階制とするのをやめ、織・繍・紫・錦・青・黒という冠の材料や色で区別し、それぞれを大小に分け、最下位に建武の階を加えた
– 「冠位十二階制」が正四位以下の位階を定めていたのに対して、一位(正・従)、二位(正・従)、三位(正・従)を、それぞれ織・繍・紫とした。以下大錦が四位(正・従)、小錦が五位(正・従)、大青が六位(正・従)、小青が七位(正・従)、大黒が八位(正・従)、小黒が初位(正・従)、建武とした
– 服色は織冠と繍冠が深紫(こきむらさき)、紫冠が浅紫(あさきむらさき)、錦冠が真緋(あけ)、青冠が紺(ふかきはなた)、黒冠が緑、建武は指定がない橡色か栗色であったとの説がある
– 「七色一三階制」は「冠位十二階制」に従三位以上の冠位を加えた制度 – 紫の地位が高くなり、青・黒が下位に置かれる。また冠の色彩ではなく材料が重視されている

七色十三階制の服色
織冠・繍冠 深紫
紫冠 浅紫
錦冠 真緋
青冠 紺
#561649 #934872 #a40522 #2a4958
黒冠 緑
#45b482
建部 橡色・栗色
#2a282c http://www.japan-post.com/color/z3/all.php 以下のページを参考にした

「四十八階制」 • 天智三年(664)に「七色十三階制」は「七色二六階制」に変更
– 藤原鎌足の大織冠はこの制度による – 紺と緑に藍が使われた
• 冠位服色に関する制度は天武十四年(685)「四十八階制」に大きく変更された – 「七色二六階制」の大織から小紫までを正位、大錦(上)から小錦(下)までを直位、大山を勤位、小山を務位、大乙を追位、小乙を進位とし、それぞれを細分化し四十八階とした
– 冠位名を正・直・勤・務・追・進という官僚に期待される徳目に変更 • 使われた色彩
– 親王以上が浄位とされて朱華(はねず) – 正位が深紫 – 直位が浅紫 – 勤位が深緑 – 務位が浅緑 – 追位が深葡萄(ふかえび) – 進位が浅葡萄(あさえび)
• 葡萄色とは葡萄葛の実で染めたもので、暗い灰赤紫の色彩を呈する
• 壬申の乱 天武元年( 672)

四十八階制の服色
正位 深紫
直位 浅紫
浄位 朱華
務位 浅緑
#561649 #934872 #f88459
#7bbc85
勤位 深緑
#016149
追位 深葡萄
#7d333a
進位 浅葡萄
#cf6870 http://www.japan-post.com/color/z3/all.php以下のページを参考にした

正位 浅紫
直位 深緋
浄位(一位・二位) 深紫
務位 浅緑
#561649 #934872 #f88459
#7bbc85
勤位 深緑
#016149
追位 深縹
#2a4968
進位 浅縹
#90b0c5
明位 朱華
浄位(三位・四位) 深紫
#561649
#ab1e1c
四十八階制の『浄御原令』による変更 持統四年(689)
http://www.japan-post.com/color/z3/all.php以下のページを参考にした

『養老律令』の「衣服令」
• 『大宝律令』(701)の位階制度 – 親王四階・諸王一四階・諸臣三十階の位階制度が採用 – 一世紀におよんだ冠位制は廃止された – 『大宝律令』は「律」も「令」も全て失われている
• 『養老律令』(757) – 『大宝律令』を引き継いだ天平宝字元年『養老律令』(757)では「律」の大部分が失われている
– 「令」は『令義解』によって復元できる
• 「衣服令」 – 皇太子の礼服、親王の礼服、諸王の礼服、諸臣の礼服、朝服、制服、内親王の礼服、内命婦の礼服、朝服(女子)、制服(女子)、武
官の礼服、朝服(武官)、制服(武官)よりなり、それぞれの位階
の服色を定めている

• 皇太子の礼服 – 礼服の冠 – 黄丹(おうに)の衣 – 牙笏(げのこつ) – 白き袴 – 白き帯 – 深紫の紗の褶(ひらみ) – 錦の襪(しとうず) – 烏皮(くりかわ)のくつ。
– 礼服の冠を着用する。袍(束帯や衣冠などの時に着る盤領〈まるえり〉の上衣)は位色の黄丹とする。象牙で作った笏を持つ。白い袴、白い帯を着ける。深紫色の紗(生糸で織目を荒く織った薄布)の褶(礼服の袴の上に付ける付属具)、錦(金銀糸を用いて文様を織り出した紋織物)の足袋を着用する。牛革製で黒漆塗の沓を履く。

皇太子の礼服
黄丹の衣 #ef5e1b
烏皮のくつ
襪(しとうず)
白い袴
深紫の紗の褶 #592c63
濱田信義編『日本の伝統色』パイ・インターナショナル、2011と http://www.japan-post.com/color/z3/all.phpの資料を参考にした

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Crown_Prince_Akihito_%26_Michiko_Shoda_Wedding_1959-4.jpg/ 1280px-Crown_Prince_Akihito_%26_Michiko_Shoda_Wedding_1959-4.jpg
今上天皇ご成婚時

• 親王の礼服 – 一品は礼服の冠
• 四品以上は品毎に各別制有り – 深紫(こきむらさき)の衣 – 牙笏 – 白き袴 – 絛(くみ)の帯 – 深緑(こきみどり)の紗の褶 – 錦の襪 – 烏皮のくつ – 綬玉珮(しゅこうはい)を佩へ。
– 一品は礼服の冠を着用する。二品から四品は各位について別に定めた冠を着用する決まりがある。袍は位色の深紫とする。象牙の笏を持つ。白い袴、格子状の平組の帯を付ける。深緑の紗の褶、錦の足袋を着用する。牛革製で黒漆塗の沓を履く。官職を示す印を組紐の帯に付け身に佩びる。

親王の礼服
深紫の衣 #592c63
玉佩 白い袴
深緑の紗の褶 #016149
濱田信義編『日本の伝統色』パイ・インターナショナル、2011と http://www.japan-post.com/color/z3/all.phpの資料を参考にした
『神宮神宝図録』神宮徴古館農業館、2009

• 諸王の礼服 – 一位は礼服の冠 – 五位以上、位及び階毎に各別制有り。諸臣も此に准れ(なぞれ) – 深紫の衣 – 牙笏 – 白き袴 – 絛の帯 – 深緑の紗の褶 – 錦の襪 – 烏皮の鞜 – 二位以下、五位以上は並浅紫(あさきむらさき)の衣。以外は並一位の服に同じ
– 五位以上は綬を佩へ – 三位以上は玉佩を加えよ。諸臣も此に准れ – 一位は礼服の冠を着用する。二位から五位は各位について別に定めた冠を着用する決まりがある。一位は袍は位色の深紫とする。象牙の笏を持つ。白い袴、格子状の平組の帯を着ける。深緑の紗の褶、錦の足袋を着用する。牛革製で黒漆塗の沓を履く。二位以下、五位以上の袍は等しく位色の浅紫とする。それ以外はみな一位の定めるところと同じものを着用する。五位以上四位以下は綬(飾り紐)を佩びる。三位以上は玉佩(即位・朝賀の大儀に、天皇をはじめ王臣が礼服に付けた飾り。)を佩びる。

諸王の礼服
深紫の衣
白い袴
深緑の紗の褶
浅紫の衣 #934872
白い袴
深緑の紗の褶
一位 二位から五位
濱田信義編『日本の伝統色』パイ・インターナショナル、2011と http://www.japan-post.com/color/z3/all.phpの資料を参考にした

• 諸臣の礼服 – 一位は礼服の冠 – 深紫の衣 – 牙笏 – 白き袴 – 絛の帯 – 深縹(こきはなた)の褶 – 錦の襪 – 烏皮のくつ – 三位以上は浅紫の衣 – 四位は深緋(こきあけ)の衣 – 五位は浅緋(あさきあけ)の衣 – 以外は並一位の服に同じ。大祀大嘗元旦に之に則り服せよ。
– 一位は礼服の冠を着用し、袍は位色の深紫とする。象牙の笏を持つ。白い袴、格子状の平組の帯を着ける。深縹の紗の褶、錦の足袋を着用する。牛革製で黒漆塗の沓を履く。二位以下、三位以上の袍は位色の浅紫とする。四位の袍は位色の深緋とする。五位の袍は位色の浅緋とする。それ以外はみな一位の定めるところと同じものを着用する。大祀(一ヵ月間潔斎して行う重要な祭祀)、大嘗祭、元旦にはこの規則に則った服装にしなさい。

諸臣の礼服
深紫の衣
白い袴
深縹の褶 #2a4968
浅紫の衣 #934872
白い袴
深縹の褶
一位 二位から三位
白い袴
深縹の褶
白い袴
深縹の褶
四位 五位
深緋の衣 #ab1e1c
浅緋の衣 #cc543b
濱田信義編『日本の伝統色』パイ・インターナショナル、2011と http://www.japan-post.com/color/z3/all.phpの資料を参考にした

• 朝服 – 一品以下、五位以上は、並皀(くり)の羅の頭巾(ときん)衣の色は礼服に同じ
– 牙笏 – 白き袴 – 金銀(こし)装(つくり)の腰帯 – 白き襪 – 烏皮の履 – 六位は深き緑の衣 – 七位は浅き緑の衣 – 八位は深き縹の衣 – 初位は浅き縹(はなた)の衣 – 並皀の縵(かとり)の頭巾。木笏。烏油(くろつくり)の腰帯。白き袴。白き襪。烏皮の履。袋は服色に従へ。
– 親王の一品以下、諸臣の五位以上は皆薄い絹で出来た黒い頭巾を着ける。親王の一品以下、諸臣の五位以上の袍の色は礼服と同じとする。一品以下五位以上は象牙の笏を持ち、白い袴、金糸銀糸で飾りを施した帯、白い足袋、黒い革製の履物を着用する。六位の袍の色は深緑とする。七位の袍の色は浅緑とする。八位の袍の色は深縹とする。初位の袍の色は浅縹とする。六位以下初位以上は無地の黒い頭巾、木の笏、黒い帯、白い袴、白い足袋、黒い革製の履物を着用する。袋は服色に準じる。

朝服に示される六位から初衣の服色
深緑の衣 #016149
白い袴
浅緑の衣 #7bbc85
白い袴
六位 七位
白い袴 白い袴
八位 初位
深縹の衣 浅縹の衣 #90b0c5
濱田信義編『日本の伝統色』パイ・インターナショナル、2011と http://www.japan-post.com/color/z3/all.phpの資料を参考にした

• 制服 – 无位は皆皀の縵の頭巾 – 黄の袍 – 烏油の腰帯 – 白き襪 – 皮の履 – 朝庭の公事に之に則り服せよ – 尋常には通して草鞋を着を得 – 家人、奴婢は橡墨(つるはみすみそめ)の衣
– 無位のものは無地の黒い頭巾、袍の色は黄色とし、黒い帯、白い足袋、革製の履物を着けて、朝廷の公の行事用の服装とする。普通は草履を履くことができる。家人や奴婢は橡墨の服を着る。

「衣服令」における色彩序列 • 位階の色彩序列 – 黄丹、紫、緋、緑、縹、黄、黒
– 皇太子の「黄丹」を別にすれば、最上位の色彩は紫であり、その下に赤、青(緑を含む)、黄、と続き、最下層の色が黒である
濱田信義編『日本の伝統色』パイ・インターナショナル、2011と http://www.japan-post.com/color/z3/all.phpの資料を参考にした

古代の色彩 • 大化三年の「七色一三階制」のころまで
– 深紫と浅紫は紫草の根 – 真緋は茜草の根 – 紺は月草の花の汁 – 緑は苅安草(かりやすそう)と月草の組み合わせ – 黒は橡色であり、「どんぐり」のかさを煮た汁で染めた
• 前田雨城『色染と色彩』、法政大学出版局、1980 • 天智三年の「七色二六階制」
– 紺と緑に藍が使用されるようになった • 「衣服令」の当時使われた色彩の染料
– 康保四年(九六七年)に施行された『延喜式』巻十四「縫殿寮 雑染用度」 を参考にすることが出来る
• 国史大系編修会編『国史大系 延喜式 中編』、吉川弘文館、1987

古代の色彩 • 『延喜式』「縫殿寮 雑染用度」で使われた染料 • 黄櫨(こうろ) 、紫草、紅花、支子(くちなし)、茜、蘇芳、搗橡(つるばみ) 、苅安草、藍 – 黄櫨は櫨(はぜのき)の樹皮から染料を採取されるが、実は木蝋を採るために使われる
– 紫草は染料であるとともに、根は紫色、乾燥したものを生薬の紫根といい、解毒剤・皮膚病薬とする
– 紅花は薬草でもあった – 支子は梔子であり、乾した果実は生薬の山梔子として吐血・利尿剤である – 茜は根から染料を採り、また生薬名を茜根といい、通経薬・止血薬である – 蘇芳は明礬媒染で赤色、灰汁で赤紫、鉄媒染では紫色に染めることができる – 搗橡は櫟(くぬぎ)から取られたもので、その実を黒染料として用いる。また樹皮や葉は薬用に供する
• 染料の多くが薬草であることが注目される

その後の位階色彩序列 • 律令体制における位階の色彩序列は11世紀初頭に最終的に定まりその位階序列が明治まで続くこととなった
天皇
黄櫨染 #7d532c
皇太子
黄丹 #ef5e1b
親王四品以上 諸王一位 諸臣一位
黒袍 #261d1c
諸王五位以上 諸臣三位以上
黒袍 #261d1c
諸臣四位
黒袍 #261d1c
蘇芳 #8e354b
縹 #006285
諸臣五位 諸臣六位
縹 #006285
諸臣七位
縹 #006285
諸臣八位
縹 #006285
諸臣初位
浅黄 #edef6d
無品親王・無官位
濱田信義編『日本の伝統色』パイ・インターナショナル、2011と http://www.japan-post.com/color/z3/all.phpの資料を参考にした

黄櫨染御袍をお召の天皇陛下
http://18yesno.up.n.seesaa.net/18yesno/b5974034.jpg?d=a1

黄櫨染御袍裂 東京国立博物館
http://image.tnm.jp/image/1024/C0007836.jpg

黄櫨
http://morinokakera.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/20101116-鹿をも殺す苦木の黄色③.JPG

黄丹資料
http://www.root168.com/product/upfile/2402.jpg
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kobo-tensho/cabinet/tokyoku_2013/13to-sh126_t1.jpg

紫草とその根 資料
http://www.root168.com/product/upfile/2402.jpg
http://www.remedy-garden.co.jp/blog/wp-content/uploads/2013/12/20131202-232240.jpg

紅花と紅花染め 資料
http://www.yrit.pref.yamagata.jp/seeds/img/beni1.jpg
http://kobe.travel.coocan.jp/photo/nishiharima/urabe_benibana/benibana_009.jpg

蘇芳 資料
http://www.wahuku.com/goods_image/A1091_Z1.jpg
http://vigo-cajon.sakura.ne.jp/sblo_files/mublog/image/DSCN0368.JPG

襲色目

襲色目(かさねいろめ)
• 平安時代末期 – 末法として意識された文化的な乱世、将来にたいする不安から自然の恵への信頼、生命の蘇りなど、サイクルの定まった自然の風物が愛された
– そこで草木のもつ季節的な色彩変化をもとにした配色の組み合わせが好まれた
• 襲色目とは – 服装の表地と裏地の色の配色や、重ねて着る衣服の色の配列のこと
– 襲色目の色彩は、染料となる植物や四季の風物などの自然観が反映されている
– 衣服のみならず打敷や懐紙、組紐、鎧の威毛(おどしげ)などにまで適用された

「満佐須計装束抄」(まさすけしょうぞくしょう)
• 仮名文による平安装束の有職故実 – 平安時代末期に成立 – 作者は源雅亮 – 平安時代後期の宮中の行事に展開する調度・装束の慣例が書かれている
• 「女房の装束の色」の項における襲色目には以下の項目がある – 春夏秋冬のいろいろ。祝いに着るいろいろ – 十月一日より、練衣(ねりきぬ)わたいれて着る – 五せちより春まで着るいろ – 四月うすぎぬにきるいろ – 五月ひねりがさね(五月捻重ね) – 六月よりのひとえがさね(単重ね) – 七月七日より着がえする – 八月一日より十五日まで。ひねりがさね

http://www.kokusaibunka.com/12_emon/meta/2011_emon_junihitoe.jpg

女房の装束の色
• 春夏秋冬のいろいろ。祝いに着るいろいろ • すおうのにおい(蘇芳の匂い)
• 「うえは淡くて。したざまに濃く匂いて。あおきひとえ。」 – 女房の衣装は、通常五枚重ねて着る。この「うえ」は一番外側の衣装のことで、下になるほど濃い蘇芳色という意味である。「におい」というのは、淡色より濃色へ、または濃色より次第に淡色へと重ねて着る様式である。単は青緑色である。
上 下

• まつがさね(松重ね) • 「うえ二つ蘇芳の濃き淡き。萌黄(もえぎ)の匂いたる三。くれないの単。」 – 衣装の一番上に濃い蘇芳、二番目には淡い蘇芳、三番、四番、五番と内側にむかって萌黄色が淡色より次第に濃色になる
。その下に着る単は「くれない」色ということ。

• しろぎつねのことなり • 「蘇芳の匂い。白絹に、はじこきうちを重ぬべきなり。」
– 蘇芳の匂いは濃中淡の三枚、「はじ」は色彩名である。はじこきうちと読めば、はじ色に濃く染めた物である。

• くれないのにおい(紅の匂い) • 「うえくれないを着て。したに淡く匂いて。紅梅のひとえ。」
– 一番上に「くれない色」を着て、二番三番と内側になるほど「くれない色」を次第に淡くする。単の色目の紅梅は、はっきりしないが
多分、紫味のある赤色、つまり今の紅色とみられる。

• もえぎのにおい(萌黄の匂い) • 「うえは淡くして。したへ濃く匂いて。くれないのひとえ。」
– 五枚の衣装の色が、すべて萌黄、つまり黄緑色で、上が淡い萌黄で下になるほど濃くなっているもの。単は「くれない色」。

• 十月一日より、練衣(ねりきぬ)わたいれて着る • 菊のようよう(菊の様々)
• 「おもてはみなすおうの匂い。うらみなしろし。あおひとえ。」 – 表は、一番上に蘇芳、二番より五番まで次第に淡くなる。裏はみな、白である。単は青緑色。

• くれないもみじ(紅もみじ) • 「くれない。やまぶき。きなる。あおき。濃き淡きくれないのひとえ。」 – くれない」は濃いピンク色、山吹は、少し赤味をもった黄色で、夏みかんの色とレモンの色の中間色。「きなる」は黄色で、今のレモン色、少し青味をもつ黄色。「あおき」は青緑 。

• 五せちより春まで着るいろ • 五せちは五節である。五節(ごせち)とは平安時代に、毎年十一月中の丑・寅・卯・辰の四日間、朝廷で行なわれた年中行事のことである。それで、五せちより春まで着るいろというのは十一月の半ばごろから春までの色のこと。現在の十二月ごろとすれば合う。
• むらさきのうすよう(紫の薄様) • 「うえよりしたへ、うすくて三。しろき二。しろきひとえ。」
– 上より下へ、紫を次第に淡くして三枚、その下に白を二枚の五つの衣装をきる。単は白である。

• やまぶきのにおい(山吹の匂い) • 「うえこくて。したへ、黄なまで匂いて。あおきひとえ。」 – 一番上は濃い山吹で、次第に下にうすくして黄になるまでする。単は青緑色。

• うめがさね(梅重ね) • 「うえしろき、こうばい匂いて。くれない一。こき蘇芳。こきひとえ。あおきひとえも心心なり。」 – 上は白く淡い紅梅、そして淡い紅梅、紅梅色と次第に濃くして三枚。くれない一枚。濃蘇芳一枚、合わせて五枚の衣装。単は深紫色と定められてはいるが、青緑色を使ってもよい。

• ゆきのした(雪の下) • 「しろき二。こうばい匂いて三。あおきひとえ。」
– 白い衣装二枚、紅梅の濃、中、淡色三枚合わせて五枚の衣装で、単は青緑色。

• むらさきむらご(紫村濃) • 「むらさき匂いて三。あおき、こきうすき二。くれないのひとえ。」 – 濃い紫より下へ、次第に淡く三枚、青緑色の濃色一枚、淡色一枚あわせて五枚の衣装。単は「くれない色」。

• ふたつのいろに(二つの色に) • 「うすいろ二。うらやまぶき二。もえぎ二。くれないのひとえがさね。」 – 薄紫の衣装を二枚重ね、裏地を山吹とする。その下に黄緑色を二枚着る。単も「くれない」を二枚重ねて着る。

• いろいろ • 「うすいろ一。もえぎ一。こうばい一。うらやまぶき一。うらこきすおう一。くれないのひとえ。」

• 四月うすぎぬにきるい • 初夏の装束の色目
• わかしょうぶ(若菖蒲) • 「おもてあおき、こきうすき三。ふたつは裏しろし。しろおもて二。裏、紅梅の匂三。しろきのすずしのひとえ。」 – 五枚の衣装の上より、表が濃い青緑で裏が白のもの一枚、表が中の青緑で裏が白を一枚、表が淡い青緑で裏が濃い紅梅、四枚目は、表が白で、裏が中の紅梅、五枚目が、表が白で裏が淡い紅梅である。単は白色の「すずし」。

• ふじ(藤) • 「うすいろの匂いて三。しろおもて二が。うらあおき。こきうすき。しろきすずしのひとえ。又くれないのすずしのひとえ。」 – 上より、表裏とも、薄紫を次第に淡くして三枚、あと二枚はともに表は白。裏は一枚を青緑の濃色とし、一枚を淡色とする。単は白い「す
ずし」か、または「くれない」のすずし。

• つつじ(躑躅) • 「くれない匂いて三。あおきこきうすき二。ひとえしろき、くれない。こころごころなり。」 – 「くれない」の濃中淡の三枚、青緑の濃淡のあわせて五枚の衣装。ひとえものは、白でも、「くれない」でも自由。

• 花たちばな(花橘) • 「やまぶきこきうすき二。しろき一。あおきこきうすき。しろひとえ。あおひとえ」 – 山吹の濃淡二枚、白一枚、青緑の濃淡で二枚。単は、白色または青緑のもの。

• うのはな(卯の花) • 「おもて、みな白くて、うらしろき二。きなる一。あおきこきうすき二。うらしろきひとえ。」 – 衣装の表絹は、すべて白である。うらは上より、白二枚、黄、濃青緑、淡青緑の順に五種である。単は白色である。

• なでしこ(撫子) • 「おもては蘇芳匂いて三。しろおもて二。うら蘇芳。くれない。紅梅。あおき濃き淡き。しろき。くれないのひとえなり。」
– 衣装の表絹は、蘇芳が上から下に三枚薄くなる。その下に白二枚、裏地は蘇芳、紅、紅梅、青緑の濃淡で、白か紅の単衣なる。

• ぼうたん(牡丹) • 「おもてはみな淡き蘇芳。裏みな白し。すずしのひとえ」

• もちつつじ(餅躑躅) • 「すおう三において。あおきこきうすき。しろきひとえ」
– 上より蘇芳で濃中淡と三枚。青緑で濃淡二枚、あわせて五枚の衣装。単は白色。

• かきつばた(杜若) • 「うすいろ匂いて三。あおきこきうすき。くれないのひとえ。」 – 薄紫を次第に淡くして三枚、青緑の濃淡で二枚、単は「くれない」。

• 五月ひねりがさね(五月捻重ね) • 梅雨期であるため、今までの中より選びだして再度用立てしているもの。ひねり出したもの
• 省略 • 六月よりのひとえがさね(単重ね)
• 例えば蘇芳と白のひとえを重ねて着るもので薄着である • 省略
• 七月七日より着がえする • はぎ、うすいろにあおたて、したに、あおきかさね。
– 淡い紫色の糸と青緑色の糸で織った織物を着て、下に青緑色の単を重ねる。
• おみなえし、きなるあおたて、したにあおきかさね。 – 「おみなえし」とは、黄色の糸と青緑色の糸で織った織物でその単を着て、したに
青緑色の単を重ねる。
• この二つは「織色」のこと • 省略

• 八月一日より十五日まで。ひねりがさね • すすき
• 「蘇芳のこきうすき三。あおきこきうすき。しろきひとえ。」 – 蘇芳を次第に淡くして三枚、青緑の濃淡で二枚、単は白。

蘇芳の匂い?
http://www.miyabi-yuki.jp/ contents/upload-images/ 2013815163141.jpg

牡丹?
http://kaluxa.net/ wp-content/uploads/ MG_5759.jpg

五衣・唐衣・裳十二単 昭和3年 賀陽宮敏子妃着用
http://shiyukai.bunka.ac.jp/wp-content/uploads/2013/09/五衣・唐衣・裳十二単 昭和3年 賀陽宮敏子妃着用.jpg
松重ね

襲色目 • 襲色目には室町時代に成立した「曇花院殿装束抄」もある。
• 著者は聖秀尼宮とされ室町時代後期の女性である。 • 特徴は五枚+単衣に上着を加え、上着+五枚+単衣で表記されている。
• 重ねの色目には永生3年(1506年) に成立した「女官飾鈔」がある。
• 例 「曇花院殿装束抄」くれないのうす様

襲色目の影響 • 仁清「藤図茶壺」から
• 藤花図茶壺は、白地に赤、薄紫、金、銀で花を描き、薄緑で葉が描かれている
• 「藤」の襲色目 • 「うすいろのにほひて三しろおもて二がうらあをきこきうすきしろきすずしのひとへ又くれなゐのすずしのひとへ、」(古事類苑 服飾部十六)
• 藤図茶壺の色彩 • 花は銀彩などによる濃淡と赤があり、「薄紫の濃淡」と「くれない」である
• 葉の色は青緑 • 地色は白
• 「藤図茶壺」には襲色目の影響を見ることができる

藤図茶壺 熱海 MOA美術館
石川県立美術館編 『野々村仁清展』 図録、1992

枕草子
• 淑景舎春宮にまいり給ふほどの事などの段 • 中宮定子の衣裳についての記述
– 「紅梅の固紋、浮紋の御衣どもに、紅のうちたる御衣、三重がうへに唯引き重ねて奉りたるに、『 紅梅には濃き衣こそをかしけれ。今は紅梅は着でもありぬべし。されど萌黄などの
にくければ。紅にはあはぬなり 』との給はすれど、唯いとめ
でたく見えさせ給ふ。奉りたる御衣に、やがて御容のにほひ
合せ給ふぞ、なほことよき人も、かくやおはしますらんとぞ
ゆかしき。」

参考文献 • 濱田信義編『日本の伝統色』パイ・インターナショナル、2011 • 『神宮神宝図録』神宮徴古館農業館、2009 • 『古事類苑明治43年版 服飾部』 吉川弘文館、1979 • 前田雨城『色[染と色彩]ものと人間の文化史38』法政大学出版局、
1980 • 長崎盛輝『かさねの色目』青幻社、2006 • 吉岡幸雄『日本の色辞典』紫紅社、2000 • 石川県立美術館編『野々村仁清展』図録、1992


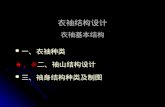







![Title [論文]潜在的な身体としての衣服 --「痙攣的な …...41 潜在的な身体としての衣服 「痙攣的な美」の分析を通じて 蘆田裕史 はじめに](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5e5861bdb3fbe6703a79dded/title-eoeoeceeoe-oecc-41-oeoeceeoe.jpg)








