高齢者見守りネットワーク構築 取り組み · 特集 高齢者見守りネットワーク構築の取り組み 特集1 見守りネットワーク構築の現状と課題
(⼀財)⽇本建設情報総合センター研究助成事業 地域防災教育の … ·...
Transcript of (⼀財)⽇本建設情報総合センター研究助成事業 地域防災教育の … ·...

(⼀財)⽇本建設情報総合センター研究助成事業
地域防災教育のための VR 技術に基づく⽔害疑似体験システム
の構築
最終報告書
平成 30 年 8 ⽉

1
⽬次 1.はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.⽔害疑似体験システムの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2.1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2.2 対象地域の地形・構造物のモデリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 2.3 ⽔害シミュレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 2.4 全天球動画の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 3.VR システムの利⽤例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 4.おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
謝辞 参考⽂献

2
1.はじめに
近年,わが国では⼤規模な⾃然災害が頻発しており,⾃然災害による⼈的被害を最⼩限に抑えることは急務な課題である.津波や地震などによる⼤規模災害では,ハード的な対策には限界があり,早期避難などのソフト的な対策が重要である.各⾃治体では,ハザードマップ等の整備が進められているが,⼀般住⺠の防災に対する意識はそれ程向上しているとは⾔えない.その理由の⼀つに,それらの防災情報からは,⾃然現象の発⽣から災害に進展していく過程を容易に把握することが困難なため⼀般住⺠が災害現象をイメージできない,という点が挙げられる.近年では、この問題点を解決するために、⾃然災害に対する正しい理解と防災意識の向上を⽬的として,従来の最⼤浸⽔深を表⽰する静的なハザードマップに代わり、津波被害の進展状況が理解できる動的なハザードマップについても作成・公開が⾏われている.また,近年ではバーチャルリアリティ(以後 VR)技術の発展・普及により⾼品質な⽴体 CG 映像による可視化も⾏われるようになっている. 著者らはこれまで,没⼊型 VR 装置およびヘッドマウントディスプレイ(以後 HMD)を⽤いた津波や洪⽔などの⽔害体験システムの構築を⾏ってきた 1)〜4).このシステムは利⽤者が VR 空間を⾃由に移動しての対話的な体験が可能であるが,使⽤上においてそれぞれに以下に述べる問題点があった.没⼊型 VR 装置は,フルスケールで臨場感の⾼い体験が可能であるが,外部に持ち出しての使⽤は困難である.⼀⽅,HMD は外部に容易に持ち出せるものの,複数⼈が同時に体験することは困難である.
そこで,著者らは,近年普及の著しいスマートデバイスに着⽬して,利⽤者⾃⾝のスマートフォンを利⽤できる津波体験システムの構築を⾏った.本システムにより、利⽤者は, 直感的に将来計画や各種の⽔害に対する安全性, 浸⽔の時間変化,避難経路等の確認を⾏うことができるため、住⺠の防災意識向上に⼤いに貢献することが期待される.なお,システムの構築には映像や⾳のリアルタイム処理が可能な Unity5)を⽤いた. 2.⽔害疑似体験システムの構築 21.システム概要 本研究は,住⺠の防災意識向上の促進を⽬的として,⼈的被害の⼤きい⽔害(特に津波、洪⽔)に焦点を絞り,実際の都市・地域環境を忠実に再現したモデルを作成した上で,⾃然災害の発⽣・進⾏過程を物理モデルに基づく⾼精度なシミュレーション⼿法により再現し,仮想現実(VR)技術を⽤いて 3 次元 CG により映像化した計算結果を⽴体表⽰させることで,災害を疑似体験可能なシステムの構築を⾏うものである。
本システムでは、図-1 左に⽰すようなスマートフォン単体で VR 可視化を⾏えるが,図-1 右に⽰す安価なスマートフォン挿⼊型 HMD に装着することで⽴体映像による可視化が可能となり,より臨場感の⾼い VR 体験も可能となる.

3
. 図-1 スマートフォン(左)と挿⼊型 HMD(右)
構築した津波体験システムは,1)対象地域の地形・構造物のモデリング,2)津波のシミュレーション,3)1)および2)の結果を⽤いて VR 可視化を⾏う位置での全天球動画の作成,という 3 つのプロセスを経ることにより構築される。以下に、各プロセスについてその概要を述べる。なお,対象地域は⾼知県中⼟佐町久礼地区を取り上げた。 2.2 対象地域の地形・構造物のモデリング 本研究では,GIS/CAD/ドローンにより取得したデータを⽤いて⾼精度な 3 次元都市・地域モデルを作成する⼿法を構築した。本⼿法の特徴は,モデリング領域を低解像度の⼤領域(地形モデル),中解像度の中領域(植⽣・構造物モデル),⾼解像度の⼩領域(構造物モデル)に分け,それぞれ別々の⽅法でモデル化を⾏う点にある.具体的には,図-2 に⽰すように,⼤領域の地形モデルには GIS データを,中領域の植⽣・構造物モデルにはドローンによる空撮データを、⼩領域の構造物モデルには3D モデリングソフトを⽤いてモデル化を⾏った(図-2 参照).そして,作成したモデルを Unity により編集および可視化を⾏うため,FBX 形式に変換して,モデルの統合を⾏った.以下に,モデリングの⽅法について⽰す.
図-2 地形・構造物のモデリング⼿法

4
地形モデルのモデル化には,GIS データとして国⼟地理院発⾏の数値標⾼ 5m メッシュを⽤いる。そして,GIS ソフトを⽤いて作成された地形モデルの表⾯上に、⾼解像度の衛星写真データを張り付ける.
また,建物などのモデリングについては3D モデリングソフトウェアを⽤いる.その際,避難所(図 3 参照)などのランドマーク的な重要構造物についてはハイエンドな3D モデリングソフトウェア(3ds Max)を⽤い,⺠家などのモデリングについて,簡易な3D モデリングソフトウェア(Google SketchUP)を⽤いた.なお,現実感を⾼めるために,建物モデルの壁⾯にはデジカメで撮影した画像の貼り付けを⾏った.図-4 は対象地域の街中のモデル(左)と実際(右)を⽰している。図より,街並のモデリングは⽐較的正確に⾏われていることが分かる。
図-2 衛星写真の貼り付け 図-3 構造物の CAD モデル
図-4 街中のモデル(左)と実際(下)
⼀⽅,砂浜や樹⽊群などの⾮⼈⼯物のモデル化については,3D モデリングソフトの使
⽤は適さない.また,可視化において重要でない地域のモデル化を3D モデリングソフトを⽤いることは効率的ではない.本研究では,それらの領域においては,図-5 に⽰すドローンを⽤いて撮影した画像データを SfM(Structure from Motion)/MVS(Multi View Stereo)技術に基づくソフト(Agisoft Photo Scan)を⽤いてモデル化を⾏った(図-6 参照).そし

5
て,別々の⼿法で作成したモデルデータを FBX データに変換して,Unity 上で統合することで,図-7 に⽰すような対象地域の再現性の⾼いモデル作成が可能となる 6).
図-5 使⽤したドローン 図-6 ドローンによるデータを⽤いたモデル化
図-7 地形・構造物モデルとの統合
2.3 ⽔害シミュレーション ⽔害シミュレーションの例として津波シミュレーションを取り上げる.前節で作成した地形モデルを⽤いて,任意形状への適合性に優れる安定化有限要素法による津波シミュレーション 7)を実施した。なお,⽀配⽅程式には浅⽔⻑波⽅程式を⽤いた. 図-8 にシミュレーションに使⽤した中⼟佐町周辺の地形モデルを⽰す.また,津波シミュレーションは太平洋の関東から九州までの沖合を含む領域に対して,三⾓形要素に基づく⾮構造格⼦を⽤いて要素分割を⾏った.計算の初期条件としては,中央防災会議南海トラフの巨⼤地震モデル検討会で検討されたケース 4(「四国沖」に「⼤すべり域+超⼤すべり域」を設定)8)を⽤いた.図-9 に津波が遡上している様⼦を⽰す.

6
図-8 中⼟佐町周辺の地形モデル
図-9 津波が遡上していく様⼦
津波のシミュレーション結果の可視化に際しては,任意の時間間隔(本例題では 1 秒間
隔)で出⼒した結果をデータ変換して Unity 内へ格納し,連続的に表⽰を⾏う(図-10 参照).なお,津波体験の臨場感を向上させるために,津波の迫る⾳を滝の⾳を⽤いて疑似的に再現した.津波の疑似⾳源は,津波の遡上に合わせて移動するよう⽔際線に設定し,移動に伴うドップラー効果や⾳が三次元的に拡がるよう機能拡張を⾏った.図-11 に沖合からの可視化映像を⽰す.

7
図-10 Unity による可視化
図-11 可視化映像の例
2.3 全天球動画の作成
中⼟佐町に点在する避難所位置からの津波体験が可能となるように,各避難所で指定した視点からの津波を再現した全天球 VR 動画を作成した.全天球動画の作成には,Unity のアセット(VR Panorama)を⽤いた.なお,画質及びフレームレートはそれぞれ 4K・30FPS に設定した.図-12 に,作成した全天球動画のキャプチャ画像を⽰す.

8
図-12 全天球動画のキャプチャ画像
3.VRシステムの利⽤例 利⽤者が各⾃のスマートフォンを⽤いて中⼟佐町に点在する避難所位置からの津波体験が可能となるように,図-13 に⽰す対象地域の VR 体験避難所マップの作製を⾏った.この VR 避難所マップは、利⽤者が地図上の避難所ごとに表⽰されている QR コードを読み込むことで,その避難所の視点から津波が来襲する様⼦を,YouTube アプリを⽤いて津波のVR 動画が閲覧可能となる。
図-13 VR 体験避難所マップ

9
図-14 VR システムの使⽤⽅法
図-14 に本 VR システムの使⽤⽅法を⽰す.利⽤者は,まずスマートフォンのカメラアプリで,QRコードをスキャンする(ステップ1:図-15 参照).次に,画⾯に表⽰された URLをタッチすることにより指定した避難所位置での VR 動画が再⽣される(ステップ 2:図-16 参照).なお,スマートフォンに搭載のジャイロセンサーにより,視点の⾓度を⾃由に変更しての可視化が可能となる.そして,Cardboard マークをタッチすることにより,図-15に⽰す⽴体視モードの動画に切り替わり,図-1 に⽰すスマートフォン挿⼊型 HMD を⽤いることにより,⽴体 VR 映像が閲覧できる(図-17 参照)(ステップ3).
図-15 マップ上の QR コードをスキャン

10
図-16 動画を閲覧している様⼦
図-17 ⽴体視モードの動画表⽰
4.おわりに
本研究では,地域防災教育のためのVR技術に基づく⽔害疑似体験システムの構築研究を⾏った。都市・地域のモデリングに対しては,GIS/CAD/ドローンにより取得したデータを⽤いて⾼精度な 3 次元都市・地域モデルを作成し,Unity 上で編集可能な⼿法を構築した。また,⽔害現象の可視化においては,Unity を⽤いて可視化を⾏うシステムを構築した。Unity に基づく可視化をシステムにより,様々な可視化デバイスへの投影が可能となった。それらの成果を踏まえて特に,近年普及が著しいスマートフォンに着⽬して,津波体験システムの構築を⾏った.
本システムは,利⽤者が⼿持ちのスマートフォンを⽤いて⼿軽に津波体験ができるため,住⺠の津波災害に対する理解度や防災意識の向上および各⾃治体や学校等での防災教育等に有⽤なツールとなることが期待される.

11
謝辞:本研究は,(⼀財)⽇本建設情報総合センターの平成 28 年度研究助成⾦の⽀援を受けた.ここに記して感謝いたします。 参考⽂献 1) 樫⼭和男,⽔害シミュレーションにおける VR 技術の適⽤,JACIC 情報,103 号,pp.28-32, 2011. 2) 川辺赳史,樫⼭和男,宮地英⽣,岩塚雄⼤,古牧⼤樹,⻄畑剛,可聴化技術を⽤いた津波疑似体験システムの構築,⼟⽊学会論⽂集 F3(⼟⽊情報学),Vol.70,No.2,pp.I_235-I_242,2014. 3)岩塚雄⼤,古牧⼤樹,⻄畑剛,川辺赳史,樫⼭和男,地域防災教育のための3次元津波浸⽔解析とその可視化に関する研究,⼟⽊学会論⽂集 F3(⼟⽊情報学), Vol.70, No.2, pp.I_152-I_159, 2014. 4)http://www.civil.chuo-u.ac.jp/lab/keisan/VR_mini_museum/newpage1.html 5) Jonathan Linowes(⾼橋憲⼀、安藤幸央、江川 崇、あんどうやすし訳),Unity によるVR アプリケーション開発,オライリー・ジャパン,2016. 6)利根川⼤介,樫⼭和男,安定化有限要素法による津波遡上および流体⼒の解析⼿法の構築,応⽤⼒学論⽂集,⼟⽊学会,Vol.12, 127-134,2009. 7) 呉奥圖,野坂創⼀,緒⽅正剛,⼤川博史,樫⼭和男,ドローンによる空撮データを⽤いた⾼精細都市モデルの構築,第 45 回⼟⽊学会関東⽀部技術研究発表会講演概要集,I-20, 2018. 8)野坂創⼀,⾦澤功樹,呉奥圖,⼤川博史,緒⽅正剛,樫⼭和男,スマートデバイスを⽤いた VR 津波防災教育⽀援システムの構築,第 45 回⼟⽊学会関東⽀部技術研究発表講演概要集 I-7,2018 9) 樫⼭和男、⼤川博史、野坂創⼀,⾼精度 3 次元モデルによる VR 体験防災⽀援システム,第 75 回⼟⽊学会全国⼤会学術講演概要集,I-20, 2018. 10) 樫⼭和男,スマートデバイスを⽤いた津波体験システムの構築,JACIC 情報,118号,pp.44-47,2018.


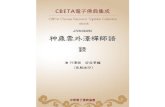
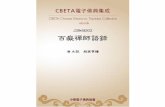
![JB430 玉泉其白富禪師語錄 - CBETAarchive.cbeta.org/download/download.php?file=pdf_ipad/J/JB430.pdf · 法語 ⽰融默監寺 ⽰秀雲禪⼈ ... ⽰[王*崇]睿悅眾 ⽰琳睿侍者](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f441354518049691132a9a3/jb430-ccoeceeoe-e-aeec-aceca-acccoe.jpg)














