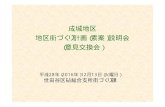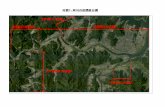社会的状況 - Hiroshima...3.2-1 3.2 社会的状況 3.2.1 人 口 事業計画地周辺の行政区である中区、東区、南区及び西区の面積、世帯数及び人口
(2)校区まちづくり協議会意見交換会の開催 ·...
Transcript of (2)校区まちづくり協議会意見交換会の開催 ·...

資料-21
(2)校区まちづくり協議会意見交換会の開催
地域ごとの子ども・子育て支援活動の把握やそれに伴う課題の抽出を目的として、校区
まちづくり協議会を対象とした意見交換会を開催しました。意見交換会では、7~8月に
実施した地域別ワークショップ等で抽出された「課題」や「地域としてできること」の意見を
参考資料として提供したうえで、各校区での活動内容や、今後の子育て支援充実への課題
や意見、解決策について、活発な意見交換が行われました。
<開催状況>
平成 26年 10月 16日(木) 八尾市文化会館
<意見の概要>
●地域の子育て支援活動状況等
多くの地域で声掛け運動や通学路の安全パトロールなどの見守り活動を実施している。
(実施にあたって学校との協力を図っている地域もあり)
校区まち協、その他地域の団体が連携し、子どもたちも参加して防災訓練を実施している。
民生・児童委員の子育て支援活動「はとぽっぽ」を月 1 回開催し、七夕やクリスマスのイベント
を実施。地域子育て支援センターの保育士からも協力を得ている。また、住民懇談会でも子どもを
テーマとした講演会等も実施している。
子育て中の保護者が集まる取り組みとして、子育てサロンやつどいの広場なども実施している。
放課後子ども教室等により、地域の大人と子どもが関わる取り組みを実施している。
(親子ものづくり、寒中登山、各種スポーツ教室、伝承ものづくり教室、コーラス、地域の工場見
学、宿題など)
子どもたちのイベントとして、えだまめ収穫祭、缶けりや竹馬などのむかし遊びを実施している。
その他、ふれあいまつり、こども祭りを開催し、こども祭りでは子どもが模擬店の手伝いをしてく
れた。
学校と地域がタッグを組んで、先生も参加するイベント等を実施している。
(年 4 回の会議の開催、グランドゴルフ用具の購入による実施等)
こども会では、青少年指導員やPTAなど地域の方々との連携のもと、工夫をしながら取り組みを
すすめている。
こども会を再編し、つなひきクラブをつくり活動している。
小学生と高齢クラブの方々が一緒に給食を食べるなど、各種世代間交流を実施している。
(その他、もちつき大会、ビンゴゲーム、高齢クラブによる昔遊びなど)
子どもたちも参加する川の清掃活動を実施した後に、清掃後の川で金魚のつかみどりを実施。
父親が多く参加することを期待したが、父親の参加は少なかった。
小学生を対象にした「まちをきれいに」をテーマとした標語の募集を実施して、採用作品は「のぼ
り」を作り地域内にて掲示する。(約 100 名の募集あり、最終的に 10 点の採用が決定した)
子育て支援の活動を実施するにあたって、地域のつどいの広場と連携をとり、子どもの意見の抽出
に努めている。
校門前の朝の挨拶運動の実施や朝のラジオ体操へ子ども達を誘うなどの活動を実施している。朝の
挨拶運動では子ども達と接点がもてるよう、声のかけ方に工夫を凝らすなどを心がけている。

資料-22
●今後の子育て支援充実への課題・意見、解決策について
こども会の加入率減少は地域共通の課題であり、根本的な原因を突き止め解決する必要がある。
こども会の活動活性化に向け、こども会とジュニア会の活動をうまく活用し、年上の子どもが年下
の子どもの面倒を見るような仕組みをつくる必要がある。
まちづくり、コミュニティ形成には、子どもだけでなく、保護者を巻きこむことが必要。そのため
には、こども会の加入数を増やして行く取り組みをしていく必要がある。
こども会活動が低下しており、全体的な取り組みを考えていく必要がある。青少年指導員やPTA
などの若い力が地域の活動を積極的に実施しており、これをこども会加入促進につなげたい。
子ども・子育ての関連活動を行うにあたり、スタッフの人材不足・高齢化が課題。地域活動のスタ
ッフを確保しようにも、地域によって人口の問題もあり対応に限界がある。
地域活動を行うスタッフを確保するため、地域の各種団体への働きかけにより人材確保をめざす。
親子イベント開催の際に保護者への積極的な声かけを行い、地域の活動への参加を促すべきだ。
若い世代が仕事中心になっていることから、今後は若い保護者を巻きこんだり、高校生や大学生な
どが積極的に手を挙げてほしいと思っている。
子どもたちが外で遊ぶ場所がないと言われており、集会所の前庭を子どもたちに開放していきた
い。
校区内に集会所がないため子どもの居場所がなく、学校の近くに一か所は必要である。
新たにこども会を立ち上げる手法として、福祉委員会でこども会の運営を支援し、保護者の負担を
軽減する取り組みが行われる地域もある。
子どもオリンピック等のイベント実施にあたり、こども会に加入していなくても参加できるなどの
対応をとっている。
(3)八尾市PTA協議会代表者交流会の開催
校区まちづくり協議会での意見交換会に加え、9月の八尾市PTA協議会の代表者交流
会においても、「子どもたちの自主性や主体性を育むために~PTAと学校・地域・行政と
ともにできること~」をテーマとして意見交換会を実施し、テーマに対する数多くの意見
をいただきました。
<開催状況>
平成 26年9月 18日(木) 八尾市役所
<意見の概要>
・地域との交流を増やし、子どもも大人も住みよいまちづくりをしていかなければならな
い。
・PTAでの活動に加え、地域での活動を行うということに、負担を感じることがある。
・子どもを主体として、子ども・学校・行政・地域がうまくバランスをとる仕組みがなけ
れば、PTA役員の担い手が少ないという課題がある中、PTAの存続に支障をきたす
可能性がある。

資料-23
3.中学生・高校生グループインタビューの実施
<開催状況>
日 時 : 平成 26年8月 31日(日) 八尾市役所
参加者 : 中学生7名(女性3名、男性4名)、高校生6名(女性5名、男性1名)
<意見の概要>
中学生 高校生
放課後・
休日の過
ごし方
<放課後・休日の過ごし方やよく行く場所について>
・放課後は学校でクラブ活動をしており、友
達と遊ぶことは少ない。
・休日もクラブ活動や塾にいっている。
・休日はテレビを見るなど、家で過ごしたり、
家族と出かけたりすることが多い。
・八尾市はあまり遊びに行くところがないの
で、休日は友達とショッピングセンターや
映画に行くことはある。
<放課後・休日の過ごし方やよく行く場所について>
・部活動をしたり、家で過ごすことが多い。
・休みのときは家で過ごすことが多い。
・他に行くところがなく、ショッピングセン
ターに行く人が多い。
・図書館に勉強に行く人も多い。
・ちょっと遊びに行くときは、自転車で行け
る範囲(自転車で 30 分くらい)のところ
になる。大阪までは交通費もかかるのであ
まり行かない。
居場所
<今後ほしい場所について>
・近所に小さい公園はあるが、小学生までの
小さい子どもが遊んでいるため遊べない。
・大きい公園は少なく場所が限られる。中規
模のちょっとした広場があれば集まりや
すい。
・遠くの公園まで皆で行くことができないた
め、大きくなくてもよいので、ボール遊び
ができる場所がほしい。
・予約などが必要ではなく、自由に使えるサ
ッカーやバスケットボールのコートを増
やしてほしい。小学生以下と中学生以上で
分けて使えるコートなど、安全面に配慮す
れば、いろいろな年代の子どもが安全に利
用できるのではないか。
<気軽にいられる居場所>
・公園内に屋根とベンチがある場所はある
が、小さい子どもと母親や、小学生が使っ
ているので、平日と休日ともに使えない。
・女子同士で話すときは、暑いときや雨のと
きでも使えるように屋根とベンチがある
だけでも過ごしやすい。
<今後ほしい場所について>
・友達と外でキックベースをすると、周囲か
ら「うるさいからやめろ」と言われたこと
がある。そのためもっと大きな屋外のグラ
ウンドや公園がほしい。

資料-24
中学生 高校生
職業体験
将来の仕
事に向け
て
<職業体験について>
・2年生の時に職場体験に2日間行ったが、
とても良い経験だったし、満足している。
もっと他にも体験できる機会や長い期間
できる場などがあればよい。
・職場体験の他に、どのような職業があるの
か知らないので、いろいろな職業の人から
話を聞く機会があれば、ぜひ行ってみた
い。(小中学校で、実際に仕事に就いてい
る人から仕事について聞く機会はなかっ
た。)
・キッザニアのようなところが近くにあれ
ば、利用したい。また、中学生になって改
めてキッザニアのようなところに行けば、
小学生の時とは違った観点で職業体験が
できる。
<将来の希望について>
・将来就きたい職業については、ドラマを見
て参考にした。
・実際にその仕事に就いている人を見て興味
をもち、その職業になりたいと思った。
・小学校の理科の授業をきっかけに技術に興
味を持ち、現在はシステムエンジニアの仕
事に就きたいと考えている。
・親の意見を聞いたりして職業を考えてい
る。
・まだ将来なりたいものはないので、これか
らゆっくり考える。
<職業体験について>
・中学生の時の職場体験で、将来の職業を具
体的に考えることができた。
<将来の希望について>
・将来希望する職業に就くため、大学に進学
したい。
・まだ具体的に夢が決まっていないので、と
りあえず大学に進学したい。
・学校の進路相談があるが、資料がない大学
もあり、具体的な情報があまりない。
・希望する職業の人に話を聞く人もいるが、
インターネットで調べている人もいる。

資料-25
中学生 高校生
八尾市の
好きなと
ころ、嫌
いなとこ
ろ
<八尾市で自慢できるものについて>
・学校からの帰り道で、田んぼと住宅街が見
えるが、そこに見える夕日は都会にはない
ほどきれいだと思う。
・八尾市の空はきれいである。自然が好きな
ので、自然が多少なりとも残っているのが
よい。
・八尾空港が好き。
・子どもにとって自慢になるようなものを知
らない。
<八尾市への希望、不満>
・学校の友達に八尾のことを聞かれるが、ど
のように説明してよいか分からない。
・もっと有名になってほしい。
・東京タワーのように、何か日本一になれる
ような1つの魅力的なシンボルがほしい。
・八尾空港が好きなため、航空ショーなど全
国の人々が参加できるようなイベントが
あれば、「八尾にいってみよう」というき
っかけになると思う。
・お笑い芸人が公演できるようなイベント会
場がほしい。
・学校にクーラーをつけてほしい。
・塾を増やしてほしい。
・自然はあるが場所が偏っているので、街路
樹を増やすなどもっと緑化してほしい。
・自転車を利用する人が多く、道路の段差解
消や車道と自転車道を分けてほしい。
<八尾市で自慢できるものについて>
・玉串川の桜並木がきれい。
・近鉄電車の準急が停まるため交通が便利。
・農産物で枝豆が有名。
<八尾市の希望、不満>
・中学生・高校生向けのボランティアを企画
して募集してほしい。これを定期的に続け
れば、「ボランティアの八尾市」として有
名になれると思う。
・保育士になりたいので、子どもと関われる
ボランティアがあれば参加したい。
・近隣のおじいちゃん、おばあちゃんに、話
しながら歩いているだけで「声が大きい。
もう少し静かにしてくれ」と注意されるこ
とがある。もう少し理解してほしい。
今後も八
尾に住み
続けたい
か
<住み続けたい:3人/7人中>
・八尾市というよりも、今住んでいる場所が
好き。
<住み続けたくない:4人/7人中>
・八尾市も災害には強いと思うが、都会にも
出てみたいし、もっと田舎にも行ってみた
い。
・東京などの大都会には興味はないが、大阪
市くらいなら住んでみたい。
・八尾市は帰省して「空がきれい」など懐か
しむ場所であるほうがよいと思う。
・新しいところに行きたい。
<住み続けたい:2人/6人中>
・現在過ごしにくいと思ったことがないの
で、嫌いではない。
・住み慣れているので、今後も住み続けたい。
・駅やスーパー、ショッピングセンターが近
く便利なので住み続けたい。
<住み続けたくない:4人/6人中>
・もっと田舎のほうに行きたい。八尾市は建
物ばかりのため、もっと自然環境が豊かな
ところに住みたい。
・騒音がうるさいので、住みたくない。道路
を暴走バイクが4~5台くらい通るとう
るさく、テレビも聞こえなくなる。
・できるだけ早く八尾市から東京に行って、
将来アナウンサーになりたい。

資料-26
4.子育て世帯へのアンケート調査の実施
<平成 24 年度(2012 年度)アンケート調査>
(調査の目的)
現計画の保育サービス量の見直しを行うため、保育ニーズ等を把握し、保育サービス
量の推計のための基礎資料とするため、アンケート調査を実施しました。
(調査対象者、実施方法)
対象 対象者 発送・回収方法 調査時期
就学前児保護者
市内に居住する平成 18年4月2日以
降に生まれた児童をもつ保護者
2,000 名を無作為に抽出
郵送発送・郵送回収
平成 24 年
9月6日
~18 日
就学児保護者
市内に居住する平成 12年4月2日~
平成 18年4月1日に生まれた児童を
もつ保護者 1,000 名を無作為に抽出
小学生本人
(4~6年生)
上記、就学児と同じ
(保護者の調査票と一緒に小学生本人
の調査票を配布)
<平成 25 年度(2013 年度)アンケート調査>
(調査の目的)
子ども・子育て支援事業計画策定のための基礎資料とするため、アンケート調査を実
施しました。
(調査対象者、実施方法)
対象 対象者 発送・回収方法 調査時期
保育所利用者 市内に居住する、市内保育所の利用者
利用している各施設を
通じて配布・回収
平成 25年
12 月 13 日
~24日
幼稚園利用者 市内に居住する、市内幼稚園の利用者
認可外保育所
利用者
市内に居住する、市内認可外保育所の
利用者
子育て支援事業
利用者
市内に居住する方で、調査期間中に子
育て支援事業を利用された就学前のお
子さんのいる方
利用している施設を
通じて配布・回収
(一部郵送にて回収)
健診受診者
市内に居住する方で、調査期間中に健
康診査を受診された就学前のお子さん
のいる方
健診受診時に配布、
郵送にて回収
※調査結果の詳細については、八尾市のホームページで公開しています。
八尾市保育サービスに関するアンケート調査結果(平成 24 年度(2012 年度)実施)
http://www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000021/21828/enquete.pdf
八尾市保育サービスや子育て支援に関するアンケート調査結果(平成 25 年度(2013 年度)実施)
http://www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000026/26877/enquete.pdf

資料-27
Ⅱ. 八尾の子育てを取り巻く現状

資料-28
1.人 口 ・世 帯 の状 況
(1)総人口・世帯数の推移と将来推計
住民基本台帳によれば、本市の人口は平成 26年(2014年)では 269,759人であり、
微減傾向が続いています。一方、世帯数については増加傾向で推移しており、平成 26
年(2014年)では 120,369世帯となっています。また、1世帯当たりの平均人員数は
減少傾向にあり、平成 26年(2014年)では 2.24人/世帯となっています。
計画期間中の総人口の将来推計については微減傾向にあり、平成 31 年(2019 年)
では 260,000人と見込まれます。
図 1 総人口・世帯数の推移(各年 4月 1日)
資料:住民基本台帳、八尾市総合計画人口推計
272,469 272,024 271,505 271,066 270,029 269,759 267,000 265,000 264,000 262,000 260,000
116,786 117,973 119,023 120,090 119,544 120,369
273,292
115,976
2.242.332.362.382.412.442.47
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
平成20年
(2008年)
平成21年
(2009年)
平成22年
(2010年)
平成23年
(2011年)
平成24年
(2012年)
平成25年
(2013年)
平成26年
(2014年)
平成27年
(2015年)
平成28年
(2016年)
平成29年
(2017年)
平成30年
(2018年)
平成31年
(2019年)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
総人口 世帯数 1世帯当たりの人員
(人) (人/世帯)
実績値 ← → 推計値

資料-29
(2)年齢4区分別人口の推移と将来推計
本市の人口を0~5歳と6~14 歳(年少人口)、15~64 歳(生産年齢人口)、65 歳
以上(高齢人口)の年齢4区分でみると、その構成比は、年少人口割合は減少する一
方で、高齢人口割合は増加しており、平成 26年(2014年)には、年少人口割合が 13.3%、
高齢人口割合が 25.8%と年少人口が高齢人口の約半数の割合となっています。
今後の推計をみても、年少人口割合が減少し続け、平成 31年(2019年)では 12.2%
と見込まれます。
図 2 年齢4区分別人口の推移(各年 4月 1日)
資料:住民基本台帳、こども未来部こども政策課推計
注:住民基本台帳による推計
12 .2%12 .4%12 .6%12 .8%
14 .3% 14 .2% 14 .1% 13 .9% 13 .7% 13 .5% 13 .3% 13 .0%
28.1%27.9%27.6%27.2%
21.0%
21.9%22.6% 23.0%
23.7%24.8%
25.8%
26.5%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
平成20年
(2008年)
平成21年
(2009年)
平成22年
(2010年)
平成23年
(2011年)
平成24年
(2012年)
平成25年
(2013年)
平成26年
(2014年)
平成27年
(2015年)
平成28年
(2016年)
平成29年
(2017年)
平成30年
(2018年)
平成31年
(2019年)
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0~5歳 6~14歳 15~64歳 65歳以上 15歳未満が占める割合
65歳以上が占める割合
(人)
実績値 ← → 推計値

資料-30
(3)計画対象人口の推移と将来推計
本市の計画対象人口の内訳をみると、0~5歳、6~11 歳は年々減少傾向にあり、
平成 26年(2014年)では、0~5歳が 13,197人、6~11歳が 14,441人、12~17歳
が 16,553人となっています。特に0~5歳の減少が大きくなっています。
また、今後の計画対象の人口の推計をみても年々減少し続け、平成 31年(2019年)
では0~5歳が 11,640 人、6~11 歳が 13,381 人、12~17 歳が 14,794 人と見込まれ
ます。
図 3 計画対象人口の推移(各年 4月 1日)
資料:こども未来部こども政策課推計
注:住民基本台帳による推計
14,566 14,230 13,966 13,654 13,520 13,360 13,197 12,787 12,533 12,186 11,934 11,640
16,546 16,343 16,043 15,625 15,230 14,800 14,441 14,218 13,967 13,755 13,549 13,381
15,940 16,116 16,306 16,485 16,637 16,606 16,553 16,339 16,034 15,645 15,206 14,794
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
平成20年
(2008年)
平成21年
(2009年)
平成22年
(2010年)
平成23年
(2011年)
平成24年
(2012年)
平成25年
(2013年)
平成26年
(2014年)
平成27年
(2015年)
平成28年
(2016年)
平成29年
(2017年)
平成30年
(2018年)
平成31年
(2019年)
0~5歳 6~11歳 12~17歳
(人)
47 ,052 46 ,689 46 ,315 45 ,764 45 ,387 44 ,76644 ,191 43 ,344 42 ,534 41 ,586
40 ,689 39 ,815
実績値 ← → 推計値

資料-31
(4)子どもの人数
18歳未満の子どもについては、就学前、小学生とも「2人」の割合が半数前後と最
も高くなっていますが、就学前では、次いで「1人」が 29.0%、小学生では、次いで
「3人」が 25.9%となっています。
図 4 18歳未満の子どもの人数
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
(5)子どものいる世帯数
平成 22 年(2010 年)の国勢調査によれば、本市の一般世帯(総世帯数から施設等
の世帯を除いたもの)である 108,585 世帯のうち、18 歳未満の子どものいる世帯は
25,420 世帯で、全体の 23.4%となっています。そのうちの約 80%が核家族となって
います。
図 5 世帯の家族類型
資料:国勢調査
29.0
15.2
46.8
53.7
17.8
25.9
3.7
5.1 0.2
2.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
就学前
小学生
1人 2人 3人 4人以上 無回答
87.5
80.1
63.0
4.0
8.5
5.7
6.9 4.5
32.0
2.1 2.9
2.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳未満世帯員のいる一般世帯
18歳未満世帯員のいる一般世帯
一般世帯
核家族 ひとり親 三世代 その他の世帯

資料-32
図 6 (参考)対象者の世帯の家族類型
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)、「次世代育成
支援に関するニーズ調査」(平成 21 年(2009 年)1 月実施)
85.9
88.0
74.9
77.7
8.8
7.7
12.0
12.8
2.9
8.4
3.1
1.4
1.9
1.7
1.5
1.7
0.5
1.2
3.2
4.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
就学前児童がいる世帯
(H24)
就学前児童がいる世帯
(H20)
小学生児童がいる世帯
(H24)
小学生児童がいる世帯
(H20)
一般世帯 三世代 一人親 その他 無回答

資料-33
2.人 口 動 態
(1)出生数・合計特殊出生率
本市の出生数は年々減少傾向にありましたが、平成 25年(2013年)の出生数は 2,081
人、合計特殊出生率は 1.33と前年を上回りました。
本市の合計特殊出生率は、全国、大阪府平均を下回って推移していましたが、平成
25年(2013年)に大阪府平均を上回りました。
図 7 出生数・合計特殊出生率の推移
資料:大阪府衛生年報 ※八尾市の合計特殊出生率は大阪府衛生年報データから独自に算出したもの
図 8 合計特殊出生率の比較
資料:人口動態統計、大阪府衛生年報
2,140 2,161 2,109 2,051 2,0812,274
1.25 1.221.27 1.28 1.27
1.33
0
1,000
2,000
3,000
平成20年
(2008年)
平成21年
(2009年)
平成22年
(2010年)
平成23年
(2011年)
平成24年
(2012年)
平成25年
(2013年)
0.00
0.50
1.00
1.50
出生数 合計特殊出生率
(人)
合
計
特
殊
出
生
率
出
生
数
1.251.22
1.271.28 1.27
1.33
1.28
1.28
1.33
1.301.31
1.32
1.37 1.371.39 1.39
1.41
1.43
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
平成20年
(2008年)
平成21年
(2009年)
平成22年
(2010年)
平成23年
(2011年)
平成24年
(2012年)
平成25年
(2013年)
八尾市
大阪府
全国

資料-34
(2)婚姻・離婚件数の推移
本市の婚姻件数は、平成 23 年度(2011 年度)まで減少を続けていましたが、平成
24年度(2012年度)から増加に転じ、平成 25年度(2013年度)は 1,335件となって
います。一方、離婚件数は平成 21年度(2009年度)をピークに減少していましたが、
近年はほぼ横ばいで推移し、平成 25年度(2013年度)は 587件となっています。
図 9 婚姻・離婚件数の推移
資料:八尾市統計書
1,290 1,2931,335
1,4551,403
1,205
663 675621 585 570 587
0
500
1,000
1,500
平成20年度
(2008年度)
平成21年度
(2009年度)
平成22年度
(2010年度)
平成23年度
(2011年度)
平成24年度
(2012年度)
平成25年度
(2013年度)
婚姻件数 離婚件数
(件)

資料-35
3.就 業 の状 況
(1)労働力人口
平成 22 年(2010 年)の国勢調査によれば、本市の労働力人口(15 歳以上就業者数
+失業者数)は 124,913人となっています。平成 17年(2005年)から平成 22年(2010
年)への変化をみると、男女ともに労働力人口は減少していますが、特に男性の労働
人口の減少が大きくなっています。
また、15歳以上人口に対する労働力人口の割合(労働力率)は、男性 68.2%、女性
43.2%となっています。
平成 17 年 平成 22 年
労働力人口 労働力人口 15 歳以上人口 労働力率
総数 132,642 124,913 226,594 55.1%
男 80,021 73,620 107,910 68.2%
女 52,621 51,293 118,684 43.2% 資料:国勢調査
(2)就業者数
平成 22年(2010年)の国勢調査によれば、本市在住の 15歳以上の就業者数は 115,123
人となっています。就業者数を産業部門別にみると、第1次産業 0.9%(1,004 人)、
第2次産業 29.1%(33,485人)、第3次産業 63.2%(72,718人)と、第3次産業の割
合が高くなっています。
図 10 産業別の就業者数の推移
資料:国勢調査
1,796 1,552 1,203 1,181 1,004
55,792 55,317 48,822
39,120 33,485
74,541 78,261 76,578
79,036
72,718
0
50,000
100,000
150,000
平成2年
(1990年)
平成7年
(1995年)
平成12年
(2000年)
平成17年
(2005年)
平成22年
(2010年)
第1次産業 第2次産業 第3次産業
(人)

資料-36
(3)両親の就労状況
ニーズ調査によると、平成 24年度(2012年度)調査では「専業主婦(夫)」は就学
前児童が 47.2%、就学児童 が 35.4%となっています。一方、「フルタイム×フルタイ
ム」、「フルタイム×パート」といったように両親が何らかの仕事についている人は、
就学前児童では 35.0%、就学児童では 43.8%となっています。平成 20年度(2008年
度)調査に比べて、就学前児童では、「専業主婦(夫)」が約 17ポイント減少している
一方で、「フルタイム×フルタイム」が約 7ポイント増加しています。
図 11 対象者の両親の就労状況(平成 24年度、平成 20年度)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)、「次世代育成支援に関するニーズ調査」(平成 21 年(2009 年)1 月実施)
図 12 (参考)母子家庭等の就労状況(就学前児童)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
4.8
1.4
11.4
3.1
21.3
14.6
15.6
17.7
13.5
15.6
27.8
35.1
47.2
64.1
35.4
35.8
11.9
0.4
0.4
0.2
0.2
0.8
1.0
0.7
0.7
5.2
0.0
2.6
0.0
0.8
8.6
1.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
就学前児童がいる世帯
(H24)
就学前児童がいる世帯
(H20)
小学生児童がいる世帯
(H24)
小学生児童がいる世帯
(H20)
ひとり親 フルタイム×フルタイム フルタイム×パート 専業主婦(夫)
パート×パート 無職 その他 無回答
フルタイムで就労
(産休・育休・介
護休業中は含ま
ない)
37.5%
フルタイム就労で
休業中(産休・育
休・介護休業)
0.0%
パートタイム、ア
ルバイト等で就
労
40.6%
不明
6.3%これまでに就労し
たことがない
3.1%
以前は就労して
いたが、現在は
就労していない
12.5%

資料-37
4.育 児 休 業 の取 得 状 況 や仕 事 や子 育 ての両 立 の状 況
(1)育児休業の取得状況
ニーズ調査によると、平成 24 年度(2012 年度)調査では育児休業を取得した(取
得中)の人は母親が 20.9%、父親が 1.0%となっています。一方、取得していないの
は母親が 12.7%、父親が 81.7%となっています。
図 13 育児休業の取得状況(就学前)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
(2)育児休業を取得していない理由
ニーズ調査によると、平成 24 年度(2012 年度)調査では、母親は「育児休業の制
度がなかった」をあげる人が 35.0%と最も高く、父親は「仕事が忙しかった」が 34.0%、
「配偶者が無職など、制度を利用する必要がなかった」が 33.6%と、高くなっていま
す。
図 14 育児休業を取得していない理由(就学前)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
62.9 20.9 12.7
81.7 16.4
0.8 1.0
3.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
母親
父親
働いていなかった 取得した(取得中である) 取得していない 無回答
16.4
0.0
7.1
0.0
0.0
35.0
16.4
34.0
22.1
11.9
29.8
33.6
21.312.1
5.7
17.9
7.9
7.9
6.2
2.9
1.2
6.0
4.0
28.3
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった
仕事が忙しかった
(産休後に)仕事に早く復帰したかった
仕事に戻るのが難しそうだった
昇給・昇格などが遅れそうだった
収入減となり、経済的に苦しくなる
保育所などに預けることができた
配偶者が育児休業制度を利用した
配偶者が無職など、制度を利用する必要がなかった
最初から制度を利用することを考えていなかった
育児休業の制度がなかった
その他
母親
父親
(%)

資料-38
5.住 まいの状 況
(1)住まいの状況
平成 22年(2010年)の国勢調査によれば、住宅に住む一般世帯の居住の状況は、「持
ち家」が最も多く、64.1%となっています。次いで、「民営の借家」(27.1%)、「公営・
都市機構・公社の借家」(6.3%)となっています。
図 15 一般世帯の住まいの状況
資料:国勢調査
民営の借家
27.1%
持ち家
64.1%公営・都市機構・
公社の借家
6.3%
社宅・公務員住宅
など
1.5% 間借り
1.0%

資料-39
6.保 育 所 、幼 稚 園 の利 用 の状 況
(1)保育所
平成 25 年度(2013 年度)における本市の保育所は 34 か所(市立7か所、私立 27
か所)、入所児童数は 4,612人となっており、入所児童数はおおむね増加傾向にありま
す。
資料:こども未来部こども施設課
注:各年 4 月 1 日
(2)幼稚園
平成 25 年度(2013 年度)における本市の幼稚園は 26 か所(市立 19 か所、私立7
か所)、園児数は 3,084人となっています。
また、市立幼稚園への応募状況は減少傾向にあります。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
3歳児 私立 601人 641人 610人 566人
4歳児 市立 654人 634人 612人 585人
私立 658人 661人 668人 637人
5歳児 市立 820人 676人 655人 630人
私立 682人 646人 656人 666人
合計 3,415人 3,258人 3,201人 3,084人
市立幼稚園への応募状況
4歳児 647人 628人 596人 581人
資料:学校基本調査
注:各年5月 1 日
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
施設数
市立 7か所 7か所 7か所 7か所
私立 24か所 25か所 25か所 27か所
合計 31か所 32か所 32か所 34か所
定員
市立 870人 870人 870人 870人
私立 2,940人 3,100人 3,130人 3,290人
合計 3,810人 3,970人 4,000人 4,160人
入所児童数
市立 919人 898人 909人 915人
私立 3,183人 3,333人 3,457人 3,621人
他市委託 60人 65人 69人 76人
合計 4,162人 4,296人 4,435人 4,612人
待機児童数 81人 48人 75人 87人

資料-40
(3)年齢別保育の場所
平成 25 年度(2013 年度)における就学前児童の年齢別の保育の場所をみると、0
~2歳は在宅等で保育している人が多く、約 63~85%となっています。3歳では、保
育所や幼稚園の保育サービスを利用している人が約 65%となり、4歳、5歳では、大
半が保育所や幼稚園の保育サービスを利用しています。特に、4歳、5歳では、約半
数が幼稚園を利用しています。
図 16 年齢別の保育の場所(平成 25年度)
資料:こども未来部こども政策課、学校基本調査
(4)簡易保育施設
平成 25 年度(2013 年度)における簡易保育施設数は1か所、年間延べ斡旋児童数
は 193人となっています。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
年間延べ斡旋児童数 471人 441人 314人 193人
施設数 3か所 3か所 2か所 1か所
15.1
27.8
36.640.4 41.3 40.9
0.0
0.0
0.0
24.4
52.056.2
84.9
72.2
63.4
35.2
6.62.9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
在宅等
幼稚園
保育所

資料-41
7.子 育 て支 援 サービスの状 況
(1)延長保育
保護者の就労形態の多様化により、通常の保育時間帯を超える保育を必要とする児
童を延長して保育します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
実施数(公立) 7か所 7か所 7か所 7か所
実施数(私立) 25か所 26か所 27か所 29か所
実施数(合計) 32か所 33か所 34か所 36か所
(2)一時預かり
家庭で子育てする保護者の育児などの心理的・身体的負担や疾病・災害によって、
一時的に保育が必要となった家庭の就学前児童を、一時的に保育します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
実施数 25か所 26か所 27か所 29か所
年間延べ利用人数 21,256人 11,265人 12,251人 10,729人
(3)休日保育
保護者の仕事などで休日など(日曜日、国民の休日および年末・年始)に家庭での
保育が困難となった就学前児童を保育します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
実施数 2か所 2か所 2か所 2か所
延べ利用人数 664人 548人 551人 791人
(4)市立幼稚園における預かり保育
市立幼稚園において、在園児を対象に保護者の希望に応じ、幼稚園保育時間終了後、
保育します。また、市内の私立幼稚園全園(7園)においても、預かり保育を実施し
ています。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
園児数 1,474人 1,310人 1,267人 1,215人
延べ利用者数 36,071人 34,091人 31,635人 32,977人
夏期預かり保育 延べ利用者数
1,238人 1,133人 1,090人 1,072人

資料-42
(5)病児・病後児保育事業
子どもが病気にかかり、保護者の仕事などにより、病気にかかった子どもを家庭で
保育ができない場合、一時的に保育します。
【病児・病後児対応型】
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
実施数 2か所 2か所 2か所 2か所
3歳未満利用者数 168人 241人 272人 247人
延べ利用日数 351日 555日 572日 528日
3歳以上利用者数 161人 186人 140人 190人
延べ利用日数 312日 337日 259日 319日
合計利用者数 329人 427人 412人 437人
合計延べ利用日数 663日 892日 831日 847日
【体調不良児対応型】
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
実施数 4か所 4か所 4か所 5か所
延べ利用日数 927日 1,080日 1,270日 1,506日
(6)子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)
「ショートステイ」は、保護者が入院・出産・冠婚葬祭・出張・看護などや、育児
疲れ・看病疲れなどの理由で、一時的に児童の養育が困難な場合に、一定期間施設で
預かります。
「トワイライトステイ」は、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間または
休日に不在となり、児童の養育が困難な場合に、施設で預かります。(夜間養護、休日
預かり、宿泊の3事業あり)
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
ショート
ステイ
実施施設 3か所 5か所 5か所 6か所
利用人員 26人 22人 28人 23人
延べ利用日数 134日 73日 124日 98日
トワイライト ステイ
実施施設 1か所 1か所 1か所 1か所
利用人員 42人 159人 106人 68人
延べ利用日数 1,406日 965日 644日 379日

資料-43
(7)養育支援訪問事業
「子育てパートナー」は、妊娠中または出産後に子育てに関して不安や悩みを抱え
ている家庭に子育てパートナーが訪問し、相談・アドバイスや、子育てに関する情報
提供を行います。
「ママ・サポート」は、出産後、親族などの応援が得られない家庭に対して、ヘル
パーが訪問して家事や育児の援助などを行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
子育てパートナー
事業
登録者数 52人 51人 33人 64人
訪問家庭数 15件 6件 5件 4件
延べ活動回数 71回 33回 20回 31回
ママ・サポート
事業
利用者数 10人 5人 16人 13人
延べ利用日数 88日 35日 166日 110日
延べ利用時間 89時間 35時間 203時間 153時間
(8)ファミリー・サポート・センター事業
子育ての援助をしてほしい人(依頼会員)と、援助をしたい人(援助会員)がお互
い会員として登録し、子育てを支えあう制度です。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
延べ利用件数 6,085件 5,218件 5,351件 5,289件
登録会員数 1,260人 1,253人 1,238人 1,193人
内訳
援助会員 320人 312人 296人 286人
依頼会員 833人 837人 847人 813人
両方会員 107人 104人 95人 94人
(9)地域子育て支援拠点事業等の在宅での子育て支援サービス
①地域子育て支援拠点事業
つどいの広場や地域子育て支援センターでの子育て家庭同士の交流などにより、子
育て家庭と地域のつながりや、子育てサークル等の育成・支援を行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
つどいの
広場
実施数 12か所 12か所 12か所 12か所
延べ利用者数 40,068人 43,336人 43,722人 46,045人
地域子育て
支援センター
実施数 3か所 3か所 3か所 3か所
延べ利用者数 9,599人 9,525人 12,766人 12,026人
②保育所や幼稚園での在宅子育て支援
保育所では在宅の就学前児童とその保護者を対象に、園庭開放や地域交流、相談事
業などを実施しています。また、市立幼稚園では幼児教室及び4歳児教室を開設し、
私立幼稚園では園庭開放などを実施しています。

資料-44
(10)ワーク・ライフ・バランス実現に向けた講座の開催回数
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
開催回数 2回 7回 10回 6回
男性参加者数 5人 104人 64人 55人
(11)子育て総合支援サイト「みらいねっと」
子育て家庭等が必要な情報を必要な時に得られるよう、子育て総合支援サイト「み
らいねっと」の運用を行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
会員登録数 320人 331人 346人 355人
新規登録数 24人 11人 15人 9人
アクセス件数(累積値) 105,493件 85,049件 73,896件 86,453件

資料-45
8.母 子 保 健 及 び医 療 の状 況
(1)妊婦乳幼児健康診査事業
妊産婦や乳幼児の疾病予防と健康保持を図るため、各種健康診査と相談・指導を行う
ことにより、保護者の育児不安を軽減し、安心して子育てができるよう支援します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
4か月児健康診査
受診者数 2,141人 2,132人 2,062人 2,049人
受診率 97.4% 98.1% 97.3% 97.8%
把握率 99.9% 100% 100% 100%
1歳6か月児
健康診査
受診者数 2,169人 2,040人 2,150人 2,018人
受診率 94.6% 96.8% 94.7% 93.7%
把握率 99.8% 99.8% 99.9% 100%
3歳6か月児
健康診査
受診者数 1,921人 2,075人 2,059人 1,995人
受診率 85.0% 87.8% 91.2% 89.0%
把握率 99.3% 99.9% 99.9% 100%
妊婦健康診査 受診者数 25,720人 25,520人 25,160人 24,828人
受診率 78.3% 79.7% 78.9% 82.4%
※ 平成 21年度から妊婦健康診査は1人あたり 14回実施になり、受診者数はその合計
※ 受診率=受診延べ数÷(妊娠届出数×14回)×100
(2)乳幼児全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
生後4か月になるまでの乳児のいる家庭を訪問し、子どもの様子や保護者の話をうかがい、
八尾市の子育て事業の情報提供などを行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
訪問率 78.6% 85.3% 83.4% 96.3%
把握率 100% 100% 100% 100%
(3)妊産婦乳幼児訪問指導
妊娠・出産・育児に不安がある人等を助産師または保健師が訪問して、相談に応じ
ます。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
被訪問者数
妊産婦 833人 831人 1,190人 1,110人
新生児 687人 675人 1,059人 942人
乳幼児 669人 623人 643人 634人

資料-46
(4)妊婦乳児等保健相談
保護者同士の交流を深め、出産や育児不安を解消するため、妊産婦・乳幼児の保護
者に対して、子どもの疾病予防や育児知識についての健康相談や健康教室等を開催し
ます。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
乳幼児相談 回数 52回 52回 52回 52回
人数 1,272人 1,101人 1,054人 1,027人
両親教室
(ママ・パパ教室)
回数 36回 33回 36回 36回
人数 694人 641人 624人 671人
離乳食講習会 回数 12回 12回 12回 12回
人数 657人 678人 586人 735人
妊婦歯科教室 回数 6回 6回 6回 6回
人数 92人 81人 91人 85人
(5)乳幼児育成指導事業
乳幼児の心身の健全な発達を促し、保護者の育児不安の解消を図るため、経過観察
が必要と判断された乳幼児に対して健康診査や相談教室などのフォロー事業を行いま
す。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
幼児フォロー
教室
回数 48回 48回 48回 48回
人数 1,301人 1,274人 1,385人 1,179人
経過観察健康
診査身体
回数 12回 12回 12回 12回
人数 323人 306人 358人 278人
経過観察健康
診査心理
回数 36回+随時 36回+随時 36回+随時 36回+随時
人数 456人 501人 545人 421人
幼児歯科教室 回数 12回 12回 12回 12回
人数 215人 222人 180人 188人
(6)保健センターにおける食育の推進
妊産婦及び乳幼児の保護者に対して正しい食生活の普及を図り、母子の健康づくりを推進
するための講習会を開催します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
幼児栄養
教室
開催数 12回 12回 12回 12回
参加者数 296人 296人 309人 317人
離乳食
講習会
開催数 12回 12回 12回 12回
参加者数 657人 678人 586人 735人

資料-47
(7)予防接種事業
感染性疾病の発生及びまん延を防ぎ、子どもの健康を守るため、予防接種を実施し
ます。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
集
団
接
種
ポリオ 接種率 87.5% 69.8% 61.1% -
接種人数 4,077人 2,986人 1,644人 -
BCG 接種率 93.7% 99.1% 98.9% 97.2%
接種人数 2,184人 2,120人 2,073人 2,049人
個
別
接
種
第2期ジフテリア(2種混合)
接種率 61.3% 57.6% 72.3% 75.6%
接種人数 1,794人 1,587人 1,992人 2,035人
3種混合※1 接種率 98.1% 94.2% 89.0% 35.7%
接種人数 8,925人 9,221人 7,915人 3,009人
麻しん風しん混合
接種率 87.5% 86.3% 90.8% 97.6%
接種人数 8,803人 8,702人 9,116人 4,265人
麻しん※2 接種人数 1人 0人 3人 0人
風しん※2 接種人数 1人 0人 6人 0人
日本脳炎※3 接種率 76.8% ※ ※ ※
接種人数 11,094人 17,248人 13,700人 9,305人
4種混合※4 接種率 - - - 70.6%
接種人数 - - 1,156人 5,950人
不活化ポリオ※1 接種率 - - - 43.9%
接種人数 - - 7,401人 3,698人
ヒブ 接種率 - - - 104.4%
接種人数 - - - 8,804人
小児用肺炎球菌
接種率 - - - 102.3%
接種人数 - - - 8,623人
子宮頸がん
予防※5
接種率 - - - 11.0%
接種人数 - - - 449人
※1 4種混合への移行途中のため減少している。 ※2 麻しん風しん混合ワクチンを接種できない場合に接種。 ※3 接種差し控え期間の未接種者がいるため、対象人数の確定ができない。
※4 3種混合及び不活化ポリオからの移行途中。 ※5 副反応による積極的勧奨の差し控えをしている。

資料-48
(8)休日急病診療所
土曜日、日曜日及び祝日等の医療空白時間帯における初期救急医療体制の充実を図
るため、休日急病診療所(内科・小児科・歯科)による対応を行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
内科 年間診療日数 73日 73日 75日 75日
患者数 1,848人 1,889人 2,070人 2,192人
小児科 年間診療日数 123日 124日 124日 124日
患者数 6,740人 7,376人 6,661人 6,931人
歯科 年間診療日数 71日 71日 72日 72日
患者数 300人 254人 258人 214人

資料-49
9.小 学 生 、中 学 生 の状 況
(1)小学生、中学生の状況
学校基本統計調査によると、平成 25年(2013年)の小学生児童数は 14,493人、中
学生徒数は 7,895人となっており、小学生は年々減少していますが、中学生は平成 21
年(2009年)以降、おおむね横ばいで推移しています。
図 17 小学生・中学生 児童・生徒数の推移
資料:学校基本調査
(2)放課後児童健全育成事業(放課後児童室事業)
放課後の仕事や病気などの理由により、放課後に保護者が不在になる小学生を対象
に、当該児童の健全な育成を図ることを目的として、学校内施設などを使用して、適
切な遊びや生活の場を提供します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
施設数 29か所 29か所 29か所 29か所
入室児童数 2,161人 2,266人 2,418人 2,481人
入室待機児童数 0人 0人 0人(28人) 0人(45人)
※ 入室児童数は各年度 4月 1日現在
※ ( )内の人数は、モデル事業として実施している小学校4~6年生を含んだ人数
16,210 16,026 15,719 15,321 14,911 14,493
7,667 7,820 7,855 7,920 7,928 7,895
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
平成20年
(2008年)
平成21年
(2009年)
平成22年
(2010年)
平成23年
(2011年)
平成24年
(2012年)
平成25年
(2013年)
小学生 中学生
(人)

資料-50
(3)青少年会館の状況
就学前の乳幼児と保護者を対象にした親子幼児教室や、小・中学生を対象にした各
種講座・教室の開催のほか、サークル活動などへの貸館を行っています。
【桂青少年会館】
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
教室・講座 事業
延べ実施回数 786回 779回 732回 734回
延べ利用者数 11,971人 11,527人 11,020人 9,856人
低学年 育成事業
延べ実施回数 240回 241回 240回 244回
延べ利用者数 15,243人 13,540人 10,898人 10,225人
移動教室 実施回数 48回 50回 52回 51回
参加人数 1,304人 1,257人 886人 1,128人
子育て
支援事業
延べ実施回数 237回 195回 192回 203回
延べ利用者数 5,837人 4,828人 4,677人 4,992人
貸館事業 延べ利用者数 18,279人 21,447人 21,058人 17,950人
【安中青少年会館】
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
教室・講座 事業(長期)
延べ実施回数 485回 531回 525回 525回
延べ利用者数 6,783人 6,547人 6,104人 7,151人
教室・講座 事業(短期)
延べ実施回数 597回 565回 559回 559回
延べ利用者数 10,421人 10,630人 10,297人 9,867人
低学年 育成事業
延べ実施回数 240回 239回 239回 241回
延べ利用者数 13,732人 13,277人 14,339人 16,664人
移動教室 実施回数 54回 52回 56回 52回
参加人数 1,767人 1,760人 1,570人 1,599人
子育て
支援事業
延べ実施回数 36回 61回 69回 71回
延べ利用者数 1,843人 2,901人 3,037人 2,947人
貸館事業 延べ利用者数 23,303人 26,820人 28,628人 27,531人
(4)いじめの認知件数
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
いじめの認知件数
(千人あたりの件数) 1.4件 1.4件 1.9件 2.0件
※いじめ・・・児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等
が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象と
なった児童等が心身の苦痛を感じているもの

資料-51
(5)不登校児童・生徒数
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
小学校合計
千人率
40人 48人 42人 45人
2.5 3.1 2.8 3.1
中学校合計
千人率
162人 165人 163人 158人
21.9 22.0 21.7 21.1
合計
千人率
202人 213人 205人 203人
8.7 9.3 9.1 9.2
大
阪
府
小学校合計
千人率
1,559人 1,535人 1,526人 1,859人
3.2 3.2 3.3 4.1
中学校合計
千人率
6,956人 7,000人 7,095人 7,639人
31.2 30.7 31.1 33.5
※不登校・・・何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない
状況にあるために年間 30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの
(6)交通事故件数(15歳以下でかつ中学生以下)
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
交通事故件数 (15歳以下でかつ 中学生以下)
98件 93件 89件 72件
(7)小学生の放課後や休日の過ごし方
①小学生(高学年)の放課後の過ごし方
ニーズ調査によると、平成 24年度(2012年度)調査では、「ゲームをしている」が
52.2%と最も高く、次いで「外で遊んでいる」(50.9%)、「友達の家で遊んでいる」
(50.0%)となっています。
図 18 放課後の過ごし方(小学生本人)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
52.2
50.9
50.0
47.8
44.3
23.0
4.8
5.7
1.7
18.3
19.1
0.0 20.0 40.0 60.0
ゲームをしている
外で遊んでいる
友達の家で遊んでいる
テレビをみている
公園で遊んでいる
本を読んでいる
学校で遊んでいる
クラブ活動をしている
その他
習い事や塾などで遊ぶ時間はない
無回答
(%)

資料-52
②小学生(高学年)の休日の過ごし方
ニーズ調査によると、平成 24年度(2012年度)調査では、「ショッピングセンター」
が 51.7%と最も高く、次いで「友達の家」(33.5%)となっています。
図 19 学校以外で休みの日などによく行く場所(小学生本人)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
51.7
33.5
31.3
19.1
13.0
8.7
6.1
9.6
7.8
0.9
0.0 20.0 40.0 60.0
ショッピングセンター
友達の家
公園
図書館
塾
クラブ活動をしているところ
運動施設
その他
あまり行かない(自宅で過ごす)
無回答
(%)

資料-53
10.子 育 て家 庭 への経 済 的 支 援
(1)児童手当
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、中学校修了までの児童を
養育している保護者に手当を支給する制度です。(子ども手当は、平成 24年(2012年)
4月から児童手当に移行しました。)
【児童手当】
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
受給者数 ― ― 20,445人 20,025人
受給対象児童数 ― ― 34,988人 34,262人
※年度末時点の受給者数および受給対象児童数
【子ども手当】
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
受給者数 21,137人 22,083人 21,139人 1人
受給対象児童数 36,297人 36,965人 36,139人 2人
(2)子ども医療費公費負担制度
子どもの健全な育成及び子育て家庭への経済的負担軽減を図るため、子どもの通
院・入院に係る医療費を助成する制度です。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
入院助成件数 2,359件 2,243件 2,361件 2,808件
通院助成件数 232,089件 231,786件 227,344件 224,462件
食事助成件数 1,657件 1,507件 1,648件 1,960件
※平成 24年 10月 1日から入院助成の対象を中学校修了まで拡充
(3)就学援助事業
経済的な理由により就学が困難な家庭に対して、小・中学校で必要な費用の一部を
援助する制度です。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
認定者数 小学校 4,930人 4,684人 4,435人 3,758人
中学校 2,371人 2,473人 2,530人 2,260人
(4)奨学金事業
「八尾市奨学基金」から生ずる果実等をもって、奨学生及び保護者の高等学校等へ
の修学に対する経済的負担軽減を図ります。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
申請者数 564人 600人 580人 398人
選定者数 300人 301人 251人 252人

資料-54
(5)私立幼稚園就園奨励費
私立幼稚園に就園する園児の保護者に対して、所得状況に応じた補助金を交付しま
す。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
申請者数 1,993人 2,009人 1,985人 1,988人
交付者数 1,560人 1,569人 1,472人 1,511人
(6)私立幼稚園就園助成費
市内の私立幼稚園に就園する園児の保護者で、就園奨励費対象外等の保護者に対し
助成します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
申請者数 1,993人 2,009人 1,985人 1,988人
交付者数 1,085人 1,101人 1,143人 1,150人
(7)助産施設への入所制度
出産費用を捻出ができない方が、安心して助産施設を利用し出産できるように、出
産費用の一部を負担します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
助産施設への
入所件数 71件 76件 66件 50件

資料-55
11.ひとり親 家 庭 の状 況
(1)児童扶養手当
父母の離婚、父母が重度の障がい、婚姻によらない出生などの理由により、父また
は母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定
と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する
制度です。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
受給者数 3,335人 3,364人 3,360人 3,291人
(2)ひとり親家庭医療費公費負担制度
ひとり親家庭の父または母および養育者とその児童が、病気やけがをした時に、医
療機関などで対象となる保険診療を受ける場合にかかる医療費の自己負担額の一部を
助成する制度です。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
助成件数 68,463件 71,843件 69,672件 70,542件
(3)母子・父子自立支援員の配置
母子家庭等の自立を総合的に支援するために母子・父子自立支援員を配置し、ひと
り親家庭等からの相談に対応します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
ひとり親
相談受付状況
(窓口での実相談件数)
生活一般 14件 203件 122件 65件
児童 0件 0件 3件 1件
生活援護 101件 288件 128件 100件
その他 0件 0件 0件 1件
合計 115件 491件 253件 167件
(4)母子生活支援施設への入所
母子家庭で、居宅で生活することが児童の福祉に欠ける場合又は居宅が無い場合の
母親と子どもの生活の安定を確保するために、母子生活支援施設にて必要な保護を行
います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
年間延べ入所世帯数 (前年度からの継続含む)
111世帯 80世帯 68世帯 81世帯
年間延べ入所者数 (前年度からの継続含む)
305人 220人 143人 195人

資料-56
(5)母子緊急一時保護制度
精神的または経済的に緊急の保護を必要とする母子世帯について、指定施設におい
て一時的に保護し、必要な相談・指導を行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
年間利用世帯数 1世帯 1世帯 0世帯 1世帯
年間利用者数 2人 2人 0人 3人
年間延べ利用日数 7日 11日 0日 8日
(6)母子父子寡婦福祉資金貸付制度
ひとり親家庭の経済的自立や生活意欲の助長、子どもの福祉増進を目的とし、貸付
資金の活用を通じて総合的に自立を支援します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
貸付
状況
技能習得資金 0件 0件 0件 0件
就学支度資金 8件 3件 0件 11件
修学資金 12件 12件 4件 4件
転宅資金 0件 0件 0件 0件
修業資金 0件 0件 0件 0件
生活資金 1件 1件 0件 0件
合計 21件 16件 4件 15件
(7)母子家庭等日常生活支援事業
母子家庭等で、生活に援助が必要であると認められる場合または生活環境が激変し
て日常生活に著しい支障が生じている場合に、家庭生活支援員が家事支援等を行いま
す。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
派遣対象家庭登録者数 19人 18人 10人 9人
延べ支援員派遣回数 1944回 1,046回 636回 122回
延べ派遣時間 2646.0時間 1537.0時間 963.0時間 282.5時間
(8)母子家庭等自立支援給付金事業
母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援し、ひとり
親家庭の自立の促進を図るために、資格取得への支援等の給付金事業を実施します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
自立支援教育訓練
給付金(給付実績) 3件 5件 3件 2件
高等技能訓練促進費
(給付実績) 28件 25件 20件 18件

資料-57
12.相 談 等 の状 況
(1)子育て総合支援ネットワークセンター事業
子育て総合支援ネットワークセンター「みらい」は、子どもと子育てに関すること、
ひとり親家庭などに関することの総合相談窓口です。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
子育て相談・
児童家庭相談
電話 148件 127件 121件 119件
来訪 4,979件 5,163件 5,452件 5,874件
メール 20件 25件 21件 30件
親子教室 74人 81人 87人 89人
子育て講演会開催数 2回 2回 2回 2回
子育て講演会参加保護者数 38人 70人 71人 44人
(2)教育相談事業
不登校やいじめ、発達面や学習面などの心配など、幼稚園、小・中学校に通う子ど
もの教育上の様々な悩みについての相談や、特別な教育的支援が必要な子どもへの学
校園での支援や家庭での養育についての相談などを行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
相談件数 712件 736件 689件 624件
相談延べ件数 9,192件 11,361件 9,687件 7,064件
(3)女性相談事業
女性の抱える様々な悩みに対応するため、女性相談員による相談事業です。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
定例相談 117件 165件 167件 169件
電話相談 40件 29件 40件 31件
(4)雇用や就労に関する相談
市内 3 か所ある地域就労支援センターにおいて、就労困難者等に対する就労支援を
行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
相談利用
件 数
新規 232件 205件 166件 154件
再相談 1,711件 1,564件 970件 772件
合計 1,943件 1,769件 1,136件 926件

資料-58
(5)人権相談
人権相談事業を通じて、子どもの人権に関する問題解決に向けて取り組みます。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
相談実績件数 90件 63件 78件 98件
内
訳
人権擁護委員による人権相談
5件 11件 9件 11件
人権政策課での 人権相談
85件 52件 69件 87件
(うち、子どもの人権に
関する相談) 2件 0件 3件 0件

資料-59
13.虐 待 の状 況
(1)児童虐待への対応
児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、要保護児童対策地域協議会
を中心とした関係機関や地域との連携強化に取り組むとともに、児童虐待防止の広
報・啓発や研修等を実施し、児童虐待防止への関心を高め、地域で子どもを見守る体
制づくりにつなげます。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
虐待通告件数のうち、 要保護児童対策地域協議会の関係機関からの通告件数割合
56.3% 37.7% 55.7% 39.4%
虐待
相談・通告
相談件数 346件 276件 301件 358件
通告件数 103件 130件 131件 114件
児童家庭
相談
相談件数
(実数) 5,127人 5,290人 5,573人 5,993人
要保護児童
対策地域
協議会
代表者会議 1回 1回 1回 1回
実務者会議 3回 3回 3回 3回
個別ケース 会議
16回 18回 33回 43回
調整会議 毎月 毎月 毎月 毎月
研修会
(職員・教員
向/市民向)
実施回数 8回 8回 8回 7回
参加者数 職員・教員 339人 市民 81人
職員・教員 315人 市民 44人
職員・教員 388人 市民 192人
職員・教員 157人 市民 66人
虐待防止啓発用ポスター掲示 1,400部 1,310部 1,297部 1,198部
児童虐待発生予防システム 依頼数:19件 把握数:11件
依頼数:27件 把握数:21件
依頼数:16件 把握数:14件
依頼数:10件 把握数:10件

資料-60
14.障 がいのある子 どもへの支 援 状 況
(1)保育所での障がい児保育の実施
障がい児を集団保育することにより、児童の心身の発達を促します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
対象
児童数
公立保育所 7か所 7か所 7か所 7か所
34人 31人 29人 29人
私立保育所 20か所 21か所 21か所 22か所
98人 88人 94人 110人
合計 132人 119人 123人 139人
(2)障がい児の通園施設
①市立医療型児童発達支援センター(いちょう学園)
肢体や体幹の機能障がいや発達に遅れのある就学前児童への療育・訓練、保護者へ
の育児に関わる指導、助言を行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
外来訓練(契約児童数) 39人 34人 31人 29人
②市立福祉型児童発達支援センター(八尾しょうとく園)
発達に遅れのある就学前児童を対象に、通所によって適切な指導・療育を行い、自
立生活に必要な知識や技能を習得させる等により、心身の発達を支援します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
児童発達支援(定員) 60人 60人 60人 60人
児童発達支援事業(定員) 10人 10人 10人 10人
教 育 相 談 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回
※ 児童発達支援(児童発達支援センター) ・・・ (旧) 知的障害児通園事業
※ 児童発達支援事業 ・・・・・・・・・・・・・ (旧) 児童デイサービス
(3)放課後児童室事業における障がい児の受け入れ
保護者が就労、疾病等により不在となる小学生を対象に、放課後に学校施設等を利
用して遊びやスポーツ等を通じた健全育成事業として実施する放課後児童室に、障が
いのある子どもの受け入れを進めます。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
入室児童数 90人 103人 116人 130人

資料-61
(4)特別児童扶養手当
20歳未満で精神または身体に障がいのある(法令による定めあり)児童を監護して
いる父または母もしくは父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を
維持すること)されている方が受給できます。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
受給者数 552人 591人 613人 643人
※ 受給者数は各年 12月末現在
(5)障がい児福祉手当
重度の障がいで、日常生活において特別の介護を必要とする満 20歳未満の在宅障が
い児が受給できます。施設入所者、障がいを支給事由とする公的年金を受けている人
は対象外です。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
支給人員 156人 156人 148人 132人
※ 支給人員は各年度3月末現在
(6)障がい者(児)医療費公費負担制度
重度の障がい者(児)が医療機関で診療を受けた時、医療保険適用の自己負担額の
一部および入院時の食事負担額、訪問看護利用料を助成する制度です。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
助成件数 50,564件 51,864件 51,175件 49,922件
(7)就園・就学相談
八尾市立学校園等への入園・入学にあたり、子どもの言葉の遅れ、発達や障がいな
どに心配や不安がある保護者に対し就園就学前の相談を行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
就園 25件 23件 28件 27件
小学校就学 90件 107件 109件 85件
中学校進学 46件 39件 31件 26件
合計 161件 169件 168件 138件
(8)特別支援教育の推進
障がいのある幼児・児童・生徒の教育の充実を図るための推進体制の確立を進める
とともに、教育・医療・福祉等の連携により、特別な支援を必要とする子どもや保護
者に対して総合的な支援を行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
学校園校内研修 3回 2回 0回 1回
学校園巡回相談 345回 342回 379回 287回
特別支援教育一般研修件数 5回 4回 4回 4回
特別支援教育コーディ ネーター養成研修件数
2回 2回 2回 2回

資料-62
15.地 域 の活 動 と子 育 てサークルの状 況
(1)こども会育成事業
異年齢間での集団活動を通して、協調性や社会性を身につけるとともに、子どもの
ニーズにあう地域のこども会活動を支援します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
こども会への加入率 31.0% 30.4% 28.2% 26.4%
(2)放課後子ども教室推進事業
学校を活用して安全・安心な子どもの活動場所を確保するとともに、地域のボラン
ティアの方々が中心となり、放課後や週末における体験・交流活動等を実施します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
実施数 21か所 21か所 20か所 20か所
(3)子育てサークルへの支援
地域の子育て力の向上を図るために、子育てサークルへの情報提供と子育てサーク
ルの自主的なネットワーク化への支援を行うとともに、子育てサークルの活動の場所
として、施設等の貸し出しを行います。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
子育てサークルネットワーク定例会議 年 12回 年 24回 年 24回 年 24回
サークル登録数 81件 85件 84件 86件
参加親子組数 1,002組 1,113組 966組 1,026組
サークル交流会 1回 0回 0回 1回
講習会
学習会
開催数 4回 2回 3回 2回
参加人数(延べ) 194人 83人 111人 61人
※ 平成 19年度以降、サークル交流会は、サークルネットワークが独自で開催

資料-63
16.子 どもの遊 び場 ・居 場 所
(1)学年の違う子どもと遊ぶ機会
ニーズ調査によると、平成 24年度(2012年度)調査では「兄弟姉妹がいる」が 74.3%
と最も高く、次いで「近所の子どもとよく遊ぶ」が 47.8%となっています。一方、「遊
ぶことが少ない、ない」は 10.0%となっています。
図 20 学年の違う子どもと遊ぶ機会(小学生本人)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
(2)遊び場の状況
ニーズ調査によると、平成 24年度(2012年度)調査では「遊び場が多い」が 12.6%、
「少ない」が 30.9%、「公園などはあるがしたい遊びができない」が 33.9%となって
います。
図 21 遊び場の状況(小学生本人)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
74.3
47.8
25.7
3.9
10.0
0.9
17.4
14.8
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
兄弟姉妹がいる
近所の子どもとよく遊ぶ
いとこなど親せきの子とよく遊ぶ
クラブなどにいる
親の友達の子どもとよく遊ぶ
その他
遊ぶことが少ない、ない
無回答
(%)
多い
12.6%
どちらともいえな
い
20.0%
公園などはある
がしたい遊びがで
きない
33.9%
少ない
30.9%
無回答
2.6%

資料-64
(3)学校体育施設開放事業(小学校・中学校)
子どもたちのスポーツレクリエーション活動と振興を図り、青少年健全育成事業の
一環として、学校体育施設開放運営委員会の運営のもと市内の小・中学校の体育施設
を開放します。
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
小中学校
体育施設
開放回数
運動場 5,890回 5,830回 5,870回 5,546回
体育館 11,958回 12,616回 13,752回 14,014回
合計 17,848回 18,446回 19,622回 19,560回
開放人数
運動場 228,441人 246,339人 222,227人 211,920人
体育館 245,420人 252,527人 291,856人 292,351人
合計 473,861人 498,866人 514,083人 504,271人
(4)近くにあったらよいと思う遊び場
ニーズ調査によると、平成 24 年度(2012 年度)調査では就学前児童保護者の大半
が「小さな子どもが安全に遊べる遊具のある公園」をあげています。その他、就学前
保護者、小学生保護者、小学生本人がともにあげているのは「ボール遊びや鬼ごっこ
ができる空き地や原っぱ」、「プールやグラウンドなどのスポーツ施設」、「いろんな図
書を自由に読むことができるところ」、「木や小川があり、木登りや泥んこ遊びなどが
できる広場」となっています。

資料-65
図 22 近くにあったらよいと思う遊び場(就学前児童保護者、小学生保護者、小学生本人)(複数回答)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
83.4
30.2
64.6
63.0
42.5
48.4
43.3
25.0
26.8
50.0
27.0
4.5
0.8
0.4
2.1
24.0
47.4
62.3
45.5
41.3
44.4
44.4
31.8
24.2
23.8
41.7
6.1
10.5
26.5
1.7
1.9
0.6
0.6
30.9
42.2
28.7
50.9
24.3
42.6
28.3
29.1
21.3
26.1
11.3
5.7
8.7
0.9
2.6
0.4
1.7
39.0
39.1
-
-
15.7
17.3
36.7
17.7
35.6
33.5
35.2
57.8
15.2
17.0
17.4
33.9
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
小さな子どもが安全に遊べる遊具のある公園
子どもの仲間づくりのためのサークルや
クラブ活動ができる場
木や小川があり、木登りや泥んこ遊びなどが
できる広場
ボール遊びや鬼ごっこができる空き地や原っぱ
小動物や昆虫とふれあうことのできる場所
プールやグラウンドなどのスポーツ施設
子どもが放課後などに集まって、子どもどうしで
自主活動などができる場
いろんな図書を自由に読むことができるところ
自習ができ、分からないところがあれば
教えてもらえるところ
工作など、ものづくりの体験ができる講座が
あるところ
英会話やパソコンなど役に立つ講座があるところ
道具があり、遊び方を教えてくれる先生の
いるところ
年齢の異なる子どもどうしが交流できるところ
子どもが土日に活動ができたり遊べたりできる場
子ども自身の悩みなどを積極的に聞き、
相談にのってくれるところ
障がいがあっても職員やボランティアが
付き添ってくれるところ
子どもにしつけをしてくれる場
子ども向けの映画や劇が見られるところ
その他
特にない
わからない
無回答
就学前児童保護者
小学生保護者
小学生本人
(%)

資料-66
17.地 域 とのかかわり
(1)住んでいるところへの好感度
ニーズ調査によると、平成 24年度(2012年度)調査では「とても好き」(29.1%)、
「好き」(44.3%)といった、住んでいるところが好きだとする人が約 73%となって
います。一方、「あまり好きではない」(2.2%)、「好きではない」(1.3%)といった住
んでいるところが好きではない人は約 3%となっています。
図 23 住んでいるところへの好感度(小学生本人)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
(2)地域活動への参加状況
ニーズ調査によると、平成 24 年度(2012 年度)調査では「何らかの地域活動に参
加している」が 43.5%、一方「どこにも入っていない(参加していない)」が 54.8%、
地域活動に参加している人の中では、こども会をあげる人が多くなっています。
図 24 参加している地域活動(小学生本人)(複数回答)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
とても好き
29.1%
好き
44.3%
どちらでもない
20.0%
あまり好きではな
い
2.2%
好きではない
1.3%無回答
3.0%
34.8
13.9
0.0
1.3
54.8
1.7
0.0 20.0 40.0 60.0
こども会に入っている
地域のスポーツクラブに入っている
ボーイ・ガールスカウトに入っている
その他
どこにも入っていない
無回答
(%)

資料-67
(3)地域社会に求める支援
ニーズ調査によると、平成 24 年度(2012 年度)調査では就学前、小学生とも「地
域全体で子どもを見守る」をあげる人が最も高くなっています。
図 25 地域社会に求める支援(就学前、小学生)
資料:「八尾市保育サービスに関するアンケート調査」(平成 24 年(2012 年)9月実施)
46.4
24.2
32.0
59.9
20.7
7.9
6.0
3.3
40.6
30.1
24.4
24.0
61.3
20.0
9.3
2.1
4.6
38.6
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
子育て中の人に手助けをする
親どうしが知り合う機会を増やす
異年齢の子どもなどが交流できる機会を増やす
親と子でふれあう機会を提供する
地域全体で子どもを見守る
さまざまな年代の人が交流できる場の設置
特にない
その他
無回答
就学前
小学生
(%)

資料-68
子育て支援等の関連施設の配置状況
平成 26 年4月1日現在
< 凡 例 >
保育所
幼稚園
地域子育て支援センター、 つどいの広場
小学校
八尾中
東部地域中部地域
南部地域
桂中
上之島中
亀井中
久宝寺中
高安中
東中
曙川南中
曙川中
南高安中
大正中
龍華中
志紀中
高美中
成法中
西部地域

資料-69
具体的施策を実現するための取り組み内容一覧
1.子どもがいきいきと育つための支援の充実
1-1 子どもの権利を尊重する意識の醸成
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
子どもの権利尊重について
の啓発の実施
・子どもたちが、自分の大切さや他の人の大切さを認めることが
できるようになり、それがさまざまな場面で具体的な態度や行
動に現れるよう取り組みを進めます。また、「子どもの権利条
約」の理念・内容の周知を図るための啓発を行います。
・子どもの人権についての意識向上を図るため、研修やセミナー
といった啓発事業を実施します。
・子どもに対し、基本的人権の主体者であることの理解と保護者
に対しても子どもの権利を尊重する意識の醸成を図るために、
「子どもの権利条約」リーフレットを配付し、保護者への啓発
とともに、人権教育学習教材として活用します。
子ども・子育てシンポジウ
ムの開催
子どもたちが、自分の大切さと相手の大切さを認めることがで
きる意識の醸成を行うとともに、自分の行動に責任を持った、
社会性のある自立した大人へと成長できるよう、また、いじめ
や虐待から守られる社会をめざすために、八尾の未来を担う子
どもたちへの取り組みを企画し実施します。
子ども向けウェブサイトに
よる子どもの主体性を高め
る情報の発信
子どもの育ちや学びに着目した子ども向けウェブサイトを活
用し、相談機関の情報やさまざまな危険から身を守る方法、八
尾市に愛着がもてるような情報等を発信します。
子どもの意見を尊重した取
り組みの実施(やおっ子元
気・やる気アップ提案事業
(子どもの「あったらいい
な」実現部門))
子どもたちをとりまくさまざまな課題に対応するため、市民自
らが計画・実施する取り組みの提案を募集し、助成金の交付し
自主的な活動を支援します。
教師・保育士等の人権研修
の実施
・「人権を大切にする心を育てる」保育について、私立保育園の
職員にも参加を呼びかけ、市全体で保育の質が高められるよ
う、様々な視点から研修および研究に取り組みます。
・学校園教職員等の人権意識の高揚と指導力の向上を図り、子ど
もたちに対する人権教育を充実させるために、人権教育に関す
る各種研修を行います。
自他の命を大切にする教育
を推進する取り組みの実施
・「自他の命を大切にし、自らの命を守り、他人の命も守ること
のできる幼児・児童・生徒の育成」を図るための特色ある取り
組みを実施する学校園を支援し、その取り組みを広めることに
より、市内学校園の命を育む教育の充実を図ります。
・「人権教育の指導方法等のあり方について[第 3次とりまとめ]」
を指針とし、知的理解を深めるとともに人権感覚を高め、自他
の人権を守ろうとする意識・態度・行動力を身につけた児童・
生徒の育成を図ります。
1-2 児童虐待防止対策の充実
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
要保護児童対策地域協議会
の充実
児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、「八尾
市要保護児童対策地域協議会」を設置し、関係機関や地域との
連携強化に取り組みます。

資料-70
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
児童虐待防止のための研
修・啓発
児童虐待防止への関心を高め、地域で子どもを見守る体制を強
化するために、児童虐待防止の広報・啓発や研修等を実施しま
す。
相談体制・ケース対応の充
実
「八尾市要保護児童対策地域協議会」における代表者会議・実
務者会議・ケース検討会議を開催し、関係機関や地域と連携し
ながら、児童虐待や虐待発生の恐れがある家庭の支援を行いま
す。
健康診査時や健康診査未受
診者の対応における児童虐
待の早期発見と発生予防
児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、児童虐
待発生予防システムとして、4か月児、1歳6か月児、3歳6
か月児健康診査未受診家庭の養育状況を把握・支援します。
児童家庭相談の充実 子どもの権利擁護および児童福祉の向上をめざし、児童虐待の
ある家庭や複数の問題を抱える家庭等、様々な家庭への支援の
ために、家庭への援助方策を検討し対応します。
1-3 いじめ・不登校や引きこもり等への対応
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
いじめの未然防止・早期発
見に向けた体制づくりと総
合的な対策の推進
八尾市いじめ防止基本方針のもと、いじめの未然防止の取り組
みの充実を図るために、学校におけるいじめ事象の早期発見と
適切で迅速な対応が図れるよう支援を行うとともに、各部局が
行ういじめ防止対策の総合的、効果的な推進を図ります。
スクールカウンセラーの活
用
スクールカウンセラーを活用し、子ども、保護者、教員へのカ
ウンセリングを行うとともに、不登校児童・生徒に対する情報
交換や対応を行います。
家庭の教育力レベルアップ
事業の実施
幼稚園や学校および地域、関係諸機関との連携のもとに、幼児
児童生徒が抱える諸課題に早期対応することで、学齢期の子ど
もの子育てに悩みや不安を抱く家庭の支援を通し、総合的な家
庭の教育力の向上を図ります。
スクールサポーターの派遣 学校園現場での様々な教育活動における子ども支援の補助を
行うために、学校園の状況や要請に応じ、教育系・心理系大学
の学生や社会人等地域人材の活用によるスクールサポーター
を派遣します。
教育相談の実施 幼児・児童・生徒の心や身体の健康の相談、教育上の諸問題の
解決に向けた相談など、子育てに関する支援を行います。加え
て、青少年に関する様々な相談も行います。
さわやかルームにおける援
助活動の実施
心理的又は情緒的な原因等、さまざまな要因により、登校の意
思があるにもかかわらず登校できない状況にある児童生徒に
対して、家庭と学校の中間点としての場を提供し、学校復帰を
めざした教育相談、学習援助及び集団生活への適応指導などの
援助活動を行います。
人権相談の実施 人権相談事業を通じて、子どもの人権に関する問題解決に向け
て取り組みます。

資料-71
2.みんなで支える、地域が主体の子育ち・親育ちのしくみの充実
2-1 子どもが主体となって活動ができる地域づくりの推進
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
子どもが地域での活動に参
加する機会づくり(やおっ
子元気・やる気アップ提案
事業(子どもいきいき実践
部門))
子どもたちをとりまくさまざまな課題に対応するため、子ども
たちが夢や希望を実現するための取り組みの提案を募集し、実
現に向けた取り組みを実施します。
すくすく子ども地域活動支
援事業の実施
地域における多彩な体験活動を推進するため、中学校区単位で
青少年育成活動団体のネットワークにより、子どもと地域が一
体となった事業を展開します。
こども会活動の育成・活性
化の支援
異年齢間での集団活動を通して、協調性や社会性を身につける
とともに、子どものニーズにあう地域のこども会活動を支援し
ます。
子どもの活動支援と八尾を
全国に発信する取り組み
(がんばる「八尾っ子」応
援事業、河内音頭こども音
頭とり講座など)
・スポーツ活動や文化活動において、顕著な成績をあげ八尾市を
全国発信した子どもたちを支援することで、子どもたちの可能
性を広げ、個性や能力の向上を図ります。
・河内音頭の次世代への継承をめざし、市内の小学生を対象に、
河内音頭を「きいて」「おぼえて」「うたう」ことを学び、実
践する講座を開催します。
「地域分権」の考え方に基
づく取り組みの推進
地域別計画の策定をはじめとして「地域分権」の考え方を取り
入れた計画内容をもとに、地域分権の推進に向けた各種制度を
実施します。
青少年活動団体への助成 市内で活動する青少年育成関係団体の活動を促進することで、
青少年の育成を図ります。
2-2 子どもの居場所づくりの支援
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
青少年センター講座による
学習・活動機会の提供
夏・冬の休暇期間を中心に青少年センターを活用した講座を開
催し、青少年に多様な学習機会や活動機会を提供します。
八尾市立青少年運動広場、
大畑山青少年野外活動セン
ターにおける活動場所の提
供
・市内青少年の自主的・組織的なスポーツ・レクリエーション活動
を促進することで、青少年の健康増進、健全育成を図ります。
・青少年が自然に親しみ、野外活動及びレクリエーション活動を
行う場を提供することで、青少年の健全育成を図ります。
桂・安中青少年会館におけ
る子ども・保護者の活動場
所・機会の提供
・青少年・児童の健全育成を図るため、「生きる力の育成」「豊
かな心の育成」「健やかな身体の育成」を目的とし、子どもや
保護者のニーズ応えながら、市内の青少年児童を対象とし、通
年平日の長期教室・土曜日及び長期休業中の短期講座として、
学習会・文化教室・スポーツ教室・各種体験教室等多様な教室・
講座を開催します。また、移動教室として、市内小学校へ出向
き、工作教室を実施します。
・子どもたちの健全育成と人権意識の高揚を目的として、市内の
小学生を対象に、学習活動、伝承遊び、文化活動、工作活動、
スポーツ活動等各種体験活動を中心とした小学生教室を開催
します。

資料-72
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
・青少年・児童の健全育成を図るため、「生きる力の育成」「豊
かな心の育成」「健やかな身体の育成」を目的とし、子どもや
保護者のニーズに応えながら文化的・体育的・体験的な各種教
室・講座を実施します。また、移動教室として、家庭や学校で
は経験できない、創作する喜びを体感してもらうため、市内各
小学校に出向き、講座を実施します。
・子どもたちの健全育成と人権意識の高揚を目的として、小学校
低学年児童を対象に、学期中の平日の放課後や長期休業中に
「低学年育成教室」(パレットクラブ)を実施します。
・音楽活動、地域活動、スポーツ活動、学習会、研修会、会議等
を行うため子育てサークルやスポーツサークル等に活動場所
を提供します。
・子育てサークルや一般利用者への活動場所の提供や青少年およ
び幼児・児童とその保護者に対し、図書室や卓球ルーム等の開
放を行います。
小・中学校体育施設の開放
によるスポーツ・レクリエ
ーションの活動場所の提供
子どもたちのスポーツレクリエーション活動と振興を図り、青
少年健全育成事業の一環として、学校体育施設開放運営委員会
の運営のもと市内の小・中学校 44校の体育施設を開放します。
社会体育振興事業による子
ども同士の親睦・活動機会
の提供
小学生軟式野球大会や市民体育大会等を通じて、青少年のスポ
ーツ振興とともに、子ども同士の親睦や活動機会を提供しま
す。
2-3 子育て支援のネットワークづくりの充実
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
(仮称)子どもセンターの
検討
家庭や地域と連携し安心して生み育てられる環境づくりを進
め、子どもの育ちを総合的に支援する体制を充実させるため
に、子ども・子育ての総合的な支援拠点の設置を検討します。
地域の子育て支援拠点とし
ての「つどいの広場」の充
実
利用者の相談に対応するため、スタッフの研修の充実を図ると
ともに、専門的知識を持つ相談員の協力を受ける等、相談体制
の充実を図ります。
子育てサークルの活性化に
向けた支援
地域の子育て力の向上を図るために、子育てサークルへの情報
提供と子育てサークルの自主的なネットワーク化への支援を
行うとともに、子育てサークルの活動の場所として、施設等の
貸し出しを行います。
地域子育て支援センターで
の保護者・子育てサークル
等のつながりづくりの支援
子育て家庭同士の交流や公園等地域へ出向くことにより、子育
て家庭と地域がつながる仕組みづくり、子育てサークル等の育
成・支援を行うことを通じて、子育て支援のネットワークづく
りの充実を図ります。
母子保健地域組織育成事業
による地域住民の活動支援
地域住民の活動を支援することにより、母子保健の知識普及を
図るとともに、地域住民の活性化を図り、地域の子育て家庭の
育児不安軽減等の支援につなげます。
地域の読み聞かせボランテ
ィアの育成
子どもの読書活動の向上のため、ボランティア団体によるイベ
ント等の開催をします。また、ボランティアによる図書館業務
のサポートの拡充を図ります。
PTA協議会活動の支援 子どもの健全育成に強く関わる保護者の PTA 活動を円滑にす
すめるために、八尾市 PTA 協議会事務局として支援を行いま
す。

資料-73
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
地区集会所、小学校区集会
所を活用した子育て支援の
活動促進
・自治会等が実施する地区集会所の整備(用地取得、新築、購入、
建替え・増改築等・耐震診断)及び自治会等が負担する家賃等
に対する補助金を交付し、自治活動の拠点整備の促進と活発な
市民活動の促進を図ることによって、子育て支援ネットワーク
づくりの充実をめざします。
・地域活動の拠点施設として小学校区集会所を整備し、活発な市
民活動の推進を図ることによって、子育て支援ネットワークづ
くりの充実をめざします。
子育て支援広場「はとぽっ
ぽ」の実施
民生委員児童委員が、子育て中の親子の交流の場を設定し、地
域における子育て支援を行います。
高齢者ふれあい農園におけ
る世代間交流の実施
高齢者の生きがいづくりに寄与するとともに、地域でのつなが
りや支えあいを大切にし、安心して暮らすことのできるまちを
めざすために、高齢者ふれあい農園での高齢者と子どもとの交
流を進めます。
地区福祉委員会など共助の
取り組みの推進
八尾市社会福祉協議会とともに第 3 次八尾市地域福祉計画・地
域福祉活動計画を策定し、地域福祉の推進に向けて、子育て支
援活動や子どもたちの登下校時の見守り活動、世代間交流など
を行っている地区福祉委員会の活動などをはじめとする共助
の取り組みを進めます。
2-4 家庭教育の充実と地域の教育力の向上
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
家庭の教育力レベルアップ
事業の実施
幼稚園や学校および地域、関係諸機関との連携のもとに、幼児
児童生徒が抱える諸課題に早期対応することで、学齢期の子ど
もの子育てに悩みや不安を抱く家庭の支援を通し、総合的にそ
の教育力の向上を図ります。
家庭教育学級による子育て
講座の開催や保護者の交流
機会の提供
家庭と地域の教育力の向上をめざし、保護者と学校園(市立幼
稚園、小学校、特別支援学校)の連携のもと、家庭教育学級(子
育てに関する講座・保護者間の交流を図る講座等)を実施しま
す。
土曜スクール(開かれた学
校づくり)の実施
地域や保護者への公開を基本とし、「学力向上」「安全・安心」
「体力向上」「小中連携」等の授業を土曜日に行い、「開かれ
た学校づくり」をより一層推進します。
2-5 子どもの安全の確保と青少年の健全育成
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
青少年健全育成に対する啓
発の実施
青少年の課題を解決していくために、青少年健全育成八尾市民
会議を中心として「少年を守る日・家庭の日」等、青少年健全
育成の啓発事業を展開します。
青少年健全育成市民会議に
おける取り組み(八尾市青
少年健全育成重点目標の設
定)
「青少年健全育成市民大会」、「家庭教育を考える市民集会」
や各地区で開催する住民懇談会を通して、地域における青少年
の健全育成や非行防止に対する住民の意識向上を図ります。
青少年ボランティアの養成 高校生、大学生等の青少年ボランティアを養成し、早期からの
ボランティア体験を進めます。市内中学生を中心にジュニアリ
ーダー養成を積極的に推進し、将来的に地域の青少年育成活動
を支える人材を育成します。

資料-74
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
地域による子どもの安全確
保の推進
地域の子どもは地域で守り、子どもたちが安心して暮らせる環
境を確保するため、青少年指導員による街頭啓発をはじめ、こ
ども110番運動や青少年を守る店等の推進を図ります。
小学生対象の消費者教育の
実施(こども消費者教室)
子どもの頃から消費生活に係る見識を深め、悪質商法や詐欺な
ど消費者トラブルに遭わないような自立した消費者の育成を
目的として、市内の小学生を対象として、消費生活問題をはじ
め、環境や食生活などの消費生活に関するさまざまな内容をテ
ーマとした講座(こども消費者教室)を開催します。
通学路安全対策計画に基づ
く取り組み推進
通学路を中心とした生活道路の事故防止対策として策定した、
通学路安全対策計画に基づき、交差点のカラー化や、路側帯の
カラー化等の安全対策工事を計画的に進めます。
防犯灯、防犯カメラの整備
促進による犯罪・事故等の
防止
・安全なまちづくりの推進に向け、犯罪・事故等の防止のために
町会で管理・運営している防犯灯へ各種補助金支援を実施しま
す。
・街頭犯罪及び女性や子どもの犯罪被害抑止のため、防犯カメラ
設置補助金交付要綱にもとづき、校区まちづくり協議会に対し
て補助金を交付します。
交通安全教育の推進 幼児、児童、生徒等を対象とした交通安全についての安全教室
を開催し、ルールやマナーをしっかり守るよう指導するととも
に、母と子の交通安全クラブによる各種事業(交通安全キャラ
バン隊・研修)等を実施します。
地域における防犯に対する
啓発の実施(防犯速報、地
域安全推進会議、防犯啓発
事業)
・地域での子ども安全確保に向け、地域住民の防犯意識の向上を
図るために、街頭犯罪に関する防犯速報を発行し、町会掲示板
へ掲出します。
・地域の安全・安心なまちづくりを担う町会に対して、市内の犯
罪発生・防犯に関する現状や地域安全への取り組み内容を啓蒙
するために、地域安全推進会議を開催します。
・市役所前・地域でのイベント・大型スーパー等を中心に、警察
や市民と連携し、自転車のひったくり防止カバーの取付けや防
犯教室をはじめとする防犯啓発活動を行います。
防災に対する啓発の実施 ・自主防災組織が結成されていない町会のある小学校区を中心
に、防災講演会等を積極的な実施や防災イベント等の啓発活動
を行ない、自主防災組織の結成・育成を進めます。
・火災の発生を未然に防ぎ子どもたちが安全で安心して暮らせる
よう、子どもたちに向けて、火災の怖さや正しい火の取扱い方
法等の指導をはじめとする防火防災全般の啓発を行います。
市立小学校・特別支援学校、
市(私)立幼稚園・保育所へ
の安全対策推進員の配置
・幼稚園及び保育所において、不審者の侵入を未然に防止するた
めに、安全対策推進員を配置する等による児童の安全を確保し
ます。
・子どもが安全に通学できる地域環境を確立するために、スクー
ルガード・リーダーを委嘱し登下校時の巡回指導等を実施しま
す。また通学路の危険箇所への対策を関係機関及び市関係各課
と連携し実施します。
学校における防犯教室の実
施
子どもが犯罪に遭わないようにするために防犯教室等を実施
します。また、防犯に対する意識を高めるために、八尾警察、
東大阪少年サポートセンターとの連携のもと、小学校高学年に
おいては、非行防止教室を実施するとともに、市内全小中学校
において子どもたちの身体とこころを守るために「薬物乱用防
止教室」を開催します。

資料-75
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
自主防災組織の訓練指導、
応急手当訓練指導の実施
・地域防災力の向上を図るために、自主防災組織の訓練指導を実
施し、子どもたちの防火・防災意識の高揚を図るとともに、防
災リーダーの育成研修や市民スポーツ祭(防災競技)開催時に、
初期消火訓練、煙中体験訓練などを実施します。
・市民に対し、応急手当訓練等を実施し救命率の向上を図るとと
もに、子どもや保護者に向けて、土曜スクールや親子救命講
習・防災体験時に、応急手当訓練などを実施します。
学校園での安全対策の推進
(校門付近での安全監視
等)
犯罪の抑止力、死角となる場所の監視、外部からの侵入防止、
校門付近での安全確保を図るために、学校園における人員配置
等を行います。
2-6 子どもに配慮したまちづくりの推進
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
「赤ちゃんの駅」の登録推
進と情報提供の充実
子育て中の親子が安心して外出できる環境を整備するために、
授乳やおむつ替えのできる施設を「赤ちゃんの駅」として登録
し、ひろく情報提供を行うことで、地域で子育てを支えるまち
づくりを進めます。
大阪府特定優良賃貸住宅の
情報提供
国や地方公共団体等が家賃額と入居者負担額との差額を一定
期間補助し、中堅所得者層向けの良質な賃貸住宅の供給を図る
事業について、その普及を図るため、入居申し込みや受付住宅
等を子育て世代をはじめとする市民に対して広く情報提供を
行います。
八尾市営住宅機能更新事業
における子育てにやさしい
住環境づくり
八尾市営住宅機能更新事業計画(八尾市営住宅長寿命化計画)
に基づき、子育て世帯が安全で安心して住み続けられるよう、
地域におけるまちづくり協議会や住民と協働し、子育てにやさ
しい居住環境の整備を進めます。
多様なニーズに対応する住
情報の提供
住宅マスタープランにおいて重点施策の一つに位置づけられ
た、住情報・住教育の推進を行います。住まいやまちづくりに
関し、多様な世代や世帯に対応した住まいに関する情報の提供
に力をいれ、快適で住み続けたくなるようなまち、住宅づくり
を促進します。
安全で安心して通行できる
道路空間等の整備
交通バリアフリー基本構想に基づき、道路特定事業計画を策定
した駅周辺の道路及び駅前広場などの重点的・一体的なバリア
フリー化を図り、すべての市民が安全・安心して移動できるま
ちづくりを推進します。
市民ニーズを考慮した地域
の公園の整備
子どもからお年寄りまですべての公園利用者の安全確保とと
もに憩える空間の創出及びバリアフリー化等、市民のニーズを
考慮した地域の公園として整備を行います。
公共施設の子育てバリアフ
リー化の推進
子育てバリアフリー化の推進のために整備した庁舎について、
引き続き維持管理することで、子育て世代等が安心かつ快適に
利用できる市役所をめざします。
市営住宅における新婚・子
育て世帯優先入居
市営住宅の空家入居募集において、ひとり親世帯を住宅困窮度
評定の加算項目としています。また、子育て世帯の入居募集を
一般世帯向け募集とは別に募集枠を設けており、3回以上落選
された方については、優遇倍率を適用します。
コミュニティセンター機能
更新における子どもに配慮
した施設整備の推進
コミュニティセンターの施設の安全性・機動性を確保するため
の改修にあわせて、子どもに配慮した施設の整備を行います。

資料-76
2-7 ワーク・ライフ・バランスの推進
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
ワーク・ライフ・バランス
の普及啓発
ワーク・ライフ・バランスの普及啓発を図るため、情報誌等へ
の記事掲載や講座・講演会等を実施します。
勤労者法律相談の実施 労働条件や職場でのトラブルなど、勤労に関する疑問や不安に
ついて、弁護士・社会保険労務士による、月3回(毎月第1・
第3水曜日と最終土曜の午後1時~午後4時)の相談を実施し
ます。
労働情報やお発行 市内事業所や勤労者に、労働に関する各種情報提供や啓発推進
を行うために労働情報やおを発行します。
男性の子育てへの参画促進
に向けた学習機会の提供や
情報の発信
男性の子育てへの参画を促進するため、学習機会の提供や情報
発信を行います。
特定事業主行動計画の推進 職員を雇用する事業主の立場から次世代育成支援対策推進法
に定められた指針を踏まえ、職員が仕事と子育ての両立を通じ
ワーク・ライフ・バランスの実現を図れるよう支援します。
国、府の優良事業所の表彰
等の啓発
国や府が表彰や登録する女性の能力活用や仕事と家庭の両立
支援など意欲ある取り組みを行う事業所をホームページ等で
紹介し、子育てしやすい環境づくりを促進します。

資料-77
3. 子どもの育ちに応じた切れ目のない支援の充実
3-1 次代の親の育成
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
職場体験学習の実施 「職場体験学習」を公共施設、商店、工場、小学校、中学校、
そして幼稚園や保育所等で実施します。
八尾の産業への理解を深め
る機会の提供
・小学生等に八尾の特色である「ものづくり」の認識を深めても
らう機会を提供するために、ものづくり企業と協力し、ロボッ
ト等を活用した出前授業を開催します。
・社会科の授業等において、八尾の特色である「ものづくり」に
ついて学習を深め、将来の八尾の産業を担う人材の育成につな
げます。
技術・家庭科の授業の推進 実践的・体験的な学習活動を通して、家族と家庭の役割、生活
に必要な衣・食・住、情報・産業等について基礎的な理解と技
能を養うとともに「生きる力を育む教育」の授業展開ができる
ように授業実践の交流や研究を進めます。
中学生、高校生が乳幼児と
ふれあう機会の提供
乳幼児とふれあうことで、乳幼児への関心を深め、幼児の心身
の発達と生活、それを支える家族の役割を理解するために、中
学校において「職場体験学習」や技術・家庭科の時間の中で育
児体験を実施します。
子どもや若者のライフプラ
ンニング支援の実施
子どもや若者が自分の将来を考えるきっかけをつくるととも
に、妊娠・出産・育児への関心を高め、次代の親育てや少子化
への対応を進めるため、乳幼児とのふれあい体験や妊娠・出
産・育児に関する情報提供を行います。
3-2 子どもと親の健康増進 ~母子保健計画~
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
保健師・保育士等の連携・
協力体制の強化
・保護者の育児不安を軽減し、安心して子育てできるよう、乳幼
児健康診査・乳児相談・乳幼児のフォロー教室・地域での相談
支援等を保健師と保育士と連携・協力して事業を行います。
・子育て家庭の状況をつかみ、地域子育て支援センター事業や保
育所の地域交流事業での支援につなぐために、保健センターで
の集団検診や連携事業へ保育士が参加し、育児相談、あそびの
紹介や情報提供をします。
妊娠から出産後の支援の推
進
地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化として「母子保
健コーディネーター(助産師)」を配置し、従来のハイリスク
の妊産婦等への支援に加え、より広く、妊産婦等全体を対象と
する相談支援を行います。
妊婦乳幼児健康診査の実施 ・妊産婦や胎児の疾病予防など母子の健康保持を図るため、妊婦
健康診査を実施し、必要な指導を行うとともに、保護者の育児
不安を軽減し、安心して子育てができるよう支援を行います。
・乳幼児の疾病予防と健康保持を図るため、各種健康診査と相談・
指導を行うことにより、保護者の育児不安を軽減し、安心して
子育てができるよう支援します。
妊産婦乳幼児訪問指導の実
施
妊産婦の妊娠中毒症や未熟児出生等の予防を図るとともに、乳
幼児を抱える保護者の育児不安の解消を図るため、妊娠中や出
産後に保健師・助産師による訪問指導を行います。

資料-78
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
こんにちは赤ちゃん事業の
実施
必要に応じた適切なサービス提供に結びつけることによる、子
どもの健やかな育成を図るために、すべての乳児がいる家庭を
訪問し、不安や悩みを聞くことによって、親子の心身の状況や
養育環境の把握と子育て関連の情報提供を行います。
妊婦乳児等保健相談の実施 保護者同士の交流を深め、出産や育児不安を解消するため、妊
産婦・乳幼児の保護者に対して、子どもの疾病予防や育児知識
についての健康相談や健康教室等を開催します。
乳幼児育成指導の実施 乳幼児の心身の健全な発達を促し、保護者の育児不安の解消を
図るため、経過観察が必要と判断された乳幼児に対して健診や
相談教室などのフォロー事業を行います。
未熟児訪問指導等の実施 未熟児を持つ保護者の不安軽減を図り、未熟児の健康管理を行
うために、未熟児に対し保健師・助産師が訪問し、養育上必要
があると認められた場合、未熟児経過観察健康診査や未熟児等
教室につなげる等の支援を行います。
母子健康手帳の交付 妊娠・出産・育児を通じて母子の健康増進を図るために、妊娠
届により母子健康手帳を交付します。
予防接種の実施 感染性疾病の発生及びまん延を防ぎ、子どもの健康を守るた
め、予防接種を実施するとともに、予防接種についての啓発を
行います。
マタニティマークの普及・
啓発
妊娠・出産に関し、安全と快適さを確保し、妊産婦がより安心
して妊娠期間を過ごせるために、マタニティキーホルダーの配
付を行うとともにマタニティマークの普及・啓発を図ります。
自殺対策に関する取り組み
の実施
総合的かつ効果的な自殺対策を推進するために、相談支援事業
の充実及び連絡協議会による関係機関の相互の連携や情報の
共有を図ります。
あなたのまちの健康相談の
実施
妊産婦や乳幼児等の子どもを持つ保護者等の相談事業の充実
を図るために、各コミュニティセンターにおいて、保健師によ
る相談を定期的に実施します。
市立病院における周産期医
療及び小児医療の提供
市立病院において、ハイリスク分娩を含む分娩対応や NICU(新
生児集中治療室)での出生児の受け入れを行うなどにより、周
産期医療を提供します。また、中学生までの内科的な病気の診
断と治療を行う小児医療を提供するとともに、中河内二次医療
圏内の複数の病院において実施されている小児救急医療の輪
番制に協力することで、小児救急への対応を行います。
特定呼吸器疾病予防回復に
関する取り組みの実施
気管支ぜん息やぜん息性気管支炎にかかっている児童の健康
回復を促すため、病気の原因や症状の把握など支援事業を行い
ます。
休日急病診療の実施 土曜日、日曜日及び祝日等の医療空白時間帯における初期救急
医療体制の充実を図るため、休日急病診療所(内科・小児科・
歯科)による対応を行います。
「食」に関する教育のサポ
ート
・次代を担う子どもたちが、望ましい食生活や生活習慣を確立す
ることができるよう、食に関する情報提供や指導方法の工夫に
ついて指導助言を行います。
・子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につ
けることをめざし、食に関するテーマの教職員研修を実施しま
す。
学校や保育所等における子
どもへの食育の推進
・子どもの「食」への関心を高めるとともに、食に関する正しい
知識を習得させ、子どもが自ら考え健全な食生活を実践する力
をつけることができるよう、学校給食を活用した食育の推進及
び学校給食の充実を図ります。

資料-79
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
・保育所において、児童に対してクッキング保育等の調理体験や
食材による食育体験を実施するとともに、保護者に対して食事
サンプルの展示や啓発文の配布等を行います。また、在宅の子
育て家庭を対象とする試食会の開催等、食への関心を高める取
り組みにより食育の推進を図ります。
・子どもたちに農業への親しみと地産地消の理念に基づく食の大
切さを感じてもらうために、農業者や JA 等と協力し、子ども
たちに野菜の栽培・収穫体験を実施します。
保健センターにおける食育
の推進(離乳食、幼児食の
正しい知識の普及)
・保護者同士の交流を深め、育児不安を解消するため、妊産婦・
乳幼児の保護者に対して離乳食講習会等を開催します。
・妊産婦及び乳幼児の保護者に対して正しい食生活の普及を図
り、母子の健康づくりを推進するため、正しい食生活について
学ぶ機会づくりとして幼児栄養教室や栄養相談を実施します。
薬物乱用の防止教育の推進 子どもの発達段階に応じた各学校園での取り組みを指導する
とともに、薬物乱用防止教室等の活用など、関係諸機関との連
携の強化を支援することで、薬物乱用の防止教育を推進しま
す。
HIV/エイズ教育の推進 エイズに関する正しい知識や理解を深めるとともに、他教科お
よび道徳教育や人権教育とも関連づけながら、児童・生徒の発
達段階に応じた内容を学校園において指導するよう支援しま
す。
喫煙や薬物・飲酒の防止等
に関する教育の推進
保健体育や道徳等の教育過程において、喫煙、飲酒、薬物乱用
防止に関する教育の充実を図ります。
こころの悩み等に関する教
育の推進
スクールカウンセラーの有効活用や教諭の指導により、子ども
に関する問題行動への対応や心の悩みに対する相談等を進め
ます。
3-3 幼児教育・保育の充実
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
幼保一体化の推進 就学前児童に質の高い幼児教育・保育を提供するために、幼保
一体化を推進します。
幼・保・小合同研修会の開
催
就学前児童への質の高い幼児教育・保育の提供と小学校へのス
ムーズな接続をめざし、幼稚園教員、保育所保育士、小学校教
員を対象とする幼保小合同研修会を開催します。
通常保育事業の実施 年間目標・年間計画・月別カリキュラムからなる保育計画を作
成し、これに基づいて週予定・日々の保育計画を立て年齢別に
保育を実施します。また、小学校への接続が円滑なものとなる
よう公民協働で 5歳児の保育要録を活用します。
保育所・認定こども園等の
整備の推進
・待機児童の解消、多様な保育ニーズへの対応、子どもの安全確
保のために、保育所等の創設や増改築、大規模修繕等の整備に
ついて、計画的に推進します。
・保育所入所児童の安全確保のため、老朽化した保育所の大規模
改修工事を行います。
保育所における第三者委
員・苦情解決の対応
公立保育所で苦情が発生した場合に、苦情解決責任者(所長)、
苦情受付担当者(所長補佐)、第三者委員(主任児童委員)の
体制で対応します。また、私立保育所においても、第三者委員
を設置する等により苦情解決への対応を行ないます。

資料-80
3-4 子育て支援サービスの充実
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
(仮称)子どもセンターの
検討
家庭や地域と連携し安心して生み育てられる環境づくりを進
め、子どもの育ちを総合的に支援する体制を充実させるため
に、子ども・子育ての総合的な支援拠点の設置を検討します。
地域子育て支援センターに
おける妊産婦・親子の交流
の機会提供
・出産を控えた妊婦が出産後の育児等へのイメージを持つこと
で、スムーズな育児につなげ、母子の心の安定を図るとともに、
親の子育て力の向上をめざすため、仲間づくりや情報交換の場
を提供します。
・在宅子育て家庭の保護者が育児不安の解消等により安心して子
育てできる環境を整備するために、在宅子育て家庭に対して、
親子教室や様々な事業を実施し、育児に関する情報提供や相談
指導を行います。
つどいの広場における交流
の機会提供
乳幼児とその保護者が気軽に集い、打ち解けた雰囲気のなかで
語り合い、相互に交流を図る場を提供します。
養育支援訪問による相談・
指導・助言の実施
養育支援が特に必要であると判断した家庭に適切な養育の実
施を確保するために、子育てパートナーを派遣し、養育に関す
る相談、指導、助言等を行います。
ママ・サポート事業による
家事支援の実施
昼間に出産後の母親及び乳児の介助をする者がいない家庭に
おいて安心して育児を行うための環境を整えるために、家庭訪
問による適切な家事支援等を行ないます。
ファミリー・サポート・セ
ンター事業の実施
市民が仕事等と育児を両立できる環境を整備し、地域における
子育て支援と児童の福祉の向上を図るために、地域において育
児の援助を行いたい人と、援助を受けたい人がお互い会員とし
て登録し、育児に関する相互扶助と奉仕の精神に基づく援助活
動を行います。
一時預かり事業の実施 安心して子育てができる環境整備を推進し、福祉サービスの充
実を図るために、在宅で子育てする保護者の心理的・身体的負
担軽減や疾病や災害で一時的に保育が困難になった家庭の就
学前児童に対して、一時的な保育のサービスを提供します。
延長保育の実施 保護者の就労形態の多様化により、通常保育時間帯を超える保
育を必要とする児童を延長して保育します。
休日保育の実施 保護者の就労形態が多様化するなかで、休日等においても保育
を必要とする児童に対応するため、休日等に保育所等で児童を
保育します。
市立・私立幼稚園における
預かり保育の実施
・多様化する保護者ニーズへの対応や幼児の健全育成を支援する
ために、幼稚園に通園する園児の保護者の希望に応じ、通常保
育時間を越えて預かり保育を実施します。
・私立幼稚園との連携を図り、預かり保育や園庭開放、子育て相
談など、地域における子育て支援サービスを提供します。
子育て短期支援事業の実施
(ショートステイ事業、ト
ワイライトステイ事業)
児童を養育している家庭の保護者が社会的な理由等で、家庭に
おける児童の養育が一時的に困難となった場合、児童福祉施設
等で一定期間養育及び保護します。
病児・病後児保育事業の実
施
保護者の就労などにより、子どもが病気の際に自宅での保育が
困難な場合、病院・保育所で病気の児童を一時的に保育します。
簡易保育施設における保育
サービスの提供
保育所等に入所を希望しながら入所できない0~1歳児に対
して簡易保育施設での保育サービスを提供します。

資料-81
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
保育所における在宅子育て
支援事業の実施
子育て家庭にとって身近な地域での支援の充実を図るために、
保育所に通っていない就学前児童とその保護者を対象とし、保
育所で園庭開放事業や地域交流事業、相談事業などを実施しま
す。
市立幼稚園における幼児教
室・4歳児教室の実施
市立幼稚園を地域に開放し、子育て家庭への支援及び地域の教
育力の向上のため、市立幼稚園において幼児教室及び4歳児教
室を開設します。
えほんデビュー事業の実施 絵本の読み聞かせを通して、親子の心を通わせる時間をもてる
ように支援するために、4か月健康診査来所時に乳児と保護者
に絵本を配布します。
桂・安中青少年会館におけ
る子育て支援教室・講座の
実施
・保護者の子育てを支援することで、幼児の健全な成長を促すた
めに、就学前の乳幼児とその保護者を対象にお話教室やリズム
体操、体操教室、遊び教室、工作教室、料理教室等を開催しま
す。また、ベビーマッサージ教室として0歳児とその保護者を
対象に、親子幼児教室として、1歳児から5歳児とその保護者
を対象に、ファミリー教室として3歳児から5歳児とその保護
者を対象に実施し、長期教室として月2回ウクレレ教室を実施
します。
・育児についての悩みの解消や、教育力の向上、遊び場の提供等
子育て支援を目的に、乳幼児、保護者を対象とした活動を通じ
て、保護者間の交流を図るとともに、多くの人々と関わる中で、
他人を思いやる心や人権感覚を自然に身に付けることをめざ
し、親子幼児教室や子育て支援講座、遊戯室開放等を実施しま
す。
安中青少年会館における出
前絵本の会の実施
子どもたちが読書に慣れ親しむことにより、人間性豊かな感性
や情緒を育むことを目的として、「絵本の会」「おはなしラン
ド」「出前絵本の会」を実施し、参加者に対し、絵本や人形劇
等に触れる機会を提供します。
3-5 子どもの生きる力を育てる学校の教育環境等の整備
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
学力向上の推進
・児童・生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導の一層の充実
を図るとともに、中学校区を単位とした授業改善や校種間連携
について研究を推進します。また、「八尾市教育フォーラム」
を開催し、保護者や市民への教育への関心を高めます。
・全中学校にネイティブ英語指導者(NET)を配置し、英語教
育の充実を図るとともに、市内全小学校でもNETを活用し、
児童が外国の生活や文化に慣れ親しんだりするなど、国際社会
を生きる基礎となる教育を推進します。
・各学校における保健体育科の授業研究会において、指導方法の
工夫改善等を通して、新しい課題に応じた情報の学びや、授業
の質を高める技術の向上を図ります。
・教職員が学校の目標達成に向けた個人目標を主体的に設定し、
学校長はその達成状況や業務遂行上で発揮された能力を育成
の観点をもって評価することで、教職員の意欲・資質能力の向
上を図るとともに、学校教育の活性化を図ります。
子どもの心に響く道徳教育
の充実
学校・家庭・地域が一体となったあいさつ運動の推進を図ると
ともに、道徳の授業を公開するなど思いやりの心や規範意識な
どの道徳性を育む活動の充実に向けた取り組みを支援します。

資料-82
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
読書推進援助事業の実施 子どもの読書環境を豊かにするために、学校図書館との連携・
援助、ブックスタートへの協力、読書通帳の発行推進等による
子育て支援を実施します。
学校図書館の利用促進と図
書環境の充実
各小中学校に学校図書館サポーターを配置し、児童・生徒の図
書館利用を促進し、学校図書館の効果的な活用を図るととも
に、図書環境の充実と魅力ある学校図書館づくりを進めます。
人権学習教材等の整備と活
用
学校園における人権教育の推進を図るため、人権学習プログラ
ム「人権教育推進のための手引き」の作成及び人権教育関係資
料・教材(書籍・視聴覚教材)の整備を行います。
生徒指導対策事業による子
どもの健全育成の推進
多発する生徒指導上の諸問題への早期発見、適切な対応、未然
防止に向けた関係諸機関等との連携や研修会の開催を実施し
ます。また、八尾市小・中生活指導研究協議会へ委託し、子ど
もたちの健全育成の推進を図ります。
健康に関する教育の推進 子どもたちの「生きる力」を育むため、健やかな体の更なる育
成をめざすため、体力向上に結びつく「プログラム」を検討し、
実践につなげます。また、健康教育の観点から歯みがき指導を
行い「健やかで心豊かな子ども」を育成します。
食育の推進 子どもの「食」への関心を高めるとともに、食に関する正しい
知識を習得させ、子どもが自ら考え健全な食生活を実践する力
をつけることができるよう、学校給食を活用した食育の推進及
び学校給食の充実を図ります。
子どもが輝く学校園づくり
支援事業の実施
特色ある学校園づくりとともに、今日的な教育課題の解決と学
校の活性化をめざし、児童・生徒や地域の実態に応じた取り組
みを推進します。
学校園施設耐震化及び施設
整備
・子どもたちが安全・安心して学校園施設を利用できるよう学校
園施設の耐震化事業を優先して行います。
・子どもたちが安全・安心して学校園施設を利用できるよう、老
朽化に伴う危険・不具合箇所の改修や特別教室以外の教室への
空調機器設置など計画的な施設改善を実施します。
学校評議員の設置 地域や社会に開かれた特色ある学校づくりを進めるため、校長
の求めに応じて学校運営について意見を述べ、また、連携協力
等のあり方について協議を行う学校評議員を各学校に設置し
ます。
学校園等安全教室・CAP
(子どもへの暴力防止プロ
グラム)子どもワークショ
ップの実施
・不審者侵入や負傷者が発生した場合の対応等、学校園の危機管
理対応能力の向上等を図るため、教職員等を対象に学校園等安
全教室を開催します。また、児童が自らを「価値ある存在」で
あると認識するとともに、暴力から逃れる方法等、児童が自分
の身を自分で守れるための知識や具体的な技術(スキル)を身
につけるため、CAP子どもワークショップを小学生を対象に
実施します。
・学校園の安全管理体制の確立のため、避難訓練(不審者侵入想
定)や関係機関より講師を招聘して防犯教室を実施します。
スクールサポーターの派遣 学校園現場での様々な教育活動における子ども支援の補助を
行うために、学校園の状況や要請に応じ、教育系・心理系大学
の学生や社会人等地域人材の活用によるスクールサポーター
を派遣します。
国際教育プログラムの推進 小中高校で実施される国際教育プログラムをサポートし、次代
を担う青少年が異文化理解を深め、多文化共生を推進するため
の事業を実施します。

資料-83
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
友好都市上海市嘉定区との
青少年交流団派遣・受入の
実施
異文化に触れ、国際感覚を養うとともに、相互理解と友好を深
めることを目的として、友好都市上海市嘉定区と隔年で青少年
交流団を派遣します。
国際理解教育に関する取り
組みの実施(多文化共生・
国際理解教育事業及び交流
事業、桂・安中青少年会館
における国際理解に係る教
室・講座の実施など)
・他者に対する理解や広い視野の醸成に資するために、映像や音
楽、衣装、料理等を通じ体感しながら国際理解に係る取り組み
や英会話教室を実施します。
・豊かな心の育成を目指し、さまざまな機会を通して豊かな感性
や人権感覚を養う活動の一環として、国際理解に係る教室・講
座等を実施します。
・豊かな心の育成を目指し、さまざまな機会を通して豊かな感性
や人権感覚を養う活動の一環として、低学年育成事業におい
て、国際理解に関する取り組みを実施します。
・市内に住む在日外国人児童、生徒を対象にした多文化共生、国
際理解教育事業を実施するとともに、市内の外国人同士及び日
本人との交流事業を実施します。
桂・安中青少年会館におけ
る障がい者(児)との交流
・子どもたちが障がいについて理解するために、障がい者が実践
しているコミュニケーションやスポーツ活動の体験教室・講座
等を実施します。
・障がい者が実践しているコミュニケーションやスポーツ活動を
通じて、障がいについて理解する契機とし、豊かな感性や人権
感覚を養うことを目的として、障がい者理解に係る体験教室・
講座等を実施します。
・障がい者が実践しているコミュニケーションやスポーツ活動を
通じて、障がいについて理解する契機とし、豊かな感性や人権
感覚を養うことを目的として、低学年育成事業において、障が
い者理解に関する学習を実施します。
環境教育やごみの分別・減
量等に関する教育・啓発の
実施(環境教育、エコクラ
ブの活動支援、子ども向け
環境イベント、出前講座、
リサイクルセンター学習プ
ラザにおける啓発など)
・市民等が環境の保全と創造について関心と理解を深め自主的な
活動を促進するため、環境教育・学習、啓発活動を推進します。
また、市民等が行う環境保全活動を支援し指導者の育成を図り
ます。
・ごみの分別や減量につき、関心を持ちやすくし、より身近なも
のとして身につけられるよう、学校園やリサイクルセンターな
どにおいて、ごみ収集に関する紙芝居の実施や、塵芥車・ごみ
の収集作業の紹介などの啓発活動を実施します。
・ごみの3R[リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、
リサイクル(再生利用)]の推進拠点として環境をテーマとし
た講座や廃棄物のリサイクル体験をはじめとした各種イベン
トの開催の他、社会見学の受入や市民活動の支援等を行いま
す。
上水道・下水道出前講座の
実施
・水の循環という観点から下水道全般について学んでもらうとと
もに、環境問題に関心をもってもらうことを目的として、小学
校等に出向き講義や実験を行います。
・市内の公立小学校の4年生を対象に、地球上に限りある水を私
たちが利用することについて、その水がどのようにして安心し
て飲める水として作られ、各家庭に配られているかを学ぶこと
で興味をもってもらい、社会環境に目を向ける一助となること
を目的に講義を行います。
ロボットプログラミング連
続教室の実施
中学生を対象としたプログラミング教室を実施します。

資料-84
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
世代間交流の実施 地域の人や自分の家族などの身近な人について考えるきっか
けとなるために、保育所に通っている子どもと高齢者の交流事
業を実施します。
文化財施設における郷土の
歴史・文化財の学習機会の
提供
文化財施設を活用して、子どもたちが文化財に触れる機会を増
進し、郷土の歴史や文化への愛着を高めることができるよう、
各施設の特徴を活かした体験学習を中心としたイベント等を
実施します。
芸術文化における学習機会
の提供(ワークショップ「み
んなで能の世界を体験しよ
う!」、吹奏楽のまち八尾
への取り組みなど)
・高安地域は能楽ワキ方・大鼓方の流儀「高安流」の発祥の地で
あり、能の名曲「弱法師」「井筒」の背景にもなった能楽と縁
の深い地であることを知ってもらい、地域文化への理解を深
め、自分たちの街に誇りをもつきっかけとするために、能の舞
台の鑑賞やそこで使用する楽器の演奏体験などを行います。
・演奏技術の向上と演奏の場を広げることにより、市民全体が吹
奏楽に触れ、楽しむことができるようなまちづくりをめざすた
めに、八尾吹奏楽フェスティバルの開催や吹奏楽アートマネー
ジャーによる小中学校吹奏楽普及事業、まちかど吹奏楽などを
行います。
3-6 放課後の子どもの活動等の充実
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
放課後子ども教室推進事業 心豊かで健やかな子どもを社会全体で育むため、学校を活用し
て安全・安心な子どもの活動場所を確保するとともに、地域の
ボランティアの方々が中心となり、放課後や週末における体
験・交流活動等を実施します。
放課後児童健全育成事業
(放課後児童室事業)
保護者が就労、疾病等により不在となる小学校全学年児童を対
象に、放課後に学校施設等を利用して遊びやスポーツ等を通じ
た健全育成事業を実施します。
「放課後子ども総合プラ
ン」に基づく取り組みの検
討
国の「放課後子ども総合プラン」に基づき、同一小学校で実施
されている放課後児童室と放課後子ども教室の連携強化を図
るとともに、放課後等の子どもの過ごし方について検討しま
す。
3-7 情報提供体制の充実
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
子育て総合支援サイト「み
らいねっと」による情報提
供
子育て家庭等が必要な情報を必要な時に得られるよう、子育て
総合支援サイト「みらいねっと」の運用を行うとともに、フェ
イスブックの活用により、子育て家庭に必要な情報を発信・提
供します。
「子育てお・う・え・ん BOOK」
の作成・配布
年度毎に「子育てお・う・え・ん BOOK」を作成し、各出張所、
保育所、幼稚園等に配布、設置します。
「八尾っ子せいちょうぶっ
く」の作成・配布
子どもの成長記録や、様々な子育て支援の場で活用する「八尾
っ子せいちょうぶっく」を母子手帳といっしょに配布します。
市窓口や子育て支援拠点に
おける子育てに関する情報
提供
・子育て家庭等が必要な情報を必要な時に得られるよう、市窓口
や子育て支援拠点に「子育てお・う・え・ん BOOK」や「子育て
MAP」を設置します。
・窓口やホームページ・市政だより等の媒体を通じて幼稚園・保
育所等の施設の利用者や希望者へ情報提供を行います。

資料-85
3-8 子育て支援サービスの相談体制の充実
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
(仮称)子どもセンターの
検討
家庭や地域と連携し安心して生み育てられる環境づくりを進
め、子どもの育ちを総合的に支援する体制を充実させるため
に、子ども・子育ての総合的な支援拠点の設置を検討します。
子育て総合支援ネットワー
クセンターにおける相談支
援の実施
子育てしやすいまちづくりの推進のため、発達面や情緒面に支
障をきたすおそれのある子どもやその保護者に対して子育て
等に関する各種相談を行います。
保育士・保健師等による一
体的な相談支援の推進(親
子 de 絵本推進事業の実施)
地域での子どもや子育て世代の居場所づくりや子育て支援の
充実を図り、保護者の子育て力の強化や子どもの成長を支えら
れるよう、コミュニティセンターに絵本を配架し、保育士・保
健師等による読み聞かせや育児相談などを実施します。
家庭支援推進保育所事業に
よる不安を抱える家庭への
支援の実施
家庭環境に配慮を要する入所児童への直接的な支援を細やか
に行うとともに、在宅支援として、地域交流会や子育て支援セ
ンターあそび会において、子育てに不安や問題を抱えている親
への支援を実施します。
就園・就学相談の実施 障がいのある幼児・児童本人や保護者の教育的ニーズを踏ま
え、就園・就学後も円滑に学校園生活を送ることができるよう、
関係機関と連携しながら、専門的な立場から就園就学相談を行
います。
女性相談の実施 女性の抱える様々な悩みに対応するため、女性相談員による相
談事業を実施します。
保育所や幼稚園における相
談・援助の実施
・保育所に通っていない就学前児童の保護者を対象に、公立保育
所・私立保育所で、子ども・子育てに関する相談を行います。
・地域における幼児教育センター的役割を担うため、未就園児の
保護者への子育て相談・入園相談を適時実施します。
利用者支援事業による相談
支援の充実
1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会
の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、または妊娠
している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域
の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行
うことを目的とし、子ども又はその保護者の身近な場所で、教
育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に
応じ相談・助言等を行います。
コミュニティソーシャルワ
ーカーの配置
市内 3か所のいきいきネット相談支援センターに CSW(コミュ
ニティソーシャルワーカー)を配置し、福祉的な支援が必要な
方に、各関係機関と連携しながら支援を行います。
3-9 ひとり親家庭等の自立支援 ~母子家庭等及び寡婦自立促進計画~
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
母子・父子自立支援員の配
置
母子家庭等の自立を総合的に支援するために母子・父子自立支
援員を配置し、ひとり親家庭等からの相談に対応します。
ひとり親家庭の子どもの保
育所への優先入所
ひとり親家庭の子どもの保育所等入所を優先して行います。
ひとり親家庭保育支援事業
の実施
母子生活支援施設の保育機能を活用し、ひとり親家庭の子ども
(0~2歳児)に対して保育サービスの提供を行います。
母子家庭等日常生活支援事
業の実施
母子家庭等で、生活に援助が必要であると認められる場合また
は生活環境が激変して日常生活に著しい支障が生じている場
合に、家庭生活支援員が家事支援等を行います。

資料-86
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
母子家庭等自立支援給付金
事業の実施
母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り
組みを支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため
に、資格取得への支援等の給付金事業を実施します。
地域就労支援事業の実施 ・就労困難者等の職業能力を高めるため、就職につながりやすい
各種 講座を実施します。
・市内3か所ある地域就労支援センターにおいて、就労困難者等
に対する就労支援を実施します。また、就労につながる生活上
の課題解決を図る「就労・生活相談事業」や就労支援の 2次的
窓口である「八尾市パーソナル・サポート事業」及び就労困難
者等に対し個別職業紹介等を行う「八尾市無料職業紹介事業」
等と連携し、就労困難者等に対する就労支援を実施します。
・ひとり親家庭の親を含む就労困難者等に対し、求人事業所の理
解を深め、また、求職者とのマッチングを図るために、①障が
い者雇用を考える集い②就職フェアやお・かしわらを開催しま
す。
児童扶養手当の支給 児童が、父又は母の離婚・父又は母の死亡・父又は母の重度障
がい・父又は母の生死不明・父又は母から1年以上遺棄されて
いる・父又は母の1年以上の拘禁・婚姻によらない出産等によ
り、父又は母に監護されているか父又は母にかわる人に養育さ
れている場合に、その父、母又は養育者に対して、児童が 18
歳に達する日以降最初の3月末まで(児童に障がいがある場合
は 20 歳まで)、手当を支給します(所得制限あり)。
ひとり親家庭医療費公費負
担制度による助成
ひとり親家庭の生活の安定と児童の健康増進、福祉の向上を図
るため、医療保険により受診した場合に医療費の一部自己負担
額を控除した額を公費で負担します(所得制限あり)。
母子生活支援施設への入所 母子家庭で、居宅で生活することが児童の福祉に欠ける場合又
は居宅が無い場合の母親と子どもの生活の安定を確保するた
めに、母子生活支援施設にて必要な保護を行います。
母子緊急一時保護制度によ
る支援
精神的または経済的に緊急の保護を必要とする母子世帯につ
いて、指定施設において一時的に保護し、必要な相談・指導を
行います。
母子父子寡婦福祉資金貸付
制度の周知
ひとり親家庭の経済的自立の助長、生活意欲の助長、子どもの
福祉増進を目的とし、貸付資金の活用を通じて総合的に自立を
支援します。
3-10 障がいのある子どもや家族への支援
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
介護給付事業・障がい児通
所給付事業・地域生活支援
事業の実施
・障がいのある児童が日常生活を営む上で、必要な介護支援を提
供します。
(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、
重度障がい者等包括支援、計画相談支援、療養介護、生活介護、
施設入所支援)
・障がいのある児童に必要な通所サービスを提供します。
(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援、障がい児計画相談支援)
・障がいのある児童が、能力や適性に応じ自立した日常生活又は
社会生活を営めるよう、必要な支援を提供します。
(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター)

資料-87
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
保育所での障がい児保育の
実施
障がい児を集団保育することにより、児童の心身の発達を促す
ために、専門講師による巡回指導を行い、一人一人の子どもの
発達に応じた保育のための必要な助言を受けるとともに、保護
者への支援として、保護者相談を実施します。
放課後児童健全育成事業
(放課後児童室事業におけ
る障がい児の受け入れ)
保護者が就労、疾病等により不在となる小学校全学年児童を対
象に、放課後に学校施設等を利用して遊びやスポーツ等を通じ
た健全育成事業として実施する放課後児童室に、障がいのある
子どもの受け入れを進めます。
市立医療型児童発達支援セ
ンター(いちょう学園)に
おける支援の実施
・肢体や体幹の機能障がいや発達に遅れのある就学前児童への療
育・訓練、保護者への育児に関わる指導、助言を行うとともに、
他の児童福祉施設等に通う児童の保護者並びに施設職員等に
対して支援します。
・子どもの障がいの早期発見・早期治療とともに、発達の遅れや
個人差のある就学前児童に対して理学療法士等の専門職によ
る助言や指導により発達を支援するとともに、保護者への育児
指導、子育て相談等を実施します。
・発達に遅れのある就学前児童に対して、集団又は個別保育によ
る療育を行います。
市立福祉型児童発達支援セ
ンター(八尾しょうとく園)
における支援の実施
発達に遅れのある就学前児童を対象に、通所によって適切な指
導・療育を行い、自立生活に必要な知識や技能を習得させる等
により、心身の発達を支援します。
障がい者(児)歯科予防教
室の実施
障がい児の円滑な歯科健診を促すとともに、歯科疾患の予防に
よる健康増進を図るためにブラッシング指導を行います。
就園・就学相談の実施 障がいのある幼児・児童本人や保護者の教育的ニーズを踏ま
え、就園・就学後も円滑に学校園生活を送ることができるよう、
関係機関と連携しながら、専門的な立場から就園就学相談を行
います。
特別支援教育推進事業の実
施
障がいのある幼児・児童・生徒の教育の充実を図るための推進
体制の確立を進めるとともに、教育・医療・福祉等の連携によ
り、特別な支援を必要とする子どもや保護者に対して総合的な
支援を行います。
市立学校園(幼稚園・小学
校・中学校)への介助員の
配置
障がいのある幼児・児童・生徒が、障がいの状況や課題に応じ
た教育を受けられるよう、介助員や特別支援教育支援員等を配
置する人的支援を行います。また、特別支援教育に対する理解
を深めるため、研修会を実施します。
特別支援教育振興事業の実
施
障がいのある子どもの教育の充実を図るための環境整備や人
的支援を行い、特別支援教育の充実を図ります。
特別児童扶養手当の支給 精神または身体に障がいのある 20 歳未満の児童を監護してい
る父親または母親もしくは養育者に対して手当を給付します
(所得制限あり)。
障がい児福祉手当の支給 身体障がい者手帳の1級・2級程度(各部位別)、最重度の知
的障がいまたは精神障がい、その他これらと同等程度と認めら
れる状態のいずれかに該当する 20 歳未満の在宅者で、日常生
活において常時介護が必要な人に対して手当を支給します。
障がい者(児)医療費公費
負担制度による助成
重度の身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)に対し医療
費の一部を助成します。
発達障がい児支援センター
における発達障がい児の療
育、保護者支援の実施
発達障がい児支援センターにおける発達障がい児の療育及び
保護者支援を社会福祉法人へ委託して実施します。

資料-88
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
八尾市立障害者総合福祉セ
ンターにおける障がい者の
自立と社会参加の促進
在宅の障がい者の自立と社会参加の促進を図るための拠点施
設である障害者総合福祉センターの円滑な運営を行います。
3-11 外国人家庭への子育て支援 具体的施策を実現するため
の取り組み 取り組み内容(平成 26年度)
子育て相談・窓口対応時の
コミュニケーションの支援
相談、窓口での説明、保育所等入所受付等の各種手続きのとき
に、外国語の通訳(中国語・ベトナム語)で対応します。
帰国・外国人児童生徒受入
等の支援
日本語指導が必要な在日外国人幼児・児童・生徒の受け入れ体
制を整備し、在日外国人幼児・児童・生徒の実態に応じ、日本
語指導等により学習面への支援を図るとともに生活面での適
応を図る。また、民族クラブ活動の支援等を通して、市立幼稚
園、小・中学校における国際理解教育を推進します。
多言語における案内文書等
の作成
保育所等入所の手続きを円滑にできるように、中国語・ベトナ
ム語による「保育利用あんない」を配布します。 3-12 子育て家庭への経済的支援
具体的施策を実現するための取り組み
取り組み内容(平成 26年度)
児童手当の支給 家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担
う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了ま
での児童を養育している保護者に対して、手当を支給します
(所得制限あり)。
子ども医療費公費負担制度
による助成
子どもの健全育成・児童福祉の向上を図るため、医療保険によ
り受診した場合に一部自己負担額を控除した額を公費で負担
します(所得制限あり)。
未熟児養育医療給付による
助成
対象となる未熟児の保護者の申請により、必要な費用のうち一
定の負担を保護者から徴収し、その残額を給付します。
助産施設への入所制度によ
る支援
出産費用を捻出ができない方が、安心して助産施設を利用し出
産できるように、生活保護世帯及び市民税非課税世帯につい
て、出産費用の一部を負担します。
私立幼稚園就園奨励費によ
る助成
私立幼稚園に就園する園児の保護者に対して、所得状況に応じ
た補助金を交付し、入園料及び保育料の経済的負担の軽減を図
ります。
私立幼稚園就園助成費によ
る助成
市内の私立幼稚園に就園する園児の保護者で、就園奨励費対象
外等の保護者に対して、経済的負担の軽減を図ります。
就学援助事業による助成 経済的理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者に対し必
要な援助を行います。
奨学金による負担軽減 「八尾市奨学基金」から生ずる果実等をもって、奨学生及び保
護者の高等学校等への修学に対する経済的負担軽減を図りま
す。
子どもの貧困対策に関する
検討
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されるこ
となく、夢と希望を持って成長していける社会の実現をめざ
し、国・府の動向を踏まえながら、子どもたちがおかれる貧困
の実態を踏まえた、教育・生活・保護者に対する就労・経済的
支援策について、調査研究を行います。
生活困窮者自立支援制度の
推進
生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立支援制度によ
り、生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援する
ため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な自立促進支援の
取り組みを進めます。

資料-89
八尾市子ども・子育て会議条例
八尾市条例第24号
八尾市子ども・子育て会議条例
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規
定に基づき、本市に八尾市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。
⑴ 法第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
⑵ その他本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項を調査審議するこ
と。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
⑴ 学識経験を有する者
⑵ 関係団体の推薦を受けた者
⑶ 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
⑷ 公募の市民(法第6条第2項に規定する保護者を含む。)
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代
理する。
(専門部会)
第6条 子ども・子育て会議は、専門的事項を分掌させるため必要があると認めるときは、専門
部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、子ども・子育て会議に属する委員のうちから会長が指名する。
3 部会に座長及び副座長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 座長は、当該部会の事務を掌理する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって子ども・子育て会議
の議決とすることができる。
(会議)
第7条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

資料-90
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議
長の決するところによる。
4 前3項の規定は、部会の会議について準用する。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、子ども・子育て会議の議事に関係のある者の出席
を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が
定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 最初に招集される子ども・子育て会議の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が
招集する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八尾市条例第166
号)の一部を次のように改正する。
「
別表中 八尾市児童福祉審議会委員 を
」
「
八尾市児童福祉審議会委員
八尾市子ども・子育て会議委員
」 に改める。

資料-91
子ども・子育て会議 委員名簿
平成 26 年度八尾市子ども・子育て会議委員
条例によ
る委員
区分
機関 委員氏名
子ども・子育て
支援事業計画
策定部会
学識経験を
有する者
相愛大学人間発達学部教授 中西 利恵
大阪大谷大学人間社会学部教授 農野 寛治 ●(座長)
関係団体の
推薦を受け
た者
大阪府八尾警察署 内山 精二
八尾市自治振興委員会 川﨑 吉継
八尾商工会議所 倉内 雅寛 ●
八尾市民生委員児童委員協議会 新坂 清美
一般社団法人 八尾市医師会 玉田 育子
大阪府八尾保健所 鳴海 好彦
一般財団法人 八尾市人権協会 西川 弥生
八尾市女性団体連合会 二宮 久子
八尾市母子寡婦福祉会 藤田 紀子
八尾市地区福祉委員長連絡協議会 村井 松之助
八尾市青少年育成連絡協議会 村尾 佳代子
子ども・子
育て支援に
関する事業
に従事する
者
八尾私立保育連盟 木村 百合加 ●
八尾市私立幼稚園協会 小 尚子 ●
市立小学校校長会 前田 稔 ●
特定非営利活動法人 KARALIN 松田 直美 ●
市立幼稚園園長会 山口 久美子 ●
子どもの保
護者
公募委員(幼稚園) 卯川 美樹 ●
公募委員(保育所(園)) 吉澤 利和 ●
公募委員(放課後児童室) 鷲田 小百合 ●
労働者を代
表する者 公募委員 木村ムジカ 由加里 ●
公募の市民
公募委員 髙砂 美香代
公募委員 遠嶋 敦子
公募委員 西田 伸恵
(各委員区分毎の氏名五十音順・敬称略)

資料-92
八尾市子ども・子育て支援推進本部設置要綱
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65号)第 61条に基づく市町村子ども・子育て
支援事業計画(以下「事業計画」という。)及び次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第
120号)第8条に基づく市町村行動計画(以下「行動計画」という。)、その他本市の子ども・子
育てに関する施策の円滑な推進にあたり、庁内関係部局からなる、八尾市子ども・子育て支援
推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を所管する。
(1) 事業計画及び行動計画の総合的かつ効果的な推進に関すること。
(2) 事業計画及び行動計画における各事業の実施状況の把握及び公表に関すること。
(3) 事業計画及び行動計画の見直しに関すること。
(4) 子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援及び次世代育成支援等に関する啓発に
関すること。
(5) その他本市における、子ども・子育てに関する講ずべき施策に係わる基本方針の協議に関
すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長及び副本部長並びに本部役員で組織する。
2 本部長は市長、副本部長は副市長、教育長、病院事業管理者及び水道事業管理者をもって充
てる。
3 本部役員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部会議は、必要に応じ本部長が招集し、議長は本部長とする。
2 本部長に事故のあるときは、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 本市における子ども・子育てに関する施策の推進にあたり、推進本部の所管事務を円滑
に推進し、講ずべき施策の検討を行うため、推進本部の下に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者で構成する。
3 幹事会には座長、副座長を置き、座長はこども政策課長を、副座長は教育政策課長をもって
充て、必要に応じて座長が会議を開催する。
4 幹事会は、協議事項に応じて、別表第2の中から幹事を招集し、開催することができる。
5 幹事会の座長が必要と認めるときは、幹事会の幹事以外の職員を出席させ、意見又
は説明を求めることができる。
(ワーキング会議)
第6条 幹事会の運営を円滑に行うために、幹事会の下にワーキング会議を置くことがで
きる。
2 ワーキング会議は、子ども・子育てに関する施策の推進に関する調査研究に必要な職員で構

資料-93
成する。
3 ワーキング会議には、座長、副座長を置き、座長にはこども政策課の職員、副座長には教育
政策課の職員をもって充て、必要に応じて座長が会議を招集する。
4 ワーキング会議は、協議事項に関係のある関係課のみで開催することができる。
(事務局)
第7条 推進本部の事務局は、こども未来部こども政策課、生涯学習部教育政策課とする。
2 事務局は、必要に応じて事務局会議を開催することができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等に関し、必要な事項は本部長が定め
る。
附 則
この要綱は、平成17年5月12日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年6月7日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年5月25日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月14日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年5月24日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年5月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

資料-94
別表第1
政策企画部長
総務部長
人事担当部長
財政部長
人権文化ふれあい部長
市民ふれあい担当部長
健康福祉部長
健康推進担当部長
こども未来部長
経済環境部長
建築都市部長
公共施設建設担当部長
土木部長
会計管理者
消防長
市立病院事務局長
水道局長
教育次長
生涯学習部長
学校教育部長
市議会事務局長
監査事務局長
別表第2
政策企画部 政策推進課長
総務部 総務課長
財政部 財政課長
人権文化ふれあい部 人権政策課長
健康福祉部 地域福祉政策課長
こども未来部 こども政策課長
経済環境部 産業政策課長
建築都市部 都市政策課長
土木部 土木総務課長
会計課 会計課長
消防本部 消防総務課長
市立病院 企画運営課長
水道局 経営総務課長
生涯学習部 教育政策課長
学校教育部 学務給食課長
市議会事務局 議事政策課長
子ども・子育て施策に関連する事業担当課長

資料-95
用語集
<か行> ○校区まちづくり協議会
各小学校区(地域の活動の状況に応じて中学校区)を「地域」の基本単位として、住民が「わ
がまち意識」を共有し、地域の未来を考え、みんなの力で地域の特色をいかして、身近な地域
の課題を解決するための組織として、地域に関わるさまざまな団体が参画してできた組織です。
平成 22 年度(2010 年度)から「校区まちづくり協議会設立準備会」として様々な活動に取り
組み、順次「校区まちづくり協議会」へ移行を進められ、平成 25 年(2013 年)11 月末にすべ
ての校区で「校区まちづくり協議会」へと移行されました。 ○合計特殊出生率
15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、その年次の年齢別出生率により、
一人の女性が 15 歳から 49 歳を経過する間に子どもを生んだと仮定した場合の出生数です。 ○子育てパートナー
市が主催する子育てパートナー養成講座を修了した八尾市在住の方が、子育てパートナーとし
て登録されています。育児等に不安や悩みを抱える就学前の子どもがいる家庭へ二人一組で訪
問し、ひとりのパートナーが子どもの相手をして、お母さんがもうひとりのパートナーとゆっ
くり話すことができます。 ○子ども家庭センター
子どもや家庭に関する相談のなかで、専門的な知識や技術を必要とする相談に応じる機関です。
児童虐待相談の他に、養護・障がい・非行・育成・保健相談等も対応しています。また、DV
防止法に基づき配偶者等からの暴力についての相談にも対応しています。
<さ行> ○児童家庭相談
すべての子どもが健全に育ち、持っている力を最大限に発揮していけるように子ども及びその
家族等の相談に応じ適切な支援を提供することです。平成 17 年(2005 年)4月より児童福祉
法において児童家庭相談に応じることが市町村の業務となっています。
○青少年育成連絡協議会
地域の青少年指導員とこども会の育成者で組織している団体です。
○スクールカウンセラー
児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止め、心理士として主に子どもたちの「心」に視点を当
て、カウンセリングを行います。
○スクールサポーター
大学生や大学院生、一般の人が市内の公立幼稚園、小・中学校で園児・児童、生徒の学習支援
や活動支援等を行います。
○スクールソーシャルワーカー
教育分野に関する知識に加えて、社会福祉などの専門的な知識や技術を持ち、福祉的な視点に
立って環境改善に向けた支援を行います。
<た行> ○特別支援教育
従来の障がい教育において対象となっていた障がいだけでなく、LD(学習障害)、ADHD(注

資料-96
意欠陥多動性障害)、高機能自閉症を含めて障がいのある児童・生徒の自立や社会参加に向けて、
その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善
又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものです。
<は行> ○パートナーシップ
協働、協力という意味です。 ○母子・父子自立支援員
ひとり親と寡婦に対し、ひとり親が抱えている諸問題について解決の糸口となる情報提供を行
う等その自立に必要な相談に対応する相談員です。 ○母子生活支援施設
配偶者のいない女性又はこれに準ずる事情のある女性及びその養育している子ども(18 歳未満)
について生活上のさまざまな問題を抱えているため十分な養育ができない場合に、自立の促進
のために生活を支援することを目的とした児童福祉施設です。
<ま行> ○民生委員児童委員
民生委員は、常に住民の立場に立って、日常生活の相談に対し必要に応じて関係機関や団体等
と連携・協働して支援に取り組みます。また、民生委員は、児童委員も兼ねており、児童に関
するさまざまな事柄を把握し、児童健全育成のための活動を支援しています。
<わ行> ○ワーク・ライフ・バランス
仕事と生活の調和のこと。平成 19 年(2007 年)12 月に国において、「仕事と生活の調和(ワ
ーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家
庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き
方が選択・実現できる社会」をめざしています。 ○ワークショップ
地域にかかわるさまざまな立場の人々が参加し、地域の課題や改善点について話し合い、さま
ざまな人々の意見を集約・共有化したり、交流を深めたりしていく手法のことです。
<その他> ○SNS
ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)。Facebook などの人と人と
のつながりを促進・サポートする、コミュニティ型の Web サイトのことです。