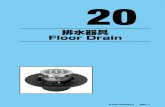大規模排水機場のリスクマネージメント①庄和排水機場 合計排水量 10.1m3/s 排水ポンプ車 13台 (庄和排水機場については、機場周辺に排水ポン
排出権取引Hishiki
-
Upload
guest6f884c -
Category
Technology
-
view
618 -
download
3
Transcript of 排出権取引Hishiki

排出権取引~日本の取るべき立場~
菱木康貴

【意見】 IPCC によると毎年72憶トンもの二酸化炭素が大気中に排出されている。
その一方で、地球が吸収できる二酸化炭素の量は年間31憶トン。つまり、排出量を31憶トンまで減らさなくては温暖化は止まらない。このような現状下では世界全体での積極的なアクションが必要であり,『排出権取引』は有効な手立てであると思う。排出量取引は、各事業所に排出できる温室効果ガスの量を割り当て(キャップ)、その枠を超えて排出した事業所が、枠に余裕のある事業所との間で排出する権利を売買する(トレード)ことを可能にする制度だ。日本においても政府や商社や金融機関も国際的な排出量取引をすでに行っているが、日本国内の排出量取引は、財界の反対が根強いために、ここ最近まで制度すら立ち上がっていなかった。他方、外国の動向に目をやると、EUは、 05 年からヨーロッパ域内排出量取引制度を始め、活発な排出量取引が行われている。また米国も NY を中心に『RGGI』という排出権取引市場を立ち上げている。時期大統領有力候補3人とも排出量取引制度導入を表明しているそうだ。連邦レベルでの法案成立も時間の問題だ。このような現状から考えると,世界規模での㏇削減への流れは止めようがないだろう。日本が世界から立ち遅れないために,私は日本がここで明確な意思表示を示す必要に迫られていると考える。
どうせ脱炭素化が避けられないのであれば ① 自ら進んで制度を導入し、少しでも有利な状態を作るか
②ぎりぎりまで抵抗して、最後は時代の趨勢や市場の圧力によって他国が整備した制度に合わせていくか。
どちらが国益に適った判断なのかをこの場において議論したい。※IPCC(Intergovernmental Panelon Climate Change): 気候変動による政府
間パネル

【議論点】 ① 自ら進んで制度を導入し、少しでも有利な状態を作りだ
していくか
② ぎりぎりまで抵抗して、最後は時代の趨勢や市場の圧力によって他国の整備した制度に合わせていくか。
国益に適った選択は①、②のどちらか。極端に表すと、『勝ち馬になるか・勝ち馬にのるか』のどちら
か ↓ また,国が削減目標達成のために,積極的に民生に介入して白熱球を禁止し,電灯型蛍光灯の使用義務づけを行うことなどに対しては賛成か。反対か。
ex).オーストラリア、ドイツのフライブルク、カルフォ
ルニアなどで実施

排出権取引: EU の現状 取引額の推移 2005年:7000憶円 2006年:1兆円超 2007年: 4.4兆円(全世界の排出権取引額の 7割)
オーストラリアやニュージーランドにおいても、排出権取引の検討が進んでいる。昨年 10月に、 EU非加盟のノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの取引制度と EU-ETS の連結が合意。 EU-ETS 、米国、これらの諸地域・国の取引市場間で、共通プラットホームの構築も検討されており、今後、グローバルな取引が活発になる見込み。
≪排出権取引を実施しての弊害≫① 排出権取引の巧拙が企業財務へ与えるインパクト大②モニタリング報告・法務など取引のインフラが未確定 ⇒実際に排出量が減少しているのかが不明③排出枠の割当の公平性をめぐって訴訟が多発④温暖化対応コストにより電力価格が上昇 ⇒ EU の電力会社は最大の排出権枠が割り当ているにも関わらず対応コストを電力価格に転嫁した結果、電力価格上昇。価格転嫁によって従来以上の利益を上げているために
非難の対象となり、社会問題に発展。 ⑤排出権自体が金融商品化し、マネーゲームに陥っている ⇒実質価値の10倍の値がついていた時期もあった

排出権取引:日本の現状は・・・産業界の強い反発 キャップ&トレードによって割り当てによりエネルギー消費 可能量が決まってしまう ⇒排出枠が営業可能枠として大きな負担になるという懸念 これ以上の CO₂削減不可能(とりわけ電力や鉄鋼などエネルギー多消費型産業)
⇒これまで削減努力をしてきた企業とそうでない企業との間
に生じる不公平感 ⇒諸外国に比べ環境技術に関しては先進的であるため 国としての見解 鴨下一郎環境相が、「EU-ETSそのものを受け入れるの
ではなく、日本独自の国内排出量制度を構築し、できれば、それを国際標準にしたい」との考えを示した。国内排出量取引制度の研究は加速させる一方で、EU-ETSそのものを導入する考えはないというのが国内の流れ。

日本:民間主導の動き
東証に温室ガス排出量取引市場、09年中に創設へ4 月 28 日読売新聞
東京証券取引所は28日、温室効果ガスの排出量取引市場を、2009年中に創設する計画を発表した。
排出量取引の方法は、先進国に温室効果ガスの削減義務を課した「京都議定書」に基づく仕組みを軸に検討する。現在、国内企業の間などで行われている相対取引を発展させることを視野に入れている。
東証は学識者や日本経団連、大手金融機関、証券会社、電力などの代表による研究会を5月に設け、実現に向けた課題などを協議する。東証が業務提携した東京工業品取引所や環境省、金融庁なども参加し、年末までに取引や決済方法などの論点をまとめる予定だ。

米国での民間主導での動き
京都議定書を批准していない米国でも、地域・民間レベルで排出権取引導入の動きが活発。
2003 年に民間の自主的な取引市場としてシカゴ気候取引所( CCX )が設立されている。米国北東部の 10州が参加する地域連合 RGGI は、 2009 年1 月から取引開始予定。カリフォルニア州でも 11年 1 月までには取引市場を導入する予定であり、その動きは太平洋岸・西部9 州の地域連合 WCI に発展している。 WCI にはカナダから 2 州が参加しており、国境を越えた広がりを示している。

参考資料:排出権取引の種類 排出目標設定取引(キャップ&トレード) CO₂排出目標値を決め,その目標値より実際排出量
が多いか少ないかで排出権を売買するしくみ。 EU で採択。
排出削減量計算方式 ( ベースライン&クレジット) CO₂排出削減行動によって, CO₂排出が減少した
とき, その削減分をクレジットとして付与するしくみ。排
出を 禁止できない場所や対象があるときに用いる方式。途
上国のように排出削減義務がない国で用いられる。

ご清聴ありがとうございました。