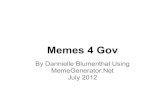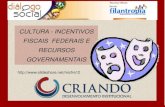Gov Semi2008 01
-
Upload
akabay -
Category
Technology
-
view
1.530 -
download
0
Transcript of Gov Semi2008 01
日 論 演習
4 /2 2 吉田 赤尾
5 / 2 吉田5 /1 3
5 /2 0
5 /2 7 佐藤6 / 3 佐藤6 /1 0
6 /1 7
6 /2 4 赤尾7 / 1 赤尾7 / 8
7 /1 5
7 /2 2 まとめ:総括の回 (詳細は後日に連絡 )
掲示板 o r電子会議 (フォーラム)(主に形式〈システム〉による相違 )スレッドフロー型 (2 ちゃんねる )コメントツリー型 (Ya h o o ! 掲示板 )コメントボード型 (m ixiコミュニティ
)…トピック (話題 )が先にありきで,参加者は自発的意志で参加
ブログ開設者による自己管理 (根拠地 )
コメント (他ブログへの書き込み ),トラックバック (自ブログでの参照・言及 )など相互参照による話題の深化
顕名性 (実名を必ずしも意味しない)
自然発生的で,螺旋 (ループ )型・遠心型の話題の展開
ブログの書き込みなどは,すべて課外作業になる
毎日とはいわないが,最低でも週1 ~ 2 回の書き込みは継続すること
ブログは外部にも開かれている(閲覧・コメント・トラックバック )ので、表現に際しては常に緊張感を保つこと
レンタル (無料 )ブログ・サービスを利用して,ブログを開設すること !!すでにブログを持っている人は,それを流用しても構わない (*)
ブログを開設し,最初の書き込み (エントリー )をしたら,赤尾までメールで, URLおよびコメントを付ける場合のハンドル・ネーム,さらに実名 (非公開 )を知らせること !!
演習ポータル・ブログでリンクする h ttp ://g o v.m a in .jp /
ただし,すでにスタイルを確立し,一定の読者がついている場合は,本演習用に新たにブログを立ち上げたほう
が無難。
m a ilto :a ka o @in f.s h iz uo ka .a c .jph ttp ://www.a ka o ko ic h i.jp /
わかば日記a ka b a y赤尾晃一
ブログのコメント欄に書き込む場合,匿名が許容される。一人が複数の HNを使い分け,騒動を自作自演する場合もある
今回は演習の特殊性から, HNはブログ開設者名と同一とし,演習の期間内の変更は認めない(人物の同一性 =顕名性 =を担保するため )
ブログには必ず,開設者名 (ハンドル・ネーム )をどこかに明記す
ること
live d o o r B lo g g o o ブログ
ヤプログ ! エキサイトブログ
Ya h o o ! ブログ アメーバブログ
F 2 C ブログ はてなダイアリー
楽天広場ブログ S e e s a a ブログ
ブログ上では個人情報 (実名・顔写真・性別・年齢・所属など)を,他者の分を含めて不用意に晒さない
ハンドル・ネームも可能な限り,実名が類推可能なものを避ける (悪い例 :a ka b a y→赤尾 )
コメントとトラックバックは受け付ける設定にしておく (承認制も可 )
参政権 (議員・首長・国民投票の投票権 )を 2 0 歳→ 1 8 歳以上に
民法など,他のさまざまな「成人」の権利を, 1 8 歳に引き下げるか, 2 0 歳のまま据え置くかを法制審議会が議論を開始している
「私が考える成人の線引き」「○○は 1 8 歳 (あるいは 1 5歳 )でもいいけど,□□は 2 0歳のままでいい。▲▲はむしろ 2 2 歳とか結婚してから,とかだよね」
根拠も含めて,どう線引きすべきかを自由に記述してください