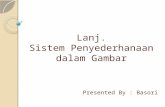gear とwinter について - Hiroshima University1 第一日 ― 研 究 発 表 ―...
Transcript of gear とwinter について - Hiroshima University1 第一日 ― 研 究 発 表 ―...

1
第一日
― 研 究 発 表 ―
年齢・年(間)を表す古英語 gear と winter について
―Ælfric’s Catholic Homilies をもとに
宇部工業高等専門学校教授 大 野 次 征
年齢・年(間)は今日の英語では year を使うが、古英語では gear ‘year’の他に winter が使
われている。両者は(1)発生 (2)競合、(3)gear へ収束の歴史をたどったと考えられる。 今回は特に(2)の競合の段階か、それとも、(3)の段階に入っているのか。また、それぞれの
語の使用環境特徴と(3)に入った(入ろうとする)根拠は何かについて古英語後期の説教集
Ælfric’s Catholic Homilies the First (c. 991 年) and Second series(c. 995 年)をもとに調査・研究
する。
La amon's Brut の MS. Cotton Otho C. xiii における文法的性の消失
―名詞に呼応する人称代名詞 hine, hire の考察―
広島大学大学院博士課程後期 田 中 敦 子
La amon's Brut には、MS. Cotton Caligula A. ix(以下 Caligula)と、それより約 50 年後に書か
れた MS. Cotton Otho C. xiii(以下 Otho)の二つの写本がある。語尾の水平化が進行した後の
13 世紀頃に書かれた作品である。一般的には、文法的性は中英語期に消滅したとされるが、
この作品については古英語期において文法的性を明確に示していた語尾-ne, -re, -um, -(e)s が存在する。本発表では、名詞の文法的性に呼応する人称代名詞 hine, hire を考察すると同時に、
名詞を直接修飾する限定詞・指示詞・形容詞語尾においても、文法的性が存在するかどうか
について考察する。 Otho においては、Caligula より少ないが、hine, him, hire によって無生名詞の文法的性が示
されている。有生名詞については、自然性に殆ど呼応する。これらの代名詞は、与格・対格
の区別が無くなり、現代英語の目的格(通格)として働く。古英語期において二つ以上文法
的性を持つ名詞 hyll, dich は、Otho では、男性名詞としてのみ示されている。また、burh には、
本来の女性名詞としての用法以外に、男性名詞としての用例が多く見られる。

2
語彙を考える ―「雨」にかんする表現を通して―
名古屋外国語大学大学院博士課程後期 菊 地 晃
人は日々の生活の場で言語を使用して互いにコミュニケーションをとっている。数多くあ
る語彙より、発話がなされている場面・状況に適切な語を選択し表現している。しかし、自分
が適切だと思い使用した表現が相手に不快感や違和感を与えてしまう状況は、母国語であっ
ても生じる場合もある。ましてや、用いた言語が他言語ならば、このような事態は常に生じ
ると考えてよい。どのような表現が相手に容認されるのか、母国語ならば経験よりある程度
推測することが可能だが、他言語となると母国語のようにはいかない。もちろん、すべての
表現を記憶すれば良いのかもしれないが、それは気が遠くなる作業である。しかし、仮に容
認される表現に「枠組み」、言い換えれば「傾向」が存在するならば、その「傾向」を把握するこ
とにより、いわゆる「適切な表現」が可能となるのではないか。ここでは、「雨」、rain と共起
して用いられる語を分析し、この「傾向」の存在を確認し導き出すことを試みる。
Jane Austen の否定表現について
-barely, hardly, rarely, scarcely, seldom の場合-
広島大学大学院博士課程後期 辰 本 英 子
本発表の目的は、Jane Austen (1775-1817)の否定表現である barely, hardly, rarely, scarcely, seldom に着目し、文脈を通してその表現が用いられる実態を考察することである。その際、
Mansfield Park (1814), Emma (1816), Persuasion (1818)を主たる言語資料とする。 Jane Austen の作品に見られる否定表現のうち、二重否定 not un- / not in- 及び not + 否定的
な意味をもつ動詞、短縮形 n’t 等の言語表現は、登場人物の性格付けや心理描写などに反映さ
せながら、普遍的な人間性を巧みに描き出すことと常に関わっている。そのような言語表現
が用いられる場合、その表現の周辺、つまり文脈が表現のもつ意味、あるいはその表現の効
果を表す手掛りになると考えられる。本発表で扱う否定表現においても、その前後関係から
Jane Austen らしい特徴が得られるのではないだろうか。否定表現がどのような場面において
用いられているか、また、どのような言語的な特徴が、文脈において効果的に用いられてい
るかについて調べながら、本発表では Jane Austen が使う否定表現の価値を再評価したい。

3
Hurston の英語 ―完了相の「done + X」を中心に―
広島女学院大学大学院博士後期課程 後 藤 弘 子
Hurston の作品は、1934 年に彼女の代表作の一つである Jonah’s Gourd Vine の初版が発行さ
れ、当時の黒人英語を見事に書き表していることで高い評価を受けてきた。彼女の作品に表
れる黒人英語は初期黒人英語と統語的・意味的にどのような相違が見られるのか。また、こ
の時代の黒人英語は白人の話す標準英語の影響を受けることによって脱クリオール化してい
るのか。これらの点を完了相「done + X(動詞原形、過去形、あるいは過去分詞形)」を中心
に考察する。本発表はアメリカにおける黒人英語の構造を歴史的に見ていくことで、奴隷時
代の初期黒人英語から Hurston の使用する 20 世紀初頭の英語への統語的・意味的変化の過程
を明らかにするひとつの試みである。
Langston Hughes の作品とブルース音楽に見られる英語
広島大学大学院博士課程後期 尾 山 誉
Langston Hughes は、黒人文学において最も重要な作家の一人である。彼の作品は、ブルー
ス音楽が録音され始めると同時期に出版され始め、その後もブルース音楽の録音と平行して
出版されていく。彼の作品には The Weary Blues (1926)、Fine Clothes to the Jew (1927)、Not Without Laughter (1930)などがあり、その中にはジャズやブルースなどの黒人音楽からの影響
が数多く見られる。このことから、彼の作品とブルース音楽の関係を考察することは意義の
あることであろう。 本発表では、戦前の Langston Hughes の作品(1921-1938)と戦前のブルースの歌詞
(1923-1938)を使用し、それらに見られる言語特徴を比較分析する。この比較において、今
回は文法項目と語彙の観点から考察する。また同時に、Langston Hughes がどのようにブルー
ス音楽を解釈し、どのように彼の作品の中にブルースのエッセンスを取り込んでいるのかも
明らかにしたい。
Shakespearean and Biblical Allusions in Great Expectations
山口県立大学・九州工業大非常勤講師 定 行 あし江
Charles Dickens の Great Expectations (1860-61)は主人公 Pip の精神的な成長の物語であるが、
Shakespeare の劇や聖書の話を連想させる箇所が多い。特に前半では Macbeth の雰囲気が色濃
く漂っているが、一方、聖書の雰囲気は最初から最後まで続いていく。両者は矛盾するわけ
ではなく、最後に Macbeth が悟りの境地に立って自分の運命を従容として受け入れていくよ

4
うに、小説の中でも主人公は最後に Magwitch を通して悟りの境地に達する。こうして Macbethと聖書の雰囲気は、途中で衝突しながらも互いに絡み合い、ついには一つに融合されるのだ。 Pip の価値観の逆転は、 “Fair is foul, and foul is fair” というあまりにも有名な台詞を連想さ
せる。善と悪、美と醜、生と死を表す言葉を、Pip はどのように使っているのだろうか。魔女
や Lady Macbeth の言葉、Macbeth の借り着のイメージ、ノアの方舟の挿話などをとりあげ、
これらが小説の言語にどう影響を及ぼしているか、考察したい。
“Death to life is crown or shame”: Sense of Honour in Samson Agonistes
広島女学院大学大学院博士後期課程 趙 卉
This paper tries to read John Milton’s Samson Agonistes from the perspective that how death is
interpreted by Samson, Manoa and the Chorus. In handling the final action of Samson, Milton created his hero as one far different from its biblical origin. The death of the Miltonic Samson is deeply rooted in Samson’s sense of shame, but at the same time it demonstrates great efforts and determination to rewrite the shame into glory. Eventually the plight of Samson’s captivity and the death he chooses are to be combined with the sense of honour. The change from shame to honour reflects Milton’s depiction of the suffering Regicide after the Restoration, and articulates for the Regicide their apocalyptic prophecy to the world.
ジェイン・オースティンの小説における “walking”
甲南女子大学大学院研修員 真 下 美 和
オースティンの小説には、屋敷内を散歩したり、部屋の中を歩いたり、屋敷の外を歩いた
りとさまざまな形態の “walking” が描かれている。オースティンの時代は、「『歩くこと』そ
れ自体が男性の特権的なふるまいだった」(大久保譲『身体―皮膚の修辞学』)ので、女性が
一人で屋敷の外を「歩くこと」は女性のマナーに反することだと考えられていた。例えば、
『自負と偏見』のエリザベスは、病気の姉を見舞いに雨でぬかるんだ道をビングリー邸まで
一人で 3 マイルも歩いて行き、それを淑女気取りのミス・ビングリーに “conceited independence” の表れだと批判されている。
また、『マンスフィールド・パーク』では、軽やかに優雅に歩くメアリー・クロフォードの
姿にエドマンドが見とれる場面があり、歩き方が女性の魅力を測る規準の一つとされている
ことがわかる。 本発表では、オースティンの小説において “walking” がどのように扱われているのか、『自
負と偏見』と『マンスフィールド・パーク』を中心に考えてみたい。

5
清教徒的気質におけるカーライルの文学観
順正短期大学非常勤講師 松 藤 亨
幼少時代父母より受けし Calvinism の宗教人生観は Carlyle の心底深く刻まれ、勤労・節倹・
従順・敬虔の実生活こそ神の御旨であり、道徳的目的に欠ける文学への不信、軽視の偏見は
容易に彼から離れることはなかった。両親の期待したエジンバラ大学での牧職への道も、広
く読書思索の中に疑念生じ、迷妄懐疑、人生漂浪の末、危うく「キリスト教の余光」により
救われ、転迷開悟、再生創造の文筆への道が示されてきた。したがって彼にとっては文学は
魂の再生に寄与する深慮瞑想の生み出す気高いもので、俗世と闘い闇を照らす光となるので
ある。特に詩人は世を導く祭司として宇宙人生の神秘をリズミカルな言葉で啓示表現する “英雄” であり、文筆の人は永続的祭司であり、世の光、火の柱として暗きを照らす巡礼の先
導者である。自然は神の霊を着た衣であり、歴史は神の意を具現する “聖書” となった。か
くして、真の文学は ‘Apocalypse of Nature’ として宇宙人生の秘儀を証しし、霊的覚醒と再生
を促す新しき “宗教” とさえなった。かく Carlyle は ‘Moral Energy’ として、勤労生産の英
国人の実践型の運命開拓の精神にヘブライ主義的瞑想信仰の深みを和合共存させた思想的文
学者であった。
The Life and Death of Jack Straw における検閲の可能性
日本大学大学院博士後期課程 藤 木 智 子
エリザベス朝の演劇 The Life and Death of Jack Straw は、1381 年、1450 年に実際にイングラ
ンドで起きたの2つの農民暴動から取材した劇である。劇の冒頭において、主人公 Jack Strawは、自分の娘は税を課される年齢に達していないと主張し、取り立てに来た収税吏を殺害す
る。主人公は Kent 州の仲間と共に決起し、蜂起軍を集め国王の元へ直談判へと向かう。最終
的に国王と蜂起軍は直接交渉をするが、Jack は課税に対する不満を訴えるという目的を達成
できずに殺害される。作者は George Peele が挙げられるが、確証はない。マローン協会版で
1,210 行と行数が短く、主人公は暴動の扇動者へと格下げされ、蜂起軍の一人である道化は、
暴動を愚弄し、暴動は無意味であると反復し、暴動の原因は副次的な印象を与える。本劇は
1594 年出版であるが、ほぼ同時期に出版された Sir Thomas More には、当時の饗宴局長 Edmund Tilney が書いたとされる検閲の手書きの注が現存する。この検閲の痕跡から、Tilney は外国
人排斥問題に特に目を光らせていたことがわかる。当時の検閲の傾向を踏まえ、本劇に対す
る検閲による削除、修正の可能性を考察する。

6
T. S. Eliot 中期の詩における死と再生 ― “Gerontion,” “Whispers of Immortality,” “The Hollow Men” を中心として ―
広島女学院大学大学院博士後期課程 野 坂 映 作
エリオット中期の3つの詩における荒廃と再生のテーマを考察する。この主題がポジティ
ブに描かれているもの、ネガティブに描かれているものを取り上げエリオットがいかに現代
を捉え、荒廃と再生を示唆しているかを見てゆく。現代は荒廃に埋もれ、人間精神は死に瀕
している。しかし死は再生と切り離せない。生があって死が来る。そして死があって再生が
訪れるという円環構造があるからだ。しかし死は本当に生をもたらすのか。現代で、その桎
梏から人間が解放されても荒廃と再生の区別が無く共存している困難さがある。荒廃と再生
の接点で如何にその困難さを突き破るかである。 “Gerontion” の主人公である老人は萎び、
乾き、生の中の死を表象する。荒廃の現代が象徴的に描かれ、そして虎キリストが破壊者と
して来る。それは人間が食い尽くされるという荒々しい所業を表している。人間の感覚、情
熱さえキリストの前では必要がないことが語られる。 “Whispers of Immortality” では死の永
遠性が説かれ、死者の性が骨で表される。そして霊性のない生が豹とともに真実性を以て迫
り人間精神の救いが希求される。 “The Hollow Men” では現代の人間の虚ろさが描かれ、眼
がかすかな望みを表す。世界が簡単に終わるほど世界の土台は脆く荒廃している。偽りの生
は人間を荒廃させている。人間が偽りの自己を滅し、キリストに従い生きれば再生の望みが
無くもないと詩人は考える。
Virginia Woolf の short fiction における外的、内的世界
― “The Duchess and the Jeweller” と “Lappin and Lapinova” ―
広島女学院大学非常勤講師 島 岡 晃 子
Virginia Woolf の short fiction への批評家の意見は、彼女の novel への彼らの熱い眼差しと比
べると、極端に冷ややかなものである。Susan Dick や Nena Skrbic が、彼女の短編作品をあえ
て short story ではなく short fiction とするのも Woolf の短編作品が short story の伝統の枠に収
まらないからであろう。しかし彼女は、絶えず新しい fiction を追求し、伝統へ挑戦していた
のではない。 ここでは short story の伝統に準ずる “The Duchess and the Jeweller”(1938)と “Lappin and Lapinova”(1939)両作品の登場人物の外的、内的世界がいかにその人物の「その人らしさ」を
伝えているのかを考察する。 “The Duchess and the Jeweller” の主人公 Oliver Bacon は “the richest jeweler in England” であるが、心は満たされてはいない。また “Lappin and Lapinova” では Ernest と Rosalind が二人だけの “wild rabbit” の世界を想像し仲むつましく暮らしているが、
Ernest がその世界を拒絶したき、その結婚生活も終焉している。

7
The Invisible Man と他者恐怖
高知大学講師 宗 洋
身も凍る2月初旬、ロンドン近郊の寒村にある「駅馬車亭」に宿を取ったのは、身体を隠
すかのように全身を防寒具で覆った男だった。そのよそ者は宿の一室で謎の実験に明け暮れ、
村人は彼を怪人として恐れるようになる。The Invisible Man (1897) は、可視/不可視という
科学ロマンスのテーマを確立したことはもとより、村を訪れたよそ者にたいする恐怖の眼差
しの物語でもある。 本発表では、他者としての透明人 Griffin が、怪人物として表象されることになる言説の磁
場を歴史的な側面から明らかにし、The Invisible Man で描かれる他者恐怖の源泉を同時代の文
学作品や図像を用いて考察する。
フォースターとアンダソンの曖昧さの問題について
宇部フロンティア大学助教授 内 海 俊 祐
E. M. Forster と Sherwood Anderson は共に曖昧模糊とした感覚を読者に与える作品を残した
作家である。かつて、これら英米の同世代作家について論じた Lionel Trilling は、両者を同質
の才能を有すると断じ、なおかつ彼らの差異にも言及している。発表では、Trilling のこの分
析を足がかりにして、これらの作家の作品の曖昧さの問題をフィクションやエッセーの中に
具体例を求めながら検証する。 本来、作品の曖昧さは作家自身の現実に対する vision の問題と深く関連している。このこ
とに関して、発表者なりの一つの体系作りを試みたいと思う。その上で、出来上がったその
体系を利用して、両作家の作品の曖昧さの質と原因を明らかにすることが本発表の最終目的
である。
ヘンリー・ジェイムズの『抗議』
戯曲版と小説版の相違点
関西大学非常勤講師 橋 本 昇 ヘンリー・ジェイムズの『抗議』は最後期に属する作品であり、戯曲版と小説版の二つの
作品がある。戯曲版は 1909 年に完成しジェイムズの劇作への試みは好ましい注目を浴びたが、
人気を得ることは出来なかった。この劇の主題は、裕福なアメリカ人であるベンダー氏によ
る伝統的イギリス芸術絵画買収問題である。特に彼の貪欲な金銭至上主義は、この劇を魅力
ある喜劇的作品にしている。

8
小説版は1911年に完成したが、戯曲版と比較するとストーリー自体に大きな変化はないが、
戯曲版では語られなかった登場人物たちの微妙な感情や意識が付随されている。 本発表においては、これら 2 つの作品の表題にもなっている、イギリスの至宝ともいうべ
き絵画をアメリカ人に渡すことに反対するイギリス民衆の激しい「抗議」に着眼し、利害を
追い求める個人の欲望が達成されない現実、すなわち保守的なイギリスの閉鎖性を中心に論
じながら、その閉鎖性を体現しているジョン卿とタイン卿、さらにサンドゲイド婦人を中心
に、両作品の相違点を考察し、ジェイムズが改訂した意図を探っていきたい。
The Hero of Redclay に見るヘンリー・ローソンのペーソス
関西学院大学大学院博士後期課程 宮 本 まゆみ
ヘンリー・ローソン(1867-1922)は、その約 35 年間の作家生活を通じて、200 余りの短篇
と少なくとも 500 以上の詩を残した。ローソンの描いた物は、オーストラリアの国土の大半
を占める bush と呼ばれる自然とそこで生活する人々であり、また、都市で貧困にあえぐ人々
であった。その作風を一言で表すのは難しいが、多くの評論家達が共通して使う表現に、
"sympathy" "self-pity" "pathos" "humour"がある。例えば、pathos を土台として、そこに humourが絶妙に織り込まれることによってその pathos が一層強調される手法などは、ローソン作品
の持つ大きな特徴の 1 つとなっている。発表では、The Hero of Redclay という短篇を取り上げ
る。まず最初に、この作品の内容を簡単に解説する。それから、The Lachlan と呼ばれる男の
登場人物と彼にまつわる 2 人の人物の死に焦点を当てて、この作品の持つ pathos の原因を探
る。さらに、どのような humour の手法がどのように作用して、最終的なローソン独特の pathosを生み出すのかを明らかにしていきたい。
Alice Walker と Native American の接点
―Meridian, The Color Purple, By the Light of My Father’s Smile の比較を通して―
広島女学院大学博士後期課程 光 森 幸 子
母方からチェロキーの血を受け継ぐ現代黒人女性作家 Alice Walker が作品に描き出す宗教
観・自然観は、自己中心的に振る舞い傷付け合い破滅に突き進む現代人に強いメッセージを
送っている。 本発表は Walkerの3つの作品を比較・検討しながら、そのなかにどのように Native American
の宗教観・自然観が取り込まれ展開し、読者に人種・性差・宗教を越えて共存し調和してい
く道を示しているのかを考察するものである。 まず Meridian では、欧米の文明・文化の強い支配によって絶滅寸前にまで追い込まれたア
メリカ先住民族とアメリカ黒人の受けてきた苦しみの共有体験が、主人公 Meridian Hill の公
民権運動の闘いにどのように結びついているのかを検討する。次に The Color Purple では、
主人公 Celie が自然の与えるサインを力に変えることによって彼女自身の持つ神の固定観念

9
と決別し、自分の声を得て立ち上がっていく過程を検討する。そして By the Light of My Father’s Smile では、キリスト教に深く根付く家父長制に縛られた父親 Se~nor Robinson が、自然や宇宙
と彼自身が繋がる存在なのだと学ぶことにより自らを解放し虐待してしまった娘と和解を果
たしていく過程を検討し、これらの作品に共通に流れる Walker のメッセージの源泉となるも
のを証明していきたい。
Beloved における死生観
広島大学大学院博士課程後期 古 川 晃 子
Toni Morrison(1931-)の第 5 作目の Beloved(1987)に登場する Beloved は、この世とあの世の
境界線を持たない存在として描かれているだけでなく、気味悪さを持ち合わせている。しか
し、Beloved を死んだ赤ん坊の蘇りであると信じる母親 Sethe やその娘 Denver は、Beloved の
得体の知れない気味悪さを難なく受容し対話を試みる。さらに、Beloved の存在の奇怪さと呼
応するように、恥辱にまみれた奴隷生活の実態がグロテスクに暴露されていく。 Baby Suggs も、やはりこの世とあの世の境目を越える存在として描出されている。Baby
Suggs は死んだ後、彼岸から義娘 Sethe へ愛を送る。また、彼女の霊は、娘として母親の愛を
要求する Beloved に消耗されていく Sethe を目の当たりにした Denver に、母を救う勇気を与
える。Beloved のようにグロテスクで、Sethe を貪る霊もあれば、Baby Suggs のように娘たち
を彼岸を越える深い愛で救う祖先の霊もある。 このように、気味の悪さと、時間による拘束を受けない世界が、Beloved を何の抵抗もなく
覆っている。本発表では、Beloved のグロテスクな霊と Baby Suggs の救いの霊をアフリカ系
アメリカ文学の伝統の中で考察することによって、Beloved に窺える Morrison 文学の死生観を
究明することを目指す。
“Death is a Master from Germany”: Paranoia and Desire in DeLillo’s White Noise
三重大学外国人教師 Taras A. Sak Don DeLillo’s White Noise (1985) is widely considered to be a “postmodern” classic, displaying several of the elements commonly held to be fundamental to such (anti-) narratives: a proliferation of signs, an ironic sense of undecidability and entropy, a lack of resolution, and so on. However, perhaps its most salient characteristic is the sense of paranoia that suffuses the text: most notably, and powerfully, in the case of Jack Gladney, protagonist and narrator. The work of Jacques Lacan―albeit problematic in many respects―may help enhance our reading of White Noise, though few critics have drawn upon it. Although fictional in nature, Jack’s paranoia speaks to our present political condition and, as such, merits closer attention―particularly in the “9/11” era. In other words, through an engagement with certain Lacanian concepts, I hope to gesture toward a re-reading of White Noise that is relevant to our current, deeply paranoid times.

10
奴隷ユーマの悲劇
京都府立大学大学院博士後期課程 森 新 子
『ユーマ』(1890)は、西インド諸島のダァ(乳母)である女奴隷の生涯を描いたハーンの中
篇小説である。従来本作品は多くの批評家により失敗作と見られてきた。しかし、最近再評
価と新しい研究が進められている。 この作品には主人公ユーマに加えられた数々の抑圧の様子が描かれ、ハーンの次第に滅び
行くダァ制度に寄せる愛惜の気持ちが見事に表出されていると思われる。高い地位を持つダ
ァなのに強要される抑圧には、①高い教育をうけられないこと、②自由への願望を断たれる
こと、③みかけだけの優越感をまわりに誇示すること、④ひたすら主家に尽くすことがあげ
られる。本発表ではこの四つの点に焦点をあてて検討したいと思う。 主家は温情の見返りに忠節を強要する。だがその温情ゆえにかえってユーマは他の奴隷た
ちから孤立し、主家の温情と自由への希求との板ばさみになる。このように孤立したユーマ
は主家の子とともに炎の中で死ぬ運命を甘んじることになる。 これまでの先行研究を概観すると、『ユーマ』を抑圧ゆえに死んでいく女奴隷の一生を描い
た小説ととらえた見方はなされていないようだ。これらの奴隷たちの抑圧はすでに過去のも
のではあるが、ハーンは生き生きと描写している。ユーマが受け、苦しんだ抑圧という観点
からこの作品を見直してみたいと思う。
ラフカディオ・ハーンが魂を通わせた有情と無情の「間あわい
」 ―日本とアイルランドにおける伝承をふまえて―
梅光学院大学大学院博士前期課程 吉 田 美奈子
日本の庭には有情と無情が存在する。ハーンが、 “In a Japanese Garden” の中で書いている。
有情とは欲望を持つ、鳥や虫、それらを見ている人間も同じ仲間である。一方、無情とは欲
望を持っていない、木や花、静寂な印象を与える石のことをいう。 ハーンの心の中では有情と無情の世界は一つに結ばれているので、この二つの世界は明確
に区別できないのである。それは有情と無情の間にはもう一つの世界、すなわち有情と無情
が共存する世界(間あわい
)があるからだ。しかし、共存するためには同種の姿でなければならな
いようだ。それは互いに魂を通い合わせるためだ。例えば、「青柳のはなし」では、無情の木
が人間の姿になって有情の人間と対面する。そして無情からやってきた人間が元の世界に戻
る時には、再び木になって戻っていく。同じ人間だったからこそ共存でき、魂を通わせ合う
ことができた。河合隼雄氏が著書『ケルト巡り』で「ハーン自身が「 間あわい
」に身を置いて生
きてきた経歴を持つ」と述べているのは、どちらともつかない境界( 間あわい
)に身を置き、時
にはそれを越える漂泊の旅人として生きてきたハーンをまさに表していると思う。

11
本研究では、人間と木の間のつながりや、日本とアイルランドにおける伝承を考えながら、
ハーンが有情と無情の「 間あわい
」にあってどのように魂を通わせたのかを探りたい。
ケルト的メタモルフォーシス考
~『ドラキュラ』とハーンの作品を中心に~
梅光学院大学大学院聴講生 納 冨 未 世
1897 年に出版されたブラム・ストーカー(Bram Stoker, 1847-1912)の代表作である『ドラ
キュラ(Dracula)』とラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn, 1850-1904)の諸作品をケルト
的変身譚として考察する。古今東西の神話または文学作品において、変身すなわちメタモル
フォーシスを題材にした物語は多く、有名なギリシャ神話を例に挙げるならば、メタモルフ
ォーシスは神の罰或いはシュリンクスやダフネのように「逃避」手段としてのものが多い。
しかしながらケルト的メタモルフォーシスはそれと一線を画する。『ドラキュラ(Dracula)』(1897)の主人公ドラキュラは物語中その姿をオオカミやコウモリに変えて人間たちを翻弄し、
ドラキュラの超人的な力が変身により効果的に示されている。ドラキュラは獣に変身し、獣
を操る力をもつ。ケルトの英雄ク・フーリンはより強大な力を得るべく戦いに際して半獣へ
と姿を変えるが、ドラキュラの変身も新たなる力を得るための、言うなれば「進化」である
と考えられはしないだろうか。ハーン作品における変身譚『青柳物語』では、柳の精が人間
に姿を変えて人間の男と結ばれる。ケルト的変身譚では人間と植物との間に恋が生まれ、二
つの異なる世界間において魂の交流がある。そして二つの世界間の隔たりを超える唯一の手
段として変身があり、それは二つの異なる世界の「結合」を意味する。さらにケルトの宗教
ドルイド教とキリスト教の「融合」を象徴的に表すアイルランドの円環十字架もまた、自ら
とは異なる世界や価値観との共存手段としての変身であるといえよう。本発表では、ケルト
的メタモルフォーシスを「進化」「結合」「融合」の 3 点から考察し、その背景にある有形無
形のケルト的思考を探る。
ハムレットの幽霊とハーンの幽霊
岡山大学・島根大学・ノートルダム清心女子大学・吉備国際大学非常勤講師
伊野家 伸 一
北村透谷は「日本文学は他界に対する観念が乏しく、そうしたところに、『幽玄を本とする
想詩』即ち西洋文学流の “思想文学” は求めることができない。実界にのみ馳求する思想は
高遠なる思慕を産まないのであって、そこからシェイクスピアの “ハムレット” のような幽
玄な “トラヂヱヂイ” は生まれてくるはずはなかった」としている。これは川村湊著『言霊
と他界』に示されているのであるが、同著には透谷の「こうした<他界>観が、日本人の中
に “蓬莱” を見出し、そこに生と死とが混在する、曖昧な二元論の世界を見た “西洋人” ラ

12
フカディオ・ハーンの精神と、まったく対立的であることは言うまでもないのである」との
指摘も見られる。 では、ハムレットの幽霊とハーンの作品に登場する幽霊を比べてみるならば、どのような
対比・相違または重畳性がみられるであろうか。ハーンの Kwaidan 等にみられる幽霊たちに
目を向けながら検討、考察を試みることにしたい。
ラフカディオ・ハーンとウィリアム・モリス
日本アイルランド協会 松 村 有 美
イギリスの観光地のどこでも目にすることの出来るウィリアム・モリスの「柳の枝」柄の
土産物。時にはウォールペーパーであったり、小物を彩る柄に使われていたりする。他にも、
モリスの「菊」柄も多く目にすることが出来た。鶴岡真弓はモリスのデザインが自然を超え
てしまっていると言う。いわば超自然の文様。それらモリスの神業には独特の曲線表現が関
わっているという。永遠に続くように見える曲線、それはハーンが夢の中で見た黒髪の女性
の髪を彷彿とさせる。またモリスが生涯を共にした妻ジェインの写真を見ると、肌は浅黒く、
豊かな黒髪は自然にカールしていて、いわゆる当時の伝統的な美人のイメージとはかけ離れ
ていたようだが、ハーンが幼い頃分かれた母ローザの面影をも感じさせる容貌なのである。
また、モリス、ハーン共々自ら記事を書き、挿絵まで描くということもしていた。 モリスはロンドンはシティで成功した父を持つ富豪の家に育った、一方、ハーンは相続に
失敗し、ロンドンのイーストエンドをさまよっていた。両者の境遇こそは違っていても、根
っこにある部分に共通した思いがあるのではなかろうか。今回の発表ではハーンとモリスに
ついて比較していきたいと思っている。
ラフカディオ・ハーンの中世英文学史講義の構想
大妻女子大学教授 松 村 恒
ラフカディオ・ハーンの東京帝国大学時代には英文学の講義は大きな割合を占めていたし、
大学での生活は殆どそれに忙殺されていたと言ってよい。しかしこの時期の自宅に戻ってか
らの執筆活動は日本の古伝承の再話に尤も脂ののったときでもあり、専らそれに精力が注が
れた。大学での講義は自身で執筆したものは少なく、大半は聴講者達の筆記ノートから編纂
された講義録によって知る他はない。足かけ七年にわたる東大時代に英文学史概説と特論の
全内容は極めて多岐にわたるので、一度にその全貌を把握するのは困難である。ハーンは英
文学史概説の構想を立てるにあたってテーヌの影響を受けているのではないかと想像される
が、これは想像に留めるだけでなく、論証さるべきことがらである。この作業仮説の間隙を
埋めてゆくことは容易ではないが、先ずはテーヌと同じ順序で始めたアングロ・サクソン文
学の概観の部分を作業の取りかかりとしたい。ハーン自身の関心が後代の文学に比べてそれ
程関心が強くなく、独自の見解を濃厚に打ち出すよりも影響の方が大きいのではないかとい

13
うことと、こうした作業の始まりとしてまとまり易いからである。 ヘルン文庫所蔵の英文学史概説はテーヌだけではないが、ハーンの個々の作品の講義内容
と、それぞれの書の解説を付き合わせてゆく作業により、そのいずれと深い関連を有するか
の見通しはある程度立てられるが、より重要なのはその文学史観である。美学研究にも傾斜
したテーヌとの関連を見るのは興味深い作業となろう。
Lafcadio Hearn と Ralph Waldo Emerson
―ハーンの「究極の大霊」を中心に―
比治山大学非常勤講師 風 呂 鞏
アメリカの思想家・詩人 Ralph Waldo Emerson(1803-82)の死去に際し Lafcadio Hearn は、
1882 年 4 月 30 日付けの THE TIMES-DEMOCRAT 紙に「エマソン論」を執筆した。その中で、
ハーンは “Yet, were we to speculate upon the tendency of his teachings, we should feel inclined to qualify that tendency as pantheistic or as leading us to believe in the union of our own being with the All-being, and to regard death only as a Nirvana for the individual mind.” と書き、エマソンの「大
霊」(Over-Soul)のことを「我々自身の存在と万物との合一」と言い換えている。エマソンの
こうした教義はハーン晩年の小品「夜光るもの」 “Noctilucae” などにも影響を与えており、
ハーンの汎神論がエマソンに近似していることは明らかである。ハーンは東大の講義にも
屡々エマソンに言及している。ハーンの教え子である大谷正信が、ハーンの死後相次いでエ
マソンの翻訳『偉人論』、『恵馬遜傑作集』の 2 冊を出版したのも、恩師ハーンに対するエマ
ソンの影響の大きさを考慮した結果ではなかっただろうか。先行研究を踏まえて、ハーンの
大谷宛書簡をも参考にしつつ、「ハーンとエマソン」との関係について考察してみたい。

14
第二日
― シンポジアム ―
文学テクストと文法化の諸問題-話し手と聞き手のコミュニケーション
序
(司会)広島大学教授 地 村 彰 之
本シンポジウムの目的は、中期英語から初期近代英語・後期近代英語を経て現代英語まで
の文法化現象について、それぞれの講師が主として研究している時代の文学テクストを通し
てパースペクティブな視点から把握することである。文法化とは、実質的な意味をもつ内容
語(content word)から機能語(function word)へ変化する過程・現象を指し、それは文法構造、
品詞の形成まで関わると言われる。法助動詞を始め、数多くの研究が今日まで行われてきた。
ここでは、さまざまな角度から各講師自らが収集した用例を踏まえて、それぞれの時代の文
法化について具体的に説明する。特に動詞 look と pray の文法化についてだけは、講師全員が
共通の事項として指摘し、通時的に見た文学テクストの文法化について体系化したい。本シ
ンポジウムでは「文学テクストと文法化」を共通のテーマとして、それぞれが専門としてい
る時代の作品の言語において、文法化現象がどのように存在しそれが作品の内容と係わるか
について論じ、フロアーと意見を交換することによって新知見を得たいと思う。 本シンポジウムでは、以下の 4 講師が、それぞれ異なる時代の文法化について報告する。
Chaucer を中心とした中期英語における preyen, bisechen, loken の使用状況
(講師)倉敷芸術科学大学助教授 大 野 英 志
本報告は Chaucer を中心とし、同時代の詩人 Langland と Gower の作品も資料として、1 人
称単数主語付きの preyen, bisechen という依頼の動詞を、また他の報告者との連携で loken の
命令形も調査対象とする。そして、これらの動詞の使用状況について述べる。 中期英語における文法化の研究では、Brinton (1996)がよく知られている。彼女は Chaucer の1人称単数主語を伴うKNOW-verbs (gessen等)の文法化についてその過程を 4つのステージで
示した。また、pray の文法化については、秋元が 15-19 世紀について調査し、「I pray you (thee)の発達は「認識的」挿入 I guess / think のそれと類似している」(2002: 204)と述べている。 本報告は上記動詞の補文構造を明確にしながら、OED や MED に詳述されていないこの時
代におけるこれらの動詞の用法を文法化(=matrix clause から pragmatic marker へ)という視点
から観察する。そして Brinton や秋元の調査を検証したい。また、可能な限り言語使用者にも
焦点を当て、文法化された表現が出現する環境にも触れたい。

15
初期近代英語期における談話標識の文法化について
(講師)鳥取大学助教授 福 元 広 二
1990 年代以降盛んになってきた通時的な視点からの文法化研究はコーパス言語学、特に電
子コーパスの完成によるところが大きい。Helsinki Corpus, Parsed Corpus of Early English Correspondence, Corpus of English Dialogues などの電子コーパスを用いて、様々なジャンルの
データを大量に分析することが可能となり、文法化のような言語変化を捉えやすくなってき
た。その一方で、文学テクストにおける登場人物の話し手と聞き手の関係が文法化とどう関
わっているかという社会言語学的・語用論的な観点からの研究はほとんど行われていない。 本発表では、まず初期近代英語期に見られる文法化の例について簡単に述べ、次に、初期
近代英語期の劇における談話標識の文法化を考察する。今回は談話標識の中でも、特に verbs of attention と呼ばれるような動詞 look, hark, hear と動詞 pray を中心に取り上げ、これらの動
詞が命令文で用いられる際に文法化が見られることを指摘する。さらには、文学テクストと
の関わりでは、劇における話し手と聞き手のコミュニケーションに関わる語用論的な観点と
文法化がどのように関係しているかについても触れる。
18 世紀英語における文法化
(講師)広島修道大学教授 水 野 和 穂
18 世紀の英語を対象に文法化を考察する。具体的な調査項目は、1)各講師と同様、動詞 look
及び pray の文法化、そして、2) fair > fairly を代表とするいわゆる flat adverb と -ly 接辞に
よる adverbialization である。考察にあたり電子コーパスを利用し、「文学テクスト」のジャ
ンルを他のジャンルとの比較によってその特徴を見出したい。また、後期近代英語は英語の
標準化において重要な時期であるが、その視点からも文法化を考え、その変化の要因や原因
を探りたい。
19 世紀における look および pray の文法化の社会言語学的考察
(講師)吉備国際大学助教授 今 林 修
Brinton (2001)によると、lookee / look’ee は、初期近代英語期まで用例がなく、18 世紀に初
めて姿を現すという。文法化の過程が propositional > textual > expressive (Traugott, 1982)とす
るならば、間違いなく lookee / look’ee は expressive であり、Halliday & Hasan (1976)のいう interpersonal の過程であろう。後期近代英語期における用例を丹念に見ていくと、OED (s.v. look, v. 4.a.)が指摘しているように、これらは “vulgar speech” で用いられる。一方、lookee か
ら遅れること 1 世紀、19 世紀には look here が出現する。そうなると 19 世紀は、look you, lookee

16
/ look’ee, look here 及び look が共存することになり、おのずからその使い分けに興味が引かれ
る。文法化理論を念頭に置き、それらの使用を社会学言語学的に分析を試みるのが本発表の
趣旨である。また、各講師と同様に 19 世紀における動詞 pray の文法化の状況についても触
れたい。