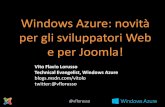ユーザが参加しやすい地域情報共有サイト構築支援システム...
Transcript of ユーザが参加しやすい地域情報共有サイト構築支援システム...

ユーザが参加しやすい地域情報共有サイト構築支援システム GeoSLS の開発
飯塚直 †
Development of GeoSLS—A System for Building Easy-to-Use Website of Local Information Nao IIZUKA, 4th grade, Faculty of Policy Management, Keio University
Abstract
I have been developing a computer system that provides local information for people involved in the system’s coverage area. It is not only a portal site for that area, but also an easy-to-use system for beginners. To make this system user-friendly, I have implemented some functions such as automatic insertion of content-related maps and photos. Yan Laboratory named this system GeoSLS. It is the acronym for “Geographically enhanced open System for Local knowledge Services.” There are some problems of automatic photo extraction algorithm, but our laboratory will continue efforts towards the development of more refined algorithm and the release of GeoSLS.
Keywords: 地域情報( local information),知識共有(knowledge sharing),地理情報
(geographical information),関連情報抽出(related information extraction) 1. はじめに†
現代のあらゆる自治体の課題として,住民の意見を
どう吸い上げるか,またどう政策に反映させていくか,
ということがある.私たちは住民として何らかの自治体
に属して暮らしているが,必ずしも行政へ意見が届き
やすい環境にいる人ばかりではない.人々の職業や
生活はますます多様化し,一堂に会して議論すること
も難しくなってきている今日,ウェブはますますその
存在意義を大きくしている(モービル,2006).どこに
いても,どんなときでも参加できるコミュニティが SNS(Social Networking Service)をはじめネット上に広がり
つつある.自治体においてもこの流れを見逃さず,地
域を限定した形で SNS を提供しているところも少なく
ない.総務省による地域 SNS 実証実験の先駆けとし
て東京都千代田区が運営している「ちよっピー」[1] で
は,新しいイベントのブレインストーミングを行わせ有
益な意見を創出させたり,地域での重大事件発生時
に住民どうしの情報共有がスムーズに行われるなど
の成果を上げている(2006年4月23日付け産経新聞
† 〒252-8520 神奈川県藤沢市遠藤 5322 慶應義塾大学総合政策学部 4 年 Email: [email protected]
朝刊 1 面の記事「顔の見える会員制ネット SNS で井戸
端会議 地域の防犯,自治体活用」に掲載). しかし,こういった地域の活性化につながるウェブサ
イトの構築には非常に手間がかかる上,専門的な技術
が必要となる.そればかりか,人件費やソフトウェアの購
入にかかる費用を勘案すると,期待される効果に見合
わないとしてウェブサイト構築をあきらめてしまうケース
も少なくないだろう. この問題を解決するため,簡便に使うことができ移植
性にも優れた地域情報共有サイト構築支援システムで
ある GeoSLS(Geographically enhanced open System for Local knowledge Services)を厳網林研究室が開発して
おり,技術的な要素全般について私が開発を担当して
いる.GeoSLS 自体は特定の地域に限定したものでは
なく汎用的なシステムである.厳研究室では GeoSLS の
活用例の一つとして,藤沢市,寒川町,茅ヶ崎市にまた
がる湘南里山地域を設定し「湘南の風」[2] というサイト
の構築を GeoSLS 開発と同時並行で進めている.本論
文は GeoSLS の開発状況についてまとめたものである. 2. 本研究の目的
本研究の目的は,地域情報共有サイト構築のための

システム「GeoSLS」の開発である.GeoSLS はウェブ
サイトの形態をとり,地域に関する施設情報や環境問
題などあらゆる情報が提供され,ユーザはその情報
を編集することができ,またサイトを利用してユーザ同
士がコミュニケーションを図ることができる.GeoSLSでは主に地域住民や地域の大学の学生,地域で働く
事業者や農家など地域に関わるすべての人々をユ
ーザとして想定しているものの,必ずしもそれに限定
せず広く公開する形をとる. システム開発にあたっては二つ重要な点がある.
一つめは,ユーザが積極的にコンテンツを書き込め
るよう工夫を凝らすこと.住民による参加が少なくては
地域サイトとしての意味が薄れてしまう.二つめは,高
度な技術を必要とせず容易にサイトが構築できるよう
にすること.インストール作業が容易でなければ誰に
も使ってもらえないからである(Nielsen,2006). 2.1 ユースケース GeoSLS の開発にあたり,それぞれの立場から
GeoSLSがどのような使われ方をするのか整理し,ユー
スケースを列挙すると図 1 のようになる.
図 1 システムのユースケース
2.2 ユースケースに対して必要とされる機能 これらのユースケースを実現させかつ便利に使える
ようにするため,システムにはいくつかの要素が重要と
なる.まずは情報の閲覧・登録にあたってできる限りユ
ーザの負担を軽減させること.本システムではパソコン
の操作に詳しくないユーザによる利用も多いと想定さ
れるため,敷居が高くては利用が望めないからである.
地域情報のため地図の重要性が高まる一方でいかに
負担なくユーザが登録した情報と地図を連携させるか,
そしてサイト内でいかにページ間を効率的にナビゲー
トさせるか,さらにはシステムのインストール段階にお
ける煩雑な作業をいかに自動化させるか,といったとこ
ろが本研究の工夫を凝らすべき点である. また,サイト内でユーザ同士のコミュニケーションツー
ルを提供することがサイト利用を促進させると考えられる.
特定の話題に関して議論が行えるような掲示板や,ユー
ザ同士でメッセージをやりとりできる機能も必要だろう. 3. システムの具体化―GeoSLS 第 2 章で述べた機能を実現するため,我々はシステム
をより具体化させ実装について検討を行った. 3.1 プラットフォーム
GeoSLS は CMS(Content Management System)をプラ
ットフォームとして採用した.一般に CMS はインストール
作業が容易であり,日常的な管理作業もウェブブラウザ
を利用した簡易なインタフェースでできるという特徴を持
つためである.本研究で必要な機能は CMS 上で動くプ
ログラムとして開発することでその恩恵を享受できる. 今回 CMS Matrix[3] というサイトを利用して各 CMS ソ
フ ト ウ ェ ア の 比較検討を行い , オ ー プン ソ ー ス の
Joomla![4] を開発プラットフォームとして選定した.これは
日本で普及しているCMSであるXOOPS[5] 等と比較して
高速に動作し,管理インタフェースが親しみやすく,移植
性が高くシステムとしての柔軟性に優れる等の理由から
である.また Joomla!と連携して写真の効率的な管理が
行える Gallery[6] というソフトウェアを同時に利用する.こ
れら GeoSLS の必要条件を表 1 に示す.
表 1 システム要件 OS クロスプラットフォーム
Web サーバ Apache
データベース MySQL
CMS Joomla!
写真管理 Gallery
コンテンツは Joomla! 上に記事単位で登録していく.
すべての記事はタイトルと本文を持っている.そのうち本
文は概要文と詳細文に分けられる.HTML を知らないユ
ーザでもWYSIWYGなインタフェースで多彩な記事を書
くことができる.写真については Galleryに登録しておき,
Joomla!の記事内から Gallery の写真を呼び出して表示
する形をとる. 一つの GeoSLS は一つの地域に関するものであるから,
他の地域で同じようなサービスを提供しようとする場合は
GeoSLS を個別に構築する必要がある.

3.2 GeoSLS の特徴的機能 2.2 節の「ユーザによる情報登録の敷居を下げる」と
いう要素を達成させるため,ユーザが入力した記事テ
キストに合わせて自動的に地図が表示される機能を設
けた.記事内の住所や目標物名に反応して自動的に
地図が挿入される仕組みである.例えば,ある店舗に
ついてのコンテンツを登録する際にユーザが入力す
べきものは住所または店舗名のみで十分であり,地図
を表示させるために緯度経度や特別なテキストなどを
入力する必要がない. また記事入力の手間を省く意味で,サーバ内の写
真データも自動的に挿入される.GeoSLS にはユーザ
が写真を登録できるようになっており,それぞれの写
真にはタイトルやコメント,位置情報を付与することが
できる.この写真データベースを用いて,各記事の内
容に応じて関連した写真が自動的に挿入される. サイト内をうまくナビゲートするための機能としては,
記事内に他の記事のタイトル文字列が含まれていれ
ばその記事へのリンクを自動生成する「記事タイトルの
オートリンク」機能を盛り込む. またユーザによる参加を活発にさせるための手段と
して,昨今の SNS に見られるようにユーザ同士のコミュ
ニケーションツールを提供する.ユーザ同士でのメッ
セージ送受信機能を用意するだけでなく,単一のコン
テンツについてコメントのやりとりができる場を設けるこ
とでテーマに即した議論が行えるようにする. 以上のような機能を「マンボット」と呼ばれる Joomla!
プラグインとして開発する.マンボット形式で開発する
ことで,Joomla!プラットフォームが持つ移植性の高さや
サイト構築環境ごとの差異吸収のための API を利用で
きるなどのメリットを享受でき,開発物の分量を最小限
に抑えることができる(Mambo CMS Project,2006). こうした GeoSLS の機能的側面での構成は図 2 のよ
うになる.
図 2 アプリケーション構成図
システムを具体化する上で,できる限りオープンソース
の技術を採用した.商用ソフトの利用には費用がかかる
ため避けたという理由もあるが,オープンソースソフトウェ
アは世界中の開発者によって日々開発が行われている
ため,自作するよりも安定しており脆弱性の修復も頻繁
に行われるという理由によるところが大きい.またベース
となる地図データについてはサイト構築者が用意するの
は金銭的にも技術的にも困難であると考え,無償で簡便
に利用できる Google Maps API[7] を利用することとした. 3.3 必要とされるデータ
GeoSLS では記事内の住所や目標物名の判別による
地図の自動埋め込み機能などを実現するため,住所と
緯度経度の対応データベース,および目標物名と緯度
経度の対応データベースが必要となる.住所データベー
スは表 2 の形式のように都道府県から番地までを住所列
に含む.目標物名データベースは表 3 の形式となる.
表 2 住所データベースの例 住所 ID 住所 緯度 経度
1 神奈川県藤沢市朝日町 1-1 35.3389549 139.4911041
2 神奈川県藤沢市朝日町 1-3 35.3384514 139.4918365
3 神奈川県藤沢市朝日町 1-6 35.3397293 139.4911346
表 3 目標物名データベースの例
目標物 ID 目標物名 緯度 経度
1 高橋造園 35.4037209 139.4167480
2 普川植木株式会社 35.3898926 139.4404907
3 藤好園 35.3991127 139.4047852
4. GeoSLS の実装 GeoSLS の開発と平行して構築を進めている「湘南の
風」では,Joomla!と Gallery をインストールしサイトを構築
中である.本研究においてソースコードによる実装を必
要とするのは 3.2 節で挙げた機能である.そのうち現在ま
でに実装した機能は,文章中の住所および店舗名判別
による地図自動埋め込み機能,文章内容に沿った関連
写真の自動埋め込み機能,記事タイトルのオートリンクに
よるサイト内ナビゲーション機能の 3 つである. これらの機能については単一のマンボットにまとめた.
ユーザが入力したテキストはそのままの状態でデータベ
ースに格納されるが,ウェブブラウザを介して記事の表
示リクエストが行われた際に記事テキストに対して動的に

図 3 のフローで示される処理を行うことでこれら 3 つの
機能を実現している.
図 3 マンボットの処理フロー
これらの処理を順に説明する. 1) 処理が必要か判断
あらかじめ管理者が設定したポリシーに従って当該
記事に対して処理が必要かどうかを判断し,処理が不
要であれば終了する. 2) 設定項目の読み込み
管理者による設定項目を読み込む.設定項目には,
地図埋め込みやオートリンクといった機能ごとの有効
あるいは無効,地図の表示サイズなどがある.
3) GeoTag の処理
次の 3 つのいずれかの形式で表される文字列を
GeoSLS では「GeoTag」と呼ぶ.
[geo:lat=<緯度>,geo:lng=<経度>]
[geo:name=<目標物名>]
[geo:addr=<住所>]
これらは地図を表示させるためにユーザによって記
事中に記述される.GeoTagを記述する際は,<緯度>と
<経度>は度単位の数値に,<目標物名>と<住所>は適
切な文字列にそれぞれ置き換える.ユーザが入力した
テキストの中に GeoTag が含まれていると,それが表示
される際に地図のプロットへと置き換えられる.緯度経
度が指定された場合はその場所にプロットされるが,
目標物名や住所が指定された場合はジオコードを行
った結果となる緯度経度にプロットが行われる.
4) 形態素解析
フローの後ほどの処理で記事から特徴語および地名
語を抽出するため,MeCab[8] という形態素解析ソフト
ウェアを用いてタイトルおよび本文の形態素解析を行
う.結果は図 4 のようになる.
藤沢 名詞,固有名詞,地域,一般,*,*,藤沢,フジサワ,フジサワ 市 名詞,接尾,地域,*,*,*,市,シ,シ 遠藤 名詞,固有名詞,地域,一般,*,*,遠藤,エンドウ,エンドー に 助詞,格助詞,一般,*,*,*,に,ニ,ニ 新た 名詞,形容動詞語幹,*,*,*,*,新た,アラタ,アラタ に 助詞,副詞化,*,*,*,*,に,ニ,ニ 建設 名詞,サ変接続,*,*,*,*,建設,ケンセツ,ケンセツ さ 動詞,自立,*,*,サ変・スル,未然レル接続,する,サ,サ れ 動詞,接尾,*,*,一段,連用形,れる,レ,レ つつ 助詞,接続助詞,*,*,*,*,つつ,ツツ,ツツ ある 動詞,自立,*,*,五段・ラ行,基本形,ある,アル,アル
図 4 形態素解析結果の例 5) 特徴語・地名語抽出
ここで特徴語とは文章を代表する特徴的な語という意
味であり,文章中に出現する特徴的な名詞を指す.タイト
ルと本文それぞれの形態素解析結果を利用してこの特
徴語と地名語の抽出を個別に行う.次にそれぞれの抽出
方法について述べる. 5.1) 特徴語の抽出
名詞であるが助数詞でない形態素を探す.それが 2語以上連続していて最後の形態素が「市」または「町」
のいずれでもないものを複合語として抽出する.また 1語のみの場合は固有名詞であって地域でないものを
意味する形態素を抽出する.以上の処理で抽出された
それぞれの複合語および形態素を特徴語とする. 5.2) 地名語の抽出
名詞であり地域を表す形態素を抽出する.その際連続
している形態素は連結する.また住所を抽出するため,
地名語の直後に続く数,「-」(ハイフン),一般名詞も地名
語として連結する.こうして抽出したそれぞれの文字列が
数で終わっている場合は住所と見なし地名語とする.最
後が数でない場合は目標物名データベースから検索を
行い,目標物名に完全一致するレコードがある場合のみ
地名語とし,また目標物名としてマークしておく. 6) 関連写真の抽出
写真管理のために使用している Gallery のデータベー
スから,タイトルまたはコメントに特徴語あるいは目標物
名を含む写真を検索し,該当した写真を関連写真とする.
その際タイトルから抽出された特徴語・目標物名を含む
写真は本文をもとに抽出された写真よりも関連が強いと
見なし,関連写真リストの先頭に配置する. 7) ジオコード
抽出された特徴語や地名語を地図へのプロットに変換
するため,データベースを用いて緯度経度を検索する.
地名語のうち住所については住所データベースの住
所列を用いて部分一致による検索を行う.一方,特徴語
と地名語のうちの目標物名については目標物名データ

ベースから部分一致による検索を行うが,この際多少
の曖昧さを残すため検索語を形態素に分解した状態
で検索を実行する.例えば特徴語として「看護医療学
部」と抽出された場合にそのまま検索するのではなく,
形態素である「看護」「医療」「学部」をそれぞれ全部目
標物名に含むレコードを検索する.
検索の結果抽出されたレコードの目標物名と検索文
字列との文字列長の類似度を計算する.文字列長の
類似度 similarityは次の式によって求められる.
ここで A は検索文字列の文字列長を表し,B は検索
結果レコードに含まれる目標物名の文字列長を表す.
経験上,similarityが0未満の場合は関連が薄いことが
多かったため,ジオコード結果から除外することとした. 8) 関連写真の埋め込み
6)関連写真の抽出 において抽出された写真を記
事に埋め込む.その際管理者設定より決められた上限
枚数を超えた分の写真は表示しない.この結果図 5 の
ような表示となる.
図 5 関連写真がページに埋め込まれた様子
9) 記事タイトルのオートリンク
管理者設定により定められた範囲の全記事のタイト
ルリストを Joomla!データベースから取得する.表示し
ようとしている記事内に他記事のタイトルが含まれてい
ればそれを当該記事へのリンクに自動的に変換(オー
トリンク)し,図 6 のような結果を得る.
図 6 オートリンクが行われた様子
10) 地図の埋め込み
GeoTag とジオコードにより緯度経度が抽出されたもの
すべてをプロットリストとする.プロットリストが 1 件でもある
場合は地図を埋め込む.Google Maps API を利用してプ
ロットごとにピンを立て,吹き出し内にそのプロットに関す
る情報を表示する.その際同緯度経度のプロットが複数
あれば同じ地点として一つのピンにまとめ,吹き出し内に
情報を並べて表示する.例えば,図 7 では「へっつい庵
ごんばち」という目標物名と「神奈川県藤沢市打戻 2982」
という住所が同じ緯度経度を表すため,一つの吹き出し
内にまとめて表示している.目標物名からプロットを行う
場合はその目標物名と完全一致する記事タイトルがあれ
ば当該記事へのリンクを作成し,さらに当該記事の概要
文をその下に埋め込むことで情報を補足している. 最後にプロットリストすべての緯度経度の中心点を計
算し,そこを地図の表示中心点とする.
図 7 地図の埋め込みが行われた様子
以上の処理を経て GeoSLS の記事の表示が行われる.
4. 現状での課題 4.1 特徴語・地名語抽出の精度 特徴語と地名語の抽出では形態素解析を用いてい
るが,形態素解析は辞書を元に行われる.現状の辞書
には一般的な語は含まれているが,地域の寺社名など
特殊な語は含まれていないため,形態素解析で誤っ
た結果が出てしまうことになる.こういった特殊な語は
現状では一つずつ手作業で辞書に加えていく必要が
あり,作業量としても少なくないが,記事タイトルに連動
して自動的に辞書に新語が追加されるようにするなど
の自動化の方法を今後模索していく.

4.2 関連写真抽出の精度 関連写真の抽出には写真に付随するタイトルおよ
びコメントを利用しているが,それらが適切に設定さ
れていなければ写真の抽出精度は著しく落ちる.す
べてのユーザが登録する写真に適切なタイトルとコ
メントが付与される保証はない.しかし現状の文字列
検索による抽出手法のほかに別の手法による関連
写真の抽出を行えば,それらの結果を組み合わせる
ことでノイズを軽減できるかもしれない.例えば写真
の位置情報を利用する場合,記事テキストの解析に
より導出された位置情報とあまりに離れた場所の写
真ならば除外する,といった方法が可能だろう. 5. GeoSLS の完成と一般公開に向けて 5.1 SNS の統合
GeoSLS は住民をはじめその地域に関わる人々を
ユーザとして想定しているが,普段は会う機会を持
てない人どうしでもウェブ上ではコミュニケーションが
可能になるといったように,地域での SNS の活用意
義は十分にある.3.2 節で述べたように,ユーザどう
しをつなぐコミュニケーションツールの提供を目標と
して SNS の統合を進める.
5.2 地図データの統合 現状の地図利用は Google Maps API をベースとし,
ポイントデータを載せて表示するにとどまっている.
厳研究室をはじめ GIS に関する研究を行っていると
ころでは,有用な地理データを ArcGISのシェープフ
ァイル(ESRI ジャパン,2007)という形式で保持して
いる場合が多いが,それを地図画像に落とし込んだ
状態で公開するのは技術的に高度かつ複雑な作業
を要するためあまり行われていないのが現状である.
ラインやポリゴンなど多彩な地理データを含むシェ
ープファイルをインポートでき,またわかりやすく表
現できるような機能があれば,地域情報サイトとして
の利用価値がますます高まるだろう. 5.3 ウェブサービスの提供 ウェブサービスとして,サイト外部のプログラムから
サイト内の情報を利用しやすくするAPIを提供するこ
とは,GeoSLS に開発者やユーザを巻き込む上で重
要である.サイト内に有益な地域情報が蓄積されて
いれば,他の開発者による派生物の出現を促し,結
果的にサイトユーザの増加につながると考えられる.
またオートリンクや地図埋め込みといった機能を他の
サイトに開放することも同じく効果的だろう.HTML 中
に 1 行埋め込めば自動的にページ内の住所を判別し
て関連する地図を埋め込んでくれるような便利なサー
ビスならば,多くの利用者を見込むことができるだろう.
5.4 GeoSLS の一般公開 これらの機能を完成させた後,GeoSLS としてのパッ
ケージ化を行う.おそらく完成物となる GeoSLS は
Joomla!,Gallery,およびマンボットを組み合わせたも
のとなるだろう.そして公開のために詳細なドキュメント
を作成し,適切な期間のテスト運用を経て,GeoSLS の
一般公開を行う予定である. 公開後は誰でも無償でGeoSLSのダウンロードやイン
ストールができ,すぐに地域情報共有サイトを構築でき
るようになるだろう. 謝辞
本研究は朝日航洋株式会社との共同研究事業とし
て行われているものである.本研究全般にわたって,
厳網林先生より多大なご指導を頂いた.また東京大学
大学院柴崎研究室の宮崎浩之氏には本論文作成にあ
たり貴重な助言を頂いた.ここに感謝の意を表したい. [1] http://www.sns.mm-chiyoda.jp/ [2] http://ecogis.jp/satoyama/ [3] http://www.cmsmatrix.org/ [4] http://www.joomla.org/ [5] http://www.xoops.org/ [6] http://gallery.menalto.com/ [7] http://www.google.com/apis/maps/ [8] http://mecab.sourceforge.jp/ 参考文献 ESRI ジャパン(2007)シェープファイル. <http://www.esrij.com/gis_data/shape/index.shtml>. P.・モービル著,浅野紀子訳(2006)『アンビエント・ファ
インダビリティ』,オライリージャパン. Mambo CMS Project (2006) Whats in a Mambot. <http://mambo-manual.org/docs/Whats_in_a_Mambot>. Nielsen, J. (2006) Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute. <http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html>.