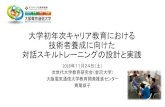(1) キャリア形成支援の取組み内容 - mhlw...PART1 大学におけるキャリア形成支援とキャリア教育 35 (2) 教育領域でキャリアコンサルタントが活用されている分野
シリーズ「キャリア教育」 秋田県のキャリア教育60 Kawaijuku Guideline 2013.4・5...
Transcript of シリーズ「キャリア教育」 秋田県のキャリア教育60 Kawaijuku Guideline 2013.4・5...

Kawaijuku Guideline 2013.4・5 59
ンターンシップを経験する生徒数は右肩上がりに増加して 2012 年度は全体の 61%が参加を予定している。 2006 年度には「高卒就職者リサーチ事業」を実施した。これは、秋田県における離職者・転職者・フリーター等の実態を把握し、今後の施策に生かすことを目的としたものである。内容は、2003 〜 2005 年度に秋田県立高校を卒業した就職者と、県内の事業所への追跡調査である。 「調査は、県内の高卒就業者約 2,000 名と、県内の高卒就職者数の多い 50 の事業所に対して行った大規模なものでした。その調査の結果、明らかになったのが、キャリア教育で育てるべき力、例えばコミュニケーション能力、意思決定能力、協調性や忍耐力といった、社会人として求められるような力に課題があるということでした。このような課題意識に基づいてその後の事業が展開されることとなりました」と藤澤指導主事は振り返る。
この調査結果を受け、2007 年度に「高等学校キャリア教育推進協議会」が発足した。協議会には、全ての公立高校のキャリア教育担当教員が参加する。
2010 年 12 月、秋田県教育委員会は、2011(平成
23)年度から 2015(平成 27)年度に関する『第六次秋
田県高等学校総合整備計画』を発表した。「生徒の社会
的自立」を縦糸に 「時代の変化に柔軟に対応した学校づ
くり」を横糸に、向こう5年間における秋田県の高等学
校教育の方向性を示したものである。「生徒の社会的自
立」、すなわち生徒が自らのキャリア形成を行っていく
力の育成を重視した同県の取組について、秋田県教育庁
高校教育課指導班 熊澤耕生主任指導主事と藤澤修指導
主事に話を伺った。
「第六次秋田県高等学校総合整備計画」における「生徒の社会的自立を目指した教育活動の推進」の具体的な施策としては、「キャリア教育の充実と学力向上に向けた取組の推進」「国際社会を力強く生きぬく教育の推進」
「地域の教育力を活用した学校間連携と地域社会との連携の強化」「各教科等の重点的な取組」の4つの柱が設けられた<表1>。 まず、秋田県のこれまでのキャリア教育を概観すると、日本における雇用形態の変化、若者の早期離職、フリーターやニートの増加といった社会問題が顕在化する中、2003 年度から、生徒に勤労観、職業観を身に付けさせ、主体的な職業選択能力の育成を目的とした「高校生インターンシップ推進事業」を開始した。事業開始以来、イ
高卒就職者の追跡調査によりキャリア教育の必要性が鮮明に
各都道府県のキャリア教育に対する考え方や政策も、高校のキャリア教育に影響を与えている。そこで、4・5月号では、都道府県のキャリア教育に関する方針や政策を聞くとともに、その都道府県の高校にキャリア教育に関する話を聞いた。今回は、児童・生徒のキャリア形成を行う力を重視した政策を行っている秋田県と、県の「キャリア教育実践モデル校」の指定を機にインターンシップを実施した、秋田県立湯沢高校を取材した。
高校間で情報交換し、小・中学校、大学でのキャリア教育を踏まえた上で、自校の計画を立案
「連携」がキーワード小・中・高・大学との連携や地域、高校間の連携を推進するコーディネーター的役割を担う秋田県教育庁
藤澤修 指導主事熊澤耕生 主任指導主事
第 9 回 シリーズ「キャリア教育」
秋田県のキャリア教育

60 Kawaijuku Guideline 2013.4・5
「ここでは各高校がキャリア教育の実践事例を発表して内容を共有するほか、小・中学校や、国際教養大学など県内の大学のキャリア教育の実践例についても講演していただいています。また、午後からは分科会に分かれ、実践についての情報交換と協議を行っています。2012年度は、副校長・教頭の分科会も設け、各校がそれぞれの学校で策定したキャリア教育全体計画を持ち寄り、それをもとに協議を行いました」(藤澤指導主事) 協議会に他校種の講演を取り入れた狙いは、高校の前と後のキャリア教育を知ることにより、生徒が中学校で既に行った体験と同じことを高校で繰り返すことがないようにし、また、生徒の体験を知った上で、自校の生徒にあったキャリア教育のプログラムを立案することにある。 秋田県ではさらに、数年前から、中学校が高校入学時に送付する生徒指導要録の写しに各生徒が中学時代にどのような体験活動をしたかを記載することとしている。 2012 年度から、義務教育課では県内全ての公立の小学生と中学生に「キャリアノート」を配布した。これによって生徒は、高校にキャリアノートを持ち上がることができる。キャリアノートは小学校・中学校版と、中学校版の2種類ある。このように小・中・高を貫く形でのキャリア教育が推進されている。また、このキャリアノートは生徒にとって、自分自身のポートフォリオであり、進路を考えるための振り返りの材料ともなる。
そして高校は、生徒の中学校までの取組を踏まえて自校のキャリア教育を立案する。 熊澤主任指導主事は「キャリア教育の『全体計画』策定過程では、各校で組織的に議論することが大切だと考えています」と話す。藤澤指導主事も「キャリア教育担当の先生だけが話し合うのではなく、例えば、国語の授業で思考力を身に付けさせようという意見が出た場合
『本当に国語だけでいいのか』といった意見が出て、他教科でも取り組めることはないかと考えながら全体計画を作ってほしいと思います」と言う。 この全体計画の中にインターンシップやボランティア活動等の体験的な活動が位置付けられるが、教育庁では、各高校で具体的に何を目標にどう取り組むのかに関する規定は設けていない。「高校卒業後、就職する生徒が多い学校、大学進学者が多い学校と、高校によってインターンシップに対するスタンスは異なるはず」というのがその理由である。ただし、事前・事後指導は重要だと認識しており、インターンシップの事例の共有は、キャリア教育推進協議会などを通して積極的に行っている。 「まず、インターンシップありきではなく、各校が教科の授業を含めた教育活動全体の中に位置付けることが重要です」(熊澤主任指導主事) 教科の授業の中でのキャリア教育について、教育庁としては、「指導主事が学校訪問で授業参観をする際、授業の中に、生徒同士で協議したり、それをまとめて発表するような場面を取り入れたりするようお願いしています」と熊澤主任指導主事は説明する。藤澤指導主事も「全ての授業時間で生徒同士が学び合う時間を作る必要はあ
(第六次秋田県高等学校総合整備計画「計画の体系図」より)
「生徒の社会的自立を目指した教育活動の推進」部分を抜粋。総合整備計画にはもう1つ「時代の大きな変化に柔軟に対応できる新たな学校づくりの推進」という柱もある。
各校が組織的な議論の上で自校にあった計画を立案することが大切
<表1>生徒の社会的自立を目指した教育活動の推進 <キャリアノート>
「キャリア教育」第 9回 秋田県のキャリア教育
キャリア教育の充実と学力向上に向けた取組の推進
国際社会を力強く生きぬく教育の推進
個のレベルやニーズに応じた多様なプログラムの実践
授業改善による学力向上の取組
教員の資質能力の向上
多様な国際教育と国際交流活動の推進
国際社会に対応できる外国語教育の推進
情報教育の充実
環境教育の推進
地域の教育力を活用した学校間連携と地域社会との連携の強化
小学校・中学校・特別支援学校及び高等教育機関との連携
地域資源の活用と地域社会との連携
計画期間内の重点実践事項の設定各教科等の重点的な取組

Kawaijuku Guideline 2013.4・5 61
りませんが、要所要所で生徒が協議をする時間を取り入れることで学習意欲が高まり、基礎的・基本的な知識・技能や思考力・判断力・表現力等の、いわゆる学力の3要素を育成することにつながっていくと考えます」と続ける。
このほか教育庁では、高校へのキャリア教育支援策として、2008 年度と 09 年度に「高校生パワーアップ推進事業」を実施した。これは、大学教員をはじめとする外部講師等の活用、博士号取得者の教員採用(課題研究等の指導で活躍)、キャリアアドバイザー等の活用、ものづくり教育支援などからなるものである。 2010 年度から 12 年度にかけては、これまでの事業をさらに強化した、学力向上とキャリア教育の推進を目指す「高校生未来創造支援事業」を実施した。取組は、<表2>のように地域医療に携わる医師不足解消を目指す
「地域医療を支えるドクター育成事業」、キャリアアドバイザーの配置、インターンシップ・ボランティア活動の充実、キャリア教育実践モデル校の指定からなる「キャリア教育等推進事業」などの5つからなる。 なお、キャリアアドバイザーは、2008 年度から設置されており、現在 10 名が配置されているが、2013 年度からは 19 名が配置される予定となっている。アドバイザーは、それぞれが担当する高校のキャリア教育支援のほか、要請があれば、近隣高校のキャリア教育の支援も行っている。 また、キャリアアドバイザーが担当する仕事の1つに「ふるさとものづくり企業紹介事業」がある。これは、日本や世界シェア上位の県内企業にスポットライトを当てて紹介する事業である。「この事業には、高校生に秋
田県の産業や県内企業の素晴らしさについて認識を深めてもらうと同時に、世の中には多様な業種があることを知ってもらうといった目的があります」(熊澤主任指導主事)
2013 年度からは「高校生未来創造支援事業」を、これまで以上にキャリア教育を前面に押し出したものにする予定だという。 新しい取組には3つの目玉がある。1つめは、大学進学を希望する高校1年生の希望者を募り、夏休みに秋田市内に集まり、2泊3日の日程で、大学の学問ガイダンスや研究室訪問を行う計画である。「秋田県は広いため、県南や県北地域の生徒は宿泊しなければなりません。しかし、宿泊することで、違う学校の生徒同士がお互いに刺激し合えるという良さもあります」(熊澤主任指導主事) 2つめは、地域との連携強化プロジェクトである。「高校生が地域の活動に参加する機会が少しずつ増えています。町おこしの企画に参加したり、地域イベントの運営に参加したりするなど、地域の活性化に高校生が一役買うことも目的の1つですが、生徒自身にとって貴重な体験であり、成長につながることを期待しています。これは、高校から申請された企画を教育委員会が審査して、採用されたものに予算的な支援を行うことになると思います」(熊澤主任指導主事) そして3つめが、高校同士の連携の推進である。「課題研究等の成果発表会を保護者や地域住民に公開している高校がありますが、これに近隣の高校生も招いて、意見交換を行うといった交流などが想定されます」(熊澤
主任指導主事) 以上からわかるように、秋田県の取組に共通するキーワードは「連携」すなわち「小中高大連携」「地域連携」「高校間連携」である。 「高校が、自校の生徒に合ったキャリア教育計画を立案したり、教育を行ったりする上で大切な小学校・中学校・大学との連携や、地域との連携、高校間の連携をスムーズに、そして活発に行うことができる環境を整える。教育庁は、そんなコーディネーターであると考えています」(藤澤指導主事)
小中高大、地域、高校間の連携のコーディネートが教育庁の役割
外部人材の活用やキャリアアドバイザーの配置など県による高校へのキャリア教育支援を実施
<表2>高校生未来創造支援事業(2012年度)
Ⅰ「地域医療を支えるドクター育成事業」(1)地域医療体験研修(県内・県外)(2)メディカルキャンプ(Ⅰ〜Ⅳ)(3)医学部ハイレベル講座・実力養成講座
Ⅱ「習熟度別学習推進事業」(1)進学コース別ハイレベル講座の
①ハイレベルコース ②スーパーハイレベルコース
(2)少人数学習の推進
Ⅲ「プロフェッショナル活用事業」(1)夏季・冬季合宿、思考力養成セミナー(2)教員研修の支援(3)外部講師の活用(4)学術顧問の活用
Ⅳ「キャリア教育等推進事業」(1)キャリアアドバイザーの配置(2)インターンシップ・ボランティア活動の充実(3)キャリア教育実践モデル校の指定
Ⅴ「ものづくり教育支援事業」(1)専門高校ものづくり・技術活動の支援(2)農水フードフェスティバル・産業教育フェア(3)産業教育フェアの開催(4)高校生商品開発コンテスト 他

62 Kawaijuku Guideline 2013.4・5
「キャリア教育」第 9回 秋田県のキャリア教育
「高大連携アドバンスト講義」に加えキャリア教育実践モデル校の指定をきっかけに医療技術・看護系のインターンシップを開始
「通常のオープンキャンパスではなく、大学には本校のために日時を設定してもらってゆっくりと訪問し、大学生の普段の姿を生徒に見せています」(佐藤先生) また、2012 年度は「キャリア教育実践モデル校」に指定されたため、1学年全体で東北大学のオープンキャンパスに参加した。 「『百聞は一見にしかず』の言葉通り、実際に大学を見た上で2年生での文理選択、さらには学部学科選択を考えさせることが目的です」(佐藤先生)
「高大連携アドバンスト講義」は、12 年前から続いている行事で、大学教員を招いて大学と同様の講義をしてもらう「出前授業」である。1年生は全員で、文系・理系それぞれ1つずつ講義を聴いて文理選択の参考にする。2・3年生は、14 大学から 26 名の大学教員を招き、各自興味のある講義を2つ選んで聴講する<表1>。 「湯沢高校の『高大連携アドバンスト講義』は、私が他校にいたときからもその評判を聞いていた取り組みです。通常これだけ多くの大学から、各分野にわたって大学教員にお越しいただくことは難しいのですが、本校でできるのは、長年実施している行事のため大学も毎年そのつもりでいてくださるからだと思います。進路指導部の教員で手分けをして講義を依頼しています。大学に依
秋田市から JR で1時間半ほど、秋田県の南の玄関口
に位置する秋田県立湯沢高校では、多様な分野の大学教
員による出前授業である「高大連携アドバンスト講義」
を実施してきた。さらに、2012 年度秋田県教育委員会
から「キャリア教育実践モデル校」に指定されたことを
機に、医療技術・看護系のインターンシップを開始して
いる。この2つの取り組みを中心に、進路指導主事の佐
藤広幸先生、進路指導副主任の髙橋洋先生、秋田県教育
庁高校教育課キャリアアドバイザーの藤井宏行先生にお
話を伺った。
「師弟共励」を“建学のこころ”とする湯沢高校は、朝学習、放課後補習、土曜補習、長期休業中の補習や1・2年生に対する夏季の勉強合宿、2・3年生に対する夏季特別セミナーなどを実施し、教員と生徒が一体となって、生徒が希望する進路実現に向けて日々切磋琢磨している。 キャリア教育においては「勤労観、職業観を育成し、確実に進路実現ができるキャリア教育を推進する」「自己の能力や適性を見つめ、進路実現に向けて計画的に努力する態度を養う」「将来、湯沢雄勝地区を政治的経済的に活性化していくリーダーを育成する」の3つを目標に掲げている。さらに1年生を「希望進路の選択」、2年生を「希望進路の決定」、3年生を「希望進路の実現」とそれぞれ定めている。 同校のキャリア教育の核となるのが「大学訪問」と「高大連携アドバンスト講義」、さらに 2012 年度から始まった「医療技術・看護系のインターンシップ」である。 「大学訪問」は1年生で、県内の秋田大学、秋田県立大学、国際教養大学と岩手大学の人文社会科学部を訪問して、各自興味のある分野の学部ガイダンスやミニ講義を受けたり、キャンパスの見学を行ったりする。
1年次に大学訪問を実施して2年次からの文理選択に備える
秋田県立湯沢高等学校
藤井宏行先生髙橋洋先生佐藤広幸先生
14大学から26名の大学教員を招いて大学の模擬授業を実施し生徒の知的好奇心を喚起

Kawaijuku Guideline 2013.4・5 63
マを書く生徒も多く、知的好奇心が刺激されている様子がうかがえる。 また、2012 年度は同日の午後に、卒業生で宮城教育大学前学長の高橋孝助氏による進路講演会を開催した。 「高橋孝助先生は、学ぶとはどういうことか、大学にはどんな心構えで進学すべきか、偏差値ではなく学びたい内容で大学や学部・学科を選んでほしいといったことを、熱く語ってくださいました」(佐藤先生) 生徒の感想を見ると、1年生は将来の仕事や生き方を真剣に考えたいという感想、2年生は大学には何のために行くのかという意識を持てたという感想、3年生は大学に入学したらどのように学び過ごしたいかという感想が多く、同じ話でも学年に応じてそれぞれ響くところがあったようだ。
頼する場合は、大学教員の名前や専門を第3希望まで書いて依頼し、調整していただいています。講義する大学教員が決まってからは、私が窓口となってやりとりしています。なお、希望する大学教員は、生徒の目標となるように、なるべく本校の卒業生に依頼しています。今年度初めて JAXA(宇宙航空研究開発機構)の研究者の方に来ていただくことができたのも、本校に同級生の先生がいたからです」と担当の髙橋先生は説明する。 佐藤先生は「生徒には非常に好評で、講義を受けた先生の研究室に入ることを目標にするなど、大学進学に向けてのモチベーションの向上につながっています」と言う。講義後には、生徒に次回聴講したい内容についてアンケートをとり、翌年の参考にしている。アンケートにはその年聴いた講義の内容から興味・関心を広げたテー
<表1>2012年度 アドバンスト講義 内容一覧
No. 学部系統 学科系統 大学 講義題
1
人文科学
語学・国際系東京学芸大学 日本人英語学習者への発音指導〜通じる英語 VS. 通じない英語〜
2 国際教養大学 EXPERIENCE AIU (English and Englishes)
3 歴史 山形大学 足もとはワンダーランド〜埋もれた資料から考える日本の歴史〜
4 教育原理、哲学 茨城大学 教育の“常識”を考える
5
社会科学
法学・法律 岩手大学 裁判員入門〜刑事法の“5W 1H”〜
6 経済・経営 福島大学 我々の暮らしはどうなる?:東日本大震災後の日本経済のゆくえ
7 社会福祉 岩手県立大学 子ども家庭福祉 ―子どもの福祉(well-being)と親支援―
8 経済 東海大学 発展途上国の経済発展と農業の役割:アジアとアフリカの比較から考える
9教育学
障害児教育 秋田大学 特別支援教育の背景と今後の方向
10 教育学 新潟大学 分数のわりざんは、どうして、“ひっくり返してかける”のか?
11 家政学 食物・栄養 秋田大学 食を科学する ―食べ物のおいしさを測る―
12芸術
音楽 山形大学 秋田が生んだ音、音楽 ―先人の音の遺産を辿ってみよう―
13 美術 秋田大学 色の「見え」の仕組みとデザイン
14 体育 体育 福島大学 スポーツ文化を科学する
15理学
生物・バイオ 秋田県立大学 ガラスの中で光合成! 人工光合成への期待
16 化学 新潟大学 燃料電池の「なぜ」
17
工学
環境 群馬大学 これからのエネルギーと脱温暖化 ―楽しい低炭素社会の構築―
18 建築 秋田県立大学 東京スカイツリーの揺れ(地震)対策
19 材料工学 岩手大学 古くて新しい「複合材料」
20 地球・惑星電離圏プラズマ物理学 宇宙科学研究所 青空のかなたの世界 ―君にも出来る宇宙の探査―
21 医学 医学 秋田大学 ドラマ“ブルドクター”の世界
22 薬学 薬学 東北薬科大学 薬を身体の中に入れる方法とその後の体内での運命
23看護・保健学
看護 秋田大学 高齢者のケア
24 理学療法 秋田大学 各種のフォームからみたスポーツ障害と理学療法
(1年生)
25 人文科学領域 秋田大学 歴史を考える資料と史料 ―近世秋田の酒造業を事例に―
26 自然科学領域 秋田大学 秋田のブナと雪のはなし

64 Kawaijuku Guideline 2013.4・5
「キャリア教育」第 9回 秋田県のキャリア教育
医療技術・看護系のインターンシップは、「キャリア教育実践モデル校」の指定をきっかけに始まった。指定とともに赴任したキャリアアドバイザーの藤井先生が受け入れ先病院との調整を担当している。 インターンシップを始めるにあたり医療技術・看護系を選んだのは、同校では毎年 60 名程度、医師、看護師、薬剤師や放射線技師、理学療法士など、医療系の仕事をめざす生徒がいること、学校の中期ビジョン(5カ年計画)で毎年医学科への進学者を輩出することを目標にしていること、近年医学科はもちろん医療技術系や看護の学部・学科も志望者が増えて狭き門となっていることから、生徒のモチベーション向上につなげようという趣旨によるものである。参加者は2年生を中心に募集した。 インターンシップの準備にあたって、藤井先生は「日程の調整が最も難しかった」と振り返る。同校は進学校であるがゆえに夏休みには補習があり、部活動も盛んなため、生徒は部活動を休んでインターンシップに参加することが難しかった。他方、病院も通常の業務で多忙なだけでなく、夏休み期間中には以前からインターンシップを実施している高校の予定が入っていたり、大学や短
大、専門学校の学生の実習の時期と重なったりするなど、受け入れ可能な日程が限られていたからだ。 医師は、秋田市の中通総合病院が毎年実施している「高校生一日医師体験」に、生徒1人が参加した。体験した高校生は他校を含め 16 名で、医師による講演、病院訪問、模擬体験(内視鏡検査、ギプス巻き、縫合)、医師との懇談が行われた。 医療技術・看護系については、湯沢市の雄勝中央病院と、隣接する横手市の平鹿総合病院で行われ、看護部(外科、内科)、薬剤科、放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科、栄養科に分かれて、35 名の生徒(内訳は2年生 32 名、3年生3名)が参加した。両病院で体験した診療科と体験内容は<表2>の通りである。 「初年度ゆえに手探りのインターンシップでしたが、忙しい中、病院が前向きに対応してくださったおかげで生徒はとても充実した体験をすることができました」と藤井先生は言う。 病院側でも、進学校からのインターンシップは初めてということで、戸惑いもあったようだ。病院から、生徒を受け入れるにあたり、あらかじめ体験したいことや仕事についての質問を提出してほしいとの要望が寄せられた。 生徒からは「1日のスケジュールや仕事に関して誇り
<表2>医療技術・看護系インターンシップの内容
JA 厚生連 平鹿総合病院(横手市) JA 厚生連 雄勝中央病院(湯沢市)
日程 体験生徒 体験内容 日程 体験生徒 体験内容
看護部(外科・内科)
6/18―192日間 5名
清潔ケア・患者移送・患者さんとコミュニケーション・看護業務見学
「看護部への質問を事前に用意」
7/25 ―262日間 7/31―8/12日間
6名
3名
(3 年生)
入浴介助・患者搬送食事介助・検査見学他
薬剤科 - - - 7/251日間 1名 講義と見学
軽調剤体験他
放射線科 6/181日間 2名
放射線を使用しない MRI検査において磁場強度の体験等
7/251日間 2名 講義と実務視察見学
臨床検査科 6/181日間 5名 結果内容の見方・講義 7/25
1日間 1名 結果内容の見方講義・実務視察見学
リハビリテーション科(理学療法)
6/181日間 2名 見学及び、可能な範囲で
患者に寄り添う8/201日間 6名 理学療法見学及び、補
助作業への参加
栄養科 - - - 8/8―92日間 2名 盛付・食材発注他
患者栄養指導傍聴
社会医療法人 明和会 中通総合病院(秋田市) 1名「高校生一日医師体験」8月 10 日・オリエンテーション(病院紹介、自己紹介等) ・医師の講演・訪問部門(放射線科、薬剤科、検査科)・ギブス巻体験(他のグループは内視鏡の体験もあり)・縫合体験 ・医師との懇談
体験科
志望者の多い医療技術・看護系で初めてインターンシップを実施

Kawaijuku Guideline 2013.4・5 65
に思うこと」「身につけるのに苦労した手技」「仕事に大切なことを漢字一文字で表現すると」など多様な質問が数多く集まり、病院からは「当日だけでは答えられないから」と、事前に回答が文書で寄せられるなど、生徒・病院双方が高い意識を持ってインターンシップに臨むことができた。 インターンシップの具体的な内容としては、例えば、看護部(外科・内科)では、車いす体験、食事介助といった実習だけでなく、新人看護師との懇談会が開かれた。また、リハビリテーション科では、病院の厚意で、実習に来ていた秋田大学の学生との懇談の場を設けてもらうことができた。 「どちらも大学合格の秘訣や部活動と受験勉強の両立法といった質問が中心になりましたが、病院という場で若い看護師さんや学生さんから話を聴けたことは、生徒のモチベーションアップにつながったと思います」(藤井先生) さらに雄勝中央病院の看護部では、大学の実習に使われている高価な人体看護ケアモデルを使っての手技体験など、通常、高校生では体験できない、看護学校での実習に準じた体験をすることもできた。 インターンシップ終了後は、事後指導として、生徒は活動内容や感想を体験中のスナップ写真とともに、A3用紙1枚にまとめ、礼状を添えて受け入れ先の病院に送った。また、1年生の希望者を対象に体験発表会を開催し、2013 年度の2回目につなげることにした。 インターンシップを終了して、先生方は生徒の成長に確かな手応えを感じている。具体的には、<表3>のインターンシップに参加した生徒の感想を読んで頂きたい。
キャリア教育の今後の課題として、「人手不足と日程調整が挙げられる」と髙橋先生は言う。授業や部活動の顧問をしながら「高大連携アドバンスト講義」の 26 名の教員とやりとりをするには時間が十分ではなく、「インターンシップ」についても、病院側との折衝を担う人手の問題と、日程調整が最大の課題となる。 「本校では現在、これらの行事を進路指導部で担当していますが、今後はキャリア教育担当を新しい分掌として立ち上げて、進路指導部と連携しながら体制の見直しを図り、キャリア教育を充実させていきたいと考えています」(佐藤先生)
◇所在地:秋田県湯沢市字新町 27 番地
◇沿革:1943(昭和 18)年、秋田県立湯沢中学校設立1948(昭和 23)年、学制改革により秋田県立湯沢南高
等学校に改称1959(昭和 34)年、校名を秋田県立湯沢高等学校に
改称
◇学級編成:[全日制]普通科 1学年普通科・理数科6クラス、2・3学年普通科5クラス、理数科1クラス
◇生徒数:男子 348 名、女子 316 名(2012 年4月現在)
◇特色:設立以来、県南の湯沢雄勝地区のセンタースクールとして位置づけられる。生徒のほとんどが国公立大学への進学を希望する進学校で、「全県一生徒が伸びる学校、生徒を伸ばす学校」をモットーに生徒を育成している。部活動も、ハンドボール、陸上、水泳でインターハイ出場や国体出場者、文化部も音楽部や吹奏楽部、演劇部が全国大会や東北大会に出場する部があるなど盛ん。
◇卒業生の進路:2012年3月卒業生 ・進学先:4年制大学(大学校含む)187 名 短期大学 7 名
専門学校 18 名
秋田県立湯沢高等学校
<表3>看護部インターンシップを体験した生徒の感想
インターンシップでは患者さんの背中を清拭したり食事介助をし
たりとさまざまな体験をさせていただきました。車椅子体験では
腕が痛くなり患者さんの大変さがわかりました。心電図や血圧の
測定では自分の臓器が動いていることを実感できました。看護の
仕事が1つ終わる度に手洗いをして清潔が大事だと学ぶととも
に、手洗いの回数だけ達成感を味わうことができました。また挨
拶は患者さんとのコミュニケーションの基本と教えられたので、
私もこれから挨拶を大切にしていきたいと思います。看護の仕事
の大変さを知った一方で、患者さんとふれあう時間が長くやりが
いのある仕事だと感じ、看護師になりたいという気持ちが更に強
くなりました。
雄勝中央病院での人体看護ケアモデルを使った手技体験の様子