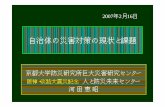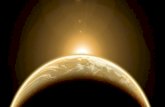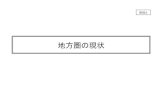岩倉市人口ビジョン(案)...上昇すると、2060年の人口は約1億200万人、2110年には9,026万人程度で安定的に推移するもの...
Transcript of 岩倉市人口ビジョン(案)...上昇すると、2060年の人口は約1億200万人、2110年には9,026万人程度で安定的に推移するもの...
-
0
岩倉市人口ビジョン(案)
平成27年11月
資料 1
-
0
目 次
第1章 我が国の人口の見通し .................................. 1
第2章 岩倉市の人口の現状分析 ................................ 2
1.人口推移に関する分析 .............................................. 2
2.世帯推移に関する分析 .............................................. 7
3.自然増減に関する分析 .............................................. 10
4.社会増減に関する分析 .............................................. 13
5.人口増減に関する分析 .............................................. 18
6.産業別就業者数の推移 .............................................. 19
第3章 人口の将来推計 ........................................ 22
1.推計方法 .......................................................... 22
2.推計結果 .......................................................... 24
第4章 岩倉市のめざすべき方向と人口の将来展望 ................ 29
1.背景 .............................................................. 29
2.めざすべき方向 .................................................... 29
3.人口の将来展望 .................................................... 29
-
1
第1章 我が国の人口の見通し
●日本の人口は、2008 年の1億 2,808 万人をピークに減少し、我が国は人口減少時代へと突入しまし
た。今後は、人口が減少し、2060年では 8,674万人まで減少すると予測されています。
●なお、合計特殊出生率が 2030年に 1.8程度、2040年に 2.07程度まで(2020年には 1.6程度)まで
上昇すると、2060年の人口は約1億 200万人、2110年には 9,026万人程度で安定的に推移するもの
と推計されています。
●このような人口の減少、高齢化に伴ってもたらされる地域の経済や社会への影響を考えると、東京
への一極集中を防ぎ、地方への特に若い世代の人口流入を図り、また出生率を早期に改善させるた
めの対策を講じていく必要性が指摘されています。
-
2
第2章 岩倉市の人口の現状分析
1.人口推移に関する分析
(1)総人口・世帯数の推移
●本市の人口は、1960 年(昭和 35 年)には 14,431 人でしたが、高度経済成長を背景とした都市圏へ
の人口集中、岩倉団地の建設等により人口は急激に増加し、1965年には、21,459人に増加しました。
その 10年後にあたる 1975年(昭和 50年)には 41,935人と、1965年の2倍近くになりました。
●その後、1993 年(平成5年)に地下鉄鶴舞線と名鉄犬山線の相互乗り入れが開始され交通利便性が
一層向上したことなどに伴い、1990年代前半には一時、転入が転出を上回る社会増に転じたものの、
総じて社会減が続いています。一方で、これを上回る形で自然増が続いてきた結果、1985 年(昭和
60年)以降は一貫して人口が増加傾向にあり、2005年(平成 17年)には 47,926人となっています。
●しかしながら、リーマンショック以降の経済環境の悪化と少子高齢化などを背景に 2010年には人口
減少に転じました。その後、ある程度の回復傾向はみられるものの、今後とも人口減少基調は続く
ことが予想されます。
●一方、世帯数については依然として増加基調にあり、2010年には 18,592世帯となっています。
図表 総人口・世帯数の推移(国勢調査)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
人口
(人・世帯)
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
人 口 21,459 33,843 41,935 42,800 42,580 43,807 46,175 46,906 47,926 47,340
世帯数 5,193 8,972 11,818 12,738 12,990 14,313 16,353 17,346 18,724 18,952
世帯数
人口・世帯数の推移(国調)
-
3
●なお、全国や愛知県の人口の推移と比較して、本市では、特に 1975年までの人口増加率が極端に高
く、高度成長期に住宅都市として急激に人口増加した状況が顕著であることが特徴になっています。
図表 総人口の推移(国勢調査)
100
120
140
160
180
200
220
240
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
全 国
愛知県
岩倉市
指数(1965年=100 )
人口の推移(国調/指数・S40基準)
-
4
(2)性別・年齢別人口の推移(人口ピラミッド)
●1980年(昭和 55年)の国勢調査による人口ピラミッドでは、団塊の世代と団塊ジュニア世代が突出
した人口構造になっています。
●しかし、少子高齢化が進み、2010年(平成 22年)の人口ピラミッドではいわゆる釣り鐘型、さらに
は、つぼ型になりつつあります。
図表 人口ピラミッド・5歳階級(国勢調査)
0~4
5~9
10~14
15~19
20~24
25~29
30~34
35~39
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64
65~69
70~74
75~79
80~84
85~89
90~94
95~99
100以上
05001,0001,5002,0002,500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
1,944
2,390
1,894
1,384
1,216
1,707
2,447
2,144
1,740
1,348
1,042
652
491
396
322
172
69
15
4
1
0
1,918
2,179
1,729
1,382
1,323
1,962
2,431
2,020
1,578
1,245
969
775
612
530
364
240
109
40
9
0
0
(人) (人)
[ 国勢調査1980年 ]
女男
0~4
5~9
10~14
15~19
20~24
25~29
30~34
35~39
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64
65~69
70~74
75~79
80~84
85~89
90~94
95~99
100以上
05001,0001,5002,0002,500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
1,172
1,106
1,157
1,053
1,067
1,443
1,722
2,224
1,911
1,566
1,330
1,542
1,791
1,597
1,254
821
498
176
38
11
1
1,097
1,033
1,124
1,108
1,128
1,422
1,754
2,031
1,773
1,469
1,295
1,543
1,887
1,663
1,290
938
636
393
188
49
10
(人) (人)
[ 国勢調査2010年 ]
女男
-
5
図表 最近の人口ピラミッド・各歳推計人口(岩倉市ホームページ H27.4.1現在)
0100200300400500 0 100 200 300 400 500
男 女
(人)(人)
男女別・年齢別人口(住基H27.4.1現)
以上100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0歳
※年少人口:0歳~14 歳 生産年齢人口:15 歳~64 歳 老年人口:65 歳以上
<老年人口>
-
6
(3)年齢3区分別の人口推移
●年少人口は、1975年(昭和 50年)までは増加していましたが、それ以降、減少し続けています。一
方、老年人口は一貫して増加しており、特に 1990 年(平成2年)以降の増加率が高くなっています。
そして、2005年(平成 17年)以降は、老年人口が年少人口を上回る結果になっています。
●生産年齢人口については、日本と同様に、1995 年(平成7年)にピークを迎え、それ以降は減少し
ています。
●なお、2010年(平成 22年)では年少人口割合 15.0%、生産年齢人口割合 64.7%、老年人口割合 20.2%
と、少子高齢化が進んでいます。
図表 年齢3区分別人口の推移(国勢調査)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
年少人口
生産年齢人口
老年人口
(人)
年齢3区分人口の推移(国調)
図表 年齢3区分別人口構成の推移(国勢調査)
0 20 40 60 80 100
1965年
1970年
1975年
1980年
1985年
1990年
1995年
2000年
2005年
2010年
24.9
28.5
29.7
28.2
24.0
18.4
16.3
15.4
14.8
15.0
70.7
67.5
65.9
66.5
69.3
73.2
73.8
71.6
69.1
64.7
4.4
4.0
4.3
5.3
6.5
7.7
9.8
12.4
16.0
20.2
(%)
年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合
年齢3区分人口構成の推移(国調)
-
7
2.世帯推移に関する分析
(1)家族類型別一般世帯数の推移
●本市における 1985 年(昭和 60 年)から 2010 年(平成 22 年)までの家族類型別の世帯数の推移を
みると、三世代同居世帯などの「その他の一般世帯」といわゆる典型的な核家族である「夫婦と子
から成る世帯」は年々減少しています。
●その一方で「単独世帯」や「夫婦のみの世帯」、「ひとり親と子から成る世帯」は増加傾向にあり、
中でも、「単独世帯」については、2010年(平成 22年)には 5,206世帯(27.5%)になり、「夫婦と
子から成る世帯」(6,024人、31.8%)に迫るまでに至っています。また、「夫婦のみの世帯」も 4,300
世帯(22.7%)とかなりのウエイトを占めるようになっています。
●このように、核家族が多くを占めるというかつての住宅都市特有の状況から、「単独世帯」や「夫婦
のみの世帯」が多くを占める小世帯化社会に着実に移行しています。
図表 家族類型別一般世帯数の推移(国勢調査)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
2,088
2,838
3,857
4,248
5,0905,206
6,491 6,393 6,444 6,3736,200
6,024
1,636
2,165
3,017
3,544
4,0764,300
748
9171,031
1,2271,469 1,611
2,0272,000
2,004 1,954 1,889 1,811
( 単独世帯)
( 夫婦と子から成る世帯)
( 夫婦のみの世帯)
( ひとり親と子から成る世帯)
( その他の一般世帯)
(世帯)
家族類型別一般世帯数の推移(国勢調査)
-
8
図表 一般世帯の家族類型比率の推移(国勢調査)
0 20 40 60 80 100
1985年
1990年
1995年
2000年
2005年
2010年
16.1
26.9
26.0
24.5
27.2
27.5
50.0
45.0
39.0
36.7
33.1
31.8
12.6
21.1
21.7
20.4
21.8
22.7
5.8
7.2
7.5
7.1
7.8
8.5
15.6
14.0
12.3
11.3
10.1
9.6
(%)
単独世帯 夫婦と子から成る世帯
夫婦のみの世帯 ひとり親と子から成る世帯
その他の一般世帯
一般世帯の家族類型比率の推移(国勢調査)
※一般世帯:昭和 60 年以降の調査では、「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分しています。一般世帯とは、ア)住居と生計
を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住
み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めています。イ)上記の世帯と住居を共に別に生計を
維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者、ウ)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿
舎,独身寮などに居住している単身者。
-
9
(2)単独世帯の性別・年齢別の推移
●本市において家族類型別比率で最も多くを占める「夫婦と子から成る世帯」に迫るような形で増加
している「単独世帯」について、最近の推移をみると、女性よりも男性の単身世帯の方が多くなっ
ています。
●年齢構成をみる、男性では、30~49 歳が最も多く、しかも 2000 年(平成 12 年)から 2005 年(平成
17 年)にかけて増加しています。これは、男性の晩婚化や外国籍労働者の増加等によるものである
と考えられます。
●一方、女性の単身世帯も増加傾向にありますが、女性の場合は、特に 65歳以上の高齢者の単身世帯
が増加しています。これは、夫の死別等によって単身になるケースが多く含まれているものと考え
られます。
図表 一般世帯の年齢別単独世帯の推移(国勢調査)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000年 2005年 2010年
288 300 232
350 500 502
404
439442
285
366 481226
306452
(世帯)
75歳以上
65~74歳
50~64歳
30~49歳
30歳未満
年齢別単独世帯の推移(女)
女
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000年 2005年 2010年
603 540 484
7981,211 1,267
618
763 877146
215
294
53
85
155
(世帯)
年齢別単独世帯の推移(男)
男
0
500
1,000
1,500
2000年 2005年 2010年
3 0 歳未満
3 0 ~4 9 歳
5 0 ~6 4 歳
6 5 ~7 4 歳
7 5 歳以上
(世帯)
年齢別単独世帯の推移(男)
男
0
500
1,000
1,500
2000年 2005年 2010年
3 0 歳未満
3 0 ~4 9 歳
5 0 ~6 4 歳 6 5 ~7 4 歳
7 5 歳以上
(世帯)
年齢別単独世帯の推移(女)
女
-
10
3.自然増減に関する分析 (1)自然増減の推移
●昭和 49 年から平成 25 年まで一貫して出生数が死亡数を上回っており、自然増になっていますが、
その差は徐々に縮まっており、自然減になることが懸念されます。
図表 自然動態の推移(資料:「愛知統計年鑑」〈住民基本台帳人口〉 日本人、S54 は愛知県住民異動調査)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
S49
S54
S59
H1
H6
H8
H9
H10
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
1,130
768
638
540588 590
614
548
621585542 556 559
502481509484520475507
447 440
204156 163
215 218243 238 249
265 261 277 260 266287307 320
355316344
411384 356
出生
死亡
(人)
自然動態の推移(住基日本人)
※S49 と S54、H25 については、当該年の1月1日から 12月 31 日までの期間。これら以外は、当該年の前年の4月1日から
当該年の3月 31 日までの期間。
-
11
(2)合計特殊出生率の推移
●本市の合計特殊出生率は、全国や愛知県と比較しても若干高い水準で推移しているものの、平成 25
年では 1.49であり、希望出生率と言われている 1.80はもとより、人口増加につながる 2.07とは開
きがあります。
図表 自然動態の推移
(資料 全国:厚労省 人口動態統計、愛知県:愛知県統計年鑑、岩倉市:愛知県衛生年報・国勢調査及び人口動態
調査女性人口各年 10月 1 日現在で算出)
1.2
1.4
1.6
1.8
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
全国
愛知県
岩倉市
合計特殊出生率の推移(岩倉市の女性人口:国調および人口動態統計調査)
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
全 国 1.32 1.29 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43
愛知県 1.34 1.32 1.34 1.34 1.36 1.38 1.43 1.43 1.52 1.46 1.46 1.47
岩倉市 1.29 1.53 1.36 1.33 1.40 1.42 1.45 1.45 1.52 1.54 1.49 1.49
※岩倉市の合計特殊出生率については、各年に届けられた出生数(愛知県衛生年報)と 15~49 歳の女性人口(国勢調査及び
愛知県人口動態調査 10 月1日)から独自に算出。
(参考)全国の合計特殊出生率と未婚率、有配偶出生率
(合計特殊出生率:厚労省 人口統計、20-49 歳未婚数、配偶関係不詳除く 15 歳以上人口、15-49 歳の有配偶人:国勢調査)
(%)
S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22
0
5
10
15
20
25
19.018.5
19.1
20.2
22.4 22.7 22.421.7
12.011.3 11.7
13.0
14.915.4 15.6 15.4
未婚率(男)
未婚率(女) 未婚率
(%)
有配偶出生率の推移(全国)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
92.7176.82 72.25 65.11 67.03 74.50 72.61
77.49
1.911.75 1.76
1.541.42 1.36
1.261.39
有配偶出生率
合計特殊出生率
合計特殊出生率
有配偶出生率
S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22
0
5
10
15
20
25
19.018.5
19.1
20.2
22.4 22.7 22.421.7
12.011.3 11.7
13.0
14.915.4 15.6 15.4
未婚率(男)
未婚率(女) 未婚率
(%)
有配偶出生率の推移(全国)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
92.7176.82 72.25 65.11 67.03 74.50 72.61
77.49
1.911.75 1.76
1.541.42 1.36
1.261.39
有配偶出生率
合計特殊出生率
合計特殊出生率
有配偶出生率
S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22
0
5
10
15
20
25
19.018.5
19.1
20.2
22.4 22.7 22.421.7
12.011.3 11.7
13.0
14.915.4 15.6 15.4
未婚率(男)
未婚率(女) 未婚率
(%)
有配偶出生率の推移(全国)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
92.7176.82 72.25 65.11 67.03 74.50 72.61
77.49
1.911.75 1.76
1.541.42 1.36
1.261.39
有配偶出生率
合計特殊出生率
合計特殊出生率
有配偶出生率
0
1
2
3
4
5
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
0
1
2
3
4
5
1.75 1.76 1.541.42
1.361.26
1.39
合計特殊出生率
※有配偶者:配偶関係のある人(未婚でない人) 配偶関係不詳:配偶関係がわからない人。
-
12
(3)未婚率の推移
●未婚率(20~49歳人口に占める 20~49歳の未婚者数の割合)の推移をみると、男女とも概ね全国平
均を僅かながら下回る形で推移しており、平成 22年では男性 21.7%、女性 14.8%となっています。
●年齢別にみると、全体的に概ね増加傾向にあり、女性に比べ男性の未婚率が高くなっています。特
に 20~24歳の男女が最も高く、次いで、25~29歳の男女が高く、いずれも 50%を超えています。
●なお、男性については、25~29歳、30~34歳の未婚率が若干低下傾向にあります。
図表 岩倉市の未婚率(20~49歳)の推移(国勢調査:配偶関係 20~49 歳人口)
0
5
10
15
20
25
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
18.519.1
20.2 22.4
22.7 22.421.7
11.3
11.7
13.0 14.9
15.4 15.6 15.4
15.316.8
19.8
23.4
22.6 22.321.7
9.0 10.4
12.8
15.4
15.0 15.2 14.8
全国( 男)
全国( 女)
岩倉市(男)
岩倉市(女)
(%)
未婚率の推移(全国比較)
図表 岩倉市の年齢階層別未婚率(20~49歳)の推移(国勢調査:配偶関係 20~49 歳人口)
0
20
40
60
80
100
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
男2 0 - 2 4
男2 5 - 2 9
男3 0 - 3 4
男3 5 - 3 9
男4 0 - 4 4
男4 5 - 4 9
女2 0 - 2 4
女2 5 - 2 9
女3 0 - 3 4
女3 5 - 3 9
女4 0 - 4 4
女4 5 - 4 9
(%)
年齢階層別未婚率の推移
-
13
4.社会増減に関する分析 (1)社会増減の推移
●昭和 49 年から平成 25 年までの人口の転出・転入状況(社会増減)については、概ね一貫して転出
超過の傾向になっています。
●平成 25年では転入者数 2,017人に対して転出者数 2,159人と、142人の転出超過となっています。
図表 社会動態の推移(資料:「愛知統計年鑑」〈住民基本台帳人口〉日本人、S54は愛知県住民異動調査)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
S49
S54
S59
H1
H6
H8
H9
H10
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
4,168
2,615
2,124
2,484
2,7272,961
2,593 2,575 2,535 2,5782,6382,522
2,226 2,3072,255 2,243
2,4002,337
2,336
2,0291,948
2,017
3,479
3,551
2,785
2,449
2,7222,852
3,028
2,7272,9402,8112,795
2,7192,645
2,6702,6022,515
2,554
2,3452,398
2,3962,309
2,159転入
転出
(人)
社会動態の推移(住基日本人)
※S49 と S54、H25 については、当該年の1月1日から 12月 31 日までの期間。これら以外は、当該年の前年の4月1日から
当該年の3月 31 日までの期間。
図表 転入超過の推移(資料:「愛知統計年鑑」〈住民基本台帳人口〉日本人、S54 は愛知県住民異動調査)
-1,200
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
S49
S54
S59
H1
H6
H8
H9
H10
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
689
-936
-661
355
109
-435
-152
-405
-233-157 -197
-419
-363-347
-272
-154
-8
-62
-367-361
-142
転入超過
(人)
社会動態の推移(住基日本人)
※S49 と S54、H25 については、当該年の1月1日から 12月 31 日までの期間。これら以外は、当該年の前年の4月1日から
当該年の3月 31 日までの期間。
-
14
(2)年齢階層別の人口移動の状況
●平成 24 年、25 年の転入・転出の状況について、年齢階層別にみると、25~29 歳、30~34 歳、20~
24 歳で転入も転出も多くなっています。就職・転勤、結婚、住宅購入などを契機に転入、転出をし
ていることがうかがえます。
●なお、平成 25年では 68人の転出超過になっていますが、中でも0~4歳における転出超過数が 104
人と多くなっています。一方、25~29歳や 20~24歳では、それぞれ、120人、56人の転入超過にな
っています。
●この結果は、平成 12~17年と平成 17~22年における人口移動数(国勢調査)ともほぼ一致しており、
20歳代の若い世代が転入超過であるものの、10歳未満の子どもと 30歳代や 40歳代前半の年齢層が
転出超過になっていることが岩倉市の社会移動の特徴となっています。
図表 最近の年齢階層別人口移動の状況(住民基本台帳 市町村転入転出数)
転入 転出 転入超過数 転入 転出 転入超過数
総数 1,992 2,096 △ 104 2,156 2,224 △ 680~4歳 137 204 △ 67 154 258 △ 1045~9歳 66 80 △ 14 75 88 △ 13
10~14歳 33 31 2 43 53 △ 1015~19歳 62 73 △ 11 64 69 △ 520~24歳 237 220 17 252 196 5625~29歳 374 387 △ 13 473 353 12030~34歳 353 334 19 347 373 △ 2635~39歳 213 242 △ 29 251 253 △ 240~44歳 144 160 △ 16 138 175 △ 3745~49歳 84 85 △ 1 108 101 750~54歳 70 68 2 58 60 △ 255~59歳 45 47 △ 2 42 60 △ 1860~64歳 64 57 7 52 78 △ 2665~69歳 30 29 1 33 35 △ 270~74歳 27 25 2 23 22 175~79歳 19 18 1 27 18 980~84歳 14 20 △ 6 4 9 △ 585~89歳 10 10 0 8 18 △ 1090歳以上 10 6 4 4 5 △ 1
H24 H25
0
500
1000
1500
2000
2500
137
237
374 473
353
0~4歳
20~24歳
25~29歳25~29歳
30~34歳
(人)90歳以上
85~89歳
80~84歳
75~79歳
70~74歳
65~69歳
60~64歳
55~59歳
50~54歳
45~49歳
40~44歳
35~39歳
30~34歳
25~29歳
20~24歳
15~19歳
10~14歳
5~9歳
0~4歳
年齢階級別人口移動状況(H24、H25)
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
H24 H25
-220-196
-387 -353
20~24歳 20~24歳25~29歳 25~29歳
(人)
※転出の値はグラフの便宜上マイナスとしている
-
15
図表 男女別・5歳階級別の人口移動数(国勢調査より独自に算出)
-196
-53 -37 -35
289
41
-168
-62
-110
-42
-63 -90 -83
-41 -20
0
29
-43
-153
-50
3 -8
265
142
-220
-57
74 49
28
-50 -45
-3 -15 8 25
-4
-300
-200
-100
0
100
200
300
H17~22
H12~17
(人) 男
-168
-58
-13
30
173
46
-128
-155
-50 -31
-37 -31 -37
0
-20 -10
91
-30
-168
-77
-9
60
243
-41
-103
-13
43 17
-13 -21
-25 -19
-1 -6
62
-24
-300
-200
-100
0
100
200
300
H17~22
H12~17
(人) 女
-
16
(3)最近の転入元・転出先の状況
●平成 24・25年における転入者の転入元と転出者の転出先についてみると、双方とも名古屋市をはじ
めとした近接あるいは隣接している自治体間の人口移動が行われている状況になっています。
図表 近隣市町村への人口移動状況 H24、H25(住民基本台帳 市町村転入転出数)
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
名古屋市
小牧市
一宮市
北名古屋市
江南市
春日井市
犬山市
愛知県その他
319
181175
101 86
4228
294
382
157
194
148
97
6540
301
-290
-176
-226
-175-142
-60 -44
-302
-338
-186-244
-136 -128
-59 -32
-380
左:H24 / 右:H25
岩倉市近隣市町村への人口移動(H24、H25)
※転出の値はグラフの便宜上マイナスとしている
-
17
●平成 22年 10月から平成 26年9月までの4年間における転出入状況をみると、転出入総数は、名古
屋市が最も多く、次いで、小牧市、国外、一宮市、北名古屋市が多くなっています。
●そして、名古屋市や清須市、岐阜県に対しては、転入超過になっていますが、国外や一宮市、江南
市をはじめとした地域に対しては、転出超過になっています。
図表 転出入状況(資料:あいちの人口(年報)平成 22 年 10 月-平成 26 年9月の4年間)
図表 社会増減数(転出入差)(資料:あいちの人口(年報)平成 22年 10 月-平成 26 年9月の4年間)
667 615
江南市
国 外 小牧市
名古屋市
一宮市
岐阜県
犬山市
東京都
神奈川県
994
北名古屋市
稲沢市
岩倉市
742
左側数値:転入数(人)
右側数値:転出数(人)
春日井市
大阪府
三重県
静岡県
1,536 1,330
1,046 1,102 647 994
629 679
410 626
264 389
277 284 241 264
257 210
198 240
175 238
196 194
153 161
江南市
国 外
小牧市
名古屋市
清須市
一宮市
岐阜県
扶桑町
大口町
東京都
神奈川県
50
206
北名古屋市
稲沢市
岩倉市
38
125
42
52
52
56 63
42
216
347 252
-
18
5.人口増減に関する分析 ●昭和 49年から平成 25年までの自然増減、社会増減数を図で表すと、以下のようになります。
●これまで、数年の周期で人口増減を繰り返しながら推移してきています。
●平成 25年も出生超過による自然増は続いているものの、徐々に自然減の方向に近づいています。
図表 自然増数と社会増減数の影響
(資料:「愛知統計年鑑」〈住民基本台帳人口〉日本人、S54 は愛知県住民異動調査)
0
200
400
600
800
1,000
-1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000
S49
S54
S59
H1
H6
H8H9
H10
H12H13
H14H15H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22H23
H24 H25
自然増数(人)
社会増減数(人)
人口増加
人口減少
※S49 と S54、H25 については、当該年の1月1日から 12月 31 日までの期間。これら以外は、当該年の前年の4月1日から
当該年の3月 31 日までの期間。
-
19
6.産業別就業者数の推移 ●本市の就業者数は平成 22 年で 22,600 人、そのうち第1次産業就業者が 268 人(1.2%)、第2次産
業就業者が 6,846人(30.3%)、第3次産業就業者が 15,486人(68.5%)となっています。
●生産年齢人口の減少に伴って第1次から第3次産業のいずれも就業者数は減少傾向にあります。
●構成比については、第3次産業の構成比が年々多くなり、第 1 次・2次産業については年々構成比
が少なくなる傾向が一貫して続いています。
●第2次産業就業者数の構成比については、愛知県よりは少なく、全国よりも多くなっています。
●産業大分類別・男女別の就業者数をみると、男性では製造業が最も多く、次いで、卸売業・小売業、
運輸業・郵便業となっています。女性では卸売業・小売業が最も多く、次いで製造業、医療・福祉
になっています。
●本市では、全国に比べて製造業や運輸業・郵便業に就業する人が男女ともに多い状況にあります。
また、女性では、電気・ガス・熱供給・水道業の就業者数が全国に比べて多い状況にあります。
図表 産業3分類別就業者数の推移(国勢調査)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
859 723 589 544 418 402 268
7,9028,134
9,168
9,109
8,4167,982
6,846
11,38912,096
13,603
15,81816,266 16,365
15,486
第1次産業
第2次産業
第3次産業
(人)
産業3区分就業者数の推移
図表 産業3分類別就業者構成比の推移(国勢調査)
0 20 40 60 80 100
1980年
1985年
1990年
1995年
2000年
2005年
2010年
4.3
3.5
2.5
2.1
1.7
1.6
1.2
39.2
38.8
39.2
35.8
33.5
32.3
30.3
56.5
57.7
58.2
62.1
64.8
66.1
68.5
(%)
第1次産業 第2次産業 第3次産業
産業3区分就業者 構成比の推移
-
20
図表 産業3分類別就業者構成比 国・県との比較(国勢調査 2010 年)
0 20 40 60 80 100
全国
愛知県
岩倉市
4.2
2.3
1.2
25.2
33.6
30.3
70.6
64.1
68.5
(%)
第1次産業 第2次産業 第3次産業
産業別就業者の構成比 全国・県との比較(H22)
図表 産業大分類別男女別就業者数及び特化係数(国勢調査 2010 年)
※特化係数:全国平均の就業者数の産業別割合に対する岩倉市の産業別割合の比率
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
A農業,林業
B漁業
C鉱業,採石業,砂利採取業
D建設業
E製造業
F電気・ガス・熱供給・水道業
G情報通信業
H運輸業,郵便業
I卸売業,小売業
J金融業,保険業
K不動産業,物品賃貸業
L学術研究,専門・技術サービス業
M宿泊業,飲食サービス業
N生活関連サービス業,娯楽業
O教育,学習支援業
P医療,福祉
Q複合サービス事業
Rサービス業(他に分類されないもの)
S公務(他に分類されるものを除く)
T分類不能の産業
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
就業者数
特化係数
(人)
就業者数(男) 就業者数(女)
特化係数(男) 特化係数(女)
男女別産業大分類別人口
総
数
A
農
業
,
林
業
B
漁
業
C
鉱
業
,
採
石
業
,
砂
利
採
取
業
D
建
設
業
E
製
造
業
F
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業
G
情
報
通
信
業
H
運
輸
業
,
郵
便
業
I
卸
売
業
,
小
売
業
J
金
融
業
,
保
険
業
K
不
動
産
業
,
物
品
賃
貸
業
L
学
術
研
究
,
専
門
・
技
術
サー
ビ
ス
業
M
宿
泊
業
,
飲
食
サー
ビ
ス
業
N
生
活
関
連
サー
ビ
ス
業
,
娯
楽
業
O
教
育
,
学
習
支
援
業
P
医
療
,
福
祉
Q
複
合
サー
ビ
ス
事
業
R
サー
ビ
ス
業
S
公
務
T
分
類
不
能
の
産
業
就業者数(総数) 23,791 268 0 1 1,531 5,314 141 526 2,291 4,172 574 487 637 1,187 736 873 1,745 82 1,438 597 1,191就業者数(男) 13,891 162 0 1 1,313 3,664 109 382 1,637 2,197 238 281 428 432 304 322 360 50 864 376 771就業者数(女) 9,900 106 0 0 218 1,650 32 144 654 1,975 336 206 209 755 432 551 1,385 32 574 221 420特化係数(総数) 0.30 0.00 0.11 0.86 1.38 1.24 0.81 1.78 1.07 0.95 1.10 0.84 0.87 0.84 0.83 0.71 0.55 1.06 0.74 0.86特化係数(男) 0.30 0.00 0.13 0.85 1.35 1.09 0.79 1.53 1.11 0.85 1.01 0.82 0.81 0.84 0.68 0.61 0.57 0.99 0.62 0.95特化係数(女) 0.31 0.00 0.00 0.83 1.43 2.07 0.83 2.80 1.03 1.05 1.23 0.87 0.92 0.85 0.96 0.76 0.51 1.16 1.09 0.74
-
21
図表 産業大分類別年齢階級別就業者数(国勢調査 2010 年)
0 20 40 60 80 100
A 農業,林業
B 漁業
C 鉱業,採石業,砂利採取業
D 建設業
E 製造業
F 電気・ガス・熱供給・水道業
G 情報通信業
H 運輸業,郵便業
I 卸売業,小売業
J 金融業,保険業
K 不動産業,物品賃貸業
L 学術研究,専門・技術サービス業
M 宿泊業,飲食サービス業
N 生活関連サービス業,娯楽業
O 教育,学習支援業
P 医療,福祉
Q 複合サービス事業
R サービス業 (他に分類されないもの)
S 公務 (他に分類されるものを除く)
T 分類不能の産業
(%)
15~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上
産業大分類別年齢構成
15~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上
総数 23,791 16.6 24.3 22.7 18.6 14.0 3.8A 農業,林業 268 1.1 4.9 4.5 8.2 27.6 53.7B 漁業 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0C 鉱業,採石業,砂利採取業 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0D 建設業 1,531 9.2 24.6 21.8 22.4 17.8 4.2E 製造業 5,314 15.9 26.5 23.5 19.0 12.7 2.4F 電気・ガス・熱供給・水道業 141 7.8 39.0 27.0 21.3 5.0 0.0G 情報通信業 526 20.7 36.9 26.2 12.2 3.8 0.2H 運輸業,郵便業 2,291 11.4 23.4 24.5 22.8 16.5 1.4I 卸売業,小売業 4,172 19.2 22.5 21.2 18.3 14.9 3.9J 金融業,保険業 574 19.5 23.7 28.7 20.9 6.4 0.7K 不動産業,物品賃貸業 487 14.0 24.2 18.7 14.2 17.5 11.5L 学術研究,専門・技術サービス業 637 17.1 26.8 24.8 16.5 11.1 3.6M 宿泊業,飲食サービス業 1,187 22.8 20.3 18.1 14.2 20.7 3.9N 生活関連サービス業,娯楽業 736 24.0 20.8 15.8 14.3 18.3 6.8O 教育,学習支援業 873 20.5 20.4 23.5 25.2 8.0 2.4P 医療,福祉 1,745 20.7 25.8 22.3 19.3 9.7 2.2Q 複合サービス事業 82 14.6 28.0 28.0 23.2 4.9 1.2R サービス業 1,438 9.6 20.0 24.1 17.5 21.6 7.2S 公務 597 15.9 27.1 24.6 18.8 11.9 1.7T 分類不能の産業 1,191 21.7 29.1 26.8 13.1 7.0 2.3
就業者総数(人)
年齢構成(%)
-
22
第3章 人口の将来推計
1.推計方法
国立社会保障人口問題研究所が推計した合計特殊出生率、生残率、純移動率をベースに用いてコー
ホート要因法により、以下の3方法で推計を行いました。
推計方法 出生・死亡に関する設定
(出生率・生残率)
移動に関する設定
(純移動率、移動数)
シミュレーション
1
・国立社会保障人口問題研究所の推計
による「合計特殊出生率」、「生残率」
を採用
・国立社会保障人口問題研究所の推計
による「純移動率」を採用
シミュレーション
2
・合計特殊出生率を 2030 年に
1.80、2040 年に 2.07 まで上昇
すると仮定 ※国の長期ビジョンと同値
・生残率は、シミュレーション1と同
じ
・同上
シミュレーション
3
・合計特殊出生率を 2030 年に
1.80、2040 年に 2.07 まで上昇
すると仮定
※国の長期ビジョンと同値
・生残率は、シミュレーション1と同
じ
・国立社会保障人口問題研究所の推計
による「純移動率」を採用
・これまでの推移に加えて、子育て世
帯が5年間で 50 世帯(10 世帯/
年)新たに流入するような移住・定
住施策を行うと仮定
※1世帯40歳未満親子4人想定
※生残率:ある年齢集団(5歳階級)が一定期間後(5年後)に生き残っている比率のこと。
■合計特殊出生率の設定値
推計方法 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年
シミュレーション1 1.48910 1.45655 1.42961 1.43141 1.43387 1.43428 1.43428 1.43428 1.43428 1.43428
シミュレーション2
シミュレーション3 1.59000 1.66000 1.73000 1.80000 1.93500 2.07000 2.07000 2.07000 2.07000 2.07000
-
23
■移住・定住促進のターゲットの家族タイプの設定
家族タイプA 家族タイプB-1 家族タイプB-2
10世帯/5年 5世帯/5年 5世帯/5年
家族タイプC-1 家族タイプC-2 家族タイプD
10世帯/5年 10世帯/5年 10世帯/5年
父親 30-34→
35-39 歳
母親 25-29→
30-34 歳
娘 5-9→
10-14 歳
息子 0-4→
5-9歳
父親 25-29→
30-34 歳
母親 25-29→
30-34歳
娘
0-4→
5-9歳
息子 0-4→
5-9歳
父親 30-34→
35-39 歳
母親 25-29→
30-34 歳
娘
0-4→
5-9歳
息子 5-9→
10-14 歳
父親 35-39→
40-44 歳
母親 35-39→
40-44 歳
娘
5-9→
10-14 歳
息子 5-9→
10-14 歳
父親 30-34→
35-39 歳
母親 30-34→
35-39 歳
娘
0-4→
5-9歳
息子 5-9→
10-14 歳
父親 30-34→
35-39 歳
母親 30-34→
35-39 歳
娘
5-9→
10-14 歳
息子 0-4→
5-9 歳
-
24
2.推計結果
■人口推計結果(総人口)
33,843
41,935
42,80042,508
43,807
46,175
46,906
47,92647,340
46,705
45,827
44,532
42,912
41,078
39,184
37,245
35,240
33,105
30,856
46,849
46,212
45,236
43,993
42,679
41,456
40,187
38,865
37,451
35,988
47,06046,643
45,907
44,926
43,900
42,986
42,038
41,053
39,985
38,874
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
実績
シミュレーション1(社人研推計準拠)
シミュレーション2:出生率増加1.80⇒2.07
シミュレーション3:出生率増加1.80⇒2.07+子育て世帯移住増(10世帯/年)
(人)
実績値 推計値
-
25
■年少人口推計結果
■生産年齢人口推計結果
6,178
5,706
5,183
4,669
4,361
4,142
3,892
3,587
3,270
2,992
6,321
6,091
5,887
5,624 5,6125,746 5,774
5,621
5,3615,194
6,689
6,4326,277
6,119
5,912 5,965
6,1706,269
6,186
5,9865,877
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
シミュレーション1(社人研推計準拠)
シミュレーション2(社人研推計準拠)出生率増加1.80⇒2.07
シミュレーション3:出生率増加1.80⇒2.07+子育て世帯移住増(10世帯/年)
(人)
29,181
27,988
27,222
26,075
24,116
21,731
20,057
18,752
17,682
16,589
29,181
27,988
27,222
26,200
24,465
22,398
21,118
20,34319,936 19,519
31,083
29,281
28,23427,661
26,846
25,334
23,487
22,40021,817 21,626
21,444
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
シミュレーション1(社人研推計準拠)
シミュレーション2(社人研推計準拠)出生率増加1.80⇒2.07
シミュレーション3:出生率増加1.80⇒2.07+子育て世帯移住増(10世帯/年)
(人)(人)
-
26
■老年人口推計結果
■老年人口比率結果
11,347
12,133
12,128 12,168
12,602
13,312
13,295
12,901
12,153
11,274
11,347
12,133
12,128 12,168
12,602
13,312
13,295
12,901
12,153
11,274
9,566
11,347
12,133
12,128 12,168
12,602
13,32913,368
13,050
12,373
11,553
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
シミュレーション1(社人研推計準拠)
シミュレーション2(社人研推計準拠)出生率増加1.80⇒2.07
シミュレーション3:出生率増加1.80⇒2.07+子育て世帯移住増(10世帯/年)
(人)
24.3
26.5
27.2
28.4
30.7
34.0
35.7
36.6 36.7 36.5
24.2
26.3
26.8
27.7
29.5
32.133.1
33.2
32.5
31.3
20.2
24.1
26.026.4
27.1
28.7
31.0
31.8 31.8
30.9
29.7
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
シミュレーション1(社人研推計準拠)
シミュレーション2(社人研推計準拠)出生率増加1.80⇒2.07
シミュレーション3:出生率増加1.80⇒2.07+子育て世帯移住増(10世帯/年)
(%)
-
27
■20~39歳女性人口推計結果
■20~39歳女性人口比率結果
5,487
5,012
4,697
4,5094,294
3,946
3,640
3,337
3,041
2,845
5,487
5,012
4,697
4,509 4,3584,128
3,9833,875
3,775 3,795
6,337
5,527
5,072
4,7824,646
4,5554,391
4,295 4,2204,159 4,225
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
シミュレーション1(社人研推計準拠)
シミュレーション2(社人研推計準拠)出生率増加1.80⇒2.07
シミュレーション3:出生率増加1.80⇒2.07+子育て世帯移住増(10世帯/年)
(人)
11.7
10.9
10.5 10.5 10.5
10.1
9.8 9.5
9.29.2
11.7
10.8
10.410.2 10.2
10.0
9.910.0 10.1
10.5
13.4
11.7
10.9
10.410.3
10.410.2
10.210.3
10.4
10.9
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
シミュレーション1(社人研推計準拠)
シミュレーション2(社人研推計準拠)出生率増加1.80⇒2.07
シミュレーション3:出生率増加1.80⇒2.07+子育て世帯移住増(10世帯/年)
(%)
-
28
■20~39歳女性人口対2010年比結果
86.6
79.1
74.1
71.1
67.8
62.3
57.4
52.7
48.0
44.9
86.6
79.1
74.1
71.168.8
65.1
62.961.2
59.6 59.9
100.0
87.2
80.0
75.5
73.371.9
69.3
67.8 66.665.6
66.7
40
50
60
70
80
90
100
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
シミュレーション1(社人研推計準拠)
シミュレーション2(社人研推計準拠)出生率増加1.80⇒2.07
シミュレーション3:出生率増加1.80⇒2.07+子育て世帯移住増(10世帯/年)
-
29
第4章 岩倉市のめざすべき方向と人口の将来展望
1.背景 ●国の長期ビジョンでは、国民の希望が実現した場合は 2030年に出生率 1.80程度まで、2040年に 2.07
程度に向上すると見込んだ上で、2060年に 1億人程度の人口を確保するとしています。
●また、愛知県人口ビジョン(策定済)においても、出生率を国と同様の 1.80、2.07程度まで向上す
るとして推計を行い、2060 年に 700 万人の人口確保が県として活力を維持する上での人口の目安と
して示されています。
●現在、中間見直しを進めている第4次岩倉市総合計画のまちづくり戦略では、「子育て世代の移住・
定住(世代循環)を促す」として、今後5年間も引き続きまちづくり戦略の実現に向けて取組を進
めることとしています。
2.めざすべき方向 ●岩倉市が単独で出生率の上昇に向けた取組をするのは難しいが、結婚・出産を望む人が安心して結
婚や出産ができるような環境を整え、プロモーションにより若い世代を呼び込み、本市で出産し、
子育て期を過ごし、愛着を持って、定住をしてもらえるような施策を総合的に進めることで出生率
の向上に努めることとします。
●30 代前半及び幼少期の住宅事情による転出をあらゆる施策から防止するとともに、市外から新婚世
帯・子育て世帯を中心とした世帯を多く迎え入れることによって、世代循環を促し、一定の人口減
少を受入れながら、活力を保ち、持続可能な岩倉市をめざすこととします。
●そこで、以下のような見込みの基で将来人口を展望するものとします。
①岩倉市でも人口の将来推計で示したように 2030 年までに出生率 1.8、2040 年までに 2.07 に向上
すると見込むこととする。
②岩倉市の強みである交通の利便性や住環境の良さ、過去から推し進めてきた良好な子育て環境を
全面に押し出し、年間 10 世帯の 40 歳未満の家族がこれまでの推移に加えて新たに転入すること
を見込む。
3.人口の将来展望
国・県の出生率の見込みと歩調を合わせ、出生率増加を見込みつつ、年間 10世帯の 40歳未
満の家族がこれまでの推移に加えて転入する前提で推計し、2040 年で 43,000 人程度の人口
をめざします。
※シミュレーション3を採用