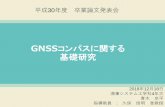東北三省 雪鄉 冰雪畫廊 · 2020. 2. 13. · 東北三省 雪鄉(冰雪畫廊)、哈爾濱(第32屆太陽島雪雕博覽 會+第21 屆冰雪大世界)、吉林(長白島賞霧淞)
ホワイトアウトナビゲーションajk-hiroshima.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/...ホワイトアウトナビゲーション...
Transcript of ホワイトアウトナビゲーションajk-hiroshima.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/...ホワイトアウトナビゲーション...
-
ホワイトアウトナビゲーション
第 2 回 机上学習会
要約
本来は雪山で吹雪など視界が無くなった時にコンパスだ
けで帰ってくる技術ですが、今回は事前にコースと方角を
知っておくことの重要性を学びます。
naoki sakata 2017/4/7
-
1 はじめに
ホワイトアウトナビゲーションとは本来、雪山で吹雪やガスに視界を遮られたときに、事前に作成した「ナビゲーシ
ョン表(同定表)」と「コンパス」を使って、目的地までたどり着く手法のことです。
前回の机上講習では読図の基本と目的地のセットまでを学びましたが、今回はこのホワイトアウトナビゲーション
の技術を使って、山行前に「どんな山に行くのか?」「どこを通るのか?」という準備を各自で出来るようにするこ
とを目的としています。
2 ナビゲーション表の作成手順
① 25,000 分の 1 の地図上に赤線で予定ルートを記入する。 ⇒3.予定ルートの記入
② 通過点をウェイポイントとして、記入していく。ウェイポイントは「山頂などのピーク」「鞍部(コル)」「分岐
点」「上り下りの変化点」「小屋などの建造物」を選ぶ。⇒ 4.ウェイポイントの記入
③ 「ベアリング表」を作成する(任意) ⇒ 5.ベアリング表作成
④ 地図上に「ベアリング」「標高」「距離」などを記入しておく ⇒ 6.ナビゲーション表の完成
3 予定ルートの記入~例題
・宮島桟橋~(榧谷コース)~包ヶ浦分岐~212m峰~(河川沿)~包ヶ浦自然公園~鷹ノ巣高砲台
跡(150m台地)~202m峰~榧谷駅~獅子岩駅~弥山~駒ヶ林~214m峰~厳島神社宝物館(多
宝塔の下~宮島桟橋
※曲線でルートを記入して OK。但し、雪山で使用する場合は、ウェイポイントを先に作成してから、直線で結
んだ方が良い。 ⇒ バックベアリングの問題
4 ウェイポイントの記入~例題
・①宮島桟橋 ②県道 43号(うぐいす歩道分岐)③博奕尾取り付き ④145m峰先のコル ⑤包ヶ浦分
岐 ⑥212m峰 ⑦河川(右股)の始点 ⑧包ヶ浦自然公園(「公」のあたり)⑨鷹ノ巣高砲台跡(150
m台地)⑩202m峰 ⑪榧谷ルートの登山道出会 ⑫407m地点下方 ⑬獅子岩駅 ⑭求聞持堂 ⑮弥
山山頂(ピストン)⑯駒ヶ林(509m)⑰史跡・名勝のマーク ⑱206m転換点 ⑲宝物館
-
5 ベアリング表作成
5.1 歩き出す方向の角度を測る(夏山の場合)
コンパスのケースを回して、中の矢印(線)と磁北線を平行にする(注:磁針はどちらを向いていても良い)
コンパスケースのダイヤル内のメモリと重なった数字(角度)を読む
ウェイポイント③
現在地
磁北線とコンパス
内の線を平行に
合わせる
この目盛と重なる
数字を読む
ルート
ウェイポイント②
ウェイポイント①
-
5.2 ベアリング表(任意で作成) 表の中に①ポイントの目標物名②標高③次のポイントまでの標高差、ベアリング(方向)、バックベアリング距離④登下降時間予想(一応の目安)を記載。
日時 山域
区間 場所 標高(m) 高低差 (m)
進む(ベア リング) 角度
戻る(バッ クベアリン グ)*
距離(m) 時間(min) 備考
* 「進む」が180度までは「戻る」は180度プラスする。 「進む」が181度からは「戻る」は180度マイナスする。
15
14
13
12
11
10
8
9
6
7
5
4
3
1
2
-
6 ナビゲーション表の作成
6.1 夏山の場合(ルート、ベアリング、標高を書き込む)
6.2 雪山の場合(ウェイポイントを直線的につなぐ※)
6
150
ベアリング
標高
800m
42
200
352
250
600m
324
200
1,000m 6
150
6/186
150
ベアリング
バックベアリング
標高
800m
42/222
200
10/190
250
600m
318/138
200
1,000m 358/178
150
※冬山は登山道が雪で
埋まっているので、直線的
に行動するから。
800m
800m
※青字は距離
※青字は距離
-
6.3 ナビゲーション表に合わせた行動
1. コンパスは体の前で水平に持つ
2. ダイヤルを次に進む角度に合わせる
3. 体を動かして、磁針とケース内の矢印に方向を合わせる
※但し、誤差があるので、神経質にならなくて良い。
6.4 距離の測り方~歩測
自分の歩幅を知る ⇒ 100mを何歩で歩けるか複歩(どちらかの足)で数える。
※大体、33~35 歩が標準。但し、登りや下り、曲がり角では誤差が大きくなることを加味すること。
6.5 高度計付きの時計を活用する
但し、時計についている高度計は気圧の変化で測定するため、明確に高度が分かる場所(ピーク、標識な
ど)でこまめに補正しておくことが必要。
※こまめに補正しないとどうなるか?⇒ 「高度が上がる=気圧が下がる」と言う原理で測定しているため、天
気が悪くなる時(低気圧が接近しているとき)には、実際の位置より高く表示するようになる。
6.6 GPS の併用
GPS を過信しない ⇒ 電池が切れる、故障する、小さな画面では根本的な方向違いは分からないなど、落と
し穴も多い。但し、正式な現在位置、標高を知るために、これ以上に正確なものはない。特に冬山には必携。
-
7 終わりに
① 「地図を読む」 ⇒ プランニングをするとき、計画書が配布されてコースが分かった時にすること
② 「地形を読む」 ⇒ 実際の山行ですること
今回は①の手法の一つを学びました。この他にも、「概念図」「アップダウン表」など、まだまだ他にも、「事前に山
を知る方法」はありますので、興味があれば調べて実践して、自分に合うものを見つけてください。
集団で行動することは様々なメリットがありますが、「連れて行ってもらうだけの登山」を続けていると全員が間違
った判断についていくという危険性も含んでいます。
個人が力をつけることは、グループ全体の安全にもつながりますし、単独登山や何らかの理由で単独行動しなく
てはならないときには、必ず必要となりますので、日頃の山行から意識してください。