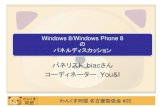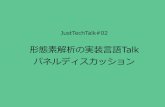パネルディスカッション : 福島の再生と科学技術コミュニケー … · Title パネルディスカッション : 福島の再生と科学技術コミュニケーション
[パネルディスカッション] discussion.pdf133 [パネルディスカッション] 武 井...
Transcript of [パネルディスカッション] discussion.pdf133 [パネルディスカッション] 武 井...
-
133
﹇パネルディスカッション﹈
武
井
協
三
内
田
宗
一
福
田
安
典
﹇司会﹈飯
倉
洋
一
飯倉洋一
それではシンポジウムに入りたいと思います。今日は武井先生の
忍頂寺文庫蔵の貴重本報告と内田さんと福田さんの報告がございました。そ
の三人の方にパネリストとして出ていただいております。武井先生がご紹介
された『女意亭有噺』とその後の内田さん福田さんの発表を重ねるといたし
ますと、『女意亭有噺』のような本をどういう関心で、あるいはどの時点で忍
頂寺務さんが認識したのか、そういう形で繋がってくる問題だと思います。
忍頂寺さんの俳人としての側面こそが本質的な部分ではないかという発表が
福田さんからあり、また、内田さんが今回発見された新聞記事(「名曲鑑賞
軽快なナンセンス物
清元「鳥羽絵」」『東京朝日新聞』昭和七年九月四日、「猟
書の趣味を聴く⑭関西版に目をつけて
歌謡本を捜す
苦心の集成『都踊く
どき』
忍頂寺務氏」『東京日日新聞』昭和九年九月二十一日)からも窺える
歌謡研究者としてだけではなく、より広がりのある忍頂寺務氏の研究学問と
いうのが見えてきたのではないかと思います。時間もあまりございませんの
で、ここでまず最初にパネリストの方々に短い時間で大きな内容を発表をし
-
134
ていただいたので、補足等もあるかもわかりませんし、またそれぞれのご発
表を聞いてのご感想やご意見ご質問等があるかもわかりません。それで、武
井先生から順にお話をいただければと思います。お願いいたします。
武井協三
私は演劇研究の立場でお二方のお話を伺っていました。内田さん
のお話で一番興味を惹いたの
は、八代目坂東三津五郎との関
係でございます。三津五郎とい
う人は河豚で死んだんですけれ
ども、大体河豚に当たって死ん
だのは自殺だったんだろう、わ
ざと河豚に当たったんだろう
と、三津五郎を直接知っている
演劇評論家の方などはそういう
ふうに言います。少なくとも私
が見てきた歌舞伎役者の中では
三津五郎が最もインテリでし
た。歌舞伎学会の会長を務めた今尾哲也という研究者がいます。今尾先生は
同志社大学から早稲田大学の大学院の演劇科に進んだんですけれども、彼は
当時演劇科の教授だった河竹繁俊とかあるいは郡司正勝とか、そういう人を
自分の先生だとは多分思ってないですね。坂東三津五郎が自分の先生だと言
ってるぐらいです。その教養人である三津五郎が、音曲の歌詞についてわか
らないことがあったら、忍頂寺さんに聞けばわかると、多分思ってたんだと
思うんですね。だから、三津五郎でもわからないことを忍頂寺さんに聞けば
わかると思っていたのは、非常に印象深いことでありました。また、福田さ
んのお話の中で中心になったのは俳句が集書の動機になってるんじゃないか
ということなんですけど、やはり別の要素も多分あったんじゃないかと思う
んですね。それは一体何だろうと。教えていただきたいんですけれども、忍
頂寺さんが実際の舞台芸能にどういうふうに接していたのか。たとえば、忍
頂寺さんの書簡なんかで、この間見た中村鴈治郎は面白かったとか、そうい
うものが出てくるのかどうか。芝居を実際どのぐらい見ていたか、全然見な
いということはないと思いますけれど、どの程度御覧になっていたか。それ
から、もう一つは、ご自分では音曲や踊りはなさらなかったのか。清元等の
音曲を実際に自分で上演する、お稽古する過程で集書するという道筋もある
いはあるんじゃないかと考えながら聞かせていただきました。どうもありが
とうございました。
飯倉
では、内田さんお願いします。
内田宗一
書簡は非常に多岐にわたるものですので、言い尽くせない部分は
さまざま出てまいりますが、今回話題に出したことに関しては特に今の段階
で補足はありません。
まず、武井先生にただ今頂いた、忍頂寺さん自身が実際の演劇などとどの
ような関係を持っていたか、ということなんですが、意外と芝居の論評みた
いな記載というものは、忍頂寺氏自身が書いたのではなくて、来翰にはある
かもしれませんが、あまり印象がありません。主に書簡のやり取りの中で問
題となっているのは、近世当時の風俗や人物考証、それからさまざまな言葉
についてであり、芝居を実際に見た鑑賞面での言及は、あまり記憶にありま
せん。ただ、ちょっと記憶があやふやなんですけれども、英十三に務が東京
へ来る機会に合わせて自分の知り合いとも引き合わせたり、芝居があるので
一緒に行こうと誘っているものはあったと記憶しています。それから、自身
が演劇に親しんでいたかどうかですが、清元は実際にやっておりました。お
稽古日についての連絡を記した葉書が残されています。また、素性がわから
-
135
ないんですけれども、名字
はわかりませんが慶吉とい
う人物からの書簡に、「お
得意の一節聞かせていただ
きたい」みたいなことを書
いてるものもあります。で
すから、清元に関しては、
ご自身も結構実演していた
ということが確認できるか
と思います。
それから、福田さんのご発表内容に関連して、書簡を見てきた立場から少
し補足いたしますと、湯朝竹山人との関係が、福田さんのご発表の中で出て
きました。『清元研究』という著書を出版するまでは、出版社との仲介役にな
ったり、お互いにいい関係だったものが、竹山人の言い方を借りれば、一方
的に絶交状を送りつけられた。竹山人の方はそれに憤慨している、という図
式があるんですが、少なくとも昭和五年の段階までは、ある程度深い仲だっ
たと想像されるのに、小野文庫・忍頂寺家に所蔵されている書簡の内、湯朝
竹山人のものは、葉書一通しか残されておりません。想像をたくましくする
に処分したのかなとも推測されます。特に本屋とのやり取りということがあ
れば、その報告等で事務連絡も含めて一定数の書簡が存在していていいはず
なんですが、今一点しかないので、絶交などを機会にご本人が処分したと考
えてもいいんじゃないかな、とちょっと思いました。もう一点は、東京に向
けてどういう視線を向けていたのかという点です。東京へ積極的に出て行こ
うという動き、それが竹山人との対立で一つ大きな壁ができた。その後、関
西の方でも発表の場となる雑誌であったり、サークルのような研究会のよう
なものができてきたので、軸足が移ったと福田さんより御指摘がありました。
確かに竹山人とはその後切れたようですし、竹山人の肩を持ってる島田筑波
に関しては書簡自体が残っておりませんので、直接の行き来があったのかど
うかわかりません。ただ、鳶魚とはその後も繋がりがありますし、それ以外
にも英十三や町田嘉章・高野辰之等、東京の人たちと関連を持ち続けている
側面もあります。特に高野辰之・英十三あたりとは、書簡の数や内容を見て
も、非常に深い仲が昭和五年以降も続いていたようですので、竹山人との対
立というのは東京との関連の中のあくまでも一面ではないか。想像をたくま
しくすれば、東京の全てに向かっていくというわけではなくて、東京の中の
ある人とは切れるけれども別の人とは繋いでいくというような判別を忍頂寺
務が行っていたと考えてもいいのかなと感じました。さらに、確かに初期の
段階では東京の雑誌へどんどん論考を発表しているんですけれども、そもそ
も昭和九年に『上方』が創刊される以前は、発表しようと思ったら東京の雑
誌しかないという状況もあるわけですので、昭和九年以前の段階ではどれだ
け積極的に東京へ出て行きたいという気持ちがあったにせよ、雑誌の発表と
いうところだけで判断し難い面もある。発表しようと思ってもその段階では
関西の雑誌がないんだから、発表したいと思ったら自然東京へとならざるを
えないというところもあります。ですから、東京との関わりを福田さんとは
違う角度から眺めることもできるのではないかというのが発表を聞いての私
の意見です。以上です。
飯倉
ありがとうございます。じゃあ、続いて福田さん。
福田安典
まず、武井先生にお答えしないといけないのですが、私の作った
レジュメ九ページ目に載せておきましたが、忍頂寺務さんは阪神で三代目清
元順三に習って清元をやっていました。これははっきりしています。もう一
つは、これはお聞きした話だけなんだけど、実際にお金のあるときには芸者
-
136
をあげて、習って披露されていたそうです。そして、第二点なんですが、内
田さんの作られた七ページ目の昭和六年七月二十二日付鳶魚からの書簡の「折
柄今昔へ御加勢願上候」は、『今
昔』に投稿せよというのではな
いのではないか。『今昔』は島田
筑波ですよね。島田筑波ともめ
始めたので、『今昔』を攻撃しよ
うじゃないかと、この箇所を私
は理解しています。その鳶魚が、
喧嘩した直後の島田と『今昔』
に一緒に書かないかと呼びかけ
たことはないんじゃないかと思
います。
それと大きな話に戻しますと、
「忍頂寺務型研究」を考えるに
当たり、務さんの場合は俳句と
故郷への愛着がベースになって
いる。しかし、俳書を集められたはずなんだけども集めてない。先ほど合山
先生ともお話したんですが、漢詩集なんてやまほど集められたにもかかわら
ず集めてない。それでいながら漢詩人の祖先のことを想うわけですよね。そ
こが非常にわかりにくい。最初の『延寿清話』も『清元研究』も全部自腹切
っているわけですよね。その物に対する誠意と、後は小野さんあたりにお聞
きしたほうがいいんでしょうけど、あまり言いにくい話になるんでしょうけ
ど、晩年不如意になられた頃でも何で入院費用として本を売らなかったのか。
ずっとそれを持ち続けているピュアさが務の魅力だと思います。
飯倉
これまでの議論で忍頂寺さんと東京との関係が少し論点になっている
と思います。忍頂寺さんが自分の成果の発表の媒体として東京の雑誌をどれ
だけ意識していたのか。それから、人間関係については若干内田さんと福田
さんとでスタンスが違うかなとも思いました。それと、福田さんの言われる
俳句や故郷淡路への愛着というのと、学問形成との関わりを「忍頂寺務型」
というような形で考えていこうというご提案があります。それから武井先生
のご質問からは、舞台芸能に対する忍頂寺さんの関わり方が実際どうであっ
たかということですね。いろいろな論点があるんですけれども、どの方面か
らでも結構なので、今度はフロアの方で何かご質問やご意見があればお願い
したいんですがいかがでしょう。肥田先生、何かございませんでしょうか。
肥田晧三
私ね、一つわからないことがございますねん。絵描いてはる忍頂
寺梅谷のお家と忍頂寺務さんのお家との関係ですな。本家とか分家とか、親
戚でもどういうふうなご関係なるのか。それで、忍頂寺さんが梅谷の別号で
ありました静村を名乗られますね。忍頂寺家一族で活躍をなさった方、世間
に名前を知られている方が、忍頂寺梅谷の静村ということがあって、その名
前を継がれたんでしょうけれども、そこの所がはっきりしないなって思てお
りますのや。それでね、
これあくまで推論なんで
すが、忍頂寺さんが昭和
の初期に、内田さんの手
紙の中にもちょっとでて
おりましたけれども、昭
和二年に大阪の井上熊太
郎から手紙を貰うておら
れる。この手紙の内容に
-
137
ついては私まだ承ってはいてませんけれども、井上熊太郎さんは大阪の船場
の道具屋さんでございますわ。確か井上柳湖堂さんとおっしゃる、大阪の古
い道具屋さん。それで、井上熊太郎さんのお家で難波の瑞龍寺にある忍頂寺
梅谷のお墓をお守りしておられたと、以前福田さんから承ったと思います。
難波の瑞龍寺に忍頂寺梅谷の墓があるということとそのお墓を井上熊太郎さ
んのお家が世話してはるということを忍頂寺さんが何かの時に知りはった。
それで井上熊太郎(柳湖堂)へ忍頂寺さんがお問い合わせなさったんと違う
かなと。どういう関係で梅谷の墓を守ってるんやろうと。それに対する井上
熊太郎の返事やないかなという気がしてますねん。実際当たっているかどう
かは知りませんけれども。これ、年代的に合わんかもしれませんけど、難波
の瑞龍寺に忍頂寺梅谷の墓があるということは、『浪速叢書』の中に入ってい
る『大阪訪碑録』に載ってございますねん。だからね、忍頂寺務さんが『浪
速叢書』の『大阪訪碑録』を見はってですな。それで忍頂寺静村の墓が大阪
にある、わしと同姓の忍頂寺という人がおると。まあ、それまでに梅谷のこ
とは知ってはったかもわかりまへんけど、梅谷の墓が大阪にあるということ
をその『訪碑録』で初めて気が付かれて、そして難波の瑞龍寺にご自身がお
参りなさって、そこでそのお墓は井上柳湖堂が世話しているということを知
りはってですな。それで井上柳湖堂へ問い合わせはったのかなと、一旦はそ
う思ったんだ。福田先生のプリントの二ページに「昭和二年井上熊太郎(梅
谷の世話をした人物)に梅谷について尋ねている」と。ほんならね、『浪速叢
書』は確かに大正の末から刊行が始まったけれども、あれが完結するのは、
昭和五年くらいやと思いますねん。『訪碑録』は、配本の中で随分後の方(昭
和四年)でなかったか。昭和二年の段階では『訪碑録』は出ていなかったん
ではないかと。それもまた、ふっとこないだまた気づきましてん。最初は一
旦、先ほど申したようなことを思ったんですけどもね。そこのところがな、
ちょっとはっきり知りたいなと思って。
それともう一つ余計なことですねんけど、お話承ってて、ちょっと思い出
しました。これも内田さんのご発表で一ページ目の東洋大学へ経歴書をお出
しになっていると。この時吉田幸一先生が東洋大学の教授をしてはります。『三
田村鳶魚全集』の鳶魚日記の戦後の分が載った第廿七巻の月報にね、松本亀
松と吉田幸一先生と朝倉治彦さん司会の対談が載ってますわ(「三田村鳶魚の
輪講会」)。その中で吉田幸一先生が戦後のことですけれども、西鶴輪講のこ
とで三田村鳶魚さんのお家へ行ったら忍頂寺さんがいてはった、確かそんな
発言をしてはったと思いますねん。そんな関係で吉田幸一さんが忍頂寺さん
とお知り合いになられて、この東洋大学の話が始まったんやろうなと思って
お聞きしておりました。
飯倉
ありがとうございました。今の井上熊太郎の書簡について、内田さん
何かないですか。
内田
ご教示ありがとうございました。まず、井上熊太郎の件です。結論か
ら言いますと、『浪速叢書』を見て問い合わせたのではない。恐らく、別のル
ートで何らかの情報を得てそれを確認するために問い合わせたのではないか
と思います。昭和二年五月十日付で井上熊太郎から忍頂寺務宛に来ている手
紙があります。まず、ここに「小生モ拝顔ヲ得ズ候得共、過日志筑ヘ参上
仕リ候節」云々とあります。ちょっとここのところは文脈がはっきりしませ
んが、「拝顔ヲ得ズ」が、もし務のことであれば直接の知り合いでなく、初
めてその手紙で接触を持ったということになります。それから、井上熊太郎
自身が志筑出身ですから、淡路への行き来もあったということがわかります。
さらに、「三井物産東京支店ニ勤務被有セ候御方ト察シ申候」これがどなた
のことを指しているのかはわかりません。その手紙をくれた務さん、あなた
は志筑で会った三井物産の方ですか、と言っているようにも取れますし……。
-
138
はい、何か。
忍頂寺晃嗣
三井物産の今お話しされた方は、多分お爺さんの弟の誠一さ
んのことではないでしょうか。父が違いますけれどもね。(※注・その後の事
実確認により、誠一さんではなく本家の方が三井造船に勤めていたとの事)
内田
ありがとうございます。シンポジウムならではで、疑問が一つ解けま
した(笑)。どういう経緯で誰と志筑で会ったのかはわかりませんが、その後、
梅谷の墓に関する話題のところで、こう言っています。「貴家書面ニ箕面山
中吉郎兵衛氏別荘ニて死去ト御聞之由、此義ハ毛頭無之、墓所ハ難波之鉄
眼寺及ビ当地有名ナル五百羅漢弐ケ所ニ有之候」ですから、どうも、忍頂
寺務さんは元々、箕面で梅谷が死んだというふうな認識を持っていたらしい。
それが、何らかの形で難波の鉄眼寺という情報を得て、そういったことにつ
いて問い合わせをしたということのようです。もしこれが『浪速叢書』を見
た上での問い合わせということであれば、「貴家書面ニ箕面」云々とは書か
なかったと思います。ですから、『浪速叢書』で見たルートとは別で、ご自身
のルーツに関して関心を持って、井上熊太郎という手がかりを得て、自主的
に問い合わせを出したということではないかと思います。あるいは、ここで
井上熊太郎からの書簡で志筑云々ということはありますから、ひょっとする
と志筑淡路ルートで井上熊太郎という人が梅谷について情報を持っているら
しいという、情報を得たという推測も成り立つかもしれません。
肥田
ありがとうございます。余計なことですけども、梅谷が死んだ別荘の
山中吉郎兵衛は大阪を代表する古道具屋ですわ。
飯倉
肥田先生、貴重な情報をいろいろとありがとうございました。それに、
忍頂寺さんに出席していただいた意義が非常にございました。他にご質問や
ご意見ございますでしょうか。はい、尾崎さん。
尾崎千佳
尾崎です。俳句のことに関して、福田さんにいろいろとご指摘い
ただきましてありがとうございました。かつて『語文』の特輯号で務の俳句
への関心はさほど深くなかったというふうなことを、断定して書いてしまっ
ていまして、昨年の研究会でもその筋でお話をした翌日に句がたくさん見つ
かってですね、こんなに恐ろしい思いをしたことは初めてだというぐらいで
した。また、今日の内田さんのご指摘にあった新聞の記事もですね、かなり
全面的に考え直さなければならない課題だなとも思っております。
福田さんのご発表で『ホトトギス』の中に務の句、木筆の句が見えるとい
うことですけれども、これは誤解を招かないように申し上げるんですが、地
方俳句欄の中に載っているということでありまして、落栗のグループの名前
をずっと探してみましたけれども、虚子選とか碧悟桐選とか選句できちんと
入っているのは、やっぱり高田蝶衣一人のようであります。それで、木筆と
か田中晩石とか和田魚里とかいった人達の句が出てくるのは、明治三十三年
くらいからかなり充実する『ホトトギス』の地方俳句欄です。全国で百五十
ぐらいある地方俳句の報告の中に出てくるので、木筆の句が出てくるのを選
んでるのは蝶衣だろうと思います。だから、蝶衣が月次の白雪会でよい句を
選んだ中に見えると思います。いずれにしても活字になったのは、この『ホ
トトギス』が最初だという点では変わりはないだろうと思います。それから、
俳句あるいは『ホトトギス』に接したことが、非常に大きな影響を与えたと
いうのはよく理解しましたが、一方で蔵書形成において俳諧の蒐書に距離を
置いていることをどう考えたらいいのかは、やはり気になるところでして、
大谷繞石とか若月紫蘭とかいったような人達や筑波会では大野洒竹等俳書を
収集する人達が出てきていることと比べると、俳諧史そのものを見渡すよう
なあるいは、貞門だの蕉門といった中核になる句集が、忍頂寺文庫の蔵書に
見えないのはどう考えるべきかということについて、もし福田さんお考えが
あれば教えていただきたいと思ってます。
-
139
飯倉
福田さんいかがでしょうか。
福田
そうね、俳諧に投句してもよかったんですよね。同じペースでね。俳
書を集めることも出来たであろうし、それを全くしない。多分合山先生から
お話しあるんだろうけど、漢籍類も安いので集められたはずなのに、集めて
いないのも非常に不思議だなっていうのがあります。それと、先ほど尾崎さ
んに教えてもらったんですけど、資料十八ページにある務の昭和九年に東京
に行くときの「出代りやお江戸にうとき島男」という句は、大谷繞石が淡路
島を去った時に詠んだ句を踏まえ作られている。そういう話になってくると、
我々が俳諧の注釈をする時に、元のはこれにあったみたいな話なんですよね。
何かますます不思議な感じなんですが、ご意見ありますか。
尾崎
今ご指摘いただいた「出代りやお江戸にうとき島男」という句は、大
谷繞石は非常に短い期間しか淡路にいないんですけども、淡路を出るときに、
入れ替わりになった永田青嵐に対して「出代や三原男は背の高さ」という句
を送ったら、青嵐が「出代つて出代つて寺男かな」と応酬したのを踏まえて
いるんだろうと思います。大谷繞石の影響、故郷への関心が非常に色濃く残
っている。忍頂寺文庫の俳書の中でも、淡路関係の俳書というのが非常に充
実してますので、その点は考えるべきことかとも思います。
飯倉
よろしいでしょうか。はい。じゃあ他に何かございませんか。では、
青田さん。
青田寿美
福田さんの資料で二点ほど。ひとつは、二十四ページの終わりの
方に「小説でも丁寧に補修されているものが多いが、これは務の奥様の仕事
であったと言う」とありますが、これは小野麗子さんから伺ったのですよね。
それでですね、小野文庫の本を見直していると、製本屋さんからご依頼の本
を補修したその領収書が和本に挟まっているケースがあります。年月日・本
の書名と代金とが記載された領収書だったと思います。それと、その話を確
か内田さんとした時に、書簡の中にも本屋とのやり取りがあって、どうも製
本はいくつか決まったところに頼んで、製本させていたということがあり、
それが時期的に最晩年のことかもしれないので、もう少し資料を見ていただ
いた上で考えていただければなと思います。あと、淡路関係のものが小野文
庫には実はたくさん残っているというお話で、小野文庫が小野さんから寄贈
されるまでそういうことに全く気付きませんでしたので、確かにご指摘通り
で興味深いのですが、それが務が集めたものなのか、それとも淡路の方々や
関係者が、務の名前が売れてきて、務と淡路の関係からもう一度淡路を再考
しようと、淡路を見直そうというような気運の流れの中で、務を担ぎ出して
きたところから形成された蔵書であるような感が、なきにしもあらずかなと。
小野文庫の傾向を考えていく中で、寄贈資料は近代関係の雑誌が多いので、
最初阪大に寄贈される時に省いたものがあるのは間違いないことなんですが、
務が集めたものと、務宛てに献本されたものもかなり大量に入っている。淡
路関係のものの中にも非売品が割と多くあって、おそらく淡路・務という流
れでの献本であったと思われるものも少なからずありますので、そのあたり
もこの場でお知らせしておきたいと思います。
飯倉
製本のことで少し思い出したんですけど、中村幸彦先生との書簡のや
り取りの中で天理図書館に入っている製本業者を紹介する内容の手紙があっ
たような記憶がございます。それから、青田さんのご指摘の淡路関係のもの
の蒐書の形成については、蔵書形成という点から重要なご指摘だと思うんで
すけれども、それについて何かございますか。
福田
大正年間くらいに淡路の写本を集めてますよね。これはその後、忍頂
寺さんが家譜を作る時の原資料になっているものをセレクトしているものと、
もう一つは仲野安雄の淡路の本がいくつか入っていて、売立目録もそのまま
小野文庫に入っているんですね。仲野安雄は淡路の勤王派の精神的なリーダ
-
140
ーであって、単に地誌として珍しいのではなくて、お家に関わるものとして
集められていると思います。そしてあと、昭和十五年頃以降の蔵書は、多分
務の名前はすごく売れてたので譲渡を受けたものと、神戸の友人間でお互い
出した本は買おうじゃないかみたいな、そういう流れがあったんだと思いま
す。
飯倉
ありがとうございます。他に。はい、どうぞ。
内田
製本の件について簡単に紹介します。池上幸二郎という人からの書簡
が二通あります。差出人の所に神田小川町「和本仕立所」とあります。そこ
でどういうことが書いてあるかといいますと、現在忍頂寺文庫に入っている
『狂歌柳下草』(
)を仕立所の池上氏から、半紙本に仕立て直すのは惜
C66
しいので補修してはどうだろうかと注文主である忍頂寺務に言ってきており
ます。ここからまずは、家の中だけではなくて専門の職人に傷んだ本の補修
を依頼したことがあるということと、場合によっては元の姿を変えた形で製
本発注することもありえたのではないかということとが読み解けます。この
件は以前福田さんが御論文で、忍頂寺文庫には異板とみなされるものがある
けれども、ひょっとするとその中には務自身の手によって体裁を変えたもの
もあるのではないか、また、小野麗子さんから受け取った資料の中には、和
本の表紙のみを綴じたようなものもあるので元とは違う形に体裁を補修する
件もあったのではないかと指摘されていたことと絡んで、蒐書の在り方、蔵
書の扱い方で一つ認識しておいてもいい事項かと思いました。
飯倉
ありがとうございます。合山先生、先程手が挙がってらっしゃいまし
たが。
合山林太郎
鷲原先生がすでに詳しくご解説されてますけれども、伊藤聴秋
とか明治の漢詩人をはじめとして、関西とか或いは淡路の幕末の漢詩の文化
圏は勤王の動きなんかとも絡んで、漢詩の読み方が非常に難しいわけなんで
す。政治の動きの中で漢詩を作っていますから、必ずしも言葉通りに読めな
いところがあって、それは漢詩集だけ見ていてもわからないところで、書簡
とか詳しい当時の状況と対照させながら考える必要があります。そういう意
味で忍頂寺聴松さんの事蹟なんかは非常に興味深くて、ここから新しい知見
が生まれる可能性があると思います。
また、福田先生がおっしゃっている「忍頂寺務型モデル」。私はこのプロジ
ェクトは昨年から見聞きしておりますから、詳しくはわかっていないんです
けれども、学問の起源というのは、近世と近代とでかなり違っているといつ
も感じながら勉強しています。近世はどちらかというと、伝統的に考証が非
常に強い。私が何回かご発表を伺っている感じだと、「忍頂寺務型モデル」と
いうのは、それともちょっと違うわけですよね。厳密で執着心のある考証と
いうところとも、ちょっと違っているところがあると思います。この研究会
では務と三田村鳶魚なんかとの繋がり等の指摘が続いているわけなんですけ
ど、むしろ考証とは違う近世文学の学問的な起源を「忍頂寺務型モデル」と
いうものに見つけられるんじゃないか。そういう方向で考えても、おもしろ
いんじゃないかなと。まあ、私わかってない面もけっこう多いと思いますか
ら、的外れだったら申し訳ないんですけれども、そういうところで今後も研
究が進むと非常によいのではないかと思います。それから、「忍頂寺務型モデ
ルの提唱」と福田先生が書かれているのは、今の研究に還元していこうとい
うことだと思うんですが、そのあたりでは具体的にどんな感じのことをお考
えになられてたりしますでしょうか。まあ、感想と質問と両方でございます。
飯倉
今の合山さんのご意見とご質問に対してどなたか。現代の学問への還
元ということについては武井先生のご発表と少し関連があると思うんですが。
武井
大変おもしろいご指摘だったと思います。ただ、忍頂寺さんの蒐書と
か学問というのは、江戸型ではないとおっしゃったその理由がちょっと私に
-
141
はわからない。忍頂寺さんが付き合っている人のメンバーを見ますと、鳶魚
ですとか町田嘉章とかそういう人なんですね。いづれもアカデミズムからは
遠い人。その中で例外的なのが高野辰之なんですけどね。ただ、高野辰之は
『日本歌謡史』(春秋社)を書いている関係があるのと、それからもう一つは
高野さんは、東大の美学の人でありまして、国文とは違ってテキストでもっ
て研究するのとはちょっと違う立場をとっていた人です。近世のものを研究
したりする中ではちょっと外れてたんじゃないかと考えてます。それで、高
野さんは別にして鳶魚の学問、町田嘉章さんの学問というのは、物知り学と
いうかそういう感じなんですね。忍頂寺さんの学問もそういう系統に属する
ものだろう。物知り学の大事さというのはもちろん非常にありまして、トリ
ヴィアルな事を突き詰めていく学問上の大切さというのは否定されるべきも
のではない。どちらかといえば、忍頂寺さんはそういう方向の学問だったん
じゃないかと考えてます。
飯倉
ありがとうございます。まだご質問ご意見あるかもしれませんけど、
時間も少なくなってきました。この「忍頂寺文庫・小野文庫の研究」ができ
るのも忍頂寺さんが蔵書を大事にずっと取っておられて、それからまた小野
麗子さんが守ってこられたからであります。さっき福田さんからどういうふ
うにしてそれを守ってこられたのかをお聞きしたいということもございまし
た。そういうことも含めまして、今回のシンポジウムにはるばる仙台からご
参加くださいました忍頂寺晃嗣さんにそのあたりのところ、また、ご感想を
伺えればと思います。宜しくお願いします。
(拍手)
忍頂寺
ただ今ご紹介いただきました忍頂寺晃嗣と申します。私は忍頂寺務
の孫にあたります。母が小野麗子といいます。母は一人娘なんですね。父の
小野は阿部家から小野家に養子に来た阿部家の四男でした。養子さんと一人
娘が結婚しましたの
で、長男の惠嗣が小
野を継いで、次男の
私が忍頂寺を継いだ
というわけでござい
ます。今日一緒に来
ましたのは私の甥
で、兄の長男です。
あともう一人ここに
方子がいますけれど
も、方子は石墨家に嫁ぎました。今日孫の写真が載っていましたけれども、
それは暢子と言います。方子の姉にあたります。私の妹ということになりま
す。私たちは五人兄弟です。もう一人今日は来ていませんが、弟の介嗣が堺
ゆきつぐ
に住んでおります。
正直言いまして、お爺さんは私が小学校三年の時に亡くなりまして、まだ
私は十歳ぐらいで何もお爺さんのことについてはわかりませんでした。大き
くなってから母からお爺さんのいろんな蔵書のことを聞きました。天理大学
にもある程度寄贈されていますし、阪大に忍頂寺文庫があるということ、小
野文庫についても聞いております。その時は、お爺さんが江戸の、母に言わ
せれば「軟派文学」を集めたとのことで、「軟派文学か。何でそんな物をお爺
さんが集めたのかな」と思って、私もまだ学生でしたので意味がよくわかり
ませんでした。ですけども、今日こうしてお爺さんの集められたいろんな蔵
書類あるいはその他のものを先生方に研究していただいてるのを見て、改め
てお爺さんは大した人だったんだな、と思いました。また、お爺さん自身も
いろんな研究をされて、本を出したりしておられたということで、私の知ら
-
142
ないお爺さんの側面をいろいろ知ることができまして、本当にありがたく思
っております。
忍頂寺家はいろんなことがありますけれども、私子供の頃はそういう家
柄にとても嫌な気がしましてですね。それで、忍頂寺をなるべく離れたいな
と思っておりましたし、一人でやっていきたいなというふうなこともありま
して、忍頂寺の家のことについては正直言って、ほとんど聞きませんでした。
そうして育ったもんで、今から思えばもっとちゃんと聞いておけばよかった
なと感じております。先生方がいろいろ研究して下さることを大変ありがた
く思っておりますし、感謝もしております。どうもありがとうございました。
(拍手)
飯倉
どうもありがとうございました。皆さん本日は本当に長時間熱心に聴
講してくださいましてありがとうございました。パネリストの先生方、どう
もありがとうございました。忍頂寺さんのご家族の皆様方、ありがとうござ
いました。また、肥田先生どうもありがとうございました。
私、プロジェク
トの代表者を務め
ておりますけれど
も、いつも司会ば
かりで、忍頂寺文
庫についての研究
を私自身力不足で
あまりさせていた
だいてないんです。
阪大にたまたま赴
任いたしまして、
忍頂寺文庫の存在を知って、何とかしてくれとも言われましたし、何とかし
なければいけないとも思いました。私自身は力を発揮することはできなかっ
たんですが、このように福田さんをはじめとしてOBの方が、大変熱心に支
えて下さいまして、このプロジェクトの前にもう一つ始まっている別のプロ
ジェクトもあって、都合六年ぐらいこれをやってるんですけれども、大分こ
の間いろいろなことがわかってきたり、今日のように忍頂寺さんと実際にお
会いして、お宅にまで伺って調査もさせていただくというところまできまし
た。そして、小野文庫の目録は青田さんのご尽力でもうすでにできておりま
して、展示も今しております。本体の忍頂寺文庫の目録の方も現在進めてお
りまして、今年度中に完成を目標にしております(大阪大学附属図書館編『大
阪大学附属図書館所蔵忍頂寺文庫目録』二〇一一年三月、大阪大学附属図書
館)。今後とも、このプロジェクトからいろいろな研究がまた生まれることを
祈念しております。
本当に今日はありがとうございました。
(拍手)
※この記録は、当日の質疑の録音の音声データを基にしており、内容をほぼ忠実に再
現している。活字への変換は、山本悠子・浜田泰彦が担当した。可能な限り、発言
者に礎稿をお送りし、聞き取れない部分や訂正すべき箇所を直して頂いている。
-
143
﹇会場風景﹈
﹇展示風景﹈
-
144
﹇展示資料(一部)﹈