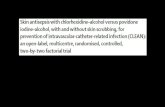年 皮膚科 MCQ 1 アトピー性皮膚炎の症状として誤っている … MCQ対策 2011.pdf2011 年 皮膚科 MCQ 問1 アトピー性皮膚炎の症状として誤っているのはどれか。1
パッシブインジケータを用いたヒト皮膚から放散する微量ガ …...3PS-3101 襲...
Transcript of パッシブインジケータを用いたヒト皮膚から放散する微量ガ …...3PS-3101 襲...

パッシブインジケータを用いたヒト皮膚から放散する微量ガスの測定
株式会社ガステック ○池田 四郎、海福 雄一郎
東海大学理学部化学科 関根 嘉香
東海大学医学部外科学系 梅澤 和夫
1. はじめに
生体ガスは、臨床検査において非侵襲的・非観血的な
サンプルとして用いられる。ヒト皮膚から放散される生
体ガス(皮膚ガス)は、ヒトの身体的・生理的状態を反
映して変化することが分かってきた 1)。パッシブインジ
ケータは、検知剤、除去剤が半密閉筐体に固定された構
造を有する比色型の受動的ガス測定器である。測定対象
ガスが開口部から分子拡散の原理に基づき捕集剤に移動
することで捕集される。捕集剤には、対象ガスとの反応
で呈色する不揮発性の薬剤が含浸されており、比色検知
が可能となる。本研究では、生体内でのタンパク質代謝
の過程で生成し、肝疾患などの疾病との関連が注目され
ているアンモニアに着目し、皮膚から放散されるアンモ
ニアに対するパッシブインジケータでの測定を検討した。
2. パッシブインジケータの構成および皮膚ガス測定
図 1には、アンモニア用パッシブインジケータの概略
を示した。捕集剤は、リン酸・グリセリンメタノール溶液
および pH指示薬を含浸させたシリカゲル担持シートを、
16 mmφに打抜いて作製した。酸性ガスの除去を目的と
した除去剤は、珪藻土を担持したシートに水酸化カリウ
ム・グリセリンメタノールおよび pH指示薬を含浸させ、
20mmφに打抜いて作製した。作製したインジケータを、
開口部が皮膚に接触するように被験者の左前腕部に一定
時間あてて皮膚ガスを捕集した。なお、各測定に際して
は古川ら 2)のアンモニア用パッシブフラックスサンプラ
ーを用いた皮膚ガス捕集も同時に行った。サンプラーの
作製に関しては既報 2)に従い、サンプリング後のアンモ
ニア捕集量の定量にはインドフェノール法および高速液
体クロマトグラフ法を適用した。
図1 アンモニア測定用パッシブインジケータの構造
捕集後インジケータを腕から取り外し、検知部の画像
をデジタルカメラまたはスキャナーで電子化して保存し
た。画像をコンピュータで処理し、発色部のR階調値お
よびG階調値を求めた。
3. 結果
3名の被験者(A:22歳男性, B:21歳男性, C:21歳男性)
を対象に、安静時における皮膚から放散するアンモニア
の測定結果のうち、例として被験者Aの場合を表1に示
す。いずれの被験者についても捕集時間が進むほどに、
検知部の色が測定前の赤から黄に変化することが確認さ
れた。また、累計アンモニア捕集量の増加に伴い黄色の
強さが増加する様子が目視により確認できた。アンモニ
ア捕集量と R 階調値および G 階調値との間には、相関
係数 r=0.76および r=0.84の直線性が認められたため、
パッシブインジケータを用いた皮膚から放散するアンモ
ニア測定が可能であることが示唆された。
表1 被験者Aのアンモニア捕集量と色調値
捕集時間(h)
累計捕集量(μg)
R階調値 G階調値 画像
0 0 200 127
3 63 194 139
5 160 189 144
Wilkinson et al.は運動中の血中アンモニアが安静時
に比べて有意に増加すると報告した 3)。またNose et al.
は、血中アンモニア濃度と皮膚ガスとしてのアンモニア
濃度の間に相関性があることを明らかにした 4)。そこで、
運動を行った際に皮膚から放散されるアンモニアのパッ
シブインジケータでの測定が可能か検討した。3 名の被
験者(D:32歳男性, E:29歳女性, F:21歳女性)のアンモ
ニア放散フラックスは安静時に比べて運動時に増加した。
パッシブインジケータの変色に着目すると、R階調値や
G階調値が運動の有無で変化する場合もあったが、現在
の仕様の下、目視で色を確認できるほどではなかった。
今後、感度の向上により1時間程度の軽い運動で増加す
るレベルのアンモニアの検知ができる可能性がある。
図 2 安静時および運動時のアンモニア放散フラックスおよび
パッシブインジケータの色変化(運動:ウォーキング, 1時間)
本研究は、東海大学湘南校舎「ヒトを対象とした研究」倫理委員会の承認を得て実施した。【引用文献】1)高橋, 関根ほか, 室内環境, 16(1),
15-22(2013) 2)古川, 関根ほか, 平成24年神奈川県ものづくり技術交流会予稿, 1PS-24(2012) 3)Wilkinson et al., Progress in Neurobiology,
91, 200-219(2010) 4)Nose et al., Analytical Sciences, 21(12), 1471-1474(2005)
3PS-3101 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

皮膚色の評価のためのメトリック色相角の有用性
関東学院大学 理工学部 ○秋本 眞喜雄、宮崎 道雄 東京工科大学 応用生物学部 池田 光里、前田 憲寿 株式会社ジェイメック 中野 慎也、ボーマン サムエル、早津 勇一
1. はじめに 皮膚色は美容や皮膚科学における治療効果の評価に極
めて重要な指標である。マンセル値やL*a*b*値が利用さ
れてきたが、目視評価と測定値とは必ずしも一致しない。
我々は、赤を基準として反時計方向に回転した色相角を
用いて皮膚色を評価する方法について検討した。 2. 皮膚の光学特性 皮膚は表皮、真皮および皮下組織の 3層からなる。表
皮の最外層が角質層である。表皮の最も内側にはメラニ
ン色素を作る細胞が存在する。表皮の下に真皮が存在す
る。真皮乳頭層には非常に細いコラーゲン線維やエラス
チン線維などで構成されているが、真皮網状層は太いコ
ラーゲン、エラスチン線維からなっている。真皮内には
血管や分泌腺が存在する。光学的には皮膚に入射した光
は、皮膚に存在するメラニンやヘモグロビンなどの色素
による吸収と真皮からの散乱を経て戻ってきた拡散反射
光が我々の眼に入り認識される。図 1は皮膚の光学特性
を示したものである。
図 1 皮膚の光学特性
3. 皮膚色の表現方法
CIE-L*a*b*均等色空間は、第一軸が明度を、第二軸と
第三軸が赤-緑および黄-青の色合を表わす三次元的な色
の座標系であり、次式で定義されている。
明度指数: 161163/1
0
*YYL (1)
クロマチックネス指数:
3/1
0
3/1
0
* 500YY
XXa (2)
3/1
0
3/1
0
* 200ZZ
YYb (3)
ただし、X0, Y0, Z0は照明光源の三刺激値を、X, Y, Zのそれは測定対象物の三刺激値である。皮膚色を表現す
る場合、色素沈着は明度指数を、紅斑には赤を基準とし
て反時計方向の色相に対して移動した角度、すなわち、
メトリック色相角を利用した。CIE-L*a*b*空間における
色相角は次式となる。
*
*1tan
abhab (4)
画像によるRGB信号の場合には次式となる。
BGRBGhRGB 2
3tan 1 (5)
色相角は色相に近似的に相関する角度として表現するも
のであり、赤色・黄色の度合いを直接的に評価できる。 4. 実験方法 肌色カラーカード15色を色彩色差計で測色し、L*a*b*
空間における色相角を計算した。さらに、画像システム
を用いて被験者の顔画像から色相角を計算し、画像の有
用性について検討した。図2は測定システムを示したも
のである。
図 2 測定システム
5. 実験結果および考察 図3は肌色カラーカードの測定から色相角を計算した
ものである。ピンク系やブロンズ系などの皮膚色の違い
が角度で表現されるため、極めて便利であると言える。
図 3 肌色カラーカードの色相角
6. まとめ 皮膚色を表現するための色相角の有用性について検討
した。色相角は角度分布で皮膚色が評価できるため、美
容効果や治療判定に活用できることが示唆された。
3PS-3102 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

金属選択性を付与したタンパク質性ナノカプセルの開発
神奈川工科大学大学院工学研究科 ○丸山 貴浩、 依田 ひろみ、 小池 あゆみ
神奈川工科大学応用バイオ科学部 柏木 潤紀、 西山 祐里
1. 背景と目的
GroELは、57 kDのサブユニットからなる7量体リング
が2 つ重なった14量体構造をしており、各リングは直径
約5 nmの空洞を有する。7量体のドーム構造をしたコシ
ャペロニンGroESがATPと共にGroELのリングに結合
して複合体を形成すると、GroEL のリング入り口に疎水
的相互作用で結合していた変性タンパク質はリング内部
に落とし込まれ折れ畳まれることがわかっている。
我々は、GroEL/GroES複合体を2つのナノ空間を持
つカプセルとして工学的に利用することを目的とし、金属
ナノ粒子を効率よく空洞内に閉じ込めることに成功してい
る。また、GroELの C末端はリング空洞の底部に配置し、
欠失させることで GroEL の機能を損なわずに空洞体積
を拡げることが可能である。本研究では、(1)GroEL の
Cysを全てAlaに置換した変異体のGly536以降を欠失し、
Gly535を配列内唯一の Cys に置換した変異体(GroEL
noCys535C)、(2)GroELのGly535以降を ZnO認識配
列に置換した変異体(GroEL 535ZnO)、(3)GroES の
空洞内壁にCysを導入した変異体を作製し、金属選択性
の向上を評価した(図1)。
図 1 GroEL/GroES複合体の構造と変異導入部位 a. GroEL/GroES複合体の構造(PDB:1AON/横から見た図)。1サブ
ユニットを青色で示した。 b. GroESの構造(空洞内部から見た図)。
変異導入部位を青と赤で示した。 c. GroELモノマーの拡大図。C末端
部位を赤色で示した。ただし、1AON中GroEL で構造決定されている
のは 524番までである。
2. 実験方法
GroEL お よ び GroES の 各種変異体は 、
QuikChange 法あるいは PCR 法を用いて作製した。
GroEL noCys535C は、発現ベクターを大腸菌 BL21
(DE3) に形質転換し、菌体を超音波破砕後、遠心分離
した上清を疎水クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラ
フィーで精製した。精製タンパク質を用い、0.5M
GroEL noCys535C / 0.5M 野生型 GroES / Au(平
均φ4 nm、2.5 mg/ml)/ 1mM ADPを混合して複合体
を作製した。
GroEL 535ZnO も同様の方法でタンパク質を精製後、
0.5M GroEL 535ZnO / 0.5M 野生型 GroES / ZnO
(0.5mg/ml)/ 1mM ADPを混合して複合体を作製した。
GroES 変異体は、構築した発現ベクターを大腸菌
BL21 (DE3) に形質転換し、菌体を超音波破砕後、遠
心分離した上清を疎水クロマトグラフィー、陽イオン交換
クロマトグラフィーで精製した。野生型 GroEL または
GroESを用いて対照試料を調製した。
試料の透過型電子顕微鏡(TEM)観察は、親水化処
理したTEMグリッド上で 1% リンタングステン酸(pH 4)
で染色し、透過型電子顕微鏡 JEM 2100(日本電子)に
て加速電圧100 kVで観察した。
3. 結果と考察
Au ナノ粒子存在下で形成した野生型 GroEL / 野生
型 GroES 複合体(図 2a)は、空洞内に粒子が内包され
ていない GroEL/GroES 複合体が多く観察されたのに
対し、GroEL noCys535C / 野生型 GroES複合体(図
2b)では複合体空洞内に Au ナノ粒子が黒点のように観
察され、複合体内に効率よく Auナノ粒子を捕捉したと考
えられた。
また、ZnO存在下で形成した野生型GroEL / 野生型
GroES 複合体(図 2c)試料では未内包の複合体が集積
したが、GroEL 535ZnO / 野生型GroES複合体(図2d)
ではZnOナノ粒子を内包したGroELが直径を拡張させ
て集積している様子が観察された。
以上の結果から GroEL noCys535C 、 GroEL
535ZnO変異体はともに、野生型GroELと比較して金属
ナノ粒子の取り込み効率が高いことが予想された。これ
は、Cys または金属認識配列によって金属ナノ粒子を
GroEL に安定に保持できるためであると考えられる。今
後は、試料の混合手順等の条件を検討し、GroEL の粒
子内包率を向上させるとともに、複数種の金属粒子混合
物からの金属選択性を評価する予定である。
図 2 GroEL変異体による金属ナノ粒子の内包 a. 野生型GroEL/野生型GroES/Au複合体、b. GroEL noCys535C/野
生型GroES/Au複合体、 c. 野生型GroEL/野生型GroES/ ZnO複合体、d. GroEL 535ZnO/野生型GroES/ZnO複合体
3PS-3103 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

表 1 メタゲノム解析による菌種名
非加熱処理廃棄物系浸出水 水素 芽胞 菌体名 相同率
Leuconostoc mesenteroides strain TS-YI-268 - 無 NCFB 529 97%
Leuconostoc mesenteroides strain TS-YI-269 - 無 NCFB 543 77%
Leuconostoc fallax KCTC 3537 strain TS-YI-270 - 無 DSM 20189 98%
Leuconostoc gasicomitatum strain TS-YI-271 - 無 TB1-10 97%
Leuconostoc holzapfe lii strain TS-YI-272 - 無 LMG 23990 95%
Leuconostoc carnosum strain TS-YI-273 - 無 NRIC 1722 94%
Leuconostoc inhae strain TS-YI-274 - 無 IH003 95%
Bacillus weihenstephanensis strain TS-YI-275 ○ 有 DSM11821 98%
Bacillus thuringiensis strain TS-YI-276 ○ 有 IAM 12077 98%
Bacillus anthracis strain TS-YI-277 ○ 有 ATCC 14578 95%
Clostridium butyricum strain TS-YI-278 ○ 有 VPI3266 98%
加熱処理廃棄物系浸出水 水素 芽胞 菌体名 相同率
Bacillus weihenstephanensis strain TS-YI-279 ○ 有 DSM11821 97%
Bacillus mycoides strain TS-YI-280 - 有 273 98%
Bacillus anthracis strain TS-YI-281 ○ 有 ATCC 14578 95%
Bacillus thuringiensis strain TS-YI-282 ○ 有 IAM 12077 99%
Bacillus amylo liquefac iens strain TS-YI-283 - 有 NBRC 15535 98%
Clostridium saccharobutylicum strain TS-YI-284 - 有 P262 36%
Clostridium butyricum strain TS-YI-285 ○ 有 VPI3266 97%
Clostridium be ijerinckii strain TS-YI-286 ○ 有 McCoyA 67 98%
Clostridium dio lis strain TS-YI-287 ○ 有 SH1 98%
本研究で見出した菌体名 類似の菌株
廃棄物浸出水中の水素産生菌の探索
神奈川工科大学大学院 ○五十嵐 雄一、斎藤 貴 工学研究科応用化学・バイオサイエンス専攻
【概要】現在、バイオマスエネルギーとして、廃棄物から水素産生菌の水素発酵を利用した水素の製造
法が知られている。本研究は、廃棄物処理場の埋め立て地または、保管地の浸出水の培養を行い、増殖
した微生物群をメタゲノム解析することで、水素産生菌の探索を行った。またメタゲノム解析により水
素産生菌が確認された浸出水について、水素産生菌の単離、定性を行った。 【実験及び結果】神奈川県内の異なる廃棄物処理場の浸出水 A~G の 7 検体を D(+)-グルコース、デン
プン、酵母エキスを含む pH 5.5 の液体培地に加え、嫌気条件下、25 ℃、250 rpm の培養条件で集積培
養を行い、増殖した微生物群のメタゲノム解析を行って水素産生菌の生息の有無の確認を行った。 次に水素産生菌が確認された浸出水を同条件で集積培養し、その後、培養液を平板培地に植菌し単離
を行った。単離した菌株は、平板培地で嫌気条件下、静置培養(25 ℃)を行い、培地上に現れたコロ
ニーを用いて、液体培地で培養した後、培養により菌体から発生した気体成分を TCD-GC で測定した。
水素の発生が確認された菌株を水素産生菌とし、
得られた菌株の 16S rDNA 遺伝子解析を行い同
定した。 神奈川県内 7 か所の廃棄物処理場の浸出水 A(屎尿、農作物収穫残渣)、B(厨芥物)、C(建築材
の焼却灰)、D (汚泥、建築資材の焼却灰)、
E~G(厨芥物の焼却灰)について評価を行った。そ
の結果、非加熱処理系浸出水 A,B からは、
Leuconostoc 属が 7 種、 Bacillus 属が 3 種、 Clostridium 属が 1 種検出し、加熱処理系浸出水
C~G からは Bacillus 属が 5 種、Clostridium 属が 4 種検出された(表 1)。
一方、非加熱、加熱処理系浸出水の水素産
生菌群を比較したところ、加熱処理系浸出水
の方が多種検出された。この要因は、焼却に
よることと、酸素濃度の低下による浸出水の
嫌気性化に起因することが考えられる。 さらに浸出水を培養し、水素産生菌の単離
を行ったところ、浸出水 A から 3 菌体
(Clostridium roseum sp.、Clostridium diolis sp.、Clostridium beijerinckii sp.)、浸
出水 E から 2 菌体(Clostridium beijerinckii sp.、Clostridium diolis sp.)を見出した。今
後、浸出水の分析を進め、それより得られた
菌株の水素産性能の評価を順次行う予定である。
3PS-3104 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

天然植物抽出物を用いたキノコ菌糸体の培養と免疫賦活活性の評価
神奈川工科大学大学院 ○井出 雄大、斎藤 貴
工学研究科 応用化学・バイオサイエンス専攻
【概要】日本の死亡原因の一つに悪性新生物であるがんがあり、種々の治療法が検討されている。近年、新
しいがん治療の一つである免疫治療が注目され、人の免疫機能を活性化するキノコの研究が行われるように
なった。担子菌類の Phellinus linteusが、高い抗腫瘍活性を有することが明らかにされたが、この菌糸体は
子実体を形成するのに時間を要し、臨床への応用には不向きと言われてきた。また、菌糸体にも抗腫瘍活性
があるものの、現在のところ菌糸体を大量培養するための条件は明らかにされていない。
イチョウは生きた化石と呼ばれ、裸子植物門イチョウ網の中で現存する唯一の種であり、その葉は生理活
性が高いため民間薬として利用されてきた。そこで、イチョウ葉抽出物の生理活性能を利用した Phellinus
linteus菌糸体の迅速な培養法の検討を行った。さらに、マウスマクロファージ細胞株を用いて菌糸体抽出物
の免疫賦活活性について評価を行い、他種キノコ抽出物との免疫賦活能を比較し評価した。
【実験及び結果】培養した菌糸体の免疫賦活活性能を評価するため、菌糸体の抽出物を 5.0×105 cell/mLに
調整したマウスマクロファージ細胞株 J774.1に添加し、培養後、免疫賦活活性試験を行った。また、Phellinus
linteusに加えて、他種のキノコについても同様に抽出物に対して免疫賦活活性試験を行い、評価を行った。
高分子多糖をマクロファージに処理した際、細胞が活性化され最終的に腫瘍懐死因子及び NOが産生され
るため、本研究では免疫賦活活性の評価として NO 産生能を指標とすることにした。図 1に示すように、
Phellinus linteus菌糸体は漢方で用いられているカワラタケ、スエヒロタケの菌糸体と比べて多糖が多く含
まれていることが確認できた。多種のキノコと Phellinus linteus菌糸体の免疫賦活能を比較するために今回
は食用キノコの中から抗腫瘍活性が高いと報告されている、エノキ、ナメコ、シイタケを含む子実体 7種に
ついても NO産生能の評価を行った。その結果を図 2に示した。その結果、Phellinus linteus菌糸体の NO
産生能が他の 7種より優れていることから、本菌株では腫瘍懐死因子である TNF-αの産生能を促進するこ
とが推測された。また、図 3に示すように液体培地に NO 産生能があることから、Phellinus linteus菌糸体
は培養中に菌糸体より生理活性成分が溶出し培地中に失われ、これに起因して免疫賦活能が低下しているこ
とが推測されるため、今後、液体培地とキノコ抽出物の成分分析を検討すると共に、食用・薬用キノコの菌
糸体、子実体の免疫賦活能を評価していく必要がある。
図 3 液体培地の NO産生能 図 2 キノコ抽出物の NO産生能
05101520253035
NO産生量
[μmol/L]
0
5
10
15
20
25
30
35
Phellinuslinteus
Liquidmedium
NO産生量
[μmol/L]
図 1 菌糸体に含まれる糖量
(赤:Phellinus linteus、
黄:Trametes versicolor
緑:Sparassis crispa)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0 100 200
吸光度
gulcose [µg / mL]
3PS-3105 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

シャント音持続時間の定量化による血管分岐がある場合における シャント機能評価の試み
桐蔭横浜大学大学院 工学研究科 ○佐々木一真、臼田豪、本橋由香、山内 忍、佐藤敏夫
大分大学 医学部 阿岸鉄三 1. はじめに 維持血液透析患者のバスキュラーアクセス(VA)機能
不全に対する治療方法として近年、インターベンション
治療が発展してきたことに伴い、日々の VA 機能のモニ
タリングが重要になっている。多くのモニタリング方法
の中でもシャント音の聴診は、毎回どこでも手軽で誰に
でも実施できることから、多くの透析施設で日常的に行
われている。しかし、スタッフの経験や個人的な判断に
よって評価基準が異なり、狭窄音を的確に聴取するには
熟練や経験が必要とされている。これまでに非侵襲的で
定量性と客観性を有する新しい VA 機能評価法として、
維持透析患者の皮膚表面に装着した加速度センサで測定
したシャント音信号に対して、ウェーブレット変換によ
る時間-周波数解析を行ってきた。その一方で、流出路静
脈が分岐し、一方に狭窄がある場合では、血液の多くは
狭窄のない方へと流れるため、狭窄近傍でシャント音の
測定・解析を行っても VA 機能良好時と同様に周波数成
分が低周波数成分が主なままとなる。しかしながら、血
管分岐を有する症例では拡張期の血流が途絶え、それに
伴ってシャント音の持続時間が短くなることから断続的
な音に変化し、狭窄病変が進行するほどその傾向が顕著
となる。そこで、分岐型擬似血管狭窄モデルを用いて狭
窄形状の変化に対する持続時間の変化を実験的に再現し、
その有用性について検証した。 2. 基準化持続時間の算出方法 シャント音の測定とウェーブレット変換による時間-
周波数解析は、産学医で共同開発した生体雑音分析装置
“Bio Sound Analyzer(薬事法未承認、以下BSA)”を使
用した。基準化持続時間の算出方法を以下に示す。BSAの電圧フルスケールは 3.5V(±1.75V)であるため、信
号の元データに 1.75V を加えてゼロ点を移動し、0~3.5V の範囲内に信号を移動する。この信号に対し、16区間移動平均による平滑化処理を行った後、上向きピー
ク(元データではプラス側ピーク)を 16 番目ずつサン
プリングしていき、そのサンプリング点の間を3次スプ
ライン関数で補間することで、シャント音信号に対する
近似曲線を作成した。その近似曲線の振幅ピークを
100%として、そこから設定した振幅閾値n%まで減衰す
るのに要する時間 Tn を求め、それをシャント音の持続
時間と定義した。今回の報告では、持続時間の低下を感
度良く検出するため、閾値を10%に設定して持続時間を
求めた。また、ピーク値から設定した閾値までの持続時
間Tは、シャント音信号採取時の被験者の脈拍周期によ
る影響を受けることが考えられる。そこで今回は、シャ
ント音の基準化持続時間(NDTn)を次式で定義した。 基準化持続時間 NDTn = ( Tn / T)
3. 実験方法 内径 6mm のシリコンチューブを用いて血管分岐がな
いストレート型と、分岐のある自己血管内シャントを再
現した擬似血管狭窄モデルを作製した。シリコンチュー
ブ内に長さ 20mm で内径が 1~5mm と段階的に狭窄率
を変化させた左右対称なチューブを留置することで狭窄
を模擬した。そして、生体組織により近い状態で擬似シ
ャント音を測定するために、作製した擬似血管狭窄モデ
ルを専用の治具に固定し、水を充填した。実験では、擬
似血管狭窄モデル内に人工心肺装置(HAS-P100、泉工
医科工業)と拍動流コントローラー(PFC100S、ソーリ
ン社スタッカート)を用いて拍動回数 60 回/min、最高
圧力120mmHg、最低圧力80mmHgに設定した拍動流
を流し、擬似シャント音の測定・解析と狭窄下流におけ
る回路内流量をメスシリンダーを用いて測定した。 4. 結果と考察 ストレート型擬似血管狭窄モデルにおいて狭窄率 0%の場合のシャント音を基準データ、各狭窄率におけるシ
ャント音を比較データとして正規化相互相関係数Rを求
めたところ、狭窄率が50%を超えると急激に回路内流量
が低下し、これに伴い擬似シャント音も大きく変化する
ことからR も大きく低下することがわかった。これは、
臨床実験結果と類似した傾向を示しており、本方法を用
いることで狭窄に伴うシャント血流量の変化をモニタリ
ングできる可能性が示唆された。また、血管分岐下流の
一方に狭窄率 33%の狭窄病変を留置した分岐型擬似血
管狭窄モデルで測定した擬似シャント音の解析結果から、
ストレート型モデルと比較して分岐型モデルの方が持続
時間が短くなることが確認できた。このように血管分岐
症例では、狭窄が進行するほど狭窄部を流れる血流が拡
張期でも途絶えるためにシャント音は断続的な音になり、
その傾向が顕著となる。そのため、周波数成分の変化で
見ると、検出感度が悪くなるような血管分岐がある場合
でも、シャント音の持続時間の短縮化のモニタリングを
併用することで血管が分岐している症例でも VA 機能評
価が可能となる可能性が示唆された。
Fig.1 狭窄率とRの関係
(ストレート型擬似血管狭窄モデル)
3PS-3106 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

嚥下音信号のスプライン補間に基づく嚥下機能評価の定量化と 嚥下反射誘発効果の評価
桐蔭横浜大学大学院 工学研究科 ○佐々木一真、臼田豪、本橋由香、山内 忍、佐藤敏夫
大分大学 医学部 阿岸鉄三 1. はじめに 厚生労働省から発表された平成 23 年人口動態統計月
報年計(概数)の概況における死因順位では、第 3 位が肺
炎であり、そのうち約 9 割が 65 歳以上の高齢者と報告
されている。高齢者では加齢に伴う摂食・嚥下機能の低
下によって、本来食道に入るべき飲食物や唾液が気道に
入ってしまうことで誤嚥を引き起こす可能性があり、肺
炎で入院を余儀なくされた高齢者の約6割が誤嚥性肺炎
ともいわれている。嚥下機能障害を有する患者に対して
は、きざみ食やとろみ調整剤などを添加して食形態を調
整した食事を提供することで誤嚥や窒息などを予防し、
より安全に食事ができるような取り組みが行われている。
その一方で、臨床現場における摂食・嚥下障害の評価方
法の一つである頚部聴診法は、日常的にかつ簡便に実施
できるが、聴診者の経験や勘に頼る主観的な方法であり、
客観的な診断基準が確立されていないといった問題があ
る。そこで、今回の報告では、嚥下音を良好に抽出する
ためのセンサ装着位置と、嚥下音の発生時間の変化から
嚥下機能を評価するための嚥下音信号処理方法について
検討した。 2. 実験方法 嚥下音の測定と時間-周波数解析には、産学医で共同開
発した生体雑音分析装置“Bio Sound Analyzer(薬事法
未承認、以下 BSA)”を使用した。今回の実験では、健
常者の喉頭隆起直上に専用の両面テープを使用して加速
度センサを装着し、被験者に試料として5mlの水を5回
ずつ嚥下してもらい、その際の嚥下音を BSA で測定・
解析した。Fig.1 に嚥下音測定時の頚部への加速度セン
サの装着の様子を示す。そして、得られた嚥下音信号に
対して、以下の方法を用いることで嚥下音発生時間を算
出した。まず、BSAの電圧フルスケールは3.5V(±1.75V)であるため、信号の元データに1.75Vを加えてゼロ点を
移動し、0~3.5V の範囲内に信号を移動させる。この信
号に対し、16区間移動平均による平滑化処理を行った後、
上向きピーク(元データではプラス側ピーク)を 16 番
目ずつサンプリングしていき、そのサンプリング点の間
を3次スプライン関数で補間することで、嚥下音信号に
対する近似曲線を作成した。そして、各音のスプライン
曲線のピーク値から-3dB 減衰した 2 点を結ぶ線分の中
点をそれぞれの嚥下音の時間位置と定め、算出したそれ
ぞれの嚥下音の時間位置の変化から、嚥下機能の変化を
定量化することを試みた。 3. 実験結果及び考察
Fig.2(a)に被験者に水を嚥下してもらった時の嚥下音
解析結果、Fig.2(b)にFig.2(a)上段の嚥下音信号に対して
3 次スプライン近似曲線を作成し、各音の発生時間を算
出した結果を示す。その結果、第Ⅰ音から第Ⅲ音の発生
時間を定量的に算出することが可能となった。また、第
Ⅱ音の発生時間の変化から嚥下機能の低下や嚥下障害に
対するリハビリテーション効果を定量的かつ客観的に評
価できる可能性があると考えられた。
Fig.1 センサ装着の様子
(a)嚥下音信号と時間-周波数解析結果
(b) 嚥下音に対する3次スプライン近似曲線 Fig.2 嚥下音解析結果(水嚥下時)
第Ⅰ音
第Ⅱ音
第Ⅲ音
3PS-3107 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

人工血管狭窄部における血管振動発生メカニズムのCFD解析
桐蔭横浜大学大学院 工学研究科 ○島崎直也、山内 忍、本橋由香、佐藤敏夫
エーティーエー 中根紀章
大分大学 医学部 阿岸鉄三
1. はじめに
血液透析療法では、血液中の老廃物や水分を除去
するために十分な血流量を確実に提供するバスキ
ュラーアクセス(VA)の確保は必須であり、血液透析
療法の治療効果を決定する重要な因子の1つである。
VA 機能の定性的評価法として、日常的に聴診による
シャント音の評価を実施しているが、聴診による
VA 機能評価は簡便に実施可能である反面、透析ス
タッフの能力や経験、感覚に左右される主観的なも
のであって定量性と客観性に欠けている。シャント
音は吻合部において大量の動脈血が静脈に流入す
ることで乱流が生じ、血管壁を振動されることで発
生するといわれているが、理論的に検討した例はほ
とんど見当たらない。そこで本研究では、有限要素
法(FEM)を用いて、シャント音の発生メカニズム
に関する理論解析を行うことで、シャント音の周波
数特性と血管狭窄状態の関係性を理論的に明らか
にすることを検討した
2. 解析方法
FEM 解析モデルとして Fig.1 に示すように吻合
部下流にできた狭窄を模擬するために、狭窄率 80%
の血管狭窄モデルを作成した。解析モデルの寸法は、
血管内径 6.0mm(狭窄部内径 1.2mm)、血管壁厚み
1mm(狭窄部厚み 1mm)、静脈部の長さ 140mm、
人工血管部の長さ 70mm、狭窄長を 20mmとした。
解析結果の有効性を検証するためには、解析モデル
と同じ実験モデルを作製し、解析結果と実験結果を
比較・検証することが必要である。そこで、塩化ビ
ニル製チューブを用いて実験用の擬似血管狭窄モ
デルも作製した。解析における塩化ビニルの材料定
数として、密度 1.0g/cm3、ヤング率 10MPa、ポア
ソン比 0.45 を定義した。モデル内を流れる流体は
水とした。また、モデルの流入口には血液透析患者
の血圧を想定して、最高血圧 120mmHg、最低血圧
80mmHg、デューティサイクル 50%、周期 1 秒(脈
拍 60 回/分に相当)の圧力波形を定義した。
3. 解析結果と PIV による検証結果
Fig.1 に示す解析モデルを使って流れ解析を行い、
得られた結果を Fig.2(a)の流線図及び Fig.2(b)のベ
クトル図にそれぞれ示す。流れ解析結果から狭窄直
後に乱流が発生し、狭窄から離れるにつれて徐々に
層流へと変化していく様子が確認できた。
次に、解析結果の有効性を検証する目的で粒子画
像流速測定法(PIV:Particle Image Velocimetry)
による擬似血管狭窄モデル内の流れの可視化を試
みた。FEM による理論解析で用いた解析モデルと
同様の形状の擬似血管狭窄モデルを作製し、吻合部
近傍の流れの可視化を行った結果を Fig.3 に示す。
解析結果と実験結果を比較すると、両者が良く一致
していることから、解析結果の有効性が確認できた。
Fig.1 吻合部下流の狭窄を模擬した
解析モデル
(a) 流線図
(b) ベクトル図
Fig.2 流れ解析結果
Fig.3 吻合部近傍の流れ可視化結果
3PS-3108 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

ウェーブレット変換による非侵襲かつ簡便な透析用血液回路内凝固の
連続モニタリング方法の検討
桐蔭横浜大学大学院 工学研究科 ○島崎直也、山内 忍、本橋由香、佐藤敏夫
大分大学 医学部 阿岸鉄三
1. はじめに
血液透析療法では、患者の血液を一分間に 200ml
程度の血流量でバスキュラーアクセスから脱血し、
ダイアライザに流入させることで血液を浄化して
いる。血液回路やダイアライザなどの異物と接触す
ることで発生する血液凝固は、ヘパリンを代表とす
る抗凝固薬を用いることで防止しているが、血液凝
固を完全に防止することはできず、少なからず血液
回路やダイアライザ内に血液凝固が発生すること
が報告されている。臨床における血液凝固の判断と
して、圧力値変化や目視、触知といった方法がとら
れているが、圧力値は血液凝固以外の要因でも変動
する可能性があり、また目視や触知といった方法で
は医療スタッフの経験と感覚から定性的な判断と
なってしまう。しかし、現在の血液透析装置には血
液凝固を専属的に監視する機能が備わっていない。
そこで本研究では、血液凝固の進展に伴って変化す
る血液回路内の血流音の経時変化を定量的に監視
することで血液凝固を専属的に検出する方法につ
いて検討した。
2. 実験方法
血液回路内の血流音の測定には血液透析患者の
バスキュラーアクセスのシャント音を測定するた
めに開発した Bio Sound Analyzer(以下 BSA)を
使用した。生理食塩液を用いてプライミングを行っ
た透析用血液回路を用意し、過去に血液凝固好発部
位として報告されているピロー部と静脈側エアト
ラップチャンバの中心部に加速度型心音センサを
装着した。血液透析装置のローラーポンプを用いて
生理食塩液と牛血液の置換を行い、流量 200ml/min
で牛血液を回路内に循環させた。循環中の牛血液に
血液凝固因子の一つである塩化カルシウムを添加
し、2 台の BSA を用いてピロー部、静脈側エアトラ
ップチャンバにおける血流音をそれぞれ連続測定
した。その後、測定した血流音に対してウェーブレ
ット変換による時間-周波数解析を行い、そのウェー
ブレット変換結果から正規化相互相関分析法を用
いて正規化相互相関係数 R を算出し、血流凝固に伴
う血流音変化を定量化することを試みた。
3. 実験結果及び考察
ピロー部におけるウェーブレット変換結果を
Fig.1(a)の上段に、R の経時変化を下段に示す。回
路内圧が上昇する 60秒前にRに大きな変化が現れ、
その部分に相当するウェーブレット変換結果を見
ると、300Hz~500Hz の周波数成分に変化が現れた。
一方、静脈側エアトラップチャンバにおけるウェー
ブレット変換結果を Fig.1(b)の上段に、R の経時変
化を下段に示す。回路内圧が上昇する 60 秒前にピ
ロー部における結果と同様に R に変化が現れ、その
部分に相当するウェーブレット変換結果を見ると、
400Hz~500Hz の周波数成分に変化が現れた。これ
らの結果から、ピロー部及び静脈側エアトラップチ
ャンバにおける血流音を測定し、ウェーブレット変
換結果から正規化相互相関係数 R を算出して、その
Rの経時変化をモニタリングすることで血液回路内
で発生する血液凝固を早期に検出できる可能性が
示唆された。
(a) ピロー部における結果
(b) 静脈側エアトラップチャンバにおける結果
Fig.1 血流音信号に対するウェーブレット変換
結果と R の経時変化
3PS-3109 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

ʤĎĐ[email protected]÷��ķ�<U[;ZÐÀ�yġ
Òe£Û��� īê~�Ăć·� � � � � � ��ï� ¢�ňĭÓ� Ċaň�¶� � �ĔÉ�ݦňąÙ¸ĝ'sö�û����û¸ĝ�üĶ�(*ň(*ŇàĖ�ĎĐhÊ�ökÐÀ�Ľü�â%)
,��+�\ęý�ökÐÀ�ňŇu�ňĻ 'AURF8ÐÀ.P[@���f£ÐÀ�ňökùÑ�DZL8Ĭ
'�ċŅ��.ÐÀ���{£���îÐÀ�c��uŅ�,+�f£ÐÀ�<@I�j�'{£��Æ��)f£
ěĉ'f£ņ����Þ���ûÐÀ!³÷�,ňÅ��÷~�,��+����ňÐÀĘk�ökĎĐ��ĥ�´
�j�čĕ´�¹k�³.ĩĮ���"ĪŃ��*ňĞŁ¿Ĭ���(+j¹�~�Úħ�,��+�\Ãň�î
ùÑ�ökÐÀ�{£´�j�<@I&''Ň�&��ňĸČtõ��.Ä����¹�´.Ě��j_��+��
�� +�ݦ���îùÑökÐÀ�čĕ��ĥ�´ňu~nĴ´����´Ĭ�äÿ�,čĕį�ÐÀ��ĎĐ
£�ý�Ħí�)ģ��û³÷�Í�,��+��îùÑ�hĞý�ökÐÀ������)<U[;Z�Úħ�
,��+�<U[;Z�ök�Ë&Èĵý����+DZL8Ĭ��*ň]Ĺ)�/Ýij�u��d��ʤĎĐý
�i���ª��Ýij.�+���ökĎĐ�¾»�� ��`���+�"�ňQO>Z���(��¹�´.Ì
�+ÎĈ.vÁ��0GY<U[;Z�ök��ĥ�´�Ü%�Ň�ň>[I';Wó�ÐÀ���þėğĢÐÀ'
ĎĐhÊÐÀ���¥§�Ăć�,��+�(*Ì÷�<U[;ZÐÀ.lġ�+^�ª©'{£´��^�²ł�
�*ň\ęý�ķ�x°'×ß�Úħ�,��+�ķ�x°�����å}ķ�'4X8IY@MJZ9ã���Ú
ħ�,��+�ňª©��î<U[;Z(*&|+��'�ŁĆ��\�ÐÀlġ�ŀ��+��ĪŃ��+���
�ÏĂć��<U[;Z�&�ʤĎĐý�Ýij¬µ�āÿ�ňĞŁ�XV[NÝij.»��Ô�(��ʤĎĐ~
Ą¨Ã�.Ĥ��+���ň{£´��$ķ�<U[;ZN1WS�lġ.Ĝ��� �ĔÉ�>V<Z23K[^�Þ���Í�XV[NÝ
ij.N5IVC9UN1[�(��lġ���
SILPOT/catalyst, (SILPOT 184 W/C, Dow Corning Toray, Ĺĺá10:1) �ëç.30 min¼º�����®ňXV[NÝij.�q��>V<Z�Ô^�@Q
[=[.g��6U@AW.Ď#ňæIJ���ëç. 75 °C� 2 hðă~��+����Íý�XV[NÝij.ĞŁ��q��PDMS N1WS.lġ���ĞŁXV[NPDMS N1WS�ňì©�ú�+QO>Z�ë~<U[;Zëç (Collagen BM, ÂøBUEZ) .7T@I�ň37 °C�{é��H?:[D[r�ň6Çľè�bñ.Ĝ���è�bñ®ňs �Ô^�<U[
;Zëç.7T@I�ň½l.đ*ı����Ć¡.Ĝ
����
�ďÖ�XV[NÝij.�q��PDMS N1WS^�1.25 mg/mL�<U[;Zëç.7T@I��lġ��N1WS.opń±ļ���ľzń±ļ��Ĩm���
�-ň�Íý�Ýijúô�Ħ�� ��"�ňðàØ
uÕĠĒ.÷��N1WS�z�ò´.Ĩm����-ň
9X[G1Z9P8IW��ĀÃ��Ň�«´ô�¯)
,���Ô�ĞŁÝij�(��<U[;Z�ʤĎĐ~
Ã��Ŀ��,+ďÖňz�ª©�(*Ň�\Þ�<U
[;Zķ�N1WS�¯),+�ē��+� �
�
Fig 1. Fabrication of PDMS film with a surface releif.
Fig 2. POM and AFM images of collagen film on the surface relief PDMS.
Fig 3. Young’s modulus of the oriented collagen film elongated parallel or perpendicular to the grating vector.
3PS-3110 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

ナノワット級バイオカロリメトリのためのMEMSカロリメータの開発
明治大学大学院 理工学研究科 ○三澤 喬
明治大学大学院 修了 齋藤 允孝
明治大学 理工学部 中別府 修
1. はじめに
バイオカロリメトリは生物の代謝熱を測定し,活動状
態を把握する分析法である.我々はMEMS技術により
高感度・高速な分析が可能となったサーモパイルセンサ
を用いて,ナノワットレベルの代謝熱を発する単体の微
生物や細胞を計測するためのカロリメータの開発を行っ
ている.
2. バイオカロリメータ
図 1(a)にバイオカロリメータの概略図を示す.バイオ
カロリメータは示差計測用の2枚のサーモパイルセンサ
と 5重恒温槽,信号増幅回路で構成されている.示差計
測はアルミ製の試料容器を設置したセンサからの出力を
回路上で減算することで試料の微小な反応のみを抽出可
能にしている.
MEMSサーモパイルセンサ(図 1(b))は 22x22 mm2の
カバーガラス(厚さ:150 m)上に Ni-Cr 熱電対を 350
対備えている.さらにカバーガラス中央部に校正用 Cr
ヒータを搭載し,ヒータ投入熱量とサーモパイル出力電
圧の関係(図 2)から,センサ感度はセンサ単体で3.5 V/W,
試料容器ありの場合 2.01 V/Wとなった.また,応答時
定数はヒータのパルス加熱に対する反応から,それぞれ
8.3 secと 131 secとなり,試料容器による熱容量の増加
の影響が表れた.
5 重恒温槽は微小な発熱を計測する際の妨げになる室
温変動を低減するために導入しており,内側から,セン
サを設置したアルミブロック,3 層のアルミボックス,
インキュベータとなっている.それぞれペルチェ素子を
備えており,インキュベータは PID 型,その他は P 型
フィードバック制御により加熱冷却をすることで一定温
度に保っている.
3.酵母代謝熱計測
MEMS カロリメータの性能を評価するためにパン酵
母(Saccharomyces cerevisiae)を用いた代謝熱計測実験
を行った.一般的に酵母1個当たりの代謝熱は20 pWと
されており,増殖過程において誘導期,対数増殖期,定
常期,死滅期があると言われている.試料容器には3 wt%
スクロース溶液にドライイースト1粒を溶かした細胞懸
濁液を 30 l,酵母・カビ用培養液を30 l,気化を防止
するための流動パラフィンを30 l投入し,参照側の容
器には 90 lの流動パラフィンを投入した.実験結果を
図 3に示す.計測の開始時と終了時とでオフセットドリ
フトが生じたため,18時間を境界としてオフセット補正
をそれぞれ分けて行った.また,開始から約 3時間は装
置が整定するまでにかかる時間のため計測は行えないが,
以降の酵母の増殖過程は確認することができた.本実験
での計測された最小代謝熱は増殖曲線から求めると,7
時間付近での 300 nW である.一方,二乗平均平方根
(RMS)を用いた際のノイズレベルは30 nW程度であり,
酵母約 1500 個以上の代謝熱計測が可能であることが示
された.
4.おわりに
2枚のサーモパイルセンサと 5重恒温槽,信号増幅回
路から構成されているMEMS バイオカロリメータを開
発し,性能としてセンサ感度は2.01 V/W,時定数131 sec,
と評価され,酵母代謝熱計測から30nW程度までの計測
限界を有することが判明した.今後はナノワットレベル
までの微小熱量計測を目指し,サーモパイルセンサ,恒
温槽等のシステムの改良を行っていく.
図 1(a)カロリメータ概略図(b)MEMSサーモパイルセンサ
図 2 ヒータ投入熱量とサーモパイルセンサ出力の関係
図 3 酵母代謝熱計測
3PS-3111 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿

走査型電気化学顕微鏡を用いた呼吸量測定による 非侵襲的で客観的な豚受精卵の品質評価の試み
神奈川県畜産技術センター ○坂上 信忠、西田 浩司、秋山 清
山形大学大学院理工学研究科 阿部 宏之 北斗電工株式会社 青柳 重夫、内海 陽介
(株)機能性ペプチド研究所 星 宏良
農研機構動物衛生研究所 鈴木 千恵、吉岡 耕治
1.はじめに 受精卵の品質を的確に評価することは、受精卵移植の受胎率向上に極めて重要である。最近では、家畜の繁殖能力の低下や夏期不妊などの問題が提起されており、客観的で非侵襲的な受精卵の評価方法が望まれる。そこで本試験では、客観的な評価法として注目される走査型電気化学顕微鏡を用いる手法で呼吸量(酸素消費量)を測定した受精卵の培養後の細胞数や透明帯からの脱出および移植後の受胎性を調査した。 2.材料及び方法 春機発動前の豚に過剰排卵処置を施し、人工授精後5日目(D5)または6日目(D6)に外科的に受精卵を採取した。受精卵は、Abeら1)の方法により呼吸量を測定した。すなわち測定液で満たした円錐形ウェルの底部に受精卵を静置し、白金微小電極を近傍に移動し、酸素が還元可能な-0.6 V vs Ag/AgClに電位を保持した後、移動速度30.0 μm/sec、走査距離160 μmに条件を設定し、コンピューター制御によりZ軸方向に走査し呼吸量を測定した。胚の呼吸量は球面拡散理論式2)に基づき、専用解析ソフトで算出した。呼吸量を測定した受精卵は、豚後期胚培養用培地(PBM)で培養し、透明帯からの脱出状況や既法3)により内細胞塊(ICM)と栄養外胚葉(TE)を分染して細胞数を計数した。また、D5受精卵を呼吸量が高い区(≥ 0.59)と低い区(< 0.59)に分け、受胚豚1頭あたり13~21個を非外科的に移植し受胎性を調査した。 3.結果と考察
PBMで 48時間培養した後に透明帯から脱出したD5受精卵の培養前の呼吸量(F=0.60)は、脱出しなかった受精卵(F=0.50)と比較して高い傾向があり(P=0.08)(表1)、24時間培養した後に透明帯から脱出したD6受精卵では、培養前の呼吸量(F=1.05)は、脱出しなかった受精卵の呼吸量(F=0.77)より有意に高かった。 また、D6受精卵の呼吸量とTE細胞数、総細胞数と
の間で高い相関が認められ(P<0.001、TE:r=0.783、総細胞数:r=0.769)、呼吸量の高い受精卵は、細胞数が多いと考えられた(図1)。 さらに、呼吸量の高い受精卵を移植した7頭中 3頭が
受胎し(受胎率42.9%)合計で 20頭(平均 6.7頭)の子豚が得られたのに対し、低い受精卵を移植した4頭は全て不受胎(受胎率0%)であった。 結論として、培養後に透明帯から脱出した受精卵の呼吸量は脱出しなかった受精卵の呼吸量と比べて有意に高く、呼吸量の高い受精卵を移植して高い受胎率が得られたことから、呼吸量の測定は非侵襲的で客観的な評価法であり、その後の発育能や受胎率に密接に関係していることが示唆された。
本試験は生研センターイノベーション創出基礎的研究推進事業の助成を受けた。 【参考文献】 1)Abe H., et al.(2004) J Mamm Ova Res. 21, 22-30 2)Shiku H., et al.(2001) Anal.Chem. 73, 3751-8 3)Sakagami N., et al.(2010) J Reprod Dev. 58: 140-6. 表1 人工授精後5日目および6日目に採取した豚受精
卵の透明帯脱出別呼吸量 人工授精後日数
透明帯からの脱出
供試 卵数
呼吸量 (F = 1014/mol s-1)
5
非脱出 脱 出 合 計
17 16 33
0.50±0.04a 0.60±0.04b 0.55±0.03
6
非脱出 脱 出 合 計
16 22 38
0.77±0.05A 1.05±0.09B 0.93±0.06
a,b:P=0.08, A,B:P<0.05
図1 D6胚盤胞の呼吸量と細胞数との関係 ◆は内細胞塊(ICM)、□は栄養膜細胞(TE)、▲は総細胞数(Total)
3PS-3112 平成26年 神奈川県ものづくり技術交流会 予稿