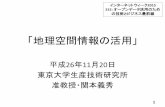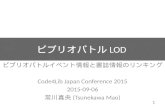8 31情報コミュニケ ションシンポジウム情報・コミュニケ ー ...8・31情報コミュニケ ションシンポジウム情報・コミュニケ ー ションシンポジウム
ワークショップ普及に向けた CANVASの実践 · 888 情報処理 Vol.58 No.10 Oct. 2017...
Transcript of ワークショップ普及に向けた CANVASの実践 · 888 情報処理 Vol.58 No.10 Oct. 2017...

888 情報処理 Vol.58 No.10 Oct. 2017
情報教育とワークショップ特集 情報教育とワークショップ
協働で創造する学びの場
国際化・情報化した社会を生き抜く子どもたちに必
要とされる力の議論が各国で行われている.これま
での近代の教育では,より多くの知識を記憶・暗記
することに評価の力点が置かれていた.しかし,大量
の情報があふれる社会では,多くの知識を得たとして
も,知識の陳腐化には対応できない.
これからを生きる子どもたちに必要な力は,「新し
いテクノロジー “も”活用し,世界中の多様な価値観
の人が協働し,新たな価値をつくりだす力」であると
考える.
そこで,筆者らは,2002年にNPO法人CANVASを
設立し,協働で創造する学びの場を,産官学を含む多
様な主体の連携で創出することに取り組んできた.
「創造的に学ぶ」,「協働で学ぶ」,「産官学を含む多
様な主体の連携で学びの場を作る」ことの意義に関
しては,さまざまな教育学者らによって語られてきた
ものの,その実践における広まりは足踏み状態が続
いていた.しかし,情報化社会を迎え,技術的な進
展により,理想として語られていたがコスト的に実現
に困難のあった学びが実現可能となり,また,技術
革新により大きく変容を遂げた社会が求める学びの
変化がそれらの学力観・学習観と一致し,改めてその
価値が見直されている.
CANVASは「協働で創造する学び」の手法として
「ワークショップ」に注目をし,その開発・普及に取
り組んできた(図 -1).設立当初に実施した国内・海
外の実態調査を踏まえ,協働で創造する学びの場を
産官学連携で創出するための方策を「開発」と「普及」
に分けて立て,15年かけて実践をしてきた.
ワークショップの意義とその開発
日本で初めて論述されたのは,1994年 10月号の
雑誌「社会教育」であるとされ,1990年代半ば以降,
ワークショップはさまざまな分野で広がりを見せてき
た.国際化・情報化に伴い,社会が抱える課題が複
雑化・多様化する中で,多様な分野の専門家が集うこ
とで解決方法を見出す手法として注目されてきた.教
育分野においても同様であり,多様な場で,多彩な
仲間との協働によって,能動的に学ぶという手法であ
ると言える.
設立時の調査において,課題の1つとしてワーク
ショップ不足を挙げ,多様なワークショップの創出を目
指し,開発にあたって10の指針を整理した.またディ
ジタル技術と創造・協働の関係,社会と創造・協働の
関係をもとにワークショップを分類し,開発を行った.
具体的には,「かんじる→かんがえる→つくる→つた
える(→かんじる)」の学びのスパイラルが起こること
を基本とし,「学び方を学ぶ」,「楽しく学ぶ」,「本物と
触れる」,「協働する」,「教え合い学び合う」,「創造する」,
「発表する」,「プロセスをたのしむ」,「答えはない」,「社
会とつながる」の10点を開発指針として掲げた.
実践を開始した当時,学校が求める学習観の相違
と諸外国と比較した課外活動の不足から,学校外の
教育に焦点を当て,学校の外から,学校も家庭も地
域も連携していく仕組みを作ることを目標とした.
石戸奈々子(NPO法人 CANVAS)
ワークショップ普及に向けたCANVAS の実践
2
図 -1 CANVAS のワークショップの様子
基専
応般

889情報処理 Vol.58 No.10 Oct. 2017
2.ワークショップ普及に向けた CANVAS の実践
開発・実践してきたワークショップの代表例
本設では,CANVAS設立から,筆者らが協力者とと
もに開発・実践してきた代表事例を示す.
(1)創造手法としてのディジタル技術の活用
ディジタル技術は創造・表現の敷居を下げ,その手
法を多様化する.まずはその特徴に着目をしたワーク
ショップの開発に集中した.
アニメ制作 (図 -2)
粘土を使ったアニメーションをつくる.ストーリーをつくる.キャラクタを描く.絵コンテを描く.粘土でキャラクタや背景をつくる.コマ撮りする.パソコンで編集し,音声を入れる.すべての行程を子どもたちが行う.アナログとディジタル,アートとテクノロジー,バーチャルとリアルのバランスをとったプログラムとして人気がある.
DJ
子どもたちが 2 枚の CD を用いて音を編集し,音楽表現を行う.ネットワーク時代は,さまざまな情報をいかに選択し,組み合わせ,加工し,新たな表現としていくかの能力が情報を制作する能力と並んで重要になる.編集力を育むワークショップである.
プログラミングでものづくり
プログラミングとは何か? コンピュータとは何か? 子どもたちに,身の回りの製品やサービスのしくみを知ってもらい,自分のオリジナルのゲームや映像をつくるワークショップも展開している.
(2)協働手法としてのディジタル技術の活用
ディジタル技術は協働を圧倒的かつ効率的に,そ
して豊かに変貌させる.2000年代後半からは,協働
の可能性を探るワークショップの開発を行った.
ネットの広場で協働する音楽制作
2005 年には,子どもたちがネット上で協働して作詞・作曲するコミュニティである「おとコトひろば」を構築した.「おと(音)」と「コトバ(言葉)」がネット上で出会う場を提供することで,音楽を軸に,地域,世代を超えたコミュニティをつくりたい,子どもたちに敷居が高いと思われがちな「音楽」に親しんでもらいたい,という思いから構築した.
表現資産を素材にする映像制作
「スーパーマン」,「ポパイ」など教育利用限定でネット上で自由に利活用することを許可された映像コンテンツを活用し,ネット上の映像編集システムでオリジナルの映像作品をつくる.大量の映像の中から素材を探し,編集する.エフェクトや音響をつけて,オリジナルの作品を完成させ,ネットで公開する.
世界とつながるアニメ制作
海外とつながるワークショップ.ユネスコの協力で,パリと日本の小中学生が携帯電話を使って 4 コマ写真マンガをつくる.街や人の写真を携帯で撮って,4 コマのストーリーを協働でつくる.同じモバイルの技術を使うが,表現はそれぞれの場所の文化や歴史,コミュニケーションの在り方で変わる.
(3)社会とのつながりを広げる手法としてのディジタル
技術の活用
子どもたちの活動が社会との接点を見出し,継続した
主体的な学習を促すワークショップ作りにつとめた.
キッズ地域情報発信基地局
自分たちが住む地域の町並みや生活・文化を,多様な表現手法で発信する取り組み.子どもたちは放課後に集まり,地域の情報を新聞,ブロク,ポッドキャスト,映像という 4 つのメディアを通じて発信する.
未来を考える
未来の郵便局を考える,未来の車を考える,未来の学校を考える.子どもたちが有識者と一緒に,時に世界の子どもたちとつながりながら,未来を想像する.社会との関係の中で創造することで子どもたちの学習効果を高め,子どもたちの創造力を社会に還元する.子どもたちが考える未来の社会を映像にし,全国のディジタルサイネージに流す「街中こどもテレビ」も実施.電車,バス,空港,学校,病院,コンビニ,書店など,約 1 万の施設のディジタルサイネージに配信された.
ワークショップの普及活動
最も重視したことはワークショップの普及である.
目指しているのは全国の子どもたちの創造力の底上
げだ.そこで,横断的組織作り,ワークショップの
パッケージ化,ファシリテータ育成,地域での継続
的取り組みを促進する仕組みづくり,情報拠点作り
の5点を普及方策として掲げ,取り組んできた.横
断的組織作りとしては,プラットフォーム団体として
CANVASを設立し,運営を担った.
(1)パッケージ化
海外においてワークショップのパッケージ化に長け
た組織の事例を調査し,プログラムをパッケージ化.
学校,保育園,児童館,文化施設,住居,商業スペー
ス等,320施設に導入されている.プログラムも,造形,
デザイン,映像,音楽,身体,ディジタル,プログラ
ミング,サイエンス,数,ことば,食など幅広い.
(2)ファシリテータの育成
ワークショップの実施にあたってはプログラムとそ
れを支えるファシリテータの態度によって質が変わる.
ワークショップを円滑に運営し,子どもたちの自主性
図 -2 アニメ制作の様子

890 情報処理 Vol.58 No.10 Oct. 2017
情報教育とワークショップ特集 情報教育とワークショップ
や創造力・表現力を引き出していく人材であるファシ
リテータ育成にも取り組んできた.
(3)地域での継続的取り組を促進する仕組みづくり
すべての子どもたちに創造的な学びの場を提供す
るためには,学校教育,地域コミュニティ,家庭など
多様な場での鑑賞,創造,表現の学習活動が大切と
なる.そこで,各地の自立的で継続的な取り組みを
促進する仕組みづくりを行うことで,全国の子どもた
ちの取り組みを活性化し,国全体の底上げを図るこ
とに取り組んだ.
(4)情報拠点づくり
新しい学びの形を伝える見本市としてのワーク
ショップを集めた博覧会イベント「ワークショップコ
レクション」を実施した(図 -3).2004年の初回開
催から11回にわたり実施.今では150のワークショッ
プが一堂に集い,過去最高では 2日で 10万人の子
どもたちが集う普及啓発イベントへと発展した.参
加者総数は 44万人にのぼり,世界最大級の子ども
創作イベントに成長した.最近は世界 45カ国が参
加する「国際デジタルえほんフェア」を併催するなど
国際色も豊かになっている.また,福岡,仙台等地
域での開催に展開しているほか,全国同時開催企画
「キッズデイ」企画へと発展している.
公教育への展開
これらの総合的な普及活動を通じて,15年の間に
述べ 50万人の子どもたちが活動に参加し,ディジタ
ル技術を使った協働・創造の学びの社会的必要性の
認知が広がるとともに需給が高まったことを実感する.
しかし,学校教育との連携や導入に関しては課題
を残した.そこで,2010年以降は「公教育への導入」
を目指し,教育情報化推進とプログラミング教育の
実践への取り組みへとつなげた.
教育情報化推進に関しては,2020年までに 1人
1台情報端末環境を整えることが政府目標として掲
げられた.これはディジタル技術を活用し,子ども
たちが協働で創造的に学ぶ環境が整うことを意味す
ると考える.
2002年から取り組んでいたディジタル技術を活用し
た学校教育で取り組むカリキュラムの1つとしてのプログ
ラミング教育に関しては,2012年より必修化を見据え,
カリキュラム開発,情報の収集と発信,指導者人材育成,
地域での継続的実施体制,プラットフォームの構築を
手掛けたが,この手法は前述のワークショップの普及の
手法と同様である.そしてこのたび,2020年からプログ
ラミング教育を必修化する政府方針が示された.
デジタルキッズの誕生を目指して
これまで 21世紀にふさわしい創造的な学びの場を
つくるという活動に邁進してきた.その活動を通じて
願っているのは,たくさんの「デジタルキッズ」が誕
生することだ.
「デジタルキッズ」は単にテクノロジーを上手に使い
こなす子どものことを指しているのではない.新しい
テクノロジー “も” 駆使し,世界中の多様な価値観・
考え方の人たちと協働するコミュニケーション力と,
新しい価値を想像する心と創造する力を兼ね備えた
子どもたちのこと.
そのために大人ができること.それは場を作るこ
とだ.政府,地方自治体,企業関係者,博物館・
科学館関係者,学校・教育関係者,大学等の研究者,
アーティスト,すべての方々との連携により,子ども
たちがフルスイングできる環境を今後も創り出してい
きたい.(2017年 7月 6日受付)
石戸奈々子 ■ [email protected]
NPO 法人 CANVAS 理事長/慶應義塾大学准教授.東京大学工学部卒業後,マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員を経て,子ども向け創造・表現活動を推進する NPO「CANVAS」を設立.著書に『子どもの創造力スイッチ!』,『デジタル教育宣言』など.
図 -3 ワークショップコレクションの様子