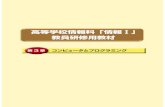コンピュータ産業の変遷 - 明治大学...33 コンピュータ産業の変遷 川 上 桂 コンピュータ産業の歴史は長くはないが、その変遷を振り返ることで
コンピュータ史資料と · 2019-12-05 ·...
Transcript of コンピュータ史資料と · 2019-12-05 ·...

研究展望
コンピュータ史資料と
ヒストリオグラフィーについて( 1 )
後藤 邦 夫叫
1 一般的注意
1-1 まえがき
本稿では, 内容が極めて多岐に渡るコンピュータ史について,これまでの研究の蓄積によっ
て形成されたヒストリオグラフイーの概要を伝え,その流れに沿って現在利用しうる文献と資
料について記述する。ただ,おびただしい文献や資料があるなかで,おおむね筆者が利用しえ
たものに基づく扱いにならざるを得ない。読者の方々のご注意によって欠落が埋められること
を期待する。なお,アメリカの中心的な研究機関や大学図書館等が所蔵する多数の「聴き取り
記録」を含む資料についても,筆者がインターネットでアクセスできたケースに限って紹介す
ることにした。
現代社会におけるコンピュータの地位が, 19世紀の産業社会における熱機関のそれに匹敵す
るという見方は今日では珍しくない。ただ,歴史的経過の著しい短縮を如何に扱うかという問
題がある。
演算部に l万数千本の真空管を使い,演算のクロック速度が100キロヘルツ, RAM はフリ
ップフロップ回路で 1キロピット 重量30トン 消費電力140キロワットの最初の汎用コンピ
ユータ ENIACがただ l台稼働していた50年前の状況は, l %にも満たない効率で10ないし20
馬力の出力を得るための巨大なニューコメン ・エンジンが出現した18世紀後半に相当する。
OSを備えた汎用機のプロトタイプIBM360の発表 (1964)は大型汎用原動機としての熱機関
の登場になぞらえることが出来ょう。わず、か20年あまり前(1977), Apple IIが発売されパーソ
* 2000年 3月20日** 桃山学院大学文学部
71

技術と文明 12巻]号(72)
ナルコンピュータ時代が始まるが,それは19世紀末の小型原動機の量産と普及の開始に相当す
る。すなわち,わずか50年のコンピュータ史には熱機関とその社会的諸関係の発展の250年の
歴史を上回る内容が込められているといわざるをえない。
このように圧縮された歴史では,時間あたりの「出来事」の密度の高さと資料の多さが問題
になる。しかも,重要な資料が現在進行中の事業に関する雑多な情報のなかでランダムに発生
し,あるものは軍事機密や企業秘密の中に埋もれている。そして膨大な情報が「時間によるス
クリーニング」を経ないままに目の前を通過してゆく。その中から何を選択すべきか。これは
「同時代史」に共通する困難な課題である。
ところが,コンピュータ史に関しては以下のような利点がある。
第一に,他の分野に比べ,歴史研究の基盤整備が進んでいることである。すなわち,コンピ
ユータ史上で最も多くの重要な発展があったアメリカにおいて,歴史研究の重要性がよく認識
されており,資料の保存,収集,研究がコンピュータそのものの研究開発と同時並行的に進め
られている。IEEE (アメリカ電気電子技術者協会) は早くからコンピュータ史の専門誌を刊行し,
さらに国際的な連合組織 IFIPは委員会を設置して大学におけるコンピュータ史のプログラム
について調査や勧告を行っている。すでに若干の大学のシラパスも紹介されている。
日本でも 1981年に情報処理学会歴史特別委員会が発足した。しかし,委員会の活動は 2冊の
通史の出版に限られている。また,年鑑,白書等の二次資料は多く出されているが,歴史研究
の蓄積や一次資料の保存と活用において アメリカ的な取り組みがこれから必要となるに違い
ない。
第二に,歴史研究者が歴史の経過をみずから経験することが出来るため,彼らの現場感覚を
歴史研究の重要な手段とすることが出来る。
筆者自身は必ずしもコンピュータとその歴史を専門とするものではないが, ENIACの出現
から約10年後,名古屋大学の助手時代に日本のコンピュータ研究のパイオニアであった故高橋
秀俊教授の集中講義で初めて系統的な知識を得てから 様々な機会にコンピュータとの接点を
もってきた。不便な初期のコンピュータによるシュミレーションの実行,委員会 ・研究会等に
おける政策の討議,本務校の教務事務のシステム化の推進や計算機教育の立ち上げへの参加,
パソコン利用者としての20年に近い経験等々である。これまで筆者があえてコンピュータ史に
関する解説的文章や研究論文を書いたのは これらの体験に基づいて,断片的な資料や知見か
( 1) Histo1 y in the Computing Cui riculum守 IEEEAnnals of History of Computing: Vol. 21, No. 1. 1999, pp. 4 16
International Federation of Information Processing (IF'IP国際情報処理連合)の「教育委員会」と「コンピュータと社会の関係に関する委員会」が共同で組織した作業グループの報告と勧告。専門家教育向けと非専門家向けのカリキュラム案や, 3大学のシラパス例,有用な文献のリストなど,行き届いたものである。このような勧告が出ることは,コンピュータ史がThomasKuhnの意味でのパラダイムになりつつあることを示す。
( 2) 情報処理学会歴史特別委員会 「日本のコンピュータの歴史』1985年,オーム社,および,情報処理学会歴史特別委員会 「日本のコンピュータ発達史』1998年,オーム社。
72

コンピュータ史資料とヒストリオグラフィーについて(l) (後iii§)
ら現実に関するより包括的なイメージを形成する ことができたからである。現在コンピュータ
の分野で働いている多くの人々の中からすぐれた歴史研究者が輩出することが期待される。本
稿がその方々の仕事に多少とも役立てば幸いである。
1-2 コンビュータ史の対象領域と時代区分
まず,コンピュータに関わる歴史研究の対象とすべき課題をとりあえず以下のように整理し,
限られた紙幅のなかで扱うことが出来るテーマを定めておくことにしよう。
( 1 )基礎理論の発展
1 )計算の理論:ブール代数やチュー リング・マシンに始まるアルゴリズムの基礎理論,プ
ログラミング言語理論などの発展史は数学基礎論や言語学とも関連する重要な領域であるが,
本稿では全面的な扱いはせず 限定した話題と若干の古典的参考書を挙げるに止める。
2)情報の符号化 .1948年の Shannonの業績のなかで明示された二つの定理以降,アナロ
グ信号のデジタル化,情報圧縮,暗号の開発などの理論分野が形成され大きな実用的価値を生
んでいる。この分野は本稿ではほとんど取り上げない。
3)回路の理論 :多数の素子で形成され複雑な応答特性を実現する回路に関する手法や理論
はコンピュータの設計技術の基礎として重要であり著しい発展を遂げた。これに関しては問題
の指摘に止める。
4)固体物性理論:磁性体や半導体,最近では誘電体は固体エレクトロニクスの基礎的材料
である。その開発は固体の量子論の研究の進歩に基づいている。その内的発展史には立ち入ら
ない。
5)その他,量子論や統計力学など,物理や数学の基礎的な分野と関わるテーマがある。歴
史的に重要と思われる話題は取り上げる予定である。
( 2)アーキテクチャと演算装置の進歩
従来の歴史研究では,コンピュータ史の基幹的分野であった。すなわち,この流れに即して
歴史を記述し,同時に,関連する他の要因を適切に配してゆく,というのがヒストリオグラフ
ィーの常道であった。既存の研究のレビューに重点をおく以上,本稿もそれに倣うことになる。
( 3)ソフトウェア開発の発展
コンピュータ産業の活動のなかで,ソフトウェアや保守サービスの売上のシェアがハードの
それを上回ってからすでに久しい。ソフトの発展の流れを軸にした通史もある。しかし,多く
はハードとの関連で扱われるのが常である。ここでも特別なケース以外はそのように扱うこと
( 3) 後藤邦夫「ボストン ・コンピュータ博物館」 『週刊朝日百科世界の歴史別冊旅の世界史技術革新の原型を訪ねて』1992年 7月,朝日新聞社。後藤邦夫「コンピューターの多様化とダウンサイジング」 中山, 後藤,吉岡編 『通史 ・日本の科学
技術第 5巻国際期』1999年 3月,学|場書房。( 4) 統計力学の「マクスウエル・デーモン」と Benettの「可逆コンピューテイング」, Feynman-
Landauer Computerと量子力学の基礎など,最近,多くのテーマが出てきた。
73

技術と文明 12巻1号(74)
にする。
( 4)パーツ,周辺機器とその生産システムの開発と生産
アーキテクチャを最低限でも構成する演算装置以外の部分,すなわち入出力装置,主記憶装
置,補助記憶装置などとそれらの部品類,およびその製造装置もコンピュータ産業の重要な分
野である。ただ,電気電子工学や精密機械工学の広汎な分野と関わるため,( 2)を中心とす
る流れの中で一部を扱うに止める。
( 5)コンピュータ関連企業の消長と経営史的課題
初期における軍需産業との関わり,大型汎用機時代の寡占体制,多様化時代におけるベンチ
ャー企業の群生など興味ある話題に事欠かなし、。技術移転の問題としても重要である。
( 6)応用分野の拡張
利用は軍事利用と科学技術計算から始まり,生産システムや事務管理へ導入され,最近では
芸術分野にまで、拡がってきた。利用側からの影響を考慮することが重要である。
( 7)社会的インパクトと批判的論評
初期における管理社会モデル(「オーウェルの1984年」), トフラーの「第三の波」に代表され
るオプティミズムから最近の「デジタル ・キャピタリズム」批判まで,おびただしい論考の流
れがある。主要な文献は記録しておきたい。
(時代区分の試み)
1970年代初頭を境に大きく 二つに分ける。すなわち,
1 )通称メインフレームの大型汎用機の標準型式が確立するまでの「単線的な発展」の時期,
および
2)本格的な固体エレクトロニクス技術や高密度磁気メモリ技術の投入で,コンピュータの
能力が著しく向上し,超並列演算を行うスーパーコンピュータから機器に組み込まれたマイク
ロチップに至る多種多様なコンピュータの「複線的発展」が見られるに至った時期,
とである。また,こ の後半期に入ると ARPAnetが立ち上がり, 86年の NSFnetの発足で本格
的なネットワーク時代に入る。本稿では前半部を本号と次号で扱い,続けて後半部を扱う 。
日本に関しては別項目として末尾にまとめて言及する。日米同時進行の状態になる以前は,
若干のタイムラグがつきまとったからである。とくに上述した転換点が日本では1970年代後半
にずれこんだ。しかし,それ以降にはハードに関しては同時進行になり, 80年代初頭の 「第 5
( 5) アメリカで1350台のコンピュータが稼働していた1957年,日本では 2台の国産機と 1台の輸入機が存在したに過ぎない。 1960年(私が始めて高橋秀俊教授の集中講義を聴講した年),国産機が31台となり輸入機の25台を上回ったが, 6台の大型機はすべて輸入品であった。1964年度末に, 日本のコンピュータの設置台数は1840に達し,はじめて西ドイツとイギリスを抜いて世界二位となったが,一位のアメリカの十分のーに過ぎなかった。この年でも大型機に関しては,国産が3台,輸入機が57台で国産機のシェアは 5%であった。「コンピュータ白書 昭和40年」日本電子計算開発協会1965年11月を参照。この40年版白書は,その後のものと異なり謄写印刷の非売品である。
74

コンピュータ史資料とヒストリオグラフィーについて( 1 ) (後藤)
世代コンピュータ開発計画」でアメリカに衝撃を与え, 85年には半導体出荷額でアメリカを上
回った。(ただし、内容的には家電製品向けが多く、コンピュータ向けが多いアメリカとでは製品の内容
には大きな違いがあった。) しかも, ARPAnetが軍用であったため,その開放以前には日米間で
の研究開発に聞きが生じたのはやむを得ない。軍用ではないが,同様の格差はパソコンの OS
の世界にも存在した。その原因は,敢えて言うと,文化的差異であるかもしれない。
1 3 主要文献と資料・通史・辞典
( 1 )基本的な研究誌とモノグラフ ・シリーズ
コンピュータ史をフォローする上で基本となる文献類をはじめに掲げておこう 。まず注目し
たいのは次の専門誌と 2種類のシリーズである。
[AHC] IEEE Annals of History of Computing; IEEE Comput巴rSociety
[TC] Technology and Culture; Society for the History of Technology
後者は Societyfor History of Technologyの学会誌で日本にも多くの読者がある。コンピュ
ータ史の専門誌ではないが関連する研究が掲載されるので無視することは出来ないという程度
である。しかし,前者は必ずフォローすべきだと思うので若干説明しておきたい。
IEEE (アメリカ電気電子技術者協会)は,本体の方の HistoryCenter (この活動については後述す
る)のほかに、傘下の IEEEComputer Societyの方にも歴史研究のシステムをもっている。そ
こで刊行されているのが上記の[AHC]である。年 4回発行で創刊号は1979年 7月号である。
各号が特集号の形式で編集されているのが特徴である。1989年には10周年記念号が発行され,
それには総括的なレビュー論文,主要な研究センターや博物館の紹介,創刊号以来の総目次が
出ている。それらの内容については必要に応じて紹介するが,博物館等に関する情報はやや古
くなった (1999年の20周年には特別号は出なかった)。
創刊当時の各号を見ると第二次大戦中の開発,たとえばイギリスの BletchleyParkで暗号解
読に使われた COLOSSUSの記事などが目に付く 。実は LosAlamos国立研究所(例の原爆を開
発した研究所)で1976年の 7月10日から15日まで,アメリカだけでなくイギリスやソ連東欧も
含めたコンピュータ開発の関係者が集まってコンピュータ史の会議が開かれ,そこで相当量の
「情報公開」がなされたのであった。すでにマイクロエレクトロニクス時代でパソコンの本格
的登場の前夜である。本格的な歴史研究もこの辺から始ま ったといえる。この会議の Proceed-
111gsは1980年に刊行された。
[MHR80] M. Metropolis, J. Howlett, and Gian-Carlo Rota, A History of Computing in the
Twentieth Century, Acad巴micPress, 1980
ただし,表題から想像されるような通史の本ではなく,戦時中からの各プロジェクトの関係
者の証言集に近い。私は COLOSSUSの話をこれで知った。日本からは末包良太氏が出席して
初期の日本のコンピュータ開発について報告している。
75

技術と文明 12巻 I号(76)
2種類のシリーズとは,いずれもミネアポリスの ミネソタ大学にある CharlesBabbage In-
stituteで編集され MITPressから出版されている。
[SHC] Series for History of Computing, Editor: I. Bernard Cohen, Associate Editor: Wil-
liam Aspray
[RHC] Reprint Series For History of Computing, Editor: M. Cambell-Kelly, Associate Edi-
tor: William Aspray
前者はコンピュータ史のモノグラフ,後者は古典的なものを含む主要著作や論文集のリプリ
ント(英訳も含む)である。いずれも 1984年から出始め,現在までにそれぞれ十数冊出ている。
不定期であるが1年に 1冊の割合である(私の手元にあるのはその中の半数くらいである)。両方の
シリーズの編集を実質的に取り仕切ってきた WilliamAsprayはIEEEの人で[AHC]でも重
要な役割を果し,いくつも著書がある。後述する Smithonianの学芸員の PaulE. Ceruzziとな
らんで,この分野のキィパーソンといってもよいだろう。これらは今後も継続して出版される
であろうから,先行研究として注意を払う必要がある。
( 2)通史について
多数の通史的書物が出版されている中から限られたものを選ぶとすれば,まず年表的な性格
をもち,最も長い期間をカバーしているものとして,
[M99] Christos J. P. Moschovitis, et al, History of the Internet, A Chronology, 1843 to the
Present, ABC-CLIO, Santa Barbara, 1999
を挙げる。1843年は Babbageが Analytical Engineについてイタリアで行った報告が,AdaAu-
gusta, Countess Lovrlaceによ って彼女の詳細な注釈とともに英語に翻訳されて出版された年で
ある。表題に示されているように時代区分と項目の選定がネ ット ワーク関連の技術と社会的事
象が主であるが,本体の発展に関する重要事項も含めである。 2段組10ページに及ぶ巻末の文
献リスト (ネッ ト上の情報のホームページアドレスを含む) は完備している。項目の最後は, 最近
の急成長で話題になっている AOLすなわち American On Lineに関するものである。
最も早い時期に出版され現在でもよ く引用されるのは,
[G72] Herman H. Goldsti日e,The Computer, from Pascal to von Neumann, Princeton Uni-
vers1ty Press, 1972
(邦訳 「計算機の歴史 パスカルからノイマンまで」末包良太ほか訳, 1979年共立出版)
である。「パスカルから」とある通り,今日のデジタル・マシンとは別系統の機械式計算器の
記述が多いのと「ノイマンまで」とあるように, EDVACにおける vonNeumannの業績に多
くの紙数を割いているのが特徴である。著者は陸軍大尉としてアバディーンの試射場と
ENI AC開発の現場ペンシルパニア大学との連絡に当たった数学者で,vonNeumannとENIAC
プロジェクトとを結びつけた人物でもある。いわば,歴史の当事者のひとりによる歴史書とし
ての価値とともに,そのことによる欠点もある。いまでは消滅した初期のハードウェア(水銀
76

コンピュータ史資料とヒストリオグラフイーについて(1 ) (後藤)
遅延線やウィリアムズ管など)の記述に詳しいのはよい。
しかし,プリンストンの EDVACに対する言及と比べ, 同時期の他のプロジェクト(UNIVAC,
Whirlwind, ERA,など)への言及が不足で, ENIAC開発グルーフ。への過小評価も目立つ。von
Neumannへの傾倒は数学者としては自然であるが,それがかえって記述の偏りの原因になっ
ている。
同時期を扱った通史で、記述のバランスがよくとれて信頼できるのが,カナダのカルガリ一大
学のコンピュータ学科教授で[AHC]の編集者を兼ねる人物による,
[W85] Michael R. Williams, A History of Computing, Prentice-Hall, 1985
である。COLOSSUSなどのイギリスでの発展や ENIACをめぐる話題も豊富で,メインフレー
ムのプロトタイプというべき IBM360で終わっている。
第 2次大戦後から現在までカバーする比較的新しいものとしては,[SHC]の一冊として刊
行された次の書物がある。
[C98] Paul E. Ceruzzi, A History of Modern Computing, MIT Press, 1998.
著者はアメリカ史が専門で理工系出身ではないが, Smithsonianの学芸員として働き,この
分野の専門家になった。一冊の中に豊富な内容をバランスよく詰め込んで、ある。註と文献もし
っかり した研究書である。同じ著者がSmithsonianの同僚とともに書いた変形で150ページば
かりの解説書がある。
[K94] Peggy A. Kidwell and Paul E. Ceruzzi, Landmark in Degital Computing, Smithsonian
Institute Press 1994.
小冊ながら,多くの写真や図があり,巻末の年表や文献リストもよい。「物」が中心なので
ネットやソフトに関する話は少ない。他方, 一般向けの本で評価が高いのは,
[S84] Joel Shu rkin, Engines of the Mind: Evolution of the Computer from Mainframe to
Microprocessors, W. W. No1 ton & Co. 1984, 2nd ed. 1996.
(邦訳「コンピュータを富ljった天才たち そろばんから人工知能へ」名谷一郎訳, 1989年,草思社)
訳書は1984年に出た版を底本としており ,96年の第 2版に追加された部分を含んで、いない。
マシンそのものよりもそれらを開発した人間たちに焦点を当てたもので,筆者は研究者ではな
くジャーナリストである。しかし,[Al-IC]の論文もよく読んで、おり記述は公正である。歴史
研究者でないために小さな間違いが限につくのはやむを得ないだろう 。
少し変わっているが,コンピュータ科学の分野で革新的な役割を演じた15人の短い評伝を集
めたものがある。人選が理論派に寄っているのが面白い。
[SL95] Dennis E. Shasha and Cathy A. Lazere, Out of Their Mind, the Lives and Discove1~
1es of 15 Great Computer Scientists, Copernicus, 1995
( 6) たとえば,第 2次大戦直後のイギリスのコンピュータ開発をになった機関のひとつであるNatio日alPhysical Laboratoryの設立を1945年としている。しかし,この研究所が1900年の設立であることは科学史家の常識である。1945年に設立されたのは独立の数学部門であった。
77

技術と文明 12巻l号(78)
日本人による著作を l冊あげるとすれば,[G72]に頼るきらいがあるとはいえ、
[083]小林功武監修・小田徹著『コンピュータ史』 1983年オーム杜
がよい。ソフトウェアの歴史に l章を割いているほか、日本における開発史の記述に特長があ
る。脚註( 2)であげ、られた文献とともに付論で扱う 。
( 3 )歴史辞典等について
このような便利なものも確かに存在する。私が実際に使って見たものを 2点挙げよう 。
[C87] James W. Cortada (ed.), Historical Dictionary of Data Processing 3Vols, Greenwood
Press, 1987
3巻の内訳は、Technologyxi + 415pp, Organization x + 309pp, Biographies xiii + 32lpp
と大部のものである。1987年刊行ということで,今では多少旧くなったことは否めないが,
Appleや Microsoftが登場し, Internetが出現し始めた時代までをカバーしている。編者の
Cortadaにはアメリカにおけるコンピュータ開発史を市場を重視して扱った次の著書がある。
[C93] James W. Cortada, The Computer l口 theUnited States, M. E. Sharpe, 1993
新しいものとしては800ページの大冊、
[L95] ]. A. Lee (ed.), International Biographical Dictionary of Computer Pioneers xiii +
816pp., Fitzroy Deaborn Publishers, 1995
がある。故人から現在活躍中の人々まで300人について,略歴,主要業績とその内容,主要著
作リスト,特許,伝記等の関連文献リストが掲載されている。日本人では山下英男,高橋秀俊
の両氏が出ている(どういうわけか,[C87]には出ている BillGatesの名はない)。 内容の出所は主と
して[AHC]である。IEEEComputers Societyの編集で著作権が明記されている。もうひとつ
の resourceは,巻末の Appendixに記されている CharlesBabbage InstituteのOralHistory
Collectionである。
1-4 研究・資料センタ一等について
学会,大学,博物館等が歴史資料を収集し研究を行っている。1989年刊行の[AHC]の10
周年記念号には[W85]の著者 Williamsによる二十数ページにわたる記述がある。わずか10
( 7) ただ, 私はこれらの便利な事典を使うためには,テキサス大学オースチン校図書館のレファレンス・ルームのお世話にならなければならなかった。
( 8) Michael R. Williams, Museums and A1 chives, IEEE Annals of History of Computing, Vol.10. No. 4.
1989 pp. 305-329.ここで取り上げられている機関等は以下のとおりである。The Computer Museum. Boston: Beyond the Limits: A New Gallery at the National Air and Space
Museum, Smithonian Institution. Washington D. C., The Information Age: Visions and Realities. An E>ト
hibition for the National Museum of American Histo1一y,Smithonian lnstitution, Washington D. C., The
Science Museum. London History of Computing and the ”Info1 mation Age": Deutsche Museum. Munich
Computer Science and Automation Hall: Charles Babbage Institute: Center for the History of lnforma-
tion P1 ocessing; The IEEE Center for the Elect1 ical Engineering; Reco1 ds in the National A1 chives Re-
lating to Early lnvolvement of the U S Government in Data P1 ocessing, 1880s to 1950s .. British
National A1 chives for the Histo1 y of Computing; AFIPS Ilisto1 y of Computing Committee;
78

コンピュータ史資辛トとヒストリオグラフィーについて( 1) (後藤)
年前の記述であるが,ホームページの記載がなく ,またその後の変化も甚だしい。以下,私が
アクセスしている代表的な事例について説明しておこう。ウェブ ・サイトの情報をインターネ
ットで検索し,それぞれの規程にしたがって日本国内で利用できるようになった。
( 1 )「コンピュータ1専物館」
1991年と92年,私が朝日新聞社の原稿のための取材を兼ねて,ボ、ストンの歴史地区の旧い建
物にあった同館を訪問した時には,世界で唯一のコンピュータ専門博物館と言われていたが,
1999年 7月1日にボストン科学博物館に統合され 場所も移転することになった。それととも
に,教育的機能が中心になり,歴史的資料,保存されていた旧い機種などは, 1996年から活動
しているカリフォルニアの ComputerMuseum History Centerに移転した。同センターは,い
わゆるシリコンパレーの一角, NASAのエームズ研究所やスタンフォード大学に隣接したモフ
エツト空港の敷地内にあり,保存活動だけでなく歴史研究の拠点としても整備されつつある。
http://computerhistory.orgでアクセスできる。このホームページは充実している。項目ごと
に独自のヒストリオグラフィーを構成して画像とともにウェブ ・サイトに掲載している。ボス
トンの状況は, http:!/mos. orgで知ることが出来る。
( 2)「スミソニアン博4初館」
正しくは NationalMuseum of American HistoryのDivision of Computers, Informations and
Societyで,収蔵品のほか,文書を含む様々なメディアに記録された資料,ヒヤリング記録な
どがある。アクセスには,ホームページから http://www.si. eclu/resource/tour/comhistでコ
ンピュータ史の索引に入り ,そこから選択する。
( 3)「IEEE歴史センター」
ニュージャージーのラトガース大学との共同で運営されており,同校の文理学部のニューブ
ランシュピク・キャンj{スにある。http://www.ieee. 01 g/organizations/history cent巴rにアク
セスして選択すれば多くの情報が得られる。1994年に行なわれた約20人の日本人に対する聴き
取り調査の記録もある。(協力者として本学会のメンバーの名前も明記されている。) 最近の話題とし
ては, SloanFoundationの支援によって開始されたアメ リカ におけるソフトウェア開発の歴史
のプロジェクトの情報がある。
( 4)「IEEEコンピュータ協会」
上記とは別に, IEEEはその傘下に ComputerSocietyを組織している。この協会は歴史の部
門をもち,さらに,すでにしばしば言及した研究誌[AHC]を刊行している。歴史部門のホ
ームページへのアクセスは,http:!/computer・org/history, [AHC]のホームページは http://
computer. org/annalsである。
( 5)「チャールズ・パベイジ研究所」
コンピュータの先駆者の名を冠したこの研究所は,文書資料やヒヤ リング記録の収集と独自
の研究活動では最も充実していると私は思う。1977年に設立され1980年にミネアポリスのミネ
79

技術と文明 12巻 1号(80)
ソタ大学の WalterLibraryに移転した。1999年秋にはキャンパス内に新しく建設された Elmer
L. And巴rsonLibraryに移転。すでに述べた二つのシ リーズ,[SI-IC]と[SRC]の編集はここ
で行なわれている。研究所へのアクセスは, http://www.cbi. unm. eduで可能である。さらに,
http://www. cbi. unm. edu/indexで資料のリストや研究プロジェク卜について知 り,http://
www. cbi. unm. edu/accessでそれらの利用方法についての知識が得られる。とくに, 300件に
及ぶヒヤ リングのデータは貴重で、ある。http://www.cbi. umn. edu/oral/ohlistでアクセスでき
る (ミネソタ大学の図書館のホームページからも入れる)。
( 6)その他
上記のホームページからリンクをたとeってゆくと多数のセンターやプロジェクトにアクセス
でき る。たおえば,サイパースペース上にコンピュータ博物館を構成するプロジェクトとして
以下のものがある。ミニコンやマイクロコンピュータ分野に特徴がある。
http://www. cyberstreet. com/hes
各大学のアーカイブも重要な情報源である。例えばペンシルバニア大学のhttp://www.
archives. upenn.eduから、同校で行なわれた ENIAC50周年行事の記録が検索できる。
2 コンピュー タ前史 Analytical Engineから ENIACまで
機械的手段で計算を行う着想はふるくからある。しかし,本稿では,論理学や集合論の演算
と同型の代数構造であるブール束をシュミレートした演算部を構成し,それを「プログラム」
として定められた手順で動かして,バイナリーコードで書かれた「データ」に対して論理的操
作のよ る「変形」を行う システム,としてコンピュータを定義する。そのうえで, この期間の
歴史について見ると,若干のオープンな課題が残っているとはいえ,重要な事項に関してほと
んど確定したと言ってよい。
2-1 19世紀の先駆者たち
パイオニアはもちろん CharlesBabbage (1972ー 1871)である。彼は,最初に DifferenceEn・
g1ne (階差機関)を発明し,後に AnalyticalEngine (解析機関)を構想するが,現在のコンピュ
ータの原型はもちろん後者である。当時の工業技術の水準で、は蒸気エンジンで駆動される機械
装置として実現されるほかはなかった。コンセプトと設計図は明確であったが, 中間段階の部
分的システムがつくられただけでシステム全体は完成しなかった。何種類かの伝記,研究書が
出版されているが,基本的には以下の全集に基づくことが必要で、ある。
[B89] Ma巾 nCambell-Kelly (ed.), The Works of Charles Babbage llvols, William Picker
rng, 1989
( 9) ほかに, Babbageの恵子のひとりが計算機関係の論文をまとめて出版したものがある。HenryProvost Babbage (ed.), Babbage ’s Calculating Engines: A Collection of Ppapers. 1889.こi1.のリプリントが[RHC]の一冊として, 1984年に刊行されている。
80

コンピュータ史資料とヒストリオグラフィーについて(1) (後藤)
全集の第 2巻が DifferenceEngine,第 3巻がAnalytical Engineにあてられている。計算機
械に対する彼の関心の始まりについては諸説があるが, 天体力学の計算や航海術に必要な各種
の数表の誤りがひどく ,正確な数値を計算して印刷する機械に対する強い需要があったという
のが有力である。それを裏書するのが,第 2巻に収録された天文学者JohnHershel!による次
の報告書である。
J. F. W. Hershel!, Report of the Royal Society Babbage Engine Committee (1829) , [889]
vol. 2 pp. 108-114
BabbageはDifferenceEngineを完成させなかったが,スエーデン人 PG. Sheutzが実際に製
作し,十分に実用的であることを示した。
第 3巻の中心は, Babbageがイタリーのトリノに招かれて行った講演を後の首相 General
Menabreaが記録し,ジュネーブの雑誌にフランス語で発表した解説である。
L. F. Menabrea, Notion sur la Machine Analytique de M. Char!巴SBabbag巴, Bibliothequeum
veraell巴deGeneve, vol. 41 (1482) (全集では62 82ページ)
しかし,最も影響力を与えたのは, AdaAugusta, Countess Lovelace (1815-1852)によって
英語に翻訳され詳細な解説を付して1843年に Taylor’sScientific Memoirsの第 3巻の Article(10)
XXIXとして発表されたものである。
Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage Esq. by L. F. Menabrea, of
Turin, Officer of the Military Eng111eers
全集第 3巻では82 114ページが訳文, 114 170ページが AdaAugustaによる NoteA - F
である。さらに本文とノートには多数の脚注があり,その末尾にはたしかに AALと記されて
いる。AdaAugustaは詩人 LordByronの娘で,後にラブレース伯爵夫人となった女性である。
ベルヌイ数計算のためのプログラム例を含む彼女のノートと註記の価値は明らかであり,これ
によって後世のわれわれは Babbageが真の意味で今日のコンピュータのパイオニアである こ
とを確認できる。
1864年に刊行された Babbageの自伝的作品(全集第11巻) Passage from the Life of a Philos-
opherには彼女の寄与が明記されており,翻訳や注釈でなく彼女自身の論文として書くように
勧めたが,そのようにならなかったのは,彼女自身がそれを望まなかったからだとしている。
たしかに,当時の社会的状況では説得力があり,ほとんど通説となっている。例えば,イギリ
スにおける初期のコンピュータ史を扱った論文集
[853] B. V. Bowden (ed_), Faster than Thought, London, 1953
は,巻頭に Adaの肖像を掲げ,巻末に彼女の翻訳とノー トの全文を再録している。邦訳のあ
(10) Richard Taylorが編集していた ScientificMemoirsは,外国の学会や学術誌の重要な科学論文を英語に訳して紹介するために発行されていた。問題の論文を紹介するように進めたのは, Babbageと相識であった電気学者の Wheatstoneである。この雑誌のリプリントがJohnsHopkins UPから出ており,私はそれを利用している。当時, TaylorはPhilosophicalMagazineも編集していた。
81

技術と文明 12巻1号(82)
る[S84]もそうである。著名な Byron学者,DorisLangley Mooreが原資料に基づいて書いた
Ada Augustaの伝記 (1977年刊行)でも同じ見解が踏襲された。
ところが,1985年に Mooreが使ったのと 同じOxfordの BodleianLibrary所蔵の原資料を数
学的内容に踏み込んで検討した結果に基づいて書かれた以下の研究書がパペイジ研究所の
[SHC]の一冊として出版され,通説とは異なる見解が提出された。
[S85] Dorothy Stein, Ada: A Life and a Legathy, MIT Press, 1985
この本では AdaAugustaと数学上の師の DeMorganとの文通などの資料によって, 1843年
頃の Adaの数学が初心者レベルであることが確認されている。翻訳はむしろ演習の意味があ
ったとされる。また,ノートや註記についても同様であったと考える。ただし,[S85]の著
者 SteinもAdaの数学者としての潜在的素質を確認しており,強い共感を示している。
Babbageの着想は,精密部品の量産のために次々と資金をつぎ込んだにもかかわらず機械と
しては実現しなかった。その理由については,当時の機械工作技術の水準,彼自身の人格的欠
点による協力者の離反,その他様々なことが述べられている。 それらには証拠があり誤りでは
ないが,私自身の推論は,大型装置をつくる際にはまず小型の装置を試作 して作動を確認し,
問題点を修正しつつスケールア ップを進めるという工学の常道を無視したために,多くの不調
和が発生したというものである。すなわち 彼は一挙に万能的な大型装置の製作を目指し,し
かもより高い性能の完成品を求めて中途で要求を付加しながら製造を進めた節がある。これで
は,開発は袋小路に入ってしまうおそれが生ずるであろう 。総じて癖のある人柄のために,
Babbageに対する好悪の評価はかなり分散する傾向がある。
先駆者の活動としてもう 一つ無視出来ないテーマがある。すなわち,Hollerithによるパン
チカード入力を用いたタピュ レータの開発と実用化である。19世紀末のアメリカで国勢調査の
集計で威力を発揮し,ビジネスの分野に浸透し IBMのルーツ となった。特に1890年の国勢調
査に用いられた型式は有名で通史的な書物には必ず登場する (その現物は千葉県幕張のビジネス
パークの一角にある rBMのオフィスのホールに展示されている)。
(ll) D. L. Moore‘Ada. Cou口lessLovelace: Byro口’sLegitimate Daughter. London. 1977 (12) De Morganは1842 3 if三頃の Adaについて,数学の第一原理を理解し洞察する力に優れてはいるが,計算力ではまだ初心者であったと評価している。BabbageがAdaの名を出そうとした意図については諸説がある。(すくなくとも Ada自身が望んだことではなかった。)数学,音楽,そして父親譲りの文筆の才能に恵まれながら,心身の不調と社会の束縛に苦しみ,生活も荒れ,三児を残して早世した女性に対しては,何人も同情を禁じえないであろう。
(13) Babbageを最も高く評価したのは,おそらく jD. Bernalであろう。彼の著書では,王立学会の頑迷に抗して,近代産業国家にふさわしい技術の開発のために英雄的に闘ったノJ勿として描かれている。J. D. Bernal, Science and Industry in Ninetennth Century, Kegan Paul, 1952. (菅原仰訳「科学と産
業」岩波書店,1953)。計算機械開発に次々と大金を要求しながら結局完成させなかった山師的人物との評もある。
82

コンピュータ史資料とヒストリオグラフィーについて(1) (後藤)
2-2 第2次大戦前の状況
さまざまな機械式計算機がこの時期には試作され一部は実用化されるが,後のデジタル ・コ
ンピュータにつながる重要な話題として, TuringMachin巴と Atanasoff-Berry一Computer(いわ
ゆるABC)を取り上げることにしよう。
( 1) Turing Machineの登場と意義
1936年から 7年にかけて発表された AlanTuringの有名な論文, OnComputable Numbers,
with an Application to the Entscheidungsproblemは, ヒルベルト によって提起された「決定問
題」すなわち,「ある数学的言明が真であることを決定するために用いられる明確に定義され
た方法は存在するか」という問いに対して,「論証を行う仮想的な機械」を導入して応えよう
としたものであった。Turingはもともと確率論を専攻し中心局限定理の証明などに取り組ん
でいたが, 1931年の「ゲーデlレの証明」(算術の公理の無矛盾性と完全性の証明に到る有限アルゴリ
ズムは存在しない)を論じた Newmanの講義に出て,数学基礎論に関心をもち,1936年から 2
年間プリンストンで研究し,上記の論文を完成させた。かつてヒルベルトの指導下で輝いたゲ
ゴチンゲンの数学教室は1933年のヒトラーの登場によ って壊滅し,中心はアメリカに移ってい
た。とくに vonNeumannはプリンストンのスターであった。
後にコンピュータの分野で名を馳せる vonNeumannも当時は TuringMachin巴の意義には気
付かなかったようである。1937年6月1日付の推薦状 (Turingにl年延長のフエローシップのため
にvonNeumannが書いたもの)には,「概周期関数と連続群論の分野で優れていた」と書かれて
いる。
Turingの帰国後間もなく,第 2次大戦が始まった。開戦前から暗号の重要性に注目してい
たイギリスの指導部は開戦とともに数学者を Bletch I巴yParkのGov巴rnmentCode and Cipher
Schoolに動員し,解読不可能といわれたドイツの暗号 Enigmaを解読した。そのさい,暗号解
読専用の電子装置として1943年に開発・配備されたのがCOLOSSUSである。この間に Tunng
が果した役割が大きかったことは,後述する大戦直後に彼が発表したコンピュータ言十画書によ
って推測される。ただ,すべては未だ明らかになってはいない。彼の仮想マシンが数学基礎論
だけでなくコンピュータ科学の基礎であることが認識されたのは後のことである。この点を理
解するには以下の 2冊のテキストが有益であろう。
[H50] D. L. Hartree, Calculating Instruments and Machines, Cambridg巴UP,1950
[M58] M. Davis, Computability and Unsolvability, McGraw Hill, 1958
後者は以下の日本語訳があり,それには訳者の行き届いた解説がある。
M.デーヴイス (渡辺茂,赤撤也訳)『計算の理論』岩波書店1966年
この問題をさらに全面的に扱ったものとして TuringMachineの50年を記念した論文集を挙
』7る。
[H88] R. Berken (eel.) , The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey, Oxfo吋,
83

技術と文明 12巻 1号(84)
1988
1994年には Springerによって再版されている。[M58]の著者 DavisやTuringの伝記の執筆
者 Hodgesのほか,著名!な数学者,コンピュータ科学者が執筆している。とくに,数学基礎論
の歴史の中での意義や関連については,以下の論文が扱う。
Robin Gandy, The Confluence of Ideas in 1936, [I-188] pp. 55-111,
コンピュータ科学との関連では, 下記が簡潔な記述によって見通しのよい理解を与える。
Martin Davis, Mathematical Logic and the Origine of Modern Computers, [H88] pp. 149-
174
1912年に生まれ1954年に不可解な死を遂げた AlanTuringの伝記は 2編ある。
[T59] Sara Turing, Alan M. Turing, I-leffers, 1959.
[H83] Andrew Hodg巴s,Alan Turing: The Enigma of Intelligence’Bui戸
前者は母親の手になる もので, 同性愛者として告発,投獄されて,青酸カリを塗ったリンゴ
を食べて死んだ息子への思いが強く出ているが,資料としての価値は後者が優れている。極め
て周到に書かれ,現在もこれを超えるものはない。ペーパーパックで版を重ね多くの読者をも
っている。この筆者も数学者で同性愛者問題への関心が研究の動機になったという。
第二次大戦直後のイギリスのコンビュータ開発において Turingが果した役割については,
次節において扱う。
( 2) Atanasoff Berry Computer (ABC)をめぐる問題
John Vincent Atanathoff (1903一)はウインスコンシン大学でヘリウムの誘電率の計算で学位
を取った物理学者で,微分方程式の数値解のための膨大な計算で悩ま され, アイオワ大学に移
ってから1936年には電子回路を使った計算装置の構想をもつに到ったという 。1937年には同僚
から工学に詳しい共同研究者と して Berryを紹介され, 1939年から開発を開始し,年末にはプ
ロトタ イプを完成した。この装置に関する論文は1941年 8月14日に受理されており, Ata-
nathoffは自分こそがコンピュータの発明者であると主張する根拠になった。この装置は真空
管を用いた二進法演算回路によ る加減のみが実行でき,線形代数の問題を解 くこ とが目的であ
ったが,実際には働かなかった。ただ,最初の汎用コンピュータ ENIACの開発者のひとりで
あった Mauchlyが41年 l月23日に Atanathoffと会い, 7月には一緒に ABCを見たという記録
がある。後に,この問題は裁判に持ち込まれたとき,これらの点が重視された。もうひとつ,
ENIACに関する知識が早々に公開され周知の事実になったという事実が決め手になった。裁
判では1973年に Atanathoffを発明者とする表決がなされた。すなわち、
Larson, E. R., Finding of Fact, Conclusion of Law and Order for” Judgement.. U.S. District
Court, District of Minesota, Fourth Division Oct. 19, 1973
がそれである。もちろん, ENIACの関係者は承服しなかった。法的決着とは別に論争が続い
たのも当然であろう。[AHC]誌上でも関連する論文が後を絶たない。私自身は, ENIACと比
84

コンピュータ史資料とヒストリオグラフィーについて(1) (後藤)
較して明らかに初歩的で不完全な ABCをもって最初のコンピュータとする意見には賛成しが
たい。
その他,この時期には電動式やリレーを用いた計算機が登場している。例えば, 1936年以来,
ドイツの KonradZuseが開発した Zシリーズもそのひとつであり, 23に至って,プログラム
可能な実用機となり航空機の設計ーに利用された。しかし,今日のコンピュータの原型とはなり
えなかった。
2-3 第二次大戦中から戦後にかけてのコンビュータ開発
第2次大戦中に行われた多数の軍事目的の研究開発のなかで,暗号解読,弾道計算,設計,
シミュレーションなど,大量のデータ処理や数値計算を効率的に遂行する手法や装置の開発が
行われた。イギリスの COLOSSUSにはすでに言及した。ハーバードの MARKIはアメリカ海
軍が使っており,そのなかで開発者の HowardAikenや伝説的名プログラマ GraceMurray
Hopperが活躍した。 しかし,名実ともに汎用コンピュータの原型となったのは,いうまでも
なくペンシルパニア大学のムーア ・スクール(電気工学科の別称)で組み立てられた ENIAC
(Electronic Numerical Integrator and Computer)である。
戦時下に着手された ENIACの開発の成果が本格的に実用段階に達したときには戦争は終了
していた。その後の展開における要因として 2点を指摘しておかなければならない。第一に戦
争終結と動員解除によって技術移転が促進されたこと 第二に冷戦の開始に伴って莫大な開発
費を伴う軍需が発生したことである。この状況は主として次の第3章のテーマであるが,この
段階ですでに片鱗が現われている。
( 1) ENIACの登場と汎用機への展開
ENJAC開発史はエピソードを含め多くが語られており,開発者の JohnPresper Eckertと
John Mauchlyの詳しい証言も残されている。1943年,陸軍のアバディーン射撃場でテストさ
れていた重砲の射撃用数表の作成に必要な大量の計算を効率的に行うために,陸軍はムーア ・
スクールに40万ドル以上を支出して計算機の開発を委託した。その根拠は,その年の 4月, 物
理学者 Mauchlyらが電子回路による問題解決の可能性を示す報告を提出したことである。また,
若い Eckertは天性のエンジ、ニアであり ,困難な課題を解決する能力があった。陸軍側の責任
(14) この内容は, 1971年 6月15日にミネソタの連邦裁判所支部で行われた Atanasoffの陳述による。彼はその後のインタピューでも同趣旨のことを繰返している。裁判の判決以外に明白に Atanasoffを支持したのは次の論文である。
Arthu1 W. Burks & Alice R. Burks, Eniac: The First General Purpose Electronic Computer, [AHC]
vol. 3 No. 4 1981
この見解は, 一般書である[S84]でも明解に否定されているし,私も ENIACの前では ABCは問題にもならないと思う。裁判官はコンビュータを知らなかったから誤った判断を下したのかも知れないが, ENIACの開発にも参加した Burksが何故このような立場をとったのであろうか。彼がEDVACをめぐる対立で vonNeumann側に立ち,プリンストンに行ったという事情を考慮すべきかもま日hない。
85

技術と文明 12巻 1号(86)
者はSimon大佐,連絡将校は数学者の Goldstein大尉であったにの Goldsteinが[G72]の著者
としてこの間の記録を残しているが,vonNeumannに関する記述の内容に問題があることはさきに指摘し
た)。
ENIACは1945年春の試運転で実用的能力を発揮し11月から本格的に稼働した。弾道計算ば
かりでなく,ロス ・アラモスの原爆開発のシミュレーションや純粋数学の計算にも威力を発揮
した。そして, l年後にアバディーンに移設されて1955年10月まで働いた。それ以前,あるい
は同時期の他の計算機に比 して,規模と性能において圧倒的な優位にあり到底比較の対象とな
るものではなかった (毎秒5千四の演算が可能であり,ハーハードの MARKIの能力の千倍であった)。
しかも, 1万8千本の真空管や多数のリレーを含んだ複雑な構造にもかかわらず安定した活動
を行った。それは Eckertの抜群の技術力のたまものである。今日の表現でいう並列演算に似
たアーキテクチャによって信頼性と能力を高めていたのである。そのかわりに,運転には高度
な熟練が必要で、あった。とくにプログラミングは大掛かりな配線の組み替えを含む複雑な作業
であり,ムーア・ス クールの計算室から抜てきされた有能な女性たちによって運転された (彼
女らは ENIACSIXと呼ばれ,後にソフトウェアの世界で活躍する)。
そのような問題点の所在は, ENIACの開発中にすでに意識されていた。 EckertとMauchly
らは,記憶容量を拡大し,データとプログラミ ングを格納する,いわゆる 「プログラム内蔵型
のシングル ・アドレス ・マシン」の着想を得た。彼らはその装置を EDVAC (Electronic Discrete
Variable Automatic Computerの略)と命名 し,陸軍側とその開発契約について話を始めていた。
しかし,開発は君、がれており ,ENIACは当初計画に沿って完成した。
このときの構想、を1944年になつて計画に参加した vonN巴umannが AFit伊 Draft of a Report
on the EDVACとして 1945年の 6月30日に単名で、公表したので、ある。これによって,彼はノイ
マン・アーキテクチャとして知られる現在のコンピュータの基本構造の提案者と しての名声を
得ることになった。 しかし, ENIACの開発中に 「次の計画」としてその構想を自分たちの手
で完成させていたと主張する EckertとMauchlyは,この「抜け駆け」に激怒し,争いは von
eumannの死後まで続くことになった。なお von Neumannのコンピュータに関する仕事に
ついては、[SHC]の一冊として出版された以下の本が有益で、ある (EDVACの構想に沿った機械
がvonNeumannと協力者 Goldstei日らによ ってプリンストン高等研究所で実現されたのは1951年である)。
[A90] William Aspray, John vo刀 Neumannand the Origine of Modern Computing, MIT,
1990
(15) von Neumannの全集には問題の AFirst Draft of a Report on the EDV ACは入っていない。全集の編者の見識と言えるであろう。そのかわりに,全集第 5巻の冒頭に, 1946年に Goldsteinと連名で軍関係者の前で講義され,当時
は公表されていなかった Onthe Principles of Large Scale Computing Machineが掲載されている。A. H. Taub (ed.). John von Neumann Collected Papers volume V, MacMillan. 1963 コンピュータの各部分の働きに対する擬人的表現(「入出力器官」「記憶」等々)をはじめ,現在わ
れわれが慣用 している概念を用いた明快な説明がvonNeuman口の報告には見られる。
86

コンピューヂ史資料とヒストリオグラフ イーについて(])(後藤)
ENI ACが公表されたのは 1946年 2月16日と記録されている。前年に公表された von
Neumannのレポートと異なり,現に動いている装置であるから人々はエキサイトした。しかし,
EDVACに関するパテントを vonNeuma日11の公表によって失い,ムーア・スク ールの首脳部
とも対立した EckertとMauchlyはその直後の 3月ムーア・スクーJレを離れ,ENIAC開発チー
ムの主要メンバーも続いた。
その夏, 7月8日から 8月末まで,ムーア ・スクールは特別に招待されたメンバーを対象と
する講習会を聞き,ENIACとEDVACに関する情報の詳細を伝達した。この講習会がその後
のアメリカのコンピュータ開発に及ぼした影響は非常に大きい。その内容は,[RI-IC]の l巻
として出版されている。
[KW85] Mat tin Cambell-Kelly and Michael R. Williams, The Moore School Lectures
(1946), MIT, 1985
( 2 )イギリスにおける展開
第 2次大戦中のアメリカとイギリスの協力関係は密接であった。核兵器やレー ダーなどあら
ゆる技術情報が交換されていたが, COLOSSUSは例外で同盟国にも情報を知らされぬまま壊
され,写真や図面の一部が公表されたのは1970年代になってからである。しかし,動員を解除
された研究者の頭の中まで管理するのは無理で、あった。ヨーロッパでの戦争が1945年の 6月に
終わると,早速行動を起こしたのは Turingである。その月のうちに彼は NPL(National Physic-
al Laboratory)によばれ,そこで vonNeumannのAFirst Draft of a Report on the EDV ACを見
せられた。その年の始めに設立された数学部門の責任者J.R. Womersはアメリカで ENIAC
とEDVACの情報を仕入れてきたころであった。彼は Turingの昔の仕事を覚えており, NPL
に引き抜こうと考えたのであった。Turingは早速仕事に掛かりその年のうちに構想をまとめた。
報告書はタイプされ1946年 2月19日に NPLの執行委員会に提出され,プロジェクトとして承
認された。それが, Proposalfor Development in Mathematical Division of an Automatic Com・
puting Engine (ACE)である。その全文は, Turi昭が47年に行った講演や,彼の助手として
NPL最初のコンピュータ, PilotACEの開発を行った Wooglerの報告ともに[RHC]の l冊と
して刊行されている。
[CD86] B. E. Carpenter and R. W. Doran, A. M. Turing’s ACE Report of 1946 and Other
Papers, MIT, 1986
Turingの構想は EDVACとはかなり異なり,サブルーチン・ライブラリや人工知能機能を
含んだ野心的なものであ った。その後の成り行きは Hodgesによる伝記[I-183]に詳しい。
Pilot ACEの完成は1950年と遅れたが,当時は最速のコンビュータとして注目された。
そのほかに,電気通信研究所 (Telecommunicatio日 ResearchEs la bl ishment)とマンチェスター大
学,ケンブリッジ大学,ハーウェルの原子力研究所,空軍,ロンドン大学のインペリアル ・カ
レジとパーベック ・カレジなどで並行して開発が進められ,とくにケンブリッジでは Maurice
87

技術と文明 12巻 l号(88)
Wilkesの主導によ って最初のプログラム内蔵型コンピュータである EDSAC(Electronic Delay
Storage Automatic Computer)を1949年に完成させ, EDYACのアイデアをアメリカに先駆けて実
現した。同じ1949年,イギリスでは, NRDC(National Research Development Corporation)が設立
され,その任務のひとつがコンピュータの開発促進であった。 このように,イギリスのコン
ピュータ開発の立ち上がりは早く ,この時期アメリカとほぼ同レベルにあったということがで
きる。それは既出の[B53]を見ても明らかである。その後ほどなく ,両国のコンピュータ産
業には明白な格差が生じた。その原因の探求は興味ある研究テーマである。これは次章に関わ
る問題であるが,とりあえず,[SI-IC]の l巻であり「失敗の歴史」ともいうべき以下の研究
を挙げる。
[H 90] John Hendry, Innovating for Failure: Government Policy and the Early British Com-
puter Industry, MIT. 1990.
(以下次号)
〔校正時補足)
本稿が印刷に入った後,[SI-IC]の l巻として,以下の書物が刊行された。
[RHOO] Paul Rojas and Ulf Hashagen (ed.). The First Computers: History and Architec-
tures MIT 2000
編者はドイツ人で, ドイツにおける初期のコンピュータ開発史のまとま った記述が収められ
ている。執筆者の中には, M剖-tin-Kelly,Aspray, C巴ruzziらの常連の名も見える。もちろん,
本稿に出てくる ABC,ENIAC, EDSAC, MARK-1などに関して,技術の内容にふみこんだ詳し
い記述がある。そのさい,現在の進んだ技術による往時の装置の再現という新らたな研究手法
が用いられている。とくに, ENIACのVLSIチッフ。上における再現や, EDSACのシュミレー
タによる分析などが注目される。
(16) 世界で最初に「商品」として納入されたコンピュータは, Ferranti社がマンチェスター大学に納入した Marklである。1951年2月のことであった。
88