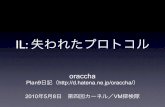チョーサーの時代 The Age of...
Transcript of チョーサーの時代 The Age of...

27比治山大学紀要,第 24号,2017Bul. Hijiyama Univ. No.24, 2017
序
英文学史上大きな地位を占めるチョーサーの生きた時代の文学を概論することは,単に過去を調べその知識を身につけるだけには止まらない。それは,チョーサーの時代の抱えた問題点が,現代に生きる我々にも共通するものとして理解されうるからだ。隣国との領土の問題から始まる戦争,それに続く世界の再構築などは,その時代とその土地にとどまらず不偏の課題として我々の前に突きつけられ得るからである。無論,十四世紀と現代は時間軸については大きく異なる。また,ヨーロッパと極東の地理的な違いも全く無視はできないが,もう一つ大きな目で,つまり人文科学の立場から捉え直せば,言い換えると同じ人間の抱えた問題として取り込むことができれば,それは時空を超えた,同時代の問題となり得るのである。チョーサーの意義は,その言語にある。当時敵対していたフランスの言語に通じ,その文学を翻訳しながら,自国の言語のアングロサクソン語の中にフランス語を取り入れて,中期英語1の洗練に大いに貢献したことである。その後,チョーサーの用いた詩型や言語が現代に見られる現代英語につながってくるのである。まさに,「英詩の父」と評される所以である。
英国文学史 チョーサーの時代
英文学史上重要な地位を占めるとされる,ジェフリー・チョーサー(Geoffrey Chaucer)は,これ
チョーサーの時代
The Age of Chaucer
貝 嶋 崇Takashi KAIJIMA
The age of Chaucer shows us not only cold and correct facts and knowledge, but also living
human wisdom. It is quite useful and beneficial to study the past and investigate the ideas of the
people in the past. In other words, the problems in his era are quite similar to those in the modern
age. The wars in his age between England and France were caused by drawing the clear border
between neighboring countries. In a sense, it is possible to say that we have the same situation as
they had, though they were in a different place and different time.
Among many significant contributions to English literature Chaucer made is there the language
he used and created in a most fine and elegant way. Every poet and writer who uses the English
language after that is quite influenced by his language. It is exactly why he is described as the
“Father of English Poetry" by John Dryden.

貝 嶋 崇28
まで1340年頃に生まれたとされてきたが,無論,今でも1340年と記述されたものは多いのだが,近年の研究書では1343年ということになっている。Hoccleve2からは,「美しい言語の最初の創始者(the
first finder of fair language)」,さらには後年にドライデン(John Dryden)からも,「英詩の父(the
Father of English Poesye)」とその業績が絶賛されたチョーサーだが,チョーサーの生まれた1340年代は,百年戦争が始まった時期である。百年戦争はフランス王国の王位継承をめぐるヴァロワ朝フランス王国と,プランタジネット朝およびランカスター朝イングランド王国との戦いであり,現在のフランスとイギリスの国境線を決定した戦争とも言われる。関係の悪化に伴い,エドワード3世3は1336年にフランスへの羊毛輸出の禁止に踏み切った。このため,材料をイングランドからの輸入に頼るフランドル伯領の毛織物産業は大きな打撃を受け, 1340年にフランドル都市連合はエドワード3世への忠誠を宣誓した。イギリスとフランスの混乱の時期に,チョーサーは生まれた。当時は,度重なるペストの流行で,人口も半減し,ロンドンの人口は4万人に満たないほど激減していた。ゴシック建築の立ち並ぶ狭い通りは,まだ舗装もされていない状態で,下水道も整ってなくて,豚も行き来していたという。街を結ぶ道路も途中には強盗や泥棒が現れて治安はあまり良くなかった。そこで,旅行するものは必ず,武器を持ち集団になって旅をするのが常識だった。旅をするものの中には,商人や騎士,僧侶や修道僧,托鉢修道士,免罪符売りの牧師などがいた。免罪符売りなどは十字架を身につけていたが,ローマの許可を得たわけでもなく,勝手に販売しあまり評判もはかばかしくなかった。彼らの多くは巡礼者というよりは,ならず者に近かった。他にも,大学の学生やミンストレルと言われる吟遊詩人などは,ギターやタンバリンのようなものなどを抱えて旅をしながら歌のレパートリーを増やしていた。そうしたものたちが,夜ともなると旅籠に集まり,エイルというビールを片手に交流していた。エドワード3世の勝利も大衆にとっては,それが増税として跳ね返っており,必ずしも生活は楽ではなかった。その不満は,ワットタイラーの乱となって現れる。ワット・タイラーの乱(Wat Tyler’s Rebellion)は,1381年にイングランドで起きた農民の反乱である。指導者は,神父のジョン・ボールとワット・タイラーとされている。教育は貧困層には普及せず,ほとんどのものは読み書きができなかった。読み書きができるのはもっぱら上流階級のものたちだけで,彼らは英語やフランス語,その上ラテン語やイタリア語などもできた。
チョーサーの同時代人
チョーサーの同時代人としてあげられるのが,ジョン・ガワー(John Gower),ウィリアム・ラングランド(William Langland),ジョン・バーバー(John Barbour)ら3名が特に著名である。無論彼らの作品は,チョーサーのものほどは後世において評価されていないが,チョーサーにない特色を持った作家たちである。まず,ジョン・ガワー(c.1330-1408)は,ケントの富裕な家の生まれと言われて,彼の詩作には
英語(中期英語)・フランス語(古フランス語)・ラテン語が用いられている。チョーサーよりも,10
歳ほど年齢が上であるが,彼自身チョーサーの弟子と呼ばれることを好んだと言われる。チョーサーは彼のことを道徳人ガワーと呼んで,チョーサー自身の作『トロイラスとクリシダ』(Troilus and
Cressida)を献呈している。ガワーの詩はラテン語やフランス語や英語で書かれているが,『恋人の懺悔』(Lover’s Confession)は英語で書かれており,彼は英語で書いたことを弁明している。このストーリーは,フランスやイタリアからの借用で,7つの大罪を犯した恋人の危害について述べたもので,その描写はチョーサーに比べて文体の快活さや迫力が欠けているという評価が一般的である。

チョーサーの時代 29
ウィリアム・ラングランド(1332-1386)は,バーミンガムにほど近いシュロップシャー出身で地位は高くないがロンドンの司祭になった人物だ。代表作は,『農夫ピアズの夢』Piers the Plowman)という寓話で,優しいやり方ではあるが日常の俗物的なものを非難している。圧制者,虚栄,強欲などを痛烈に攻撃する一方で,健康的でシンプルな農夫の生き方を賛美している。ピアズこそが,神から万人に与えられた義務を熟知し真っ当に実践しているというのだ。用いられている文体はチョーサーのものよりさらに田舎風でそのために一層読みづらいものになっているという。民衆の詩として定着していた。また夢を意味するvisionは当時の流行でもあった。しかし,当時からそれに対して,夢の話だと軽蔑し,彼の出自をバカにする批評家も多くいた。ジョン・バーバー (c.1320-1395)はスコットランド,アバディーン出身の詩人で,最初にスコット
ランド語で世に知られる詩を書いたということで有名である。現存している作品は,歴史ロマンスで『ブルース』(The Brus) という名のストーリーで主人公はロバート・ブルースである。彼は後のスコットランドの国王ロバート1世(Robert I, 1274-1329)として知られ,父方の祖先はノルマンディーのブリー (Brix) を出自とするスコット=ノルマン(英語版)の家系であり,母方はフランス・ゲール人の家系であるとされている。ロバート1世はイングランド王国に対する独立戦争においてスコットランドを率いてその地を独立国家として回復したとされる伝説的な国民的な英雄である。今日のスコットランドでは,ロバート1世は国民的英雄として記憶されている。特にバノックバーンの戦い(Battle of Bannockburn)は有名で,その勝利が彼の名声を決定づけた。その戦いは,1314年6月24
日にスコットランド王国とイングランド王国の間で行われた会戦で,イングランド側の大将はエドワード2世でウェールズ,イングランド中部,北部諸州から2万を超える軍を召集していた。その主力となるのは弓兵と重装騎兵であり,この二つはスコットランド軍に対して圧倒的な優位を誇っていた。一方,ロバート1世はその数約半分に満たない1万の軍勢を率い,しかもその大半が歩兵で騎兵は数百人しかいなかったとされる。しかし,ロバート1世はその不利な状況に諦めることなく,戦場をバノックバーンに選び,イングランド軍の重装騎兵に対抗するため,小さな落とし穴を幾つも掘らせたりして,徹底抗戦をした。その結果,スコットランドに侵攻したエドワード2世率いるイングランド軍をスターリング近郊で打ち負かし,大方の予想を裏切り大敗させたのである。チョーサーと同時代人の詩ではなく散文で次の二つも,忘れてはならない。一つはウィクリフ(John
Wyclif, c.1330-1384)による聖書の翻訳であり,もう一つはジョン・マンデヴィル(Sir John
Mandeville,?-1372)による『東方旅行記(マンデヴィル旅行記)』である。ウィクリフは,イングランドのヨークシャーに生まれ,宗教改革の先駆者とされる人物である。
1376年頃ローマ・カトリック教会の批判と改革に着手。真の主権に基づかない教会の形式的な権威を否定し,聖書のみを唯一の実践の基盤とし,旧約聖書を初めて英訳した。また,マンデヴィルは『ジョン・マンデヴィル卿の東方旅行記』(The Voyage and Travels of Sir
John Mandeville, Knight)の作者として知られるセント・オールバン出身の騎士とされているが,それはその著作の前書きに書いてあることで,その実証的な確証はされていない。また,その文体も粗野で洗練されていないものでそのことが一層,作者の出自を疑わせている。批評家の中には,架空のペンネームに過ぎないと考えるものもいる。また,この書は自身の冒険の脚色からできているとされている。その内容は二部に分かれており,まず第1部ではコンスタンティノープルからはじまり,ビザンツ帝国の首都から南下して,キプロス,シリア,エルサレム,シナイ砂漠の修道院を訪れる。それから第2部ではインド,中国からジャワやスマトラに向かう。また作中に登場する首から上が犬になった女,双頭の雁,巨大なかたつむり,体全体を覆う程の巨大な一本足の人間など,ファンタジーに登場するようなものたちが登場し,読むものの関心を強く引く。ただ出典がマルコポーロなどからと思われるもの見られ,作品としての評価は定まっていない。

貝 嶋 崇30
チョーサー
さてこの章のタイトルにもなっている人物ジェフリー・チョーサーに話を戻してみる。チョーサーは,ロンドンのワイン商人の息子として生まれた。裕福で評判のいいワイン商人で,貴族でもないのに,息子のジェフリーに高い教育を受けさせることができるほどだった。ケンブリッジで教育を受けたとも言われている。ラテン語,フランス語,それからイタリア語を学び,さらには浅くだが,当時の科学も学んだとされる。ともかく読書好きだったようだ。1357年に小姓としてライオネル王子の宮廷に出仕するようになった。その2年後,フランスで兵士として従軍し過酷な戦いに身を投じた。しかし,そこで捕虜となったが,エドワード3世が補償金を支払ったために無事にイギリスへと戻ることができた。当時は騎士になるにはまず,小姓とされるpage,その次は従者とされるesquire,それから騎士のknightという3つのランクがあった。1374年にはチョーサーは従者にはなれたものの,とうとう騎士の称号はもらえなかった。しかし,彼は騎士以外の道を求め,違う方面で活躍するようになる。ジョン・オブ・ゴーントの庇護のもと,運にも恵まれ活躍する場を見出していくことになる。ゴーントは,イングランドの王族でイングランド王エドワード3世とフィリッパ・オブ・エノーの第4子で三男であり,ランカスター家の祖で,ランカスター朝創始者ヘンリー4世の父となる人物である。そのおかげで,1372年には,ジェノアの総督と交渉するための代表団の一員となり,ジェノアへと派遣され,両国の通商関係の問題を協議した。その間,彼はフローレンスを訪れ,ダンテやボッカチオなどと出会うという知遇を得たのではないかと想像される。その後の1374年には,その功績が認められたのか,ロンドン港の税関の羊毛や皮革の監査官に任命される。そこで地道に仕事をした結果からか,1378年に今度は,イタリアのミラノへ大使として就任する。それから8年後の1386年に,今度はケント州の議員にもなるが,幸運は長くは続かなかったようだ。不興を買った理由は定かではないが,その後すぐに監査官の職を解かれ,その後寂れた土地で年金生活を送るようになった。しかし,詩人として名を残し,世界にその名を知られるようになった作品『カンタベリー物語』(The
Canterbury Tales)がそこから生まれるのだ。無論,最初に書いた作品が最初に大当たりしたわけではない。チョーサーの詩作の段階は,3つの時期に分けて考えるのが最も妥当だろうと思われる。誰しも,最初からその才能が一挙に花開くのは望ましいことだが,残念ながら,ものを書くというのはそういうことではない。習作時代を経験してから,自分のオリジナルな世界や文体を持つのが一般的だろうし,それには王道はないと考えられる。
第1期
まず第1期は,フランス時代といっていいだろう。それから次の第2期はイタリア時代,そして最後の第3期はこのカンタベリー時代である。チョーサーは裕福なワイン商のもとに生まれたと書いたが,そのおかげで,彼はフランス語などを学ぶ機会を得ていた。イタリアに赴任する前の段階では,そのフランスの文学の影響が大きいと思われる。それから,イタリアに滞在することで,それまでのフランスとは異なる当時のイタリアの文学の影響を受けた。そして,年金生活になり,彼は本当の自分に向き合って,オリジナルの作品を書き始めたのだろう。第1期のフランス時代は,作品であれば,フランスの『薔薇物語』(The Romance of the Rose)の翻訳である。さらには,『宮廷愛』(The Court of Love)などが挙げられる。特にその作風には翻訳ということもあり,フランス語に見られる優美さが彼の言語の栄養となり吸収され消化されていくことになる。また,何も言語ばかりではなく,フランス文学で好意的に取り上げられる花にもひときわ留意して取り上げる。デイジーの花は,フランス語ではマルガリータといい,作品の中でも多く登場する。また,鳥についてもナイチンゲールなどがよく取り上げられていたので,チョーサーもそれに

チョーサーの時代 31
習いフランスから言語ばかりではなく,文化も自分の血肉として取り込んだ。また,この時期にチョーサーは,フランスで流行していたテーマも積極的に取り上げる。それは,宮廷恋愛であり,そこに咲く騎士道精神である。おそらく小姓として仕えながらイングランドで見聞きした宮廷での経験が大いに役立ったに違いない。
第2期
第2期は,第1期に比べてチョーサーには大きな影響のあった時期だといっていいだろう。当時の一流の文学者ダンテ4やペトラルカ5,さらにはボッカチオ6の影響の時代だからである。そうしたイタリア文化に触れ,次第にチョーサーはフランスの宮廷恋愛などに興味を失っていく。『トロイラスとクリシダ』もボッカチオの影響を受けているとされる。また,『ほまれの宮』(The House of
Fame)は1374年から82年にかけて書かれた詩で,ほまれの宮殿において,ほまれという女神が名誉と不名誉を決定する場面で大勢のものものたちがほまれを求めて群がるものの,結局はThe House of
Rumourといううわさの宮に連れて行かれるということが描かれている寓話的な詩である。それは,ダンテの『神曲』の影響を受けていると知られている。この時期には,他にも,『哀れみへの不満』(The
Complaint to Pity)や『ヴィーナスの不満』(The Complaint of Venus)などが挙げられるが,特に注目すべきものは,『百鳥のつどい』(The Parliament of Fowls)であろう。700行余りで書かれたロイヤルライムで,聖バレンタインの日に,自然宮に鳥たちが配偶者を求めて集まり,あるメスが3羽のオスを求めたために,一年もの間,配偶者選びを待たされるという夢物語である。この物語にもダンテの地獄の門の表現に似たものが使われていて,その翻訳のライムもボッカチオから真似たものだった。ここでのコンベンションとして,夢を起点にしており,時期は5月の朝で,場面は庭というものが用いられている。無論これは,その後のシェークスピアの『夏の夜の夢』にも出てくるものである。このイタリア時代に言えることは,より多くの影響を直接的に強く受けているのが特徴だが,それでもまだカンタベリー時代に見られる円熟した作風は見られない。
第3期
フランス時代,イタリア時代と当時のヨーロッパ文化を代表するような文化体験をその栄養分として,チョーサーは自分のオリジナルの文体と作品世界を作り上げることとなる。それが,この第3期である。それを円熟期と称する批評家もいる。この時期を代表する作品は,いうまでもなく『カンタベリー物語』(The Canterbury Tales)と呼ばれる巡礼の物語である。英雄2連詩という韻律を採用した約17000行の韻律詩は,1387年から1400年にかけて執筆された未完の作品である。カンタベリー大聖堂に詣でるために,ロンドンの郊外のタバードと言う名の旅亭で29名の巡礼者たちが,宿の主人の発案で巡礼の行き帰りに,それぞれが二つの話を披露して旅の憂さを慰めると言うのが構想であった。のちに巡礼の数は2名増え31になったが,実際にはチョーサー自身が二つ,それから,22名のものが二つづつで合計24しかなく,しかも話は目的地に到着しないまま未完で終わる。特にそのプロローグが,巡礼者たちを描いた絵巻物のようなまとめにもなっており,作品の文体からも圧巻だと評されている。プロローグの後は,1がボッカチオの影響の見られる騎士の話,2が粉屋の話,3が執達吏の話などで共に卑猥な喜劇となっている。4が料理人の話,5が弁護士の話,6はけち臭い水夫の話,これもボッカチオのデカメロンに出てくる話である。7は女修道院長の話で宗教的な話になっている。8と9はトポス卿の話で指名されるままにその武勇伝が披露されるが,中途で宿屋の主人がそれを遮る。フランスのロマンスを彷彿とさせるものと言われる。10は,修道士の話で,ダンテに材を得たものだ。11は女子修道院の司祭の話で,フランスの狐物語から想を得たものと言われている。12は医者の話で,

貝 嶋 崇32
『薔薇物語』から取られた少女ヴァージニアの話である。13は免罪符売りの僧の話で,3人で黄金の山を発見したものの,内輪揉めの挙句結局死んでしまうと言う話だ。14はバースの女房の話で,女の最も好むものは亭主を尻にひくことだというのがテーマになっている。15は托鉢修道士と16は宗教裁判召喚係の話で,お互い商売敵どうし相手の実情を暴露し合い,悪口合戦を繰り返す。17はオックスフォードの神学生の話だが,これもデカメロンから取られている。18は,老いた商人の話で,若い妻を寝取られた煩悩だらけの物語だ。19は槍持ちの話で,タタールの王女と魔法の指輪が出てくる。20
は郷紳の話であり,21は第二の修道女の話で殉教がテーマである。22は,司教聖堂つきの参事会員の従者の話で,錬金術のインチキを披露するものだ。23は賄方の話で,カラスの色がなぜ黒いのかと言う由来を説明したものだ。そして最後に,24は牧師の物語で,懺悔や恩寵そして7つの大罪について語られている。その中でも最も有名な部分の一つは以下のプロローグの冒頭である。
Whan that aprill with his shoures soote
The droghte of march hath perced to the roote,
And bathed every veyne in swich licour
Of which vertu engendred is the flour;
Whan zephirus eek with his sweete breeth
Inspired hath in every holt and heeth
Tendre croppes, and the yonge sonne
Hath in the ram his halve cours yronne,
And smale foweles maken melodye,
四月の雨が優しく三月の干ばつの草木の根元に染み込みその葉脈を満たしそこから緑なす花が生じる西風が優しく吹きつけあたり一面の林や森の若い作物が芽吹く 若い太陽は白羊宮に半ば達し小鳥たちも囀り始める
ここには春まだ浅き風物の生命の息吹が格調高く語られていて,緑なす大地が春の訪れにより,それまで静かに耐えてきた生命活動が,春の訪れとともにエネルギーを取り戻して,豊かな自然が喜びに溢れかえる様子が,ほんの短い詩行で手に取るように具体的に表わされている。弱強5歩格の2連が対になっており,英雄連と呼ばれている詩型が用いられている。この一部を見ただけでも,その作品全体の価値までが想像できるようだ。他にも,代表作として触れておくべき作品は,『百鳥のつどい』,『トロイラスとクリセダ』などあるが,ここでは紙面の都合上,以下の『薔薇物語』(The Romaunt of the Rose)を取り上げておきたい。この作品は,1370年代にチョーサーのフランス時代に書かれた翻訳である。オリジナルは,1235年頃にロリス(Guillaume de Lorris)によって書かれたとされる22000行からなる中世フランスの韻文ロマンスである。前編は寓意的な恋愛詩とされており,宮廷愛がそのテーマとなっている。チョーサーの関係した宮廷でも取り上げられていた。その断片を翻訳し,現在見られるの7700行の部分訳になっ

チョーサーの時代 33
ている。主人公のラマントが,理性や嫉妬など寓意的な人物から励まされたり,邪魔されたりして,最後には神の寵愛を得るという話である。そこには,風刺も含まれているとされている。ここでは,断片Aの冒頭部をオリジナルとチョーサーの英訳で見ておくことにする。
ⅠMaintes gens dient que en songes
N’a se fables non et mençonges;
Mais l’en puet tiex songes songier
Qui ne sunt mie mençongier; [1]Ains sunt après bien apparant .
Si en puis bien trere à garant
Ung acteur qui ot non Macrobes ;
Qui ne tint pas songes à lobes;
Aincçois escrist la vision
Qui avint au roi Cipion.
ⅡMany men seyn that in sweveninges
Ther nis but fables and lesinges;
But men may somme swevenes seen,
Which hardely ne false been,
But afterward ben apparaunte.
This may I drawe to waraunte
An authour, that hight Macrobes,
That halt not dremes false ne lees,
But undoth us the avisioun
That whylom mette king Cipioun.
From the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
人はいう夢は嘘と幻ばかりだが嘘でない夢もあるやもしれぬ後になって正夢になるものもその裏付けに話をしようかマクローブという男がいて夢は嘘だと思いもせずスキピオの国王のみた夢を記録に残した
中期フランス語のオリジナルの意味をチョーサーは比較的逐語訳で訳しているが,同じ脚韻のものは,

貝 嶋 崇34
apparentとMacrobesとCipiounの3つあり,他にも似ているものもあるが,異なる語を持ってきて,二連句の韻を踏ませている。さらには,言葉のつながりである。流れるように言葉の繰り返しなどで,切れ目のない同様な韻文に仕立てている。オリジナルよりも優っているのは,オリジナルの最後の2行の歩格が字足らずなのに対して,チョーサーはちゃんと韻の数を合わせているところだろうか。何よりも増して,原文の意味を生かし,違えることなく英語をあてがって韻を踏ませているのは,素晴らしいことだ。文体を磨くのは,翻訳するのに限ると思う時があるが,この例を引いた理由は,チョーサーの文章修行がこのフランス語訳にあったのではないのかと思うからである。語彙,それから,文章の流れ,さらにはその魂と言える詩のテーマまで,このような翻訳作業を続けながら,フランス詩の持つ文体を自分の骨肉としていったのではないだろうか。
これまでチョーサーの時代を概観しながら,チョーサーのことを述べてきた。彼の評価を一言で評することは困難だが,これまでそのチョーサーがどのように評価されてきたかは,その後に続く英文学を代表するような大作家たちの言葉に耳を貸すのが一番だろう。例えば,先ほどにも引用したが17
世紀の詩人ジョン・ドライデン(John Dryden, 1661-1700)は,チョーサーのことを他にも“perpetual
fountain of good sense”と評している。良識の枯れることのない泉とチョーサーを称えて,彼の紡ぎ出す言葉の圧倒的な量とその質について天才的だと断じている。また多くの文学批評家も彼のことをその時代の天才詩人であり,言語だけではなくその宗教性,批判精神や深い思想などを,温かみのある言葉で表現したとしてこれ以上ないくらいに評価している。また,彼がその後のイギリスを代表する多くの詩人に大きな影響を与えていることなども考えると,「英詩の父」と称えたドライデンの言葉もあながち大げさではないように思われる。チョーサーがことさらに春の季節とその花々や鳥などを好んだことは,他の作品にも出てくるはしばしの詞から見て取れる。自由奔放に摘み取った自然の野原に見られる比喩などからも,チョーサーの持つ自然愛や慈しみが詞によって切り取られており,まるで新しい発見のように読むものの心を突き動かす力を持っている。ある研究者は,「チョーサーは,フランス語やイタリア語から借り受けて,イギリス精神に独特のイギリスらしい特質を付け加えた」と評している。しかも,彼は英語を学ぶ学徒であったが,彼の本を学ぶだけでも世界の知恵を台無しにはしないと結論づけている。無論これを持ってチョーサーの人となりを言い切ることはできないだろうが,語彙の面に限らず,英語という言語をかくも豊かにした最初の人物としてのチョーサーの作品に今後とも耳を傾けるべきであろう。
注
1 中世英語と呼ばない点に留意してほしい。歴史の区分と区別するためである。2 Thomas Hoccleve(c.1368-1426)のこと。イギリスの詩人である。3 エドワード3世(1312-1377)は,プランタジネット朝のイングランド王で50年間在位し,イン
グランドを強国に育て上げ,百年戦争を開始したとされる。4 ダンテ・アリギエーリ(Dante Alighieri,1265-1321)は,イタリア都市国家フィレンツェ出身の詩人,哲学者,政治家。
5 フランチェスコ・ペトラルカ(Francesco Petrarca, 1304-1374)は,イタリアの詩人・学者・人文主義者。
6 ジョヴァンニ・ボッカッチョ(Giovanni Boccaccio, 1313-1375)は,中世イタリア,フィレンツェの詩人。

チョーサーの時代 35
主な参考文献
T.G.Tucker and W. Murdoch, A New Primer of English Literature, Whitecombe and Tombs Limited,
1911.
Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature, Clarendon Press, Oxford, 1944.
さらには以下のものからも引用させて頂いた。Richard Garnett, C.B., LL.D. English Literature; An Illustrated Record, vol 1, The Macmillan Company;
London, 1905.
〈キーワード〉チョーサー,十四世紀,中期英語,英詩の父,『カンタベリー物語』
貝嶋 崇(現代文化学部言語文化学科国際コミュニケーションコース)
(2017. 11. 1 受理)