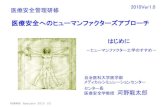4. マレーシア...28 4. マレーシア マレーシア 1章 医療インフラ及び制度、医療関連市場(医薬品・医療機器) 1.1 医療提供体制 1.1.1 医療機関の分類とデータ
トピックス レジオネラ対策 - kao(花王)集団発生 保険所への届出...
Transcript of トピックス レジオネラ対策 - kao(花王)集団発生 保険所への届出...

レジオネラ対策
●はじめにレジオネラ症(Legionellosis)は、レジオネラ ニューモフィラ(Legionela pneumophila)に代表されるレジオネラ属菌による感染症である
が、確定診断できるまでの期間が結核に次ぐほどの長さを必要とすることを特徴とする疾患である。 臨床症状だけからの診断は困難
で、原因菌を発見するまでに培養期間が長く、同定にも時間がかかることが原因する。また、レジオネラ属菌は土壌、湖・河川に広く分布
しているため、ヒト生活圏と重なって日常での接触を避けることはできない。知らずしらずのあいだに感染し、発症してからの診断でも
見逃しを起こす、すなわち すリ抜けをしやすいことから集団発生にもつながりやすい。レジオネラ症は、感染症法に定められた「第4類
感染症;全数届出義務」の感染症でもあることから、できる限り早期発見が必要な感染症である。
以下、 レジオネラ症の概 要、 レジオネラ感染に至る経過、 早期診断のためのポイント、 届出から事 後 措 置 まで
の一連についてまとめた。
レジオネラ症レジオネローシス : Legionellosis
病 原 体:レジオネラ属菌
感 染 症:レジオネラ肺炎、ポンティアック熱
好発年齢:50~60歳代が最も多い
性 差:男性対女性比(約3:1)
分 布:土壌、淡水、温泉
好発時期:梅雨時期、夏季
エアロゾル粒子 (拡大図)
レジオネラ属菌の生息と感染経路
感染源(分布) 自 然 界 1. 土壌、淡水 2 . 河川・湖
風 呂・温 泉 1. 循環浴槽 2 . ジェット風呂 3 . 浴場、温泉
人口環境水 1. 冷却塔水 2 . 吸水塔 3 . 加湿水 4 . 修景水
感染(伝播)経路【空気感染】
疾患(感染症)と症状
レ ジ オ ネ ラ 肺 炎 発熱、悪寒、頭痛、咳、痰、胸痛、全身倦怠感、呼吸困難、 しばしば 下痢[肺炎を伴う(胸部X線)]
ポンティアック熱 発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、全身倦怠感[肺炎を伴わない]
7~10日間感染症成立
エ ア ロ ゾ ル の 吸 引 1. 冷却水 2 . 加湿器 3 . 循環式浴槽
気 道 の 吸 引 で 起こる 1. 気管内挿管 2 . 温泉水吸引
呼吸管理装置から直接 1. 酸素呼吸器 2. ネブライザー
嚥下・経口の可能性(可能性として) 1. 消化管穿通、血中拡散 2 .口腔・咽頭粘膜の外傷
(アメーバ等原虫類に寄生)
トピックストピックス
インフェクション コントロール コーディネータ 近藤 静夫

診 断
レジオネラ肺炎の診断と診断基準第1ステップ 疑診時、疑わしい患者の呼吸器由来検体を採取し、検査を急ぐ。
第2ステップ 検査結果を待ち、レジオネラ属菌が検出されたら確定診断とする。
レジオネラ属菌の検出に要する期間1)短期間で検出できる(培養分離のみで推定)場合: 6~7日(選択分離培地で5日間+非選択培地1~2日間)
2)分離株(推定株)の種と血清群を同定する場合: 培養分離した6~7日間に加え、検査の追試期間を要する
臨 床 材 料
ポンティアック熱は肺炎にならないので、診断にすり抜けが起こっても発熱のみで回復することが多いために心配は少ないが、レジオネラ肺炎の場合は重症化して死亡につながることが少なくない。したがって、診断基準をよく守って、早めに手を打つことが肝要である。疑診の段階で問診、肺炎様の症状を自覚する前の10日間ほどの生活経過を聞き取りし、疑わしい場合は遅滞なく患者の臨床材料をサンプリングして、検査を急がなければならない。
診断のポイントは、レジオネラ症を強く疑ってかかるところにある
第1ステップ 疑 診:レジオネラ肺炎が疑われるa)臨床症状、理学的所見、一般検査所見及び胸部X線像から急性細菌性肺炎が 疑われるが、患者の喀痰や気道吸引物などの呼吸由来検体を通常の方法で 培養しても肺炎の原因と考えられる菌種が検出されない。
b)肺の浸潤陰影は急速に進展するが、浸潤陰影の程度に比して低酸素血症が 低く、一般肺炎に有効なβ-ラクタム剤やアミノ配糖体剤が奏効しない。c)旅行歴、大酒などの生活習慣病、糖尿病、腎障害、免疫不全などの基礎疾患がある。
診 断;積極的疑いをもった診断を行う検 体;早期サンプリングを果たす
培 養 検 査
最適の検体
レジオネラが優勢に存在する臨床材料である
培養培地
レジオネラ属菌同定の手順
検液調製
0.1~0.5mL
GVPC培地
10日間培養(36±1℃)2~4日間隔で3回観察
5日目釣菌
L-システイン不含培地 (基礎培地の脱Lーシステイン)
BCYEα寒天培地(基礎培地)
推 定
未処理検体1 酸処理検体2 熱処理検体3
患者由来の臨床材料
レジオネラ属菌と思われるコロニー数をカウントする
24~48時間培養し、BCYEα寒天培地にのみ発育したグラム陰性桿菌をレジオネラ属菌と推定する
接 種
培 養
観 察
選択培地
自発蛍光よる検出法:360nmのUVを照射し、蛍光の有無で検出する馬尿酸水解試験:1%馬尿酸液にニンヒドリンを加え、紫色を呈する抗血清によるスライド凝集反応:市販の免疫血清(ウサギ)による凝集反応マイクロプレート ハイブリダイゼーション:DNA-DNAハイブリダイゼーション(DDH)による検出
追
試
験
1234

集団発生保険所への届出
医療施設・医療関係者の義務
発生時の対応
レジオネラ肺炎が確定診断された場合
第2ステップ 確 診:レジオネラ肺炎の確定診断a)患者の呼吸器由来材料につき、レジオネラ属菌の培養試験をする。
b)市販の試薬キットで尿中レジオネラ特異抗体を検出する。 結果が陽性の場合:レジオネラ肺炎を確定診断する。 結果が陰性の場合:必ずしも レジオネラ肺炎が陰性とはいえない。
c)患者呼吸由来材料の直接塗末標本のヒメネス染色で、マクロファージ内に多数の 赤色桿菌を認める。
d)マイクロプレート定量凝集法又は間接蛍光交代法で、患者血清の抗レジオネラ 抗体価が有意上昇するかどうかを調べて証明する。
e)レジオネラ属菌に、共通のプライマーを用いて、患者の呼吸器由来材料から、 Polymerase chain reaction(PCR) 法によってレジオネラ属菌に特異的な塩基配列を 証明する方法は、今後更に検討する必要がある。
培 養:培養期間が長い(4日)
検 出:検出限界が原因する
確 定:クロスチェックの必要性確認
発病前10日間に、感染源と疑われる水利用施設でエアロゾルに暴露された可能性がないか調査する。発病前10日間に、業務、観光、慰安その他の目的で国内、国外旅行に参加していないか調査する。患者居住地周辺住民及び同一職場内での発病者の有無を聞き取り調査する。発病者のみならず、その施設の来訪者、周辺住民を対象とした疫学調査(採血、採尿を含む)を実施する。
12
3
4
注 釈:WHOは L. pneumophila SG1 に対する血清抗体価が、ペア血清で4倍又はそれ以上(128倍以上)の上昇、単一血清では256倍以上を示す場合を有意とし、この菌種の他の血清群及びその他の菌種については更なる検討が必要としてきたが一般にはこの基準を他の血清群や菌種にも適用している。 近年、マイクロプレート凝集反応では、陽性下限をペア血清で4倍上昇して64倍以上、単一血清で128倍以上とする考えがある。
注 釈:確定診断のための検査を実施しても、すべての検査が陽性になるとは限らない。培養でレジオネラ属菌が検出されているのに血清抗体価の有意上昇のない症例、尿中特異抗体が強陽性なのに培養も血清抗体価上昇も陰性の症例もある。これらのことは各検査方法の価値を貶しめるものではないし、 1つの検査方法だけでは不十分であることを認識しなければならない。
第4類 感染症(全数届出義務):7日以内
感染症法に定められた取り扱い
●レジオネラ症を診断した医師は7日以内に患者の年齢、性別、診 断方法等を添えて所轄の保険所に届け出る義務がある。● 同一施設又は地域で6ヶ月以内に2名以上の患者が発生したと きは集団発生と認め、主治医は所轄の保険所長に報告しなけれ ばならない。複数患者の発病期間が6ヶ月以上離れている場合は、 関連症例として取り扱う。● 患者がレジオネラ肺炎と確定診断された場合には、患者の周辺に 顕性又は不顕性の感染者がいないか、周辺各医療機関、診療 所 と連携して疑わしい患者の発見・感染源の特定に努めると共に、 迅速且つ慎重な検索を行うべきである。● 患者が確定診断されれば、直ちに疫学調査及び感染源と思わ れる水利用設備から採水し、細菌検査を実施する。●これらのことが実施できるような各医療機関は、自らの細菌検査 担当者の技術向上と設備・資材の充実に心がけねばならない。
多発 アウトブレイク
集団発生が起こった場合の措置集団発生が起こった場合の措置病院・施設の対応 保険所の立ち入りに協力○感染源として疑わしい温泉、浴場、その他の水利用施設を 使用停止し、現状維持とする。1
○当該の施設を立ち入り検査し、検体を採取する。2
○採取した検体を検査し、感染源を特定する。3
○近隣医療施設へ多発を報告し、類似例の報告を求める。4
【洗浄・消毒・水の交換を禁止】
対 象 者:建築物環境衛生管理関係者
集団発生時 :保険所の行う措置及び指導
【冷却塔などの水利用施設の維持管理】
【感染源の調査及び感染予防対策】
保険所の指導保険所の指導

予防と対策
「Pro-アクティブ」と「Re-アクティブ」 リスクマネジメント用語であり、潜在しているリスク、突発的に発生する事故をできる限り未然に防止するために、考えられる範囲で予測して講じる事前対策を「Pro-アクティブ」という。 一方、事故発生後に講じる事後対策のことを 「Re -アクティブ」という。 レジオネラ症は、その徴候もなく、予知不可能の状態で発生してくる感染症であるため、環境水の日常管理が予防のための唯一の手段となる。すなわち「Pro-アクティブ」が最も重要なものであり、仮に診断が確定されてからの対策に転じることにしても、原因個所の特定、遺伝子の解明までも求められるようになって、かえって時間と費用が多大になって跳ね返る不測の事態を招くことになる。 したがって、日常生活で接している環境水の汚染を定期的に測定管理することが重要である。
水利用設備のレジオネラ属菌に対する管理策
水利用設備・装置の清潔維持
◎主治医は、7日以内に所轄の保険所へ届出する。
◎保険所の指導のもと、具体的対策を実行する。
◎主治医は、所轄の保険所長に届出を行う。◎単発発生時に加え、より 厳しい対策となる。
● 急性細菌性肺炎が疑われる患者の調査● 患者の家庭の入浴設備等水利用施設調査● 医師、看護・検査にあたる職員の教育● 建築物環境衛生管理関係者当の教育● 建築物の所有者、維持管理者の職務の強化● 冷却塔などの水利用施設の維持管理改善● その他に、指導があると考えられる業務・責務 (集団発生時の「発生源特定」などの指導)
● 患者の発見・感染源特定のための調査、実験● 感染源と思える水利用施設の細菌検査● 当該レジオネラ属菌の疫学的調査、検討● 近隣病院へ集団発生を通報し、情報を集める● 発症者の家族及び同一事業所の保菌者検査● 患者住居周辺居住者、関係者の保菌者検査● 原因の水利用施設、風呂場などの閉鎖
保険所への届出 参照
「Pro-アクティブ」 「Re-アクティブ」診 断 レジオネラ症例(単発)が発生してしまった場合
集団発生(6ヶ月以内に2名以上)してしまった場合
環境水モニタリング
◎ レジオネラ属菌の培養と検出に長日数が必要で「確定診断」が遅れるため、疑診の段階で強い疑い を持った診断が必要となる。
◎ 疑診の段階で当該患者の臨床材料のサンプリング を急ぎ、早期検査が重要である。
◎給水・給湯設備、冷却塔・冷却水系、加湿器、水景施設、蓄熱槽、風呂・温泉の環境水の定期検査計画と実施が重要なポイントになる。
◎ビル衛生管理法に基づく「水質検査」及び「環境・設備の維持管理」の基準に適合するような日常管理が重要である。
◎「環境・設備の維持管理」の基準に適合していない場合、「清 掃」、「洗浄」、「殺菌・消毒」などの適切な処置と対策を講じなければならない。
1)貯水タンクを設置している場合は、末端の蛇口で60℃以上が保たれるよう、元のタンク温度を設定する。2)蛇口からの湯の使い始めは、しばらく流し、滞留水を放出してから使用する。3)蛇口が混合栓の場合は、最低月1回は冷却栓を締め湯水栓を開け、30分程度湯を流し熱湯消毒をする。4)シャワーヘッドなど蛇口に付けた器具は、最低月1回は消毒する。
1)末端蛇口での残留塩素を週に一度は0.1mg/リットル(0.1ppm)以上であることを確認する。2)給湯と同じように、使い始めの滞留水を放出する。
給湯設備
給 水 系
1)休止期間中は水を抜いておく。2)毎回滞留部分を洗浄後、清浄水を使用する。3)ネブラーザーは、特に滅菌水使用がよい。
加 湿 器
1)貯水槽、水道水の残留塩素濃度を適性に保ち、定期的にチェックする(0.4~0.6ppm)。2)毎回滞留部分を洗浄後、清浄水を使用する。
貯 水 槽
1)循環・ろ過装置及び消毒装置を設ける。2)定期的に水質検査と掃除を実施する。
水景施設
1)エリミネータ(クーリングタワーの除滴板(しぶき止)を強化し、飛沫飛散を抑える。2)清掃を定期的に行い、抗レジオネラ用空調水処理剤を投入する3)冷却水系に溜まる炭酸カルシウムやケイ酸マグネシウム成分のスケールの防止に適切な薬剤を使用する。 4)冷却水系を塩素系消毒剤などで消毒する。
冷却塔及び冷却水系