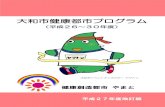フランスの公共交通を活かしたまちづくり...58 都市とガバナンス Vol.24...
Transcript of フランスの公共交通を活かしたまちづくり...58 都市とガバナンス Vol.24...

都市とガバナンス Vol.2458
ヨーロッパのまちづくり政策
はじめに
フランスではパリやリヨンのような大都市だけでなく、地方都市でも中心市街地に活気
がある。その活気を生み出しているのは、公共交通や歩行者・自転車を中心にした交通政
策と、シャッター商店街を作らないまちづくりであろう。
この 20 年ほど、フランスでは多くの地方都市で新しくトラム 1(路面電車)の路線が開
業している。SNCF(フランス国鉄)の TGV に乗ってパリから地方都市に移動すると、
駅前からすぐにトラムに乗ることができる都市が多い。フランスの都市圏の規模は日本の
それと比べて決して大きくなく、人口規模でいえば 100 万人に満たないところがほとんど
だが、こうした都市圏の多くが新しく軌道系交通を整備しており、これは日本の現状とは
大きく異なる。中には都市圏人口が 10 万人程度にもかかわらずトラムを新規に整備した
ところさえ存在する。
こうした政策の背景には、公共交通の整備・運営について採算性以外の面も重視する考
え方がある。都市圏人口の少ないフランスでは公共交通の利用者は決して多くなく、また
運賃もあまり高くないこともあり、日本と違ってほとんどの鉄道やバスが赤字運営である。
フランスでは公共交通や歩行者・自転車を中心にした交通政策で中心市街地の活性化に成功している。本稿はこうした政策が実現している背景にある法、組織、財源、計画及び合意形成などの制度について概説し、その実際の運用状況について紹介した。 全体を通しての結論としては、公共交通を中心としたまちづくりでは明快な政策方針と制度的なフォロー、国でなく地方がイニシアチブをとることが必要だといえる。また具体的な施策としては、道路空間の有効活用や駐車政策などの複数の施策を積極的かつスピーディに行うことが効果的とみられる。そして何よりも、公共交通だけが単体で魅力ある交通手段となるだけではなく、中心部における商業施設の活性化などを通じて公共交通の目的地となる中心部の魅力を高めることが最も重要である。
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
ヨーロッパのまちづくり政策
テーマ
流通経済大学経済学部准教授 板 谷 和 也早稲田大学理工学術院教授 森 本 章 倫
1 日本では次世代型の路面電車のことをLRTと呼ぶことが多いが、フランスではこうした路面電車も、旧来からの名称であるトラム(Tram)と呼ぶことが多いため、本稿では以降も路面電車のことをトラムと呼ぶ。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2458
ヨーロッパのまちづくり政策
はじめに
フランスではパリやリヨンのような大都市だけでなく、地方都市でも中心市街地に活気
がある。その活気を生み出しているのは、公共交通や歩行者・自転車を中心にした交通政
策と、シャッター商店街を作らないまちづくりであろう。
この 20 年ほど、フランスでは多くの地方都市で新しくトラム 1(路面電車)の路線が開
業している。SNCF(フランス国鉄)の TGV に乗ってパリから地方都市に移動すると、
駅前からすぐにトラムに乗ることができる都市が多い。フランスの都市圏の規模は日本の
それと比べて決して大きくなく、人口規模でいえば 100 万人に満たないところがほとんど
だが、こうした都市圏の多くが新しく軌道系交通を整備しており、これは日本の現状とは
大きく異なる。中には都市圏人口が 10 万人程度にもかかわらずトラムを新規に整備した
ところさえ存在する。
こうした政策の背景には、公共交通の整備・運営について採算性以外の面も重視する考
え方がある。都市圏人口の少ないフランスでは公共交通の利用者は決して多くなく、また
運賃もあまり高くないこともあり、日本と違ってほとんどの鉄道やバスが赤字運営である。
フランスでは公共交通や歩行者・自転車を中心にした交通政策で中心市街地の活性化に成功している。本稿はこうした政策が実現している背景にある法、組織、財源、計画及び合意形成などの制度について概説し、その実際の運用状況について紹介した。 全体を通しての結論としては、公共交通を中心としたまちづくりでは明快な政策方針と制度的なフォロー、国でなく地方がイニシアチブをとることが必要だといえる。また具体的な施策としては、道路空間の有効活用や駐車政策などの複数の施策を積極的かつスピーディに行うことが効果的とみられる。そして何よりも、公共交通だけが単体で魅力ある交通手段となるだけではなく、中心部における商業施設の活性化などを通じて公共交通の目的地となる中心部の魅力を高めることが最も重要である。
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
ヨーロッパのまちづくり政策
テーマ
流通経済大学経済学部准教授 板 谷 和 也早稲田大学理工学術院教授 森 本 章 倫
1 日本では次世代型の路面電車のことをLRTと呼ぶことが多いが、フランスではこうした路面電車も、旧来からの名称であるトラム(Tram)と呼ぶことが多いため、本稿では以降も路面電車のことをトラムと呼ぶ。
都市とガバナンス Vol.24 59
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
しかし、フランスで新しく整備されたトラムはどれも美しく、街のシンボルになるような
ものばかりである。
魅力的な大量交通機関を整備するのは、街の中心部に人を集めるためである。古くから
の市街地には歴史があり、文化があり、人が集まるポテンシャルがある。フランスでも、
かつては行き過ぎたモータリゼーション 2 のため、地方都市の中心部がシャッター商店街
と化し駐車場ばかりが目立っていた時期もあった。それは現在の日本よりもひどい状況
だったという。
そうした中心部を豊かな空間に変えたのは、交通政策とまちづくりの方針転換だった。
各地でトラムが次々に整備される背景には、それを可能にした制度の変革があった。具体
的には政策方針を定める基本法を制定したうえで、組織、財源、計画、そして意思決定に
関わる制度が整備されている。これらの制度的変化がフランスの都市のあり方を変貌させ
たといって過言ではない。
これらはフランスの地方分権政策の一環として実現してきている。ミッテラン政権と
なった 1982 年以降、交通分野における地方分権は時間をかけて進展してきた。現在では
中央政府が政策の方針と枠組みを定め、地方政府はそのルールのもとで各々の環境に即し
た将来像を定め、直面する課題の解決に向けて努力するというかたちができあがりつつあ
る。
こうした制度的背景を持つフランスの都市圏中心部のまちづくりは、短期間のうちに大
きく街の姿を一変させて中心部に賑わいを取り戻す実効性の高さが特徴であり、日本でも
参考になる部分が多いと考える。そこで本稿では、コンパクトな市街地作りに不可欠な公
共交通を中心としたまちづくりを行うフランスの交通政策について、その制度枠組みと具
体的な事例を紹介することとしたい 3。
1.フランスにおける交通政策の背景
フランスの都市交通を取り巻く状況は、日本と大きく異なる。最も大きな差異は、フラ
ンスでは公共交通は単独では採算が取れない事業だということである 4。そのため、フラ
ンスの公共交通は公的な補助金の存在を前提として維持運営を行う枠組みとなっている。
フランス地方都市の中心部で特に目を引くのは、魅力的なトラムや都市型レンタサイク
ル 5 であるが、こうしたものが実現する背景では行政が積極的に交通政策を展開している。
2 2014年9月時点でトラムを運行しているフランスの都市圏は29に上るが、1980年代前半にはトラムは3都市圏(リール、マルセイユ、サンテティエンヌ)に残るのみとなっていた。近代的なトラムを新規に整備した最初の事例は、1985年のナント都市圏である。3 本稿の対象は、フランス地方行政のうちコミューン(Commune・基礎自治体)及びEPCI(Etablissement Public de Coopération Intercommunale・コミューン間協力機関)が担当する部分とする。州(Région)、県(Département)の担当部分についてはここでは触れない。4 フランスに限らず、欧米諸国では一般的に公共交通は不採算である。5 パリでは「Vélib’(ヴェリブ)」、リヨンでは「Velo’v(ヴェロブ)」といった愛称がつけられている。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2460
ヨーロッパのまちづくり政策
本節ではこうした政策の裏づけとなる制度について述べる。
(1) 国内交通基本法 LOTI
ア 交通権
フランスにおける種々の制度的変革は、1982年に制定されたLOTI6 が基点となっている。
LOTI はフランス国内の交通に関する原則とその将来にわたる方向性を示したものであり、
制定以降も幾度となく修正が加えられている。
この中で、世界で初めて「交通権」が明文化された。交通権は、フランスのすべての国
民の移動する権利である。
それまではフランスでも、長らく移動手段の中心に自動車を位置づけた政策を展開して
きていた。その結果として自動車の走行に適した道路が多数整備され、自動車の運転が自
由にできる人にとっての移動は便利になった。しかし一方で、何らかの事情で自動車を運
転できない人には移動しにくくなってしまっただけでなく、駐車需要への対応に追われた
都市中心部がその魅力を失いつつあった。そのため、自動車以外の交通手段で移動できる
ようにすることが、国策として求められたのである。
交通権の保障された社会は、簡単に実現できるものではない。そのため基本法でも、交
通権は全国民に保障されるとはせず、その実現に向けて努力しなければならない、と表現
されている。この法律のもとで、交通権の実現に向けた各種の交通政策が積極的に行われ
てきたといえよう。
イ LOTI における方針
LOTI が成立したのは、政権交代が実現したことの影響が大きい。当時の社会党は交通
に関わる多くの公約を掲げて選挙に勝利した。ミッテラン政権で設備大臣に就任したフィ
テルマンは、1970 年代を通じて TGV や VAL といった新しい交通システムが実用化され
たことを評価しつつ、自動車交通への過度の依存とそれによる公共交通の陳腐化を問題視
し、さらに交通関連の効率化が進まないことを経済停滞の一因として指摘した。このよう
な交通問題の解決と、問題の背景にある時代に合わず互いに矛盾している交通関係法律を
整理しようとする意図のもとで、LOTI が策定された。
そのため LOTI が示す交通政策の方向性は、全交通手段を考慮した交通システムの運営
を行政が行うことを原則とする総合政策の実現をめざすというものになっている。LOTI
の中では、公共交通システムの整備・維持における国や地方自治体の果たすべき役割と責
任を明らかにし、その実施に関して地方分権を推進することになっている。つまり、利用
6 Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’ Orientation des Transports Intérieurs(国内交通基本法)。現在は交通法典(Code des Transports)の一部となっている。本稿では以下、交通法典の当該部分を指す言葉として「LOTI」を用いる。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2460
ヨーロッパのまちづくり政策
本節ではこうした政策の裏づけとなる制度について述べる。
(1) 国内交通基本法 LOTI
ア 交通権
フランスにおける種々の制度的変革は、1982年に制定されたLOTI6 が基点となっている。
LOTI はフランス国内の交通に関する原則とその将来にわたる方向性を示したものであり、
制定以降も幾度となく修正が加えられている。
この中で、世界で初めて「交通権」が明文化された。交通権は、フランスのすべての国
民の移動する権利である。
それまではフランスでも、長らく移動手段の中心に自動車を位置づけた政策を展開して
きていた。その結果として自動車の走行に適した道路が多数整備され、自動車の運転が自
由にできる人にとっての移動は便利になった。しかし一方で、何らかの事情で自動車を運
転できない人には移動しにくくなってしまっただけでなく、駐車需要への対応に追われた
都市中心部がその魅力を失いつつあった。そのため、自動車以外の交通手段で移動できる
ようにすることが、国策として求められたのである。
交通権の保障された社会は、簡単に実現できるものではない。そのため基本法でも、交
通権は全国民に保障されるとはせず、その実現に向けて努力しなければならない、と表現
されている。この法律のもとで、交通権の実現に向けた各種の交通政策が積極的に行われ
てきたといえよう。
イ LOTI における方針
LOTI が成立したのは、政権交代が実現したことの影響が大きい。当時の社会党は交通
に関わる多くの公約を掲げて選挙に勝利した。ミッテラン政権で設備大臣に就任したフィ
テルマンは、1970 年代を通じて TGV や VAL といった新しい交通システムが実用化され
たことを評価しつつ、自動車交通への過度の依存とそれによる公共交通の陳腐化を問題視
し、さらに交通関連の効率化が進まないことを経済停滞の一因として指摘した。このよう
な交通問題の解決と、問題の背景にある時代に合わず互いに矛盾している交通関係法律を
整理しようとする意図のもとで、LOTI が策定された。
そのため LOTI が示す交通政策の方向性は、全交通手段を考慮した交通システムの運営
を行政が行うことを原則とする総合政策の実現をめざすというものになっている。LOTI
の中では、公共交通システムの整備・維持における国や地方自治体の果たすべき役割と責
任を明らかにし、その実施に関して地方分権を推進することになっている。つまり、利用
6 Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’ Orientation des Transports Intérieurs(国内交通基本法)。現在は交通法典(Code des Transports)の一部となっている。本稿では以下、交通法典の当該部分を指す言葉として「LOTI」を用いる。
都市とガバナンス Vol.24 61
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
者の交通権の実現が国と地方自治体にとっての政策目標となり、そのための施策を実施す
るために財政的な支出を行うことが必要となったのである。具体的には、都市交通に関す
る計画策定や公共交通の運行等については一部財源的支援も含めて地方政府の責任で行
い、国は主に国際交通と国内都市間幹線交通を担当し、都市交通については間接的に携わ
ることになった。
こうした枠組みを作るために、LOTI はそれまでのモード別の法律群を一つにまとめ、
整合的な法体系となるよう構築されている。加えて、計画で示される施策の評価に際して
は、採算性ではなく社会的経済性による効率性を重視しなければならないことも明記され
た。
つまり LOTI は、地方交通を採算事業でなく公益事業と捉え、その運営は地方政府が責
任をもって行うことを求めているのである。
(2)都市交通に関わる組織
ア AOTU の役割
フランスの都市交通は、LOTI の枠組みのもと地方自治体が大きな役割と責任を担って
いる。フランスは日本と違い現在でもコミューン 7 が多数存在しているが、特に都市化が
進んだ地域ではコミューン内で住民の交通行動が完結することはほとんどなく、複数のコ
ミューンが一つの都市圏を形成していることが多い。そのため交通に限らず多くの政策分
野で、EPCI8 制度を用いて複数コミューンの業務の一部を広域連合・広域組合に移し、一
体的な政策を行うのが一般的である。
LOTI では都市交通のあり方と方向性について詳細に定められているが、この「都市交通」
の対象となる地域のことを都市交通区域 9 と呼ぶ。都市交通区域は各都市圏の実情に合わ
せて指定する 10 ことになっているが、多くの場合は広域連合の範囲全体を指定している。
この都市交通区域に指定されると、そうでない場合と比べて行政側の権限が大きくなる。
都市交通区域におけるすべての交通政策の責任を負う機関を AOTU11 と呼ぶ。AOTU
は広域連合の一部門であり、日本でいえば市役所の交通政策課等に相当する。AOTU に
は交通計画の策定や財源の確保など、交通に関わる権限の多くが集中している。LOTI で
は AOTU の役割として、交通に関わる施設整備・運営、規制、情報提供、交通政策(事
業者の選択・契約、サービスレベルの設定など)・交通計画の策定、資金調達・投資など
7 Commune(基礎自治体)。日本の市町村に相当する。8 Établissement public de coopération intercommunale(コミューン間協力機関)。日本の広域連合、一部事務組合に相当する。9 PTU(Périmètre des Transports Urbains)。10 都市交通区域は地方自治体の側が自主的に形成するものであり、中央政府が強制的に指定するような性格のものではない。11 Autorité Organisatrice de Transport Urbain。都市圏交通局等と訳される。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2462
ヨーロッパのまちづくり政策
が明記されている。つまり AOTU は、公共交通・道路交通を問わず、都市圏内のすべて
の交通に関して、計画・整備・運営・財政等あらゆる面での施策を実施し、またそれに関
する責任を負うということである。
フランスの広域連合には独立した議会が設置されている。AOTU はすべての交通政策
の責任を負うが、その予算や計画等の施行に際しては、議会の承認が必要であることは言
うまでもない。
イ 事業者の役割
さて、地方自治体の交通政策課である AOTU は交通政策に関する大きな役割を担って
はいるものの、実際の公共交通機関の運行は AOTU が自ら行うところは少なく、委受託
の関係で交通事業者が行う。フランスで公共交通を運営する事業者には、大きく半官半民
の企業(混合経済会社・SEM)と完全私企業とがある。
日本の多くの事例と異なるのは、車両や施設などの資産は必ずしも事業者が所有してい
るわけではなく、AOTU が所有してその使用権を事業者が得るようなかたちになってい
ることが少なくないということである。特にトラムの場合は AOTU が施設を整備・保有
するのが一般的である。
事業者の多くは、フランスだけでなく世界各国で公共交通事業を展開する、公共交通グ
ループ 12 に所属している。各事業者は契約を通じて都市圏での運営権を委ねられ、各公共
交通グループはスタッフ派遣、ツール提供等を通じて各事業者の運営を助けている。なお
都市圏が小規模な場合など、日本の公営企業と同様の形態で地方自治体が直接に運行業務
を担当することもある。
フランスでは原則として、各都市交通区域で一社が独占的に契約を結ぶかたちをとって
いる。企業間競争は、入札の段階すなわち都市圏を担当できるか否かを決める時点で行わ
れるのみであり、実際の運営にあたって複数の企業どうしが競争することはない。これは、
サービス水準は基本的に AOTU が決定するため、事業者が単独で行える施策が限られて
いることによる影響が大きい。もともとフランスの公共交通は赤字経営で企業論理による
経営が成り立たずに行政の介入が強まった経緯があるが、現在の公共交通運営事業者は行
政による経営条件の改善を受けて、それを前提にして実際の交通サービス運営を担当して
いるということである。
(3)都市交通の財源制度
ア AOTU の財源
12 KEOLISやTRANSDEVが著名。交通に限らず、地方自治体を取引相手とした「低リスク・低収益」の事業を各国で展開している。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2462
ヨーロッパのまちづくり政策
が明記されている。つまり AOTU は、公共交通・道路交通を問わず、都市圏内のすべて
の交通に関して、計画・整備・運営・財政等あらゆる面での施策を実施し、またそれに関
する責任を負うということである。
フランスの広域連合には独立した議会が設置されている。AOTU はすべての交通政策
の責任を負うが、その予算や計画等の施行に際しては、議会の承認が必要であることは言
うまでもない。
イ 事業者の役割
さて、地方自治体の交通政策課である AOTU は交通政策に関する大きな役割を担って
はいるものの、実際の公共交通機関の運行は AOTU が自ら行うところは少なく、委受託
の関係で交通事業者が行う。フランスで公共交通を運営する事業者には、大きく半官半民
の企業(混合経済会社・SEM)と完全私企業とがある。
日本の多くの事例と異なるのは、車両や施設などの資産は必ずしも事業者が所有してい
るわけではなく、AOTU が所有してその使用権を事業者が得るようなかたちになってい
ることが少なくないということである。特にトラムの場合は AOTU が施設を整備・保有
するのが一般的である。
事業者の多くは、フランスだけでなく世界各国で公共交通事業を展開する、公共交通グ
ループ 12 に所属している。各事業者は契約を通じて都市圏での運営権を委ねられ、各公共
交通グループはスタッフ派遣、ツール提供等を通じて各事業者の運営を助けている。なお
都市圏が小規模な場合など、日本の公営企業と同様の形態で地方自治体が直接に運行業務
を担当することもある。
フランスでは原則として、各都市交通区域で一社が独占的に契約を結ぶかたちをとって
いる。企業間競争は、入札の段階すなわち都市圏を担当できるか否かを決める時点で行わ
れるのみであり、実際の運営にあたって複数の企業どうしが競争することはない。これは、
サービス水準は基本的に AOTU が決定するため、事業者が単独で行える施策が限られて
いることによる影響が大きい。もともとフランスの公共交通は赤字経営で企業論理による
経営が成り立たずに行政の介入が強まった経緯があるが、現在の公共交通運営事業者は行
政による経営条件の改善を受けて、それを前提にして実際の交通サービス運営を担当して
いるということである。
(3)都市交通の財源制度
ア AOTU の財源
12 KEOLISやTRANSDEVが著名。交通に限らず、地方自治体を取引相手とした「低リスク・低収益」の事業を各国で展開している。
都市とガバナンス Vol.24 63
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
フランスでは基本法のもと、交通政策に関する地方自治体の責任と権限を強化している
が、これだけでは施策をスピーディに進めることはできない。フランスにおいて交通政策
の実効性が高く、計画が数年で実現する背景には、AOTU が自らコントロールできる財
源制度が存在する。
都市交通に関する毎年の財源調達とその支出についての計画は、AOTU が策定する。
AOTU の収入源は一般財源、地方債、中央政府からの補助金、VT13 が存在する。このう
ち前 2 者は交通だけでなく、例えば上下水道や廃棄物処理など、広域連合の業務全体に対
して支出されるものであるが、後 2 者は交通政策に限定して使用される、目的税的な性質
を持った収入である。なお地方債の起債理由は投資的経費に限定されており、交通に関し
ては大規模な施設整備に限られる。
AOTU はこれらの収入を、施設整備や交通運営(事実上、交通事業者に対する補助)
等に対して支出する。
イ 交通負担金(VT)
フランスの都市交通政策において非常に大きな役割を果たしているのは、上述の VT で
ある。1970 年代に創設され、幾度かの制度変更を経て現在に至っているが、AOTU にとっ
て最も重要な財源である。というのは、他の財源と違って VT は目的税的な性格を持ち、
しかも AOTU が独自に税率等を設定できる財源だからである。
VT は、都市交通区域内に立地する従業員 10 人以上の法人を対象に、その給与総額に対
して課税するものである。なおフランスの地方税制度では、このような外形標準に対して
課税するのは一般的で特に珍しいものではない。徴収主体は URSSAF14 であり、収入は手
数料等を差し引いた上で AOTU に支払われる。
VT の税率は上限が定められており、各都市圏が独自に設定するためそれぞれ異なる。
ただ TCSP15 といわれる専用軌道を持った公共交通を整備する場合には、制限税率が大き
く上がるようになっている。こうした制度設計となっているのは、国が地方に対して
TCSP 導入を促すツールとして VT を活用する意図があるのではないかと考えられる。フ
ランスでトラム等の新設が相次いでいる要因の一つがこの制度である。
ウ 運賃収入の扱い
これらと別に、交通事業者も日本の鉄道・バスと同様に乗客から運賃を徴収している。
13 Versement Transportのこと。交通負担金、交通税等と訳される。14 les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’ allocations familiales(社会保障費徴収機関)。日本のかつての社会保険庁に相当。15 Transports Collectifs en Site Propreのこと。直訳すると「公共交通の専用空間」となる。専用軌道を走るトラムあるいは専用レーンを走るバスなど、道路交通に影響されずに走行することのできる公共交通機関がこれに該当する。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2464
ヨーロッパのまちづくり政策
この運賃収入もAOTUの収入の一部と考えてよい。AOTUはその都市圏の公共交通のサー
ビスレベルを決定して予算措置を行っているのだが、これはつまり交通事業者の支出額と、
そこから予測運賃収入額を差し引いた補助額を決定しているということである。事業者側
は運賃水準等を自らの判断で変更することはできない。前述の運賃収入以外の AOTU の
収入は交通施設の整備など様々に用いることができるが、運賃収入は公共交通の運営のみ
に使われる。
事業者にとっては、補助金があることで採算性が確保でき、運営努力の結果として収入
が増加すれば利益の増加につながるという仕組みになっている。このような枠組みの存在
が、公共交通を運営する企業グループが形成される要因の一つになっていると考えられる。
(4)都市交通の計画制度
前項までで、フランスでは地方自治体が独自財源をもとに交通政策を一括して進めてい
るということについて記した。
民間事業者が営利事業として公共交通事業を営む場合と異なり、地方自治体は公金を
使って広範な影響のある施策を進めることになるため、あらかじめ民主的な方法で策定し
た計画をもとに施策を進めるのが望ましい。
LOTI ではこのような、都市交通政策に不可欠なツールである計画制度についても明文
化しており、PDU16 という名称の計画を AOTU が策定することを定めている。
PDU は都市圏内のすべての交通に関する計画である。都市圏内の交通に関する整備・
運営計画と予算案は毎年策定されるが、PDU は毎年の交通整備・運営に関する指針とし
て利用されるものであり、その都市圏の将来像とその実現のためのプロジェクト案・交通
政策の原則が中心的に記述されたものである。
PDU の内容は都市圏ごとに異なるが、計画の目的は LOTI の中で以下のように示され
ている。
• 自動車交通の削減
• 経済性・環境保全に効果的な公共交通・自転車交通・歩行者交通の整備・支援・強化
• 国道・県道を含めた、都市圏内の全道路ネットワークの効率的な整備・運営
• 駐車政策の体系化・課金システムの適用
• 旅客交通・物流の合理化
• 公共交通・自家用車の相乗りによる通勤の促進と、そのための地方自治体・民間企業
による通勤交通計画策定支援
• 公共交通利用促進のため、駐車料金などその他の交通手段も考慮した運賃・料金体系
16 Plan de Déplacements Urbains。都市交通計画。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2464
ヨーロッパのまちづくり政策
この運賃収入もAOTUの収入の一部と考えてよい。AOTUはその都市圏の公共交通のサー
ビスレベルを決定して予算措置を行っているのだが、これはつまり交通事業者の支出額と、
そこから予測運賃収入額を差し引いた補助額を決定しているということである。事業者側
は運賃水準等を自らの判断で変更することはできない。前述の運賃収入以外の AOTU の
収入は交通施設の整備など様々に用いることができるが、運賃収入は公共交通の運営のみ
に使われる。
事業者にとっては、補助金があることで採算性が確保でき、運営努力の結果として収入
が増加すれば利益の増加につながるという仕組みになっている。このような枠組みの存在
が、公共交通を運営する企業グループが形成される要因の一つになっていると考えられる。
(4)都市交通の計画制度
前項までで、フランスでは地方自治体が独自財源をもとに交通政策を一括して進めてい
るということについて記した。
民間事業者が営利事業として公共交通事業を営む場合と異なり、地方自治体は公金を
使って広範な影響のある施策を進めることになるため、あらかじめ民主的な方法で策定し
た計画をもとに施策を進めるのが望ましい。
LOTI ではこのような、都市交通政策に不可欠なツールである計画制度についても明文
化しており、PDU16 という名称の計画を AOTU が策定することを定めている。
PDU は都市圏内のすべての交通に関する計画である。都市圏内の交通に関する整備・
運営計画と予算案は毎年策定されるが、PDU は毎年の交通整備・運営に関する指針とし
て利用されるものであり、その都市圏の将来像とその実現のためのプロジェクト案・交通
政策の原則が中心的に記述されたものである。
PDU の内容は都市圏ごとに異なるが、計画の目的は LOTI の中で以下のように示され
ている。
• 自動車交通の削減
• 経済性・環境保全に効果的な公共交通・自転車交通・歩行者交通の整備・支援・強化
• 国道・県道を含めた、都市圏内の全道路ネットワークの効率的な整備・運営
• 駐車政策の体系化・課金システムの適用
• 旅客交通・物流の合理化
• 公共交通・自家用車の相乗りによる通勤の促進と、そのための地方自治体・民間企業
による通勤交通計画策定支援
• 公共交通利用促進のため、駐車料金などその他の交通手段も考慮した運賃・料金体系
16 Plan de Déplacements Urbains。都市交通計画。
都市とガバナンス Vol.24 65
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
の適用
冒頭に「自動車交通の削減」と掲げられているように、都市圏内の住民が公共交通や自
転車などを快適に利用できるようにすることは、どの都市圏の PDU にも共通の目標となっ
ている。
LOTI の制定当初における PDU の規定はきわめて概念的なもので、細部は後に政令で
規定することになっていた。1983 年以降、いくつかの都市圏で実験的に PDU 策定作業が
行われ、グルノーブルのようにトラムの新規整備が実現するなどの成果が上がった。しか
し全国的に PDU を活かした交通政策が普及するのは、1996 年の LAURE17 法制定に際し
ての LOTI 改定に伴って、人口 10 万人以上の都市圏において PDU の策定が義務づけられ
たことによるものである。上述の PDU の目的も、この改定で LOTI の法文に加わったも
のである。
PDU の内容は都市圏の現状分析等に留まらず、実施されることを前提とした将来計画
を含んだものである。したがって、計画実施の際の財源調達計画や、実施された計画・政
策の評価手法といったことも計画に示されることが少なくない。
PDU の策定は各々の都市圏行政の責任のもとで進められる。1996 年の改定の際、PDU
策定義務のある都市圏の策定期限が 1999 年度中と設定されたが、リヨン都市圏以外はこ
の期限に間に合わず、最終的な期限は 2004 年 7 月となった。それまでに策定に関わるす
べての手続きを終えられたのは、策定が義務化されていた 72 都市圏のうち 50 都市圏であっ
た。また策定後も 5 年後の見直しと、将来計画の目標年次となる 10 年後の改訂が義務づ
けられている。
PDU の内容を実際に見てみると、調査に基づく数値的な分析は、日本ほど詳細に行わ
れない場合も少なくない。しかし、若干アバウトではあっても PDU を見ればその都市圏
の交通を AOTU が将来どのようにしたいと考えているかは明快に把握できる。需要の予
測や費用・便益の分析を詳細に行うことも重要だが、それよりも将来の方針を住民に分か
りやすく示すことを優先しているとも考えられる。
(5)合意形成に資する制度
日本で交通関係のプロジェクトが進まない理由の一つとして、住民の理解がなかなか進
まないことがあるのではないかと筆者は考える。これに対しフランスでは、古くから大規
模な開発に際して計画案を広く一般に公開し意見を収集する試みが行われてきている。
一般にフランスでは専門家に対する信頼が厚く、計画案そのものの策定に関してはほと
んど専門家に委ねられてきたが、一方で地域固有の問題や計画の細かい瑕疵の指摘といっ
17 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’ Air et l’ Utilisation Rationnelle de l’ Energie。大気とエネルギーの効率的利用に関する法律。大気法とも呼ばれる。この法律の制定に伴ってLOTIも改定された。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2466
ヨーロッパのまちづくり政策
た点で一般住民の意見も重視されており、議会で計画案の承認を受ける前に住民意見を取
り入れることがごく一般的に行われ、1930 年頃という極めて早い段階から徐々に法制化さ
れてきている。
ただし、この法制化は主として土地収用について行われてきたものであり、土地収用の
有無を問わず環境に影響を与えうる事業一般に対して住民意見を取り入れる手法が法制化
されたのは 1983 年以降のことである。したがって交通関連での住民参加の歴史は、法的
にはそれほど古いわけではない。
ア 合意形成に関わる手法
現在は、計画の構想段階で行われる公開協議(Débat Public)、計画策定の全段階で行わ
れる事前協議(Concertation Préarable)、計画段階の最後、議会承認の直前に行われる公
開事前調査(Enquête Publique)の 3 種が、合意形成を目的とした住民参加のプロセスと
して位置づけられている。またこれら以外に住民投票(Référendum Local)が政策の是非
を問う目的で制度化されている。これらのうち住民投票以外は、ある条件を満たす計画に
関してはすべて、法的に実施が義務づけられている。計画策定・実施過程の中で行わなけ
ればならないことが明示されていることで、どのような施策でも最低限の合意形成がなさ
れているといえる。
これらのうち、都市交通政策で重要なのは事前協議と公開事前調査である。
事前協議は、一定以上の規模のプロジェクトの計画段階から完成に至るまで、継続して
行わねばならないプロセスである。具体的には、逐次事業の計画等の情報を住民に開示す
ると同時に、住民の意見を聴取するものである。都市計画法典で規定された手続きだが、
方法は明記されておらずそれぞれの裁量に委ねられている。説明会や展示会、広報誌といっ
た手段を用いて計画について広く周知し、意見を手紙・E-Mail、電話等で把握するという
かたちが多い。
一方の公開事前調査は、プロジェクト計画の議会での議決に先立って、その妥当性を検
討するプロセスである。フランスでは、議決された計画の内容を変更することはほぼ不可
能であるため、その前の段階で計画の是非を検討するこのプロセスは極めて重要である。
具体的には、プロジェクトと直接利害関係のない調査委員会が、公共の場でプロジェク
トの説明を住民に対して行った上で意見聴取を行い、専門家の意見も取り入れて報告書を
作成するものである。住民は自由に意見表明ができ、その意見は専門家の意見とともにそ
のまま報告書に記載される。1 ヶ月程度の期間で行われ、その間は住民に対する説明が継
続され、広報誌の配布や調査員による聞き取り調査なども行われる。そして、報告書は議
会に提出され、議決の際の判断基準として利用される。
こうした合意形成に関する制度が法制化され、実際に住民の理解を深めるような工夫が
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2466
ヨーロッパのまちづくり政策
た点で一般住民の意見も重視されており、議会で計画案の承認を受ける前に住民意見を取
り入れることがごく一般的に行われ、1930 年頃という極めて早い段階から徐々に法制化さ
れてきている。
ただし、この法制化は主として土地収用について行われてきたものであり、土地収用の
有無を問わず環境に影響を与えうる事業一般に対して住民意見を取り入れる手法が法制化
されたのは 1983 年以降のことである。したがって交通関連での住民参加の歴史は、法的
にはそれほど古いわけではない。
ア 合意形成に関わる手法
現在は、計画の構想段階で行われる公開協議(Débat Public)、計画策定の全段階で行わ
れる事前協議(Concertation Préarable)、計画段階の最後、議会承認の直前に行われる公
開事前調査(Enquête Publique)の 3 種が、合意形成を目的とした住民参加のプロセスと
して位置づけられている。またこれら以外に住民投票(Référendum Local)が政策の是非
を問う目的で制度化されている。これらのうち住民投票以外は、ある条件を満たす計画に
関してはすべて、法的に実施が義務づけられている。計画策定・実施過程の中で行わなけ
ればならないことが明示されていることで、どのような施策でも最低限の合意形成がなさ
れているといえる。
これらのうち、都市交通政策で重要なのは事前協議と公開事前調査である。
事前協議は、一定以上の規模のプロジェクトの計画段階から完成に至るまで、継続して
行わねばならないプロセスである。具体的には、逐次事業の計画等の情報を住民に開示す
ると同時に、住民の意見を聴取するものである。都市計画法典で規定された手続きだが、
方法は明記されておらずそれぞれの裁量に委ねられている。説明会や展示会、広報誌といっ
た手段を用いて計画について広く周知し、意見を手紙・E-Mail、電話等で把握するという
かたちが多い。
一方の公開事前調査は、プロジェクト計画の議会での議決に先立って、その妥当性を検
討するプロセスである。フランスでは、議決された計画の内容を変更することはほぼ不可
能であるため、その前の段階で計画の是非を検討するこのプロセスは極めて重要である。
具体的には、プロジェクトと直接利害関係のない調査委員会が、公共の場でプロジェク
トの説明を住民に対して行った上で意見聴取を行い、専門家の意見も取り入れて報告書を
作成するものである。住民は自由に意見表明ができ、その意見は専門家の意見とともにそ
のまま報告書に記載される。1 ヶ月程度の期間で行われ、その間は住民に対する説明が継
続され、広報誌の配布や調査員による聞き取り調査なども行われる。そして、報告書は議
会に提出され、議決の際の判断基準として利用される。
こうした合意形成に関する制度が法制化され、実際に住民の理解を深めるような工夫が
都市とガバナンス Vol.24 67
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
なされたうえで実際に行われているということが、フランスにおいて住民の反対があって
もプロジェクトがスムースに進捗することの多い背景にあると考えられる。
(6)各制度の連携
以上でフランスの交通政策に関わる主な制度を概観した。フランスの交通政策は、それ
ぞれが単独で行われるのではなくすべてが連携している。例えばトラムの整備を行う場合
でいえば、単にトラムを走らせるだけでなく、同時にバス路線の再編や運賃制度の見直し
などを行い、公共交通ネットワークを再整備する。トラム路線の計画では、トラムによっ
て結ばれる郊外と中心部のそれぞれにおける都市計画面に配慮し、ニュータウン地区や郊
外で主要な施設の集まるところと中心部を結ぶように路線が配置される。
こうした計画や政策は、地元自治体の AOTU が VT や PDU といったツールを活用して
進めていく。特に VT があることの利点は非常に大きい。何しろ、VT は赤字企業や営利
目的でない組織も支払わなければならない。日本の状況でたとえるなら、通勤手当がそれ
ぞれの職員に支給されず、代わりにその分が自治体の税収となるようなイメージである。
各都市でトラムのような比較的投資額の大きい整備が可能になったのは VT に拠るとこ
ろが大きい。地元自治体が自ら財源を確保できるので、国に頼らず自力で魅力ある交通手
段を整備できるのである。
LOTI によって定められた方針のもと、AOTU が VT や PDU などの制度を活用して交
通政策を立案・実施するという枠組みが確立しているので、フランスの交通政策は特定の
都市だけで大きな成果が出るのではなく、多くの主要都市で同様の施策が推進されてきて
いるのである。プロジェクトの進捗スピードは日本と比べるとはるかに速く、例えばトラ
ム新規路線の整備では、通例計画から開業まで 2 年か 3 年ほどしかかからない。
フランスの各都市で、トラムの整備やパリのヴェリブに代表される貸自転車のような交
通政策が促進されているのは、交通権を保障し環境に配慮した交通システムを実現させる
目的で交通政策の枠組みが確立しているためなのである。
2.フランスにおける交通政策の具体的事例
本節では、前節で紹介した制度によってどのようなまちが現出しているか、具体的な事
例によって紹介したい。
(1) トラムの有無でまちはどう変わるか
フランスでは、トラムが走り出すと都市中心部の姿が大きく変貌し、多くの人が歩き活
気溢れる街が実現する。
トラムは、郊外では専用軌道上を高速で走り、中心部に入ると道路上を低速で走行する。
つまり、郊外と中心部とをダイレクトかつ短時間で移動できる手段なのである。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2468
ヨーロッパのまちづくり政策
郊外では一般の鉄道と同様に走行する。そして中心部では、トラムの走る道路には公共
交通と歩行者・自転車以外は入ることができないようにするのが一般的である。こうする
ことで自動車交通による渋滞に巻き込まれずに走ることができるようになる。したがって
フランスのトラムに乗って、信号待ちでいらいらすることは基本的にない。
このような道路は、日本ではトランジットモールと呼ばれているが、安全確保上の問題
で警察が難色を示すことが多く、効果的な導入事例はほとんどない。そのため、このシス
テムの魅力を感じるには欧米諸国に行って体験するしかない状況である。
フランス中部のオルレアンの中心部では、トラム第 1 路線の開業に伴って駅前商店街が
トランジットモールになった。トラムが走らないときには多くの歩行者がいて活況を呈し
ている。そして多くの乗客を乗せたトラムが走るときだけ、道路の真ん中が鉄道路線に変
わるのである。
こうした空間は街に賑わいをもたらす。一方、同じオルレアンの大聖堂前の道路は、駅
写真1 オルレアン駅前のトランジットモール(トラム車両なし)
写真 2 オルレアン駅前のトランジットモール(トラム車両到着)
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2468
ヨーロッパのまちづくり政策
郊外では一般の鉄道と同様に走行する。そして中心部では、トラムの走る道路には公共
交通と歩行者・自転車以外は入ることができないようにするのが一般的である。こうする
ことで自動車交通による渋滞に巻き込まれずに走ることができるようになる。したがって
フランスのトラムに乗って、信号待ちでいらいらすることは基本的にない。
このような道路は、日本ではトランジットモールと呼ばれているが、安全確保上の問題
で警察が難色を示すことが多く、効果的な導入事例はほとんどない。そのため、このシス
テムの魅力を感じるには欧米諸国に行って体験するしかない状況である。
フランス中部のオルレアンの中心部では、トラム第 1 路線の開業に伴って駅前商店街が
トランジットモールになった。トラムが走らないときには多くの歩行者がいて活況を呈し
ている。そして多くの乗客を乗せたトラムが走るときだけ、道路の真ん中が鉄道路線に変
わるのである。
こうした空間は街に賑わいをもたらす。一方、同じオルレアンの大聖堂前の道路は、駅
写真1 オルレアン駅前のトランジットモール(トラム車両なし)
写真 2 オルレアン駅前のトランジットモール(トラム車両到着)
都市とガバナンス Vol.24 69
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
前と同様に重要な道路であるにもかかわらずトラム第 1 路線が走らなかったためにしばら
くの間自動車が自由に走行できる状態のままになっていた。しかし、トラム第 2 路線がこ
の道路を通ることになり、ここでは交通処理の関係で車道は残したものの、道路の様子は
大きく様変わりした。これこそがトラム導入の最大の成果といえないだろうか。
(2) トラムをどう活用するか
多くのフランスの都市では中心部への自動車の進入を制限し、駐車場の台数や価格を自
治体側でコントロールしている。トラム沿線以外から中心部に移動するには、トラムの駅
に併設されたパーク&ライド用の駐車場まで自動車で移動し、そこからトラムに乗ればよ
い。トラム利用とセットの駐車料金は、非常に安く設定されている。
もちろんバスとトラムの連携も良好で、プラットホーム上でトラムとバスが乗り換えら
れる施設もフランス中で目にする。トラムは郊外では専用軌道を走っているものの、原則
写真 3 オルレアン大聖堂前(2003 年)
写真 4 オルレアン大聖堂前(2015 年)
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2470
ヨーロッパのまちづくり政策
として地上に路線が敷かれているため、このようにホーム脇に車道を配置して利便性を高
めることは比較的容易にできる。
ストラスブールでは中心部に地下駐車場を多数配置しているが、その地下駐車場への入
口より中心に行く道路には自動車で進入することはできない。また、地下駐車場の料金水
準は郊外のパーク&ライド用の駐車場より高く設定されている。パーク&ライド駐車場を
併設したトラム停留所は、待ち合い施設が充実しバスとの乗り換えもスムースである。
こうしたハード面の工夫だけでなく、ソフト面での配慮も目につく。運賃は廉価で一日
乗車券も充実しており、マップや時刻表も十分すぎるくらいである。他方で、改札がない
ことの代わりとして車内検札の際の罰則は厳しく、きっぷを持っていないとその場で高額
の罰金を支払わねばならない。こうした信用乗車制度は、日本でも導入をめざした自治体
があるが公共交通に対する考え方が大きく異なるため、なかなか実現しない。
写真 5 ストラスブール中心部の地下駐車場 その奥は自動車進入禁止
写真 6 ストラスブール ロトンド駅隣接のパーク&ライド駐車場
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2470
ヨーロッパのまちづくり政策
として地上に路線が敷かれているため、このようにホーム脇に車道を配置して利便性を高
めることは比較的容易にできる。
ストラスブールでは中心部に地下駐車場を多数配置しているが、その地下駐車場への入
口より中心に行く道路には自動車で進入することはできない。また、地下駐車場の料金水
準は郊外のパーク&ライド用の駐車場より高く設定されている。パーク&ライド駐車場を
併設したトラム停留所は、待ち合い施設が充実しバスとの乗り換えもスムースである。
こうしたハード面の工夫だけでなく、ソフト面での配慮も目につく。運賃は廉価で一日
乗車券も充実しており、マップや時刻表も十分すぎるくらいである。他方で、改札がない
ことの代わりとして車内検札の際の罰則は厳しく、きっぷを持っていないとその場で高額
の罰金を支払わねばならない。こうした信用乗車制度は、日本でも導入をめざした自治体
があるが公共交通に対する考え方が大きく異なるため、なかなか実現しない。
写真 5 ストラスブール中心部の地下駐車場 その奥は自動車進入禁止
写真 6 ストラスブール ロトンド駅隣接のパーク&ライド駐車場
都市とガバナンス Vol.24 71
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
以上のような施策を複合的に組み合わせて、初めてフランスのトラムはデザイン以外の
面でも魅力的な交通手段となったのである。こうした工夫がなければ、トラムは自動車と
対抗できる交通手段にはなり得なかった。モータリゼーションが進んだフランスにおいて、
自動車利用者の目を公共交通に向けるためにはこうした施策が必要だったのであろう。
さて、こうした努力でトラムの魅力を高めても、目的地となる中心部の魅力が伴わなけ
ればトラム整備は無意味な投資となってしまう。そのため中心部において再開発を行い、
重要な都市施設を集積させる努力が各都市で重ねられている。つまり、中心部活性化にお
いて最も重要なのは街の商店街を魅力的にできるかどうかである。
フランスでも日本と同様に大規模商業施設の存在感は大きい。しかし、一方で零細な小
売店舗の売り上げも落ちていない。これには、中心部における商業施設を政策的に保護し
ていることによる影響がある。大規模店舗の立地は現在では厳しく制限されているが、そ
れは住民の生活上不可欠な中小の商業者への配慮によるものである。
特に旧来の商店街はそれぞれの街の中心部にあることが多い。環境負荷や財政支出の少
ない街をつくるためには、中心部の居住者を積極的に増やしていくことが求められる。こ
うしたコンパクトシティ政策を展開する際に、中心部にもかかわらず徒歩圏内で買い物が
できないようでは居住者の増加は期待できない。
こういった政策運営によって、住民は中心部の商店街と大規模な郊外商業施設のどちら
で買い物をするか選択できる状態となっている。ニーズによってどちらに行くのが望まし
いかは異なるため、こうした状況は住民にとってプラスに働くだろう。またこの状況下で
は、郊外と中心部の商業者間で競争が起きる。結果として、中心部の努力の足りない商業
施設は淘汰されることになる。このことが中心部の商店一店一店の魅力を高め、全体とし
て魅力ある中心部を作る一因になっているともいえる。
ストラスブールの中心部にはシャッターの降りた商店はほとんど見当たらず、道路は多
くの老若男女で溢れてい
る。日本ではこうした光
景はショッピングセン
ターで主に見られるが、
地方都市の中心市街地で
はほとんど見ることがで
きない。持続可能性の面
でどちらが望ましいか、
再考してもよいのではな
いだろうか。
写真 7 ストラスブール中心部は多くの人で賑わう
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2472
ヨーロッパのまちづくり政策
(3)タブーなき合意形成の取り組み
合意形成についても考えてみたい。日本でもフランスと同様に計画制度は存在しそれを
広く情報提供することも定められているが、自治体の方針はなかなか住民に浸透しない。
それは、形式に囚われているところがあるということと、本当に必要な情報を効果的に伝
える方策について十分に検討していないことによるのではないか。
例えば公開事前調査は、地方議会の議員が万能でないことを前提に、プロジェクトの概
要を専門家が住民意見も含めて分かりやすく取りまとめた文書を作成することを目的とし
た制度である。日本の地方議員も、全員がすべての政策に精通しているわけではないとい
うことは言うまでもないが、それをフォローするような政策的仕組みは存在するだろうか。
議員は万能であるという前提のもとで諸制度が組み立てられていないだろうか。
タブーなく、目的を遂行するための手段を検討することが何よりも重要である。フラン
スの事前協議では、もちろんスライドを使って責任者がプレゼンを行い、その内容につい
て議論するようなことも行うが、住民の理解を深めるためであれば多様な手段を駆使して
いる点が特徴的である。
フランス西部のアンジェでは 2011 年にトラムが開業した。この導入にかかる議論にお
いて、アンジェでは 1 分の 1 の模型(モックアップ)を中心部の案内施設に持ち込み、多
くの住民にトラムがどのようなものか知ってもらうために活用した。
情報提供や意見収集のためには手間と投資を惜しまないフランス地方自治体の姿勢は、
日本の民間企業のそれにつながるものがあるようにも思える。
写真 8 アンジェのトラム
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2472
ヨーロッパのまちづくり政策
(3)タブーなき合意形成の取り組み
合意形成についても考えてみたい。日本でもフランスと同様に計画制度は存在しそれを
広く情報提供することも定められているが、自治体の方針はなかなか住民に浸透しない。
それは、形式に囚われているところがあるということと、本当に必要な情報を効果的に伝
える方策について十分に検討していないことによるのではないか。
例えば公開事前調査は、地方議会の議員が万能でないことを前提に、プロジェクトの概
要を専門家が住民意見も含めて分かりやすく取りまとめた文書を作成することを目的とし
た制度である。日本の地方議員も、全員がすべての政策に精通しているわけではないとい
うことは言うまでもないが、それをフォローするような政策的仕組みは存在するだろうか。
議員は万能であるという前提のもとで諸制度が組み立てられていないだろうか。
タブーなく、目的を遂行するための手段を検討することが何よりも重要である。フラン
スの事前協議では、もちろんスライドを使って責任者がプレゼンを行い、その内容につい
て議論するようなことも行うが、住民の理解を深めるためであれば多様な手段を駆使して
いる点が特徴的である。
フランス西部のアンジェでは 2011 年にトラムが開業した。この導入にかかる議論にお
いて、アンジェでは 1 分の 1 の模型(モックアップ)を中心部の案内施設に持ち込み、多
くの住民にトラムがどのようなものか知ってもらうために活用した。
情報提供や意見収集のためには手間と投資を惜しまないフランス地方自治体の姿勢は、
日本の民間企業のそれにつながるものがあるようにも思える。
写真 8 アンジェのトラム
都市とガバナンス Vol.24 73
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
3.土地利用政策と交通政策の連携:ナントの交通まちづくりから
フランスのまちづくりの特徴の一つは、土地利用政策と交通政策が上手に連携されてい
る点にある。本来、土地利用と交通は相互関係にあるため、交通のみを計画したとしても、
土地利用計画と整合性がとれていなければ、その効果を十分に発揮することはできない。
例えば最新の公共交通システムを入れても都心部に魅力がなければ誰も利用しないし、道
路整備によってクルマ利用環境を向上させれば、相対的に広大な土地を有する郊外部が発
達する。つまり都市と交通は同時にデザインすることが肝要である。本節では、フランス
で人口規模第 6 位のナントを事例に、交通まちづくりについて紹介する。
(1) ナント・メトロポール(Nantes Métropole)の概要
人口約 59 万人(2010 年)のナント・メトロポールは、24 のコミューンにより構成され、
各コミューンがナント・メトロポールに、都市内交通、公共空間の整備、道路空間の整備、
都市整備に関する権限を移譲することで一体的な交通計画の立案を可能としている。また
近年の人口変動を見ると、ナント・メトロポールの外縁部で人口が増加(スプロール化)
している 18 一方で、通勤等の移動はメトロポールへ集中している。そのため、メトロポー
ルの域外からの通勤者も念頭に置いた都市交通を考えることは極めて重要であり 19、交通
計画の立案には人口 88 万 5,000 人のナント都市圏(Aire urbaine / AU)を対象としている。
図にナント・メトロポールとナント都市圏の位置関係を示す。
18 1996 〜 2006年の人口増加数は、ナント・メトロポールで24,530人、メトロポール圏外のAUで27,345人である。19 居住する市町村域内へ通勤する住民の割合は、1982年では57%だったが、2006年には37%に減少している。なお、メトロポールにおける1日当たりの(通勤も含めた)移動数は200万、所要時間は1移動当たり18分、1日当たり65分、移動距離は8.1km、トリップ回数は約3.5回である。
写真 9 アンジェで合意形成に用いられた室内展示のトラム模型
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2474
ヨーロッパのまちづくり政策
ナント・メトロポールが管轄する交通手段は、現時点でトラムが 3 路線・45km、BRT
(Busway)が 1 路線・7km、一般の路線バスが 55 路線、クロノバス(Chronobus)20 が 7
路線、鉄道(TER)が 5 路線 21 である。なお、障害者用のデマンドバス(ProxiTan)や
水上バスも運行している。加えて、自転車政策もナント・メトロポールの誇る政策であり、
自転車専用道路が 470km、駐輪アーチが 6,500 本、屋根付き駐輪場が 2,000 台分、ワンウェ
イ式の乗り捨て自転車(Bicloo)が 880 台・103 拠点設置されている。
(2) ナントがめざす都市構造
ナントが目指している都市の姿は、人口減少社会への対応として我が国で着目されてい
る「コンパクトシティ」である。ナントでは 2 つのコンパクトシティのタイプが提示され
ている。その一つが、バス路線などの枢軸となる都市交通を設け、その路線を中心に住居
を誘導する「コリドー型」であり、もう一つが既存の中心地や鉄道駅を極として極同士を
連結する「ポーラリゼーション型」(多極型)である。コリドー型を採用する地域とポー
ラリゼーション型を採用する地域との違いは、駅間距離である。鉄道やトラムのように駅
間距離が離れている場合はポーラリゼーション型になり、バスのように駅間距離が非常に
近い場合はコリドー型になる。なお現状では、95% の住民が都市交通拠点の 500m 以内に
居住しているので、多くの地域がコリドー型に近いといえる。
都市計画として着目すべきは、土地利用全体を俯瞰して、将来、どの拠点を中心に都市
を発展させるかを常に考えている点にある。一般的に都市交通は需要がある地域に通すこ
とを前提とするが、ナントでは既に需要がある地域に都市交通を通すのではなく、計画的
に住居を誘導するために都市交通を整備するという選択をしている。つまり、都市交通の
図 1 ナント都市圏の位置
20 定時性・速達性等、路線バスのサービス内容を向上させた高速運行バス。21 TERについては州政府との共同運営で、メトロポール域内はメトロポール、域外は州政府が運営している。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2474
ヨーロッパのまちづくり政策
ナント・メトロポールが管轄する交通手段は、現時点でトラムが 3 路線・45km、BRT
(Busway)が 1 路線・7km、一般の路線バスが 55 路線、クロノバス(Chronobus)20 が 7
路線、鉄道(TER)が 5 路線 21 である。なお、障害者用のデマンドバス(ProxiTan)や
水上バスも運行している。加えて、自転車政策もナント・メトロポールの誇る政策であり、
自転車専用道路が 470km、駐輪アーチが 6,500 本、屋根付き駐輪場が 2,000 台分、ワンウェ
イ式の乗り捨て自転車(Bicloo)が 880 台・103 拠点設置されている。
(2) ナントがめざす都市構造
ナントが目指している都市の姿は、人口減少社会への対応として我が国で着目されてい
る「コンパクトシティ」である。ナントでは 2 つのコンパクトシティのタイプが提示され
ている。その一つが、バス路線などの枢軸となる都市交通を設け、その路線を中心に住居
を誘導する「コリドー型」であり、もう一つが既存の中心地や鉄道駅を極として極同士を
連結する「ポーラリゼーション型」(多極型)である。コリドー型を採用する地域とポー
ラリゼーション型を採用する地域との違いは、駅間距離である。鉄道やトラムのように駅
間距離が離れている場合はポーラリゼーション型になり、バスのように駅間距離が非常に
近い場合はコリドー型になる。なお現状では、95% の住民が都市交通拠点の 500m 以内に
居住しているので、多くの地域がコリドー型に近いといえる。
都市計画として着目すべきは、土地利用全体を俯瞰して、将来、どの拠点を中心に都市
を発展させるかを常に考えている点にある。一般的に都市交通は需要がある地域に通すこ
とを前提とするが、ナントでは既に需要がある地域に都市交通を通すのではなく、計画的
に住居を誘導するために都市交通を整備するという選択をしている。つまり、都市交通の
図 1 ナント都市圏の位置
20 定時性・速達性等、路線バスのサービス内容を向上させた高速運行バス。21 TERについては州政府との共同運営で、メトロポール域内はメトロポール、域外は州政府が運営している。
都市とガバナンス Vol.24 75
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
整備が土地利用を誘発させることを想定しており、目標の都市像へ近づけるために交通計
画を立案していると捉えることもできる。
例えば、トラムと BRT のどちらを採用するかについてもまちづくりの視点が加わって
いることは興味深い。ナントの交通戦略・研究局ディレクターの Damien Duhamel 氏によ
ると、両者の比較から、①運行実態からみてトラムの方が優れた運行実績を出しており、
② BRT よりもトラムのほうが都市の再構築に対する貢献度(輸送力ではない付加価値)
が高いことからトラムを採用したとしている。また、トラムの方が、不動産価格の上昇に
も効果があったとし、現在の BRT の利用者数は 3 万 5,000 にのぼり、1 日のトリップ数の
予測値(2 万〜 2 万 5,000)を上回っており、既に飽和状態であると指摘している。
写真 10 ナントのトラムと結節点
写真 11 ナントの BRT と自転車シェアシステム(Bicloo)
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2476
ヨーロッパのまちづくり政策
(3) ナントのPDU
ナントの 2010 〜 2015 年の PDU は 2030 年を目標年次として、サンナゼールからナント
までを対象地域とする広域整合スキーム SCOT(2007 年 3 月 26 日)や、大気保護計画(環
境法典第 R222-13 条)などに基づいて策定されている。つまり PDU は、単なる交通政策
にとどまらず、環境や都市計画等、様々な目的のもとに定める基準を満たすものとなって
いる。この PDU における理念(課題と目標)は、①環境保全に役立つこと、②都市計画
と移動との連携(都心再整備に役立つこと)、③誰でも利用しやすいモビリティの保障、
④魅力ある大都市圏の形成、⑤市民の行動様式を考慮に入れること、⑥これらを少ない予
算で実現することにより、「移動の利便性と持続可能性を併せ持つ都市の実現」を追求す
ること、である。
この PDU のもと、2030 年に自動車以外の交通方法の占める割合を 67% とすることを目
標としている。現在は、自動車移動が 42.5% であり、この数値は減少傾向にある。徒歩は
26.8% で高い水準にあるが、公共交通は 15.8% で伸びとどまっている。なお、自転車利用
の促進は特に力を入れているが、現時点では 4.5% にすぎない。
今後、ナント・メトロポールの人口は、2015 年から 2030 年までの間に約 10 万人の増加
が見込まれており、増加する住民に対してガイドマップ等を作成して住居の誘導に努めて
いる。現在、ナント・メトロポールにおいては、人口 60 万人のうち約 95% の住民がバス
かトラムの駅から半径 500m 以内の地域に居住している。一方、ナント・メトロポール域
外においては、人口の 50% しか都市交通の駅から半径 500m の地域に居住しておらず、自
動車に頼る生活行動となっているため、メトロポール域外に居住する人々の都市交通拠点
から 500m 以内への集約が課題となっている。
パーソントリップ調査によると、都市空間整備に力を入れた地域に居住する住民の平均
移動距離は約 5km であり、徒歩での移動の割合が大きい。一方、都市空間整備が不十分
な地域(スプロール化した地域)に居住する住民の場合は約 9km であり、徒歩の割合は
少ない。居住地の集約を
図るためには、より良い
トラムやバスを交通手段
として提供するだけでは
なく、歩きやすく自転車
が利用しやすい都市空間
を再整備することが重要
であるといえる。
図 2 PDU(2010-2015)における交通と土地利用の連携
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2476
ヨーロッパのまちづくり政策
(3) ナントのPDU
ナントの 2010 〜 2015 年の PDU は 2030 年を目標年次として、サンナゼールからナント
までを対象地域とする広域整合スキーム SCOT(2007 年 3 月 26 日)や、大気保護計画(環
境法典第 R222-13 条)などに基づいて策定されている。つまり PDU は、単なる交通政策
にとどまらず、環境や都市計画等、様々な目的のもとに定める基準を満たすものとなって
いる。この PDU における理念(課題と目標)は、①環境保全に役立つこと、②都市計画
と移動との連携(都心再整備に役立つこと)、③誰でも利用しやすいモビリティの保障、
④魅力ある大都市圏の形成、⑤市民の行動様式を考慮に入れること、⑥これらを少ない予
算で実現することにより、「移動の利便性と持続可能性を併せ持つ都市の実現」を追求す
ること、である。
この PDU のもと、2030 年に自動車以外の交通方法の占める割合を 67% とすることを目
標としている。現在は、自動車移動が 42.5% であり、この数値は減少傾向にある。徒歩は
26.8% で高い水準にあるが、公共交通は 15.8% で伸びとどまっている。なお、自転車利用
の促進は特に力を入れているが、現時点では 4.5% にすぎない。
今後、ナント・メトロポールの人口は、2015 年から 2030 年までの間に約 10 万人の増加
が見込まれており、増加する住民に対してガイドマップ等を作成して住居の誘導に努めて
いる。現在、ナント・メトロポールにおいては、人口 60 万人のうち約 95% の住民がバス
かトラムの駅から半径 500m 以内の地域に居住している。一方、ナント・メトロポール域
外においては、人口の 50% しか都市交通の駅から半径 500m の地域に居住しておらず、自
動車に頼る生活行動となっているため、メトロポール域外に居住する人々の都市交通拠点
から 500m 以内への集約が課題となっている。
パーソントリップ調査によると、都市空間整備に力を入れた地域に居住する住民の平均
移動距離は約 5km であり、徒歩での移動の割合が大きい。一方、都市空間整備が不十分
な地域(スプロール化した地域)に居住する住民の場合は約 9km であり、徒歩の割合は
少ない。居住地の集約を
図るためには、より良い
トラムやバスを交通手段
として提供するだけでは
なく、歩きやすく自転車
が利用しやすい都市空間
を再整備することが重要
であるといえる。
図 2 PDU(2010-2015)における交通と土地利用の連携
都市とガバナンス Vol.24 77
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
(4) 整備・開発手法等について
ナント・メトロポールの諸計画では、都市空間内での移動速度を低減することを原則と
し、歩行者専用空間や自転車専用道路の充実に努めている。その手法は、まず道路の優先
順位をつけることである(道路の段階化・階層化)。すなわち道路を幹線系道路と支線系
道路に分け、歩行者専用空間、自転車の優先空間を設定し、特定の道路は速度を制限する
という手法を用いる。計画に関する予算については当然メトロポール議会の承認が必要で
あるが、これらのアイディアや哲学が計画に適合していないと(単に道路を整備し建物を
つくるだけの計画では)審議対象とならない。
具体的な都市交通政策としては、まず駐車場の抑制政策が挙げられる。例えば、コミュー
ンから都市交通網の整備を求められた場合、マンション開発の際に駐車台数の割当を少な
くして地域の自動車保有台数を減らす「エコカルチエ」の設定等を、交通網整備の条件と
して契約を結ぶことがある。また、道路の混雑緩和に速度規制が有効であるとの認識が行
政にあることも特徴的である。実際に道路の制限速度を時速 30km とする地域(ゾーン
30)を増やした結果、渋滞が減少したとの報告もある 22。交通の流動性を高めるために、
社会実験の結果を踏まえ、今後環状道路の制限速度を時速 90km から 70km に制限する予
定である。ただし、都心部のゾーン 30 化はさほど難しくはないが、都心以外の地域につ
いては自動車中心の交通行動がとられているため難しく、今後の課題とされている。
(5) 住民・企業への説明、広報活動
交通計画を実施するうえで当局と住民や企業等とで考え方を共有する必要があるが、そ
のために広報活動は極めて重要である。住民に対しては、学校教育の一環として広報要員
を学校に派遣したり、様々なイベントの際にモビリティマネジメント(MM)の説明をし
たりしている。また、コミューンの首長(maire)に対しても十分な説明を行っている。
例えば、交通空白区域で開発を行おうとする首長に対しては、「開発は可能だが都市交通
を開通させる予定はないので、当該区域では都市交通以外の交通(自動車交通など)になる」
と説明している。加えて、区域内の企業等での MM の実施や、駐輪所設置等の交渉の可
能性を指摘している。
また、企業に対する MM として、企業に出向いて公共交通利用促進に関する啓発活動
等を実施している。対象事業所は 370 か所、対象従業員数は 10 万 5,000 人に上る。企業向
けの説明・広報活動について、メトロポール内の 3 分の 1 の企業とメトロポールの交通局
との間で MM 契約を締結し、各企業の労使委員会に出張して説明活動を行い、カープー
リング、カーシェアリング等を促進している。また、雇用者による定期代の負担制度等、
22 ロワール川の橋を渡る自動車のトリップ数が15%減少していることから、都心への流入交通量が減少したと考えられる。なお、自動車以外も含めた総トリップ数は(人口が増加しているため)増加している。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2478
ヨーロッパのまちづくり政策
法制度に関する説明も行っている。
(6) 道路・駐車政策
PDU の基本となっているのが過度の自動車依存からの脱却である。そのため駐車政策
は、自動車交通の抑制や公共交通の利用促進に大きな役割を果たす。都心での駐車政策の
哲学・目標として、①都心居住者の駐車スペースの確保、②都心非居住者の自動車でのア
クセス・駐車の制限、③経済活動の促進のため業務用車輛の進入を考慮、の 3 つが挙げら
れる。都心に進入可能な車輛は、バス、緊急車輛、許可を得ている公共用自動車、タクシー、
荷捌き等のための業務用車輛、都心居住者の車輛に限定され、これら以外の自動車につい
ては、環状道路を「バリケード」の役割として設定して迂回させ、郊外から都心部への通
過交通を抑制している。自動車の都心への進入抑制は、自動車で占拠されていた都心の大
通りが歩行者を中心とした市民への開放につながるが、こうした各移動手段が占める空間
の見直し・再整備により、新しい都市空間、生活空間の市民への供給を進めている 23。また、
都心における道路空間再整備の目標は、道路の幅員を問わずすべて最高 2 車線までとする
ことである。現状では、都心で 1 本のみ 4 車線道路が残存しているが、それ以外の自動車
道路はすべて 1 車線ないし 2 車線化が実現している。
一方で郊外における交通施策の目標は、自動車から公共交通への乗り継ぎの促進である。
上述の環状道路とトラム駅の結節点等に、パーク&ライド駐車場を 8,000 台分設置してい
る。このような、乗り継ぎシステムの整備により、従来は自動車のみで移動していた場合も、
複数の異なる移動手段を組み合わせて利用する交通行動をとるようになっている 24。
おわりに
以上、フランスの交通政策の制度的背景と具体的事例について、都市政策や若干の商業
政策との関わりも含めて概観した。フランスの政策展開を見てくると、以下のようなこと
が言えそうである。
公共交通を中心としたまちづくりを行うためには、その政策方針を明快にし、制度的な
フォローを行った上で地元自治体が施策を推進していくことが有効である。またその施策
は、特に道路空間を有効に活用することと中心部における駐車政策を積極的に行うこと、
さらに必要な施設整備はスピーディに実施することで、いくつかの施策を複合的に行うこ
とが効果的とみられる。そして何より、公共交通だけが単体で魅力ある交通手段となるだ
けではほとんど意味がない。中心部における商業施設の活性化などを通じて、公共交通の
23 例えば、Cours des 50-Otages(50人の捕虜通り)は、5車線だった1970年には、1日当たりの通過自動車台数が約5万台だったが、2012年には約5,000台にまで減少している。なお、この通りでは、トラム、バス、自転車それぞれの専用道路が整備されている。24 特に外環道路内側より長距離の移動の場合。
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.

都市とガバナンス Vol.2478
ヨーロッパのまちづくり政策
法制度に関する説明も行っている。
(6) 道路・駐車政策
PDU の基本となっているのが過度の自動車依存からの脱却である。そのため駐車政策
は、自動車交通の抑制や公共交通の利用促進に大きな役割を果たす。都心での駐車政策の
哲学・目標として、①都心居住者の駐車スペースの確保、②都心非居住者の自動車でのア
クセス・駐車の制限、③経済活動の促進のため業務用車輛の進入を考慮、の 3 つが挙げら
れる。都心に進入可能な車輛は、バス、緊急車輛、許可を得ている公共用自動車、タクシー、
荷捌き等のための業務用車輛、都心居住者の車輛に限定され、これら以外の自動車につい
ては、環状道路を「バリケード」の役割として設定して迂回させ、郊外から都心部への通
過交通を抑制している。自動車の都心への進入抑制は、自動車で占拠されていた都心の大
通りが歩行者を中心とした市民への開放につながるが、こうした各移動手段が占める空間
の見直し・再整備により、新しい都市空間、生活空間の市民への供給を進めている 23。また、
都心における道路空間再整備の目標は、道路の幅員を問わずすべて最高 2 車線までとする
ことである。現状では、都心で 1 本のみ 4 車線道路が残存しているが、それ以外の自動車
道路はすべて 1 車線ないし 2 車線化が実現している。
一方で郊外における交通施策の目標は、自動車から公共交通への乗り継ぎの促進である。
上述の環状道路とトラム駅の結節点等に、パーク&ライド駐車場を 8,000 台分設置してい
る。このような、乗り継ぎシステムの整備により、従来は自動車のみで移動していた場合も、
複数の異なる移動手段を組み合わせて利用する交通行動をとるようになっている 24。
おわりに
以上、フランスの交通政策の制度的背景と具体的事例について、都市政策や若干の商業
政策との関わりも含めて概観した。フランスの政策展開を見てくると、以下のようなこと
が言えそうである。
公共交通を中心としたまちづくりを行うためには、その政策方針を明快にし、制度的な
フォローを行った上で地元自治体が施策を推進していくことが有効である。またその施策
は、特に道路空間を有効に活用することと中心部における駐車政策を積極的に行うこと、
さらに必要な施設整備はスピーディに実施することで、いくつかの施策を複合的に行うこ
とが効果的とみられる。そして何より、公共交通だけが単体で魅力ある交通手段となるだ
けではほとんど意味がない。中心部における商業施設の活性化などを通じて、公共交通の
23 例えば、Cours des 50-Otages(50人の捕虜通り)は、5車線だった1970年には、1日当たりの通過自動車台数が約5万台だったが、2012年には約5,000台にまで減少している。なお、この通りでは、トラム、バス、自転車それぞれの専用道路が整備されている。24 特に外環道路内側より長距離の移動の場合。
都市とガバナンス Vol.24 79
フランスの公共交通を活かしたまちづくり
目的地となる中心部の魅力を高めることが最も重要である。
こうした考え方をもとに日本の現状について考察すると、ほぼすべての面で大きな障壁
があることに気づかされる。交通政策の側では、地方自治体が新しい施策を実施するため
の独自財源がない。また、合意形成手法が十分でないこともありトラムやトランジットモー
ルの導入に向けた議論がなかなか成熟しない。加えて、自治体側では駐車に関わるコント
ロールが難しい。
そのためますます自動車の利便性が際立ち、地方都市ではほとんどの買い物を郊外商業
施設で行うようになりつつある。フランスの政策だけが正しいわけではないが、日本の現
状が相当にいびつであることは間違いない。今後の日本の政策推進に際しては、交通政策
をまちづくりの中で位置づけ、フランスなどの事例を参考にしながら日本の実情に合った
やり方を模索していく必要がありそうである。
本稿の一部は、公益財団法人日本都市センターの 2014 年度調査研究「都市自治体にお
ける地域公共交通のあり方に関する調査研究」において、2015 年 3 月 7 日から 14 日にか
けて実施した海外事例調査で得た知見に基づいています。調査資料の収集及び取りまとめ
に尽力された日本都市センターの石田雄人元研究員、加藤祐介研究員に記して謝意を示し
ます。
参考文献・URL
1. 望月真一『路面電車が街をつくる 21 世紀フランスの都市づくり』鹿島出版会、2001
年
2. ヴァンソン藤井由実『ストラスブールのまちづくり トラムとにぎわいの地方都市』学
芸出版社、2011 年
3. 氏岡庸士「フランスの都市交通と費用負担−事業所税の実態と役割」運輸と経済第 57
巻第 6 号、1997 年、66-78 頁
4. 柴山多佳児・家田仁「ローカル公共交通サービスのグローバル・オペレータ」運輸と経
済第 66 巻第 10 号、58-66 頁
5. 板谷和也・原田昇「フランスの都市圏交通に関する計画コントロールシステム 交通基
本法としての LOTI の役割」都市計画論文集第 39 巻第 3 号、2004 年、517-522 頁
6. 日本都市センター『人口減少時代における地域公共交通のあり方−都市自治体の未来を
見据えて−』日本都市センター、2015 年
Copyright 2015 The Authors. Copyright 2015 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.