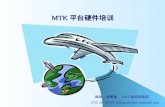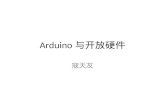安全で安心してくらせるまち - Iruma...1,243件 1,300件 1,400件...
Transcript of 安全で安心してくらせるまち - Iruma...1,243件 1,300件 1,400件...

152
第2編
第4章
〈評価項目〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
観光客入れ込み客数(年単位) 観光の振興を図るために、来訪客を増やします。
1,075,000人1,100,000
人1,100,000
人
第1節 交通安全
第2節 消防
第3節 防災
第4節 防犯
第5節 国民保護
第6節 基地
第7節 消費生活
安全で安心してくらせるまち交通安全をはじめ消防・防災・防犯体制などを充実し、安全で安心してくらせるま
ちを目指します。
第5章
第1項 交通環境の整備第2項 交通安全対策の充実
第1項 広域化の実現第2項 消防力の強化・充実
第1項 防災体制の充実第2項 自主防災組織の育成・充実
第1項 防犯体制の充実
第1項 国民保護体制の整備
第1項 基地周辺環境整備の推進
第1項 消費者の権利の尊重と自立の支援

154 155
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章交通安全第1節
第1項 交通環境の整備
■目標・自治会等の地域や狭山警察署等の関係機関と連携を図りながら、交通事故の危険から市民を守り、安心して日
常生活が送れる交通環境を目指します。
・放置自転車対策を推進し、環境美化の推進や歩行者の安全な通行の確保を図ります。
■現状・交通事故防止のため、道路反射鏡、道路照明灯、道路標示などの交通安全施設の整備を行っています。
・駅周辺における歩道の安全確保のため、市内の各駅周辺に13ヶ所の自転車駐車場を設置しています。
・自転車が安全に通行できる環境整備は進んでいません。
・自転車放置に対する指導や撤去等、放置自転車の解消に向けての取組を実施しています。
■課題・交通安全施設の整備充実に向けた市民からの要望は多く、対応が求められています。
・自転車道の整備については、歩道や道路の幅員、安全対策などが課題となります。
・放置自転車は、都市景観上の美観を損ねるとともに、歩道の幅員を減少させ、歩行者の通行を妨げるなど交通
安全上の問題があることから対策が必要となっています。
■5年間の取り組み・交通安全施設の整備を進め、交通の安全確保を目指します。
・自転車が安全に通行できる環境の整備について検討します。
・各駅周辺における自転車駐車場の確保・充実を図ります。
・自転車放置に対する指導や撤去等に努めるとともに、マナー向上のための啓発にも努め、放置自転車解消を目
指します。
〈事業体系〉
交通安全施設の充実
自転車通行環境の整備方策の検討
放置自転車の解消
交通安全施設の整備
自転車通行環境の整備方策の検討
放置自転車の解消
交通環境の整備
◆施策1 交通安全施設の充実 事業① 交通安全施設の整備
地域や関係機関と連携し、道路反射鏡や道路照明灯等の交通安全施設の整備を進めます。
◆施策2 自転車通行環境の整備方策の検討 事業① 自転車通行環境の整備方策の検討
地域や関係機関と連携し、自転車が安全に通行できる環境の整備方策について検討します。
◆施策3 放置自転車の解消 事業① 放置自転車の解消
放置自転車対策として、駅周辺に自転車駐車場施設の確保・充実を目指します。また、自転車放置に対する
指導や撤去に努めるとともに、マナー向上のための啓発活動などを推進します。
〈評価項目〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
道路反射鏡設置数市民の交通の安全確保を図るために、設置数を増やします。
1,901件 2,150件 2,300件
道路照明灯設置数市民の交通の安全確保を図るために、設置数を増やします。
1,243件 1,300件 1,400件
放置自転車撤去台数駅周辺の景観を美化し、歩道・通行帯の安全性を向上させるために、撤去台数を減らします。
244台 200台 150台
放置自転車撤去及び返却状況の推移
0
100
200
300
400
500
15
20
25
30
35
40
返却率
28.4
23.6
19.4
36.5
31.1
451
128
296
70
366
71
304
111
244
76
H18 H19 H20 H21 H22
撤去台数(自転車・原付) 返却台数(自転車・原付)
(台) (%)
放置自転車の撤去

154 155
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章交通安全第1節
第1項 交通環境の整備
■目標・自治会等の地域や狭山警察署等の関係機関と連携を図りながら、交通事故の危険から市民を守り、安心して日
常生活が送れる交通環境を目指します。
・放置自転車対策を推進し、環境美化の推進や歩行者の安全な通行の確保を図ります。
■現状・交通事故防止のため、道路反射鏡、道路照明灯、道路標示などの交通安全施設の整備を行っています。
・駅周辺における歩道の安全確保のため、市内の各駅周辺に13ヶ所の自転車駐車場を設置しています。
・自転車が安全に通行できる環境整備は進んでいません。
・自転車放置に対する指導や撤去等、放置自転車の解消に向けての取組を実施しています。
■課題・交通安全施設の整備充実に向けた市民からの要望は多く、対応が求められています。
・自転車道の整備については、歩道や道路の幅員、安全対策などが課題となります。
・放置自転車は、都市景観上の美観を損ねるとともに、歩道の幅員を減少させ、歩行者の通行を妨げるなど交通
安全上の問題があることから対策が必要となっています。
■5年間の取り組み・交通安全施設の整備を進め、交通の安全確保を目指します。
・自転車が安全に通行できる環境の整備について検討します。
・各駅周辺における自転車駐車場の確保・充実を図ります。
・自転車放置に対する指導や撤去等に努めるとともに、マナー向上のための啓発にも努め、放置自転車解消を目
指します。
〈事業体系〉
交通安全施設の充実
自転車通行環境の整備方策の検討
放置自転車の解消
交通安全施設の整備
自転車通行環境の整備方策の検討
放置自転車の解消
交通環境の整備
◆施策1 交通安全施設の充実 事業① 交通安全施設の整備
地域や関係機関と連携し、道路反射鏡や道路照明灯等の交通安全施設の整備を進めます。
◆施策2 自転車通行環境の整備方策の検討 事業① 自転車通行環境の整備方策の検討
地域や関係機関と連携し、自転車が安全に通行できる環境の整備方策について検討します。
◆施策3 放置自転車の解消 事業① 放置自転車の解消
放置自転車対策として、駅周辺に自転車駐車場施設の確保・充実を目指します。また、自転車放置に対する
指導や撤去に努めるとともに、マナー向上のための啓発活動などを推進します。
〈評価項目〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
道路反射鏡設置数市民の交通の安全確保を図るために、設置数を増やします。
1,901件 2,150件 2,300件
道路照明灯設置数市民の交通の安全確保を図るために、設置数を増やします。
1,243件 1,300件 1,400件
放置自転車撤去台数駅周辺の景観を美化し、歩道・通行帯の安全性を向上させるために、撤去台数を減らします。
244台 200台 150台
放置自転車撤去及び返却状況の推移
0
100
200
300
400
500
15
20
25
30
35
40
返却率
28.4
23.6
19.4
36.5
31.1
451
128
296
70
366
71
304
111
244
76
H18 H19 H20 H21 H22
撤去台数(自転車・原付) 返却台数(自転車・原付)
(台) (%)
放置自転車の撤去

156 157
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
第2項 交通安全対策の充実
■目標・地域や学校等における交通安全教室や交通安全運動の実施により、交通安全思想の普及・浸透を図り、交通事
故防止のための徹底的な取組を行い、交通事故のない社会の実現を目指します。
・複雑化する交通事故をめぐる諸問題から交通事故当事者を救済するために、交通事故相談の充実を図ります。
■現状・市内における交通事故(人身)の件数は減少傾向にあるものの、毎年約800件、交通事故死傷者数は毎年約1千
人にのぼります。
・交通弱者といわれる高齢者や子どもが当事者となるケースが多く発生しており、交通事故防止に向けた対策が
急務となっています。
・交通事故は、被害者・加害者とも損害賠償をはじめとする多くの問題が発生し、その解決に苦慮しています。
■課題・交通事故の発生を防ぐためには、地域・関係機関・関係団体等が連携を図り、市内の交通環境の変化に対処し
ていくことが求められています。
・学校や地域において、交通安全教育による交通道徳の高揚と、啓発活動による交通安全意識の高揚が必要となっ
ています。
・交通事故相談が、交通事故当事者のさまざまな問題解決に必要となっています。
■5年間の取り組み・自治会・狭山警察署・狭山地方交通安全協会等の地域・関係機関・関係団体等と緊密に連携して交通危険箇所
を把握するとともに、高齢者や子ども等に対する交通安全教室の実施や啓発活動を通じて交通ルールの遵守と
マナー向上を図り、交通事故の減少に努めます。
・交通事故当事者の問題解決のために、相談事業の充実を図ります。
〈事業体系〉
交通事故防止の促進
交通事故相談の充実
交通安全対策推進協議会活動の支援
交通安全意識の向上
交通事故相談の実施
交通安全対策の充実
◆施策1 交通事故防止の促進 事業① 交通安全対策推進協議会活動の支援
地域・関係機関・関係団体等の協力のもと、交通事故撲滅のために諸施策・運動を展開する交通安全対策推
進協議会の活動を支援します。
事業② 交通安全意識の向上
市民の交通安全意識を高めるため、高齢者や子どもを対象とした交通安全教室の開催や、地域・関係機関・
関係団体等と連携した交通事故防止運動等の啓発活動を通じて、交通事故を防止するとともに、交通事故発生
件数の減少と交通死亡事故の撲滅を目指します。
◆施策2 交通事故相談の充実 事業① 交通事故相談の実施
交通事故当事者のさまざまな問題解決のための交通事故相談を実施し、専門相談員が指導や助言を行います。
〈評価項目〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
交通安全教室参加人数交通安全意識の高揚を図るために、参加人数を増やします。
21,066人 22,000人 23,000人
交通(人身)事故発生件数
交通安全運動や啓発活動を増やすことで、交通(人身)事故件数を減らします。
880件 800件 0件
交通事故件数の推移
800
1,000
1,200
H18 H19 H20 H21 H22
1,137
1,064
1,061
987
1,115
929880
880 813
891
事故件数(件) 死傷者数(人)
交通安全教室

156 157
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
第2項 交通安全対策の充実
■目標・地域や学校等における交通安全教室や交通安全運動の実施により、交通安全思想の普及・浸透を図り、交通事
故防止のための徹底的な取組を行い、交通事故のない社会の実現を目指します。
・複雑化する交通事故をめぐる諸問題から交通事故当事者を救済するために、交通事故相談の充実を図ります。
■現状・市内における交通事故(人身)の件数は減少傾向にあるものの、毎年約800件、交通事故死傷者数は毎年約1千
人にのぼります。
・交通弱者といわれる高齢者や子どもが当事者となるケースが多く発生しており、交通事故防止に向けた対策が
急務となっています。
・交通事故は、被害者・加害者とも損害賠償をはじめとする多くの問題が発生し、その解決に苦慮しています。
■課題・交通事故の発生を防ぐためには、地域・関係機関・関係団体等が連携を図り、市内の交通環境の変化に対処し
ていくことが求められています。
・学校や地域において、交通安全教育による交通道徳の高揚と、啓発活動による交通安全意識の高揚が必要となっ
ています。
・交通事故相談が、交通事故当事者のさまざまな問題解決に必要となっています。
■5年間の取り組み・自治会・狭山警察署・狭山地方交通安全協会等の地域・関係機関・関係団体等と緊密に連携して交通危険箇所
を把握するとともに、高齢者や子ども等に対する交通安全教室の実施や啓発活動を通じて交通ルールの遵守と
マナー向上を図り、交通事故の減少に努めます。
・交通事故当事者の問題解決のために、相談事業の充実を図ります。
〈事業体系〉
交通事故防止の促進
交通事故相談の充実
交通安全対策推進協議会活動の支援
交通安全意識の向上
交通事故相談の実施
交通安全対策の充実
◆施策1 交通事故防止の促進 事業① 交通安全対策推進協議会活動の支援
地域・関係機関・関係団体等の協力のもと、交通事故撲滅のために諸施策・運動を展開する交通安全対策推
進協議会の活動を支援します。
事業② 交通安全意識の向上
市民の交通安全意識を高めるため、高齢者や子どもを対象とした交通安全教室の開催や、地域・関係機関・
関係団体等と連携した交通事故防止運動等の啓発活動を通じて、交通事故を防止するとともに、交通事故発生
件数の減少と交通死亡事故の撲滅を目指します。
◆施策2 交通事故相談の充実 事業① 交通事故相談の実施
交通事故当事者のさまざまな問題解決のための交通事故相談を実施し、専門相談員が指導や助言を行います。
〈評価項目〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
交通安全教室参加人数交通安全意識の高揚を図るために、参加人数を増やします。
21,066人 22,000人 23,000人
交通(人身)事故発生件数
交通安全運動や啓発活動を増やすことで、交通(人身)事故件数を減らします。
880件 800件 0件
交通事故件数の推移
800
1,000
1,200
H18 H19 H20 H21 H22
1,137
1,064
1,061
987
1,115
929880
880 813
891
事故件数(件) 死傷者数(人)
交通安全教室

158 159
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章消防第2節
第1項 広域化の実現
■目標・大規模災害における初動対応の強化と、地域の安全・安心に対する備えを向上させるために、消防の広域化を
目指します。
・消防救急無線のデジタル化の推進、消防救急無線の広域化・共同化、消防指令業務の共同運営の実現を目指し
ます。
■現状・国により「市町村の消防の広域化に関する基本指針」が策定されたことを受け、平成22年1月に所沢・飯能・狭
山・入間・日高の5市による「埼玉県消防広域化第4ブロック協議会」を設立し、消防広域化を実現するための広
域消防運営計画を策定するなど、広域化に向けて準備を進めています。
・平成25年4月1日を目途に消防広域化の実現を目指しています。
■課題・大規模災害に対処するためには、消防力の強化と充実が必要となります。
・現状の消防組織の規模で対処できる災害活動には限界があり、近年のように複雑化・多様化する大規模災害に
おいては、初動体制の強化と統一的な指揮下での効率的な部隊運用及び高度資機材等の整備が求められていま
す。
■5年間の取り組み・埼玉県消防広域化第4ブロック検討委員会協議会において策定した広域化に向けた運営計画に基づき、平成25
年度に消防広域化を実現し、住民サービスの向上、消防体制の充実強化及び高度化を図ります。
〈事業体系〉
広域化の推進 消防広域化の推進広域化の実現
◆施策1 広域化の推進 事業① 消防広域化の推進
消防広域化を実現することで、構成5市における消防業務の共同運用を図り、大規模災害への初動対応を強
化します。また、消防広域化による消防指令業務の共同運営と、消防救急無線のデジタル化の実現を目指します。
第2項 消防力の強化・充実
■目標・住民の生命、身体や財産を守るため、消防力の充実強化と消防体制の整備を図ります。
■現状・複雑化・多様化・大規模化する災害に対処するために、消防力の強化と充実が求められています。
・消防団については活性化を図っているものの、入団者が減少する傾向にあります。
・火災の発生を未然に防ぐために、火災予防活動の強化・充実が重要であり、市民や各事業所の従業員が初期消
火技術等を習得できるよう、積極的に訓練を実施しています。
■課題・市街地の拡大や建築物の大規模化・高層化に対応して、消防力の増強と消防体制の充実を図る必要があります。
・地域防災の要である消防団の充実と活性化が必要となっています。
・住宅防火対策の強化・推進と、大規模災害に対する防災意識の普及啓発活動を充実する必要があります。
・年々高度化していく救命処置については、専門的で高度な教育訓練や技術的な研修により、知識の習得や技術
の向上に努めていく必要があります。
・災害や救急に対する市民の意識の高揚や積極的な関わりが必要となります。
■5年間の取り組み・消防施設等の整備、消防団の充実、災害対策対応訓練の充実を図ることにより、各種災害に対応できる消防力
の強化と充実に努めます。
・各消防協力団体の火災予防事業がさらに効果のあるものになるよう、各団体の活性化を図ります。
・市民に対して、火災予防を効果的に呼びかけるために各種事業を積極的に展開します。
・広報用品の整備と初期消火技術等を習得するため、訓練資器材の整備を図ります。
・※救急救命士の養成と、※高度救急システムの構築、運用により救命率の向上を目指します。
〈事業体系〉
消防体制の充実 消防施設等の整備
火災予防の充実 消防協力団体の活性化
救急体制の充実 救急業務の高度化推進
消防団の活性化
広報活動の実施
救急処置の普及啓発
災害対応訓練の実施
火災予防査察の実施
消防力の強化・充実
※救急救命士:救急救命士法第2条「厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」をいう。※高度救急システム:救急隊員等が救急現場活動において、常に最新の知識及び技術を提供できるように研修体制等を構築するシステム。

158 159
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章消防第2節
第1項 広域化の実現
■目標・大規模災害における初動対応の強化と、地域の安全・安心に対する備えを向上させるために、消防の広域化を
目指します。
・消防救急無線のデジタル化の推進、消防救急無線の広域化・共同化、消防指令業務の共同運営の実現を目指し
ます。
■現状・国により「市町村の消防の広域化に関する基本指針」が策定されたことを受け、平成22年1月に所沢・飯能・狭
山・入間・日高の5市による「埼玉県消防広域化第4ブロック協議会」を設立し、消防広域化を実現するための広
域消防運営計画を策定するなど、広域化に向けて準備を進めています。
・平成25年4月1日を目途に消防広域化の実現を目指しています。
■課題・大規模災害に対処するためには、消防力の強化と充実が必要となります。
・現状の消防組織の規模で対処できる災害活動には限界があり、近年のように複雑化・多様化する大規模災害に
おいては、初動体制の強化と統一的な指揮下での効率的な部隊運用及び高度資機材等の整備が求められていま
す。
■5年間の取り組み・埼玉県消防広域化第4ブロック検討委員会協議会において策定した広域化に向けた運営計画に基づき、平成25
年度に消防広域化を実現し、住民サービスの向上、消防体制の充実強化及び高度化を図ります。
〈事業体系〉
広域化の推進 消防広域化の推進広域化の実現
◆施策1 広域化の推進 事業① 消防広域化の推進
消防広域化を実現することで、構成5市における消防業務の共同運用を図り、大規模災害への初動対応を強
化します。また、消防広域化による消防指令業務の共同運営と、消防救急無線のデジタル化の実現を目指します。
第2項 消防力の強化・充実
■目標・住民の生命、身体や財産を守るため、消防力の充実強化と消防体制の整備を図ります。
■現状・複雑化・多様化・大規模化する災害に対処するために、消防力の強化と充実が求められています。
・消防団については活性化を図っているものの、入団者が減少する傾向にあります。
・火災の発生を未然に防ぐために、火災予防活動の強化・充実が重要であり、市民や各事業所の従業員が初期消
火技術等を習得できるよう、積極的に訓練を実施しています。
■課題・市街地の拡大や建築物の大規模化・高層化に対応して、消防力の増強と消防体制の充実を図る必要があります。
・地域防災の要である消防団の充実と活性化が必要となっています。
・住宅防火対策の強化・推進と、大規模災害に対する防災意識の普及啓発活動を充実する必要があります。
・年々高度化していく救命処置については、専門的で高度な教育訓練や技術的な研修により、知識の習得や技術
の向上に努めていく必要があります。
・災害や救急に対する市民の意識の高揚や積極的な関わりが必要となります。
■5年間の取り組み・消防施設等の整備、消防団の充実、災害対策対応訓練の充実を図ることにより、各種災害に対応できる消防力
の強化と充実に努めます。
・各消防協力団体の火災予防事業がさらに効果のあるものになるよう、各団体の活性化を図ります。
・市民に対して、火災予防を効果的に呼びかけるために各種事業を積極的に展開します。
・広報用品の整備と初期消火技術等を習得するため、訓練資器材の整備を図ります。
・※救急救命士の養成と、※高度救急システムの構築、運用により救命率の向上を目指します。
〈事業体系〉
消防体制の充実 消防施設等の整備
火災予防の充実 消防協力団体の活性化
救急体制の充実 救急業務の高度化推進
消防団の活性化
広報活動の実施
救急処置の普及啓発
災害対応訓練の実施
火災予防査察の実施
消防力の強化・充実
※救急救命士:救急救命士法第2条「厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」をいう。※高度救急システム:救急隊員等が救急現場活動において、常に最新の知識及び技術を提供できるように研修体制等を構築するシステム。

160 161
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
◆施策1 消防体制の充実 事業① 消防施設等の整備
常備・非常備の消防車両の更新、消防活動のための資機材・装備の整備、震災に対応するための耐震性防火
水槽の整備、消防救急デジタル化に伴う消防緊急通信指令施設の整備等により、積極的に消防力の強化を図り
ます。
事業② 消防団の活性化
消防団の活性化を支援するとともに、消防団員の被服及び各地区に配備する震災用初期救助資機材・救急処
置活動資機材・水害用資器材を搭載した消防車の充実強化を図ります。
事業③ 災害対応訓練の実施
さまざまな災害に適切に対応し、被害を最小限におさえるために、あらゆる災害に対処できる高度な訓練を
実施します。また、会場となる事業所の関係者及び地域住民と連携した総合的な消防活動の訓練を行うことに
より、災害対応技術の習熟を図ります。
◆施策2 火災予防の充実 事業① 消防協力団体の活性化
幼年消防クラブ、消防少年団、女性防火クラブ、防火安全協会など防火協力団体の各事業が、効果的に展開
されるよう支援するとともに、各団体との共同事業を積極的に推進します。
事業② 広報活動の実施
広報いるま、市公式ホームページ、各種メディア等を利用して火災予防の広報や、各種イベントでのPR活動、
各種講習会や訓練指導の機会に火災予防に関する呼びかけを行います。また、市民、事業所等との積極的な関
わりの中で、効果的に広報活動を行うことで、防火防災意識の高揚を図ります。
事業③ 火災予防査察の実施
防火対象物からの火災発生を未然に防ぐため、積極的に予防査察を実施します。また、これらの防火対象物
を効果的に管理するために、防火対象物管理システムの整備運用を図ります。
◆施策3 救急体制の充実 事業① 救急業務の高度化推進
救急救命士の養成と高度な救急技術の習得、高度救急システムの構築と運用を図ります。
事業② 救急処置の普及啓発
市民の救急に対する意識の向上と、※AEDの取り扱いや「心肺蘇生法」などの救急救命技術の普及啓発を図
ります。
〈評価項目〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
年間の火災件数火災予防活動を充実させることで、火災件数を減らします。
69件前年度比-10%
35件
救命率救急体制を充実させることで、心肺停止傷病者のうち1ヶ月以上生存した人の割合を増やします。
4.1% 6.7% 6.7%
救急救命士の人数高度な救急医療を確保するために、人数を増やします。
25人 30人 30人
消防団員の人数地域の消防力を強化・充実するために、人数を維持します。
297名 現状維持 303人
住宅用警報器の設置率 火災予防を充実させるために、設置率を高めます。 75.1% 90.0% 100.0%
出火件数の推移
救急出場及び搬送人員の推移
40
50
60
70
80
H18 H19 H20 H21 H22
60
50
69
46
70
(件)
4,000
5,000
6,000
4,000
5,000
6,000
H18 H19 H20 H21 H22
4,5594,559
5,107
4,649 4,6034,654
4,951
5,580
5,080 5,0635,131
救急出場件数(件) 搬送人数(人)(件) (人)
救命講習会
消防操法大会
※AED:自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator,AED)のこと。心室細動の際に機器が自動的に解析を行い、必要に応じて電気的なショック(除細動)を与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器。

160 161
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
◆施策1 消防体制の充実 事業① 消防施設等の整備
常備・非常備の消防車両の更新、消防活動のための資機材・装備の整備、震災に対応するための耐震性防火
水槽の整備、消防救急デジタル化に伴う消防緊急通信指令施設の整備等により、積極的に消防力の強化を図り
ます。
事業② 消防団の活性化
消防団の活性化を支援するとともに、消防団員の被服及び各地区に配備する震災用初期救助資機材・救急処
置活動資機材・水害用資器材を搭載した消防車の充実強化を図ります。
事業③ 災害対応訓練の実施
さまざまな災害に適切に対応し、被害を最小限におさえるために、あらゆる災害に対処できる高度な訓練を
実施します。また、会場となる事業所の関係者及び地域住民と連携した総合的な消防活動の訓練を行うことに
より、災害対応技術の習熟を図ります。
◆施策2 火災予防の充実 事業① 消防協力団体の活性化
幼年消防クラブ、消防少年団、女性防火クラブ、防火安全協会など防火協力団体の各事業が、効果的に展開
されるよう支援するとともに、各団体との共同事業を積極的に推進します。
事業② 広報活動の実施
広報いるま、市公式ホームページ、各種メディア等を利用して火災予防の広報や、各種イベントでのPR活動、
各種講習会や訓練指導の機会に火災予防に関する呼びかけを行います。また、市民、事業所等との積極的な関
わりの中で、効果的に広報活動を行うことで、防火防災意識の高揚を図ります。
事業③ 火災予防査察の実施
防火対象物からの火災発生を未然に防ぐため、積極的に予防査察を実施します。また、これらの防火対象物
を効果的に管理するために、防火対象物管理システムの整備運用を図ります。
◆施策3 救急体制の充実 事業① 救急業務の高度化推進
救急救命士の養成と高度な救急技術の習得、高度救急システムの構築と運用を図ります。
事業② 救急処置の普及啓発
市民の救急に対する意識の向上と、※AEDの取り扱いや「心肺蘇生法」などの救急救命技術の普及啓発を図
ります。
〈評価項目〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
年間の火災件数火災予防活動を充実させることで、火災件数を減らします。
69件前年度比-10%
35件
救命率救急体制を充実させることで、心肺停止傷病者のうち1ヶ月以上生存した人の割合を増やします。
4.1% 6.7% 6.7%
救急救命士の人数高度な救急医療を確保するために、人数を増やします。
25人 30人 30人
消防団員の人数地域の消防力を強化・充実するために、人数を維持します。
297名 現状維持 303人
住宅用警報器の設置率 火災予防を充実させるために、設置率を高めます。 75.1% 90.0% 100.0%
出火件数の推移
救急出場及び搬送人員の推移
40
50
60
70
80
H18 H19 H20 H21 H22
60
50
69
46
70
(件)
4,000
5,000
6,000
4,000
5,000
6,000
H18 H19 H20 H21 H22
4,5594,559
5,107
4,649 4,6034,654
4,951
5,580
5,080 5,0635,131
救急出場件数(件) 搬送人数(人)(件) (人)
救命講習会
消防操法大会
※AED:自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator,AED)のこと。心室細動の際に機器が自動的に解析を行い、必要に応じて電気的なショック(除細動)を与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器。

162 163
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章防災第3節
第1項 防災体制の充実
■目標・市民が安心して暮らせるまちを実現するため、災害時に迅速かつ的確に対応できる防災体制づくりを推進しま
す。
・市民が防災に関心を持ち、地域ぐるみで災害に対応できる防災体制の構築を目指します。
・災害時の建築物の倒壊による被災者を最小限にすることを目指します。
■現状・全国的には台風や集中豪雨などの風水害による被害が年々増加傾向にあります。
・東海地震、首都圏直下地震などの地震の発生が懸念されています。
・本市では災害時に備え、地域防災計画の充実と、防災施設、備蓄品、※防災行政無線など防災体制の整備に努
めています。
■課題・防災情報システムの有効活用を図るとともに、防災情報連絡体制の充実に努め、防災体制の強化を図っていく
必要があります。
・訓練参加者の増加を図りながら、より実践的な防災訓練を実施し、市民の防災意識の更なる高揚を図っていく
必要があります。
・地震による被害の軽減を図るために、住宅の耐震化率の向上が求められています。
■5年間の取り組み・「入間市地域防災計画」を必要に応じて見直し、充実を図ります。
・防災訓練の内容充実と参加者の増加を図ります。
・指定避難所の標示板、誘導標識板の更新、備蓄品の整備を計画的に進めます。
・住宅等の建築物の耐震化を推進し、市民の生命・身体・財産を地震による建築物の倒壊等の被害から保護しま
す。
・防災情報システムの有効活用や防災行政無線の整備充実を図るとともに、防災情報連絡体制を充実し、迅速な
情報伝達を図ります。
〈事業体系〉
防災体制の強化 地域防災計画の推進
防災情報ネットワークの充実 防災情報システムの整備
防災訓練の実施
近隣市等との協力体制の充実
防災情報連絡体制の整備
防災施設等の整備
建築物の計画的な耐震化の促進
防災体制の充実
◆施策1 防災体制の強化 事業① 地域防災計画の推進
地域防災計画の基本となる「入間市地域防災計画」を推進します。また、災害事象の変化や市民ニーズを的確
に捉え、国・県の防災計画との整合を図りながら、必要に応じて計画の見直しを行います。
事業② 防災訓練の実施
本市の自主防災組織の特徴をいかし、各※自主防災会における地域防災力の向上を図るために、防災訓練を
実施します。また、災害の発生に迅速に対応するため、防災関係機関との連携を図ります。さらに、訓練内容
の充実と訓練参加者の増加に努めます。
事業③ 防災施設等の整備
指定避難所として、市内の小中学校や公民館等56ヶ所を指定しています。指定避難所を市民に周知するため、
避難所標示板及び誘導標識板の更新や維持管理を計画的に実施します。さらに、指定避難所における備蓄品の
整備を進めます。
事業④ 近隣市等との協力体制の充実
近隣市との相互応援協定を充実するとともに、国、県等との協力体制の強化に努め、広域的な相互協力体制
の充実を図ります。また、姉妹都市である新潟県佐渡市とは、大規模災害時における相互援助協定を結んでい
ます。
事業⑤ 建築物の計画的な耐震化の促進
災害時の建物の倒壊による被災者を最小限にすることを目的に、「入間市建築物耐震改修促進計画」に基づき、
建築物の耐震性の重要性を啓発するとともに、地震に対する安全性の向上を図り、既存建築物の耐震改修等を
含む耐震化施策を総合的に進めます。
◆施策2 防災情報ネットワークの充実 事業① 防災情報システムの整備
市域の気象について24時間監視を行い、リアルタイムで地震や台風・雷雨・豪雨・降雪等の情報を市民に提
供します。また、防災情報システムの安定化に向けて、災害時の情報伝達手段である防災行政無線のデジタル
化を検討します。
事業② 防災情報連絡体制の整備
防災行政無線、※CATV、※コミュニティFM放送等の情報伝達手段により、市民に正確な情報を迅速に伝
達できるよう、各防災関係機関との連携を図ります。また、「茶の都メール」の登録者が増加するよう啓発を図
ります。市民への防災情報として地区別防災マップを作成し配布します。
〈評価項目〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
入間市防災訓練に参加した市民の人数
市民の防災意識と地域の防災力を高めるために、参加人数を増やします。
20,034人 22,500人 25,000人
茶の都メールの「防災情報」を登録した人数
市民生活の安全を確保するために、登録人数を増やします。
3,348人 4,000人 5,000人
住宅の耐震化率 安全な市民生活を確保するために、耐震化率を高めます。
82.7% 90.0% 90.0%
※自主防災会:各自治会が母体となって地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う任意団体。入間市では121の自主防災会を組織している。※CATV:同軸ケーブルや光ファイバーケーブルなどを使ったテレビ放送。当初は難視聴解消のための共同アンテナによる受信、有線による分配を目的とし
たが、現在では双方向通信や衛星を利用したネットワークサービスをはじめ、インターネット接続サービス、IP電話などに使われている。有線テレビ。ケーブルテレビ。
※コミュニティFM放送:通常のFMより出力の小さい、市町村単位の小規模なFMラジオ放送。平成4年(1992)に郵政省(現総務省)が制度化した。細かい地域情報の提供、住民参加型の番組制作を通じて地域の活性化を図る狙いがある。
※防災行政無線:住民へ防災情報を伝達する無線通信システム。入間市では固定系親局1ヶ所、遠隔制御器1ヶ所、固定系子局125ヶ所を設置している。

162 163
第2編
第5章
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章防災第5節
第1項 防災体制の充実
■目標・市民が安心して暮らせるまちを実現するため、災害時に迅速かつ的確に対応できる防災体制づくりを推進しま
す。
・市民が防災に関心を持ち、地域ぐるみで災害に対応できる防災体制の構築を目指します。
・災害時の建築物の倒壊による被災者を最小限にすることを目指します。
■現状・全国的には台風や集中豪雨などの風水害による被害が年々増加傾向にあります。
・東海地震、首都圏直下地震などの地震の発生が懸念されています。
・本市では災害時に備え、地域防災計画の充実と、防災施設、備蓄品、※防災行政無線など防災体制の整備に努
めています。
■課題・防災情報システムの有効活用を図るとともに、防災情報連絡体制の充実に努め、防災体制の強化を図っていく
必要があります。
・訓練参加者の増加を図りながら、より実践的な防災訓練を実施し、市民の防災意識の更なる高揚を図っていく
必要があります。
・地震による被害の軽減を図るために、住宅の耐震化率の向上が求められています。
■5年間の取り組み・「入間市地域防災計画」を必要に応じて見直し、充実を図ります。
・防災訓練の内容充実と参加者の増加を図ります。
・指定避難所の標示板、誘導標識板の更新、備蓄品の整備を計画的に進めます。
・住宅等の建築物の耐震化を推進し、市民の生命・身体・財産を地震による建築物の倒壊等の被害から保護しま
す。
・防災情報システムの有効活用や防災行政無線の整備充実を図るとともに、防災情報連絡体制を充実し、迅速な
情報伝達を図ります。
〈事業体系〉
防災体制の強化 地域防災計画の推進
防災情報ネットワークの充実 防災情報システムの整備
防災訓練の実施
近隣市等との協力体制の充実
防災情報連絡体制の整備
防災施設等の整備
建築物の計画的な耐震化の促進
防災体制の充実
◆施策1 防災体制の強化 事業① 地域防災計画の推進
地域防災計画の基本となる「入間市地域防災計画」を推進します。また、災害事象の変化や市民ニーズを的確
に捉え、国・県の防災計画との整合を図りながら、必要に応じて計画の見直しを行います。
事業② 防災訓練の実施
本市の自主防災組織の特徴をいかし、各※自主防災会における地域防災力の向上を図るために、防災訓練を
実施します。また、災害の発生に迅速に対応するため、防災関係機関との連携を図ります。さらに、訓練内容
の充実と訓練参加者の増加に努めます。
事業③ 防災施設等の整備
指定避難所として、市内の小中学校や公民館等56ヶ所を指定しています。指定避難所を市民に周知するため、
避難所標示板及び誘導標識板の更新や維持管理を計画的に実施します。さらに、指定避難所における備蓄品の
整備を進めます。
事業④ 近隣市等との協力体制の充実
近隣市との相互応援協定を充実するとともに、国、県等との協力体制の強化に努め、広域的な相互協力体制
の充実を図ります。また、姉妹都市である新潟県佐渡市とは、大規模災害時における相互援助協定を結んでい
ます。
事業⑤ 建築物の計画的な耐震化の促進
災害時の建物の倒壊による被災者を最小限にすることを目的に、「入間市建築物耐震改修促進計画」に基づき、
建築物の耐震性の重要性を啓発するとともに、地震に対する安全性の向上を図り、既存建築物の耐震改修等を
含む耐震化施策を総合的に進めます。
◆施策2 防災情報ネットワークの充実 事業① 防災情報システムの整備
市域の気象について24時間監視を行い、リアルタイムで地震や台風・雷雨・豪雨・降雪等の情報を市民に提
供します。また、防災情報システムの安定化に向けて、災害時の情報伝達手段である防災行政無線のデジタル
化を検討します。
事業② 防災情報連絡体制の整備
防災行政無線、※CATV、※コミュニティFM放送等の情報伝達手段により、市民に正確な情報を迅速に伝
達できるよう、各防災関係機関との連携を図ります。また、「茶の都メール」の登録者が増加するよう啓発を図
ります。市民への防災情報として地区別防災マップを作成し配布します。
〈評価項目〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
入間市防災訓練に参加した市民の人数
市民の防災意識と地域の防災力を高めるために、参加人数を増やします。
20,034人 22,500人 25,000人
茶の都メールの「防災情報」を登録した人数
市民生活の安全を確保するために、登録人数を増やします。
3,348人 4,000人 5,000人
住宅の耐震化率 安全な市民生活を確保するために、耐震化率を高めます。
82.7% 90.0% 90.0%
※自主防災会:各自治会が母体となって地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う任意団体。入間市では121の自主防災会を組織している。※CATV:同軸ケーブルや光ファイバーケーブルなどを使ったテレビ放送。当初は難視聴解消のための共同アンテナによる受信、有線による分配を目的としたが、現在では双方向通信や衛星を利用したネットワークサービスをはじめ、インターネット接続サービス、IP電話などに使われている。有線テレビ。ケーブルテレビ。
※コミュニティFM放送:通常のFMより出力の小さい、市町村単位の小規模なFMラジオ放送。平成4年(1992)に郵政省(現総務省)が制度化した。細かい地域情報の提供、住民参加型の番組制作を通じて地域の活性化を図る狙いがある。
※防災行政無線:住民へ防災情報を伝達する無線通信システム。入間市では固定系親局1ヶ所、遠隔制御器1ヶ所、固定系子局125ヶ所を設置している。

164
第2編
第5章
防災訓練参加者数の推移
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
150
200訓練参加団体
177
183180
174 175
20,069
17,468
H19 H20 H21 H22 H23
訓練者総数
20,623 20,034
22,446(人)
防災訓練

164
第2編
第5章
防災訓練参加者数の推移
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
150
200訓練参加団体
177
183180
174 175
20,069
17,468
H19 H20 H21 H22 H23
訓練者総数
20,623 20,034
22,446(人)
防災訓練
165
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
◆施策1 防災意識の高揚 事業① 防災意識の啓発
� 市民や自主防災会の防災意識を高めるための情報提供を進めるととも
に、防災に関する講座や学習会を実施し、地域における防災行動力の強
化を図ります。
◆施策2 自主防災組織の育成・充実 事業① 自主防災組織の支援
� 自主防災会との連携を図りながら、活動の支援や指導、情報交換を行い防災行動力の強化を図ります。また、
地域における災害時要援護者対策の充実を図り、助け合う「共助」体制を充実します。
第2項 自主防災組織の育成・充実
■目標・地震や台風などの災害から市民の生命・身体・財産を守るために設置された自主防災組織を支援・育成し、市
民の防災意識の高揚を図ることで、地域防災力を高めることを目指します。
■現状・本市の自主防災会は自治会重複型となっており、地域に密着した防災活動を展開しています。
・各自主防災会の組織率は100%を達成しており、各自主防災会の防災に対する関心も高い状況です。
・防災訓練には、多くの市民、団体が参加しています。
■課題・地震や台風などの災害から市民の生命・身体・財産を守るため、さらに自主防災会の主体的な地域防災力の向
上を図る必要があります。
・�地域の特性に応じた実践的な防災訓練を実施し、地域における「共助」を担う各自主防災会として、さらに防災
意識の高いまちづくりを進める必要があります。
■5年間の取り組み・市民や自主防災会の防災意識の高揚に努め、地域防災力の強化を図ります。
・地域の特性に応じた実践的な防災訓練を実施し、防災意識の高いまちづくりを進めます。
・�災害時要援護者対策の充実など、「共助」を担う各自主防災会の活動がさらに充実するよう支援や指導を行います。
〈事業体系〉
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期目標値
目標達成値
災害に備えて準備や対策をとっている市民の割合(市民意識調査)
災害に備えて準備や対策をとっている市民の割合を増やすことで、自主防災組織の育成の達成度を測ります。
55.3% 60.0% 65.0%
〈評価項目〉
防災意識の高揚
自主防災組織の育成・充実
防災意識の啓発
自主防災組織の支援
自主防災組織の育成・充実

166
第2編
第5章
167
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
◆施策1 防犯体制の整備・充実 事業① 地域防犯活動の支援
� 防犯体制の整備・充実のため、自治会・狭山警察署・狭山地方防犯協会や狭山市・入間市暴力排除推進協議
会など、各防犯関係機関とより密接な連携及び情報交換を図り、地域防犯活動を支援します。また、各地域で
活動する※地域防犯ネットワーク(通称:アポック)及び自治会等が行う防犯活動を支援します。さらに、防犯
のまちづくり推進条例の普及啓発を図ります。
◆施策2 防犯施設の整備・充実 事業① 防犯灯の設置及び維持管理
� 防犯上必要な場所に、自治会からの申請に基づき防犯灯を設置します。また、老朽化した防犯灯の改修も併
せて行います。さらに、防犯灯管理体制の充実に向けて防犯灯管理システムの導入を検討します。
事業② ※防犯パトロールステーションの整備
� 地域からの要請により地域防犯活動の拠点となる防犯パトロールステーションを整備し、地域の防犯活動を
支援します。
◆施策3 防犯意識の高揚 事業① 防犯意識の啓発
� 防犯意識の高揚を図るため、市民や自治会を対象とした防犯講座等を実施します。また、狭山地方防犯協会
や狭山市・入間市暴力排除推進協議会に負担金を支出し、防犯啓発活動を支援します。
◆施策4 防犯情報伝達手段の整備 事業① 安全・安心メールの活用
� 犯罪被害発生状況や不審者の出没などの防犯情報を、速やかに市民に伝達する※「茶の都メール」の活用を図
るため、市民の利用登録をさらに促進します。
防犯第4節
第1項 防犯体制の充実
■目標・�自治会・地域防犯活動団体・狭山警察署等の関係機関と連携を図りながら、犯罪を起こしにくいまち、犯罪の
ないまちづくりを進め、市民が安全で安心して暮らせるまちを目指します。
■現状・引ったくり、車上狙いなどの街頭犯罪や振り込め詐欺などの悪質な犯罪が増加しています。
・地域コミュニティが希薄になりつつあり、地域の防犯力が低下してきています。
■課題・市民の防犯意識の啓発や防犯施設を整備し、防犯体制の充実を図ることが必要です。
・�自治会等が実施する地域防犯活動の支援とともに、防犯灯や地域防犯活動の拠点の整備を進めることが求めら
れています。
■5年間の取り組み・狭山警察署と連携し、自治会や防犯関係団体が実施する防犯活動を支援します。
・防犯上必要な場所に防犯灯を設置するとともに、適正な維持管理に努めます。
・市民の防犯意識を高めるため、地域防犯活動を支援します。
・犯罪や防犯に関する情報の迅速な提供に努めます。
〈事業体系〉
防犯体制の整備・充実
防犯施設の整備・充実
防犯意識の高揚
防犯情報伝達手段の整備
地域防犯活動の支援
防犯灯の設置及び維持管理
防犯パトロールステーションの整備
防犯意識の啓発
安全・安心メールの活用
防犯体制の充実
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期 目標値
目標 達成値
自主防犯パトロール活動を実施している自治会の割合
活動している自治会の割合を増やすことで、市民の防犯意識及び地域の防犯体制の充実の達成度を測ります。
95.0% 98.0% 100.0%
茶の都メールの「防犯情報」を登録した人数
市民生活の安全を確保するために、登録人数を増やします。
2,411人 3,000人 4,000人
〈評価項目〉
防犯パトロール
※茶の都メール:行政情報等を携帯電話やパソコンに配信するメール配信サービスのことをいう。 その中に大雨や台風等の発生した場合に災害情報をお知らせする災害情報と犯罪被害発生状況や不審者の出没などに関する情報を随時お知らせする防犯情報がある。
※地域防犯ネットワーク(アポック):従来、自主防犯活動は、各団体が単独で実施していたが、地域防犯ネットワーク(APOC)では、地域内にある学校・PTA・自治会等の団体や居住する個人が連絡体制を確立して市や警察から発信される各種情報を共有し、犯罪等に対しみんなで目を配り、街を守っていく活動。
※防犯パトロールステーション:地域防犯パトロール活動を積極的に展開し、地域が目を配ることによって犯罪を少なくするため、地域防犯パトロールなどさまざまな防犯活動を実施する拠点としての「民間交番」をいう。元加治駅構内に設置した。

166
第2編
第5章
167
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
◆施策1 防犯体制の整備・充実 事業① 地域防犯活動の支援
� 防犯体制の整備・充実のため、自治会・狭山警察署・狭山地方防犯協会や狭山市・入間市暴力排除推進協議
会など、各防犯関係機関とより密接な連携及び情報交換を図り、地域防犯活動を支援します。また、各地域で
活動する※地域防犯ネットワーク(通称:アポック)及び自治会等が行う防犯活動を支援します。さらに、防犯
のまちづくり推進条例の普及啓発を図ります。
◆施策2 防犯施設の整備・充実 事業① 防犯灯の設置及び維持管理
� 防犯上必要な場所に、自治会からの申請に基づき防犯灯を設置します。また、老朽化した防犯灯の改修も併
せて行います。さらに、防犯灯管理体制の充実に向けて防犯灯管理システムの導入を検討します。
事業② ※防犯パトロールステーションの整備
� 地域からの要請により地域防犯活動の拠点となる防犯パトロールステーションを整備し、地域の防犯活動を
支援します。
◆施策3 防犯意識の高揚 事業① 防犯意識の啓発
� 防犯意識の高揚を図るため、市民や自治会を対象とした防犯講座等を実施します。また、狭山地方防犯協会
や狭山市・入間市暴力排除推進協議会に負担金を支出し、防犯啓発活動を支援します。
◆施策4 防犯情報伝達手段の整備 事業① 安全・安心メールの活用
� 犯罪被害発生状況や不審者の出没などの防犯情報を、速やかに市民に伝達する※「茶の都メール」の活用を図
るため、市民の利用登録をさらに促進します。
防犯第4節
第1項 防犯体制の充実
■目標・�自治会・地域防犯活動団体・狭山警察署等の関係機関と連携を図りながら、犯罪を起こしにくいまち、犯罪の
ないまちづくりを進め、市民が安全で安心して暮らせるまちを目指します。
■現状・引ったくり、車上狙いなどの街頭犯罪や振り込め詐欺などの悪質な犯罪が増加しています。
・地域コミュニティが希薄になりつつあり、地域の防犯力が低下してきています。
■課題・市民の防犯意識の啓発や防犯施設を整備し、防犯体制の充実を図ることが必要です。
・�自治会等が実施する地域防犯活動の支援とともに、防犯灯や地域防犯活動の拠点の整備を進めることが求めら
れています。
■5年間の取り組み・狭山警察署と連携し、自治会や防犯関係団体が実施する防犯活動を支援します。
・防犯上必要な場所に防犯灯を設置するとともに、適正な維持管理に努めます。
・市民の防犯意識を高めるため、地域防犯活動を支援します。
・犯罪や防犯に関する情報の迅速な提供に努めます。
〈事業体系〉
防犯体制の整備・充実
防犯施設の整備・充実
防犯意識の高揚
防犯情報伝達手段の整備
地域防犯活動の支援
防犯灯の設置及び維持管理
防犯パトロールステーションの整備
防犯意識の啓発
安全・安心メールの活用
防犯体制の充実
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期 目標値
目標 達成値
自主防犯パトロール活動を実施している自治会の割合
活動している自治会の割合を増やすことで、市民の防犯意識及び地域の防犯体制の充実の達成度を測ります。
95.0% 98.0% 100.0%
茶の都メールの「防犯情報」を登録した人数
市民生活の安全を確保するために、登録人数を増やします。
2,411人 3,000人 4,000人
〈評価項目〉
防犯パトロール
※茶の都メール:行政情報等を携帯電話やパソコンに配信するメール配信サービスのことをいう。 その中に大雨や台風等の発生した場合に災害情報をお知らせする災害情報と犯罪被害発生状況や不審者の出没などに関する情報を随時お知らせする防犯情報がある。
※地域防犯ネットワーク(アポック):従来、自主防犯活動は、各団体が単独で実施していたが、地域防犯ネットワーク(APOC)では、地域内にある学校・PTA・自治会等の団体や居住する個人が連絡体制を確立して市や警察から発信される各種情報を共有し、犯罪等に対しみんなで目を配り、街を守っていく活動。
※防犯パトロールステーション:地域防犯パトロール活動を積極的に展開し、地域が目を配ることによって犯罪を少なくするため、地域防犯パトロールなどさまざまな防犯活動を実施する拠点としての「民間交番」をいう。元加治駅構内に設置した。

168
第2編
第5章
169
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
◆施策1 国民保護体制の整備充実 事業① 国民保護計画の推進
� 本市の国民保護体制の基本となる「入間市国民保護計画」について、国の基本指針や埼玉県国民保護計画との
整合を図るため、必要に応じて計画を見直します。
事業② 国民保護訓練の実施
� 市民の生活を脅かす武力攻撃事態や大規模テロの発生を想定した国民保護訓練を、関係機関・関係団体・自
主防災会と連携しながら実施します。
事業③ 国民保護活動資機材の整備
「入間市国民保護計画」に基づく、市民の避難・誘導・救助等を実施するために必要な資機材を整備します。
◆施策2 国民保護意識の高揚 事業① 国民保護意識の啓発
� 広報紙、パンフレットの配布等を通じて、市民や自主防災会の国民保護への理解と意識の高揚を図ります。
国民保護第5節
第1項 国民保護体制の整備
■目標・�市民の生命・身体・財産を守るため、「入間市国民保護計画」の充実を図り、武力攻撃事態や緊急対処事態に迅
速に対応できる国民保護体制の整備を目指します。
■現状・�外国からの武力攻撃や大規模テロなど、国民の生活を脅かす危機的状況に置かれるような事態の発生が危惧さ
れています。
・�危機的事態の発生に備え、国民保護のための体制の整備が進められており、本市も武力攻撃などにおける国民
の保護のための措置に関する法律(国民保護法)に基づく「入間市国民保護計画」を策定しています。
■課題・�市は市民の生命・身体・財産を守るため、市民の避難・誘導・救助等を迅速かつ的確に実施できる国民保護体
制を構築する必要があります。
■5年間の取り組み・「入間市国民保護計画」の推進を図ります。
・国民保護計画に係る関係機関、自主防災会、関係団体等との連携・協力体制を整備します。
・市民の参加により効果的な国民保護訓練を実施するとともに、必要な資機材の計画的な整備に努めます。
・市民の国民保護への理解と意識の高揚を図ります。
国民保護体制の整備充実
国民保護意識の高揚
国民保護計画の推進
国民保護訓練の実施
国民保護活動資機材の整備
国民保護意識の啓発
〈事業体系〉
国民保護体制の整備
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期 目標値
目標 達成値
国民保護訓練参加者数市民への意識啓発を図り、地域の防災力を高めるために、参加者数を増やします。
366人 500人 700人
〈評価項目〉
国民保護訓練

168
第2編
第5章
169
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
◆施策1 国民保護体制の整備充実 事業① 国民保護計画の推進
� 本市の国民保護体制の基本となる「入間市国民保護計画」について、国の基本指針や埼玉県国民保護計画との
整合を図るため、必要に応じて計画を見直します。
事業② 国民保護訓練の実施
� 市民の生活を脅かす武力攻撃事態や大規模テロの発生を想定した国民保護訓練を、関係機関・関係団体・自
主防災会と連携しながら実施します。
事業③ 国民保護活動資機材の整備
「入間市国民保護計画」に基づく、市民の避難・誘導・救助等を実施するために必要な資機材を整備します。
◆施策2 国民保護意識の高揚 事業① 国民保護意識の啓発
� 広報紙、パンフレットの配布等を通じて、市民や自主防災会の国民保護への理解と意識の高揚を図ります。
国民保護第5節
第1項 国民保護体制の整備
■目標・�市民の生命・身体・財産を守るため、「入間市国民保護計画」の充実を図り、武力攻撃事態や緊急対処事態に迅
速に対応できる国民保護体制の整備を目指します。
■現状・�外国からの武力攻撃や大規模テロなど、国民の生活を脅かす危機的状況に置かれるような事態の発生が危惧さ
れています。
・�危機的事態の発生に備え、国民保護のための体制の整備が進められており、本市も武力攻撃などにおける国民
の保護のための措置に関する法律(国民保護法)に基づく「入間市国民保護計画」を策定しています。
■課題・�市は市民の生命・身体・財産を守るため、市民の避難・誘導・救助等を迅速かつ的確に実施できる国民保護体
制を構築する必要があります。
■5年間の取り組み・「入間市国民保護計画」の推進を図ります。
・国民保護計画に係る関係機関、自主防災会、関係団体等との連携・協力体制を整備します。
・市民の参加により効果的な国民保護訓練を実施するとともに、必要な資機材の計画的な整備に努めます。
・市民の国民保護への理解と意識の高揚を図ります。
国民保護体制の整備充実
国民保護意識の高揚
国民保護計画の推進
国民保護訓練の実施
国民保護活動資機材の整備
国民保護意識の啓発
〈事業体系〉
国民保護体制の整備
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期 目標値
目標 達成値
国民保護訓練参加者数市民への意識啓発を図り、地域の防災力を高めるために、参加者数を増やします。
366人 500人 700人
〈評価項目〉
国民保護訓練

170
第2編
第5章
171
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
◆施策2 補助事業等の拡充 事業① 民生安定事業の実施
� 公共施設・設備の整備にあたっては、防衛省所管の補助事業を計画的かつ積極的に活用するように努めます。
また、公共施設・設備の改修にあたっても、計画的な補助採択がなされるように、機会を捉えて国に対して要
望します。
事業② 調整交付金事業の拡充
� 防衛施設の周辺地域における生活環境または開発の制限に及ぼす影響に対して、必要な整備を行う費用であ
る特定防衛施設周辺整備調整交付金について、計画的かつ継続的に交付するように国に強く要望します。
◆施策1 障害防止対策の推進 事業① 航空機騒音対策の推進
� 住宅防音工事の充実と告示後住宅についての防音工事、事務所や店舗などの住宅防音工事の実施を国に対し
て要望します。また、空調機器の稼働に伴う電気料助成の対象範囲の拡大など、施策の充実について国に対し
て要望します。
事業② 安全飛行等の要望
� 周辺住民の不安を軽減するため、安全飛行の徹底や騒音の低減について、航空自衛隊入間基地や防衛省など
の関係機関に対して、あらゆる機会を捉えて要望します。また、本市上空を飛行する航空機の増加に対して、
安全飛行の徹底について防衛省などに要望します。
基地第6節
第1項 基地周辺環境整備の推進
■目標・�基地の存在により生じる生活環境への影響について必要な対応を図り、市民が安全に安心して生活できる地域
づくりを推進します。
■現状・�本市には航空自衛隊入間基地が所在し、近隣にはアメリカ空軍横田基地が所在するため、基地を離着陸する航
空機の騒音など、市民は日常生活において有形、無形の影響を受けています。
・�国により、住宅に対する防音工事の実施、公共施設の防音対策に対する補助、また、市民の生活環境の整備に
向けた助成等が行われています。
■課題・�航空機の騒音や、基地が所在することで発生する事故等に対する不安は、基地周辺住民にとって完全に払拭さ
れてはいないため、引き続き騒音対策の拡充や安全飛行の徹底を国に対して求めていく必要があります。
■5年間の取り組み・�航空機の騒音を緩和するため、告示後住宅を含めた住宅防音工事の実施や事務所・店舗の防音工事の拡大を求
めます。
・安全飛行の徹底及び夜間や休日などの時間外における飛行回数の削減による騒音被害の軽減を要望します。
・施設・設備等の整備にあたっては、防衛省が所管する補助金の活用を検討し、計画的に国に対して要望します。
〈事業体系〉
障害防止対策の推進
補助事業等の拡充
航空機騒音対策の推進
安全飛行等の要望
民生安定事業の実施
調整交付金事業の拡充
基地周辺環境整備の推進
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期 目標値
目標 達成値
環境整備に関する要望活動の回数
基地周辺の生活環境を改善するために、活動回数を維持します。
3回 現状維持 現状維持
〈評価項目〉

170
第2編
第5章
171
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
◆施策2 補助事業等の拡充 事業① 民生安定事業の実施
� 公共施設・設備の整備にあたっては、防衛省所管の補助事業を計画的かつ積極的に活用するように努めます。
また、公共施設・設備の改修にあたっても、計画的な補助採択がなされるように、機会を捉えて国に対して要
望します。
事業② 調整交付金事業の拡充
� 防衛施設の周辺地域における生活環境または開発の制限に及ぼす影響に対して、必要な整備を行う費用であ
る特定防衛施設周辺整備調整交付金について、計画的かつ継続的に交付するように国に強く要望します。
◆施策1 障害防止対策の推進 事業① 航空機騒音対策の推進
� 住宅防音工事の充実と告示後住宅についての防音工事、事務所や店舗などの住宅防音工事の実施を国に対し
て要望します。また、空調機器の稼働に伴う電気料助成の対象範囲の拡大など、施策の充実について国に対し
て要望します。
事業② 安全飛行等の要望
� 周辺住民の不安を軽減するため、安全飛行の徹底や騒音の低減について、航空自衛隊入間基地や防衛省など
の関係機関に対して、あらゆる機会を捉えて要望します。また、本市上空を飛行する航空機の増加に対して、
安全飛行の徹底について防衛省などに要望します。
基地第6節
第1項 基地周辺環境整備の推進
■目標・�基地の存在により生じる生活環境への影響について必要な対応を図り、市民が安全に安心して生活できる地域
づくりを推進します。
■現状・�本市には航空自衛隊入間基地が所在し、近隣にはアメリカ空軍横田基地が所在するため、基地を離着陸する航
空機の騒音など、市民は日常生活において有形、無形の影響を受けています。
・�国により、住宅に対する防音工事の実施、公共施設の防音対策に対する補助、また、市民の生活環境の整備に
向けた助成等が行われています。
■課題・�航空機の騒音や、基地が所在することで発生する事故等に対する不安は、基地周辺住民にとって完全に払拭さ
れてはいないため、引き続き騒音対策の拡充や安全飛行の徹底を国に対して求めていく必要があります。
■5年間の取り組み・�航空機の騒音を緩和するため、告示後住宅を含めた住宅防音工事の実施や事務所・店舗の防音工事の拡大を求
めます。
・安全飛行の徹底及び夜間や休日などの時間外における飛行回数の削減による騒音被害の軽減を要望します。
・施設・設備等の整備にあたっては、防衛省が所管する補助金の活用を検討し、計画的に国に対して要望します。
〈事業体系〉
障害防止対策の推進
補助事業等の拡充
航空機騒音対策の推進
安全飛行等の要望
民生安定事業の実施
調整交付金事業の拡充
基地周辺環境整備の推進
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期 目標値
目標 達成値
環境整備に関する要望活動の回数
基地周辺の生活環境を改善するために、活動回数を維持します。
3回 現状維持 現状維持
〈評価項目〉

172
第2編
第5章
173
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
事業② 消費生活情報の提供
� 消費生活講座を開催し、消費者教育や啓発に努めるとともに、広報いるま、市公式ホームページ等を利用し、
消費者に消費生活情報を提供します。
事業③ 消費団体の育成・支援
� 消費者団体が地域において実施する消費生活関係の研究会、講習会、講演会等の自主的活動を育成・支援し
ます。
事業④ 店舗等立入検査の実施
� 消費者の利益を擁護するため、店舗等で販売されている商品について、生命、身体に危害をおよぼす恐れが
多い製品、家庭用品の品質、商品の量目、飲食料品の品質、危害または障害の発生する電気用品の表示につい
て適正かどうか立入検査を実施し、指導・是正を図ります。
◆施策1 消費者の権利の尊重と自立の支援 事業① 消費生活相談の実施
� 国民生活センター及び県消費生活支援センターと連携した消費生活相談を行うとともに、消費生活相談員に
ついては、研修等により資質向上を図り、消費者トラブル相談の的確な対応に努めます。
消費生活第7節
第1項 消費者の権利の尊重と自立の支援
■目標・�悪質商法等の消費者トラブルが起こらないように、消費者自らが消費生活問題に関してさまざまな知識を得て、
自立した消費者となるような情報の提供や啓発を行うとともに、消費者の相談体制の充実を図ります。
・�商品の表示等を確認する立入検査を実施することで、消費者が安心して商品を購入できるような社会の実現を
目指します。
■現状・�新たな悪質商法は次々と出現しており、未然防止に向けて広報いるま、市公式ホームページ等による情報提供
を行い、相談対応については国民生活センターや県消費生活支援センターと連携して実施しています。
・消費者団体が行う消費生活に関する講演会等の事業に対して補助をしています。
・�立入検査については、消費生活用製品安全の表示、家庭用品品質の表示、商品の量目、飲食料品の品質、危害
及び障害の発生する電気用品の表示について、店舗内商品を確認し、店舗への違反指導を実施しています。
■課題・�消費者トラブルに対処するには、個々の消費者が自主的に行動することが必要であり、消費者に対して的確に
情報提供することや相談窓口の充実が求められています。
・�高齢化により会員が減少する傾向にある消費者団体について、若い消費者を取り込み、消費者の自立に向けた
事業の実施を行っていくことが課題となっています。
・消費者の安全・安心の確保を図るため、立入検査事業の充実が課題となっています。
■5年間の取り組み・�消費生活に関する相談に対応することにより、市民の消費生活における権利及び利益を確保するとともに、消
費者被害の未然・拡大防止を図ります。
・�複雑多岐にわたる消費生活上の諸問題に対応できるように適切な知識や情報の提供を行い、消費者意識の向上
を図ります。
・消費者団体による消費生活関係の講習会等の自主事業の支援に努めます。
・商品の安全等の表示が適正であるかを確認するため、店舗等の立入検査を行います。
消費者の権利の尊重と自立の支援 消費生活相談の実施
消費生活情報の提供
消費団体の育成・支援
店舗等立入検査の実施
〈事業体系〉
消費者の権利の尊重と自立の支援
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期 目標値
目標 達成値
相談件数相談件数を増やすことで、自立した消費者を増やします。
1,140件 1,500件 1,500件
店舗立入検査等件数商品の安全性を確保するために、検査件数を増やします。
20件 23件 25件
消費者団体の講習会等の実施件数
消費者の自立を支援するために、実施件数を増やします。
19件 20件 21件
〈評価項目〉
消費生活相談件数の推移
900
1,200
1,500(件)
H18 H19 H20 H21 H22
1,248
1,140 1,168
1,141
1,272
消費生活講演会

172
第2編
第5章
173
第2編
第5章
安全で安心してくらせるまち第5章
事業② 消費生活情報の提供
� 消費生活講座を開催し、消費者教育や啓発に努めるとともに、広報いるま、市公式ホームページ等を利用し、
消費者に消費生活情報を提供します。
事業③ 消費団体の育成・支援
� 消費者団体が地域において実施する消費生活関係の研究会、講習会、講演会等の自主的活動を育成・支援し
ます。
事業④ 店舗等立入検査の実施
� 消費者の利益を擁護するため、店舗等で販売されている商品について、生命、身体に危害をおよぼす恐れが
多い製品、家庭用品の品質、商品の量目、飲食料品の品質、危害または障害の発生する電気用品の表示につい
て適正かどうか立入検査を実施し、指導・是正を図ります。
◆施策1 消費者の権利の尊重と自立の支援 事業① 消費生活相談の実施
� 国民生活センター及び県消費生活支援センターと連携した消費生活相談を行うとともに、消費生活相談員に
ついては、研修等により資質向上を図り、消費者トラブル相談の的確な対応に努めます。
消費生活第7節
第1項 消費者の権利の尊重と自立の支援
■目標・�悪質商法等の消費者トラブルが起こらないように、消費者自らが消費生活問題に関してさまざまな知識を得て、
自立した消費者となるような情報の提供や啓発を行うとともに、消費者の相談体制の充実を図ります。
・�商品の表示等を確認する立入検査を実施することで、消費者が安心して商品を購入できるような社会の実現を
目指します。
■現状・�新たな悪質商法は次々と出現しており、未然防止に向けて広報いるま、市公式ホームページ等による情報提供
を行い、相談対応については国民生活センターや県消費生活支援センターと連携して実施しています。
・消費者団体が行う消費生活に関する講演会等の事業に対して補助をしています。
・�立入検査については、消費生活用製品安全の表示、家庭用品品質の表示、商品の量目、飲食料品の品質、危害
及び障害の発生する電気用品の表示について、店舗内商品を確認し、店舗への違反指導を実施しています。
■課題・�消費者トラブルに対処するには、個々の消費者が自主的に行動することが必要であり、消費者に対して的確に
情報提供することや相談窓口の充実が求められています。
・�高齢化により会員が減少する傾向にある消費者団体について、若い消費者を取り込み、消費者の自立に向けた
事業の実施を行っていくことが課題となっています。
・消費者の安全・安心の確保を図るため、立入検査事業の充実が課題となっています。
■5年間の取り組み・�消費生活に関する相談に対応することにより、市民の消費生活における権利及び利益を確保するとともに、消
費者被害の未然・拡大防止を図ります。
・�複雑多岐にわたる消費生活上の諸問題に対応できるように適切な知識や情報の提供を行い、消費者意識の向上
を図ります。
・消費者団体による消費生活関係の講習会等の自主事業の支援に努めます。
・商品の安全等の表示が適正であるかを確認するため、店舗等の立入検査を行います。
消費者の権利の尊重と自立の支援 消費生活相談の実施
消費生活情報の提供
消費団体の育成・支援
店舗等立入検査の実施
〈事業体系〉
消費者の権利の尊重と自立の支援
評価項目名 目標値設定の考え方 現状値 後期 目標値
目標 達成値
相談件数相談件数を増やすことで、自立した消費者を増やします。
1,140件 1,500件 1,500件
店舗立入検査等件数商品の安全性を確保するために、検査件数を増やします。
20件 23件 25件
消費者団体の講習会等の実施件数
消費者の自立を支援するために、実施件数を増やします。
19件 20件 21件
〈評価項目〉
消費生活相談件数の推移
900
1,200
1,500(件)
H18 H19 H20 H21 H22
1,248
1,140 1,168
1,141
1,272
消費生活講演会