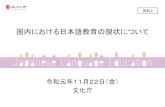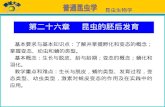教育基本法 (平成十八年十二月二十二日 法律第百二十号) ·...
Transcript of 教育基本法 (平成十八年十二月二十二日 法律第百二十号) ·...
<図書館と関係法令> 日本国憲法 教育基本法(昭和22年) 社会教育法(昭和24年) 図書館法(昭和25年) 博物館法(昭和26年)
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年)
2
(1) 教育基本法の改正について
①(旧)教育基本法制定の経緯
「教育ニ関スル勅語」発布(明治23年10月30日) 終戦(昭和20年8月15日) 日本国憲法の公布(昭和21年11月3日) 施行(昭和22年5月3日)
6 旧教育基本法の制定(昭和22年3月31日)
1(1)②教育基本法の改正について
7
旧教育基本法の制定 (昭和22年3月31日公布・施行)
新しい教育諸制度の構築・整備
教育改革国民会議(平成12年)
中央教育審議会における審議(平成13~15年)
与党教育基本法に関する協議会(平成15~18年)
教育基本法改正 (平成18年12月22日公布・施行)
改正に向けた主な議論
制定後約60年 はじめての改正
教育をとりまく環境の変化
社会全体 家庭 学校 地域社会 子ども
<教育を取り巻く環境の変化>
8
社会
家庭 学校 地域社会
子供
●科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化 ●価値観の多様化 ●社会全体の規範意識の低下 等
●教育力の低下 ●育児に不安や悩み を持つ親の増加等
●いじめ、校内暴力 などの問題行動 ●質の高い教員の 確保 等
●教育力の低下 ●近隣住民間の連帯 感の希薄化 ●地域の安全、安心 の確保の必要性
●基本的生活習慣の乱れ ●学ぶ意欲の低下や学力低下傾向 ●体力の低下 ●社会性の低下、規範意識の欠如等
(参考)旧法制定時と法改正当時の社会状況変化 事項 旧法制定当時 当時(平成18年度)
総人口 7,810万1千人(S22) 1億2,775万7千人(H17) 平均寿命 (男) 50.06歳(S22)
(女) 53.96歳(S22) (男) 78.53歳(H17) (女) 85.49歳(H17)
合計特殊出生率 4.54(S22) 1.26(H17) 総人口に占める 65歳以上人口
4.8%(S22)
20.1%(H17)
高校進学率 42.5%(S25) 97.7%(H18) 大学進学率 10.1%(S30) 52.3%(H18) 外国人学生数(大学等) 4,703 人(S35) 10万4,427 人(H17) 第一次産業 (農業、林業、漁業)
48.5%(S25)
4.8%(H17)
第二次産業 (鉱業、建設、製造業)
21.8%(S25)
26.1%(H17)
第三次産業 (サービス業)
29.6%(S25)
67.2%(H17) 9
○教育改革国民会議(平成12年) 「教育改革国民会議報告-教育を変える 17の提案」を報告
・人間性豊かな日本人の育成 ・一人ひとりの才能を伸ばし創造性に富む人間の育成 ・新しい時代に新しい学校づくり ・教育振興基本計画と教育基本法
<改正に向けた議論>
10
○臨時教育審議会(昭和59~62年)
○中央教育審議会における審議 (平成13年~平成15年)
(21世紀の教育が目指すもの) ①自己実現を目指す自立した人間の育成 ②豊かな心と健やかな体を備えた人間の育成 ③「知」の世紀をリードする創造性に富んだ人間の育成 ④新しい「公共」を創造し、21世紀の国家・社会の形成に主体
的に参画する日本人の育成 ⑤日本人の伝統・文化を基盤として国際社会を生きる教養ある
日本人の育成
11
(中間報告後)国民からの意見募集、全国5会場で公聴会、 有識者・団体等ヒアリング
(教育基本法改正の必要性と改正の視点)
21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から、重要な教育の理念や原則を明確にするため、改正する。
<改正の視点>
・信頼される学校教育の確立
・「知」の世紀をリードする大学改革の推進
・家庭の教育力の回復、学校・家庭・地域
社会の連携・協力の推進
12
<改正の視点(続き)>
・「公共」に主体的に参画する意識や態度の 涵養 ・日本の伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する 心と国際社会の一員としての意識の涵養 ・生涯学習社会の実現 ・教育振興基本計画の策定
13
国会における論点 (第164回通常国会、第165回臨時国会)
• 改正の必要性 • 憲法改正との関係 • 国民的議論が不十分ではないか • 「我が国を愛する態度」について、学校における指導や評価の在り方、「態度」ではなく「心」を扱うべきではないか
等
15
どのような人間の育成を目指すか前文の改正や教育の目標等などを通じて明確化。
・知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって
自己実現を目指す自立した人間
・公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的
に参画する国民
・我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を
生きる日本人
教育の目標や生涯学習の理念などを規定。
③主な改正点
16
教育の目標を新設(第2条)
「公共の精神」「伝統と文化を尊重」「環境の保全に寄与する態度」 など
教育に関する重要事項として新たに条を設け規定
生涯学習の理念、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力、教育振興基本計画
19
前文
第1章 教育の目的・理念
・教育の目的・理念の明示
・「生涯学習の理念」「教育の機会均等」を規定
第2章 教育の実施に関する基本
「義務教育」、「学校教育」、「教員」、「社会教育」、
「政治教育」、 「宗教教育」、「大学」、「私立学校」、
「家庭教育」、「幼児期の教育」、
「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」
21
(2) 教育基本法の構成
第3章 教育行政
・教育行政における国と地方公共団体の役割分担、
教育振興基本計画の策定等
第4章 法令の制定
・この法律の諸条項を実施するための必要な法令
の制定について規定
22
(2) 教育基本法の構成
1(3)図書館関連の主な規定
①教育の目標(第2条) 【新設】
②生涯学習の理念(第3条)【新設】
③家庭教育(第10条)【新設】
④社会教育(第12条)
⑤学校、家庭及び地域住民等の
相互の連携協力(第13条)【新設】
⑥教育行政(第16 条)
⑦教育振興基本計画(第 17 条)【新設】
23
25
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲 げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と 道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自 律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んず る態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共 の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度 を養うこと。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛すると ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
①教育の目標(第2条)【新設】 教育の目的を実現するための5つの努力目標を規定
26
① 基本的事項
… 知(知識・教養)・徳(情操・道徳)・体(健康な体)
② 主に自分自身に係ること
… (例)個性を尊重する教育を行うこと、創造性を培うこと、 勤労を重んずる態度を養うこと
③ 主に社会とのかかわりに係ること
… (例)男女平等、公共の精神に基づく社会参画
④ 主に人としての生存や、自然との共生に係ること
… (例)環境保全
⑤ 主に日本人として、国際社会とのかかわりの中で 必要となること … (例)伝統と文化の尊重、他国の尊重
5つの努力目標とは
「生涯学習の理念」を教育に関する基本的な理念として規定。
「生涯学習社会」
• その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習できる社会
• その成果を適切に生かすことのできる社会
29
②生涯学習の理念(第3条)【新設】
生涯教育① 「生涯学習のために自ら学習する意欲と能力を
養い、社会の様々な教育機能を相互の関連性を考慮しつつ総合的に整備・充実しようとするのが生涯教育の考え方」、
「国民一人一人が充実した人生を送ることを目指して生涯にわたって行う学習を助けるために、教育制度全体がその上に打ち立てられるべき基本的理念」
(昭和56年中教審答申「生涯教育について」)
31
「生涯教育の必要は、現代のごとく変動の激しい社会では、いかに高度な学校教育を受けた人であっても、次々に新しく出現する知識や技術を生涯学習しなくてはならないという事実から、直接には意識されたのであるが、生涯教育という考え方はこのように生涯にわたる学習の継続を要求するだけでなく、家庭教育、学校教育、社会教育の三者を有機的に統合することを要求している。」
(昭和41年社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」)
32
生涯教育②
保護者が子供の教育について第一義的責任を
有することを規定
国や地方公共団体が家庭教育支援に努めるべきことを規定
(参考)図書館法 (平成20年改正で追記)
第三条 図書館奉仕の留意事項
「家庭教育の向上に資することとなるように」
※家庭教育は、本来、保護者の自主的な判断によって、
行われるべきもの。国や地方公共団体が介入すべき
ことではない。
※行政が行うのは「支援」
33
③家庭教育(第10条)【新設】
(社会教育)
第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会に
おいて行われる教育は、国及び地方公共団体
によって奨励されなければならない。 ※改正により下線部を新たに規定
34
④社会教育(第12条)
国や地方公共団体により社会教育が奨励されなければならない旨を明記。
現代的課題の例
生命、健康、人権、豊かな人間性、
家庭・家族、消費者問題、地域の連帯、
まちづくり、交通問題、高齢化社会、
男女共同参画型社会、科学技術、
情報の活用、知的所有権、国際理解、
国際貢献・開発援助、人口・食糧、環境、
資源・エネルギー等 生涯学習審議会「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について(答申)」
(平成4年)
36
国や地方公共団体による社会教育の振興方策を例示(ハード⇒ハード+ソフト)
38
④社会教育(第12条)
(社会教育) 第12条 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民 館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の 利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当 な方法によって社会教育の振興に努めなければ ならない。 ※改正により下線部を新たに規定
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めることを規定
<例>
放課後子ども教室(地域と学校の連携) 等
40
⑤学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力(第13条) 【新設】
教育基本法改正を受けた主な動き
学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育職員免許法、教育公務員特例法の改正(平成19年7月)
社会教育法、図書館法、博物館法の改正(平成20年6月)
教育振興基本計画の策定(平成20年7月)
43
<生涯学習・社会教育関係動向>
教育基本法改正(平成18年12月)後の動向
(1)中央教育審議会答申
「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策 について
~知の循環型社会を目指して~(答申)」(平成20年2月)
(2)社会教育法等の改正 (平成20年6月)
(3)教育振興基本計画(第一期)の策定 (平成20年7月)
(4)「中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」
(平成25年1月)
※ここで指摘された課題について現在検討中
(5)教育振興基本計画(第二期)の策定 (平成25年6月)
2 中央教育審議会答申と教育振興基本計画について
44
(参考)中央教育審議会
(所掌事務) 文部科学大臣の諮問に応じて、人材の育成やスポーツの振興に関する重要事項を調査審議し、文部科学大臣に意見を述べること 等
(構成) ・委員 30名以内 ・5分科会 (このほか、必要に応じて部会を設置)
中央教育審議会 概要 HP
45
(1)中央教育審議会答申
「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策
について~知の循環型社会を目指して~
(答申)」平成20年2月19日
第Ⅰ部 今後の生涯学習の振興方策
第Ⅱ部 施策を推進するにあたっての行政の在り方
46
第Ⅰ部 今後の生涯学習の振興方策について 国民一人一人の生涯を通じた学習への支援 ○多様な学習機会の提供、再チャレンジが可能な環境の 整備
(社会教育施設等を活用した多様な学習の場の充実) 地域独自の課題や公共の課題など、民間に よっては提供されにくい分野の学習支援のため、 図書館等の社会教育施設を機能強化
(相談体制の充実) 社会教育施設等において、起業や就業、ボランティア 活動、社会参加等新たなチャレンジをしようとする人 に対する学習相談や、学習機会を提供。
48
社会全体の教育力向上 ○社会教育施設のネットワーク化 -公民館、図書館、博物館等の活用-
(地域の教育力向上のための社会教育施設の活用)
地域が抱える様々な教育課題への対応、社会の要請が高い
分野の学習や家庭教育支援等、地域における学習拠点・
活動拠点としての取組を推進することが必要。
図書館では
・レファレンスサービスの充実と利用促進 ・課題解決支援機能の充実 ・多様な情報源への入り口「地域のポータルサイト」へ ・学校図書館への支援
49
施策を推進する際の留意点
3つの視点に留意すること
①「個人の要望」と「社会の要請」のバランスの視点
②「継承」と「創造」等を通じた持続可能な社会の発展を目指す視点
③連携・ネットワークを構築して施策を推進する視点
50
第Ⅱ部 施策を推進するに当たっての行政の在り方 2.今後の行政等の在り方
(2)社会教育を推進する地域の拠点施設の在り方
51
(社会教育施設全般)
・地域課題に対応するために、関係者、関係機関で横断的なネットワークを築き、特定の機能を持たせること。社会教育施設が地域のネットワークの拠点、連携を促進するコーディネーターになること
・計画・実践・評価・改善のサイクル(「PDCA サイクル」)の着実な実施と地域住民等への情報提供
⇒運営状況の自己評価、改善を図る努力義務、
地域住民等への情報提供についての努力義務を課すこと
(司書等の在り方)
・司書・司書補の資格要件の見直し
・研修の充実
・各図書館での研修等の実施
52
生涯学習・社会教育の推進を支える人材の在り方
(図書館) ・住民の個人的な学習支援という従来の役割に加え、地域の 課題解決、医療・健康、福祉、法務等に関する情報や地域 資料等、地域の実情に応じた情報提供サービス
・「知の拠点」として質量両面の充実
社会教育を推進する地域の拠点施設の在り方
(3)教育振興基本計画について
(平成20年7月1日閣議決定)
教育基本法第17条に基づき政府として初めて策定した計画
教育基本法に示された教育の理念の実現に向けて、今後10年間を通じて目指すべき教育の姿を明らかにするとともに、今後5年間に取り組むべき施策を総合的・計画的に推進するもの
54
(参考)教育基本法 (教育振興基本計画) 第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的 な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本 的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本 的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなけれ ばならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に 応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に 関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
55
今後10年間を通じて目指すべき教育の姿
①義務教育修了までに、すべての子どもに、自立して 社会で生きていく基礎を育てる ・公教育の質を高め、信頼を確立する ・社会全体で子どもを育てる
②社会を支え、発展させるとともに、国際社会をリード する人材を育てる ・高等学校や大学等における教育の質を保証する ・「知」の創造等に貢献できる人材を育成する。こうした 観点から、世界最高水準の教育研究拠点を重点的 に形成するとともに、大学等の国際化を推進する。
56
4つのビジョン(基本的方向性)、8のミッション(成果目標)、
30のアクション(基本施策)を掲げる(配布資料参照)。
57
http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/09/19/1339769_1_2.pdf
社会を生き抜く力の養成 ~多様で変化の激しい社会での個人の自立と協働~ 未来への飛躍を実現する人材の養成 ~変化や新たな価値を主導・創造し、社会の各分野を牽引していく人材~ 学びのセーフティネットの構築 ~誰もがアクセスできる多様な学習機会を~ 絆づくりと活力あるコミュニティの形成 ~社会が人を育み、人が社会をつくる好循環~
第二期教育振興基本計画の概要 (平成25年6月14日閣議決定:平成25~29年度の計画)
【教育行政の4つのビジョン】
資料P.8
第2期教育振興基本計画(図書館関係)
○個々人が、社会の中で自立して、他者と連携・協働しながら、生涯にわたって 生き抜く力 や地域の課題解決を主体的に担うことができる力を身につけられる ようにする。 ○このため、現代的・社会的な課題に対応した学習や、様々な体験活動及び読書 活動が主体的な実践につながるよう、各学校や公民館、図書館等の社会教育 施設による提供のみならず、一般行政や民間等の多様な提供主体とも連携して、 推進する。
基本的な考え方
成果目標 3 生涯を通じた自立・協働・創造に向けた力の修得
基本施策 11 現代的・社会的な課題に対応した学習等の推進
【基本的方向性 1】 社会を生き抜く力の養成
○(略)家庭の経済的格差の教育格差への影響や格差の再生産・固定化が指摘されてい ることを踏まえ、挫折や困難を抱えた子ども・若者(例えば、若年無業者、引きこもり、高 校中退者など)や非正規労働者・早期離職者が自立し、再び社会に参画できるようにす るため、福祉・労働・保健・医療行政等と緊密に連携・協力し、学習支援や体験活動の 実施、キャリアアップや学び直しの機会の提供等を行う。 (主な取組) 「貧困の連鎖」防止等に向けた多様な主体と連携した学習支援等 関係行政機関、NPO等が連携して行う地域の公民館、図書館等を活用した若者の 自立・社会参画支援の取組を推進 等
基本的な考え方
成果目標 6 意欲ある全ての者への学習機会の確保
基本施策 18 学習や社会生活に困難を有する者への学習機会 の提供など教育支援
【基本的方向性 3】 学びのセーフティネットの構築
<基本施策 20> ○ 活力あるコミュニティが人々の学習を支え、生き抜く力をともに培い、人々の学習がコミュニティを 形成・活性化させるという好循環の確立に向けて、地域の教育資源を結びつけ、学校や公民館等を 拠点とした多様な人々のネットワーク・協働体制を確立する必要がある。
○ (略)学校や公民館等の社会教育施設をはじめとする学びの場を核にした地域コミュニティの形成を 目指した取組を推進する。(以下略) <基本施策22> ○(略)地域や学校をはじめとする豊かなつながりの中で、家庭教育が行われるよう、親子の育ちを応 援する学習機会を充実するとともに、コミュニティの協働による家庭教育支援を強化する。
基本的な考え方
成果目標 8 互助・共助による活力あるコミュニティの形成 基本施策 20 絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた 学習環境・協働体制の整備推進
基本施策 22 豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実
【基本的方向性 4】 絆づくりと活力あるコミュニティの形成
都道府県・政令指定都市・中核市における 教育振興基本計画策定状況
(平成24年3月現在)
・策定済み
43都道府県、18政令指定都市、27中核市
・今後新たに策定、または他の計画の見直しにより策定
を予定 7件
(1)新たに基本計画を策定する予定 2県1市
(2)既存の計画の見直しにより策定する予定 1府
・未定または検討中 1県
61
(参考)
全国の市区町村の策定状況
(政令指定都市・中核市を含む1720市区町村対象)
策定済み 898(52.2%)
今後新たに策定、または他の計画の見直し により策定を予定 241(14.0%)
未定または検討中 581(33.8%)
62
出典:文部科学省ホームページhttp://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/plan/1295603.htm
自治体の教育振興基本計画もぜひ見てみてください例
(4) 「第6期中央教育審議会生涯学習分科会における 議論の整理」(平成25年1月)
第1章 今後の社会教育行政等の推進の在り方について
1.社会の変化の中で求められるもの
2.社会教育の役割
3.今後の社会教育行政の取組の方向性
4.生涯学習振興行政の調和・統合機能の強化
第2章 今後の生涯学習・社会教育の振興の具体的方策
について
5つの柱に基づく具体的方策
63
社会教育行政が抱える課題
①地域コミュニティ変質への対応
②多様な主体による社会教育事業の展開への対応
③社会教育の専門職員の役割の変化への対応
取組の方向性
「自前主義」からの脱却
→「ひらく・つながる・むすぶ」機能の発揮
・様々な機関との連携・協働の推進
関係行政部局 初等中等教育機関
高等教育機関 民間団体
・連携・協働を推進するための体制の整備等
⇒ネットワーク型行政の推進
65
1.絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた学習 活動や体制づくりの推進 (2)学びの場を核にした地域コミュニティの形成の推進 公民館等社会教育施設(学びの場)を核とした地域コミュニティ形成の推進 (4)豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実 乳幼児期の子育て家庭を対象とした支援充実のため、図書館等の社会教育施設にお ける学習機会の提供のみならず、保健・福祉分野とも連携して多様な学習機会を提供
2.現代的・社会的課題に対応した学習機会及びライフ ステージに応じた学習機会の充実 (1)現代的・社会的課題に対応した学習の推進 ・現代的・社会的な課題に対応した学習機会の充実やその学習成果を生かした地域 課題の解決に取り組む公民館等に対する支援を行うことも有効 ・学習機会の提供にあたっては、社会教育施設での講座等の提供のみにとどまらず、 首長部局・大学等・民間団体・企業等の様々な主体とも連携・協働することが重要
〔図書館関係〕
3.社会生活を円滑に営む上で困難を有する者への学習機会 の充実 (1)子ども・若者への学習支援 学校や公民館、図書館等を中核として、地域若者サポートステーションなどの多様な 主体と連携・協働しつつ、子ども・若者の居場所を提供し、社会生活を円滑に営む上 で困難を有する者への学び直しや社会参画、自立を支援する体制を構築
第2章 今後の生涯学習・社会教育の振興の具体的方策について
「大学図書館の整備について」(審議のまとめ) (平成22年12月科学技術・学術審議会学術分科会
研究環境基盤部会 学術情報基盤作業部会)
(3)大学図書館に求められる機能・役割
④他機関・地域等との連携及び国際対応
○ 大学図書館の役割を果たすためには、学内の多様な
組織との連携の他、学外の関連機関との連携も重要。
また、MLA連携や公共図書館との連携も重要。
68
(次回 意見交換) 今後の生涯学習・社会教育について 「図書館と様々な機関の連携・協働について -ネットワーク型行政の推進に向けて-」
個人の学習支援や課題解決支援に向けた、 所属する図書館と様々な機関との 連携・協働の在り方について 現状と課題、実践事例、意見 等
69
参考 ・田中壮一郎監修 教育基本法研究会編著
『逐条解説 改正教育基本法』第一法規(2007)
・鑓水三千男 『図書館と法』日本図書館協会(2009)
・文部科学省ホームページ「教育基本資料室」
http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm
・同上「教育振興基本計画」
http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/
・中央教育審議会「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策
について~知の循環型社会の構築を目指して~」(答申) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1216131_1424.html
・中央教育審議会生涯学習分科会「中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/toushin/1330378.htm
・文部科学省生涯学習政策局社会教育課平成25年度社会教育主事講習資料
70