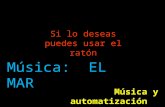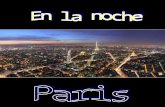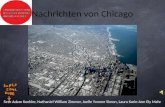EMSAN/JSSA GRM における 1970 年以前の邦人...
Transcript of EMSAN/JSSA GRM における 1970 年以前の邦人...
先端芸術音楽創作学会会報 Vol.4 No.3 pp.17–20
研究報告
EMSAN/JSSAデータベース報告―GRMにおける 1970年以前の邦人作曲家の仕事について―
水野みか子Mikako Mizuno名古屋市立大学
Nagoya City University
概要
JSSA は 2012 年7月、データベース委員会を立ち上げ、EMSAN のデータベース・プロジェクトに共同研究者という形で参加することを決めた。これにより、それまで JSSA メンバー数名が個人として参加してきた EMSAN データベース研究に対して、組織としての JSSA が携わることとなった。本発表では、EMSAN/JSSA データベース研究会の概要とともに、2012年 12月時点でのデータベースの形態とデータの量を報告し、ヒストリカルなデータ確認調査の一部について考察する。
1. はじめに
本発表は、ソルボンヌ大学MINT-OMF (Musicologie,Informatique et Nouvelles Technologies / ObservatoireMusical Francais, Universite Paris-Sorbonne)と JSSAの研究者による電子音響音楽データベース構築プロジェクト <EMSAN/JSSA データベース > に関して、その研究体勢とシステム構築の概要、日本人作品やテキストの整理状況を報告するとともに、電子音響音楽作品を対象とするカタログやデータベースを包摂するという意味で EMSAN と共通する組織である GRM における邦人作曲家関連の資料について、それをどのように読み、アジア電子音響音楽分野の研究に組み込みうるかについて考察するものである。JSSA データベース委員会は、これまで、EMSANのフランス側研究者との合同会議を含めて4回のミーティングを行い、データベースの構造やアイテム内容・定義について議論してきた。今回の発表は、それら研究会での議論を踏まえてのものである。
2. <EMSAN DATABASE>の研究体勢現状とシステム概要
<EMSAN database>は、非アジア圏を含む音楽学研究者がアジアの電子音響音楽研究にとりくむための基
礎資料となることを目的に、現在作成されつつあるカタログ形式のデータベースである。データベースの形態としては、電子音響音楽作品とそれに関するテキスト(writings)について関連諸項目の情報が、書き込みと読み取り、ともにオンライ上で可能なオープンソースとなることを目指している。
<EMSAN database>の構築は、2008年から進められている国際プロジェクトであり、これまでに台湾、中国に関して、CHEARSやWOCMATなどが一定の基盤を作ることに成功し、システム構築やデータ収集方法に関して方向性を暗示できる段階にまで進んできた。一方、日本の電子音響音楽に関するデータベース化は、2008年という出発点は同時期でありながら、研究チーム体勢やファイナンシャルな問題から具体化が遅れ、2012 年になってようやく成果が見え始めたところである。音楽作品に関するカタログ作成の研究は、「データベース」という用語が情報処理技術の応用分野のひとつを意味することが一般的になった今日の時代趨勢においてさえ、参照項目やコンテンツ記述用語などに関する規定のフレームワークに則った資料を収集する人文系歴史研究であるという局面は、未だ十全に保持されている。この意味で、電子音響音楽に関するデータベース研究はJSSAに適合する学際的研究分野の一つである。歴史研究や資料収集という人文系学問方法の蓄積を持たない JSSAが <EMSAN database>の日本側研究母体となった背景には、データベース化対象の音楽作品が「電子音響音楽」であり、そこには必然的に音響学や情報処理のテクノロジーの調査が必要である、という明確な理由がある。加えて、対象が、歴史研究というにしては、せいぜい 60年くらいの短いタイムスパンに限定されているので、音楽学に限定した研究としてはあまり重点が置かれない、という状況もある。しかしながら、2008年以来の 4年間に、東アジアの他の国に比べて日本での電子音響音楽データベース研究が後手に回った大きな理由は、中国、韓国、台湾に比べて、日本には (1970年以前の)初期電子音響音楽作品が圧倒
– 17–
先端芸術音楽創作学会会報 Vol.4 No.3 pp.17–20
的な存在感を占めていることである。しかも、そうした50~60年代への音楽学からのアプローチは、同時代の、電子的手段を用いない作品と同じ土壌で、いわば共時的音楽文化の広がりの中でのみ考察されてきたのである。音声信号処理や演奏アンサンブルで生起する生体信号や動作情報の処理といった音楽情報処理の <技術 >の変遷を <音楽史 >の事象として記述するためには、音楽学は、減算合成やフーリエ変換に代表される音声信号処理の諸用語やインターフェイス、インタラクティヴ・デザイン、マッピング・ストラテジーなどといった、技術のシチュエーションを枠づける用語以外に、かつての音楽理論や表現・美学の受容と変容を規定できるような用語やコンセプトを獲得せねばならない。そうした面での議論や論考が未だ十分でないため、電子音響音楽のデータベースでは、音楽作品を記述する共通基盤となるべきパラメータとして何を設定できるか、という根本的な問題から出発する必要があった。このラディカルな問題への対処法の第一として、EM-
SAN/JSSA データベース研究チームは、まずは、作品数の多さからすれば格段に活気的な、1990 年代以降の電子音響音楽を記述するのに必要なパラメータを設定し、遡って、それを 1950~60年代のミュジック・コンクレートやテープ作品に当てはめる方法を検討した。日本の電子音響音楽の通史が存在しないので、第二の対処法として、包括性を目指した先行研究を参照する方法を採った。すなわち、日本の電子音響音楽を西欧にむけて通史的視野で語った柴田南雄などのわずかな例を除いて、包括的な日本電子音響音楽作品関連の研究や論考は少ないのであり、楽譜という伝搬メディアを持ちにくい電子音響音楽に関する作品情報が海外に知られるには、管弦楽や室内楽とは異なる経路で、かつ、作曲家や中小組織の草の根的経路を辿る場合が多い。ごく一部の電子音響音楽作品は放送等を通じて西欧でもきわめて知名度が高いが、多くの作品は詳細が不明なままであり、通史としてもイメージがつかみにくい、という感慨を欧米の会議で聞くこともしばしばであった。そこで、1960 年代までのアジアの電子音響音楽にかんする欧語による包括的カタログとして、Hugh Davies の <Repertoire International desMusiques Electroacostiques> を参照した。そこでは、compositeur, titre de l’oeuvre, fonction, date, duration,pistes, appendices, notesといったパラメータ・アイテムが提示され、< fonction>のアイテムは(図1)のように分類された。
Davies のカタログは、頒布こそ MIT Press であるものの、O.R.T.F に属していた時代の、ポワンカレ通りの GRM(Le Groupe de Recherches de l’O.R.T.F, 5,Avenue de Recteur Poincare)とニューヨークの Indepen-dent Electronic Music Center(Trumansburg) の協力で出
図 1. Daviesのカタログにおける< fonction>アイテム
版されているのであり、当時の GRM資料が日本関連の作品データにも影響を与えたことは明らかである。
<EMSAN/JSSAデータベース >において、著作や音楽作品に関する関連項目の数と内容は、当該データベースを特徴づける最も重要な基礎構築部分であるが、この点に関して、EMSAN データベースは、Daiviesのカタログを念頭に置き、EMFや ZKMなど、現在・近未来の作品まで視野に入れた、類似の対象領域を持つアーカイヴを参照している。
3. 電子音響音楽のデータベース項目
EMSAN/JSSAデータベースは、大きくは writingsとmusical works という二つのジャンル分かれ、それらに関する editorial boards へのコンタクト、ヘルプの項目が付されている。
Writingsのジャンルでは、行番号(各著作アイテムに一つずつ対応)、入力作業タグ(change, remove, duplicate)、タイム・スタンプ(最終更新日)、著者名(ローマ字表記、原語表記)、著作タイトル(欧語または欧語翻訳、原語または原語訳、transliteration)、出版者(社)、出版年、出版地、ドキュメント・メディアの形式、原語の言語、データ入力者、備考(コメント)、アブストラクトのコラムが用意されている。
Musical works のジャンルでは、Davies の 1967 年カタログを土台としながら、電子テクノロジーの進展に伴うメディアの変化や社会全般におけるコミュニケーション手段や情報技術の浸透度によって作品提示形態が変化してきた状況を、作品コンセプトや美学と重ね合わせて組み直している。作品タイトルは、日本語や中国語などの原語、欧語(英語)訳、そして原語発音をローマ字で表記する translit-eration という、原則三種類の表記で記入される。アジア初演を記入し、アジアの作曲家による作品でもアジア以外の地域でのみ演奏されたものは、ここが空欄となる(図2)。テクノロジー関連項目は 1950 年から 2010 年までの作品をカバーするために、できる限り多くの選択肢を含むものであり、作品によっては、ほとんどの項目が空欄になることもありうる。
– 18–
先端芸術音楽創作学会会報 Vol.4 No.3 pp.17–20
図 2. EMSAN database 編集の一画面
音楽学的な資料検討が必要な作品も多く、データベースへの入力が難しいものもある。例えば、丹波明の電子音響音楽作品として、ボードレールによる《二つの詩》(1966)と《エチュード第二番、バッハへのオマージュ》(1964、アニメーションのための音楽) が入力されており、この二作品はいずれも GRMで制作されたものであるが、実は丹波氏が GRMで制作したと思われる電子音響音楽には、他に、下記がある。
1. Music for the film《9 Pieces》 9 min. , 1964.2. Music for TV《Interlude》 5min20. , 1964.3. Music for the film《Morphogrammes 0》4min30.
, 1965.4. Music for the film《Goya》 3 min. , 1966.5. Music for the film《Inconnue d’Orly》 10 min.,
1966.
データベースに入力するには、これらの作品についての資料研究が必要である。そのため、次章では GRMの資料状況一般を述べた上で、邦人作品に関する問題点を指摘する。
4. GRM資料の成り立ちと邦人作品の記録
1958 年の GRM 設立から 1960 年代前半まで、シェフェールが収集した音響素材は、ベルナール・バシェが率いるグループ・メンバー有志によって分類・整理され、Mireille Chamass-Kyrouの統括責任のもと、シェフェールの著書『音楽オブジェ論』や『音響オブジェのソルフェージュ』において系統的に論じられることとなる。1963 年から 65 年まで、集団的に獲得されたソルフェージュの基盤(le groupe solfege)は、バシェの教育課程で見いだされた優れた音楽家としての BeatrizFerreyra やエンジニアの Guy Reibel によって受け継がれた。ウニヴェルシテ通りのスタジオの地下に《騒音のエチュード》のオリジナル磁気テープがあるのを見つけた Genevicve Mche は Francois Bayle と共同で 30 年の長きにわたり責任を持って管理保管と整理に努めた。
1964年、Bourdanセンターに GRMが移ったとき、ベイルによって創設された <phonothque> は、音響記録の番人 (phonothcaire) としての Genevieve Mache のもと、世界初の音響作品アーカイヴとして組織され、音響作品そのものと作品に関連するテキスト、写真、メモ、スコア、コンサート評、録画を管理してきた。音響作品という新しいメディアの保管・管理のために、「視覚的にわかりやすい」整理法が優先され、音楽作品をラジオ放送や会議その他の音のドキュメントとは区別するための「カートン付きボックス」の中でインデックス化するという方法が採られた。このインデックスが 2001年のデジタル化作業まで使われたのである。この指標は三つのアルファベット文字と数字の組み合わせで構成されている。第一の文字 K,L,M は、磁気テープのスピードによって、それぞれ、19cm/s、38cm/s、76cm/sに該当する。第二以下のアルファベットは、録音されたスタジオのイニシャルを示し、数字はプロダクションの時代順を示している。DATや CDの導入時には、同様に、DUR、CDURなどが始まる (図 3)。
GRMにおけるかつてのデータ整理のインデックス化の方法を邦人作品にあてはめて照合した。アルファベット三文字の指標によると、先に挙げた丹波作品のうち、1、2は、それぞれ、SUR989と SUR340である。これらはフィルムやテレビの権利があって音楽作品としては公表されていない。GRMドキュメント係の Jean-Baptist Garcia氏によれば、3に関する情報は現在 Garcia氏がアプローチできる範囲には無い。
図 3. 丹波明に関する GRM手書きカード
さらに、丹波が GRMで制作し、かつ、GRMには記録・保存されているが日本で伝えられていないものとして、(表1)の三つがある。このうち《Enrich.Sono-Dram》と《Le No Mus.Orient.》はラジオで放送したものであり、後者は、タイトルから、「能」を紹介したものと推察される。
Mche/Tamba《Synergies》は、現在の GRMドキュメ
– 19–
先端芸術音楽創作学会会報 Vol.4 No.3 pp.17–20
htb
表 1. 丹波明の創作記録
Enrich. LUR1932Sono-DramaLe No Mus.Orient. 12 LUR2138Plac 30 ??Mche/Tamba 1962 7’44 LUR2092, SUR282Synergies
ント関係者がバイブルと呼ぶ RepertoireAcousmatique1948-1980によると、Bernard Macheがリードして集団作品 (Mcheの作品)として完成させたものとして記録されている。また、平義久の《Hierophnies 》は SUR738、《Hi-
erophnies 》は LUR2335 で同定されているが、前者はウニヴェルシテ通りでステレオ録音されたテープにあり、後者は 38cm/sのモノラル 1/4インチの磁気テープに録音されたものである。誤記をどの時点で修正するかについては、現在のドキュメント担当者の仕事範囲にはなく、《Microphonie》と示された平の作品は《Hiero-phonie》であると推察されるが、この誤記修正はすぐには反映されない。言い換えれば、この場合、作曲者という一次レヴェルでは《Hierophonie》が正しいあろうと推測されるが、GRM の <phonotheque> で記述されてきた、という二次レヴェルにおいては《Microphonies》が事実として残されているということになる。
GRMドキュメントのチーフである Evelyne Gayouによると、こうした、現在の整理状況で不明、もしくは誤記の可能性が出てきた場合には、GRMディレクター室の「ボックス引き出し」に戻る方法がある。「ボックス引き出し」のカード分類は以下のようになっている。
• GRMの機材やスタジオで創作した作品•「GRMの人」とその他という分類• ラジオで放送した作品 • E(etrangre)の印づけ
また、篠原真の作品について、「GRMアーカイヴ」として、つまり、GRMの制作ではなく他の場所で制作されたものの音源として、カールスルーエ ZKMから送られた <Memoire> と <Personnage> が CD で存在しているが、篠原真に関するカード記録はいずれも ER語尾のインデックス(海外制作作品)を持ち、GRMでの篠原の作業記録情報は、現時点でアプローチ可能な範囲には無い。
5. ヒストリカル作品についての今後の EMSAN/JSSAデータベース研究のタスク
EMSAN がアジアのオリジナル言語を伝えつつ西欧語圏の音楽学に資することを目的としていることに立ち返ってみれば、今後の EMSAN/ JSSA データベース研究のタスクとして以下のように整理できる。a. データベース作成作業は、中・長期的には、オープンソースとして読み取り・書き込み双方が可能なものとするが、現時点では、特定の editorial membersが、カタログ・アイテムの固定と入力作業のルールを確定している時点にある。b.最小限のデータが確定できて、上演された記録のある作品を優先すべきである。c.将来の音楽学研究に資することを目的としながら、現時点ですでに音楽学的研究を必要としているので、データベース作成作業と並行してこうした個別作業を行う必要がある。現時点で必要性が確認され、かつ、着手可能である事柄として下記の 4 点(c-1.~c-4.)を指摘することができる。c-1. 手書きの書き込みを含む Daiviesの情報を、日本音楽の西洋における受容の事項として検討する。c-2. 日本語で参照できる日本側(一次)資料を確認する。c-3. GRMを始めとする既存アーカイヴを確認する。c-4. 翻訳:邦人作品に関する用語の訳に関連して、作曲者自身への確認とともに、これまでに受容されてきているスタンダード・カタログとしての Davies の訳語との照合を行う。註)1967年、<Electronic Music Review> 第 2/3号
(4月/7月)として出版された。Daviesは 1980年代までに、出版カタログに手書きで多くの修正を書き込んでいる。
6. 著者プロフィール
水野みか子 (Mikako MIZUNO)
日本交響楽振興財団作曲賞、アルス・ポエティカ音楽祭などに入賞・入選。ブールジュ国際電子音響音楽祭、CERPS、ISEA、ISCMはじめ欧米各地の音楽祭、放送、作品保存などで取り上げられている。音楽学分野では、音楽理論、電子音楽、音楽の空間性などをテーマに研究している。名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授。
JSSAメンバーを中心とする「日本の電子音響音楽に関するデータベース構築の研究」は、サントリー文化財団の助成を受けています。
– 20–