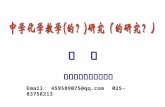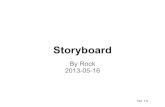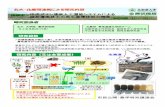家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究...― ―165...
Transcript of 家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究...― ―165...

― ―165
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
本研究の目的は会社員を対象として家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクト、仕事への動
機づけとの関連を検討することであった。家族構造には「結びつき」「利害的関係」「勢力」「開放性」
という4因子が用いられ、父・母・子の三者関係において測定された。
調査対象者はある企業に勤める子どもを持たない男性109名、子どもを持つ男性118名、子どもを
持たない女性101名、子どもを持つ女性22名の計350名で質問紙による調査を行った。子どもを持
たない男女は子どもの視点として家族構造を測定され、子どもを持つ男女は親の視点として家族構
造を測定された。分析の結果、男女という性別及び子ども視点・親視点という立場の違いそれぞれ
において家族構造の各因子がワーク・ファミリー・コンフリクトや仕事への動機づけに与える影響
が異なることが示された。これらの結果は、性別や立場によって重視すべき家族の特性や関係性が
変わることを意味している。
キーワード:�家族構造、ワーク・ファミリー・コンフリクト、仕事への動機づけ、子ども視点と親視点
【問題・目的】 近年、女性の社会進出化などの新しい社会的な流れは、労働の環境や形態にも大きな変化を与え、
同時に新しい問題も起こした。その1つが少子化問題であろう。若島ら(2008)は労働と少子化問題
の関連について、大学生の男女と仕事を持つ社会人の男女を対象とした調査において、仕事を持ち
ながら結婚している女性は子どもを出産することに対するリスクを高く認知し、さらに子どもに対
する志向性も低下しやすいことを示した。これは、仕事と家庭の両方に対する負担が出産意欲を低
*東北大学大学院教育学研究科准教授 **東北大学大学院教育学研究科研究生 ***立正大学大学院心理学研究科修士課程****東北大学大学院教育学研究科博士課程前期
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
若 島 孔 文*
野 口 修 司**
狐 塚 貴 博***
板 倉 憲 政****
宇佐美 貴 章****
黒 澤 泰****
閏 間 理 絵***

― ―166
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
下させている可能性を示唆している。これに伴い、女性の負担を減らすために男性の育児休暇を推
奨するなど様々な試みが行われているものの、未だ多くの問題を抱えていると言えるだろう。この
ような状況の中、日本のみならず多くの国々において仕事と家庭の調和に注目した制度や施策が行
われており、代表的なものとして「ファミリー・フレンドリー」や「ワーク・ライフ・バランス」など
が挙げられる。
1. ファミリー・フレンドリーとワーク・ライフ・バランス
まずファミリー・フレンドリー(以下 FF)とは1980年代に米国で用いられるようになった「仕事
と家庭生活の両立」に基づいた考え方であり、FF 制度の具体的内容としては育児休暇や介護休暇
などを含む家庭事情における休暇制度やフレックスタイム制度といった柔軟な勤務形態、所定外労
働の免除などが挙げられる。FF 制度導入の効果についてはいくつかの研究が行われており、例え
ば松田(2005)は FF 制度が整備されていない職場に勤める女性は無職女性よりも苦痛(distress)が
高いのに対して、FF 制度が整備されている職場に勤める女性はそうではないことを述べている。
さらに藤本(2004)は FF 制度が整備された職場で働く男女は組織での働きがいが高まり、離転職の
可能性が低下するのに対し、整備されていない職場では全く逆の影響が示されたことを明らかにし
た。この結果を踏まえて、藤本(2004)は FF が経営戦略や人事戦略の面においても効果が期待でき
ることや、女性だけではなく男性に対しても効果的であることを述べている。
次にワーク・ライフ・バランス(以下 WLB)とは1990年代後半からイギリスで用いられるように
なった「仕事と(仕事以外の)生活を両立する施策」のことである。脇坂(2007)はWLBが伝統的な「仕
事と家庭の両立」論と異なる点として、従業員のニーズにかなうだけでなく、企業にとっても利益
になるという意味で「win–win」の状況をもたらすことを挙げている。また FF と WLB に関して、
脇坂(2007)や渡井(2007)は両者の言葉に大きな違いは無いものの、FF は特に家庭に軸を置いた概
念であるのに対して、WLB は家庭のみではなく、自己啓発や地域活動、そして独身の男女、定年前
の高齢者をも含めたより広い概念であることを述べている。
わが国でも、2007年に男女共同参画会議がワーク・ライフ・バランスに関しての提言をまとめて
いる。その報告書の中で、この概念を「老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓
発など様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態」と定義した。さらに、①あら
ゆる人のためのもの、②人生の段階に応じて、希望する「バランス」を決める事ができる、③「仕事
の充実」と「仕事以外の生活」の好循環をもたらすと3つの要素に整理している。Frone(2003)はレ
ビューの中でワーク・ファミリー(ライフ)・バランスを方向の側面(仕事→家庭、家庭→仕事)と内
容(葛藤:一方の役割の要求が他方の役割の要求に反すること、促進:家庭(もしくは仕事)によって
得られたもしくは発展された経験や、スキル、機会の効力(virtue)によって、仕事(もしくは家庭)
の参加がより簡単になること)と定義している。さらに、Frone(2003)はこの分野においての研究は、
原因(WLB の促進要因、阻害要因は何か?)、結果(WLB であることは一対どのような結果になる
のか?)、戦略(企業や個人がどうやって WLB を高めることができるのか?)�の3側面から研究が

― ―167
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
進んでいると述べている。一方でこのような仕事と家庭の要因に関して、両者間における葛藤に注
目した概念として「ワーク・ファミリー・コンフリクト」が挙げられる。
2. ワーク・ファミリー・コンフリクト
ワーク・ファミリー・コンフリクト(以下 WFC)とは仕事と家庭間の葛藤のことであり、「仕事役
割と家庭役割が相互にぶつかり合うことから発生する役割間葛藤」であると定義されている(渡井,
2007)。WFC に関して、例えば加藤(2002)は WFC への対処として夫婦一体の対処行動が有効な対
処の一つと示唆したが、その前提条件として夫婦の関係性において認識が一致していること、勢力
が均衡であることを挙げている。また、加藤・金井(2007)は共働き家庭における WFC のうち、女
性では時間葛藤と家庭-仕事葛藤が不満足感や精神的不健康に直接つながり、男性では、選択葛藤
が不満足感や精神的不健康に直接つながることを示した。これは就労者としては同じ立場であった
としても、男女によって影響される葛藤要因が異なることを示している。さらに渡井(2007)は日本
における少ない先行研究をまとめた上で、幼児期の子どもを持つ女性労働者において抑うつの関連
要因となっていること、夫のサポートが葛藤に対する緩衝要因となっていることや、海外の先進国
と比較して日本女性の WFC の高さや精神的健康度との関連が際立っていることなどを挙げてい
る。Greenhaus ら(1985)は WFC が「仕事から家庭への葛藤」と「家庭から仕事への葛藤」の2方向
があり、さらに「時間」、「ストレス反応」、「行動」の3つの形態を含めた6次元により構成されると
定義している。この定義に基づき Carlson ら(2000)が開発したのが多次元的 WFC 尺度であり、こ
の尺度は渡井ら(2006)により日本語版による標準化が行われている。
3. 家族の構造
ここまで仕事と家庭に関する概念について述べてきたが、次に家庭に関する要因、特に家族の構
造について説明する。家族の構造、機能については数多くの理論が存在し、数多くの要因が取り上
げられてきた。最初にこれまで提唱されてきた理論において検討された要因について概括する。ま
ず Olson ら(1979)の円環モデルでは家族システムを理解するために、結びつき、柔軟性、コミュニ
ケーションの三点の検討をくわえることがあげられている。また、Skinner ら(2000)による家族機
能のプロセスモデルでは課題の達成(Task�accomplishment)、役割の遂行(Role�Performance)、コ
ミュニケーション、情緒表現、かかわり、統制、規範・価値(Values�and�Norms)の7領域の相互関係
によって家族の構造が理解できるとしている。最後に Beavers�&�Hampson(2000)の家族機能のシ
ステムモデルでは遠心的―求心的という家族スタイルと家族の有能性(Family�Competence)の2つ
が家族機能の理解に重要としている。このようにこれらの理論で扱われている要因には類似してい
るものもあれば独自のものもあるなど、参考すべき理論の選択には考慮が必要であった。
これらに対し、狐塚ら(2008)は上記の理論を含めた現在の家族研究において、家族アセスメント
に用いられている11の尺度を参考に246項目の質問紙を作成し、より強い関連を示している要因が
何であるのかを検討した。その結果、第1パターンとして「結びつき」「利害的関係」「勢力」「葛藤」

― ―168
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
「ルール」「開放性」「統制力」「社会的興味」の8因子を抽出し、その中でも特に信頼性の高い第2パター
ンとして「結びつき」「利害的関係」「勢力」「開放性」の4因子を抽出した。一方で野口(2008)は家族
を1つの全体として捉えるのでなく、父―母、父―子、母―子という3つそれぞれの二者関係に関して、
「結びつき」の程度の高・中・低から家族の構造を分類した。その結果、構造の違いにより家族満足
度や家族内ストレスに差が見られることを明らかにしたものの、「結びつき」という一要因から分類
することの限界についても指摘した。本研究では狐塚ら(2008)において第2パターンとして提案さ
れている「結びつき」「利害的関係」「勢力」「開放性」の4因子を取りあげる。「結びつき」とは家族内
でのお互いの愛情や仲の良さ、親密さ、まとまり、「利害的関係」とは家族という集団の形態維持や
各自が自分自身の利害においてのみ関わる家族との関係性、「勢力」とは家族内における権威や決定
力、影響力、「開放性」とは家族が家族以外の人とどれだけ関わっているのか、をそれぞれ意味して
いる。
4. 仕事に対する動機付け
本研究では仕事に対する動機付けについても取り上げる。Deci(1975)の内発的動機づけの観点
から検討を加えた Senécal ら(2001)によると、仕事に対する内発動機づけに影響をあたえる要因と
して雇用者から自律性を重んじられていると感じることが挙げるれている。同時に家庭生活に対す
る内発的動機づけを高める要因としてパートナーから大事にされることを挙げており、家庭、仕事
それぞれに対する動機づけはそれぞれの領域における要因によって高められやすいとしている。さ
らに Michel�&�Hargis(2008)は仕事に対する満足感に関して仕事要因と家庭要因があたえる影響
について調べたところ、仕事に従事し熱中する度合いなどの仕事要因が仕事満足感にあたえる影響
が家庭要因にくらべて非常に大きいことを示した。
このように仕事に対する動機づけについては、仕事領域における要因のはたらきの占める割合が
大きいことが示されてきているものの、仕事―家庭領域における主要なパラダイムである葛藤理論
(Conflict�theory,�例えば Greenhaus�&�Powell,�2006)では仕事と家庭の関係はゼロサムゲームであ
るとしている。つまり、人は限られた資源しか有していないため、家庭、もしくは仕事に用いた資
源や時間は他方に費やすことはできないと考える。この考え方にもとづくと、家庭生活に資源、時
間を費やすことで動機づけを含め仕事に負の影響があらわれると考えることは可能であろう。また、
最近提唱されるようになったパラダイムとして強化理論(Enrichment�theory,�例えば Greenhaus�&�
Powell,�2006)がある。Greenhaus�&�Powell(2006)によると、家庭が仕事によい影響をあたえるメ
カニズムのひとつとして心身のエネルギーの源としての家庭生活のはたらきを挙げている。この強
化理論の立場をふまえると家庭生活の充実と仕事への動機づけには関連が見られるだろう。
Brummelhuis ら(2008)は仕事でバーンアウトしやすくなる要因として仕事のプレッシャーや仕事
時間とならんで買い物や洗濯などの家事の時間が多さと0歳から6歳の幼い子どもがいることを挙
げている。この知見は家庭の影響が仕事へのモチベーションに影響をあたえることを示す一例であ
ろう。

― ―169
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
WFC と仕事意欲との関連について、金井・若林(1998)は女性のパートタイマーを対象として適
度な WFC が仕事意欲を最も高める一方で、WFC が高すぎても低すぎても仕事意欲が低下してい
くことを明らかにした。以上のことからも、家族の構造と WFC の関連に仕事動機づけを加えるこ
とは十分に有効であると言えるだろう。
5. 本研究の目的
以上から、WFC に関して夫婦関係という家庭要因から検討されてきた研究はあるものの、子ど
もを含めた三者間の関係から関連を検討した研究は行われていないと言える。また、狐塚ら(2008)
が明らかにした家族の構成因子を用いることで野口(2008)が課題として挙げていたより複数の要
因から関連を検討することが可能となるだろう。そこで本研究では狐塚ら(2008)の第2パターンに
おける「結びつき」「利害的関係」「勢力」「開放性」の4因子を参考にし、家族の構造と WFC、さらに
は仕事に対する動機付けとの関連を検討することを目的とする。
先にも述べたように、加藤(2002)は WFC への対処に関して夫婦の関係性における認識の一致と、
夫婦関係の勢力が均衡であることの重要性を述べている。これを狐塚ら(2008)の家族構成因子に
関連させた場合、夫婦関係の認識が一致していることはお互いの葛藤が少なくなり、不一致の場合
には葛藤が多くなってくることが考えられる。これにより夫婦間の結びつきにも差が生まれること
が予想されるだろう。また勢力に関して、加藤(2002)ではパートナーよりも勢力が低いか、あるい
は同程度かの比較が行われているが、当然パートナーよりも勢力が高い場合の関係性も考えられる。
その際、相手よりも優位な状況にあるため、勢力による葛藤は少ないことが考えられるだろう。よっ
て以下の仮説が成り立つ。
仮説1:�家族の結びつきが強い場合、結びつきが弱い場合と比べて WFC が低くなり、仕事に対する
動機付けが高くなるだろう。
仮説2:�両親間の勢力においてパートナーよりも勢力が高い場合や同程度の場合、パートナーより
も勢力が低い場合と比べて WFC が低くなるだろう。
また加藤(2002)では夫婦関係の良し悪しに関わらず、他のサポーターの存在によって WFC に対
する対処が可能であることを述べている。これは狐塚ら(2008)における開放性に当てはまると言
えるだろう。よって次の仮説が成り立つ。
仮説3:�調査対象者個人の開放性が高い場合、開放性が低い場合と比べて WFC が低くなるだろう。
以上の仮説を検討するとともに、他の変数に関しても探索的に検討する。

― ―170
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
【方法】 質問紙による調査を実施した。調査期間は2008年9月~ 12月で調査対象者は単体従業員数13000
人程度、連結従業員数93000人程度の企業 A の男女社員。質問紙の構成は、①家族構造として父―母、
父―子、母―子という三者関係を基本として「結びつき」「利害的関係」「勢力」「開放性」を問う項目、
②渡井ら(2006)の「WFC 尺度日本語版」18項目、③田尾(1984)の仕事への動機付けを問う尺度7項
目が用いられた。家族構造を測定する項目は野口(2008)の測定法を参考に、「結びつき」「利害的関
係」「勢力」「開放性」の程度を1(弱い)~ 10(強い)の10件法にて回答してもらった。また父・母・子
という3つの二者間における家族構造を測定するため、各因子の特徴に従い「結びつき」については
二者間の程度(例:父―母間の結びつきの程度)、「利害的関係」「勢力」については二者がそれぞれ
相手に対して持っている程度(例:父から母に対する利害的関係の程度と、母から父に対する利害
的関係の程度)、「開放性」については、家族の各個人が持っている程度(例:父が持っている開放性
の程度、母が持っている開放性の程度)をそれぞれ測定した。さらに、家族構造を測定する項目につ
いては子どもの有無によって、子どもを持たない場合には自分を子どもの立場とした父・母・子(子
が調査対象者)の関係について回答してもらい、子どもを持つ場合には自分を親の立場とした父・母・
子(父・母のいずれかが調査対象者)の関係について回答してもらった。また、子どもを持つ人にお
いては第一子、第二子、第三子等、各子どもとの関係にそれぞれにおいて回答してもらった。欠損
等を除外した結果、子どもを持つ男性118名(平均39.90歳)、子どもを持たない男性109名(平均
32.23歳)、子どもを持つ女性22名(平均36.26歳)、子どもを持たない女性101名(平均32.08歳)の計
350名(平均34.90歳)のデータを分析に使用した。
【結果】1. 因子分析及び信頼性分析
まず、WFC尺度18項目に対して天井効果およびフロア効果の検討を行った後、主因子法・バリマッ
クス回転による因子分析を行った。その結果、4因子構造が妥当であると判断された(Table�1)。累
積寄与率は65.15%であった。
第1因子は6項目で構成されており、「職場で、有効かつ必要な態度や行動は、家庭ではむしろ逆
効果だろう」や「家庭で、問題をうまく解決する行動は、職場では有用でないように思う」といった、
一方での効果的な行動が他方には効果的ではないだろうという行動に対する効力感が関連している
項目により構成されていた。そこで第1因子を「行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤」因子(α
= .92)と名づけた。
第2因子は3項目で構成されており、「職務を果たすのに多くの時間を使うため、家族との活動が
できないことがある」や「自分が家族と過ごしたい時間を、思っている以上に仕事にとられる」と
いった仕事の時間が家庭での活動に与える影響に関する項目により構成されていた。そこで第2因
子を「仕事の時間に基づく家庭への葛藤」因子(α= .87)と名づけた。
第3因子は3項目により構成されており、「仕事から帰ったとき、精神的に疲れきっていて、家族

― ―171
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
のために何もすることが出来ないことがよくある」や「職場でのストレスのために、家に帰っても自
分の好きなことさえ出来ないことがある」といった仕事によるストレスが家庭での活動に与える影
響に関する項目により構成されていた。そこで第3因子を「仕事のストレスに基づく家庭への葛藤」
因子(α= .83)と名づけた。
第4因子は3項目により構成されており、「家庭でのストレスのために、職場でも家族のことが頭
を離れないことがよくある」や「家族と時間を過ごすために、自分のキャリアアップに役立つ職場で
の活動に時間をかけられないことがよくある」といった家庭での時間やストレスが仕事へ与える影
響に関する項目により構成されていた。そこで第4因子を「家庭の時間・ストレスに基づく仕事へ
の葛藤」因子(α= .73)と名づけた。
なお、仕事への動機付けに関する項目については田尾(1984)において1因子として用いられてい
たことや、主因子法・バリマックス回転を行った結果も1因子による構造が妥当であると判断され
たため、そのように用いた。信頼性分析の結果、7項目でα= .73であった。
2. 第1子・第2子間における家族構造因子の比較
次に2人以上の子どもを持つ男女において、調査対象者と第1子・第2子間における家族構造因子
に差があるのかを比較するため対応のあるt検定を行った。なお、3人以上の子どもを持つ親のサ
ンプルが少なかったため、第1子と第2子のみの比較とした。その結果、全ての因子において第1子
と第2子の間において有意差、有意傾向ともに示されなかった。本分析においては第1子と第2子に
おいて違いが認められなかったため、これ以降の分析では子どもを持つ人の群における子どもの
Table�1 ワーク・ファミリー・コンフリクト尺度の因子分析結果(バリマックス回転後の因子負荷量)項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性
職場で、有効かつ必要な態度や行動は、家庭ではむしろ逆効果だろう。 .86 .11 .14 .14 .80
職場では効果的な行動は、良い親や配偶者となるには役に立たない。 .81 .13 .06 .12 .69
家庭で、問題をうまく解決する行動は、職場では有用でないように思う。 .80 .09 .16 .18 .71
家庭ではうまくいく行動が、職場では効果的でないように思う。 .76 .10 .15 .15 .63
仕事の際に使う問題解決行動は、家庭での問題解決には効果的でない。 .73 .07 .18 .21 .61
家庭では有効かつ必要な態度や行動は、職場ではむしろ逆効果だろう。 .68 .18 .10 .17 .54
職務を果たすのに多くの時間を使うため、家族との活動ができないことがある。 .11 .91 .18 .12 .88
自分が家族と過ごしたい時間を、思っている以上に仕事にとられる。 .16 .86 19 10. .82.
仕事に時間が取られるため、仕事と同様に家庭での責任や家事をする時間が取りにくい。 .13 .59 .38 .08 .51
仕事から帰ったとき、精神的に疲れきっていて、家族のために何もすることが出来ないことがよくある。
.15 .14 .75 .18 .64
仕事から帰ったとき、くたくたに疲れていて、家族といろいろなことをしたり、家族としての責任が果たせないことがよくある。
.20 .44 .73 .12 .78
職場でのストレスのために、家に帰っても自分の好きなことさえ出来ないことがある。 .24 .35 .57 .23 .56
家庭でのストレスのために、職場でも家族のことが頭を離れないことがよくある。 .23 .06 .09 .77 .66
家庭での責任からくるストレスがよくあるので、仕事に集中するのが難しいことがある。 .17 .06 .22 .69 .56
家族と時間を過ごすために、自分のキャリアアップに役立つ職場での活動に時間をかけられないことがよくある。
.25 .29 .10 .48 .38
因子寄与 3.94 2.43 1.81 1.59 9.77
累積寄与率 26.25 42.43 54.53 65.15

― ―172
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
データとして、第1子のデータのみを用いることとする。
3. 家族構造因子間における相関
次に子どもを持たない人と子どもを持つ人のそれぞれにおいて、家族全体に関する家族構造因子
間の相関分析を行った(Table�2・3)。なお、今後は子どもの有無によって変わる回答の視点に従い、
子どもを持たない人は子ども視点の男女、子どもを持つ人は親視点の男女と表記する。家族構造因
子については家族全体の程度を算出するため「結びつき」については父―母、父―子、母―子の程度
を合計して3で割った値を家族全体の結びつき得点とした。「利害的関係」「勢力」についてはまず二
者間で互いに示されている程度を合計して2で割ることで二者間における程度とした(例:父から
母に対する利害的関係と母から父に対する利害的関係の程度を合計して2で割ったものが父―母間
における利害的関係の程度)。次にそれぞれ算出した3つの二者間の程度をさらに合計して3で割っ
たものを家族全体の利害的関係、勢力の得点とした。「開放性」については父・母・子がそれぞれ持っ
ている開放性の程度を合計して3で割ったものを家族全体の開放性得点とした。それぞれの平均値
(標準偏差)は子ども視点の男女では結びつきが6.91(2.25)、利害的関係が5.14(2.67)、勢力が5.89
(1.78)、開放性が5.75(2.32)であり、親視点の男女では結びつきが8.44(1.69)、利害的関係が5.96(3.11)、
勢力が6.81(1.41)、開放性が6.08(2.05)であった。分析の結果、子ども視点の男女では全ての因子に
おいて有意な正の相関が示されたが、親視点の男女では「結びつき」と「勢力」、「利害的関係」と「勢
力」においてのみ有意な正の相関が示され、それ以外の結果は示されなかった。
4. 性別(男性・女性)×視点(子ども視点・親視点)におけるWFC、仕事への動機付けの比較
次に調査対象者の性別と視点による違いを検討するために、性別(男性・女性)×視点(子ども視点・
Table�2 子ども視点の男女における家族構造因子の相関分析結果
結びつき 利害的関係 勢力 開放性 平均値 SD
結びつき .15* .59** .36** 6.92 2.25
利害的関係 .36** .28** 5.14 2.67
勢力 .32** 5.89 1.78
開放性 5.75 2.32
*p < .05,�** p< .01
Table�3 親視点の男女における家族構造因子の相関分析結果
結びつき 利害的関係 勢力 開放性 平均値 SD
結びつき .11 .41** .15 8.44 1.69
利害的関係 .32** .15 5.96 3.11
勢力 .13 6.81 1.41
開放性 6.08 2.05
**p < .01

― ―173
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
親視点)を独立変数とし、WFC因子、仕事への動機付け因子を従属変数とした二要因分散分析を行っ
た(Table�4)。その結果、「仕事の時間に基づく家庭への葛藤」因子では性別に10%水準の有意傾向(F
(1,345)=3.69,�p < .10)と視点に5%水準の有意差(F(1,345)=3.93,�p < .05)が示され、男性は女性
よりも仕事の時間に基づく家庭への葛藤が有意に高い傾向があること、親視点は子ども視点よりも
同様の葛藤が有意に高いことが示された。「仕事のストレスに基づく家庭への葛藤」因子では視点
に10%水準での有意傾向(F(1,345)=2.87,�p < .10)が示され、子ども視点は親視点よりも仕事のス
トレスに基づく家庭への葛藤が有意に高い傾向があることが示された。それ以外では有意差・有意
傾向共に示されなかった。
5. 家族構造各因子の群わけにおけるWFC、仕事への動機付けの比較
子ども視点の男女、親視点の男女別に家族構造因子の群わけを独立変数、WFC と仕事への動機
付けを従属変数としたt検定及び分散分析を行った(Table�5 ~ 15)。
結びつき・開放性においては度数から高群、低群にそれぞれ群わけし、独立したt検定を行った。
利害的関係・勢力においては二者関係において一方の値から他方の値を引き、値が+・0・-のいず
れになるかによって3群に分類した上で一元配置分散分析を行った(例:父から母に対する利害的
関係から母から父に対する利害的関係を引き、結果が+になれば利害的関係の父・高位群、0になれ
ば父母・同位群、-になれば母・高位群として分類した)。
まず男性・子ども視点に関して、家族の結びつきと開放性の高群・低群においてはどの従属変数
にも有意な差は認められなかった。利害的関係では、父―子間の「仕事のストレスに基づく家庭へ
の葛藤」において10%水準の有意傾向(F(2,105)=2.53,�p < .10)が認められた。多重比較の結果、子・
高位の群が父子同位の群よりも仕事のストレスに基づく家庭への葛藤が有意に低い傾向が示され
た。勢力では、父―子間の「行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤」において10%水準の有意傾
向(F(2,106)=2.61,�p < .10)が示された。多重比較の結果、父・高位の群が子・高位の群よりも行
動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤が有意に低い傾向が示された。また、母―子間の「仕事の
時間に基づく家庭への葛藤」において10%水準の有意傾向(F(2,106)=2.52,�p < .10)及び「仕事の
ストレスに基づく家庭への葛藤」において5%水準(F(2,106)=4.63,�p < .05)の有意差が示された。
多重比較の結果、仕事の時間に基づく家庭への葛藤、仕事のストレスに基づく家庭への葛藤のどち
Table�4 性別(男性と女性)と視点(子ども視点と親視点)による二要因分散分析結果性 別 男 性 女 性
性別 視点 交互作用視 点 子ども視点 親視点 子ども視点 親視点
平均値 (SD) 平均値 (SD) 平均値 (SD) 平均値 (SD) F 値 F 値 F 値
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 16.03 5.60 15.23 5.18 15.10 5.00 14.95 4.69 0.72 n.s. 0.44 n.s. 0.21 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 8.83 3.78 9.56 3.36 7.70 3.31 8.86 3.77 3.69 † 3.93 * 0.21 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 8.93 3.36 7.96 3.01 8.97 3.40 8.45 3.11 0.38 n.s. 2.87 † 0.27 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.72 2.88 6.17 2.37 6.13 2.55 6.59 2.28 0.06 n.s. 0.02 n.s. 2.11 n.s.
仕事への動機づけ 20.36 5.85 22.68 5.23 20.40 5.70 20.32 5.55 2.38 n.s. 2.22 n.s. 2.53 n.s.† p < .10,*p < .05

― ―174
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
らにおいても母子・同位の群が子・高位の群よりも有意に葛藤が低いことが示された。
Table�5 �男性・子ども視点における家族の利害的関係に関する一元配置分散分析及び多重比較結果(二者それぞれが高位、二者が同位の3群間比較)
父 – 母・利害的関係 父 – 子・利害的関係父・高位
(n =11)父母・同位(n =86)
母・高位(n =12) F 値 多重比較
父・高位(n =25)
父子・同位(n =67)
子・高位(n =16) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 17.18(8.78) 15.88(5.31) 16(4.24) 0.26 n.s. 14.64(5.66) 16.54(5.25) 15.44(6.46) 1.15 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 7.82(3.82) 8.77(3.81) 10.25(3.47) 1.26 n.s. 8.80(3.85) 8.96(3.82) 8.75(3.61) 0.03 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 7.45(3.56) 9.06(3.30) 9.33(3.58) 1.21 n.s. 8.96(3.46) 9.37(3.36) 7.31(2.70) 2.53 † 子・高位<
父子・同位家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.55(3.83) 6.7(2.71) 7.08(3.34) 0.12 n.s. 6.32(2.41) 6.96(3.07) 6.44(2.87) 0.53 n.s.
仕事への動機づけ 19.36(7.86) 20.4(5.53) 21(6.52) 0.23 n.s. 22.12(5.67) 19.61(5.98) 20.88(5.45) 1.75 n.s.
母 – 子・利害的関係母・高位
(n =24)母子・同位(n =68)
子・高位(n =17) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 14.71(7.08) 16.72(4.89) 15.12(5.81) 1.42 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 8.46(4.18) 8.57(3.76) 10.41(3.04) 1.78 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 8.21(3.44) 9.25(3.39) 8.65(3.12) 0.92 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.25(3.21) 6.76(2.87) 7.24(2.49) 0.60 n.s.
仕事への動機づけ 20.42(6.89) 20.03(5.70) 21.59(4.99) 0.48 n.s.† p < .10
Table�6 �男性・子ども視点における家族の勢力に関する一元配置分散分析及び多重比較結果(二者それぞれが高位、二者が同位の3群間比較)
父 – 母・勢力 父 – 子・勢力父・高位
(n =30)父母・同位(n =57)
母・高位(n =21) F 値 多重比較
父・高位(n =26)
父子・同位(n =59)
子・高位(n =24) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 15.90(6.18) 15.60(5.01) 17.10(6.33) 0.55 n.s. 14.27(5.73) 16.07(5.49) 17.83(5.35) 2.61 † 父・高位<
子・高位仕事の時間に基づく家庭への葛藤 9.80(3.97) 8.46(3.41) 8.76(4.30) 1.28 n.s. 9.19(3.75) 8.41(3.67) 9.50(4.12) 0.86 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 9.23(3.74) 8.86(2.97) 8.38(3.71) 0.40 n.s. 8.23(3.06) 8.88(3.21) 9.79(3.95) 1.37 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.43(2.75) 7.21(2.71) 6.00(3.35) 1.65 n.s. 5.73(2.32) 6.95(2.90) 7.25(3.21) 2.17 n.s.
仕事への動機づけ 21.30(6.27) 20.54(5.58) 18.86(5.87) 1.11 n.s. 21.08(5.62) 20.59(5.52) 19.00(6.85) 0.89 n.s.
母 – 子・勢力母・高位
(n =26)母子・同位(n =61)
子・高位(n =22) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 16.08(6.22) 15.79(5.35) 16.64(5.74) 0.18 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 9.23(4.03) 8.18(3.58) 10.18(3.79) 2.52 † 母子・同位
<子・高位仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 9.08(3.43) 8.23(3.09) 10.68(3.48) 4.63 * 母子・同位
<子・高位家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.46(2.42) 6.67(2.89) 7.18(3.40) 0.39 n.s.
仕事への動機づけ 20.81(6.11) 20.74(5.37) 18.77(6.79) 1.01 n.s.† p < .10,*p < .05

― ―175
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
次に男性・親視点に関して、結びつきでは母―子間の「行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤」
において低群は高群よりも葛藤が5%水準で有意に低いことが示された(t(114)=2.03,�p < .05)。
また、開放性では子・開放性の「行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤」と「仕事の時間に基づ
く家庭への葛藤」においてそれぞれ高群は低群よりも各葛藤が10%水準で有意に低い傾向にあるこ
とが示された(t(109)=1.81,�p < .10�及び�t(109)=1.91,�p < .10)。利害的関係では、父―母間の「家
庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤」において10%水準の有意傾向(F(2,111)=2.52,�p < .10)
が認められた。多重比較の結果、父母・同位の群が母・高位の群よりも葛藤が有意に低い傾向が示
された。また父―子間の仕事のストレスに基づく家庭への葛藤において10%水準の有意傾向(F
(2,109)=2.84,�p < .10)が認められた。多重比較の結果、父・高位の群が子・高位の群よりも葛藤が
有意に低い傾向が示された。勢力では、父―母間の「家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤」
において5%水準での有意差が示された(F(2,111)=4.73,�p < .05)。多重比較の結果、父・高位の
群が父母・同位、母・高位の群よりも葛藤が有意に低いことが示された。また、母―子間の「行動の
効力感に基づく仕事・家庭への葛藤」において5%水準での有意差が示された(F(2,105)=3.29,�p
< .05)。多重比較の結果、子・高位の群が母・高位よりも葛藤が有意に低い傾向が示された。
Table�7 男性・親視点における家族の結びつき・開放性に関する t 検定結果(高群・低群間の比較)父 – 母・結びつき 父 – 子・結びつき 母 – 子・結びつき
高群(n=65) 低群(n=52)t 値
高群(n=63) 低群(n=54)t 値
高群(n=67) 低群(n=49)t 値
平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 15.37(5.61) 15.06(4.65) 0.32 n.s. 15.57(5.64) 14.83(4.62) 0.77 n.s. 16.12(5.77) 14.29(3.97) 2.03 *
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 9.57(3.47) 9.54(3.26) 0.05 n.s. 9.71(3.71) 9.37(2.93) 0.55 n.s. 9.64(3.60) 9.55(2.94) 0.14 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 7.83(3.17) 8.12(2.82) 0.51 n.s. 7.90(3.07) 8.02(2.96) 0.20 n.s. 7.91(3.24) 7.96(2.72) 0.09 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.02(2.39) 6.37(2.34) 0.79 n.s. 5.86(2.31) 6.54(2.40) 1.56 n.s. 6.06(2.53) 6.20(2.08) 0.33 n.s.
仕事への動機づけ 22.28(5.43) 23.19(4.97) 0.94 n.s. 22.29(5.87) 23.15(4.37) 0.91 n.s. 22.28(5.32) 23.08(5.02) 0.82 n.s.
父・開放性 母・開放性 子・開放性
高群(n=64) 低群(n=50)t 値
高群(n=70) 低群(n=44)t 値
高群(n=69) 低群(n=42)t 値
平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 14.69(4.93) 15.82(5.53) 1.15 n.s. 14.93(4.92) 15.59(5.67) 0.66 n.s. 14.57(4.86) 16.38(5.54) 1.81 †
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 9.17(3.25) 9.92(3.47) 1.18 n.s. 9.10(3.22) 10.14(3.51) 1.62 n.s. 9.14(3.26) 10.36(3.22) 1.91 †
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 7.73(2.93) 8.30(3.10) 1.00 n.s. 7.69(3.06) 8.45(2.89) 1.33 n.s. 7.74(3.07) 8.52(2.87) 1.34 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.16(2.39) 6.12(2.25) 0.08 n.s. 6.21(2.51) 6.02(1.98) 0.45 n.s. 6.09(2.50) 6.19(1.97) 0.23 n.s.
仕事への動機づけ 23.02(5.21) 22.20(5.23) 0.83 n.s. 22.09(4.90) 23.57(5.61) 1.49 n.s. 22.01(4.80) 23.64(5.67) 1.62 n.s.† p < .10,p < .05*

― ―176
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
Table�8 �男性・親視点における家族の利害的関係に関する一元配置分散分析及び多重比較結果(二者それぞれが高位、二者が同位の3群間比較)
父 – 母・利害的関係 父 – 子・利害的関係父・高位
(n =15)父母・同位(n =77)
母・高位(n =22) F 値 多重比較
父・高位(n =26)
父子・同位(n =63)
子・高位(n =23) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 15.53(6.00) 15.19(5.37) 15.09(4.51) 0.03 n.s. 14.08(4.52) 15.73(5.77) 14.96(4.47) 0.94 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 8.27(3.24) 9.55(3.46) 10.32(3.09) 1.66 n.s. 8.35(3.43) 9.92(3.29) 9.87(3.15) 2.24 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 7.80(3.55) 7.88(3.01) 8.41(2.79) 0.28 n.s. 6.88(2.75) 8.17(3.10) 8.83(2.79) 2.84 † 父・高位<
子・高位
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 5.87(2.10) 5.95(2.36) 7.18(2.44) 2.52 † 父母・同位
<母・高位 5.73(2.63) 6.16(2.26) 6.70(2.24) 1.03 n.s.
仕事への動機づけ 22.73(4.95) 22.35(5.28) 23.27(5.10) 0.28 n.s. 23.23(5.67) 22.43(5.27) 22.17(4.69) 0.29 n.s.
母 – 子・利害的関係母・高位
(n =19)母子・同位(n =74)
子・高位(n =19) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 13.42(4.65) 15.47(5.30) 15.84(5.54) 1.34 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 8.84(4.11) 9.74(3.23) 9.47(2.93) 0.55 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 7.37(3.15) 7.95(3.05) 8.89(2.64) 1.27 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 5.74(2.40) 6.07(2.28) 7.00(2.49) 1.60 n.s.
仕事への動機づけ 23.16(6.04) 22.42(5.39) 22.53(3.64) 0.15 n.s.† p < .10
Table�9 �男性・親視点における家族の勢力に関する一元配置分散分析及び多重比較結果(二者それぞれが高位、二者が同位の3群間比較)
父 – 母・勢力 父 – 子・勢力
父・高位(n =31)
父母・同位(n =48)
母・高位(n =35) F 値 多重比較
父・高位(n =75)
父子・同位(n =29)
子・高位(n =5) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 14.77(6.25) 14.35(5.13) 16.71(4.13) 2.23 n.s. 15.73(5.64) 13.72(3.70) 14.60(3.51) 1.63 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 9.16(3.73) 9.88(3.36) 9.34(2.99) 0.49 n.s. 9.77(3.55) 9.10(2.88) 9.80(1.30) 0.43 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 7.90(3.22) 7.94(2.82) 7.91(3.16) 0.00 n.s. 8.17(3.12) 7.34(2.78) 8.20(2.28) 0.81 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 5.16(2.13) 6.46(2.18) 6.80(2.53) 4.73 *
父・高位<父母・同位、母・高位
6.16(2.38) 5.97(2.16) 8.00(1.58) 1.70 n.s.
仕事への動機づけ 23.23(4.39) 22.42(5.46) 22.89(5.20) 0.25 n.s. 23.01(5.09) 22.62(5.56) 22.40(4.51) 0.08 n.s.
母 – 子・勢力
母・高位(n =73)
母子・同位(n =26)
子・高位(n =9) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 16.03(5.42) 13.92(3.86) 12.33(4.61) 3.29 *
仕事の時間に基づく家庭への葛藤子・高位<母・高位 9.37(3.61) 10.19(2.51) 9.67(3.04) 0.58 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 7.90(3.01) 7.81(2.88) 8.33(3.39) 0.10 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.08(2.37) 6.54(2.08) 6.33(2.65) 0.38 n.s.
仕事への動機づけ 22.85(5.34) 22.69(5.26) 23.11(3.48) 0.02 n.s.† p < .10,*p < .05

― ―177
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
次に女性・子ども視点に関して、結びつきでは母―子間の仕事の時間に基づく家庭への葛藤にお
いて低群は高群よりも5%水準で有意に低いことが示された(t(99)=2.36,�p < .05)。開放性では、
子・開放性の「仕事の時間に基づく家庭への葛藤」において5%水準の有意差(t(99)=2.34,�p < .05)
が、さらに「仕事への動機づけ」において1%水準の有意差(t(99)=2.72,�p < .01)が示され、それ
ぞれ低群が高群よりも有意に低いことが示された。利害的関係では、父―母間の「仕事への動機づ
け」において5%水準での有意差(F(2,98)=3.51,�p < .05)が示されたものの、多重比較では有意な
結果は示されなかった。勢力においても、母―子間の「仕事への動機づけ」で10%水準の有意傾向(F
(2,98)=2.45,�p < .10)が示されたものの、多重比較では有意な差は示されなかった。
Table�10 女性・子ども視点における家族の結びつき・開放性に関する t 検定結果(高群・低群間の比較)父 – 母・結びつき 父 – 子・結びつき 母 – 子・結びつき
高群(n =57)低群(n =43)t 値
高群(n =56)低群(n =45)t 値
高群(n =62)低群(n =39)t 値
平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 15.04(5.26) 15.40(4.54) 0.36 n.s. 15.14(4.70) 15.04(5.41) 0.10 n.s. 15.05(4.99) 15.18(5.08) 0.13 n.s.仕事の時間に基づく家庭への葛藤 7.98(3.45) 7.40(3.14) 0.88 n.s. 7.96(3.27) 7.38(3.37) 0.88 n.s. 8.31(3.45) 6.74(2.87) 2.36 *事のストレスに基づく家庭への葛藤 8.82(3.33) 9.21(3.54) 0.56 n.s. 9.09(3.23) 8.82(3.63) 0.39 n.s. 9.37(3.54) 8.33(3.10) 1.50 n.s.家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.16(2.58) 6.16(2.53) 0.01 n.s. 6.09(2.64) 6.18(2.46) 0.17 n.s. 6.08(2.71) 6.21(2.32) 0.24 n.s.仕事への動機づけ 20.67(5.25) 19.95(6.32) 0.62 n.s. 20.82(5.64) 19.87(5.79) 0.84 n.s. 20.84(5.93) 19.69(5.30) 0.98 n.s.
父・開放性 母・開放性 子・開放性高群(n =47)低群(n =52)
t 値高群(n =47)低群(n =54)
t 値高群(n =47)低群(n =54)
t 値平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 15.32(5.06) 15.17(4.88) 0.15 n.s. 15.34(5.30) 14.89(4.77) 0.45 n.s. 14.85(5.24) 15.31(4.82) 0.46 n.s.仕事の時間に基づく家庭への葛藤 7.94(3.38) 7.58(3.30) 0.53 n.s. 7.57(3.57) 7.81(3.10) 0.36 n.s. 8.51(3.44) 7.00(3.06) 2.34 *仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 9.23(3.30) 8.83(3.54) 0.59 n.s. 8.81(3.27) 9.11(3.53) 0.44 n.s. 9.04(3.36) 8.91(3.46) 0.20 n.s.家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.06(2.59) 6.19(2.52) 5.81 n.s. 0.25(2.35) 6.41(2.71) 1.18 n.s. 6.23(2.66) 6.04(2.47) 0.39 n.s.仕事への動機づけ 20.28(5.67) 20.29(5.76) 0.01 n.s. 19.74(5.65) 20.96(5.73) 1.07 n.s. 22.00(5.45) 19.00(5.59) 2.72 ***p < .05,**p < .01
Table�11 �女性・子ども視点における家族の利害的関係に関する一元配置分散分析及び多重比較結果(二者それぞれが高位、二者が同位の3群間比較)
父 – 母・利害的関係 父 – 子・利害的関係父・高位
(n =16)父母・同位(n =77)
母・高位(n =8) F 値 多重比較
父・高位(n =22)
父子・同位(n =59)
子・高位(n =19) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 14.75(3.97) 15.43(5.09) 12.63(5.76) 1.19 n.s. 14.64(4.17) 15.05(5.08) 15.63(5.88) 0.20 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 8.25(3.66) 7.79(3.29) 5.75(2.25) 1.66 n.s. 7.73(3.35) 7.61(3.23) 7.84(3.72) 0.04 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 9.63(4.16) 9.00(3.28) 7.38(2.67) 1.19 n.s. 8.95(3.67) 8.64(3.30) 9.89(3.43) 0.97 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 5.69(3.05) 6.32(2.48) 5.13(2.10) 1.09 n.s. 6.05(2.54) 6.02(2.64) 6.47(2.44) 0.23 n.s.
仕事への動機づけ 18.06(5.48) 21.21(5.31) 17.25(7.85) 3.51 * n.s. 20.18(4.71) 20.49(6.06) 20.26(5.99) 0.03 n.s.
母 – 子・利害的関係母・高位
(n =18)母子・同位(n =59)
子・高位(n =24) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 15.33(5.05) 15.00(4.53) 15.17(6.18) 0.03 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 7.00(3.43) 8.27(3.30) 6.83(3.09) 2.15 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 9.22(3.75) 8.88(3.35) 9.00(3.38) 0.07 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.22(2.44) 5.85(2.41) 6.75(2.94) 1.08 n.s.
仕事への動機づけ 19.94(5.96) 20.59(5.90) 20.25(5.18) 0.10 n.s.*p < .05

― ―178
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
最後に女性・親視点に関して、結びつきでは父―子間の「仕事への動機づけ」において高群が低群
よりも有意に低い傾向があることが示された(t(20)=2.72,�p < .01)。開放性においては有意な差
は示されなかった。利害的関係では父―母間の「仕事への動機づけ」において5%水準での有意差(F
(2,17)=3.70,�p < .05)が示された。多重比較の結果、父・高位の群が父母・同位よりも有意に低い
ことが示された。勢力では、父―母間の「行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤」と「仕事のス
トレスに基づく家庭への葛藤」においてそれぞれ5%水準での有意差(F(2,18)=4.25,�p < .05�及び�
F(2,18)=4.52,�p < .05)が認められた。多重比較の結果、それぞれ母・高位の群が父母・同位の群
よりも葛藤が有意に低いことが示された。また、母―子間の「仕事のストレスに基づく家庭への葛
藤」において1%水準の有意差(F(2,19)=16.00,�p < .01)が認められた。女性・親視点の勢力にお
いては子・高位の群の度数が0であったため、結果的に母・高位の群が母子・同位の群よりも葛藤が
有意に低いことが示された。
Table�12 �女性・子ども視点における家族の勢力に関する一元配置分散分析及び多重比較結果(二者それぞれが高位、二者が同位の3群間比較)
父 – 母・勢力 父 – 子・勢力父・高位
(n =43)父母・同位(n =30)
母・高位(n =28) F 値 多重比較
父・高位(n =34)
父子・同位(n =36)
子・高位(n =31) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 14.30(4.22) 15.53(5.55) 15.86(5.48) 0.98 n.s. 14.94(5.19) 15.11(5.22) 15.26(4.68) 0.03 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 7.58(3.04) 7.30(3.32) 8.32(3.71) 0.74 n.s. 7.41(2.99) 8.00(3.36) 7.68(3.66) 0.27 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 8.88(3.24) 8.43(3.10) 9.68(3.91) 1.00 n.s. 8.65(3.13) 9.19(3.33) 9.06(3.82) 0.24 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 5.88(2.06) 5.93(2.33) 6.71(3.34) 1.02 n.s. 6.15(2.28) 6.08(2.42) 6.16(3.02) 0.01 n.s.
仕事への動機づけ 19.67(5.53) 21.13(5.25) 20.71(6.44) 0.64 n.s. 20.21(4.30) 20.86(6.12) 20.06(6.61) 0.19 n.s.
母 – 子・勢力母・高位(n
=38)母子・同位(n
=37)子・高位(n
=26) F 値 多重比較平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 14.39(5.19) 14.68(4.64) 16.73(5.04) 1.93 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 7.55(3.57) 7.97(3.51) 7.54(2.67) 0.19 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 8.42(3.80) 8.95(3.06) 9.81(3.18) 1.29 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 5.74(2.49) 6.27(2.42) 6.50(2.83) 0.78 n.s.
仕事への動機づけ 21.97(5.72) 19.62(5.89) 19.19(5.03) 2.45 † n.s.† p < .10

― ―179
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
Table�14 �女性・親視点における家族の利害的関係に関する一元配置分散分析及び多重比較結果(二者それぞれが高位、二者が同位の3群間比較)
父 – 母・利害的関係 父 – 子・利害的関係父・高位
(n =4)父母・同位(n =11)
母・高位(n =5) F 値 多重比較
父・高位(n =5)
父子・同位(n =11)
子・高位(n =4) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 13.50(5.80) 16.36(4.43) 13.40(5.46) 0.86 n.s. 15.20(6.06) 14.55(5.34) 16.25(2.50) 0.16 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 5.75(3.20) 10.00(3.87) 8.80(3.77) 1.90 n.s. 7.20(3.63) 9.45(4.32) 9.25(3.30) 0.57 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 8.00(0.00) 9.45(3.42) 7.60(3.78) 0.70 n.s. 8.20(1.79) 8.09(3.78) 11.00(1.41) 1.39 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.25(3.77) 6.55(2.25) 6.60(1.82) 0.03 n.s. 6.40(2.30) 6.64(2.58) 6.25(2.50) 0.04 n.s.
仕事への動機づけ 25.50(5.20) 17.64(5.01) 20.80(4.87) 3.70 * 父母・同位<父・高位 18.40(8.85) 20.82(4.62) 19.75(4.65) 0.29 n.s.
母 – 子・利害的関係母・高位
(n =4)母子・同位(n =15)
子・高位(n =1) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 14.25(1.71) 15.53(5.53) 11.00 0.44 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 8.75(3.86) 9.27(3.86) 3.00 1.24 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 8.25(2.06) 8.87(3.52) 8.00 0.08 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 7.25(1.50) 6.53(2.47) 3.00 1.33 n.s.
仕事への動機づけ 19.00(6.98) 19.67(5.21) 29.00 1.40 n.s.
*p < .05
Table�13 女性・親視点における家族の結びつき・開放性に関する t 検定結果(高群・低群間の比較)父 – 母・結びつき 父 – 子・結びつき 母 – 子・結びつき
高群(n =8)低群(n =14)t 値
高群(n =16)低群(n =6)t 値
高群(n =8)低群(n =13)t 値
平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 16.75(4.77) 13.93(4.48) 1.39 n.s. 15.69(5.17) 13.00(2.37) 1.21 n.s. 14.38(4.07) 14.69(4.80) 0.16 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 9.75(3.45) 8.36(3.97) 0.83 n.s. 8.94(4.11) 8.67(3.01) 0.15 n.s. 8.00(3.12) 8.92(3.95) 0.56 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 8.50(3.16) 8.43(3.20) 0.05 n.s. 8.50(3.25) 8.33(3.01) 0.11 n.s. 7.50(3.34) 8.54(2.50) 0.81 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.63(1.69) 6.57(2.62) 0.05 n.s. 6.81(2.04) 6.00(2.97) 0.62 n.s. 6.75(2.12) 6.62(2.50) 0.13 n.s.
仕事への動機づけ 18.13(5.84) 21.57(5.17) 1.44 n.s. 19.06(5.47) 23.67(4.59) 1.83 † 18.88(5.22) 21.15(5.98) 0.89 n.s.
父・開放性 母・開放性 子・開放性
高群(n =10)低群(n =11)t 値
高群(n =11)低群(n =10)t 値
高群(n =14)低群(n =7)t 値
平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 15.8(6.16) 14.45(3.17) 0.62 n.s. 16.18(5.98) 13.90(2.73) 1.14 n.s. 15.29(5.66) 14.71(2.36) 0.33 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 8.6(3.81) 8.82(3.97) 0.13 n.s. 8.82(3.46) 8.60(4.33) 0.13 n.s. 8.64(3.54) 8.86(4.56) 0.12 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 7.7(3.40) 9.27(2.90) 1.14 n.s. 7.82(3.49) 9.30(2.75) 1.07 n.s. 7.79(3.07) 10.00(3.06) 1.56 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 7.1(2.33) 6.00(2.28) 1.09 n.s. 7.18(2.18) 5.80(2.35) 1.40 n.s. 6.93(2.30) 5.71(2.29) 1.14 n.s.
仕事への動機づけ 19.2(6.63) 21.18(4.77) 0.79 n.s. 19.73(5.88) 20.80(5.69) 0.42 n.s. 19.93(5.48) 20.86(6.44) 0.35 n.s.† p < .10

― ―180
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
【考察】1. 本研究における家族構造因子
まず本研究における家族構造因子について考察する。家族構造因子間において相関分析を行った
結果、子ども視点の男女においては「結びつき」「利害的関係」「勢力」「開放性」の4因子全てにおい
て正の相関が示された。また、親視点の男女においては「勢力」が「結びつき」「利害的関係」と正の
相関を示したのみでそれ以外には有意な結果は示されなかった。この子ども視点と親視点の結果の
違いは注目すべきものである。本研究の調査対象者の年齢平均は子ども視点は30代前半、親視点は
30代後半と大きな開きがあるわけではない。それにも関わらず、家族構造因子の関連に違いが見ら
れるということは子ども、親というそれぞれの立場の違いによって重視すべき家族構造因子が異な
ることを意味する。例えば柏木・若松(1994)は「親となる」ことによる発達として性差に違いはあ
るものの、男女ともに「親となる」ことにより自身の視野の広がりや自己抑制など多くの要因に変化
が自覚されることを明らかにしている。このことからも親になる前と後により家族構造の関連が変
化することも十分に考えられるだろう。視点の違いによる影響の違いについては WFC も含めて後
に考察する。また、「利害的関係」が他の因子を正の相関を示したことも注目すべき点である。本研
究における家族構造4因子を抽出した狐塚ら(2008)は「利害的関係」が他の因子と負の相関を示し
たことを述べている。本研究において異なる結果を示した理由についてはいくつか推測できる。ま
ず1点目は調査対象者の違いである。狐塚ら(2008)は大学生を調査対象としていたのに対して、本
Table�15 �女性・親視点における家族の勢力に関する一元配置分散分析及び多重比較結果(二者それぞれが高位、二者が同位の3群間比較)
父 – 母・勢力 父 – 子・勢力父・高位
(n =5)父母・同位(n =11)
母・高位(n =5) F 値 多重比較
父・高位(n =13)
父子・同位(n =6)
子・高位(n =2) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD) 平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 15.20(6.02) 17.09(3.56) 10.60(2.97) 4.25 * 母・高位<
父母・同位 13.38(4.66) 18.00(3.95) 17.50(3.54) 2.57 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 9.00(4.30) 9.82(3.63) 6.00(2.83) 1.92 n.s. 7.85(3.78) 11.17(3.37) 7.00(2.83) 1.97 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 8.20(1.79) 10.00(3.16) 5.60(2.30) 4.52 * 母・高位<
父母・同位 7.54(2.57) 10.00(4.20) 10.50(0.71) 1.80 n.s.
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 5.80(1.79) 7.09(2.51) 6.00(2.45) 0.68 n.s. 5.92(2.43) 7.33(2.07) 8.00(1.41) 1.24 n.s.
仕事への動機づけ 17.80(6.42) 20.45(6.02) 22.20(4.09) 0.75 n.s. 18.69(5.50) 23.50(5.01) 20.50(7.78) 1.56 n.s.
母 – 子・勢力母・高位
(n =15)母子・同位(n =6)
子・高位(n =0) F 値 多重比較
平均値(SD)平均値(SD)平均値(SD)
行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤 14.07(4.88) 17.67(3.56) 2.66 n.s.
仕事の時間に基づく家庭への葛藤 7.87(3.56) 10.83(3.82) 2.86 n.s.
仕事のストレスに基づく家庭への葛藤 7.20(2.08) 11.83(3.13) 16.00 **
家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤 6.67(2.41) 6.17(2.23) 0.19 n.s.
仕事への動機づけ 20.07(6.16) 20.67(4.72) 0.05 n.s.
*p < .05,**p < .01

― ―181
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
研究は会社員を対象とした。大学生の多くは精神的にも経済的にも親の保護下から自立しようとし
ている段階であるのに対して、会社員は自ら働き給料を得ているということからも大学生よりも自
立した存在であると言える。利害的関係が強いということは「普段の関わりは希薄だが、お互いや
家族にとって重要なときには関心を示すという度合いが強い」ことを意味する。大学生と会社員を
比較した場合、自立しきれていない大学生では利害的関係の強さを「お互いに重要な時に “ しか ”
関わりを持たない」と否定的に捉えることにより他の因子と負の相関を示したのに対して、自立し
た会社員では「重要な時に “ こそ ” お互いがしっかりと関わりが持てる」と肯定的に捉えることによ
り他の因子と正の相関を示したと考えられるのではないだろうか。2点目として考えられるのは、
利害的関係の測定の仕方である。狐塚ら(2008)は多くの質問項目を因子分析することにより「利害
的関係」因子を抽出したのに対して、本研究では野口(2008)の測定法にならい父・母・子という3つ
の二者間においてお互いに対する利害的関係の程度を10件法で直接回答してもらうことを試みた。
この測定法の違いによる影響も考えられるかもしれない。これらの点については今後も検討してい
く必要がある。また、本研究は企業 A の社員のみを対象とした限定的な調査と言える。それらを
踏まえた上で、次からは家族構造と WFC との関連について考察していく。
2. 仮説の検討
仮説を検討するために、男性・子ども視点、男性・親視点、女性・子ども視点、女性・親視点という
それぞれの群において家族の構造と WFC、仕事への動機付けとの関連を検討した。その結果、仮
説1に関して男性・親視点においては母―子間の結びつきが高い群が低い群よりも行動の効力感に
基づく仕事・家庭への葛藤が高いこと、女性・子ども視点においては母―子間の結びつきが高い群
が低い群よりも仕事の時間に基づく家庭への葛藤が高いこと、女性・親視点においては父―子間の
結びつきが高い群が低い群よりも仕事への動機付けが低いことが示され、仮説1とは逆の結果にな
ることが明らかにされた。仮説2に関して男性・親視点においては勢力が妻よりも高い群が妻と同
程度及び妻よりも低い群と比べて、家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤が低いこと、女性・
親視点においては夫よりも勢力が高い群が夫と同程度の群と比べて、行動の効力感に基づく仕事・
家庭への葛藤及び仕事のストレスに基づく家庭への葛藤が低いことが明らかにされた。これについ
ても仮説2はほとんど支持されていないと言えるだろう。仮説2の検討において特徴的な点は、両
親間の勢力関係では自分と配偶者が同程度であるよりも自らの勢力が高い方が WFC が低く、仕事
への動機付けが高いことであろう。仮説3に関して女性・子ども視点においては自分の開放性が高
い群が低い群よりも仕事の時間に基づく家庭への葛藤が高く、仕事への動機付けも高いことが示さ
れた。これは女性・子ども視点に関して仕事への動機付けについては仮説が支持されたものの、
WFC については仮説と逆の結果を示したと言える。このように本研究では父・母・子という三者
間の関係について、性別と視点の違いから検討を行うことによって多くの仮説とは異なる結果や、
それ以外の特徴的な結果が示された。これらの結果に関して、次から家族構造各因子の特性に基づ
きながら考察を加えていく。

― ―182
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
3. 家族の「結びつき」に基づいたWFCとの関連
まず子ども視点に関して、男性は結びつきの程度と WFC 及び仕事への動機付けとの関連は示さ
れなかったものの、女性は母との結びつきが高いことにより仕事の時間に基づく家庭への葛藤が高
いことが示された。結びつきとは家族内での親密さや愛情を意味している。これは家族への親密さ
が高いことにより家族と関わる時間が多く必要となり、それゆえに仕事の時間による葛藤が生まれ
ていることが考えられるだろう。
親視点に関して、男性では妻と子の結びつきが高いことにより行動の効力感に基づく仕事・家庭
への葛藤が高いことが示され、女性では夫と子の結びつきが高いことにより仕事への動機付けが低
いことが示された。これは男女ともに配偶者と子どもの親密さが高いことにより自身の WFC が高
くなったり、仕事への動機付けが低下することを意味する。この影響に関して、Minuchin(1974)
の家族構造モデルから考察してみる。Minuchin(1974)のモデルでは、家族という1つのシステム
の中において下位のシステムであるサブシステムが形成されることを述べている。例えば夫婦間で
のサブシステムや兄弟間でのサブシステムなどである。そして、家族内において他のサブシステム
との間には境界線が生まれるとしている。構造モデルでは家族システムにおいてこの境界線が両親
と子どもの間に生まれる世代間の境界線が最も健康的な家族の条件として挙げられている。さて、
このモデルを本研究の結果にあてはめた場合、まず父親における結果としては妻と子の結びつきが
強くなることにより行動に基づく仕事・家庭への葛藤が高くなっていく。これは父親1人のサブシ
ステムと母親と子どものサブシステムとの間に境界線が生まれている可能性が考えられるだろう。
それにより、例えばサブシステム間でトラブルが起こったときに父親は孤立し、問題解決がより困
難になることが予想される。それゆえに行動に基づく葛藤が高まるのだろう。同様に、母親におけ
る結果としても夫と子の結びつきが強くなることにより自身の仕事に対する動機付けが低下するこ
とが示されている。これは母と父子間に境界線が生まれ、母親が孤立することで仕事に対する意欲
が低下することが考えられる。このように自身が関わる結びつきではなく、他の家族間の結びつき
の強さが WFC や仕事への動機付けに関連することを明らかにした結果は、これまでの WFC 研究
には無い新しいものであると言えるだろう。
4. 家族の「利害的関係」に基づいたWFCとの関連
子ども視点に関して、男性では父―子間において自分の利害的関係が父よりも高い方が、父と同
程度であるよりも仕事のストレスに基づく家庭への葛藤が低いことが明らかにされた。女性におい
ては利害的関係による結果は示されなかった。利害的関係が相手よりも高いということは、お互い
にとって重要な時のみに関われば良いと考える程度が相手よりも強いという、より一方的な関係性
が考えられる。言い換えれば、重要な時以外は家族と関わらなくても良いと考えることにより、仕
事と家庭における葛藤が低減されていることが窺えるだろう。男性・親視点においても、自分が子
どもよりも利害的関係の程度が高いことにより仕事のストレスに基づく家庭への葛藤が低下してい
る。ここまでの結果からすると、子ども視点と親視点に関わらず男性の親子関係においては相手よ

― ―183
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
りも自分の利害的関係が高いことにより WFC が低下することが窺える。
一方で夫婦関係に注目すると少し結果が異なっている。男性・親視点の夫婦関係では自分と妻の
利害的関係が同程度であることが、妻の方が利害的関係が強い場合よりも家庭の時間・ストレスに
基づく仕事への葛藤が低いことが示されている。これは妻の方が一方的であることによって、自分
が家庭に関与しなければならない度合いが高まっていることが考えられる。これは先の関連と同様
のものであると言える。しかし、女性・親視点においては自分と夫の利害的関係が同程度であるよ
りも夫の利害的関係が強い方が、自分の仕事に対する動機付けが高まるという肯定的な結果が示さ
れた。これにより考えられるのは、自分の夫が重要な時のみに関心を示し、それ以外には興味を示
さないことによってある程度の家事・育児を果たしていれば思う存分仕事に集中できるという状況
が考えられるのではないだろうか。利害的関係については関連した先行研究も少ないため、今後さ
らなる検討が必要である。
5. 家族の「勢力」に基づいたWFCとの関連
子ども視点に関して、男性では父―子間において自分の勢力が父親よりも高いことにより行動の
効力感に基づく仕事・家庭への葛藤が高まること、さらに母―子間において自分の勢力が母親より
も高いことにより仕事の時間に基づく家庭への葛藤及び仕事のストレスに基づく家庭への葛藤が高
まることが示された。これは総じて、自分の勢力が親よりも高いことにより WFC が高まることが
示されている。山下(2008)は父親の権威を認知している子どもの方が自分の家族に対する評価が
高いことを述べているが、本研究においては父親のみならず母親も含めて親の勢力が高いことが肯
定的に作用していると言えるだろう。勢力とは家族内における影響力や権力、リーダーシップなど
を意味している。相手よりも勢力が高いということは、自分の思い通りに相手に影響を与えること
ができる一方で、時には相手との関わりにおいて自分がリーダーシップを取らなければいけないと
いった負担になることも考えられる。例えば介護などで親の面倒を見なければいけなくなったとき、
勢力としては子どもが優位になっているものの、仕事に対しては大きな負担となることが予想され、
それが葛藤へと繋がるのだろう。また、岩井・保田(2008)は夫婦を子どもの立場とした親との世代
間における援助に関して、親から子どもに対する援助の方が子どもから親に対する援助よりも夫婦
それぞれの親子間のバランスを均衡化させやすいことを述べている。このように、子どもが成人し
た親子関係においても子どもの勢力が親を超えないことというのは家族関係のバランスにとって重
要な要因であると言えるのだろう。
親視点に関して、男性では父―母間において妻よりも勢力が高い方が妻と同等、あるいは妻の方
が高い場合よりも家庭の時間・ストレスに基づく仕事への葛藤が低いことが示された。一方で女性
の場合も夫よりも勢力が高い方が夫と同等の場合よりも行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤
や仕事のストレスに基づく家庭への葛藤が低いことが示された。これは夫婦のどちらにとっても相
手よりも自分の勢力が高い方が WFC が低いことを意味している。例えば、柴山(2007)は共働き夫
婦における子どもの送迎分担について、夫婦で送迎を分担するきっかけは妻が夫に話し合いを持ち

― ―184
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
かけ、調整の主導者になる過程が見られることを述べている。これは妻が夫よりも強い勢力を持と
うとすることが夫の WFC に繋がることを示す一例であると言えるだろう。また、親視点における
勢力の影響として特に興味深いのは、男性の母―子間において子どもの勢力が妻よりも高い場合に、
自分の行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤が低いということである。これは自らが関わらな
い母―子関係において、妻の影響力が子どもに強く及んでいれば自分の影響力を子ども与える余地
が少なくなってしまうものの、もし子どもの勢力が強くて妻が振り回されがちであったならば、自
分が父としての勢力を行使する機会を得るために結果として行動に基づいた葛藤が少なくなると
いったことが考えられるのではないだろうか。
6. 家族の「開放性」に基づいたWFCとの関連
子ども視点に関して、男性においては開放性に関する関連は見られなかった。女性においては自
らの開放性が高いことにより仕事の時間に基づく家庭への葛藤が高くなったり、一方で仕事に対す
る動機付けも高まるという興味深い結果が示された。開放性とは家族以外との関わりの多さを意味
している。働く社会人にとって仕事や職場とは最も身近な開放性の要因と言えるだろう。つまり、
毎日仕事に出かけて家族以外の人と関わることにより開放性が高くなり、仕事への動機付けも刺激
されている一方で、それゆえに家族と過ごす時間が減っていることに葛藤を抱えていることが考え
られる。これに関連することとして、塹江(1990)は8つの企業における従業員を対象として「生き
がい」について調査した結果、女性は男性に比べて家庭の生きがいが強い意味を持つことを述べて
いる。子どもを持たない女性は多くの場合において家族のためというよりもむしろ自分のために働
いていると言えるだろう。その自由な選択としての仕事と、生きがいとしての家庭が子ども視点の
女性のみにこのような葛藤を生み出しているのかもしれない。
親視点に関して、女性においては開放性に関する関連は見られなかったものの、男性においては
自分の子どもの開放性が高まることにより行動の効力感に基づく仕事・家庭への葛藤や仕事の時間
に基づく家庭への葛藤が低下することが示された。これは子どもにとって自分や妻といった家族以
外の人間と関わる機会が多いことにより、自分が子どもと過ごすために行動や時間を費やす必要性
が減り、結果として WFC が低下することが考えられるだろう。
7. 総合考察及び今後の課題
本研究において家族構造と WFC との関連を検討した結果、性別や視点に違いにより WFC や仕
事への動機付けに関連している家族の要因や関連性が異なってくることが明らかにされた。それら
の総合的な結果から、例えば親視点における夫婦間の勢力関係のように、一方を立てればもう一方
が立たずといったような状況や、子ども視点における女性のように家族以外の関わりの多さが仕事
の動機付けにつながると同時に家族に対する申し訳無さにもつながっているような、どっちが良い
とも取れないような状況も窺えることが明らかになった。これらの状況から考えると、家族誰もが
WFC を感じないような状況を作るということは非常に困難であると言える。WFC に関連する問

― ―185
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
題として取り上げられるとものとしてネガティブ・スピルオーバーがある。ネガティブ・スピルオー
バーとは仕事あるいは家庭において生じたネガティブな影響がもう一方の環境においてもネガティ
ブに影響するというものである。例えば小泉ら(2001;2003)は仕事から家庭へのネガティブ・スピ
ルオーバーが抑うつや夫婦関係に悪影響を及ぼすことを述べている。このような場合、支援の方法
としては仕事と家庭の葛藤を家族内から無くすことを目指すのではなく、家族内において特定の誰
かにのみ葛藤が集中しないように家族全員で分散していくということが重要になってくるのではな
いだろうか。その意味ではワーク・ライフ・バランスという言葉は個人内におけるバランスだけで
はなく家族全体にとってのバランスとしても当てはまると言えるのだろう。
本研究では今後検討すべき課題もいくつか挙げられる。まずは調査対象者が一社のみの社員で
あったため、より多くの企業や職種を含めた検討を行う必要があるだろう。また、家族構造因子に
ついても利害的関係の関連が狐塚ら(2008)とは異なっていた。これが大学生と会社員という調査
対象者による影響なのか、あるいは測定法による影響なのかを検討していかなければならないだろ
う。最後に、子ども視点と親視点における家族構造因子の関連を検討した際、両者において共通し
て強い関連を持っていた因子が「勢力」であった。子ども視点と親視点のどちらにも役立つ要因と
して勢力に焦点を当てた検討も必要であると言えるだろう。
【引用文献】Beavers,�R.�&�Hampson,�R.B. 2000 The�Beavers�systems�model�of�family�functioning.�Journal�of�Family�Therapy.�
22,�pp.128–143.
Brummelhuis,�L.L.,� van�der�Lippe,�T.,�Kluwer,�E.S.,�&�Flap,�H. 2008 Positive� and�negative� effects� family�
involvement�on�work–related�burnout.�Journal�of�Vocational�Behavior,�73,�387–396.
Carlson,�S.,�Kacmer,�K.,�Williams,�J.�2000�Construction�and�initial�validation�of�a�multidimensional�measure�of�work�
family�conflict.�J�Vocat�Behav,�56,�pp.249–276.
Deci,�E.L. 1975 Intrinsic�Motivation.�New�York� :�Plenum�Press(安藤延男・石田梅男訳 1980 内発的動機づけ�
誠信書房)
Frone,�M.�R. 2003 Work–Family�Balance.�In�J.�C.�Quick�&�L.�E.�Tetrick�(Eds.).�Handbook of occupational health
psychology�(pp.�143–162).�Washington,�DC:�American�Psychologist�Association.
藤本哲史 2004 ファミリー・フレンドリーな職場環境の従業員モラール効果:男女比較分析 経営行動科学学会年
次大会発表論文集,⑺,pp.71–80
Greenhaus,� J.�&�Beutell,�N.J. 1985 Sources�of�conflict�between�work�and� family�roles.�Acad�Manage�Rev,�10,�
pp.76–88.
Greenhaus,�J.�&�Powell,G. 2006 When�work�and�family�are�allies:�A�theory�of�work–family�enrichment.�Academy�
of�Management�Review,�31,�72–92.
塹江清志 1990 「仕事」の「生きがい」の「意味」について 日本経営工学会誌,41⑸,pp.342–347.
岩井紀子・保田時男 2008 世代間援助における夫側と妻側のバランスについての分析―世代間関係の双系化論に対
する実証的アプローチ 家族社会学研究,20⑵,pp.34–47.

― ―186
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
金井篤子・若林 満 1998 女性パートタイマーのワーク・ファミリー・コンフリクト 産業・組織心理学研究,11⑵,
102–122.
柏木惠子・若松素子 1994 「親となる」ことによる人格発達:生涯発達的視点から親を研究する試み 発達心理学研
究,5⑴,pp.72–83.
加藤容子 2002 共働き女性のワーク・ファミリー・コンフリクトへの対処:夫婦の関係性の観点から 経営行動科学,
16⑵,pp.75–87.
加藤容子・金井篤子 2007 共働き夫婦におけるワーク・ファミリー・コンフリクト―「クロスオーバー効果」と「対
処行動の媒介・緩衝効果」の吟味 産業・組織心理学研究,20⑵,pp.15–25
小泉智恵・菅原ますみ・北村俊則 2001 児童を持つ共働き夫婦における仕事から家庭へのネガティブ・スピルオー
バー : 抑うつ,夫婦関係,子育てストレスに及ぼす影響 精神保健研究,⒁,pp.65–75.
小泉智恵・菅原ますみ・前川暁子・北村俊則 2003 働く母親における仕事から家庭へのネガティブ・スピルオーバー
が抑うつ傾向に及ぼす影響 発達心理学研究,14⑶,pp.272–283
狐塚貴博・野口修司・閏間理絵・石橋曜子・若島孔文 2008 家族構造の測定における構成因子に関する研究 立正大
学臨床心理学研究,6,19–32.
Lawler,�E.E. 1973� Motivation�in�work�organization.�Monterey,�Calif.�:�Brooks/Cole�Pub.�Co.
松田茂樹 2005 女性の就業とディストレスの関係�:�ファミリー・フレンドリー制度の効果と役割の質 社會科學研
究,57⑴,pp.113–125
Michel,� J.S.,�&�Hargis,�M.�B. 2008 Liking�mechanisms�of�work–family�conflict�and�segmentation.� Journal�of�
Vocational�Behavior,�73,�509–522.
Minuchin,�S. 1974 Family�and�family�Therapy.�Cambridge,�MA:�Harvard�University�Press =山根常男・監訳
1984 家族と家族療法,誠信書房
野口修司 2008 青年期における家族構造と社会的勢力に関する研究 立正大学大学院平成19年度修士論文
Olson,�D.�H.,� Sprenkle,�D.�H.�&�Russell,�C.� S. 1979 Circumplex�Model� of�Marital� and�Family�Systems: Ⅰ .�
Cohesion�and�Adaptability�Dimensions,�Family�Types,�and�Clinical�Applications.�Family�Process,�18⑴ ,�pp3–28
Senécal,�C.,�Vallerand,R.J.,�&�Guay,�F., 2001 Antecedents� and�outcomes�of�work–family� conflict:� toward�a�
motivational�model.�personality�and�social�psychology�bulletin,�27⑵ ,�176–186.
柴山真琴 2007 共働き夫婦における子どもの送迎分担過程の質的研究 発達心理学研究,18⑵,pp.120–131.
Skinner,�H.,�Steinhauer,�P.,�&�Sitarenios,�G. 2000 Family�assessment�measure(FAM)�and�process�model�of�
family�functioning.�Journal�of�Family�Therapy.�22,�pp.190–210.
田尾雅夫 1984 課業の複雑さと内的動機づけの関係に及ぼす対人関係変数の仲介効果について心理学研究,55⑴,
pp.15 ~ 21.
若島孔文・須永直人・野口修司 2008 少子化問題,解決への提言 ―日本家族心理学会第24回大会準備委員会によ
る調査結果を中心として― 家族心理学年報,26,193–205.
脇坂�明 2007 ワーク・ライフ・バランスの国際比較 学習院大学経済経営研究所年報,21,pp.63–87
渡井いずみ 2007 ワーク・ライフ・バランスとワーク・ファミリー・コンフリクト(特集 多様化する労働形態とワー
ク・ライフ・バランス) ストレス科学,22⑶,pp.164–171
渡井いずみ・錦戸典子・村嶋幸代 2006 ワーク・ファミリー・コンフリクト尺度(Work–Family�Conflict�Scale:�
WFCS)日本語版の開発と検討 産業衛生学雑誌,48⑶,pp.71–81.

― ―187
� 東北大学大学院教育学研究科研究年報 第57集・第2号(2009年)
山下美紀 2008 親の権威の有無と家族関係との関連―女子大学生調査 ノートルダム清心女子大学紀要,生活経営
学・児童学・食品・栄養学編,32⑴,pp.47–58.

― ―188
家族構造とワーク・ファミリー・コンフリクトに関する研究
� The�purpose�of�this�study�was�to�examine�the�relationship�between�family�structure,�work-
family�conflict,�and�motivation�toward�work.�We�measured�Family�structure� for� father-mother-
child�triad�with�using�four�factors;�Coherence,�Interest,�Power,�and�Openness.�The�research�was�
conducted�with�350�workers;�109�male�workers�without�children,�118�male�workers�having�child,�
101�female�workers�without�children,�and�22�female�workers�having�child.�Those�without�children�
completed� the�questionnaire� from� the�point� of� view�of� child.�Meanwhile,� those�with� child�
completed� it� from�the�point�of�view�of�parent.�The�analysis�showed�that�each� factor�of� family�
structure�had�different�effect�on�work-family�conflict�and�motivation�toward�work�because�of�the�
perspective�of�difference;�gender,� and�parent-child� standpoint.�The� result� indicates� that� the�
difference�of�gender�and�parent-child�standpoint�changes�valued�aspect�and�relationship� in�a�
family.
Key�words:�family�structure,�work-family�conflict,�motivation� toward�work,�parent�standpoint�
and�child�standpoint.
Research�on�Family�Structure�and�Work-Family�Conflict
Koubun�WAKASHIMA(Associate�Professor,�Graduate�school�of�Education,�Tohoku�University)
Shuji�NOGUCHI(Postgraduate,�Graduate�school�of�Education,�Tohoku�University)
Takahiro�KOZUKA(Graduate�Student,�Graduate�school�of�Psychology,�Rissho�University)
Norimasa�ITAKURA(Graduate�Student,�Graduate�school�of�Education,�Tohoku�University)
Takaaki�USAMI(Graduate�Student,�Graduate�school�of�Education,�Tohoku�University)
Tai�KUROSAWA(Graduate�Student,�Graduate�school�of�Education,�Tohoku�University)
Rie�URUMA(Graduate�Student,�Graduate�school�of�Psychology,�Rissho�University)