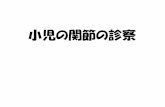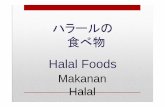ササパイラの身体診察パイラの身体診察身体診察の教科書において最高峰として名高い『Sapiraʼs Art and Science of Bedside Diagnosis』。身体診察の手技はも
食の安全とハラールのあり方についての考察 - JAFIT- 29-...
Transcript of 食の安全とハラールのあり方についての考察 - JAFIT- 29-...

-�29-
日本国際観光学会論文集(第21号)March,2014
《研究ノート》
食の安全とハラールのあり方についての考察-ASEAN諸国からのインバウンドを迎えるために-
In�20�3,�the�“foods�camouflage�problems”�in�a�hotels�and�restaurants�occurred�frequently.�It�will�be�a�problem�with�which�“food”�
is�related�safely,�and�if�it�makes�a�mistake,�it�will�be�a�problem�which�threatens�a�user’s�health.
This�is�the�same�as�greet�the�Muslims�from�the�ASEAN�countries�where�the�increase�is�expected�from�now.�Because,�a�Muslim�
eats�halal�and�camouflage�is�not�allowed�absolutely.
If�camouflage�is�discovered,�then�it�is�likely�to�develop�into�international�issues.
杉すぎ
山や ま
維し げ
彦ひ こ 四国学院大学�社会学部/
一般社団法人�国際観光政策研究所四国学院大学�社会学部/一般社団法人�国際観光政策研究所
1 はじめに
20�3年、有名ホテルや、レストラン、
百貨店、などにおける「食材偽装問題」
の発覚は、とどまることを知らない。こ
のことにより利用客が減少することで、
ブランド価値そのものが根こそぎ揺らぎ
始めることとなった。これらの施設の関
係者においては、最終的に利用客(消費
者)を保護するという思いはなかったも
のと考えられる。
このことは観光に携わる者にショック
を与えたばかりか、利用客に対する裏切
り行為でもある。さらに、「食」の安全に
も関与する問題であり、今回の事件では
身体的な被害者は無かったものの、一歩
間違えば利用客の健康を脅かす問題であ
る。特に、海外からの観光客(インバウ
ンド)に対しては、わが国の信用問題に
発展しかねない。
例えば、今後増えることが予測されて
いる ASEAN 諸国からのインバウンド
は、イスラム教徒(以後ムスリムと記載)
が多いと思われる。そこで、ハラール(ハ
ラルともいう。後述する)と呼ばれる宗
教の教義に従った食事を提供する必要が
生じる。もし偽装した食材を提供した場
合簡単には済まされない問題が発生する
恐れがある。それは、ムスリムに対し禁
忌な食材を提供したり、ハラールを偽装
して提供した場合、それが発覚した際は
大きな宗教的問題へとなってしまう。ま
た、それが故意であれば問題はさらに拡
大し、国際問題に発展する可能性もある。
従ってムスリムの観光客を迎えることを
簡単に考えていると、後で重大な展開に
なりかねない恐れがあることに注意しな
ければならない。
2 背景
観光庁及び日本政府観光局(以後
JNTOと記載)は20�3年の「日・ASEAN
友好協力40周年」を契機に、ASEAN 諸
国における訪日プロモーションンの本格
展開を始めた。これは中国、韓国のみな
らず、VJC(ビジット・ジャパン・キャ
ンペーン)ン対象国をその外周まで広げ
ることである。
わが国における20��年の訪日外国人数
(表-1)を見ると韓国�66万人(1万人単
位で四捨五入、以下同様)、中国�04万人
で、合計すると、総数622万人の44%に相
当する。さらに台湾�00万人、香港36万人
を加えると、その割合は66%となる。こ
の数の観光客が減少すれば国内の観光産
業にダメージを与えることは簡単に想像
できる。
また、これらの国々に続き訪日者数が
多い、タイ、シンガポール、マレーシア、
インドネシアにも着目し、これらの国々
からの観光客数を増加させることと、こ
れらの国々からのインバウンドが訪日し
Country 20�� 20�2 伸率(%)South�Korea �,658,073� 2,044,249� 23.3China �,043,246� �,429,855� 37.�Taiwan 993,974� �,466,688� 47.6Hong�Kong 364,865� 48�,704� 32.0Thailand �44,969� 260,859� 79.9Singapore ���,354� �42,253� 27.7Malaysia 8�,5�6� �30,288� 59.8Indonesia 6�,9��� �0�,498� 63.9Philippines 63,099� 85,�27� 34.9Vietnam 4�,048� 55,228� 34.5Asia�Total 4,723,66�� 6,396,226� 35.4Grand�Total 6,2�8,752� 8,367,872� 34.6
出所:日本政府観光局(JNTO)作成表より筆者抜粋・作成
表-1 国別訪日外国人数(単位:人)

-�30-
日本国際観光学会論文集(第21号)March,2014
た際に発生する問題について考察する。
特に注意すべきことは、イスラム教(イ
スラームと記載)を知る必要がある。マ
レーシア、インドネシアはムスリムが多
い国であり、外務省の統計情報によれば、
それぞれの人口の6�%1、88%2がムスリ
ムである。また、シンガポールは�4%3タ
イも5%4がムスリムである。
表-1に見られるように、実際20�2年は
東南アジア諸国からの訪日者数は減少す
ることなく順調な伸率であった。注目す
べき点は前記した ASEAN 諸国のうち、
タイ79.9%、マレーシア59.8%、インドネ
シア63.9%と、大きい伸率を示しているこ
とである。20�2年の観光庁の資料5によれ
ば、わが国において訪日外国人の一人あ
たりの消費額を見ると、中国�6.4万円は例
外的に高額であるが、韓国6.3万円、台湾
8.2 万 円、香 港 9.5 万 円 で あ る。ま た、
ASEAN諸国では、タイ��.8万円、シンガ
ポール�3.0万円、マレーシア�3.5万円、(イ
ンドネシアはリストに数値なし)である。
今後これら ASEAN 諸国からの観光客が
増加すればVJC5大市場(中国・韓国・台
湾・香港・米国)からの観光客が減少し
ても、わが国における消費金額はこれま
で以上となることも十分期待できる。
3 目的
本研究ノートではムスリムのインバウ
ンドに対する問題点と今後の可能性を考
察することを主目的とする。
ハラールを食するムスリムは、わが国
を訪れるこれからの新規観光客として期
待ができる。しかし、わが国においてハ
ラールを独特な宗教的な食文化として理
解しても、実際にはその仕組みを理解し
て食品を提供するレストランやホテルは
数少ない。
そこで、まずは肉牛に着目し日本独自
のハラール・ビーフを ASEAN 諸国から
のインバウンドに対し供給することがで
きないか考察する。ジャパン・ブランド
のハラール・ビーフがわが国全域で流通
することになれば、全国にてそれを用い
たレストランやホテルが増え観光客は日
本各地に滞在が可能になる。
「観光資源」とは観光対象としての可能
性を持つ資源と定義6され、施設、名勝、
郷土料理、伝統や文化、などを言うこと
が多い。研究の中でムスリムのインバウ
ンドを考える上で、ハラールに視点を置
き、「畜産農家」、「屠畜事業者」、「卸売事
業」、「食肉流通事業者」、「食肉販売業者」、
なども同一線上の「観光資源」の一部と
して位置付けをする。それに連結し、わ
が国における食肉を中心としたハラール
認証制度の仕組みをまずは考察する。
最近わが国のみで有効なローカル・ハ
ラール認証なるものが行われ始めたが、
これは訪日ムスリムに対し有効であるか
疑問である。他にも、プライベート認証
なる一部の在日ムスリムのみで有効な認
証まで行われている。これらについて何
らかの整理を行う必要があると考える。
また、ハラールという「食」に関する
事項を6次産業化することで、農林畜産
業の生産性向上とその地域における安定
した雇用の確保ができれば、ムスリムの
インバウンドを呼び込むことにつなが
る。これは、「日本再生戦略」に位置づけ
られる「食と農林業の再生」および「観
光振興」といった国家成長戦略に結び付
けることができる。
本研究ノートはこれから筆者の行う研
究の糸口として筆者が調査済みである部
分を項目ごとに調査研究報告としてまと
めた。今後、問題の発見によりその目的
をさらに明確化することになるであろう。
4 イスラーム
(1)わが国におけるムスリム
わが国において多くの人は、イスラー
ムのイメージとして暴力や危険というイ
メージが多い。本来の姿とは異なる誤っ
た理解をされているケースがほとんどで
ある。また、「女性軽視」「厳しい戒律」な
どネガティブなものもある7。身近ではな
い宗教であるため、イスラームは異文化
であり理解が難しいと言うことになろう。
わが国には、神道(5�.2%)、仏教(43.0
%)、キリスト教(�.0%)の信者がおり8、
イスラームは新興宗教(もしくは新宗教)
以上に知名度がないものである。
現在わが国のムスリム人数はそのほと
んどが外国人であるため、正式な調査は
行われていない。何らかの理由で訪日し
そのまま定住した者やその家族、それら
の者と結婚した日本人などである。また、
わずかではあるがイスラームに改宗した
日本人もいる。
筆者が在日外国人数をもとに、それら
の国々における本国でのムスリムの比率
を用い、在日ムスリム数を算出すると6
万人を超える。その数は国別にすると、
インドネシア約2万5000、バングラデシ
ュ約1万�000、パキスタン約8800、イラ
ン約5200、マレーシア約4000、中国(回
族)約2500、トルコ約2200、エジプト約
�300、スリランカ約�000、他にインド、
ネパール、ミャンマー、などのムスリム
も多く在住している。
ムスリムはイスラームの発祥地である
中東を中心に、全世界において�6.2億人
おり全人口の23.4%9にもおよぶ。キリス
ト教に次ぐ信者をもつ宗教で、その数は
2030年には2�.9億人になると予測されて
いる9。
在日ムスリムにおいては母国と異なる
諸問題が発生している。特に「食」に関
する問題は生活の中でも重要であり、在
日ムスリムの大きな問題要素となってい
る�0。わが国においてハラール・レストラ
ンなど外食ができるところは数える程し
かなく、食材の入手に関してもJR新大久
保駅(東京都新宿区)北側にある「ムス
リム・スポット(新大久保文化通り)」��
や、全国各地に存在するマスジド(イス
ラーム寺院、モスクともいう)付近にて開
業するハラール食材店を利用している。
今後わが国においてもハラールを提供
する飲食店が増えることで、在日ムスリ
ムへの供給のみならず、訪日するムスリ
ムへの「おもてなし」の場にもなりうる。
従ってこの機会にイスラームという宗
教について正しい理解をするチャンスで
あり、その上で今後ムスリムの観光客を
迎え入れるべきであると考える。

-�3�-
日本国際観光学会論文集(第21号)March,2014
(2)イスラームとは
ムスリムではない筆者は宗教を専門と
した研究者ではないため、これまでに文
献などによりイスラームを理解したこと
をまとめる。
イスラームの啓典である「クルアーン
(コーランともいう)」はイスラームの思
想的原点である。イスラームの聖典は、
神アッラーフ(アッラーまたはアラーと
もいう)から預言者ムハンマドに啓示さ
れた啓典「クルアーン」と、ムハンマド
の言行録「ハディース」とがある。クル
アーンはイスラームの思想的原点、根源
であり、ムスリムにとってクルアーンは
神の言葉であり、なおかつ聖域である。
ムスリムが依って立つ規範として、大
きな存在になるのがシャリーア(いわる
るイスラーム法のこと)である。クルアー
ンは神の言葉そのものであり、シャリー
アの重要な法源となっている。
シャリーアは現代では時代錯誤的な戒
律であると思われがちであるが、実際に
は文章化されていないため法学者が時代
的背景、土地、環境、社会的状況などに
適応するように解釈し、判断をする。
ムスリムの旅行者が自国外への旅行に
対する解釈も、彼らが生活する国の事情
に合わせ臨機応変に変化がある。従って
わが国にムスリムを迎え入れるには、相
手国ごとに対応する必要が生じる。
クルアーンやシャリーアでムスリムが
守らねばならない以下のような戒律や教
義(六信・五行)があるが説明は省く。
六信�(ムスリムが信じなければならな
い6つの信仰箇条)
五行�(ムスリムが最大限の努力をして実
践しなければならない5つの戒律)
この六信・五行の規程を忠実に守り善
行を積み重ねるのがムスリムの務めであ
り、なおかつムスリムの日常を律するこ
とを、今後ムスリムを迎えるために我々
は知っておく必要がある。グローバル化
の中でイスラームは世界中に広がり、ム
スリムと直接接触する機会が増えた今、
我々はイスラームについて正しい理解を
しないと大きな問題となってしまう。そ
ればかりか国際問題へと発展する可能性
もある。わが国は石油や天然ガスなどエ
ネルギー資源のほとんどを中東から輸入
している。すなわちムスリムの人々の
国々であり、これらの国々との友好関係
を保つためにも、イスラームを知ること
は有意義なことである。ASEAN 諸国か
らのインバウンドを受け入れる場合も同
様である。
5 ハラール
(1)ハラールとハラーム
ここでムスリムのインバウンドを扱う
とき、最重要なポイントは「ハラール
( )」である。
これまでの文献などの調査を整理し、
まとめると、「ハラール」とはムスリムが
食しても良いものと理解されることが多
いが、実際はシャリーアにおいて「合法」
であるという意味である。逆に「不法」ま
たは「禁止」を「ハラーム( )(ハラ
ムともいう)」という。そして「ハラール」
と「ハラーム」の中間に位置する疑わし
いものを「シュブハ」といい、できる限り
避けることが望ましいとされている。
イスラームにおいて豚は不浄なもので
あり、食してはならない。その他にも牙
や爪がある虎や犬、猫、熊、なども食べ
ることが禁止されている。貝類、タコ、イ
カ、生の魚、なども禁忌である。スンニ
派ではうろこのない魚(ウナギ、ナマズ、
など)も同様であるが、エビは許されて
いる。また、死肉、生き血も口にしては
ならない。シャリーアにより飲酒も禁止
されていることに加え、発酵食品もアル
コールが含まれるものは許されない。
ムスリムが生活する国々では正式なハ
ラール認証団体によって承認を受けた食
材、加工食品、医療品、化粧品、これら
の原料、添加物、などにハラールの認証
の証として証明書を発行し、製品に英文
で「HALAL」またはアラビア語で「 」
と表示することを許可する(図-1)。
ASEAN 諸国はムスリムが多数いること
から、マクドナルドやケンタッキーフラ
イドチキンなどファーストフード店を含
めた飲食店はハラールの証明書の取得と
表示が義務付けられている。その表示は
国々によって異なる(図-2)。
ハラール認証の対象は直接ムスリムが
消費、利用するものだけでなく、間接的
なものもハラール認証の対象となるた
め、ハラール食材を用いた、飲食店やケー
タリングサービスも認証の対象となる。
また、食材や食品以外の衣類、玩具、コ
ンピュータ、ハラール製品の輸送、ハラー
ル食品の製造や加工を行うプラントにま
で及ぶ。特に食肉に関する規則では、家
畜が食べる餌、屠畜場は専用のラインで
あり専門のムスリムの手により決められ
た作業が行われる事、その際家畜の頭を
聖地メッカの方向へ向け血液が完全に抜
けてから解体をすること、保管や輸送は
豚肉と一緒にしないこと、など細かいこ
とまで決められている。シャリーアに規
程はないが植物の肥料に豚の糞尿を使う
ことも禁忌であると解釈されている。
(2)ハラール認証
ハラール認証は世界共通の認証機関は
なく、世界各国のハラール認証機関によ
りそれぞれの国の事情に合わせ行われて
いる。これは前述したようにシャリーア
図-1� マレーシアレストランに表示さ
れた認証証明書
(マレーシアの認証)出所:筆者撮影(20�2年6月)

-�32-
日本国際観光学会論文集(第21号)March,2014
に従っているため、各国それぞれに認証
団体が存在する。
ハラールの認証は取り扱う食材や商品
により方法が異なり、前述したように認
証は簡単に出来るものではない。JETRO
のホームページによれば、わが国におけ
るハラール認証団体は「宗教法人日本ム
スリム協会(JMA)」「宗教法人イスラミ
ックセンター・ジャパン(IJC)」「宗教法
人日本イスラーム文化センター」「NPO
法人日本ハラール協会(JHA)」などがあ
げられている�2。
わが国におけるこれらの団体は、わが
国がイスラームの国ではないため、該当
国の認証機関からライセンスを取得して
その業務を代行する形で行い、それぞれ
の国へ輸出をするためのハラール認証を
行っている。世界で1番厳しい認証がサ
ウジアラビアで、ハラールでない食品の
販売や輸入、流通まで禁止されている。
次いで厳しいのがマレーシアで、政府機
関 で あ る JAKIM(Jabatan�Kemajuan�
Islam�Malaysia:Department�of�Islamic�
Development�Malaysia)が認証を行い、
証明書を交付している。
これらの団体はムスリムが生活する国
への輸出(アウトバウンド)認証を行っ
ているため、インバウンドに対する国産
品の国内消費のためのハラール認証につ
いては現在のところ考えていないようで
ある。筆者が20�3年6月26日に日本ムス
リム協会へ電話にてインタビューしたと
ころ「今後必要に迫られれば考えなけれ
ばならない問題だ」との回答を得た。確
かにイスラームを国教としないわが国の
ハラール認証は国内で生産、流通、消費
する食材や商品に対して考えられていな
いのが現状で、今後ムスリムの ASEAN
諸国からのインバウンドの増加が予測さ
れることに伴いどのようにしていくのか
課題が残る。
(3)�インバウンド・ツアーにおけるハ
ラール
インバウンド・ツーリズムの中で
ASEAN 諸国のムスリムを積極的に受け
入れているのが沖縄ツーリスト(OTS)
である。筆者は20�3年6月28日同社を訪
れ国際事業本部国際部の方々に話を聞い
た。その中で1番に努力したのが「食」
であり、例えば沖縄そばの場合、ダシに
は豚骨を用いず昆布をベースにし、みり
んも使わない。具材は三枚肉(皮付き豚
ばら肉)を用いず、かまぼこも油で揚げ
ないなどの注意を払った。また、ホテル
やレストランでは、専用の食材用冷蔵庫
や調理器具も新規購入し専用にするな
ど、多くの事項に注意を払った。食事の
メニューについては特段の配慮を行い、
実際に訪日客に調理現場などを見てもら
うなど、同社の努力や経験は、順調に
ASEAN 諸国からのインバウンド数を伸
ばしている。
このように、インバウンドへの必要な
対処を怠らないことで信用を得て実績を
伸ばすことが出来る。
(4)ハラール食材偽装の現実
インバウンド・ツーリズムではムスリ
ムの訪日に合わせ食材などを準備すれば
良いが、わが国に居住する在日ムスリム
は「食」に関する問題は毎日のことであ
り、食材の入手に対する苦労は大きい。
在日ムスリムは全国にあるハラール専
門店、またはハラール取扱店にて食材を
購入している。また、これらの店はイン
ターネットによる通販も行っており在日
ムスリムは遠方にいても安心してハラー
ル食材が入手できる。
筆者の調査によればJR大久保駅付近に
は、20�2年�2月現在6軒のハラール食材
店が狭いエリアに集中している。ここは
第4章で述べた通称「ムスリム・スポッ
ト」であり、観光地であるコリアタウンに
隣接している。ここには関東地方に在住
する在日ムスリムがハラール食材を求め
てやって来る。6軒のハラール食材店の
経営者の国籍は様々で、ムスリムはイン
ド人とバングラデシュ人、ノン・ムスリム
はネパール人とミャンマー人である。ここ
では出身国産の食材を購入できるだけで
なく、ハラール食材も購入できる。そのメ
インがハラール・ミートである。
牛肉や羊肉はオーストラリアまたはニ
ュージーランドからの輸入品で、鶏肉は
ブラジルからの輸入品。また輸入のヤギ
肉を販売する店もある。これらのハラー
ル・ミートはそれぞれの国のハラール認
証機関のマークが付されている。
20�2年�2月、筆者があるハラール食材
店にて国産ハラール・ビーフを発見した。
アラビア語と英語表記のハラールのマー
クはあるがどこの国の認証団体によるも
のか記載がない(図-3)。牛肉のパッケー
ジには「JAPANESE��00% HOKKAIDO�
BEEF」� 「FRESH� HALAL� MEAT�
SLAUGHTED�IN�JAPAN�BY�ISLAMIC�
WAY」と記載されているだけである。筆
者が所属する国際観光政策研究所が販売
元に対し調査を行った結果、正規な方法
で処理がなされていないことが判明し
た。担当者からは『自主規制をする』と
の回答を得が、20�3年6月現在、未だ流
通していた。今後この偽装ハラール・ビー
フが何等かの方法で海外へ輸出されるこ
とがあれば、国際問題へと発展する可能
性は否めない。
また、インバウンドに提供した場合、
その事実が発覚すれば同様な問題が生
じ、使用したレストランやホテルのその
後の営業についても危うくなることであ
ろう。
「食」の偽装はムスリムからの信頼を失
うだけでなく、宗教的な大きな問題へと
図-2 各国のハラール証明のマーク
出所:�http://www.jas.org.sg/magazine/yomimono/�shiro/halal/halal.htmlより取得

-�33-
日本国際観光学会論文集(第21号)March,2014
展開する恐れがあるので、絶対行っては
いけない行為である。また、今後のハラー
ル・ミートの「ジャパン・ブランド」化
展開にも水を差すことになるであろう。
6 6次産業とハラール
(1)食の安全
近年、「食の安全」について多くのとこ
ろで議論がなされている。有害な物質が
食品を経由して体内に侵入しないよう、
様々な場面で安全に注意をしなければな
らない。我々が健康に過ごすためには安
全な食生活が必要不可欠である。すなわ
ち、「食の安全」は、口に入るすべてのも
のの、栽培、採取、捕獲、飼育、養殖と、
運搬、保存、加工、調理に至り、口に入
るまでの食物の経路の安全性が求められ
る。これは、生産者、加工企業、運輸従
事者、販売者、調理者、など食品に携わ
るすべての者の法令遵守もさることなが
ら、社会的使命をどうとらえているかと
いう倫理観(マインド)の問題でもある。
すなわち、食に関係するすべての関係者
は、「食の安全」という「信頼」が得られ
ていなければならない。
20�3年に発覚した宅配業者による
「クール便」や日本郵便の「チルドゆうパ
ック」の温度管理の問題も消費者を無視
した行動であり、食品に対する安全観念
の欠如でしかない。
そう考えると、ムスリムに対し「保証
できるハラールの食品を提供する」とい
う考えも「食の安全」の考え方と同じで
ある。すなわち、わが国を訪れる者に対
し提供される食物についても同様に、「安
全」という「信頼」が得られなければな
らない。
(2)食による地域活性化
食の安全に伴い「食育」や「スローフー
ド」といった食をテーマにした新しい動
きが生まれ、着地型観光の推進により「産
地産消」とい言葉も生まれた。「食」の地
域ブランド化が大きな流れとなり、B 級
グルメも「ご当地グルメ」として地域活
性化やニュー・ツーリズムに一役買うよ
うになった。
地域活性化を目指す方法として、観光
資源が乏しい地域では、「食」を用いた地
域ブランド化は、ご当地グルメなどが全
国ブランドになることで地域活性への早
道であるかもしれない。そして、「食」を
ブランド化することは、その地域に新た
な雇用が生まれ、観光客などへの効果、
6次産業化、交流人口の増加から地域活
性化につながる。また、メディアにも取
り上げられやすく、地域のイメージの向
上にも寄与する�3。
食を楽しむことは旅行者にとって観光
資源(アトラクション)であり、なおか
つ旅行者の観光体験となることを一般に
「フード・ツーリズム」という�4。地域の
豊かな風土、人材、食材などを活用し、
「食」と関連する産業などをリンクするこ
とで複数の観光資源を掘り起こし、地域
の産業の拡大や雇用の拡大を目指すこと
もできる。
フード・ツーリズムはムスリムのイン
バウンドにおけるハラール・フードのあ
り方と同じと考える。すなわちこれは「ハ
ラール・ツーリズム」の一部と考えられ
る。ハラール・ツーリズムとは、中東や
北アフリカから移民の多いヨーロッパで
はメジャーである。ツアーの食事がハ
ラール・フードであるのはもちろん、礼
拝時間には礼拝施設を準備し、宿泊施設
にはクルアーンを用意し、観光地も他の
宗教施設を出来る限り目にしない工夫を
する�5など、ムスリム向けのツアーが企画
されている。また、一部では地域の協力
によって成り立っている。すなわち、イ
スラームにはムスリム相互扶助の精神と
制度があり、クルアーンには両親や血縁
者はもちろん、孤児、貧しい者、近隣者
に加え、見知らぬ人、旅人にも親切にす
るよう命じているからである。
(3)6次産業のビジネスデザイン
6次産業を考える上で、ここでも「食
の安全」が問い正される。6次産業とは、
第1次産業(農林水産業)、第2次産業
(食品加工)、第3次産業(流通販売)の
一体化を推進し、地域に新たな食農ビジ
ネスを創出する取り組みである。すなわ
ち、農林水産の生産にとどまらず、それ
を原材料とした加工品の製造を行い、同
一カ所または近隣地域にて販売などの
サービスまで一貫して行うことである。
農家などの経営を多角化し収益を高める
ことを目的とする。しかし、安易に作物
などを加工して販売することにより、農
家などに責任が生じる。逆に考えれば地
域全体がチームを組むことで、設備投資
や衛生管理、責任の明確化、など制度設
計を確実なものに仕上げることでその地
域全体の活性化へとつながる。生産物や
加工品のブランド化、特産品の新規開発、
農村レストランや民泊、など地域独自の
コミュニティの形成が農業などを通じて
可能となる。
そこで、その地域ならではの特産品の
開発の中で、ハラールに関する農作物や
ブランド食肉の開発を行うことで、今後
増加するであろうムスリムのインバウン
ドの需要に対しビジネスチャンスとなる
と考える。その場合、第5章で述べたよ
図-3 ムスリム・スポットで販売されていた国産ハラール・ビーフ
出所:筆者撮影(20�2年�2月)

-�34-
日本国際観光学会論文集(第21号)March,2014
うにわが国には国内での消費のためのハ
ラール認証団体が存在しないため、輸出
のための認証をもって国内で消費する
ケースも発生している。
(4)�「ジャパン・ブランド」のハラール・
ミート
レストランやそこで提供される食事、
特に郷土料理や名物料理は旅行に於いて
重要な観光資源の要素となる。観光従事
者であれば、インバウンドに日本料理を
味わって欲しいと考えるのが自然であ
る。「食」の提供は安全であることが前提
であるので、すき焼きやしゃぶしゃぶ、
焼き鳥、などにハラールであるビーフや
チキンを準備する必要が生じる。そこで、
わが国を代表する松坂牛や名古屋コーチ
ンなどをハラール認証してムスリムに提
供すれば良いだけのことと、簡単に考え
てしまいがちだ。しかし、第5章で述べ
たようにわが国では国内向けのハラール
認証を行ってはいない。従って、海外へ
輸出認証を受けたものを国内で消費でき
るよう流通し、市場へ投入することで「ジ
ャパン・ブランド」のハラール・ミート
を商品化へ向う糸口となるかもしれない
が、問題は何も解決されていない。
わが国が世界に誇る「ジャパン・ブラ
ンド」のハラール・ミートを地球の隅々
まで流通することとともに、国内におい
ても流通させるため研究を行わなければ
ならない。
7 今後の研究計画及び方法
(1)基礎データの整理と収集
まず、20�3年度に発表される観光庁の
統計に基づき、対象となる ASEAN 諸国
からのムスリムの観光客数の調査および
消費金額、訪問先、食事、おみやげ品、
などを調査し、わが国内の動向調査から
ムスリムがわが国における志向を知るこ
とから始める。
(2)調査の枠組みと方法
次にわが国におけるハラール食材の消
費ネットワークの実態調査。「ムスリム・
スポット」には関東地方に在住する在日
ムスリムがハラール食材を求めてやって
くる。これまでの筆者の研究で分かった
ことは、地域との「共生」において、コ
リアタウンとは形を変えた「共生」をし
ているのが、在日ムスリムが集散する「ム
スリム・スポット」である。そこに、集
中して営業するハラール食材店がこれま
での研究では重要なポイントとなった。
この研究で行った調査からハラール食材
店ではハラールの食肉も販売している
が、牛肉や羊肉のほとんどは輸入品で、
鶏肉は輸入品とローカル認証の日本製を
取り扱っている現実が見えた。しかし、
同時に大久保のムスリム・コミュニティ
におけるハラール食材店は、群馬県やそ
の他のハラール食材店とのネットワーク
を形成し、それは在日ムスリムのネット
ワークの展開を表している。そこで方法
として、このネットワークと流通経路、
及び消費者ネットワークの繋がりを調査
することで、そのローカル認証やプライ
ベート認証なども知ることができる。次
のステップとして、今後オリジナルのハ
ラール・ミートが全国規模で展開できる
か可能性を調査する。
同時にわが国におけるハラール認証に
ついてどのような仕組みで行われている
か、すでに取組みが行われている人吉(熊
本県)やこれから取組みを開始する神戸
などの事例調査をし、また、イスラーム
を国教としないオーストラリアや EU 諸
国などの認証事情を調査し、わが国にお
いて日本人によるハラール認証の可能性
を考察する。
(3)�これまでの公的機関の取り組みと今後
観光関連では観光庁と JNTO が共催
で、20�3年2月1日に「ジャパン・ムス
リムツーリズム・セミナー」を開催した。
筆者は参加していないが、最終的な結論
としてイスラームやムスリムに対し理解
をし、企業や自治体がそれぞれに試行錯
誤をしながら、臨機応変にそれぞれが受
け入れを行えばよいということであっ
た�6。また、20�3年5月に「Japan-ASEAN�
Travel�Mart�20�3」を初めて行った。こ
れは、訪日ツアーの造成と訪日外国人旅
行者数の拡大のため ASEAN6か国の旅
行会社約�20社を招請し、わが国において
インバウンドを扱う観光関連企業や団体
と商談の場を作った。引き続きこれらの
ような行事への積極的な参加で動向を調
査する。
政府は20�2年に「特定地域再生事業費
補助金事業」として熊本県人吉市のプロ
ジェクト「地域起点型アジア市場の研究
プロジェクト事業」を助成している。こ
れは、ASEAN からの訪日外国人旅行者
および在日ムスリムをターゲットに、将
来的には輸出も視野に入れ、ハラール食
品を新たな市場開拓や食品加工場の環境
整備に取り組み、安定雇用と定住及び交
流人口の増加を図る�7としている。このこ
とは、地域における農林水産物の有効利
用と6次産業化に加え、観光と連携した
地域活性化となる。
民間の取り組みでは、一般社団法人日
本能率協会が20�3年3月に行った食品安
全シンポジウムにおいてハラールの認証
制度について取り上げていた�8。筆者が所
属する国際観光政策研究所が同協会の産
業振興センターの担当者に聞いたとこ
ろ、20�4年2月に行われる国際ホテル・レ
ストランショーの主催者であり、その中で
わが国におけるハラールに関する取り組
みの紹介を行うことが決定している。
これら公的機関の行事に参加し、新し
い取組みについて調査し把握していく。
8 まとめと今後の課題
(1)異文化理解
ムスリムはその人々の生活する国々の
事情、各自の生活習慣や環境、宗派、な
どにより信仰の度合いや厳格さが異な
る。インバウンドを受け入れる側はどの
レベルにスタンダードを置くのではな
く、まずは相手方の状況に合わせ対応を
する必要がある。第5章で述べた沖縄
ツーリストでは3年の歳月をかけること
で、双方Win-Winな関係を構築した。そ
のために、相手方との綿密な摺合せが必

-�35-
日本国際観光学会論文集(第21号)March,2014
要であった。ASEAN 諸国からのムスリ
ムを迎えるには、イスラームの正しい知
識を得る努力と、相手を理解することを
怠ってはならない。
「おもてなし」の気持ちであるホスピタ
リティ・マインドは観光業界だけでなく
各地の農業、畜産、水産、など地域従事
者が地の産物をムスリムのインバウンド
に味わってもらいたいと思うことで、地
域の活性化に結び付く。また、地域の村
おこし、街づくりに「食」が貢献する。
その中で「ハラール・フード」のブラン
ド化で特産品の生産量が増加し、第6次
産業の成長が見込める。
そのためにも、地域全体が一丸となり
目的意識を共有し、協力や相手を理解す
ることが必要となる。
(2)政府機関の取り組みへの期待
各省庁がそれぞれの事情に応じた取り
組みを行っている。もちろん農林水産庁
や厚生労働省では ASEAN 諸国のムスリ
ムや在日ムスリムに焦点を合わせたもの
ではなく、輸出品のハラール認証に関す
るものである。将来的に中東やアフリカ
などからのムスリムもわが国を訪れるで
あろう。そのことも踏まえ、省庁の壁を
取り払い、リーダーシップをもったハ
ラール・フードの認定機関の設立をする
ような動きを大いに期待したいところで
ある。
わが国のインバウンド・ツーリズムに
関しては観光庁が主導するのは当然であ
るが、2020年に開催されるオリンピック
を含め、ムスリムに限らず外国人旅行者
が増えることは容易に予測できる。これ
まで述べたようにわが国の「食」の問題
は同様にヒンドゥー教(ヒンズー教とも
いう)、シク教(シーク教ともいう)、ユ
ダヤ教、モルモン教、でも発生するであ
ろう。また、宗教上の理由による、断食、
喫煙、礼拝、なども考慮する必要もある。
また、一部の国からの旅行者は、先住民
であるか否か、人種、習慣、など全く異
なる場合もある。個人的な問題として健
康上食生活に制限があったり、身体的問
題を持つ者もいるであろう。
このように、世界中から訪日する外国
人旅行者に関し、取り組みを一元化して
迎え入れるためには、ハラール・フード
認定機関を含めた総合的な取組みをして
いく方法を考えていきたい。
9 おわりに
筆者は第3章で述べたように6次産業
における新しいビジネスのあり方に関す
る研究を始めたところである。これは、
農林水産物の有効利用による6次産業お
よび観光分野との連携による地域活力の
向上を目指した研究で、「ジャパン・ブラ
ンドのハラール・ミート」の創出に向け
た取り組みを中心に行うものである。こ
の研究はわが国における先行研究は存在
せず情報も乏しいため、現在台湾での事
例を調査中である。あわせて、沖縄県で
の ASEAN 諸国からのインバウンド誘致
政策とハラールの制度設計化に向けた取
り組みおよび神戸における公的助成によ
る神戸牛のハラール化も調査中である。
また、正式ハラール認証団体を持つノン・
ムスリムの国、例えば、オーストラリア、
ニュージーランド、ヨーロッパ諸国、な
どの事情を詳しく知る必要がある。
本研究ノートは筆者の研究における序
章にあたる部分であり結論を提示するこ
とは出来ない。しかし、「ハラール・フー
ド」および「ハラール環境」などの問題
は早期にアクションを起こす必要がある
ため、これまでの調査研究報告と今後の
研究方法について述べるにとどめた。
主要参考文献
・�C.M.�Hall・L.�Sharples・R.�Mitchell・N.�
Macionis・B.�Cambourne(2007)「Food�
Tourism� Around� the� World :
Development,�management�and�markets」
Butterworth�Heinemann
・�M.�S. ゴードン(2004)「イスラム教:
ISLAM�Revised�Edition」(奥西俊介・
訳)青土社
・�大川玲子(20�3)「イスラーム化する世
界:グローバリゼーション時代の宗教」
平凡社
・�大村次郷(20�0)「シルクロード:歴史
と今がわかる事典」岩波書店
・�片倉ともこ(�99�)「イスラームの日
常」岩波書店
・�小杉秦(�994)「イスラームとはなに
か:その宗教・社会・文化」講談社
・�小杉秦・林佳世子・東長靖(2008)「イ
スラーム世界研究マニュアル」名古屋
大学出版会
・�小林天心(20��)「国際観光誘致のしか
た:インバウンド・ツーリズム振興の
基本」虹有社
・�塩尻和子・池田美佐子(2004)「イス
ラームの生活を知る事典」東京堂出版
・�塩尻和子・青柳かおる(2007)「おもし
ろいほどわかるイスラーム」日本文芸社
・�田嶋淳子(20�0)「国際移住の社会学:
東アジアのグローバル化を考える」明
石書店
・�内藤正典(2009)「イスラムの怒り」集
英社
・�並木頼寿(2008)「日本人のアジア認
識」山川出版
・�橋本卓爾・大西敏夫・藤田武弘・内藤
重之(2004)「食と農の経済学:現代の
食糧・農業・農村を考える」ミネルヴ
ァ書房
・�樋口直人・稲葉奈々子・丹野清人・福田
友子・岡井宏文(2007)「国境を超える:
滞日ムスリム移民の社会学」青弓社
・�保坂俊司(20�2)「よくわかる世界三大
宗教」学研パブリッシング
・�堀川紀年・石井雄二・前田弘「国際観
光学を学ぶ人のために」世界思想社
・�宮崎正勝(2006)「早わかり中東&イス
ラーム」日本実出版社
・�山下晋司(2009)「観光人類学の挑戦:
「新しい地球」の生き方」講談社
・�渡戸一郎・井沢泰樹(20�0)「多民族化
社会・日本:多文化共生の社会的リア
リティを問い直す」明石書店
・�沖縄県文化観光スポーツ部(20�3)「平
成25年�ビジット沖縄計画:世界水準の
観光リゾート地の形成に向けて」沖縄

-�36-
日本国際観光学会論文集(第21号)March,2014
県文化観光スポーツ部観光政策課
・�沖縄県(20��)「沖縄2�世ビジョン:み
んなで創る�みんなの美ら島�未来の沖
縄」沖縄県企画部企画調整課
・�日本産業リサーチセンター(20�0)「観
光産業の現状と問題点-経済社会の変
化とその産業構造の与える影響-」帝
京大学経済学部
・�杉山維彦(20�3)「ASEAN諸国からの
インバウンドを円滑に行うための考
察」『第�7回日本国際観光学会全国発表
梗概集』34-35頁、日本国際観光学会
・�杉山維彦(20�3)「ASEAN諸国を対象
としたインバウンド観光におけるわが
国の課題-ハラール・フード・ビジネ
スの展開と観光学の新しい地平を求め
て-(前篇)」『月刊「国際観光情報」』、
�0月号、5-�4頁、一般財団法人国際
観光サービスセンター
・�杉山維彦(20�3)「ASEAN諸国を対象
としたインバウンド観光におけるわが
国の課題-ハラール・フード・ビジネ
スの展開と観光学の新しい地平を求め
て-(後篇)」『月刊「国際観光情報」』、
��月号、3-�3頁、一般財団法人国際
観光サービスセンター
参考文献
1 �外務省「マレーシア」『各国・地域情
勢:アジア』http://www.mofa.go.jp/
mofaj/area/malaysia/data.html 20�3
年6月1日閲覧2 �外務省「インドネシア」『各国・地域情
勢:アジア』http://www.mofa.go.jp/
mofaj/area/indonesia/data.html
20�3年6月1日閲覧3 �外務省「シンガポール」『各国・地域情
勢:アジア』http://www.mofa.go.jp/
mofaj/area/singapore/data.html
20�3年6月1日閲覧4 �外務省「タイ」『各国・地域情勢:アジ
ア 』http://www.mofa.go.jp/mofaj/
area/thailand/data.html 20�3年6月
1日閲覧5 �国土交通省観光庁(20�2)「訪日外国人
の消費者動向�平成23年�年次報告書」、
p.�26 �日本国際観光学会(2007)「観光学大事
典」、p.787 �杉山維彦(20�3)「ASEAN諸国を対象
としたインバウンド観光におけるわが
国の課題~ハラール・フード・ビジネ
スの展開と観光学の新しい地平を求め
て~(前篇)」『月刊国際観光情報』20�3
年�0月号、p.78 �e-Stat政府統計の総合窓口(20�3)「宗教
統計調査」http://www.e-stat.go.jp/SG�/�
estat/Newlist.do?tid=00000�0�847����
20�3年6月1日閲覧より筆者算出9 �Pew� Research� Center(20��)「The�
Future�of�the�Global�Muslim�Population�
Projections�for�20�0-2030」,�p.�3�0 �杉山維彦(20�2)「大久保におけるムス
リム・スポットの発生と現状」『第�6回
日本国際観光学会全国発表レジュメ
集』日本国際観光学会、p.32�� �杉山維彦(20�2)「大久保におけるムス
リム・スポットの発生と現状」『第�6回
日本国際観光学会全国発表レジュメ
集』日本国際観光学会、p.33�2 �JETRO 日本貿易振興会(20�3)「国・
地域別情報(J=FILE)」『貿易・投資
相談 Q&A:ハラル証明の取得手続き』
http://www.jetro.go.jp/world/qa/
t_basic/04A-09090� 20�3年6月5日
閲覧�3 �筒井隆志(20�2)「「食」の文化による
地域活性化~新たな地域ブランド創造
の試み~」参議院事務局企画調整室『立
法と調査 N0.326、p.��2�4 �日本国際観光学会(2007)「観光学大事
典」、p.25�5 �Al�Watan�Daily「Halal�tourism�on�the�
rise� worldwide」http://alwatan.com/
kw/Default.aspx?MgDid=650433&pag
eId=473 20�3年8月20日閲覧�6 �週間観光経済新聞(20�3年2月�6日号)
「ムスリム旅行者、官民で受け入れ充実
へ」、(通巻2692号)�7 �首相官邸「平成24年度特定地域再生事
業費補助金事業の概要書」および「平
成24年度特定地域再生計画策定事業の
内容説明書」http://www.kantei.go.jp/
jp/singi/tiikisaisei/bosyuu/pdf/j_0�.
pdf 20�3年8月�5日閲覧�8 �日本能率協会「創立70周年記念食品安
全シンポジウム:米国「食品安全強化
法」の最新情報とアジアにおける海外
展開の動向がわかる」http://school.jma.
or.jp/foodsqm/�program02.html 20�3
年7月�2日閲覧
【本稿は所定の査読制度による審査を経たものである。】