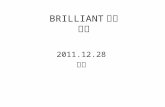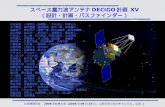春日部市にふさわしい食育の研究 - Kasukabe · 4 1.はじめに...
Transcript of 春日部市にふさわしい食育の研究 - Kasukabe · 4 1.はじめに...

春日部市にふさわしい食育の研究
~みんなで楽しく取り組むかすかべの食育~
平成26年3月

1
目 次
0.概要図 ................................................................... 3
1.はじめに ................................................................. 4
1.1 本研究の背景 .......................................................... 4
1.2 本調査の目的 .......................................................... 4
1.3 本研究の手法 .......................................................... 5
1.4 食育とは .............................................................. 5
1.5 本報告書の概要 ........................................................ 6
2.春日部市における食育の取り組みの成果と今後の課題.......................... 7
2.1 分野別にみる食育の課題 ................................................ 7
2.1.1 食と健康 .......................................................... 7
2.1.2 食と教育・文化 .................................................... 9
2.1.3 食と産業・経済 ................................................... 14
2.1.4 食とコミュニティ ................................................. 15
2.1.5 食と生活・環境 ................................................... 16
2.2 本市の食に関する対外的評価 ........................................... 18
2.3 食育推進における課題まとめ ........................................... 18
3.食育推進のモデル ........................................................ 20
3.1 食育推進のモデル自治体における取り組みとその成果...................... 20
4.春日部市にふさわしい食育とは ............................................ 27
4.1 春日部市がめざす食育の視点 ........................................... 27
4.2 春日部市にふさわしい食育 ............................................. 29
4.3 春日部市にふさわしい食育の軸 ......................................... 30
4.4 春日部にふさわしい食育のイメージ ..................................... 30
4.5 食育のメインターゲット ............................................... 32
4.6 食育推進において連携できる人(団体) ................................. 33
4.7 市民が行政に望むこと ................................................. 35
4.8 生産者・事業者等が行政に望むこと ..................................... 36
5.食育の事業提案 .......................................................... 38
5.1 人づくり ............................................................. 38
5.1.1 かすかべ食育大学の開催 ........................................... 38
5.1.2 味覚教室の開催 ................................................... 39
5.1.3 高校生・大学生とつくる食育の教材 ................................. 40
5.2 場づくり ............................................................. 42
5.2.1 かすかべの食のテキスト(素材辞典)の作成.......................... 42

2
5.2.2 食育ホームページの作成 ........................................... 43
5.2.3 かすかべ食育協力店の実施 ......................................... 46
5.3 組織づくり ........................................................... 47
5.3.1 庁内推進体制 ..................................................... 47
5.3.2 庁外推進体制 ..................................................... 48
5.3.3 連携による取り組み ............................................... 49
6.まとめ .................................................................. 59
7.おわりに ................................................................ 60
資料編 ...................................................................... 62
1(国)第2次食育推進基本計画(平成23年~27年)の要点 .................... 62
2 春日部市食育推進計画の要点 ............................................. 63

3
0.概要図

4
1.はじめに
本研究は、「春日部市健康づくり計画(第2次)・食育推進計画 1」をより実行性のある計画として
いくため、本市にふさわしい食育の具体的な施策及び事業を提案することを目的とするものである。
1.1 本研究の背景
食生活の乱れなどを発端とし、全ての国民が心身の健康を確保し生きる力を身につけていくため、
平成17年7月に「食育基本法 2」が施行された。翌年度から「食育推進基本計画」、そして平成23
年度から「第2次食育推進基本計画 3」が実施されている。一方、埼玉県においても同様に平成20
年度から「食育推進計画」、平成25年度から「第2次食育推進基本計画」に取り組んでいる。
国や県のこのような動向を踏まえて、本市においても、今年度初めて「食育推進計画 4」が策定
されることとなった。
計画策定に先立って行われた市民生活習慣実態調査の結果からは、食育の関心の薄さや朝食の欠
食、食のコミュニケーションの機会の減少や食のバランスの乱れなどの課題が明らかになっており、
このまま何も対策を講じないと、心や体の健康を損ねるだけではなく、医療費の増大や農業・産業
の衰退、日本の伝統的な食文化の喪失など社会の活力が失われる可能性がある。
これらを社会全体の問題ととらえ、市内のさまざまな関係者・関係団体等(行政や地域、市民、
学校、企業、飲食店・小売業者等)が連携・協働して、継続的かつ効果的に食育に取り組むことに
より、健康づくり計画・食育推進計画の基本理念である「笑顔あふれ、健康で幸せにいきいきと暮
らせるまちづくり」の実現を目指すことが今こそ必要である。
1.2 本調査の目的
春日部市初の食育推進計画をより実行性のある計画としていくために、市民がみんなで楽しく取
り組める食育の具体的な施策および事業を提案することを目的とする。
食育の取り組みを、より大きな「市民運動」として行っていくためには健康的視点や栄養価だけ
ではなく、産業を活性化させるという経済的視点も必要ではないかと考えた。また、継続的な取り
組みとして行くためには、身近で楽しいものであることが必要である。
このような視点にたち、春日部市が目指すべき、春日部市にふさわしい食育を見極めたうえで、
提案を行っていきたい。
1 健康増進法に規定する「市町村健康増進計画」(『健康日本21』地方計画)と食育基本法の規定による「市町村食育推進計
画」とを総合的・一体的に策定した計画。計画期間は平成26(2014)年度から平成35(2023)年度までの10か年。 2 「近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐく
むための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、国及び、地方公共
団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合
的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与するこ
とを目的とする」法律(出典:「食育基本法」第1条) 3 巻末の資料を参照のこと。 4 巻末の資料を参照のこと。

5
1.3 本研究の手法
本研究は、以下の手法により実施した。
①内閣府・文部科学省・厚生労働省・農林水産省のホームページ等により先進自治体の取り組みに
ついて情報を収集した。
②市の課題の整理については、健康課が健康づくり計画策定にあたり実施した「春日部市市民生活
習慣実態調査」の結果等により分析した。
③先進事例研究については、視察、講演会への出席、ホームページ等により情報を収集した。
④具体的な食育の事業提案については、他自治体のホームページ、食育に関する各種文献等から情
報収集を行った。
1.4 食育とは
国の「食育基本法」によると、「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべ
きもの」、また「様々な経験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な食
生活を実践することができる人間を育てる」こととされている。
国の資料 5によると、食育の理念としては、「豊かな人間形成」と「心身の健康の増進」をめざす
ものであり、分野としては、①食に関する基礎の習得(食を通じたコミュニケーション、食に関す
る基本所作)、②食に関する基礎の理解(自然の恩恵等への感謝、環境との調和、食文化、食料事情
ほか)、③食に関する知識と選択力の習得・健全な食生活の実践(食品の安全性、食生活・栄養のバ
ランス、食生活リズム)など広範な内容が含まれるとされている。
食育には、規則正しい食生活や栄養バランスのとれた食事などを実践することだけではなく、食
の安全性に関する理解、食を通じたコミュニケーションやあいさつ・マナーを身につけること、ま
た自然の恵みへの感謝や伝統的な食文化などへの理解を深めること、そして食品廃棄の削減や食品
リサイクルに関する活動なども含まれる。
したがって、本研究で考える食育の範囲は、保健分野における栄養・食生活に限定したものでは
なく、教育・文化、産業・経済、コミュニティ、生活・環境など食に関連したあらゆる分野を含む
ものとして考える。
5 出典:内閣府『平成25年度版食育白書』 資料編「食育の考え方の体系的な整理」

6
ところで、食育は「育」という漢字が入っているため、子どもに対する教育のことであるという
印象を持っている人が多いのではないだろうか。そのイメージを払しょくするため、研究グループ
で「食育」に代わる名称がないか検討したが、見いだせなかった。そのかわり、「食で育む」という
キーワードを考えた。食に関する知識を教えて育てるという発想ではなく、ともに学びながら、「食」
でひとやまちを「育」んでいこうという発想である。
「食」は「人」を「良」くすると書く。食育は人やまちを良くする可能性を秘めていると考える。
1.5 本報告書の概要
第2章では、春日部市における食育の取り組みの成果と今後の課題を明記する。次いで第3章で
は、食育推進のモデルについて言及する。そして第4章では春日部市にふさわしい食育について考
察する。第5章では、理想像を実現するための方策として食育の事業を提案する。 後に、第6章
で全体を総括する。
食育の範囲は、保健分野のみならず食に関連したあらゆる分野を含む
キーワードは、「食で育む」

7
2.春日部市における食育の取り組みの成果と今後の課題
春日部市にふさわしい食育を考える前に、本市におけるこれまでの食育の取り組みの成果と今後
の課題を整理する。
2.1 分野別にみる食育の課題
「健康づくり計画・食育推進計画」は、「春日部市総合振興計画」の部門計画として位置付けら
れている。つまり、健康づくり計画・食育推進計画の基本理念である「笑顔あふれ、健康で幸せに
いきいきと暮らせるまちづくり」を通して総合振興計画の基本理念「市民主役・環境共生・自立都
市」を目指すものである。
先に述べたように、食育に関しては分野が幅広く、食育を進めることにより、総合振興計画で掲
げる7つの目標のうち、「保健・医療・福祉」、「教育・文化」、「産業・経済」、「コミュニティ」、「生
活・環境」における課題を解決することができるという視点に立ち、これらの分野における本市の
課題を分野別にみていくことにする。なお、「保健・医療・福祉」については、分かりやすくするた
め「健康」と置き換えるものとする。
分析に使用したのは、主に「健康づくり計画・食育推進計画」の策定にあたり実施した市民生活
習慣実態調査の結果である。
2.1.1 食と健康
食は健康に大きく関わる問題であり、国の第2次食育推進基本計画では、平成27年度までに「食
育に関心をもっている国民の割合を 90%以上」という目標を掲げている。本市においても平成 34
年度までに90%以上という数値目標を掲げている。
本市の状況は「食育に関心がある」、「どちらかといえば関心がある」人は、一番高い幼児・小学
生の保護者でさえ82%、成人では66.3%、中学生に至っては30.4%にとどまっている。(図表1)
関心が低いということは、食育に関する情報が少ないことも関連していると考えられる。本市で
は各担当課で、これまでも各年代に応じた事業を実施してきたが、情報にアクセスする人は一部の
限られた人で、まだまだ食育に関する情報提供が充分ではないことが考えられる。

8
国は、栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合を、60%以上にし、内臓脂肪症
候群(メタボリックシンドローム)6の予防や改善のための適切な食事、運動等を継続的に実施して
いる国民の割合を50%以上にするという目標を掲げている。
本市の状況は、栄養のバランスやエネルギーに配慮している人の割合が成人で56%と、やや少な
い。現在、成人向けに健康相談や健康教育を行っているが、生活習慣病 7の発症の予防の観点から、
さらに若いうちからの健康教育が必要であると考える。(図表2)
このような状況を受けて、国では「健康日本21(第二次)8」において、主要な生活習慣病予防
の科学的根拠に基づいて栄養状態、食物摂取、食行動に関する目標 9を設定しており、本市におい
ても同様に取り組みを行う必要があると考える。
6 内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。内臓脂肪型肥
満とは、おなかの内臓のまわりに脂肪がたまるタイプの肥満。(出典:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/metabo02/ ) 7 生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている疾患の総称.。がん、循環器疾患、心臓病、糖尿病などが主なも
の。(出典:厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/seikatu/ ) 8 平成25年度から10年間の計画として策定。基本方針では、少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会
環境の改善を通じて、子どもからら高齢者まで全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライフステージに
応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、その結果、社会保障制度が持続可能なものとなることをねら
いとしている。(出典:厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html ) 9 具体的には、「適切な量と質の食事をとる者の増加」として、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日が
ほぼ毎日の者の割合の増加(目標値80%)、食塩摂取量の減少(目標値8g)、野菜と果物の摂取量の増加(目標値 野菜摂
取量の平均値350g、果物摂取量100g未満の者の割合30%)、さらに「共食の増加」として、食事を一人で食べる子どもの
割合の減少を設定している。(出典:同上)
食と健康の課題は、食育に関心のある人が少ないこと
栄養バランス等に配慮している人が少ないこと

9
2.1.2 食と教育・文化
次に、食と教育・文化についてみていく。
まずは、朝食の欠食について考える。
子どもの基本的な生活習慣の乱れは、学習意欲や体力、気力の低下の要因となることから、国は、
朝食を欠食する国民の割合を、子どもは0%にするという目標を掲げている。そして 20 歳代・30
歳代男性については、15%以下にするという目標を掲げている。
本市では、朝食を欠食する人(朝食をほぼ毎日食べているわけではない人)の割合は、幼児・小
学生で0.2%、中学生が1.7%、高校生が6.7%、成人が4.9%であった。成人の中でも特に割合が
低い 20・30 歳代男性では、全く食べない人は14.8%と国の目標を達成しているものの、朝食を抜
くことがある人は58%と半数以上になっている。(図表3)
なお、本市における平成34年度までの目標値は、中学生0%、20・30歳代男性については10%
としている。

10
【コラム】朝食の摂取と学力調査の平均正答率・体力との関係(平成25年版食育白書から)
毎日朝食を食べる子どもほど、学力調査の平均正答率が高い傾向にある。(図表-36)さらに、
平成 22 年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、毎日朝食を摂る子どもほど、
体力合計点が高い傾向にある(図表-37)。
これは、朝食を食べて栄養補給がしっかり出来ているという面もあるが、生活習慣が整い、食
に感謝して朝食をきちんと食べる子どもは学力も体力も高くなっている、ということでもある。

11
次に、共食について考える。
国は朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を週10回以上にするという目標を掲げ
ている。
本市では、できるだけ家族みんなで食事をしている市民(週5~7日一緒に食べている成人)の割
合を平成34年度までに80%にするという数値目標を掲げているが、現状は朝食66.6%、夕食72.6%
にとどまっている。(図表4)(図表5)
一方で中学生の11.6%、高校生の15.7%がいつも朝食を一人で食べている。一人で食べる子ども
は、疲れやすくイライラすることが多いという調査結果がある 10。
昨今、家族と一緒に暮らしていても一人で食事をとる「孤食」、さらには、家族と一緒の食卓に座
っていてもそれぞれが好きな料理を食べる「個食」等の状況が見受けられる。こうした「孤食」や
「個食」の状況が続くと、バランスの良い食事の摂取や基本的生活習慣の確立、さらには、マナー
の習得などに支障を来すことが食育白書などで指摘されており、改善の必要がある。
10 次ページコラム参照。

12
【コラム】家族との食事と心身の状況(平成24年版食育白書から)
一人で食べる子どもは、疲れやすく、イライラすることが多い傾向がある。この結果から、「共
食」は、精神面の安心感をもたらすことが分かる。
次に、栄養成分表示の普及について考える。
外食をするときや、食品を購入するときなどに栄養成分表示を参考にしている人の割合は、幼児・
小学生の保護者は90.2%と高いものの、成人の約20%が参考にしていないと答えている。(図表6)
栄養バランス等に配慮した食生活を送るために「食事バランスガイド 11」等を活用した正しい知
識のさらなる普及が求められている。
11 「食事バランスガイド」は、平成12年に当時の文部省、厚生省、農林水産省により決定された「食生活指針」の具体策
として厚生労働省と農林水産省により策定されたもので、食事の望ましい組合せやおおよその量をイラストで分かりやすく
示したもの。(出典:農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/ )

13
栄養成分表示を参考にしていない人がなぜ参考にしていないのかを尋ねたところ、いちいち見て
いられないからという理由が多数を占めていたが、栄養成分表示の見方が分からないからという回
答も約2割を占めていた。(図表7)この層に働きかけることで、栄養成分表示を参考にする人を増
やすことができる。
次に、食品の安全に関する基礎的な知識について考える。
国は、食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合を90%以上という目標を掲げ
ている。
本市では、37.4%にとどまっており、食の安全性に関する情報(食中毒や食品表示等)の提供や
学習機会が少ないことが伺える。(図表8)なお、平成34年度までの目標値は72%である。
食と教育・文化の課題は、朝食や共食の大切さが浸透していない こと
栄養成分表示や食品の安全性に関する基礎的な知識の普及が充分でないこと

14
2.1.3 食と産業・経済
次に、産業・経済、特に農業についてみていく。
本市は、肥沃(ひよく)な土壌と豊かな水利に恵まれ、米、野菜、果樹等の栽培に適している。
農業振興地域の指定は2,991haであり、市全体の約45%を占めている 12。
また、市内には5件の農産物直売所があり、79件の庭先直売所(平成25年9月9日現在)があ
る。特徴的な農産物としては、甘熟梨、赤米、黒豆、トマト、ナスなどがある。
このような中、地元産の食材を購入するように心がけている市民の割合は、47%という状況であ
る。(図表9)食育推進計画では、平成34年度までに60%にするという目標を掲げている。
地域で生産したものを地域で消費する「地産地消13」の取り組みは、消費者に「顔が見え、話がで
きる」関係で地場産物を購入する機会を提供し、食料自給率の向上や農業の活性化を図る上で重要
な取り組みとして国においても利用促進の基本方針 14が定められている。需要が増えることで生産
量が増えるという好循環を生み出すためには、関係者が連携し、地場産物を購入しやすい環境づく
りや給食、外食・中食産業や食品加工業での地場産物の活用の促進に取り組むことが必要である。
地産地消の観点から、国は、学校給食における地場産物を使用する割合を30%以上にするという
目標 15を掲げている。県の目標は、食材の種類ベースで30%以上である。
本市の学校給食における地場産物の使用状況は、5つの分類の合計で26%、分類別にみると米は
12 出典:平成25年度 埼玉の土地 13 地産地消とは、国内の地域で生産された農林水産物(食用に供されるものに限る。)をその生産された地域内において消
費する取り組み。食料自給率の向上に加え、直売所や加工の取り組みなどを通じて、6次産業化にもつながるもの。(出典:
農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tisyo/ ) 14 地産地消については、平成22年12月に公布された「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域
の農林水産物の利用促進に関する法律」に基づき、平成23年3月に「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並
びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針」(農林水産省告示第607号)を定めた。同基本方針においては、地場
産物の使用の促進の目標として①平成32年度までに年間販売額が1億円以上の直売所の割合を50%以上とすること、②平
成27年度までに学校給食における地場産の使用割合を30%以上とすることなどを規定している。(出典:内閣府『平成25年版食育白書』) 15 各都道府県において当該都道府県産の農林水産物の供給が不足している場合に国内産の農林水産物を活用していくこと
も、学校給食に地場産物を使用する目的に鑑みれば有効であることから、平成25年12月26日に食育推進会議において、
第2次食育推進基本計画が一部改定され、平成24年度において全国平均77%となっている学校給食における国産の食材を
使用する割合(食材ベース)について、平成27年度までに80%以上とする新たな目標が追加された。(出典:内閣府ホーム
ページ http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/plan/ )

15
100%市内産であるが、野菜類の使用はわずか1%にとどまっている。(図表10)
食育推進計画においては、平成 34 年度までに使用量を 31%にするという目標を掲げており、こ
れを実現させるためには、野菜類の使用の割合を1%から9%に引き上げる必要がある。また給食に
おいて米飯給食の回数を上げる 16ことも有効である。
2.1.4 食とコミュニティ
次に、食とコミュニティについてみていく。
地域におけるきめ細かな食育の推進にはボランティアの力が欠かせず、国は、食育の推進にかか
わるボランティア 17の数を平成21年度の現状値34.5万人から平成27年度までに37万人にすると
いう目標を掲げている。
本市で行った調査によると、ボランティア活動に参加しているのは成人の 1.5%であるが、潜在
的に参加の意思を持っている人を含めると16.7%がボランティア活動への参加が可能になる。
16 平成21年3月31日付け文部科学省スポーツ・青少年局長通知「学校における米飯給食の推進について」によると、米飯
給食の実施が平成19年度に全国平均で週3回の状況になったことを踏まえ、既に過半を占める週3回以上の地域や学校につ
いては、週4回程度などの新たな目標を設定し、実施回数の増加を図ることされている。(出典:文部科学省ホームページ
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1283835.htm ) 17 国においては、健康づくりのための食育アドバイザーとして活動している「食生活改善推進員」や、ボランティアの中核
となり地域の食育を推進していく「食育推進リーダー」の育成など、地域に根ざした食育の活動を推進している。地域の食
生活改善推進員の養成は市町村が行い、ボランティア団体として住民のニーズにあった食育および健康づくり事業を推進し
ている。食生活改善推進員は、地域における食育推進活動の 大の担い手であり、平成23年度は一年間で約270万回、延
べ1,684万人に対して活動を実施した。(出典:内閣府『平成25年版食育白書』)
食と産業・経済の課題は、地元産の食材のPRが不十分であること
給食における地場産物の使用量が少ないこと

16
現在ボランティア活動に参加している人が多いのは70歳以上の女性であり、参加者も高齢者に偏
っている。一方、参加の意欲が高いのは30歳代、40歳代の女性を筆頭に、60歳代女性、40歳代男
性となっている。(図表 11)この年代の人たちに働きかけると同時に、子育て世代の親へのアプロ
ーチが必要である。
2.1.5 食と生活・環境
国では、世界的な食糧問題・環境問題を解決すべく、関係省庁が連携し、官民をあげてさまざま
な食品ロス 18削減の取り組み 19が行われている。
18 「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。我が国の食品廃棄物発生量約1,700万トン/年のう
ち約500~800万トン(平成22度推計)が食品ロスであり、その削減が喫緊の重要課題とされている。(出典:消費者庁ホ
ームページhttp://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html ) 19 関係省庁(消費者庁、内閣府、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省)が連携し、官民をあげて、食品ロス削減
国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)を展開している。また、食品産業に対し、食品廃棄物の発生自体を減らす「発生
抑制」の取り組みを促進するため、平成24年4月に食品リサイクル法にもとづく「発生抑制の目標値」が設定された。食品
業界において「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」が発足し、フードチェーン全体での話し合いを行って
いる。(出典:農林水産省ホームページhttp://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/index.html )
食とコミュニティの課題は、ボランティア活動への参加が少ないこと
潜在的なボランティアの活用ができていないこと

17
また、自然の恵みに感謝して食べ物を大切にするという観点からも、「もったいない 20」という気
持ちも育成していかねばならない。
本市においては、まず家庭・学校において取り組みを進めていく必要がある。本市の小・中学校
の学校給食における残さいの状況は次のとおりである。栄養士を中心とした給食指導により、5年
間で一人一食あたり59.6gから41.9gにまで減らすことができている。(図表12)
平成 25 年度に文部科学省から「学校給食優良校」の表彰を受けた市内内牧小学校では、栄養教
諭の指導のもと、5年前(平成21年度)から本格的に食育に取り組んできた 21。取り組みをはじめ
たころから明らかに給食の残さいが減っており、取り組みの有効性を示している。(図表13)
20 広辞苑第五版(1998)によると「そのものの価値が生かされず無駄になるのが惜しい」こと。 環境分野で初のノーベル
平和賞を受賞したケニア人女性ワンガリ・マータイが、来日の際に感銘を受けた「もったいない」という日本語を環境を守
る世界共通語「MOTTAINAI」として広めることを提唱(2005)。これがきっかけとなり、スタートしたMOTTAINAIキャンペーンは、地球環境に負担をかけないライフスタイルを広め、持続可能な循環型社会の構築を目指す世界的な活動とし
て展開されている。(出典:MOTTAINAIキャンペーンホームページhttp://www.mottainai.info/ ) 21 食育の3つの柱(①魅力ある学校給食 ②多様な交流給食 ③食に関する指導)をたて、学校・家庭・地域と連携を深め
た食育を推進している。特徴的な取り組みとしては、教員との連携(教科指導との関連を持たせた献立)、家庭との連携(保
護者による「食育ボランティア」を通じた食育活動)、地域との連携(内牧地区の産物を使った献立)など。成果として、平
成25年6月以降朝食を欠食する児童がいない状態を維持している。(平成25年10月22日聞き取り)
食と生活・環境の課題は、食品ロスが多いこと
「もったいない」の意識の醸成が不十分であること
出典)内牧小学校提供資料

18
2.2 本市の食に関する対外的評価
共栄大学が行った「『春日部の魅力』に関するイメージ調査報告書(平成 21(2009)年3月)22」
によると、本市の印象について、「食」に関する評価は市内外ともに低い評価であった。(図表 14)
乏しい「食」への印象が指摘されていると同時に、今後特産品や料理などの「食」の開発に取り組
む必要があると指摘されている。
2.3 食育推進における課題まとめ
食と健康では、食育に関心のある人や栄養バランス等に配慮して食事している人が少ないこと、
食と教育・文化では、朝食や共食の大切さが浸透していないことや栄養成分表示や食品の安全性に
関する基礎的な知識の普及が充分でないことが課題であった。
食と産業・経済では、地元産の食材のPRが不十分であること、給食における地場産物の使用量
22 共栄大学国際経営学部山田耕生研究室による調査。市内外を対象としたアンケート調査に基づき、本市の魅力について研
究したもの。
本市の「食」に関する評価は、市内外ともに低い評価である
食のイメージが乏しいことを示している
図表14 春日部市の印象についての市内外相関図
出典)「『春日部の魅力』に関するイメージ調査報告書(平成21(2009)年3月)」

19
が少ないこと、食とコミュニティでは、ボランティア活動への参加が少ないこと、潜在的なボラン
ティアの活用ができていないことが課題であった。
そして、食と生活・環境では、食品ロスが多いことや「もったいない」の意識の醸成が不十分で
あることが課題であることが分かった。
本市においては、学校給食や健康指導、社会教育などを通じて食育の取り組みが行われているも
のの、まだ情報の提供や教育の機会は充分ではなく、食育が全世代に浸透しているとはいえない状
況である。
国内で食育の取り組みが「周知」から「実践」へと移行している中にあって、本市は改めて「周
知」から始めなければならない状況にある。短期間で効率よく「実践」へと導いていくためには戦
略が必要である。
そこで、研究グル―プでは、これらの課題から本市に不足しているものを3つに整理した。①主
体的に取り組む人 ②情報を集約・発信する場 ③連携して取り組むための組織である。(図表15)
主体的に取り組む人を育て、情報を集約・発信し、関係機関が連携して一体的かつ継続に取り組
んでいくことにより、目標を達成できるものと考える。
次章以降では、食をうまく活用し、まちづくりに活かしている自治体の事例を考察し、本市が食
育で何を目指すのかを考えていきたい。
図表15 春日部市の食育の課題まとめ
本市に不足しているものは、
①主体的に取り組む人 ②情報を集約・発信する場 ③連携して取り組むための組織

20
3.食育推進のモデル
食育のモデル自治体における取り組みの方向性と成果について考察する。
3.1 食育推進のモデル自治体における取り組みとその成果
特色のある自治体5つ(埼玉県坂戸市、愛知県今治市、福井県小浜市、東京都足立区、東京都墨
田区)と総合的に進めている自治体1つ(新潟県新発田市)に注目した。なお、特色のある自治体
として参考にした自治体は、実際には複合的に食育に取り組んでいるが、特徴的な部分をあえて強
調していることを断わっておく。
「健康増進型」の坂戸市では、「健康で医療費が少なく、生き生きと暮らすことができる『健康長
寿社会』の実現」を目指しており、大学と連携した食育推進事業により医療費抑制の効果が検証さ
れた。(21ページ参照)
「農業振興型」の今治市では、「地域の農林水産物やその加工品を食材として積極的に取り入れる
ことで健康的な食生活を実践し、生涯にわたって健全な心身を育む」ことを目指し、「食と農のまち
づくり」を進めており、成果として学校給食における地産地消が進み、そのノウハウを活かしたま
ちづくりが進められている。(22ページ参照)
「観光振興型」の小浜市では、「食育が市民の健康面に波及し、地域の産業の活性化につながるこ
と」を目指し、全国に先駆けて「食のまちづくり」を進めており、「食育ツーリズム」などの食に関
連した観光交流人口の増加がみられている。(23ページ参照)
「次世代育成型」の足立区では、「子どもたちの健やかな成長や生涯を通じた健康づくりを実現す
る」ことを目指し、「おいしい給食」の取り組みを行っており、成果として学校給食における残菜率
の削減、給食の時間を楽しいと感じている児童・生徒の数の増加がみられている。(24ページ参照)
「住民協働型」の墨田区では、「手間かけて みんながつながる すみだの食育」を基本理念に「み
んなが健康でたのしい食環境を通じて豊かな人生をおくる」ことを目指している。5つの基本目標
である「食」で「ひと」「家庭」「まち」「安心」「協働」を育むプロセスを「すみだらしい食育文化」
ととらえ、多様な主体による協働の活動が育まれている。(25ページ参照)
「総合型」の新発田市では、「食の循環をまちづくりに活用することで、誰もが“愛せるまち 誇
れるまち”と実感できる活力みなぎるふるさと新発田を次代に引き継ぐ」ことを目指し「食の循環
によるまちづくり」を進めている。「食」を核として、産業、健康、教育、環境、観光に結びつけた
まちづくりが着々と進んでいる。特に学校教育においては、全小中学校、全幼稚園・保育園で食育
のプラン推進が行われており、中学3年生で「一人で小煮物(のっぺ)のある夕食1食分をつくれ
る子ども」が増加している。(26ページ参照)

21
◆基本理念
食生活をはじめとした健康づくりを推進するためには、自己努力はもとより、地域の力、行政の力をバラン
スよく有効に機能させることが重要で、市民一人一人が互いに支え合う環境を構築し、誰もが毎日健康で医
療費が少なく、生き生きと暮らすことができる「健康長寿社会」の実現を目指す。
◆事業のあゆみ(坂戸市の健康づくり・食育事業のあゆみ) 平成15年3月 「あなたの出番!おいでおいで健康づくり計画」(健康日本21坂戸市計画) を策定
(平成16年度~平成25年度)
平成18年4月 葉酸プロジェクト推進事業開始
平成19年4月 食育推進事業開始
平成20年3月 坂戸市健康なまちづくり計画(健康日本21坂戸市計画(後期)・坂戸市食育推進計画)を策
定(平成21年度~平成25年度)
平成24年4月 「健康長寿埼玉プロジェクト」のモデル都市に坂戸市指定。「野菜もりもり促進事業」(葉
酸プロジェクト推進事業・食育推進事業)開始(2年間)
◆特色ある取り組み(坂戸市の健康づくり・食育事業の取り組み) 葉酸プロジェクト推進事業
○葉酸の働きや必要性、望ましい野菜摂取量の目安などの講義、個別栄養指導の実施
○野菜摂取量の変化、血液の変化についての分析
○さかど葉酸添加食品の開発
○食の健康づくり応援店制度の実施
食育推進事業
○大学と連携した市内小中学校の食育授業
○小学生の搾乳体験授業、30m位の海苔巻き作りイベントの実施
○小中学生と保護者対象のアンケート実施と効果検証
◆取り組みの成果 ○葉酸プロジェクト推進事業は、野菜摂取量の増加により医療費抑制の点で有効であった。
○食育推進事業では、一般的に学年が高くなると朝食の欠食者が増加する傾向があるが、坂戸市の小学生で
はその傾向が見られなかった。この事業は有効であり、継続的な取り組みが必要である。
出典:「坂戸市健康なまちづくり計画~健康日本21坂戸市計画(後期)・坂戸市食育推進計画~(平成21年度~平成25年
度)」、「埼玉県ホームページ 健康長寿埼玉プロジェクト(http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kenkochoju/)」
健康を増進(健康増進型) …埼玉県坂戸市
34.0%
36.0%
38.0%
40.0%
42.0%
44.0%
野菜2皿以下(1日)野菜5皿以下(1日)
1か月に支払った医療費が
「なし」の人の割合
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1中2 中3
毎日朝食を食べる児童生徒の割合

22
◆基本理念 市民一人ひとりが食に関する正しい知識を持って食を選択する力を養い、また、地域の農林水産物やその
加工品を食材として積極的に取り入れることで健康的な食生活を実践し、生涯にわたって健全な心身を育む
◆食育のあゆみ(今治市の食と農の歴史) 昭和58年 4月 学校給食に有機農産物の導入開始
平成17年12月 「食料の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言」を議決
平成18年 9月 今治市食と農のまちづくり条例を制定
平成22年 3月 今治市食育推進基本計画を策定(平成22年度~平成26年度)
◆特色ある取り組み(今治市の学校給食)
○給食の調理をセンター方式から自校方式へ切り替え
○地元の有機農産物や特別栽培米等を優先的に使用
○地産地消の学校給食から様々な食育授業を実施
○学校給食で培った知識やノウハウを活かしたまちづくりを実施
◆取り組みの成果
○学校給食の米は100%地元産特別栽培米
年 度 栽培農家数 作付面積 学校給食年間使用料の割合
平成15年度 26名 13ha 100%
平成21年度 87名 39ha 100%
○学校給食のパンの約80%は地元産小麦
年 度 作付面積 学校給食年間使用料の割合
平成13年度 1.2ha 2週間分
平成22年度 21ha 約80%
○有機農業の知識や技術を学ぶ担い手の養成
・平成11年度から「今治市実践農業講座」を開講
・平成21年度までに約150人が修了
・就農や直売所の出荷者など様々な分野で安全な食べ物づくりを実践
出典:「今治市食と農のまちづくり条例(平成18年制定)」、「今治市食育推進基本計画(平成22年度~平成26年度)」、「安井
孝(2010)『地産地消と学校給食』コモンズ」、「第14回iJAMP自治体実務セミナー 活力ある農業・地域づくり
に 向けて(2013年8月28日)時事通信社」
地産地消の推進(農業振興型) …愛知県今治市

23
◆基本理念(重点テーマ)
食育が市民の「健康面に波及すること」・「地域の産業の活性化につながること」
◆食育のあゆみ(小浜市の食のまちづくりの歴史) 平成12年 全国に先駆けて「食のまちづくり」の取り組みを開始
平成13年 小浜市食のまちづくり条例を制定
平成15年 御食国(みけつくに)若狭おばま食文化館の開館【※1】
平成16年 御食国若狭おばま「食育文化都市」宣言
平成19年 ブルーパーク阿納の開館【※2】
平成20年 小浜市食育推進計画を策定(平成20年度~平成22年度)
平成21年 わかさ国府の郷 四季菜館の開館【※3】
平成23年 小浜市元気食育推進計画を策定(平成23年度~平成27年度)
※1 食にまつわる歴史・文化や伝承料理などを展示する「ミュージアム」、郷土料理などを作り味わう「キ
ッチンスタジオ」、伝統工芸を肌で感じる「若狭工房」などがある複合施設
※2 「釣る」・「さばく」・「食べる」を自然の中で満喫することができる体験交流施設
※3 地場産農林水産物の料理実習や加工体験等ができる施設
◆特色ある取り組み(食育ツーリズム)
小浜市と民間事業者が協力して、市の資源を十分活用した食に関する体験型の教育旅行「食育ツーリズム」
メニューを確立し、地域産業の活性化と交流人口の増加につなげていく取り組み。
具体的には、①~③などを組み合わせた「食育ツーリズム」
①食育事業(キッズ・キッチンなどの調理体験)と農林水産業体験
②市内の食や農の関わる伝統行事(虫送りなど)
③市内観光
◆取り組みの成果(平成27年度までの目標値) ○食育ツーリズムへの参加者数 - ⇒ 4,000人
○食育ツーリズムの講師養成(食や命の大切さ等について語ることができる人材育成)
○食育および食に関連した観光交流人口の増加
食文化館:平成22年度 22万人 ⇒ 32.2万人
道の駅 :平成23年度目標値 34.5万人 ⇒ 54.5万人
出典:「小浜市食のまちづくり条例(平成13年制定)」、「小浜市元気食育推進計画(平成23年度~平成27年度)」
地域のにぎわいづくり(観光振興型) …福井県小浜市

24
◆基本理念
区民がさまざまな体験を通して、食への感謝と理解を深め、食を考え選択する力を身につけ、子どもたち
の健やかな成長や生涯を通じた健康づくりを実現することをめざす。
◆食育のあゆみ(足立区の食で育む足立の未来) 平成19年度 第1次食育推進計画(平成19年度~平成22年度)
平成20年度 おいしい給食の取り組み第Ⅰ期(普及・啓発)
平成23年度 第2次食育推進計画(平成23年度~平成27年度)
おいしい給食の取り組み第Ⅱ期(定着化)
◆特色ある取り組み(足立区 おいしい給食の取り組み・24年度)
○もりもり給食ウイーク(学校・保育園において、食べる時間の確保と食育の取り組み)
○給食メニューコンクール(小・中学校からテーマに沿った給食のメニューを募集)
○おいしい給食&食育フェスタ(10月6日(土)千寿本町小学校で開催)
○足立オールおいしい給食デー(給食メニューコンクールにおいて受賞作品を給食として提供)
○魚沼産コシヒカリ給食の日(足立区の友好自治体である新潟県魚沼市で田植えや稲刈りを体験)
○小松菜給食の日(地域でとれる産地に親しむ。地産地消運動)
◆取り組みの成果 ○レシピ本「東京・足立区の給食室」 7万7千部発行
○おすすめレシピと健康情報(Aメール配信) 登録者数4万6千人
○あだち食の健康応援店 62店舗
○「おいしい給食」 取り組みの成果
事 項 対象 平成20年度 平成22年度
①学校給食における平均残菜率(主食・
主菜・副菜)
小学校 7% 5.5%
中学校 13% 10%
②給食の時間を楽しいと感じている児
童・生徒の数
小学校 89% 97%
中学校 79% 82%
③食事をつくってくれた人等に感謝し
て食べている児童・生徒の数
小学校 84% 83%
中学校 79% 70%
出典:「足立区食育推進計画~食で育む足立の未来~(平成23年度~平成27年度)」、「足立区の食育活動報告集(平成22
年4月)」、「足立区ホームページ おいしい給食(http://www.city.adachi.tokyo.jp/kyushoku/)」、「足立区の給食
室製作委員会 協力:足立区教育委員会(2011)『東京・足立区の給食室』アース・スター エンターテイメント」
子どもの豊かな人間性を育む(次世代育成型) …東京都足立区

25
◆基本理念 みんなが健康でたのしい食環境を通じて豊かな人生をおくる 『手間かけて みんながつながる すみだの食育』
◆食育のあゆみ(墨田区の協働による食育推進のしくみづくり) 平成19年度 行政主導:墨田区食育推進計画の作成
平成20年度 行政主導+民支援(移行①):本格実施 専任担当配置
平成21年度 民主体+行政支援(移行②):すみだ食育推進リーダー会発足、農林水産省食育先進地モデ
ル実証事業(31プログラム)実施
平成22年度 民主導+行政支援(移行③):「民」のしくみ、すみだ食育goodネット設立
平成23年度 民主導+行政支援(自立):食育推進計画改定(地域展開型)⇒庁内作業部会(25担当)
による検討のほか、地域分科会を中心に公募区民、地域団体、NPO、PTA、児童館、事業者、企業、
大学関係者等の参画の機会をつくり、20歳~80歳代の参加を得て改定作業を実施
◆特色ある取り組み(墨田区の協働による食育事業) 5つの基本目標『食で「ひと」「家庭」「まち」「安心」「協働」を育む』を実現するプロセスを「すみだら
しい食育文化」ととらえ、多様な主体による協働の活動を育んでいる。
・複数の産地の生産者と区民を結ぶ青空市「ヤッチャバ」を、すみだ食育goodネット、ボランティアが
中心となり毎週末開催
・すみだ水族館の協力のもと、漁業関係者等と魚の命と食育について考えるパネルディスカッションを開催
・区民が栄養バランスを考えて考案した「すみだ彩り弁当」を、民間の弁当販売業者の区内店舗にて販売
◆取り組みの成果 ○食育推進体制の構築
「民」と「区」の協働による食育推進体制が確立しその基礎が整った。
・「すみだ食育推進会議」 学識経験者、食育に関する地域団体の代表者、区民などにより構成
・「墨田区庁内食育推進会議」 食育関連部署20担当の職員で構成
・「すみだ食育goodネット」 地域の食育の取り組みをつなぎ支援する組織
○食育に関する人材育成
平成20年度から平成22年度までに実施された「すみだ食育推進リーダー育成講習会」により52名の
食育推進リーダーが誕生(平成25年度も定員20名として講習会を実施)。
○食育推進運動の展開
毎年6月の食育月間に「すみだ食育フェスティバル」を開催(すみだ食育goodネットを主軸とした運
営委員会による運営。平成25年度協力団体77団体。参加者数約2万人)。
○食育の取り組みに関する情報発信
区のホームページや地域応援サイト「いっしょにネッと」における「食育通信」の発行、「すみだ食育g
oodネット」のホームページと活動冊子の配布等を通して、広く情報発信
○食育に関する調査・研究
・定量的な指標による調査: 「健康」に関する区民アンケート調査や食育フェスティバル等の開催時に認
知度・関心度等の調査
・定性的な調査: 食育活動における主体化、協働化を指標とした調査を行い取り組みの傾向を把握
出典:「墨田区食育推進基本計画(平成24年度~平成28年度)」、「第3期・第5回内閣府食育推進評価専門委員会参考資料
(平成25年2月28日)」、「内閣府資料:食育推進に関する市町村の実践事例調査報告書(平成25(2013)年11月)」、「墨
田区地域応援サイト いっしょにネット すみだ食育館(http://www.sumida25.net/syokuiku)」、「すみだ食育goodネッ
トホームページ(http://xn--good-483cqb8ojunb9b0281n6v8b.com/)」
地域のつながりを構築(住民協働型) …東京都墨田区

26
◆基本理念(食の循環によるまちづくり条例 前文から) 貴重な財産である「豊かなる大地」を育み、日々の暮らしの中で「食」の大切さを理解し、新たな発想と
着実な行動で「食の循環」をつくり、この循環をまちづくりに活用することで、誰もが「愛せるまち 誇れる
まち」と実感できる活力みなぎるふるさと新発田を次代に引き継ぐ
※食の循環とは…食に関する営みが、農産物の生産、加工、流通、調理、食事、残さ処理、堆肥生産、そし
て堆肥の大地への還元に至る一連の過程として連鎖していること
◆食育のあゆみ(新発田市食の循環によるまちづくりの歴史) 平成17年度 「食と農の資源循環型社会づくりCFT(クロス・ファンクショナル・チーム)※」設置
平成18年度 企画分野に政策専門員(食担当)を配置
平成19年度 教育委員会内に「食育推進室」を新設。「食とみどりの新発田っ子プラン」策定
平成20年度 「新発田市食の循環によるまちづくり条例」制定
平成21年度 企画分野に「食の循環によるまちづくり推進室」を新設。推進計画策定
平成23年度 「食の循環によるまちづくり推進室」と「食育推進室」を統合し「食育推進課」を新設。
※日産自動車が改革活動の一環として取り入れた手法で、課題解決のために部署や役職にとらわれず必要な
人材を集めて構成されるチームのこと。これを応用し、庁内職員、学校教諭、学校栄養職員で構成する
組織でプランの検討を行い、食を核としたまちづくりの必要性を提案した
◆特色ある取り組み(全市をあげての食育の取り組み)
○「食の循環によるまちづくり」を、総合振興計画の一部に組み込んでいる
○CFTにより、庁内の分野横断的連携と市民との協働の基礎や共通認識が図られた
○官民一体で推進するため任意団体「新発田市食の循環によるまちづくり推進委員会」を組織
○全小中学校、全幼稚園・保育園が一体となり「食とみどりの新発田っ子プラン」を進めている
◆取り組みの成果 ※平成20年度から4年間の増加量 ○小煮物(のっぺ)を一人で作れる中学3年生の割合
12.9% → 26.2% 13.3%の増加
○食事がいつも楽しいと思う小学6年生の割合
46.7% → 57.1% 10.4%の増加
○食物を残すことがとても「もったいない」と思う中学3年生の割合
52.1% → 60.0% 7.9%の増加
出典:「内閣府資料:食育推進に関する市町村の実践事例調査報告書(平成25(2013)年11月)」、「新発田市食の循環によ
るまちづくり条例(平成20年制定)」、「新発田市食の循環によるまちづくり推進計画(平成21年度~平成27年度)」、「新
発田市食の循環によるまちづくり公式サイト(http://www.syoku-jyunkan.jp/)」
食の循環によるまちづくり(総合推進型) …新潟県新発田市

27
4.春日部市にふさわしい食育とは
これまでみてきた食育における課題、食育推進のモデル自治体における取り組みを参考に、本市
にふさわしい食育を考察する。
4.1 春日部市がめざす食育の視点
食育の効果はすぐにあらわれるものではなく、10 年、20 年とかかるかもしれない。効果を持続
させるためには、継続的な取り組みが必要である。また、できるだけ多くの人を巻き込み、市民運
動として行うことにより大きな効果が期待できる。
では、食育に関心の少ない人にどのようにアプローチすればよいだろうか。
厚生労働省の報告書 23によると、「栄養状態や食物摂取状況を改善するためには、個人や集団が適
切な知識とスキルを得て、望ましい態度を形成し、具体的な食行動として実践することが必要なこ
と、個人や集団の行動変容には、環境づくり、とりわけ食環境 24の改善が重要である」とされてい
る。(図表16)
23 出典:厚生労働省「健康づくりのための食環境整備に関する検討会報告書」(平成16(2004)年3月)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1202-4.html 24 上記報告書によると、生産から消費までの各段階での整備を行い、人々がより健康的な食物入手がしやすい環境を整える
「食物へのアクセス」と、すべての人が健康や栄養・食生活に関する正しい情報を的確に得られる状況を作り出す「情報へ
のアクセス」があり、食環境とは「食物へのアクセス」と「情報へのアクセス」、並びに両者の統合を意味するとされる。
図表16 健康づくりと食環境との関係

28
知識・態度・行動レベルに訴えていくためには、情報を入手しやすいように整備したり周囲の環
境を改善したりすることと同時に、身近な人(家族、友人、職場)を通して訴えかけるなどのきっ
かけづくりが必要であることが分かる。
では、食育に関心のない人が自ら行動するようになるためにはどのような動機づけが必要なのだ
ろうか。
図表17は、教育場面において生徒の自ら学ぶ意欲が発現するプロセスを表すモデルである。
内発的な動機づけを支えているものとして、「有能感」「自己決定感」「他者受容感」という3つの
要素がある。有能感とは「自分なら頑張ればできる」という本人の気持ちであり、自己決定感とは
「自分のことは自分で決めている」という気持ちである。他者受容感とは「自分は周りの大切な人
から受容されている」という気持ちである。この3つの要素が自ら学ぶ意欲をもたらし、楽しさや
満足感が生まれるということである。
図表17 内発的学習意欲の発現プロセス
出典)桜井茂男(1997)『学習意欲の心理学 自ら学ぶ子どもを育てる』誠信書房
食育のアプローチは、身近な人から
「できる」という気持ちを引き出し、楽しく学べる工夫を

29
4.2 春日部市にふさわしい食育
食育により何を目指すのか。研究グループでは、 終的な理想形「10年後の未来」について、次
のように検討した。
身近な人から伝える、楽しい食育!
「10年後の未来」
○【ふ】ふるさとの食文化が伝わっている →【食文化】を育む
・地元の食材や旬をいかした食事を楽しんでいる
・「和食 25」文化が次世代に継承されている
・高校生までに和食や郷土食が作れるようになっている
○【さ】サンキューの気持ちで食べている →【こころ】を育む
・五感を使ってわくわくしながら食を楽しんでいる
・「いただきます」「ごちそうさま」などのあいさつができている
・食べ残すことを「もったいない」と感じる気持ちが育っている
○【わ】和気あいあいと食卓を囲んでいる →【家庭】を育む
・家族や仲間と一緒においしく楽しく食べている
・地域での共食の機会が増加している
○【し】生涯にわたって食でひとを育てている →【ひと】を育む
・栄養バランス、適量を判断し、自己管理を実践している
・食事と生活習慣病との関連について知識をもち食生活に活かしている
・知識や経験を生かして食の大切さを伝えている
○【い】一連の食の営みが整っている →【まち】を育む
・農業体験などを通じて食の循環を理解している
・地産地消が定着、生産者と消費者がつながっている
・安心して中食 26・外食を活用できる環境が整っている
春日部市にふ・さ・わ・し・い食育とは
食で「文化」「こころ」「家庭」「ひと」「まち」を育む
食環境が豊かで魅力的なまち
25 平成25年12月、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録された。「和食」は、「自然の尊重」
という日本人の精神を体現した食に関する「社会的慣習」として提案された。特徴としては「多様で新鮮な食材とその持ち
味の尊重」、「栄養バランスに優れた健康的な食生活」、「自然の美しさや季節の移ろいの表現」、「正月などの年中行事との密
接な関わり」である。(出典:農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/index.html ) 26 中食とは、惣菜店やコンビニエンスストア・スーパーなどでお弁当や惣菜などを購入したり、外食店のデリバリーなどを
利用して、家庭外で商業的に調理・加工されたものを購入したりして食べる形態の食事。単身者、高齢者の世帯のみでなく、
全世帯で中食の利用は増加傾向にあり、健康管理の上でも、中食の選び方を考える必要がある。(出典:厚生労働省 メタボ
リック症候群が気になる方のための健康情報サイト e-ヘルスネット
http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-03-010.html )

30
10 年後の理想を、食で「食文化」「こころ」「家庭」「ひと」「まち」を育む、「食環境が豊かで魅
力的なまち」となることと考えた。これは同時に、本市の総合振興計画に掲げる将来像「人・自然・
産業が調和した 快適創造都市―春日部―」を目指していくものでもある。
4.3 春日部市にふさわしい食育の軸
理想の食育「食環境が豊かで魅力的なまち」を推進していくための、5つの軸について検討する。
前節で、春日部にふさわしい食育として挙げた5つの視点から考えると次のようになる。
ふ ふるさとの食文化を伝える →【食文化】を育む
さ サンキューの気持ちで食べる →【こころ】を育む
わ 和気あいあいと食卓を囲む →【家 庭】を育む
し 生涯にわたって食で人を育てる →【ひ と】を育む
い 一連の食の営みを整える →【ま ち】を育む
【食文化】を育むには、地域の食の発信や「和食」の継承を含む。
【こころ】を育むには、食を楽しむ気持ちや感謝の醸成、食品ロスの削減を含む。
【家庭】を育むには、親子や夫婦で、また世代間交流しながら楽しく食べる共食の推進、共食の
機会の提供を含む。
【ひと】を育むには、栄養成分表示や食の安全の知識の普及、食と健康についての学習機会の提
供、ライフステージをつなぐ切れ目のない食育を含む。
【まち】を育むには、食の循環(生産から食卓まで)の理解、地産地消の推進、安心して外食・
中食を利用できるしくみづくりを含む。
4.4 春日部にふさわしい食育のイメージ
「食文化」「こころ」「家庭」「ひと」「まち」の5つの軸で取り組みを行い、さらにそれぞれの取
り組みを互いに連携させつなげることで、はじめて 春日部市に「ふ・さ・わ・し・い」食育が開花
する。今までは、それぞれ「点」で行われていた食育の取り組みをつなげることで、「食育の環わ
27」
27 内閣府「食育ガイド(A Guide to “Shokuiku”)」に掲載された食育の考え方。(内閣府ホームページ)
http://www8.cao.go.jp/syokuiku/data/guide/
春日部にふさわしい食育とは、食で「食文化」「こころ」「家庭」「ひと」「まち」を育み、
「食環境が豊かで魅力的なまち」を目指すことである

31
がつながり、「食環境が豊かで魅力的なまち」を目指すことができる。(図表18)(図表19)
図表18 春日部市にふさわしい食育のイメージ
図表19 食育の環のイメージ

32
4.5 食育のメインターゲット
では、どの世代を中心に進めていくのがよいだろうか。図表 20 は、食育についてどの世代を中
心に進めるのが良いかを市民に聞いた結果である。
調査結果から、小学生、幼稚園・保育園が多く、次に中学生、子育て中の親となっている。
確かに子ども自身への食育は大切である。人間の嗜好が形成されるのは離乳期から10歳ごろまで
であり、この時期に脳のネットワークの正しい構築が重要であることは専門家から指摘されている
とおりである 28。また、おいしさと個人の嗜好は密接な関係にあり 29、おいしさを理解するように
なるためには、子どもの時から、「食事は楽しい、おいしい」という感覚を育てることや、様々な食
品の味を体験し味覚学習をすることが必要であると考えられている。
では、家庭における食育の担い手はだれか。
図表21は食事を主に作る(提供する)のはだれかを聞いた結果である。
幼児から高校生まで、食事を主に作るのは父母などの家の人がほとんどを占めている。この結果
からも、まず子どもをもつ保護者に向けた食育が重要であることが分かる。
28 子供のころに与えた食べ物が、どのように成長後の嗜好に関わるかを研究した結果、離乳期完了前のカツオだし風味食体
験は成長後のカツオだしへの嗜好性を著しく高めることが分かった。このころに経験した食が子供の嗜好の大枠に影響する
ことが明らかになった。(出典:伏木亨(2008)『味覚と嗜好のサイエンス』丸全(株)) 29 嗜好のパターンとしては、①生理的な欲求が満たされるおいしさ ②食文化に合致したおいしさ ③情報がリードするお
いしさ ④やみつきになるおいしさ がある。このうち、②と③は人間特有のもので、特に②は幼児期から食べ続けると好
きになりやすいといえる。(出典:伏木亨(2008)『味覚と嗜好のサイエンス』丸全(株))

33
そうはいっても、食育に無関心であったり協力が得られなかったりする保護者もいるであろう。
その場合には、義務教育である小・中学校において直接子どもたちへの学びを提供することが重要
になってくる。幸い、本市では全小・中学校で給食を通じた食育 30が行われており、栄養士を中心
として今後も取り組んでいくことにより効果が期待できる。さらに取り組みを拡大して実施するに
は、校長先生をはじめとする教職員や地域の人の協力が必要であろう。
また、思春期から青年期へ移行していく時期にあたる高校生・大学生は、成長段階にあるため引
き続きサポートしていくことが必要である。日々の食べる行為の加減や積み重ねが生活習慣病の可
能性など長期的に影響を及ぼしていくことを考えると、この時期までに食の大切さを認識し、食を
選択する力を身につけることの重要性が分かる。
本市は、「日本一幸せに子育てができるまち」の実現に向けて子育てしやすい環境づくりを目指し
ており、子どもをもつ世代を中心に取り組みを進めることは、方向性が一致している。
4.6 食育推進において連携できる人(団体)
食育推進計画を進めるにあたり所管及び関係機関として考えられるのは、図表 22 のとおりであ
る。食育推進計画策定にあたっては、これらの団体のメンバーと関係課職員で構成するワーキング
グループで計画案や取り組み方針の検討を行ってきた経過がある。
30 市栄養士会では、ホームページを開設し(http://www.boe.kasukabe.saitama.jp/eiyou/top.html) 、栄養士会の活動紹介
や食育通信、学校給食献立・レシピなどを公開している。
メインターゲットは、子どもをもつ保護者、次に乳幼児~中学生までの子ども、
その次に高校生・大学生

34
図表22 食育推進計画の所管及び関係機関
ここでは記載を省略するが、このほかにも食や農に関係する各種団体やボランティアなどが数多
く存在する。
千葉県市川市では、計画策定の作業経緯から発展し、庁内の食育事業関係課で関わりのある関係
団体を巻き込んで食育を推進しており、新たな取り組みにつながっている 31。本市においても、こ
のような手法でネットワークを構築していくことは可能ではないだろうか。
また、各学校においてはPTAや地域の人々と連携することにより取り組みを強化することがで
きるし、地域においては趣旨に賛同する食品関係事業者と連携することにより食育にあまり関心が
ない層に対するアプローチもできる。
また見方を変えて、指導されるターゲットとなるべき人に、食育の推進役として主体的にかかわ
ってもらうよう働き掛けることも可能である。例えば、高校生や大学生に食育の教材を作成しても
らうことなどが考えられる。また、子どもを育て上げたシニアの方などに、少しの講習を受講して
もらった後で学校などでの食育サポーターとなってもらうこともできる。
先ほどの調査で、27.3%が全ての年代に食育を行った方がよいと回答していたが、これらの手法
により、全ての年代にきめ細かく食育を浸透させることができると考える。
31 庁内食育関係課で関わりのある関係団体のネットワーク会議「市川市食育推進関係機関連絡会」を中心として市内の民間
団体やNPO法人、大学などからイベント参加の声が上がり、波及効果として行政と民間、民間と教育、民間とNPO法人
などが連携し、新たな取り組みにつながっている。(出典:内閣府資料(平成25(2013)年11月)『食育推進に関する市町
村の実践事例調査報告書』)
連携できる人(団体)は、食育推進の所管課と関わりのある関係団体、趣旨に賛同する各種
団体・ボランティア・食品関係事業者、食育のターゲットとなるべき高校生・大学生、シニ
ア層など
関係機関等
健康課(健康センター、健康福祉センター)医師会、歯科医師会、歯科衛生士会、助産師会、母子保健推進員、食生活改善推進員協議会、春日部保健所地域活動栄養士会
介護保険課 地域包括支援センター
国民健康保険課
高齢者支援課
子育て支援課(児童館)
保育課(公立保育所、子育て支援センター) 子育て支援拠点
暮らしの安全課 くらしの会
市民参加推進課(市民活動センター、コミュニティセンター、男女共同参画推進センター)
学務課 私立幼稚園協会、学校栄養士会
指導課(小・中学校)
社会教育部 中央公民館(公民館)
環境政策推進課
資源循環推進課
農政課 農業団体連合会など
商工観光課 道の駅「庄和」、商工会議所
防災対策課
政策課 包括的連携協定を締結している大学
シティセールス広報課
所 管
健康保険部
福祉部
市民生活部
学校教育部
環境経済部
その他

35
4.7 市民が行政に望むこと
食育の取り組みを行っていく上で、市民、事業者が行政に望むことを明らかにする。
まず、市民のニーズは図表23のとおりである。
幼児・小学生の保護者の一番の関心事は、「心身の健全な発育」、次いで「食生活の乱れ」と「生
活習慣病の予防」、そして「食や自然に対する感謝」であることが分かった。中・高校生は、容姿が
気になる年頃であり、肥満ややせの増加に関心をもっている。また、昨今のニュースでたびたび話
題となっている、食の安全についても関心が高いことが分かった。
子どもをもつ市民が関心をもっている食育に関する情報は、
「心身の健全な発育」、「食生活の乱れ」、「生活習慣病の予防」

36
4.8 生産者・事業者等が行政に望むこと
まずは、生産者等のニーズについて考える。
以下は、農林水産省が農業の6次産業化 32を進めるにあたり課題の抽出を行った結果である。
この調査から、生産における課題は需要に即した生産物の安定供給とコスト低減、加工における
課題は生産性の向上と加工技術等の習得、販売における課題は広告宣伝や販路の開拓等の販売促進
機能の強化であることが分かる。
本市の農業生産者全てが6次産業化を目指しているわけではないが、これらの課題は共通した課
題であると考える。
例えば学校給食等において、年間の必要量等を把握したうえで供給体制を整えれば、安定供給に
つなげることができる。まずは、生産者等の声を聞くことが重要である。
32 農林水産省が推進している取り組みで、農山漁村の活性化のため、地域の第1次産業とこれに関連する第2次、第3次産
業(加工・販売等)に係る事業の融合等により地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行うもの。(出典:農林水産省ホー
ムページ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html )
図表24 農業の6次産業化に向けた課題 (平成24 年度 食料・農業・農村白書から)
出典

37
次に、事業者等のニーズを考える。図表25は、内閣府が食育推進活動を取り組むにあたって行政
に期待することを尋ねた結果である。
事業者が行政に期待することは、食育推進に関する情報の提供や食育推進に関する先進事例の紹
介、そして食育推進に関して企業同士が交流する場の提供であることが分かる。
事業者を含めたネットワークの構築により、事業者の期待に応えることができると同時に、事業
者と一体となって食育を進めることができる。
生産者等のニーズは、「需要に即した生産物の安定供給」、「広告宣伝や販路の開拓等の販売
促進機能の強化」など
図表25 行政に期待すること
出典:内閣府「企業分野等における食育推進の実態・分析調査」(平成20(2008)年7月公表)
事業者等のニーズは、食育推進に関する情報の提供や食育推進に関する先進事例の紹介、そ
して食育推進に関して企業同士が交流する場の提供など

38
5.食育の事業提案
第2章で食育における課題(不足しているもの)を、①主体的に取り組む人 ②情報を集約・発
信する場 ③連携して取り組むための組織と考えた。そして、第3章で食育推進モデル自治体にお
ける取り組みの方向性について考えてきた。
食育の取り組みを大きな運動として取り組んでいくためには、まず食育を理解し、推進する人を
増やすことが必要である。そして食育に関心を持った人が「楽しみながら」かつ「身近な人のため
に」行う食育活動をサポートする場、また食育推進に関わる多様な主体や活動をつなぐ組織が必要
である。
食で【食文化】【こころ】【家庭】【ひと】【まち】を育み、理想の食育「食環境が豊かで魅力的な
まち」を推進していくために、人づくり、場づくり、組織づくりの3つの視点から事業提案をする。
それぞれについて、春日部に「ふさわしい」食育の5つの軸及びライフステージ 33のどこをター
ゲットとしているのかを明らかにしたうえで提案をしていく。なお、提案書は、50 ページから 58
ページに掲載する。
5.1 人づくり
食育推進計画においても、「市民、地域、行政が役割分担を行いつつ、ライフステージをつなぐ
切れ目のない食育を推進していく」とされている。あらゆる年代にくまなく食育を浸透させるため
には、要となる春日部の食育を支える人材(食育推進リーダー)を育成することが必要である。リ
ーダーの活動を通じて、次にさまざまな事業展開が可能である。
行政の役割は、食育について実践的に学ぶ場を提供することと、知識を身に付けた人が学んだこ
とを身近な人に伝える役割を果たせるよう後方支援していくことであると考える。
5.1.1 かすかべ食育大学の開催
食育の軸は【ひと】【まち】、主なライフステージは「高齢期」「壮年期」である。
食に関する正しい知識をもつ人材を育成し、春日部市の食育の推進役となってもらうために、大
学を開催するものである。
参考としたのは、墨田区の「すみだ食育推進リーダー育成講習会」の取り組み。地域の食育推進
に貢献する意欲があり全日程受講できる方を対象に、毎年10日間の日程で実施し、講習後は、地域
の食育力の向上を図る人材として活躍している。
現在、食育においてとくに国等からの資格が認められたものは、栄養士、管理栄養士 34のみであ
33 春日部市食育推進計画では、ライフステージを大きく8つ {1.胎児期 2.乳幼児期(0~6歳) 3.小学生期(7~12歳) 4.中学生期(13~15歳) 5.高校生期(16~18歳) 6.青年期(19~39歳) 7.壮年期(40~64歳) 8.高齢期(65歳以上)} に分けている。 34「栄養士」は、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者(栄養士法1条1項)。「管理栄養士」は、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて(中略)栄養改善上必要な指導等を
行うことを業とする者(出典:栄養士法1条2項)。

39
り、ほかに公的な食育資格はない 35。現状では、栄養士等は学校や病院等施設での食の指導などを
主な業務としており、地域での食育にほとんど携わってはいない。では食育の人材はいないかとい
うとそうではない。子どもを育て上げた人や現役を退いたもののかつて食に携わってきた人など宝
となるべき人材がいる。
そこで、資格の有無にかかわらず、地域で食育に携わりたいという意思をもつ人材を掘り起こし、
自主的な学びを通して春日部の食育の推進役として育成することを提案する。修了生には、「食育推
進リーダー」の認定証を交付し、人材登録していただくことにより地域への取り組みにつなげてい
く。
この取り組みにより、①春日部の食育の推進役が育つ ②家庭や地域に食育の取り組みが広がる
③息の長い安定的な食育活動を行うことが可能になる などの効果が期待される。(図表26)
5.1.2 味覚教室の開催
食育の軸は【ひと】【家庭】、主なライフステージは「小学生期」(とその保護者)である。
和食を中心とした食文化を次世代に伝えるために、地域が一丸となって、子どもたちの味覚を鍛
え、食の基礎教育を行うものである。
参考としたのは、「味覚の一週間 36」の取り組み。食文化の乱れが深刻となったフランスで、フラ
ンス料理という国民的遺産の素晴らしさを発見、学習する場として開催され、現在、企業だけでな
35 「フードスペシャリスト」、「食生活アドバイザ―」「食育アドバイザー」などはすべて、民間の任意の資格である。 36 「味覚の一週間」は1990年10月15日、ジャーナリストで料理評論家のジャン=リュック・プティルノー氏とパリのシ
ェフたちが一緒になり、「味覚の一日」を開催したことに始まる。1992年からは「味覚の一週間」という名称になり、2013年に24周年を迎えた。「味覚の一週間」の中心的な活動である「味覚の授業」(2013年度)では、200校、5000クラス、150,000人の子供たちが参加した。(出典:味覚の一週間ホームページ http://www.legout.jp/ )
図表26 「かすかべ食育大学」の開催

40
く、政府機関も参画し国を挙げた「食育」へと成長している。そしてフランスでの取り組みを参考
に、ここ数年、民間団体により日本でも広まりつつある 37。 また、札幌市中央区では調理専門学校
と連携して味覚教室などの食育の教え方マニュアルを作成している例もある38。
対象とするのは、小学校中学年。小学生期に行う理由は、人間の嗜好が形成されるのは離乳期か
ら10歳ごろまでであり、嗜好が固まる前でかつおいしさを表現できる年齢というのがその理由。高
学年を対象にする場合は、調理実習等とセットにし、低学年を対象にする場合は、保護者と一緒に
することによりアレンジが可能である。
現状のまま、嗜好のまま偏った食事を続けていると、食を楽しめないばかりか健康を害する可能
性もある。一方、味覚教室を実施することにより、①味わう楽しさを知る ②食への関心が高まる
③和食や素材のおいしさが次世代に伝わる などの効果が期待される。(図表27)
5.1.3 高校生・大学生とつくる食育の教材
食育の軸は【ひと】【こころ】、主なライフステージは「高校生期」「青年期」である。
将来子どもを産み育てる「未来の親」たちに、食生活や健康への関心を高めてもらうため、同世
代の高校生や大学生と協働して食育の教材を作成するもの。
37 日本における「味覚の一週間」は、2014年、日本での開催4年目を迎える。「味覚の一週間」の3つの柱は、①食のプロ
フェッショナルから、味の基本と味わうことの大切さを学ぶ「味覚の授業」、②家族や友人とコミュニケーションを通じて、
味わう楽しさを見つける「味覚の食卓」、③さまざまな味覚体験活動に参加して、食の楽しみを広げる「味覚のアトリエ」で
ある。(出典:味覚の一週間ホームページ http://www.legout.jp/ ) 38 光塩学園調理製菓専門学校と札幌市中央区で共同開発したK-Cプログラム(食育の教え方マニュアル)をホームページ
に掲載し、食育の取り組みを進めている。(出典:札幌市ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/chuo/kenko/recipe/kcpuroguramu.html )
図表27 味覚教室の開催

41
参考にしたのは、愛知県教育委員会が高校生と共同で作成した学校教育資料(高校生向け資料)
「食生活大作戦 39」の取り組みや、兵庫県が同様に作成した高校生向け「健康マイ・プラン手帳 40」
の取り組み。
食育に関する様々な取り組みが行われている中で、若い世代に向けた取り組みや、若い世代の参
画が少ないことから、検討した事業である。作成に関わった学生の意識変革はもちろんのこと、同
世代からのアプローチによる効果的な情報発信をねらいとする。市内に食に関する専門学校等がな
いことから、高校・大学のクラブ活動の協力を得て作成する。作成した教材は、学校の授業での活
用や市民への配布などにより活用していく。
まずは同世代へ向けた教材の作成を目指すが、発展形として子どもや一般・高齢者向けの教材を
作成することも考えられる。例えば、福井県では高校生が授業で作成した「食育カルタ 41」を活用
し、食育の取り組みが行われている。保育実習にとどまらず、「ふくい食育ボランティア」として登
録し、保育園や小学校で出前授業をしたり、高齢者向けの食育カルタの制作を検討したりと広がり
をみせている。(図表28)
39 高校生を対象とした望ましい食生活を実践していく能力を身に付けるための啓発資料として平成25年(2013)11月作成。
食事のチェックシートや間食(夜食)やダイエット、朝ごはんなどについて記載、イラストを県立高校生が担当している。(出
典:愛知県教育委員会ホームページ http://www.pref.aichi.jp/0000066850.html ) 40 若い世代(特に、将来を考え受験や就職に備える時期である高校2年生)が食生活や健康づくりに関心を持ち、知識と実
践をサポートするために平成24年(2012)3月に作成した手帳。「自分の健康は自分で考えよう」をメッセージに、自分で
チェックシートやワークシートに「マイ・プラン」を考えながら記録できる内容。編集は、庁内関係課職員と大学教授、高
校教諭、栄養士会、保健所などで構成するマイ・プラン手帳作成検討会メンバーであるが、高校生が描いたイラストやまん
がを掲載している。(出典:兵庫県ホームページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/eiyoukenkoumyplan.html ) 41 食と農を学ぶ農業高校生として、授業で学んだことを食育活動として広めることはできないかと考えた県立若狭東高等学
校生活科学科の高校生が、平成18、19年度に制作したもの。カルタの内容は地元の食材や郷土料理、食事の基本的なマナー
や栄養を取り扱ったものなど。高校生が保育実習で子どもたちと一緒にカルタ遊びをする中で、子どもたちに食の大切さを
伝えている。(出典:福井県ホームページ http://info.pref.fukui.jp/hanbai/120_syokuiku/business_activity.php )
図表28 高校生・大学生とつくる食育の教材

42
これにより、 ①健康や食生活への関心が向上する ②自らの食生活を考え実践する若者が育つ
③学校と地域とのつながりが生まれる などの効果が期待できる。
5.2 場づくり
食育に関心のある人もそうでない人に対しても、折りにふれて正しい食育の情報にアクセスでき
る環境を整えることが必要である。
行政の役割は、望ましい食生活に関する知識や食の安全・安心に関する情報、食育の推進に向け
た取り組みなどの情報をホームページ等を通じて分かりやすく提供するとともに、市民一人ひとり
が食育を実践しやすいよう場(環境)を整えることであると考える。
5.2.1 かすかべの食のテキスト(素材辞典)の作成
食育の軸は【まち】【食文化】、主なライフステージは「小学生期」「青年期」である。
地元農産物に関する情報を集約化させ、地域の食を活用した収穫体験や調理実習などの際に活用
できるような食育のテキストを作成していくもの。
参考にしたのは、イタリアのスローフード 42で実施されている味覚のワークショップ 43。ワーク
ショップのベースとなっているのは、「マスター・オブ・フード 44」という食のテキストである。こ
れらを通して、教育分野のみならず地域のブランド化、さらには観光事業の景観を活かしたツーリ
ズムに直結する仕組みになっている。経済的視点に立った食育ということがポイントであり、食育
の取り組みを持続可能なものとするための秘訣となるということである。これを習った日本版ワー
クショップが各地で実践されている。
本市では、幸いなことに米、野菜、果樹等の栽培が身近に行われており、農業体験できる施設や
農産物直売所・庭先直売所も多く存在する。食文化を語る前に、まず地域で作られている食材その
ものをきちんと知る必要がある。食材の品種と味の違い、おいしい調理の仕方までを含めてその特
徴が物語として語られるようになって初めて、地域の特産品として認識されたことになるのではな
いか。その基礎ができないかぎり応用(食のブランド化)はできない。
テキストの作成にあたっては、農林振興センターや農家等と連携することにより知識を深め、さ
らに料理人や食の専門家などと連携することによりその幅を広げることができる。子どもに分かり
42 スローフードとは、1986年にファストフードへの反対をきっかけに起こった、食を中心とした地域の伝統的な文化を尊
重しながら、生活の質の向上を目指す世界運動。スローフードの理念に賛同する会員が所属する国際的なNPOであるスロ
ーフード協会は、イタリアで1989年に設立され、現在世界150ヶ国に1,300以上の支部を持ち、10万人以上が参加してい
る。スローフードジャパンは全国で47支部、1000人を超える協会会員の活動を支える。(出典:スローフードジャパン ホ
ームページ http://www.slowfoodjapan.net/ ) 43 イタリアでは「ラボラトリー」とも呼ばれている味覚のワークショップが、スローフードの大学、イベントなどで年400回以上も開催されている。伝統的な食材を通して、その歴史、環境、加工法、素材を学び、その味わい、風味、香りなどを
実際にテイスティングをして知るというもの。輸入食品や大量生産の食品の氾濫などで、地域の伝統的な食品や農産物など
が途絶えてなくなるという危機から始められたもの。(出典:金丸弘美(2007)『創造的な食育ワークショップ』岩波書店) 44 スローフード協会の手で会員向けに作られた食のテキスト。テキストは、チーズ、トリュフ・きのこ、オリーブオイルな
どイタリア人が日常に食べるものを中心に18種類23講座が作られている。講師にはスローフード協会のメンバーをはじめ、
生産者や食品の組合のメンバーなどが登録されている。(出典:金丸弘美(2007)『創造的な食育ワークショップ』岩波書店)

43
やすいテキストを作成することにより、調理実習や学校の食育の副教材などにそのまま活用するこ
とができる。また、取り組みに関わった人たちはその物語を伝える側になり、あらゆる場面で魅力
を伝えていくことになる。
これにより、①地元農産物に対する知識の集約化ができる ②地元農産物の魅力を多方面に発信
できる ②いろいろなモノ(物・者)とのつながりが生まれる などの効果が期待できる。(図表
29)
5.2.2 食育ホームページの作成
食育の軸は【ひと】【家庭】、主なライフステージは「青年期」(「胎児期・乳幼児期」「小学生期」)
である。
本市における食の情報を集約化させ、食に関する情報を楽しく、分かりやすく、タイミング良く
提供するためにホームページを作成するものである。
では、ターゲットとする子どもをもつ親に何をどう伝えるべきか。図表30は、関東農政局が母親
や若者を中心とした現代人の食生活の現状と課題を探った調査結果である。
図表29 かすかべの食のテキスト(素材辞典)の作成

44
21 歳から 45 歳の女性は、7割前後が栄養の知識よりも「献立や調理方法」の実践を知りたいと
答えている。一方男性では「バランスの取れた食事の取り方」が も多くなっている。(図表30)
一方、市で行った意識調査を年代別に分析すると、子育てをしている世代と思われる 20 代~40
代が重視している項目は「食生活・食習慣の改善」「食品の安全性に関する理解」「自然の恩恵や生
産者等への感謝・理解」であることが分かる。また、その年代は、食に関する意識がとても高いこ
とが分かった。(図表31)(図表32)
図表30 食生活改善のために知りたい情報
出典:関東農政局「 近の食生活に関するアンケート調査」(平成16(2004)年6月公表)

45
これらを総合的に判断すると、子育てしている世代は食育への関心が高く、子どもに規則正しい
食習慣や望ましい食生活、自然の恵み等への感謝を身に付けてもらおうと日々努めている姿が浮か
び上がってくる。そのため、より実践的なアドバイスや体験できる場を求めていると考えられる。
このことから、子どもに「食べる楽しさ」や「感謝のきもち」を伝えるために役に立つホームペ
ージとなるように配慮しながら作成する。子どもに分かりやすく説明できるような内容であるとい
うことは、すべての年代にとっても分かりやすい内容であるといえる。市民の間で食育の共通認識
ができれば、次の段階として他の年代への食育の取り組みにつながっていくのではないか。
このことにより、①食を通じて子育てへの支援ができる ②子どもの食生活・食習慣の改善がで
きる ③市民の間に食育の共通認識が図られ、次の取り組みにつながる などの効果が期待できる。
(図表33)
・ 幼児・小学生をもつ保護者は子どもが規則正しい食習慣を身に付けられるよう食に関する意識が高い傾向がみられる。
・ 「できるだけ家族で食べる」「夕食後のおやつを控える」を心がけている人は多い。
・ 外食は週数回以上利用するのは1割に満たず少なく、家庭の手作り料理を食べている人が多い傾向にある。
・ 栄養表示は保護者の6割くらいが見たことがあり、そのうち9割近くの人が参考にしており、食への関心が高い。
・ 食育への関心も高く、関心がある、どちらかといえば関心がある人は8割くらいである。
・ 食育を受ける環境にあると思う、まあそう思う人は8割弱である。
出典)春日部市生活習慣実態調査(平成25年3月)
図表32 実態調査から分かる幼児・小学生をもつ保護者の意識
図表33 食育ホームページの作成

46
5.2.3 かすかべ食育協力店の実施
食育の軸は【ひと】【まち】、主なライフステージは「青年期」である。
栄養成分表示や健康に配慮したメニュー等の提供により食育や健康づくりを応援してくれる店舗
と連携をとりながら食育を推進するしくみをつくる。
主なターゲットとしているのは、外食等の機会が多い青年期の世代である。実態調査からも、20
歳代~30歳代の男性、20歳代女性の中食利用率が高いことが分かる。(図表34)
参考としたのは、足立区の「あだち食の健康応援店 45」及び坂戸市「健康づくり応援店 46」の取
り組み。いずれも、栄養成分表示や栄養情報提供、ヘルシーメニューの提供など健康づくりを応援
してくれる店舗を指定し、食に関する情報の発信基地となってもらっている。足立区では、さらに
体験・見学ができる食の店についても対象としており、飲食店、コンビニエンスストア、弁当屋、
食品販売店などが登録している。
ただし、単に指定をして終わるのではなく、その後の活用の仕方が重要である。足立区では、栄
養士が隔月で作成した「食の健康応援店だより」を置いてもらったり、年1回情報交換会を開催し
たりすることによって店舗間、店と市の連携を図っている。
これにより、①栄養成分表示の活用により、外食・惣菜の選択能力を習得できる ②地元農産物
の活用意識が向上する ③食育協力店間、食育協力店と市との連携強化が図れる などの効果が期
45 「あだち食の健康応援店」は、①からだサポートの店(栄養成分表示をしている、野菜たっぷり・塩分ひかえめなどの健
康に配慮したメニューを提供している) ②体験・見学ができる食の店 ③食のミニ情報発信の店 のいずれかが対象。登
録制で1年ごとに更新している。(出典:足立区ホームページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kokoro/fukushi-kenko/kenko/shokuiku-oen.html ) 46 「健康づくり応援店」は、①葉酸たっぷりメニュー ②健康応援メニュー(カロリーひかえめ、塩分ひかえめ、脂肪ひか
えめ、野菜たっぷり、バランスのとれたメニュー) ③地元農産物活用メニュー などの「げんき満開メニュー」や食品を
提供する店が対象。栄養士が申請されたメニューの栄養計算や健康メニューの開発支援を行っている。(出典:坂戸市ホーム
ページ http://www.city.sakado.lg.jp/22,7675,202.html )

47
待できる。(図表35)
5.3 組織づくり
食育の運動や取り組みを支えるため、市内のさまざまな関係者・関連団体等(行政や地域、市民、
学校、企業、飲食店・小売業者等)が連携・共同していくためのしくみの確立が重要である。
行政の役割は、庁内・庁外の推進体制を整え、関係者が課題を共有できるよう連携のしくみを整
えることであると考える。
5.3.1 庁内推進体制
食育推進にあたり、庁内の連携を図るため、食育推進庁内担当者会議及び勤務栄養士ネットワー
クの2つを提案する。
参考としたのは、市川市の取り組み47。「勤務栄養士ネットワーク」は市が「健康都市推進プログ
ラム」を実施するにあたり、栄養士の横のつながりを強化するために開始したものであった。市に
おける課題を発見し、推進目標(朝食、生活習慣病予防、地元の食材の利用促進など)を立て、そ
れに基づく情報発信(出前講座や市の食育番組への出演等)を行ってきた。
まず、食育推進庁内担当者会議は、食育関係課の担当者間の連携を図るための会議であり、食育
推進関係課4課(保育課、健康課、農政課、学務課)と食育関連課の担当者で構成するもの。年3
回程度の会議により、食育事業における連携、ホームページへの掲載等具体的な話し合いを行う。
47 出典:内閣府(2013)『食育推進に関する市町村の実践事例調査報告書』(内閣府ホームページ
http://www8.cao.go.jp/syokuiku/more/research/jireichousa/ )及び市川市への電話での聞き取り(平成26年1月17日)
による。
図表35 かすかべ食育協力店の実施

48
勤務栄養士ネットワークは、保健・福祉・教育等の分野に勤務する栄養士の連携の強化を図り、
食育に関する情報交換・情報発信を行うもの。庁内の勤務栄養士(健康課、保育課、小学校、中学
校)で構成し、随時集まって情報交換等を行う。
これにより、①庁内の連携が図れる ②統一した動きで事業を展開できる ③事業実施における協
力体制ができる などの効果が期待できる。(図表36)
5.3.2 庁外推進体制
庁外の推進体制を図るため、「食育ネットワーク」を提案する。
食育推進に関わる各種関係機関や団体等が、事業や活動に関する情報交換等を通じて各自の食に
関する取り組みの充実や共同事業の展開等につなげるとともに、市と連携・協力した取り組みを推
進するもの。
参考としたのは、北九州市の取り組み。食育に取り組んでいる市内の団体・事業者・大学・個人
等が、相互に情報を共有し、連携・協力しながら食育を進めていくための食育推進ネットワーク 48を
構築している。登録団体等には情報交換会への参加や啓発イベント等への協力を呼び掛け、ともに
食育を盛り上げていただいている。登録団体の情報はネットワーク内及び庁内食育関連部局で共有
するとともに、団体名と活動内容はホームページにも掲載している。
このことにより、①産民公学の連携が図れる ②統一した動きで事業を展開できる ③事業実施に
おける協力体制ができる などの効果が期待できる。(図表36)
48 「北九州市食育推進ネットワーク」には、平成25年8月末現在52団体11個人が登録している。登録は無料、随時申し
込みを受け付けている。(出典:北九州市ホームページ http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0156.html )
図表36 食育の推進体制

49
5.3.3 連携による取り組み
一例として11月の地産地消月間 49に行う食育イベントを提案する。
地産地消月間に、農産物のPRと併せて、行政・地域の食育の取り組みを広く楽しく周知すると
ともに、地域での食の取り組みをつなげる機会とするものである。
参考としたのは、墨田区の食育イベント 50の取り組み。すみだ食育goodネットの会員である区民、
地域団体、NPO、事業者、企業、大学、区等の関係者による協働の取り組みとして食育月間に合わせ
て行われている。それぞれの催しを一つの団体が行うのではなく、地域で活動している人たちがつ
ながって実施されているのが特徴である。
本市においては、毎年11月23日に農業祭 51が行われている。農業に理解を深めるというまさに
食育にふさわしい催しである。農業祭に食育の要素を加え、食育のネットワークの会員の取り組み
を活用することにより、地産地消月間(食育)のイベントとして展開することが可能である。
これにより、①食育の取り組みを広く楽しく周知できる ②産民公学の連携が深まる ③新たな取
り組みにつながる などの効果が期待できる。(図表37)
49 埼玉県では、多くの農産物が出そろう11月を「埼玉県地産地消月間」と定め、「近いが うまい 埼玉産」をキャッチフレ
ーズに、地産地消の取組を進めている。(出典:埼玉県ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/page/2013gekkan.html ) 50 食育イベント「手間かけて すみだ食育 てんこもり2013」では複数の団体が協働して催しが行われた。例えば、パネ
ルディスカッション】では、高知や秋田の生産者と墨田の事業者が、【子ども向け体験教室~豆腐作りから学ぶ、食の大切さ】
では、豆腐工房と児童館が、【食器づくりのワークショップ】では助産院やクリエイター(美術研究所)などがイベントを担
当した。まさに、テーマ「人とまち 食への想いで つなげよう」に合致したイベントであった。(出典:すみだ食育通信
http://www.sumida25.net/syokuiku_news_backnumber.html ) 51 春日部市農業祭は、市民の皆さんに農業に対する認識を深めてもらい、農産物の消費拡大を図ることを目的に春日部市主
催、春日部市農業団体連合会主管により開催されている。主な催しは、農産物品評会(品評会出品物の展示、即売)、カモレ
ース、軽食の提供など。
図表37 連携による取り組み

50
提案書1-1 食育の5つの軸→ 食文化 家庭 こころ ひと まち
主な対象となるライフステージ→ 胎児期 乳幼児期 小学生期 中学生期 高校生期 青年期 壮年期 高齢期
企画名
目的
時期
場所
対象
内容
方法
実施機関
連携機関
予算
効果
展開例
・第1期生は20名程度を広報、ホームページ等で募集(募集に当たっては要項を作成)する。・受講者は、市内在住・在勤で全日程の授業に参加でき、受講後、食育推進リーダーとして地域の食育推進に貢献する意欲のある者とする。・第2期以降については、応募人数や食育大学の反響等に応じ、募集要件に課題(「私が考える春日部市にふさわしい食育」等のテーマで原稿用紙1枚程度)を課す。・講師についてはなるべく多分野の有識者を招聘する。・授業は市役所別館、公民館、保健センター等を使用して行う。・授業を一部公開する等、開かれた大学とし、外部に受講生の活動を広く知ってもらう。・授業の一貫として市内等を視察する場合のため、市民農園を行う農家等、協力を得られる先を確保しておく。・費用は原則無料とする。ただし、調理実習等の材料費、視察等の交通費等は実費徴収することを検討する。若しくは、当該実費負担分を見込んだ受講費を入学時に徴収する。・やむを得ない理由による欠席者へのフォローを検討(なるべく全受講生に『食育推進リーダー』となってもらうため)する。
健康課食育担当
『かすかべ食育大学』の開催
食に関する意識改革、食育に取り組む機会の提供及び食に関するさまざまな課題に対応でき、市の食育の推進役となれる人材の育成を図るため、講座、研修会等を開催する。
平成27年度~
市役所別館、公民館、保健センター等
子どもが独立した人(子どもを育て上げた人)、現役を退いたもののかつて食に携わってきた人、(資格がなくても)地域で食育に携わりたい人
◆全5~10回程度のカリキュラムを作成し、主に大学の講義形式で授業を実施する。◆授業の内容は春日部市食育推進計画に沿った内容とする。◆修了者には『食育推進リーダー』の認定証を交付し、人材登録を行ってもらう。◆食育推進リーダーには、家庭や地域における食育の推進、次期以降の食育大学での講師、市の食育イベントでのパネルディスカッション等、市の食育を推進するための活動をお願いする。◆カリキュラムは、参加者の負担にならない分量・時間・日程とし、かつ、参加者の意欲及び知識を高めるものとする。
講師謝礼(講師、協力団体への謝礼等)旅費(視察時の交通費)需用費(教材等の作成費用等)役務費等(市民総合災害補償に該当しない場合)
・受講生、修了生による食育イベント事業の企画、開催(既存の市イベントでのブース開設を含む。)・受講生、修了生によるカリキュラムの編纂、食育大学の運営(スタッフとして参画)・修了生を中心メンバーとした食育推進団体の設立・企業、大学との連携による特製弁当の開発・市役所、市立病院食堂での健康メニュー開発
① 市の食育の進行役となる人が育つ② 修了生の家庭、地域等において食育に取り組む場が広がる③ 食育推進リーダーが毎年度誕生することで息の長い安定的な食育活動を行うことが可能
市内生産者組合、JA、栄養士、保健師、食育に取り組む企業
関連度がより強い

51
提案書1-2 食育の5つの軸→ 食文化 家庭 こころ ひと まち
主な対象となるライフステージ→ 胎児期胎児期・乳幼児期
小学生期 中学生期 高校生期 青年期 壮年期 高齢期
企画名
目的
時期
場所
対象
内容
方法
実施機関
連携機関
予算
効果
展開例
主に小学校3,4年生(公民館事業として実施する場合はその保護者も対象とする)※嗜好が固まる前でかつおいしさを表現できる年齢
味覚教室のプログラム例(※):○導入(ルール説明)○4つの基本の味(甘い、酸っぱい、しょっぱい、苦いの試食)○複合の味の試食(甘いと酸っぱいの試食)○うま味の比較(昆布と鰹節、うま味調味料の試食)○塩の比較(自然塩、精製塩の試食)○野菜の味の違い(生野菜と温野菜の試食)○複雑な味の試食(ポン酢の試食)※6人×5グループの想定。試食とクイズ形式で楽しく進める
健康課(食育担当者)及び食育推進リーダー(食育大学生・修了生)
消耗品費(使い捨てカップ等)食糧費(調味料、野菜等)
・ホームページにプログラムマニュアルの掲載(自前で実施する場合を想定)・出前講座として実施(小学校等からの申請を受けて実施。スタッフは食育推進リーダー)
~アレンジ例~・料理教室前の15分間でできるミニ味覚教室(料理教室とセットでの実施)・妊婦・乳幼児の保護者向け(離乳食教室等での実施)・高齢者向け(糖尿病予防教室等での実施)
小学校、公民館など
1 味覚教室のプログラム作成 ・内容の決定 ・教室の進め方マニュアル作り ・掲示用教材の作成2 味覚教室の実施 ・小学校(放課後子ども教室などへの売り込み) ・親子味覚教室(夏休み中に公民館等で開催。小学校3~4年生対象)
①味わう楽しさを知ることができる②食への関心が高まる③和食や素材のおいしさを次世代に伝えることができる
味覚教室の開催
和食を中心とした食文化を次世代に伝えるために、地域が一丸となって、子どもたちの味覚を鍛え、食の基礎教育を行う。おいしいものが分かる子どもたちを育てる。
プログラム作成:平成27年度~教室の開催:平成28年度~
小学校、公民館

52
提案書1-3 食育の5つの軸→ 食文化 家庭 こころ ひと まち
主な対象となるライフステージ→ 胎児期 乳幼児期 小学生期 中学生期 高校生期 青年期 壮年期 高齢期
企画名
目的
時期
場所
対象
内容
方法
実施機関
連携機関
予算
効果
展開例
・学生ボランティアの育成・学生ボランティアによる出前講座の実施(食育かるた大会など)・地元産食材を使ったレシピの考案
①学生を巻き込みながら実施することで学生の健康づくりや食生活への関心が向上する。②自分で健康づくりや食生活を考え実践する若者が育つ。③学校と地域とが積極的に関わることでつながりが生まれる。
市内には、食物や栄養、調理について学ぶ学校が無いことから、市内の高校や市と包括的連携協定を結んでいる大学で活動するクラブやサークル(家庭部・漫画研究会など)に協力してもらい、食育教材の企画および作成を行う。□高校生・大学生向けの「食育手帳」の企画、作成 《内容》①朝ごはんの大切さや役割 ②自分の適正体重を知る(ダイエットは必要か?) ③健康な体をつくる正しい食事 ④運動部で活躍するための効果的な食事の取り方 ⑤将来、パパ・ママになるあなたに知ってほしいこと ※高校生や大学生が食生活や健康づくりに興味を持ち、知識と実践を手助けできる ような内容とする。□高校や大学において「食育手帳」を活用した授業の実施□「食育かるた」の企画、作成□「食育かるた」は公民館や児童館、保育所などに配布し広く市民の方に利用してもらう。
・予算の確保・高校や大学に協力依頼・食育教材の企画、作成・食育教材の配布
健康課(食育担当者)子育て支援課保育課
市内の高校市と包括的連携協定を結んでいる大学
謝礼消耗品費印刷製本費
高校生・大学生とつくる食育の教材
高校生や大学生など、若い人たちの 「食」に対する関心は薄い傾向にある。そこで、高校生や大学生が、食育に関する様々な取り組みに携わることで、食生活や健康づくりへの関心を高めてもらい、将来、子供を産み育てる「未来の親」を育てることを目的とする。
平成27年度
・市内にある高校・市と包括的連携協定を結んでいる大学
高校生、青年期(大学生)

53
提案書2-1 食育の5つの軸→ 食文化 家庭 こころ ひと まち
主な対象となるライフステージ→ 胎児期 乳幼児期 小学生期 中学生期 高校生期 青年期 壮年期 高齢期
企画名
目的
時期
場所
対象
内容
方法
実施機関
連携機関
予算
効果
展開例
【テキストの内容】米、赤米、黒豆、果樹(梨、いちご)、野菜(なす、トマト、きゅうり)、ホンモロコなど種類や季節ごとなどに分けて掲載※春日部版素材辞典として作成
【付録情報】・春日部市の農産物直売所・収穫体験ができる農家一覧・地元のおやつ・年中行事を祝うレシピ(花餅、甘酒、ぼたもち、柏餅、まんじゅう、団子、赤飯など)・地元素材を使ったレシピ(新たな名物料理などが開発されたらそれも掲載)
①情報収集・県農林振興センター、JA、農家等(春日部の地元郷土料理の作成方法や歴史を収集)・直売所・農業体験場所(庭先の直売所や農業の体験ができる場所について、市内農家あて、調査依頼を通知)・農産物紹介事業に参加した事業所(レシピや写真を収集し、栄養士の協力で栄養価などを再計算することも検討)②企画・編集・食育推進庁内担当者会議メンバーの中から関係課職員でプロジェクトチームを立ち上げ、企画・編集を行う。③ホームページへの掲載・食育のホームページに、情報等を掲載する。
※出版化に当たっては、協賛企業を募り、ゼロ予算で出版する。
食育推進庁内担当者会議メンバーのうち関係課職員(農政課、健康課、学務課など)によるプロジェクトチーム
県農林振興センター、JA、農家、直売所、農産物紹介事業の参加事業所、管理栄養士など
消耗品費(用紙、文房具等)
・収穫体験、調理実習などのときに配布・活用・食育授業の副教材としての活用(出版化も検討)・スーパー、農産物売り場において配布・食育の教材づくり(かるた、マンガ、カレンダー)の基礎資料
①地元農産物に対する知識の集約化ができる②地元農産物の魅力を多方面に発信できる③いろいろなモノ(物・者)とのつながりが生まれる
かすかべの食のテキスト(素材辞典)の作成
地場産物に関する情報を集約化させ、地域の食を活用した収穫体験や調理実習などの際に活用できるような食育のテキストを作成する。
平成26年度
提供・配布場所:ホームページでPDFを配布(希望多数の場合は出版化も検討)
一般(特に幼児~小学生の子どもをもつ親)

54
提案書2-2 食育の5つの軸→ 食文化 家庭 こころ ひと まち
主な対象となるライフステージ→ 胎児期 乳幼児期 小学生期 中学生期 高校生期 青年期 壮年期 高齢期
企画名
目的
時期
場所
対象
内容
方法
実施機関
連携機関
予算
効果
展開例
■食環境が豊かで魅力的なまち 春日部市 □ 新着情報□ 春日部市食育推進計画□ ふ ふるさとの食文化を伝える ・かすかべの食のテキスト ・食文化□ さ サンキューの気持ちで食べる ・味覚ワークショップ ・食事のマナー□ わ 和気あいあいと食事をつくっている ・早寝早起き朝ごはん ・共食 ・給食レシピ ・親子で作ろうレシピ ・朝食レシピ
□ し 生涯にわたって食でひとを育てる ・かすかべ食育大学 ・食生活の改善 ・食の安心安全 ・減塩レシピ□ い 一連の食の営みを整える ・春日部市食育協力店 ・旬の食材・産地の知識□ 子育て応援サイト(食事の教材) ・乳幼児期の食事 ・小学生期の食事 ・中学生期の食事 ・高校生期の食事□ キッズのページ ・たべものクイズ他□ リンク集 ・食育白書他
健康課(食育担当者)及び食育推進庁内担当者会議メンバー
なし
・栄養士による食育通信の発行(メルマガの発行)・掲載レシピをまとめた料理本の発行・食育クッキング動画の掲載
食育関連課と関係のある団体、食育ネットワークなど
①情報収集②担当者会議③企画会議
①食を通じて子育てへの支援ができる。②子どもの食生活・食習慣の改善ができる。③市民の間に食育の共通認識が図られ、次の取り組みにつながる。
食育ホームページの作成
本市における食の情報を集約化させ、食に関する情報を楽しく、分かりやすく、タイミング良く提供するためにホームページを作成する。
平成26年度~
市ホームページ内
一般(特に子どもをもつ親とその子ども)

55
提案書2-3 食育の5つの軸→ 食文化 家庭 こころ ひと まち
主な対象となるライフステージ→胎児期・
乳幼児期小学生期 中学生期 高校生期 青年期 壮年期 高齢期
企画名
目的
時期
場所
対象
内容
方法
実施機関
連携機関
予算
効果
展開例
「かすかべ食育協力店」の実施
外食や総菜等における栄養成分表示を進め、健康に配慮したり地元農産物を活用したりしたメニューの提供により、外食においても栄養バランスを保てるような取り組みを行い、健康増進を図る。
平成27年度
市内の飲食店、食料品店等
一般(主に外食や総菜をよく利用する20代から40代の世代)
●以下の1~5のうちのいずれかのメニューや食品を提供している店舗を認定。1.健康づくりに配慮したメニューを提供している。(例)・野菜たっぷりメニュー(1日分の野菜を使用、1/2日分の野菜を使用などの表示)・来店者の要望に合わせられる(いくつかの基準を設定<ご飯小盛り、塩分1/4など>)2.学校給食等、市のおすすめメニューを提供している。※市のおすすめメニュー・・・市民に広めたい学校給食等の健康づくりメニューを認定委員会で決定3.地元農産物を使ったメニューを提供している。4.栄養成分表示を提示している。5.体験・見学ができる場を提供している。●協力店へ市から情報を提供1.情報交換会を年に数回実施2.協力店へメール等で市や協力店間の情報を発信。必要に応じてアンケート等にも協力依頼する。
①栄養成分表示の活用により、外食、惣菜の選択能力を習得できる②地元農産物の活用意識が向上する③食育協力店間、食育協力店と市の連携強化が図れる
健康課(食育担当者)、学務課、農政課、保育課
消耗品費(用紙、文具等)委員謝礼印刷製本費(協力店認定ステッカー、提供メニュー表示のカード、マップ等)
・ホームページへの掲載やPRのちらし作成などにより、広く周知・市のイベント、各種講座等での連携
保健所(県職員)、食育ネットワーク、市内生産者組合、JA、行政関係機関等、商工会など
1.「かすかべ食育協力店認定委員会」を立ち上げる。 (保健所(県職員)、食育推進庁内担当者会議のメンバー、商工会、JA、市内生産者等)2.「かすかべ食育協力店認定委員会」の基準、要綱等を決める。3.周知4.申請手続き(申請書を作成して提出)5.審査(委員会メンバーが店舗へ出向き確認、栄養計算等の実施)6.認定(審査内容をもとに委員会で認定の有無を決定し、認定証を渡す)7.3~5年ごとに見直して再認定し、更新手続きを実施

56
提案書3-1 食育の5つの軸→ 食文化 家庭 こころ ひと まち
主な対象となるライフステージ→ 胎児期 乳幼児期 小学生期 中学生期 高校生期 青年期 壮年期 高齢期
企画名
目的
時期
場所
対象
内容
方法
実施機関
連携機関
予算
効果
展開例
・毎年テーマを決めて、統一した動きで事業を展開 (例)朝食、和食、野菜、共食、食の循環などから毎年テーマを設定・6月の食育月間(もしくは11月の地産地消月間)にあわせて関連イベントを開催
①食育推進庁内担当者会議 メンバー:各課の担当者 食育推進関係課(4課):保育課、健康課、農政課、学務課 関連課(15課):政策課、暮らしの安全課、市民参加推進課、高齢者支援課、 子育て支援課、介護保険課、国民健康保険課、商工観光課、指導課、中央公民館 (以上は、計画策定ワーキングメンバー所属課。以下は、新たに追加) 防災対策課、シティセールス広報課、環境政策推進課、資源循環推進課、社会教育課
②勤務栄養士ネットワーク メンバー:栄養士・管理栄養士(健康課、保育課、小学校、中学校)
①食育推進庁内担当者会議 年3回開催(1回は食育に関する研修、もう2回は食育に関する情報交換) ・今年度の事業予定について ・ホームページの更新について ・イベント等について(連携できるものは連携して実施)
②勤務栄養士ネットワーク 年数回開催 ・情報交換 ・取り組みの方向性についての話し合い
事務局:健康課
食育ネットワーク
なし
①庁内の連携が図れる②統一した動きで事業を展開できる③事業実施における協力体制ができる
庁内推進体制 ①食育推進庁内担当者会議 ②勤務栄養士ネットワーク
①食育推進庁内担当者会議 食育関係課の担当者間の連携を図る。②勤務栄養士ネットワーク 保健・福祉・教育等の分野に勤務する栄養士の連携の強化を図り、食育に関する情報交換・情報発信を行う。
平成26年度~
保健センターほか
市民一般

57
提案書3-2 食育の5つの軸→ 食文化 家庭 こころ ひと まち
主な対象となるライフステージ→ 胎児期 乳幼児期 小学生期 中学生期 高校生期 青年期 壮年期 高齢期
企画名
目的
時期
場所
対象
内容
方法
実施機関
連携機関
予算
効果
展開例
市民一般
会員:食育関係機関、食育に取り組む市内の団体・事業所、食育に取り組む 市内在住・在学・在勤の個人 活動内容: (1)会員相互の食育に関する情報交換・交流に関すること (2)会員の自主的な食育活動の推進に関すること (3)会員相互の連携・協力による食育活動の推進に関すること
※情報交換会を年2回開催 (1回は食育に関する研修と意見交換、もう1回は食育月間イベントに向けての話合いなど)
①情報交換により食に関する取り組みの充実を図れる②会員相互の連携が図れる③事業実施における協力体制ができる
募集方法:会員からの申込書の提出による 経費:入会金、会費等の費用はなし。交通費等は参加者の負担とする 会員の特典: ・情報交換会等への参加 ・食育関係の資料の提供 ・ホームページ・情報誌等で会員の取り組み紹介
事務局:健康課、農政課、学務課
(食育関係課と関係のある団体) 医師会、歯科医師会、薬剤師会、埼玉県立大学、保健所、埼玉県助産師会粕壁地区、 母子保健推進員、埼玉県栄養士会、春日部保健所地域活動栄養士会、 食生活改善推進員協議会、子育て支援センター、児童館、公立保育所、くらしの会、 農業団体連合会、商工会議所、私立幼稚園協会、PTA連絡協議会(学校) 包括的連携大学(その他団体・個人) 生産者(個人経営農業者など)、食品関係事業者(ガス会社、スーパー、飲食業など)、 NPO・ボランティア団体、個人(食育推進リーダー、料理研究家)など
講師謝礼(講演会講師謝礼)
・ホームページにおいて会員の取り組み紹介・6月の食育月間(もしくは11月の地産地消月間)に合わせて関連イベントを開催・会員の取り組み等を紹介する情報誌・食育実践事例集の作成・食育実践事業コンテストの実施・食育出前講座一覧の作成
庁外推進体制 食育ネットワーク
食に関係する各種関係機関及び団体等が、相互の情報交換等を通じて自主的な取組みの充実や協働事業の展開等につなげるとともに、市と連携・協力して食育を推進する。
平成27年度~
保健センターほか

58
提案書3-3 食育の5つの軸→ 食文化 家庭 こころ ひと まち
主な対象となるライフステージ→ 胎児期 乳幼児期 小学生期 中学生期 高校生期 青年期 壮年期 高齢期
企画名
目的
時期
場所
対象
内容
方法
実施機関
連携機関
予算
効果
展開例
保健センターほか
市民一般
①食育にあまり関心のない人にも食育を広く楽しく周知できる②産民公学の連携が深まる③新たな取り組みにつながる
テーマに沿った催しとする。(朝食、和食、野菜、共食、食の循環などから毎年テーマを設定)○講演会&食育実践報告会(保健センター講習室1) 基調講演と会員の食育実践報告会○食育イベント(一例として) ・給食レストラン 給食×飲食店 ・地産地消食堂 飲食店×生産者 ・収穫から調理まるごと体験 生産者×食生活改善推進員協議会 ・クッキングで異文化交流 料理教室×国際交流協会○展示 ・(保健センター講習室)学校給食と地元農産物 ・(市民活動センター)食育関係の市民団体による展示 ・(市役所市民ホール)食育のポスター展など ・(図書館3館)食育コーナー、絵本の読み聞かせ○ワークショップ(市民活動センター) ・食育ネットワーク会員によるワークショップ○その他協賛イベント(市内各所)
スケジュール 4月 ネットワーク会議(イベント開催について話し合い) 7月 協賛イベント募集(~8月)10月 イベント告知(ポスター、リーフレット、HP)11月 イベント告知(広報)11月 イベント開催(農業祭と併せて実施)12月 ネットワーク会議(イベント振り返り、次回のイベントに向けて話し合い)
健康課、農政課、学務課
食育推進庁内担当者会議、勤務栄養士ネットワーク、食育ネットワーク、かすかべ食育協力店など
講師謝礼消耗品費(模造紙等)印刷製本費(ポスター・リーフレット)
・かすかべの給食メニュー本の出版・給食レストランの常設・複数の企業・団体のコラボ企画 (地産地消グルメマップ、地産地消メニューの弁当の販売、定期観光ツアーの開発など)
ネットワークの連携による取り組み(一例として地産地消月間イベント)
行政・地域の食育についての取り組みを広く楽しく周知するとともに、地域での食の取り組みをつなげる機会とする。
平成27年度~

59
6.まとめ
国の第2次食育推進基本計画でも示されているとおり、食育に関する施策の実効性を高めていく
ためには、食育に係る多様な関係者が、その特性や能力をいかしつつ、互いが密接に連携・協力し
て、地域レベルでのネットワークを築いていくことが極めて重要である。
本市にもようやく食育推進計画ができた。その施策を継続的かつ効果的に推進するため、従来
の施策を補完する視点で、春日部にふさわしい食育、みんなで楽しく取り組むかすかべの食育につ
いて考えてきた。
春日部にふさわしい食育は、食で「食文化」「こころ」「家庭」「ひと」「まち」を育むことであり、
めざす10年後の姿は「食環境が豊かで魅力的なまち」であると考えた。
そして、食育の軸は次の5つに整理した。
ふ ふるさとの食文化を伝える →【食文化】を育む
さ サンキューの気持ちで食べる →【こころ】を育む
わ 和気あいあいと食卓を囲む →【家 庭】を育む
し 生涯にわたって食で人を育てる →【ひ と】を育む
い 一連の食の営みを整える →【ま ち】を育む
この5つの軸で取り組みを行い、さらにそれぞれの取り組みを互いに連携させつなげることで、
「食育の環」ができ、春日部市に「ふ・さ・わ・し・い」食育が実を結ぶことになる。そのための
方策として、人づくり、場づくり、組織づくりの3つの視点から事業提案をした。
人づくりとして、
「かすかべ食育大学」の開催では、春日部市の食育の推進役を育成する。
「味覚教室の開催」では、子どもたちの味覚を鍛え、食の基礎教育を行う。
「高校生・大学生とつくる食育の教材」では、「未来の親」たちの食への関心を高めるため、若い
世代と協働で食育の教材を作成する。
これらにより食育の推進役(将来の食育の推進役)を育成していく。
場づくりとして、
「かすかべの食のテキスト(素材辞典)の作成」では、地元農産物に関する情報を集約化させ、
食育に活用できるようなテキストを作成する。
「食育ホームページの作成」では、本市における食の情報を集約化させ、食に関する情報を楽し
く、分かりやすく、タイミング良く提供するホームページを作成する。
「かすかべ食育協力店」の実施では、食育や健康づくりを応援してくれる店舗と連携をとりなが
ら食育を推進するしくみをつくる。
これらにより、食育推進の基盤を整備していく。

60
組織づくりとして、
「食育推進庁内担当者会議」では、食育関係課の担当者間の連携を図る。
「勤務栄養士ネットワーク」では、保健・福祉・教育等の分野に勤務する栄養士の連携の強化を
図る。
「食育ネットワーク」では、食育推進に関わる各種関係機関や団体間の連携及び市との連携を図
る。
これらにより、食育推進の体制を整えていく。
これらの取り組みがつながって連携していくにより、ライフステージをつなぐ切れ目のない食育
や生産から食卓までの一連の食の営みを整えるといった「食育の環」の循環が生まれることになる。
そしてその取り組みは、「食」で「食文化」「こころ」「家庭」「ひと」「まち」を「育」むことへ向か
ってゆく。
このことは、同時に市の食育推進計画で目指す将来像“こころも からだも 栄養ゆたかな春日
部市”に向けて推進するものであり、同計画の5つの基本目標(①食に関する正しい知識の普及 ②
「共食」の推進 ③食に関する感謝の気持ちの育成 ④食の安全・安心と情報発信 ⑤地産地消の
推進と食文化の継承)とも合致する。
市内で次々に新たな取り組みの花が生まれ、「食」で「育」む取り組みが至る所で行われるように
なったとき、「食環境が豊かで魅力的なまち」に近づくことができる。総合振興計画に掲げる将来像
“人・自然・産業が調和した 快適創造都市―春日部―”を市民が実感できることであろう。
7.おわりに
2013年の食に関するニュースでもっとも大きかったのは、和食が世界文化遺産に登録されたこと
であった。これは単に料理だけでなく各地の伝統や食事の楽しみ方、その歴史的背景などが評価さ
れたものである。これがきっかけとなり、和食を作る頻度が増えたという人が多くなり、和食を見
直す傾向が高まっている 52。
その一方で、ホテル・飲食店等のメニューに相次いで食品虚偽表示が発覚したことや飲食店やコ
ンビニ等で働く者の行きすぎた悪ふざけで企業に損害を与えたニュースも後を絶たなかった。
いつでも手軽に食材や食物を入手でき便利で快適な世の中になったのと引き換えに、家庭の食卓
の崩壊やそれに伴うモラルの低下、食の安全性などの新たな問題が出て来ているのは明らかである。
このままで10年後の食の未来は明るいとは決して言えない。現状のまま何も策を講じなければ、
52 日清オイリオグループの生活科学研究室が20~60代の女性を対象に調べた「わが家の夕食メニューの変化」によると、
10年前に比べて和食を作る頻度が増えたという人が多く、年齢とともに健康への意識が高まり、和食を見直す傾向にあるこ
とが分かった。(農林水産省メールマガジン2014年(平成26年)1月17日第571号
http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/bk.html )

61
健康を害するだけではなく、数十年後、子どもたちが親世代になったときに、これまで家庭の食卓
を通じて養われてきた道徳心や常識、そして和食をはじめとした地域の食のすばらしさが次世代に
伝わらなくなってしまうのではないだろうか。改めて危機感を感じた。
一方、本市における食において喜ばしいニュースもあった。内牧小学校が文部科学大臣から2度
目の学校給食優良校を受賞したことである。 近の受賞歴をみても、平成20年から25年の間に5
つの小学校が同賞を受賞しており、春日部の給食の取り組みが高く評価されていることが分かる。
そのほかにも、「かすかべフードセレクション事業」や「農産物紹介事業」により、生産者・販売者
と消費者をつなぐ動きが進行中である。
そして、本市初の食育推進計画が策定された。これらを追い風にして、春日部市にふさわしい食
育の取り組みを行っていくことにより、少しずつであるかもしれないが、私たちの描いた10年後の
未来「食環境が豊かで魅力的なまち」へ向けての基盤を整えることができると考える。
後に、今回の研究において多くのアドバイスをいただいたかすかべ未来研究所政策形成アドバ
イザーの牧瀬先生、視察等に快く応じていただいた足立区、墨田区の皆様、電話で情報をいただい
た自治体の皆様に感謝を申し上げる。
かすかべ未来研究所 研究員
健康課 石原 真澄
農政課 厚川 高一
学務課 亀田 美智子
総務課 杉山 紫穂
政策課 森田 貴実香
政策課 舟田 由彦

62
資料編
1(国)第2次食育推進基本計画(平成23年~27年)の要点

63
2 春日部市食育推進計画の要点
○春日部市食育推進計画のポイント
○春日部市食育推進計画の概要
国・県の動向を踏まえた上で、第2次の「健康づくり計画」及び本市として初めての計画となる「食育推進計画」を
一体的に策定。本計画の計画期間は、平成26(2014)年度から平成35(2023)年度までの10 か年。
■(キャッフレーズ)こころも からだも 栄養ゆたかな 春日部市
■ 特徴
①ライフステージをつなぐ切れ目のない食育
②市民(個人・家庭)、地域、行政が役割分担を担いつつ、連携・協働して取り組む食育
【ライフステージごとのポイントと取り組み】
1 胎児期・乳幼児期
(1)胎児期 胎児の健やかな成長のために十分な栄養をとり、正しい食生活や食習慣に関する知識や重要性を再認識する
(2)乳幼児期(0~6歳) おいしく楽しく食べる意欲を育て、基本的な食行動を身につける
2 学童期・思春期
(1)小学生期(7~12歳) 食の基本的な知識を養い、食の体験を広げ、食を大切にする心を育てる
中学生期(13~15歳) 食に関する基本的な習慣を固め、食に関する判断力を身につける
(2)高校生期(16~18歳) 食を選択し、自己管理能力を身につける
3 青年期(19~39歳) 食生活を確立し、自分に合った食生活や健康の管理を実践する
4 壮年期(40~64歳) 身体の変化に対処し、望ましい食習慣を再度確立し、次世代に食の大切さを伝える
5 高齢期(65歳以上) 元気に長生きするために食事バランスに配慮し、次世代に食に関する知識や経験を伝える
【食育推進のための市の取り組み】 下線部は数値目標
1 食に関する正しい知識の普及
食育に関心を持っている市民の割合の増加《現状値》66%⇒《目標値》90%
朝食を欠食する市民の割合の減少《現状値》中学生2%、20~30歳代男性15%
⇒《目標値》中学生0%、20~30歳代男性10%
(1)知識の普及の強化
(2)相談の実施と充実
(3)健康教育の充実
(4)人材の育成
2 「共食」の推進
朝食や夕食等、できるだけ家族みんなで食事をしている市民の割合の増加《現状値》66%⇒《目標値》80%
(1)保育所・学校における「共食」の推進
(2)「共食」についての啓発等の推進
3 食に関する感謝の気持ちの育成
(1)「親としての自覚」づくりへの支援
(2)保育所・学校での指導の充実
(3)体験の機会の提供
(4)食品ロスの削減
4 食の安全・安心と情報提供
(食中毒や食品表示など)食品の安全に関する基礎的な知識を持っている市民の割合の増加《現状値》37%⇒《目標値》72%
(1)食の安全に関する理解の促進
(2)環境保全型農業の推進
(3)農業体験等の推進
(4)出前講座の実施
(5)災害に対する備えの普及
5 地産地消の推進と食文化の継承
学校給食に地場産物を使用する割合の増加 《現状値》市内産26%、県内産16%⇒《目標値》市内産31%、県内産26%
地元産の食材を購入するよう心がけている市民の割合の増加《現状値》47%⇒《目標値》60%
(1)地産地消運動の推進
(2)地場農産物の活用
(3)食文化の掘り起こしと継承