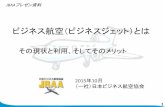航空分野における事故等調査の状況と ヒューマン …航空分野の事故・重大インシデントの調査制度の経緯 昭和49年1月11日 航空事故調査委員会
参考資料1 JAXA 航空の研究開発のあり方と方向性について 本文 · 武田...
Transcript of 参考資料1 JAXA 航空の研究開発のあり方と方向性について 本文 · 武田...

1
JAXA 航空の研究開発のあり方と方向性について
《「次期基本計画に向けた JAXA 航空の研究開発に関する外部有識者委員会」中間報告》
はじめに
現在計画期間中の第 3 期科学技術基本計画は、平成 23 年 3 月 31 日をもって期間終了(第 3 期期
間:平成 18 年 4 月~平成 23 年 3 月)となる。第 4 期科学技術基本計画は、国の科学技術行政の総
合調整・企画立案を行う総合科学技術会議(CSTP)により検討がなされ、平成 22 年度末に閣議決定
される予定である。第 4 期科学技術基本計画に向けて文部科学省航空科学技術委員会では、航空
科学技術分野の今後の方向性等をとりまとめ(第 10回基本計画特別委員会(H21.12.15)参考
資料)ており、今後、平成22年度より具体策についての議論が開始されるところであるが
航空科学技術委員会での議論の前提として、JAXA より次期に実施すべき研究開発課題案を示し、
それに基づき航空科学技術委員会でご議論いただく。JAXA より航空科学技術委員会に提出する素
案には、 JAXA 航空の研究開発のあり方や方向性について産学官の技術的見地からの意見を反映
することが求められている。
次期基本計画に向けた JAXA 航空の研究開発に関する外部有識者委員会(以下本委員会)では、
平成 21 年 12 月より検討を開始し、平成 22 年 3 月までに 3 回の委員会を行ってきた。本報告書は本
委員会の中間報告の位置付けで、第1 回から第3 回に集中的に検討してきた、主に次期中期計画期
間に実施すべき研究開発課題案について本委員会の要望をまとめたものである。
1.本委員会について
1.1 本委員会の目的と検討項目
次期(第4期)科学技術基本計画期間(平成 23~平成 27 年度)における JAXA 航空の研究開発の
あり方や方向性について、航空科学技術委員会に提出する案に、産学官の技術的見地からの意見
を反映することを目的とする。
本委員会の検討項目は、下記 3 点である。
(1)次期基本計画期間における JAXA 航空の研究開発課題と計画線表の案
(2)研究開発課題に関連する研究開発目標(指標)の案
(3)人材育成、産学官連携、国際協力、広報の進め方の案
1.2 委員構成
以下に、本委員会の委員およびオブザーバーの構成を示す。
委員長
小林 修 東海大学 工学部航空宇宙学科航空宇宙学専攻 特任教授
[JAXA 航空プログラム推進委員会委員長]
委員
○産業界
柳田 晃 (社)日本航空宇宙工業会 技術部部長
矢古宇 慎一 (株)JALエンジニアリング 技術部 副部長

2
黒木 英昭 全日本空輸(株) 整備本部ラインメンテナンスセンター Team MOC 室 室長
長尾 牧 朝日航洋(株) 航空事業本部運航統括部 担当部長
海田 武司 三菱重工業(株) 名古屋航空宇宙システム製作所研究部 次長
村重 敦 川崎重工業(株) 航空宇宙カンパニー技術本部 研究部 空力技術課長
若井 洋 富士重工業(株) 航空宇宙カンパニー 研究部主管
山本 政彦 (株)IHI 航空宇宙事業本部 技術開発センター エンジン技術部
プロジェクトグループ 主幹
○学界
武田 展雄 (社)日本航空宇宙学会 ICAF(国際航空疲労委員会)国内委員会委員長
[東京大学大学院新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻 教授]
渡辺 紀徳 (社)日本航空宇宙学会 原動機・推進部門委員会委員長
[東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻 教授]
宮沢 与和 (社)日本航空宇宙学会 人材育成委員会委員長
[九州大学大学院 工学研究院 航空宇宙工学部門 教授]
○研究機関
藤井 直樹 (独)電子航法研究所 通信・航法・監視領域 領域長
○他分野
萩原 太郎 HOYA(株)執行役 技術担当
[文部科学省 航空科学技術委員会 委員]
秦 康範 山梨大学工学部土木環境工学科 防災研究室 准教授
後藤 新一 (独)産業技術総合研究所 新燃料自動車技術研究センター長
原田 広史 (独)物質・材料研究機構 超耐熱材料センター センター長
兼ロールス・ロイス航空宇宙材料センター長
オブザーバ(関係省庁)
鈴木 三千紀 総務省消防庁国民保護・防災部応急対策室 航空専門官
中村 文俊 文部科学省研究開発局参事官(宇宙航空政策担当)付 参事官補佐
畑田 浩之 経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課 課長補佐
清水 哲 国土交通省監理部総務課 地球環境保全調整官
千葉 英樹 国土交通省技術部航空機安全課 課長補佐
江口 真 国土交通省管制保安部保安企画課 航空管制技術調査官
山下 範夫 防衛省技術研究本部航空装備研究所 研究調整官
1.3 スケジュール
以下に、本委員会の今後の予定を含めたスケジュールを示す。
外部有識者委員会 スケジュール(案)
平成 21 年 12 月 22 日
(開催済) 第 1 回
●次期基本計画における JAXA 航空の研究開発課題(案)について
(たたき台としての JAXA 案の提示)
●事務局提案についての意見・提案の依頼
平成 22 年 1 月 25 日
(開催済) 第2回 ●意見・提案を踏まえた検討結果について

3
平成 22 年 2 月 17 日
(開催済) 第3回
●研究開発課題と計画線表の案とりまとめ
(研究開発課題案のとりまとめ後航空科学技術委員会に提出)
平成 22 年 4 月 第4回 ●航空科学技術委員会からの意見の反映について
●研究開発目標(指標)案の検討
平成 22 年 5 月 第5回 ●技術基盤(施設設備整備)について
●人材育成、産学官連携、国際協力、広報の進め方について
平成 22 年 6 月 第6回 ●研究開発目標(案)について
(研究開発目標(指標)案のとりまとめ後航空科学技術委員会に提出)
2.議論の前提
2.1 JAXA 航空におけるこれまでの取組みと現行計画
総合科学技術会議による「第 3 期科学技術基本計画」、文部科学省科学技術・学術審議会の研究
計画・評価分科会が定めた「航空科学技術に関する研究開発の推進方策について」に基づき、現在
JAXA 航空プログラムグループは事業を実施している。中でも戦略重点科学技術とされた事業(国産
旅客機高性能化技術の研究開発、クリーンエンジン技術の研究開発、運航安全・環境保全技術の研
究開発、静粛超音速機技術の研究開発)については、資源を重点的に配分しつつ実施を行っている
ところである。文部科学省、科学技術・学術審議会の研究計画・評価分科会による必要性、有効性、
妥当性についての中間評価等をうけつつ、適切に研究開発を行っている。
以下に、研究開発事業の主な成果を示す。
○ 国内外協力
国産旅客機の先端技術開発に共同研究で取り組んだ。同機 ATO(正式客先提案)における性能検
査・保証をし、企業はその後事業化決定、開発に至った。今後も技術協力を継続する。
圧縮機試験設備の改修整備を行い、エコエンジン圧縮機の設備供用による試験を開始。
消防庁と包括協定、電子航法研究所と共同研究契約を結び、災害時の運航管理技術や GBAS を用
いた運航方式の共同開発を実施、一部技術について導入・評価を開始。
ソニックブーム評価技術などで NASA 等海外研究機関との共同研究を進めるとともに、国際民間航
空機関におけるソニックブームの環境基準検討に参画、協力した。
○ 技術実証
航空用エンジン低 NOx燃焼器につき、実機形態の環状燃焼器での実証試験を行い世界最高水準の
NOx低減性能を達成。
超音速機のソニックブーム低減に関わる設計コンセプトを創案して国際特許を取得、風洞試験や数
値シミュレーションによりその技術的目処付けを行った。
○ 技術創出・移転
NOx低減のための計測技術開発にあたって、ステレオ干渉画像法計測装置(3 次元計測)を世界で
初めて開発し、燃焼場での計測に適用。

4
CRM 計測スキル手法を海上保安庁へ導入、飛行データ解析ツールを我が国の 75%の運航会社に導
入するなど、ヒューマンエラー防止ツールを技術移転。
5NM 級高高度ライダーを開発し、航空機メーカと実用化に向けた検討を開始。
超小型航法装置が世界最高水準の性能を実証し、アビオメーカに技術移転。
なお、添付資料 1 にこれまでの取り組み(JAXA 航空技術の成果と社会への貢献)を示す。
2.2 航空を取り巻く国内外の動向
航空を取り巻く世界情勢は、次のようにまとめることができる。
○ 地球温暖化による環境変動
世界的な環境への取組みが進んでいる。
・ 1997 年 京都議定書
・ 2009 年 12 月 COP15@ コペンハーゲン
○ 航空機産業による環境への影響と航空交通量
の増加
・ 世界の CO2 排出量の約 2%が航空産業によるもの
・ 航空機の大型化、マイクロジェットや無人機の増加により、世界の航空交通量は今後 20 年
間で倍増と予測 (FAA)
・ 2050 年の航空産業による排ガス割合は 3%に ( IPCC: 気候変動に関する政府間パネル)
○ 国際基準の強化
ICAO において:
・ 航空環境保全委員会(CAEP)において、騒音・排出ガス基準が「強化」。今後も基準対象の
拡大・厳格化が続く見込み。
・ 2009 年 10 月 9 日の「国際航空産業と気候変動に関するハイレベル会合」にて、気候温暖化
に対する特定業界による世界初となる世界規模の合意「COP15 に向けた宣言文」を採択。2050
年まで毎年 2%の燃費向上等を宣言。
○ 世界の航空技術開発の動向
・ 激化する航空機開発競争
- 航空産業の大幅な成長が見込まれるなか、米国や欧州などに加え、中国、インド、
韓国、ブラジル、メキシコなども、国の威信をかけて航空機産業の育成・国際的競
争力の強化を企図。
- 特に中国は莫大な国家資金を投入し、ARJ21 や C919 の開発計画や、航空科技国
家実験室や国産航空機エンジンの開発基地などの大型試験設備の建設などを筆
頭にダイナミックな政策を展開。
・ 地球規模課題の解決(環境に優しい航空技術の開発)
- 環境にやさしい機体・エンジンの開発(低 CO2、低騒音、燃費向上、脱化石化)
- 航空管制高度化による CO2 排出量の削減
・ 航空機の交通量増加に対応する「安心・安全」の確保
- 航空管制高度化による先進航空交通システムの確立 (米国 NextGen、欧州
SESAR)
2000年平均温度を基準(=0)とする。
Globalwarmingart.com
図1 COP15

5
○ 国内の航空技術開発の動向
・ 国内航空産業が盛り上がりを見せつつあり、次の 5 年間は非常に重要
- MRJ の事業化決定と海外受注獲得
- C-X、P-X 機の初飛行
- ホンダジェットの開発
以上を踏まえ、航空を取り巻く社会情勢を 3 つのキーワードでまとめると、次のようになる。
○航空輸送需要の増加とアジア市場の成長 →「国際的優位性」
世界の航空輸送需要は今後 20 年間で倍増
アジア市場の需要は約 3 倍(世界最大規模)へと成長の見込み
・我が国航空機産業の飛躍的成長ポテンシャル
・航空交通量の大幅な増加への対応
・ニーズの多様化
取り組み:
・国際基準策定への技術協力に、より積極的な貢献
・遠くを速く、近くを手ごろに、より快適に(高速性、利便性、快適性)
○環境保全と経済発展の両立への要求の高まり →「エコ」
地球温暖化への危機感の浸透
排出ガス、騒音規制の強化
石油価格の変動等に伴う脱化石エネルギーへの取り組み強化
取り組み:
・低炭素社会の実現
・低公害、低騒音
○安全への要求の高まり →「安全安心」
安全・安心な社会への要求の更なる高まり
高密度安全運航に向けたニーズの高まり
地震に代表される大規模災害への対応強化
取り組み:
・航空事故率の低減
・災害対応分野における航空技術の利用
なお、添付資料 2 に第 3 期科学技術基本計画中の主な情勢の変化を示す。
2.3 航空科学技術委員会における検討状況
平成 21 年 6 月以降、航空科学技術委員会において、第 4 期(平成 23~平成 27 年度)科学技術基
本計画策定に向けた基本認識、方向性等について議論され、これまでの検討結果について中間的
な報告書としてとりまとめられている。以下に、この報告書の内容をまとめる。
○航空科学技術が果たすべき役割として下記が設定。
①先進的な航空機の研究開発の推進

6
②次代を担う人材の創出
③開発機に対する国の安全証明(型式証明等)の的確な実施
④継続的な安全性・環境性の向上
○これを受け、第 4 期の研究開発の方向性は下記のとおり
① 「出口志向の研究開発プロジェクト」
② 「戦略的な基礎・基盤研究」
③ 「人材育成の中核機能」
○重点的に推進すべき領域としては下記の 2 点
① 航空機のライフサイクルを通じて「低環境負荷(超低 CO2、低燃費、低騒音等)」、「低コスト」な
先端的・基盤的技術
② 航空機の特性である「高速性」を活かしつつ、かつ高い「安全性」、「利便性」、「快適性」を兼ね
備えた先端的・基盤的技術
3.検討内容
3.1 検討の手順
本委員会におけるこれまでの検討手順を、以下に示す。
① 議論の前提を踏まえ、JAXA が 3 つのキーワード「1.エコ 2.安全・安心 3.国際的優位性」を設
定。さらに、重点領域「1.低環境負荷、低コストの追求 2.安全・安心の追求 3.航空輸送の利便性
の追求」を定め、それに資する研究開発課題案を 25 項目提示。
② 本委員会(第 1 回)にて議論実施
③ 委員会後、それぞれの委員に対して、議論の前提、JAXA が設定した重点領域の妥当性、各研
究開発課題案の妥当性および想定される成果の引き取り手、期待する成果の成熟度レベル、必要と
なる時期、優先度についてアンケートを実施。
④ アンケート結果を集計し、本委員会(第 2 回)にてアンケートのまとめ方について、および集計結
果について議論
⑤ アンケート結果および本委員会での議論を踏まえ、研究開発課題案を JAXA にて作成
⑥ 研究開発課題案について本委員会(第 3 回)にて議論
⑦ これまでの本委員会での議論・検討結果に基づき、中間報告として次期中期計画期間に実施す
べき研究開発課題案をとりまとめ
なお、各委員へのアンケート結果に基づき行った、JAXA 提示の研究開発課題素案から本委員会
からの研究開発課題案への選定・整理の考え方について、以下に示す。
○ 研究開発課題優先度:原則、受取手が要望する優先度が「高」を重要として選択

7
ただし、JAXA 先端的・基盤的研究および研究開発からの技術ストックを考慮
○ 研究開発課題の必要となる時期
• アンケート結果の 5 年:「2017 年までに・・・」
• アンケート結果の 10 年:「2022 年までに・・・」
• アンケート結果の継続:「継続して・・・」
○ 技術成熟レベル(図2参照)
• C~D:成果の受取手とJAXAの協力のもと実施する研究開発
• B~C:JAXAが主体的に実施する研究開発
○ 上記選定プロセスの後課題の整理を行い、出口志向の個別研究開発課題案(7 項目)の提案
参考 各技術課題の技術成熟レベルと必要時期サマリ
図2 技術成熟レベルにみる研究開発の役割イメージ
大学 JAXA 産業界
役割の重み
産業界との協力
大学との協力2
34
5
67
89
1
技術成熟レベルA(TRL 1‐2相当)アイデア提案、基本原理の発見、
応用対象の明確化
技術成熟レベルB(TRL 3‐5相当)
重要部分の成立性評価、
実験室レベル以上での試作試験、環境試験
技術成熟レベルC(TRL 6‐8相当)
実環境下においてサブシステム以上で実証
技術成熟レベルD(TRL 9相当)ミッション等で実際に使用・運用
今回のアンケートに用いた技術成熟レベル

8
3.2 検討の結果
3.1にて示した手順により、次の7つの個別研究開発課題案を選定した。
①航空機の CO2 排出の抜本的な削減(地球規模環境課題、省エネルギー化への対応)
(超低 CO2 エンジン技術、機体の抵抗低減技術、高信頼性軽量構造技術)
②航空機のライフサイクルコストの削減
(低コスト加工・組立技術、低コスト整備・検査技術)
③航空機起源の環境負荷低減(空港エリアにおける環境課題への対応)
(全機騒音の低減化技術、NOx 低減技術)
④航空機安全性の向上
(機体安全性を向上させる構造技術、飛行時の安全性を向上させる運航技術、無人機の利用拡
大のための安全性向上技術、社会・行政ニーズへの技術協力)
⑤災害救援能力の向上
(災害時の航空機運用の効率向上技術、災害時の航空機による消火能力の向上技術)
⑥将来航空交通システム構築のための運航技術の開発
(将来航空交通システム構築のための運航技術)
⑦国際優位技術の先行的獲得
(次世代超音速旅客機技術、回転翼航空機の高性能化技術)
以上の他に、これまでの JAXA における先端的・基盤的研究および研究開発からの技術ストックが不
足するために、以下の技術課題を個別研究開発課題案へは入れないものの戦略的・先行的研究開
発として取り組むべき研究開発課題とした。
・ 極超音速エンジン/機体技術
・ 革新機体コンセプト
・ 高信頼性軽量材料・構造技術
・ バイオ燃料のライフサイクル解析技術
・ 水素燃料供給・利用技術
・ ハイブリッドエンジンシステム技術
・ 電動化航空機システム技術
・ ヘリコプタの高速化技術
・ 粒子状物質(PM)の低減技術
表 1 に個別研究開発課題案を、表 2 に戦略的・先行的研究開発の課題を示す。また、個別研究開
発課題案と戦略的・先行的研究開発を含めた研究課題詳細について、添付資料 3 に示す。
3.3 委員からの意見について
各委員に対して行ったアンケートには、直接的に個別研究開発課題案選定の折に反映されなかった
ものの、今後の航空科学技術の研究開発の実施に対して重要な意味を持つと思われるコメント・ご意
見があった。以下に主なものをまとめて列挙しておく。
○ JAXA の立ち位置、役割についてのご意見
<航空に関する国家戦略と JAXA について>
・航空に関する国家戦略(府省横断による総合政策)、日本としての航空行政のあり方を明記し、そ
の中での JAXA としての立ち位置を明確にすべきと考える。

9
・国家戦略についての考えが見えない。例えば次世代超音速機の恩恵を一番受けられるのは日本
だが、それを国家戦略とするかという議論があれば、それに向かう全ての技術は必要であるというこ
とになる。そういった大きな筋が欲しい。
<日本の航空科学技術と JAXA の位置づけについて>
・日本の科学技術基本計画における、航空科学技術の位置付けを明確に行い、日本として必要な
JAXA の役割の位置付けを行うのが適当ではないか。
・関連各省庁、産業界、大学等も含めた航空科学オールジャパン体制の構築を進め、JAXA 航空科
学が日本の航空科学の中心研究開発機関として活動できる体制を議論すべきである。
<技術戦略議論する場について>
・日本の航空関係の技術戦略について,このようなメンバーで議論して行く機会が持てれば,より良
いのではないか。そのような場の設定も JAXA に期待される一つの活動と思われる。
○ 航空科学技術の研究開発と基盤的・先端的技術の研究について
・研究のための研究にならないようにする必要がある。
・研究の目的・目標・課題とその解決策の重要度・優先度を見極め、研究の道筋を明確にすべきと考
える。

10
おわりに
次期基本計画に向けた JAXA 航空の研究開発に関する外部有識者委員会では、平成 21 年 12 月
より検討を開始し、平成 22 年 3 月までに 3 回の委員会を行ってきた。第 1 回から第 3 回の委員会で
は、主に次期中期計画期間に実施すべき研究開発課題案について集中的に検討してきた。本報告
書では、委員会の概要、議論の前提、および検討経緯を説明した上で、次期中期計画期間に実施す
べき研究開発課題案の委員会の要望について取りまとめ、提示した。今後、本報告内容が JAXA よ
り航空科学技術委員会へ提出される研究開発課題案に盛り込まれ、第3期科学技術基本計画に続く
我が国の科学技術基本計画に反映されることを強く希望する。
なお、本報告は次期中期計画期間に実施すべき研究開発課題案についてのみ取りまとめた中間報
告である。今後本委員会で更に検討を進め、研究開発課題案に研究開発目標案、人材育成や産学
官連携の具体案等を含めた上で最終報告を行う予定である。
平成 22 年 3 月 3 日
次期基本計画に向けた JAXA 航空の研究開発に関する外部有識者委員会
委員長 小林 修
添付資料1:これまでの取り組み(JAXA 航空技術の成果と社会への貢献)
添付資料2:第 3 期科学技術基本計画中の主な情勢の変化
添付資料3-1:個別研究開発課題案と戦略的・先行的研究開発のサマリー
添付資料3-2:具体的研究課題案の概要

11
表1 個別研究開発課題案
個別研究開発課題 具体的研究開発課題(案) 成果の出口 成果の時期と内容(成果受け手の観点からの技術成熟度)
1-1. 超低CO2エンジン技術 製造者・2017年までに、CO2の抜本的削減につながる超高バイパス比エンジン技術や石油燃料に依存しない燃料多様化エンジン技術について、実環境条件における技術成立性を実証(成熟度C)・2022年までに、製造者と協力して、超低CO2エンジン実機実証(成熟度D)
1-2. 機体の抵抗低減技術 製造者・2017年までに、機体-エンジンインテグレーションも含めた抵抗・騒音低減技術について、技術成立性を実証(成熟度B)・2022年までに、製造者と協力して、実環境条件において技術実証(成熟度C)
1-3. 高信頼性軽量構造技術製造者 ・2017年までに、複合材の実機への適用拡大技術、構造健全性維持技術を確立(成熟度C-D)
・2022年までに、製造者と協力して、複合材の実機への適用拡大(成熟度D)
2-1. 低コスト加工・組立技術製造者 ・2017年までに低コスト複合材製造、接合技術(金属含む)について、要素技術を確立(成熟度B)
・2022年までに、製造者等への技術移転(成熟度D)
2-2. 低コスト整備・検査技術製造者
、運航者
・2017年までに、実機適用レベルの低コスト複合材構造検査・修理技術、および、金属構造に対する腐食対策技術を確立(成熟度C-D)・2022年までに、運航者等への技術移転(成熟度C-D)
3-1. 全機騒音の低減化技術製造者 ・2017年までに、フライト条件での騒音計測・予測法の確立、騒音低減技術の実環境試験実証(成熟度B
-C)・2022年までに、製造者と協力して、騒音低減技術の飛行実証(成熟度D)
3-2. NOx低減技術製造者 ・2017年までに、低NOx燃焼性能を実環境条件での要素技術成立性実証(成熟度B)
・2022年までに、製造者と協力して、実機実証(成熟度D)
4-1. 機体安全性を向上させる構造技術製造者 ・2017年までに、製造者と協力して、鳥衝突、異物衝突、非常着陸状態における機体および客室安全性
の試験解析技術を確立(成熟度D)
4-2. 飛行時の安全性を向上させる運航技術製造者運航者
・2017年までに、乱気流事故防止技術を、ユーザーと共同で実機実証(成熟度C-D)・2017年までに、ヒューマンエラー防止技術をユーザーと共同で実運用(成熟度C-D)
4-3. 無人機の利用拡大のための安全性向上技術 行政機関・2017年までに、産学官連携体制を整え、その体制の中で、小型無人機安全性向上技術の確立(成熟度B)・2022年までに小型無人機安全基準策定への技術的貢献(成熟度C)
4-4. 社会・行政ニーズへの技術協力 製造者、運航者、行政機関
継続的に実施
5-1. 災害時の航空機運用の効率向上技術 行政機関・2017年までに、ユーザーによる情報共有ネットワークの利用実証(成熟度D)・2017年までに、製造者と共同で、災害時の消防防災ヘリコプタの安全確実な運航につながる技術を実証(成熟度D)
5-2. 災害時の航空機による消火能力の向上技術 行政機関、製造者 ・2017年までに、飛行機(例えば、消防飛行艇)の技術課題解決と機能高度化を実現(成熟度C)
6. 将来航空交通システム構築のための運航技術の開発
6. 将来航空交通システム構築のための運航技術運航者、行政機関
・2017年までに、ICAOグローバルATM運用概念で必要とされるキー技術を国際基準として提供(成熟度D)
7-1. 次世代超音速旅客機技術製造者、行政機関
・2017年までに、小型超音速旅客機の実現を可能とするキー技術(例えば、ソニックブーム低減技術)の実証(成熟度C)・2022年までに、大型超音速旅客機の実現を可能とするキー技術(例えば、離着陸性能)の実証(成熟度B)
7-2. 回転翼航空機の高性能化技術 製造者、運航者 ・2017年までに、実機を用いた騒音低減化技術の飛行実証(成熟度C-D)
1. 航空機のCO2排出の抜本的な削減(地球規模環境課題、省エネルギー化への対応)
2. 航空機のライフサイクルコストの削減
3. 航空機起源の環境負荷低減(空港エリアにおける環境課題への対応)
7. 国際優位技術の先行的獲得
5. 災害救援能力の向上
4. 航空機安全性の向上
表2 戦略的・先行的研究開発の課題
具体的研究開発課題(案) 成果の出口 内容
極超音速エンジン/機体技術 極超音速機 超音速機の次のターゲットとして、キー技術の研究開発を実施し、次々期にプロジェクト化を狙う。
革新機体コンセプト 将来機体・エンジン 革新機体概念の技術的成立性を実証
高信頼性軽量材料・構造技術 将来機体・エンジン 次世代加工技術、エンジンへの複合材適用、多機能材、スマート構造モニタリングの実環境実証
バイオ燃料のライフサイクル解析技術 将来エンジンバイオ燃料のライフサイクル解析や燃料生成の持続性検証。他分野(学界、燃料業界、エアライン)と連携協力した研究開発。(一部は、超低CO2エンジン技術に融合)
水素燃料供給・利用技術 将来エンジン水素供給インフラや液体水素燃料の利用技術等、他分野の水素利用技術と相補的な研究開発。水素航空機システムとしての技術課題も踏まえた検討を実施。(一部は、超低CO2エンジン技術に融合)
ハイブリッドエンジンシステム技術 将来エンジンモータ技術、ハイブリッドシステム技術等の個別技術は、幅広い選択肢を意識しながら、着実に研究。10年以降先での実用化をにらんだ戦略的な研究開発。(一部は、超低CO2エンジン技術に融合)
電動化航空機システム技術 将来機体・エンジン将来の航空機の国際競争力向上に貢献する新コンセプト技術を先行して獲得する。他分野との連携を密にして電動推進系技術や電動化システム技術を高度化。
ヘリコプタの高速化技術製造者、行政機関、
運航者ヘリコプタの高速化技術実証を通して飛行領域を拡大し、新たなヘリコプタ利用を開拓することを狙いとした研究開発
粒子状物質(PM)の低減技術 将来エンジンPMの計測技術について、自動車など他分野の技術動向をふまえた研究開発。PM低減技術については、ガスタービンエンジン燃焼器の固有性を考慮した研究開発。
戦略的・先行的研究開発