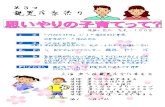堺市民芸術文化ホールの音響設計初期エネルギー比(C80)は約-1.2~-0.9dBであった。1...
Transcript of 堺市民芸術文化ホールの音響設計初期エネルギー比(C80)は約-1.2~-0.9dBであった。1...

技術報告技術報告
*1 TAKAHASHI Aiko :(株)NHKテクノロジーズ ファシリティ技術本部 建築センター*2 ITAGAKI Naomi :(株)NHKテクノロジーズ ファシリティ技術本部 建築センター*3 KITAMURA Koichi :(株)NHKテクノロジーズ ファシリティ技術本部 建築センター 設計部長
1.はじめに 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺)は老朽化した堺市民会館の建替事業により整備した複合施設(表-1、図-1)で、2019年10月に開館した。「フェニーチェ堺」という愛称は、堺市が大坂夏の陣や第二次世界大戦などにより何度も焦土と化したところから、都度不死鳥のように力強く立ち上がってきたことに由来する。以下に音響設計の概要についてホールの室内音響を中心に報告する。
高橋 藍子 *1、板垣 直実 *2、北村 浩一 *3
Acoustical Design and Characteristics of Sakai Performing Arts Center
堺市民芸術文化ホールの音響設計
表-1 建物の概要
図-1 フロアマップ(1~2階)
14

GBRC Vol.45 No.2 2020.4
2.大ホール 客席の三方を囲む3層のバルコニーを備えたシューボックス型ホール(図-2、3および写真-1)で、客席の幅×長さ×高さは最大約27
×32×20m、音響反射板設置時の舞台は約18×10×12mである。客席の半球型天井(写真-2、3)と側壁拡散体(写真-4)が特徴的で、吊りボルトを使用しない準構造化天井は、中低音域を整反射、高音域のみ乱反射させることを意図した形状とした。天井仕上げは1.2mm厚のスチールプレートを挟み込んだ石膏ボードであり、約37kgの面重量を確保している。この仕上げ材をアングルを用いて鋸歯状に留め付けている(図-4)。客席側壁は大きさと角度の異なる3種類の木製ユニット(図-5、Ⅰ~Ⅲ)とコンクリート面で構成されている。側壁仕上げ下地については軽鉄を使用せず、木製軸組みまたは躯体に直貼りとし、板振動による低域の吸音や経年変化によるビリツキ音発生といった懸念の少ない工法を採用した。 音響測定は空席時と満席時(1,713人/2,000席)について実施した。舞台に反射板を設置した演奏会形式(写真-5)の残響時間の実測結果(図-6)は約2.0~1.7秒(500Hz/空席時~満席時実測値、以下同様)、平均吸音率は約20.7~23.5%であり、初期減衰時間(EDT)は約1.9~1.6秒、初期エネルギー比(C80)は約-1.2~ -0.9dBであった。1
階客席中央におけるエコータイムパターンからは空席時・満席時とも豊かな初期反射音が得られていることが示されている(図-7)。
表-2 大ホールの主な仕上げ(寸法:mm)
写真-1 大ホール 客席
図-3 大ホール 断面図
15

GBRC Vol.45 No.2 2020.4
空席時の音圧レベル分布(図-8)は7.5dBの偏差であり、2000席規模のホールとしては舞台の音が客席全体にまんべんなく伝わっている。また、1階客席中央・第1、第3バルコニーの3箇所について残響曲線(図-9)を比較し、自然な減衰を示していることを確認した。 舞台の反射板を収納し、幕設備を設置した講演会形式(写真-6)の残響時間は約1.5~1.3秒(500Hz/空席時実測値~満席時予測値)であり、反射板の有無により、0.5
秒程度の残響可変幅を確保することができた(図-6)。 また、日本建築総合試験所で行った客席椅子の吸音力測定結果から一人あたりの吸音力(実験値)を推定した。この結果を満席時の残響時間実測結果から推定した吸音力(実測値)と比較した(図-10)。500Hzより低音域では実測値が実験値を0.05m2・sabin程度上回っていたが、高音域では0.05m2・sabin程度下回っていた。
写真-2 大ホール 客席天井
写真-5 大ホール 演奏会形式
写真-6 大ホール 講演会形式
図-4 大ホール 天井仕上げ詳細図(寸法:mm)
写真-3 大ホール 客席天井下地
図-5 大ホール 壁仕上げ詳細図
写真-4 大ホール 客席側壁(拡散体)
16

GBRC Vol.45 No.2 2020.4
3.小ホール 音楽、文楽、演劇など様々な用途に対応可能な多機能ホールで、客席の幅×長さ×高さは最大約12×16×9m、舞台は12×10×8mである(図-11、12)。客席上部照明ブリッジ両サイドは開口率50%の木リブ仕上げとなっていて、技術ギャラリー内に反射または吸音パネル等を仮設することで、音響調整が可能な構造となっている。また、技術ギャラリー内の天井は周波数特性を調整するためにグラスウール・ガラスクロス額貼り仕上げに特注厚(10mm厚品)を採用した(写真-8)。また、客席壁仕上げは大小様々な寸法の木ルーバーによる不規則な凹凸形状として、拡散性を考慮した。 大ホールと同様に空席時と満席時(245人/312席)の音響測定を実施した。舞台反射板を設置した演奏会形式(写真-9)の残響時間の実測結果(図-13)は約1.2~1.1
秒(500Hz/空席時~満席時実測値、以下同様)、平均吸音率は約22.2~24.6%、初期減衰時間(EDT)は約1.3
図-8 大ホール 音圧レベル分布(空席時)
図-9 大ホール 減衰曲線(空席時)
図-10 大ホール 客席椅子の吸音力
図-6 大ホール 残響時間周波数特性
図-7 エコータイムパターン(1階客席中央)
図-11 小ホール 平面図
図-12 小ホール 断面図
表-3 小ホールの主な仕上げ(寸法:mm)
17

GBRC Vol.45 No.2 2020.4
~1.2秒、初期エネルギー比(C80)は約1.1~1.3dBであった。1階客席中央におけるエコータイムパターンからは豊かな初期反射音が得られていることが示されている(図-14)。空席時の音圧レベル分布(図-15)は5.0dBの偏差であった。また、1階客席前方・中央・後方の3箇所について残響曲線(図-16)を比較し、自然な減衰を示していることを確認した。 なお、反射板とは舞台側壁(長さ約9.3m×高さ6.5m×両サイド)の移動間仕切壁のことであるが、舞台袖の開口を開閉するだけでなく、黒塗装された裏面を客席側に半回転させて袖幕パネル(ウィング)として使用でき、また設置角度を変えて反射音の方向を調整できる。反射板を半回転させた講演会形式(写真-10)の残響時間は約0.9~0.8秒(500Hz/空席時実測値~満席時予測値)であり、舞台正面の昇降式大黒幕と反射板の開閉のみで、0.4
秒程度の残響可変幅を確保することができた(図-13)。 小ホールについても日本建築総合試験所で行った客席椅子の吸音力測定結果から一人あたりの吸音力(実験値)を推定した。この結果を満席時の残響時間実測結果から推定した吸音力(実測値)と比較した(図-17)。500Hz
より高音域で実測値が実験値を0.03m2・sabin程度下回っていた。大ホールと比べるとその差は小さい。
写真-7 小ホール 照明ブリッジ 写真-9 小ホール 演奏会形式
写真-8 小ホール 技術ギャラリー 写真-10 小ホール 講演会形式
図-13 小ホール 残響時間周波数特性
図-14 小ホール エコータイムパターン(1階客席中央)
図-15 小ホール 音圧レベル分布(空席時)
18

GBRC Vol.45 No.2 2020.4
練習に適した比較的響きの短い空間とした。壁の仕上げは2種類の有孔板(8φ15mm間隔および6φ150mm間隔)として、平坦な周波数特性が得られるよう配慮した。天井中央部は石膏ボード(厚み12.5mm+15mm)による反射面、天井四周の平場は岩綿吸音板(厚み9mm)による吸音面とした。天井や壁全体を傾け、さらに凹凸形状とすることでフラッタエコー(多重反射、いわゆる鳴き龍)やブーミング(低音でのこもり、いわゆる部屋鳴り)を低減するよう配慮した。床仕上げは、小スタジオ1、2がナラフローリング、小スタジオ3はリノリウムを採用した。4. 3 多目的室 多目的室(写真-19)は約160m2のアクティングエリアと約5.5mの天井高さを持ち、第4のホールとしての活用を期待している。床仕上げにはバーチ縁甲板15 mm厚、下地には緩衝材付きの鋼製床組とすることでダンスなどに適した空間とした。壁の仕上げは不燃木練付化粧有孔板(8φ15mm間隔および6φ150mm間隔の2種類)、天井は15 mm厚のリブ付き岩綿吸音板とした(写真-20)。
4.スタジオ 大小5室あるスタジオおよび多目的室(表-4)はすべて浮き構造を採用した。多目的利用に配慮しながらも、各室の残響時間(図-18)が示すように、ゆるやかな特徴を持たせる計画とした。4. 1 大スタジオ 天井全面に配置されたグリッドバトンを用いて照明やスピーカなどを自由に取り付けることが可能な設えとし、大・小ホールに続く第3のホールとして演劇や演奏会の本公演などにも利用されることを目指した。 最大の特徴は磁器質タイルを用いた壁仕上げである。高さ×幅×厚さが180mm×40mm×15~25mmの磁器質タイルの目地部で吸音させる特殊な構造(写真-11、12)であり、日本建築総合試験所で吸音率の測定を行い(図-19)、レゾネータ型の吸音体として機能していることを確認した。天井に用いる岩綿吸音板は特注厚(15mm
厚、黒塗装品)を採用し、できるだけ響きの長さが平坦になるように調整した。壁のうち一面はダンスなどの練習に使用できるよう鏡貼りとしたが(写真-13)、鏡を使わない場合には有孔板による吸音仕上げの移動間仕切りで目隠しできるよう配慮した(写真-14)。外壁側の大窓にはロールカーテンを設置し、全体で0.1秒程度の残響可変幅を確保することができた。外壁窓は3重窓とし、外部との遮音性能にも配慮した(写真-15)。4. 2 小スタジオ 小スタジオ1~3(写真-16~18)は打楽器やバンドの
図-16 小ホール 減衰曲線(空席時)
図-17 小ホール 客席椅子の吸音力
表-4 スタジオ諸元
図-18 スタジオ残響時間周波数特性
図-19 大スタジオ タイル壁吸音率
19

GBRC Vol.45 No.2 2020.4
写真-11 大スタジオ タイル壁
写真-12 大スタジオ タイル壁下地
写真-13 大スタジオ SLW・ロールカーテン開
写真-14 大スタジオ SLW・ロールカーテン閉
写真-15 大スタジオ 外壁窓
写真-16 小スタジオ1
写真-17 小スタジオ2
写真-18 小スタジオ3
20

GBRC Vol.45 No.2 2020.4
5.おわりに 拡声を使わない生音主体のコンサートホールの規模としては1,500席あたりが理想的と言われており、その規模を超えたあたりから格段に音響設計が難しくなる。本施設の大ホールは2,000席であるが、3層のバルコニー席を採用して、平面方向ではなく高さ方向に客席数を確保した。全ての客席をできる限り舞台に寄せることで強いエネルギーの直接音が得られ、約25mという中規模ホール並の客席幅に収めることで聴衆の両耳に直接入射する側方反射音が確保しやすくなるよう配慮することで、立ち上がりが良く臨場感がある音場を実現できた。また、舞台天井反射板から意匠的かつ音響的に連続して客席に張り出したキャノピー型プロセニアムアーチと半球型の客席大天井は、客席の前方から後方までバランス良く初期反射音を到達させることを意図したものである。フライタワーを持つホールの多くでは、プロセニアムを境にして高さが大きく変化しているために、客席の中央において初期反射音が確保できずに、「音が抜ける」または「音が上がる」、あるいは「舞台に音がこもる」など評価される懸念があるが、本施設の大ホールは客席と舞台との響きの差が少なく演奏者と聴衆との一体感が得られやすい空間を実現できたと考えている。
また、大・小ホール壁面仕上げは木材による様々な寸法を持った凹凸によるテクスチャーで構成されている。情報伝達に必要な中~低音を確実に反射させつつ、いわゆる超高音域の音だけを拡散させる役割を持つ。これは壁に近い客席における反射音を和らげるだけではなく、楽器どうしの音がよくブレンドされたアンサンブル、つまりハーモニーを生み出す効果があると言われている。視覚から入る情報が聴感上の印象に与える影響は大きいため、デザインに細かく変化をつけることにより単調な大面積の平面に比べて圧迫感を緩和し、木質系の温もりが伝わるような建材を採用することは音響上も好ましいものであると考えている。 堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺)は故柳澤孝彦氏が代表を務めた柳澤孝彦+TAK建築研究所によって設計された施設である。柳澤氏は残念ながら本施設の開館を待たずして工事期間中の2017年8月にご逝去された。無事開館を迎える事ができたのは柳澤氏の遺志を継いだ所員や施工各社と堺市役所の尽力の結果である。同氏は新国立劇場をはじめ多くの文化施設を手掛けられているが、本施設を象徴的する大ホールの木製パネルや大スタジオのタイル壁をはじめとする特徴的な仕上げどれひとつとっても、その遺志を存分に感じることができる施設となっている。 開館以降は堺市や堺市文化振興財団を中心として、運営にも非常に力を入れており、国内外の有名オーケストラ・指揮者・ソリストはもちろん、文楽や年越しカウントダウンコンサートを行うなど多くの興味深い公演が行われている。また、日本国内ではほとんど納入実績のないイタリアFAZIOLI社F308という長さ3mを超える大型コンサートグランドピアノを導入するなど他施設との差別化に対する取り組みも話題になっている。 堺といえばこれまでも貿易拠点として「東洋のベニス」と呼ばれた戦国時代からの商人文化や、昨年世界遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」などが世界的な注目を浴びてきたが、本施設も堺市から世界に向けた芸術文化の発信拠点として活用されることを信じている。
【執筆者】
*2 板垣 直実(ITAGAKI Naomi)
*1 高橋 藍子(TAKAHASHI Aiko)
*3 北村 浩一(KITAMURA Koichi)
写真-19 多目的室
写真-20 多目的室 天井仕上げ
21