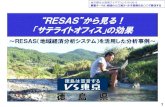東アジアの少子高齢化と持続的経済発展の課題 - JAAS · 2010-07-13 · 東アジアの少子高齢化と持続的経済発展の課題 69 当する人口ピラミッドは図3
少子高齢化の進展で変わる個人金融資産の将来像 - NOMURA...2010.10 4...
Transcript of 少子高齢化の進展で変わる個人金融資産の将来像 - NOMURA...2010.10 4...

2010.10
4
少子高齢化の進展で変わる個人金融資産の将来像
目 次
Ⅰ. はじめにⅡ. 少子高齢化社会における個人金融資産の展望1. 少子高齢化が個人資産総額へ及ぼす影響2. 少子高齢化が個人資産構成へ及ぼす影響Ⅲ. 少子高齢化社会で高まる相続の重要性1. 増加する相続資産2. 相続の重要性が高まる理由3. 見えざる資産移動Ⅳ. 個人金融資産はどこへ集まるのか1. 個人間の資産分布はどう変わるのか2. 世代間の資産分布はどう変わるのか
3. 地域間の資産分布はどう変わるのかⅤ. わが国への示唆1. 個人金融資産の重要性2. 個人金融資産を維持・拡大するためにⅥ. 金融機関への示唆1. 変わるリテールビジネスチャンス2. 取引履歴を予め作るために3. 魅力的な商品・サービスを提供するために4. サービスの利便性を高めるためにⅦ. おわりに
野村資本市場研究所 宮本 佐知子
1. わが国の個人金融資産は, 今大きな転換期を迎えている。 今後は人口動態という
長期的で確実な要素によって, 個人金融資産の構造が変わる要素が増えてくるから
である。
2. 少子高齢化社会では, 「貯蓄する人」 が減り 「貯蓄を取崩す人」 が増えてゆく。
現状の世代別・就労別の貯蓄率が変わらないと想定し, 今後の人口構成の変化が及
ぼす影響を試算すると, 急速な高齢化と退職世帯の貯蓄取崩しが及ぼす影響は大き
く, 個人金融資産総額は2020年までに約35兆円減少するとの結果が得られた。
3. 人口動態の変化で今後, 増加するのが相続資産である。 相続を通じた個人間・世
代間・地域間での資産移動は, 個人資産分布に大きな影響を与えると見られる。
4. わが国にとって, 個人金融資産を減らさないことは重要な意味を持つ。 そのため
には, 現在ある人的資本や金融資産をそれぞれ有効活用する方策が考えられ, 国や
地方自治体による政策的なサポートが望まれよう。
5. 金融機関にとっては, 個人金融資産を巡る競争は, いわば 「限られたパイの奪い
あい」 を意味しよう。 金融機関は, ①年間50兆円以上の個人資産が毎年相続で動く
ことと, ②相続資産が地域を越えて移るために個人資産は大都市圏へ一層偏ってゆ
くこと, という大きな潮流変化に対して, 早くから戦略を立てるべきであろう。
要 約 と 結 論

Ⅰ. はじめに
わが国の個人金融資産は, 今大きな転換期
を迎えている。 これまで個人金融資産は増え
続けてきたが, 今後は少子高齢化の進展によ
り構造が変わる要素が増えてくるからである
(図1)。 実はわが国の個人金融資産のトレン
ドには, 既に2000年頃から変化が見られてい
た。 総額を変化させる主な要因は, 以前は新
規流入資金だったのだが, 2000年以降は評価
損益の変動に変わっており, 実質的に個人金
融資産総額は頭打ち状態になっていたのであ
る (図2)。
少子高齢化社会では, 「貯蓄する人」 が減
り 「貯蓄を取崩す人」 が増えてゆく。 また高
齢化の進展と共に, 個人資産が次世代へと受
け継がれてゆく。 今後は, 人口動態という長
期的で確実な要素によって, 個人金融資産に
も大きな変化が見られてゆこう。
本稿の構成は次の通りである。 まず, 今後
の人口変化によって, 今後の個人金融資産総
額がどう変わるのか, その影響を示す (第Ⅱ
章)。 次いで, 人口変化によって, 今後の個
人金融資産の分布がどう変わるのか, その影
響を示す (第Ⅲ章・第Ⅳ章)。 最後に, この
ような人口変化に伴う大きな構造変化に対し,
国全体ではどのような対応が望まれるのか
(第Ⅴ章), 金融機関ではどのような戦略対応
が考えられるのかを検討したい (第Ⅵ章)。
2010.10
5
図1 今後の人口見通し
(出所) 国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口 (平成18年推計)」 から野村資本市場研究所作成
14
12
10
8
6
4
2
0
40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
千万人)
05 10 15 20 25 3014歳以下60-69歳
15-24歳70歳以上
25-59歳60歳以上/全人口 右軸)
%
図2 個人金融資産残高変化の要因分解
(出所) 日本銀行統計から野村資本市場研究所作成
兆円)100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-1001990
評価損益貯蓄増減金融資産残高の変化
92 94 96 98 00 02 0604 08(年度

Ⅱ. 少子高齢化社会における個人金融資産
の展望
1. 少子高齢化が個人金融資産総額へ及ぼ
す影響
わが国では2014年に3人に1人が60歳以上
の社会になるが, その後も60歳以上の割合は
上昇してゆくと予想されている。 わが国の労
働慣行では定年制度を設ける企業が多く, 60
歳を境に退職する人が増えてゆくことから,
60歳を境に貯蓄する側から貯蓄を取崩す側へ
と移る人が増えてゆく (図3)。 そこで以下
では, 今後迎える本格的な少子高齢化社会の
下で, 人口構成が変わるにつれて, 個人金融
資産の総額や構成がどう変わるのかを展望す
る。
まず, 働いている現役世帯と, 退職して年
金生活に入っている世帯とでは, 毎月の収支
がどう異なるのかを確認する (図4)。 足下
では, 現役世帯では可処分所得のうち27%を
貯蓄しているのに対し, 退職世帯は消費支出
が可処分所得を上回り, 可処分所得の32%に
相当する赤字となっている。
また, それぞれの世帯の貯蓄率は, 1990年
代以降の動きも異なっている。 50歳代までの
現役世帯の貯蓄率は, 不況下でもほぼ横ばい
で推移しており, 収入減に合わせて支出も切
り詰め, 貯蓄割合を維持してきた。 ところが
退職世帯の貯蓄率を見ると, 赤字の拡大が続
2010.10
6
図4 現役世帯と退職世帯の貯蓄率
(注) 1.ここでは黒字率のことを貯蓄率と表している。黒字率=(可処分所得-消費支出)/可処分所得。2.現役世帯は二人以上の勤労者世帯, 退職世帯は二人以上の60歳以上無職世帯対象。
(出所) 総務省 「家計調査報告」 から野村資本市場研究所作成
現役世帯
95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08
40
35
30
25
20
15
10
5
095 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08
退職世帯
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
~29歳40~49歳60~69歳
30~39歳50~59歳70歳~
図3 年齢別の労働力率 (男性)
(出所) 総務省 「国勢調査報告 (2005年)」 から野村資本市場研究所作成
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 015 19歳
20 24歳
25 29歳
30 34歳
35 39歳
40 44歳
45 49歳
50 54歳
55 59歳
60 64歳
65 69歳
70 74歳
75 79歳
80 84歳
85歳以上
~~~~~~~~~~~~~~

いている。 公的年金の支給開始年齢の引上げ
等により収入が減少する一方で, 支出はほと
んど変わっておらず, 貯蓄の取崩しが一層進
んでいるからである1)。 わが国では財政赤字
が拡大する中, 将来の消費税率引上げや社会
保障費の伸び抑制が議論されていることや,
老齢厚生年金の支給開始年齢も引上げられて
ゆくこと等から, 今後, 退職世帯の状況が改
善するとは見込みづらいと思われる。
このまま世代別・就労別の貯蓄率が変わら
ないと想定すると, 今後60歳以上の人口が増
えるにつれて, わが国全体の家計部門の貯蓄
率は低下すると考えられる。 試算によると,
2013年には貯蓄率がゼロを下回り, その後も
低下を続けると見込まれる。 この貯蓄率の見
通しを基に, 今後の個人金融資産総額を試算
すると, 人口構成の急速な高齢化と退職世帯
の貯蓄取崩しが及ぼす影響は大きく, 個人金
融資産総額は2020年までに約35兆円減少する
との結果となった (シナリオ1, 図5)。
また仮に, 現役世帯の貯蓄率は変わらない
一方で, 退職世帯の貯蓄率が今後も低下し続
けると想定すると, 個人金融資産総額への影
響は更に大きく, 2020年までに約120兆円減
少するとの結果となった (シナリオ2, 図5)。
2. 少子高齢化が個人金融資産構成へ及ぼ
す影響
ただし, 個人金融資産総額が減少する見通
しであるとはいえ, 全ての金融資産が一律に
減少するわけではないと考えられる。 という
のも, 世代ごとに金融資産の構成が異なるた
め, 高齢化が進展し世代別人口構成が変わる
と, 家計全体の金融資産の構成も変わる可能
性が高いからである。
わが国では一般に, 年齢が高くなるほど資
産額も多くなることに加えて, 金融資産に占
める有価証券の割合が高くなる傾向が見られ
る (図6)。 そのため, 高齢化が進展し世代
別人口構成が変わると, 家計全体の金融資産
に占める有価証券の割合も高くなってゆくと
予想される。
2020年までに家計全体の金融資産構成がど
う変わるかを試算すると, 預貯金が20兆円減
少するのに対し, 有価証券は僅かながら増加
すると見込まれる (シナリオ1)。 またシナ
リオ2では, 全ての金融資産が減少するもの
の, 減少幅が最も大きい資産は預貯金である
ことはシナリオ1と共通する。
2010.10
7
図5 個人金融資産の見通し
(注) 1.シナリオ1は世代別・就労別の貯蓄率が変わらないと想定した場合の推計結果。2.シナリオ2は世代別・勤労世帯の貯蓄率は変わらないものの, 60歳以上無職世帯の貯蓄率は低下し続けると想定した場合の推計結果。3.年齢別労働力率が変わらないことを前提とした。
(出所) SNA 統計, 日本銀行統計, 国立社会保障・人口問題研究所統計等を基に野村資本市場研究所推計
1,600
1,500
1,400
1,300
1,2002000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
シナリオ1シナリオ2
(予想)

Ⅲ. 少子高齢化社会で高まる相続の重要性
1. 増加する相続資産
このように, 今後の人口変化が個人金融資
産へ及ぼす影響を検討すると, 現状のままで
は個人金融資産総額は減少してゆく可能性が
高いと考えられる。 その一方, 今後の人口変
化に伴い相続資産は増加が続くと見込まれる。
相続資産の規模は, 控えめに見積もっても
年間50兆円と推定される (図7)。 この推定
額には, 相続税統計で把握できる資産に加え
て, 相続税の対象とならず統計で捕捉できな
い相続資産も含めている。 今後, 高齢化が進
展する中で相続資産規模は更に拡大してゆく
と予想され, 今後10年を考えると累計500兆
円以上の資産が次世代へと移ると見込まれる
が, これはわが国の個人金融資産総額の1/3
に相当する規模である。 現在の家計部門全体
の資産は高齢世帯に偏っており, 60歳以上の
世帯が金融資産の6割, 有価証券の7割を有
している。 高齢化の進展でこの割合も更に高
まってゆくと考えられ, 今後のわが国の個人
金融資産を見通す上では, 相続の重要性はま
すます高まってゆくと考えられる。
2. 相続の重要性が高まる理由
今後の個人金融資産を見通す上で, 相続が
重要である理由はその規模だけではない。 個々
人の資産形成においても, 相続資産の相対的
な重要度が一層高まることも挙げられる。 わ
が国の場合, 資産蓄積は若年層や中年層より
も高齢層の方が進んでいるため, 相続で次世
代へ移る資産規模は, 個々の家計の観点から
は, そもそも相当の金額と考えられる。
個人資産についてその形成過程を考えると,
①親から受け継ぐ相続資産と, ②自らの収入
を元に築いた資産の二種類から成るが, 研究
によれば前者①は個人資産全体の3~4割を
2010.10
8
図6 世代別の金融資産構成
(注) 二人以上の世帯対象。(出所) 総務省 「家計調査」 (2008年) から野村資本市場研究所作成
20歳代 30歳代 40歳代
50歳代 60歳以上(勤労者世帯 60歳以上(無職世帯
預貯金 74% 預貯金 64%
その他 20%
有価証券 6%
有価証券 11%
有価証券 8%
有価証券 16% 有価証券 20%
有価証券 10%
その他 28%その他 37%
その他 18%その他 25%その他 33%
預貯金 53%
預貯金 56% 預貯金 60% 預貯金 62%

占めると推定されている。 今後は下記の点か
らも, その重要性は更に高まろう。
第一に, 近年では勤続年数が長くなっても
所得が伸びづらくなっている点が挙げられる。
そのため現役世代の資産形成は, 前の世代が
同年期であった時と比べて平均的に遅れをとっ
ており, 相続で受け継ぐ資産の重要度が相対
的に高まってゆくと考えられる。
第二に, 一人当たりの相続割合が増えると
見られる点も挙げられる。 人口動態から判断
すると, これから相続する世代の兄弟姉妹数
は, 既に相続を受けている世代に比べて半減
するため, 一人当たりが受け取る相続資産の
割合が増えると見込まれるからである。 親が
残す資産額が同じでも, 子一人がもらえる相
続資産額は増えることになろう。
3. 見えざる資産移動
相続というライフイベントは, その特性と
して, まとまった資産の持ち主を変えてゆく。
相続時には, 親世代の資産が子世代へ必ず移
るし, それが金融資産なら親の口座から子の
口座へと異なる口座へ必ず移る。 そのため,
個人金融資産の分布は一朝一夕で変わるもの
ではないが, 相続がもたらす影響は確実に及
ぶものであり, しかも少子高齢化の進展と共
にその影響は大きくなってゆくと予想される。
また, 相続による資産分布への影響は, そ
の資産内容からも大きくなっていると考えら
れる。 相続財産に占める現預金の割合は, 戦
後長らく8%前後で推移してきたが, 1992年
以降は上昇が続き, 直近では21%と過去最高
に達している (図8)。 このことは, 相続資
産の流動性や使途の自由度が, 以前と比べて
高くなっていることを意味していよう。 同時
に, 現預金での相続は, 不動産等と異なり売
却等で時間を要さないため, 被相続人の口座
から相続人の口座へと瞬時に移動することも
意味している。 そのため, 相続に伴う資産移
動スピードは速まっていると考えられ, 見え
ざる資産移動がもたらす個人資産分布への影
響も, その分大きくなっていると考えられる。
2010.10
9
図7 相続資産規模の見通し
(注) 1.一人当たり平均資産額×死亡者数と, 相続税対象資産の推定実勢評価額を合計して推計。2.予想については一人当たり平均資産額と相続税対象資産は直近値を基に横ばいと仮定した。
(出所) 国税庁統計, 総務省統計, 国立社会保障・人口問題研究所統計等から野村資本市場研究所推計
兆円) (万人
(年
60
55
50
45
40
150
120
90
60
30
02000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(予想)
死亡者数(右軸)
相続資産額(左軸)
図8 相続資産に占める現預金割合の推移
(出所) 国税庁統計から野村資本市場研究所作成
%)22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 048 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 2000 04 08
(年

Ⅳ. 個人金融資産はどこへ集まるのか
1. 個人間の資産分布はどう変わるのか
このように 「相続」 は, 資産規模や, 個人
の資産形成への影響, そして個人資産分布へ
の影響を考えると, その重要性が一層高まっ
てゆくと予想される。 そこで, 相続によって
個人間・世代間・地域間の資産分布がどう変
わるのかを, 以下では順に検討する。
まず, 個人間の資産分布への影響に注目し
たい。 表1は, 相続税統計からわかる資産額
階級別の相続の実態である。 相続税は, その
年に他界した人のうち, 資産保有額が多い上
位約4%の人しか対象とならない, いわば富
裕層対象の税金である。 その相続税統計によ
ると, 大卒サラリーマンの平均生涯賃金 (3
億円) を超える資産を相続する人が, 2008年
だけで約3,500人いたと推定される。 「1億円
を超える資産を相続する人」 に対象を広げれ
ば約2万9,000人になる。 更に 「4,000万円を
超える資産を相続した人」 に対象を広げると,
表1で把握できる相続人数合計15万2,234人
に加えて, 基礎控除等で相続税の申告が不要
で統計の対象とならない人達も含まれること
になる。
そのため, 相続で多額の資産を受け取るこ
とは, ごく一部の限られた人だけの話ではな
いだろう。 金融機関の顧客の中にも, 相続を
契機に資産額が急増する人は, 少なからず現
れているのではないかと推察される。
2. 世代間の資産分布はどう変わるのか
相続は個人間の資産分布を変えるだけでは
なく, 世代間の資産分布も変えてゆく。 これ
に関連する近年の注目すべき変化として, 長
寿化の進展が挙げられる (図9)。 人口統計
2010.10
10
表1 課税価格階級別の相続状況 (2008年)(億円)
(出所) 国税庁統計より野村資本市場研究所作成
課税価格階級被相続人の数 課税価格 納付税額 法定相続人の数
相続人1人当たりの平均相続額納税前 納税後
人数 割合 金額 割合 金額 割合 人数 割合 金額 金額
1億円以下1億円超2億円超3億円超5億円超7億円超10億円超20億円超30億円超50億円超70億円超100億円超
10,81222,4306,9794,5241,4658817031306414113
22.5%46.7%14.5%9.4%3.1%1.8%1.5%0.3%0.1%0.0%0.0%0.0%
8,97631,28116,89317,1238,5837,2729,3873,1052,410785909531
8.4%29.2%15.8%16.0%8.0%6.8%8.8%2.9%2.2%0.7%0.8%0.5%
1301,2801,4312,2821,4801,5082,25988771820922397
1.0%10.2%11.4%18.3%11.8%12.1%18.1%7.1%5.7%1.7%1.8%0.8%
25,21373,21724,89716,5205,5163,3602,657509244454412
16.6%48.1%16.4%10.9%3.6%2.2%1.7%0.3%0.2%0.0%0.0%0.0%
0.40.40.71.01.62.23.56.19.917.420.744.2
0.40.40.60.91.31.72.74.46.912.815.636.2
合計 48,016 100.0% 107,254 100.0% 12,505 100.0% 152,234 100.0% 0.7 0.6
1億円
3億円

などから推計すると, 近年の長寿化の結果,
親の資産を相続する長子の年齢も上昇してお
り, 1970年代には相続時点での長子の年齢は
40~50歳代であったが, 現在では50~60歳代
である。 親世代の資産は, 父親と母親それぞ
れの他界時ごとに子世代へ移転されてゆこう
が, 父親他界時にはその資産の大半が配偶者
(母親) へ移る可能性もあるため, 親世代の
資産が全て子世代へと移るのは母親他界時で
あろう。 その観点から考えると, 親世代の資
産を実際に相続するのは, 長子が既に退職し
た後である可能性が高いと考えられる。
相続時期の遅れは, 世代間の資産分布に影
響すると考えられる。 そもそもわが国では年
齢が上がるほど平均資産額が多く, 60歳代以
上の世代が個人資産の6割を占めることは既
に述べたが, 相続年齢が上昇していることは,
相続を通じて多額の資産が60歳以上の間で循
環していることを意味する。 そのため, 高齢
化の進展と相続を通じて, 個人資産が60歳以
上の世代にますます偏在してゆくと考えられ
る。
3. 地域間の資産分布はどう変わるのか
相続が個人資産の地域分布をどのように変
えるのかを考える上では, 地域間の人口統計
に注目すべきである。 地域を越えて移動する
人が増えるにつれて, 親と異なる地域に住む
子が増えてゆくため, 将来, 異なる地域に住
む親子間の相続も増えてゆくと予想されるか
らである。 その結果, 転入者が多い地域では,
他県に住む親から県内に住む子へと, 相続資
産が流入し, 逆に転出者が多い地域では, 県
内に住む親から他県に住む子へと, 相続資産
が流出すると考えられる。
資産の地域分布を変える人口要因として,
すぐに思いつくのは 「引越」 であろう。 ただ
し引越の場合, 取引金融機関や口座を変えな
2010.10
11
図9 長寿化の進展
(注) 1.50歳以上の死亡者の年齢別構成を示した。2.1990年までは 「90~94歳」 に90歳以上が全て含まれる。
(出所) 厚生労働省統計から野村資本市場研究所作成
%)男性
50~54歳 60~64歳 70~74歳 80~84歳 90~94歳 100歳以上
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1970年1980年 1990年 2000年 2009年
%)女性
50~54歳 60~64歳 70~74歳 80~84歳 90~94歳 100歳以上
25
20
15
10
5
0
1970年1980年 1990年 2000年 2009年

い人もいるため, 本人の引越と共に資産も動
くとは限らない。 また, 転居者が若年である
ほど資産も少ないことが多く, 人口移動に伴
う地域金融資産への影響は短期的には小さい
だろう。 むしろ, 個人資産の地域分布を変え
る要因として注目すべきは, 人が移動して数
十年たった後に起こる, 「相続」 を通じた資
産移動であろう。
戦後の人口移動の推移を確認すると, 1960
年代前後に最も多くの人が移動しており, 現
在の3倍以上もの人数が毎年, 地方圏から大
都市圏へと移動していたことに気づく。 当時
は高度成長期であり, 戦後ベビーブーム世代
前後の進学や就職期とも重なり, 大都市圏へ
移動した人が多かったのだが, ここで注目し
たいのは, 高度成長期に地方圏から大都市圏
へ移動した若者が今や, 親から資産を相続す
る年齢に達していることである。 つまり,
「地方圏に住む親から大都市圏に住む子へ」
という相続事例が多くなっていると考えられ
るのである。
そこで, 過去の人口移動による将来の相続
人数の変化と, 相続人一人当たりの相続額を
推定し, 2020年までの10年間に相続を通じて
地域を移る資産がいくらになるかを推計した
(図10)。 その結果, 他県から相続資産が流入
し, 地域個人金融資産の増加割合が大きい地
域は, 埼玉県, 千葉県, 神奈川県の順である。
逆に, 他県へ相続資産が流出し, 地域個人金
融資産の減少割合が大きい地域は, 山形県,
秋田県, 長崎県の順である。
この結果を解釈すると, 次のようになろう。
まず, 東京・大阪の二大都市圏では, 相続を
通じて資産が流入すると見込まれ, 特に東京
圏では流入額もその影響も大きい。 ただし流
入資産は, 東京圏では東京都よりも埼玉県,
千葉県, 神奈川県が多く, 大阪圏では大阪府
よりも滋賀県, 奈良県が多い。 この背景には,
進学や就職等で地方圏から大都市圏へ移った
当初は東京や大阪といった都心へ向かったも
2010.10
12
図10 2020年までに相続がもたらす地域個人金融資産の変化
(出所) 野村資本市場研究所
流入
流出
5%以上0%以上5%未満0%未満-5%未満-5%以下-10%未満-10%以下

のの, 最終的な住まいは郊外に求めた人が当
時は多かったことが考えられる。 資産流入が
期待できるこれらの地域では, 相続を通じて
富裕層の人数や割合も増えることが予想され
る。 また, 二大都市圏以外でも, 地域経済圏
の中心県では資産流入が見込まれたり, 流出
の影響が限定的である。 しかしその他の地域
では, 資産流出の影響が相対的に大きくなっ
ている。
ところで, 図10では資産が流出する地域が
ほとんどであるが, 足下では預金がむしろ増
加している地域金融機関も多く, 相続で域内
資産が流出するリスクを肌身で感じていない
金融機関も少なくないと見られる。 これは営
業努力や金融緩和等の影響に加えて, 構造的
要因として郵便貯金から流出した資金が, 域
内の他の金融機関へシフトしたことも一因で
あると見られる。 地域別の郵便貯金からの流
出額は相続による資産流出額を上回ると推定
され, 実際には, 地域全体の個人預金額は減
少している地域が多いことに気づきづらいか
らであろう。
しかし, 2007年以降は郵便貯金からの流出
ペースが次第に鈍化, 足下では流出が止まり
つつある2) (図11)。 そのため, 今後は相続に
よる資金移動の影響が, そのまま顕在化する
ことにより, 地域ごとの金融機関を取り巻く
環境変化が, より見えやすくなると予想され
る。
但し, 上記の推計は話が複雑になることを
避けるために様々な前提をおいている。 例え
ば第一に, 他県に住む子が資産を相続する場
合, 土地など実物資産は地域住民へ売却し,
金融資産に換えてから自分の住む地域の口座
へ移すと想定した。 しかし, 売却が遅れれば,
他県に資産が移る時期が遅れる可能性はあろ
う。
第二に, 両親それぞれから子が資産を相続
すると想定した。 しかし実際は, 父親他界時
には資産は配偶者である母親の元へ行き, 母
2010.10
13
図11 郵便貯金残高の推移 (前年差)
(注) 2007年10月に日本郵政公社は民営化したが, 図では民営化前後で振替貯金等を調整してある。
(出所) ゆうちょ銀行資料, 旧日本郵政公社公表資料から野村資本市場研究所作成
兆円)0
-5
-10
-15
-202001 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(年
表2 アンケートに見る遺産に対する考え方
(注) 質問1は子がいる人, 質問2は子が二人以上いる人を対象。
(出所) ホリオカ・山下・西川・岩本 (2002) 「日本人の遺産動機の重要度・性質・影響について」 (『郵政研究所月報』 第163号) を基に野村資本市場研究所が再構成
(%)
日本 米国
質問1 遺産を残す予定について遺産を残す余れば遺産として残すその他
質問2 遺産の分配方法について均等に面倒を見てくれた子に多くその他
26704
493219
46513
9621

親他界時になって両親の資産がようやく子へ
移る可能性があろう。
第三に, 相続資産は兄弟姉妹間で均等に受
け継ぐと想定した。 しかし, アンケート調査
によると, 面倒を見てくれた子に資産を多く
遺したいと考える人も少なくない (表2)。
そのため, 地元で親の面倒を見る子に多くの
資産が遺り, 他県に住む子に遺る資産が少な
い可能性はあろう。
第四に, 平均的な家計を対象にしており,
富裕層は対象としていない。 そのため, 仮に
富裕層データも含めた場合, ここでの試算結
果よりも流入・流出額共に大きくなろう。
Ⅴ. わが国への示唆
1. 個人金融資産の重要性
ここまでは, 今後迎える少子高齢化社会の
下で, わが国の個人金融資産がどう変わるの
かを検討してきた。 第Ⅱ章で検討した通り,
わが国の家計貯蓄率は早晩マイナスになり,
家計部門の金融資産は減少してゆくと予想さ
れる。 別の言い方をすると, 家計全体で見れ
ば毎年の収入以上を消費に充てることになる
ため, これまでのように資金が余らずに, む
しろ不足することになるだろう。
このことを国全体というマクロの視点から
見ると, 貯蓄・投資バランス (ISバランス)
において, これまでの 「家計部門の貯蓄超過」
の状態が変わっていくことを意味する。 これ
までわが国では, 「家計部門の貯蓄超過」 が
「政府部門と企業部門の貯蓄不足」 を埋める
形が続いてきた。 また, 国債や株式の資金の
出し手を遡ってみると, 直接的・間接的に家
計部門の資金で賄われる面が大きかった。 家
計は資産の多くを預金や保険として金融機関
に預け, 銀行や生命保険会社はその投資先と
して国債など有価証券を保有していることか
ら, 家計は金融機関を通じて間接的にも政府
や企業に資金を貸していると考えることもで
きる。 実際, 2009年末時点では, 家計は国債
を35兆円保有し, 金融機関を経由した間接的
2010.10
14

な保有額も加えると366兆円 (残高の54%)
と推定される。 また家計は株式を97兆円保有
し, 金融機関を経由した間接的な保有額も加
えると166兆円 (残高の70%) と推定され
る3)。
家計資産を減らさないような政策は, 金融
市場の安定を維持するためにも, 今後の成長
を支える原資を確保するためにも大切であろ
う。 家計資産を減らさないための政策は幾つ
か考えられる。
2. 個人金融資産を維持・拡大するために
まず, 高齢化に伴い現役世帯が減少するペー
スを遅らせるため, 労働力率を引上げるよう
な政策が考えられる。 「70歳まで現役」 が普
通の社会となり, 退職年齢を今よりも遅らせ
て働き続ける人が増えれば, 個人金融資産を
減らさず, むしろ増加させることができる。
例えば, 60~70歳の男性労働力率が50歳代並
に上昇することを想定すると, 個人金融資産
は2020年までに約75兆円増加すると見込まれ
る。
因みに2010年3月に発表された EUの新成
長戦略 「欧州2020」 では, 次の10年に向けた
目標として, 労働力率引上げが盛込まれた。
日本にとって労働力率引上げは, 経済成長や
家計資産拡大の効果が期待できるだけではな
い。 他先進国に比べて高齢化のスピードが速
いだけに年金制度など社会構造の変化が追い
ついていない事態へ対処する補完的効果も期
待できるだろう。
個人金融資産総額を減らさない別の方法と
しては, 資産収益率を引上げるような政策が
考えられる。 試算によると, 現在家計が保有
している有価証券の価値が毎年約2%増加す
れば, 2020年時点でも現在の個人金融資産水
準を維持することができる。 仮にその倍の4
%増加することを想定すると, 個人金融資産
は2020年までに約55兆円増加する。
現在のように預金金利が低い中では, 預金
に偏った資産配分から有価証券への投資を拡
大し, 家計資産全体の収益率を引上げること
が必要になろう。 そのためには, 国全体の経
済成長率を高め, 成長の果実を家計資産増加
として享受できるようにすることが必要であ
ろう4)。 これまで政府は家計に金融市場を通
じた長期投資を促すことで成長分野への資金
の流れを作ることを目指してきたが, 今後も
税制などを通じた誘導策を維持する必要があ
るだろう。
また高齢化社会・人口減少社会の下で国全
体の経済成長率を高めるためには, 一人当た
りの生産性を引上げることが大切な課題だが,
高等教育 (大学段階) はこのような人材を養
成し, 長期的な成長をもたらすための本源的
投資と考えられる。 政府支援としては 「教育
機関への支援」 と 「家計への直接支援」 の両
面から必要だろうが, 国全体の生産性引上げ
に有効と考えられるにもかかわらず, 現在手
薄になっているのは, 税制優遇を通じた, 高
2010.10
15

等教育段階での家計の教育費負担軽減策であ
る (教育資金積立制度, 詳しくは補論参照)。
ここまでは, わが国全体の個人金融資産を
維持・拡大させる方策を議論してきたが, 第
Ⅳ章で検討した通り, 相続によって地域を越
えて資産が動く結果, 個人金融資産が減少す
る時期やペースが, わが国全体の動きと比べ
て早い・速い地域も少なくない。 このことは,
地域全体の活力や税収などに影響を及ぼすた
め, 地方自治体にとっても見過ごすことがで
きない課題であろう。 上記のような個人金融
資産を減らさない方策は, 国だけでなく地方
自治体にも検討の余地があると思われる。 ま
た, 相続したものの売却できないために生じ
る空き家問題への対策として, 空き家活用ビ
ジネスに取り組む自治体も見られており, 地
域に合わせた工夫が今後一層求められてゆこ
う。
この他, 家計資産を減らさないために金融
機関が果たすべき役割も重要であろう。 金融
機関側からのサポートとして, 家計へ提供す
る金融商品やサービス, 金融教育に工夫を凝
らすなどの努力が求められよう。
Ⅵ. 金融機関への示唆
1. 変わるリテールビジネスチャンス
最後に, ここまで議論してきた個人金融資
産への分析を基に, 金融機関にとってリテー
ルビジネスチャンスがどう変わるのかを検討
したい。
少子高齢化の進展で個人金融資産総額をは
じめこれまで拡大してきた多くの市場が頭打
ち・縮小する見通しの中で, 相続で動く資産
は規模自体が拡大している。 足下の規模は全
国合計で年間50兆円にも達し, 47都道府県で
単純平均すると1県当たり1兆円にも上る。
相続で動く資産が大きいだけに, それを手中
に収めることは市場シェアを引上げ 「規模の
効果」 を出す上で有効な手段になりうること
から, 今後, 相続資産の獲得は, リテールビ
ジネスの重要な戦略課題になってゆこう。 ま
た相続による都道府県間資産移動があるもの
の, それでもどの地域においても地域内に留
まる資産の方が圧倒的に大きい。 資産の流出
が予想される地域においても, 有望なビジネ
スチャンスであることには変わりはない。
このように注目を集める相続だが, 特有の
難しさもある。 相続とは一般に, 誰が・いつ・
どのくらいもらえるのか, 不確実な要素が多
いからである。 また, 相続が発生してから金
融機関が相続人へアプローチをかけたくても,
2010.10
16

既に資産は被相続人 (親) の口座から相続人
(子) の口座へと移っており, 後者の口座は
他金融機関にある場合も少なくないため追跡
も難しい。 しかし, 相続を通じた見えざる資
産移動は, 着実に進行しているのである。
そのため, 相続を通じて資産がどこへ集まっ
てゆくのかを認識するべきである。 第Ⅳ章で
の議論をまとめると, 下記のようになる。
(1) 個人間では, 相続資産をもらえる人と
もらえない人との資産格差が拡大してゆく。
金融機関にとっては, 顧客へのアプローチを
考える上では 「現在」 の取引状況・収益性だ
けでなく, 今後相続で資産が増える可能性も
考慮した 「将来」 の観点も必要であることを
示唆している。
(2) 世代間では, 長寿化に伴い相続人の年
齢も上昇していることから, 個人資産の大半
は60歳以上で循環し偏在が進んでゆく。 金融
機関にとっては, ①個別に将来の相続人がわ
からない場合には世代でセグメントを絞った
マーケティングが有効であること, ②60歳前
後の世代こそが近い将来の優良顧客であるこ
とを踏まえて, この世代のニーズに応えた商
品・サービスを提供できるような工夫が必要
であることを示唆している。
(3) 地域間では, 過去に人口が流入した地
域へ, 今後は相続を通じて個人資産が移って
ゆく。 金融機関にとっては, 相続人との接点
を軸に, 顧客属性を分類し, それぞれの属性
に応じたサービスを提供することが重要であ
ることを示唆している。
つまり, 「近い将来の相続人」というセグメ
ントにターゲットを絞り, 属性に合わせて取
引関係を築くことが戦略上のポイントとなる。
これに対して, 相続世代に差し掛かっている
団塊世代が金融機関を選ぶ上で重視している
ポイントは, アンケート調査によると, 第一
に 「以前からの取引」, 第二に 「有利な商品
やサービスの存在」, 「店舗・ATMの利便性」
であった。
これらを総じてみると, 相続発生前から予
めメイン口座の一つとして取引頻度を高めて
いてこそ相続発生時にも資産の預入先として
選ばれる口座になる。 相続発生前から取引履
歴を作り緊密な取引を行うためには, 近い将
来の相続世代にセグメントを絞り, 退職後の
人生で使い勝手の良い口座にするという仕掛
け作りによって, このセグメントのニーズに
応えることが大切になる。 以下では, 「取引
履歴を予め作ること」 「魅力的な商品・サー
ビスの提供」 「サービスの利便性」 の3つの
ポイントについて, 検討したい。
2. 取引履歴を予め作るために
相続というライフイベントが生じる前から
「取引履歴」 を作る戦術としては, 第一に,
「退職金へのアプローチ」 が有用と考えられ
る。 近年の長寿化に伴い, 相続時期が後ずれ
し相続人年齢も上昇していることは既に指摘
したが, その結果, 多くの人にとってライフ
2010.10
17

イベントの順番は, 「父親からの相続」 →
「退職」 → 「母親からの相続」 になっている
と見られる (図12)。
そのため 「退職金へのアプローチ」 は, 実
は退職金そのものを取り込むことだけでなく,
その後受け取る「母親からの相続資産」を預け
入れてもらうための前哨戦としても位置付け
られる。 一般的な家庭の場合は, 父親からの
相続資産の大半は (配偶者である) 母親の元
へ行くため, 母親からの相続の方が子世代の
資産形成には重要と考えられる。
退職金の規模を統計で見ると, 大卒平均が
2,026万円, 高卒平均が1,606万円となってい
る。 この内の半分は住宅ローン等の借金返済
や消費に充てられるため, 預貯金や資産運用
に回るのは残りの半分と見られる。 これに対
して相続資産は, 母集団の多さから信頼性が
高いと見られるアンケート調査によると平均
4,234万円となっている。 これらの数字から,
金融機関が受け入れる資金規模としては,
「相続」 の方が 「退職」 よりも多いと考えら
れるが, ライフイベントとして 「相続」 より
も 「退職」 の方が時期を特定しやすいため,
「退職金へのアプローチ」 は展開しやすいと
いう利点がある。
第二に, 「取引履歴」 を作る上で, 富裕層
の場合は親世代が子世代へ資産を遺す可能性
が高い, ということに注意すべきであろう。
富裕層である親世代との取引関係を既に築い
ているのであれば, 金融機関はその取引関係
を活用して, 子世代とも取引関係を築く方法
を考えることも一案である。 例えば, 商品を
通じて子世代の情報を得ることや, 親世代か
ら子世代を顧客として紹介してもらえるよう
な仕組みを作ることなどの方法が考えられよ
う。
第三に, 「取引履歴」 を作る上で, 子世代
が相続を受ける少し前のニーズに応えること
で, 相続前に予め緊密な取引を築いておくこ
とも重要である。 現役所得の伸び悩みや, 相
続タイミングの遅れなどにより, 現在の40~
50代はかつての40~50代よりも資産形成事情
は厳しく, ファイナンスニーズはむしろ高まっ
ている。
例えば, これまで多くの金融機関は, 20~
30歳代を中心とする 「若年時のライフイベン
トでの取引関係」 を作ることに注力する傾向
が強かったように思われる。 20~30歳代の時
点でメイン口座化に成功すれば, それ以降は
2010.10
18
図12 ライフイベントと世代別資産
(注) 資産額は世代別の世帯平均資産額である。(出所) 総務省統計, 厚生労働省統計等から野村資本市場
研究所推計・作成
万円)6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
実物資産貯蓄現在高負債現在高
母親の資産
父親の資産
昔 今
昔 今
退職
20代 30代 40代 50代 70代~60代

顧客のライフステージが上がるにつれて顧客
取引額も自動的に増えてゆく, という戦略で
あったと考えられる。
しかし, 将来の相続人と取引を開始・緊密
化するという目的のためには, 「熟年時から
のライフイベント」 を利用して取引関係を構
築することが有効である。 この観点からは,
実は, 「教育ローン」という商品は戦略商品と
して位置付けられるものであろう。 「子供の
教育費負担」 は家計を圧迫する要因であるが,
統計で見ると, 特に大学生の子を持つ世帯に
おける教育費負担が最も重く, 月々の収支は
赤字である (図13)。 アンケート調査による
と東京の私立大学へ子を進学させた親の5人
に1人はローンで入学費用を工面している。
大学生の子を持つ親は 「近い将来の相続人」
世代であることを意識し, 「教育ローン」 と
いう古くからある商品も, 「近い将来の相続
人」 との取引履歴作りという目的の下で捉え
直すことが考えられよう。
3. 魅力的な商品・サービスを提供するた
めに
相続資産を活用するための商品・サービス
を充実させることによって, 相続資産を移し
たくなるような適切な受け皿作りを考えるこ
とも有効であろう。 この場合に, 「安い手数
料」 など利用者のコスト意識に訴えることも
勿論大切であるが, そのような観点だけでな
く, 「相続人世代のニーズを満たすことに正
面から取り組んだ商品・サービス」 を提供す
ることの方がより重要であると考えられる。
そもそもわが国の平均的な家計の資産構成
を見ると, 60歳以上の世帯は金融資産に占め
る有価証券の割合が高く, 60歳以上の世帯は
そもそも運用への関心が高いと考えられる
(図6)。 これに加えて, 例えば近年の長寿化
により相続する時点での子の平均年齢が上昇
していることを考慮すると, いわゆる 「長寿
リスクに対応できるような商品・サービス」
2010.10
19
図13 子の学齢別の世帯収支状況
(注) 両親と子1人の世帯について子の学齢別の平均世帯収支状況を示した。(出所) 総務省 「全国消費実態調査 (平成16年)」 から野村資本市場研究所作成
教育支出/消費支出 可処分所得-消費支出%) 万円)20181614121086420
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4未就学児
小中学生
高校生
大学生
未就学児
小中学生
高校生
大学生

を充実させることは, 今後, 退職後の新たな
マネープランを必要とするこのセグメント層
へ, 強くアピールすると考えられる。
相続資産に占める現預金の割合は過去最高
に達していることは既に指摘したが (図8),
近年は年金・医療など公的制度への不安が高
まる一方, 伝統的にリスクに対する緩衝材と
なってきた 「家族間の支え合い」 も期待しに
くくなっており, 個人が老後に直面するリス
クは以前よりも大きくなっている。
このような状況下での現預金比率の上昇は,
高齢者が抱える様々なリスク (特に想定以上
に長生きしたことによる資金不足) に対する
ヘッジ手段が不足しているという問題点を,
改めて示唆していると考えられる。 家計のリ
スクコントロール上のニーズが多様化してい
るにもかかわらず, 適切なリスク管理を行う
ことができる選択肢が現状では限られている。
今後は, 家計のリスクコントロール上の穴を
埋めるような金融商品を開発し提供すること
が, 金融機関に期待される大切な役割であろ
う。
この中では, 多様な運用期間への対応も求
められよう。 長寿化の動きは男女で異なるこ
とも考慮すると, 平均的な夫婦にとっての適
切な運用期間は, 夫本人の年齢だけから自動
的に決まるものではないだろうし, 子の相続
後までも視野に入れるのであれば, 運用期間
は世代を超えて考えることも求められよう。
長期に亘る運用は, 富裕層顧客の方がニー
ズは高い。 これに対応するためには, 富裕層
の資産額や資産内容に応じて, 特有のリスク
をヘッジする商品や世代を超えた運用体制,
ファミリーオフィスのような包括的サポート
まで, 様々な商品・サービスが求められよう。
また子へ遺す資産内容は必ずしも金融資産だ
けではない。 例えば米国で金融機関が提供す
る金融サービスのうち, 資産額上位層でニー
ズが高まるサービスとしては, 教育資金作り,
相続計画作り, トラストサービス, 寄付計画
なども挙げられる。
また, 近い将来の相続人世代のニーズを満
たすことに正面から取り組んだ商品・サービ
スを提供するためには, これまでと発想を転
換して, 現役世代ではなく退職世代を中心に
見据えたビジネス戦略を検討すべきであると
考えられる。
今後は個人の資産形成において相続の重要
性が高まることに鑑み, 個人の生涯にわたる
資産選択を考えるときに, 相続資産の活用の
ための提案力が金融機関に求められるだろう。
最終的には, 退職後の長い人生のマネープラ
ンを支えるための, 有用な仕組みや必要情報
を提供することで, 相続した資産を入れたく
なるような適切な受け皿となることを目指す
ことが必要である。 多くのわが国の金融機関
では, 退職後のマネープランを支えるサービ
スが現時点では十分とは言えず, 時間をかけ
て取り組んでゆく必要があろう。
因みに米国では, 高齢化問題は, 足下でこ
2010.10
20

そ金融・景気問題の陰に隠れているが, 今後
一層増えてゆく高齢者層のニーズへの対処は
既に金融機関の重要な課題と認識されている。
長寿化は米国でも進んでおり, 退職後のイン
カム確保のために自助努力が一層求められる
こともわが国と同様である。 米国の相続資産
規模は日本の1.6倍あるが, 今後はベビーブー
マー世代も加わりその規模は急速に拡大する
と見込まれており, 資産移転のための商品・
サービスの開発も進められている。
米国で高齢化社会を研究している専門家に
よると, 退職後のためのファイナンシャル・
プランニングでは, ①長寿リスク, ②健康,
③財産, ④遺産, ⑤流動性を考慮する。 加え
て, 望ましい場所で, 望ましい人々と, 自分
の好きなことをやっているかといった点も,
退職後の生活を充実させる上では大事なこと
であり, 長寿化社会では現在ある商品・サー
ビスだけではなく, さまざまな新しい商品・
サービスの開発が必要とされているとも指摘
している。
わが国の金融機関においても, 相続資産の
受け皿作りという観点を意識するにあたって
は, 充実した退職後の生活を可能にさせるファ
イナンシャルプランの在り方も含め, 様々な
商品・サービスやその提供の仕方を工夫する
ことにより, 当該セグメント層にとって魅力
的な金融機関となりうるのではないだろうか。
4. サービスの利便性を高めるために
ここまで 「取引履歴作り」 や 「魅力的な商
品・サービス」 について検討してきたが, こ
れに加えて 「サービスの利便性」 も重要項目
である。 ただし, どの地域でも同じサービス
を提供するのではなく, 金融機関との接点を
軸にしたサービスの利便性を, 考えるべきだ
ろう。 例えば, 近くに住んでいるから便利な
サービスと, 遠くに住んでいるから便利なサー
ビスとでは異なるため, 金融機関との接点が
異なれば, 求めるサービス内容も異なると考
えられるからである。 それに合わせて, 店舗
スタイルやコストのかけ方も変わってくるだ
ろう。
相続で動く資産を自行へ誘導することを考
えると, 相続を通じて資産が流入する地域の
マーケットは, 「県内に住む親子間の相続」
に加えて 「他県に住む親と県内に住む子の相
続」 の二種類である (図14左側)。 そのため,
金融機関の地域戦略は, 県内相続に絡むサー
ビスのみならず, 他県にいる親から資産を相
続する子へのサービスも充実させることが重
要であろう。 また, 資産流入地域である大都
市圏では, 職住の地域が異なる人 (例えば東
京圏では埼玉都民や千葉都民と称される人)
が少なからずいる。 退職を機に金融機関との
接点が変わることを踏まえたマーケティング
戦略は有効だろう。
逆に, 相続を通じて資産が流出する地域で
2010.10
21

は, わが国全体の個人金融資産よりも状況は
厳しい。 このような地域の相続マーケットは,
「県内に住む親子間の相続」 に加えて 「県内
に住む親と他県に住む子の相続」 の二種類で
ある (図14右側)。 そのため, 金融機関の地
域戦略も, 県内相続に絡むビジネスを着実に
捉えることに加え, 他県に住むからこそ便利
なサービスを提供することで, 資産流出を防
ぐことがポイントとなろう。 県内マーケティ
ングに加えて, 県外に住む子世代との関係を
構築するためのマーケティングも重要なポイ
ントとなろう。
また, 全国展開する金融機関の場合は, 資
産の流出元と流入先の両方に店舗を有してい
る。 そのため, 店舗間の連携を進める仕組み
作りは, 戦略上特に有効だと考えられよう。
Ⅶ. おわりに
このように, わが国の個人金融資産は, 人
口動態という長期的で確実な要素によって,
大きな変化が見られてゆこう。 個人金融資産
において 「相続」 は重要な意味を持っており,
今後その重要性は一層高まると考えられる。
現在, 個人資産全体の6割を60歳代以上が保
有しており, その資産が次世代へと順に移転
されてゆくことは, 大規模な個人資産の世代
移転という大きな潮流がまさに今, 進行して
いることを示唆している。 そのスピードは思
いのほか速いことにも注意すべきである。 実
際, 60歳以上が保有する資産の割合は, 過去
15年間で3割から6割へと倍増しているので
ある。
わが国にとって, 個人金融資産を減らさな
いことは重要な意味を持っている。 そのため
には, 人的資本や金融資本を有効に活用する
2010.10
22
図14 資産流入県と流出県の相続マーケット
(出所) 野村資本市場研究所
資産流入県 資産流出県
親(資産を遺す世代)
子(相続する世代)
県内在住 県内在住
県内在住県内在住
他県在住
他県在住
県内の相続資産
他県からの相続資産
親(資産を遺す世代)
子(相続する世代)
県内の相続資産

方策が考えられ, 国や地方自治体からの政策
的なサポートが望まれよう。
金融機関にとっては, 個人金融資産を巡る
競争は, いわば 「限られたパイの奪いあい」
を意味している。 金融機関は, ①年間50兆円
以上という個人資産の大きな塊が毎年移転す
るということと, ②相続で資産が地域を越え
て移転するために個人資産は大都市圏へ一層
偏ってゆくこと, という大きな潮流変化に対
して, 早くから戦略を立てるべきであろう。
金融機関はこれまで, 経済規模や個人金融資
産が右肩上がりであることを前提としたビジ
ネスモデルを続けてきたところもあると思わ
れ, この潮流変化は大きな戦略転換を迫るも
のであろう。 しかし, 相続で動く資産を捉え
れば, 預かり資産増加やシェア拡大を効率的
に進められることに注目し早く行動に移した
金融機関こそが, リテール市場で選ばれる金
融機関になりうるのではないだろうか。
(補論) 教育資金積立制度について
補論として, 税制優遇の付された教育資金
積立制度をわが国でも検討すべきと考えられ
る背景と制度の概要を紹介したい。
1. 背景
教育とは, 個々人にとっては能力を高め将
来の可能性を広げたり収入を増やすための投
資であり, 国にとっても国際競争力を維持す
るために必要不可欠な投資である。 しかし直
近で家計を取り巻く状況が変化する中, 教育
費の問題が以前にも増して注目されてきてい
る。
主要先進国では, 教育を重要な政策課題に
位置づけており, 家計の教育費負担を支援す
る制度についても工夫を重ねている。 中でも
大学教育は, 経済成長を支える人材養成とい
う点で, 重要な課題である。
わが国でも昔から教育の重要性は認識され
てきたが, 近年は 「教育」 を巡る国際競争も
激しくなっている。 例えば大学進学率を比較
すると, わが国のアジアでの順位は第5位で
あり, 人口が減少しているわが国は, 「人材」
面での優位性を保てるのか危ぶまれる情勢に
ある。
主要先進国と比べてわが国では特に大学教
育費の家計負担が重い。 OECD統計で大学
教育費についての官・民での負担割合を比較
すると, OECD加盟国平均は民間負担割合
2010.10
23

が27%であるのに対し, わが国は66% (家計
は53%) と加盟国平均の2倍であり, 個々の
家計自身が費用の大半を負担する状態にある。
また, わが国のデータからも, 教育費のう
ち, 大学段階が特に負担が重いこと, 家計の
大学教育費負担が近年増していることも分か
る。 後者について, 大学授業料の可処分所得
に対する割合を確認すると, 1998年から2008
年の間に国立校で7.9%から10.1%へ, 私立
校では12.9%から16.0%へ上昇している。 そ
のため, 子の教育段階別の家計教育費負担を
比べると, 子が大学生の世帯では平均で支出
超過に陥っており, 貯蓄の取崩しや借入れで
不足分を賄っている。
このような大学生の子を持つ世帯の厳しい
状況は, 本文で議論した平均賃金伸び悩みや
相続時期の遅れなどとも表裏一体の関係にあ
ると見られる。 また年金, 医療, 介護など様々
な局面で家計の負担が増える中で, 親自身の
生活資金が枯渇するリスクを考慮したときに,
子の教育に充当できる資金を確保しづらくなっ
ているという問題も抱えている。 そのため,
家計の教育費の問題は, 実は景気悪化による
収入減といった問題だけではなく, 人口動態
的な面とも密接に関連しているのである。
そのため, 大学教育費用をいかに確保・手
当するかは家計の重要な関心事になっている。
実際, 世論調査によると子育て世代の貯蓄目
的の筆頭が, 子の教育費である。 また教育費
用の借入れニーズも高い。
しかし, 家計が教育資金を確保するために
利用できる公的制度は近年, 改革や民営化の
流れの中で, 国の関与度合いが低下している
ものが多くなっている。 かつては教育資金を
貯めるため・借りるための両面から, 政府が
家計を支援する制度があった。 しかし現在は,
大学教育資金を貯めるための公的支援制度は
なく, 借りるための制度も利用窓口が縮小さ
れている (ただし残された窓口である日本政
策金融公庫や日本学生支援機構のローンや奨
学金利用者は増加しており, 家計側での教育
資金調達手段へのニーズはむしろ高まってい
ることを裏付けている。)。
子ども手当て, 高校教育の実質無償化によ
り, 高校までの教育費問題への対応は講じら
れたが, 最も負担の重い大学教育費について
は公的な手当てがなされていない。 政府が教
育支出を大胆に増やせない限り, これまで通
り家計の自助努力に頼る姿は変えられないだ
ろう。 その中で現実的な導入のしやすさを考
えると, 喫緊に求められている選択肢とは,
家計の自助努力を支援し, 努力した効果を実
感できるような政策であろう。
家計の教育費問題の本質は, 多額の支出が
大学在学期に集中することにある。 そのため,
問題の解決策は「時間分散」手段の提供である。
「負担の時間分散」 の観点からは, 「先に貯め
る」 と 「後で支払う」 制度は車の両輪である
と考えられ, 現在わが国では 「先に貯める」
制度が欠けている。
2010.10
24

2. 制度の概要
具体的な制度として, 次のような 「個人奨
学金口座」 の導入が望ましいのではないだろ
うか。 これは, 両親や祖父母等が子の大学教
育資金を積み立て運用する際, 税制上の優遇
措置を受けられるという制度である。 具体的
には下記の通りである (図15)。
まず, 資金提供者が受取人 (子) を指定し
た個人奨学金口座へ資金を拠出する。 この口
座は, 金融機関・証券会社の保護預かり口座
及び信託口座であり, 名義は資金提供者だが,
受取人を子に特定するものである。 運用権限
は親等が代理で持つことができ, 運用益 (利
子・配当・譲渡益) は非課税とする。
子が大学へ進学する時点で, 個人奨学金口
座にある全額を, 子本人名義の口座へ振り替
えることができる。 この資金を大学教育とい
う本来の目的に沿って利用したことを証明す
るために, 確定申告時に書類提出を義務づけ
る。 目的を限定する代わりに, 運用益を非課
税とすることに加えて, 資金が贈与税の対象
となる場合には, 振替時点で5年分の贈与税
基礎控除枠の前倒し利用も認めるものとする。
この口座は親だけでなく親族等も設定可能で
あるほか, 子本人が一旦就職した後で大学等
に入り直す場合にも利用可能な制度とするこ
とで, 広く人的資本育成に役立てることを目
指す。
この制度導入により, 次の効果が期待でき
よう。 第一に, 現在高齢世代に偏在する資産
を, 次世代育成のため早期に移転を促すこと
ができる。 これによって, 子育て世代の教育
費負担を支援すると共に, 将来の教育費負担
への不安を緩和させることで, 現在萎縮して
いる消費を喚起する効果が期待される。
第二に, 家計の自助努力を支援し, 努力し
た家計に報いることができる。 教育資金は住
宅や老後の生活費などに比べて必要資金や発
生時期を予め見積もりやすいため, 事前の自
2010.10
25
図15 個人奨学金口座案
(出所) 野村證券
受取人(子)を指定した個人奨学金口座
引出
資金提供者(親族
受取人(子
運用
資金拠出

助努力を支援する制度がふさわしいだろう。
また, わが国では (例えば米・英に比べて)
現役世代の貯蓄率が高いので, 制度の恩恵を
より多くの家計が享受できると考えられる。
第三に, 長期投資の担い手となる子育て世
代への金融教育を兼ねることができる。 個人
向け国債に対する理解も深められよう。
実は, 米国や英国でも, 類似の制度が既に
導入されている。 米国では1990年代以降, 税
制優遇措置を通じた家計向けの教育費負担支
援が増えており, その中でも重要な役割を果
たしているのが529プランと称される, 税制
優遇の付された教育資金積立制度である。
1988年にミシガン州で採用されたのが始まり
で, 1996年以降数次にわたり税制優遇措置の
整備が進み, 2006年には連邦税の非課税措置
が恒久化したこともあって急速に普及が進ん
でいる。 この制度は, 両親や祖父母等が子の
大学教育資金を積み立て運用する際, 税制上
の優遇措置を受けられるという制度であり,
子の親族でなくても拠出することができる。
529プランには二種類あるがそのうち最も普
及している制度では, 拠出資金を個人口座で
積立て, 金融機関の提供する金融商品の中か
ら投資先を選択し運用する。 受益者である子
が進学する際, 口座に積み立てられた資金を
受け取るが, 資金は予め定められた大学教育
目的に利用する必要があり, 目的外利用に対
しては税制優遇が認められず10%のペナルティ
も課される。
英国でもチャイルド・トラスト・ファンド
という税制優遇が付された子供のための貯蓄
制度が2005年から導入された。 この制度は,
子の誕生時と7歳の誕生日に国から給付金と
して£250のバウチャーが支給され, 親が子
のために金融機関に開設したチャイルド・ト
ラスト・ファンド口座でその給付金を金融商
品で運用し, 運用益は非課税で積み立てるこ
とができるという制度であり, 子の親族でな
くても口座へ拠出することができる。 ただし,
2010年に発足したキャメロン政権はこの制度
を見直し, 2010年8月から国からの給付金を
削減, 今後は給付金そのものを停止する方針
である。 529プランと異なる点としては, 年
間拠出額に上限 (£1200) が設けられている
こと, 子が18歳になるまで口座から資金を引
き出せないが使途制約はないことである。 こ
の制度では, 目的を教育資金作りに限定せず,
子が大人になった時点で自身のために使える
資金を得ることを目指しており, 子の人生の
選択肢を広げると同時に人生のスタート時点
での格差を埋める一助となることが期待され
ている。
大学教育費の家計負担を巡る問題の本質は,
多額の支出が在学期に集中することにある。
大学教育費を巡る 「負担の時間分散」 は, 人
口が減少しているわが国では, 人材立国を目
指すため, 政府・民間を問わず社会全体とし
て取り組んでゆくべきテーマであろう。
2010.10
26

《注》
1) 背景には, 介護保険料やエネルギー・通信費上
昇の影響も挙げられるが, これに加えて年齢が上
がると過去の消費水準を切り下げることに抵抗が
生じる効果 (ラチェット効果) が働きやすいとも
考えられよう。
2) 但し日本経済新聞の報道 (2010年5月15日) に
よると, 2010年度については, 郵便貯金のうち期
間10年を主とする定額貯金の集中満期を迎えるこ
とから, ゆうちょ銀行では預金残高は引き続き減
少するとの見方を示している。
3) 日本銀行資金循環統計より計算した。
4) 家計自らが資産分散することで, 海外への有価
証券投資を通じてその高い経済成長をとりこむこ
とも考えられる。
2010.10
27

ディスクレイマー 本資料は表紙に記載されている野村グループの関連会社により作成されたもので、表紙などに従業員やその協力者が記載されている1社あるいは複数
の野村グループの関連会社によって単独あるいは共同で作成された資料が含まれます。ここで使用する「野村グループ」は、野村ホールディングス、およ
びその関連会社と子会社を指し、また、日本の野村證券(「NSC」)、英国のノムラ・インターナショナル plc (「NIplc」)、米国のノムラ・セキュリティーズ・インタ
ーナショナル・インク (「NSI」)、インスティネット LLC (「ILLC」)、香港の野村国際(香港) (「NIHK」)、韓国のノムラ・フィナンシャル・インベストメント(韓国)
(「NFIK」) (韓国金融投資協会(「KOFIA」)に登録しているアナリストの情報は KOFIA のイントラネット http://dis.kofia.or.kr でご覧いただけます)、シンガポー
ルのノムラ・シンガポール・リミテッド (「NSL」) (登録番号 197201440E、 シンガポール金融監督局に監督下にあります)、オーストラリアのノムラ・オースト
ラリア・リミテッド (「NAL」) (ABN 48 003 032 513) (オーストラリアのライセンス番号 246412、オーストラリア証券投資委員会(「ASIC」)の監督下にあります)、
インドネシアのP.T.ノムラ・セキュリタス・インドネシア (「PTNSI」)、マレーシアのノムラ・セキュリティーズ・マレーシアSdn. Bhd. (「NSM」)、台湾のNIHK 台北
支店 (「NITB」)、インドのノムラ・フィナンシャル・アドバイザリー・アンド・セキュリティーズ (インディア) プライベート・リミテッド (「NFASL」)、 (登録住所:
Ceejay House, Level 11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai- 400 018, India;電話: +91 22 4037 4037、ファックス: +91 22 4037
4111; CIN 番号:U74140MH2007PTC169116、SEBI 登録番号(株式ブローカレッジ): BSE INB011299030、NSE INB231299034、 INF231299034、 INE
231299034, MCX: INE261299034、SEBI 登録番号(マーチャントバンキング):INM000011419、SEBI 登録番号(リサーチ):INH000001014)、スペインの NIplc
マドリッド支店 (「NIplc, Madrid」)が含まれます。リサーチ・レポートの表紙のアナリスト名の横に記載された「CNS タイランド」の記載は、タイのキャピタル・
ノムラ・セキュリティーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド (「CNS」)に雇用された当該アナリストが、CNS 及び NSL 間のアグリーメントに基づき、NSL にリ
サーチ・アシスタントのサービスを行っていることを示しています。リサーチ・レポートの表紙の従業員氏名の横に記載された「NSFSPL」は、ノムラ・ストラク
チャード・ファイナンス・サービシーズ・プライベート・リミテッドに雇用された当該従業員が、インタ-カンパニー・アグリーメントに基づき、特定の野村の関
連会社のサポ―トを行っていることを示しています。リサーチ・レポートの表紙のアナリスト名の横に記載された「BDO-NS」(「BDO ノムラ・セキュリティー
ズ・インク」を表します)の記載は、BDO ユニバンク・インク(「BDO ユニバンク」)に雇用され BDO-NS に配属された当該アナリストが、BDO ユニバンク、NSL
及び BDO-NS 間のアグリーメントに基づき、NSL にリサーチ・アシスタントのサービスを行っていることを示しています。BDO-NS は BDO ユニバンクと野村
グループのジョイント・ベンチャーで、フィリピンの証券ディーラーです。 本資料は、(i)お客様自身のための情報であり、投資勧誘を目的としたものではなく、(ii)証券の売却の申込みあるいは証券購入の勧誘が認められていな
い地域における当該行為を意図しておらず、かつ(iii)野村グループに関するディスクロージャー以外は、信頼できると判断されるが野村グループによる独
自の確認は行っていない情報源に基づいております。 野村グループに関するディスクロージャー以外は、野村グループは、本資料の正確性、完全性、信頼性、適切性、特定の目的に対する適性、譲渡可能性
を表明あるいは保証いたしません。また、本資料および関連データの利用の結果として行われた行為(あるいは行わないという判断)に対する責任を負い
ません。これにより、野村グループによる全ての保証とその他の言質は許容可能な 大の範囲まで免除されます。野村グループは本情報の利用、誤用
あるいは配布に対して一切の責任を負いません。 本資料中の意見または推定値は本資料に記載されている発行日におけるものであり、本資料中の意見および推定値を含め、情報は予告なく変わること
があります。野村グループは本資料を更新する義務を負いません。本資料中の論評または見解は執筆者のものであり、野村グループ内の他の関係者の
見解と一致しない場合があります。お客様は本資料中の助言または推奨が各自の個別の状況に適しているかどうかを検討する必要があります。また、必
要に応じて、税務を含め、専門家の助言を仰ぐことをお勧めいたします。野村グループは税務に関する助言を提供しておりません。 野村グループ、その執行役、取締役、従業員は、関連法令、規則で認められている範囲内で、本資料中で言及している発行体の証券、商品、金融商品、
またはそれらから派生したオプションやその他のデリバティブ商品、および証券について、自己勘定、委託、その他の形態による取引、買持ち、売持ち、あ
るいは売買を行う場合があります。また、野村グループ会社は発行体の金融商品の(英国の適用される規則の意味する範囲での)マーケットメーカーある
いはリクイディティ・プロバイダーを務める場合があります。マーケットメーカー活動が米国あるいはその他の地域における諸法令および諸規則に明記さ
れた定義に従って行われる場合、発行体の開示資料においてその旨が別途開示されます。 本資料はスタンダード・アンド・プアーズなどの格付け機関による信用格付けを含め、第三者から得た情報を含む場合があります。当該第三者の書面によ
る事前の許可がない限り、第三者が関わる内容の複製および配布は形態の如何に関わらず禁止されております。第三者である情報提供者は格付けを
含め、いずれの情報の正確性、完全性、適時性あるいは利用可能性を保証しておらず、原因が何であれ、(不注意あるいは他の理由による)誤りあるいは
削除、または当該内容の利用に起因する結果に対する一切の責任を負いません。第三者である情報提供者は、譲渡可能性あるいは特定の目的または
利用への適性の保証を含め(ただしこれに限定されない)、明示的あるいは暗黙の保証を行っていません。第三者である情報提供者は格付けを含め、提
供した情報の利用に関連する直接的、間接的、偶発的、懲罰的、補償的、罰則的、特別あるいは派生的な損害、費用、経費、弁護料、損失コスト、費用
(損失収入または利益、機会コストを含む)に対する責任を負いません。信用格付けは意見の表明であり、事実または証券の購入、保有、売却の推奨を
表明するものではありません。格付けは証券の適合性あるいは投資目的に対する証券の適合性を扱うものではなく、投資に関する助言として利用するこ
とはお控えください。 本資料中に含まれる MSCI から得た情報は MSCI Inc.(「MSCI」)の独占的財産です。MSCI による事前の書面での許可がない限り、当該情報および他の
MSCI の知的財産の複製、再配布あるいは指数などのいかなる金融商品の作成における利用は認められません。当該情報は現状の形で提供されていま
す。利用者は当該情報の利用に関わるすべてのリスクを負います。これにより、MSCI、その関連会社または当該情報の計算あるいは編集に関与あるい
は関係する第三者は当該情報のすべての部分について、独創性、正確性、完全性、譲渡可能性、特定の目的に対する適性に関する保証を明確に放棄
いたします。前述の内容に限定することなく、MSCI、その関連会社、または当該情報の計算あるいは編集に関与あるいは関係する第三者はいかなる種
類の損失に対する責任をいかなる場合にも一切負いません。MSCI および MSCI 指数は MSCI およびその関連会社のサービス商標です。 Russell/Nomura 日本株インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社および Frank Russell Company に帰属します。なお、野
村證券株式会社および Frank Russell Company は、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するもので
はなく、インデックスの利用者およびその関連会社が当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 本資料は投資家のお客様にとって投資判断を下す際の諸要素のうちの一つにすぎないとお考え下さい。また、本資料は、直接・間接を問わず、投資判断
に伴う全てのリスクについて検証あるいは提示しているのではないことをご了解ください。野村グループは、ファンダメンタル分析、定量分析等、異なるタイ

プの数々のリサーチ商品を提供しております。また、時間軸の捉え方や分析方法の違い等の理由により、リサーチのタイプによって推奨が異なる場合が
あります。野村グループは野村グループのポータル・サイト上へのリサーチ商品の掲載および/あるいはお客様への直接的な配布を含め、様々な方法に
よってリサーチ商品を発表しております。調査部門が個々のお客様の要望に応じて提供する商品およびサービスはお客様の属性によって異なる場合が
あります。 当レポートに記載されている数値は過去のパフォーマンスあるいは過去のパフォーマンスに基づくシミュレーションに言及したものである場合があり、将来
のパフォーマンスを示唆するものとして信頼できるものではありません。情報に将来のパフォーマンスに関する示唆が含まれている場合、係る予想は将来
のパフォーマンスを示唆するものとして必ずしも信頼できるものではありません。また、シミュレーションはモデルと想定の簡略化に基づいて行われており、
想定が過度に簡略化され、将来のリターン分布を反映していない場合があります。本資料で説明のために作成・発行された数値、投資ストラテジー、イン
デックスは、EU 金融ベンチマーク規制が定義するベンチマークとしての使用を意図したものではありません。 特定の証券は、その価値または価格、あるいはそこから得られる収益に悪影響を及ぼし得る為替相場変動の影響を受ける場合があります。 金融市場関連のリサーチについて:アナリストによるトレード推奨については、以下の 2 通りに分類されます;戦術的(tactical)トレード推奨は、向こう 3 ヶ
月程度の見通しに基づいています;戦略的(strategic)トレード推奨は、向こう 6 ヶ月から 12 ヶ月の見通しに基づいています。これら推奨トレードについては、
経済・市場環境の変化に応じて、適宜見直しの対象となります。また、ストップ・ロスが明記されたトレードについては、その水準を超えた時点で推奨の対
象から自動的に外れます。トレード推奨に明記される金利水準や証券のプライスについては、リサーチ・レポートの発行に際してアナリストから提出された
時点の、ブルームバーグ、ロイター、野村のいずれかによる気配値であり、その時点で、実際に取引が可能な水準であるとは限りません。 本資料に記載された証券は米国の 1933 年証券法に基づく登録が行われていない場合があります。係る場合、1933 年証券法に基づく登録が行われる、
あるいは当該登録義務が免除されていない限り、米国内で、または米国人を対象とする購入申込みあるいは売却はできません。準拠法が他の方法を認
めていない限り、いかなる取引もお客様の地域にある野村の関連会社を通じて行う必要があります。 本資料は、NIplc により英国および欧州経済領域内において投資リサーチとして配布することを認められたものです。NIplc は、英国のプルーデンス規制機
構によって認可され、英国の金融行為監督機構とプルーデンス規制機構の規制を受けています。NIplc はロンドン証券取引所会員です。本資料は、英国
の適用される規則の意味する範囲での個人的な推奨を成すものではなく、あるいは個々の投資家の特定の投資目的、財務状況、ニーズを勘案したもの
ではありません。本資料は、英国の適用される規則の目的のために「適格カウンターパーティ」あるいは「専門的顧客」である投資家のみを対象にしたも
ので、したがって、当該目的のために「個人顧客」である者への再配布は認められておりません。本資料は、香港証券先物委員会の監督下にある NIHK
によって、香港での配布が認められたものです。本資料は、オーストラリアで ASIC の監督下にある NAL によってオーストラリアでの配布が認められたもの
です。また、本資料は NSM によってマレーシアでの配布が認められています。シンガポールにおいては、本資料は NSL により配布されました。NSL は、証
券先物法(第 289 条)で定義されるところの認定投資家、専門的投資家もしくは機関投資家ではない者に配布する場合、海外関連会社によって発行され
た証券、先物および為替に関わる本資料の内容について、法律上の責任を負います。シンガポールにて本資料の配布を受けたお客様は本資料から発
生した、もしくは関連する事柄につきましては NSL にお問い合わせください。本資料は米国においては 1933 年証券法のレギュレーション S の条項で禁止
されていない限り、米国登録ブローカー・ディーラーである NSI により配布されます。NSI は 1934 年証券取引所法規則 15a-6 に従い、その内容に対する責
任を負っております。本資料を作成した会社は、野村グループ内の関連会社が、顧客が入手可能な複製を作成することを許可しています。 野村サウジアラビア、NIplc、あるいは他の野村グループ関連会社はサウジアラビア王国(「サウジアラビア」)での(資本市場庁が定めるところの、)「オー
ソライズド・パーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インスティテューションズ」以外の者への本資料の配布、アラブ首長国連邦(「UAE」)におい
ては、(ドバイ金融サービス機構が定めるところの、)「専門的顧客」以外の者への配布、また、カタール国の(カタール金融センター規制機構が定めるとこ
ろの、)「マーケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」以外の者への配布を認めておりません。サウジアラビアおいては、「オーソラ
イズド・パーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インスティテューションズ」以外の者、UAE の「専門的顧客」以外の者、あるいはカタールの「マー
ケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」以外の者を対象に本資料ならびにそのいかなる複製の作成、配信、配布を行うことは直
接・間接を問わず、係る権限を持つ者以外が行うことはできません。本資料を受け取ることは、サウジアラビアに居住しないか、または「オーソライズド・パ
ーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インスティテューションズ」であることを意味し、UAE においては「専門的顧客」、カタールにおいては「マー
ケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」であることの表明であり、この規定の順守に同意することを意味いたします。この規定に従
わないと、サウジアラビア、UAE、あるいはカタールの法律に違反する行為となる場合があります。 カナダ投資家へのお知らせ:本資料は個人的な推奨ではありません。また投資目的、財務状況、あるいは特定の個人または口座の特定のニーズを考慮
したものではありません。本資料はオンタリオ証券委員会の NI 31-103 のセクション 8.25 に基づいてお客様へ提供されています。 台湾上場企業に関するレポートおよび台湾所属アナリスト作成のレポートについて:本資料は参考情報の提供だけを目的としています。お客様ご自身で
投資リスクを独自に評価し、投資判断に単独で責任を負っていただく必要があります。本資料のいかなる部分についても、野村グループから事前に書面
で承認を得ることなく、報道機関あるいはその他の誰であっても複製あるいは引用することを禁じます。「Operational Regulations Governing Securities
Firms Recommending Trades in Securities to Customer」及びまたはその他の台湾の法令・規則に基づき、お客様が本資料を関係者、関係会社およびそ
の他の第三者を含む他者へ提供すること、あるいは本資料を用いて利益相反があるかもしれない活動に従事することを禁じます。NIHK 台湾支店が執行
できない証券または商品に関する情報は、情報の提供だけを目的としたものであり、投資の推奨または勧誘を意図したものではありません。 本資料のいかなる部分についても、野村グループ会社から事前に書面で同意を得ることなく、(i)その形態あるいは方法の如何にかかわらず複製する、あ
るいは(ii)配布することを禁じます。本資料が、電子メール等によって電子的に配布された場合には、情報の傍受、変造、紛失、破壊、あるいは遅延もしく
は不完全な状態での受信、またはウィルスへの感染の可能性があることから、安全あるいは誤りがない旨の保証は致しかねます。従いまして、送信者は
電子的に送信したために発生する可能性のある本資料の内容の誤りあるいは欠落に対する責任を負いません。確認を必要とされる場合には、印刷され
た文書をご請求下さい。

日本で求められるディスクレイマー レポート本文中の格付記号の前に※印のある格付けは、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付け(無登録格付け)です。
無登録格付けについては「無登録格付に関する説明書」https://www.nomura.co.jp/retail/bond/noregistered.html をご参照ください。 当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して 大 1.404%(税込み)(20 万円以下の
場合は、2,808 円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等
の諸経費、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリ
スクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。 国内株式(国内 REIT、国内 ETF、国内 ETN を含む)の売買取引には、約定代金に対し 大 1.404%(税込み)(20 万円以下の場合は 2,808 円(税込み))
の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取
引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。
国内 REIT は運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内 ETF は連動する指数等の変動により損失が生じるおそ
れがあります。 外国株式の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し 大 1.026%
(税込み)(売買代金が 75 万円以下の場合は 大 7,668 円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等
は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取
引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失
が生じるおそれがあります。 信用取引には、売買手数料(約定代金に対し 大 1.404%(税込み)(20 万円以下の場合は 2,808 円(税込み)))、管理費および権利処理手数料をいただ
きます。加えて、買付の場合、買付代金に対する金利を、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をいただきます。委託保証金は、売
買代金の 30%以上(オンライン信用取引の場合、売買代金の 33%以上)で、かつ 30 万円以上の額が必要です。信用取引では、委託保証金の約 3.3 倍ま
で(オンライン信用取引の場合、委託保証金の約 3 倍まで)のお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるお
それがあります。詳しくは、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、等をよくお読みください。 CBの売買取引には、約定代金に対し 大 1.08%(税込み)(4,320 円に満たない場合は 4,320 円(税込み))の売買手数料をいただきます。CBを相対取引
(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、
別途手数料をいただくことがあります。CBは転換もしくは新株予約権の行使対象株式の価格下落や金利変動等によるCB価格の下落により損失が生じ
るおそれがあります。加えて、外貨建てCBは、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。債券の価格は市場の金利水準
の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、
投資元本を割り込むことがあります。加えて、外貨建て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 個人向け国債を募集によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできま
せん。個人向け国債を中途換金する際、原則として次の算式によって算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より
差し引かれます。(変動 10 年:直前 2 回分の各利子(税引前)相当額×0.79685、固定 5 年、固定 3 年: 2 回分の各利子(税引前)相当額×0.79685) 物価連動国債を募集・売出等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入対価のみをいただきます。当該商品の価格は市場の金利水準及
び全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。想定元金額は、全国消費者物価指数の発行時からの変化
率に応じて増減します。利金額は、各利払時の想定元金額に表面利率を乗じて算出します。償還額は、償還時点での想定元金額となりますが、平成 35
年度以降に償還するもの(第 17 回債以降)については、額面金額を下回りません。 投資信託のお申込み(一部の投資信託はご換金)にあたっては、お申込み金額に対して 大 5.4%(税込み)の購入時手数料(換金時手数料)をいただき
ます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して 大 2.0%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信
託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)( 大
5.4%(税込み・年率))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があり
ます。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等によ
り基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容
や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の 大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前
交付書面をよくお読みください。 金利スワップ取引、及びドル円ベーシス・スワップ取引(以下、金利スワップ取引等)にあたっては、所定の支払日における所定の「支払金額」のみお受払
いいただきます。金利スワップ取引等には担保を差入れていただく場合があり、取引額は担保の額を超える場合があります。担保の額は、個別取引によ
り異なりますので、担保の額及び取引の額の担保に対する比率を事前に示すことはできません。金利スワップ取引等は金利、通貨等の金融市場におけ
る相場その他の指標にかかる変動により、損失が生じるおそれがあります。また、上記の金融市場における相場変動により生じる損失が差入れていただ
いた担保の額を上回る場合があります。また追加で担保を差入れていただく必要が生じる場合があります。お客様と当社で締結する金利スワップ取引等
と「支払金利」(又は「受取金利」)以外の条件を同一とする反対取引を行った場合、当該金利スワップ取引等の「支払金利」(又は「受取金利」)と、当該反
対取引の「受取金利」(又は「支払金利」)とには差があります。商品毎にリスクは異なりますので、契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読みく
ださい。 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)取引を当社と相対でお取引いただく場合は手数料をいただきません。CDS 取引を行なうにあたっては、弊社との間で
合意した保証金等を担保として差し入れ又は預託していただく場合があり、取引額は保証金等の額を超える場合があります。保証金等の額は信用度に
応じて相対で決定されるため、当該保証金等の額、及び、取引額の当該保証金等の額に対する比率をあらかじめ表示することはできません。CDS 取引
は参照組織の一部又は全部の信用状況の変化や、あるいは市場金利の変化によって市場価値が変動し、当該保証金等の額を超えて損失が生じるおそ
れがあります。信用事由が発生した場合にスワップの買い手が受取る金額は、信用事由が発生するまでに支払う金額の総額を下回る場合があります。

また、スワップの売り手が信用事由が発生した際に支払う金額は、信用事由が発生するまでに受取った金額の総額を上回る可能性があります。他の条
件が同じ場合に、スワップの売りの場合に受取る金額と買いの場合に支払う金額には差があります。 CDS 取引は、原則として、金融商品取引業者や、
あるいは適格機関投資家等の専門的な知識を有するお客様に限定してお取り扱いしています。 有価証券や金銭のお預かりについては料金をいただきません。証券保管振替機構を通じて他の証券会社へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、
移管する銘柄ごとに 10,800 円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。 野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第 142 号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 Copyright © 2018 Nomura Securities Co., Ltd. All rights reserved.