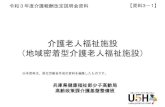2019年度介護報酬改定について ~介護職員の更なる処遇改善~ · また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。
改正介護保険法対応 『指定介護老人福祉施設における介護事...
Transcript of 改正介護保険法対応 『指定介護老人福祉施設における介護事...
-
改正介護保険法対応
『指定介護老人福祉施設における介護事故発生防止等に
向けた指針策定にあたって(全国経営協版)』
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
全国社会福祉施設経営者協議会
-
目 次 1.はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.福祉サービスにおけるリスクマネジメントの意義 ~良質かつ安心・安全なサービス提供に向けた取り組み~・・・・・・・・・・3
3.指定基準改正内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4.リスクマネジメントの内容
リスクマネジメントに関する組織的な取り組み・・・・・・・・7 ~リスクマネジメントの取り組みにあたっての基本~
リスクマネジメントの取り組みを支える仕組み・・・・・・・・9
事故発生時の対応について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
再発防止策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
取り組み全体の関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
5.リスクマネジメント指針の策定(例) ~指定基準を踏まえて基本部分を整理~・・・・・・・・・・・・・・・・・17
-
1.はじめに
平成 18年 4月から改正介護保険法が施行された。 この結果、施設サービス共通の指定基準改正事項として、①事故発生防止の
ための指針の整備、②事故等の報告、分析を通じた改善策の周知徹底のための
体制整備、③事故防止委員会及び従事者への研修を実施するということが新た
に設けられ、事故発生防止等に関するリスクマネジメントの意識付けとその具
体的な対応が制度上に位置付けられた。 社会福祉法人経営においては、制度の変更如何によらず、サービスの質の向
上と経営の信頼性の確保という観点から、現状を好機ととらえ、リスクマネジ
メントにより積極的かつ適正に取り組んでいくことはとても重要である。 本会では、2000 年から福祉施設におけるリスクマネジメントに関する研究を
重ね、これまでにリスクマネジメントのあり方と課題の整理及びリスクマネジ
ャーの機能や役割をまとめてきた。また、リスクマネジメントを推進する中核
的な役割を担う人材育成を目的とした「リスクマネジャー養成講座」を平成 14年度より毎年開催している。 本冊子は、指定介護老人福祉施設を経営する会員法人が今般の改正介護保険
制度において指定基準として新たに設けられた「事故の発生又はその再発を防
止するための措置」を講ずるべく、これまでの本会の研究成果をもとに制度改
正に伴う具体的対応とリスクマネジメントの基本的事項を全国経営協版として
とりまとめたものである。
利用者が安心して安全な生活を送るための取り組みとしてリスクマネジメン
ト体制の構築・充実を図るために活用いただける内容となっている。
-
2.福祉サービスにおけるリスクマネジメントの意義
~良質かつ安心・安全なサービス提供に向けた取り組み~ 福祉サービスにおけるリスクマネジメントの目的・考え方については、以下
のとおりであり、実践する上での基本となる。 〔目的・基本的な考え方〕 ◇ 「利用者の安全を最大の眼目としたサービスの質の向上と利用者
満足度の向上を目指す」活動である
◇ より良いサービスを提供すればサービスの提供の場面における事
故の発生を防ぐことが可能となる ◇ 福祉サービスの質の向上の必要性が高まるなか、利用者の安心や安
全を確保することが福祉サービスの提供にあたっての基本である
ことからも事故防止対策を中心とした福祉サービスにおける危機
管理体制の確立が急務の課題である
-
3.指定基準改正内容について
平成 18 年 4 月からの改正介護保険によって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に、①事故発生防止のための指針の整備、②事故等の報告、
分析を通じた改善策の周知徹底のための体制整備、③事故防止委員会及び従事
者への研修等が盛り込まれた。
「事故発生の防止及び発生時の対応」 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じな
ければならない。
また、上記基準省令に対する解釈通知「指定介護老人福祉施設の人員、施設及び
運営に関する基準について(平成12年老企第43号)」に規定する内容が、以下のよ
うに改正された。
「指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準について(平成12年老企第43
号)」の改正内容
(1)事故発生の防止のための指針(第1項第1号)
「事故発生の防止のための指針」に盛り込むべき項目としては、
① 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方
② 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項
③ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針
④ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそう
になった場合(ヒヤリ・ハット事例)及び現状を放置しておくと介護事故に結び
つく可能性が高いもの(以下「介護事故等」という。)の報告方法等の介護に係
る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
⑤ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針
⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
⑦ その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針
等を想定している。
・ 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の
防止のための指針を整備すること。 ・ 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が
報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備す
ること。 ・ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
-
(2) 事実の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底
(第1項第2号)
報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について、施設
全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰
を目的としたものではないことに留意することが必要である。
具体的には、
① 介護事故等について報告するための様式を整備すること。
② 介護職員その他の従事者は、介護事故等の発生又は発見ごとにその状況、背景等を
記録するとともに、イの様式に従い介護事故等について報告すること。 ③ (3)の事故発生の防止のための委員会において、②により報告された事例を集
計し、分析すること。
④ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の
発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。
⑤ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。
⑥ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。
を想定している。
(3) 事故発生の防止のための委員会(第1項第3号)
当該施設における「事故発生の防止のための委員会」は、介護事故発生の防止及び
再発防止のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種(例えば施設長(管理者)、
事務長、介護支援専門員、医師、看護職員、介護職員、生活相談員)により構成する。
構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の安全対策を担当する
者を決めておくことが必要である。
なお「事故発生防止のための委員会」は、運営委員会など他の委員会と独立して設
置・運営することが必要であり、責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。
また、委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが望
ましい。
(4) 事故発生の防止のための従業者に対する研修(第1項第3号)
介護職員その他の従事者に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、事
故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設におけ
る指針に基づき、安全管理の徹底を行うものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プロ
グラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には
必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。
(5) 損害賠償(第3項)
指定介護老人福祉施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなけ
ればならない。そのため、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有する
ことが望ましい。
-
4.リスクマネジメントの内容
信頼性の高い、良質かつ安心・安全なサービス提供
リスクマネジメント体制の構築
7頁から参照
リスクマネジメントに関する組織的な取り組み
経営者の役割・責任 ⇒ 日常的な組織的な取り組みの促進、体制の点検・見直し、職員の意識を高める姿勢と取り組み
事故発生時の適切・誠実な対応と再発防止に向けた検討 ⇒ 責任の所在と情報伝達経路の明確化、誠実な説明と迅速な対応
事故要因分析・再発防止に向けた取り組みの推進
継続的な質改善
事故予防
◇ リスクアセスメント、リスクへの気づきを高める取り組み、ハードの改善 等
⇒アセスメントシートの活用、KYT トレーニングの実施、マニュアルの策定 等
発生時の適切な対応
◇ 事故発生時の迅速かつ誠実な対応、記録の整備
⇒事故発生時のマニュアルの整備、対応責任と情報伝達経路の明確化 等
再発防止
◇ 事故要因分析と再発防止策の検討
⇒インシデント(ヒヤリハット)レポート・事故報告書等の活用、要因分析手法の
確立、個別支援計画やマニュアルへの留意点の反映 等
9頁から参照
苦情・相談体制の活用
日常的な利用者・家族
とのコミュニケーショ
ン=信頼関係の構築
-
〔リスクマネジメントに関する組織的な取り組み〕
~リスクマネジメントの取り組みにあたっての基本~
各事業所において、リスクマネジメントに関する取り組みを進めるにあたっ
て、下記のような基本的な認識が重要である。
そしてなにより、法人・事業所全体の問題としてサービスの質の向上に向け
たリスクマネジメントに取り組むためには、経営トップないし管理者の責任と
取り組みに向けた姿勢が何より不可欠である。
法人・事業所のトップがリスクマネジメントに対する方針を明確にし、組織
として体制の整備に努める必要がある。
体制の整備ないし構築を進める上の基本的な考え方として以下のポイントが
ある。
○組織風土の改善及び組織づくり
職員一人ひとりが「安全」に関して認識し、何かあればいつでも気軽に言い
合える風通しの良い組織風土が必要。経営者はその組織風土醸成に向けて意識
的に取り組む必要がある。
また、リスクマネジメントの取り組みには、すべての職員の参画が求められ、
それには職員と経営者との連携が重要になる。
さらに、事故の再発防止、適切な対応の観点から「事故やリスクに関する情
報」と「利用者情報」を収集・管理し、組織内で情報を共有化していくことは
必要不可欠である。また、そのための情報共有化の仕組みを構築した上で、今
後の取り組みに活用していく。事故要因分析や再発防止策を検討しマニュアル
等に反映したとしても、その内容が直接サービス提供にあたる職員に周知・徹
底がなされなければ、継続的な事故予防への取り組みにはつながらない。
なお、継続的なサービスの質の向上に取り組むため、利用者の笑顔と満足を
提供するという目的に照らし、日頃から職員のリスクに対しする「気づき」が
重要となる。いくら体制が整備されていたとしても、個々のサービス提供者が、
危険や改善点に気づかなくては、事故予防や再発防止策に結びつかない。
その意味からは、職員に対する教育体制の強化によるリスクへの気づきを高
める取り組みが、リスクマネジメント体制を下支えする重要な要因となるので
ある。
-
○利用者像の的確な把握(アセスメント、個別援助計画)
利用者一人ひとりに対して、適切かつ安全なサービスを提供するにはそれに
基づく個別援助計画作成が重要となる。
利用者の身体・精神状況から、その特性を捉えることで固有のリスクを把握
するためのアセスメントを実施し、どのような事故発生が想定されるのかを事
前に把握しておく必要がある。つまり、事故予防の観点からのリスクアセスメ
ントを実施しその結果にもとづいて、個別支援計画やマニュアルへ個別のリス
ク要因を反映し適切なサービス提供に結びつけることが重要になる。
○サービスの標準化
提供するサービスの質にばらつきが出ないよう、サービス提供プロセスを業
務フローなどで明確にし、サービスの標準化を図り、その質を一定レベル維持
することは重要である。すなわちどの職員が実施しても同一のサービスが提供
できるように業務や作業の標準化を図ることで、サービスの質の一定の確保や
リスクの見落とし防止を高める、「リスクコントロール」の可能性が強化できる。
また、サービスを標準化することは、事故要因分析と再発防止策の観点から、
サービス提供プロセスのどこに問題があったのかを明確にすることが可能とな
る。そして、その問題箇所の顕在化により、その後の改善につなげるという一
連のシステムが構築される。
なお、サービスの標準化=サービスの画一化ではなく、基本となる標準化さ
れた定型的なサービスをより効率的かつ安全に提供し、継続的な見直しと改善
を図っていくことが、利用者の個別性に配慮した個別支援をより充実させると
いう認識が重要である。
○利用者・家族などとのコミュニケーション
契約時における利用者・家族等への十分な情報提供と同意は、介護保険事業
等における指定基準上でも明確に義務づけられている。これは、事業所側から
の一方的な説明で終わらすのではなく、双方向のコミュニケーションの場とし
てとらえるべきである。同様に利用者・家族等からの苦情についても、単なる
「苦情」として処理するのではなく、サービスの質のための貴重な情報源とし
て業務改善につなげていくことが重要である。
そして何より、利用者・家族との信頼関係の構築がサービスの質の重要な要
素であり、この観点からの取り組みが不可欠である。
-
〔リスクマネジメントの取り組みを支える仕組み〕
●リスクマネジメントのPDCAサイクル
①リスクマネジメント基本方針の策定
・リスクマネジメントに関する基本方針を定めるとともに、リスクマネジメ
ントに関する経営者の役割、責任及び権限を文書によって定め、関連する
部門及び部署に伝達する。
②リスクマネジメントの計画策定
・発生する可能性のあるリスクを抽出し、具体的な対応方法
を策定
P(PLAN)
③リスクマネジメントの実施
・立案した計画に沿ってリスクマネジメントを実施
④リスクマネジメントの評価
・ リスクマネジメントやそのシステムが目的やねらいに対
してうまく機能しているかどうかの評価
⑤リスクマネジメントの評価結果を踏まえた改善
・④の評価結果を受けて、必要に応じた改善策の構築
⑥管理者による見直し
・管理者がシステムの見直しを実施
●マニュアル等各種ツールの整備・開発
○サービスと業務の標準化に向け、必要となる各種ツールを開発し、その運
用(メンテナンス含む)を図る
○記録の様式と記載方法は統一化する
○個人情報保護に配慮する
D(DO)
C(CHECK)
C(CHECK)
A(ACTION)
-
○記録保管等に関するルールを明確化する
<必要になるツールの種類と内容等>
種 類 内 容 等
◆事故報告書
○発生した事故を適切に記録し、その後の対応に活用する。
<活用事例>
・職員教育や研修における資料
・訴訟対応などを含めたトラブル発生後の記録資料
<記載上の留意点>
・記載内容としては、「日時」「場所」「状況」「事故後の対応」「想
定される原因」等の事故発生時の事実関係をはじめ、併せて「再
発防止策」「利用者側の反応」などがある。
◆ヒヤリハット報告書
○現状を放置しておくと事故に結びつく可能性が高い事項を記録
し、その要因分析等による改善策を講じることを目的とする。
<留意点>
・事故まで至らないケースを扱うため、職員によって「ヒヤリ」「ハ
ット」であるかどうかに気づかないことがないよう、具体事例
や気づきのポイントを含め、該当するケースの基準を明確にし
ておく。
・「ヒヤリ」「ハット」にも危険度に違いがあるので、その区別を
示す指標を設けておくことも望ましい。
◆事故防止・対策におけ
る業務マニュアル
○リスクマネジメントの観点から、事故防止、事故対応について
の業務マニュアルを整備しておくことにより、全職員が「安全」
に関する意識付けと情報の共通化を図る。
○マニュアルの有無は、リスクマネジメントに向けた取り組みを
十分に行っていたかどうかの指標にもなる。
<留意点>
・マニュアルは、リスクマネジャーを中心に職員レベルで作成す
ることがポイント
・作成したマニュアルは定期的に見直し、必要に応じて改訂する。
-
図1 ヒヤリ・ハットレポート様式例(特別養護老人ホームの例)
出典:全国経営協編「全社協ブックレット1 福祉施設におけるリスクマネジャーの実践」31頁、全社協、平成 17年 4月
●研修・教育の取り組み
○サービスと業務の標準化に基づいたリスクマネジメントが実施されるよう、
定期的に、体系的に教育・研修を実施する
○「事故報告書」、「ヒヤリ・ハット報告書」の内容を職員全員に周知し、職員
間で情報の共有化を図る
○経験年数によるリスクマネジメントに関する習得度を考慮したキャリア別研
修や新人職員等を対象にしたフォローアップ研修などを実施する
<リスクマネジメント体制を支える職場研修> ⅰ「事故防止基本視点チェックリスト」の活用 以下に事故防止のための基本視点チェックリストを示しているが、本来であれば、(1)の業務
の標準化に加えて、サービスの提供時に必ず行わなければならない業務の確認を手順書どおりに実
施されているかを定期的にチェックする機会を設け、周知徹底が図れるようトレーニングを行うこ
とが必要となる。(業務チェックリストの活用)
施設長 課長 主任 担当者 ◆ヒヤリ・ハットレポート◆
報告日 年 月 日
発生日 年 月 日 時間 □AM □PM 時 分頃 報告者 利用者 氏名
年齢 歳 性別 □男 □女
利用者の身体状況 発見者 職 種 □介護職員 □生活相談員
□看護師 □その他
ヒヤリ・ハットの場面 □移動(移動中) □食事介護中 □入浴介護中 □入浴介護中 □その他 ( ) ヒヤリ・ハットの内容・状況 利用者の状況 事故防止対策
-
(例) 確認をしていますか? 車椅子 □ タイヤはパンクしていませんか? 空気量は適切ですか? □ 車椅子のストッパーはしっかりかかっていますか? □ 車椅子操作の介助は、手や衣服が危険な位置にないか確認していますか? □ 利用者の座る位置は適切な位置になっていますか? □ クッションなどはずれていませんか? など 確認をしていますか? 配薬 □ 薬を置きっぱなしにしていませんか? □ 配薬前に手順書に添って確認をしていますか?
□ 配薬時、名前と顔の確認をおこなっていますか? □ 服薬するまで見守っていますか? □ 利用者の座席周辺に飲み残しの薬はありませんか? など
ⅱ観察能力における研修 「専門職」の視点による観察能力を高め、利用者の心身の状態を把握する。
ⅲ危険性の認知能力(リスクの予見、回避)の研修 利用者にとって意外なものが障害となる場合が多い。生活の場において安全、快適に暮らせる
ためには、職員の気配りや気づき、要因を除去する行動が必要となってくる。 ○ベッドの高さは利用者にあっているか ○床頭台や物品は整理整頓されているか ○通路に障害物はないか ○作業中に利用者から離れず、安全確保ができているか このように、様々な場面において、危険を予知し、回避するためのトレーニングが必要となって
くる。その一つとして、KYT(危険予知訓練)がある。 ◇参考
『福祉施設における危険予知訓練(KYT)かんたんガイド』 著者/古澤章良・遠山敏・佐藤彰俊・砂川直樹 発行/筒井書房 著書によると、『職員が日々の業務のなかで「何かおかしいな」、「危ないかもしれない」といった
危険を予知する能力を高める取り組みです。職員一人ひとりがこのような危険に対する感受性を高め
ることができれば、事故を未然に防ぐことが大いに期待できます』と目的が示されている。
出典:「社会福祉法人・施設におけるリスクマネジメント実践 ~そのツールと手法~ Ver.Ⅱ」27 頁~28 頁、全国青年経営者会
-
●リスクマネジメントの推進に中核的な役割を果たす担当者(リスクマネジャー)
や専門委員会の設置
○リスクマネジメントに関する担当者とともに、そのすべての業務を統括す
る役割の担当責任者(以下、リスクマネジャー)を設置する
○リスクマネジャーは、組織全体として適正なリスクマネジメントに取り組
むための継続的改善を行う。
○リスクマネジャーをリーダーとし、リスクマネジメントに関する専門委
員会を設置する
-
〔事故発生時の対応について〕
①確立された経路に沿って速やかで正確な情報伝達
○組織内の責任及び権限の明確化(決定、指示命令など)した情報伝達体
制に従って対処
○責任領域と責任者の選任、決定、指示命令の明確化は重要
情報伝達経路
事 故 分 析
受 傷 な し 受 傷 あ り
看 護 師 に 報 告
リ ー ダ ー を 中 心 に 対 応 策 を 決 定 し 日 誌 、 申 し送 り ノ ー ト に 記 載 し 、 申 し 送 り 時 に 申 し 送 る 。
対 応 策 検 討
上 位 権 者 及 び 経 営 層 に 報 告 を 行 う 。
報 告 を 受 け R M が 指 示 を 出 す 。
領 域 に 責 任 を 持 つ 管 理 者 (例 え ば 部 署 長 )に報 告 を 行 う 。 不 在 の と き も 想 定 し て お く 。
リ ー ダ ー に 報 告受 診 指 示
同 行
入 院 な し 入 院 あ り
相 談 員 に 報 告
病 院 受 診
R M(リ ス ク マ ネ ジ ャ ー )
当 事 者 若 し くは 発 見 者 が 事 故 報 告 書 に 記 載
事 故 報 告 書 提 出
ご 家 族
事 故 委 員 会
事 故 発 生
結果報告
指示
★ 1
★ 2
★ 3
★ 4
★1 事故が発生した場合には、まずは適切な対応が必要となります。受傷した場合は判断できる者の
迅速な対応及び指示が必要となり、また一方では、どのような状況が起きるかを想定した日頃か
らの救命における準備と職員訓練が重要。 ★2・★3
組織において、生じた事故に対して適切な対応を要することと、再発防止のための事故の原因を
除去する処置をとらなくてはならないことから、その領域に責任のもつ管理者→上位権者→経営
層、及びRM(リスクマネジャー)に報告が必要となる。 ★4 管理者からの情報及び指示を受け、家族への報告を行う場合には、日頃からの関係を築いている
職に就いている者が担当するのが適当。
-
出典:「社会福祉法人・施設におけるリスクマネジメント実践 ~そのツールと手法~ Ver.Ⅱ」30 頁、全国青年経営者会
②事故への処置・対応 ○応急手当、病院搬送、捜索 等
○緊急時の病院へ搬送など、医療機関へつなげるまでに行う処置
○事故の正確な把握
○事故に関する報告内容と方法(①施設内、②利用者家族)
事故に対しての処置及び結果
RM
経営層による見直し
・内容確認・原因の特定・分析
事故報告書
部署長
報告
指示・命令
報告
指示・命令
6ヶ月ごとに分析結果を報告する。(時間・場所・種別等)
1.是正処置の計画(処置の必要性の場合)2.是正処置の計画の結果 → 承認3.是正処置後の活動、実践についての効果と確認 → 承認
事故委員会
本人要因
職員要因
環境要因
※1
※2
※3
★1 ★2
★3
★1 事故報告書より ⇒ ・内容確認
・原因の特定、分析を行い 是正処置計画を立案、PDCA管理体制に基づく対応を実施しなくてはなりません。
★2 全ての不適合において委員会にて分析を行い、その結果を定められた期間ごとに報告する
ことが必要となります。 ★3 組織における全ての不適合においては、経営層に文書報告(情報伝達)を要し、経営層か
らの指示を仰ぐ必要性があります。 <是正処置計画、是正処置の計画の結果、是正処置後活動の効果の確認>
是正処置とは・・・再発防止のため、不適合の原因となるものを取り除く処置 不適合とは・・・適した状態ではないこと (例)手順書に示されたとおりに実践されていない 立っていなくてはならないものが倒れている
定期的に点検しなくてはならないものがなされていない
出典:「社会福祉法人・施設におけるリスクマネジメント実践 ~そのツールと手法~ Ver.Ⅱ」32 頁、全国青年経営者会
-
〔再発防止策〕
① 事故要因の分析と改善策への反映(事故報告書、ヒヤリ・ハット事例の収
集と活用)
② 個別支援計画・マニュアル等の見直し
③ リスクマネジメントに関する研修・教育
〔取り組み全体の関連事項〕
① 利用者の声を積極的に取り入れる
○ 苦情・相談体制を活用し、利用者の声をサービスの改善に活かす
○ 日常的に利用者・家族とのコミュニケーションに努める
② 利用者の心身の状態を把握する
○ リスクアセスメントなどを実施し、利用者の心身の状況把握に努める
③ 十分な情報提供と利用者の理解
○ リスクマネジメントの基本指針等、すべての情報が利用者・家族に提供さ
れ、その内容について正しく理解されるための努力を行う
○上記のための閲覧指針等を整備する
-
5.リスクマネジメント指針の策定(例)
~指定基準を踏まえて基本部分を整理~
各事業所によるリスクマネジメント指針の策定にあたり、今回改正された指
定基準(P.4 参照)を踏まえて基本部分を整理すると以下のようになる。
なお、重要なのは、以下の基本部分を踏まえつつ、各法人が自らの経営方針
に基づいたリスクマネジメント指針を策定するという観点である。また、実際
の指針策定の際には、個別のサービスマニュアル等、指針を補完する各種関連
ツールの作成等も含め、リスクマネジメントを組織全体の取り組みとして実行
可能なものにしておく必要がある。
リスクマネジメント指針(基本部分の例示)
1.施設における介護事故の防止に関する基本的考え方
〔基本方針の策定〕
◇ リスクマネジメントを、利用者の安全を最大の眼目としたサービスの質の向上と利用者満足度の
向上をめざす活動としてとらえる。言い換えれば、より良いサービスを提供すればサービスの提
供の場面における事故等の発生を防ぐことができる。
◇ 利用者の人権を尊重する意識の徹底をめざし、法人のリスクマネジメントに関する体制の整備を
行う。
◇ リスクマネジメントの基本方針の内容については、管理責任者及び職員に周知、理解させる。
2.介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項
〔管理者の関与と責任の明確化〕
◇ 上記リスクマネジメントの基本方針に沿って、リスクマネジメントに取り組む体制と責任を明確
にする。
〔原因分析・課題抽出・仕組みづくり〕
◇ リスクマネジメントに関する委員会などを設置し、対策や情報の共有を図るとともに、事故予防
対策を講じるための仕組み・システムをつくる。
◇ リスクマネジメント担当者及びリスクマネジャーを配置し、その役割と権限を明確化する。
〔現場の創意工夫を活かす〕
◇ 業務改善提案等、職員の悩み・工夫をくみ上げる仕組みを構築するとともに、自らの創意工夫に
よりサービスの質を改善していくという意識を高揚させる。
-
〔リスク情報を出しやすい環境づくり〕
◇ 現場の職員がリスク情報を出しやすい環境づくりをしたうえで、リスク分析を行う組織づくりを
行う。
・ 事故や安全に関する情報収集
・ 業務改善のための情報分析
・ 事故防止対策方針の決定
・ 対策の実践
・ 実践の検証
・ 対策の標準化
といったサイクルを繰り返していくことができる組織づくりが必要
〔危険に気づくこと〕
◇ 現在のサービスのなかに内包されているリスクに気づき、その内容を把握するためのシステムの
構築
〔ヒューマンエラーへの対策〕
◇ ヒューマンエラーは避けがたいものであることを前提に、職員同士や利用者とのコミュニケーシ
ョンを重視する。
3.介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針
〔研修・教育への取り組み〕
◇ 安全で安心なサービス提供を行うにあたって必要になる職員の業務範囲と質を明確化する
◇ リスクへの気づきを高める職員教育を実施する。
◇ 事故発生時の対応に関するシミュレーション、採用時研修やフォローアップ研修など、事故対
応等に関する技術向上の研修を実施する。
4.施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになっ
た場合(ヒヤリ・ハット事例)及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が
高いもの(以下「介護事故等」という。)の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的
とした改善のための方策に関する基本方針
〔事故報告書〕
◇ 発生した事故については、統一の様式で「事故発生報告書」を作成し、一元的に把握する。
◇ 内容は、事故の日時、場所、状況、事故後にとった処置、考えられる原因のほか、検討した再発
防止策や利用者の反応なども記載する。
〔ヒヤリ・ハット事例〕
◇発生した事故だけではなく、利用者の障害に至らない「ヒヤリ」としたり、「ハッ」とした体験(ヒ
15
-
ヤリ・ハット事例)をレポートとして報告し、分析することによって安全対策を検討する。 ヤリ・ハット事例)をレポートとして報告し、分析することによって安全対策を検討する。
◇上記内容には、発生した場面など、事実確認・原因の特定及び分析を行うための情報を盛り込む。 ◇上記内容には、発生した場面など、事実確認・原因の特定及び分析を行うための情報を盛り込む。
(記録の際の留意点) (記録の際の留意点)
◇個人情報保護への取り組みや記録の保管等に関するルールを定める。 ◇個人情報保護への取り組みや記録の保管等に関するルールを定める。
◇記録様式については、定期的に点検・見直しを行い改善に努める。 ◇記録様式については、定期的に点検・見直しを行い改善に努める。
〔事故要因の分析〕 〔事故要因の分析〕
◇ 事故報告書やヒヤリ・ハット報告書については、ソフト面、ハード面、環境面、人的面などから、
要因分析を行い、再発防止策に関する方法等を定める。
◇ 事故報告書やヒヤリ・ハット報告書については、ソフト面、ハード面、環境面、人的面などから、
要因分析を行い、再発防止策に関する方法等を定める。
5.介護事故等発生時の対応に関する基本方針 5.介護事故等発生時の対応に関する基本方針
〔マニュアルの作成〕 〔マニュアルの作成〕
◇ 事故発生時、迅速な報告及び誠実な対応を行うためのマニュアル等を作成し、情報の共有化を図
る。
◇ 事故発生時、迅速な報告及び誠実な対応を行うためのマニュアル等を作成し、情報の共有化を図
る。
◇ 危機管理マニュアルのようなリスク管理だけのものではなく、「食事介助マニュアル」「入浴介助
マニュアル」などの個別のサービスマニュアルに安全対策の視点を盛り込む。
◇ 危機管理マニュアルのようなリスク管理だけのものではなく、「食事介助マニュアル」「入浴介助
マニュアル」などの個別のサービスマニュアルに安全対策の視点を盛り込む。
◇ マニュアルの作成には、リスクマネジャーを中心に、個々の職員が認識しているリスクを洗い出
して、職員レベルの作業を行う。
◇ マニュアルの作成には、リスクマネジャーを中心に、個々の職員が認識しているリスクを洗い出
して、職員レベルの作業を行う。
◇ 定期的な見直し改善を行う。 ◇ 定期的な見直し改善を行う。
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
〔利用者等の理解に向けて〕 〔利用者等の理解に向けて〕
◇ 法人が策定しているリスクマネジメントの各種基本指針を利用者・家族等に開示する。 ◇ 法人が策定しているリスクマネジメントの各種基本指針を利用者・家族等に開示する。
◇ その閲覧のための基本指針を策定する。 ◇ その閲覧のための基本指針を策定する。
◇ 本人要因におけるリスクに関する説明と同意などを含め、利用者・家族等との信頼関係の構築に
向けた努力を行う。
◇ 本人要因におけるリスクに関する説明と同意などを含め、利用者・家族等との信頼関係の構築に
向けた努力を行う。
7.その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 7.その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針
◇リスクの発見・確認のための「予防措置」を講じる。 ◇リスクの発見・確認のための「予防措置」を講じる。
◇事故要因分析と再発防止策の検討を積極的に行う。 ◇事故要因分析と再発防止策の検討を積極的に行う。
◇苦情・相談体制を活用し、利用者の声をサービスの改善に活かす。 ◇苦情・相談体制を活用し、利用者の声をサービスの改善に活かす。
-
〔参考文献〕
○ 全国経営協編「全社協ブックレット1 福祉施設におけるリスクマネジャーの実践」 全社協、平成 17年 4月 ○ 「社会福祉法人・施設におけるリスクマネジメント実践 ~そのツールと手法~ Ver.Ⅱ」
全国青年経営者会、平成 18 年 3 月
○「社会福祉法人 福祉施設におけるリスクマネジメントの基本的な視点」 全国経営協、平成 14 年 3 月
○ 「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」
厚生労働省 福祉サービスにおける危機管理に関する検討会、平成 14年 3月