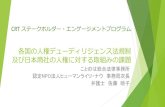民法記述式解法テクニック講座 - OHARA...- 1 - 111 1 出題実績 民法 問題45...
Transcript of 民法記述式解法テクニック講座 - OHARA...- 1 - 111 1 出題実績 民法 問題45...

資格の大原 行政書士講座
民法記述式解法テクニック講座
行政書士試験は、択一式のみで合格点を突破することは難しく、記述式でもしっかりと
得点をしていただく必要があります。そこで、民法総則・物権・債権につきまして問題演
習をしながら、基本的な解き方をマスターしていただきます。
この機会に記述式の得点力アップを図りましょう。


目次
1. 出題実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1
2. 民法総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 2
3. 民法物権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 8
4. 民法債権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
5. その他(参考)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P24

- 1 -
1111 出題実績
◆民法
問題 45 問題 46
H18 債権各論/売買/手付解除 担保物権/抵当権/物上代位
H19 債権各論/不法行為/正当防衛 債権総論/債務不履行/金銭債務の特則
H20 債権各論/賃貸借/信頼関係の法理 債権総論/債権譲渡/債務者に対する対抗要件
H21 債権総論/保証/保証人の求償 物権総論/不動産物権変動/民法 177 条の第三者
H22 債権総論/代位弁済/求償権 債権総論/相殺/509 条の趣旨
H23 担保物権/抵当権/抵当権の消滅事由 総則/代理/表見代理
債権各論/不法行為/使用者責任
H24 債権総論/保証/検索の抗弁権 相続/遺留分/遺留分減殺請求
H25 総則/代理/無権代理 物権総論/動産物権変動/即時取得の特則

- 2 -
2222 民法総則
問題1 Aは、Bから、よい絵画があれば買い受けたい旨相談を受けていた。以前より
Cから有名画家X作の油絵を所有しているが、売却したいと思っている旨を聞か
されていたAは、当該油絵が真作に間違いないものかどうかを確かめたところ、
Cが真作であることを保証する言動を示したので、これを信じて当該油絵を時価
相当額で買い受けて代金を支払い、Bに対して同様の保証をしたうえで当該油絵
を転売して代金を受け取った。しかし、当該油絵が贋作であることが判明したた
め、Bは、Aとの売買契約は要素の錯誤があるから無効であるとして代金の返還
を請求するとともに、Aの錯誤を理由にA・C間の売買契約の無効を主張し、A
のCに対する代金返還請求権を代位行使しようとしている。BのA・C間の売買
契約の無効の主張が認められるには、どのような要件を満たす必要があるか。40
字程度で記述しなさい。なお、A、Bいずれにも重大な過失はなく、それぞれ要
素の錯誤による無効を主張して自己の代金返還請求権を行使する要件は満たして
いるものとする。
(下書用)
10 15

- 3 -
問題1 正解例
BがAに対する債権を保全する必要があり、Aが要素の錯誤を認めていなければならな
い。(41 字)
無効は、原則としていつでも誰でも主張することができるが、錯誤(民法 95 条)によ
る無効を主張することができるのは、表意者保護の趣旨から、表意者に限られる。
しかし、第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がそ
の意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは意思表示
の無効を主張する意思がなくても、第三者は、当該意思表示の無効を主張して、その結果
生ずる表意者の債権を代位行使することが許される(最判昭和 45.3.26)。
よって、本問の場合、第三者たる債権者Bが、表意者Aの錯誤を理由として、A・C間
の売買契約の無効を主張するためには、「BがAに対する債権を保全する必要があること」
「Aが要素の錯誤を認めていること」を満たす必要がある。
ここがポイント! 意思表示
・平成 25 年に択一式で出題されたが、記述式の出題実績はない。
・事例形式で原則・例外を把握しているかを問う出題や、判例の知識を問う出題が予想
される。
・94 条2項の第三者は判例が多いため、択一式対策としても、しっかりと復習しておき
たい。

- 4 -
問題2 Aは、Bに対し、Cの代理人であると偽り、Bとの間でCを売主とする売買契
約(以下、「本件契約」という。)を締結した。ところが、CはAの存在を知らな
かったが、このたびBがA・B間で締結された本件契約に基づいてCに対して履
行を求めてきたので、Cは、Bからその経緯を聞き、はじめてAの存在を知るに
至った。他方、Bは、本件契約の締結時に、AをCの代理人であると信じ、また、
そのように信じたことについて過失はなかった。Bは、本件契約を取り消さずに、
本件契約に基づいて、Aに対して何らかの請求をしようと考えている。このよう
な状況で、AがCの代理人であることを証明することができないときに、Bは、
Aに対して、どのような要件の下で(どのようなことがなかったときにおいて)、
どのような請求をすることができるか。「Bは、Aに対して、」に続けて、下線部
について、40 字程度で記述しなさい(「Bは、Aに対して、」は、40 字程度の字
数には入らない)。(平成 25 年 問題 45)
(下書用)
Bは、Aに対して、
10 15

- 5 -
問題2 正解例
AがCの追認を得ることができなかったときは、履行又は損害賠償の請求をすることが
できる。(43 字)
Cの追認がなく、Aが制限行為能力者でなかったときは、履行又は損害賠償を請求でき
る。(41 字)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本
人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又
は損害賠償の責任を負う(民法 117条1項)。
前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知
っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき(相手方が悪意又は善意有過失の
とき)、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用し
ない(民法 117条2項)。
ここがポイント! 代理
・記述式で平成 23 年、25 年に出題されている。
・無権代理や表見代理については、択一式対策としてしっかり学習しておきたい。
・条文だけでなく、判例の学習も必要である。

- 6 -
問題3 以下の(相談)に対して、〔 〕の中に、適切な文章を40字程度で記
述して補い、(回答)を完成させなさい。
(相談)「私の友人が今年の3月1日に亡くなったのですが、友人の子X(15歳)には他
に身寄りがなく、5月1日に私がXの未成年後見人として選任されました。Xが
Yに対する貸金債権を相続していたことがわかったため、私は、Xのために6月
1日にYに対して弁済を求めました。しかし、Yは、その債権の弁済期は 10 年
前の3月 31 日であり、すでに消滅時効期間が満了していると主張して、弁済を
拒んでいます。私は、XのためにYに対して弁済を求めることができますか。」
(回答)「民法上、債権は、原則として、10 年間行使しないときは、時効により消滅しま
す。でも例えば、時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者又は成年被後見
人に法定代理人がないときは、〔 〕から6か月を経過するまでの間
は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は完成しません。これは、『時
効の停止』と呼ばれる制度で、時効を中断するのが困難な一定の事由がある場合
に、時効の完成を一定の期間猶予するものです。よって、当該期間を経過してい
ないのであれば、まだ時効は完成しておらず、あなたは、XのためにYに対して
弁済を求めることができると思われます。」
(下書用)
10 15

- 7 -
問題3 正解例
その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職し
た時(40字)
債権は、10 年間行使しないときは、消滅する(民法 167条1項)。
時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がない
ときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就
職した時から6か月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時
効は、完成しない(民法 158条1項)。
本問の〔 〕の中には、「時効の停止」の制度により時効の完成が猶予され
る期間について記述するのが適切である。よって、民法 158 条1項に基づいて、「その未
成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時」とい
う語句を入れることになる。
ここがポイント! 時効
・択一式で頻出の論点のため、今後は記述式の対策も必要である。
・取得時効の成立要件や時効の中断については確実におさえておきたい。
・条文だけでなく、判例の学習も必要である。

- 8 -
3333 民法物権
問題4 Aは、Bに貸している絵画をXに売り渡したが、Bは、もうしばらく貸してお
いてほしいと希望した。そこで、AはBに対して、以後はXのためにその絵画を
保管することを命じ、これをXが承諾した。しかし実は、その絵画はAがYから
預かっていたものであり、BはYからの返還請求を受けて、その絵画を引き渡し
た。この場合、A・X間の引渡しの方法は、民法上、何と呼ばれるか。また、X
は、Yから絵画を取り戻すために、Yに対して、どのような権利に基づき、いか
なる請求をすればよいか。40字程度で記述しなさい。なお、A・X間の契約当時、
Xは、平穏にかつ公然と絵画の占有を始めたものとし、Aがその絵画の所有者で
はないことについてXは善意であり、かつ、過失がなかったものとする。
(下書用)
10 15

- 9 -
問題4 正解例
指図による占有移転と呼ばれ、Xは、Yに対して、所有権に基づき返還請求をする。
(38字)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のため
にその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占
有権を取得する(民法 184 条)。
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、
過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(民法 192 条)。
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の
賠償を請求することができる(民法 200 条1項)。
まず、本問の事案では、本人Aが代理人Bに対して以後第三者Xのために絵画を占有す
ることを命じ、Xがこれを承諾しており、A・X間の引渡しの方法は、「指図による占有
移転」と呼ばれる。
次に、Xが絵画を取り戻す手段としては、①占有訴権(占有回収の訴え)、②物権的請
求権(物権的返還請求権)が考えられる。
①の占有回収の訴えを提起するには、「その占有を奪われた」こと(侵奪)が必要であ
るが、本問の事案では、侵奪があったとはいえない。
②の物権的請求権については、指図による占有移転の方法による即時取得が認められる
から(最判昭和 57.9.7)、Xは所有権を取得し、「所有権」に基づき「返還請求」をする
ことができる。
ここがポイント! 動産物権変動
・平成 25 年に「即時取得」が出題されたが、平成 18年以降占有訴権や物権的請求権の
出題実績はない。
・事例形式での出題が予想される。
・どのようなときにどのような請求ができるか。要件と請求内容をしっかりと確認して
おきたい。

- 10 -
問題5 Aの指輪が、Bによって盗まれ、Bから、事情を知らない宝石店Cに売却された。
Dは、宝石店Cからその指輪を 50万円で購入してその引渡しを受けたが、Dもま
たそのような事情について善意であり、かつ無過失であった。盗難の時から1年
6か月後、Aは、盗まれた指輪がDのもとにあることを知り、同指輪をDから取
り戻したいと思っている。この場合、Aは、Dに対し指輪の返還を請求すること
ができるか否かについて、必要な、または関係する要件に言及して、40 字程度で
記述しなさい。(平成 25 年 問題 46)
(下書用)
10 15

- 11 -
問題5 正解例
Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価を弁償して、Dに対し指輪の返還を請求
できる。(43 字)
Aは、6カ月以内にDに50万円を支払って、所有権に基づき指輪の返還を請求するこ
とができる。(45 字)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、
過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(民法 192 条)。
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗
難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(民法
193 条)。
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物
を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った
代価を弁償しなければ、その物を回復することができない(民法 194 条)。
ここがポイント! 即時取得
・成立要件をしっかりと確認しておきたい。
・また、今回のように特則が問われることもあるため、原則・例外はあわせて覚えてお
く必要がある。

- 12 -
問題6 Aは、Bに金銭を貸し付けたが、その際、B所有の甲建物にAの抵当権が設定さ
れて、その旨の登記がされた。その後、Bは、知人のCに、低廉な賃料で甲建物を
賃貸する契約を締結した。当該賃貸借契約に抵当権の実行としての競売手続を妨害
する目的が認められ、Cの占有により甲建物の買受希望者が減少し、売却価額が下
落するおそれがあり、かつ、今後Bが抵当権に対する侵害が生じないように甲建物
を適切に維持管理することが期待できない場合、Aは、Cを相手にして、どのよう
な権利を行使し、また、この権利を行使するにあたり、どのような内容の請求をす
ることができるか。「Aは、Cを相手にして、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
なお、「Aは、Cを相手にして、」は、字数に算入しない。
(下書用)
Aは、Cを相手にして、
10 15

- 13 -
問題6 正解例
抵当権に基づく妨害排除請求権を行使し、直接自己への甲建物の明渡しを求めることが
できる。(43 字)
① 抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有す
る者についても、その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的
が認められ、その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先
弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、当該占有者に対
し、抵当権に基づく妨害排除請求として、上記状態の排除を求めることができる(最判
平成 17.3.10)。
② 抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり、抵当不動産の所有者において抵当権
に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない
場合には、抵当権者は、占有者に対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを求めること
ができる(同判例)。
次の要件を満たすときは、抵当権に基づく妨害排除請求により、占有権原を有する占有
者を排除することができる。
① 占有権原の設定に競売手続を妨害する目的が認められるとき。
② 抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるよ
うな状態があるとき。
また、抵当不動産の所有者に抵当権侵害が生じないように適切に維持管理することを期
待できない場合、抵当権者は、占有者に対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを求める
ことができる。
ここがポイント! 抵当権
・平成 18年に「物上代位」、平成 23 年に「抵当権の消滅事由」が出題されている。
・今後は、法定地上権、抵当権侵害等での出題が予想される。
・保証等と関連しての出題も可能なため、しっかりと対策をしておきたい。

- 14 -
4444 民法債権
問題7 次の【事例】において、Xは、Yに対して、どのような権利について、どのよう
な契約に基づき、どのような請求をすることができるか。40 字程度で記述しなさ
い。
【事例】
A(会社)は、B(銀行)より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、
X(信用保証協会)との間でBに対する信用保証委託契約を締結し、Xは、同契約
に基づき、AのBに対する債務につき信用保証をした。Xは、それと同時に、Y
との間で、Aが信用保証委託契約に基づきXに対して負担する求償債務について
Yが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。AがBに対する上記借入債務の
弁済を怠り、期限の利益を失ったので、Xは、Bに対して代位弁済をした。(平成
21年 問題45)
(下書用)
10 15

- 15 -
問題7 正解例
Aに対する求償債権について、連帯保証契約に基づき、保証債務の履行を請求すること
ができる。(44 字)
Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づき、求償債務の弁済を請求することが
できる。(43 字)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済
をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の
財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対
して求償権を有する(民法 459 条1項)。
本問の場合、保証人Xは、主たる債務者A(会社)に対して求償権を有する。よって、
「どのような権利について」は、「Aに対する求償債権(求償権)について」となる。
また、X・Y間の契約なので、「連帯保証契約に基づき」となる。
本問の事例に登場する契約は、「消費貸借契約」「信用保証委託契約」「連帯保証契約」
である。「消費貸借契約」は「貸金債権の主たる債務者A」「貸金債権の債権者B」間で、
「信用保証委託契約」は「貸金債権の主たる債務者A」「貸金債権の保証人X」間で、「連
帯保証契約」は「求償権の債権者X」「求償権の保証人Y」間で締結されている(ほかに、
連帯保証かどうかは不明であるが、「貸金債権の債権者B」「貸金債権の保証人X」間で、
「保証契約」が締結されているはずである)。事案を読み取ることができれば、X・Y間
の契約なので、「連帯保証契約に基づき」となるのは明らかである。
そして、X・Y間の契約は連帯保証契約なので、「保証債務の履行(求償債務の弁済)
を請求することができる」となる。
ここがポイント! 保証債務
・平成 21 年に「保証人の求償」、平成 24 年に「検索の抗弁権」が出題されている。
・事例問題を作成しやすい論点のため、今後も対策をしておく必要がある。
・登場人物が多いケースでは、いかに事例を整理することができるかが鍵となる。
・1つの図に情報を全て詰め込むのではなく、図を分割するという方法もある。

- 16 -
問題8 Aは、Bの預金通帳と届出印鑑を持ってC銀行へ行き、Bの預金の払戻しを求
めた。そこで、Cの窓口担当の銀行員は、Aに対して支払を行ったが、実は、そ
の預金通帳と印鑑は、AがBから盗んだものであった。民法及び判例によれば、
この場合におけるAのような者を何と呼ぶか。また、Cの支払が効力を有するた
めには、民法上、いかなる要件を満たす必要があるか。40字程度で記述しなさ
い。
(下書用)
10 15

- 17 -
問題8 正解例
Aを債権の準占有者と呼び、CはAに受領権限がないことについて善意無過失である必
要がある。(44 字)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がな
かったときに限り、その効力を有する(民法 478条)。
本問の事案では、Aは債権の準占有者に当たる。よって、CがAに対してした支払が効
力を有するためには、弁済者Cが、Aに受領権限がないことについて善意であり、かつ、
過失がない必要がある。
ここがポイント! 弁済
・平成 22 年に「代位弁済における求償権」に関して出題されている。
・用語を問う問題や定義を問う問題の対策も必要である。
・善意、善意無過失、善意無重過失の違いは、注意が必要である。

- 18 -
問題9 Aは、Bとの間で、B所有の甲土地を目的とする賃貸借契約を締結した。Aが、
Bから甲土地の引渡しを受けて占有を開始しようとしたところ、Cが無断で甲土地
の使用を始めた。このような場合、最高裁判所の判例によると、Aは、Cに対して、
賃借権の対抗要件を備えていれば、賃借権に基づく妨害排除請求権を行使すること
ができる。ではこのほかに、民法及び最高裁判所の判例によれば、Aは、どのよう
な手段により、Cの占有を排除することができるか。40字程度で記述しなさい。
(下書用)
10 15

- 19 -
問題9 正解例
Aは、債権者代位権の転用により、Bの所有権に基づく妨害排除請求権を行使すること
ができる。(44 字)
賃借人は、次のいずれかにより、賃借権を妨害する第三者を排除することができる。
① 賃借権に基づく妨害排除請求権(最判昭和 30.4.5)
② 占有訴権(民法 197条)
③ 債権者代位権の転用(大判昭和 4.12.16)
賃借人は、賃貸人の妨害排除請求権を代位行使することができ、この場合、債務者(賃
貸人)が無資力である必要はない(大判昭和 4.12.16)。
本問事案の場合、まず、「Aは、Bとの間で、B所有の甲土地を目的とする賃貸借契約
を締結した。Aが、Bから甲土地の引渡しを受けて占有を開始しようとしたところ、Cが
無断で甲土地の使用を始めた」とあることから、A・B間で賃貸借契約が締結されたにも
かかわらず、Cの不法占有により、甲土地の使用収益をすることができない状態にあるこ
とがわかる。
このような場合、判例は、賃借人Aは、①賃借権に基づく妨害排除請求権(最判昭和
30.4.5)、②占有訴権(民法 197 条)、③債権者代位権の転用(大判昭和 4.12.16)、のい
ずれかにより、賃借権を妨害する第三者Cを排除することができる。本問では、①の手段
につき既に指摘されていることから、②と③の手段を検討することになる。
まず、②占有訴権を行使するには、占有権を取得する必要がある。しかし、本問事案の
場合、「Aが、Bから甲土地の引渡しを受けて占有を開始しようとしたところ、Cが無断
で甲土地の使用を始めた」とあることから、賃借人Aは、未だ甲土地の占有権を取得して
いないことがわかる。
したがって、賃借人Aは、②占有訴権を行使することができない。
次に、③債権者代位権の転用を行使するには、判例は、土地の賃借人が賃貸人に対して
当該土地の使用収益をさせよという債権を有する場合において、第三者が当該土地を不法
に占拠し使用収益を妨げているときは、土地の賃借人は当該債権を保全するために、民法
423条によって賃貸人の有する土地妨害排除の請求権を行使することができるとしている
(大判昭和 4.12.16)。
本問事案の場合、「Aは、Bとの間で、B所有の甲土地を目的とする賃貸借契約を締結

- 20 -
した」とあり、AはBに対して、甲土地の使用収益をさせよという債権(賃借権)を有す
ることから、賃貸人Bの有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができ
ることがわかる。
よって、本問では、債権者代位権の転用により、賃貸人Bの有する所有権に基づく妨害
排除請求権を行使することができる旨を記述すればよい。
ここがポイント! 賃貸借
・平成 20 年に「信頼関係の法理」が出題されている。
・狙われそうな論点は多々あるが、「転貸借」、「敷金」、「賃借権を妨害する第三者の排
除」等は確実に復習しておきたい。

- 21 -

- 22 -
問題10 Xは、産業廃棄物の処理業者であるAが、X所有の甲山林にテレビやパソコン
等の電気機器を違法に投棄しているところを発見した。Xが調査したところ、A
は、産業廃棄物の排出事業者であるBから、テレビやパソコン等の電気機器の廃
棄処分を委託されていたことを突き止めた。そこで、Xは、Aに対して、投棄し
た廃棄物の除去に代わる請求を、Bに対して、甲山林の原状回復の請求をしたい
と考えている。以上の事例において、Xが取りうる民法上の手段を、40字程度で
記述しなさい。
(下書用)
10 15

- 23 -
1.XのAに対する請求について
本問の事案では、Aは、X所有の甲山林にテレビやパソコン等の電気機器を違法に投棄
していたことから、Xに対し損害を与えていることがわかる。本問では、Aに対し「投棄
した廃棄物の除去に代わる請求」を記述せよとのことであるから、民法上これに該当する
請求は、損害賠償請求である。また、XとAとの間に契約関係はないから、損害賠償請求
の根拠は、不法行為である(民法 709 条)。
2.XのBに対する請求について
次に、XのBに対する請求であるが、請求の内容は、「甲山林の原状回復の請求」であ
る。つまり、甲山林に違法に投棄された電気機器を除去するようBに対し請求するという
ことがわかる。甲山林はXが所有していることから、Xは、その所有権に基づき、物権的
請求権を行使することが民法上認められている。物権的請求権のうち、要求されている記
述に該当するものは、物権的妨害排除請求である。
なお、Xは、占有権を有しているので、占有保持の訴えにより妨害の停止を請求すること
もできる(民法198条)。
問題 10 正解例
Aに対して不法行為に基づく損害賠償請求が、Bに対して所有権に基づく妨害排除請
求ができる。(44字)
ここがポイント! 不法行為
・平成 19 年に「正当防衛」、不法行為の問題ではないが平成 22 年に「509 条(不法行為
に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺の禁止)の制度趣旨」、平成 23 年に「使
用者責任」が出題されており、不法行為は問われることが多い分野である。
・狙われそうな論点は多々あるが、「監督者責任」、「未成年者が責任能力を有する場合
の判例」、「土地工作物責任」などは確実に復習しておきたい。
・請求内容から、「債務不履行」「無権代理」「物権的請求権」といった様々な分野と関
連付けて出題できる分野である。

- 24 -
5555 その他(参考)
1 試験科目・出題形式(平成 25 年度本試験)
法 令 等(46 問) 一 般 知 識 等(14 問)
形 式 五肢択一 多肢選択 記述 五肢択一
基礎法学 2 問 - - 政治 3 問
憲 法 5 問 1 問 - 経済 1 問
行政法 19 問 2 問 1 問 社会 3 問
民 法 9 問 - 2 問 情報通信 1 問
商 法 5 問 - - 個人情報保護 3 問
- - - - 文章理解 3 問
合 計 40 問 3 問 3 問 合 計 14 問
得 点 1 問 4 点 1 問 8 点 1 問 20 点 得 点 1 問 4 点
配 点 160 点 24 点 60 点 配 点 56 点
2 記述式採点基準
記述式の採点基準は受験年度によって異なる。
・択一が易しい→記述式の採点基準は厳しくなる傾向。
・択一が難しい→記述式の採点基準は緩くなる傾向。
基準が厳しい場合は、曖昧な解答を書いても得点にならない。
基準が緩い場合は、択一が難しいので、記述式で得点できないと致命傷になりかねない。

- 25 -
3 基本的学習方法
(1)学習の際には、次の点について意識すること。
要件・効果
出題のほとんどは、要件を問われているといっても過言ではな
い。また、要件・効果から、どのような請求ができるかも問わ
れることがある。特に民法において出題可能性があるところは、
しっかりとおさえておきたい。
定義 記述で出題しやすい用語の定義は、ていねいに繰り返し読み、
正確に覚えたい。
趣旨 過去に一度のみ出題されたことがある。択一式においても趣旨
を意識できれば、理解が深まり、応用力がつく。
(2)厳しい基準に照準を合わせ、自身の解答が正確かどうかの確認に時間をかけるこ
と。
→自身の答えに不安がある場合は講師に尋ねること。
(3)最初のうちは模範解答を写すだけでもOK。

- 26 -
4 不用意な失点を避けるための工夫
(1) ミスの起こりやすいパターンを事前に把握しておくこと。
(2) 同じ論点であっても、類似問題も解く。
→問題によって出題形式、問われている内容に差異があるので、解答用紙を利用
して、実際にマス目に書いて類似問題を解く。解答力を養うことができる。
(3) “自分なり”の間違える癖、苦手なところを明確にしておく。
→イージーミスを放っておくと、本試験で繰り返す。個人毎で間違える癖、苦手
なところは違うので、問題演習で間違えた内容を書き出し、原因を分析して対
策を練る。
・要件同士のつなぎ言葉に注意
例)「かつ」か「又は」か…
・字数いっぱいまで丁寧な解答を心がける
例)誰が、誰に、何を等を特定する
・事例問題では登場人物を書き間違えないよう注意
→必ず図を書いて、問題文と照らし合わせる
・複数の要件がある場合は、すべて書き出してから不要なものを消去する
→問題文で満たされている要件は書かない
・効果発生のための要件ではなく、効果が発生しないための要件を書くこともある
例)錯誤無効が主張できないのはどのような場合か
→表意者に重過失があるか、又は、法律行為の要素に錯誤がない場合
・「時」をあらわすフレーズの書き忘れに注意
例)遅滞なく、相当な期間を定めて、60日以内に
・書面が要求される場合には「書面で」と明記する(特に行政法)
・誤字・脱字に注意。

- 27 -
5 解答の書き方
(1)基本ルール
記述式を解答する際には、次のルールを守ること。
①原則として、字数は、句点を含めて 35~45 文字(最後の「。」も 1マス使う)。
②原則、問われた通りに答える。
例)「どのようなものか。」と問われたら「~なもの。」、「誰の、どのような行為に
よるか」と問われたら「~の~による」等
③出題上のルールを守って解答する。
例)括弧を埋める問題、後ろに文章が続く問題等
(2)解答の手順
②事例整理・論点の把握
①問題文の確認
③情報の書き出し・選択
④下書き作成・清書
⑤見直し
・まず、出題上のルールや答え方を確認する。
・まず、要件や効果等の情報を全て書き出し、そ
れから、解答に不要なもの※を削る。
※解答に不要な情報とは、問題文にすでに記載されてい
る要件等のこと。出題者はそれ以外の要件等を理解して
いるか問いたいものである。
・情報をつなぎ合わせて、下書きを作成する。
・その際に、前述の基本ルールを守る。
・清書の際は、転記ミスに注意!
・問題を整理して、どの論点が問われているか把
握する。(行政法はどの法律の知識が問われてい
るかも注意!)
・事例問題は、必ず図を書いて、問題文と照らし
合わせること。
・基本ルールを中心に見直しをする。
・最低でも、誤字・脱字、句点等の形式面は確認。
![平成27年司法試験予備試験論文式試験問題と出題趣旨 - 法務省平成27年司法試験予備試験論文式試験問題と出題趣旨 [憲 法] 違憲審査権の憲法上の根拠や限界について,後記の〔設問〕にそれぞれ答えなさい。〔設問1〕](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/60144202d989701f507d946e/27eeeeeeeeoeeoee-coe.jpg)