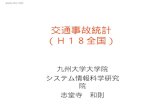通信鉄塔設計要領について(通知) - MOD...1 第1章 総 則 1-1 目 的...
Transcript of 通信鉄塔設計要領について(通知) - MOD...1 第1章 総 則 1-1 目 的...

防整技第7380号
2 8 . 4 . 1
大 臣 官 房 会 計 課 長
地 方 協 力 局 施 設 管 理 課 長
防衛大学校総務部管理施設課長
防衛医科大学校事務局経理部施設課長
防 衛 研 究 所 企 画 部 総 務 課 長
統合幕僚監部総務部総務課長
陸上幕僚監部防衛部施設課長
海上幕僚監部防衛部施設課長 殿
航空幕僚監部防衛部施設課長
情報本部計画部事業計画課長
各 地 方 防 衛 局 調 達 部 長
帯 広 防 衛 支 局 長
東 海 防 衛 支 局 長
熊 本 防 衛 支 局 長
名 護 防 衛 事 務 所 長
防 衛 装 備 庁 長 官 官 房 会 計 官
整備計画局施設技術管理官
( 公 印 省 略 )
通信鉄塔設計要領について(通知)
標記について、関連文書に基づき、別紙のとおり定めたので通知する。
関連文書:防整技第7367号(28.4.1)
添付書類:別紙
写送付先:整備計画局施設計画課長、整備計画局施設整備官、整備計画局提供施設
計画官、地方協力局地方協力企画課長、地方協力局提供施設課長

別 紙
通信鉄塔設計要領
<平成28年4月>
整備計画局施設技術管理官

1
第1章 総 則
1-1 目 的
この要領は、通信鉄塔の計画・設計等において標準的な事項を定め、業務の効率化に
資することを目的とする。
1-2 適用範囲
この要領は、鋼構造の通信鉄塔等の計画及び設計に適用する。
1-3 適合法令及び規準等
この要領に明記されていない事項については、関係法令及び規準等によるものとする。
(1)建築基準法 (昭和25年 法律第201号)
(2)電波法 (昭和25年 法律第131号)
(3)航空法 (昭和27年 法律第231号)
(4)労働安全衛生法 (昭和47年 法律第57号)
(5)日本工業規格 (JIS)
(6)鉄筋コンクリート構造計算規準 (日本建築学会、以下「学会RC規準」とい
う。)
(7)鋼構造設計規準 (日本建築学会、以下「学会S規準」という。)
(8)鋼構造設計規準 ―許容応力度設計法― (日本建築学会、以下「学会S規準」
という。)
(9)建築基礎構造設計指針 (日本建築学会、以下「学会基礎指針」という。)
(10)塔状鋼構造設計指針・同解説 (日本建築学会)
(11)建築物荷重指針・同解説 (日本建築学会)
(12)鋼管構造設計施工指針・同解説 (日本建築学会)
(13)通信鉄塔設計要領・同解説(建設電気技術協会、以下「協会要領」という。)
(14)建築構造設計基準及び同解説((社)公共建築協会)
(15)官庁施設の総合耐震計画基準((社)公共建築協会)
(16)鋼構造接合部設計指針(日本建築学会)
(17)鋼構造座屈設計指針(日本建築学会)
(18)その他関連法、規準及び規格
1-4 鉄塔の呼称
鉄塔の呼称は、鉄塔高、基本構造(断面形状、屋上式・地上式、自立式・支線式の別
等)及び用途(マイクロ・OH用等)がわかるように、次の例による。
例 30メートル屋上式(自立四角)マイクロ鉄塔
25メートル地上式(自立三角)短波鉄塔

2
(1) 鉄塔高とは、基礎天端より、鉄塔本体の最上部(航空障害灯や避雷針を含ま
ず)までの高さとする。
(2) 基礎構造は、他の項目により明らかな場合は、その一部又は全部を省略して
よい。
(3) 自立式、支線式の別は、支線式の場合のみ記載し、自立式の場合は省略して
よい。
第2章 配置計画
2-1 鉄塔の配置及び高さ
(1) 鉄塔の配置及び高さについては、調査等の結果をふまえ決定する。
(2) 屋上式、地上式の選定
ア 通信鉄塔は、通信施設の電気的性能の向上、敷地の有効利用、保全性及
び経済性を考慮し、なるべく屋上式で計画する
イ 局舎の規模が小さく、鉄塔とアンバランスな場合、又はその他の理由で
構造上屋上式とすることが不適当な場合は地上式とすることができる。な
お、地上式の場合は、給電線等の伝送損失を少なくするため、局舎の近く
に配置するよう考慮する。
(3) アンテナ種別による考慮
ア マイクロ及びOH鉄塔
マイクロ及びOH鉄塔は、別に実施する回線設計に基づき、建設候補地
を調査し、現地の状況に即した建設位置及び高さを決定する。
イ 対空無線、レーダ、タカン鉄塔
対空無線、レーダ、タカン鉄塔は、周辺の建造物等が電波覆域の障害と
ならないよう、適切な位置及び高さを設定する。
ウ 短波鉄塔
(ア) 短波鉄塔は、アンテナの展張面数、指向性及び良好な効率が得られ
るよう放射空間を考慮して配置及び高さを設定する。
(イ) 鉄塔の間隔は、使用する可能性のある最も長い波長の半波長ダブレ
ットアンテナが展張可能なように設定する。
(ウ) 鉄塔の高さは、半波長ダブレットアンテナの地上高がλ/4以上を原
則とする。
(4) 既存通信所への影響
近接する通信所がある場合は、設置する鉄塔が、通信所の障害にならないこ
とを確認する。

3
(5) 法的制約
鉄塔の建設については、法律上種々の制約を受けるが、特に次の地域に建設
する場合は、それぞれの法令に基づき、事前に関係機関と協議を行うなど、必
要な処置をとる。
ア 自然公園法第13条により、特別地域に指定されている地域
イ 文化財保護法第43条により、重要文化財の指定に係わる制限をうける
地域及び、埋蔵文化財包蔵地に指定されている地域
ウ 航空法第49条のより、物件の制限区域に指定されている区域
エ 都市緑地保全法第3条により、緑地保全地区に指定されている区域
オ 森林法第25条により、保安林に指定されている地域
カ 電波法第102条の2により、重要無線通信回線として指定されている
区域
キ 測量法第22条に規定する測量標の効用を損なうおそれのある区域
ク 各地方自治体の景観保護条例により制約を受ける地域
第3章 構造計画
3-1 一般事項
通信鉄塔の設計は、次の事項を十分検討し、安全かつ合理的な構造とする。
(1)搭載するアンテナの所要高、形状及び数量
(2)アンテナの取付方向、取付方法、揺れの許容値及びスペースダイバシティー間
隔
(3)給電線等の形式、数量及び布設方法
(4)維持管理上の作業性
(5)耐風圧力及び耐地震力
(6)敷地の状況による制約
(7)施工性及び経済性
(8)日影障害及びテレビ電波受信障害、その他周辺環境との整合
(9)将来計画
3-2 鉄塔の形状
(1) 鉄塔各部の名称
鉄塔各部の名称は、別図による。
(2) 断面形状
鉄塔平面形状は、次を標準とする。
ア 短波アンテナ用鉄塔・・・・・・・・・・・・・ 正三角形

4
イ 対空用鉄塔・・・・・・・・・・・・・・・・・ 正三角形又は正方形
ウ マイクロ、OH、タカン及びレーダ用鉄塔・・・ 正方形
エ 反射板用鉄塔は、基礎部を正方形とし、反射板取付け部は、支持ボルト
間隔に合わせて矩形としてよい。
(3) 骨組形状
塔本体は、形鋼又は鋼管を使用したトラス構造で、単純で力学的に明解な架
構とし、図3-2・1に示すKトラス形、逆Kトラス形、ダブルワーレン形、
プラット形、ブライヒ形(又はつづみ形)又は、この組合せを標準とする。
図3-2・1 骨組の種類
斜材角度θは、45度前後を標準とし、30度~55度(K型は、18度~
55度)に納まるような結構とする。
ア Kトラス形・逆Kトラス形は、主柱材に補剛材を入れ易い比較的規模の
大きいものに使用する。腹材の全部を圧縮材及び引張材として計算され、
鉄塔下部のように塔体幅が大きい部分には有利である。また、積雪の多い
地方の鉄塔脚部に対し、積雪の沈降力に対して有利な組み方である。
イ ダブルワーレン形は、根開きの比較的狭いものに使用する。腹材の全部
を圧縮材及び引張材として計算され、形鋼を使用する普通の鉄塔で塔体幅
の比較的小さい鉄塔の中部より上部にかけて使用されるほか、鋼管使用の
鉄塔にもよく採用されている。
ウ シングルワーレン形のみの構造は、不安定構造であるので、小規模なも
のに限り使用する。
エ プラット形は、比較的塔体幅の大きい場合に適するが、風速が大きく、
積雪の多い地域では不利なこともあり、採用に当たっては十分に検討を行
うこと。
オ ブライヒ形(つづみ形)はダブルワーレン形の改良型ともみられ、最も
広く採用されている。
(4) 塔頂部形状
塔頂部幅及び形状は、取付けるアンテナの形状、数量、取付方法、ねじれ角
の許容値、給電線等の布設及び作業性等を考慮して定める。

5
(5) 根開き
根開きは、建設場所の状況、取付けるアンテナの形状及び地盤の支持力等を
考慮して定めるが、概ね式3-2・1~3-2・3を標準とする。
ア 短波用三角鉄塔
------------------3-2・1
イ OH用鉄塔
------------------3-2・2
ウ その他の鉄塔
------------------3-2・3
B:根開き H:塔高 D:パラボラアンテナの直径
エ 屋上式の場合は、柱脚部を建物の柱に合わせ、極力正方形になるように
計画する。
3-3 部材計画
(1) 主柱材の座屈長
大規模な鉄塔は、主柱材の座屈長を短縮するための補剛材が入れ易い形態を
採用する。
(2) 断面変形防止用水平材等
塔体断面の変形を防ぐために、節点毎に水平材及び水平筋違材を設ける。た
だし、小規模な鉄塔の場合は、その一部を省略してよい。
(3) 主柱材の曲がり点の水平材
主柱材の曲り点には、主柱材の傾きの差により生じる水平力を負担させるた
めの、水平材及び水平筋違材を設ける。
(4) 荷重作用点
荷重作用点は、原則として節点になるよう骨組を構成する。
(5) 反射板用鉄塔の接合部
反射板用鉄塔の接合部のボルトは、接合部のすべりをできるだけ小さくする
目的で、高力ボルト(F8T)を使用する。
H
7≦ B ≦
H
5
B ≒2.5
D+
5.5
H
5.5
H≦ B ≦
4.5
H

6
3-4 附属構造物
(1) パラボラアンテナの取付方法
ア パラボラアンテナは、原則としてアンテナリングを設けて取付ける。
イ アンテナリングの高さ(縦方向の幅)は、取付ける可能性のあるアンテナ
の最大のもの又は、ダイバシティ間隔に合わせる。
ウ OH等の大型アンテナは、支持枠を用いることにより、アンテナの取付け、
方向調整が容易になることから、塔側面に支持枠を設けて取付ける。
(2) プラットホーム
高所作業を安全に行うため、プラットホームを設け、床の材料は、グレーチ
ングやエキスパンドメタルとする。
また、閃光式航空障害灯を設ける場合は,保守点検用のプラットホームも必
要に応じ考慮する。
踏板の大きさや手摺の高さは、労働安全衛生規則第563条(作業床)を参
考にする。
(3) フィーダラック
フィーダラックは、塔体断面の中央部に設け、片面又は両面式で、給電線等
の布設に対して十分に余裕があるように設計する。
(4) 昇降設備
ア マイクロ用鉄塔及び対空用鉄塔等、比較的登はん頻度が多いものは、なる
べく塔内側階段とする。ただし、塔幅が狭く階段を設けることが難しい部分
は、塔内側梯子(背もたれ付)とする。
イ 小規模な鉄塔及び短波用三角鉄塔は、塔外側梯子(背もたれ付)又はステ
ップボルトとし、転落防止装置を設ける。
(5) 踊り場
アンテナ取付部の下部、比較的作業頻度が多い部分及び梯子の途中20メー
トル以内毎に、原則として踊り場を設ける。
第4章 材料と許容応力度
4-1 構造材料
原則として、JIS規格品とし、次のとおりとする。
(1) 鋼 材
構造用材料は、表4-1・1を標準とする。

7
表4-1・1 使用鋼材の規格
鋼 材 名 一般の場合 応力が大きい場合(大形鋼)
形 鋼 類 SS-400 SS-540
鋼 管 STK-400 STK-490、(STK-540)
鋼 板 SS-400 SM-400、SM-490
中 ボ ル ト SS-400 SS-490
高力ボルト F-8T F-8T
アンカーボルト SNR-400 SNR-400
注: 中ボルトの使用にあたっては、特定行政庁へ問い合わせて使用
するのが望ましい。
(2) 鉄筋用棒鋼
鉄筋用棒鋼は、SD-295又は、SD-345とする。
(3) 基礎用コンクリート
普通コンクリートで、設計基準強度は、原則として 21N/mm2とする。ただし、レ
ディーミクスコンクリートⅠ類の使用が困難な場合は 18N/mm 2とすることができ
る。
4-2 許容応力度
構造材料の許容応力度は、材料の種類に応じ建築基準法施行令及び国土交通省告示の
規定により次のとおりとする。
(1) 鋼 材
鋼材の許容応力度は、表4-2・1のとおりとする。
表4-2・1 鋼材の許容応力度(厚さ40㎜以下.短期) 単位:N/mm2
応力の種類 基準強度 引 張 圧 縮 曲 げ せん断 支圧
材 質 F ft fc fb fs fL
SS-400、SM-400A、STK-400 235 235 235 235 135.6 441
SS-490 275 275 275 275 158.7 515
SM-490A、STK-490 325 325 325 325 187.6 609
SS-540 375 375 375 375 216.5 703
注:1 基準強度Fは、平成12年建設省告示第2464号第一による。
2 引張、圧縮、曲げ、せん断の各許容応力度の算出は、建築基準法施
行令第90条第一による。
3 支圧の許容応力度の算出は、平成13年国土交通省告示第1024
号第1の三による。

8
4 長期許容応力度は、表4-2・1の値の1/1.5倍とする。
(2) 接合用ボルト
接合用ボルトの許容応力度は、表4-2・2のとおりとする。
表4-2・2 接合用ボルトの許容応力度(短期) 単位:N/mm2
応力の種類 基準強度 引 張 せん断 支 圧
ボルトの種類 F ft fs fL
中ボルト4.6、4.8 240 240 180 接合される鋼材
中ボルト5.6、6.8 300 300 180 の1.25F以下
高力ボルトF-8T 640 375 180 ―
注:1 許容応力度は、建築基準法施行令第96条及び平成12年建設省告
示第2464号、第2466号による。
2 長期許容応力度は、表4-2・2の値の1/1.5倍とする。
3 中ボルトの許容応力算出には有効断面積を使用する。
(3) 鉄 筋
鉄筋の許容応力度は、表4-2・3のとおりとする。
表4-2・3 鉄筋許容応力度(径25㎜以下) 単位:N/mm2
応力の種類 長 期 短 期
鉄筋の種類 ft及びfc fs補強 ft及びfc fs補強
異径鉄筋 SD-295 196 195 295 295
〃 SD-345 215 195 345 345
(4) 溶 接
溶接継目の許容応力度は、表4-2・4のとおりとする。
表4-2・4 溶接継目の許容応力度(厚さ40㎜以下.短期) 単位:N/mm2
継目の形式 材 質 応 力 の 種 類
ft fc fb fs
突合せ SS-400、SM-400、STK-400 235 135.6
SM-490、STK-490 325 187.6
突合せ以外 SS-400、SM-400、STK-400 135.6 135.6
SM-490、STK-490 187.6 187.6
注: 長期許容応力度は、表4ー2・4の値の1/1.5倍とする。

9
(5) コンクリート
コンクリートの許容応力度は、表4-2・5のとおりとする。
表4-2・5 コンクリートの許容応力度 単位:N/mm2
応力の種類 長 期 短 期
設計基準強度 fc fs fc fs
21 7 0.7 14 1.05
18 6 0.6 12 0.9
(6) 鉄筋のコンクリートに対する付着
鉄筋のコンクリートに対する許容付着応力度は、表4-2・6のとおりとす
る。
表4-2・6 鉄筋のコンクリートに対する許容付着応力度 単位:N/mm2
コンクリートの 部位 長 期 短 期
設計基準強度 鉄筋 上ば筋 その他 上ば筋 その他
21 異形鉄筋 1.4 2.1 2.1 3.15
18 1.2 1.8 1.8 2.7
21 丸 鋼 0.8 1.2 1.2 1.8
18 0.7 1.0 1.05 1.5
注: 上ば筋とは、曲げ材にあってその鉄筋の下に厚さ30cm以上のコンク
リートが打ち込まれる場合の水平鉄筋をいう。
(7) 形鋼のコンクリートに対する付着
形鋼のコンクリートに対する許容付着応力度は、表4-2・7のとおりとす
る。
表4-2・7 形鋼のコンクリートに対する許容付着応力度 単位:N/mm2
コンクリート 部 材 長 期 短 期
21 形 鋼 0.42 0.63
18 0.36 0.54
(8) コンクリートくい
コンクリートくいは、第9章の9-7のとおりとする。
4-3 材料の定数

10
設計に用いる材料の物理定数は、表4-3・1による。
表4-3・1 材料の物理定数
材料 鋼 材 コンクリート
項目
ヤング係数(N/mm2) 2.05×105 2.17×104
せん断弾性係数(N/m2) 7.9 ×104 9.0 ×103
ポアソン比 0.3 0.2
線膨張係数(1/℃) 1.2×10-5 1.0×10-5
密 度(g/cm3) 7.85 無筋 2.3
鉄筋 2.4
注: コンクリートのヤング係数、せん断弾性係数はFc
21の値を示す。異なる強度の場合には「学会RC規
準」を参照し、計算する。
第5章 荷 重
5-1 荷重の種類
設計用荷重は、塔体の重量、アンテナ等の重量、架渉線展張力、風、地震等の荷重等
を適切に評価して算定する。
また、荷重の評価においては将来計画を考慮した載荷物を対象として算定を行うもの
とし、将来計画が困難な場合は、適切に割増しした荷重を考慮する。
荷重の種類は、次のとおりとする。
(1)固定荷重
(2)積載荷重
(3)雪荷重
(4)風荷重
(5)地震荷重
(6)架渉線荷重
(7)その他の荷重
5-2 荷重の算定
荷重の算定は、次のとおりとする。
(1) 固定荷重
鉄塔本体、踊場、階段(梯子)、ケーブルラック等の重量で、材料の種類、
材料寸法等に基づき、実状に応じて算定する。

11
(2) 積載荷重
アンテナ、給電線等、避雷針等の搭載物量で、実状および将来計画に応じて
算定する。踊場等に積載される荷重は、「設計基準」の歩行用屋根相当の値と
して算定する。
ただし、雪、風荷重とは組合わせない。
(3) 雪荷重
雪荷重は、過去の記録、資料を調査し、荷重の決定にあたっては「建築基準
法施行令」及び「条例」によるほか、実状に応じて算定する。
積雪地帯では、冬期に塔体及び空中線に雪が付着し、また踊場に積雪して荷
重が増加するほか、風荷重に対する見付面積が増大する。特に架渉線の雪付着
による引張荷重と風荷重の増加に留意する必要がある。この場合の風圧力は、
夏期の暴風時の風速ではなく、その地方の冬期の最大風圧による風圧力を用い
てよい。
また、多雪地域で塔脚部が長期間積雪中に埋もれる場合は、雪の沈降する力
の影響を考慮するものとする。ただし、最大積雪深さが、1m未満の場合は、
この沈降する力は考慮する必要はない。
(4) 風荷重
風荷重は、式5-2・1により節ごと算定する。
P = qz×cf×A -------------------------5-2・1
P :風荷重(N)
qz :当該部分の速度圧(N/m2)
cf :風力係数
A :受風面積(m2)
なお、条例等により算定した値が、上式の値を上回る場合は、これを採用す
る。
ア 速度圧
速度圧は、式5-2・2および5-2・3により節ごとに算定する
qz = q×kz -------------------------5-2・2
q = 0.6×E×Vo2×β -------------------------5-2・3
ただし qz ≧ 2350 N/m2
ここに q :鉄塔頂の速度圧
kz:当該部分の係数
kz = 1.0 :HがZb以下の場合
= (Zb/H)2α :HがZbを超え、ZがZb以下の場合
= (Z/H)2α :HがZbを超え、ZがZbを超える場合
Zb:平成12年建設省告示第1454号第1表に掲げる数

12
値
Z :当該部分の地盤面からの高さ(m)
E = Er2×Gf
Er:平均風速の高さ方向の分布係数
Er = 1.7×(Zb/ZG)α :HがZb以下の場合
= 1.7×(H/ZG)α :HがZbを超える場合
ZG:平成12年建設省告示第1454号第1表に掲げる
数値
α:平成12年建設省告示第1454号第1表に掲げる
数値
H :鉄塔高さ(鉄塔頂部の地上からの高さ(m))
Gf:ガスト影響係数(平成12年建設省告示第1454号第
1表に掲げる数値)
Vo:基準風速(m/s)(平成12年建設省告示第1454号第2
表に掲げる数値)
β:設計用補正値(β= 1.42)
イ 風力係数
受風面の種類とそれを受ける風圧力との関係を示すものが風力係数であ
って、各種受風面に対する風力係数(cf)の値は、平成12年建設省告示1
454号に準じた値を用いる。
(ア) 鉄塔のトラス部分に対する風力係数は、式5-2・4で算出した
充実率と表5-2・1より算定する。
表5-2・1 鉄塔(トラス部分)の風力係数
充実率 (1) (2) (3)
種類 φ≦0.1 0.1<φ<0.6 0.6≦φ
鋼管 (a) 1.4 (1)(3)とに掲げ 1.4
(b) 2.2 る数値を直線的 1.5
(c-1,2) 1.8 に補間した数値 1.4
(d) 1.7 1.3
形鋼 (a) 2.0 1.6
(b) 3.6 2.0
(c-1,2) 3.2 1.8
(d) 2.8 1.7
ラチス構造物の風力係数

13
充実率φの算出については正風時、斜風時について算出する。
図5-2・1において、
φ= Aγo/Ao -------------------------式5-2・4
ここに、φ :充実率
Aγo:斜線部面積
Ao :外郭面積 = b×h
図5-2・1
(イ) 鉄塔の単材に対する風力係数は、表5-2・2による。
表5-2・2 単材の風力係数
種 類 風力係数
形 材 (山形鋼) 2.0
鋼 管 直径 10cm以下のもの 1.2
(コンクリー 直径 10cmを 表面のなめらかなもの 0.8
ト円柱を含む)超えるもの 直径の2%程度の凹凸のあるもの 0.9
(ウ) パラボラアンテナの風力係数
a レドーム無しパラボラアンテナの風力係数は、図5-2・2 に
よる。
図5-2・2 パラボラアンテナの風力係数
b レドーム(全面に凸で頂角120°~150°の形状のもの)付パラボ
ラアンテナの風力係数は図中の値が1.4を超える部分については、1.

14
4とする。シートレドーム付の風力係数は、シートが破れ易いこと
を考慮して、レドームなしの値とする。
c グリッドパラボラアンテナの風力係数は全方向1.2とする。
(エ) その他のアンテナの風力係数
a ディスコーン、コーナーレフレクタ及びこれらに類する物は 、1.
6とする。
b 八木アンテナ、ロケット条アンテナ及びこれらに類する物は 、1.
2とする。
(オ) 梯子及び階段等の塔内側の附属構造物に対する風力係数は、2.0
とする。
(カ) プレート型反射板の風力係数は、1.2とする。
(キ) 特殊アンテナの風力係数
OH用パラボラアンテナ、レーダ、TACAN等の特殊なものの
風力係数は、製造メーカーの資料等を参考にして定める。
(ク) この項に記載のない形状のものは、風洞実験による値及び建築物
荷重指針(日本建築学会)における類似のものの値を用いる。
ウ 受風面積
(ア) 塔体の受風面積は、一つの構面の垂直投影面積とする。ただし、
風向に平行な構面及び塔内側の部材は含めない。
なお、垂直投影面積は線図より求められる投影面積を継手部のプ
レート等を考慮して割増ししたものとし、割増率は、部材がアング
ルの場合は10%、鋼管の場合は12%とする。
トラス架構の受風面積を図5-2・3に示す。
図5-2・3 受風面積
(イ) 梯子及び階段等の受風面積は、正面か側面の垂直投影面積の何れ
受風面積:斜線部

15
か大きい方とする。
(ウ) パラボラアンテナ及び反射板の受風面積は正面の面積とする。
(5) 地震荷重
地震荷重は、式5-2・5、5-2・6により、節ごと算定する。
Qi = Ci・Wi ----------------- 5-2・5
Hi = Qi-1 - Qi ----------------- 5-2・6
Ci = Z・Rt・Ai・Co
ここに、 Qi:i節の地震時層せん断力(kN)
Ci:i節の層せん断力係数
Wi:i節以上の建物重量(kN)
Z :地域係数
Rt:振動特性係数
Ai:i節の層せん断力係数の分布係数
Co:標準せん断力係数(≧1.0)
Hi:当該節の水平力
ア 振動特性係数 Rt
鉄塔の振動特性係数 Rtは、鉄塔の一次固有周期 Tt、局舎の一次固有周
期 T、地盤種別に応じた数値 Tcにより、式5-2・7及び5-2・8よ
り求める。
(ア) 地上から立つ鉄塔
Tt<Tc の場合 Rt = 0.8
Tc≦Tt<2Tc の場合 --------5-2・7
Rt = 0.8{1-0.2(Tt/Tc - 1)2
2Tc≦Tt の場合 Rt = 1.28Tc/Tt
(イ) 屋上式鉄塔の場合
Tt/T<0.6 の場合 Rt = 1.8
0.6≦Tt/T<0.8 の場合 Rt = 3Tt/T
0.8≦Tt/T<1.2 の場合 Rt = 2.4 --------5-2・8
1.2≦Tt/T<2.4 の場合
Rt = 0.8 + 1.6{2-(Tt/T/1.2)}2
2.4≦Tt/T の場合 Rt = 0.8
アングルトラス鉄塔以外の場合、局舎上に立つ鉄塔は局舎と鉄塔の連成
モデルにより地震応答解析を実施することが望ましいが、困難な場合は安
全性を考慮し地震力を算定するものとする。
(ウ) 鉄塔、局舎の一次固有周期
鉄塔の一次固有周期は、式5-2・9より求めることができる。

16
Tt = 0.015H(アングルトラス構造の場合)
Tt = 0.015H(パイプトラス構造の場合) -------5-2・9
Tt = 0.015H(シリンダー構造の場合)
Tt = 0.020H(パイプラーメン構造の場合)
ここに、Tt:鉄塔の一次固有周期(sec)
H :塔 高(m)
局舎の一次固有周期は、式5-2・10により求めることができ
る。
T = h(0.02+0.01α) -------------5-2・10
ここに、T :庁舎の一次固有周期(sec)
h :庁舎の高さ(m)
α:庁舎の高さのうち鉄骨部分の高さの比
イ 層せん断力分布係数 Ai
i階の層せん断力分布係数は式5-2・11より求める。
-------------5-2・11
ここに、Ai :i階の層せん断力分布係数
αi:i階より上の部分の重量と総重量の比
Tt :鉄塔の1次固有周期(sec)
ウ 地震地域係数 Z
建築基準法施行令第88条第1項に基づく建設省告示(昭和55年告示
第1793号)による。
(6) 架渉線荷重
ア 架渉線張力
(ア) 架渉線による引張力は、線のなす曲線を近似的に放物線として、
式5-2・12により算定する
--------------5-2・12
T:引張力(N)
W:単位長さの線に加わる荷重(N/m)
l:スパン長(m)
d:ゆるみ度(m)通常スパンの1/20~1/100程度とする。
ただし、最大値は、次のとおりとする。
5φ高鋼線を使用する場合 5500(N)
5φカッパプライを使用する場合 13800(N)
その他の場合は、架渉線の破断強度の70%以下とする。
(イ) 架渉線の中央部に集中荷重が加わるときは、式5-2・13によ
Ai = 1+(1 αi - αi)・2Tt (1+3Tt)
T = W・l2
8・d

17
り算定し、値を式5-2・12に加算する。
------------5-2・13
P:集中荷重(N)
(ウ) 架渉線(碍子を取付けた場合も同じ。)の風力係数は、1.2とす
る。
(エ) 風荷重を考慮する場合は、引張力{(ア)又は(イ)}に風荷重
引張を幾何学合成して鉄塔本体への点荷重として加える。
(7) その他の荷重
その他の荷重には、作業者の体重による作業荷重があり、梯子、踊り場等に
対する積載荷重として考慮されるが、塔体に対しては短期荷重であり、風荷重
に比較して僅少であるので通常は省略される。
5-3 荷重の組合せ
構造計算における設計応力は、各荷重に応力を適切に組合せて求める。地震荷重と風
荷重は、合成しない。
荷重の組合せは、表5-3・1による。
表5-3・1 荷重の組合せ
設計応力の種類 荷重について想定する状態 荷 重 の 組 合 せ 備 考
長期の応力 常 時 G + P + 0.7S 架渉線その他の
短期の応力 暴 風 時 G + P + 0.35S + W 荷重は実状に応
地震時 G + P + 0.35S + K て組合せる。
G:固定荷重 P:積載荷重 S:雪荷重 W:風荷重 K:地震荷重
第6章 応力及び変形の算定
6-1 一般事項
(1) 応力及び変形の算定
ア 塔体骨組の応力及び変形は、各部材を断面性能に応じた弾性剛性を有す
る線材に置換し、立体骨組として算定する。ただし、軽微なものについて
は、平面構造の集合体と考えて外力をある仮定のもとに、各構面に分割し
て算定してよい。平面構造として取扱う場合は、構面の傾斜に注意しなけ
ればならない。
イ 鉛直荷重時及び水平荷重時(風荷重、地震荷重)について算定する。水
平荷重は、塔体の構面に対して直角方向及び45°方向から作用する場合
T =P・l
4・d

18
について算定する。
ウ 応力の計算方法は、原則として解析式解法とし、節点荷重を求めたあと、
節点間隔、主柱材の傾き等により電子計算機を利用して求める方法とする。
(2) 大規模鉄塔の計算
屋上式で鉄塔高45メートルを超える鉄塔、地上式で鉄塔高60メートルを
超える鉄塔、その他耐震性を特に確かめる必要のある鉄塔は動的解析を行うこ
とを標準とする。
(3) 骨組のモデル化
解析のモデル化は、一般的に応力材(平面結構における平面ブレース材を含
む)について行う。
応力材以外の主要な補強材及び支援材は、骨組の応力及び変形に及ぼす影響
が少ないので、一般にモデル化は行わない。
注:1 応力材とは、主柱材、水平材、斜材、踊場上下弦材等をいう。
2 補強材とは、ラチス材、対辺材、水平ブレース材等をいう。
3 支援材とは、側補強材、裏打材等をいう。
(4) 節点荷重
固定荷重、積載荷重、風荷重及び地震荷重等は、各節点について、その上下
の節点の中心までの範囲の各荷重が塔体隅の各節点に均等作用するものとして
算定する。
(5) 接合条件
各部材の節点は、部材の応力中心線の交点に設定し、主柱材は剛接合、その
他の部材はピン接合とする。
(6) ねじり力
トラス鉄塔にかかるねじり力は、図6-1・1、6-1・2のように各構面
に分割し、平面トラスに加わる水平力として取扱うことができる。
ただし、加力点においては、ねじり力を各構面に伝えることができるように
筋かいなどで十分に補強する必要がある。

19
正三角形の場合 正方形の場合
Q :各構面の分割力(N)
Mt:ねじりモーメント(N・m)
a :辺長(m)
図6-1・1 ねじり力
Mtは、ねじりモーメントで図6-1・2のとおり算定する。
Mt = Pa・Lsinθ
図6-1・2 パラボナアンテナによるねじりモーメント
(7) たわみ(倒れ角、おがみ角)及びねじり角の制限
ア 鉄塔(基礎を含む)のたわみ及びねじり角の許容値は、台風等の荷重を
受けた場合に、表6-1・1の値以下とする。
ただし、アンテナ形状及び周波数帯により、許容値が異なることから必
ず運用上の要求を確認すること。参考として図6-1・3、図6-1・4
に示す。
2・a
MtQ
・a3
2・MtQ

20
表6-1・1 許容たわみ角
周 波 数 帯 たわみ、ねじり角
200 ~ 400 MHZ帯 3 度
2000 MHZ帯以上 1 度
反 射 板 0.1 度
イ レーダ及び計測用鉄塔等、たわみが規制されるものは、運用上の要求に
基づき定める。
ウ 地震時におけるたわみ角等は、特に計算しなくてもよい。
図6-1・3 鉄塔のたわみ角とねじれ角との合
成振れ角の許容範囲(利得の約15dB低下する角度)
図6-1・4 128QAM-208Mdps方式に於けるXPD劣化に対する合成振れ角許容範囲
第7章 部材の設計
7-1 一般事項
(1) 設計応力
部材の短期の設計応力は、各部材について長期の応力と水平荷重時の応力の

21
和の最大値(引張力、圧縮力のそれぞれについて)とする。
(2) 設計応力度
応力材及び主要な補強材の設計応力度は、部材が直接風荷重を受けることに
よる応力及び節点の拘束曲げ応力等の二次応力を考慮し、表4-2・1、4-
2・2に示す許容応力度より小さくなるように設計する。
(3) 上部節部材との関係
主柱材及び斜材は、応力計算の結果にかかわらず原則として、塔体下部の断
面の大きさが塔体上部の断面の大きさを下回らないよう設計する。
(4) 形鋼の組合わせ
アングル構造で腹材が大形になる場合は、なるべくはさみ材を用いた組立材
(二丁合せ)として設計する。
7-2 断面の設計
(1) 断面設計
断面は、一般に「学会S規準」により、圧縮材又は、引張材として設計する
ほか次の各項により行う。
(2) 引張材の設計
ア 引張応力を受ける部材の設計は、式7-2・1、7-2・2により算定
する。
σt = T/An ---------------------7-2・1
ft/σt = Sf ---------------------7-2・2
σt:引張応力度(N/mm2)
T :引張力(N)
An :有効断面積(mm2)〔次項イによる〕
ft :長期許容引張応力度(N/mm2)〔表4-2・1による。〕
短期の場合は、長期に対して1.5倍とする。
Sf :安全率 概ね 1.25 以上
山形鋼、みぞ形鋼等を、ガセットプレートの片側のみ設ける場合は、そ
の有効断面から突出脚の1/2の断面を、減じた断面によって算定する。
イ 有効断面積
接合部に中ボルト又は高力ボルト等を用いる引張材の有効断面積は、こ
れらの配置形式により次のとおりとする。
(ア) 並列ボルト配置
An = Ak - n・d・t ---------------------7-2・3
An:有効断面積(㎜ 2)
Ak:引張材の全断面積(㎜ 2)

22
n :破断線上にあるボルトの数
d :ボルトの穴径(㎜)
t :引張材の穴部の板厚(㎜)
図7-2・1
(イ) 千鳥又は不規則なボルト配置
ボルト相互の位置関係により、各破断線についての有効断面積を
式7-2・4により算定、これらのうちの最小値として求める。
An = Ak - Σα・d・t ----------------7-2・4
α:破断面の第一穴については、α= 1とし第二穴以下につい
ては、これに先立つ穴との相互位置関係に応じて次のとお
りとする。
b/g ≦ 0.5の時 α= 1.0
図7-2・2 0.5 < b/g < 1.5の時 α= 1.5 - (b/g)
b/g ≧ 1.5の時 α= 0
(3) 圧縮材の設計
ア 圧縮応力を受ける部材の設計は、式7-2・5、7-2・6により算定
する。
σc = N/A ---------------7-2・5
fc/σc = Sf ---------------7-2・6
σc:圧縮応力度(N/mm2)
N :圧縮力(N)
A :有効断面積(mm2)
fc :許容圧縮応力度(N/mm2)〔次項イによる。〕
Sf :安全率 概ね 1.25 以上
イ 許容圧縮応力度
許容圧縮応力度は、次のとおりとする。

23
λ≦Λの場合
---------------7-2・7
---------------7-2・8
λ>Λの場合
---------------7-2・9
Λ:限界細長比
-------------7-2・10
F :平成12年建設省告示第2464号第一に定める基準強度
(N / m m 2 )
λ:有効細長比(単一材)
λ= lk/i -------------7-2・11
lk:座屈(mm)
i :座屈軸についての断面二次半径(mm)
fc:許容圧縮応力度(N/mm2)
E :ヤング係数(N/mm2)
ただし、短期許容圧縮応力度は、上式による長期許容圧縮応力度の数値
の1.5倍とする。
ウ 座屈長さ(lk)
部材の座屈長さは、原則として節点間距離(補強材がある場合は、補強
された支点間距離)とする。
エ 細長比の制限
概ね、次のとおりとするとする。
主 材 100 以下
その他の応力材、主要補強材 170 以下
支 援 材 250 以下
オ 組立圧縮材
充腹軸についての、有効細長比の算定は、単一材の規定による。
非充腹軸についての、有効細長比は、式7-2・12、7-2・13に
fc ={1 - 0.4(λ Λ)2}F
ν
ν =3
2+
2
3×
λ
Λ
2
fc =0.277・F
(λ Λ)2
Λ =F 1.5
1500

24
より算定する。
---------------7-2・12
ただし、λ1 ≦ 20 のとき
λ ye = λ y ---------------7-2・13
λy :素材が一体として作用するとみなしたときの細長比
λye:有効細長比
m :つづり材のよって組立てられる素材又は、素材群の数λ 1は、式
7-2・14、7-2・15により算定する。
a はさみ板、帯板形式
λ 1 = l1/i1 ---------------7-2・14
l1:つづり点間の区間長(mm)
i1:素材の最小断面二次半径(mm)
λ1 ≦ 50となるように区間長をとる。
b ラチス形式
---------------7-2・15
l2:ラチス材の長さの材軸方向の成分(mm)
ld:ラチス材の長さ(mm)
e :素材の重心軸の間の距離(mm)
A :柱を構成する素材断面の和(mm2)
Ad:ラチス材の断面積 ただし、複ラチス材の場合は、両ラチス
材断面積の和(mm2)
n :つづり材断面の数
(4) 板要素の幅厚比及び鋼管の径厚比の制限
圧縮材は、全体座屈のほかに、板要素が導いて局部座屈するおそれがあるの
で幅厚比(b/t)、(d/t)及び径厚比(D/t)は、式7-2・16~2・20により
算定する。
ア 一縁支持、他縁自由の板突出部分
(ア)単一山形鋼、はさみ板を有する複山形鋼
----------------7-2・16
b :板要素の幅(mm)
t :板要素の厚さ(mm)
F :降伏点(N/mm2)
(イ)柱及び圧縮材一般の突出フランジ、梁の圧縮部分から突出している
λye = λy2 +
m
2・λ1
2
λ1 = πnAd
A・
l2・e2
ld3
b
t≦ 0.44
E
F

25
板、山形鋼及び梁の圧縮フランジ
---------------7-2・17
イ 二縁支持の板
(ア)柱又は、圧縮材一般のウェブプレート
---------------7-2・18
d :二縁で支持される板要素の幅(mm)
(イ)梁のウェブプレート
---------------7-2・19
ウ 鋼管の径厚比
----------------7-2・20
D:鋼管の公称外径(mm)
t:管厚(mm)
(5) 曲げ材の設計
曲げ応力を受ける部材の設計は、式7-2・21~7-2・27 により算
定する。
ア 圧縮側
cσb = M/Zc -------------------- 7-2・21
cσb/fb = Sf -------------------- 7-2・22
cσb:圧縮曲げ応力度(N/mm2)
M :曲げモーメント(N・mm)
Zc :圧縮側断面係数(mm3)
fb :許容曲げ応力度(N/mm2)
Sf :安全率 概ね 1.25 以上
イ 引張側
tσb = M/Zt -------------------- 7-2・23
tσb/fb = Sf -------------------- 7-2・24
tσb:引張側曲げ応力度(N/mm2)
Zt :引張側断面係数(mm3)
Sf :安全率 概ね 1.25 以上
ウ 許容曲げ応力度
許容曲げ応力度fbは、式7-2・25、7-2・26により算定し大き
い方の値とする。ただし、fb ≦ ftとする。
b
t≦ 0.53
E
F
d
t≦ 1.6
E
F
d
t≦ 2.4
E
F
D
t≦ 0.114
E
F

26
-------------------- 7-2・25
-------------------- 7-2・26
溝形断面材及び荷重面内に対称軸を有しない部材で、幅厚比の制限に従
う場合は、式7-2・26により算定する。
fb :許容曲げ応力度(N/mm2)
lb :圧縮フランジの支点間距離(mm)
i :圧縮フランジとはりせいの1/6とからなるT形断面のウェブ軸ま
わりの断面二次半径(mm)
ft :許容引張応力度(N/mm2)表4-2・1による。
------------------- 7-2・27
M2/M1は、図7-2・3のように、単
曲率の場合に正、複曲率の場合には
負とする。
h :はりせい(mm)
Af :圧縮フランジの断面積(㎜ 2)
Λ :式7-2・10による。
図7-2・3
(6) 組合せ応力材の設計
組合せ応力を受ける部材の設計は、式7-2・28~7-2・31 により
算定する。
ア 圧縮力と曲げモーメント
--------------- 7-2・28
--------------- 7-2・29
fc :許容圧縮応力度(N/mm2)
fb :許容曲げ応力度(N/mm2)
fb = 1 - 0.4(lb i)2
CΛ2ft
fb =lb・h Af
89000
C = 1.75 - 1.05M2
M1+ 0.3
M2
M1
2
σc
fc+
cσb
fb≦ 1
かつcσb - σc
ft≦ 1

27
ft :許容引張応力度(N/mm2)表4-2・1による。
σc :圧縮応力度(N/mm2)式7-2・5による。
cσb:圧縮側曲げ応力度(N/mm2)式7-2・21による。
tσb:引張側曲げ応力度(N/mm2)式7-2・23による。
イ 引張力と曲げモーメント
------------------ 7-2・30
------------------ 7-2・31
σt:引張応力度(N/mm2)式7-2・1による。
(7) 補剛材
圧縮材の水平移動を拘束するための補剛材は、補剛される材の圧縮力の2%
以上の短期軸方向力が加わるものとして算定する。
7-3 部材の接合
(1) 応力の伝達
ア 接合部は、部材の応力の伝達に注意し、付加応力、集中応力及び過大な
局部変形が生じない形式で、工場及び工事現場における施工が確実にでき
るよう設計する。
イ 応力材の接合部は、原則として部材の全強度を伝達できるよう設計する。
ウ 補強材等の接合部は、原則として部材の全強度の1/2を超えて伝達で
きるよう設計する。
注:全強度とは一般には、部材の有効断面積に許容引張応力度を乗じたも
の。
(2) 接合方法
接合部は、原則として、工場内で行う接合は溶接接合、工事現場で行う接合
はボルト接合として設計し、リベット接合は用いない。
鉄塔構造材(主材、腹材、座屈抑え材、水平ブレース等)は、原則として高
力ボルトによる摩擦接合とする。
鉄塔構造材以外のボルト接合は、建築基準法施行令第67条によることとす
る。なお、9m以下の鉄塔構造材及び階段、ケーブルラック、踊り場等の構造
部材はこの限りではない。
(3) 主柱材の継手
アングルトラス構造の場合は、原則として、バットアングルを使用し、二面
せん断のボルト接合とする。
σt + tσb
ft≦ 1
cσb - σt
ft≦ 1

28
(4) ボルト接合
ア ボルトの最小接合本数は原則として、表7-3・1のとおりとする。
表7-3・1 ボルトの最小接合本数表
部 材 径 最小本数
主柱材継手 M16以上 2本
主柱材継手以外の応力材・補強材 M16以上 2本
補剛材 2本
ただし、主柱材以外は、部材形状によりM12を使用してもよい。
補剛材については、小規模な鉄塔の場合は、最小本数1本としてよい。
イ ボルト穴の径は、ボルトの公称軸径より1.0mmを超えてはならない。
ただし、ボルトの径が、20mm以上を超えかつ構造耐力上支障がない場合
においては、ボルト穴の径をボルトの径より1.5mmまで大きくすることが
できる。
ウ ボルト穴の中心間距離は、公称軸径の2.5倍以上とする。標準ピッチ
は、表7-3・2のとおりとし、ボルトが、二列配置となる場合は、千鳥
配置とする。
表7-3・2 標準ピッチ表(mm)
径 12 16 20 22 24
ピッチ 40 50 60 65 75
エ ボルト穴中心から縁端までの最小距離は、表7-3・3とする。
表7-3・3 最小縁端距離(mm)
径 12 16 20 22 24
縁端の種類
せん断縁、手動ガス切断縁 25 30 35 40 45
圧延縁、自動ガス切断縁の 20 25 30 30 35
こ引縁、機械仕上縁
オ ボルトで締める板の総厚は、ボルト径の5倍以下とする。
ただし、高力ボルトの場合は、適用しない。
(5) 中ボルト、高力ボルトの接合の設計
中ボルト及び高力ボルト接合の設計は次のとおりとする。

29
ア せん断接合
せん断力を受けるボルトは、式7-3・1、7-3・2により算定した
値のうち、大きい方の値とする。
(ア)せん断
RS/N = Sf --------------------7-3・1
N :設計応力(N)
Sf:安全率 概ね 1.25 以上
RS:ボルトの許容せん断力(N)
RS = (n・πd2/4)・fs
RS = (n・πd2/2)・fs
n :ボルト本数
d :ボルト径(mm)
fs:ボルトの許容せん断応力度(N/mm2)
(イ)支 圧
RL/N = Sf --------------------7-3・2
Sf:安全率 概ね 1.25 以上
RL:ボルトの許容支圧力(N)
RL = n・d・t・fL 1面支圧
RL = 2n・d・t・fL 2面支圧
n :ボルト本数
d :ボルト径(mm)
t :接合される両材片の板厚(又は、板厚の和)の小さい
方の値(mm)
fL:接合材の許容支圧応力度(N/mm2)
イ 引張接合
引張力を受けるボルトは、式7-3・3により算定する。
Rt/N = Sf -------------------7-3・3
N :設計応力(N)
Sf:安全率 概ね 1.25 以上
Rt:ボルトの許容引張力(N)
Rt = (n・πd2/4)・ft
n :ボルト本数
d :ボルト径(mm)
ft:ボルトの許容引張応力度(N/mm2)
(6) 高力ボルトの設計は、式7-3・4、7-3・5により算定する。
ア せん断の場合

30
Rso/N = Sf --------------------7-3・4
N :設計応力(N)
Sf :安全率 概ね 1.25 以上
Rso:ボルトの許容せん断力(N)
Rso = (n・πd2/2)・fso 2面せん断
n :ボルト本数
d :ボルト径(mm)
fso:ボルトの許容せん断応力度(N/mm2)
イ せん断と引張を同時に受ける場合
Rst/N = Sf --------------------7-3・5
Sf :安全率 概ね1.25以上
Rst:ボルトの許容力(N)
Rst =(n・πd2/4)・fst
n :ボルト本数
d :ボルト径(mm)
fst:引張を受ける場合の許容せん断応力度(N/mm2)
fst = fso・(1 - σt/F)
fso:許容せん断応力度(N/mm2)
σt:引張応力度(N/mm2)
F :基準張力(N/mm2)
(7) 溶接接合
ア 応力を伝達すべき溶接継目の形式は、特別の場合を除いてつぎの3種類
とする。
(ア)突合わせ溶接
(イ)すみ肉溶接
(ウ)部分溶け込み溶接
イ すみ肉溶接のサイズは、表7-3・4のとおりとする。
すみ肉溶接のサイズは、薄い方の母材の厚さ以下でなければならない。

31
表7-3・4
ウ すみ肉溶接の長さは、原則として、すみ肉サイズの10倍以上で、かつ、
40ミリメートル以上とする。
ただし、有効長さは、ビートの始点及びクレータを除いた部分の長さと
する。
(8) 溶接接合の設計
引張力、圧縮力又は、せん断力を受ける溶接継目の設計は、 式7-3・6
により算定する。
各種応力度
--------------------7-3・6
σ :各種応力度(N/mm2)
P :溶接接合を通じて伝達される力(N)
a :有効のど厚(mm)
l :有効溶接長さ(mm)
ρw:各種許容応力度(N/mm2)表4-2・4による。
第8章 柱 脚
8-1 一般事項
(1) 応力の伝達
柱脚は、塔体からの応力を基礎又は、局舎に安全に伝達できるように設計す
る。
(2) 構面傾斜による付加水平力
柱脚の荷重は、塔体の最下節の構面傾斜による付加水平力を考慮する。
σ =Σa・l
P≦ ρ

32
(3) 設計応力度
柱脚の設計応力度は、許容応力度より小さくなるように設計する。
8-2 柱脚の定着方法及び設計
柱脚の鉄塔の規模、形式及び局舎の規模、構造種別及び施工性等に応じて適切な
形式を選定して設計する。
(1) 柱脚埋込み式
主柱材を基礎に埋込む方法。
(2) 柱脚埋込み式の設計は、式8-2・1、8-2・2により算定する。
ア 付着応力
-----------------8-2・1
イ せん断応力
-----------------8-2・2
τo :付着応力度(N/mm2)
τ :せん断応力度(N/mm2)
as :主柱材の断面積(mm2)
σsa:主柱材の許容応力度(N/mm2)
τoa:許容付着応力度(N/mm2)
τal:許容せん断応力度(N/mm2)
L :主柱材の埋込み長さ(mm)
ρa :埋込まれた主柱材の周辺長(mm)(山形鋼では4×フランジ幅)
ρp :埋込まれた主柱材周辺長(mm)
(山形鋼では(2+√2)×フランジ幅)
(3) アンカーボルト埋込み式
アンカーボルトを基礎に埋込んでアンカーボルトにて主柱材のベースプレー
トを固定する方法。
(4) アンカーボルト埋込み式の設計は、次のとおりとする。
ア アンカーボルトの引揚耐力
せん断力と引張力を同時に受けるアンカーボルトは、式8-2・3によ
り算定する。
--------------------8-2・3
n :ボルト本数
A :ボルトの断面積(mm2)
τo = as・σsa
ρa・L< τoa
τ = as・σsa
ρP・L< τal
n・A・fts
To= Sf

33
To :引揚力(N)
Sf :安全率 概ね 1.25 以上
fts:せん断力と引張力を同時に受けるアンカーボルトの許容引張応
力度(N/mm2)
fts = 1.40fto - 1.6τ
fto:ボルトの許容引張応力度(N/mm2)
τ :ボルトのせん断応力度(N/mm2)
イ アンカーボルトの定着長さ
アンカーボルトの定着長さは、式8-2・4により算定する。
-----------------8-2・4
n :ボルト本数
L :アンカーボルトの定着長さ(mm)
d :アンカーボルトの直径(mm)
To :引揚力(N)
fa :鉄筋コンクリートの短期許容付着応力度(N/mm2)
ウ ベースプレートの厚さ
ベースプレートの厚さは、式8-2・5により算定する。
------------------8-2・5
t :ベースプレートの厚さ(mm)
M :ベースプレートを片持梁、三片固定又は、二片固定とみなした
場合の端部モーメント(N・mm)
bc :曲げ圧縮側の場合は、単位幅として1㎝とする。曲げ圧縮側の場
合は、有効幅(mm)
fb1:ベアリングプレート等面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度
(N/mm2)
(5) 局舎の鉄骨骨組と接合する形式主柱材とアンカーフレーム又は、鉄骨骨組を
突合せ溶接で接合する方法。
第9章 基 礎
9-1 一般事項
(1) 基礎は、圧縮、引抜き、転倒及び水平移動に対して、安全でなければならな
L =n・π・d・fa
To≧ 40d
T =bc・fb1
6・M
fb1 =1.3
F(長期)

34
い。
(2) 基礎は、塔体に有害な沈下及び傾斜が生じないようにしなければならない。
(3) 繰り返し荷重を受けることを考慮し、短期の圧縮力、引き抜力及び水平力の
短期許容支持力(度)を適宜低く抑える。
(4) 基礎の設計応力度は、許容応力度より小さくなるように設計する。
9-2 基礎形式(独立鉄塔)
基礎形式は、鉄塔構造の形式と荷重の大きさ、地形地質、地盤沈下等予想される地盤
の変動、施工の容易性、確実性及び安全性、近接した建築物や地下埋設物の有無、工事
期間、振動騒音等に関する規則の有無等を総合的に判断して選定する。
(1) 直接基礎
比較的良質な地盤に適用し、基礎帯は、鉄筋コンクリート構造の逆T字型を
標準とする。
(2) くい基礎
上層の地盤が軟弱で直接基礎では、所定の支持力が得られない場合に適用す
る。くい基礎は、原則として支持くいとする。
ただし、比較的変位を大きく許容できる場合等は、摩擦くいとしてよい。
9-3 地盤支持力の確認
鉄塔建設位置の地盤は、ボーリング調査等を実施して、所要の支持力が得られること
を確認するものとする。
ただし、地表からの推定及び近接地点のボーリングデータ等により所要の支持力を得
られることが確認できる場合は、ボーリング調査等は省略してもよい。
9-4 支持地盤
基礎は、良質の硬い地盤に支持させるものとし、圧密沈下のおそれのある粘性土層、
液状化現象を生じるおそれのある砂質層、及び著しいボイリング、ヒービング現象が生
じるおそれのある地層は、原則として支持層としてはならない。やむを得ず、これらの
地層に支持させる場合は、充分な対策を講じるものとする。
また、凍上現象を生じる地域は、地盤面より基礎フーチング下端までの深さを、凍結
深度以上とする。
9-5 地中梁
多柱式基礎には、基礎間に地中梁を設け、基礎部の転倒モーメントを負担させるもの
とする。(フーチング底面には、モーメントが生じないものと仮定し、地中梁端部のモ
ーメントを算定する。)

35
梁の仮定断面寸法は、次を目安とする。
梁幅 ≧ 支持点間隔 × 1/15
梁成 = 支持点間隔 × 1/5~1/7程度
9-6 直接基礎の設計
(1) 引抜き耐力
引抜き耐力は、式9-6・1により算定する。
W1 + (2/3)W2 > T --------------------9-6・1
W1:フーチング及び地中梁の自重(kN)
W2:フーチングの鉛直上方にある土の重量(kN)
T :引抜き力(kN)
ただし、地下水等により浮力を受ける場合は、W1の低減(9.8kN/m3)を行うも
のとする。
(2) 圧縮耐力
圧縮耐力は、次のとおりとする。
ア フーチング底面に圧縮力のみが作用する場合は、接地圧は一様に分布す
るものとして式9-6・2により算定する。
fe > P/A --------------------9-6・2
fe:地盤の許容応力度(kN/m2)(平成13年国土交通省告示第111
3号による。)
P :フーチングに作用する圧縮力(フーチングの自重及び鉛直上方に
ある土の重量を含む)(kN)
A :フーチングの底面積(m2)
イ フーチングの底面に圧縮力とモーメントが作用する場合は、接地圧は直
線的に分布するものとして式9-6・3により算定する。
fe > αP/A --------------------9-6・3
fe:地盤の許容応力度(kN/m2)
P :フーチングに作用する圧縮力(フーチングの自重及び鉛直上方に
ある土の重量を含む)(kN)
A :フーチングの底面積(m2)
α:αは、圧縮力の偏心と底面の形状によって決まる接地圧係数で次
のように算定する。
ε ≦ 1/6の場合 α = 1 + 6・ε
ε >1/6の場合 α = 2/(1.5-3・ε)
ε:偏心率
ε= M/P・L

36
M:モーメント(kN・m)
L:モーメントの作用する方向におけるフーチングの底
面長さ(m)
(3) 水平耐力
基礎に作用する水平力は、式9-6・4により算定する。
Ha = (2/3)・μ・P ≧ H -------------------- 9-6・4
Ha :短期許容摩擦抵抗力(kN)
μ :フーチングの底面と地盤との間の摩擦係数で表9-6・1による。
表9-6・1 摩擦係数
土 質 摩擦係数
粘土質地盤(湿) 0.2
同 (乾) 0.5
砂質地盤 (湿) 0.2 ~0.3
同 (乾) 0.5
玉石・砂利 0.5
P :フーチング底面に係る圧縮力(kN)
H :水平力(kN)
なお、水平力は、基礎底面の摩擦力で抵抗するものとし、基礎の側圧抵抗は
期待しないものとする。
(4) 基礎の沈下
基礎の沈下量は、「学会基礎指針」により算定する。
9-7 くい基礎の設計
(1) 引抜き耐力
引抜き耐力は、式9-6・1による他、現場造成杭の場合にはくいの自重等
を加算できる。
算定方法は「学会基礎指針」による。
(2) 圧縮耐力
圧縮耐力は、式9-7・1により算定する。
R > P/A -------------------- 9-7・1
R:くいの許容鉛直支持力(kN/m2)
P:くい先端に作用する圧縮力(kN)
A:杭先端の断面積(m2)
くいの許容鉛直支持力は、くい体の許容圧縮応力度等から決まる許容圧縮力

37
及びくい先端の地盤の許容支持力のうち、いずれか小さいものとする。
許容圧縮力及びくい先端の地盤の許容支持力のうち、いずれか小さいものと
する。
ア くい体の許容圧縮力
くい体の許容圧縮力は、くい材の許容圧縮応力度に杭の最小断面積を乗
じた値以下とし、かつ、継手による低減及び長さ径比による低減を行う。
イ くい先端の地盤の許容支持力は、平成13年国土交通省告示第1113
号より算定する。
(3) 水平耐力
水平力を受けるくいについては、くい材の応力がその許容値をこえないこと、
かつ、くいの変位が上部構造に有害な影響を及ぼさないことを確認する。また、
くいが全長にわたってくいの回転あるいは横移動するような、地盤の破壊に対
して、安全であることを確かめる。
算定方法等は、「学会基礎指針」による。
なお、原則として、水平力はフーチングの側圧抵抗、底面の摩擦抵抗を期待
せず、くいにより抵抗させるものとし、また、くい頭は固定として算定する。
9-8 基礎スラブの設計
(1) 独立フーチング基礎
独立フーチングのせん断力及び曲げモーメントは、フーチングを柱脚の表面
及びその延長線において固定された4個の幅広な長方形片持梁からなるものと
して算定する。算定方法は、「学会基礎指針」及び「学会RC規準」による。
(2) くい基礎
くい基礎は、くいの反力を基礎スラブの底面に作用する集中荷重とし、(1)
に準じて算定する。
第10章 鋼材の防錆処理
10-1 溶融亜鉛めっき
鋼材は、コンクリート埋込部分を除き全て、JIS H8641 により、溶融亜鉛め
っきを施すものとする。
亜鉛の付着量は、次のとおりとする。
鋼材 550g/m2以上
中ボルト及び座金 350g/m2以上

38
10-2 塗装
航空法上の標識塗装が必要な場合及び周辺環境との色彩調和をはかる必要がある場合
は、亜鉛めっき面の上に塗装を行う。
また、重化学工業地帯や、海岸地区等の腐食環境が過酷な条件で使用される場合は、
亜鉛めっき面の上に塗装を行うことができる。
第11章 支線式鉄塔
11-1 鉄塔の形状
塔体は、正三角形断面のトラス構造又は、単一鋼管構造の三方向支線を標準とする。
ただし、大規模なもので、四方向支線とした方が有利な場合は、正方断面トラス構造
又は、単一鋼管構造の四方向支線としてよい。
11-2 部材計画
(1) 支線
支線は、塔体構造と支持点間隔のバランスを考慮し、段数を定め柱体に対す
る角度が、30度以上になるように設計する。
(2) 後方支線
アンテナ吊線等による特定方向に、相当な水平荷重を受ける場合は、それに
対抗する後方支線を設ける。
後方支線は、原則として、柱体に対する角度が40度以上になるように設計
する。
(3) 支線の付属物
ア 支線に付属する碍子、ターンバックル、シャックル、アンカーロッド等
は、支線に相当する耐力を有するものを使用する。
イ 金物類は、溶融亜鉛めっきを施す。
(4) 柱脚部の構造
柱脚部の構造は、塔体の揺れによる局部曲げ応力が生じないようにピン構造
とし、特に必要な場合を除き、塔体を基礎に埋込み又は、ボルト止め等はしな
いものとする。電波の送受信特性上必要がある場合は、所要の性能が得られる
よう、支線及び塔体に、高周波電気絶縁を施す。
(5) 電気的性能
電波の送受信特性上必要がある場合は、所要の性能が得られるよう、支線及
び塔体に、高周波電気絶縁を施す。

39
11-3 付属構造物
梯 子
ア トラス構造の場合は、一つの面のトラス接点に水平材を設けて、梯子の
代わりとする。
イ 鋼管構造の場合は、ステップボルト又は、梯子を設ける。
11-4 材料
(1) 支線の材料
支線の材料は、JIS G3537の亜鉛めっき鋼撚線を標準とする。
ただし、特に必要な場合は、JSS(日本鋼構造協会)-9ストランドロー
プ、JSS-10スパイラルロープ及びJSS-11ロックドコイルロープ並
びに安全性を充分確かめた上で、化学繊維の絶縁ロープを使用してよい。
(2) 支線の許容応力度
支線に使用される構造用ワイヤーロープ及び定着部の許容耐力は、切断荷重
及び定着長さの1/3.5とし、短期応力に対する割増しは行わない。
11-5 応力の算定
塔体の応力は、塔体自体で受ける風圧力及び吊線等の荷重に対し支線の取付点を支持
点とする連続梁として、最も不利な方向について算定する。
支線の張力は、塔体及び支線で受ける風圧力及び吊線等の荷重の、最も不利な組み合
わせにより算定する。
支線の応力算定は、「学会塔状指針」の図式解法又は、略算法による。
11-6 風圧力
(1) 塔本体に対する風圧力は、自立式鉄塔に準じて算定する。
(2) 単一鋼管に対する風圧力は、付属物を考慮して、風力係数を1.2として算定
する。
(3) 支線に対する風圧力は、風力係数を1.2として算定する。
11-7 基礎
(1) 支線の基盤は、鉄筋コンクリート基礎とし、支線の張力に対し安全なように
設計する。
(2) 塔体の基礎は、柱脚部に作用する圧縮力及び水平力に対して安全なように設
計する。

40
第12章 付帯設備
12-1 避雷設備
20メートルを超える鉄塔に避雷針設備を設けるものとする。また、20メートル以
下であっても、襲雷頻度及び地形等に応じて設置を考慮する。
12-2 航空障害灯及び昼間障害標識
航空法第51条及び51条の二に該当するものは、航空障害灯及び昼間障害標識を設
置する。
12-3 登はん防止柵
鉄塔には、必要に応じて登はん防止柵を設ける。
12-4 表示板
鉄塔には、名称、高さ、位置、標高、完成年月日及び製造会社等を記入した表示板を
設ける。
12-5 作業用電源コンセント
鉄塔の踊場には、必要に応じて作業用電源コンセントを設ける。
12-6 転落防止装置
鉄塔には、墜落防止装置を設ける。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪ Kトラス形
逆Kトラス形
ブライヒ形
アンテナリング
鉄塔の高さ
節の高さ
節点間の番号
頂部塔体幅
リング直径
踊場直径
塔頂部
手摺
踊場
踊場支材
ブライヒ水平材
斜材
梯子垂直ラック
節点
主柱材用補助材
斜材用補助材
主柱材曲点
水平材
主柱材
柱脚
斜材
階段垂直ラック 裏組材
斜材
水平ブレス材
裏打斜材
裏打水平材
鉄塔各部名称図 (単位:m)
平面形状
水平ブレス
水平ブレス補助材
階段踊場
対辺材
中間平面
踊場外周材
振れ止め
踊場床
踊場平面
リング
振れ止め
垂直ラックリング平面
梯子
別図
-73-
別 図