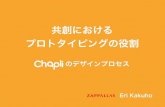車載品質への 設計の役割は大きい - Nikkan...第1章...
Transcript of 車載品質への 設計の役割は大きい - Nikkan...第1章...
第 1章 車載品質への設計の役割は大きい
8
設計力という言葉がここ数年、散見されるようになってきた。設計ではなく「設計力」である。もちろん現場力ほどにはまだポピュラーではないが、モノづくりにおいては設計力が現場力と同様に重要な役割を果たしていることは言うまでもない。設計力については、2009 年に出版した拙著『「設計力」こそが品質を決める―デンソー品質を支えるもう一つの力―』(日刊工業新聞社刊)に詳しく著したが、その中では筆者が培った車載製品の開発設計の経験を基に、他の分野の開発設計にも通じる普遍的な内容に置き換えて解説している。実は、この設計力と本書で取り上げるデザインレビューとは表裏一体の関係にある。この理解を促すことが本書の目的である。従って、第 1章から第 3章では設計力について、第 4からは設計力を踏まえたデザインレビューについて述べる。
1―1 あってはならない重致命故障
車載品質が厳しいのは当然のことである。従って、そこで用いられる設計力は車載品質の厳しさにふさわしいものでなければならない。そこで、設計力に入る前に車載品質について触れる。 車は多くの機能から成り立っている(図 1.1)。走る、曲がる、止まると言った基本機能以外に安全、快適、利便、環境とさまざまな機能を併せ持っている。安全では最近注目されているシステムにプリクラッシュセーフティシステムがある。前方の車に接近しすぎると自動的に減速し、ブレーキもかかるシステムである。快適ではやはりオートエアコンが挙げられるであろう。利便では高速道路の自動料金システム ETC(Electronic Toll Collection System)、やカーナビゲーションシステム(情報通信)、環境では燃費向上や CO2 削減に効果があるハイブリッドシステムや 2014 年 12 月に量産車として初めて市場に出すと自動車メー
9
カが発表している燃料電池システムなどさまざまなシステムがある。 このように車は多くの機能を併せ持って安全・快適な移動空間を実現している。しかし、どの機能一つを取り上げても一旦故障すると人命に直結する可能性が高い。このような人命に関係する故障は“重致命故障”と呼ばれ、代表的な故障にOR(暴走)、FH(火災)がある。もちろん重致命故障は起こしてはいけないし、絶対に起こさないようにモノづくりに取り組むわけである。
1―2 市場環境は過酷で期間は長い
ところが車はさまざまな環境下で使用されている。図 1.2に示すように、北極圏のような極寒の地、逆に炎熱の砂漠のような酷暑の地、そのような特殊な環境ではなくても延々と坂道を登る場合、特に負荷大の状態での登坂路は車にとって厳しい。また、最近では日本も局地的な集中豪雨で道路が冠水し、渡河もどきの環境を経験された方もいるであろう。このように車はさまざまな環境下に曝されるのであるが、これはさまざまなストレスに曝されるということを示している。 図 1.3にストレスの例を示す。温度・振動は言うまでもなく、湿度・
図 1.1 車は多くの機能から成り立っている
止まる
走る
安全
曲がる
快適
利便
環境 重致命故障OR/FH
第 1章 車載品質への設計の役割は大きい
10
水没・オイル浸漬・塩害・飛石や電気的ノイズ・EMC(Electro-Magnetic Compatibility)など、実に多くのストレスに曝される。例えば温度は-40 ℃~150 ℃にもなる。むろん車が使用される地域や車種、車の部位によって異なるがトランスミッション内部に使用される製品では 150 ℃に耐えねばならない場合もある。一概に 150 ℃と言ってもこれはとてつもなく厳しい環境である。例えば 150 ℃で使える樹脂材料を考
振動
水
塩害 EMC
温度 湿度オイルなど
サージ電圧
図 1.3 車載製品はさまざまなストレスに曝される
図 1.2 車はさまざまな環境で使用される
11
えると厳しさが分かる。高機能エンジニアリングプラスチックに分類される樹脂材料で特に高価な材質を除くと、使用可能な樹脂材料は PPS(Polyphenylene Sulfide)など一部に限られる。実際、モノづくり、特に開発設計はその製品の使われる環境が 100 ℃を超えると急カーブで難しさは増してくる。筆者の経験から 100 ℃を越えると、10 ℃上がるごとに 2乗倍から 3乗倍で難しくなる(図 1.4)。 一方、車が市場で使われる期間を見てみる。図 1.5に示すように 10年経っても半分以上の車が市場で使われている。20 年経過しても何割かの車はまだ活躍しているのである。当然「20 年も経った車だから重致命故障を起こしてもしかたがない」とはならない。車が過酷なストレスの下に長期間曝される(以下過酷な環境と呼ぶ)のだから、搭載されている製品もしかりである。しかし、厳しい環境のもとでも人命に関わる故障は絶対に起こしてはいけないのである。従って、車載製品の開発設計目標期間は長くなる。例えば 12 年 20 万 km、さらに 16 年 30 万kmなどが掲げられる。 人命に影響を与える故障は、車が使われている限り 20 年以上でも
140
(℃)
120各部の最高温度(例) 100
60
80
トランスミッション
吸気マニホールド
室内床面 車室内
エンジンルーム
図 1.4 車載製品の温度環境は厳しい