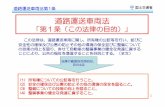運賃・料金の額の範囲について - Kintetsu Bus運賃・料金の額の範囲について 上限額 下限額 大型車 中型車 小型車 大型車 中型車 小型車
自動車便覧平成24年8月現在 禁無断転載・複製 平成24年8月現在...
Transcript of 自動車便覧平成24年8月現在 禁無断転載・複製 平成24年8月現在...

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
びんらん
一般財団法人 関東陸運振興センター
自動車便覧
平成24年版

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
は し が き
この「自動車便覧」は、関東運輸局(旧東京陸運局)監修による「陸運要覧」の付録「自動車関係各
種申請早わかり」を引きついで、昭和47年に、当振興センター独自に編集スタートしたものであります。
また昭和54年には、当時の東京陸運局管内自動車標板協議会から一般ユーザー用として「自動車のしお
り」(後に「車の手続きガイド」に改訂)を刊行したのを機会に、内容、装幀ともに一新し、以後、毎
年改訂・増補を重ねてきております。
わが国の自動車保有台数は、平成24年3月末現在7,911万台になっております。
成熟度合を深めつつある「くるま社会」が今後、健全に、秩序ある発展をとげるためには、多くの自
動車に関する諸規定が正しく理解され、また法令に基づく諸手続が正確且つ迅速に行なわれることが必
要であります。
本書は、自動車関係に携わる各方面の方々に必携の手引書として、ご利用いただけるよう、複雑多岐
に亘る諸規定、諸手続をできるだけ平易に又具体的に解説してあります。
幸い発刊以来、各方面で広くご利用いただいておりますが、今後共当振興センターの事業の一環とし
て、常に内容を充実し、皆様にご満足いただけるよう努力する所存でございます。
当振興センターの自動車登録番号標交付事業をはじめ、各種の自動車ユーザーサービス業務ともども、
一層のご指導、ご協力をお願いする次第であります。
平成24年4月
一般財団法人 関東陸運振興センター

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
目 次 は じ め に………………………………………………………………………………………………………………………1
1 道路運送車両法…………………………………………………………………………………………………………………1
2 道路運送法………………………………………………………………………………………………………………………1
3 貨物自動車運送事業法…………………………………………………………………………………………………………2
4 貨物利用運送事業法……………………………………………………………………………………………………………2
5 自動車抵当法……………………………………………………………………………………………………………………2
6 自動車損害賠償保障法…………………………………………………………………………………………………………3
7 自動車の保管場所の確保等に関する法律……………………………………………………………………………………3
8 使用済自動車の再資源化に関する法律………………………………………………………………………………………3
Ⅰ 自動車の登録・検査申請・届出早わかり
1 登録自動車
1 新規登録申請・新規検査申請(新たに自動車を登録・検査する場合)………………………………………………9
2 変更登録申請・自動車検査証記入申請(登録自動車の所有者の住所等を変更した場合)…………………………14
3 移転登録申請・自動車検査証記入申請(登録自動車の所有者名義を他の者に変更する場合)……………………18
《相続(所有者の死亡)による登録》……………………………………………………………………………………21
4 更正登録申請・自動車検査証記入申請(登録した内容について錯誤、又は脱落がある場合)……………………24
5 抹消登録申請(登録自動車の使用を一時中止する場合、又は登録自動車を一時抹消輸出する場合、又は登録
自動車を滅失、解体、自動車の用途を廃止した場合)…………………………………………………………………25
6 登録事項等証明書の交付請求
(登録されている現在の内容の証明を受ける場合及び過去の履歴の証明を受ける場合)……………………………34
7 自動車登録番号の変更申請(ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合)………………………………35
8 自動車抵当権の設定、変更、移転、更正、抹消登録……………………………………………………………………36
9 諸再交付申請
(ナンバープレートの封印、自動車検査証、検査標章を紛失、破損、脱落等により再交付を受ける場合)………38
� 字光式自動車登録番号標の交付申請(光るナンバープレートを取りつける場合)…………………………………39
� 希望番号制について(関東運輸局管内のケース)………………………………………………………………………40
� 継続検査申請(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)……………………………44
� 自動車検査証記入申請・構造等変更検査(自動車の構造等に変更があった場合)…………………………………45
� 自動車検査証の記入申請
(自動車検査証の記載事項について変更があった場合で変更登録等を伴わない場合)………………………………47
� 保安基準関係…………………………………………………………………………………………………………………49
2 二輪の小型自動車
1 新規検査申請(250㏄を超えるオートバイを新たに検査を受けて使用する場合) …………………………………79
2 自動車検査証の記入申請(自動車検査証に記載されている事項に変更があった場合)……………………………81
3 自動車検査証の返納(自動車を廃車又は使用を中止する場合)………………………………………………………83
4 車両番号の変更(ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合)……………………………………………84
5 諸再交付申請(自動車検査証、検査標章を紛失、破損、脱落等により再交付を受ける場合)……………………86
6 継続検査申請(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)……………………………87
7 検査記録事項等証明書の交付請求(届出されている現在の内容の証明を受ける場合)……………………………88
3 軽自動車

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
A 検査対象軽自動車………………………………………………………………………………………………………………89
1 新規検査(検査対象軽自動車を新たに使用する場合)…………………………………………………………………89
2 検査証記入申請(検査証の記載事項に変更があった場合)……………………………………………………………91
3 自動車検査証又は限定自動車検査証の返納届(軽自動車を廃車又は使用を中止する場合)………………………93
4 自動車検査証又は限定自動車検査証及び検査標章の再交付申請
(検査証又は検査標章をき損、紛失等により再交付を受ける場合)……………………………………………………95
5 継続検査申請(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)……………………………96
B 検査対象外軽自動車……………………………………………………………………………………………………………97
1 使用の届出……………………………………………………………………………………………………………………97
2 軽自動車届出済証の記入申請(届出済証の記載事項に変更があった場合)…………………………………………99
3 他の都道府県から転入又は転出する場合 ………………………………………………………………………………100
4 軽自動車届出済証の返納(廃車又は使用を中止する場合) …………………………………………………………101
5 軽自動車届出済証の再交付申請 …………………………………………………………………………………………102
4 その他
1 OCRシート(申請書)の使用区分 ……………………………………………………………………………………103
2 軽OCRシート(申請書)の使用区分 …………………………………………………………………………………104
3 手数料一覧 …………………………………………………………………………………………………………………105
4 自動車登録番号標及び車両番号標の交付手数料及び頒布価格表 ……………………………………………………108
Ⅱ 自動車運送事業の免許等申請早わかり
1 定 義 ……………………………………………………………………………………………………………………111
2 許可基準 ……………………………………………………………………………………………………………………112
3 欠格事由 ……………………………………………………………………………………………………………………113
4 処理方針について …………………………………………………………………………………………………………114
5 許可申請書 …………………………………………………………………………………………………………………161
6 旅客自動車関係の運行管理者 ……………………………………………………………………………………………194
7 貨物自動車関係の運行管理者 ……………………………………………………………………………………………199
8 整備管理者 …………………………………………………………………………………………………………………203
9 重大事故の報告 ……………………………………………………………………………………………………………205
� 貨物利用運送事業法 ………………………………………………………………………………………………………207
� 貨物軽自動車運送事業 ……………………………………………………………………………………………………209
� 自家用自動車の貸渡の許可申請 …………………………………………………………………………………………210
Ⅲ 自動車の諸税早わかり
1 自動車重量税 …………………………………………………………………………………………………………………229
1 納税義務者 …………………………………………………………………………………………………………………229
2 課税対象車 …………………………………………………………………………………………………………………229
3 非課税及び車両総重量のないものとされている自動車 ………………………………………………………………229
4 納付時期及びその他 ………………………………………………………………………………………………………229
5 税 率 表 …………………………………………………………………………………………………………………231
2 自動車税 ………………………………………………………………………………………………………………………232
1 納税義務者 …………………………………………………………………………………………………………………232
2 課税対象車 …………………………………………………………………………………………………………………232

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3 非課税の範囲 ………………………………………………………………………………………………………………232
4 賦課期日 ……………………………………………………………………………………………………………………232
5 自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課及び還付 ……………………………………………………………232
6 納 期 ……………………………………………………………………………………………………………………232
7 月割税額表 …………………………………………………………………………………………………………………232
3 自動車取得税 …………………………………………………………………………………………………………………235
1 納税義務者 …………………………………………………………………………………………………………………235
2 課税対象車 …………………………………………………………………………………………………………………235
3 課税対象 ……………………………………………………………………………………………………………………235
4 非課税の範囲及び納税義務の免除 ………………………………………………………………………………………235
5 課税標準 ……………………………………………………………………………………………………………………235
6 税 率 ……………………………………………………………………………………………………………………236
7 免 税 点 ……………………………………………………………………………………………………………………236
8 納 期 ……………………………………………………………………………………………………………………236
9 納付方法 ……………………………………………………………………………………………………………………236
4 軽自動車税 ……………………………………………………………………………………………………………………237
1 納税義務者及び課税対象車 ………………………………………………………………………………………………237
2 非課税の範囲 ………………………………………………………………………………………………………………237
3 賦課期日等 …………………………………………………………………………………………………………………237
4 標準税率 ……………………………………………………………………………………………………………………237
5 身体障害者に対する減免 ……………………………………………………………………………………………………238
6 商品中古自動車に係る自動車税の軽減 ……………………………………………………………………………………239
7 平成24年度の税制改正の概要について ……………………………………………………………………………………240
Ⅳ 自動車損害賠償責任保険早わかり
1 契約締結の強制と保険会社の引受義務 …………………………………………………………………………………257
2 自賠責保険契約を締結しなくともよい自動車 …………………………………………………………………………257
3 自賠責保険契約を締結できない自動車 …………………………………………………………………………………257
4 自賠責保険証明書の備付義務 ……………………………………………………………………………………………257
5 車検期間と保険期間のリンク ……………………………………………………………………………………………257
6 保険標章(保険ステッカー)表示制度 …………………………………………………………………………………257
7 契約解除の制限 ……………………………………………………………………………………………………………257
8 政府の保障事業 ……………………………………………………………………………………………………………258
9 保険金の支払い ……………………………………………………………………………………………………………258
� 保険金の請求 ………………………………………………………………………………………………………………260
� 自動車損害賠償責任保険料表 ……………………………………………………………………………………………263
⑴ 営業用乗用自動車以外の保険料表
⑵ 営業用乗用自動車保険料表
Ⅴ 自動車の保管場所早わかり
1 証明書交付の申請手続き …………………………………………………………………………………………………267
2 法律適用地域一覧表 ………………………………………………………………………………………………………267
3 認定条件 ……………………………………………………………………………………………………………………268

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
附 録
1 運輸支局及び自動車検査登録事務所の管轄区域一覧(関東運輸局管内) …………………………………………271
2 全国運輸局、運輸支局の所在地及び支局等コード一覧 ………………………………………………………………272
3 サービスコードの見方 ……………………………………………………………………………………………………276
4 軽自動車検査協会事務所及び所在地一覧 ………………………………………………………………………………282
5 関東運輸局、及び管内運輸支局並びに軽自動車検査場案内図 ………………………………………………………285
6 自動車の種別 ………………………………………………………………………………………………………………293
7 自動車のナンバープレートの見方 ………………………………………………………………………………………294

1
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
は じ め に
この本は、道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法、自動車抵当法、並びに関連す
る諸法律の申請手続き等を収録して運輸支局、又は自動車検査登録事務所に申請書を提出するための利便をはかるととも
に、自動車関係条文等を記載して、より高度の知識を必要とする方々の参考書的役割をはたし、側面より運輸行政事務の
スピード化、合理化に資することを目的として発刊致しました。
自動車の数は日に日に増加しつつあり、これに伴い生ずる種々の問題は社会福祉の上にも重大な影響を与えることにな
るので、「くるま社会」の秩序ある規制は今後ますます強められることになるでしょう。自動車の運行に際しては、自動
車の運転者に対して交通の安全とその円滑化を求めて規制をしている道路交通法があり、自動車そのものについては道路
運送車両法、自動車損害賠償保障法の規制が基幹となり、これに付随して自動車の保管場所の確保等に関する法律、自動
車重量税法、自動車抵当法、地方税法(自動車税関係)が適用されていますが、以下主要法律の大要について記載しました。
1.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
この法律の主な目的は、⑴自動車について所有権の公証を行う、⑵自動車の安全性の確保及び公害の防止、並びに整備
技術の向上をはかり整備事業の健全な発達に資する、⑶自動車の流通社会を発展させ延いては公共の福祉に寄与すること
である。
⑴の自動車の所有権の公証については、自動車を一台毎に検査・登録する制度を採用した結果、道路運送車両法第4条
の行政登録として下記の効果を得られる。
ア.自動車使用の実態の把握ができること。
イ.自動車盗難の予防に役立つこと。
ウ.車両保安確保の手段となること。
又、これらの行政上必要とする登録制度を整備し、公示方法を採用することにより、車両法第5条の民事登録制度を同
時に活用して、動産である自動車を不動産的扱いとし、登記的な法律上次のような効果を得られる。
エ.所有権の得喪について第三者対抗力の付与
オ.自動車抵当法の利用
カ.所有権留保契約付譲渡が可能
以上が自動車の検査・整備とともに重要な柱となっている。
なお、自動車の登録は全国統一のコンピューターシステムでオンライン・リアルタイム方式で処理され、自動車に関す
る情報をOCRシートに記入して入力し、磁気ディスクに記憶させた後、自動車検査証を出力させて完了するものである。
2.道路運送法(昭和26年法律第183号)
この法律は道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保するとともに、道路運送に関する秩序を確立することによ
り、道路運送の総合的な発達を図り、それによって公共の福祉を増進することを目的としており、昭和26年6月に制定さ
れ、その後社会経済、その他諸情勢の著しい変化により、幾多の改正を経て現在に至っている。
旅客自動車運送事業は、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業及び無償旅客自動車運送事業等に大別され、
さらにそれぞれの運送形態により、次のように分類されている。
一般旅客自動車運送事業
イ.一般乗合旅客自動車運送事業
路線を定めて定期に運行する自動車により、乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
(乗合バス事業)

2
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ロ.一般貸切旅客自動車運送事業
イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業
(貸切バス事業)
ハ.一般乗用旅客自動車運送事業
1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
(ハイヤー、タクシー事業)
特定旅客自動車運送事業
(道路運送法の改正により昭和46年12月1日法律第96号から許可扱いとなる。)
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業
3.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及
びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事
業の健全な発展を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として平成元年12月制定され、平成2年12月1日か
ら施行された。
貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業に分類されている。
一般貨物自動車運送事業
従来の一般路線と一般区域を一本化したものです。このうち、特別積合せ貨物運送を行う事業者は、事業計画で、
その旨を明らかにすることになっています。
特定貨物自動車運送事業
従来の特定事業に対応したものです。
貨物軽自動車運送事業
従来の軽車両等運送事業に対応したものです。
4.貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)
この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図
るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を
確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的としており、平成元年12月19日(法律第82
号)に制定され、平成2年12月1日から施行された。
貨物利用運送事業は、利用者と運送事業者との間に立って両者を接続する業務を担うものであり、輸送のニーズが高度
化・多様化し、サービスの専門化が進むなかで、その果す役割も一段と高まってきていることから、従来の輸送機関別規
制から各種輸送機関の有機的な結合等により利用運送事業者の創意工夫を生かした事業活動が迅速かつ的確に行えるよう
横断的規制に見直しを行ったものである。
5.自動車抵当法(昭和26年法律第187号)
この法律は、道路運送車両法により民事的効力を付与された自動車の登録制度を利用して、自動車にも抵当権の公示制
度がこの法律により確立されることとなり、自動車を使用目的とした諸事業、特に道路運送法にもとづく自動車運送事業
の健全な発展と輸送の振興を期待し、金融の円滑の確保、自動車の割賦販売の促進に寄与することになる。即ち、この制
度は債務者、又は物上保証人が債務の担保に供した自動車を、そのまま使用しながら利益をあげて債務の弁済を続けるこ
とができ、債権者は債務者が弁済不能になった場合には、債権の優先的弁済を受けることができる制度である。

3
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
6.自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)
昭和29年3月末における我が国の自動車の保有台数は100万台を突破し、車両数の増加に伴い、自動車事故も急速に増
加した。事故による被害者のなかには、満足な補償も受けられずに悲惨な状態に置かれる人もあって社会上重大問題とな
りつつあった。自動車損害賠償保障法は、これら被害者の保護救済を目的とし、併せて自動車運送の健全な発達に資する
ために制定された。
この法律に規定されている主な保障制度は下記のとおりである。
⑴ 自動車損害賠償責任保険 (略称、自賠責保険)
⑵ 自動車損害賠償責任共済 ( 〃 責任共済)
⑶ 政府の自動車損害賠償保障事業 ( 〃 保障事業)
⑴の保険は、自動車(法第2条第1項)の運行に当り一台毎に保険会社(法第6条)と保険を締結して被害者の保護救
済をはかるものである。
⑵の保険は、農業協同組合、農業協同組合連合会(法第54条の3)と責任共済として保険を締結して、⑴と同一制度で
実施するものである。
⑶の事業は主に下記の三つに分けられる。
ア.ひき逃げの場合(法第72条第1項)
加害者が不明で法第3条の損害賠償の請求ができない場合、請求により定められた金額を保障する制度である。
イ.無保険の場合(法第72条第1項)
強制保険対象車でありながら保険を締結していなかった自動車の事故か、あるいは保険は締結してあったが自動
車が盗難にあったか、又は無断使用運転等での事故に対しては、被保険者の保有者責任が発生しないので、加害者
が被害者に直接損害賠償をしないときは、無保険と同様に取扱い、政府が保障事業から、てん補金を支払って加害
者から回収することになる。
ウ.法第10条(適用除外)のうちで、道路以外の場所のみで運行の用に供する自動車による事故も該当する。
自賠責保険では一定限度額までの補償であり、相手の財物や自車の損害は補償されないため、多くは自賠責保険の他に、
いわゆる自動車保険(⑴対人賠償保険、⑵対物賠償保険、⑶車両保険、⑷搭乗者傷害保険)に締結している。
7.自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)
この法律は、自動車の保有者等に保管場所を確保させ、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけると
ともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化及び道路交通の円滑化を図ることを目的と
しており、法律適用地域に使用の本拠の位置を有する自動車の新規、移転等の登録申請には、保管場所を確保しているこ
とを証する書面を添付しなければならないこととなっている。
又、関連法律として道路運送車両法第56条(自動車車庫に関する勧告)で自動車の点検、整備の環境条件の向上を図り、
自動車を常時保管するための施設を客観的に認識を付与したものである。
現在本条に基づき、乗車定員11人以上の自動車及び自動車運送事業用自動車の車庫について一般的勧告が行われている。
又、「国土交通省令」で定める技術上の基準は自動車点検基準第7条に定められており、車両の面積、洗車設備、検車
設備を備えて置くべき点検整備用工具について規定している。
8.使用済自動車の再資源化に関する法律(平成14年7月12日法律第87号)
年間400万台(中古車輸出を含めれば、約500万台)排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値
が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル等の処理が行われてきまし

4
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
た。他方、産業廃棄物最終処分場のひっ迫により、使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっ
ています。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低下・不安定な変動により、近年、従来のリサイクルシステム
は機能不全に陥りつつあり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じている状況にあります。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル等
の適正処理を図るため、自動車リサイクル法が成立し、平成14年7月に公布されました。同法は、平成17年1月1日に本
格施行されました。
自動車リサイクル法では拡大生産者責任の考え方に基づき、使用済自動車の処理行程で発生するフロン類、エアバック
類及びシュレッダーダストについて、自動車製造業者及び輸入業者(以下「製造業者等」という。)に対して引取り及び
リサイクル(フロン類については破壊)を義務付けます。それとともに、引取業者、解体業者等の関係者による使用済自
動車の引取り・引渡しのルールを定め、シュレッダーダスト等が製造業者等に確実に引き渡されるようリサイクルルート
を整備します。
製造業者等のリサイクルに充てる費用は、リサイクル料金として新車販売時(制度施行時の既販車は最初の車検時まで)
に自動車の所有者があらかじめ預託することとします。製造業者等の倒産・解散による減失を防ぐため、リサイクル料金
は資金管理法人が管理し、製造業者等はシュレッダーダスト等のリサイクルにあたりその払渡しを請求できることとしま
す。なおリサイクル料金はあらかじめ製造業者等が定めて公表し、不適切な料金設定に対しては国が是正を勧告する仕組
みとしています。
なお、この『自動車便覧』に関連する法律、規則等の略語は下記の通りであります。

5
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
〔略 語〕
車 両 法 道路運送車両法
車 両 法 施 規 道路運送車両法施行規則
登 規 自動車登録規則
登 令 自動車登録令
車 庫 法 自動車の保管場所の確保等に関する法律
実 施 要 領 自動車の検査等実施要領
重 量 税 法 自動車重量税法
自 賠 法 自動車損害賠償保障法
運 送 法 道路運送法
運 送 法 施 規 道路運送法施行規則
貨 物 運 送 法 貨物自動車運送事業法
利 用 事 業 法 貨物利用運送事業法
貨物運送法施規 貨物自動車運送事業法施行規則
利用事業法施規 貨物利用運送事業法施行規則
ダ ン プ 法 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
ダンプ法施規 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則
保 安 基 準 道路運送車両の保安基準
様 式 省 令 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令
登 免 税 法 登録免許税法
割 賦 法 割賦販売法
経 過 省 令 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
経 過 政 令 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
事 務 規 程 検査事務規程(検査対象軽自動車)
取 扱 細 則 検査事務取扱細則(検査対象軽自動車)
印 税 法 印紙税法
手 数 料 令 道路運送車両法関係手数料令
返 証 規 程 軽自動車検査協会自動車検査証返納証明書交付事務規程
自動車リサイクル法 使用済自動車の再資源化等に関する法律

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
Ⅰ 自動車の登録・検査申請・届出早わかり

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

�
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1 登録自動車
1 新規登録申請・新規検査申請(車両法第7条、第59条)
(新たに自動車を登録・検査する場合)
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第7条(新規登録の申請) 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、
その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条
に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提
出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
⑴ 車名及び型式
⑵ 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
⑶ 原動機の型式
⑷ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑸ 使用の本拠の位置
⑹ 取得の原因
2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関す
る証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
3 第1項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあっては、それぞれ当該各号に掲げる書面の提出をもっ
て当該自動車の掲示に代えることができる。
⑴ 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
⑵ 第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第4項の規定による完成検査終了証(発行
後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第2号において同じ。)
⑶ 第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第�4条の5第1項の規定による有効な保安基準適合証の交
付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。同
条第7項において同じ。)保安基準適合証
⑷ 第71条の2第1項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第�4条の5の2第1項の規定による有
効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
4 第1項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第�6条の2
から第�6条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供された
ときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもってそれぞれ当該各号に掲げ
る書面の提出に代えることができる。
⑴ 第33条第4項 譲渡証明書
⑵ 第75条第5項 完成検査終了証
⑶ 第�4条の5第2項 保安基準適合証
⑷ 第�4条の5の2第2項において準用する第�4条の5第2項 限定保安基準適合証
5 前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の申請書に記
載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会
するものとする。
6 第1項の申請は、新規検査の申請又は第71条第4項の交付の申請と同時にしなければならない。
第5�条(新規検査) 登録を受けていない第4条に規定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けて
いない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の

10
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けな
ければならない。
2 新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなけ
ればならない。
3 国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求める
ことができる。
4 第7条第3項(第2号に係る部分に限る)、第4項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、第1項の場合
に準用する。
OCRシート第1号様式 ○ ○ ○ ○※△は諸元に変更があるものは必要。登録申請人(所有者)本人が直接申請する場合は実印を押印。検査申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。
登令第15条
様式省令第2条第1項 第2号様式 △ △ ○
手数料納付書 ○ ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(105頁参照)を貼付 車両法施規第6�条
完成検査終了証 ○
発行されてから9か月以内のもの。※完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証※預託済証明印の押印を受けること
車両法第7条第3項2号第75条第4項
登録識別情報等通知書 ○一時抹消登録申請時に交付されたもの 車両法施規第36条第3項
車両法第18条の3登規第6条の1�
◦自動車通関証明書◦完成検査終了証◦排出ガス検査終了証◦輸入車特別取扱自動車届出済書
○輸入の事実を証明する書面(輸入の自動車の場合に限り必要)※預託済証明印の押印等を受けること
関税法第67条、自管第1�号の1 H7.3.16 (通達)車両法第7条、登規第6条
譲渡証明書 ○ ○ ○ ○ 譲渡人は実印を押印。譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要
車両法第7条、第33条登規第6条
印鑑(登録)証明書 注1 ○ ○ ○ ○ 発行されてから3ヶ月以内のもの(所有者) 登令第16条
委任状 ○ ○ ○ ○
所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)実印を押印。使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
登令第14条第1項第3号
自動車保管場所証明書 ○ ○ ○ ○自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)①使用者のもの ②証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
車庫法第4条
必 要 書 類
新車中古車新規
輸入車新規
説 明 欄 参 考 条 文型式指定新規
持込新規

11
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
新車中古車新規
輸入車新規
説 明 欄 参 考 条 文型式指定新規
持込新規
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)
○ ○ ○ ○
①使用者が個人の場合・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの) ②使用者が法人の場合・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)
(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号(18.1.30)
使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要)
○ ○ ○ ○
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号(18.1.30)
自動車予備検査証 ○ ○ ○保安基準に適合していることが確認できる書面 有効な自動車予備検査証(交付を受けた自動車の場合に限り必要)
車両法第71条
自動車検査票 ○ ○ ○保安基準に適合していることが確認できる書面 合格印のある自動車検査票(持込み検査を受ける場合に必要)
実施要領 3−3−1
点検整備記録簿 ○ 提示する。 車両法第5�条第3項
保安基準適合証 ○乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合証(保安基準適合証は指定整備を行ったものについてのみ必要)
車両法第�4条の5 〃 5の二
自動車重量税納付書 ○ ○ ○ ○ 所定の重量税印紙(22�頁参照)を添付 重量税法第8条、第10条
自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条
自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照)
地方税法第152条 第6��条の11
自動車登録番号標交付通知書 ○ ○ ○ ○登録手続き終了後、登録事項等通知書とともにナンバー交付所に提示してナンバープレートの交付を受け、それを当該自動車に取りつけ、封印の取りつけを受ける。
車両法施規第4条74東陸整登資第4号 (4�.2.8)
注1 印鑑証明書の取扱について①申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付②申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので
氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす③申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実
印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付
④登録令第14条第1項第2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面(民法108条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)

12
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
所有者と使用者が異なる場合
使用者の住所を証するに足りる書面
(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要)
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号(18.1.30)
土砂等運搬大型自動車使用届出書
申請者は使用者。輸送課に提出する。
ダンプ法第3条第1項ダンプ法施規第1条
大型自動車(大型ダンプ)の場合 事業証明書
経営する事業の種類 呈示を求める書類等
建設業砂利採取業採石業砕石業
砂利販売業
その他
建設業法による許可書の写し砂利採取法による登録の写し採石法による登録の写し大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、又は、砕石のための設備に係る登記簿謄本等砂利の山元、又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、又は商工会議所、市町村等による事業内容証明書、若しくは納税証明書(事業税)廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、又は生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等
「ダンプカー使用事業者の協業化の促進及びダンプカーの使用の届出の取扱等について」(依命通達)自貨第163号(54.11.27)
事業用自動車又は貸渡自動車の場合
事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書及び手数料納付書にそれぞれ輸送担当部署の経由印が必要。
自家用バスの場合 整備管理者選任届及び使用上の誓約書
整備管理者の略歴書を添付して整備課に提出する。
車両法第52条車両法施規第33条
改造自動車の場合
改造自動車等審査結果通知書
あらかじめ改造自動車等届出書を運輸局又は自動車検査独立行政法人に提出して審査を受け、「改造自動車等審査結果通知書」の交付を受けて検査を受けるときに添付する。
「改造自動車等の取扱いについて」(依命通達)自技第23�号(7.11.21)
爆発性液体を運搬するため、車台にタンクを固定した自動車の場合
タンク証明書又はその写し 市町村長等の行う完成検査に合格したことを証する書面(タンク証明書)を提示する。
消防法第11条第5項実施要領3−2−2
・道路運送車両の保安基準の緩和又は緩和制限を受けた自動車
・危険物を運搬する自動車 ・付属装置付自動車 ・トラック・トラクタ ・タンク自動車
OCRシート第7号様式 検査証備考欄に記載を要する申請の場合に必要
様式省令第2条「道路運送車両の保安基準の緩和認定の取扱要領について」関整車第1812号(平成9年9月26日)
*上記書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。
⑤申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付

13
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
・被けん引車 OCRシート第8号様式 検査証備考欄にけん引車の車名・型式を記載する場合に必要
様式省令第2条
保安基準第31条第2項の自動車(排出ガス規制)
排出ガス検査終了証又は排出ガス試験成績表
排出ガス規制に適合しているかどうか判定する。
施行規則第36条
保安基準第30条第2項又は第31条第5項、第7項若しくは第14項の規定により国土交通大臣の指定を受けた自動車
適合することを証する書面 諸規定に適合しているかどうか判定する。 施行規則第36条
臨時乗車定員 臨時乗車定員を定めた旨の書面
実施要領3−2−3
土砂等運搬車以外のダンプ車
比重証明書物品積載装置の仕様届出書
比重証明書は官公署等の発行した証明書が必要である。
高圧ガス運搬車容器証明書 高圧ガス(LPガスを含む。)を運搬す
るタンク車は、容器証明書の提示が必要である。
高圧ガス取締法第44条実施要領4−11−3
高圧ガスを燃料とする自動車
⒈LPガス改造自動車完成検査表(改造車)
⒉LP改造車ガス燃料装置点検整備記録簿(中古車)
高圧ガスを燃料とする自動車には、LPガス自動車完成検査表又は点検整備記録簿のいずれかが必要である。
「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする自動車の構造取扱基準について」関整車第1118号関整整第108号関整事公第110号 (63.4.20)
緊急自動車
緊急自動車の指定申請済証明書又は届出済証明書等
⒈緊急自動車は、すべて公安委員会による指定又は公安委員会への届出が必要である。
⒉緊急自動車指定申請済証明書又は届出済証明書等とは使用者等が公安委員会に指定又は届出申請中である旨の書面で差支えない。
⒊前記証明書等の提出があった場合には、保安基準第1条第1項第13号の緊急自動車として検査する。
道路交通法施行令第13条「緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いの変更について」自車第1113号(53.11.27)78東陸整車乙第506号 (53.11.30)
道路維持作業用自動車
道路維持作業用自動車の指定申請済証明書又は届出済証明書等
⒈道路維持作業用自動車は、すべて公安委員会による指定又は公安委員会への届出が必要である。
⒉道路維持作業用自動車指定申請済証明書又は届出済証明書等とは、使用者等が公安委員会に指定又は届出申請中である旨の書面で差支えない。
⒊前記証明書等の提出があった場合には、保安基準第1条第1項第13号の2の道路維持作業用自動車として検査する。
道路交通法施行令第14条の2
「緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いの変更について」自車第1113号(53.11.27)78東陸整車乙第506号 (53..11.30)
希望番号を事前に予約している場合
希望番号予約済証 希望番号を事前に予約している場合に必要(40頁参照)
字光式番号標を希望する場合
字光式番号標交付願簿 字光式番号標を希望する場合に必要(3�頁参照)
局通達72東陸整登資第63号72東陸整車第627号72東陸整整第204号

14
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
2 変更登録申請・自動車検査証記入申請(車両法第12条、第67条)
(登録自動車の所有者の住所等を変更した場合)
変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第12条(変更登録) 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若
しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由のあった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変
更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請
をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請
は、同時にしなければならない。
3 第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条(第3号及び第4号に係
る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4 第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変
更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証
の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時
期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本
拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があった場合については、適用しない。
3 国土交通大臣は、第1項の変更が運輸省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれ
があると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受ける
べきことを命じなければならない。
4 第5�条第3項及び第62条第2項の規定は、構造等変更検査について準用する。
必 要 書 類
所有者 (使用の本拠の位置の変更)
使用者の住所を変更した場合
(使用の本拠の位置の変更)
使用者を変更した場合
た場合
使用の本拠の位置のみを変更し
(フレーム交換した場合)
車台番号を変更した場合
乗せ換えた場合
場合及び型式の違った原動機を
自動車を改造して型式が変った
説 明 欄 参 考 条 文
氏名・名称を変更した場合
住所を変更した場合
OCRシート 第1号様式 ○ ○ ○ ○ ○
型式、若しくは原動機の型式又は自動車の諸元(構造)関係の変更を伴う申請の場合は第2号様式を使用し、その他の場合は第1号様式を使用する。登録申請人
(所有者)本人が直接申請する場合は押印。検査申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。
登令第15条
様式省令 第2条第1項又は 第2号様式 ○ ○
手数料納付書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(105頁参照)を貼付 車両法施規第6�条
変更事項が確認できる書面 ○ ○ ○
下記参照 注1 国自管第166号国自技第232号
(H18.1.30)登録令第14条

15
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
所有者 (使用の本拠の位置の変更)
使用者の住所を変更した場合
(使用の本拠の位置の変更)
使用者を変更した場合
た場合
使用の本拠の位置のみを変更し
(フレーム交換した場合)
車台番号を変更した場合
乗せ換えた場合
場合及び型式の違った原動機を
自動車を改造して型式が変った
説 明 欄 参 考 条 文
氏名・名称を変更した場合
住所を変更した場合
使用者の住所を証するに足りる書面
(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
○
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人 ⒜商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書⒝本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規第38条、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録の同時申請の場合は不要)
○※
○ ○ ○
①新使用者のもの ②概ね1ヶ月以内 ③使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更登録は必要であるが、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。 ④変更の原因が住居表示の変更のみの場合は不要 ※所有者、使用者が異なるときは不要
車庫法第4条
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)
○
①使用者が個人の場合・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)②使用者が法人の場合・商業登記簿謄
(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)自管第73号 (45.5.22)
フレーム販売証明書フレーム交換(打刻塗まつ)許可書、理由書、顛末書等
○フレーム販売証明書は販売店で発行。申請者は所有者で押印が必要。車台番号のき損等により提出を求められる場合がある。
車両法 第31条、第32条登令第40条
点検整備記録簿 ○ 提示する。 車両法第67条第4項
改造自動車等審査結果通知書 ○
改造自動車等届出書を提出し、運輸局又は自動車検査独立行政法人より通知の交付を受け検査を受けるときに添付する。
自車第256号 (42.4.4)
委任状 注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)が押印。使用者の委任状
(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
登令第14条 第1項第3号

16
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
所有者 (使用の本拠の位置の変更)
使用者の住所を変更した場合
(使用の本拠の位置の変更)
使用者を変更した場合
た場合
使用の本拠の位置のみを変更し
(フレーム交換した場合)
車台番号を変更した場合
乗せ換えた場合
場合及び型式の違った原動機を
自動車を改造して型式が変った
説 明 欄 参 考 条 文
氏名・名称を変更した場合
住所を変更した場合
自動車検査証 注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提出する。限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証
車両法 第67条第1項
自動車予備検査証 ○ ○ ○保安基準に適合していることが確認できる書面 有効な自動車予備検査証(交付を受けた自動車の場合に限り必要)
車両法第71条
自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条
自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・
235頁参照)地方税法第152条
登録識別情報 注3 ○ ○ 電子的に提供するか、OCRシートへの記載が必要
車両法第18条の3登規第6条の1�
注1 変更事項が確認できる書面の取扱について①所有者又は使用者が個人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる
住民票又は外国人登録原票記載事項証明書。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要
②所有者が個人の場合で氏名の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
③所有者又は使用者が法人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要
④所有者が法人の場合で名称の変更の場合(合併・分割を除く)・発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
⑤住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 ・個人…市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 ・法人…商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請があっ た場合、登記の変更を促した上で受理する。⑥使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の
場合は不要) ○個人 ・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び
住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) ○法人 ・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) ・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続
的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
⑦上記の各書面は、所有者にかかるものは原本を提出、使用者にかかるものは写しで可とする。市区町村の発行した住居表示の 変更の証明書は写しで可とする
(注)所有者と使用者が異なる場合はそれぞれの書類が必要となります。
注2 登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更を行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は、使用者の委任状、自動車検査証は不要。
注3 登録識別情報の通知を受けているものに限り必要。

17
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
届出事項変更届出書 使用者の氏名・名称及び住所等を変更した場合、又は使用者変更した場合に必要。使用者変更の場合には、旧使用者の使用廃止届出書も添付する。
ダンプ法第3条第3項ダンプ法施規第2条
土砂等運搬大型自動車使用届出書
ダンプ法第3条第1項 第5条ダンプ法施規第1条 第7条
大型自動車(大型ダンプ)の場合 事業証明書
経営する事業の種類 呈示を求める書類等
建設業砂利採取業採石業砕石業
砂利販売業
その他
建設業法による許可書の写し砂利採取法による登録の写し採石法による登録の写し大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、又は砕石のための設備に係る登記簿謄本等砂利の山元、又は買主との売買契約書、又は仮契約書の写し、又は商工会議所、市町村等による事業内容証明書、若しくは納税証明書(事業税)廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、又は生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等
「ダンプカー使用事業者の協業化の促進及びダンプカーの使用の届出の取扱等について」(依命通達)自貨第163号(54.11.27)
事業用自動車又は貸渡自動車の場合
事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書及び手数料納付書にそれぞれ輸送担当部署の経由印が必要
ナンバー変更を伴う場合
自動車登録番号標交付通知書
登録手続き終了後、登録事項等通知書とともにナンバー交付所に提示してナンバープレートの交付を受け、それを当該自動車に取りつけ、封印の取りつけを受ける。
車両法施規第4条74東陸整登資第4号 (4�.2.8)
◦道路運送車両の保安基準の緩和又は緩和制限を受けた自動車
◦危険物を運搬する自動車◦付属装置付自動車◦トラック・トラクタ◦タンク自動車
OCRシート第7号様式 検査証備考欄に記載を要する申請の場合に必要
様式省令第2条「道路運送車両の保安基準の緩和認定の取扱要領について」関整車第1812号
(平成9年9月26日)
◦被けん引車 OCRシート第8号様式 検査証備考欄にけん引車の車名・型式を記載する場合に必要
様式省令第2条
*前項の書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。

18
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
売買による移転
(所有権解除)
割賦完済による移転
相続による移転
会社合併による移転
分割による移転
判決による移転
説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート 第1号様式 (専用2号様式)
○ ○ ○ ○ ○ ○登録申請人(新所有者・旧所有者)本人が直接申請する場合は実印を押印。記入申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。
登令第15条様式省令 第2条第1項
手数料納付書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(105頁参照)を貼付 車両法施規第6�条
譲渡証明書 ○ ○ ○新旧所有者を記入し、旧所有者は実印を押印する。(分割の場合は、事実が確認できる商業登記簿謄(抄)本及び分割計画書又は分割契約書の写しで当該自動車が特定できる場合は不要)
車両法第33条
印鑑(登録)証明書注1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 発行されてから3ヶ月以内のもの(新旧所有者の印鑑
(登録)証明書)登令第16条
①相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
②遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
③遺産分割に関する調停調書④遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
⑤判決謄本(確定証明書付)⑥申請人である相続人の実印
を押印した遺産分割協議成立申立書(申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限る) ・民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと及びその年月日を記載 ・申立書による申請の同意を得ていること及びその年月日を記載
○ ○
必要書類のうちいずれかの書面(判決による場合は、判決正本(確定証明書付き、場合によっては執行文 ①原本提示の上、写しを添付))
民法第�07条登令第14条
戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書 ○
〔上記のうち①を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの。②③④⑤を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認できるもの。⑥を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と申請人である相続人の関係が証明できるもの〕
民法第�07条登令第18条
3 移転登録申請・自動車検査証記入申請(車両法第13条、第67条)
(登録自動車の所有者名義を他の者に変更する場合)
変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第13条(移転登録)新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新
所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条第1号若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る
自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければらならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
4 第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 1登録自動車の2(14頁)を参照。

1�
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
売買による移転
(所有権解除)
割賦完済による移転
相続による移転
会社合併による移転
分割による移転
判決による移転
説 明 欄 参 考 条 文
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 ○ 合併の事実が証明できる書面 商法第101条
第102条
委任状 ○ ○ ○ ○ ○ ○所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)実印を押印。使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
登令第14条 第1項第3号
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録の同時申請の場合は不要)
○ ○ ○ ○
①新使用者のもの ②概ね1ヶ月以内 ③使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更登録は必要であるが、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
車庫法第4条
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
(使用の本拠の位置が変更になり使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)
○ ○ ○
①使用者が個人の場合・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)②使用者が法人の場合・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)
(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車 両 法 施 規 第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)自管第73号 (45.5.22)
自動車検査証 注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有効期間内のものを(抹消登録と同時申請の場合を除く)提示する。
車両法 第67条第1項
自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条
自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条
第6��条の11
登録識別情報 注3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 電子的に提供するか、OCRシートへの記載が必要 車両法第18条の3登規第6条の1�
注1 印鑑証明書の取扱について①申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付②旧所有者が海外へ転出し印鑑(登録)証明書が発行されない場合は、自動車検査証住所から海外転出までの住所のつながりが証
明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」及び在外日本大使館、領事館及び外国官憲が証明したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明、拇印証明書等であれば印鑑証明書と見なす
③申請人(新旧所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす
④申請人(新旧所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付
⑤登録令第14条第1項第2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面(民法108条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録又はその写し。なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)
⑥申請者(旧所有者)が破産管財人による場合は裁判所の許可証(写しでも可)、車両価格100万円以下である場合は当該価格が確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等若しくは破産管財人の申立書(申請した自動車は破産法第78条第2項に規定する裁判所の許可を受けている旨又は破産法第78条第3項に該当し裁判所の許可が必要ない旨を記載)を添付
⑦新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、
「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付
⑧旧所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、
「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付
注2 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は、使用者の委任状、自動車検査証は不要
注3 登録識別情報の通知を受けているものに限り必要

20
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
新所有者と使用者が異なる場合
使用者の住所を証するに足りる書面
(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規第38条、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号(18.1.30)
所有者が未成年者の場合 親権者又は後見人の同意書若しくは承諾書
戸籍簿謄抄本及び印鑑証明書の添付が必要。
民法第818条、第838条登令第14条第1項第2号
旧所有者の氏名、若しくは名称、又は住所の変更を伴う場合
戸籍簿謄抄本、住民票、又は登記簿謄抄本等
変更事項が確認できるもの。 登令第18条 第24条
譲渡人と譲受人との代表者(取締役も含む)が同一人である場合
取締役会議事録等 法人(代表者)から個人、個人から法人(代表者)も同様。
会社法第356条、第365条
土砂等運搬大型自動車使用届出書
使用者が変更した場合に必要。旧使用車の使用廃止届出書も添付する。
ダンプ法第3条第1項・第5条、ダンプ法施規第1条・第7条
大型自動車(大型ダンプ)の場合 事業証明書
経営する事業の種類 呈示を求める書類等
建設業砂利採取業採石業砕石業
砂利販売業
その他
建設業法による許可書の写し砂利採取法による登録の写し採石法による登録の写し大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、又は砕石のための設備に係る登記簿謄本等砂利の山元、又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、又は商工会議所、市町村等による事業内容証明書、若しくは納税証明書(事業税)廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、又は生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等
自貨第163号(54.11.27)「ダンプカー使用事業者の協業化の促進及びダンプカーの使用の届出の取扱等について」(依命通達)
事業用自動車又は貸渡自動車の場合
事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書及び手数料納付書にそれぞれ輸送担当部署の経由印が必要。
自家用バスの場合 整備管理者選任届及び使用上の誓約書
整備管理者の略歴書を添付して整備課に提出する。
車両法第52条車両法施規第33条
ナンバー変更を伴う場合自動車登録番号標交付通知書
登録手続き終了後、登録事項等通知書とともにナンバー交付所に提示してナンバープレートの交付を受け、それを当該自動車に取りつけ、封印の取りつけを受ける。
車両法施規第4条74東陸整登資第4号 (4�.2.8)
・道路運送車両の保安基準の緩和又は緩和制限を受けた自動車
・危険物を運搬する自動車・付属装置付自動車・トラック・トラクタ・タンク自動車
OCRシート第7号様式 検査証備考欄に記載を要する申請の場合に必要
様式省令第2条「道路運送車両の保安基準の緩和認定の取扱要領について」関整車第1812号(平成9年9月26日)
・被けん引車 OCRシート第8号様式 検査証備考欄にけん引車の車名・型式を記載する場合に必要
様式省令第2条
*前項の書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。

21
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1 相続の開始
相続は、車の所有者の死亡によって開始する(民法第
882条)。相続開始の効力は相続開始の時から発生し、この
時点で相続人の資格範囲および順位が決定する。
2 相続の開始場所
相続は被相続人の住所において開始する(民法883条)。
3 相続の順位
相続の順位は次の順位による。
第1順位 子及びその代襲者
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹及びその代襲者
配偶者は常に相続人になる(民法第887条、第8�0条)。
代襲相続とは、相続人になるべき子が相続開始以前に
死亡、欠格、又は廃除によって相続権を失った場合には、
その者の子が同順位で相続人となる。兄弟姉妹が相続人
である場合も同様に認められる。これを代襲相続という。
4 申請書作成上の注意事項
⑴ 共同相続による申請をするか、単独相続による申請
をするか決めること。
⑵ 相続の順位により、相続人をたしかめること。
⑶ 相続人に未成年者が含まれているか否をたしかめる
こと(親権者が代理行為をする)。
⑷ 親権を行使するさい利益相反行為となるときは特別
代理人を選任すること(家庭裁判所に申立請求をする)。
《相続(所有者の死亡)による登録》
〔相続による自動車の各種登録の具体例及び申請に必要な主な書類〕
父死亡 被
相続人
父()甲
()甲()乙
()乙
相続人
配偶者
長男A
長女B
次男C
(被相続人)
長男A
配偶者
長女B
次男C
(未成年者)
父死亡 被
相続人
父()甲
()甲()乙
()甲()乙
相続人
配偶者
長女B
次男C
(長男Aの代襲者)
孫E孫F孫G
(被相続人)
長男A
父
の死亡前に
に死亡した。
配偶者
孫E
孫F
孫G
配偶者
長女B
次男C
⎝⎛
⎠⎞
⎭⎬⎫未成年者
相 続 例 1 相 続 例 2
⒜共同相続の場合
イ主な申請書類
ア)戸籍謄本
被相続人の死亡、被相続人と申請人の関係が全て証
明できるもの
注:被相続人父�甲及び長男Aに対するもの
イ)印鑑証明書(相続人全員)
ただし、未成年者の相続人について、印鑑証明書の
交付を受けられない場合には住民票及び親権者の印
鑑証明書
ロその他の必要書類
移転登録申請(18頁参照)
⒜共同相続の場合
イ主な申請書類
ア)戸籍謄本
被相続人の死亡、被相続人と申請人の関係が全て証
明できるもの
イ)印鑑証明書(相続人全員)
ただし、未成年者の相続人について、
印鑑証明書の交付を受けられない場合には住民票及
び親権者の印鑑証明書
ロその他の必要書類
移転登録申請(18頁参照)

22
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⒝共同相続後即第三者へ譲渡する場合
イ主な申請書類
ア)相続例1のb項参照
ロその他の必要書類
移転登録申請(18頁参照)
⒞共同相続後即抹消登録(廃車)する場合
イ主な申請書類
ア)b項に同じ
ロその他の必要書類
抹消登録申請(25頁参照)
⒟単独相続の場合
イ主な申請書類
ア)戸籍謄本
被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全
て証明できるもの
〔注〕:被相続人父�甲及び長男Aに対するもの
イ)印鑑証明書(相続人)
ウ)遺産分割協議書
注:他の相続人が相続を放棄した場合は相続放棄申述書
ロその他の必要書類
移転登録申請(18頁参照)
ハ相続する自動車の価格が100万円以下であることを確
認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し
等を添付した場合
ア)戸籍謄本
被相続人の死亡、被相続人と申請人である相続人の
関係が証明できるもの
イ)印鑑証明書(相続人)
ウ)遺産分割協議成立申立書
・民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと
及びその年月日を記載
・申請書による申請の同意を得ていること及びその
年月日を記載
エ)その他の必要書類
移転登録申請(18頁参照)
⒠単独相続後即第三者へ譲渡する場合
イ主な申請書類
ア)相続例1のe項参照
ロその他の必要書類
⒝共同相続後即第三者へ譲渡する場合
イ主な申請書類
ア)a項(共同相続)の申請書類に、さらに、相続人
全員の印鑑証明書
ロその他の必要書類
移転登録申請(18頁参照)
⒞共同相続後即抹消登録(廃車)する場合
イ主な申請書類
ア)b項に同じ
ロその他の必要書類
抹消登録申請(25頁参照)
⒟単独相続の場合
イ主な申請書類
ア)戸籍謄本
被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全
て証明できるもの
イ)印鑑証明書(相続人)
ウ)遺産分割協議書
注:他の相続人が相続を放棄した場合は相続放棄申述書
ロその他の必要書類
移転登録申請(18頁参照)
ハ相続する自動車の価格が100万円以下であることを確
認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し
等を添付した場合
ア)戸籍謄本
被相続人の死亡、被相続人と申請人である相続人の
関係が証明できるもの
イ)印鑑証明書(相続人)
ウ)遺産分割協議成立申立書
・民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと
及びその年月日を記載
・申請書による申請の同意を得ていること及びその
年月日を記載
エ)その他の必要書類
移転登録申請(18頁参照)
⒠単独相続後即第三者へ譲渡する場合
イ主な申請書類
ア)d項(単独相続)の申請書類に、さらに、相続人
の印鑑証明書

23
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
移転登録申請(18頁参照)
⒡単独相続後即抹消登録(廃車)する場合
イ主な申請書類
ア)e項に同じ
ロその他の必要書類
抹消登録申請(25頁参照)
【注】親権を行使するさい、利益相反行為となるときは特別代理人を選任すること。(家庭裁判所に申立請求する)
ロその他の必要書類
移転登録申請(18頁参照)
⒡単独相続後即抹消登録(廃車)する場合
イ主な申請書類
ア)e項に同じ
ロその他の必要書類
抹消登録申請(25頁参照)

24
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
及び住所の更正
氏名または名称
車台番号の更正
説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第1号様式 又は 第2号様式 ○ ○
登録申請人(現所有者)及び記入申請人(使用者)は記名、押印又は署名する。(103頁参照)代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。
様式省令 第2条第1項登令第15条
手数料納付書 ○ ○ 手数料不要。 車両法施規第6�条
登録事項が誤りであることを明らかにできる書面
○ 戸籍簿謄抄本、登記簿謄抄本、住民票等 登令第14条 第1項第1号
○ 車台番号の拓本(石ずり)
理 由 書 ○ ○ 更正に係る理由を明記すること。
委 任 状 ○ ○ 代理人が申請する場合に必要。申請人(委任者)は押印する。
登令第14条 第1項第3号
自動車検査証 ○ ○ 提出する。 車両法第67条第1項
自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条
4 更正登録申請・自動車検査証記入申請(車両法第67条、登令第25条、第28条)
(登録した内容について錯誤、又は脱落がある場合)
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 登録自動車2(14頁)を参照。
第25条(更正登録) 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを
発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の錯誤に基づくものであるときは、更正の登録を
し、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし、登録上利害関係を有する
第三者がある場合は、この限りではない。
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の更正の登録(道路運送車両法第7条第1項第1号、第2号、第3号若しくは
第5号に掲げる事項又は自動車登録番号に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、地方運輸局長の許
可を受けなければならない。
第28条 登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請人は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の
登録を申請することができる。
項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
大型ダンプ車の場合 届出事項変更届出書 使用者の氏名、又は名称及び住所を更正する場合に必要。
ダンプ法第3条第3項ダンプ法施規第2条
事業用自動車又は貸渡自動車の場合
事業用自動車等連絡書
*上記書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。

25
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
5 抹消登録申請(車両法第15条、第15条の2、第16条、第69条、第69条の2、第69条の3)
(登録自動車の使用を一時中止する場合、又は登録自動車を一時抹消輸出する場合、又は登録自動車を滅失、
解体、自動車の用途を廃止した場合)
第15条(永久抹消登録) 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由のあった日(当該事由が使用済自動車
の解体である場合にあっては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理
センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として
政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申
請をしなければならない。
⑴ 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
⑵ 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなったとき。
2 引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者をいう。第100条第1項第3号において同じ。)は、
同法の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自
らが当該自動車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。
3 登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第1項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及
び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通
省令で定める事項を明らかにしなければならない。
4 第1項の場合において、登録自動車の所有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7
日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請
をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
第15条の2(輸出抹消登録) 登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しよう
とするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から当該輸出をする時までの間に、輸
出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、そ
の自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であって輸出抹消仮登録を受けさせる必要性
に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定
されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が
経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和2�年法律第61号)第70条第2
項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合にお
いて、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
4 第2項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明
書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から15日以内に、国土交通大臣に
当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第1項の規定に
よる一時抹消登録の申請があったものとみなして一時抹消登録をするものとする。
第16条(一時抹消登録) 登録自動車の所有者は、前2条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供するこ
とをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
2 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があっ
た日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内

26
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
⑴ 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
⑵ 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなったとき。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
4 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとすると
きは、当該輸出の予定日から国土交通省令定める期間さかのぼった日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令
で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受け
なければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定
されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
6 前条第3項及び第4項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第4項の規定による届出があった場合に
ついて準用する。この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸
出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第5
項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
7 国土交通大臣は、前項において準用する前条第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたと
きは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。
第18条(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置) 国土交通大臣は、一時抹消登録をした自動車について、
国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第3項又は第5項の規定による届出がなされないことその他の事情
から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又は違反するおそれがあると
認めるときは、これらの規定による届出をなすべき旨の催告その他の当該自動車に係る自動車登録ファイルの正確な記
録を確保するために必要と認められる措置を講ずることができる。
2 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変
更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更が
あった旨を証明することができる契約書その他の資料を作成し、又は取得して、これを国土交通省令で定める期間保存
し、国土交通大臣から求められたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
3 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該
所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。
第18条の3(登録識別情報の提供) 新規登録(一時抹消登録があった自動車に係るものに限る。)、変更登録、移転登録、
永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところによ
り、登録識別情報を提供しなければならない。ただし、申請者が登録識別情報を提供できないことにつき正当な理由が
ある場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2 一時抹消登録があった自動車を譲渡する者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲受人に提供し
なければならない。
第6�条(自動車検査証の返納等) 自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があったときは、その事由があっ
た日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内
に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
⑴ 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
⑵ 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号の
指定の際)存したものでなくなったとき。
⑶ 当該自動車について第15条の2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第16条第1項の申請に基づく一時抹消登
録があったとき。
⑷ 当該自動車について次条第3項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。

27
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
2 第54条第2項又は第54条の2第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査
証を国土交通大臣に返納しなければならない。
3 国土交通大臣は、第54条第3項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は第54条の2第6項の規定による自動車
の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至ったときは、返納を受けた自動車検査証を
返付しなければならない。
4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することを
やめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。
第6�条の2(解体等又は輸出に係る届出) 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)
の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があったときは、その事由があった日(当
該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、国土
交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 第15条第2項及び第3項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車」と読み替
えるものとする。
3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しよ
うとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から当該輸出をする時までの間に、
国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書
の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合
であって当該届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で
定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項本文の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が
予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
5 第15条の2第3項及び第4項の規定は、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の輸出に係る第3項本文の規定によ
る届出があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出
予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二
輪自動車検査ファイルに記録」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第6�条の2第4項」と、「輸出抹消仮登録証
明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
6 国土交通大臣は、前項において準用する第15条の2第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受
けたときは、その旨を第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録するものとす
る。
第6�条の3(準用規定) 第18条の規定は、自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について
準用する。この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファ
イル又は二輪自動車検査ファイル」と、同条第1項中「第16条第3項又は第5項」とあるのは「第6�条の2第1項又は
第3項」と、同条第2項中「次項」とあるのは「第6�条の3において準用する第18条第3項」と読み替えるものとする。

28
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
永久抹消登録 輸出抹消仮登録
一時抹消登録
説 明 欄 参 考 条 文
重量税還付対象
(重量税還付対象外)
リサイクル対象
滅失・用途廃止永久抹消
OCRシート 第3号の2様式 ○ ○ ○ 登録申請人(所有者)は記名して実印を押印する。代
理人により申請するときは、代理人は記名でよい。登令第15条様式省令第2条第1項
第3号の3様式 ○ ○登録申請人(所有者)は記名して実印を押印する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。重量税還付申請欄には①金融機関名・支店名・口座番号・口座種類を記載する。
登令第15条様式省令第2条第1項
手数料納付書 ○ ○ 手数料(105項参照) 車両法施規第6�条
印鑑証明書 注1 ○ ○ ○ ○ ○ 発行されてから3ヶ月以内のもの(所有者) 登令第16条
委任状 ○ ○ ○ ○ ○ 代理人が申請する場合に必要。申請人(所有者)は実印を押印する。
登令第14条 第1項第3号
自動車検査証 ○ ○ ○ ○ ○ 返納する。 車両法第6�条
ナンバープレート ○ ○ ○ ○ ○ 申請の際にナンバープレート交付所に返納する。 車両法第20条第1項車両法施規第10条
解体報告記録がなされた日 ○ ○「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から㈶自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日
登令第46条
移動報告番号 ○ ○ 解体がされた時に引取業者から通知される番号 登規第6条の2
重量税還付申請の委任状 ○申請書代理人欄に代理人の押印が必要。重量税還付金受領権限を委任する場合、所有者本人の自署・押印又は記名の場合は実印を押印した委任状
国税通則法第124条租税措置法第�0条12
重量税還付申請書付表2 ○ OCRシート第3号様式の3重量税還付申請欄の氏名・名称等のオーバーフローの場合
租税措置法第�0条12
重量税還付申請書付表3 ○ OCRシート第3号様式の3重量税還付申請欄が共同所有の場合
租税措置法第�0条12
滅失(罹災証明書) ○ 罹災を証明する書面
用途廃止(写真及び申立書) ○ 用途廃止の写真及び申立書
解体(マニフェストB2票・解体証明) ○
大型特殊・被牽引自動車を解体したとき 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条自動車リサイクル法第2条
輸出予定日 ○ 輸出予定日 車両法第15条の2
登録識別情報 注2 ○ ○ ○ ○ ○ 電子的に提出するか、OCRシートへの記載が必要 車両法第18条の3登規第6条の1�
注1 印鑑証明書の取扱について①申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付②申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので
氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす③申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印
を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付
④申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付
注2 登録識別情報の通知を受けているものに限り必要
永久抹消・輸出抹消仮登録・一時抹消登録

2�
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
なかった時
輸出抹消仮登録後輸出され
一時抹消登録後
説 明 欄 参 考 条 文
出(重量税還付)
使用済自動車の解体届
出(重量税還付対象外)
使用済自動車の解体届
滅失・用途廃止
輸出しようとするとき
輸出されなかった時
所有者を変更する時
自動車検査証返納後の
OCRシート 第1号様式 ○
登録申請人(所有者)は記名及び押印する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。
登令第15条様式省令第2条第1項
第3号の2様式 ○ ○ ○ ○登録申請人(所有者)は記名及び押印若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。
登令第15条様式省令第2条第1項
第3号の3様式 ○ ○
登録申請人(所有者)は記名及び押印若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。重量税還付対象の場合には、重量税還付申請欄には金融機関名・支店名・口座番号・口座種類を記載する。
登令第15条様式省令第2条第1項
車両法施規第6�条
手数料納付書 ○ ○ ○ 手数料(105項参照)
委任状 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※
代理人が申請する場合に必要。申請人(所有者)は記名及び押印若しくは署名する。※署名不可
登令第14条 第1項第3号
解体報告記録がなされた日 ○ ○
「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から㈶自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日
登令第46条
移動報告番号 ○ ○ 解体がされた時に引取業者から通知される番号
登規第6条の2
重量税還付申請の委任状 ○申請書代理人欄に代理人の押印が必要。重量税還付金受領権限を委任する場合、所有者本人の自署・押印又は記名の場合は実印を押印した委任状
租税措置法第�0条12
重量税還付申請書付表2 ○OCRシート第3号様式の3重量税還付申請欄の氏名・名称等のオーバーフローの場合
租税措置法第�0条12
重量税還付申請書付表3 ○ OCRシート第3号様式の3重量税還付申請欄が共同所有の場合
租税措置法第�0条12
滅失(罹災証明書) ○ 罹災を証明する書面
用途廃止(写真及び申立書) ○ 用途廃止の写真及び申立書
解体(マニフェストB2票・解体証明)
大型特殊・被牽引自動車を解体したとき 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条自動車リサイクル法第2条
輸出予定日 ○ 輸出予定日 車両法第15条の2
輸出抹消仮登録証明書 ○ 輸出予定日から遡って6ヶ月前から輸出する間に申請した時に交付される証明書
車両法第15条の2第4項
譲渡証明書 ○※
○※
○※
○※
○ 譲渡人のみ押印が必要。譲受人は所有者のみを記入する。※所有者に変更があった場合
車両法第7条・第33条登規第6条の8・第6条の11・第6条の13
輸出予定届出証明書 ○ 輸出予定日から遡って6ヶ月前から輸出する間に申請した時に交付される証明書
車両法第16条第6項・第7項
輸出抹消仮登録後及び一時抹消登録後の申請

30
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
なかった時
輸出抹消仮登録後輸出され
一時使用中止後
説 明 欄 参 考 条 文
出(重量税還付)
使用済自動車の解体届
出(重量税還付対象外)
使用済自動車の解体届
滅失・用途廃止
輸出しようとするとき
輸出されなかった時
所有者を変更する時
自動車検査証返納後の
登録識別情報等通知書 ○ ○ ○ ○ ○一時抹消登録をした自動車を輸出する場合及び解体等をする場合
車両法第16条第2項・第4項・第5項第18条第3項
新所有者の住所を証する書面
○※
○※
○※
○※ ○
住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写し可)(発行されてから3ヶ月以内)※所有者に変更があった場合
登規第6条の8・第6条の11・第6条の13
〔永久抹消登録申請の流れ〕
【永久抹消登録申請】①重量税還付対象永久抹消登録 確定日の翌日から有効期間満了 までの期間が1ヶ月以上のもの (大型特殊・被牽引自動車を除く)
●申請書…3号の3○手数料…無料○所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○自動車検査証○ナンバープレート○氏名・住所等に変更がある場合 …関連のある住民票・謄本等 ◎重量税還付関係●解体報告記録がなされた日●移動報告番号●代理人申請の場合 ◇重量税還付申請の委任状 (申請書代理人欄に代理人の押印が必要) ◇重量税還付金受領権限を委任する場合 所有者本人の自署・押印又は、記名の場 合は実印を押印した委任状●重量税還付申請書…付表2 氏名・名称等のオーバーフローの場合●重量税還付申請書…付表3 共同所有の場合●登録識別情報の通知を受けている場合は登録 識別情報 ※登録ファイルの所有者と申請者が異なる場合、 最終所有者が還付対象になることから、登録 ファイルの所有者と申請者が一致することが 必要であり、移転登録を同時処理とする。
②リサイクル対象永久抹消登録 (還付対象外) (大型特殊・被牽引自動車を除く)○手数料…無料●申請書…3号の3●解体報告記録がなされた日●移動報告番号○所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○自動車検査証○ナンバープレート○氏名・住所等に変更があるの場合 …関連のある住民票・謄本等○登録識別情報の通知を受けている場合は登録 識別情報
③滅失・用途廃止永久抹消登録○手数料…無料○申請書…3号の2○所有者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○滅失…罹災証明等○用途廃止…写真及び申立書(使用目的を記載)○自動車検査証○ナンバープレート○氏名・住所等に変更があるの場合 …関連のある住民票・謄本等○解体…マニフェストB2票・解体証明 (大型特殊・被牽引自動車を解体した時)○登録識別情報の通知を受けている場合は登録 識別情報
●銀行等・郵便局への振込 税務署より「国税還付金振込通知書」 が送付され、指定口座に振込 ※郵便局は郵便貯金総合通帳 「ぱるる」の口座のみ
●郵便局窓口での受取 税務署より「国税還付金送金通知書」 が送付され、申請書に記載した郵便局 の窓口にて受領
重量税還付申請書付表1(申請者用)の交付
○記載内容 登録番号・車台番号 還付金額・ 申請者 氏名・住所 代理受領者 氏名 住所 振込口座 金融名・口座番号等
〔重量税還付について〕
※受取りに約3ヶ月 かかります

31
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
〔輸出抹消仮登録申請の流れ〕
【輸出抹消仮登録申請】◎輸出予定日からさかのぼって「6ヶ月前」から 輸出する間に申請 ●申請書 第3号の2○手数料納付書 350円○輸出予定日○印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○氏名・住所等に変更がある場合 …関連のある住民票・謄本等 (変更登録申請が必要)○車検証・ナンバープレート○登録識別情報の通知を受けている場合は登録識 別情報 ※輸出抹消登録を要しない自動車 ○大型特殊車両 ○被牽引自動車 ○登録証書の交付を受けた自動車 (一時抹消登録時は対象車両)
※本邦に再輸入することが見込まれる登録自動 車の届出 ●活魚運搬車 ●申請書 第3号の2 ●車検証 ●再輸入の見込まれる書面 運搬に係る契約書・事業計画書 ●申請書に届出人(所有者)の署名又は、記 名・押印 (代理人の場合、委任状でも可)
【輸出がされなかった時】◎輸出抹消仮登録証明書の返納届出
●輸出抹消仮登録証明書●申請書 第3号の2○手数料納付書 350円○申請書に届出人(所有者)の署名又は、 記名・押印 (代理人の場合、委任状でも可)
※届出先 最寄りの運輸支局等
【輸出が確認された時】関税法に基づき、輸出の照会・確認の後、輸出抹消登録で完了
◎輸出抹消仮登録証明書の返納を受けた 時は、一時抹消登録の申請があったも のとみなし、登録識別情報等通知書を 交付する。
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
交
付
〔一時抹消登録申請の流れ〕 ②-1
〔解体をしたとき〕
【一時抹消登録申請】●申請書 3号の2○手数料納付書 350円○印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○氏名・住所等に変更がある場合 …関連のある住民票・謄本等 (変更登録が必要)○車検証・ナンバープレート○登録識別情報の通知を受けている場合は登録識 別情報
①使用済自動車の解体届出(重量税還付含む) (大型特殊・被牽引自動車を除く)●登録識別情報等通知書●申請書 第3号の3(手数料 無料)●申請書に届出人(所有者)の押印 (代理人の場合、解体届出・還付申請の委任状 でも可)●解体報告記録がなされた日●移動報告番号●代理人申請の場合 ◇申請書の代理人欄に代理人の押印が必要 ※重量税還付金の受領権限を委任する場合 所有者本人の自署・押印した委任状又は、 記名の場合は印鑑証明書とその実印で作成 した委任状●所有者の変更があった場合 ◇譲渡証明書、合併(登記簿謄本)・相続(戸籍 謄本) ◇新所有者の住所を証する書面…住民票・謄本 等(写しでも可・発行日から3ヶ月以内)○氏名・住所等に変更があった場合、届出者の住 所を証する書面…住民票・謄本等(写しでも可 ・発行日から3ヶ月以内)
②使用済自動車の解体届出(還付対象外) (大型特殊・被牽引自動車を除く)●登録識別情報等通知書●申請書 第3号の3(手数料 無料)●申請書に届出人(所有者)の署名又は記名・ 押印(代理人の場合、委任状でも可)●解体報告記録がなされた日●移動報告番号●所有者の変更があった場合 ◇譲渡証明書、合併(登記簿謄本)・相続 (戸籍謄本) ◇新所有者の住所を証する書面…住民票・ 謄本等(写しでも可・発行日から3ヶ月 以内)○氏名・住所等に変更があった場合、届出者 の住所を証する書面…住民票・謄本等(写 しでも可・発行日から3ヶ月以内)
③滅失・用途の廃止 (大型特殊・被牽引自動車を除く)●登録識別情報等通知書●申請書 第3号の2(手数料 無料)●申請書に届出人(所有者)の署名又は記名・ 押印(代理人の場合、委任状でも可)○滅失…罹災証明等○用途廃止…写真・申立書(使用目的を記載)○氏名・住所等に変更があった場合、届出者 の住所を証する書面…住民票・謄本等(写 しでも可・発行日から3ヶ月以内)●所有者の変更があった場合 ◇譲渡証明書、合併(登記簿謄本)・相続 (戸籍謄本) ◇新所有者の住所を証する書面…住民票・ 謄本等(写しでも可・発行日から3ヶ月 以内)
※届出先 最寄りの運輸支局等
登録識別情報等通知書の交付
【運行しようとするとき】 新規登録で終了
【輸出しようとするとき】 輸出の届出 次ページ ②-2へ

32
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
輸出をしようとするとき 【輸出の届出】
(大型特殊・被牽引自動車を除く)◎輸出予定日からさかのぼって「6ヶ月前」から 輸出する間に申請
①輸出予定日②登録識別情報等通知書③申請書 第3号の2④手数料納付書 350円⑤申請書に届出人(所有者)の署名又は、記名・ 押印(代理人の場合、委任状でも可)⑥氏名・住所等に変更があった場合、届出者の住 所を証する書面…住民票・謄本等 (写しでも可・発行日から3ヶ月以内)⑦所有者の変更があった場合 ◇譲渡証明書、合併(登記簿謄本)・相続(戸籍 謄本) ◇新所有者の住所を証する書面 …住民票・謄本等(写しでも可・発行日から 3ヶ月以内)
※⑥⑦の場合、届出者に1号シートを購入して もらい、記入の上申請※届出があった場合であって、登録ファイルに 記録されている所有者の氏名若しくは名称又 は住所に変更があったときは、当該変更につ いて登録ファイルに記録するものとする。
※届出先 最寄りの運輸支局等
【輸出がされなかった時】◎輸出予定届出証明書の返納届出
●輸出予定届出証明書●申請書 第3号の2○手数料納付書 無料●申請書に届出人(所有者)の署名又は、 記名・押印 (代理人の場合、委任状でも可)
※届出先 最寄りの運輸支局等
【輸出が確認された時】関税法に基づき、輸出の照会・確認の後、その旨、自動車登録ファイルに記録するものとする。
◎輸出予定届出証明書の返納を受けた時 は、その旨、自動車登録ファイルに記 録するとともに、登録識別情報等通知 書を返付する。
輸
出
予
定
届
出
証
明
書
の
交
付
〔一時抹消登録申請の流れ〕 ②-2
【輸出をしようとするとき】
前ページ
②ー1から
●申請書 1号様式●登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書●申請書に新所有者の記名・押印(署名は不可) (代理人の場合、委任状でも可)●譲渡証明書・その他所有権を証明するに足りる書面 合併…登記簿謄本 相続…戸籍謄本●新所有者の住所を証する書面 …住民票・謄本等 (写しでも可・発行日から3ヶ月以内)
※届出先 最寄りの運輸支局等
※登録ファイル・二輪自動車検査ファイルに記録 した後、登録識別情報等通知書・自動車検査証 返納証明書を新所有者に返付する。
〔一時抹消登録・自動車検査証返納後の所有者変更に係る記録の申請〕

33
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
ナンバープレートを紛失した場合
理由書 返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書
局通達77東陸整登資乙第23号
所有者の氏名、若しくは名称、又は住所等の変更を伴う場合
OCRシート第1号様式 (103頁参照) 様式省令第2条第1項
手数料納付書 手数料(105頁参照) 車両法施規第68条
変更事項が確認できる書面 戸籍簿謄抄本、又は住民票、若しくは登記簿謄抄本等。
登令第18条 第24条
委任状 代理人が申請する場合に必要。一時抹消登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録の場合には、各々の委任項目を併合できる。
登令第14条 第1項第3号
大型自動車(大型ダンプ)の場合
土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書
申請者は使用者。 ダンプ法第5条ダンプ法施規第7条
事業用自動車、又は貸渡自動車の場合
事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書及び手数料納付書にそれぞれ輸送担当部署の経由印が必要。
所有者が死亡して使用を一時中止する場合
移転登録の相続の欄(18頁参照)
一度相続移転をしてから抹消登録手続をすることになるので両方の書類が必要となる。
移転登録相続の欄(25頁参照)
所有者の死亡前に滅失・解体等された場合
戸籍簿の謄本及び代表相続人の印鑑証明書
相続手続をする必要がないので相続人の代表が抹消登録を行う。
*下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。
(注)登録識別情報等通知書は再交付できないので大切に保管すること。

34
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第3号様式 第4号様式
①自動車登録番号及び車台番号の記載が必要 但し、以下の場合は、自動車登録番号又は車台番号のいずれか一方の
記載で可能。 ・私有地における放置車両で、車両が放置されている場所、見取図、
放置期間、放置車両の写真を記載した書類を提出した場合、自動車登録番号のみで請求できる。
・裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合であって、債務名義等の書類の提出又は提示によって裁判手続きに利用することが確認できる場合、自動車登録番号のみで請求できる。
・自動車登録番号が明らかにできないことがやむを得ないと確認できる場合は、車台番号のみで請求できる。
②請求者個人の氏名及び住所の記載が必要③「請求の事由」欄に具体的な請求理由の記載が必要 但し、自動車登録ファイル上の現在の所有者(一時抹消中及び一時抹
消後の所有者変更記録がされている所有者含む)本人からの請求の場合は不要
様式省令 第2条第1項登録規則第26条 第27条
手数料納付書 手数料(105頁参照) 車両法施規第6�条
身分証明書
提示する。 ・運転免許証 ・健康保険の被保険者証 ・外国人登録証明書 ・住民基本台帳カード ・その他法令の規定により交付された書類であって、本
人確認ができる書類 ・上記に掲げる書類をやむを得ない理由により提示でき
ない場合は、交付請求する者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類
登録規則第2条
6 登録事項等証明書の交付請求(車両法第22条)
(登録されている現在の内容の証明を受ける場合及び過去の履歴の証明を受ける場合)
最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第22条(登録事項等証明書) 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事
項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第102条第1項の
規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。
3 第�6条の15から第�6条の17までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、
登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供
を受けようとする者の委託を受けて、その者に対し、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を電気通信回線を使用し
て送信する業務(以下「情報提供業務」という。)を行うため、国土交通大臣に対し、当該委託に係る登録情報の提供
を電気通信回線を使用して請求することができる。
4 国土交通大臣又は登録情報提供機関は、第1項の規定による請求をする者又は前項の委託をする者について、国土交
通省令で定める方法により本人であることの確認を行うものとする。
5 第1項及び第3項の規定による請求は、請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明
らかにしてしなければならない。ただし、自動車の所有者が当該自動車について第1項の規定による請求をする場合そ
の他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
6 国土交通大臣は、第1項の規定による請求若しくは第3項の委託が不当な目的によることが明らかなとき又は第1項
の登録事項等証明書の交付若しくは第3項の登録情報の提供により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあ
ることその他の第1項又は第3項の規定による請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒む
ことができる。

35
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第1号様式 又は 第3号様式
第1号様式は変更登録、移転登録と同時に申請する場合に使用する。第3号様式は上記以外の場合に使用する。(103頁参照)登録申請人(所有者)本人が直接申請する場合は押印する。代理人により申請するときは代理人は記名でよい。「交付を受ける理由」欄に記載が必要。
登令第15条様式省令 第2条第1項
手数料納付書 手数料不要。 車両法施規第6�条
委 任 状 代理人が申請する場合に必要。申請人(委任者)は押印する。 登令第14号 第1項第3号
自動車検査証 提出する。 車両法第67条第1項
理 由 書ナンバープレートを紛失、滅失等の場合に必要。※返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書
局通達77東陸整登資乙第23号
自動車登録番号標交付通知書登録手続き終了後、登録事項等通知書とともにナンバー交付所に提示してナンバープレートの交付を受け、それを当該自動車に取りつけ、封印の取りつけを受ける。
車両法施規第4条局通達74東陸整登資第4号
事業用自動車等連絡書 事業用自動車、又は貸渡自動車の場合に必要。
自動車税・自動車取得税申告書 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条
7 自動車登録番号の変更申請(登令第43条)
(ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合)
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第43条(自動車登録番号の変更) 運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第11条第2項において準用する同条
第1項の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があったときは、自動車登録番
号を変更することができる。
2 道路運送車両法第9条及び第10条の規定は、前項の規定により自動車登録番号を変更する場合について準用する。

36
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
8 自動車抵当権の設定、変更、移転、更正、抹消登録 (登令第49条、第50条、第51条、第52条、第55条、第58条)
担保とする登録自動車を管轄する運輸支局、又は自動車検査登録事務所に申請する。
第4�条(設定の登録) 抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し、且つ、登録の原因
に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は自動車抵当法第6条但書の定があるときは、これを
記載しなければならない。
2 自動車抵当法第1�条の2第1項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の
規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第6条ただし書の定めがあると
き、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。
第50条 抵当権の設定の登録の申請をする場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書にその債務者の
氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
第51条 一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定登録の申請をする場合には、申請書にその債権の価格を
記載しなければならない。
第52条(共同抵当) 同一の債権を担保するため2両以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合に
は、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
第55条(移転の登録)抵当権(元本の確定前の根抵当権を除く。)の移転の登録の申請をする場合には、申請書に添えて
債権の移転を証する書面を提出しなければならない。
第58条(登録の抹消)登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができ
ないときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があったときは、申請書にその謄本を添付
して、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。
3 登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合に
おいて、申請書に添付して、債権証書、債権の受取証書並びに自動車抵当法第12条の規定により抵当権を行使すること
ができる定期金及び損害賠償の受取証書を提出したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることが
できる。

37
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
設定登録
変更登録
移転登録
更正登録
まっ消登録
説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第5号様式及びワンライティング用紙の抵当権登録申請書
○ ○ ○ ○ ○
申請人(登録義務者)は記名して実印を押印する。代理人により申請するときは申請人(委任者)の押印は省略できる。(103頁参照)登録免許税(106頁参照)設定、変更、移転、更正登録の登録権利者は債権者、登録義務者は債務者。まっ消登録の登録権利者は債務者、登録義務者は債権者。
登令第16条経過省令第35条税率は、登免税法第9条 別表1様式省令第2条第1項
債務者の印鑑証明書 ○ ○ ○ ○ 発行されてから3か月以内のもの。 登令第16条
債権者の印鑑証明書 ○
債権者の資格証明書 ○ ○ ○ ○ 登記簿謄抄本、又は住民票等で発行されてから3か月以内のもの。
登令第14条
金銭消費貸借契約書若しくは自動車割賦販売契約書及び抵当権設定契約書の写し
○原本持参の必要あり。 民法第521条以下
割賦法第4条登令第14条
変更に係る契約書の写し又は登記簿謄抄本 ○ 更改契約書、債務引受契約書等。 民法第513条
登令第14条
抵当権付債権の譲渡契約書等の写し ○ 原本持参の必要あり。 民法第375条
更正に係る契約書の写し又は登記簿謄抄本 ○ 原本持参の必要あり。 登令第14条
債務者に対する通知書又は債務者の承諾書 ○
承諾書の場合はそれぞれ押印した印鑑証明書の添付が必要。 登令第14条民法第376条
(抵当権の処分の対抗要件)
抵当権の変更について登録上利害関係をもつ第三者がある場合はその第三者の承諾書
○ ○ ○ ○利害関係をもつ第三者とは、例えば利息の場合後順位の抵当権者等。
登令第14条
債務弁済証明書、又は抵当権放棄書 ○
抵当権者(債権者)は実印を押印する。 登令第14条
委 任 状 ○ ○ ○ ○ ○ 代理人が申請する場合に必要。申請人(登録義務者)は実印を押印する。
登令第14条 第1項第3号

38
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
9 諸再交付申請 (車両法第11条(封印)、第70条(検査証、検査標章)、車両法施規第41条、第41条の2)
(ナンバープレートの封印、自動車検査証、検査標章を紛失、破損、脱落等により再交付を受ける場合)
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
※検査標章及び封印の場合は最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請してもよい。
第11条(自動車登録番号標の封印等) 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当
該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交
通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあっては、国土交
通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第28条の3第1項の規定による委託を受けた者(以
下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
2 前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第3�条第2項の規定に基づく国土交通省令で定める様
式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となった場合について準用する。この場合に
おいて必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
3 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき(次項た
だし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付
受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
4 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録
番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむ
を得ない事由に該当するときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該
当しなくなったときは、封印のみを取り外した場合にあっては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを
受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあっては国土交通省令で定めるところにより当該自動
車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければなら
ない。
第70条(再交付) 自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が
滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることが
できる。
第41条(臨時検査合格標章の再交付の申請書) 法第70条の臨時検査合格標章の再交付の申請書は、第10号様式による。
第41の条2(検査標章の再交付) 検査標章の再交付の申請をする者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の
申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。
2 検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合のほ
か、次の各号に掲げる場合とする。
⑴ 検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなった場合
⑵ 検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなくなった場合(当該自動車を引き
続き運行の用に供する場合に限る。)
⑶ その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
第41の条3(臨時検査合格標章の再交付) 前条第2項の規定は、臨時検査合格標章の再交付について準用する。

3�
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
封印再交付
検査証再交付
検査標章再交付
説 明 欄 参 考 条 文
再封印申請書 ○ 申請人は所有者。再交付を受ける理由を記入する。
OCRシート第3号様式 ○ ○ 申請人は使用者。再交付を受ける理由を記入する。(103頁参照)
様式省令 第2条第1項
手数料納付書 ○ ○ 手数料(105頁参照) 車両法施規第6�条
自動車検査証 ○ ○ ○ 提示する。検査証再交付の場合はき損等で提出できる場合に限る。
車両法施規第41条の2
本人を確認できる書面 ○
使用者又は代理人本人の次に掲げる書面を提示する。①運転免許証②被用者保険証、国民健康保険被保険者証③パスポート、外国人登録証明書④顔写真付き又は氏名及び住所を確認できる身分証明書
� 字光式自動車登録番号標の交付申請 (光るナンバープレートを取りつける場合)
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
登 録 別 そ の 他 必 要 書 類 参 考 条 文
新規登録申請の際に交付申請する場合
登録自動車の1(9頁)の必要書類の他に字光式登録番号標交付願が必要。
局通達72東陸整登資第63号72東陸整車第627号72東陸整整第204号
変更登録の際に交付申請する場合
登録自動車の2(14頁)の必要書類の他に字光式登録番号標交付願が必要。
同 上
移転登録の際に交付申請する場合
登録自動車の3(18頁)の必要書類の他に同上が必要。 同 上
登録番号の変更を申請する場合
登録自動車の7(35頁)の必要書類の他に同上が必要。 同 上
(注)番号標の取りつけ装置(照明器具)は、保安基準に適合するよう取りつけること。

40
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
� 希望番号制について(関東運輸局管内のケース)1 希望できる番号の区分
⑴ 4桁以下のアラビア数字の部分のみが自由に選べます。
なお、申し込むことができるのは、「登録自動車」と「自家用の軽自動車」の場合です。(「二輪車」は対象外)
但し、軽自動車でレンタカー・駐留軍人・軍属の私有車、および昭和50年3月31日以前に指定を受けた車両番号標
(33・66・88・00)は除きます。
⑵ 特に人気が高いと考えられる番号については、コンピューターによる抽選制とします。(毎週月曜日に前週に受付
けたものについて抽選を行います。)
【全ての運輸支局等、軽自動車検査協会事務所等において抽選希望ナンバーとなっている番号】
※登録自動車については、1回の抽選における当選個数は4個、ただし小型乗用車、小型貨物車は8個となっています。
※軽四輪自動車については、1回の抽選における当選個数は1個となっています。
注1 関東運輸局管内において、登録自動車【88】の1回の抽選における当選個数は2個
ただし小型乗用車、小型貨物車は4個となっています。
注2 東京運輸支局において、普通乗用車【8】・【88】の1回の抽選における当選個数は1個となっています。
神奈川運輸支局において、普通乗用車【8】の1回の抽選における当選個数は2個となっています。
平成17年より抽選希望ナンバーの一部見直しが毎年行われております。
平成24年5月現在、関東運輸局管内における特定運輸支局等で抽選希望ナンバーに移行された番号は下記の通りです。
【抽選希望ナンバーに移行された番号(登録自動車)】
※1回の抽選における当選個数は2個、ただし小型乗用車、小型貨物車は4個となっています。
注3 東京運輸支局において、普通乗用車【55】の1回の抽選における当選個数は1個となっています。
神奈川運輸支局において、普通乗用車【1188】の1回の抽選における当選個数は1個となっています。
1 7 8 (注2)
88 (注1)(注2) 333 555 777
888 1111 3333 5555 7777 8888
地域名表示 抽選対象になっている番号 交付を受ける運輸支局等
品 川 3・5・9・11・33・55・77・111・1122・1188 (注3) 東 京 運 輸 支 局
足 立 3 足立自動車検査登録事務所
練 馬 3・5・55 練馬自動車検査登録事務所
多 摩 3 多摩自動車検査登録事務所
横 浜3・5・9・11・33・55・77・111・1000・1001・1122・1188・2525・8008 (注3)
神 奈 川 運 輸 支 局
大 宮 3・1122 埼 玉 運 輸 支 局

41
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
【抽選希望ナンバーに移行された番号(軽四輪自動車)】
※1回の抽選における当選個数は1個となっています。
※登録自動車については、事業用・レンタカー・駐留軍人・軍属の私有車を除く
⑶ その他の一般希望ナンバーについては、番号がなくならない限り申し込みに応じて払い出します。
2 申し込み方法
⑴ 下記の申し込み方法があります。
① 登録車については、運輸支局等に隣接して設置されている「希望ナンバー予約センター」または軽自動車につい
ては、軽自動車検査協会に隣接されている「軽希望ナンバー予約センター」の窓口に直接お申し込み下さい。抽選
希望ナンバーについては当選後に、その他の一般希望ナンバーについては申し込み時に予約することとなります。
② 登録車の場合は、「希望ナンバー予約センター」に軽自動車の場合は、「軽希望ナンバー予約センター」に郵送や
FAXでお申し込み下さい。
※FAXや郵送による取扱いについては、郵送事務手数料(500円)及び郵送料(実費)を支払うことになります。
③ 下記のホームページからお申し込み下さい。
www.kibou-number.jp
⑵ 希望ナンバープレートは、注文製作となるため、予約済証交付日より起算して4営業日から交付可能となります。
但し、軽自動車の字光式番号標につきましては、予約済証交付日より起算して5営業日から交付可能となります。
⑶ 自動車の登録または軽自動車の届出は、ナンバープレートの交付可能日を待って行うことになります。
3 交付手数料および頒布価格(軽自動車の場合)
⑴ 希望ナンバープレートは、通常のナンバープレートと異なり、注文製作となるなどの理由から下記の手数料(軽自
動車の場合は頒布価格)となります。
⑵ 交付手数料(軽自動車の場合は頒布価格)は予約の際に支払うことになります。
東京・神奈川地域
登録車 大型番号標 2,420円 大型字光式番号標 3,130円
中型番号標 2,050円 中型字光式番号標 2,650円
軽自動車 中型番号標 2,050円 中型字光式番号標 3,250円
埼玉・千葉地域
登録車 大型番号標 2,470円 大型字光式番号標 3,180円
中型番号標 2,100円 中型字光式番号標 2,700円
軽自動車 中型番号標 2,100円 中型字光式番号標 3,280円
群馬・茨城・栃木・山梨地域
登録車 大型番号標 2,520円 大型字光式番号標 3,230円
中型番号標 2,150円 中型字光式番号標 2,750円
軽自動車 中型番号標 2,150円 中型字光式番号標 3,310円
※前後2枚を取り付ける場合には、上記価格の2倍額となります。
地域名表示 抽選対象になっている番号 頒布を受ける事務所等
大 宮 2525 埼 玉 事 務 所
熊 谷 1122・2525 埼 玉 事 務 所 熊 谷 支 所
所 沢 2525 埼 玉 事 務 所 所 沢 支 所
富士山 3776 山 梨 事 務 所

42
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
希望ナンバー予約手続方法
[一般希望ナンバー] [抽選希望ナンバー]抽選希望ナンバー以外 13通り
予 約 申 込 抽 選 申 込
登 録 申 請
当選後抽選対象希望番号受付証と引き換えに予約申込
抽選対象希望番号受付証の交付
抽 選
予約成立(希望番号予約済証の交付)
⬇
⬇
登 録⬇
プ レ ー ト 交 付⬇
⬇
⬇
⬇
⬇⬇
(プレート製作・納入)
※インターネットによる手続方法については、下記のアドレスで参照して下さい。
www.kibou-number.jp
○希望ナンバーで登録や届出するためには、その登録申請や届出の前に予約手続きが必要となります。
○抽選希望ナンバーの場合は、先ず抽選に当選する必要があります。
○当選された方は、抽選対象希望番号受付証に記載されている有効期間内(抽選日から起算して6営業日以内)に抽選対
象希望番号受付証を持参のうえ、希望番号予約済証の交付を受けて下さい。
○希望番号予約済証が交付された後に申込者の都合により解約した場合、希望番号による登録手続や届出ができなかった
場合、希望番号予約済証の有効期間が経過し効力が失われた場合などは、交付手数料または頒布価格は返還しません。

43
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ナンバー表示文字 予 約 セ ン タ ー 所 在 地 電話番号
品 川 (一財)関東陸運振興センター 品川支部 東京都品川区東大井1−12−14 03−3474−2649足 立 〃 足立支部 東京都足立区南花畑5−12−1 03−3850−3881練 馬 〃 練馬支部 東京都練馬区北町2−8−6 03−3934−3070多 摩 〃 多摩支部 東京都国立市北3−30−3 042−527−5454八王子 〃 八王子支部 東京都八王子市滝山町1−270−4 042−691−5891横 浜 (一社)神奈川県自動車会議所 横浜事業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町3575 045−932−3245川 崎 〃 川崎事業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜3−24−1 044−288−2250相 模 〃 相模事業所 神奈川県愛甲郡愛川町大字中津字桜台4074−1 046−285−0194湘 南 〃 湘南事業所 神奈川県平塚市東豊田字道下36�−14 0463−51−1144大 宮 (一財)関東陸運振興センター 埼玉支部 埼玉県さいたま市西区中釘2084−2 048−624−9255熊 谷 〃 熊谷支部 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原701−3 048−532−8125
所沢・川越 〃 所沢支部 埼玉県所沢市牛沼700−3 04−2998−2011春日部 〃 春日部支部 埼玉県春日部市増戸738−3 048−752−6221
群馬・高崎 〃 群馬支部 群馬県前橋市上泉町3�7−6 027−261−0341千葉・成田 〃 千葉支部 千葉県千葉市美浜区新港200 043−242−4627野田・柏 〃 野田支部 千葉県野田市上三ヶ尾207−25 04−7121−2511習志野 〃 習志野支部 千葉県船橋市習志野台8−57−1 047−466−0726袖ヶ浦 〃 袖ヶ浦支部 千葉県袖ヶ浦市長浦580−221 0438−63−5516水 戸 〃 茨城支部 茨城県水戸市住吉町2�2−10 029−247−5854
土浦・つくば 〃 土浦支部 茨城県土浦市卸町2−1−5 029−842−7901宇都宮・那須 (一社)栃木県自動車整備振興会 宇都宮事務所 栃木県宇都宮市八千代1−4−11 028−658−3311
とちぎ 〃 佐野事務所 栃木県佐野市下羽田町2001−3 0283−20−6100山梨・富士山 (一財)関東陸運振興センター 山梨支部 山梨県笛吹市石和町唐柏1000−6 055−262−4777
希望ナンバー予約センター
ナンバー表示文字 予 約 セ ン タ ー 所 在 地 電話番号
品 川 (一財)関東陸運振興センター 品川支部軽出張所 東京都港区港南3−3−10 03−3472−5334足 立 〃 足立支部軽出張所 東京都足立区入谷8−10−8 03−3853−1084練 馬 〃 練馬支部軽出張所 東京都板橋区新河岸1−12−26 03−5922−6178多 摩 〃 多摩支部軽出張所 東京都府中市朝日町3−16−22 042−358−6381八王子 〃 八王子支部軽出張所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3−6−1 042−557−2881
横浜・川崎 (一社)神奈川県自動車会議所 神奈川事業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町3�14−3 045−931−2560相 模 〃 軽相模事業所 神奈川県愛甲郡愛川町大字中津字桜台4071−33 046−284−2500湘 南 〃 湘南事業所 神奈川県平塚市東豊田字道下36�−14 0463−51−1144大 宮 (一財)関東陸運振興センター 埼玉支部軽出張所 埼玉県上尾市平方領々家字前511−3 048−726−0916熊 谷 〃 熊谷支部軽出張所 埼玉県深谷市折之口1��0−6 048−574−1860
所沢・川越 〃 所沢支部軽出張所 埼玉県入間郡三芳町北永井360−14 049−274−3051春日部 〃 春日部支部軽出張所 埼玉県春日部市下大増新田131−1 048−731−1178
群馬・高崎 〃 群馬支部軽出張所 群馬県前橋市中町322−1 027−261−5633千葉・成田 〃 千葉支部軽出張所 千葉県千葉市美浜区新港223−17 043−242−5684
習志野 〃 習志野支部軽出張所 千葉県船橋市習志野台8−56−1 047−402−5666野田・柏 〃 野田支部 千葉県野田市上三ヶ尾207−25 04−7121−2511袖ヶ浦 〃 袖ヶ浦支部軽出張所 千葉県袖ヶ浦市長浦580−25� 0438−63−4962水 戸 〃 茨城支部軽出張所 茨城県東茨城郡茨城町若宮887−67 029−293−9669
土浦・つくば 〃 土浦支部軽出張所 茨城県土浦市卸町2−2−8 029−843−3366宇都宮・那須 (一社)栃木県自動車整備振興会 西川田支所 栃木県宇都宮市西川田本町1−2−37 028−645−5485
とちぎ 〃 佐野事務所 栃木県佐野市下羽田町字新田2001−3 0283−20−6100山梨・富士山 (一財)関東陸運振興センター 山梨支部軽出張所 山梨県笛吹市石和町唐柏7�1−1 055−262−7549
軽希望ナンバー予約センター

44
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第3号様式 (専用3号様式)
申請者は使用者で記名、押印又は署名が必要。(103頁参照) 登令第15条様式省令第2条第1項
手 数 料 手数料は自動車検査票、又は保安基準適合証に貼付する。(105頁参照)
70東陸整車乙第146号70東陸整登資乙第28号
自動車検査証 提出する。 車両法第62条第1項
自動車検査票 提出する。 実施要領3−3−1
点検整備記録簿 提示する。 車両法第62条第3項車両法施規第3�条
保安基準適合証 保安基準適合証は指定整備を行ったものについてのみ必要。 車両法第�4条の5
限定自動車検査証 提出する。(限定自動車検査証を交付されたものに限る) 車両法第71条の2
限定保安基準適合証 限定自動車検査証に記載された保安基準に適合していない部分を指定整備を行ったものについてのみ必要
車両法第�4条の5の2
自動車税の滞納がないことを証する書面
納税証明書を提示する。 車両法第�7条の2
自動車重量税納付書 重量税(22�頁参照) 重量税法第8条、第10条
自動車損害賠償責任保険証明書 提示する。自動車検査証の新たな有効期間をカバーするだけの期間が必要。(257頁参照)
自賠法第9条
� 継続検査申請(車両法第62条)
(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)
最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第62条(継続検査) 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、
自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行
なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣
に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間
を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検
査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
3 第5�条第3項の規定は、継続検査について準用する。
4 次条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受ける
ことができない。
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申
請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
※前記書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書面が必要となります。 土砂等運搬大型自動車…自重計技術基準適合証 LPG車…LPガス燃料装置点検整備記録簿 CNG車…CNG自動車燃料装置点検整備記録簿

45
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第1号様式 自動車の諸元(構造)関係の変更を伴う申請の場合は第2号様式を使用し、その他の場合は第1号様式を使用する。検査申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。
登令第15条
様式省令第2条第1項 第2号様式
手数料納付書 所定の手数料印紙(105項参照)を貼付 車両法施規第6�条
点検整備記録簿 検査を受ける場合に必要。 車両法第67条第4項
改造自動車等審査結果通知書 改造自動車等届出書を提出し、運輸局又は自動車検査独立行政法人より通知の交付を受け検査を受けるときに添付する。
自車第256号(42. 4. 4)
委任状 使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
登令第14条第1項第3号
自動車検査証 提出する。限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証
車両法第67条第1項
自動車検査票 合格印のあるものを提出 実施要領 3– 3– 1
自動車重量税納付書 所定の重量税印紙(22�頁参照)を貼付 重量税法第8条、第10条
自動車損害賠償責任保険証明書 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条
自動車税・自動車取得税申告書 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条
自動車税の滞納がないことを証する書面
納税証明書を提示する。 車両法第�7条の2
� 自動車検査証記入申請・構造等変更検査(車両法第67条)
(自動車の構造等に変更があった場合)
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 1登録自動車の2(14頁)を参照
項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
土砂等運搬車のダンプ車
⒈自重計技術基準適合証⒉貨物担当課の経由印
⒈ダンプ規制法でいう、砂利、土砂、石灰石又はけい砂等を運搬する車両に適用する。
⒉車両総重量8トン又は最大積載量5トン以上の車両に適用する。
⒊土砂等運搬車の表示番号等の指定は貨物担当課の経由印等で判定する。
ダンプ規制法「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令の取り扱い等について」(依命通達)自車第1�6号(43.3.11)
高圧ガス運搬車 容器証明書 高圧ガス(LPガスを含む。)を運搬するタンク車は、容器証明書が必要である。
高圧ガス取締法第45条実施要領4−11−2
タンク車
⒈爆発性液体(危険物)を運送するタンク車はタンク証明書(完成検査済証又は設置許可申請書及びタンク検査済証)
⒉比重証明書
⒈危険物を運搬するタンク車には、市町村長等の行う完成検査(タンク証明書)が必要である。
⒉危険物以外の物品を運搬するタンク車には、積載物品の比重証明書が必要である。
実施要領3−2−3
高圧ガスを燃料とする自動車
⒈LPガス改造自動車完成検査表(改造車)
⒉LP改造車ガス燃料装置点検整備記録簿 (中古車)
高圧ガスを燃料とする自動車には、LPガス自動車完成検査表又は点検整備記録簿のいずれかが必要である。
「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする自動車の構造取扱基準について」 関整車第1118号 関整整第108号 関整事公第110号 (63.4.20)
その他添付書類等

46
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
緊急車
緊急自動車の指定申請済証明書又は届出済証明書等
⒈緊急自動車は、すべて公安委員会による指定又は公安委員会への届出が必要である。
⒉緊急自動車指定申請済証明書又は届出済証明書等とは使用者等が公安委員会に指定又は届出申請中である旨の書面で差支えない。
⒊前記証明書等の提出があった場合には、保安基準第1条第1項等13号の緊急自動車として検査する。
道路交通法施行令第13条「緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いの変更について」 自車第1113号(53.11.27) 78東陸整車乙第506号 (53.11.30)
道路維持作業用自動車
道路維持作業用自動車の指定申請済証明書又は届出済証明書等
⒈道路維持作業用自動車は、すべて公安委員会による指定又は公安委員会への届出が必要である。
⒉道路維持作業用自動車指定申請済証明書又は届出済証明書等とは、使用者等が公安委員会に指定又は届出申請中である旨の書面で差支えない。
⒊前記証明書等の提出があった場合には、保安基準第1条第1項第13号の2の道路維持作業用自動車として検査する。
道路交通法施行令第14条の2「緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いの変更について」 自車第1113号(53.11.27) 78東陸整車乙第506号 (53.11.30)
改造自動車
改造自動車等審査結果通知書(写)及び関係書類
改造自動車の検査申請の場合には、通知書(写)のほか、改造概要説明書、改造部分詳細図、外観図及び強度計算書等を添付すること。
改造自動車等の取扱いについて 自車23�号(7.11.21) 関整車第4563号 (7.11.21)

47
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
� 自動車検査証の記入申請(車両法第67条)
(自動車検査証の記載事項について変更があった場合で変更登録等を伴わない場合)
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 1登録自動車の2(14頁)を参照。
必 要 書 類
名称が変った場合
使用者の氏名または
使用者の住所が変った場合
変更した場合
事業用から自家用に用途を
説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第1号様式又は 第2号様式 ○ ○ ○ 検査申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署
名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。様式省令 第2条第1項
手数料納付書 ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(105項参照)を貼付 車両法施規第6�条
事由を証する書面等 ○ ○
①使用者が個人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票又は外国人登録原票記載事項証明書。住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる
「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要。なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面(公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの))が必要。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。②使用者が個人の場合で氏名の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票又は外国人登録原票記載事項証明書③使用者が法人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要。なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面が必要。挙証書面としては(公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの))が必要。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。④使用者が法人の場合で名称の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書⑤使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合・個人…市区町村の発行した住居表示の変更の証明書・法人…商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する・ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合に限る。・上記①〜⑤の各書面は写しで可とする。⑥事業用自動車等連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)⑦構造変更を伴わない諸元等の変更の場合・自動車検査票等
車両法第7条第3項2号第75条第4項
委任状 ○ ○ ○ 使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
登令第14条 第1項第3号
自動車検査証 ○ ○ ○ 提出する。限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証
車両法第67条第1項

48
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
名称が変った場合
使用者の氏名または
使用者の住所が変った場合
変更した場合
事業用から自家用に用途を
説 明 欄 参 考 条 文
自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条
自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条
項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
届出事項変更届出書 使用者の氏名・名称及び住所等を変更した場合、又は使用者変更、並びに事業用から自家用に用途を変更した場合に必要。使用者変更の場合には、旧使用者の使用廃止届出書も添付する。
ダンプ法第3条第3項ダンプ法施規第2条
土砂等運搬大型自動車使用届出書
ダンプ法第3条第1項 第5条ダンプ法施規第1条 第7条
大型自動車(大型ダンプ)の場合 事業証明書
経営する事業の種類 呈示を求める書類等
建設業砂利採取業採石業砕石業
砂利販売業
その他
建設業法による許可書の写し砂利採取法による登録の写し採石法による登録の写し大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、又は砕石のための設備に係る登記簿謄本等砂利の山元、又は買主との売買契約書、又は仮契約書の写し、又は商工会議所、市町村等による事業内容証明書、若しくは納税証明書(事業税)廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、又は生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等
「ダンプカー使用事業者の協業化の促進及びダンプカーの使用の届出の取扱等について」(依命通達)自貨第163号(54.11.27)
事業用自動車又は貸渡自動車の場合
事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書及び手数料納付書にそれぞれ輸送担当部署の経由印が必要
*上記書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。

49
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
� 保安基準関係 自動車の審査については、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則及び道路運送車両の保安基準並びにこれらの法令
に基づく国の関係通達によるほか、自動車検査独立行政法人審査事務規程の定めるところによる。
下記内容については保安基準関係の自動車の構造装置及び性能についての基本となるものである。
条 項 項 目 基 準 内 容
2 条
長 さ
幅高 さ車 体 外 へ の 突 出 量
○12ⅿを超えないこと(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)
○2.5ⅿを超えないこと。○3.8ⅿを超えないこと。○外開き式窓等は最外側より250㎜以上、高さから300㎜以上突出していないこと。
3 条 最 低 地 上 高 ○安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有すること。
4 条 車 両 総 重 量
4条の2
軸 重隣 接 軸 重
輪 荷 重
○10トンを超えないこと。○次表の隣接軸距に応じた数値を超えないこと。
○5トンを超えないこと。(ロードローラーのうち1車軸に1個の車輪のみ取り付けられたものは適用除外)
5 条 安 定 性
○かじ取り車輪の荷重割合(空、積車時)は20%以上であること。○最大安定傾斜角度(空車時)は左側、右側にそれぞれ35 ま゚で傾けた場合に転覆しないこと。(車両総重量≦1.2×車両重量の場合は30 )゚
○側車付二輪は25゜○被けん引車(ポールトレーラーを除く)35゜○ポールトレーラー:左右外側車輪の接地面の中心間隔が荷台床面の地面からの高さの1.3倍以上
6 条 最 小 回 転 半 径 ○12ⅿ以下
7 条接 地 圧接 地 部
○接地部は道路を破損する恐れのない構造であること。○200㎏/㎝を超えないこと。(空気入ゴムタイヤ又は、固形ゴムタイヤ(接地部の厚さ25㎜以上)以外のもの(そりを除く)100㎏/㎝)
○カタピラ:3㎏/㎠
8 条 原動機及び動力伝達装置○運行に十分耐える構造及び性能であること。○原動機は運転者席で始動できること。○二重アクセルリターンスプリングを備えること。
自 動 車 の 種 類車両総重量
最遠軸距
⒈セミトレーラ以外の自動車
5.5ⅿ未満 20㌧
5.5ⅿ以上7ⅿ未満 22㌧(長さ9ⅿ未満は20㌧)
7ⅿ以上 25㌧(長さ9ⅿ未満は20㌧)(長さ9ⅿ以上11ⅿ未満は22㌧)
⒉セミトレーラ
5ⅿ未満 20㌧
5ⅿ以上7ⅿ未満 22㌧
7ⅿ以上8ⅿ未満 24㌧
8ⅿ以上9.5ⅿ未満 26㌧
9.5ⅿ以上 28㌧
隣接軸距 1.8ⅿ未満 (1.3ⅿ以上1.8ⅿ未満) 1.8ⅿ以上
隣接軸重 18㌧ 19㌧ただし、軸重≦9.5㌧の時 20㌧

50
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
9 条 走 行 装 置
○堅ろうで安全な運行を確保できるものであること。○接地部は、滑り止めを施してあること。○亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。○タイヤ摩耗限度 (滑り止めの溝の深さはいずれの部分においても表のとおりであること。)
10 条 操 縦 装 置
(配 置)○かじ取りハンドル中心から左右それぞれ500㎜以内で、運転者が定位置で容易に操作できること。(始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置、制動装置の操作装置、前照灯、警音器、方向指示器、窓拭器、洗浄液噴射装置及びデフロスタの操作装置)
(識別表示)○運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をすること。(点火時期調節装置、噴射時期調節装置、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置、前照灯、警音器、窓拭器、洗浄液噴射装置及びデフロスタの操作装置)
○変速装置の操作装置、又はその附近には変速段ごとの操作位置を識別できる表示をすること。
○方向指示器の操作装置、又はその附近には方向指示器が指示する方向ごとの操作位置を運転者が運転席で容易に識別できる表示をすること。
11 条 か じ 取 り 装 置
○堅ろうで安全な運行を確保できるものであること。○運転者が定位置で容易に、かつ、確実に操作できること。○かじ取り時に、車わく、フェンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。○回転角度とかじ取り車輪のかじ取り角度は、左右について著しい相違がないこと。○操だ力は左右について著しい相違がないこと。○もっぱら乗用の用に供する自動車のかじ取り装置は、自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造であること。(ハンドル軸の中心線と当該中心線を通り車両中心線に平行な直線とのなす角度が35 を゚こえる構造のかじ取り装置にあってはこの限りでない。)
11条の2 施 錠 装 置
○もっぱら乗用の用に供する自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はかじ取り装置には施錠装置を備えなければならない。
○堅ろうであり、かつ容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることのない構造であること。
○運転者が運転者席で容易に操作できること。○施錠中は始動装置を操作できないこと。○走行中、振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。
12 条13 条 制 動 装 置 略
14 条 緩 衝 装 置○地面からの衝撃に対して十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるばねその他の緩衝装置を備えなければならない。(大型特殊自動車等省略できる自動車有り)
15 条 燃 料 装 置
(燃料タンク及び配管)○ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないよう取り付けられていること。
○もっぱら乗用の用に供する自動車は、衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において燃料が著しく漏れるおそれの少ない構造であること。
タイヤの種類 溝深さ限度
乗用車用タイヤ
1.6㎜以上軽トラック用タイヤ
小型トラック用タイヤ
トラック及びバス用タイヤ(低床式トレーラ用タイヤを含む)
二輪自動車用タイヤ 0.8㎜以上

51
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
(燃料タンクの注入口、及びガス抜口)○自動車の動揺により燃料が漏れない構造であること。○排気管の開口方向になく、かつ排気管の開口部から300㎜以上離れていること。○露出した電気端子及び電気開閉器から200㎜以上離れていること。○車室の内部(隔壁により仕切られた運転者室を除く)に開口していないこと。
16 条17 条 L P G 関 係 等 略
17条の2 電 気 装 置
○車室内等の電気配線は被覆され、且つ、車体に定着されていること。○車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生じるおそれのあるものは、適当におおわれていること。
○蓄電池は、自動車の振動、衝げき等により移動し、または損傷することがないようになっていること。車室内等にある場合は木箱その他適当な絶縁物でおおわれていること。
○無線設備の機能に継続的、かつ、重大な障害を与えるおそれのないこと。
18 条 車 わ く 及 び 車 体
○堅ろうで運行に十分耐えること。○車体は車枠に確実に取り付けられ振動、衝撃等によりゆるみを生じないこと。○車体の外形その他自動車の形状は鋭い突起を有し又は回転部分の突出等他の交通の安全を妨げるおそれのないこと。(大型特殊・小型特殊自動車を除く。)
○リヤオーバハングは最遠軸距の1/2以下(物品を車体の後方へ突出して積載しないものは2/3以下、その他の自動車のうち小型自動車は11/20以下)であること。(小型特殊自動車等適用除外有り)
○①前面衝突時の乗員保護規制 自動車(もっぱら乗用の用に供する自動車であって定員11人以上のもの、車両総重量2.8トンを超える貨物車、二輪車、側車付二輪車、トレーラ等を除く。)の車枠及び車体は、その自動車の前面が、衝突等による衝撃を受けた場合、運転者席及びこれと並列で自動車の側面に隣接する乗車人員に、過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
②側面衝突時の乗員保護規制 ①の規定が適用される自動車(もっぱら乗用の用に供する自動車であって定員10人以上のもの及び座席の地上面からの高さが700㎜を超えるものを除く。)の車枠及び車体は、その自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合、運転者席及びこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
○車体の後面には最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大積載容量及び物品名)を表示しなければならない。車両総重量が20トンを超える自動車にはその旨の表示を車体の前面にする。
○幼児等の運送を目的とした乗車定員11人以上の自動車は車体の前面、後面及び両側面にこれらの者の運送を目的とする自動車である旨表示しなければならない。
18条の2 巻 込 防 止 装 置 等
(巻込防止装置)○普通トラック及び車両総重量8トン以上の普通車(定員11人以上又はバス型状のものを除く。)の両側面には次に示す巻込防止装置を備えること。(歩行者等を後車輪へ巻き込むおそれの少ない構造の自動車を除く。)
○地上高は下縁450㎜以下、上縁650㎜以上。○平面部の上縁と荷台等との間隔550㎜以下。○タイヤ等の間げき400㎜以下。○平面部は最外側のタイヤ接地部中心点を結ぶ直線よりも外側のこと。(突入防止装置)○貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が3.5トン超えの自動車及びトラクタを除く。)は下縁の高さ700㎜以下、車幅の60%以上、後端より600㎜以下。

52
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
○貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が3.5トン超えのものは、下縁の高さ550㎜以下、平面部の高さ100㎜以上、装置の両端位置が後軸の車輪の最外側の内側100㎜の間・車両後面からの距離450㎜以下。
19 条 連 結 装 置○堅ろうで運行に十分耐えること。○確実に結合する構造でけん引車又は被けん引車に走行中振動等により分離しないよう適当な安全装置を備付けること。
20 条 乗 車 装 置
○乗車人員が動揺・衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できること。
○運転者及び助手以外の者の乗車装置を備える場合は客室を設けること。(二輪車、側車付二輪車、緊急車を除く)
○運転者室及び客室には必要な換気が得られる構造であること。○自動車の座席、座席ベルト、安全まくら、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装には、難燃性の材料を使用すること。(二輪車、側車付二輪車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊車、小型特殊車を除く。)
○インストルメントパネルは自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものであること。(二輪車等適用除外あり)
21 条 運 転 者 席
○運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられない構造であること。
○運転者席の幅は始動装置・制動装置等運転に際して操作を必要とする装置(乗車人員、積載物品等により操作を妨げられない装置を除く)の左右最外側までの範囲とし、この場合、最小範囲は、ハンドル中心から左右それぞれ200㎜までとする。
22 条 座 席
○1人当たりの座席は次のとおり。(運転者席及びまたがり式の座席を除く。)
○前方の座席等との間隔は定員11人以上の自動車は200㎜、幼児用座席は150㎜(対面式座席の場合はこれらの2倍以上)
○運転者以外の者の用に供する1名分の座席は幅380㎜以上、奥行400㎜以上あること。ただし、巾400㎜以上の着席する必要な空間を有すること。
○もっぱら乗用の用に供する自動車の座席及び当該座席の取り付け装置は衝撃等による衝撃を受けた時、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えること。ただし、またがり式の座席、折りたたみ式の座席(専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられたもの)、横向きの座席、非常口付近の座席、日常点検をする場合に取りはずしを必要とする座席を除く。
○乗用車の座席の後面部分は衝突等による衝撃を受けたとき、後席乗員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造であること。
550㎜以下650㎜以上
400㎜以下 450㎜以下 400㎜以下巻込防止装置 550㎜以下 450㎜以下
(負荷後)
巻込防止装置
100㎜以内
100㎜以上
突入防止装置
550㎜以下
座席の種類 巾 奥 行 備 考
一般の座席 380以上 400以上 巾400以上の空間
非常口付近の座席 380以上 250以上 〃
補助座席・車掌席 300以上(400以上の空間) 250以上 1人用に限る
幼児用座席 270以上 230〜270 座面高さ250以下前向きであること
単位(㎜)

53
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
22条の2 座 席 定 員 等
○座席定員等は、次式①、②を満足させること。 ①A≧1/2(A+B) ②A≧1/3(A+B+C) A:一般席の定員(運転者席含む) B:補助座席及び車掌席の定員(1人用) C:立席の定員(車椅子の用に供する床面には立席を設けないものとして計算する。)○車椅子の用に供する床面とは、車椅子用の表示がなされ、かつ、車椅子の固定器具又は握り棒を床面又はその周辺の壁等に備えた床面で、立席用の床面と明瞭に区分されているものをいい有効長さ120㎝、有効巾80㎝を最低限とする。
22条の3 座 席 ベ ル ト 等
○次表のとおり座席ベルトを備えること。
○座席ベルト取付装置は次の各号に適合すること。 ⑴ 衝突等により座席ベルトから受ける荷重に十分耐えること。 ⑵ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないこと。 ⑶ 座席ベルトが有効に作用する位置に備えられていること。 ⑷ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えられていること。
⑸ 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。○座席ベルトは次の各号に適合すること。 ⑴ 自動車が衝撃を受けた場合に当該座席ベルト装着者に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
⑵ 第二種座席ベルトは自動車が衝撃を受けた場合に、当該座席ベルト装着者が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止できること。
⑶ 第一種座席ベルトは自動車が衝撃を受けた場合に、当該座席ベルト装着者が座席の前方に移動することを防止できること。
⑷ 容易に脱着ができ、かつ、長さ調節ができること。 ⑸ 第二種座席ベルト並びに運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の運行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造のものであること。
⑹ 普通乗用車又は、小型車・軽自動車(定員11人以上の自動車を除く。)には、運転者席の座席ベルトが装着されていない場合に、その旨を運転者に警報する装置を備えること。
22条の4 頭 部 後 傾 仰 止 装 置 等
○専ら乗用(普通・小型・軽)、小型トラック、軽トラックの運転者席と助手席にはヘッドレストを備えること。(タクシーは4席分)
○ヘッドレストは次の各号に適合すること。 ⑴ 乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止できること。 ⑵ 乗車人員の頭部等に傷害を与えない構造であること。 ⑶ 振動、衝撃等により脱落しないように備えてあること。
自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別
乗用車小型トラック軽トラック
運転者席その他の自動車の側面に隣接する座席であって前向きのもの
第二種座席ベルト(三点式)
上記以外の座席 第一種座席ベルト(二点式)又は第二種座席ベルト
普通トラック高速路線バス貸切バス自家用バス
すべての座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト
一般路線バス 運転者席及びそれと並列する座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト

54
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
22条の5 年少者用補助乗車装置
○年少者用補助乗車装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 ⑴ 年少者用補助乗車装置を備える座席及び座席ベルトを損傷しないものであること。 ⑵ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。
⑶ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者及び当該年少者用補助乗車装置が第22条の3第3項の基準に適合する座席ベルト等により座席の前方に移動しないようにすることができるものであること。
⑷ 容易に着脱することができるものであること。
23 条 通 路
○定員11人以上の自動車(緊急車を除く。)ハイヤー・タクシー及び幼児専用車には、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けること。(乗降口から直接着席できる座席を除く。)
○安全かつ容易に通行できるものであること。○幅300㎜以上、高さ1,600(1,200)㎜以上。
24 条 立 席
○客室内の有効幅300㎜以上、有効高さ1,800㎜以上の専ら座席の用に供する床面以外の床面に限り設けることができる。(緊急車の立席及び車掌の用に供する立席を除く。)
○立席人員1人の占める広さは0.14平方メートルとする。○座席の前縁から250㎜の床面は専ら座席の用に供する床面とする。○幼児専用車には立席を設けることができない。
25 条 乗 降 口
○衝撃により容易に開放しないこと。○乗降口のうち1個は、右側面以外の面に設けること。○バス、幼児専用車、左側面1ヶ所以上。○ハイヤー・タクシー、定員11人以上の自動車(緊急車及び幼児専用車を除く)の乗降口は次の基準に適合していること。(乗降口から直接着座できる座席のためのみの乗降口を除く。)
○有効幅600㎜以上、有効高さ1,600(1,200)㎜以上。( )内の数値は、すべての座席の前縁と最も近い乗降口との車両中心線方向の最短距離が2ⅿ未満の場合。
① 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。② 床面の高さが地上450㎜(幼児専用車は300㎜)を超える乗降口には、乗降用取手を備えること。
26 条 非 常 口
○幼児専用車及び定員30人以上の自動車(緊急車を除く)には非常口を設けること。(すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車を除く。)
○客室の右側面の後部又は後面に設けられていること。○一般の非常口は幅400㎜以上、高さ1,200㎜以上であること。○その他の非常口の規定あり。扉、非常口付近、表示、警報装置の基準もある。
27 条 物 品 積 載 装 置○堅ろうで安全、確実に物品を積載できる構造であること。○土砂等運搬大型自動車には最大積載量を超えて土砂等を積載できるような物品積載装置を備えてはならない。
28 条 高 圧 ガ ス 運 送 装 置 略
対象車
項目 ハイヤー・タクシー 幼児専用車
定員11人以上の自動車
自家用 事業用
高さ最下段 450以下 300以下 450以下 450以下
その他 400以下 200以下 400以下 400以下
有効奥行 − 200以上 − 300以上(290)
単位(㎜)

55
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
29 条 窓 ガ ラ ス
○自動車の窓ガラスは安全ガラスであること。(乗員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられたものを除く。)
(前面ガラスの基準)① 損傷した場合に運転者の視野が確保できること。② 容易に貫通されないもの。(前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方部分除く)の基準)① 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないもの。② 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲における可視光線の透過率が70%以上のもの。
(はり付け及び塗装の禁止)○前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)には次のもの以外の標識、ポスター等を装着、はり付け、刻印及び塗装を行ってはならない。
① 国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの。② 臨時検査合格標章③ 検査標章④ 道路交通法に定める違法駐車ステッカー、故障ステッカー⑤ 車室内に備えるはり付け式の後写鏡⑥ はり付けられ又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲における可視光線の透過率が70%以上確保できるもの。
(参考図)
30 条 騒 音 防 止 装 置
(使用過程車)○騒音の大きさは次表の数値を超えないこと。(単位デシベル)
近接排気騒音の適用時期
・ステッカー等の貼付禁止・透過率70%以上
項目種別 近 接 排 気 定 常
二輪車・側車付二輪車 94
注(85) 85
乗 用 車リアエンジン以外 96
リアエンジン 100
自動車
その他の
総重量3.5t 超
150KW超 99
150KW以下 98
総重量3.5t 以下 97
項目
種別
型式指定車(法75条)軽認定車
(施行規則62条の3)
騒音認定車
施行規則62条の3の2
大臣指定車新型届出少 数特別取扱
その他
並行、試作等
二輪車・ 側車付二輪車
46.4. 1※1
(47.1.1)51.1.1 54.1.1
H1.4.1※2(61.6.1)
乗 用 車 H3.4.1※2(63.6.1)
その他の自動車
H4.4.1※2(H1.6.1)
��
��
���
���
��
(注)排気騒音は近接排気騒音が適用される製作年以前の車両にのみ適用される。
※1()内は、46.3.31以前に型式指定及び軽認定を受けた自動車の適用時期を示す。 ※2()内は、輸入車以外の自動車の適用時期を示す。

56
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
項 目
種 別
普通・小型・軽自動車(定員10人以下の乗用車、二輪車・側車付二輪車を除く。)
定員10人以下の乗用車で、普通・小型・軽自動車(二輪車・側車付二輪車を除く。)
総重量1.7t 超3.5t 以下
総重量1.7t 以下
軽自動車運転者席の前方にエンジン
運転者席の前方にエンジン以外
総重量3.5t 超200HP(150KW※)超
乗 用
乗用以外
総重量3.5t 超200HP(150KW※)以下
全輪駆動車
全輪駆動車以外
乗 用
乗用以外
後部エンジン定員7人以上
定員6人以下
後部エンジン以外定員7人以上
定員6人以下
小型二輪車
軽二輪車
近接排気騒音
10年規制前
10年規制
11年規制
12年規制
13年規制
10799 ← ←
99← ← ←
105 ← ←
←
9898
←
103 ←
←
97 ←97
97
←
103
←100 ← ←
100
←96 ← ←
96
99← ← ←
9494 ← ←
適 用 時 期
H10年規制 H11年規制 H12年規制 H13年規制
新型 継続 輸入 新型 継続 輸入 新型 継続 輸入 新型 継続 輸入
10.10.1 11.9.1 12.4.1
13.10.1 15.9.1 15.9.1
13.10.1 14.9.1 14.9.1
12.10.1 13.9.1 13.9.1
13.10.1 14.9.1 14.9.1
12.10.1 14.9.1 14.9.1
11.10.1 12.9.1 13.4.1
11.10.1 12.9.1 13.4.1
12.10.1 13.9.1 13.9.1
11.10.1 13.9.1 14.4.1
10.10.1 11.9.1 12.4.1
11.10.1 13.9.1 14.4.1
10.10.1 11.9.1 12.4.1
13.10.1 15.9.1 15.9.1
10.10.1 11.9.1 12.4.1
項 目
種 別
普通・小型・軽自動車(定員10人以下の乗用車、二輪車・側車付二輪車を除く。)
定員10人以下の乗用車で、普通・小型・軽自動車(二輪車・側車付二輪車を除く。)
総重量1.7t 超3.5t 以下
総重量1.7t 以下
軽自動車運転者席の前方にエンジン
運転者席の前方にエンジン以外
総重量3.5t 超200HP(150KW※)超
全輪駆動車、トラクタ及びクレーン車
全輪駆動車、トラクタ及びクレーン車以外
乗用
乗用以外
後部エンジン定員7人以上
定員6人以下
後部エンジン以外定員7人以上
定員6人以下
小型二輪車
軽二輪車
適 用 時 期
H10年規制 H11年規制 H12年規制 H13年規制
新型 継続 輸入 新型 継続 輸入 新型 継続 輸入 新型 継続 輸入
13.10.1 15. 9.1 15. 9.1
10.10.1 11.9.1 12.4.1
13.10.1 15.9.1 15.9.1
13.10.1 14.9.1 14.9.1
12.10.1 13.9.1 13.9.1
13.10.1 14.9.1 14.9.1
12.10.1 14.9.1 14.9.1
11.10.1 12.9.1 13.4.1
11.10.1 12.9.1 13.4.1
12.10.1 13.9.1 13.9.1
11.10.1 13.9.1 14.4.1
10.10.1 11.9.1 12.4.1
11.10.1 13.9.1 14.4.1
10.10.1 11.9.1 12.4.1
13.10.1 15.9.1 15.9.1
10.10.1 11.9.1 12.4.1
総重量3.5t 超200HP(150KW※)以下
全輪駆動車
全輪駆動車以外
乗 用
乗用以外
10年規制前
10年規制
11年規制
12年規制
13年規制
定
常
加
速
定
常
加
速
定
常
加
速
定
常
加
速
定
常
加
速
83 82
80 8382 81 ← ← ← ←
82 81← ← ← ← ← ←
78 83 ← ← ← ←
← ← 80 81
79 8079 80
← ←
74 78 ← ←
← ←
74 76 74 7674 76
74 76
← ←
70 78
← ←
72 76 ← ← ← ←72 76
← ←
72 76
74 75← ← ← ← ← ← 72 73
71 73 ← ← ← ← ← ←
条 項 項 目 基 準 内 容
平成10年規制前〜13年規制 近接排気騒音規制の規制値と適用時期 (単位デジベル)
(注)(150KW※)はH10年規制以降のもの
○内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止できる消音器を備えなければならない。
○基準に適合させる騒音防止装置を備えなければならない。
(新 車)○騒音の大きさは次表の数値を超えないこと。 平成10年規制前〜13年規制 定常・加速騒音の規制値と適用時期 (単位デシベル)
(注)(150KW※)はH10年規制以降のもの

57
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
31 条ば い 煙、 悪 臭 の あ るガ ス、 有 害 な ガ ス 等の 発 散 防 止 装 置
(アイドリング規制) ガソリン又はLPGを燃料とする自動車○一酸化炭素は測定値が4.5%以下であること。ただし、H10年アイドル規制以降の自動車は1%及び4サイクルの軽自動車は2%以下であること。
○炭化水素は測定値が1200PPMを超えないこと。(特殊エンジン3300PPM、2サイクルエンジン7800PPM)ただし、H10年アイドル規制以降の自動車は300PPM及び4サイクルの軽自動車は500PPM以下であること。
(黒煙規制) 軽油を燃料とする自動車○黒煙は3回測定し、その測定した値の平均値が50%以下であること。(H5年及びH6年規制車は40%以下)(H9年規制以降の自動車は25%以下)
(排出ガス発散防止装置)○原動機の作動中、確実に機能するものであること。○遮熱板の損傷又は脱落がないこと。(無接点式についてはこの限りではない)○温度警報装置を備えること。(無接点式についてはこの限りではない)(冷房装置)○導管は客室内に配管されていないこと。(損傷を受けないようおおいで保護されている部分を除く。)
○安全装置は車室内にガスを噴出しないように取り付けてあること。(排気管)○左向き又は右向きに開口していないこと。○発散する排気ガス等により自動車登録番号標の数字等の表示を妨げる位置に開口していないこと。
○車室内に配管されていないこと。○接触、発散する排気ガス等により自動車若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないこと
○ガソリン及びLPガスを燃料とする自動車はブローバイ・ガス還元装置を備えること。○ガソリンを燃料とする自動車は燃料蒸発ガス発散抑止措置を備えること。自動車排出ガス規制の経緯・カソリン車・LPG車(表1〜6)・ディーゼル車(表7〜11)

58
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
成分 測定方法48年度規制
50年度規 制
51年度規制53年度規 制 測定方法 53年規制 12年規制 成分 測定方法 17年規制
ガソリン LPG 慣性重量1t以下
慣性重量1t超
CO
10モード(g/㎞) 26.0 18.0 2.70 ➡ ➡ 10・15モード
(g/㎞) 2.70 1.27CO
コンバインモード(g/㎞)
1.9211モード(g/ test) 85.0 ➡ ➡ 11モード
(g/ test) 85.0 31.1
HC
10モード(g/㎞) 3.80 3.20 0.39 ➡ ➡ 10・15モード
(g/㎞) 0.39 0.17NMHC 0.08
11モード(g/ test) 9.50 ➡ ➡ 11モード
(g/ test) 9.50 4.42
NOx
10モード(g/㎞) 3.00 3.00 1.60 0.84 1.20 0.48 10・15モード
(g/㎞) 0.48 0.17NOx 0.08
11モード(g/ test) 11.0 8.00 9.00 6.00 11モード
(g/ test) 6.00 2.50
識 別 記 号 − A B C E E GH、HN ABA新型生産車の適用時期 48.4.1 50.4.1 51.4.1 53.4.1 3.11.1 12.10.1 17.10.1継続生産車の適用時期 48.12.1 50.12.1 52.3.1 54.3.1 3.11.1
14.9.119.9.1
輸入車の適用時期 ※1 51.4.1※2 53.3.1 56.4.1 5.4.1 19.9.1
表⒈ ガソリン・LPG乗用車(2サイクルエンジンを除く)
※1:新型生産車の適用時期48.4.1、継続生産車の適用時期48.12.1。ただし、型式指定自動車(法第75条の指定)に限る。※2:型式指定自動車(法第75条の指定)の適用時期は、50.4.1
条 項 項 目 基 準 内 容
表⒉ 2サイクル軽乗用車
注:1・2年規制については、3.11.1より測定方法が10・15モードに変更、輸入車については、5.4.1から。※1:新型生産車の適用時期48.4.1、継続生産車の適用時期48.12.1。ただし、型式指定自動車(法第75条の指定)に限る。※2:型式指定自動車(法第75条の指定)の適用時期は、50.4.1
成分 測定方法 48年度規 制
50年度規制 53年度規 制 測定方法 53年規制 12年規制 成分 測定方法 17年規制
暫定
CO
10モード(g/㎞) 26.0 2.70 ➡ ➡
10・15モード(g/㎞)
2.70 1.27CO
コンバインモード(g/㎞)
1.9211モード(g/ test) 85.0 ➡ ➡ 85.0 31.1
HC
10モード(g/㎞) 22.5 5.60 0.39 ➡ 0.39 0.17
NMHC 0.0811モード(g/ test) 33.0 9.50 ➡ 9.50 4.42
NOx
10モード(g/㎞) 0.50 ➡ ➡ 0.48 0.48 0.17
NOx 0.0811モード(g/ test) 6.00 ➡ ➡ 6.00 2.50
識 別 記 号 − A E E GH、HN ABA新型生産車の適用時期 48.4.1 50.4.1 52.10.1 53.4.1 3.11.1 12.10.1 17.10.1継続生産車の適用時期 48.12.1 51.4.1 52.10.1 54.3.1 3.11.1
14.9.119.9.1
輸入車の適用時期 ※1 51.4.1※2 52.10.1 56.4.1 5.4.1 19.9.1
表⒊ ガソリン・LPG軽量車(車両総重量1.7トン以下)
※1:新型生産車の適用時期48.4.1、継続生産車の適用時期48.12.1。ただし、型式指定自動車(法第75条の指定)に限る。※2:型式指定自動車(法第75条の指定)の適用時期は、50.4.1
成分 測定方法48年度規制 50年度
規 制 54年規制 56年規制 63年規制 測定方法 63年規制 12年規制 成分 測定方法 17年規制ガソリン LPG
CO
10モード(g/㎞) 26.0 18.0 17.0 ➡ ➡ 2.70 10・15モード
(g/㎞) 2.70 1.27CO
コンバインモード(g/㎞)
1.9211モード(g/ test) 130.0 ➡ ➡ 85.0 11モード
(g/ test) 85.0 31.1
HC
10モード(g/㎞) 3.80 3.20 2.70 ➡ ➡ 0.39 10・15モード
(g/㎞) 0.39 0.17NMHC 0.08
11モード(g/ test) 17.0 ➡ ➡ 9.50 11モード
(g/ test) 9.50 4.42
NOx
10モード(g/㎞) 3.00 3.00 2.30 1.40 0.84 0.48 10・15モード
(g/㎞) 0.48 0.17NOx 0.08
11モード(g/ test) 20.0 10.0 8.00 6.00 11モード
(g/ test) 6.00 2.50
識 別 記 号 − H J L R R GJ、HP ABE新型生産車の適用時期 48.4.1 50.4.1 54.1.1 56.1.1 63.12.1 3.11.1 12.10.1 17.10.1継続生産車の適用時期 48.12.1 50.12.1 54.12.1 56.12.1 1.12.1 3.11.1
14.9.119.9.1
輸入車の適用時期 ※1 51.4.1※2 56.4.1 58.4.1 3.4.1 5.4.1 19.9.1

59
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
表4−⒈ ガソリン・LPG中量車(車両総重量1.7トン超〜2.5トン以下)
※1:新型生産車の適用時期48.4.1、継続生産車の適用時期48.12.1。ただし、型式指定自動車(法第75条の指定)に限る。※2:型式指定自動車(法第75条の指定)の適用時期は、50.4.1※3:13年規制以降は、3.5トン以下。
成分 測定方法48年度規制 50年度
規 制 54年規制 56年規制 元年規制 測定方法 元年規制 6年規制 10年規制 13年規制ガソリン LPG
CO
10モード(g/㎞) 26.0 18.0 17.0 ➡ ➡ ➡ 10・15モード
(g/㎞) 17.0 ➡ 8.42 3.36
11モード(g/ test) 130.0 ➡ ➡ ➡ 11モード
(g/ test) 130.0 ➡ 104.0 38.5
HC
10モード(g/㎞) 3.80 3.20 2.70 ➡ ➡ ➡ 10・15モード
(g/㎞) 2.70 ➡ 0.39 0.17
11モード(g/ test) 17.0 ➡ ➡ ➡ 11モード
(g/ test) 17.0 ➡ 9.50 4.42
NOx
10モード(g/㎞) 3.00 3.00 2.30 1.60 1.26 0.98 10・15モード
(g/㎞) 0.98 0.63 ➡ 0.25
11モード(g/ test) 20.0 11.0 9.50 8.50 11モード
(g/ test) 8.50 6.60 ➡ 2.78
識 別 記 号 − H J L T T GA GC GK、HQ新型生産車の適用時期 48.4.1 50.4.1 54.1.1 56.12.1 1.10.1 3.11.1 6.12.1 10.10.1 13.10.1継続生産車の適用時期 48.12.1 50.12.1 54.12.1 57.11.1 2.9.1 3.11.1 7.11.1 11.9.1
15.9.1輸入車の適用時期 ※1 51.4.1
※2 56.4.1 59.4.1 3.4.1 5.4.1 8.4.1 12.4.1
表4−⒉ ガソリン・LPG中量車(車両総重量1.7トン超〜2.5トン以下)
成分 測定方法 17年規制
COコンバインモード
(g/㎞)
4.08
NMHC 0.08
NOx 0.10
識 別 記 号 ABF新型生産車の適用時期 17.10.1継続生産車の適用時期 19.9.1
輸入車の適用時期 19.9.1
表⒌ 軽自動車(乗用車以外)
注:⒈( )内は、2サイクルエンジンの規制値を示す。
成分 測定方法48年度規制 50年度
規 制 54年規制 57年規制 測定方法 2年規制 10年規制 14年規制ガソリン LPG
CO
10モード(g/㎞) 26.0 18.0 17.0 ➡ ➡
10モード or(g/㎞)
10・15モード(g/㎞)
➡ 8.42 5.11(17.0)
11モード(g/ test) 130.0 ➡ ➡ ➡ 104.0 58.9
(130.0)
HC
10モード(g/㎞)
3.80(22.5) 3.20 2.70
(15.0) ➡ ➡ ➡ 0.39(➡)
0.25(➡)
11モード(g/ test)
17.0(70.0) ➡ ➡ ➡ 9.50
(➡)6.40(➡)
NOx
10モード(g/㎞)
3.00(0.50) 3.00 2.30
(0.50)1.60(➡)
1.26(➡)
0.74(➡)
0.48(➡)
0.25(➡)
11モード(g/ test)
20.0(4.00)
11.0(➡)
9.50(➡)
7.50(➡)
6.00(➡)
3.63(➡)
識 別 記 号 − H J M V GD GM、HS新型生産車の適用時期 48.4.1 50.4.1 54.4.1 57.1.1 2.10.1 10.10.1 14.10.1継続生産車の適用時期 48.12.1 50.12.1 54.12.1 57.12.1 3.9.1 11.9.1
15.9.1輸入車の適用時期 − 51.4.1 56.4.1 59.4.1 4.4.1 12.4.1
表6−⒈ ガソリン・LPG重量車(車両総重量2.5トン超)
注:⒈ 並行輸入車、試作車等は規制対象外。 ⒉ 13年規制以降は、3.5トン超。
成分 測定方法48年度規制 52年度規制 54年規制 57年規制 元年規制
測定方法4年規制 7年規制
10年規制 13年規制ガソリン LPG ガソリン LPG ガソリン LPG ガソリン LPG ガソリン LPG ガソリン LPG ガソリン LPG
CO(%)
6モード
1.6 1.1 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ガソリン13モード(g/ kwh)
136 105 ➡ ➡ 68.0 26.0
HC(ppm) 520 440 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 7.9 6.8 ➡ ➡ 2.29 0.99
NOx(ppm) 2200 2200 1850 1390 990 850 7.2 7.2 5.9 5.9 ➡ 2.03
識 別 記 号 − − J M T Z GB GE GL、HB新型生産車の適用時期 48.4.1 52.8.1 54.4.1 57.1.1 1.10.1 4.10.1 7.12.1 10.10.1 13.10.1継続生産車の適用時期 48.12.1 53.4.1 54.12.1 57.12.1 2.9.1 5.9.1 8.11.1 11.9.1
15.9.1輸入車の適用時期 − − 56.4.1 59.4.1 3.4.1 6.4.1 9.4.1 12.4.1

60
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
表6−⒉ ガソリン・LPG重量車 (車両総重量2.5トン超)
成分 測定方法 17年規制
CO
JE05M(g/㎞ h)
21.3
NMHC 0.31
NOx 0.90
識 別 記 号 ABG新型生産車の適用時期 17.10.1継続生産車の適用時期 19.9.1
輸入車の適用時期 19.9.1
表7 二輪自動車・側車付二輪自動車(ガソリンエンジンに限る。)
成分 測定方法10年規制 11年規制
4サイクル 2サイクル 4サイクル 2サイクルCO 二輪車モード(g/㎞) 20.0 14.4 ➡ ➡HC 二輪車モード(g/㎞) 2.93 5.26 ➡ ➡NOx 二輪車モード(g/㎞) 0.51 0.14 ➡ ➡識 別 記 号 BA BB BC BD対 象 二 輪 自 動 車 軽二輪 小型二輪新型生産車の適用時期 10.10.1 11.10.1継続生産車の適用時期 11.9.1 12.9.1輸入車の適用時期 12.4.1 13.4.1
表8−⒈ ディーゼル乗用車
測定方法
※1:6モードppm(49年〜)
※2:10モードg/㎞(61年〜)
※3:10・15モードg/㎞(3年〜)
※149年度規制
※152年度規制
※154年規制
※157年規制
※261年・62年規制
※22年規制
※33年規制
※34年規制
※36年規制
※39年規制
※310年規制
980 ➡ ➡ ➡ 2.70 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡670 ➡ ➡ ➡ 0.62 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡
590 500 450 3900.98 0.72 ➡ ➡ ➡ 0.55 ➡
1.26 ➡ ➡ 0.84 ➡ − 0.55
50 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 40 25 ➡50 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 40 25 ➡− − − − − − − − 0.34 0.14 ➡− − − − − − − − − 0.34 0.14− − K N Q X Q or X Y KD KE KH
49.9.1 52.8.1 54.4.1 57.1.1 61.10.1(62.10.1) 2.12.1 3.11.1 4.10.1 6.10.1 9.10.1 10.10.1
50.4.1 53.4.1 55.3.1 57.12.1 62.9.1(63.9.1) 3.11.1 3.11.1 5.9.1 7.9.1 11.7.1 11.9.1
− − − − 63.4.1(1.4.1) 5.4.1 5.4.1 6.4.1 8.4.1 12.4.1 12.4.1
黒煙
3モード(%)無負荷急加速(%)
成 分
COHC
NOx車両重量(1265㎏以下)NOx車両重量(1265㎏超)
粒子状物質(g/㎞)
(1265㎏以下)(1265㎏超)
識 別 記 号
新型生産車の適用時期
継続生産車の適用時期
輸入車の適用時期
条 項 項 目 基 準 内 容
注:⒈ 61年規制はM/T車、62年規制A/T車である。 ⒉ 適用時期欄中( )は62年規制を示す。
表8−⒉ ディーゼル乗用車
測定方法
10・15モード(g/㎞)
14年規制測定方法
17年規制上限値 平均値 上限値 平均値0.98 0.63
コンバインモード(g/㎞)
0.84 0.630.24 0.12 0.032☆ 0.024☆0.43 0.28 0.19 0.140.45 0.30 0.20 0.15
0.110.052 0.017 0.0130.056 0.019 0.014
25 4モード(%) 2525 無負荷急加速(%) 25
KM・HT ADBKN・HU ADC14.10.1 17.10.1
16.9.1 19.9.1
黒煙
4モード(%)無負荷急加速(%)
成 分
COHC
識別記号車両重量1265㎏以下車両重量1265㎏超
新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
☆平成17規制よりNMHC(非メタン炭化水素)
NOx車両重量1265㎏以下車両重量1265㎏超
PM車両重量1265㎏以下車両重量1265㎏超
表9−⒈ ディーゼル軽量車(車両総重量1.7トン以下)
測定方法
6モード(ppm)
49年度規制 52年度規制 54年規制 57年規制 58年規制 測定方法 63年規制 測定方法 5年規制 9年規制
980 ➡ ➡ ➡ ➡ 10モード(g/㎞)10・15モード(g/㎞)
2.7010・15モード(g/㎞)
2.70 ➡670 ➡ ➡ ➡ ➡ 0.62 0.62 ➡1000 850 700 ➡ 610
1.26 0.84 0.55590 500 450 390 ➡50 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 40 2550 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 40 25− − − − − − 0.34 0.14− − K N P S KA KE
49.4.1 52.8.1 54.4.1 57.10.1 58.8.1 63.12.1 5.10.1 9.10.150.4.1 53.4.1 55.3.1 58.9.1 59.7.1 1.11.1 6.9.1 11.7.1− − 56.4.1 59.4.1 60.4.1 3.4.1 7.4.1 12.4.1
黒煙
3モード(%)無負荷急加速(%)
成 分
COHC
NO(DI)NO(IDI)
粒子状物質 (g/㎞)識 別 記 号新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
注:⒈ DIは直接噴射式を、IDIは副室式を示す。 ⒉ 63年規制については、3.11.1より測定方法が10・15モードに変更、輸入車については5.4.1から。

61
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
表9−⒉ ディーゼル軽量車(車両総重量1.7トン以下)
測定方法
10・15モード(g/㎞)
黒煙
4モード(%)無負荷急加速(%)
成 分
COHCNOxPM
識 別 記 号新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
14年規制測定方法
17年規制上限値 平均値 上限値 平均値0.98 0.63
コンバインモード
(g/㎞)
0.84 0.630.24 0.12 0.032☆ 0.024☆0.43 0.28 0.19 0.140.11 0.052 0.017 0.013
25 2525 25
KP・HW ADE14.10.1 17.10.1
16.9.1 19.9.1
☆平成17規制よりNMHC(非メタン炭化水素)
表10−⒈ ディーゼル中量車(車両総重量1.7トン超〜2.5トン以下)
測定方法
6モード(ppm)
49年度規制 52年度規制 54年規制 57年規制 58年規制 63年規制 測定方法 5年規制 9年規制 10年規制
980 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡10・15モード(g/㎞)
2.70 ➡ ➡670 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 0.62 ➡ ➡1000 850 700 ➡ 610 500
1.82 MT0.97AT(➡)
MT(➡)AT0.97590 500 450 390 ➡ 350
50 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 40 25 ➡50 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 40 25 ➡− − − − − − 0.43 MT0.18 AT(➡) 0.18− − K N P S KB KF KJ
49.9.1 52.8.1 54.4.1 57.10.1 58.8.1 63.12.1 5.10.1 9.10.1 10.10.150.4.1 53.4.1 55.3.1 58.9.1 59.7.1 1.11.1 6.9.1 11.7.1 11.9.1− − 56.4.1 59.4.1 60.4.1 3.4.1 7.4.1 12.4.1 12.4.1
黒煙
3モード(%)無負荷急加速(%)
成 分
COHC
NOx(DI)NOx(IDI)
粒子状物質 (g/㎞)識 別 記 号新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
注:DIは直接噴射式を、IDIは副室式を示す。
表10−⒉ ディーゼル中量車(車両総重量1.7トン超〜2.5トン以下)
測定方法
10・15モード(g/㎞)
黒煙
4モード(%)無負荷急加速(%)
成 分
COHCNOxPM
識 別 記 号新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
15年規制測定方法
17年規制上限値 平均値 上限値 平均値0.98 0.63
コンバインモード
(g/㎞)
0.84 0.630.24 0.12 0.032☆ 0.024☆0.68 0.49 0.33 0.250.12 0.06 0.020 0.015
25 2525 25
KQ・HX ADF15.10.1 17.10.1
16.9.1 19.9.1
☆平成17規制よりNMHC(非メタン炭化水素)
表11−⒈ ディーゼル重量車(車両総重量2.5トン超)
測定方法
6モード(ppm)
49年度規制 52年度規制 54年規制 57年規制 58年規制 63年規制 元年規制 2年規制 測定方法 6年規制 9年規制 10年規制 11年規制
980 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡
ディーゼル13モード
(g/ kwh)
9.20 ➡ ➡ ➡670 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 3.80 ➡ ➡ ➡
1000 850 700 ➡ 610 (3.5㌧以下)520 ➡ ➡ 7.80
(3.5㌧以下)5.80
(12㌧以下)5.80
(12㌧超)5.80
590 500 450 390 ➡ ➡ (3.5㌧以下)350 ➡ 6.80
50 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 40 (3.5㌧以下)25
(12㌧以下)➡
(〃)➡
50 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 40 (〃)25
(〃)➡
(〃)➡
− − − − − − − − 0.96 (〃)0.49
(〃)➡
(〃)➡
− − K N P S U W KC KG KK KL49.9.1 52.8.1 54.4.1 57.10.1 58.8.1 63.12.1 1.10.1 2.10.1 6.10.1 9.10.1 10.10.1 11.10.150.4.1 53.4.1 55.3.1 58.9.1 59.7.1 1.11.1 2.9.1 3.9.1 7.9.1 11.7.1 11.9.1 12.9.1− − 56.4.1 59.4.1 60.4.1 3.4.1 3.4.1 4.4.1 8.4.1 12.4.1 12.4.1 13.4.1
黒煙
3モード(%)
無負荷急加速(%)
成 分
COHCNOx(DI)NOx(IDI)
粒子状物質(g/ kwh)
識 別 記 号新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期注:⒈ 並行輸入車、試作車等は規制対象外。 ⒉ DIは直接噴射式を、IDIは副室式を示す。 ⒊ 63年規制は、車両総重量3.5トン以下の車が規制対象。
⒋ 元年規制は、車両総重量3.5トンを超える車が規制対象。 ⒌ 2年規制は、車両総重量8トンを超えるトラクタ、クレーン車が規制対象。

62
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
表11−⒉ ディーゼル重量車(車両総重量2.5トン超)
測定方法
13モード(g/ kwh)
黒煙
4モード(%)無負荷急加速(%)
成 分
COHCNOxPM
識 別 記 号新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
15年規制(GVW12トン以下)
16年規制(GVW12トン超) 測定方法
17年規制
上限値 平均値 上限値 平均値 上限値 平均値3.46 2.22 3.46 2.22
JE05モード(g/㎞ h)
2.95 2.221.47 0.87 1.47 0.87 0.23☆ 0.17☆4.22 3.38 4.22 3.38 2.7 2.00.35 0.18 0.35 0.18 0.036 0.027
25 25 2525 25 25
KR・HY KS・HZ ADG15.10.1 16.10.1 17.10.1
16.9.1 17.9.1 19.9.1
☆平成17規制よりNMHC(非メタン炭化水素) 注:並行輸入車、試作車等は規制対象外。※:58年、元年規制はGVW 8t超のクレーン作業用自動車等を除く。なお、2年規制はGVW8t超のクレーン作業用自動車等に限る。
表12.その他燃料 乗用車
測定方法
コンバインモード(g/㎞)
成 分
CONMHC
粒子状物質(g/㎞)
車両重量1265㎏以下車両重量1265㎏超
新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
NOx車両重量1265㎏以下車両重量1265㎏超
17年規制上限値 平均値1.92 1.150.08 0.050.19 0.140.20 0.150.017 0.0130.019 0.01417.10.1
19.9.1
表13.その他燃料 軽量車(車両総重量1.7トン以下)
測定方法
コンバインモード(g/㎞)
成 分
CONMHCNOx粒子状物質
新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
17年規制上限値 平均値1.92 1.150.08 0.050.19 0.140.017 0.01317.10.1
19.9.1
表14.その他燃料 中量車(車両総重量1.7トン超〜3.5トン以下)
測定方法
コンバインモード(g/㎞)
成 分
CONMHCNOx粒子状物質
新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
17年規制上限値 平均値4.08 2.550.08 0.050.33 0.250.020 0.01517.10.1
19.9.1
表15.その他燃料 重量車(車両総重量3.5トン超)
測定方法
JE05モード(g/㎞)
成 分
CONMHCNOx
粒子状物質新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
17年規制上限値 平均値21.3 16.00.31 0.232.7 2.00.036 0.02717.10.1
19.9.1
表16.その他燃料 軽貨物自動車
測定方法
コンバインモード(g/㎞)
成 分
CONMHCNOx
粒子状物質新型生産車の適用時期継続生産車の適用時期輸入車の適用時期
17年規制上限値 平均値6.67 4.020.08 0.050.20 0.150.019 0.01419.10.1
20.9.1

63
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
31条の2 特 定 自 動 車 の 特 例
1 「自動車NOx法」の概要 大都市地域における窒素酸化物(NO x)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。これまでも、工場等に対する規制や自動車排出ガス規制の強化に加え、自動車NO x法(平成4年)に基づいて特別の排出基準を定めての規制(車種規制)をはじめとする対策を実施してきましたが、自動車の交通量の増大等により対策の目標とした二酸化窒素に係る大気環境基準をおおむね達成することは困難な状況です。一方、粒子状物質(PM)による大気汚染も大都市地域を中心に浮遊粒子状物質の環境基準の達成状況が低いレベルが続くという大変厳しい状況で、特に、近年、ディーゼル車から排出される粒子状物質については、発がん性のおそれを含む国民の健康への悪影響が懸念されています。このため、窒素酸化物に対する従来の対策を更に強化するとともに、自動車交通から生ずる粒子状物質の削減を図るために新たな対策を早急に講ずることが強く求められています。
こうした背景を受けて、平成13年6月に自動車NO x法の改正法(自動車NO x・PM法)が成立しました。
「自動車NOx・PM法」には、① 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質に関する総量削減基本方針・総量削減計画(国及び地方公共団体で策定する総合的な対策の枠組み)
② 車種規制(対策地域のトラック、バス、ディーゼル乗用車などに適用される自動車の使用規制)
③ 事業者排出抑制対策(一定規模以上の事業者の自動車使用管理計画の作成等により窒素酸化物及び粒子状物質の排出の抑制を行う仕組み)
などが含まれています。2 車種規制とは 車種規制とは、自動車NOx・PM法の対策地域に指定された地域で、トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車に関して特別の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準(以下「排出基準」といいます。)を定め、これに適合する窒素酸化物及び粒子状物質の排出量がより少ない車を使っていただくための規制です。この規制は対策地域内に使用の本拠の位置を有する新車と現在使用している車について適用されます。
① 自動車使用車種規制の施行日 平成14年10月1日② 対策地域
対策地域〈首都圏〉
埼玉県
川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、本庄市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、さいたま市、北足立郡、入間郡大井町、同郡三芳町、比企郡川島町、同郡吉見町、児玉郡上里町、大里郡大里町、同郡岡部町、同郡川本町、同郡花園町、北埼玉郡騎西町、同郡南河原村、同郡川里町、南埼玉郡及び北葛飾郡
千葉県
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市及び東葛飾郡
東京都
特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町及び同郡日の出町
神奈川県
横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、高座郡、中郡、足柄上郡中井町、同郡大井町、愛甲郡愛川町及び津久井郡城山町
対策地域〈愛知・三重圏〉
愛知県
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡平和町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡十四山村、同郡飛島村、同郡弥豊町、同郡佐屋町、同郡佐織町、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡武豊町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、宝飯郡音羽町、同郡小坂井町及び同郡御津町

64
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
③ 指定自動車
参考1 特定自動車排出基準 適合・非適合車………………………表12 特定自動車排出基準に適合しない 使用過程車の使用可能最終日………表2
三重県
四日市市、桑名市、鈴鹿市、桑名郡長島町、同郡木曽岬町、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町
対策地域〈大阪・兵庫圏〉
大阪府
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、泉北郡、泉南郡熊取町、同郡田尻町及び南河内郡美原町
兵庫県
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡播磨町及び揖保郡太子町
車 種 ナンバープレートの分類番号
普通トラック 1、10〜19、100〜199
小型トラック 4、40〜49、400〜4996、60〜69、600〜699
大型バス(定員30人以上) 2、20〜29、200〜299
マイクロバス(定員11人以上30人未満) 2、20〜29、200〜299
特種自動車(トラック、バス、ディーゼル乗用車をベースとしたものに限る) 8、80〜89、800〜899
ディーゼル乗用車(定員11人未満)
3、30〜39、300〜3995、50〜59、500〜5997、70〜79、700〜799

65
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
車両総重量
ディーゼル車
ガソリン・LPG車
窒素酸化物等排出基準
〔測定モード〕
排出ガス規制区分(型式の識別記号)
適否
窒素酸化物等排出基準
〔測定モード〕
排出ガス規制区分(型式の識別記号)
適否
ト ラ ッ ク ・ バ ス
1.7t以下
NOx:0.48(0.25)g/㎞
PM:0.055(0.026)g/㎞
〔10.15〕
平成14年規制適合車(KP−、HW−)
平成9年規制適合車(KE−、HA−)
平成5年規制適合車(KA−)
昭和63年規制適合車(S−)
昭和58年規制適合車(P−)
昭和57年規制適合車(N−)
昭和54年規制適合車(K−)
昭和52年度規制以前(記号なし)
× × × × × × × ×
NOx:0.48(0.25)g/㎞
〔10.15〕
平成12年規制適合車(GJ−、HP−)
平成10年アイドリング規制適合車(GG−、HL−)
昭和63年規制適合車(R−)
昭和56年規制適合車(L−)
昭和54年規制適合車(J−)
昭和50年度規制適合車(H−)
昭和48年度規制以前(記号なし)
○ ○ ○ × × × ×
1.7t超
2.5t以下
NOx:0.63(0.40)g/㎞
PM:0.06(0.03)g/㎞
〔10.15〕
平成15年規制適合車(KQ−、HX−)
平成10年規制適合車(KJ−、HE−)
平成9年規制適合車(KF−、HB−)
平成5年規制適合車(KB−)
昭和63年規制適合車(S−)
昭和58年規制適合車(P−)
昭和57年規制適合車(N−)
昭和54年規制適合車(K−)
昭和52年度規制以前(記号なし)
× × × × × × × × ×
NOx:0.63(0.40)g/㎞
〔10.15〕
平成13年規制適合車(GK−、HQ−)
平成10年規制適合車(GC−、HG−)
平成6年規制適合車(GA−)
平成元年規制適合車(T−)
昭和56年規制適合車(L−)
昭和54年規制適合車(J−)
昭和50年度規制適合車(H−)
昭和48年度規制以前(記号なし)
○ ○ ○ × × × × ×
2.5t超
3.5t以下
NOx:5.9(4.50)g/kWh
PM:0.175(0.09)g/kWh
〔D13〕
平成15年規制適合車(KR−、HY−)
平成9年規制適合車(KG−、HC−)
平成6年規制適合車(KC−)
平成元年規制適合車(U−)
昭和63年規制適合車(S−)
昭和58年規制適合車(P−)
昭和57年規制適合車(N−)
昭和54年規制適合車(K−)
昭和52年度規制以前(記号なし)
× × × × × × × × ×
NOx:5.9(4.50)g/kWh
〔G13〕
平成13年規制適合車(GK−、HQ−)
平成10年規制適合車(GE−、HJ−)
平成7年規制適合車(GB−)
平成4年規制適合車(Z−)
平成元年規制適合車(T−)
昭和57年規制適合車(M−)
昭和54年規制適合車(J−)
昭和52年度規制以前(記号なし)
○ ○ ○ × × × × ×
3.5t超
NOx:5.9(4.50)g/kWh
PM:0.49(0.25)g/kWh
〔D13〕
平成16年規制適合車(KS−、HZ−)
平成15年規制適合車(KR−、HY−)
平成11年規制適合車(KL−、HM−)
平成10年規制適合車(KK−、HF−)
平成6年規制適合車(KC−)
平成2年規制適合車(W−)
平成元年規制適合車(U−)
昭和58年規制適合車(P−)
昭和57年規制適合車(N−)
昭和54年規制適合車(K−)
昭和52年度規制以前(記号なし)
○ ○ ○ ○ × × × × × × ×
NOx:5.9(4.50)g/kWh
〔G13〕
平成13年規制適合車(GL−、HR−)
平成10年規制適合車(GE−、HJ−)
平成7年規制適合車(GB−)
平成4年規制適合車(Z−)
平成元年規制適合車(T−)
昭和57年規制適合車(M−)
昭和54年規制適合車(J−)
昭和52年度規制以前(記号なし)
○ ○ ○ × × × × ×
乗用車
NOx:0.48(0.25)g/㎞
PM:車両重量1265㎏以下
0.055(0.026)g/㎞
車両重量1265㎏超
0.055(0.028)g/㎞
〔10.15〕
平成14年規制適合車(KM−、KN−、HT−、HU−)
平成10年規制適合車(KH−、HD−)
平成9年規制適合車(KE−、HA−)
平成6年規制適合車(KD−)
平成4年規制適合車(Y−)
平成2年規制適合車(X−)
昭和61、62年規制適合車(Q−)
昭和58年規制適合車(P−)
昭和57年規制適合車(N−)
昭和54年規制適合車(K−)
昭和52年度規制以前(記号なし)
× × × × × × × × × × ×
特定
自動
車排
出基
準適
合・
非適
合車
特定
自動
車排
出基
準適
合・
非適
合車
〔表
1〕
注1「○」は適、「×」は否を示す。ただし、「×」となっている自動車であっても、型式によってはNOx及びPMの排出量が特に少なく基準に適合となるものもある。
注2窒素酸化物等排出基準欄の( )内の数値は、平均排出ガス基準値を示す。また、10・15は10・15モード、D13はディーゼル自動車13モード、G13はガソリン自動車13モードを示す。

66
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
排 出 基 準 に 適 合 し な い 使 用 過 程 車 の 使 用 可 能 最 終 日 の 一 覧 表
自動車の種別
初度登録年月日
使用可能最終日
普通トラック
平成元年9月30日以前
平成元年10月1日〜平成5年9月30日
平成5年10月1日〜平成8年9月30日
平成8年10月1日〜平成14年9月30日
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
小型トラック
平成2年9月30日以前
平成2年10月1日〜平成6年9月30日
平成6年10月1日〜平成9年9月30日
平成9年10月1日〜平成14年9月30日
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
初度登録日から起算して8年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
大型バス(定員30人以上)
昭和61年9月30日以前
昭和61年10月1日〜平成2年9月30日
平成2年10月1日〜平成5年9月30日
平成5年10月1日〜平成14年9月30日
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
初度登録日から起算して12年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
マイクロバス
(定員11人以上30人未満)
特種自動車
(車検期間が1年のもの)
昭和63年9月30日以前
昭和63年10月1日〜平成4年9月30日
平成4年10月1日〜平成7年9月30日
平成7年10月1日〜平成14年9月30日
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
特種自動車
(車検期間が2年のもの)
昭和63年9月30日以前
昭和63年10月1日〜平成4年9月30日
平成4年10月1日〜平成7年9月30日
平成7年10月1日〜平成14年9月30日
★平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
ディーゼル乗用車
(車検期間が1年のもの)
平成元年9月30日以前
平成元年10月1日〜平成5年9月30日
平成5年10月1日〜平成8年9月30日
平成8年10月1日〜平成14年9月30日
平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
ディーゼル乗用車
(車検期間が2年のもの)
平成7年9月30日以前
平成7年10月1日〜平成14年9月30日
平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
特定
自動
車排
出基
準に
適合
しな
い使
用過
程車
の使
用可
能最
終日
〔表
2〕
(★)平成14年9月30日現在において、検査証の有効期間の残余期間が1年を超える自動車にあっては、「平成15年9月30日」を「平成16年9月30日」と読み替える。
注「以降」には、基準時点も含まれます。例えば「平成15年9月30日以降」は、「平成15年9月30日か、それより後」となります。

67
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
32 条 前 照 灯 等
①走行用前照灯
②すれ違い用前照灯
33 条 前 部 霧 灯
○前面に備えることができる。○左右同数であって、同時に3個以上点灯しないこと。○取付け位置は車両中心面に対し左右対称であり、その照明部の上縁の高さが地上0.8ⅿ以下であって、すれ違い用前照灯の上縁以下、下縁の高さが地上0.25ⅿ以上となるように取付けられていること。
○照明部の最外縁が自動車の最外側から400㎜以内となるように取付けられていること。○灯光の色は白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。○照射光線は、他の交通を妨げないものであること。○照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。○点灯操作状態の表示を備えること。
項 目 基 準
備え付け 前面
取付個数 2個又は4個(二輪車、側車付二輪車は1個又は2個)
取付位置 ・左右同数 ・車両中心面に対し対称(二輪車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものは、それらの中心が車両中心面に対して対称であること。)
灯光の色 白色
性 能 ・夜間前方100ⅿの距離の交通上の障害物を確認できること。 ・最高光度の合計は225,000cd を超えないこと。
そ の 他
①照射光線は進行方向を正射すること。②照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわないこと。③点灯操作状態の表示装置を備えること。④前照灯照射方向調整装置 ・照射方向を左右に調整できないこと。 ・手動式のものは運転席で容易に、かつ適切に操作できるこ と。
項 目 基 準
備え付け 前面の両側(二輪車、側車付二輪車は前面)
取付個数 2個(二輪車、側車付二輪車は1個又は2個)
取付位置
・左右同数 ・照明部の上縁の高さ1.2ⅿ以下、下縁の高さ0.5ⅿ以上(二輪車、側車付二輪車は照明部の中心が1.2ⅿ以下)
・照明部の最外縁は、自動車の最外側から400㎜以内(二輪車、側車付二輪車は対象外)
・車両中心面に対して対称
灯光の色 白色
性 能 ・照射光線は他の交通を妨げないこと。 ・夜間前方40ⅿの距離の交通上の障害物を確認できること。
そ の 他
①照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわないこと。②前照灯照射方向調整装置 ・すべての乗車又は積車状態ですれ違い用前照灯の照射光線を他の交通を妨げないようにすることができること。
・照射方向を左右に調節できないこと。 ・手動式のものは、運転席で容易にかつ、適切に操作できること。
③二輪車、側車付二輪車の走行用及びすれ違い用前照灯は、エンジンが作動している場合は常にいずれかが点灯している構造であること。

68
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
○前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5 の゚平面及び下方5 の゚平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10 の゚平面及び前部霧灯の外側方向45 の゚平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
33条の2 側 方 照 射 灯
○両側面の前部に1個ずつ備えることができる。○光度は5,000cd 以下であること。○主光軸は取付け部より40ⅿから先の地面を照射しないものであり、かつ、取付け部より後方の地面、左側に備えるものにあっては取付け部より右側の地面、右側に備えるものにあっては取付け部より左方の地面を照射しないこと。
○取付け部は光軸の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。○灯光の色は白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。○照明部の上縁の高さが、すれ違い用前照灯の上縁以下となるように取付けられていること。
○照明部の最前縁は、自動車の前端から2.5ⅿ以内にあること。○方向指示器が作動している場合に限り、当該方向指示器が方向を指示している側のもののみが点灯する構造であること。
34 条 車 幅 灯
○前面の両側に備えること。○夜間前方300ⅿから点灯を確認できかつ、その照射光線は他の交通を妨げないこと。○車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45度の平面及び車幅灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
○灯光の色は白色であること。ただし、方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の車幅灯は橙色であってもよい。
○照明部の上縁の高さが地上2.1ⅿ以下、下縁の高さが地上0.35ⅿ以上となるように取付けられていること。(二輪車、側車付二輪車照明部中心2ⅿ以下)
○照明部の最外縁は自動車の最外側から400㎜以内となるように取付けられていること。○車両中心面に対して対称の位置に取付けられたものであること。○方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の車幅灯は、これらを作動させた場合に方向を指示している側又は両側のものが消灯する構造であること。
34条の2 前 部 上 側 端 灯
○前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。○夜間前方300ⅿの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないこと。
○灯光の色は、白色であること。○前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに前部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部上側端灯の内側方向45度の平面及び前部上側端灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
○トレーラー以外の自動車に備えるものは、その照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていること。(トレーラーに備えるものは、取付けられる最高の高さ。)
○照明部の最外縁は、自動車の最外側から400㎜以内となるように取り付けられていること。
○前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
○前部上側端灯の照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに200㎜以上離れるように取り付けられていること。
○車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
35 条 前 部 反 射 器○被けん引自動車の前面の両側に左右対称に備えること。○夜間前方150ⅿの距離から走行用前照灯で照射したときその反射光を照射位置から確認できること。

69
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
○反射部の形状は文字及び三角形以外であること。○反射光の色は白色であること。○反射部の上縁の高さが地上1.5ⅿ以下、下縁の高さが地上0.25ⅿ以上となるように取付けられていること。
○反射部の最外縁は、自動車の最外側から400㎜以内となるように取付けられていること。○前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10 の゚平面及び下方10 の゚平面(前部反射器の反射部の上縁の高さが地上0.75ⅿ未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5 の゚平面)並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の内側方向30 の゚平面(被牽引自動車に備える前部反射器にあっては、内側方向10 の゚平面)及び外側方向30 の゚平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
35条の2 側方灯及び側方反射器
①次の自動車の両側面に側方灯又は側方反射器を備えること。 (専ら乗用を除く。) ○長さ9ⅿ以上の普通車…前部、中央部、後部 ○長さ6ⅿ以上9ⅿ未満の普通車…前部、後部 ○長さ6ⅿ未満の普通車であるトラクタ…前部 ○長さ6ⅿ未満の普通車であるトレーラ…後部 ○ポールトレーラ…後部〔側 方 灯〕○夜間側方150ⅿの距離から点灯を確認できること。○灯光の色は前部及び中央部は橙色、後部に備えるものにあっては橙色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であること。
○照明部の上縁の高さが地上2.1ⅿ以下、下縁高さが地上0.25ⅿ以上となるように取付けられていること。(二輪車、側車付二輪車照明部中心2ⅿ以下)
(構 造)○前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの3分の1以内となるように取付けられていること。
○後部に備える側方灯の照明部の最外縁は、自動車の後端から1,000㎜以内となるように取付けられていること。
○運転者席で消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯、車幅灯のいずれかが点灯しているとき消灯できない構造のこと。
(側方反射器)○夜間側方150ⅿから走行用前照灯で照射した場合に確認できること。○側方反射器は文字及び三角形以外であること。○反射光の色は前部又は中央部に備えるものにあっては橙色、後部に備えるものにあっては橙色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であること。
○反射部の上縁の高さが地上1.5ⅿ以下、下縁高さが地上0.25ⅿ以上となるように取付けられていること。
○長さ6ⅿ未満の自動車の後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動車の後端から当該自動車の長さの3分の1以内となるように取付けられていること。
○前部に備える側方反射器の反射部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの3分の1以内となるように取付けられていること。
○後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動車の後端から1,000㎜以内となるように取付けられていること。
36 条 番 号 灯
○後面に備えること。○夜間後方20ⅿから自動車登録番号標の数字等の表示が確認できること。○灯光の色は白色であること。○運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯、車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できないこと。(追越合図灯を除く。)ただし、前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。

70
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
37 条 尾 灯
○後面の両側に備えること。○夜間後方300ⅿから点灯を確認できること。○運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯、車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できないこと。ただし、前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に尾灯が点灯しない装置を備えることができる。
○尾灯の灯光の色は赤色であること。○尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45度の平面及び車幅灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
(取付位置)○照明部の上縁の高さが地上2.1ⅿ以下、下縁の高さが地上0.35ⅿ以上であること。(二輪車は照明部の中心が2ⅿ以下)
○照明部の最外縁は、自動車の最外則から400㎜以内となるようにとりつけられていること。
○車両中心面に対して対称であること。
37条の2 後 部 霧 灯
○後面には後部霧灯を備えることができる。○数は2個以下であること。○光度は尾灯の光度を超えるものであること。○前照灯又は前部霧灯のいずれかが点灯している場合においてのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれかが点灯している場合においても消灯できる構造であること。ただし、尾灯が点灯している場合に限り前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯している構造とすることができる。この場合において尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯している構造であること。
○灯光の色は、赤色であること。○照明部の上縁の高さが地上1ⅿ以下、下縁の高さが地上0.25ⅿ以上となるように取り付けられていること。また、制動灯の照明部から100㎜以上離れていること。
○点灯操作状態を運転者に表示する装置を備えること。○車両中心面に対して対称であること。(両側に備えるものに限る。)○後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5 の゚平面及び下方5 の゚平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25 平゚面及び後部霧灯の外側方向25 の゚平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
37条の3 駐 車 灯
○前面及び後面の両側、又は後面の両側に駐車灯を備えることができる。○夜間、前方及び後方150ⅿから前面及び後面の点灯を確認できること。○前面に備える駐車灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
○照明部の最外縁は、自動車の最外側から400㎜以内に取り付けられていること。○後面に備える駐車灯の灯光の色は、赤色でそのすべてが同一であること。○後面の駐車灯は全てが同時点灯すること(長さ6ⅿ未満又は巾2ⅿ未満の自動車は片側のみでもよい。)
○前面の駐車灯は後面の駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。○原動機が停止している状態で点灯できること。○車両中心面に対して対称であること。
37条の4 後 部 上 側 端 灯
○後部上側端灯を備えることができる。○夜間後方300ⅿの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないこと。
○灯光の色は、赤色であること。

71
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
○後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに後部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部上側端灯の内側方向45度の平面及び後部上側端灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
○取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。○照明部の、最外縁は、自動車の最外側から400㎜以内となるように取り付けられていること。
○両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
○後部上側端灯の照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに200㎜以上離れるように取り付けられていること。
○尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
38 条 後 部 反 射 器
○後面に備えること。○被けん引車以外に備えるものの反射部は、文字及び三角形以外の形であること。○被けん引車に備えるものの反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、一辺が150㎜以上200㎜以下のものであること。
○夜間後方150ⅿから走行用前照灯で照射したとき、その反射光を照射位置から確認できること。
○反射光の色は赤色であること。○反射部の上縁の高さが地上1.5ⅿ以下、下縁の高さが地上0.25ⅿ以上となるように取り付けられていること。
○最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400㎜以内となるように取り付けられていること。
○車両中心面に対して対称であること。○後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10 の゚平面及び下方10 の゚平面(後部反射器の反射部の上縁の高さが地上0.75ⅿ未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5 の゚平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向30 の゚平面及び後部反射器の外側方向30 の゚平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
38条の2 大 型 後 部 反 射 器
○貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7t以上のものの後面には、前条の基準の後部反射器のほか次の後部反射器を備えること。
(備付け)①後面に備えなければならない。(取付位置)①上縁の高さ地上1.5ⅿ以下②車両中心面に対し対称(取付個数)①4個以下(反射部・蛍光部の色)①反射光の色…黄色②蛍光の色…赤色(性 能)①夜間後方150ⅿから走行用前照灯で照射したとき、その反射光を照射位置から確認できること。
②昼間後方150ⅿから走行用前照灯で照射したとき、その蛍光を確認できること。(その他)①一辺が130㎜以上の長方形②反射部の面積800㎠以上(2個以上の場合はその和)③蛍光部の面積400㎠以上(2個以上の場合はその和)

72
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
38条の3 再 帰 反 射 材
○自動車(乗用車を除く。)の両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる。○テープ状又はシート状で、テープ状の場合の幅は、50㎜以上60㎜以下であること。○再帰反射材は、綿状再帰反射材又は輪郭表示再帰反射材のいずれかとする。○綿状再帰反射材又は輪郭表示再帰反射材の反射光の色は、側面においては白色又は黄色、後面においては赤色又は黄色。
○特徴等表示再帰反射材は、輪郭表示再帰反射材と併用する場合に使用することができる。
○綿状再帰反射材は、地面に可能な限り平行に取り付けられていること。○綿状再帰反射材は、その自動車の長さ及び幅の80%以上を識別できること。○不連続の再帰反射材は、その間隔が最も短い再帰反射材の長さの50%を超えないこと。○再帰反射材は、その下縁の高さが地上0.25m以上であること。○輪郭表示再帰反射材は、地面に可能な限り平行又は垂直に取り付けられていること。○特徴等表示再帰反射材は、側面の輪郭表示再帰反射材の内側のみに取り付けられていること。
39 条 制 動 灯
○後面の両側に備えること。○灯色の色は赤色であること。○昼間後方100ⅿから点灯を確認できるものであり、照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
○主制動装置又は補助制動装置操作時のみ点灯すること。○尾灯と兼用の制動灯は同時に点灯した時の光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上であること。
(取付位置)①上縁の高さ地上2.1ⅿ以下、下縁の高さ地上0.35ⅿ以上②車両中心面に対し対称③照明部の最外縁は、自動車の最外側から400㎜以内(両側に備えるものに限る。)④制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45度の平面及び制動灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
39条の2 補 助 制 動 灯
○備えなければならない。(乗用車、バン型貨物で3.5トン以下のもの)○照射光線は他の交通を妨げないものであること。○数は1個であること。(車両中心面上に取付けられないものを除く。)○照明部の下縁の高さ地上0.85ⅿ以上又は後面ガラス最下端の下方0.15ⅿより上方であって制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
○補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。○補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。○補助前照灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。○構造上車両中心面上に取付けられないものは、照明部の中心を車両中心面から150㎜までの間に取付けるか、車両中心面の両側(車両中心面に最も近い位置)に1個づつ取り付けることができる。
○補助制動灯の灯光の色は、赤色であること。○制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10度の平面及び下方5度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向10度の平面及び制動灯の外側方向10度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
40 条 後 退 灯
○備えなければならない。(二輪車、側車付二輪車を除く)○数は2個以下であること。○後退灯は、変速装置(被けん引自動車にあっては、そのけん引自動車の変速装置)を後退の位置に操作している場合にのみ点灯する構造であること。
○後退灯の灯光の色は、白色であること。

73
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
○後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方5度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向30度の平面及び後退灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
○照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。○車両中心面に対し対称であること。(両側に備えるものに限る。)
41 条 方 向 指 示 器
乗用車、トラック等(大型貨物自動車等を除く)○車両中心線上の前方及び後方30ⅿから指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個づつ備えること。
○後面の両側に備える方向指示器は、次の範囲の全ての位置から見通すことができること。
・方向指示器の中心を含む水平面から上方15度、下方15度の範囲、(指示部上縁の高さが0.75ⅿ未満のものは下方5度。)
・方向指示器の中心を含む水平面から内側方向45度、外側方向80度の範囲○両側面には次の基準に適合する方向指示器を備えること。(トレーラを除く。) ・指示部の最前縁は自動車の前端から2.5ⅿ以内に取付けること。(長さ6ⅿ以上の自動車は、自動車の長さの60%以内)
・自動車の後端(両側に方向指示器を備えたものは、これを結ぶ直線)を含み、車両中心面に直交する鉛直面上で自動車の最外側から外側1ⅿの点における地上1ⅿから2.5ⅿまでの全ての位置から指示部が見通せること。
○指示部の上縁の高さが2.1ⅿ(側面は2.3ⅿ)以下、下縁の高さが0.35ⅿ以上であること。○前方または後方に対して方向の指示を表示する指示部の最内縁の間隔は600㎜(幅1,300㎜未満車は400㎜)以上、指示部の最外縁は自動車の最外側から400㎜以内であること。
○車両中心面に対し対称であり、橙色であること。○方向指示器を表示する方向100ⅿ(側面方向指示器は30ⅿ)の距離から昼間に点灯を確認できること。
○毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅すること。○運転者席において直接かつ容易に作動状態を確認できない場合は、作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
○方向指示器は非常点滅表示灯と同時に点滅することができる。○面積等の基準あり。
大型貨物自動車等(車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上の普通自動車)(セミトレーラーをけん引するけん引自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の形状に類する自動車を除く。)
○車両中心線上の前方及び後方30ⅿから指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個づつ備えること。
○後面の両側には、後方10ⅿにおける地上2.5ⅿまでの全ての位置から指示部が見通すことのできる位置に方向指示器を備えること。
○両側面の前部(トレーラーを除く。)及び中央部には次の基準に適合する方向指示器を備えること。
(前 部) ・自動車の前端から運転者室または客室の外側後端までの間に取り付ける。 ・後面の両側の方向指示器を結ぶ直線を含み、車両中心面に直交する鉛直面上で自動車の最外側から外側1ⅿの点における地上1ⅿから2.5ⅿまでの全ての位置から指示部が見通せること。
(中央部) ・指示部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端から2.5ⅿ以内に取り付けること。(トレーラーは、前端から4.5ⅿ以内)
・自動車の最外側から外側1ⅿの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方1ⅿから後端までの地上1ⅿから1.6ⅿまでの全ての位置から指示部が見通せること。

74
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
○指示部の上縁の高さ2.1ⅿ(側面は2.3ⅿ)以下、下縁の高さ0.35ⅿ以上であること。○前方または後方に対して方向の指示を表示する指示部の最内縁の間隔は、600㎜以上、指示部の最外縁は自動車の最外側から400㎜以内であること。
○車両中心面に対して対称であり、橙色であること。○方向指示器を表示する方向100ⅿ(前部の側面方向指示器は30ⅿ)の距離から昼間に点灯を確認できること。
○毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅すること。○運転者席において直接かつ容易に作動状態を確認できない場合は、作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
○方向指示器は非常点滅表示灯と同時に点滅することができる。○面積等の基準あり。
二輪車及び側車付二輪車○車両中心面上の前方及び後方30ⅿから指示部が見通すことができる位置に少なくとも左右1個づつ備えること。
○指示部の中心の高さが2.3ⅿ以下であること。○前面に備えるものは、指示部の中心間隔が300㎜以上(光源が8w以上のものは、250㎜以上)、前照灯が2個備えられたものは最外側の前照灯より外側に備えること。
○後面に備えるものは、指示部の中心間隔が150㎜以上、尾灯が2個以上備えられたものは最外側の尾灯より外側に備えること。
○車両面に対し対称であり、橙色であること。○前方及び後方100ⅿの距離から昼間に点灯を確認できること。○毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅すること。○運転席において直接かつ容易に作動状態を確認できない場合は、作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
○面積等の基準あり。
連結車両○トレーラーとトラクタを連結した場合には、その状態において次の基準に適合する方向指示器を備えること。
(トレーラー及びトラクタが大型貨物自動車等以外の場合)○車両中心線上の前方及び後方30ⅿから指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個づつ備えること。
○後面の両側に備える方向指示器は、次の範囲の全ての位置から見通すことができること。
・方向指示器の中心を含む水平面から上方15度、下方15度の範囲(指示部上縁の高さが0.75ⅿ未満のものは下方5度。)
・方向指示器の中心を含む水平面から内側方向45度、外側方向80度の範囲。○両側面には次の基準に適合する方向指示器を備えること。 ・指示部の最前縁は自動車の前端から2.5ⅿ以内に取付けること。(連結全長6ⅿ以上の自動車は、自動車の長さの60%以内)
○自動車の後端(両側に方向指示器を備えたものは、これを結ぶ直線)を含み、車両中心面に直交する鉛直面上で自動車の最外側から外側方1ⅿの点における地上1ⅿから2.5ⅿまでの全ての位置から指示部が見通せること。
(トレーラー及びトラクタが大型貨物自動車等の場合)○車両中心線上の前方及び後方30ⅿから指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個づつ備えること。
○後面の両側には、後方10ⅿにおける地上2.5ⅿまでの全ての位置から指示部が見通すことのできる位置に方向指示器を備えること。
○側面に備える方向指示器(中央部を除く。)の指示部の最前縁はトラクタの前端から連結全長の60%以内に取り付けられかつ、トレーラー後面の方向指示器を結ぶ直線を含み車両中心面に直交する鉛直面上で自動車の最外側から外側方1ⅿの点における地上1ⅿから2.5ⅿまでのすべての位置から指示部が見通せること。
○指示部の上縁の高さ2.1ⅿ(側面は2.3ⅿ)以下、下縁の高さ0.35ⅿ以上であること。

75
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
○前方または後方に対して方向の指示を表示する指示部の最内縁の間隔は、600㎜以上、指示部の最外縁は自動車の最外側から400㎜以内であること。
○車両中心面に対して対称であり、橙色であること。○方向指示器を表示する方向100ⅿ(前部の側面方向指示器は30ⅿ)の距離から昼間に点灯を確認できること。
○毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅すること。○運転者席において直接かつ容易に作動状態を確認できない場合は、作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
○方向指示器は非常点滅表示灯と同時に点滅することができる。○面積等の基準あり。
41条の2 補 助 方 向 指 示 器
○補助方向指示器を両側面に1個ずつ備えることができる。○方向指示器と連動して点滅すること。○灯光の色は、橙色であること。○車両中心面に対して対称であること。○両側面に備える補助方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。
41条の3 非 常 点 滅 表 示 灯
○非常点滅表示灯を備えること。(二輪車、側車付二輪車を除く。)○車両中心面上の前方及び後方30ⅿから指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。
○指示を表示する方向100ⅿの距離から昼間点灯を確認できること。○点滅回数は毎分60回以上120回以下の一定周期で点滅すること。○灯光の色は橙色であること。○車両中心面に対して対称であること。○左右に取り付けられたものは同時に点滅すること。○指示部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600㎜以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもののこの指示部の最外縁は、自動車の最外側から400㎜以内に取付けられていること。
○指示部の上縁の高さが地上2.1ⅿ以下、下縁の高さが地上0.35ⅿ以上であること。○両側面に備える指示部の最前縁は、自動車の前端から2.5ⅿ以内であること。○前方及び後方に表示するものの各指示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、長さ6ⅿ以上の自動車は40㎠以上、その他の自動車は20㎠以上であること。
○運転者が運転者席において直接かつ容易に非常点滅表示灯の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
42 条 灯 光 の 色 等 の 制 限
(灯光の色が橙色又は赤色の灯火)○次の灯火を除き、後方を照射若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5ⅿ以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、走行中に使用しない灯火、緊急自動車の警光灯、路線バスの終車灯、ハイヤー・タクシーの空車灯・料金灯・非常灯、事業用バスの地上2.5ⅿを超える高さの後部に設けられた赤色マーカー・ランプ、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
(灯光の色が白色の灯火)○次の灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯火の色が白色の灯火を備えてはならない。
番号灯、後退灯、走行中使用しない灯火、室内照明灯、路線バスの方向幕灯、ハイヤー・タクシーの社名表示灯
(青紫色の灯火の禁止)○路線バス以外は前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色の灯火を備えてはならない。(速度表示灯と紛らわしい灯火の禁止)○前面ガラスの上方には速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。

76
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
(点滅又は光度が増減する灯火の禁止)○側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、ハイヤー・タクシーの非常灯を除き点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。
(赤色又は白色の反射器の禁止)○反射光の色が赤色の反射器で前方に表示するもの又は反射光の色が白色の反射器で後方に表示するものを備えてはならない。
(灯火等による眩惑防止)○自動車に備える灯火の直射光(前照灯にあっては、すれ違い用前照灯の直射光)又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転を妨げないこと。
(後面灯火の前方への照射又は表示の禁止)○側方灯(両側面の後部に備える赤色のものに限る。)、尾灯、後部霧灯、駐車灯(後面に備えるものに限る。)、制動灯、補助制動灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示する灯火の灯火は、前方を照射し、又は前方に表示するものでないこと。
(光度の制限)○前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、尾灯、後面に備える駐車灯、制動灯、補助制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(ハイヤー・タクシー)の非常灯及び走行中使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き光度が300カンデラ以下であること。
○火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火及び補助制動灯は、他の灯火と兼用でないこと。
43 条 警 音 器
○備えなければならない。○音は連続し、音の大きさ、音色が一定であること。○警音器の音の大きさは、前方7ⅿの位置で112デシベルから93デシベルであること。○緊急車のサイレン、右左折及び後退時の警報装置を除いては警音器と紛らわしいものをつけてはならない。
43条の2 非 常 信 号 用 具
○備えなければならない。○夜間200ⅿの距離から確認できる赤色の灯光を発すること。○自発光式であること。○使用に便利な場所に備え付られており、かつ、振動等により損傷又は作動しないこと。
43条の3 警 告 反 射 板
(備付けの義務はなく自動車に備える場合の要件)○反射部及びけい光部からなる一辺が400㎜以上の中空の正立正三角形で帯状部の幅が50㎜以上であること。
○夜間150ⅿの距離から走行用前照灯で照射した時、その反射光を照射位置から確認できること。
○反射光の色は赤色であること。○路面上に垂直に設置できるものであること。
43条の4 停 止 表 示 器 材
(備付けの義務はなく自動車に備える場合の要件)○反射部及びけい光部からなる一辺が500㎜以上の中空の正立正三角形で、帯状部の幅が80㎜以下であること。
○反射部は中空の正立正三角形で、帯状部の幅が25㎜以上、50㎜以下であること。○けい光部は反射部に内接する中空の正立正三角形で、帯状部の幅が30㎜以上、33㎜以下であること。
○夜間200ⅿの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
○昼間200ⅿの距離からけい光を確認できること。○反射光、けい光の色は赤色であること。○路面上に垂直に設置できること。○容易に組立てられること。○使用に便利な場所に備えられていること。

77
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
44 条 後 写 鏡 等
○後写鏡を備えなければならない。(トレーラーを除く。)○容易に方向の調節ができ、一定の方向に保持できること。○取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8ⅿ以下のものは歩行者等が接触した場合に衝撃を緩和できる構造であること。(二輪車、側車付二輪車を除く。)
○車室内に備えるものは衝突等による衝撃を受けた場合に乗員に傷害を与えるおそれの少ないこと。(専ら乗用以外の普通車、定員11人以上の自動車を除く。)
○運転者が運転者席において、自動車の左右の外側線上後方50ⅿまでの間にある車両の交通状況及び自動車の左外側線付近の交通状況を確認できるものであること。
45 条 窓 拭 器 等
(窓拭器)○自動車(二輪車、側車付二輪車を除く。)の前面ガラスの直前の視野を確保できる自動式の窓拭器を備えること。
○左右に備える場合は同時に作動すること。(洗浄液噴射装置及びデフロスタ)○自動車(二輪車、側車付二輪車を除く。)には、次の基準に適合する洗浄液噴射装置及びデフロスタを備えること。ただし、車室と車体外とを仕切ることのできない自動車はデフロスタを要しない。
①前面ガラスの直前の視野を確保するのに十分な洗浄液を噴射すること。 ②普通乗用車、小型車、軽自動車(定員11人以上の自動車を除く。)に備えるデフロスタは前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合、直前の視野を速やかに確保することができること。
③走行中の振動等により損傷し、又は作動するものでないこと。(サンバイザ)○衝突等による衝撃を受けた場合に、乗車人員に傷害を与えるおそれが少ない構造であること。(定員11人以上の自動車を除く。)
46 条 速 度 計 等
○速度計及び走行距離計を備えること。(軽自動車は走行距離計を省略できる。)○速度計は容易に走行時の速度を確認できること。○自動車の速度計が40㎞/ hを指示した時、計測した速度が31.0㎞/ h〜42.5㎞/ h(二輪は29.1㎞/ h〜42.5㎞/ h)○速度計は照明装置を備えたもの、自発光式のもの又は文字板及び指示計に自発光塗料を塗ったもので運転者を眩惑させないものであること。
47 条 消 火 器
○次の自動車には消火器を備えること。(トレーラーは①〜④を除く。) ①火薬類を運送する自動車(第51条⑵に規定する数量を超えるもの。) ②危険物を運送する自動車(第1条表1の危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数料以上のもの。)
③可燃物を運送する自動車(第1条表2に掲げる数料以上のもの) ④可燃性ガス及び酸素を運送する自動車(150㎏以上のもの) ⑤上記①〜④の自動車をけん行する自動車 ⑥放射性輸送物等を運送する場合に使用する自動車 ⑦定員11人以上の自動車 ⑧定員11人以上の自動車をけん引する自動車 ⑨幼児専用車○運送物品等の消火に適応するものであるほか、次の基準に適合すること。 ①消防法に規定する技術上の規格に適合すること。 ②走行中の振動等により損傷し又は作動するものでないこと。 ③使用に際して容易に取り外しができるように取り付けられたものであること。 ④消火器は次の場所に備えること。 ・火薬類を運送する自動車及びこれをけん引するトラクタは見張人の使用に便利な場所
・その他の自動車にあっては、運転者、助手等の使用に便利な場所
48 条 内圧容器及びその附属装置 略

78
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
条 項 項 目 基 準 内 容
48条の2 運 行 記 録 計○車両総重量8トン以上または、最大積載量5トン以上の普通トラック及びこれをけん引するトラクタ(緊急自動車、トレーラーを除く。)には備えなければならない。
48条の3 速 度 表 示 装 置
○車両総重量8トン以上または、最大積載量5トン以上の普通トラック及びこれをけん引するトラクタ(緊急自動車、トレーラーを除く。)には備えることができる。
○速度表示装置は60㎞/ hを超える速度にあっては3個、40㎞/ hを超え60㎞/ h以下の速度にあっては2個、40㎞/ h以下の速度にあっては1個、自動的に点灯するものであること。
○速度表示装置は、前面ガラスの上方で、かつ地上1.8ⅿ以上であること。○速度表示装置は、横配列であり、左側、右側、中間の順に点灯すること。○前方100ⅿの距離から点灯している灯火の数を確認できるものであること。○灯火の色は黄緑色であること。○平坦な舗装路面で速度35㎞/ h以上において正15%、負10%以下であること。○運転席でその作動状態を確認できる灯火その他の装置を備えること。○表示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は40㎠以上であること。
49 条 緊 急 自 動 車
○赤色で前方300ⅿの距離から点灯を確認できる警光灯を備えること。○車両前方20ⅿの位置において90デシベル以上120デシベル以下のサイレンを備えること。
○消防車は朱色、救急車、血液輸送車、臓器等移植用緊急輸送車は白色であること。また、その他の緊急車にあっては、指定色なしとする。
49条の2 道路維持作業用自動車
○道路維持作業用自動車には車体の上部の見やすい箇所に次の基準に適合する灯火を備えること。
①黄色で点滅式であること。 ②150ⅿの距離から点灯が確認できること。
50 条 旅客運送事業用自動車 略
50条の2 ガス運送容器を備える自動車
○第2条から第48条の3までの規定のほか、車台の後部にバンパその他の緩衝装置を備えること。
○ガス運送容器の後面及び附属装置とバンパその他の緩衝装置との間には十分な間隔があること。
51 条 火薬類を運送する自動車
○第2条から第48条の3までの規定のほか次の基準に適合すること。 ①荷台その他火薬類を積載する場所と原動機との間は不燃性の隔壁で仕切ること。 ②車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気配線は被覆され、車体に定着されていること。
③車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。
52 条 危険物を運送する自動車 略
53 条 乗車定員及び最大積載量
○安全な運行を確保し、及び公害を防止できる範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとすること。
○二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあっては乗車定員2人以下とすること。○乗車定員は12才以上の者の数をもって表す。○12才以上の者1人は、12才未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。○最大積載量は次の数値により記載する。(タンク車、ミキサー車及び粉粒体運搬車を除く。)100㎏〜5,000㎏は50㎏毎、5,000㎏を超えるものは100㎏毎とする。

79
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
2 二輪の小型自動車
1 新規検査申請(車両法第59条、車両法施規第36条第4項)
(250cc を超えるオートバイを新たに検査を受けて使用する場合)
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第59条(新規検査)Ⅰ登録自動車の1(9頁)を参照。
施行規則第36条(新規検査の申請)3軽自動車の1(89頁)を参照。
OCRシート第1号様式 ○ ○ ○ ○ 所有者・使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。※△は諸元欄に変更があるものは必要。
登令第15条
様式省令第2条第1項 第2号様式 △ △ ○
手数料納付書 ○ ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(105頁参照)を貼付 車両法施規第69条
完成検査終了証 ○発行されてから9か月以内のもの。※完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証
車両法第7条第3項 第75条第4項
自動車検査証返納証明書 ○ 提出する。 車両法施規第36条第4項
◦(二輪)自動車通関証明書◦排出ガス検査終了証◦輸入車特別取扱自動車届出済書◦輸入自動車等の打刻届出書
○輸入の事実を証明する書面(輸入の自動車の場合に限り必要)
車両法施規第7条、登規第6条
譲渡証明書 ○ ○ ○ ○ 所有者の変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印 車両法施規第33条、登規第6条
委任状 ○ ○ ○ ○
①所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)※記名及び押印があるか、若しくは署名が必要。②使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)※記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
登規第14条第1項第3号
使用者の住所を証するに足りる書面
(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
○ ○ ○ ○
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) ②法人・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)
必 要 書 類
新車中古車新規
輸入車新規
説 明 欄 参 考 条 文型式指定新規
持込新規

80
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)
○ ○ ○ ○
①使用者が個人の場合・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)②使用者が法人の場合・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等③各書面は写しで可とする
車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)自管第73号(45.5.22)
自動車予備検査証 ○ ○ ○保安基準に適合していることが確認できる書面 有効な自動車予備検査証(交付を受けた自動車の場合に限り必要)
車両法第71条
自動車検査票 ○ ○ ○保安基準に適合していることが確認できる書面 合格印のある自動車検査票(持込み検査を受ける場合に必要)
実施要領3−3−1
点検整備記録簿 ○ 提示する。 車両法第59条第3項
保安基準適合証 ○ 保安基準適合証は指定整備を行ったものについてのみ必要
車両法第94条の5、5の二
自動車重量税納付書 ○ ○ ○ ○ 所定の重量税印紙(229頁参照)を貼付 重量税法第8条、第10条
自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条
軽自動車税申告書 ○ ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第447条
必 要 書 類
新車中古車新規
輸入車新規
説 明 欄 参 考 条 文型式指定新規
持込新規
※上記書類のほか、必要に応じて下記の書類を添付する。 事業用自動車又は貸渡自動車の場合…事業用自動車等連絡書 (事業用自動車等連絡書及び新規検査申請書を運輸支局の輸送担当部署に提出し、経由印を受けてから登録担当窓口に提出する。)

81
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
2 自動車検査証の記入申請(車両法第67条)
(自動車検査証に記載されている事項に変更があった場合)
変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) Ⅰ登録自動車の2(14頁)を参照。
必 要 書 類
所有者(名義)変更の場合
(所有権解除)
割賦完済による場合
及び住所が変った場合
所有者の氏名または名称
が変った場合
使用者及び使用者の住所
(フレーム交換した場合)
車台番号を変更した場合
管轄変更(転入)の場合
説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第1号様式 ○ ○ ○ ○ ○①所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が申請する場合は、所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)ただし、使用者の氏名又は名称、住所若しくは使用の本拠の位置の変更の場合は、所有者のものは不要
登令第15条
様式省令 第2条第1項又は 第2号様式 ○
手数料納付書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手数料不要 車両法施規第69条
譲渡証明書 ○ ○所有者の変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印
車両法 第7条、第33条登規第6条
事由が確認できる書面注1 ○ ○ 下記注1参照 登法第18条
使用者の住所を証するに足りる書面
(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
○ ○
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規第36条第1項、
「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)
委任状 ○ ○ ○ ○ ○ ○
①所有者の委任状(代理人による申請の場合であって、使用者の氏名又は名称若しくは住所の変更の場合、あるいは申請書に所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)※記名及び押印があるか若しくは署名が必要②旧所有者のものは不要③使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)※記名及び押印があるか、若しくは署名が必要④旧使用者のものは不要
登令第14条 第1項第3号
自動車検査証 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提出する。限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証
車両法 第67条第1項

82
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
所有者(名義)変更の場合
(所有権解除)
割賦完済による場合
及び住所が変った場合
所有者の氏名または名称
が変った場合
使用者及び使用者の住所
(フレーム交換した場合)
車台番号を変更した場合
管轄変更(転入)の場合
説 明 欄 参 考 条 文
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)
○ ○ ○
①使用者が個人の場合・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等②使用者が法人の場合・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等③各書面は写しで可とする
車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)自管第73号 (45.5.22)
自動車検査票 ○ 自動車検査票等合格印のあるものを提出 実施要領3−3−1
自動車重量税納付書 ○ 所定の重量税印紙(229頁参照)を貼付 重量税法第8条、第10条
フレーム販売証明書フレーム交換(打刻、塗まつ)許可書理由書、顛末書等
○フレーム販売証明書は販売店で発行。申請者は所有者で押印が必要。車台番号のき損等により理由書等の提出を求められることがある。
車両法 第31条、第32条登令第40条
検査標章再交付申請書 ○ 申請人は使用者。手数料(105頁参照) 車両法施規第41条
自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提示する。 自賠法第9条
軽自動車税申告書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(237頁参照) 地方税法第447条
ナンバープレート ○※
○※
○※
○ ナンバー交付所に返納する。※使用の本拠の位置が変わりナンバープレートが変更になる場合のみ
車両法第20条第1項車両法施規第10条
理由書 ○ ○ ○ ○
⒜自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書を添付⒝車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)を添付
局通達77東陸整資乙第23号
注1 事由が確認できる書面等とは①使用者又は所有者が個人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる
住民票又は外国人登録原票記載事項証明書。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要
②使用者又は所有者が個人の場合で氏名の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
③使用者又は所有者が法人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要
④使用者又は所有者が法人の場合で名称の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
⑤使用者又は所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合・個人…市区町村の発行した住居表示の変更の証明書・法人…商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する。
※上記書類のほか、必要に応じて下記の書類を添付する。 事業用自動車又は貸渡自動車の場合……事業用自動車等連絡書 (事業用自動車等連絡書及び自動車検査証の記入申請書を運輸支局の輸送担当部署に提出し、経由印を受けてから登録担当窓口に提出する。)

83
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3 自動車検査証の返納(車両法第69条)
(自動車を廃車又は使用を中止する場合)
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に返納証明書の交付を申請する。
第69条(自動車検査証の返納等)Ⅰ登録自動車の5抹消登録申請(25頁参照)
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第3号様式の2①使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が申請する場合は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)
登令第15条様式省令 第2条第1項
手数料納付書 所定の手数料印紙(105頁参照)を貼付 車両法施規第69条
使用者の委任状申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要。 ①記名及び押印があるか若しくは署名が必要。自動車検査証返納証明書交付申請と同時に、記入申請する場合は申請人の委任状について各々の委任項目を併合できる。
登令第14条 第1項第3号
自動車検査証返納する。限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証 車両法第69条
自官第50号・自車第46号(52.5.24)
ナンバープレート ナンバー交付所に返納する。 車両法第20条第1項車両法施規第10条
理由書
⒜自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書を添付⒝車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)
局通達77東陸整資乙第23号
軽自動車税申告書 使用者、所有者の押印が必要。(237頁参照) 地方税法第447条
※上記書類のほか、必要に応じて下記の書類を添付する。 事業用自動車又は貸渡自動車の場合……事業用自動車等連絡書 (事業用自動車等連絡書及び自動車検査証の返納申請書を運輸支局の輸送担当部署に提出し、経由印を受けてから登録担当窓口に提出する。)
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第1号様式①新所有者の記名及び押印が必要(代理人が届出をする場合は新所有者の記名及び押印のある委任状でも可)
登令第15条様式省令 第2条第1項
手数料納付書 手数料不要。 車両法施規第69条
自動車検査証返納証明書 提出できない場合、不受理とする。 車両法第36条第1項
新所有者の住所を証する書面 ①発行されてから3ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
当該自動車の所有権を証するに足りる書面
①変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書、相続その他一般承継である場合はその事実を証する戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
車両法第33条施行規則第40条の11
(一時使用中止後に所有者を変更する場合)

84
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
4 車両番号の変更(車両法施規第38条)
(ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合)
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第38条(自動車検査証の記入の申請等)
1・2・3項 省略
4 運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車
について自動車検査証の記入の申請があった場合において、当該自動車の車両番号が第36条の17に規定する基準に適合
しなくなったと認められるときは、その車両番号を変更するものとする。
5 運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車
について自動車検査証の記入の申請があった場合において、車両番号標が滅失し、き損し、その識別が困難となり又は
法第76条の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなったときは、車両番号を変更することができる。
6 運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前2項の規定によ
り車両番号を変更したときは、その変更について、自動車検査証に記入しなければならない。
7 前3項の規定は、二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第4項中「第36条の17」とあるのは「第
36条の18」と読み替えるものとする。
8 法第67条第3項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。
⑴ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年
法律70号)第13条第1項に規定する指定する自動車にあっては、使用の本拠の位置(同法第6条第1項に規定する窒
素酸化物対策地域外から同項に規定する窒素酸化物対策地域内への変更(変更後の使用の本拠の位置が自動車から排
出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政
令第406号)による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
施行令(平成4年政令第365号)第1条の特定地域であった地域(以下この号において「旧特定地域」という。)であ
る場合にあっては、旧特定地域外から旧特定地域内への変更)に限る。)
⑵ 自動車の長さ、幅又は高さ
⑶ 車体の形状
⑷ 原動機の型式
⑸ 燃料の種類
⑹ 自家用又は事業用
⑺ 用途
⑻ 被牽引自動車にあっては、牽引自動車の車名又は型式
⑼ 乗車定員又は最大積載量
⑽ 牽引自動車にあっては、被牽引自動車の車名又は型式

85
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第1号様式
又は 第3号様式
第3号様式は車両番号の変更のみの場合に使用する。①使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が申請する場合は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)②「交付を受ける理由」欄に記載が必要
登令第15条
様式省令 第2条第1項
手数料納付書 手数料不要。 車両法施規第69条
使用者の委任状 申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要。 ①記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
登令第14条 第1項第3号
自動車検査証 限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証 車両法第67条第1項
ナンバープレート ナンバー交付所に返納する。 車両法第20条第1項車両法施規第10条
理由書①車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)
局通達77東陸整資乙第23号
※上記書類のほか、必要に応じて下記の書類を添付する。 事業用自動車又は貸渡自動車の場合……事業用自動車等連絡書 (事業用自動車等連絡書及び自動車検査証の記入申請書を運輸支局の輸送担当部署に提出し、経由印を受けてから登録担当窓口に提出する。)

86
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
再
交
付
自動車検査証
再
交
付
検査標章
説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第3号様式 ○ ○
①使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が申請する場合は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)②「再交付を受ける理由」欄に記載が必要(発見した場合は返納する旨の記載を含む)
登令第15条
様式省令 第2条第1項
手数料納付書 ○ ○ 所定の手数料印紙(105頁参照)を貼付 車両法施規第69条
使用者の委任状 ○ ○ 申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要。①記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
登令第14条 第1項第3号
自動車検査証 ○ ○ 自動車検査証再交付の場合はき損又は識別が困難となった場合に限り必要
車両法第70条車両法施規第41条の2
理由書 ○ ○
①代理人が申請する場合で委任状の提出がある場合において自動車検査証が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書が別途必要(発見した場合は返納する旨の記載を含む)
局通達77東陸整資乙第23号
使用者又は代理人本人を確認できる書面 ○
下記いずれかのもの①運転免許証 ②被用者保険証、国民健康保険被保険者証 ③パスポート、外国人登録証明書 ④顔写真付き又は氏名及び住所を確認できる身分証明書
5 諸再交付申請(車両法第70条(検査証、検査標章)、車両法施規第41条、第41条の2)
(自動車検査証、検査標章を紛失、破損、脱落等により再交付を受ける場合)
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
※検査標章の場合は最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請してもよい。
第70条(再交付) Ⅰ登録自動車9(38頁)を参照。
施行規則第41条 (検査標章等の再交付の申請書)Ⅰ登録自動車9(38頁)を参照。
施行規則第41条の2 (検査標章の再交付) Ⅰ登録自動車9(38頁)を参照。

87
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第3号様式 申請者は使用者で記名、押印または署名が必要。(103頁参照) 登令第15条様式省令第2条第1項
手 数 料 手数料は、自動車検査票又は保安基準適合証に貼付する。(105頁参照) 70東陸整車乙第146号70東陸整登資乙第28号
自動車検査証 提出する。 車両法第62条第1項
自動車検査票 提出する。 実施要領3−3−1
点検整備記録簿 提示する。 車両法第62条第3項車両法施規第39条
保安基準適合証 保安基準適合証は指定整備を行ったものについてのみ必要。 車両法第94条の5
自動車税の滞納がないことを証する書面
納税証明書を提示する。 車両法第97条の2
自動車重量税納付書 重量税(229頁参照) 重量税法第8条 第10条
自動車損害賠償責任保険証明書
提示する。自動車検査証の新たな有効期間をカバーするだけの期間が必要。(257頁参照)
自賠法第9条
6 継続検査申請(車両法第62条)
(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)
最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第62条(継続検査) Ⅰ登録自動車の�(44頁)を参照。

88
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート第3号様式 第4号様式
①所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要(代理人が請求する場合は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)②「交付を受ける理由」欄に記載が必要
登令第15条様式省令第2条第1項
手数料納付書 所定の手数料印紙を貼付 車両法施規第69条
委任状 所有者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)①記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
所有者又は代理人本人を確認できる書面
下記いずれかのもの ①運転免許証 ②被用者保険証、国民健康保険被保険者証 ③パスポート、外国人登録証明書 ④顔写真付き又は氏名及び住所を確認できる身分証明書・※上記書面を不携帯等の場合で、請求者が郵送料を負担した上で郵送による交付を希望したときは、送付先が私書箱等で請求者の住所が明らかでない場合を除き応じて差し支えないものとする。・自動車登録検査業務電子情報処理システムに記録されている現在の所有者と請求者の氏名又は名称及び住所が一致しないときは、当該証明書を交付しないものとする。ただし、契約書その他の資料をもって、請求者が当該自動車の所有者であることが確認できるときはこの限りではない
7 検査記録事項等証明書の交付請求(車両法第72条の3)
(届出されている現在の内容の証明を受ける場合)
最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第72条の3(証明書の交付) 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第72条第1項
に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求する
ことができる。

89
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3 軽自動車A 検査対象軽自動車
1 新規検査(車両法第59条、第74条の4、車両法施規第36条第4項)
(検査対象軽自動車を新たに使用する場合)
使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所に申請する。
第59条(新規検査) Ⅰ登録自動車の1(9頁)を参照。
第74条の4 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第61条の2、第63条第1項、第63条の2、第
63条の3、第63条の4、第71条の2第2項、第74条から第75条の2まで及び第75条の4を除く。)の規定を適用する場
合においては、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「軽自動車検査協会」とする。
第36条(新規検査の申請)
4 車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について新規検査を申請する者は、当該自動
車の使用者であることを証する書面を提出しなければならない。この場合において、法第69条第4項の規定により自動
車検査証返納証明書の交付を受けているときは、これをあわせて提出するものとする。
OCRシート軽第1号様式 ○ ○ ○ 使用者は申請者欄に押印又は署名、所有者は所有者欄へ押印が必要。手数料(107頁参照)※△型式指定車以外は軽第1号様式と軽第2号様式が必要
経過省令第1条
OCRシート軽第2号様式 △ △
申請審査書 ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(107頁参照)を貼付
完成検査終了証 ○ 型式指定自動車の場合に必要で発行されてから9カ月以内のもの。
車両法第7条第3項
自動車検査証返納証明書軽自動車検査証返納確認書 ○ 返納手続の時に軽自動車検査協会、軽自動車協会より
交付されたもの。車両法施規第36条第4項
使用者であることを証する書面○ ○ 譲渡証明書
譲渡人のみ押印が必要。車両法施規第36条第4項車両法第33条
○ 軽自動車検査証返納確認書譲渡人のみ押印が必要。
車両法施規第36条第4項
使用者の住所を証する書面 ○ ○ ○住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面等で発行されてから3か月以内のもの。
車両法施規第36条第1項自管第81号自車第360号(47.5.17)
軽自動車検査票 ○ ○
持込みは検査を受ける場合に必要。新車は白色、中古車で標準車の場合は、若草色で分解整備記録簿(写)と兼用のもの(検査票(甲)、又、標準車以外で計測、計算を要する場合は、白色の検査票(表が(甲)、裏が(乙)となっている)。を添付する。
事務規程3−1取扱細則3−1
定期点検整備記録簿 ○ 提示する。 車両法第59条第3項
排出ガス対策証明書 ○ ○
証明書は次のいずれかである。 ⑴ 完成検査終了証 ⑵ 排出ガス検査終了証 ⑶ 公的な試験機関において実施された試験結果を
表わす書面
車両法施規第36条第6項保安基準 第31条第2項・第3項
必 要 書 類
新車中古車新規
説 明 欄 参 考 条 文型式指定新規
持込新規

90
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
保安基準適合証又は限定保安基準適合証 ○ 指定整備を行ったものについてのみ必要。 車両法第94条の5及び
〃 5の2
自動車重量税納付書又は非課税証明書 ○ ○ ○
昭和49年4月30日以前に車両番号の指定を受けたことがあるものの返納証明書(検査証備考欄に○重と記載の あるものを除く)、軽自動車届出済証、軽自動車届出済証返納証明書(又は軽自動車届出済証返納済確認書等これに代わる書面)は重量税の非課税証明書として兼用する。重量税(229頁参照)
重量税法第5条重量税法第8条附則第12項重量税政令第6条
自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条
自動車取得税及び軽自動車税申告書 ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。
(235・237頁参照)地方税法第447条第122条
必 要 書 類
新車中古車新規
説 明 欄 参 考 条 文型式指定新規
持込新規
※上記書類のほか、必要に応じて下記の書類を添付する。※平成17年2月1日より、検査を受ける場合には、預託証明書(リサイクル券等)の提示が必要となります。(自動車リサイクル法第74条附則第1条第3項)
⒈ 事業用自動車又は貸渡自動車の場合……事業用自動車等連絡書 (事業用自動車等連絡書及び新規検査申請書をそれぞれ運輸支局の輸送担当部署に提出し、経由印を受けてから軽自動車検査
協会の事務所に提出する。)⒉ 緊急自動車又は道路維持作業用自動車の場合……公安委員会の指定申請済証明書等⒊ 改造自動車等であらかじめ審査を受けた自動車の場合……改造自動車等審査結果通知書(又は写)及び改造等に係る添付資料

91
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
を変更した場合
所有者または使用者
(所有権解除)
割賦完済の場合
住所を変更した場合
氏名または名称及び
使用者又は所有者の
入した場合
他の都道府県から転
車を売買した場合
他の都道府県の自動
場合
車両番号を変更する
構造変更の場合
説 明 欄 参 考 条 文
OCRシート軽第1号様式または軽専用1号様式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新使用者の押印又は署名、及び新・旧
所有者の押印が必要。経過省令第1条
OCRシート軽第2号様式 ○
申請審査書 ○ 所定の手数料印紙(107頁参照)を貼付
使用者の住所を証する書面 ○ ○ ○ ○
住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面等で発行されてから3か月以内のもの。
車両法施規第38条自管第81号自車第360号
(47.5.17)
軽自動車検査票 ○ 事務規定3−1取扱細則2−1−4
点検整備記録簿 ○ 持込み検査を受ける場合に必要。 車両法第67条第3項車両法施規第38条
改造自動車等審査結果通知書 ○
改造車は諸元を計測して、乗車定員、最大積載量の指示をうけるがこの場合少部分の簡単な改造のものを除いて、あらかじめ改造自動車等届出書を事務所長に提出して審査を受け、改造自動車等審査結果通知書の交付を受けて検査を受けるときに添付する。
取扱細則3−6
自動車検査証又は限定自動車検査証 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提出する。 車両法第67条第3項
車両法施規第38条
自動車重量税納付書又は非課税証明書 ○
重量税(229頁参照) 重量税法第5条重量税法第8条附則第12項重量税政令第6条
ナンバープレート ○ ○ ○ ○
事務所の指示により取りはずしてナンバー交付所に返納し、新しいナンバープレートの交付を受ける。
車両法施規第38条第4項自管第50号自車第546号
(52.5.24)
車両番号標未処分理由書 ○ナンバープレートを紛失、又はその他の理由により返納できないときに必要。
(33頁参照)
通達52軽検業第45号(52.6.1)
自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照)
使用者の変更に限る自賠法第9条
2 検査証記入申請(車両法第67条、車両法施規第38条)
(検査証の記載事項に変更があった場合)
使用の本拠の位置が変る場合は、変更後の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所に申請する。その他
の場合は、管轄の軽自動車検査協会の事務所に申請する。
第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) Ⅰ登録自動車の2(14頁)を参照。
第38条(自動車検査証の記入の申請等) 第36条第1項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とす
る自動車検査証の記入の申請をする場合に準用する。
2・3・4・5・6・7・8省略

92
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
を変更した場合
所有者または使用者
(所有権解除)
割賦完済の場合
住所を変更した場合
氏名または名称及び
使用者又は所有者の
入した場合
他の都道府県から転
車を売買した場合
他の都道府県の自動
場合
車両番号を変更する
構造変更の場合
説 明 欄 参 考 条 文
自動車取得税及び軽自動車税申告書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。
(235・237頁参照)地方税法第447条、第122条
申請依頼書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 届出人(使用者・所有者)の申請書に押印できないときに必要
※構造変更の場合は、平成17年2月1日より、検査を受ける場合には、預託証明書(リサイクル券等)の提示が必要となります。(自動車リサイクル法第74条附則第1条第3項)
(注)○構造変更の場合のナンバープレートは自家用←→事業用、又は貨物車←→特種車となる場合に必要です。
※前頁の書類のほか、必要に応じて下記の書類を添付する。1 事業用自動車又は貸渡自動車の場合……事業用自動車等連絡書 (事業用自動車等連絡書及び検査証記入申請書をそれぞれ運輸支局の輸送担当部署に提出し、経由印を受けてから軽自動車検
査協会の事務所に提出する。)2 緊急自動車又は道路維持作業用自動車……公安委員会の指定申請済証明書等

93
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
永久返納 輸出予定届出
一時使用中止
説 明 欄 参 考 条 文
重量税還付対象
永久返納
リサイクル対象
永久返納
滅失・用途廃止
OCRシート 軽第4号様式 ○
届出人(使用者)は署名または押印する。 車両法第69条経過省令第1条事務規定5−3取扱細則5−4
軽第4号の2様式 ○ ○届出人(使用者)は署名または押印する。所有者が異なる場合は、所有者の押印が必要。
車両法第69条経過省令第1条事務規定5−3取扱細則5−4
軽第4号の3様式 ○ ○届出人(使用者)は署名または押印する。所有者が異なる場合は、所有者の押印が必要。
車両法第69条経過省令第1条事務規定5−3取扱細則5−4
申請依頼書 ○ ○ ○ ○ ○ 届出人(使用者・所有者)の申請書に押印できないときに必要
登令第14条 第1項第3号
自動車検査証又は限定自動車検査証 ○ ○ ○ ○ ○ 返納する。 車両法第69条
旅規第39条の2
ナンバープレート ○ ○ ○ ○ ○申請の際にナンバープレート交付所に返納する。 自官第50号・
自車第546号 (52.5.24)
解体報告記録がなされた日 ○ ○「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から㈶自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日
車両法第99条の3
移動報告番号 ○ ○ 解体がされた時に引取業者から通知される番号 車両法第99条の3
重量税還付申請の委任状 ○申請書代理人欄に代理人の押印が必要。重量税還付金受領権限を委任する場合、所有者本人の自署・押印又は記名の場合は実印を押印した委任状
租税措置法第90条15
重量税還付申請書付表2 ○ OCRシート軽第4号様式の3重量税還付申請欄の氏名・名称等のオーバーフローの場合
租税措置法第90条15
重量税還付申請書付表3 ○ OCRシート軽第4号様式の3重量税還付申請欄が共同所有の場合
租税措置法第90条15
輸出予定日 ○ 輸出予定日 車両法第69条の2第3項
永久返納・輸出予定届出・一時使用中止
3 自動車検査証又は限定自動車検査証の返納届(車両法第69条、施行規則第39条の2)
(軽自動車を廃車又は使用を中止する場合)
管轄の軽自動車検査協会の事務所に申請する。
第69条(自動車検査証の返納等)Ⅰ登録自動車の5抹消登録申請(25頁参照)

94
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類
かった時
輸出予定届出後輸出されな
一時使用中止後
説 明 欄 参 考 条 文
出(重量税還付)
使用済自動車の解体届
出(重量税還付対象外)
使用済自動車の解体届
滅失・用途廃止
輸出しようとするとき
輸出されなかった時
所有者を変更する時
自動車検査証返納後の
OCRシート 軽第1号様式 ○
届出人(所有者)は署名または押印する。 車両法第69条経過省令第1条事務規定5−3取扱細則5−4
軽第4号の2様式 ○ ○ ○ ○届出人(所有者)は署名または押印する。 車両法第69条
経過省令第1条事務規定5−3取扱細則5−4
軽第4号の3様式 ○ ○届出人(所有者)は署名または押印する。 車両法第69条
経過省令第1条事務規定5−3取扱細則5−4
申請依頼書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 届出人(使用者・所有者)の申請書に押印できないときに必要
解体報告記録がなされた日 ○ ○
「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から㈶自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日
車両法第99条の3
移動報告番号 ○ ○ 解体がされた時に引取業者から通知される番号 車両法第99条の3
重量税還付申請の委任状 ○申請書代理人欄に代理人の押印が必要。重量税還付金受領権限を委任する場合、所有者本人の自署・押印又は記名の場合は実印を押印した委任状
租税措置法 第90条15
重量税還付申請書付表2 ○ OCRシート軽第4号様式の3重量税還付申請欄の氏名・名称等のオーバーフローの場合
租税措置法 第90条15
重量税還付申請書付表3 ○ OCRシート軽第4号様式の3重量税還付申請欄が共同所有の場合
租税措置法 第90条15
輸出予定日 ○ 輸出予定日 車両法第69条の2第3項
譲渡証明書 ○※
○※
○※
○※
○ 譲渡人のみ押印が必要。譲受人は所有者のみを記入する。※所有者に変更があった場合
車両法第7条第33条登規6条
輸出予定届出証明書 ○ ○ 輸出予定日から遡って6ヶ月前から輸出する間に申請した時に交付される証明書
車両法第69条の2第4項、第5項
自動車検査証返納証明書 ○ ○ ○ ○ ○ 車両法第69条
新所有者の住所を証する書面 ○
住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面等で発行されてから3ヶ月以内のもの
施行規則 第40条の7
輸出予定届出後及び一時使用中止後

95
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
自動車検査証又は限定自動車検査証再交付申請書OCRシート軽第3号様式
使用者の押印又は署名が必要。再交付を受ける理由を記入する。手数料(107頁参照)
経過省令第1条
自動車検査証又は限定自動車検査証
き損等で提出できる場合。 車両法第70条車両法第71条の2
検査標章再交付申請書
使用者の押印又は署名が必要。再交付を受ける理由を記入する。手数料(107頁参照)申請書は検査証再交付申請書の課題を訂正して使うこと。
車両法第70条車両法施規第41条
検査標章 破損等その一部が残っており提出できる場合。 事務規程7−1−3車両法施規第41条の2
4 自動車検査証又は限定自動車検査証及び検査標章の再交付申請 (車両法第70条、車両法第71条の2、車両法施規第41条、第41条の2)
(検査証又は検査標章をき損、紛失等により再交付を受ける場合)
管轄の軽自動車検査協会の事務所に申請する。
※検査標章の場合は、もよりの軽自動車検査協会の事務所に申請してもよい。
車両法第70条(再交付) Ⅰ登録自動車の9(38頁)を参照。
車両法第71条の2(限定自動車検査証等) Ⅰ登録自動車の9(38頁)を参照。
施行規則第41条(検査標章等の再交付の申請書)Ⅰ登録自動車の9(38頁)を参照。
第41条の2(検査標章の再交付)Ⅰ登録自動車の9(38頁)を参照。
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
自動車税申告書(使用廃止用) 使用者、所有者の押印が必要。
車両番号標未処分理由書 ナンバープレートを紛失等の理由により返納できないときに必要。(33頁参照)
通達52軽検業第45号(52.6.1)
事業用自動車等連絡書 事業用自動車又は貸渡自動車の場合に必要。(あらかじめ運輸支局に提出)
その他の添付書類
注 軽自動車検査証返納確認書の再交付をする場合 ⑴ 軽自動車協会へ軽自動車検査証返納確認書の交付申請をすること。

96
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
継続検査申請書OCRシート軽第3号様式または軽専用3号様式
使用者の押印又は署名が必要。手数料(107頁参照) 経過省令第1条
自動車検査証又は限定自動車検査証
提出する。 車両法第62条第1項車両法施規第37条2の2
軽自動車検査票 持込み検査を受ける場合に必要。軽自動車検査票(甲)
事務規程3−1取扱細則3−1
点検整備記録簿 提示する。 車両法第62条第3項車両法施規第39条
保安基準適合証又は限定保安基準適合証
指定整備を行ったものについてのみ必要。 車両法第94条の5車両法第94条の5の2
軽自動車税の滞納がないことを証する書面
軽自動車税納税証明書。継続検査申請書に納税済の印を押したものでもよい。
車両法第97条の2
自動車重量税納付書又は非課税証明書
自動車検査証の初度検査年が49年5月以降のものについて必要。(但し、49年4月以前に車両番号の指定を受けたものでも検査証の備考欄 に○重と記載のあるものは必要。)重量税(229頁参照)
重量税法第5条、重量税法第8条、附則第12項重量税法政令第6条
自動車損害賠償責任保険証明書
自動車検査証の新たな有効期間をカバーするだけの期間が必要。(257頁参照)
自賠法第9条
5 継続検査申請(車両法第62条、第74条の3)
(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)
最寄りの軽自動車検査協会の事務所に申請する。
第62条(継続検査) Ⅰ登録自動車の�(44頁)を参照。
※平成17年2月1日より、検査を受ける場合には、預託証明書(リサイクル券等)の提示が必要となります。(自動車リサイクル法第74条附則第1条第3項)

97
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
B 検査対象外軽自動車
1 使用の届出(車両法第97条の3、車両法施規第63条の2)
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第97条の3(検査対象外軽自動車の使用の届出等) 検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管
轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 第73条第1項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
3 前項において準用する第73条第1項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交
通省令で定める。
第63条の2(検査対象外軽自動車の使用の届出等) 車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供
しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に軽自動車届出書を提出しなければならない。
この場合において、運輸監理部長又は運輸支局長は、第63条の6第2項の軽自動車届出済証返納証明書その他の必要
な書面の提出を求めることができる。
2 第36条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、前項の軽自動車届出書を提出する場合に準用する。
3 法第97条の3第1項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外
軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによって行う。ただし、試運転、又は回送その他特別の
事由がある場合は、法第97条の3第2項で準用する法第73条第1項の規定により表示すべき車両番号標として臨時運転
番号標を賃与し、かつ、臨時運転番号標賃与証を交付することによって行う。
4 法第97条の3第2項で準用する法第73条第1項の規定により表示すべき車両番号標(臨時運転番号標を除く。)、軽自
動車届出書、軽自動車届出済証、臨時運転番号標及び臨時運転番号標貸与証の様式は、それぞれ第14号様式、第15号様
式、第16号様式、第17号様式及び第17号様式の2による。
5 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対
象外軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内にお
ける当該車両番号に係る検査対象外軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する様式に適合しないことと
なったときであっても、同項に規定する様式に適合するものとみなす。
6 第11条第3項の規定は、第4項の車両番号標及び臨時運転番号標について準用する。
必 要 書 類新
車
中古車
説 明 欄 参 考 条 文
軽自動車届出書 ○ ○
①届出者欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)②所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい)、所有者印押印
車両法施規第63条の2
譲渡又は販売を証する書面 ○ 軽自動車販売証明書等販売店で発行
自動車重量税納付書 ○ 所定の重量税印紙を貼付 重量税法第9条
軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用) ○ 提出する 重量税法第5条
軽自動車届出済証返納済確認書 ○ 所有者の変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印

98
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類新
車
中古車
説 明 欄 参 考 条 文
使用者の住所を証するに足りる書面
(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
○ ○
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) ②法人 ⒜商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)⒝本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規 第63条の2第2項、国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)
○ ○
①個人 ⒜公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)⒝住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等②法人 ⒜商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)⒝事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等③各書面は写しで可とする
車両法施規 第63条の2第2項、国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)
自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ 提示する(257頁参照) 自賠法第9条
自動車取得税申告書及び軽自動車税申告書 ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(235・237頁参照)(二輪の軽
自動車の場合は自動車取得税は不要。)地方税法第447条 第699条の11
※上記書類のほか、必要に応じて下記の書類を添付する。 事業用自動車又は貸渡自動車の場合……事業用自動車等連絡書 (事業用自動車等連絡書及び軽自動車届出書を運輸支局の輸送担当部署に提出し、経由印を受けてから登録担当窓口に提出する。)

99
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
軽自動車届出済証記入申請書
①申請者欄:使用者(変更の場合は新使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)②所有者欄:所有者(変更の場合は新所有者)氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。)、所有者印押印③旧使用者欄:使用者に変更があった場合に、旧使用者について記入、旧使用者印押印④旧所有者欄:所有者の変更があった場合に、旧所有者について記入、旧所有者印押印⑤その他の記載事項欄:変更があった事項については変更後の内容を、変更がなかった事項については従前の内容を記入⑥備考欄:車両番号が変更となる場合は、旧車両番号を備考欄に記入
車両法施規 第63条の4第2項
軽自動車届出済証 提出する。①軽自動車届出済証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印のある理由書を添付
車両法施規 第63条の6第1項
新使用者の住所を証するに足りる書面
(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) ②法人 ⒜商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)⒝本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規 第63条の4第3項国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
(使用の本拠の位置が新使用者の住所と異なる場合に限り必要)
①個人 ⒜公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)⒝住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等②法人 ⒜商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)⒝事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等③各書面は写しで可とする
車両法施規 第63条の2第2項国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)
車両番号標車両番号変更の場合にのみ必要。②車両番号標が盗難又は遺失等により車両番号を変更する場合は、返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の押印のある理由書
車両法第20条第1項、車両法施規第10条
自動車損害賠償責任保険証明書 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条
自動車取得税申告書及び軽自動車税申告書
使用者、所有者の押印が必要。(235・237頁参照)(二輪の軽自動車の場合は自動車取得税は不要。)
地方税法第447条 第699条の11
2 軽自動車届出済証の記入申請(車両法施規第63条の4)
(届出済証の記載事項に変更があった場合)
届出した運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第63条の4(軽自動車届出済証の記載事項の変更) 検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証の記載事項につ
いて変更があったときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自
動車届出済証の記入を受けなければならない。
2 前項の記入を受けようとする者は、第17号様式の3による申請書を提出しなければならない。
3 第36条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする前項
の申請書を提出する場合に準用する。
4 第36条第2項の規定は、使用者の変更(当該検査対象外軽自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)
又は自動車運送事業の用に供しない検査対象外軽自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする第
2項の申請書を提出する場合に準用する。
※上記書類のほか、必要に応じて下記の書類を添付する。 事業用自動車又は貸渡自動車の場合……事業用自動車等連絡書 (事業用自動車等連絡書及び軽自動車届出済証の記入申請書を運輸支局の輸送担当部署に提出し、経由印を受けてから登録担当窓口に提出する。)

100
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
軽自動車届出済証返納届(旧車両番号用)
①返納者欄:返納者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)②所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。)、所有者印押印③所有者の変更を伴わない場合は、軽自動車届出済証返納済確認書は不要
車両法施規 第63条の6第1項
軽自動車届出書(新車両番号用)
①届出者欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)②所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。)、所有者印押印
車両法施規第63条の2
軽自動車届出済証 提出する。①転出元の車両番号に関する軽自動車届出済証がない場合は、届出出来ない。
車両法施規 第63条の6第1項
新使用者の住所を証するに足りる書面
(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人 ⒜商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)⒝本店以外で商業登記簿謄
(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする
車両法施規 第63条の2第2項、国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
(使用の本拠の位置が新使用者の住所と異なる場合に限り必要)
①個人 ⒜公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)⒝住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等②法人 ⒜商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)⒝事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等③各書面は写しで可とする
車両法施規 第63条の4第3項、国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)
車両番号標車両番号変更の場合にのみ必要。②車両番号標が盗難又は遺失等により車両番号が返納できない場合は、返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の押印のある理由書
車両法第20条第1項車両法施規第10条
自動車損害賠償責任保険証明書
提示する。(257頁参照) 自賠法第9条
自動車取得税申告書及び軽自動車税申告書
使用者、所有者の押印が必要。(235・237頁参照)(二輪の軽自動車の場合は自動車取得税は不要。)
地方税法第447条 第699条の11
3 他の都道府県から転入又は転出する場合

101
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
軽自動車届出済証返納届
ただし、車両の滅失・解体の場合は軽自動車届出済証返納済確認書は不要①返納者欄:返納者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)②所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。)、所有者印押印③解体の場合は返納届の「解体」欄を囲む
車両法施規 第63条の6第1項
軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
①請求者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)②解体の場合は不要
車両法施規 第63条の6第2項
軽自動車届出済証 提出する。①軽自動車届出済証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印のある理由書を添付
車両法施規 第63条の6第1項
車両番号標返納する。車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の押印のある理由書
車両法第20条第1項、車両法施規第10条
軽自動車税申告書(使用廃止用)
使用者、所有者の押印が必要。 地方税法第447条 第699条の11
4 軽自動車届出済証の返納(車両法施規第63条の6)
(廃車又は使用を中止する場合)
届出した運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第63条の6(軽自動車届出済証の返納等) 検査対象外軽自動車の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅
滞なく、当該軽自動車届出済証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
⑴ 法第54条第2項又は法第54条の2第6項の規定により、検査対象外軽自動車の使用の停止を命ぜられたとき。
⑵ 使用の本拠の位置が、軽自動車届出済証の交付を受けた運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域外になったとき。
⑶ 検査対象外軽自動車の使用を廃止したとき。
2 前項の規定により軽自動車届出済証の返納があったときは、申請により、当該軽自動車届出済証を返納した者に対し、
軽自動車届出済証返納証明書を交付するものとする。
3 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第54条第3項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は法第54条の2第6項
の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至ったときは、返納を受
けた軽自動車届出済証を返付しなければならない。
※上記書類のほか、必要に応じて下記の書類を添付する。 事業用自動車又は貸渡自動車の場合……事業用自動車等連絡書 (事業用自動車等連絡書及び軽自動車返納届を運輸支局の輸送担当部署に提出し、経由印を受けてから登録担当窓口に提出する。)注返納手続後当該自動車を再使用する場合は、運輸支局又は自動車検査登録事務所から軽自動車届出済証返納証明書の交付を受けること。

102
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文
軽自動車届出済証再交付申請書
①申請者欄:申請者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、申請者印押印(記名押印に代えて署名でもよい)②記載事項欄:当該車両の車両番号及び再交付を受ける理由を記入 ※軽自動車届出済証(提出可能な場合)
車両法施規第63条の7
5 軽自動車届出済証の再交付申請(車両法施規第63条の7)
届出した運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。
第63条の7(軽自動車届出済証の再交付) 検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証が滅失し、き損し又はそ
の識別が困難となったときは、その再交付を受けることができる。
2 軽自動車届出済証の再交付を受けようとする者は、第10号様式による申請書を提出しなければならない。

103
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
4 そ の 他
1 OCRシート(申請書)の使用区分 (平成20年9月1日 国土交通省令第76号)
申請書の様式 申 請 の 内 容
1号様式
・新規登録・検査(型式指定車)・変更・移転登録・更正登録(諸元変更のないもの)・使用の本拠の位置の変更に係る自動車登録番号標の交付・予備検査(諸元変更のないもの)・自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付・自動車検査証の記入(諸元変更のないもの)・自動車予備検査証の記入(諸元変更のないもの)・所有者変更記録・(整備工場コード)
2号様式・諸元変更に係る変更・更正登録・諸元変更に係る自動車検査証の記入・諸元変更に係る自動車予備検査証の記入
1号様式+2号様式
・新規登録・検査(一般車)・変更・移転・更正登録(諸元変更を伴うもの)・諸元変更に係る自動車登録番号標の交付・自動車予備検査(諸元変更を伴うもの)・自動車検査証の記入(諸元変更を伴うもの)・自動車予備検査証の記入(諸元変更を伴うもの)
3号様式
・自動車登録番号標の交付(自動車登録番号の変更のみのもの)・継続検査・臨時検査・自動車登録番号の変更に係る自動車検査証の記入・自動車検査証の再交付・自動車予備検査証の再交付・限定自動車検査証の再交付・検査標章の再交付・登録事項等証明書の交付の請求(現在・詳細)・検査記録事項等証明書の交付の請求(現在・詳細)・(整備工場コード)
3号様式の2
・永久抹消・輸出仮抹消・一時抹消登録(使用済自動車の解体でないもの)・再輸入見込み届出・一時抹消登録後の解体等・輸出の届出(使用済自動車の解体でないもの)・輸出予定届出証明書の交付・輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書の返納の届出・自動車検査証返納証明書の交付
3号様式の3・永久抹消登録(使用済自動車の解体に限る)・一時抹消登録後の解体等の届出(使用済自動車の解体に限る)・(自動車重量税の還付)
4号様式 ・登録事項等証明書の交付の請求(30両一括)・検査記録事項等証明書の交付の請求(30両一括)
5号様式 ・抵当権の登録
6号様式 ・登録の嘱託
7号様式
検査に関する申請であって、次の事項について申請する場合・トラックトラクタの長さ、幅、高さ等・付属装置付き自動車の付属装置の記載・タンク自動車の積載容量、積載物品等・保安基準緩和事項
8号様式検査に関する申請であって、次の事項について申請する場合・被けん引車の場合のけん引車の車名・型式・けん引車の場合の被けん引車の車名・型式

104
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
申請書の様式 申 請 の 内 容
9号様式1号様式、専用2号様式の申請書及び第6号様式の嘱託書だけでは記載することができない次の事項について申請する場合・所有者・使用者の氏名・名称または住所
10号様式 1号様式から9号様式までの申請書だけでは記載することができない部分について申請する場合・登録・検査事項の補助
専用1号様式現所有者と現使用者が同一の場合であって、次の申請をする場合・所有者の住所又は使用の本拠の位置の変更に係る変更登録・所有者の住所又は使用の本拠の位置の変更に係る自動車検査証の記入(二輪の小型自動車)
専用2号様式・移転登録と使用者の氏名・名称及び住所又は自動車の使用の本拠の位置に係る自動車検査証の記入を同時
に行う場合・使用者及び所有者の氏名・名称及び住所又は自動車の使用の本拠の位置の変更に係る自動車検査証の記入
を行う場合(二輪の小型自動車)
専用3号様式 ・継続検査 ・(整備工場コード)
2 軽OCRシート(申請書)の使用区分
申請書の様式 申 請 の 内 容
軽1号様式新規検査(軽型式指定車)、自動車予備検査証(軽諸元欄事項に変更のないもの)、自動車予備検査証に基づいての自動車検査証の交付、新規検査(自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車で軽諸元欄事項に変更がないもの)、自動車検査証又は自動車予備検査証の記入、自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録
軽2号様式 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入
軽1号様式+軽2号様式
新規検査(軽型式指定以外)、自動車予備検査証(軽諸元欄事項変更を伴うもの)
軽3号様式 継続検査又は臨時検査、自動車検査証の記入、自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標章の再交付、検査記録事項等証明書の交付
軽4号様式 自動車検査証返納証明書の交付
軽4号様式の2 解体等又は輸出に係る届出、本邦に輸入することが見込まれる自動車の届出
軽4号様式の3 解体等に係る届出
軽5号様式 新規予備検査、自動車検査証、自動車予備検査証の記入、自動車検査証の備考欄記載事項用の補助
軽6号様式 記載事項等の補助
軽専用1号様式 自動車検査証の記入
軽専用2号様式 継続検査

105
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3 手数料一覧自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙で納付するもの。(検査対象外軽自動車を除く)(昭和26.6.30 政令第255号)
申 請 の 種 類 適 用手数料
自動車検査登録印紙
自動車審査証紙
⑴ 新規登録申請 一両につき 700円
⑵ 変更登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録申請、車両法第15条の2第5項の一時抹消登録・輸出予定届出証明書交付申請
一両につき 350円
⑶ 移転登録申請 一両につき 500円
⑷ 登録事項等証明書又は検査記録事項等証明書の交付請求
一枚につき、次に掲げる金額⒈ 自動車一両ごとに作成する証明書 イ 現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの ロ 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されてい
る事項に係るもの(二枚目以降は)
300円
1,000円(300円)
⑸ 新規検査申請
一両につき次に掲げる金額⒈ 完成検査終了証の提出がある自動車、登録識別情報等通知
書又は自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車
⒉ 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。)
⒊ その他の自動車 イ 小型自動車 ロ 小型自動車以外の自動車
1,100円
400円 900円
400円 1,600円
400円 1,700円
⑹ 継続検査申請
一両につき次に掲げる金額⒈ 保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査
証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車⒉ 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合
証の提出がない自動車に限る。)⒊ その他の自動車 イ 小型自動車 ロ 小型自動車以外の自動車
1,100円
400円 900円
400円 1,300円
400円 1,400円
⑺ 構造等変更検査申請一両につき次に掲げる金額⒈ 小型自動車⒉ 小型自動車以外の自動車
400円 1,600円
400円 1,700円
⑻ 予備検査申請
一両につき次に掲げる金額⒈ 登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書ととも
に保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車
⒉ 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。)
⒊ その他の自動車 イ 小型自動車 ロ 小型自動車以外の自動車
1,100円
400円 900円
400円 1,600円
400円 1,700円
⑼ 自動車検査証返納証明書の交付申請 一件につき 350円
⑽ 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付申請
一件につき 300円
⑾ 自動車の型式指定の申請 一件につき 42万円
⑿ 指定自動車整備事業の指定申請 一件につき 29,000円
⒀ 自動車登録原簿の閲覧請求 一件につき 100円
⒁ 自動車登録原簿に係る登録事項等証明書の交付申請 一件につき 200円
※⒀、⒁の手数料は道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令を廃止する政令(昭和62.8.11政令281号)附則第3項、第4項による。

106
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
申 請 の 種 類 摘 要 税率又は金額
⑴ 運輸支局長が行う臨時運行の許可申請 一両につき 750円
⑵ 回送運行許可証の交付申請
⒈ 有効期間が一か月以内の許可証 2,050円
⒉ 有効期間が一か月を超え二か月以内の許可証 4,100円
⒊ 有効期間が二か月を超え三か月以内の許可証 6,100円
⒋ 有効期間が三か月を超え四か月以内の許可証 8,200円
⒌ 有効期間が四か月を超え五か月以内の許可証 10,200円
⒍ 有効期間が五か月を超え六か月以内の許可証 12,300円
⒎ 有効期間が六か月を超え七か月以内の許可証 14,300円
⒏ 有効期間が七か月を超え八か月以内の許可証 16,400円
⒐ 有効期間が八か月を超え九か月以内の許可証 18,400円
10. 有効期間が九か月を超え十か月以内の許可証 20,500円
11. 有効期間が十か月を超え十一か月以内の許可証 22,500円
12. 有効期間が十一か月を超え十二か月以内の許可証 24,600円
⑶ 自動車整備士の技能検定の申請 一件につき(学科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については)
7,200円(2,450円)
⑷ 優良自動車整備事業者の認定の申請 一件につき 20,000円
⑸ 抵当権の設定登録申請 債権金額、又は極度金額 1,000分の3
⑹ 抵当権の移転登録申請 債権金額、又は極度金額 1,000分の1.5
⑺ 根抵当権の一部譲渡による移転の登録 一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 1,000分の1.5
⑻ 抵当権の抹消した登録の回復の登録、又は登録の更正、若しくは変更の登録申請 一両につき 1,000円
⑼ 抵当権のまっ消登録申請 一両につき 1,000円
⑽ 一般乗合旅客、一般貸切旅客、自動車運送事業の許可 許可件数 一件につき 90,000円
⑾ 一般貨物自動車運送事業の許可 許可件数 一件につき 120,000円
⑿ 一般乗用旅客、特定旅客、特定貨物自動車運送事業の許可 許可件数 一件につき 30,000円
⒀ 個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の許可で政令で定めるもの 許可件数 一件につき 15,000円
⒁ 第一種利用運送事業の登録 登録件数 一件につき 90,000円
⒂ 第二種利用運送事業の許可 許可件数 一件につき 120,000円
⒃ 倉庫業の許可 許可件数 一件につき 90,000円
⒄ 倉庫の位置の変更の許可 倉庫の新設に係る許可で政令で定めるものに限る。倉庫の数 一個につき 30,000円
収入印紙で納付するもの。

107
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
申 請 の 種 類 摘 要 手数料
⑴ 新規検査
完成検査終了証の提出がある自動車自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る)(持込検査)その他の自動車(持込検査)
1,100円
1,100円1,100円
1,200円1,400円
⑵ 継続検査
保安基準適合証の提出がある自動車限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る)(持込検査)その他の自動車(持込検査)
1,100円1,100円
1,200円1,400円
⑶ 構造等変更検査 1,400円
⑷ 予備検査限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る)(持込検査)その他の自動車(持込検査)
1,100円
1,200円1,400円
⑸ 自動車検査証、検査標章予備検査証、限定自動車検査証の再交付 300円
⑹ 自動車検査証返納 自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合 350円
⑺ 輸出届出 輸出予定届出証明書の交付を受ける場合 350円
計器収納によるもの。(検査対象軽自動車)

108
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
4 自動車登録番号標及び車両番号標の交付手数料及び頒布価格表 平成9年3月14日 関整登資第47号認可 平成9年4月1日 実施
種 別都県別
大 型 中 型
ペイント式 字 光 式 ペイント式 字 光 式
東 京 都 980円 1,960円 720円 1,420円
神 奈 川 県 980円 1,960円 720円 1,420円
埼 玉 県 990円 1,980円 740円 1,460円
千 葉 県 990円 1,980円 740円 1,460円
茨 城 県 1,040円 2,070円 760円 1,510円
群 馬 県 1,040円 2,070円 760円 1,510円
栃 木 県 1,040円 2,070円 760円 1,510円
山 梨 県 1,040円 2,070円 760円 1,510円
◎ 登録番号標交付手数料
種 別都県別
中 型小 型
ペイント式 字 光 式
東 京 都 720円 2,400円 520円
神 奈 川 県 720円 2,400円 520円
埼 玉 県 740円 2,440円 540円
千 葉 県 740円 2,440円 540円
茨 城 県 760円 2,480円 570円
群 馬 県 760円 2,480円 570円
栃 木 県 760円 2,480円 570円
山 梨 県 760円 2,480円 570円
◎ 車両番号標頒布価格
備考 上記の金額は1枚当たりの単価です。従って一車両に2枚取り付ける場合はその倍額となります。
備考 上記の金額は1枚当たりの単価です。従って一車両に2枚取り付ける場合はその倍額となります。

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
Ⅱ 自動車運送事業の免許・許可申請早わかり

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

111
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1 定 義⑴ 定義(運送法第2条)
1.この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2.この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3.この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。
4.この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5.この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6.この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車をいう。
7. この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所
並びに自動車道をいう。
8.この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路
以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送
事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動
車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
⑵ 定義(貨物運送法第2条)
1.この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自
動車運送事業をいう。
2.この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及
び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車
運送事業以外のものをいう。
3.この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運
送する事業をいう。
4.この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び
二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
5.この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車をいう。
6.この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の
事業場において集貨された貨物の仕分けを行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業
場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の
運送を定期的に行うものをいう。
7.この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する
者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物
の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

112
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
2 許可基準⑴ 許可基準(運送法第6条及び第43条第3項)
許可は次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
A 一般旅客自動車運送事業(許可基準)
1.当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
2.前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
3.当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
B 特定旅客自動車運送事業(許可基準)
1.当該事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送
事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
2.当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
⑵ 許可基準(貨物運送法第6条及び第35条第3項)
国土交通大臣は、許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない。
A 一般貨物自動車運送事業(許可基準)
1.その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
2.前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
3.その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
4.特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運
転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するた
め特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
B 特定貨物自動車運送事業(許可基準)
その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。

113
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3 欠格事由⑴ 欠格事由(運送法第7条)
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
1.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から2年を経過していない者であるとき。
2.許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの
日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人
のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを
問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号及び第49条第2項第4号並びに第79条の4第1
項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から2年を経過していないものを含む。)で
あるとき。
3.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合に
おいて、その法定代理人が前2号のいずれかに該当する者であるとき。
4.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前3号のいずれかに該当する者であるとき。
⑵ 欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)
次の各号のいずれかに該当する者は、許可を受けることができない。
1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経
過しない者。
2.一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しな
い者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以
内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号
において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号のいずれ
かに該当するもの。
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの。

114
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
4 処理方針についてA 一般貨物自動車運送事業
平成2年10月1日付関東運輸局では、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請について、事
案の迅速かつ、適切な処理を図るため、平成2年12月1日以降関東運輸局管内運輸支局において受理する申請について
審査項目の具体的な基準を掲げ、これにより処理することとし、公示されている。
公 示
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について
標記の申請については、事案の迅速、かつ、適切な処理を図るため、下記のとおり審査項目の具体的な基準を掲げ、こ
れにより処理することとしたので公示する。
平成15年2月28日
平成19年8月28日
平成20年4月1日
関東運輸局長 淡 路 均
記
許可申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条に規定する許可の基準に基づいて、
厳正公正に行うものであるが、次の各項については、特に要件の充足に重点をおいて審査する。
Ⅰ 一般貨物自動車運送事業の許可申請
1.営業所
⑴ 使用権原を有することの裏付けがあること。
⑵ 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等
関係法令に抵触しないものであること。
⑶ 規模が適切であること。
2.車両数
⑴ 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両
以上とすること。
⑵ 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車
を1両と算定する。
⑶ 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可
能なもの。)の地域における事業については、⑴に拘束されないものであること。
3.事業用自動車
⑴ 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
⑵ 使用権原を有することの裏付けがあること。
4.車庫
⑴ 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340
号に適合するものであること。
⑵ 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべ
てを収容できるものであること。
⑶ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
⑷ 使用権原を有することの裏付けがあること。
⑸ 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等関係法令に抵触しないものであること。

115
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑹ 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。
5.休憩・睡眠施設
⑴ 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
⑵ 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
⑶ 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車
庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地
との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、
20キロメートル)を超えないものであること。
⑷ 使用権原を有することの裏付けがあること。
⑸ 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等
関係法令に抵触しないものであること。
6.運行管理体制
事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。
⑴ 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業
用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。
⑵ 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子
会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、
事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑶ 勤務割及び乗務割が、平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
⑷ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑸ 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼
等が確実に実施される体制が確立していること。
⑹ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運
輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。
⑺ 危険品の運送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保さ
れるものであること。
7.資金計画
⑴ 所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金調達について十分な裏付けがあること。
⑵ 自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。(エ、オ及びカについては、ア
の車両費(リース料)に含まれているものを除く。)
ア.車 両 費 取得価格(割賦未払金及び自動車取得税を含む)
リースの場合は、リース料の1ヵ年分
イ.建 築 費 取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)
賃借の場合は、借料、敷金等の1ヵ年分
ウ.土 地 費 取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
賃借の場合は、借料の1ヵ年分
エ.保 険 料 ① 強制賠償保険料の1ヵ年分
② 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の
1ヵ年分
③ 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分
オ.各 種 税 自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分
カ.運転資金 人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チューブ

116
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
費のそれぞれ2ヵ月分に相当する金額
8.法令遵守
⑴ 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守する
こと。
⑵ 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険
等加入義務者が社会保険等に加入すること。
⑶ 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるか
を問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違
反により、申請日前3ヵ月間(悪質な違反については6ヵ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使
用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を
受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任
した者を含む。)ではないこと。
その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
⑷ 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヵ月以内に実施され
る地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合
等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。
9.損害賠償能力
⑴ 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)
の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。
⑵ 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、⑴号に適合するほか
当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。
10.許可に付す条件等
⑴ 2.⑶に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するな
どの条件を付すものとする。
⑵ 許可に際しては、許可日から1年以内に事業開始することの条件を付すものとする。
⑶ 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すものとする。
11.特別積合せ貨物運送をする場合
特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査は、上記の各項に加え、次の各号につ
いても審査する。
⑴ 荷扱所
ア.使用権原を有することの裏付けがあること。
イ.農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)
等関係法令に抵触しないものであること。
ウ.規模が適切であること。
⑵ 積卸施設
ア.営業所・荷扱所に併設するものであること。
イ.使用権原を有することの裏付けがあること。
ウ.農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)
等関係法令に抵触しないものであること。
エ.施設は、貨物の積卸機能のみならず、荷捌き・仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。
オ.施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。
⑶ 営業所及び荷扱所の自動車の出入口
複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業

117
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
所及び荷扱所の自動車の出入口の設置が、当該出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないも
のであること。
⑷ 運行系統及び運行回数
ア.運行系統毎の運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。
イ.取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が的確であること。
ウ.運行車の運行は少なくとも1日1往復以上の頻度で行われるものであること。ただし、一般的に需要の少ない
と認められる島しょ、山村等の地域においては、この限りでない。
⑸ 積合せ貨物管理体制
ア.貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有するものであること。
イ.貨物の滅失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有するものであること。
ウ.貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有するものであること。
⑹ 運行管理体制
運行系統別の乗務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
12.貨物自動車利用運送をする場合
貨物自動車利用運送をする一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査は、上記の1から10までの各項に加え、
次の各号についても審査する。
⑴ 貨物自動車利用運送に係る営業所については、1⑴〜⑶によること。
⑵ 業務の範囲については、「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。
⑶ 保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。
Ⅱ 特定貨物自動車運送事業の許可申請
1.運送需要者
⑴ 運送需要者は単数の者に特定され、当該運送需要者に係る大部分の輸送量を確保できること。
⑵ 運送需要者と直接運送契約を締結するものであり、運送の指示等において第三者が介入するものでないこと。
2.運送契約期間等
運送需要者との間に1年以上継続した運送契約(輸送品目、輸送数量、運賃等)があること。
3.営業所
Ⅰ.1.によること。
4.車両数
車両数は、5両以上とすること。
5.事業用自動車
Ⅰ.3.によること。
6.車庫
Ⅰ.4.によること。
7.休憩・睡眠施設
Ⅰ.5.によること。
8.運行管理体制
Ⅰ.6.によること。
9.法令遵守
Ⅰ.8.によること。
10.損害賠償能力
Ⅰ.9.によること。
11.許可に付す条件

118
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
Ⅰ.10.⑵によること。
12.貨物利用運送事業
Ⅰ.12.によること。
13.その他
特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約に基づいて許可するものであるから、既にこの
許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自
動車運送事業の許可申請の手続を行うこと。
附 則
1.この処理方針は、平成15年4月1日以降当局管内運輸支局において受理する申請について適用する。
2.平成2年10月1日付けで公示した「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針に
ついて」は、平成15年3月31日限りこれを廃止する。
附 則(平成19年8月28日一部改正)
1.本処理方針は、平成19年9月10日以降に申請を受け付けたものから適用するものとする。
2.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自
整第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っ
ている一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者については施行日から2年間、施行前に一般貨物自
動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可を申請したものについては、その申請による運輸の開始の日から2
年間、外部委託を継続することを可能とする。
附 則(平成20年4月1日一部改正)
本処理方針は、平成20年7月1日以降に申請を受け付けたものから適用するものとする。
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請について、事案の迅速かつ適切な処
理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。
平成13年11月22日
関東運輸局長 上 子 道 雄
記
1.営業区域
⑴ 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域は別表のとおりと
する。
⑵ 営業区域に営業所を設置するものであること。
2.営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するも
のであること。
⑴ 営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること。
⑵ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑶ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地
法(昭和27年法律第229号)等関係法令の規定に抵触しないものであること。
⑷ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
3.事業用自動車

119
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
申請者が使用権原を有するものであること。
4.最低車両数
⑴ 申請する営業区域において、別表に定める車両数以上の事業用自動車を配置するものであること。
⑵ ⑴の車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、当該複数の営業所に配置する
車両数を合算したものとするが、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。
5.自動車車庫
⑴ 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以
内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
⑵ 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用
自動車の全てを収容できるものであること。
⑶ 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
⑷ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑸ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑹ 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備え
られているものであること。
⑺ 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年
政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用
権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触
しないものであること。
6.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
⑴ 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自
動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
⑵ 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
⑶ 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるもので
あること。
⑷ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑸ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
7.管理運営体制
⑴ 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
⑵ 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理
計画があること。この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号、以下「運輸規則」と
いう。)第22条第1項に基づき関東運輸局長が指定する地域において道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」
という。)第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する
場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。
⑶ 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑷ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されると
ともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑸ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第
104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑹ 上記⑵〜⑸の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
⑺ 運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則第36条第2項に定める指導を行うことができる体制が確立され
ていること。
⑻ 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められてい

120
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
るとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
⑼ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社
法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を
持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業
務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑽ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
8.運転者
⑴ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
⑵ この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するもので
ないこと。
⑶ 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
⑷ 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされ
るものであること。
9.資金計画
⑴ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次のイ〜
トの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
イ 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
ロ 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
ハ 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
ニ 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
ホ 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
ヘ 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
ト その他 創業費等開業に要する費用(全額)
⑵ 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されてい
ること。なお、事業開始当初に要する資金は、次のイ〜ハの合計額とする。
イ ⑴イに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによっ
て取得する場合は、⑴イと同額とする。
ロ ⑴ロ及びハに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによっ
て取得する場合は、⑴ロ及びハと同額とする。
ハ ⑴ニ〜トに係る合計額
10.法令遵守
⑴ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送
事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
⑵ 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法((以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険
等加入義務者が社会保険等に加入すること。
⑶ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問
わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、以下のす
べてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。
イ 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)
等の違反により申請日前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁
止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因
となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含
む。)ではないこと。

121
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ロ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ケ月間及び申請日以降
に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分
を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に
当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ハ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に
190日車を超える輸送施設の使用停止命令以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた
者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分
を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ニ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日
以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場
合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業
務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ホ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便
を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に
当該命令された事項が改善されていること。
ヘ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
ト 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令
第33号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
チ 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(酒酔い運転、
酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)
がないこと。
リ 申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項
に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。
11.損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するた
め講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は
共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
12.適用
⑴ 福祉輸送サービスに限る事業にあっては、1.⑴及び4.⑴の規定及びその業務の範囲は別紙に定めるところによる
ものとするが、事業の特性を踏まえて業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。
⑵ 別途定める地域に限る運送にあっては、業務の範囲を当該地域に係る運送に限定する旨の条件を付すこととする。
⑶ 道路運送法施行規則第4条第8項第3号に規定するハイヤー(以下「ハイヤー」という。)のみを配置して行う事
業については、必要に応じ業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。
⑷ 別途定める営業区域においてハイヤーを配置して事業を行う場合にあっては、必要に応じ業務の範囲に条件を付す
こととする。
⑸ 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。
13.申請時期等
⑴ 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとする。ただし、法第8条の緊急調整地域に指定されている地域を営業区域と
する申請の受付は行わない。
⑵ 処分時期
原則として随時行うこととする。ただし、標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができる
こととする。

122
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
14.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成9年4月3日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の需給調整等
の運用基準について」及び「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の経営免許申請
事案の審査基準について」は、平成14年1月31日限り廃止する。
3.10.⑵イ及びハのタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務
適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。
4.事案の処理に際しては本審査基準によるほか、細部取扱い通達の定めによるものとする。
附 則(平成14年7月1日一部改正)
1.本公示は、平成14年7月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成14年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成15年3月25日一部改正)
1.本公示は、平成15年4月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成15年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成16年3月31日一部改正)
1.本公示は、平成16年4月1日以降受付ける申請について適用する。
2.リフト付きタクシー等特殊なサービスに限る事業に係る申請の平成16年4月1日以降の許可処分にあたっては、12.
⑴に規定する条件を付すこととする。
3.附則2.を除き、平成16年3月31日以前に受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成17年4月28日一部改正)
1.本公示は、平成17年6月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成18年3月29日一部改正)
1.本公示は、平成18年4月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成18年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成18年9月27日一部改正)
1.本公示は、平成18年10月10日以降受付ける申請について適用する。
2.平成18年10月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成19年3月22日一部改正)
1.本公示は、平成19年4月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成19年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成19年7月30日一部改正)
1.本公示は、平成19年9月10日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
3.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自
整第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っ
ている一般乗用旅客自動車運送事業者については、施行日から2年間、施行前に一般乗用旅客自動車運送事業の許可
を申請したものについては、その申請による運輸の開始の日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。
附 則(平成20年6月30日一部改正)
1.本公示は、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。

123
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
都県名 営業区域の名称 区 域 車両数
東
京
都
特別区・武三交通圏北 多 摩 交 通 圏
南 多 摩 交 通 圏西 多 摩 交 通 圏
島 し ょ 区 域
東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市及び東久留米市八王子市、日野市、多摩市、稲城市及び町田市青梅市、福生市、あきる野市、羽村市及び西多摩郡瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村島しょ毎
10両以上
5両以上10両以上
5両以上1両以上
神
奈
川
県
京 浜 交 通 圏県 央 交 通 圏
湘 南 交 通 圏小 田 原 交 通 圏
横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市藤沢市、茅ケ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、相模原市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、厚木市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町及び愛甲郡愛川町、清川村鎌倉市、逗子市及び三浦郡葉山町小田原市、南足柄市、足柄上郡大井町、中井町、開成町、山北町、松田町及び足柄下郡箱根町、湯河原町、真鶴町
10両以上
10両以上5両以上
5両以上
千
葉
県
京 葉 交 通 圏東 葛 交 通 圏千 葉 交 通 圏北 総 交 通 圏
東 総 交 通 圏山 武・ 東 金 交 通 圏市 原 交 通 圏東 海 交 通 圏
南 房 交 通 圏
市川市、船橋市、習志野市、鎌ケ谷市、八千代市及び浦安市松戸市、柏市、流山市、野田市及び我孫子市千葉市及び四街道市佐倉市、成田市、香取市、八街市、印西市、富里市、白井市、印旛郡酒々井町、栄町、香取郡多古町、神崎町、東庄町及び山武郡芝山町銚子市、匝瑳市及び旭市東金市、山武市及び山武郡大網白里町、九十九里町、横芝光町市原市茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡一宮町、睦沢町、白子町、長柄町、長南町、長生村及び夷隅郡御宿町、大多喜町木更津市、君津市、袖ヶ浦市、富津市、鴨川市、館山市、南房総市及び安房郡鋸南町
10両以上5両以上10両以上
5両以上5両以上5両以上5両以上
5両以上
5両以上
埼
玉
県
県 南 中 央 交 通 圏
県 南 東 部 交 通 圏
県 南 西 部 交 通 圏
県 北 交 通 圏
秩 父 交 通 圏
川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市及び北足立郡伊奈町春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、加須市(ただし、平成22年3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域に限る。)、南埼玉郡宮代町、白岡町及び北葛飾郡杉戸町、松伏町川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町及び秩父郡東秩父村熊谷市、行田市、加須市(ただし、平成22年3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域を除く。)、本庄市、羽生市、深谷市、児玉郡美里町、上里町及び大里郡寄居町秩父市及び秩父郡横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
10両以上
5両以上
5両以上
5両以上5両以上
群
馬
県
東 毛 交 通 圏
沼 田・ 利 根 交 通 圏渋 川・ 吾 妻 交 通 圏
太田市、館林市、桐生市、みどり市及び邑楽郡大泉町、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町沼田市、みなかみ町及び利根郡川場村、昭和村、片品村渋川市及び吾妻郡東吾妻町、高山村、中之条町、長野原町、六合村、草津町、嬬恋村
5両以上5両以上
5両以上
別 表
附 則(平成21年9月30日一部改正)
本公示は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
附 則(平成22年3月23日一部改正)
本公示は、平成22年3月23日以降受け付ける申請について適用する。
ただし、栃木県県南交通圏については、平成22年3月29日以降受け付ける申請について適用する。
附 則(平成23年9月30日一部改正)
本公示は、平成23年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
ただし、埼玉県県南中央交通圏については、平成23年10月11日以降受け付ける申請について適用する。

124
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
都県名 営業区域の名称 区 域 車両数
群馬県及
び埼玉県
中・ 西 毛 交 通 圏 群馬県前橋市、高崎市、伊勢崎市、佐波郡玉村町、安中市、富岡市、藤岡市、北群馬郡吉岡町、榛東村、神流町、上野村、甘楽郡甘楽町、下仁田町、南牧村及び埼玉県児玉郡神川町 5両以上
茨
城
県
県 北 交 通 圏
水 戸 県 央 交 通 圏
鹿 行 交 通 圏県 南 交 通 圏
県 西 交 通 圏
北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、久慈郡大子町及び東茨城郡城里町ひたちなか市、水戸市、笠間市、那珂市、那珂郡東海村及び東茨城郡大洗町、茨城町鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市及び鉾田市石岡市、つくば市、土浦市、牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、小美玉市、稲敷郡阿見町、美浦村、河内町及び北相馬郡利根町筑西市、古河市、坂東市、下妻市、常総市、結城市、桜川市、結城郡八千代町及び猿島郡境町、五霞町
5両以上
5両以上5両以上
5両以上
5両以上
栃
木
県
宇 都 宮 交 通 圏
県 南 交 通 圏
塩 那 交 通 圏
芳 賀・ 真 岡 交 通 圏日 光 交 通 圏
宇都宮市、鹿沼市、下野市、栃木市(ただし、平成23年10月1日に編入された旧上都賀郡西方町の区域に限る。)、河内郡上三川町、上都賀郡西方町及び下都賀郡壬生町足利市、栃木市(ただし、平成23年10月1日に編入された旧上都賀郡西方町の区域を徐く。)、佐野市、小山市及び下都賀郡野木町、岩舟町大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡塩谷町、高根沢町及び那須郡那珂川町、那須町真岡市及び芳賀郡益子町、茂木町、市貝町、芳賀町日光市
5両以上
5両以上
5両以上5両以上5両以上
山
梨
県
甲 府 交 通 圏東 八・ 東 山 交 通 圏峡 西 交 通 圏峡 北 交 通 圏峡 南 交 通 圏東部・富士北麓交通圏
甲府市、甲斐市、中央市及び中巨摩郡昭和町山梨市、甲州市及び笛吹市南アルプス市、西八代郡市川三郷町及び南巨摩郡富士川町韮崎市及び北杜市南巨摩郡南部町、早川町及び身延町大月市、都留市、富士吉田市、上野原市、北都留郡小菅村、丹波山村及び南都留郡忍野村、富士河口湖町、道志村、鳴沢村、西桂町、山中湖村
5両以上5両以上5両以上5両以上5両以上
5両以上
別 紙
福祉輸送サービス事業に係る業務の範囲は、下記に定める旅客及び使用車両によるものとする。
記
1.対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。
⑴ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
⑵ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
⑶ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
⑷ 上記⑴〜⑶に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単
独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑸ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける
患者
2.福祉輸送サービスに使用する自動車及び乗務する者の要件は、以下に掲げるものとする。
⑴ 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第86号)による改正後の道路運送法施行規則
(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若し
くはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアッ
プシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)を使用する場合にあっては、
介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実
施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了した者、又は財団法人
全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない。
⑵ ⑴によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護

125
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
一定規模以上の減車の基準について
「特定地域の指定及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置の
実施について(平成21年9月30日公示)」中Ⅳ.の基準を下記のとおり定めたので公示する。
平成21年9月30日
関東運輸局長 神 谷 俊 広
記
一定規模以上の減車
一定規模以上の減車については、保有車両数が次の計算式により算出した車両数のうち、いずれかの車両数を下回るこ
ととなる場合とする。
① 基準車両数 × 0.9(1両未満の端数がある場合には端数は切り捨てる。)
② 基準車両数 - 当該地域の最低車両数
(最低車両数とは、同公示中Ⅲ.1.⑴②に示す最低車両数とする。)
公 示
特定地域の指定及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置の実
施について
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)の施行
に伴い、特定地域の指定及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措
置について、下記のとおり定めたので公示する。
平成21年9月30日
関 東 運 輸 局 長 神 谷 俊 広
東京運輸支局長 矢 田 淑 雄
神奈川運輸支局長 石 橋 健
埼玉運輸支局長 上 岡 一 雄
群馬運輸支局長 栗 本 久
千葉運輸支局長 飯 村 勉
茨城運輸支局長 鬼 沢 秀 通
栃木運輸支局長 四月朔日 功一
山梨運輸支局長 春 原 俊 男
記
Ⅰ.特定地域の指定等
1.特定地域の指定
国土交通大臣は、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する営業区域を特定地域として指定するものとし、当該指定は告
示により行うものとする。
⑴ 人口10万人以上の都市を含む営業区域であって、①から③までのいずれかに該当するもの。
従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければならない。
上記に係る福祉輸送サービスに限定する事業にあっては、営業区域を都県単位とし、また最低車両数を1両とする。

126
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
① 日車実車キロ又は日車営収が、平成13年度と比較して減少していること。
② 前5年間の事故件数が毎年度増加していること。
③ 前5年間の法令違反の件数が毎年度増加していること。
⑵ 人口10万人以上の都市を含まない営業区域であって、①から③までのいずれにも該当するもの。
① 人口が概ね5万人以上の都市を含むこと。
② イからハまでのいずれかに該当すること。
イ 日車実車キロ又は日車営収が、平成13年度と比較して10%以上下回っていること。
ロ 前5年間の事故件数が毎年度増加していること。
ハ 前5年間の法令違反の件数が毎年度増加していること。
③ 当該営業区域を含む都道府県知事又は市町村長から、国土交通大臣に対して、当該地域を指定することについ
て要請があったこと。
2.指定期間等
1.の指定は、原則として毎年10月1日を目途に3年を超えない範囲で期間を定めて指定するものとする。ただし、
1.⑵の指定は、原則として毎年4月1日を目途に3年を超えない範囲で期間を定めて指定できるものとする。
Ⅱ.特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置を実施するに当たって
の基本的な考え方等
1.基本的な考え方
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号。以
下「法」という。)、法施行規則及び本通達をはじめとする関係通達の運用に当たっては、「平成19年度の特別監視地
域の指定に伴い試行的に実施する増車抑制対策等の措置について(平成19年11月20日付け公示)」の特定特別監視地
域制度の導入以降、それぞれの一般乗用旅客自動車運送事業者がこれまでに実施してきた一般乗用旅客自動車運送事
業の適正化及び活性化に資する取組み(需要喚起、労働条件の改善、減車等)を十分に考慮するものとする。
2.基準車両数
特定特別監視地域制度の導入以降、一般乗用旅客自動車運送事業者による様々な取組みが実施されていることを踏
まえ、特定地域における処分その他特定地域における各種取組みの実施に係る基準となる車両数は、特定特別監視地
域の指定時(継続して指定(準特定特別監視地域又は特別重点監視地域の指定を含む。)されている場合は、当該継
続して指定された最初の指定時。)における営業区域ごとの当該事業者の一般の需要に応じることができるタクシー
車両(以下「一般タクシー車両」という。)の合計数とする。ただし、当該営業区域において個別に講じている施策
に基づき、関東運輸局長が特別な配慮が必要と認める場合には、関東運輸局長が別途公示する車両数とすることがで
きるものとする。また、法の施行の際、特定特別監視地域に指定されていない営業区域が特定地域に指定された場合
の当該特定地域における基準車両数は、特定地域の指定時における営業区域ごとの当該事業者の一般タクシー車両の
合計数とする。
なお、「特定事業計画における事業再構築の実施のために必要となる特例措置の実施について(平成22年1月27日
付け公示。以下「事業再構築特例公示」という。)」8.に基づき認定事業者(以下「親会社」という。)が他の一般
乗用旅客自動車運送事業者(以下「完全子会社」という。)を完全子会社化し、当該完全子会社の一般乗用旅客自動
車運送事業を廃業した場合にあっては、当該完全子会社の基準車両数を当該親会社の基準車両数に加えるものとする。
Ⅲ.特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の申請に対する取扱い
以下に定めるところにより行うものとする。
1.法人タクシー・ハイヤーに係る新規許可等
⑴ 処理方針
特定地域における法人タクシー・ハイヤーに係る新規許可の申請(業務の範囲を限定(ハイヤーに係るものを除

127
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
く。)する旨の条件を付された許可を受けようとする申請を除く。)に対しては、運輸開始後の一定期間における収
支計画の提出を求めた上で、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の
審査基準について(平成13年11月22日付け公示(平成21年9月30日一部改正)。以下「審査基準」という。)」に適
合することに加え、次に掲げる基準に適合するものに限り許可するものとする。ただし、特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する基本方針(平成21年国土交通省告示第1036号。以下「基本方針」
という。)の趣旨に照らし、特別な事情があると認めるものについては、この限りでない。
① 収支計画
提出された収支計画上の営業収入が、申請する営業区域で当該運輸開始後に新たに発生する輸送需要によるも
のであることが明らかであること。
② 最低車両数
原則として、次に掲げる営業区域の区分に応じ、それぞれ次に定める車両数とする。
イ 東京特別区又は政令指定都市を含む営業区域 40両
ロ 人口が概ね30万人以上の都市を含む営業区域 30両
ハ その他の営業区域 20両
⑵ 適用開始時期
⑴の規定は、法施行日以降に処分をするものから適用する。
⑶ 営業区域の拡大に係る事業計画変更認可への準用
⑴及び⑵の規定は、営業区域の拡大に係る事業計画の変更認可について準用する。この場合において、⑴中「新
規許可の申請(業務の範囲を限定(ハイヤーに係るものを除く。)する旨の条件を付された許可を受けようとする
申請を除く。)」とあるのは「営業区域拡大に係る事業計画変更認可の申請(業務の範囲を限定(ハイヤーに係るも
のを除く。)する旨の条件を付された認可を受けようとする申請を除く。)」と「許可する」とあるのは「認可する」
と読み替えるものとする。
⑷ 限定解除への準用
⑴及び⑵の規定は、業務の範囲を限定する旨の条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者における当該条件
の解除について準用する。この場合において、⑴中「新規許可の申請(業務の範囲を限定(ハイヤーに係るものを
除く。)する旨の条件を付された許可を受けようとする申請を除く。)」とあるのは「限定解除の申請」と、「許可す
る」とあるのは「限定解除する」と読み替えるものとする。
2.個人タクシーに係る新規許可
⑴ 処理方針
特定地域における個人タクシーに係る新規許可の申請に対しては、運輸開始後の一定期間における収支計画の提
出を求めた上で、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認可
申請事案の審査基準について(平成13年12月27日付け公示(平成19年3月22日一部改正))」に適合することに加え、
提出された収支計画上の営業収入が、申請する営業区域で当該運輸開始後に新たに発生する輸送需要によるもので
あることが明らかであるものに限り許可するものとする。ただし、基本方針の趣旨に照らし、特別な事情があると
認めるものについては、この限りでない。
⑵ 適用開始時期等
⑴の規定は、法施行日以降に処分をするものから適用する。ただし、法施行日前に申請を受理したものについては、
なお従前の例によるものとする。この場合において、許可申請者に対する法令及び地理の試験の合格基準について
は、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に係る法令及び地理の試験の
実施について(平成14年1月31日付け公示(平成20年6月13日一部改正))」で定める合格基準にかかわらず、法令
試験及び地理試験ともに正解率95%以上とする。
3.増車の認可
⑴ 処理方針

128
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
特定地域における営業区域内の増車(一般の需要に応じることができるタクシー・ハイヤー車両の合計数を増加
させる事業計画の変更をいう。)の認可の申請に対しては、増車後の一定期間における収支計画等基準適合を証す
る書面の提出を求め、かつ、申請後に法令遵守状況の確認を行うための監査を実施した上で、審査基準に適合する
ことに加え、次に掲げる基準(ハイヤー車両の増車にあっては、①及び④に限る。)に適合するものに限り認可す
るものとする。ただし、基本方針の趣旨に照らし、特別な事情があると認めるものについては、この限りでない。
① 収支計画
提出された収支計画上の増車車両分の営業収入が、申請する営業区域で当該増車実施後に新たに発生する輸送
需要によるものであることが明らかであること。
② 運転者の確保状況
一般タクシー車両に係る運転者の確保状況について、1両当たり1.5人以上であること。ただし、地域の標準
的な運転者数など実情を踏まえて、関東運輸局長が当該地域における1両当たりの運転者数を公示した場合には、
その人数以上であること。
③ 実働率
一般タクシー車両に係る実働率について、80%以上であること。ただし、地域の標準的な実働率など実情を踏
まえて、関東運輸局長が当該地域における実働率を公示した場合には、その率以上であること。
④ 法令遵守状況
申請後に監査を実施した結果、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分を受けなかったこと。
⑵ 適用開始時期
⑴の規定は、法施行日以降に処分をするものから適用する。
⑶ 福祉輸送自動車の取扱い
福祉輸送自動車の合計数を増加させる事業計画の変更の認可の申請に対しては、従前の事前届出書の様式の記載
事項と同程度の内容が確認できることをもって、速やかに認可するものとする。
4.一般タクシー車両への種別等の変更の届出
関東運輸局長は、特定地域における営業区域内の一般タクシー車両以外(ハイヤー又は特殊車両)から一般タク
シー車両への種別等を変更する事業計画の変更(以下、「種別等変更」という。)を実施しようとする事業者について
法令遵守状況の確認を行うため、種別等変更の実施前に監査を実施し、その結果、法令遵守状況に問題がある場合に
は、当該事業者に対して種別等変更前の状態へ戻す事業計画変更の勧告を行うなどの措置を講じる。
⑴ 実施地域及び適用開始時期
特定地域において実施するものとし、地域指定をした日以降に種別等変更の届出を受理するものから適用する。
⑵ 対象となる種別等変更
基準車両数を超えることとならない種別等変更
⑶ 事前届出書の提出時期
「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届
出について(平成14年1月18日付け国自旅第153号)」(以下「増減車届出通達」という。)の記2の規定にかかわら
ず、種別等変更実施予定日の60日前までに届出書を提出させるものとする。
⑷ 種別等変更実施前の監査の実施
① ⑵に該当する種別等変更の届出受理後、種別等変更が実施されるまでの間に、当該事業者に対して監査を実施
することとする。
② 当該監査については、労働基準監督機関との合同監査により実施するよう努めるものとする。
③ 当該監査を実施した結果、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分(以下「車両使用停止以上の処分」
という。)を課すこととなる法令違反(以下「違反」という。)が確認された場合には、当該監査終了時に当該事
業者に対して、当該車両使用停止以上の処分が確定するまでの間の措置として、次の各措置を講じることとする。
ア.当該種別等変更の届出に基づく種別等変更の実施を当面見合わせる旨の指導(種別等変更見合わせ勧告)。

129
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
イ.当該監査の結果に基づき、後日、車両使用停止以上の処分が確定した際に、④の当該種別等変更を実施しな
かった場合の事業計画への変更の勧告を行う旨の通知(当該種別等変更を実施しなかった場合の事業計画への
変更勧告処分の予告)。
ウ.ア.及びイ.の指導及び通知については、運輸支局長が文書により行うものとする。
④ 当該車両使用停止以上の処分が確定した際に、当該種別等変更の届出による種別等変更について、当該種別等
変更を実施しなかった場合の事業計画への変更の手続(当該種別等変更を実施しなかった場合の事業計画への変
更の届出。以下同じ。)を行うよう運輸支局長が文書により指導する。(当該種別等変更を実施しなかった場合の
事業計画への変更の勧告)
⑤ 種別等変更を実施した事業者に対しては、違反の有無にかかわらず、定期的に繰り返し監査を実施することと
する。
⑸ 運転者確保状況及び実働率の調査
① ⑵に該当する種別等変更の届出受理後、種別等変更が実施されるまでの間に、当該事業者に対して、一般タク
シー車両に係る運転者の確保状況及び実働率を調査することとする。
② 当該調査を実施した結果、一般タクシー車両に係る運転者の確保状況又は実働率が次の基準を下回る場合には、
種別等変更が実施されるまでの間に当該事業者に対して、当該種別等変更の届出に基づく種別等変更の実施を当
面見合わせるよう運輸支局長が文書により指導する。(種別等変更見合わせ勧告)
ア.一般タクシー車両に係る運転者の確保状況について、1両当たり1.5人以上であること。ただし、地域の標
準的な運転者数など実情を踏まえて、関東運輸局長が当該地域における1両当たりの運転者数を公示した場合
には、その人数以上であること。
イ.一般タクシー車両に係る実働率について、80%以上であること。ただし、地域の標準的な実働率など実情を
踏まえて、関東運輸局長が当該地域における実働率を公示した場合には、その率以上であること。
③ 当該種別等変更の届出による種別等変更が実施された場合には、当該種別等変更を実施しなかった場合の事業
計画への変更の手続を行うよう運輸支局長が文書により指導する。(当該種別等変更を実施しなかった場合の事
業計画への変更の勧告)
Ⅳ.特定地域における減車実施事業者に対する監査の特例
減車により、営業区域ごとの一般タクシー車両の合計数が、Ⅱ.2.の基準車両数を関東運輸局長が公示する基準以上
下回っている一般乗用旅客自動車運送事業者(Ⅲ.1.⑴②による引き上げ前の最低車両数基準を下回っているものを除
く。)については、「旅客自動車運送事業の監査方針の細部取扱いについて(平成21年9月30日付け公示)」の記1⑵⑱、
⑶⑪及び⑷の規定にかかわらず、原則として、巡回監査、呼び出し監査及び呼び出し指導の対象としないものとする。
なお、事業再構築特例公示に基づく休車による供給輸送力減少については、基準車両数からの減少として取り扱わな
いものとする。
附 則(平成22年1月27日一部改正)
1.本公示は、平成22年1月27日から適用する。
附 則(平成22年12月21日一部改正)
1.改正後の公示は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月12日一部改正)
1.改正後の公示は、平成23年4月12日から適用する。

130
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
運転者の確保状況及び実働率にかかる地域の標準的な基準について
「特定地域の指定及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置の
実施について(平成21年9月30日公示)」中運転者の確保状況及び実働率の基準を下記のとおり定めたので公示する。
平成21年9月30日
関東運輸局長 神 谷 俊 広
記
1.運転者の確保状況
各事業者の現状、増車後の運転者数及び実働率並びに勤務状況の計画に基づき個別に判断することとし、標準的な算
定方法は次のとおりとする。
1日当たり所定労働時間 × 週当たり営業日数 × 車両における勤務形態 ÷ 週当たり所定労働時間
= 1両当たり必要人員(ただし1人以上)
2.実働率
実働率については、申請事業者の申請前12ヶ月の実働率の平均が、各交通圏毎に直近年度の実働率を下回らないもの
であることとし、各交通圏の直近年度の実働率については別表のとおりとする。
附 則
本公示は、平成21年10月1日以降に処分をするものから適用する。
附 則(平成22年10月1日一部改正)
本公示は、平成22年10月1日以降適用する。
附 則(平成23年4月12日一部改正)
本公示は、平成23年4月12日以降適用する。
附 則(平成23年7月8日一部改正)
本公示は、平成23年7月8日以降適用する。
別 表
都 県 交 通 圏 実働率
東 京
特別区・武三交通圏 84.8%北多摩交通圏 85.2%南多摩交通圏 90.3%西多摩交通圏 88.3%大島 53.6%新島 50.9%神津島 13.4%三宅島 50.4%八丈島 72.4%父島 38.6%
神奈川
京浜交通圏 87.2%県央交通圏 92.6%湘南交通圏 84.2%小田原交通圏 81.8%
千 葉
京葉交通圏 85.0%東葛交通圏 80.4%千葉交通圏 73.3%北総交通圏 77.2%東総交通圏 72.0%山武・東金交通圏 68.2%市原交通圏 74.2%東海交通圏 73.3%南房交通圏 70.4%
都 県 交 通 圏 実働率
埼 玉
県南中央交通圏 80.6%県南東部交通圏 75.2%県南西部交通圏 83.0%県北交通圏 77.5%秩父交通圏 63.1%
群 馬
東毛交通圏 72.3%沼田・利根交通圏 63.0%渋川・吾妻交通圏 65.1%群馬県及び埼玉県中・西毛交通圏 71.2%
茨 城
県北交通圏 64.9%水戸県央交通圏 71.5%鹿行交通圏 65.8%県南交通圏 69.5%県西交通圏 65.0%
栃 木
宇都宮交通圏 72.6%県南交通圏 75.5%塩那交通圏 68.8%芳賀・真岡交通圏 67.3%日光交通圏 61.7%
山 梨
甲府交通圏 87.4%東八・東山交通圏 75.5%峡西交通圏 63.5%峡北交通圏 72.8%峡南交通圏 61.1%東部・富士北麓交通圏 71.1%

131
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」の細部取扱いに
ついて
平成13年11月22日
関東運輸局自動車第一部長
平成13年11月22日付け公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の
審査基準について」の細部取扱いは下記による。
記
2.営業所
⑵について
・自己所有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用
権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められ
る場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出
を求めないこととする。
⑶について
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については、添付、提示又は写しの提出
を求めないこととする。
3.事業用自動車
・リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の写しの添付をも
って、使用権原を有するものとする。
・営業区域を遵守した適切な営業が確保されるよう、関東運輸局各運輸支局ごとに定めた「ハイヤー・タクシー車両
の表示等に関する取扱い」の規定により車両に営業区域等の表示をさせることとする。
4.最低車両数
⑴について
・10両若しくは5両の最低車両数については、通常のタクシー・ハイヤー事業を実施する上で適切と認められる事業
規模の基準であることから、当該最低車両数の算定においては、一般の需要に応じることができない車椅子専用車
両等は含めないこととする。
・別途定める地域に限定した運送を行う場合の最低車両数については、別途定めるところによるものとする。
5.自動車車庫
⑴について
・1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、適切な運行
管理が行われないおそれが高いことから認めないこととする。
・運行管理をはじめとする管理については、運行管理のほか、事業用自動車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等
の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断することとする。
⑷について
・2.⑵に同じ。
⑸について
・2.⑶に同じ。
⑺について
・道路幅員証明書の添付をもって確認することとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合
は、この限りでない。

132
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
6.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
⑷について
・2.⑵に同じ。
⑸について
・2.⑶に同じ。
7.管理運営体制
⑴について
・専従する役員のうち1名は、10.⑴の法令試験に合格した者(10.⑴ただし書きにおいて法令試験を省略できる場合
を除く。)であることとする。
⑵について
・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の9に規定する要件を満たす管理計画を有するも
のとする。
・申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するか否かについては、選任を予定する運行管理者の職務経
歴書等の添付をもって確認することとする。
⑶について
・複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化
されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。
⑷について
・常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。
・原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。
⑺について
・別に定める基準を満たす指導を行う体制を有するものとする。
⑼について
・グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管
理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)5ー3②に規定される要件を満たす計画を有する
ものとする。
⑽について
・旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより、苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。
9.資金計画
⑴〜⑵について
・道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とする。
・自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、預貯金以外の流動資産を含めることができることとする。
・預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の添付をもって確認するものとする。
・預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等の添付をもって確認するものとする。
・その他道路運送法施行規則第6条第1項第6号から第9号に規定する添付書類を基本とし審査する。
10.法令遵守
⑴について
・必要な法令の知識については、専従の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格することをもって、これを有
するものとする。ただし、患者等の輸送サービスに限定する事業を行う場合にあっては、これを省略することがで
きる。なお、法令試験を省略して許可となった者が一般タクシー事業を行うために条件解除を行う場合にあっては
法令試験に合格することを要する。
⑵について
・「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、

133
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の添付を求め、確認することとする。
⑶について
・「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った者に対して、道路運送法、貨物
自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき
行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)を起算日として、これを行うものと
する。
11.損害賠償能力
・契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを
証する書類の添付を求め、確認するものとする。
12.適用
⑴について
・いわゆる車載自動車による旅客及び貨物の運送の取扱いについては、平成16年3月2日付け国自旅第211号、国自
貨第142号に定めるところによるものとする。
14.挙証等
上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の添付又は提出を求めることとする。
附 則(平成16年3月31日一部改正)
本取扱いは、平成16年4月1日以降に処分を行う事案について適用する。
附 則(平成16年7月22日一部改正)
本取扱いは、平成16年8月1日以降に申請の処分を行う事案について適用する。
附 則(平成17年5月13日一部改正)
1.本取扱いは、平成17年6月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成19年7月30日一部改正)
1.本取扱いは、平成19年9月10日以降受付ける申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成20年6月30日一部改正)
1.本取扱いは、平成20年7月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成21年9月30日一部改正)
本取扱いは、平成21年10月1日以降受付ける申請について適用する。

134
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
項 目 所要資金額 事業開始当初に要する資金 備 考
イ 車両費(取得価格(含未払金))
(分割の場合頭金及び2月分の賃借料。ただし、一括払いの場合左欄と同額)
(1年分のリース料) (2月分のリース料)
ロ 土地費(取得価格(含未払金))
(分割の場合頭金及び2月分の賃借料。ただし、一括払いの場合左欄と同額)
(1年分の賃借料) (2月分の賃借料)
ハ 建物費(取得価格(含未払金))
(分割の場合頭金及び2月分の賃借料。ただし、一括払いの場合左欄と同額)
(1年分の賃借料) (2月分の賃借料)
ニ 機械器具及 び什器備品 (取得価格(含未払金)) (左欄と同額)
ホ 運転資金
・運送費
人件費 (2月分)
燃料油脂費 (2月分)
修繕費 (2月分)
その他経費 (2月分)
・管理経費
人件費 (2月分)
その他経費 (2月分)
計 (左欄と同額)
ヘ 保険料等
自賠責保険料 (1年分)
任意保険料 (1年分)
自動車重量税 (1年分)
自動車税 (1年分)
自動車取得税 (全額)
登録免許税 (全額)
計 (左欄と同額)
ト その他創業費等 (全額) (左欄と同額)
合 計
50%相当額
自己資金額
別添様式
1.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
※備考欄には、内訳等を適宜記載する。

135
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
2.資金の調達方法
⑴ 法人の場合
項 目 既存法人 設立法人
資 本 金
剰 余 金 等
増資資本金
合 計
出資者名 出資金額
項 目 申請事業充当額
現金預金
その他流動資産
調達資金合計(自己資金額)
⑵ 個人の場合
金融機関名額 預貯金等の種類 預貯金等の発行番号 申請日現在預貯金額
合 計(自己資金額)

136
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等の審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等について、事案の迅速かつ適
切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。
平成14年1月25日
関 東 運 輸 局 長 上 子 道 雄
東京陸運支局長 向 良 一
神奈川陸運支局長 瀬 谷 憲 雄
埼玉陸運支局長 冨 田 征 弘
群馬陸運支局長 瀬 下 幸 夫
千葉陸運支局長 小 林 一 雄
茨城陸運支局長 会 田 幸 治
栃木陸運支局長 嵯 峨 康 志
山梨陸運支局長 佐 藤 市 夫
記
1.事業計画の変更の認可(道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第15条第1項)
⑴ 平成13年11月22日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の
審査基準について」(以下「許可基準」という。)の1.〜9.・11.〜13.(12.⑸を除く。)の定めるところに準じて審査
する。
ただし、福祉輸送サービス事業に限定する事業において、都県の境界に接する市町村(東京都特別区または政令指
定都市にあっては区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要
因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接する市町村(東京都特別区又は政令
指定都市にあっては区をいう。以下「隣接市町村」という。)であって、隣接市町村の長、学校、病院、福祉施設等
の施設管理者等から、申請者に対し、隣接市町村の地域を発地又は着地とする要介護者の輸送(既存の営業区域が発
地又は着地となる場合を除く。)について文書による要請があり、申請者が事業許可取得後3年以上経過している場
合には、隣接市町村を含む区域(ただし、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村の区域
が変更された場合は、従前の区域。)を営業区域とすることができる。(隣接市町村を含む区域を設定した場合、営業
所は隣接市町村の区域を除く営業区域内にあることを要するものとする。)
なお、隣接市町村を営業区域とする事業計画の変更の認可に当たっては、「隣接市町村の区域に係る輸送は、隣接
市町村に接する都県の境界に接する市町村に所在する営業所において運送の引受けを行うものに限る。」との条件及
び2年間の期限を付すものとする。
⑵ 事業規模の拡大となる申請については、申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する
常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以
下「申請者等」という。)が、以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)
等の違反により申請日前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁
止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因
となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含
む。)ではないこと。
ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以上の処分であって、以下に掲げるもの
を除く。
イ 運転者の道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による処分(関東運輸局長が定める処分基準の初犯又は
初回欄の適用がある場合に限る。)

137
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ロ 申請日前3ケ月間及び申請日以降に関東運輸局長が定める処分基準において20日車未満の自動車等の使用停止
処分を行うべきものとされている法令違反に係るもの(処分日車数が20日車未満に軽減された場合を含み、加重
により20日車以上となった場合を除く。)
② 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ケ月間及び申請日以降
に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分
を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に
当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以上の処分であって、以下に掲げるもの
を除く。
イ 運転者の道路交通法の違反による処分(関東運輸局長が定める処分基準の初犯又は初回欄の適用がある場合に
限る。)
ロ 申請日前6ケ月間及び申請日以降に関東運輸局長が定める処分基準において20日車未満の自動車等の使用停止
処分を行うべきものとされている法令違反に係るもの(処分日車数が20日車未満に軽減された場合を含み、加重
により20日車以上となった場合を除く。)
③ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に
190日車を超える輸送施設の使用停止命令以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた
者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分
を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以上の処分であって、以下に掲げるもの
を除く。
イ 運転者の道路交通法の違反による処分(関東運輸局長が定める処分基準の初犯又は初回欄の適用がある場合に
限る。)
ロ 申請日前1年間及び申請日以降に関東運輸局長が定める処分基準において20日車未満の自動車等の使用停止処
分を行うべきものとされている法令違反に係るもの(処分日車数が20日車未満に軽減された場合を含み、加重に
より20日車以上となった場合を除く。)
④ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便
を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に
当該命令された事項が改善されていること。
⑤ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、事業の改善の警告を受けた場合
にあっては、申請日前に当該警告された事項が改善されていること。
⑥ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
⑦ 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令
第33号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
⑧ 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運
転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
⑨ 申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項
に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。
⑩ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日
以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場
合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業
務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
2. 事業の譲渡譲受の認可(法第36条第1項)

138
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑴ 事業の全部を譲渡譲受の対象とするものであること。ただし、「タクシー事業に係る事業の分割譲渡の取扱いにつ
いて」(平成10年12月17日付け自旅第198号)において認められている場合において分割譲渡が行われる場合は、この
限りでない。
⑵ 事業を譲り受けようとする者について、許可基準の1.〜13.(譲受人が既存事業者の場合にあっては許可基準1.〜9.
及び11.〜13.並びに上記1.⑵)の定めるところに準じて審査する。ただし、許可基準の13.⑴ただし書きについては
適用しない。
3.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は第37条第1項)
⑴ 合併若しくは分割により事業を承継する法人又は相続人について、許可基準の1.〜13.(合併又は分割後に存続す
る事業者若しくは相続人が既存事業者の場合にあっては許可基準1.〜9.及び11.〜13.並びに上記1.⑵)の定める
ところに準じて審査する。ただし、許可基準の13.⑴ただし書きについては適用しない。
⑵ 分割の認可については、分割後において存続する事業者が、許可基準の4.の基準を満たさない申請については、
認可しないこととする。
⑶ 分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条及び会社の分割に伴う労
働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等が行われてい
るものであること。
⑷ 事業の一部の分割の認可については、設立会社等が次のいずれかに該当するものであること。
① 既存のタクシー事業者(1人1車制個人タクシー事業者を除く。)
② 分割会社の50%を超える出資による子会社
4.許可又は認可に付した条件の変更等(法第86条第1項)
⑴ 許可又は上記1.〜3.の認可に付した条件又は期限について、変更若しくは解除又は期限の延長を行う場合には、
許可基準及び上記1.〜3.の定めるところにより審査する。
⑵ 許可基準の12.(⑸を除く。)に基づき付した業務の範囲を一定の事業に限定する旨の条件の解除は、緊急調整地域
に指定された地域では行わない。
5.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成9年4月3日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の事業計画の
変更に関する審査基準について」及び昭和61年2月1日付け公示「道路運送法施行規則第15条第1項第3号に基づく
一般乗用旅客自動車運送事業の区域の指定について」は、平成14年1月31日限り廃止する。
3.1.⑵①、②及び③のタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー
業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。
4.事案の処理に関しては本審査基準によるほか、細部取扱い通達の定めによるものとする。
附 則(平成14年7月1日 一部改正)
1.本公示は、平成14年7月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成14年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成16年7月22日 一部改正)
本公示は、平成16年8月1日以降に申請の処分を行う事案について適用する。
附 則(平成21年9月30日 一部改正)
本公示は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。

139
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
附 則(平成21年11月30日 一部改正)
本公示は、平成21年12月1日以降に処分するものから適用する。
「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等の審査基準について」の細部取
扱いについて
平成14年1月25日
関東運輸局自動車第一部長
平成14年1月25日付け公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申
請等の審査基準について」の細部取扱いは下記による。
記
1.事業計画の変更の認可等
⑴〜⑵について
① 許可基準の1.〜9.・11.〜13.の定めるところに準じる審査は、以下のとおり行うものとする。
⒜ 営業区域の拡大に係る申請については、事業の許可申請と同等の申請とみなし、許可基準の1.〜9.・11.・12.
について十分な審査を行う。
⒝ 自動車車庫の新設又は位置の変更に係る申請においては許可基準の5.・6.⑴について、収容能力の拡大に係
る申請においては許可基準の5.について、また、収容能力の縮小に係る申請においては許可基準の4.・5.に
ついて、それぞれ十分な審査を行う。
⒞ 事業用自動車の数の変更(自動車車庫の収容能力の増加を要するものに限る。)に係る申請においては許可基
準3.・11.について十分な審査を行う。
⒟ 営業区域の廃止に係る申請については、廃止しようとする営業区域内のすべての営業所及び自動車車庫の廃止
の手続き並びに当該営業所に配置する事業用自動車の数の変更(すべての減車)の手続きを伴うものであること
を確認することとする。
② 事業規模の拡大となる申請は、営業区域の拡大並びに自動車車庫の新設、位置の変更(収容能力の拡大を伴うも
のに限る。)及び収容能力の拡大並びに自動車車庫の収容能力の増加を要する事業用自動車の数の変更に係るもの
とする。
「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った者に対して、道路運送法、貨
物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づ
き行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)を起算日として、これを行うもの
とする。
③ 経過措置として、平成14年1月31日現在で一般乗用旅客自動車運送事業を行っている者(以下「既存事業者」と
いう。)に係る許可基準の4.・5.⑴・6.⑴・7.⑵・11.の基準については、以下のとおり取り扱うものとする。
⒜ 同日現在で基準を満たしていなかった営業所(その後基準を満たしたものを除く。)については、許可基準の4.
は適用しない。
⒝ 同日現在で基準を満たしていなかった自動車車庫(その後基準を満たしたものを除く。)については、許可基
準の5.⑴は適用しない。
⒞ 同日現在で基準を満たしていなかった休憩、仮眠又は睡眠のための施設(その後基準を満たしたものを除く。)
については、許可基準の6.⑴は適用しない。
⒟ 許可基準の7.⑵の「法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管
理者として選任する場合」には、「道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(平成
12年5月26日法律第86号)附則第6条の規定に基づき改正前の道路運送法第23条第1項の規定の例により運行管

140
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
理者を選任する場合」を含むものとする。
⒠ 許可基準の11.については、同日現在で基準を満たしていなかった者(その後基準を満たした者を除く。)の拡
大前の営業区域内の車両に限り、平成16年9月30日までは適用しない。
2.事業の譲渡譲受の認可
⑵について
・上記1.の③に規定する経過措置(⒜を除く。)を準用するものとする。
3.合併、分割又は相続の認可
⑴について
・上記1.の③に規定する経過措置(⒜を除く。)を準用するものとする。
⑶について
・労働契約の承継等については、当該法律に基づく客観的な資料の提出を求めることとする。
4.許可又は認可に付した条件の変更等
⑴について
・許可に際しては、「許可日から6月以内に事業開始すること。」の条件を付すものとする。
・営業区域の拡大の認可に際しては、「認可日から6月以内に当該営業区域内において事業を開始すること。」の条件
を付すものとする。
・患者等の輸送サービスに限定する事業を行う者が、一般タクシー事業を行うにあたって、同限定事業に用いている
セダン型等の一般の需要に応じることが適している車両を、一般タクシー事業の車両として使用する場合は、最低
車両数の算定対象とする。
⑵について
・本規定は、緊急調整地域に指定された地域において、これらの条件の解除を行えばタクシーの数が増加することと
なることから、施行規則第7条第3号の趣旨を維持するために設けることとしたものである。
5.挙証等
上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の添付又は提出を求めることとする。
附 則(平成16年3月31日 一部改正)
1.本取扱いは、平成16年4月1日以降受付けた申請について適用する。
2.平成16年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成16年7月22日 一部改正)
本取扱いは、平成16年8月1日以降に申請の処分を行う事案について適用する。
附 則(平成18年9月27日 一部改正)
本取扱いは、平成18年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
附 則(平成20年6月30日 一部改正)
1.本取扱いは、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出

141
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
の処理方針について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届
出について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その処理方針を下記のとおり定めたので公示する。
平成14年1月25日
関 東 運 輸 局 長 上 子 道 雄
東京陸運支局長 向 良 一
神奈川陸運支局長 瀬 谷 憲 雄
埼玉陸運支局長 冨 田 征 弘
群馬陸運支局長 瀬 下 幸 夫
千葉陸運支局長 小 林 一 雄
茨城陸運支局長 会 田 幸 治
栃木陸運支局長 嵯 峨 康 志
山梨陸運支局長 佐 藤 市 夫
記
1.事前届出書の提出時期及び提出先
変更実施予定日の7日前までに当該変更に係る営業所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出すること。
なお、当該変更に係る営業所の所在地を管轄する運輸支局長が2以上の場合には、いずれかの運輸支局長を経由して
関東運輸局長あて提出すること。
2.事前届出書の様式及び添付書類等
⑴ 事前届出書の様式は、道路運送法施行規則第4条第8項第3号に基づき、事業計画にタクシー及びハイヤーの別ご
との数を記載させる地域として、平成14年1月25日付け公示において関東運輸局長が指定した地域(以下「タクシー・
ハイヤー指定地域」という。)にあっては別紙1、その他の地域にあっては別紙2によるものとする。
⑵ 事業用自動車の合計数が増加となる届出(以下「増車の届出」という。)の事前届出書には、次に掲げる書面を添
付すること。
① 既に認可を受けた自動車車庫の位置、収容能力(面積及び収容余力(余裕面積))を示す書面
② 営業所における配置車両数が増加する場合は、当該増加後に必要となる自動車車庫の面積を示す書面
③ 自動車車庫の面積に余裕が少ない場合は車両の収容状況を示す平面図等の書面
④ 当該届出が増車の届けである場合には、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の
者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告
示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があることを証する書面
(契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書等)
3.増車の届出及び受理等
⑴ 増車の届出が4.⑴・⑵のいずれかに該当することとなる場合には、道路運送法第31条第1号に基づく事業改善命
令の対象となるので、必要な手続きを行った上で届出を行うこと。
⑵ 届出に係る営業区域が道路運送法第8条第1項の規定による緊急調整地域に指定されている場合には、当該営業区
域内の増車の届出(タクシー・ハイヤー指定地域にあっては増車の届出及びタクシーの合計数の増加の届出)は受理
することができない。ただし、道路運送法施行規則第7条ただし書きに規定する事業用自動車に係る増車の届出につ
いては、この限りでない。
4.事業の改善命令等
届出受理後、次の⑴・⑵に該当する場合には、事業計画の変更命令を発動する。

142
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑴ 増車の届出であって、届出者が当該届出に係る営業区域内における一般乗用旅客自動車運送事業について道路運送
法、タクシー業務適正化特別措置法及びこれらに基づく命令の違反により輸送施設の使用停止命令以上の処分を受け、
増車実施予定日において当該処分期間が終了していないとき。
⑵ 営業所ごとに、配置車両数(事業用自動車及び道路運送法第78条第3号に基づく自家用自動車の合計数)によって
義務づけられる人数以上の有資格の運行管理者が選任されていないと認められるとき。
5.福祉輸送サービスに限る事業を行う者の取扱い
福祉輸送サービスに限る事業(以下「限定事業」という。)を行う者が、一般の需要に応じるために事業用自動車(道
路運送法施行規則第1条第2項第1号の自動車をいう。以下「一般自動車」という。)を増車しようとする届出を行う
場合については、次のとおり取扱うものとする。
なお、当該増車が自動車車庫の収容能力の増加を要するものである場合には、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人
1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等の審査基準について」の4.許可又は認可に付した条件の変更等(法
第86条第1項)に定めるところによるものとする。
⑴ 当該限定事業者の許可に付されている業務の範囲を限定する旨の条件の解除等
① 届出書に、業務の範囲を限定する旨の条件の解除を申請するものであることを明記すること。
② 増車しようとする一般自動車の数(限定事業に用いているセダン型等の一般の需要に応じることが適している車
両を、一般タクシー事業の車両として使用する場合は、当該車両数を含む。以下同じ。)が、当該増車に係る営業
区域(一般タクシーの営業区域。以下同じ。)の最低車両数以上である場合に限り、当該条件の解除を行うものと
する。
③ ②の条件の解除を行う場合にあっては、当該事業者の営業区域を一般タクシーの営業区域に変更することとする。
この場合において、限定事業に用いる事業用自動車については、引き続き、業務の範囲を限定することとし、営業
区域については当該事業者の従前の営業区域の範囲を認めることとする。
④ ②及び③の場合については、関東運輸局長が書面によりその旨を明らかにすることとする。
⑵ 当該増車しようとする一般自動車の数が最低車両数未満である場合には、許可に付されている業務の範囲を限定す
る旨の条件の解除を受けられないこととなるため、当該条件に違反することとなり、道路運送法第40条の規定に基づ
く許可の取消処分等の対象となるため、最低車両数以上の車両数で届出を行うこと。
附 則
本公示は、平成14年2月1日以降受け付ける申請について適用する。
附 則(平成16年3月31日 一部改正)
本公示は、平成16年4月1日以降受け付ける申請について適用する。
附 則(平成17年5月13日 一部改正)
本公示は、平成17年6月1日以降受け付ける申請について適用する。
平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成18年9月27日 一部改正)
本公示は、平成18年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
附 則(平成20年1月21日 一部改正)
本公示は、平成20年1月22日以降受け付ける申請について適用する。
附 則(平成20年3月27日 一部改正)
本公示は、平成20年5月1日以降受け付ける申請について適用する。

143
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
別 紙1
年 月 日
関 東 運 輸 局 長 □□□□殿
関東運輸局 ○○運輸支局長 ◇◇◇◇殿
住 所
氏名又は名称
代 表 者 名
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出書
(道路運送法施行規則第4条第8項第3号に基づく関東運輸局長指定地域)
道路運送法第15条第3項及び道路運送法施行規則第15条第2項で準用する同規則第14条の規定に基づき、一般乗用旅客
自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)を次のとおり変更するので届出いたします。
氏名又は名称及び 住所並びに代表者氏名
変更しようとする事項 ・営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びに種別ごとの数並びにタクシー及びハ イヤーの別ごとの数
実 施 予 定 日 年 月 日
そ の 他
新旧 新 旧
種別 一般車両 福祉車両
計
一般車両 福祉車両
計タクシー
ハイヤー
内 訳タクシー
ハイヤー
内 訳
営業所名
車椅子
寝台専用
車椅子・
寝台兼用車
回転シート
セダン型
車椅子
寝台専用
車椅子・
寝台兼用車
回転シート
セダン型
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
変更に係る新旧対照表
タクシー・ハイヤー等 の別
※1 種別は、一般車両(一般の需要に応じることができる事業用自動車)及び福祉車両(一般車両以外の事業用自動車)の別とする。※2 一般車両のうち貨客車については、車両数を括弧書きとし内数とする。※3 福祉車両のうち軽自動車については、車両数を括弧書きとし内数とする。

144
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
別 紙2
年 月 日
関 東 運 輸 局 長 □□□□殿
関東運輸局 ○○運輸支局長 ◇◇◇◇殿
住 所
氏名又は名称
代 表 者 名
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出書
(道路運送法施行規則第4条第8項第3号に基づく関東運輸局長指定地域以外の地域)
道路運送法第15条第3項及び道路運送法施行規則第15条第2項で準用する同規則第14条の規定に基づき、一般乗用旅客
自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)を次のとおり変更するので届出いたします。
氏名又は名称及び 住所並びに代表者氏名
変更しようとする事項 ・営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びに種別ごとの数
実 施 予 定 日 年 月 日
そ の 他
変更に係る新旧対照表
※1 種別は、一般車両(一般の需要に応じることができる事業用自動車)及び福祉車両(一般車両以外の事業用自動車)の別とする。※2 一般車両のうち貨客車については、車両数を括弧書きとし内数とする。※3 福祉車両のうち軽自動車については、車両数を括弧書きとし内数とする。
新旧 新 旧
種別
一般車両
福祉車両
計 一般車両
福祉車両
計
内 訳 内 訳
営業所名
車椅子
寝台専用
車椅子・
寝台兼用車
回転シート
セダン型
車椅子
寝台専用
車椅子・
寝台兼用車
回転シート
セダン型
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

145
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請等に係る法令試験の実施について
「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」(平成13年11
月22日付け公示)及び「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等の審査
基準について」(平成14年1月25日付け公示)に規定する法令試験に関して、その実施方法を下記のとおり定めたので公
示する。
平成14年2月1日
関東運輸局長 上 子 道 雄
記
1.試験の実施時期等
⑴ 許可申請書等を受理した日以降、適宜実施する。なお、試験の実施日時、場所については、実施予定日の10日前ま
でに申請者あてに通知する。
⑵ 再試験の実施にあたっては、⑴に準じて再度通知する。
2.受験者の確認等
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請者本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する
事業に専従する役員1名を受験者とする。)であることが確認できる運転免許証等を提示すること。
3.出題範囲及び設問形式等
⑴ 出題範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
① 道路運送法
② 道路運送法施行令
③ 道路運送法施行規則
④ 旅客自動車運送事業運輸規則
⑤ 旅客自動車運送事業等報告規則
⑥ タクシー業務適正化特別措置法(特別区・武三交通圏、神奈川県京浜交通圏、千葉県京葉交通圏、東葛交通圏、
千葉交通圏及び埼玉県県南中央交通圏に限る。)
⑦ タクシー業務適正化特別措置法施行規則(特別区・武三交通圏、神奈川県京浜交通圏、千葉県京葉交通圏、東葛
交通圏、千葉交通圏及び埼玉県県南中央交通圏に限る。)
⑧ 道路運送車両法
⑨ 道路運送車両法施行規則
⑩ 自動車点検基準
⑪ 自動車事故報告規則
⑫ その他一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
⑵ 設問の方式
○×方式及び語群選択方式とする。
⑶ 出題数
30問
⑷ 合格基準
出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合には、再試験を実施する。
⑸ 試験時間
50分とする。

146
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
4.その他
⑴ 自動車六法等(情報通信機器を除く。)の持ち込みを可とする。
⑵ 試験当日、受験者は筆記用具の他、本人であることが確認できる運転免許証、パスポート等を持参すること。
附 則
本公示は、平成14年2月1日以降受け付ける申請について適用する。
附 則(平成20年6月13日 一部改正)
本公示は、平成20年6月16日以降受け付ける申請について適用する。
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準につ
いて
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業(以下「個人タクシー事業」という。)に限る。)の許可及
び譲渡譲受認可(相続認可を含む。)申請について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとお
り定めたので公示する。
平成13年12月27日
関東運輸局長 上 子 道 雄
記
Ⅰ 許可(道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第4条第1項)
1.営業区域
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域は別表1のとおり
とする。
2.年 令
申請日現在で65才未満であること。
3.運転経歴等
⑴ 有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る。以下同じ。)を有していること。
⑵ 申請日現在における別表2の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める国内の自動車運転経歴、タクシー又
はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。
4.法令遵守状況
⑴ 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けた
ことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
① 法又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制
限(禁止)の処分
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分
③ タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止
処分
④ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業
の廃止命令の処分
⑤ 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法
(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀
剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これらに準ずる法令の違反による処分
⑥ 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づ

147
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
く輸送施設の使用停止以上の処分
⑵ 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反による処分(同法の規定による反則金の納付を命ぜられ
た場合又は反則点を付された場合を含む。)を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、反則点
1点を付された場合(併せて同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は反則金の納付のみを
命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていないものとみなす。
⑶ ⑴又は⑵の違反により現に公訴を提起されていないこと。
5.資金計画
⑴ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の①
〜④の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
① 設備資金(③を除く。)
80万円以上
ただし、80万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかである場合は、当該所要額とする。
② 運転資金
80万円以上
③ 自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金
④ 保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに、旅客自動車運送事業者が事業
用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置
の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に係る保険
料の年額
⑵ 所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
6.営業所
個人タクシー事業の営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
⑴ 申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。
⑵ 申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、居住する住居に永続性が認め
られるものであること。
⑶ 使用権原を有するものであること。
7.事業用自動車
使用権原を有するものであること。
8.自動車車庫
⑴ 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
⑵ 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
⑶ 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
⑷ 土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
⑸ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農
地法(昭和27年法律第229号)等の関係法令に抵触しないものであること。
⑹ 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36
年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る
使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令
に抵触しないものであること。
⑺ 10.に定める法令及び地理の試験合格後の関東運輸局長が指定する日までに確保できるものであること。
9.健康状態及び運転に関する適性

148
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑴ 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営
業に支障がない健康状態にあること。
⑵ 独立行政法人自動車事故対策機構等において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない
状態にあること。
10.法令及び地理に関する知識
関東運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。
ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用
されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除する。
なお、法令及び地理の試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする。
11.その他
申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。
12.申請の時期等
⑴ 申請の受付
毎年9月とする。ただし、法第8条に基づく緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は
行わない。
⑵ 法令及び地理の試験の実施
毎年11月に実施する。
⑶ 申請内容の確認
申請内容の確認のため、⑵の試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施する。
Ⅱ 許可等に付す期限及び条件(法第86条第1項)
1.許可等に付す期限
許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可(以下「許可等」という。)に当たっては、当該許可又は認可の日から概
ね3年間の期限を付すこととする。
2.許可等に付す条件
許可等に当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。
⑴ 引き続き有効な第二種運転免許を有するものであること。なお、当該第二種運転免許の取り消し処分を受けた場
合には許可を取り消す。
⑵ 使用する事業用自動車は1両であり、他人に当該事業用自動車を営業のために運転させてはならない。
⑶ 患者輸送等の特殊な需要に特化した運送のみを行うものでないこと。
⑷ 事業用自動車の両側面に見やすいように「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」と表示すること。
⑸ 月に2日以上の定期休日を定めること。
⑹ 関東運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別の事情がない限りこれに応じること。
⑺ 営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、1年間は保存すること。
⑻ 氏名等の記載とともに写真を貼付した事業者乗務証を車内に掲示すること。
⑼ 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持
等取締法のいずれかに抵触する行為により処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがある。
⑽ 年齢が満65才に達した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第38条第2項に定め
るところにより同項の認定を受けた高齢者に対する適性診断を受けること。また、公的医療機関等の医療提供施設
において健康診断を毎年受診すること。
⑾ 行政処分基準(「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21年9月30日付け関
自監旅第219号、関自旅二第1116号、関自保第230号)をいう。)において許可を取り消すこととされている事項に
該当した場合には、許可を取り消す。

149
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑿ 申請書、添付書類及び陳述の内容が事実と異なることが判明した場合には、許可を取り消すことがある。
⒀ 許可等の期限更新時において、年齢が満75才に達する日以降の期限は付さない。
⒁ 許可等の日から4ヶ月以内に事業を開始すること。
Ⅲ 譲渡譲受及び相続の認可(法第36条第1項及び第37条第1項)
1.譲渡譲受の認可
⑴ 譲渡人の資格要件
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること。
① 年齢が65才以上75才未満であること。
② 年齢が65才未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者であること。
③ 年齢が65才未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者であること。
⑵ 譲受人の資格要件
Ⅰ.に定める基準を満たす者であること。
⑶ 申請の時期等
① 申請の受付
毎年5月、9月及び1月とする。
② 法令及び地理の試験の実施
毎年7月、11月及び3月に実施する。
③ 申請内容の確認
申請内容の確認は、②の試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施する。
2.相続の認可
⑴ 被相続人の死亡時における年齢が75才未満であること。
⑵ 相続人がⅠ.に定める基準を満たす者であること。
⑶ 申請の受付、法令及び地理の試験並びに処分は、随時行うこととする。ただし、申請が被相続人の死亡後60日以
内になされるものであること。
Ⅳ 挙証等
申請内容について、客観的な挙証等があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.平成9年5月15日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の経営免許及
び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」(以下「旧公示」という。)は、平成14年1月31日限り廃止する。
3.本公示Ⅰ.4.⑴③及び⑥のタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタク
シー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。
4.事案の処理に際しては本審査基準によるほか、別途公示する細部取扱いによるものとする。
5.経過措置
⑴ 平成14年2月1日以降2年間、本公示Ⅰ.別表2のC.2.規定については、「10年以上の自動車の運転を専ら職業
とした期間のうち、申請する営業区域における期間が5年以上、かつ、申請日以前3年以内に2年以上あること」
とすることができる。
⑵ 平成14年2月1日以降3年間、本公示Ⅰ.10.の規定中「10年以上タクシー・ハイヤー事業者」とあるのは「10年
以上同一のタクシー・ハイヤー事業者」とし、「申請日以前5年間無事故無違反」とあるのは「申請日以前3年間
無事故無違反」とすることができる。
⑶ 平成14年2月1日以降2年間、本公示Ⅲ.1.⑴①及びⅢ.2.⑴の規定中「75才未満」とあるのは「75才以下」とする。

150
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑷ 平成14年については、本公示Ⅲ.1.⑶①に「3月」を、②に「4月」を加え適用する。
附 則(平成14年1月31日一部改正)
本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
附 則(平成17年5月13日一部改正)
本公示は、平成17年6月1日以降に受付ける申請について適用する。
附 則(平成18年8月29日一部改正)
1.本公示は、平成18年9月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.本公示施行日以前の旧岩槻市における、本公示Ⅰ.3.⑵別表2各欄の運転経歴要件の申請する営業区域においての
運転経歴については、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請する場合、県南東部交通圏における運転経歴と
みなす。
また、本公示Ⅰ.10.に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日以前に県南東部交通圏において、
タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されていた期間とみなす。
3.経過措置
⑴ 本公示施行日以降から平成20年9月30日までの間に、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請しようとす
るものであって、本公示施行日以前に旧岩槻市における、本公示Ⅰ.3.⑵別表2各欄の運転経歴要件の申請する営
業区域においての運転経歴があるもので、本公示施行日以降も引き続きさいたま市岩槻区に運転経歴があるものは、
県南東部交通圏に運転経歴があるものとみなす。
また、本公示Ⅰ.10.に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日前に旧岩槻市において、タク
シー・ハイヤー事業者に運転者として雇用され、本公示施行日以降引き続き旧岩槻市において雇用されていたもの
が、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請しようとする場合、県南東部交通圏において雇用されていた期
間とみなす。
⑵ 本公示施行日以降から平成19年9月30日までの間に、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請しようとす
るものであって、本公示施行日以前から引き続きさいたま市岩槻区に居住し、かつ、申請日前継続して1年以上居
住しているものが、申請後において県南東部交通圏内に転居し、平成14年1月31日付けで公示した「一般乗用旅客
自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可申請、譲渡譲受及び相続認可申請に係る細部取扱
いについて」Ⅲ.1.Ⅲ.に規定する挙証資料等を、平成14年1月31日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1
人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に係る法令及び地理の試験の実施について」4.⑵に規定する挙証資
料の提出期限までに提出できる場合にあっては、申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているも
のとみなす。
附 則(平成19年3月22日一部改正)
本公示は、平成19年4月1日以降に受付ける申請について適用する。
附 則(平成21年9月30日一部改正)
本公示は、平成21年10月1日以降に受付ける申請について適用する。
附 則(平成22年3月23日一部改正)
本公示は、平成22年3月23日以降に受付ける申請について適用する。
附 則(平成23年2月3日一部改正)
本公示は、平成23年2月3日より適用する。
附 則(平成23年9月30日一部改正)
本公示は、平成23年10月1日以降に受付ける申請について適用する。
ただし、埼玉県県南中央交通圏については、平成23年10月11日以降に受付ける申請について適用する。

151
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
営業区域の名称 区 域
特別区・武三交通圏北 多 摩 交 通 圏
南 多 摩 交 通 圏京 浜 交 通 圏県 央 交 通 圏
県 南 中 央 交 通 圏県 南 東 部 交 通 圏
県 南 西 部 交 通 圏
千 葉 交 通 圏京 葉 交 通 圏東 葛 交 通 圏中・ 西 毛 交 通 圏
宇 都 宮 交 通 圏
東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市東京都立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市及び東久留米市東京都八王子市、日野市、多摩市、稲城市及び町田市神奈川県横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、相模原市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、厚木市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町及び愛甲郡愛川町、清川村埼玉県川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市及び北足立郡伊奈町埼玉県春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、加須市(ただし、平成22年3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町、大利根町の区域に限る。)、南埼玉郡宮代町、白岡町、及び北葛飾郡杉戸町、松伏町埼玉県川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町及び秩父郡東秩父村千葉県千葉市及び四街道市千葉県市川市、船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、八千代市及び浦安市千葉県松戸市、柏市、流山市、野田市及び我孫子市群馬県前橋市、高崎市、伊勢崎市、佐波郡玉村町、安中市、富岡市、藤岡市、北群馬郡吉岡町、榛東村、多野郡神流町、上野村、甘楽郡甘楽町、下仁田町、南牧村及び埼玉県児玉郡神川町栃木県宇都宮市、鹿沼市、下野市、河内郡上三川町、栃木市(ただし、平成23年10月1日に編入された旧上都賀郡西方町の区域に限る。)及び下都賀郡壬生町
申請時の年齢 運 転 経 歴 要 件
A.35才未満 1.申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
2.申請日以前10年間無事故無違反であること。
B.35才以上 40才未満
1.申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
2.1.の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。3.申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年
以上であること。4.申請日以前10年間無事故無違反である者については、40才以上65才未満の要件によることができるもの
とする。
C.40才以上 65才未満
1.申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
2.申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。
別 表1
別 表2
(適 用) 1)B.1.及びC.1.の「自動車の運転」に係る自動車については、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表
第一に規定する普通自動車(四輪以上の自動車に限る。)、小型自動車(四輪以上の自動車に限る。)及び軽自動車(民間患者輸送事業の用に供する自動車に限る。)とする。
2)B.3.及びC.2.の「タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること」については、当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き運行管理者又は整備管理者として選任された場合を含む。

152
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に係る法令及び地理の試験の実施につい
て
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業(以下「個人タクシー事業」という。)に限る。)の許可並
びに譲渡譲受又は相続の認可(以下「許可等」という。)申請者に対して実施する法令及び地理の試験(以下「試験」という。)
の実施方法等を下記のとおり定めたので公示する。
平成14年1月31日
関東運輸局長 上 子 道 雄
記
1.試験の実施時期
⑴ 許可申請の場合
原則として11月10日から11月17日までの間におけるいずれかの日に実施する。
⑵ 譲渡譲受認可申請の場合
① 初試験
原則として、1月に受付ける申請について3月10日から3月17日まで、5月に受付ける申請について7月10日か
ら7月17日まで、9月に受付ける申請について11月10日から11月17日までの間のいずれかの日に実施する。
② 再試験
原則として初試験の実施月の4ヶ月後とする。
⑶ 相続認可申請の場合
随時実施する。
2.試験回数
⑴ 許可申請
1回の申請について、1回(初試験のみ)とする。
⑵ 譲渡譲受及び相続認可申請
1回の申請について、初試験を実施し、不合格となった者に対しては再試験を実施する。
3.出題範囲及び設問形式等
次のとおりとする。
法令試験 地理試験
出題範囲
別表のとおり 申請する営業区域内の地名、道路、交差点、主要公共施設、河川、橋、公園、名所・旧跡等の名称及び場所、主要ターミナル等周辺の交通規制、その他個人タクシー事業の遂行に必要な地理に関する事項
設問方式○×方式及び語群選択方式 ○×方式及び選択肢方式(語群選択及び地図上の番号を選
択する方式)
出 題 数40問(ただし、タクシー業務適正化特別措置法の特定指定地域(以下「特定指定地域」という。)については、同法に関係する問題を5問付加し45問とする。)
30問
配 点 1問1点 1問1点
合格基準36点以上(ただし、特定指定地域に係る試験は41点以上とする。)
27点以上
試験時間 50分(ただし、特定指定地域に係る試験は60分とする。) 50分

153
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
4.試験終了後の取扱い
⑴ 試験結果の公表等
① 法令・地理試験の実施結果に基づき、試験実施月の翌月に次の事項を関東運輸局報に掲載するとともに、関東運
輸局及び関係運輸支局の掲示板に掲示する方法で公表する。
⑴ 申請者数
⑵ 合格者数
⑶ 法令試験、地理試験受験者のそれぞれの最高点、最低点及び平均点
② 試験問題は、試験終了後の持ち帰りを認め、これにより問題の公表とする。
⑵ 合格者の取扱い
合格者に対しては、⑴①の公表と同時に申請に係る挙証資料の提出期限又は提示等の日時を通知する。
⑶ 不合格者の取扱い
① 許可申請者の場合
却下処分とする。
② 譲渡譲受及び相続認可申請者の場合
初試験の者については、再試験の通知を行い、再試験の者については、却下処分とする。
5.その他
⑴ 試験の実施日時、場所については、事前に関東運輸局報に公示するとともに受験者あてに通知する。
⑵ 「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基
準について」(平成13年12月27日付け関自旅2第6490号)のⅠ.10.のただし書きに基づき地理試験の免除を申請する
者に対しては、⑴の通知の際にその旨を明記する。
⑶ 試験に欠席した者については、不合格とし却下処分とする。
⑷ 許可申請後、申請した営業区域が緊急調整地域に指定された場合には、試験は行わないこととし、却下処分とする。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降、管轄する陸運支局において受付ける申請について適用する。
2.経過措置
平成14年については、本公示1.⑵①に「3月に受付ける申請については、4月20日から4月30日までの間のいず
れかの日に実施する。」を加え適用する。
附 則(平成16年11月9日 一部改正)
1.本公示は、平成17年1月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
附 則(平成17年12月22日 一部改正)
1.本公示は、平成18年1月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
附 則(平成19年3月22日 一部改正)
1.本公示は、平成19年4月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
2.平成19年3月31日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成20年6月13日 一部改正)
1.本公示は、平成20年6月14日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
2.平成20年6月13日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。

154
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
出 題 範 囲
1.道路運送法関係
①道路運送法 ②道路運送法施行令 ③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則 ⑥一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款⑦一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)の許可等に付された期限の更新申請の審査及び取扱基準⑧一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について⑨一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について⑩タクシー・ハイヤー車両の表示に関する取扱通達の内容⑪一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)の休止及び廃止の取扱いについて(平成14年1月31日公示)⑫旅客自動車運送事業運輸規則第29条の規定に基づく地図の規格及び指定事項について(平成14年1月31日公示)⑬運転免許取消処分を受けた個人タクシー事業者の取扱い等について(平成14年4月26日付け関自旅2第29号)⑭タクシー業務適正化臨時措置法の施行について(「道路運送法に違反する運送の引受け又は継続の拒否要件」に限る。)
(東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域に限る。) (昭和45年10月29日付け70東陸自1旅2第7848号) 改正(昭和53年5月17日付け78東陸自1旅2第1314号) 改正(平成7年2月21日付け関自旅2第376号)
*⑥〜⑩までは、申請する営業区域において、申請月の前月末現在有効なものであって、個人タクシー事業に関するものに限る。再試験の者についても、再試験の者以外の者と同様の内容とする。
2―1.タクシー業務適正化特別措置法関係(申請に係る営業区域が同法に基づく特定指定地域の場合のみ出題)
①タクシー業務適正化特別措置法 ②タクシー業務適正化特別措置法施行令③タクシー業務適正化特別措置法施行規則④タクシー業務適正化特別措置法関係通達⑤タクシー乗り場及び乗車禁止地区に関する事項
2―2.タクシー業務適正化特別措置法関係(申請に係る営業区域が同法に基づく特定指定地域以外の指定地域の場合のみ出題)
①タクシー業務適正化特別措置法(第44条から第47条までに限る。)②タクシー業務適正化特別措置法施行規則(第28条から第38条までに限る。)
3.道路運送車両法関係
①道路運送車両法 ・第1条(この法律の目的) ・第11条(自動車登録番号標の封印等) ・第12条(変更登録) ・第13条(移転登録) ・第15条(永久抹消登録) ・第19条(自動車登録番号標等の表示の義務) ・第20条第2項(自動車登録番号標の廃棄等) ・第41条(自動車の装置) ・第42条(乗車定員又は最大積載量) ・第47条(使用者の点検及び整備の義務) ・第47条の2(日常点検整備) ・第48条(定期点検整備) ・第49条(点検整備記録簿) ・第54条第1項、第2項(整備命令等) ・第57条(自動車の点検及び整備に関する手引) ・第58条(自動車の検査及び自動車検査証) ・第61条(自動車検査証の有効期間) ・第62条(継続検査) ・第66条(自動車検査証の備付け等) ・第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) ・第69条第2項(自動車検査証の返納等) ・第70条(再交付)②自動車点検基準 ・第1条第1号(日常点検基準) ・第2条第1号(定期点検基準) ・第4条(点検整備記録簿の記載事項等)③道路運送車両の保安基準 ・第29条(窓ガラス) ・第43条の2(非常信号用具) ・第43条の3(警告反射板) ・第43条の4(停止表示器材) ・第50条(旅客自動車運送事業用自動車) ・第53条(乗車定員及び最大積載量)④自動車事故報告規則 ・第2条(定義) ・第3条(報告書の提出) ・第4条(速報)⑤道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 ・③に掲げる条項について具体的に定める事項
別 表

155
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可申請、譲渡譲受及び相続認可申請に係る細
部取扱いについて
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準(平
成13年12月27日付け公示。以下「審査基準」という。)に係る申請書の様式、申請書の記入要領、申請書の添付書類並び
に法令及び地理試験合格後の挙証資料等の細部取扱いについて、下記のとおり定めたので公示する。
平成14年1月31日
関東運輸局長 上 子 道 雄
記
Ⅰ.審査基準について
1.審査基準10の取扱い
⑴ 地理試験免除に係る規定において雇用先のタクシー・ハイヤー事業者が複数である場合の判断については、申請
日以前10年間における雇用先の変更に伴う離職期間の合計が30日以内である場合に限って、雇用が継続しているも
のとみなす。
なお、「申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者」には、当初
タクシー又はハイヤー運転者として雇用され引き続き運行管理者又は整備管理者に選任されている者は含まない。
⑵ 地理試験免除に係る規定に基づく申請で、法令試験合格後の挙証資料において、地理試験免除に係る規定に適合
しないことが判明した場合は地理試験に合格しなかったものとして却下処分とする。
2.審査基準の別表2.B.3.の取扱い
「申請日以前継続して3年以上あること」の判断については、申請日以前3年間における雇用先の変更に伴う離職
期間の合計が30日以内である場合に限って、雇用が継続しているものとみなす。
Ⅱ.申請書の様式について
1.許可申請については、別添⑴のとおりとする。
2.譲渡譲受認可申請については、別添⑵のとおりとする。
3.相続認可申請については、別添⑶のとおりとする。
Ⅲ.申請書の記入要領、申請書の添付書類並びに法令及び地理試験合格後の挙証資料等について
1.許可申請については、別添⑷のとおりとする。
2.譲渡譲受認可申請については、別添⑸のとおりとする。
3.相続認可申請については、別添⑹のとおりとする。
Ⅳ.その他
1.申請事案の処分の時期
⑴ 許可申請については、標準処理期間の範囲内で随時処分することとする。
ただし、特別監視地域に指定された営業区域にあっては、毎年2月1日から2月9日までの間におけるいずれか
の日とする。
⑵ 譲渡譲受及び相続認可申請については、標準処理期間の範囲内で随時処分することとする。
2.申請書は3部(正、副、控)作成(A4版、左綴じ)し、申請する営業区域を管轄する運輸支局の輸送担当に提出
することとする。
3.「審査基準 記Ⅰ.8.⑺」の規定に基づき、申請時点において「車庫未確保」の場合は、申請書の内、「8ページ」、「9
ページに貼付する車庫の写真」及び「10ページ」は、申請時に提出せず、法令及び地理試験合格後の関東運輸局長が
指定する日までに別添⑷Ⅲの挙証資料と共にそれぞれ正、副2通を関東運輸局自動車交通部旅客第二課あて提出する

156
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
こととする。
4.挙証資料については、公示したもの以外でも必要に応じ申請者に提出を求める場合がある。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降、管轄する陸運支局において受付ける申請について適用する。
2.平成9年7月3日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の経営免許申請、
譲渡譲受及び相続認可認可申請に係る申請書の様式等について」は、平成14年1月31日限り廃止する。
ただし、平成14年1月31日以前に管轄する陸運支局において受付けた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成16年1月22日 一部改正)
1.本公示は、平成16年2月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
2.平成16年1月31日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成16年7月30日 一部改正)
1.本公示は、平成16年8月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
2.平成16年7月31日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成17年5月13日 一部改正)
1.本公示は、平成17年6月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成17年12月22日 一部改正)
1.本公示は、平成18年1月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
2.平成17年12月31日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成20年9月12日 一部改正)
本公示は、平成20年9月12日以降に行う処分から適用する。

157
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について、
下記のとおり定めたので公示する。
平成13年12月27日
関東運輸局 東京陸運支局長 向 良 一
記
平成13年12月27日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認
可申請事案の審査基準について」Ⅰ.1.6.7.及び8.⑴から⑹までの規定を準用する。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.平成9年5月15日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更
に関する審査基準について」は、平成14年1月31日限り廃止する。ただし、平成14年1月31日以前に受付けた申請に
ついては、なお従前の取扱いによる。
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について、
下記のとおり定めたので公示する。
平成13年12月27日
関東運輸局 神奈川陸運支局長 瀬 谷 憲 雄
記
平成13年12月27日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認
可申請事案の審査基準について」Ⅰ.1.6.7.及び8.⑴から⑹までの規定を準用する。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.平成9年5月15日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更
に関する審査基準について」は、平成14年1月31日限り廃止する。ただし、平成14年1月31日以前に受付けた申請に
ついては、なお従前の取扱いによる。
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について、
下記のとおり定めたので公示する。
平成13年12月27日
関東運輸局 埼玉陸運支局長 冨 田 征 弘
記
平成13年12月27日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認
可申請事案の審査基準について」Ⅰ.1.6.7.及び8.⑴から⑹までの規定を準用する。

158
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.平成9年5月15日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更
に関する審査基準について」は、平成14年1月31日限り廃止する。ただし、平成14年1月31日以前に受付けた申請に
ついては、なお従前の取扱いによる。
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について、
下記のとおり定めたので公示する。
平成13年12月27日
関東運輸局 群馬陸運支局長 瀬 下 幸 夫
記
平成13年12月27日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認
可申請事案の審査基準について」Ⅰ.1.6.7.及び8.⑴から⑹までの規定を準用する。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.平成9年5月15日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更
に関する審査基準について」は、平成14年1月31日限り廃止する。ただし、平成14年1月31日以前に受付けた申請に
ついては、なお従前の取扱いによる。
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について、
下記のとおり定めたので公示する。
平成13年12月27日
関東運輸局 千葉陸運支局長 小 林 一 雄
記
平成13年12月27日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認
可申請事案の審査基準について」Ⅰ.1.6.7.及び8.⑴から⑹までの規定を準用する。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.平成9年5月15日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更
に関する審査基準について」は、平成14年1月31日限り廃止する。ただし、平成14年1月31日以前に受付けた申請に
ついては、なお従前の取扱いによる。

159
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更に関する審査基準について、
下記のとおり定めたので公示する。
平成13年12月27日
関東運輸局 栃木陸運支局長 嵯 峨 康 志
記
平成13年12月27日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認
可申請事案の審査基準について」Ⅰ.1.6.7.及び8.⑴から⑹までの規定を準用する。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.平成9年5月15日付け「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の事業計画の変更
に関する審査基準について」は、平成14年1月31日限り廃止する。ただし、平成14年1月31日以前に受付けた申請に
ついては、なお従前の取扱いによる。
公 示
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の休止及び廃止の取扱いについて
個人タクシー事業者に係る道路運送法第38条第1項の規定(以下「法の規定」という。)による手続きについては、1
人1車制という特殊性に鑑み、下記のとおり定めたので公示する。
平成14年1月31日
関 東 運 輸 局 長 上 子 道 雄
東京陸運支局長 向 良 一
神奈川陸運支局長 瀬 谷 憲 雄
埼玉陸運支局長 冨 田 征 弘
群馬陸運支局長 瀬 下 幸 夫
千葉陸運支局長 小 林 一 雄
栃木陸運支局長 嵯 峨 康 志
記
1.事業の休止
以下の取扱いによるところとする。
⑴ 休止期間が30日以内の場合
運転日報に明記することとする。
⑵ 休止期間が30日を超える場合
法の規定に基づき事業休止届出書(別添様式1)正本1通を管轄する運輸支局へ提出することとする。
なお、当該届出書については、事業者が所属する事業者団体を経由して提出することができるものとし、この場合、
事業者団体は提出された届出書を一定期間ごとにとりまとめの上、管轄する運輸支局へ一括して提出することができ
るものとする。
2.事業の廃止
事業を廃止した場合には、法の規定に基づき廃止した日から30日以内に事業廃止届出書(別添様式2)正副2通を管
轄する運輸支局へ提出するものとする。

160
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
附 則
本公示は平成14年2月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。
附 則(平成17年12月22日 一部改正)
1.本公示は、平成18年1月1日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。

161
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
5 許可申請書⑴ 許可の申請(運送法第5条)
申請内容(一般乗合)
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
3.路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送
事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあっては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗
合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定
める事項に関する事業計画
4.事業計画
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業
⑴ 路線に関する次に掲げる事項
イ 起点及び終点の地名及び地番
ロ キロ程
ハ 主たる経過地
⑵ 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
⑶ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員11人未
満の事業用自動車の数
⑷ 自動車車庫の位置及び収容能力
⑸ 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ
又は重量
⑹ 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程
添付書類
1.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
2.事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
3.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
4.事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じてい
ることを証する書類
5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証
のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
7.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
イ 組合契約書の写し
ロ 組合員の資産目録
ハ 組合員の履歴書

162
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
8.個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
9.法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
10.次に掲げる事項を記載した路線図
ア 路線
イ 営業所及び停留所の位置及び名称
ウ 自動車車庫の位置
エ 道路法(昭和27年法律第180号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場
所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
オ 縮尺及び方位
路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業
⑴ 路線に関する次に掲げる事項
イ 起点及び終点の地名及び地番
ロ キロ程
ハ 主たる経過地
⑵ 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
⑶ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
⑷ 自動車車庫の位置及び収容能力
⑸ 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ
又は重量
⑹ 運行系統
⑺ 乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程
⑻ 運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあっては、当該発車時刻又は到着時刻
添付書類
1.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
2.事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
3.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
4.事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じてい
ることを証する書類
5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証
のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
7.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類

163
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
イ 組合契約書の写し
ロ 組合員の資産目録
ハ 組合員の履歴書
8.個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
9.法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
10.次に掲げる事項を記載した路線図
ア 路線
イ 営業所及び乗降地点の位置及び名称
ウ 自動車車庫の位置
エ 運行系統
オ 道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごと
のキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
カ 縮尺及び方位
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業
⑴ 営業区域
⑵ 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
⑶ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
⑷ 自動車車庫の位置及び収容能力
⑸ 運送の区間
⑹ 発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
添付書類
1.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
2.事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
3.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
4.事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じてい
ることを証する書類
5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証
のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
7.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
イ 組合契約書の写し
ロ 組合員の資産目録

164
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ハ 組合員の履歴書
8.個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
9.法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
10.次に掲げる事項を記載した路線図
ア 営業区域
イ 営業所並びに発地及び着地の位置及び名称
ウ 自動車車庫の位置
エ 縮尺及び方位
⑵ 許可の申請(貨物自動車運送事業法第4条、貨物自動車運送事業法施行規則第2条)
申請内容
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.事業計画
ア 主たる事務所の名称及び位置
イ 営業所の名称及び位置
ウ 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車の別をいう。)及
び事業用自動車の種別ごとの数
エ 自動車車庫の位置及び収容能力
オ 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための
施設の位置及び収容能力
カ 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
キ 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
※ 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、ア〜オに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し
なければならない。
⑴ 貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置
⑵ 業務の範囲
⑶ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
⑷ 利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「利用する事業者」と
いう。)の概要
※ 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、ア〜オに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し
なければならない。
⑴ 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
⑵ 営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力
⑶ 各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置するもの(運行車)の数
⑷ 運行系統
⑸ 運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数
添付書類
1.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
2.事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書類

165
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
ア.施設の案内図、見取図、平面(求積)図
イ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ウ.施設の使用権原を証する書面
自己所有…不動産登記簿謄本等
借 入…賃貸借契約書等
エ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
オ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入…売買契約書又は売渡承諾書等
リース…自動車リース契約書
自己所有…自動車検査証(写)
4.特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
ア.事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類(100キロを超える系統)
イ.次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺20万分の1以上の平面図)
⑴ 起点、終点及び経過地の位置
⑵ 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
⑶ 縮尺及び方位
ウ.積合せ貨物運送に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
エ.推定による1年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出基礎を記載した書類
5.貨物自動車利用運送を行う場合
ア.営業所の使用権原を証する書面
自己所有…不動産登記簿謄本等
借 入…賃貸借契約書等
イ.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類
ウ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
6.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
ア.定款又は寄付行為及び登記事項証明書
イ.最近の事業年度における貸借対照表
ウ.役員又は社員の名簿及び履歴書
7.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
ア.定款(認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
イ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ウ.設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
8.個人にあっては、次に掲げる書類
ア.資産目録
イ.戸籍抄本
ウ.履歴書
9.法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面(宣誓書)

166
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について
一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、道
路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に基づく以下の処分に関して、その審査基準を下記のとおり定め
たので公示する。
平成13年12月27日
関 東 運 輸 局 長 上 子 道 雄
東京陸運支局長 向 良 一
神奈川陸運支局長 瀬 谷 憲 雄
埼玉陸運支局長 冨 田 征 弘
群馬陸運支局長 瀬 下 幸 夫
千葉陸運支局長 小 林 一 雄
茨城陸運支局長 会 田 幸 治
栃木陸運支局長 嵯 峨 康 志
山梨陸運支局長 佐 藤 市 夫
記
1.許可(道路運送法(以下「法」という。)第4条第1項)
⑴ 運行の態様の定義
① 路線定期運行とは、路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起終点及び停留所の時刻設定が定
時である運行の形態をいう。
② 路線不定期運行とは、路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起点又は終点に係る時刻の設定
が不定である運行の形態をいう。
③ 区域運行は、路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行の形態をいう。
⑵ 事業の適切性
① 路線定期運行又は路線不定期運行を行う場合にあっては、路線の設定が、事業用自動車の運行上問題のないもの
であること。
② 区域運行を行う場合にあっては、営業区域の設定が、原則、地区単位(大字・字、町丁目、街区等)とされてい
ること。ただし、地域の実情により、隣接する複数の地区を営業区域とすることができる。
③ 路線不定期運行及び区域運行は、利用者利便の確保のため路線定期運行との整合性がとられているもの(地域公
共交通会議又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第9条第2項に規定する
協議会(以下「地域公共交通会議等」という。)で地域交通のネットワークを構築する観点から協議が調っている
こと。ただし、交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であって路線定期運行によるものが不在である場合等明ら
かに路線定期運行との整合性をとる必要がない場合はこの限りではない。)であること。
⑶ 路線定期運行に係る事業計画等
① 営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合す
るものであること。
イ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、
農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないものであること。
ハ 事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。
② 事業用自動車
イ 申請者が、使用権原を有するものであること。

167
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ロ 道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること。
ハ 乗車定員は、11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足るものであること。ただし、
地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて
事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合には11人未満の乗車定員と
することができる。
ニ 運行計画を的確に遂行するに足る車両数を有すること。
③ 最低車両数
1営業所ごとに、最低5両の常用車及び1両の予備車を配置するものとする。ただし、地域公共交通会議等の協
議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂
行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合はこの限りでない。
④ 自動車車庫
イ 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメート
ル(特別な事情があると認められる場合においてはこの限りではない。)の範囲内にあって運行管理をはじめと
する管理が十分可能であること。
ロ 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事
業用自動車の全てを収容できるものであること。
ハ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
ニ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
ホ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
ヘ 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備
えられているものであること。
ト 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和
36年政令第265号)に抵触しないものであること。
なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事
業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
チ 着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫又は駐車場が確保されてい
ること。
⑤ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
イ 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及
び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル(特別な事情があると認められる場合においてはこの限りで
はない。)の範囲にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
ロ 事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
ハ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
ニ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
ホ 着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠施設が確保されていること。
⑥ 停留所
イ 事業用自動車の運行上問題のないものであること。
ロ 申請者が、原則として3年以上の使用権原を有するものであること。
ハ 道路法(昭和27年法律第180号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令に抵触しないものであること。
⑦ 運行計画
一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領について(平成13年9月27日付け国自旅第90号)に
定めるところによるクリームスキミング的運行を前提とするものでないこと。
⑷ 路線不定期運行に係る事業計画等

168
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
① 営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、⑶①②④⑤に準ずるものであること。
② 最低車両数は、1営業所ごとに、最低3両を配置するものとする。ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基
づく場合等、地域の実情に応じて事業計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合はこの限
りでない。
③ 当該運行系統の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
④ 乗降地点が、⑶⑥に準ずるものであること。
⑤ 運行系統に係る時刻の設定については、次のいずれかによるものとする。
イ 発車時刻のみが設定されているものであること。
ロ 到着時刻のみが設定されているものであること。
ハ 発車時刻又は到着時刻のいずれもが設定されていない場合には、他の交通機関の終着時刻に依存するものであ
ること又は旅客の需要に応じたものであること。
⑸ 区域運行に係る事業計画等
① 営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、⑶①②④⑤に準ずるものであることとし、営業所は営業
区域内にあることを要するものとする。ただし、地域の実情により、適切な運行管理が図られる地理的範囲内に営
業所があると認められる場合は、この限りでない。
② 最低車両数は、⑷②に準ずるものであること。
③ 当該運送の区間の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
④ 運送の区間ごとに発車時刻若しくは到着時刻又は運行間隔時間のいずれかが設定されているものであること。な
お、発車時刻は、営業所について、到着時刻は、目的地について定めることを原則とする。ただし、運行間隔時間
を設定する場合であって、地域公共交通会議等の協議結果に基づく一定の時間帯別の運行回数等が明示されている
ときにはこの限りでない。
⑤ 通信施設等を利用して事前予約等に応じた乗合運行の形態となっているものであること。
⑹ 管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の業務を執行する常勤役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管
理計画があること。
③ 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されると
ともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令
第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②〜⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会
社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会
社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関
する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑧ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
⑺ 運転者
① 事業計画及び運行計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
③ 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
⑻ 資金計画
① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。

169
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
なお、所要資金は次のイ〜トの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
イ 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
ロ 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
ハ 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
ニ 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
ホ 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
ヘ 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
ト その他 創業費等開業に要する費用(全額)
② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されて
いること。なお、事業開始当初に要する資金は、次のイ〜ハの合計額とする。
イ ①イに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いに
よって取得する場合は、①イと同額とする。
ロ ①ロ及びハに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いに
よって取得する場合は、①ロ及びハと同額とする。
ハ ①ニ〜トに係る合計額
⑼ 法令遵守
① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗合旅客自動車運
送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保
険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを
問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、以下
のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。
イ 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)
等の違反により申請日前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)
の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となっ
た事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ロ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ケ月間及び申請日以
降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を
受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に
その法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ハ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降
に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者
が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人
の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ニ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請
日以降に営業の停止命令、承認の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人であ
る場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法
人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ホ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利
便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し、改善命令等を受けた場合にあっては、申請
日前にその命令された事項が改善されていること。
ヘ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

170
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ト 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労
運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
チ 申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転による道路交通法第75条の2第1
項に基づき公安委員会から自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。
リ 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省
令第33号)、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成
12年運輸省・建設省令第9号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
⑽ 損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償する
ために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保
険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。ただし、公営の事業者は、この限りではない。
⑾ 許可に付す条件
運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこと。
⑿ 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとする。
2.事業計画の変更の認可(法第15条第1項)
⑴ 1⑵〜⑻、⑽の定めるところに準じて審査することとする。
⑵ 事業規模の拡大となる申請については、⑴のほか、申請者等が1⑼③に定める法令遵守の点で問題のないこと。た
だし、申請者の営業政策が申請の主たる目的ではないと明らかに認められる場合においてはこの限りではない。
3.事業の譲渡及び譲受の認可(法第36条第1項)
⑴ 事業を譲り受けしようとする者について、1⑵〜⑾の定めるところに準じて審査することとする。
⑵ 譲渡譲受の対象となる財産のうち、国庫補助金により取得した財産であって、補助要綱等で定める処分制限期間内
の財産の有無を確認し、当該処分制限期間内の財産がある場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法
律(昭和30年法律第179号)(以下「補助金適正化法」という。)第22条に基づく財産処分の承認を受けさせること。
⑶ 対象となる路線における事業の全部を譲渡譲受の対象とするものに限り適用することとし、それ以外の事業の一部
譲渡については、事業計画及び運行計画の変更の手続によることとする。
4.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は法第37条第1項)
⑴ 合併若しくは分割により事業を承継する法人又は相続人について、1⑵〜⑾の定めるところに準じて審査すること
とする。
⑵ 分割の認可については、分割後において存続する事業者が、運行態様に応じ1⑶③、1⑷②、1⑸②の基準を満た
さない申請については認可しないこととする。
⑶ 分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条及び分割に伴う労働契約
の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等が行われているもの
であること。
⑷ 合併及び分割並びに相続対象となる財産のうち、国庫補助金により取得した財産であって、補助要綱等で定める処
分制限期間内の財産の有無を確認し、当該処分制限期間内の財産がある場合には、補助金適正化法第22条に基づく財
産処分の承認を受けさせること。
5.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。

171
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
附 則
1.この公示は、平成14年2月1日以降に処分するものから適用するものとする。
2.平成6年8月25日付け公示「一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請事案及び事業計画変更認可申請事案の審査基
準について」は、平成14年1月31日限りで廃止する。
3.事案処理に際して、本審査基準に規定した要件の具体的な適用については、細部取扱い通達の定めによるものとする。
4.タクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時特別措
置法の違反による処分等を含む。
附 則(平成14年7月1日 一部改正)
1.この改正は、平成14年7月1日以降に処分するものから適用するものとする。
附 則(平成16年7月22日 一部改正)
本処理方針は、平成16年8月1日以降に処分を行うものから適用するものとする。
附 則(平成17年5月13日 一部改正)
1.この改正は、平成17年6月1日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成18年9月27日 一部改正)
1.この改正は、平成18年10月1日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成18年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成19年7月30日 一部改正)
1.この改正は、平成19年9月10日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
3.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整
第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っ
ている一般乗合旅客自動車運送事業者については施行日から2年間、施行前に一般乗合旅客自動車運送事業の許可を
申請したものについては、その申請による運輸の開始の日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。
附 則(平成20年6月30日 一部改正)
1.この改正は、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成21年9月30日 一部改正)
1.この改正は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成21年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成22年8月24日 一部改正)
1.この改正は、平成22年9月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成22年8月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
関自旅一第1268号
平成13年12月27日
一部改正 平成16年7月22日
一部改正 平成17年5月13日
一部改正 平成18年9月27日
一部改正 平成20年6月30日
一部改正 平成21年9月30日

172
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
管内陸運支局長 殿
関東運輸局 自動車第一部長
「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の細部取扱について
平成14年2月1日から改正道路運送法の施行に伴い、「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請
等の審査基準について」(平成13年12月27日付け関自旅一第1267号)を制定し、公示したところであるが、平成13年9月
27日付け国自旅第93号により自動車交通局旅客課長から「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の細部
取扱についての通達があったことに伴い、今般、下記のとおり関東運輸局長及び管内各陸運支局長の権限に係る許可及び
事業計画変更認可申請等事案の審査事務について、さらなる迅速化、透明化等を図るため、細部取扱を定めたので、貴職
におかれても内容を了知されるとともに、関係団体等に対し通知を行い、標記通達については、各陸運支局の窓口に備置
し、申請者等の求めに応じ配布することができるよう事務処理等に遺漏のないよう取り図らわれたい。
記
1.許 可
⑴ 運行の態様の定義
①〜③について
・運行の態様が①から③までのいずれかとなっていること。
⑵ 事業の適切性
②について
・営業区域内の地点と営業区域外の地点との間を運行する形態については、当該地点間を運送の区間とし、当該区
間において、原則として旅客の乗降が行われないこと。
③について
・「交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であって路線定期運行によるものが不在である場合等」の「等」には、
路線定期運行では困難な需要に対応する空港アクセス型、観光需要対応型等の輸送形態が含まれる。
⑶ 路線定期運行に係る事業計画等
① 営業所
・営業所、事務所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設を
営業所とする。
イについて
・自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、
使用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認め
られる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの
提出を求めないこととする。
ロについて
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付、提示又は写し
の提出を求めないこととする。
② 事業用自動車
イについて
・リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の写しの添付
をもって、使用権原を有するものとする。
ハについて
・「事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合」とは、旅客の積み残
しが生ずるおそれがない場合等、旅客の利便が阻害されない場合をいい、その事業計画に応じ個別に判断する

173
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ものとする。
ニについて
・車両数については、③の要件もともに満たす必要がある。
③ 最低車両数
・「過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等」とは、過疎地及びこれらに準ずる地域内の運行のみの場合、事業
の管理の受託を併せて行う営業所である場合、定期観光運送のみを行う場合等とし、その地域の実情に応じ個別
に判断するものとする。
④ 自動車車庫
イについて
・「特別な事情があると認められる場合」とは、地域協議会若しくは地域公共交通会議又は道路運送法施行規則(昭
和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第9条第2項に規定する協議会(以下「地域協議会等」という。)
において路線の新設について協議が調っている場合のほか、個別に判断するものとし、土地の利用状況、事業
の形態等を勘案し、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき運輸大臣が
定める地域及び運輸大臣が定める距離」(平成3年運輸省告示第340号)に基づき関東運輸局長が定めた距離と
することができる。
ニについて
・⑶①イに同じ。
ホについて
・⑶①ロに同じ
ヘについて
・必要な点検等ができる測定用器具等とは、自動車点検基準第6条第3号に定めるものとする。
トについて
・道路幅員証明書の添付をもって確認するものとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな
場合は、この限りでない。
チについて
・長時間停留とは、運行終了後の当該運行に係る運転者の休息期間中における停留の場合のほか、個別に判断す
るものとする。
・高速バスとは、専ら一の市町村(特別区を含む。)の区域を超えて設定された概ね50キロメートル以上のキロ
程の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送する形態をいう。
・着地における自動車車庫の確保については、共同運行会社との運輸に関する協定においてその使用について明
記されていれば足るものとし、それ以外の場合は、ニに準ずるものとする。
⑤ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
イについて
・特別な事情がある場合とは、営業所周辺に適切な施設を確保した上で、更に、路線の起終点等で運転者の休憩
仮眠を行わせるために施設を設置する場合をいう。
ハについて
・⑶①イに同じ。
ニについて
・⑶①ロに同じ。
ホについて
・長時間停留とは、運行終了後の当該運行に係る運転者の休息期間中における停留の場合とする。
・高速バスとは、専ら一の市町村(特別区を含む。)の区域を超えて設定された概ね50キロメートル以上のキロ
程の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送する形態をいう。

174
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
・着地における睡眠施設の確保については、共同運行会社との運輸に関する協定においてその使用について明記
されていれば足るものとし、それ以外の場合は、ニに準ずるものとする。
なお、ホテル等の宿泊施設の使用も可能とする。
⑥ 停留所
ロについて
・⑶①イに準ずるとともに、使用するに当たって関係者間の調整を要する停留所にあっては、その調整が終了し
ていること。なお、「原則として3年以上」とあるのは、道路占用許可、道路使用許可については、道路管理
者等が附する期限まででよいこととする趣旨であり、その他の停留所に係る土地、建物、施設等については3
年以上であることとする。
ハについて
・事業者が関係機関に対して行う道路占用許可、道路使用許可を得ているか若しくは確実に得られる見込みのあ
ることとする。
⑷ 路線不定期運行に係る事業計画等
⑤について
・時刻の設定については、途中の乗降地点の発着時刻が不定となっていること等、一運行に係る運行系統の時刻設
定が不定となっていること。
⑸ 区域運行に係る事業計画等
①について
・「適切な運行管理が図られる地理的範囲内」については、例えば、営業区域に隣接する地区(大字・字、町丁目、
街区等)内である場合など、地域の実情に応じ、個別に判断するものとする。
④について
・運送の区間には、原則として基軸経路を設定すること。
ただし、旅客個々の予約状況により実際の運行経路が設定される場合に運行間隔時間を設定するときはこの限り
でない。
・発車時刻又は到着時刻は、方面別の運送の区間ごとに設定すること。
・運行間隔時間は、一運行に係る時刻設定が困難な場合に設定すること。
⑹ 管理運営体制
①について
・専従する役員のうち1名は、⑼①の法令試験に合格した者であることとする。
②について
・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の9に規定される要件を満たす管理計画を有す
るものとする。
③について
・複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確
化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。
④について
・常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。
・原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。なお、着地において長時間停留する高速バス路線
で着地における運転手への点呼の場合等対面して行うことが困難であると認められる場合にあっては、電話等の
方法により行うこととする。
⑤について
・事故防止等についての教育及び指導体制には、旅客又は公衆に対する公平かつ懇切な取扱いに関するものも含む
ものとする。

175
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑧について
・旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより苦情を処理することが可能な体制を有するものとす
る。
⑻ 資金計画
①〜②について
・規則第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とする。
・自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることが
できることとする。
・預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の添付をもって確認するものとする。
・預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。
・従前から運行が行われていた路線を廃止すると同時に当該事業者の関連会社等が引き続き運行を行う等、明らか
に事業の継続性が認められる事案については、廃止する事業者の運行実績を踏まえた2ヶ月分の収入見込み額を
自己資金の一部と見なすことができる。
・その他規則第6条第1項第6号から第9号に規定する添付書類を基本とし審査することとする。
⑼ 法令遵守
①について
・必要な法令の知識については、専従の役員1名が関東運輸局等が行う法令試験に合格していることをもって、こ
れを有するものとする。
・公営事業者に関する役員の範囲は、組織規定、所掌事務規定、決裁権限規定、会計機関規定、内部会議規定、地
方議会規定等に規定されているとともに、実態としても、路線の廃止、廃止等の事業計画、職員の任免、事業資
産の調達等一般乗合旅客自動車運送事業の運営に関する重要事項の決定に関して権限を有するか否かにより判断
するものとする。
②について
・「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、
社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の添付を求め、確認することとする。
③について
・本規定は、これらの処分を受けた者は事業を適切に運営しない蓋然性が極めて高いことから、法第7条の欠格事
由の規定に準じて事業の適切な運営を確保する観点から設けたものである。
・本規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくとも、相談役、顧問等として事業
の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼすおそれが否定できないことから、これらの者についても本規程の対象
とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するものであるので留意することとする。
・「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、法、貨物自
動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき
行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断するものとする。
⑽ 損害賠償能力
・契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを
証する書類の添付を求め、確認することとする。
2.事業計画の変更の認可
・1⑵〜⑻、⑽の定めるところに準じる審査は以下のとおり行うものとする。
⒜ 路線の新設、営業区域の設定に係る申請においては、事業の許可申請と同様なものとみなし1⑵〜⑻、⑽につい
て十分な審査を行う。ただし、道路の付け替え等に伴う必然的な路線の乗せ替えの場合においては、1⑶②ロ、⑥
又は1⑷①④について速やかに審査を行うものとする。

176
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⒝ 自動車車庫の新設、位置の変更及び収容能力の拡大に係る申請においては、1⑶①ハ、③、④、⑤イ、1⑷①、
②又は1⑸①、②(収容能力の拡大の場合は1⑶①ハ、③、④、1⑷①、②又は1⑸①、②)について十分な審査
を行うものとする。
なお、1⑶④イ、1⑷①又は1⑸①については、営業所の統廃合に伴い残った自動車車庫の使用状況、路線新設
時の土地の利用状況、事業の形態等を勘案し、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1号の規
定に基づき運輸大臣が定める地域及び運輸大臣が定める距離」(平成3年運輸省告示第340号)に基づき関東運輸局
長が定めた距離とすることができる。
⒞ 事業用自動車の最大の大きさ等の変更に係る申請においては、1⑶②、③、④ロ、ト、1⑷①、②又は1⑸①、
②について十分な審査を行うものとする。
⒟ 自動車車庫の収容能力の縮小に係る申請においては、1⑶③、④、1⑷①、②又は1⑸①、②について十分な審
査を行うものとする。
・ただし、経過措置として、平成14年1月31日現在で一般乗合旅客自動車運送事業を行っている者(以下「既存事業
者」という。)に係る1⑶③及び1⑶⑤イの基準については、以下のとおり取り扱うものとする。
⒜ 同日現在で基準を満たしていなかった営業所(その後基準を満たしたものを除く。)については、1⑶③は適用
しない。
⒝ 同日現在で基準を満たしていなかった休憩、仮眠又は睡眠のための施設(その後基準を満たしたものを除く。)
については、1⑶⑤イは適用しない。
・事業規模の拡大となる申請は以下のものをいう。
① 運行の態様の変更(増加する場合に限る。)に伴う当該事業計画変更に係るもの。
② 路線の新設に係るもの。
③ 自動車車庫の新設、位置の変更(収容能力の拡大を伴うものに限る。)及び収容能力の拡大に係るもの。
④ 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ
又は重量の増加に係るもの。
・申請者の営業政策が申請者の主たる目的ではないと明らかに認められる場合とは、以下のものをいう。
① 続行便の運行実績が相当数に及ぶ場合又は混雑率が相当高い場合等で、利用者利便の改善を主たる目的として行
う、必要限度までの大型車両の導入、増車又は迂回路線等の開設。
② 経営効率化等の一環として系列子会社へ路線を移管する場合で、路線及び運行内容が、移管前後で概ね同一であ
るもの。
③ 道路整備、都市計画整備に伴う車庫の移設で当該車庫の収容能力が拡大する場合等
④ 路線の開設、輸送力の増強等の拡大施策が、地方公共団体等が実施する地域整備計画に組み込まれているもので
ある場合
⑤ 当該申請が、地域協議会等において協議が調っている場合、道路の付け替え等に伴う必然的な路線の乗せ替えの
場合及び地元からの新設要望に基づく場合(需要施設等の規模、要望の頻度、要望経緯等に基づいて総合的に判断
されたもの)のほか、個別に判断するものとする。
⑥ 高速バス路線の新設において、地方公共団体の長又は議会から、その新設目的及び新設事業者を具体的に示して、
生活交通の確保、地域活性化等公共の福祉の増進に資する内容の路線新設等に係る要望書が提出されている場合(共
同運行会社を除く他の一般乗合旅客自動車運送事業者が不在の場合に限る。)
・一般乗合旅客自動車運送事業を経営しない系列子会社の役員のうち、非常勤役員又は常勤非常勤の別を問わず監査役
は、処理方針の2⑵①〜③の役員には該当しないものとする。
3.事業の譲渡譲受の認可
⑴について
・譲受人が既存事業者の場合には、当該譲受人に対して実施する法令試験を省略する。

177
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
・上記2.のただし書きに規定する経過措置(⒜を除く。)を準用するものとする。
・譲渡譲受事案の資金計画にあっては、譲渡譲受契約により取得する事業用資産を所要資金項目の対象外とし、流動
資産額については、譲渡譲受時点の見込み貸借対照表の提出をもって確認するものとする。
⑵について
・国庫補助金により取得した財産が、補助要綱等で定める処分制限期間内または外であることが確認できる書類の添
付を求めて確認し、処分制限期間内の財産がある場合には、当該財産処分の承認の申請の有無により確認すること
とする。
4.合併・分割又は相続の認可
⑴について
・合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場合には、当該既存事業者たる法人の役員
若しくは相続人に対して実施する法令試験を省略する。
・上記2.のただし書きに規定する経過措置(⒜を除く。)を準用するものとする。
⑶について
・労働契約の承継等については、当該法律に基づく客観的な資料の提出を求めることとする。
⑷について
・国庫補助金により取得した財産が、補助要綱等で定める処分制限期間内または外であることが確認できる書類の添
付を求めて確認し、処分制限期間内の財産がある場合には、当該財産処分の承認の申請の有無により確認すること
とする。
5.挙証等
・上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の提出を求めることとする。
附 則(平成16年7月22日 関自旅一第428号 一部改正)
本取扱は、平成16年8月1日以降に処分を行うものから適用するものとする。
附 則(平成17年5月13日 関自旅一第141号 一部改正)
1.この改正は、平成17年6月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成18年9月27日 関自旅一第1182号、関自旅二第1602号 一部改正)
1.この改正は、平成18年10月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成18年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成20年6月30日 関自旅一第352号、関自旅二第952号 一部改正)
1.この改正は、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成21年9月30日 関自旅一第720号、関自旅二第1128号 一部改正)
1.この改正は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成21年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成22年8月24日 関自旅一第558号、関自旅二第14191号 一部改正)
1.この改正は、平成22年9月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成22年8月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。

178
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
一般乗合旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施方法について
「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」(平成13年12月27日付け公示)に
規定する法令試験に関して、その実施方法を下記のとおり定めたので公示する。
平成14年2月1日
関東運輸局長 上 子 道 雄
記
1.試験の実施時期等
⑴ 許可等申請書を受理した日以降、適宜実施する。なお、試験の実施予定の日時、場所については、実施予定日の10
日までに書面をもって申請者あて原則郵送により通知する。
⑵ 再試験にあたっては、⑴に準じて再度通知する。
2.受験者の確認等
⑴ 当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請す
る事業に専従する業務を執行する常勤役員1名を受験者とする。)であることが確認できる運転免許証等の提示をす
ること。
3.出題範囲及び設問形式等
⑴ 出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
① 道路運送法
② 道路運送法施行令
③ 道路運送法施行規則
④ 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令
⑤ 旅客自動車運送事業運輸規則
⑥ 旅客自動車運送事業等報告規則
⑦ 自動車事故報告規則
⑧ 道路運送車両法
⑨ 道路運送車両法施行規則
⑩ その他一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要となる法令等
⑵ 設問の方式
○×方式及び語群選択方式とする。
⑶ 出題数
30問
⑷ 合格基準
出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合には、再試験を実施する。
⑸ 試験時間
50分とする。
4.その他
① 自動車六法等(情報通信機器を除く。)の持ち込みを可とする。
② 試験当日、受験者は筆記用具の他、本人であることが確認できる運転免許証、パスポート等を持参すること。
附 則
1.この公示は、平成14年2月1日以降に受け付けた申請について適用する。

179
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
附 則(平成18年9月27日 一部改正)
1.この改正は、平成18年10月1日以降受付けた申請について適用する。
2.平成18年9月30日以前に受付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
公 示
一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について
一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、道
路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に基づく以下の処分に関して、その審査基準を下記のとおり定め
たので公示する。
平成12年1月6日
関 東 運 輸 局 長 磯 田 壯一郎
東京陸運支局長 増 井 潤
神奈川陸運支局長 小 林 新 一
埼玉陸運支局長 高 橋 邦 夫
群馬陸運支局長 甲 田 秀 久
千葉陸運支局長 小 坂 利 廣
茨城陸運支局長 中 村 進 一
栃木陸運支局長 塚 本 建 生
山梨陸運支局長 島 崎 満 雄
記
1.許 可(法第4条第1項)
⑴ 営業区域
原則、都県単位とする。
ただし、都県の境界に接する市町村(東京都特別区又は政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。
以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済
事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
なお、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村区域の拡大があった場合
は、拡大後の市町村を含む区域を営業区域とし、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、行政区の分
割等により、当該市町村区域の縮小があった場合には、従前の区域を営業区域とするものとする。
⑵ 営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合する
ものであること。
① 営業区域内(⑴ただし書きにより含むこととなる隣接する市町村の範囲を除く。)にあること。
なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
② 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
③ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農
地法(昭和27年法律第299号)等関係法令に抵触しないものであること。
④ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。
⑶ 事業用自動車
① 車種区分
車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は、次のとおりとする。

180
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車…大型車、小型車以外のもの
小型車…車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
② 事業用自動車
申請者が、使用権原を有するものであること。
⑷ 車両数
① 最低車両数
営業所を要する営業区域毎に3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両。
なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定す
る旨の条件を付すこととする。
⑸ 自動車車庫
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル
の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業
用自動車の全てを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備え
られているものであること。
⑦ 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36
年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る
使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令
に抵触しないものであること。
⑹ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び
自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能である
こと。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑺ 管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管
理計画があること。
③ 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されると
ともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令
第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②〜⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める

181
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、
事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑧ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
⑻ 運転者
① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
⑼ 資金計画
① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次のイ
〜トの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
イ 車両費 取得価格(未払金を含む。)又はリースの場合は1年分の賃借料等
ロ 土地費 取得価格(未払金を含む。)又は1年分の賃借料等
ハ 建物費 取得価格(未払金を含む。)又は1年分の賃借料等
ニ 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む。)
ホ 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
ヘ 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
ト その他 創業費等開業に要する費用(全額)
② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されて
いること。
なお、事業開始当初に要する資金は、次のイ〜ハの合計額とする。
イ ①イに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いに
よって取得する場合は、①イと同額とする。
ロ ①ロ及びハに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いに
よって取得する場合は、①ロ及びハと同額とする。
ハ ①ニ〜トに係る合計額
⑽ 法令遵守
① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運
送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保
険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを
問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が次のイ
からハのすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
イ 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)
等の違反により申請日前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)
の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となっ
た事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ロ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ケ月間及び申請日以
降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を
受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に
その法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ハ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降
に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者
が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人

182
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
⑾ 損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償する
ために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保
険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
ただし、公営の事業者は、この限りではない。
⑿ 許可等に付す条件等
① 離島での輸送、会葬者の輸送、車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた輸送、
法第21条第2号に基づく許可を受けて乗合運送を行うことを内容とする輸送等の特殊な申請については、その内容
に応じ、それぞれの特性を踏まえて弾力的に判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸
送に限定する旨の条件等を付すこととする。
② 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。
⒀ 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとする。
2.事業計画の変更の認可(法第15条第1項)
⑴ 1.⑴〜⑼、⑾〜⒀(⑿②を除く。)の定めるところに準じて審査することとする。
⑵ 事業規模の拡大となる申請については、⑴のほか、申請者等が以下のすべてに該当するものであること等法令遵守
の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ケ月間及び申請日以降
に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人であ
る場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行
する常勤の役員として存在した者を含む。)ではないこと。
② 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ケ月間及び申請日以降
に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受け
た者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法
人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
③ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に
190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法
人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務
を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
④ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便
を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し、改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に
当該命令された事項が改善されていること。
⑤ 申請日前1年間及び申請日以降において自らの責に帰する重大事故を発生させてないこと。
⑥ 申請日前1年間及び申請日以降に、特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(酒酔い運転、
酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)
がないこと。
⑦ 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出
を適切に行っていること。
3.事業の譲渡及び譲受の認可(法第36条第1項)
⑴ 事業を譲り受けしようとする者について、1.⑴〜⒀の定めるところに準じて審査することとする。

183
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑵ 事業の全部を譲渡譲受の対象とするものに限り適用することとし、それ以外の事業の一部譲渡については、事業計
画の変更の手続によることとする。
4.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は法第37条第1項)
⑴ 合併若しくは分割により事業を承継する法人又は相続人について、1.⑴〜⒀の定めるところに準じて審査するこ
ととする。
⑵ 分割の認可については、分割後において存続する事業者が、1.⑷の基準を満たさない申請については認可しない
こととする。
⑶ 分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条及び会社の分割に伴う労
働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等が行われてい
るものであること。
5.許可又は認可に付した条件の変更等
上記1.〜4.の許可又は認可に付した条件又は期限について、変更もしくは解除又は期限の延長を行う場合には、上
記1.〜4.の定めるところにより行うものとする。
6.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
1.この公示は、平成12年2月1日以降当局管内陸運支局で受理する申請から適用する。
2.「一般貸切旅客自動車運送事業免許申請事案の審査基準について」(平成9年3月21日公示)及び「一般貸切旅客自
動車運送事業事業計画変更認可申請事案の審査基準について」(平成9年3月21日公示)は、平成12年1月31日限り
これを廃止する。
附 則(平成13年3月30日 一部改正)
1.この改正は、平成13年4月2日以降受け付けた申請について適用する
2.平成13年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成14年1月31日 一部改正)
1.この改正は、平成14年2月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成14年1月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
3.1.⑽②、2.⑵①及び2.⑵②におけるタクシー業務適正化特別措置法に基づく処分には、平成14年1月31日以前
のタクシー業務適正化臨時措置法に基づく処分を含むものとする。
4.事案処理に際して、本審査基準に規定した要件の具体的な適用については、細部取扱い通達の定めによるものとする。
附 則(平成14年7月1日 一部改正)
1.この改正は、平成14年7月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成14年6月28日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成16年7月22日 一部改正)
この改正は、平成16年8月1日以降に処分するものから適用するものとする。
附 則(平成17年5月13日 一部改正)
1.この改正は、平成17年6月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成18年1月27日 一部改正)
1.この改正は、平成18年2月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成18年1月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。

184
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
附 則(平成19年7月30日 一部改正)
1.この改正は、平成19年9月10日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
3.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自
整第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っ
ている一般貸切旅客自動車運送事業者については施行日から2年間、施行前に一般貸切旅客自動車運送事業の許可を
申請したものについては、その申請による運輸の開始の日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。
附 則(平成20年6月30日 一部改正)
1.この改正は、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成21年9月30日 一部改正)
1.この改正は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成21年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
関自旅1第1493号
平成14年1月31日
一部改正 平成16年7月22日
一部改正 平成17年5月13日
一部改正 平成18年9月27日
一部改正 平成19年7月30日
一部改正 平成20年6月30日
一部改正 平成21年9月30日
管内陸運支局長 殿
関東運輸局 自動車第一部長
「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の細部取扱について
平成14年1月31日付け国自旅第163号により、国土交通省自動車交通局旅客課長から別添のとおり「一般貸切旅客自動
車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」の細部取扱についての通達があったので、今般、関東運輸
局長及び管内陸運支局長の権限に係る許可及び事業計画変更認可申請等事案の審査事務について、さらなる迅速化、透明
化を図るため、下記のとおり細部取扱いを定めたから了知されるとともに、関係団体等に対し周知を図り、また、貴運輸
支局の窓口において申請者等の求めに応じて配布できるよう、事務処理上遺漏のないよう取り計らわれたい。
記
1.許 可
⑵ 営業所
・営業所、事務所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設を営
業所とする。
②について
・自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使
用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる
場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提

185
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
出は求めないこととする。
・なお経過措置として、平成14年2月28日までに受け付けた申請に係る使用権原の期間については、なお従前の取
扱いによる。
③について
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付、提示又は写しの
提出を求めないこととする。
⑶ 事業用自動車
②について
・リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の写しの添付を
もって、使用権原を有するものとする。
⑸ 自動車車庫
④について
・⑵②に同じ。
⑤について
・⑵③に同じ
⑥について
・必要な点検等ができる測定用器具等とは、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第6条第3項に定めるも
のとする。
⑦について
・道路幅員証明書の添付をもって確認するものとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場
合は、この限りでない。
⑹ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
③について
・⑵②に同じ。
④について
・⑵③に同じ。
⑺ 管理運営体制
①について
・専従する役員のうち1名は、⑽①の法令試験に合格した者であることとする。
②について
・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の9に規定される要件を満たす管理計画を有す
るものとする。
③について
・複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確
化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。
④について
・常時密接な連絡を取れる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。
・原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。なお、対面して行うことが困難であると認められ
る場合にあっては、電話等の方法により行うこととする。
⑤について
・事故防止等についての教育及び指導体制には、旅客又は公衆に対する公平かつ懇切な取扱いに関するものも含む
ものとする。
⑦について

186
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
・グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備
管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)5-3②に規定される要件を満たす計画を有
するものとする。
⑧について
・旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより苦情を処理することが可能な体制を有するものとす
る。
⑼ 資金計画
①〜②について
・道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とす
る。
・自己資金には、当該申請事業に係る預貯金の他、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることがで
きることとする。
・預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の添付をもって確認するものとする。
・預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。
・その他道路運送法施行規則第6条第1項第6号から第9号に規定する添付書類を基本とし、審査することとする。
⑽ 法令遵守
①について
・必要な法令の知識については、専従の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格していることをもって、こ
れを有するものとする。
②について
・「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、
社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の添付を求め、確認することとする。
③について
・本規定は、これらの処分を受けた者は事業を適切に運営しない蓋然性が極めて高いことから、法第7条の欠格事
由の規定に準じて事業の適切な運営を確保する観点から設けたものである。
・本規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくとも、相談役、顧問等として事業
の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼすおそれが否定できないことから、これらの者についても本規定の対象
とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するものであるので留意することとする。
・「すべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと」には、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
(平成13年法律第57号)に基づき申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃
止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける
原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)でない
ことを含むものとする。
・「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法、
貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に
基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断するものとする。
⑾ 損害賠償能力
・契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを
証する書類の添付を求め、確認することとする。
2.事業計画の変更の認可等
⑴〜⑵について
・1.⑴〜⑼、⑾〜⒀の定めるところに準じる審査は、以下のとおり行うものとする。

187
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⒜ 営業区域の拡大に係る申請においては、事業の許可申請と同等の申請とみなし1.⑴〜⑼、⑾、⑿について十
分な審査を行うものとする。
⒝ 自動車車庫の新設、位置の変更に係る申請においては、1.⑵④、⑷、⑸、⑹①について、収容能力の拡大に
係る申請においては、1.⑵④、⑷、⑸について、また収容能力の縮小に係る申請においては1.⑷、⑸について、
それぞれ十分な審査を行うものとする。
⒞ 自動車車庫の収容能力の増加を要する事業用自動車の数の変更に係る申請においては、1.⑵④、⑷、⑸、⑹
①について十分な審査を行う。
⒟ 営業所の廃止に係る申請においては、1.⑵①、⑸①、⑹①について十分な審査を行うものとする。
⒠ 営業区域の廃止にかかる申請については、廃止しようとする営業区域内のすべての営業所及び自動車車庫の廃
止の手続き並びに当該営業所に配置する事業用自動車の数の変更(すべての減車)の手続きを伴うものであるこ
とを確認することとする。
・事業規模の拡大となる申請は、営業区域の拡大、営業所の新設並びに自動車車庫の新設、位置の変更(収容能力の
拡大を伴うものに限る。)及び収容能力の拡大並びに自動車車庫の収容能力の増加を要する事業用自動車の数の変
更に係るものとする。
・「すべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと」には、自動車運転代行業の業務の適正化に
関する法律(平成13年法律第57号)に基づき申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は
営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を
受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)で
ないことを含むものとする。
・「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法、
貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基
づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断するものとする。
3.事業の譲渡譲受の認可
⑴について
・譲受人が既存事業者の場合には、当該譲受人に対して実施する法令試験を省略する。
・譲渡譲受事案の資金計画にあっては、譲渡譲受契約により取得する事業用資産を所要資金項目の対象外とし、流動
資産額については、譲渡譲受時点の見込み貸借対照表の提出をもって確認するものとする。
4.合併、分割又は相続の認可
⑴について
・合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場合には、当該既存事業者たる法人の役員
若しくは相続人に対して実施する法令試験を省略する。
⑶について
・労働契約の承継等については、当該法律に基づく客観的な資料の提出を求めることとする。
6.挙証等
・上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の提出を求めることとする。
附 則(平成16年7月22日 関自旅一第429号)
本取扱は、平成16年8月1日から処分を行うものから適用するものとする。
附 則(平成17年5月13日 関自旅一第144号)
1.この改正は、平成17年6月1日以降受け付けた申請に適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。

188
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
附 則(平成18年9月27日 関自旅一第1202号)
1.この改正は、平成18年10月1日以降受け付けた申請に適用する。
2.平成18年9月30日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成19年7月30日 関自旅一第430号)
1.この改正は、平成19年9月10日以降受け付けた申請に適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成20年6月30日 関自旅一第347号)
1.この改正は、平成20年7月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成21年9月30日 関自旅一第722号)
1.この改正は、平成21年10月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.平成21年9月30日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。
公 示
一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について
「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」(平成12年1月6日公示)に規定
する法令試験に関して、その実施方法等を下記のとおり定めたので公示する。
平成14年2月1日
関東運輸局長 上 子 道 雄
記
1.法令試験の実施時期等
⑴ 法令試験は、毎月1回実施する。
⑵ 初回の法令試験は、許可申請書等を受理した月の翌月に実施することとし、法令試験の実施予定日の10日前までに、
実施予定日時及び場所等を記載した書面を郵送により申請者あて通知する。
⑶ 初回の法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、再度の法令試験を実施することとし、この場合は⑵
に準じて再度通知する。
2.受験者の確認等
⑴ 当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請者本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請す
る事業に専従する役員1名を受験者とする。)であることが確認できる運転免許証等を提示すること。
3.出題範囲及び設問形式等
⑴ 出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
① 道路運送法
② 道路運送法施行令
③ 道路運送法施行規則
④ 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令
⑤ 旅客自動車運送事業運輸規則
⑥ 旅客自動車運送事業等報告規則
⑦ 道路運送車両法
⑧ 道路運送車両法施行規則

189
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑨ 自動車事故報告規則
⑩ 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
⑪ 一般貸切旅客自動車運送事業運賃・料金
⑫ その他一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要となる法令等
⑵ 設問の方式
○×方式及び語群選択方式とする。
⑶ 出題数
30問
⑷ 合格基準
出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合には、再試験を実施する。
⑸ 試験時間
50分とする。
4.その他
⑴ 自動車六法等(情報通信機器を除く。)の持ち込み可とする。
⑵ 試験当日、受験者は筆記用具の他、本人であることが確認できる運転免許証、パスポート等を持参すること。
附 則
1.この公示は、平成14年3月1日以降実施する法令試験について適用する。
2.「法令試験の実施について」(平成12年1月19日公示)は、平成14年2月28日限り廃止する。

190
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
公 示
特定旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の審査基準について
特定旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、道路運送
法(昭和26年法律第183号。道路運送法(以下「法」という。)に定める基準に関する事項について、その審査基準を以下
のとおり定めたので公示する。
平成14年1月31日
関 東 運 輸 局 長 上 子 道 雄
東京陸運支局長 向 良一
神奈川陸運支局長 瀬 谷 憲 雄
埼玉陸運支局長 冨 田 征 弘
群馬陸運支局長 瀬 下 幸 夫
千葉陸運支局長 小 林 一 雄
茨城陸運支局長 会 田 幸 治
栃木陸運支局長 嵯 峨 康 志
山梨陸運支局長 佐 藤 市 夫
記
1.許 可(法第43条第1項)
⑴ 運送需要者
① 運送需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、実質的に単数と認められる場合はこの限りで
はない。
② 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契
約であると認められること。
⑵ 取扱客
① 一定の範囲に限定されていること。
② 需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させること
を事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること。
⑶ 路線又は営業区域
① 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
② 路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。
⑷ 公衆の利便
申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車
運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
⑸ 営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合する
ものであること。
① 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
② 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農
地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないものであること。
③ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
⑹ 事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること。
⑺ 自動車車庫
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル

191
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業
用自動車の全てを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑦ 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しない
ものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があ
り、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
⑻ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び
自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑼ 管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管
理計画があること。
③ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備される
とともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令
第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②〜⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める
子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、
事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑽ 運転者
① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
③ 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
⑾ 法令遵守
申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問
わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の①か
ら③のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)
等の違反により申請日前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の
処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となっ
た事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
② 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ケ月間及び申請日以降

192
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受け
た者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法
人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
③ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に
190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法
人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務
を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
⑿ 損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償する
ために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保
険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
ただし、公営の事業者は、この限りではない。
⒀ 申請時期
許可の申請は随時受け付けるものとする。
2.事業計画の変更の認可(法第43条第5項(法第15条準用))
⑴ 1.⑴〜⑽、⑿、⒀の定めるところに準じて審査することとする。
⑵ 事業規模の拡大となる申請については、申請者等が以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題
のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ケ月間及び申請日以降
に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人であ
る場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行
する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
② 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ケ月間及び申請日以降
に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受け
た者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法
人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
③ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に
190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法
人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務
を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
④ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便
を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にそ
の命令された事項が改善されていること。
⑤ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
⑥ 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運
転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
⑦ 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出
を適切に行っていること。
3.標準処理期間
1.については3ヶ月、2.については2ヶ月とする。
附 則

193
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1.本基準は平成14年2月1日以降に申請するものから適用する。
2.1.⑾、2.⑵①及び2.⑵②におけるタクシー業務適正化特別措置法に基づく処分には、平成14年1月31日以前の
タクシー業務適正化臨時措置法に基づく処分を含むものとする。
附 則(平成14年7月1日 一部改正)
1.この改正は平成14年7月1日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成14年6月28日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成16年7月22日 一部改正)
この改正は、平成16年8月1日以降に処分するものから適用するものとする。
附 則(平成17年5月13日 一部改正)
1.この改正は、平成17年6月1日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
附 則(平成19年7月30日 一部改正)
1.この改正は、平成19年9月10日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
3.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自
整第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っ
ている特定旅客自動車運送事業者については施行日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。
附 則(平成20年6月30日 一部改正)
1.この改正は、平成20年7月1日以降に受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。

194
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
6 旅客自動車関係の運行管理者(運送法第23条)
運行管理者は事業用自動車の運行の安全の確保に関する事項を責任をもって適正に処理しなければならず、そのために
は、専門的な知識及び経験が要求される。
A 運行管理者(運送法第23条)
事業者は事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令(運輸規則第47条の9)で定
める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
B 運行管理者資格者証(運送法第23条の2)
① 運行管理者試験に合格した者
② 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備
える者
但し、次に該当するものは資格者証の交付は受けられない。
イ 道路運送法第23条の3の命令により資格者証の返納を命じられ、返納を命ぜられた日から2年を経過していない
者は資格者証の交付は受けられない。
ロ この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は資格者
証の交付は受けられない。
●国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者(運輸規則第48条の5)
⑴ 次の表に掲げる資格者証の種類に応じ、旅客自動車運送事業の種類の事業用自動車の運行管理に関し5年以上の
実務の経験を有し、かつ、その間に国土交通大臣が認定する講習を5回以上受講した者であること。
⑵ 次の表に掲げる資格者証の種類に応じ、旅客自動車運送事業の種類の事業用自動車の運行管理に関し1年以上実
務の経験を有し、かつ、その間に国土交通大臣が告示で定める職務に2年以上従事した経験を有する者であること。
資格者証の種類1.一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
2.一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
3.一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
4.特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
旅客自動車運送事業の種類
一般乗合旅客自動車運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業一般乗合旅客自動車運送事業一般貸切旅客自動車運送事業一般乗用旅客自動車運送事業
C 運行管理者の業務(運輸規則第48条)
① 車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。(バス)
② 異常気象時等において輸送の安全確保のための措置を講ずること。
③ 国土交通大臣が告示で定める基準に従い運転者を定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成
し、これに従い乗務員を事業用自動車に乗務させること。
●国土交通告示第1675号
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準を次のように定め、平成14年2月1日から施行する。
平成13年12月3日
国土交通大臣 林 寛 子
旅客自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、運転者の労働時間等の改善が過
労防止にも資することに鑑み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)と

195
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
する。
④ 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすること
ができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
⑤ 乗務員が有効に利用することができる休憩、睡眠又は仮眠に必要な施設を適切に管理及び保守すること。
⑥ 運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができない
おそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。(バス)
⑦ 乗務しようとする運転者及び乗務を終了した運転者に対して点呼を行い、報告を求め、指示を与え、記録し、及び
その記録を1年間保存すること。
⑧ 事業用自動車の乗務員に対し乗務の記録をさせるとともに、その記録を1年間保存すること。なお、ハイタクにあっ
ては車両毎に整理して保存すること。
⑨ 運行記録計により記録しなければならない場合において、運行記録計を管理し、及びその記録を1年間保存するこ
と。なお、ハイタクにあっては、運転者ごとに整理して保存すること。
運行記録計による記録を必要とする場合
(これらはいずれも事業用自動車の運転者が乗務した場合に限る。)
・乗合バス-起点から終点までの距離が100キロメートルを超える運行系統を運行するとき。
・貸切バス-運転者が乗務したとき。
・ハイタク-運輸局長が指定した地域内にある営業所に属する運転者が乗務したとき。
⑩ 運行記録計により記録しなければならない場合において、運行記録計により記録することのできない事業用自動車
を運行の用に供さないこと。
⑪ 事業用自動車に係る事故が発生した場合は、必要な事項を記録し、事業自動車の運行を管理する営業所において3
年間保存すること。
●事故の記録事項
⑴ 乗務員の氏名
⑵ 事業自動車の登録番号、その他事業用自動車を識別できる表示
⑶ 事故の発生日時
⑷ 事故の発生場所
⑸ 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
⑹ 事故の概要(損害の程度を含む。)
⑺ 事故の原因
⑻ 再発防止対策
⑫ 運転基準図を作成して営業所に備え、これにより事業用自動車の運転者に対し、適切な指導をすること。(乗合バス)
⑬ 運行表を作成し、これを事業用自動車の運転者に携行させること。(乗合バス)
⑭ 運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適合する自動車を使用する
こと。(貸切バス)
⑮ 運行ごとに運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、これを当該運
転者に携行させ、及びその指示書を1年間保存すること。(貸切バス)
運行指示書の記載事項
・運行の開始及び終了の地点及び日時
・乗務員の氏名
・運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
・乗客が乗車する区間
・運行に際して注意を要する箇所の位置
・乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)

196
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
・乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
・睡眠に必要な施設の名称及び位置
・運送契約の相手方の氏名又は名称
・その他運行の安全を確保するために必要な事項
⑯ 運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
⑰ 運転者ごとに必要な事項を記載し写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、運転者の属する営業所に備
えて置かなければならない。
●運転者台帳に記載すべき事項
⑴ 作成番号及び作成年月日
⑵ 事業者の氏名又は名称
⑶ 運転者の氏名、生年月日及び住所
⑷ 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
⑸ 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許に関する事項
・運転免許証の番号及び有効期限
・運転免許証の年月日及び種類
・運転免許証に条件が付されている場合は、当該条件
⑹ 事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
⑺ 運転者の健康状態
⑻ 死者又は負傷者が生じる事故を引き起こした者・運転者として新たに雇い入れた者・高齢者に対し、国土交通
大臣が告示で定める特別な指導の実施及び国土交通大臣が認定する適性診断の受診の状況
⑼ 乗務員台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真。なお、ハイタクの運転
者にあっては、縦2.4㎝以上、横3.6㎝以上の大きさの写真
⑱ 事業用自動車に運転者が乗務する場合には、次号の規定により運転者証を表示するときを除き、乗務員証を携行さ
せ及びその者が乗務を終了したときは返還させること。(ハイタク)
⑲ 事業用自動車に運転者が乗務する場合には、運転者証を表示させ、その者が乗務を終了した場合には運転者証を保
管して置くこと。(ハイタク)
⑳ 事業用自動車の乗務員に対し国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状
態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項、乗務員の服務、非常信
号用具の取扱い方等について適切な指導監督をしなければならない。
また、次の者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならない。
⑴ 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又は第4号に
掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
⑵ 運転者として新たに雇い入れた者
⑶ 高齢者(65才以上の者をいう。)
� 事業用自動車に非常信号用具を備え付けること。
� 選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
� 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件を備えない者に事業用自動車を運転させないこと。
� 自動車事故報告規則第5条の規定により事故警報が発せられた場合には、その事故警報に定められた事故防止対策
に基づき事業用自動車の運行の安全の確保に関し、従業員を指導及び監督すること。
以上のことは、事業用自動車の運行の安全を確保するために運行管理者の職務及び権限として与えるべき事項を定めた
ものである。したがって、これらの事項を適確に処理する処理基準としての運行管理規程を定め、これに基づいて運行管
理者は職務を確実に遂行しなければならない。

197
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
事業の種類1.一般乗合旅客自動車運 送事業
2.一般貸切旅客自 動車運送事業
3.一般乗用旅客自 動車運送事業
4.特定旅客自動車運送事 業
運行管理者の選任が必要な営業所
乗車定員11人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所、乗車定員10人以下の事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所
事業用自動車の運行を管理する営業所
事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所
乗車定員11人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所、乗車定員10人以下の事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所
資格者証の種類
旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は左記の運行管理者資格者証、特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
選任すべき運行管理者の数
営業所が運行を管理する事業用自動車の数を40で除して得た数※に1を加算して得た数
営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数※に1を加算して得た数
営業所が運行を管理する事業用自動車の数を40で除して得た数※に1を加算して得た数
営業所が運行を管理する事業用自動車の数を40で除して得た数※に1を加算して得た数
※:除して、1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
② ①の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、それらの業務を統括する運行管理者を選任しなければ
ならない。
E 運行管理者の選任等の届出(運輸規則第68条)
運行管理者を新たに選任したとき、変更したとき及びすでに届出されている運行管理者が当該営業所の運行管理者で
なくなったときは、当該届出事由の発生した日から15日以内に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又
は運輸支局長に届け出なければならない。
選任(解任)届
⑴ 届出者の氏名、又は名称及び住所
⑵ 事業の種類
⑶ 営業所の名称及び位置
⑷ 選任又は解任の年月日
⑸ 運行管理者の氏名及び生年月日
⑹ 資格者証の番号及び交付年月日
⑺ 選任の場合にあっては、運行管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務の内容)
⒜ 選任届
① 既設の営業所において運行管理者を新しく選任したとき。
② 営業所を新設し運行管理者を選任したとき。
③ 運行管理者を増員したとき。
⒝ 選任・解任届
① 人事異動等で運行管理者が変わったとき。
⒞ 解任届
① 営業所を廃止したとき。
② 選任されている運行管理者が転勤、又は退職等により欠員で、後任の運行管理者を選任しないとき。
D 運行管理者等の選任(運輸規則第47条の9)
① 次の表の第一欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれの第二欄に掲げる営業所ごとに第三欄の運行管理者資格者証
を有する者の中から、第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。

198
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
F 運行管理者の研修(運輸規則第48条の4)
運輸監理部長又は運輸支局長から運行管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、運行管理者に研修を受け
させなければならない。

199
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
7 貨物自動車関係の運行管理者(貨物運送法第18条)
運行管理者は事業用自動車の運行の安全の確保に関する事項を責任をもって適正に処理しなければならず、そのために
は、専門的な知識及び経験が要求される。
A 運行管理者(貨物自動車運送事業法第18条)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定め
るところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
B 運行管理者資格者証の交付(貨物自動車運送事業法第19条)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
1.運行管理者試験に合格した者
2.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を
備える者
2.国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の
交付を行わないことができる。
1.次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者
2.この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3.運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
C 運行管理者の業務(安全規則第20条)
① 運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
② 乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
③ 国土交通大臣が告示で定める基準に従い運転者を定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成
し、これに従い乗務員を事業用自動車に乗務させること。
●国土交通告示第1365号
貨物自動車運送輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第3条第4項の規定に基づき、事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準を次のように定め、平成13年9月1日から施行する。
平成13年8月20日
国土交通大臣 林 寛 子
貨物自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、運転者の労働時間等の改善が過
労防止にも資することに鑑み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)と
する。
④ 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすること
ができないおそれのある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
⑤ 運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができない
おそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
⑥ 過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を行うこと。
⑦ 事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載するとともに、貨物が運搬中に荷崩れ等によ
り落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等について従業員に対し指導及び監督を行う
こと。
⑧ 乗務しようとする運転者及び乗務を終了した運転者に対し点呼を行い、報告を求め、及び適切な指示をあたえ、並

200
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
びに記録をし、その記録を1年間保存すること。
⑨ 事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに記録させ、その記録を1年間保存する
こと。
⑩ 運行記録計により記録しなければならない場合において、運行記録計を管理し及びその記録を1年間保存すること。
運行記録計による記録を必要とする場合(これらはいずれも事業用自動車の運転者が乗務した場合に限る。)
ア 普通トラックで車両総重量が8トン以上、又は最大積載量が5トン以上のもの及びこれらの車両をけん引するけ
ん引自動車を運行するとき。
イ 特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車。
⑪ 運行記録計により記録しなければならない場合において、運行記録計により記録することのできない事業用自動車
を運行の用に供さないこと。
⑫ 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、必要な事項を記録し及びその記録を事業用自動車の運行を管理する
営業所において、3年間保存すること。
●事故の記録事項
⑴ 乗務員の氏名
⑵ 事業用自動車の登録番号、その他事業用自動車を識別できる表示
⑶ 事故の発生日時
⑷ 事故の発生場所
⑸ 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
⑹ 事故の概要(損害の程度を含む。)
⑺ 事故の原因
⑻ 再発防止対策
⑬ 乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行ごとに運行指示書を作成し、これに
より運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者に携行させ、及びその運行指示書を1年間保存する
こと。
●運転指示書に記載すべき事項
⑴ 運行の開始及び終了の地点及び日時
⑵ 乗務員の氏名
⑶ 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
⑷ 運行に際して注意を要する箇所の位置
⑸ 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
⑹ 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
⑺ その他運行の安全を確保するために必要な事項
⑭ 運転者ごとに必要な事項を記載し写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、運転者の属する営業所に備
えて置かなければならない。
●運転者台帳に記載すべき事項
⑴ 作成番号及び作成年月日
⑵ 事業者の氏名又は名称
⑶ 運転者の氏名、生年月日及び住所
⑷ 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
⑸ 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許に関する事項
・運転免許証の番号及び有効期限
・運転免許証の年月日及び種類
・運転免許証に条件が付されている場合は、当該条件

201
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑹ 事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
⑺ 運転者の健康状態
⑻ 死者又は負傷者が生じる事故を引き起こした者・運転者として新たに雇い入れた者・高齢者に対し、国土交通
大臣が告示で定める特別な指導の実施及び国土交通大臣が認定する適性診断の受診の状況
⑼ 乗務員台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真
⑮ 事業用自動車の乗務員に対し国土交通大臣が告示で定めるところにより、貨物自動車運送事業に係る主な道路の状
況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必
要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関する遵守すべき事項、乗務員の服務、非常信号用具の取扱い方等
について適切な指導監督をしなければならない。
また、次の者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならない。
⑴ 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又は第4号に掲
げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
⑵ 運転者として新たに雇い入れた者
⑶ 高齢者(65才以上の者をいう。)
⑯ 異常気象時等において輸送の安全確保のための措置を講ずること。
⑰ 選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
⑱ 自動車事故報告規則第5条の規定により事故警報が発せられた場合には、その事故警報に定められた事故防止対策
に基づき、事業用自動車の運行の安全確保について従業員に対する、指導監督を行うこと。
⑲ 特別積合せ貨物運送に係る運行系統にあっては乗務基準を定め、これらの基準の遵守について乗務員に対し適切な
指導監督を行うこと。
⑳ 運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について
助言を行うことができる。
以上のことは、事業用自動車の運行の安全を確保するために運行管理者の職務及び権限として与えるべき事項を定めた
ものである。したがって、これらの事項を適確に処理する処理基準としての運行管理規程を定め、これに基づいて運行管
理者は職務を確実に遂行しなければならない。
D 運行管理者等の選任(安全規則第18条)
① 営業所ごとに事業用自動車の台数に応じて一定の数以上の運行管理者を選任しなければならない。運行管理者の選
任数を表にまとめると次のとおりである。
なお、本条の趣旨からして、運行管理者は他の営業所の運行管理者を兼務することはできない。
事業用自動車の両数(被けん引車は除く) 運行管理者数
29両まで(運行車+運行車以外)1人
5両以上29両まで(運行車以外)
30両〜 59両(運行車+運行車以外) 2人
60両〜 89両( 〃 ) 3人
90両〜119両( 〃 ) 4人
120両〜149両( 〃 ) 5人
150両〜179両( 〃 ) 6人
180両〜209両( 〃 ) 7人
210両〜239両( 〃 ) 8人
運行管理者の選任を必要とする営業所

202
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
② ①の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、それらの業務を統括する運行管理者を選任しなければ
ならない。
E 運行管理者の選任(解任)の届出(安全規則第19条)
運行管理者を新たに選任したとき、変更したとき及びすでに届出されている運行管理者が当該営業所の運行管理者で
なくなったときは、当該届出事由の発生後遅滞なく次に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸
支局長に届け出なければならない。
選任(解任)届
⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑵ 貨物自動車運送事業の種類
⑶ 運行管理者の氏名及び生年月日
⑷ 運行管理者が交付を受けている運行管理者資格者証の番号及び交付年月日
⑸ 選任する場合、運行管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場
合は、その職名及び職務内容)
⑹ 運行管理者でなくなった場合にあっては、その理由
F 運行管理者の研修(安全規則第23条)
運輸監理部長又は運輸支局長から運行管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、運行管理者に研修を受け
させなければならない。

203
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
8 整備管理者A 整備管理者(車両法第50条)
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及
び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める
自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験
その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
事業の種 類
自動車の種類 整備管理者の選任を要する使用の本拠
事
業
用
●バス 乗車定員11人以上
自動車の使用の本拠ごと
●トラック・ハイタク 乗車定員10人以下
5両以上の使用の本拠ごと
自
家
用
●バス 乗車定員11人以上
●乗車定員30人以上は1両以上の使用の本拠ごと●乗車定員11人以上29人以下は2両以上
●大型トラック (車両総重量8トン以上)
5両以上の使用の本拠ごと
レンタカー及び貨物軽自
動車運送事業者
●バス 乗車定員11人以上
自動車の使用の本拠ごと
●大型トラック (車両総重量8トン以上)
5両以上の使用の本拠ごと
●その他の自動車 乗車定員10人以下 車両総重量8トン未満
10両以上の使用の本拠ごと
整備管理者の選任を必要とする使用者
B 整備管理者の資格(車両法施行規則第31条の4)
1.次のいずれかに該当する者でなければ、整備管理者になることができない。
① 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の
経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
② 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検
定に合格した者であること。
③ 前2号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。
2.車両法若しくは車両法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、車両法第53条の規定に基づく解任命令によ
り解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることができない。
C 整備管理者の権限(車両法施行規則第32条)
1.整備管理者に与えなければならない権限は次のとおりです。
① 車両法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
② 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
③ 車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
④ 日常点検及び定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
⑤ 日常点検、定期点検又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
⑥ 定期点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
⑦ 車両法第49条第1項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

204
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑧ 自動車車庫を管理すること。
⑨ 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
2.整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければ
ならない。
D 整備管理者の選任届等(車両法第52条、車両法施規第33条)
1.整備管理者の選任を必要とする使用者において整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局
長(運輸支局を経由して)にその旨を届出なければならない。これを変更したときも同様である。
2.整備管理者選任届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(車両法施規第33条)
① 届出者の氏名又は名称及び住所
② 届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
③ 整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
④ 車両法施行規則第31条の3各号に掲げる自動車の数
⑤ 整備管理者の氏名及び生年月日
⑥ 車両法施行規則第31条の4各号(整備管理者の資格)のうち前号の者が該当するもの
⑦ 整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合はその職名及び職務の内容)
3.届出書には整備管理者の資格(車両法施行規則第31条の4)に該当することを信じさせるに足る書面を添付しなけ
ればならない。
E 整備管理者の研修(運輸規則第46条、安全規則第15条)
旅客及び貨物自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第50条の規定により選任した整備管理者につい
て研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。

205
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
9 重大事故の報告(道路運送法第29条、貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則)
自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者又は整備管理者を選任する義務のある自家用自動車の使用者は、その使用す
る自動車が次の事故(重大事故といっている)を引き起した場合には、運輸監理部長又は運輸支局長を経由して国土交通
大臣に報告する義務があります。
A 報告を必要とする事故(重大事故)(自動車事故報告規則第2条)
次のいずれかに該当する事故
1.自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道事故(軌道車両を含む。
以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの。
2.10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの。
3.死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を
受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの。
4.10人以上の負傷者を生じたもの。
5.自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの。
6.自動車に積載されたコンテナが落下したもの。
7.操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第
4号に掲げる傷害が生じたもの。
8.酒気帯び運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無
免許運転(同法第64条の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第85条第5項から第9項まで
の規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第117条の2第3号の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの。
9.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
10.救護義務違反(道路交通法第117条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があったもの。
11.自動車の装置(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故
障」という。)により、自動車が運行できなくなったもの。
12.車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)。
13.橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大
正10年法律第76号)による軌道施設を含む。)を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの。
14.高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。)又
は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)にお
いて、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの。
15.前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示し
たもの。
B 報告書の提出(自動車事故報告規則第3条)
旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、特定第二種貨物利用
運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自
家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用自動車にあっては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自
動車を除く。)について事故があった場合には、30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書三通を当該自動車の使
用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
C 事故速報(自動車事故報告規則第4条)
前記Aの1、3、4、5、8に該当する事故が生じた場合、又は国土交通大臣の指示があったときは、前記Bによる

206
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を
運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければなりません。
第5条(保険会社の仮渡金の金額) 法第17条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者、又は傷害を受けた者1人に付き、次のとおりとする。 1.死亡した者 290万円 2.次の傷害を受けた者 40万円 ア 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの イ 上腕、又は前腕の骨折で合併症を有するもの ウ 大腿、又は下腿の骨折 エ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの オ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの 3.次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 20万円 ア 脊柱の骨折 イ 上腕、又は前腕の骨折 ウ 内臓の破裂 エ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの オ 14日以上病院に入院することを要する傷害 4.11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受 けた者 5万円
〔自動車損害賠償保障法施行令抜すい〕

207
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
� 貨物利用運送事業法(利用運送法)
この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者の行
う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送を利用してする貨物の運送をいう。
利用運送事業……他人(荷主)の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業をいう。運送事業者の行う運送(実運送
に係るものに限る)を利用してする貨物の運送をいい、
荷主より運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負う事業であります。
また、利用運送事業は、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」とに区分されます。
第一種貨物利用運送事業……他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業
以外の事業
第二種貨物利用運送事業……他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の
行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨
物の集荷及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業
第一種貨物利用運送事業
◎登録の申請(利用運送法第4条)
利用運送事業を経営しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出するものとする。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
3.事業の経営上使用する商号があるときはその商号
4.利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲
◎添付書類
1.次に掲げる事項を記載した事業の計画
ア 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
イ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ウ その他事業の計画の内容として必要な事項
2.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
3.貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
4.既存の法人の場合
ア 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
イ 最近の事業年度における貸借対照表
ウ 役員又は社員の名簿及び履歴書
5.法人を設立しようとする場合
ア 定款又は寄附行為の謄本
イ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ウ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込
みを記載した書類
6.個人の場合
ア 財産に関する調書
イ 戸籍抄本
ウ 履歴書
7.欠格事由のいずれにも該当しない旨を証する書類

208
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
◎登録の拒否(利用運送法第6条)
国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒
否しなければならない。
1.1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を
経過しない者
2.第二種貨物利用運送事業の許可又は第一種貨物利用運送事業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を
経過しない者
3.申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
5.その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
6.その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

209
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
� 貨物軽自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第36条、貨物自動車運送事業法施規第33条)
貨物軽自動車運送事業の経営の届け出をしようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事
業経営届出書を運輸支局長に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.事業の開始の予定日
3.次に掲げる事項を記載した事業計画
ア 主たる事務所の名称及び位置
イ 営業所の名称及び位置
ウ 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く)又は二輪の自動
車の別をいう。)及び事業用自動車の種別ごとの数
エ 自動車車庫の位置及び収容能力
オ 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
カ 事業用自動車の運行管理の体制
キ 自動車車庫の使用権限を有する旨の宣誓
ク 自動車車庫について、都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓
4.運送約款

210
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
� 自家用自動車の貸渡の許可申請(運送法第80条第2項)
公 示
自家用自動車の有償貸渡しの許可基準について
自家用自動車の有償貸渡しの許可申請について、事案の迅速かつ適正な処理を図るため、道路運送法施行規則第52条の
規定に基づくほか、その審査基準等を下記のとおり定めたので公示する。
平成18年3月31日
関東運輸局 運輸支局長
記
1.許可基準について
許可は、次の点について審査のうえ行うこととする。
① 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
ア 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特
定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していな
い者であるとき。
ウ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合にお
いて、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき。
エ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと
同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。
② 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているもの
ではないこと。
③ 貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車種区分によることとする。
ア 自家用乗用車
イ 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7ⅿ以下の車両に限る。
ウ 自家用トラック
エ 特種用途自動車
オ 二輪車
なお、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、3.の要件を満たさなければならない。
④ 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものである
こと。
ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
2.許可に対する条件
許可には、次の条件を付することとする。
⑴ 次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならな
い。
ア 貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ 法人の役員

211
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
ウ 貸渡料金及び貸渡約款
⑵ 貸渡自動車の増車若しくは代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)又は事務所
の名称若しくは所在地の変更をしようとする者は、あらかじめ、当該貸渡自動車の車種別の数、配置事務所等又は変
更後の事務所の名称若しくは所在地を当該車両の配置事務所又は当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長に主たる
事務所に係る許可証の写し(当該運輸支局長の許可を受けている場合を除く。)を添えて、届け出なければならない。
⑶ 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7ⅿを超える車両に限る。)及び霊柩車の貸渡しを行ってはならない。
⑷ 自家用マイクロバス(乗車定員が29人以下であり、かつ車両長が7ⅿ以下の車両に限る。)の貸渡しを行う場合は、3.
の要件を満たさなければならない。
⑸ 許可時においてレンタカー型カーシェアリング(会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸
渡すことをいう。以下同じ。)を次に例示する環境に配慮した車両を使用して行う場合に、貸渡し開始後に車両を代
替し、例示した車両を使用せず当該貸渡しを継続しようとする場合にあっては、アイドリングストップの励行等エコ
ドライブについて会員に研修・啓蒙を行う実施計画を届出なければならない。
(想定される環境に配慮した車両)
・天然ガス自動車(CNG自動車)
・電気自動車
・ハイブリッド車
・メタノール自動車
・低燃費かつ低排出認定車
・アイドリング・ストップ車
⑹ レンタカー型カーシェアリングを環境に配慮した車両を使用して行っている、又はレンタカー型カーシェアリング
でアイドリング・ストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行っている(以下、「環境型カーシェ
アリング」という。以下同じ。)場合、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地の変更をしようとする場合は、あらか
じめ、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届けなければならない。
⑺ 許可を受けた者が新たに環境型カーシェアリングを行おうとする場合は、あらかじめ、当該貸渡自動車の配置事務
所の所在地について、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。
⑻ 「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について」(平成16年3月16日付け国自旅第234号)によ
り運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)を行っ
てはならず、その旨を事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。
⑼ 自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させてはならない。
⑽ 貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。
⑾ 貸渡自動車がその配置事務所に存するか、それ以外の事務所に一時的に存するかにかかわらず、当該配置事務所に
おいて貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理を実施しなければならない。
なお、環境型カーシェアリングを行う場合であって、IT等の活用により車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状
況を適確に把握することが可能であると認められるときには、この限りでない。
⑿ 別記1の事項を記載する貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存しな
ければならない。
⒀ 環境型カーシェアリングを行う場合であって、IT等の活用により車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況を適
確に把握することが可能である場合を除き、借受人には、別記2の事項を記載した貸渡証を交付し、貸渡自動車の運
転者にこれを携行するように指示しなければならない。
⒁ 前年の4月1日から3月31日までの期間に係る別記様式の「貸渡実績報告書」並びに前年度の6月30日、9月30日、
12月31日及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を
管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。
⒂ 貸渡人が道路運送法、貨物自動車運送事業法及び道路運送車両法並びに本条件に違反したときは、貸渡自動車の貸

212
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
渡しを停止させ、又は許可を取り消すことがある。
⒃ 貸渡しの廃止をしたときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。
3.自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例
自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとし、自家用マイクロバスの貸渡しを行お
うとする者は、その7日前までに、車両毎に、その旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出
なければならないこととする。なお、既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者が当該届出を行う際には、原則
として、直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写しを添付又は提示することとする。
① 現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上
の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
② 既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受け
ていないこと。
附 則
1.本公示は、平成18年4月1日以降の申請より適用する。
2.平成16年5月13日付け第 号で公示した「自家用自動車の有償貸渡しの許可基準について」は、平成18年3月31日
限りで廃止する。
3.本公示が適用される以前の基準により既に許可を受けている者については、主たる事務所の所在地を管轄する運輸
支局長から最初に受けた許可を本公示による許可とみなす。
4.本公示に基づく許可申請等の記載事項及び添付書類は、別に定める「自家用自動車有償貸渡許可申請等手続細則」
によることとする。
〔別記1〕
貸渡簿(貸渡原票を綴ったものによって、貸渡簿に代えることができる。)の記載事項については、次のとおりとする。
ア 借受人の氏名又は名称及び住所
イ 運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号(運転免許証の写しの添付により代えることができる。)
ウ 貸渡自動車の登録番号又は車両番号
エ 貸渡日時及び時間
オ 貸渡事務所、返還事務所
カ 運行区間又は行先及び利用者人数並びに使用目的(自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合に限る。)
キ 走行キロ数
ク 貸渡料金
ケ 事故に関する事項
〔別記2〕
貸渡証の記載事項については、次のとおりとする。
ア 借受人の氏名又は名称及び住所
イ 運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号(運転免許証の写しの添付により代えることができる。)
ウ 貸渡自動車の登録番号又は車両番号
エ 貸渡日時及び時間
オ 貸渡事務所、返還事務所
カ 貸渡人の氏名又は名称及び住所
キ 次の遵守事項
ア 「運行中必ず携帯し、警察官又は地方運輸局若しくは運輸支局の職員の請求があったときは、呈示しなければな
らない」旨の記載

213
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
イ 「自動車の借受けに付随して、貸渡人から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む。)を受けることがで
きない」旨の記載
ウ 貸渡自動車に係る事故及び故障等が発生した場合の処置(処置方法、連絡先等)に関する記載
エ 「貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検を借受人が実施することとなる」旨の記載

214
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
運輸
支局
名事
務所
数区
分車
両
数
延貸
渡回
数延
貸渡
日車
数延
走行
キロ
総貸
渡料
金
乗用
車(
うち
軽自
動車
)
マイ
クロ
バス
トラ
ック
(う
ち軽
自動
車)
特種
用途
車(
うち
軽自
動車
)
二輪
車(
うち
軽二
輪車
)
合
計
貸 渡 実 績 報 告 書(平成 年度)
年
4月
1日
から
年
3月
31日
まで
(
)運
輸支
局長
あ
て
事業
者名
住
所
代表
者名
電話
番号

215
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
事務所別車種別配置車両数一覧表
(平
成
年
度第
四
半期
分)
運輸
支局
長
殿
氏名
又は
名称
平成
年
月
日
代表
者名
運輸
支局
名事
務所
数所
在
地
乗用
車マ
イク
ロバ
スト
ラッ
ク特
種車
二輪
車合
計
小
計
小
計
合
計
1
.こ
の報
告書
は、
毎年
度四
半期
(6
、9
、12
、3
月末
現在
)毎
に別
葉で
作成
する
こと
2
.事
務所
名小
計欄
は、
運輸
支局
の管
轄区
域別
に配
置す
る自
動車
の総
数を
記載
する
こと
3
.下
段は
軽自
動車
数を
記載
する
こと
別
記
様
式
住
所

216
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
自家用自動車有償貸渡許可申請等手続細則
平成18年3月31日
自家用自動車の有償貸渡しの許可申請についての取扱いは、平成18年3月31日付公示「自家用自動車の有償貸渡の許可
基準について」によるほか、下記によることとする。
記
1.許可申請
⑴ 申請書の記載事項
申請様式例によるものとする。
⑵ 添付書類
① 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
② 会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿とする。)
③ 申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする。)の欠格事由に該当しない旨の確認書(様式例1)
④ 事務所別車種別配置車両数一覧表(様式例2)
⑤ 以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画(様式例3)
ア 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
1)事務所ごとに配置する責任者
2)従業員への指導・研修の計画等
イ 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
ウ その他貸渡しの適正化を図るための計画
1)保険の加入状況・加入計画
2)整備管理者(整備責任者)の配置計画等
⑥ レンタカー型カーシェアリング(会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをい
う。以下同じ。)を環境に配慮した車両を使用して行う場合には、⑵①〜⑤以外に次に掲げる書類を添付するもの
とする。
ア 当該貸渡自動車の車名及び型式
イ アの自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
ウ イの保管場所を管理する事務所の所在地
エ IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
オ 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
カ 会員規約又は契約書
キ ⑦に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に
研修・啓蒙を行う実施計画。
⑦ ⑥の場合において、対象となる貸渡自動車は以下のとおりとする。
想定される車両
・天然ガス自動車(CNG自動車)
・電気自動車
・ハイブリッド車
・メタノール自動車
・低燃費かつ低排出認定車
・アイドリング・ストップ車

217
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
⑶ 変更届の記載事項
届出様式例1によるものとする。
⑷ 廃止届の記載事項
届出様式例2によるものとする。
附 則
1.この細則は、平成18年4月1日以降の申請より適用する。
2.平成16年5月31日付東運輸第590号「自家用自動車有償貸渡許可申請手続細則」は、平成18年3月31日限りこれを
廃止する。
届 出 事 項 添 付 書 類
増 車 ・様式例4(事務所別車種別配置車両数新旧対照表)・許可書の写し(他支局における許可事業者に限る)・直近2年間の自家用マイクロバスの貸渡簿の写し (自家用マイクロバスの増車に限る)
代 替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴う場合)
・様式例4(事務所別車種別配置車両数新旧対照表)・許可書の写し(他支局における許可事業者に限る)
事務所の名称及び所在地 ・許可書の写し(他支局における許可事業者に限る)
※自家用マイクロバスの増車にあっては、その7日前までに、車両毎に当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出るものとする。
⑵ 事後届出
以下の表の左欄に掲げる事項について変更したときは、右欄に掲げる書類を添えて遅滞なく届け出るものとする。
届 出 事 項 添 付 書 類
貸渡人の氏名又は名称及び住所 無し
法人の役員 様式例1(欠格事由に該当しない旨の確認書)
貸渡料金及び貸渡約款 変更後の貸渡料金表及び変更後の貸渡約款
貸渡しの廃止 無し
2.変更届出
⑴ 事前届出
以下の表の左欄に掲げる事項について変更したときは、右欄に掲げる書類を添えて※あらかじめ届け出るものとする。

218
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
自 家 用 自 動 車 有 償 貸 渡 許 可 申 請 書
事 務 所 の 名 称 所 在 地
自家用自動車有償貸渡しを下記のとおり行いたいので、道路運送法第80条第2項及び同法施行規則第52条の規定により
関係書類を添えて申請いたします。
記
申請様式例
平成 年 月 日
運輸局 運輸支局長 殿
住 所
氏名又は名称 ㊞
代 表 者 名
1.貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の役職・氏名
2.貸渡人の事務所の名称及び所在地
3.貸渡しの実施計画
貸渡約款に定められたもののほか、別添のとおり実施する。
4.貸渡しを必要とする理由

219
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
添付書類
1.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
2.会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿)
3.確認書(欠格事由)
4.事務所別車種別配置車両数一覧表
5.貸渡しの実施計画
〔レンタカー型カーシェアリング〕
上記1.〜5.の他
6.カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
7.6.の自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
8.7.の保管場所を管理する事務所の所在地
9.IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
10.車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
11.会員規約又は契約書
12.「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日
付け自旅第138号)2.⑸②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画

220
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
確 認 書
様式例1
運輸局 運輸支局長 殿
平成 年 月 日
氏 名 ㊞
① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経
過していない者。
② 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家
用自動車の有償貸渡しの許可の取り消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者。
③ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記
①及び②に該当する者。
④ 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により、処分を受けている者。
私は、以上の項目に該当しないものであることを確認致します。

221
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
事務所名 所 在 地配 置 車 両 数
乗 用 マイクロ トラック 特 種 二 輪 合 計
合 計
※下段は軽自動車を記載
様式例2
○事務所別車種別配置車両数一覧表

222
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
様式例3
貸渡しの実施計画
⑴ 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
① 事務所ごとに配置する責任者
② 従業員への指導・研修の計画等
・新規採用の従業員に対して、自動車運送事業類似行為防止を図るための道路運送法関係法令の研修を行うとともに、
毎年1回責任者から全従業員に対して講習を行うこととする。
・自動車運送事業類似行為防止を図るための小冊子を作成し、全従業員に配布する。
⑵ 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
貸渡しに際しては、「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について」(平成16年3月16日付け国
自旅第234号)の趣旨を徹底し、運転者に係る情報提供を行う場合には、その適正化に努めることとする。
⑶ その他貸渡しの適正化を図るための計画
① 保険の加入状況・加入計画
貸渡しを行う車両の全てについて、次の任意保険(共済)に加入する。
事 務 所 名 役 職 氏 名
保 険 内 訳 補 償 金 額 保 険 会 社 名
対 人 保 険 万円
対 物 保 険 万円 (免責額 万円)
搭乗者保険 万円
② 整備管理者(整備責任者)の配置計画 等
事 務 所 名 氏 名 資格の有無
有 ・ 無
有 ・ 無

223
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1.貸渡人の氏名又は名称 2.貸渡人の住所 3.法人の役員
4.事務所の名称 5.事務所の所在地 6.事務所の新設・廃止
7.貸渡料金 8.貸渡約款 9.増車(※マイクロバス・その他)
10.代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴うもの)
自 家 用 自 動 車 の 有 償 貸 渡 し に 係 る 届 出 書
届出様式例1
平成 年 月 日
運輸局 運輸支局長 殿
住 所
氏名又は名称 ㊞
代 表 者 名
連 絡 先
自家用自動車の貸渡しについて、下記のとおり変更���
するした
���
のでお届けします。
記
1.貸渡人の氏名又は名称及び住所
2.変更事項(該当番号を○印すること。)
3.変更事項の新旧(新設・役員増員・増車は「新」欄のみ、役員減員・廃止は「旧」欄のみ記入。)
番号 新 旧
※マイクロバスの増車届出については、「5.確認事項」について記載のこと。
4.変更年月日
平成 年 月 日

224
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
5.確認事項(マイクロバスの増車届出についてのみ記載。)
・他車種におけるレンタカー事業当初開始年月日(平成 年 月 日)
※新たなマイクロバスを導入する場合
・理 由
添付書類
1.貸渡人の氏名または名称(添付書類なし)
2.貸渡人の住所(添付書類なし)
3.法人の役員:欠格事由に該当しない旨の確認書
4.貸渡人の事務所の名称:許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
5.貸渡人の事務所の所在地:許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
6.事務所の新設・廃止:許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
7.貸渡料金:変更後の貸渡料金
8.貸渡約款:変更後の貸渡約款
9.増車:① 事務所別車種別配置車両数新旧対照表
② 許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
③ 直近2年間の自家用マイクロバスの貸渡簿の写し(マイクロバスの増車に限る)
10.代替(事務所別車種別配置車両数の変更を伴うもの)
① 事務所別車種別配置車両数新旧対照表
② 許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)

225
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
自 家 用 自 動 車 の 有 償 貸 渡 し の 廃 止 届
自家用自動車有償貸渡しを下記のとおり廃止したので、お届けいたします。
記
届出様式例2
平成 年 月 日
運輸局 運輸支局長 殿
住 所
氏名又は名称 ㊞
代 表 者 名
1.貸渡人の氏名又は名称及び住所
2.廃止年月日
平成 年 月 日
3.有償貸渡しを廃止した理由

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
Ⅲ 自動車の諸税早わかり

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

229
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1 自動車重量税(重量税法 昭和46年法律第89号)
自動車重量税は、道路整備をはじめとする交通政策上の所要の施策のための財源を求めるため設けられた目的税で、国
税である。自動車の使用者はその重量に応じて課税される。
1 納税義務者(重量税法第4条)
⑴ 自動車検査証、及び軽自動車届出済証の使用者欄に記載される使用者は納税義務者となる。
⑵ 同一自動車を2人以上で使用し、使用者欄に連名で記載されている使用者は連帯納税義務を負う。
⑶ 自動車の所有者と使用者が異なる場合には、所有者は連帯して納税義務を負う。但し、次の場合を除く。
a 所有権を留保している売買における場合の所有者
b 譲渡により担保の目的となっている場合の所有者
2 課税対象車(重量税法第3条)
検査自動車、及び届出軽自動車
3 非課税及び車両総重量のないものとされている自動車 (重量税法第5条、同法施行令第2条、同法施行規則第1条、第2条)
1.非課税自動車
⑴ 大型特殊自動車
⑵ 昭和49年4月30日までに車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車、及び使用の届出の際に軽自動車届出済証返
納証明書等の添付された届出軽自動車
⑶ 臨時検査の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間が延長されない自動車
2.車両総重量のないものとされる自動車の例
セミトレーラ
バンセミトレーラ
ダンプセミトレーラ
コンテナセミトレーラ
ドリー付トレーラ等(ただし非課税自動車によりけん引される場合を除く。)
4 納付時期及びその他(重量税法第8条、第9条、第13条、第14条、第16条、同法施行令第8条)
ア 納付時期、及び方法
新規、又は継続等の検査、及び使用の届出をした場合は、自動車検査証の交付、又は返付、及び車両番号の指定を
受けるときまでに自動車重量税印紙を所定の納付書に貼付して提出する。
イ 納付の不足の場合
運輸支局長は、自動車検査証の交付等の後又は車両番号の指定後において、検査又は車両番号の指定を受けた者が
納付した重量税額に不足がある場合、自動車重量税認定通知書により通知を行う。
また、納付期限後までに納付の事実がない場合には、納付すべき者の納税地の所轄税務署長に対し、自動車重量税
納付不足額通知書により通知する。
ウ 納税者は過誤納の事実を知ったときは、過誤納のあった日から1年以内にその事実を確認する運輸支局長の証明書
(自動車重量税過誤納証明書)の交付を自動車重量税過誤納証明書交付請求書により受けることができ、又運輸支局
長が過誤納の事実を知ったときは納税者に通知(自動車重量税過誤納通知証明書)することとされている。
納税者はこの証明書、又は通知書を住所地の所轄税務署長に提出し還付を受けることになる。

230
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
自動車重量税の廃車還付制度について
自動車重量税の廃車還付制度の創設
使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期限内に使用済みとなり、使
用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設
けられました。
平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引渡した使用済自動車から適用になります。
還付を受けるための手続
使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引渡し、その後、
ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた時に、運輸支局等において行う解体を事由と
する永久抹消登録申請又は解体届と同時に還付申請をすることとなります。
申請様式
【登録自動車に係る還付申請の関係様式】
自動車重量税還付申請書付表2(氏名又は名称のオーバーフロー、住所コードの設定のない場合用)
自動車重量税還付申請書付表3(共同所有の場合用)
還付申請手続きに関する委任状
還付金の受領権限に関する委任状
【軽自動車に係る還付申請の関係様式】
自動車重量税還付申請書付表2(氏名又は名称のオーバーフロー、住所コードの設定のない場合用)
自動車重量税還付申請書付表3(共同所有の場合用)
還付申請手続きに関する委任状
還付金の受領権限に関する委任状
(ご注意)
自動車重量税還付申請書は、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式となっており、これらの手続きと
同時に還付申請を行うことになります。したがって、同様式については、これらの手続を行う運輸支局等に近接する関係
団体の窓口で入手することができます。

231
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
5 税率表(重量税法第7条、租税特別措置法第90条の11)
自動車重量税・税率早見表
乗 用(定員10人以下)
3 年 2 年 1 年
自家用 自家用 自家用 事業用
0.5t以下
(5,000) 千円
⑶ 15.0(5,000) 千円
⑵ 10.0(5,000) 千円
⑴ 5.0千円
2.7
〜1 ⑹ 30.0 ⑷ 20.0 ⑵ 10.0 5.4
〜1.5 ⑼ 45.0 ⑹ 30.0 ⑶ 15.0 8.1
〜2 ⑿ 60.0 ⑻ 40.0 ⑷ 20.0 10.8
〜2.5 ⒂ 75.0 ⑽ 50.0 ⑸ 25.0 13.5
〜3 ⒅ 90.0 ⑿ 60.0 ⑹ 30.0 16.2
特 種 用 途
2 年 1 年
自家用 事業用 自家用 事業用
1t以下
(5,000) 千円
⑵ 10.0千円
5.4(5,000) 千円
⑴ 5.0千円
2.7
〜2 ⑷ 20.0 10.8 ⑵ 10.0 5.4
〜3 ⑹ 30.0 16.2 ⑶ 15.0 8.1
〜4 ⑻ 40.0 21.6 ⑷ 20.0 10.8
〜5 ⑽ 50.0 27.0 ⑸ 25.0 13.5
〜6 ⑿ 60.0 32.4 ⑹ 30.0 16.2
〜7 ⒁ 70.0 ● 37.8 ⑺ 35.0 18.9
〜8 ⒃ 80.0 43.2 ⑻ 40.0 21.6
〜9 ⒅ 90.0 48.6 ⑼ 45.0 24.3
〜10 ⒇100.0 54.0 ⑽ 50.0 27.0
〜11 �110.0 59.4 ⑾ 55.0 29.7
〜12 �120.0 64.8 ⑿ 60.0 32.4
〜13 �130.0 70.2 ⒀ 65.0 35.1
〜14 �140.0 75.6 ⒁ 70.0 ● 37.8
〜15 �150.0 81.0 ⒂ 75.0 40.5
〜16 �160.0 86.4 ⒃ 80.0 43.2
〜17 �170.0 91.8 ⒄ 85.0 45.9
〜18 �180.0 97.2 ⒅ 90.0 48.6
〜19 �190.0 102.6 ⒆ 95.0 51.3
〜20 �200.0 108.0 ⒇100.0 54.0
ト ラ ッ ク
2 年(車両総重量8t未満) 1 年
自家用 事業用 自家用 事業用
1t以下
千円
7.6千円
5.4千円
3.8(2,800) 千円
2.7
〜2 15.2 10.8 7.6 5.4
〜2.5 22.816.2
11.48.1
〜3(5,000) ⑹ 30.0
(5,000) 15.0
〜4 ⑻ 40.0 21.6 ⑷ 20.0 10.8
〜5 ⑽ 50.0 27.0 ⑸ 25.0 13.5
〜6 ⑿ 60.0 32.4 ⑹ 30.0 16.2
〜7 ⒁ 70.0 ● 37.8 ⑺ 35.0 18.9
〜8 ⒃ 80.0 43.2 ⑻ 40.0 21.6
〜9 ⑼ 45.0 24.3
〜10 ⑽ 50.0 27.0
〜11 ⑾ 55.0 29.7
〜12 ⑿ 60.0 32.4
〜13 ⒀ 65.0 35.1
〜14 ⒁ 70.0 ● 37.8
〜15 ⒂ 75.0 40.5
〜16 ⒃ 80.0 43.2
〜17 ⒄ 85.0 45.9
〜18 ⒅ 90.0 48.6
〜19 ⒆ 95.0 51.3
〜20 ⒇100.0 54.0
〜21 �105.0 ● 56.7
〜22 �110.0 59.4
〜23 �115.0 62.1
〜24 �120.0 64.8
〜25 �125.0 67.5
〜26 �130.0 70.2
〜27 �135.0 72.9
〜28 �140.0 75.6
〜29 �145.0 78.3
有効期間
車両総重量
有効期間
車両重量
有効期間
車両総重量
小 型 2 輪
自家用 事業用
3年 2年 1年 3年 2年円
6,600円
4,400円
2,200円
4,800円
3,200
バ ス(定員11人以上)
1 年
自家用 事業用
1t以下
(5,000) 千円
⑴ 5.0千円
2.7
〜2 ⑵ 10.0 5.4
〜3 ⑶ 15.0 8.1
有効期間
車両総重量
軽(検査対象外)新車の届出時1回限り
2 輪 その他
自家用 事業用 自家用 事業用円
5,500 円
4,300円
11,300 円
8,100
軽(検査対象車)
3 年 2 年
自家用乗用 自家用 事業用円
11,400 円
7,600 円
5,400
以下「トラック」に同じ
( )内の数字はそれぞれ特定の印紙を貼付した場合の枚数を示す。●印は、同額印紙が58. 5. 1より発行されていることを示す。
(注)車両重量の端数が10㎏未満の場合は切り捨てて計算する。非課税自動車は大型特殊自動車、届出済軽自動車(中古車)
自動車重量税印紙の種類(20種類)同額印紙…2,500 2,800 4,400 5,000 6,300 8,800 13,200 25,200 31,500 37,800 56,700 ( の印紙は58.5.1発行)
補助印紙…100 200 500 1,000 3,000 7,000 7,500 10,000 20,000

232
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
2 自動車税(地方税法 昭和25年法律第226号)
自動車税は自動車の主たる定置場所在の都道府県において、その所有者に課する普通税である。
主たる内容は以下のとおり。
1 納税義務者(法第145条)
ア 自動車の所有者(自動車の売買があった場合において売主が所有権を留保しているときは、買主が当該自動車の所
有者とみなされる。但し、買主が自動車税を滞納したときは、売主は一定の要件のもとに、その第二次納税義務を負
うこととされている。)
イ 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、こららの組合、財
産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人が所有する自動車で、公用、又は公
共の用以外に供されるものについては、その使用者。
2 課税対象車(法第145条第1項)
乗用車、バス、トラック等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型自動車、並びに大型特殊
自動車を除く。)
3 非課税の範囲(法第146条)
ア 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、こららの組合、財
産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人。
イ 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する救急自動車。その他これに類するもので
都道府県の条例で定めるもの。
4 賦課期日(法第148条)
4月1日
5 自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課及び還付(法第150条)
ア 賦課期日後に次に掲げる事由で納税義務が発生した場合は、登録された月の翌月分から、その年度末までの月割計
算金額を納付する。
⒜ 新規登録
⒝ 非課税車の譲り受け
イ 年度の中途に自動車の名義変更があったときは、すべてその年度の末日に所有者の変更があったものとして、その
年度分までは旧の所有者に課税され、新所有者の方には翌年度分から課税される。
ウ 年度の中途に自動車の用途、又は構造変更等がされて、税率に異動が生じたときは、すべて年度の末日に変更が行
われたものとして、その年度分までは変更前の税率で課税され、翌年度から新税率で課税される。
エ 廃車した場合は、登録した月の翌月分以降は月割計算により還付される。
6 納 期(法第149条)
ア 普通納付する場合は年1回(5月)
イ 5のアの場合はそれぞれの登録のとき。
7 月割税額表(次頁の表)

種 別 標準税率 11ヵ月分 10ヵ月分 9ヵ月分 8ヵ月分 7ヵ月分 6ヵ月分 5ヵ月分 4ヵ月分 3ヵ月分 2ヵ月分 1ヵ月分
乗
用
車
電気自動車 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,4001.0㍑以下 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
1.0㍑超 1.5㍑以下 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,8001.5㍑超 2.0㍑以下 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,2002.0㍑超 2.5㍑以下 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,7002.5㍑超 3.0㍑以下 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,2003.0㍑超 3.5㍑以下 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,8003.5㍑超 4.0㍑以下 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,5004.0㍑超 4.5㍑以下 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,3004.5㍑超 6.0㍑以下 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300
6.0㍑超 111,000 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200
貨
客
兼
用
車
1㌧以下
1.0㍑以下 13,200 12,100 11,000 9,900 8,800 7,700 6,600 5,500 4,400 3,300 2,200 1,1001.0㍑超 1.5㍑以下 14,300 13,100 11,900 10,700 9,500 8,300 7,100 5,900 4,700 3,500 2,300 1,100
1.5㍑超 16,000 14,600 13,300 12,000 10,600 9,300 8,000 6,600 5,300 4,000 2,600 1,300
1㌧超2㌧以下
1.0㍑以下 16,700 15,300 13,900 12,500 11,100 9,700 8,300 6,900 5,500 4,100 2,700 1,3001.0㍑超 1.5㍑以下 17,800 16,300 14,800 13,300 11,800 10,300 8,900 7,400 5,900 4,400 2,900 1,400
1.5㍑超 19,500 17,800 16,200 14,600 13,000 11,300 9,700 8,100 6,500 4,800 3,200 1,600
2㌧超3㌧以下
1.0㍑以下 21,200 19,400 17,600 15,900 14,100 12,300 10,600 8,800 7,000 5,300 3,500 1,7001.0㍑超 1.5㍑以下 22,300 20,400 18,500 16,700 14,800 13,000 11,100 9,200 7,400 5,500 3,700 1,800
1.5㍑超 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,0003㌧超 計算
ト
ラ
ッ
ク
1㌧以下 8,000 7,300 6,600 6,000 5,300 4,600 4,000 3,300 2,600 2,000 1,300 6001㌧超 2㌧以下 11,500 10,500 9,500 8,600 7,600 6,700 5,700 4,700 3,800 2,800 1,900 9002㌧超 3㌧以下 16,000 14,600 13,300 12,000 10,600 9,300 8,000 6,600 5,300 4,000 2,600 1,3003㌧超 4㌧以下 20,500 18,700 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500 6,800 5,100 3,400 1,7004㌧超 5㌧以下 25,500 23,300 21,200 19,100 17,000 14,800 12,700 10,600 8,500 6,300 4,200 2,1005㌧超 6㌧以下 30,000 27,500 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,5006㌧超 7㌧以下 35,000 32,000 29,100 26,200 23,300 20,400 17,500 14,500 11,600 8,700 5,800 2,9007㌧超 8㌧以下 40,500 37,100 33,700 30,300 27,000 23,600 20,200 16,800 13,500 10,100 6,700 3,3008㌧超 9㌧以下 46,800 42,900 39,000 35,100 31,200 27,300 23,400 19,500 15,600 11,700 7,800 3,9009㌧超 10㌧以下 53,100 48,600 44,200 39,800 35,400 30,900 26,500 22,100 17,700 13,200 8,800 4,40010㌧超 11㌧以下 59,400 54,400 49,500 44,500 39,600 34,600 29,700 24,700 19,800 14,800 9,900 4,90011㌧超 12㌧以下 65,700 60,200 54,700 49,200 43,800 38,300 32,800 27,300 21,900 16,400 10,900 5,40012㌧超 13㌧以下 72,000 66,000 60,000 54,000 48,000 42,000 36,000 30,000 24,000 18,000 12,000 6,00013㌧超 14㌧以下 78,300 71,700 65,200 58,700 52,200 45,600 39,100 32,600 26,100 19,500 13,000 6,50014㌧超 15㌧以下 84,600 77,500 70,500 63,400 56,400 49,300 42,300 35,200 28,200 21,100 14,100 7,00015㌧超 16㌧以下 90,900 83,300 75,700 68,100 60,600 53,000 45,400 37,800 30,300 22,700 15,100 7,50016㌧超 17㌧以下 97,200 89,100 81,000 72,900 64,800 56,700 48,600 40,500 32,400 24,300 16,200 8,10017㌧超 18㌧以下 103,500 94,800 86,200 77,600 69,000 60,300 51,700 43,100 34,500 25,800 17,200 8,60018㌧超 19㌧以下 109,800 100,600 91,500 82,300 73,200 64,000 54,900 45,700 36,600 27,400 18,300 9,10019㌧超 20㌧以下 116,100 106,400 96,700 87,000 77,400 67,700 58,000 48,300 38,700 29,000 19,300 9,600
けん引車
小 型 10,200 9,300 8,500 7,600 6,800 5,900 5,100 4,200 3,400 2,500 1,700 800普 通 20,600 18,800 17,100 15,400 13,700 12,000 10,300 8,500 6,800 5,100 3,400 1,700
被
け
ん
引
車
小 型 5,300 4,800 4,400 3,900 3,500 3,000 2,600 2,200 1,700 1,300 800 400
普
通
8㌧以下 10,200 9,300 8,500 7,600 6,800 5,900 5,100 4,200 3,400 2,500 1,700 8008㌧超 9㌧以下 15,300 14,000 12,700 11,400 10,200 8,900 7,600 6,300 5,100 3,800 2,500 1,2009㌧超 10㌧以下 20,400 18,700 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500 6,800 5,100 3,400 1,70010㌧超 11㌧以下 25,500 23,300 21,200 19,100 17,000 14,800 12,700 10,600 8,500 6,300 4,200 2,10011㌧超 12㌧以下 30,600 28,000 25,500 22,900 20,400 17,800 15,300 12,700 10,200 7,600 5,100 2,50012㌧超 13㌧以下 35,700 32,700 29,700 26,700 23,800 20,800 17,800 14,800 11,900 8,900 5,900 2,90013㌧超 14㌧以下 40,800 37,400 34,000 30,600 27,200 23,800 20,400 17,000 13,600 10,200 6,800 3,40014㌧超 15㌧以下 45,900 42,000 38,200 34,400 30,600 26,700 22,900 19,100 15,300 11,400 7,600 3,80015㌧超 16㌧以下 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,20016㌧超 17㌧以下 56,100 51,400 46,700 42,000 37,400 32,700 28,000 23,300 18,700 14,000 9,300 4,60017㌧超 18㌧以下 61,200 56,100 51,000 45,900 40,800 35,700 30,600 25,500 20,400 15,300 10,200 5,10018㌧超 19㌧以下 66,300 60,700 55,200 49,700 44,200 38,600 33,100 27,600 22,100 16,500 11,000 5,50019㌧超 20㌧以下 71,400 65,400 59,500 53,500 47,600 41,600 35,700 29,700 23,800 17,800 11,900 5,900
バ
ス
30人以下 33,000 30,200 27,500 24,700 22,000 19,200 16,500 13,700 11,000 8,200 5,500 2,70030人超 40人以下 41,000 37,500 34,100 30,700 27,300 23,900 20,500 17,000 13,600 10,200 6,800 3,40040人超 50人以下 49,000 44,900 40,800 36,700 32,600 28,500 24,500 20,400 16,300 12,200 8,100 4,00050人超 60人以下 57,000 52,200 47,500 42,700 38,000 33,200 28,500 23,700 19,000 14,200 9,500 4,70060人超 70人以下 65,500 60,000 54,500 49,100 43,600 38,200 32,700 27,200 21,800 16,300 10,900 5,40070人超 80人以下 74,000 67,800 61,600 55,500 49,300 43,100 37,000 30,800 24,600 18,500 12,300 6,100
80人超 83,000 76,000 69,100 62,200 55,300 48,400 41,500 34,500 27,600 20,700 13,800 6,900
スクールバス
特種用途車
30人以下 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,00030人超 40人以下 14,500 13,200 12,000 10,800 9,600 8,400 7,200 6,000 4,800 3,600 2,400 1,20040人超 50人以下 17,500 16,000 14,500 13,100 11,600 10,200 8,700 7,200 5,800 4,300 2,900 1,40050人超 60人以下 20,000 18,300 16,600 15,000 13,300 11,600 10,000 8,300 6,600 5,000 3,300 1,60060人超 70人以下 22,500 20,600 18,700 16,800 15,000 13,100 11,200 9,300 7,500 5,600 3,700 1,80070人超 80人以下 25,500 23,300 21,200 19,100 17,000 14,800 12,700 10,600 8,500 6,300 4,200 2,100
80人超 29,000 26,500 24,100 21,700 19,300 16,900 14,500 12,000 9,600 7,200 4,800 2,400小 型 三 輪 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500
表 1自動車税月割税額表(自家用)東京都主税局
H19.4.1
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

種 別 標準税率 11ヵ月分 10ヵ月分 9ヵ月分 8ヵ月分 7ヵ月分 6ヵ月分 5ヵ月分 4ヵ月分 3ヵ月分 2ヵ月分 1ヵ月分
乗
用
車
電気自動車 7,500 6,800 6,200 5,600 5,000 4,300 3,700 3,100 2,500 1,800 1,200 6001.0㍑以下 7,500 6,800 6,200 5,600 5,000 4,300 3,700 3,100 2,500 1,800 1,200 600
1.0㍑超 1.5㍑以下 8,500 7,700 7,000 6,300 5,600 4,900 4,200 3,500 2,800 2,100 1,400 7001.5㍑超 2.0㍑以下 9,500 8,700 7,900 7,100 6,300 5,500 4,700 3,900 3,100 2,300 1,500 7002.0㍑超 2.5㍑以下 13,800 12,600 11,500 10,300 9,200 8,000 6,900 5,700 4,600 3,400 2,300 1,1002.5㍑超 3.0㍑以下 15,700 14,300 13,000 11,700 10,400 9,100 7,800 6,500 5,200 3,900 2,600 1,3003.0㍑超 3.5㍑以下 17,900 16,400 14,900 13,400 11,900 10,400 8,900 7,400 5,900 4,400 2,900 1,4003.5㍑超 4.0㍑以下 20,500 18,700 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500 6,800 5,100 3,400 1,7004.0㍑超 4.5㍑以下 23,600 21,600 19,600 17,700 15,700 13,700 11,800 9,800 7,800 5,900 3,900 1,9004.5㍑超 6.0㍑以下 27,200 24,900 22,600 20,400 18,100 15,800 13,600 11,300 9,000 6,800 4,500 2,200
6.0㍑超 40,700 37,300 33,900 30,500 27,100 23,700 20,300 16,900 13,500 10,100 6,700 3,300
貨
客
兼
用
車
1㌧以下
1.0㍑以下 10,200 9,300 8,500 7,600 6,800 5,900 5,100 4,200 3,400 2,500 1,700 8001.0㍑超 1.5㍑以下 11,200 10,200 9,300 8,400 7,400 6,500 5,600 4,600 3,700 2,800 1,800 900
1.5㍑超 12,800 11,700 10,600 9,600 8,500 7,400 6,400 5,300 4,200 3,200 2,100 1,000
1㌧超2㌧以下
1.0㍑以下 12,700 11,600 10,500 9,500 8,400 7,400 6,300 5,200 4,200 3,100 2,100 1,0001.0㍑超 1.5㍑以下 13,700 12,500 11,400 10,200 9,100 7,900 6,800 5,700 4,500 3,400 2,200 1,100
1.5㍑超 15,300 14,000 12,700 11,400 10,200 8,900 7,600 6,300 5,100 3,800 2,500 1,200
2㌧超3㌧以下
1.0㍑以下 15,700 14,300 13,000 11,700 10,400 9,100 7,800 6,500 5,200 3,900 2,600 1,3001.0㍑超 1.5㍑以下 16,700 15,300 13,900 12,500 11,100 9,700 8,300 6,900 5,500 4,100 2,700 1,300
1.5㍑超 18,300 16,700 15,200 13,700 12,200 10,600 9,100 7,600 6,100 4,500 3,000 1,5003㌧超 計算
ト
ラ
ッ
ク
1㌧以下 6,500 5,900 5,400 4,800 4,300 3,700 3,200 2,700 2,100 1,600 1,000 5001㌧超 2㌧以下 9,000 8,200 7,500 6,700 6,000 5,200 4,500 3,700 3,000 2,200 1,500 7002㌧超 3㌧以下 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,0003㌧超 4㌧以下 15,000 13,700 12,500 11,200 10,000 8,700 7,500 6,200 5,000 3,700 2,500 1,2004㌧超 5㌧以下 18,500 16,900 15,400 13,800 12,300 10,700 9,200 7,700 6,100 4,600 3,000 1,5005㌧超 6㌧以下 22,000 20,100 18,300 16,500 14,600 12,800 11,000 9,100 7,300 5,500 3,600 1,8006㌧超 7㌧以下 25,500 23,300 21,200 19,100 17,000 14,800 12,700 10,600 8,500 6,300 4,200 2,1007㌧超 8㌧以下 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,4008㌧超 9㌧以下 34,200 31,300 28,500 25,600 22,800 19,900 17,100 14,200 11,400 8,500 5,700 2,8009㌧超 10㌧以下 38,900 35,600 32,400 29,100 25,900 22,600 19,400 16,200 12,900 9,700 6,400 3,20010㌧超 11㌧以下 43,600 39,900 36,300 32,700 29,000 25,400 21,800 18,100 14,500 10,900 7,200 3,60011㌧超 12㌧以下 48,300 44,200 40,200 36,200 32,200 28,100 24,100 20,100 16,100 12,000 8,000 4,00012㌧超 13㌧以下 53,000 48,500 44,100 39,700 35,300 30,900 26,500 22,000 17,600 13,200 8,800 4,40013㌧超 14㌧以下 57,700 52,800 48,000 43,200 38,400 33,600 28,800 24,000 19,200 14,400 9,600 4,80014㌧超 15㌧以下 62,400 57,200 52,000 46,800 41,600 36,400 31,200 26,000 20,800 15,600 10,400 5,20015㌧超 16㌧以下 67,100 61,500 55,900 50,300 44,700 39,100 33,500 27,900 22,300 16,700 11,100 5,50016㌧超 17㌧以下 71,800 65,800 59,800 53,800 47,800 41,800 35,900 29,900 23,900 17,900 11,900 5,90017㌧超 18㌧以下 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,30018㌧超 19㌧以下 81,200 74,400 67,600 60,900 54,100 47,300 40,600 33,800 27,000 20,300 13,500 6,70019㌧超 20㌧以下 85,900 78,700 71,500 64,400 57,200 50,100 42,900 35,700 28,600 21,400 14,300 7,100
けん引車
小 型 7,500 6,800 6,200 5,600 5,000 4,300 3,700 3,100 2,500 1,800 1,200 600普 通 15,100 13,800 12,500 11,300 10,000 8,800 7,500 6,200 5,000 3,700 2,500 1,200
被
け
ん
引
車
小 型 3,900 3,500 3,200 2,900 2,600 2,200 1,900 1,600 1,300 900 600 300
普
通
8㌧以下 7,500 6,800 6,200 5,600 5,000 4,300 3,700 3,100 2,500 1,800 1,200 6008㌧超 9㌧以下 11,300 10,300 9,400 8,400 7,500 6,500 5,600 4,700 3,700 2,800 1,800 9009㌧超 10㌧以下 15,100 13,800 12,500 11,300 10,000 8,800 7,500 6,200 5,000 3,700 2,500 1,20010㌧超 11㌧以下 18,900 17,300 15,700 14,100 12,600 11,000 9,400 7,800 6,300 4,700 3,100 1,50011㌧超 12㌧以下 22,700 20,800 18,900 17,000 15,100 13,200 11,300 9,400 7,500 5,600 3,700 1,80012㌧超 13㌧以下 26,500 24,200 22,000 19,800 17,600 15,400 13,200 11,000 8,800 6,600 4,400 2,20013㌧超 14㌧以下 30,300 27,700 25,200 22,700 20,200 17,600 15,100 12,600 10,100 7,500 5,000 2,50014㌧超 15㌧以下 34,100 31,200 28,400 25,500 22,700 19,800 17,000 14,200 11,300 8,500 5,600 2,80015㌧超 16㌧以下 37,900 34,700 31,500 28,400 25,200 22,100 18,900 15,700 12,600 9,400 6,300 3,10016㌧超 17㌧以下 41,700 38,200 34,700 31,200 27,800 24,300 20,800 17,300 13,900 10,400 6,900 3,40017㌧超 18㌧以下 45,500 41,700 37,900 34,100 30,300 26,500 22,700 18,900 15,100 11,300 7,500 3,70018㌧超 19㌧以下 49,300 45,100 41,000 36,900 32,800 28,700 24,600 20,500 16,400 12,300 8,200 4,10019㌧超 20㌧以下 53,100 48,600 44,200 39,800 35,400 30,900 26,500 22,100 17,700 13,200 8,800 4,400
バ
ス
30人以下 26,500 24,200 22,000 19,800 17,600 15,400 13,200 11,000 8,800 6,600 4,400 2,20030人超 40人以下 32,000 29,300 26,600 24,000 21,300 18,600 16,000 13,300 10,600 8,000 5,300 2,60040人超 50人以下 38,000 34,800 31,600 28,500 25,300 22,100 19,000 15,800 12,600 9,500 6,300 3,10050人超 60人以下 44,000 40,300 36,600 33,000 29,300 25,600 22,000 18,300 14,600 11,000 7,300 3,60060人超 70人以下 50,500 46,200 42,000 37,800 33,600 29,400 25,200 21,000 16,800 12,600 8,400 4,20070人超 80人以下 57,000 52,200 47,500 42,700 38,000 33,200 28,500 23,700 19,000 14,200 9,500 4,700
80人超 64,000 58,600 53,300 48,000 42,600 37,300 32,000 26,600 21,300 16,000 10,600 5,300小型三輪1㌧以下 4,500 4,100 3,700 3,300 3,000 2,600 2,200 1,800 1,500 1,100 700 300
表 2自動車税月割税額表(営業用)東京都主税局
種 別 標準税率 11ヵ月分 10ヵ月分 9ヵ月分 8ヵ月分 7ヵ月分 6ヵ月分 5ヵ月分 4ヵ月分 3ヵ月分 2ヵ月分 1ヵ月分
バ
ス
30人以下 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,00030人超 40人以下 14,500 13,200 12,000 10,800 9,600 8,400 7,200 6,000 4,800 3,600 2,400 1,20040人超 50人以下 17,500 16,000 14,500 13,100 11,600 10,200 8,700 7,200 5,800 4,300 2,900 1,40050人超 60人以下 20,000 18,300 16,600 15,000 13,300 11,600 10,000 8,300 6,600 5,000 3,300 1,60060人超 70人以下 22,500 20,600 18,700 16,800 15,000 13,100 11,200 9,300 7,500 5,600 3,700 1,80070人超 80人以下 25,500 23,300 21,200 19,100 17,000 14,800 12,700 10,600 8,500 6,300 4,200 2,100
80人超 29,000 26,500 24,100 21,700 19,300 16,900 14,500 12,000 9,600 7,200 4,800 2,400
一般乗合用バス
H19.4.1
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

235
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3 自動車取得税(地方税法 昭和25年法律第226号)
自動車取得税は自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の都道府県において、当該自動車の取得者に課す
る普通税である。
主たる内容は以下のとおり。
1 納税義務者(法第113条第1項)
自動車の取得者
2 課税対象車(法第113条第2項)
乗用車、バス、トラック等(特殊自動車、小型自動車、及び軽自動車のうち二輪のものを除く。)
3 課税対象(法第113条、法第114条)
ア 一般的な取得(有償、無償を問わないが、販売業者の販売のための取得、製造業者の製造による取得等は含まない)
の場合。
イ 所有権留保の売買の場合は、当該売買契約の締結を取得とみなされ、買主が取得者とみなされ課税される。
ウ 販売業者が販売のために取得した自動車、製造業者が製造により取得した自動車を運行の用に供した場合は、当該
運行の用に供することを自動車の取得とみなされ、当該販売業者等が取得者とみなされ課税される。
エ 外国で自動車を取得したものが、当該自動車を国内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該運行の用に供す
ることを自動車の取得とみなされ、当該者が取得者とみなされ課税される。
4 非課税の範囲及び納税義務の免除(法第115条、法第125条第1項、法第126条)
ア 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財
産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人の自動車の取得。
イ 相続に基づく自動車の取得。
ウ 法人の合併、又は分割に基づく自動車の取得。
エ 会社更生法に基づき新会社に移転すべき財産を定めた場合における新会社の自動車の取得。
オ 信託、又は保険業法の規定による取得。
カ 譲渡担保債権者が譲渡担保として、自動車を取得したが担保された債権が6か月以内に消滅したため、再び設定者
に自動車が移転した場合における取得。
キ 割賦代金等の完済により自動車の所有権が買主に移転する場合(買主の変更による新買主を除く)。
ク 自動車販売業者から自動車を取得した者が、次の理由で1か月以内に自動車を返還した場合は、申請により納税義
務を免除される。
a 自動車の性能が良好でないとき。
b その他、契約の内容と異なるとき。
5 課税標準(法第118条)
ア 取得価額。
イ 無償による取得、その他特別の事情がある取得、交換等による取得の場合は通常の取引価額として総務省令で定め
るところにより算定した金額。
ウ 自動車取得税の軽減措置内容
対 象:燃費基準を達成している普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、かつ、低排出ガス認定制度により低
排出ガス車の認定を受けているもの(改造自動車等の手続きが取られ、自動車検査証に型式指定番号及

236
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
び類別区分番号の記載のないものを除く)
【取得期間 平成24年4月1日~平成27年3月31日】
6 税 率(法第119条)
軽自動車、及び営業用自動車 3% その他の自動車 5%
7 免税点(法第120条)
50万円以下
8 納 期(法第122条)
ア 新規登録、又は軽自動車の使用届出のとき。
イ 移転、又は変更登録を要する自動車の取得は、事由があった日から15日を経過する日。(その日前に登録を受けた
ときは、その登録のとき)
9 納付方法(法第124条)
自動車を登録、又は届出した都道府県に申告納税する。
車 種
新車(税額免除等の措置) 中古車(取得価額控除)
軽減率等
排出ガス規制適合年度 窒素酸化物排出量等の減少率 対27年度
燃費基準値比 控除額 適用基準17年 21年 対17年 対21年
電気自動車
非課税
45万円
プラグインハイブリッド車
天然ガス自動車 ○ 10%低減達成
新車と同条件車乗用車(ガソリン) ○ 75%低減達成 +20%達成※1
乗用車(ディーゼル) ○
乗用車(ガソリン) 75% ○ 75%低減達成 +10%達成※2 30万円 新車と同条件車
乗用車(ガソリン) 50% ○ 75%低減達成 基準達成※3 15万円 新車と同条件車
(注)重複適用はありません。※1 平成27年度燃費基準を算定していないもので、平成22年度燃費基準を算定している自動車については、「平成22年度燃費
基準比+50%」と読み替えます。※2 平成27年度燃費基準を算定していないもので、平成22年度燃費基準を算定している自動車については、「平成22年度燃費
基準比+38%」と読み替えます。※3 平成27年度燃費基準を算定していないもので、平成22年度燃費基準を算定している自動車については、「平成22年度燃費
基準比+25%」と読み替えます。 ○ 別途、移動等の目標が定められたバス車両及びタクシーで構造・設備基準に適合したものについても取得控除措置が設
定されました。 ○ 別途、8t超トラック等で衝突被害軽減ブレーキ搭載等の基準を満たしたものについても取得控除措置が設定されました。

237
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
4 軽自動車税(地方税法 昭和25年法律第226号)
軽自動車税は当該自動車の主たる定置場所在の市区町村においてその所有者に課する普通税である。
主なる内容は以下のとおり。
1 納税義務者及び課税対象車(法第442条の2)
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型自動車が課税対象車となり、納税義務者はその所有者(自
動車の売買があった場合において売主が所有権を留保しているときは、買主が当該自動車の所有者とみなされる。但し、
買主が自動車税を滞納したときは、売主は一定の要件のもとに、その第二次納税義務を負うこととされている)。
2 非課税の範囲(法第443条)
国、並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、及び地方開発事業団。
3 賦課期日等(法第445条)
・4月1日に軽自動車を取得(所有)した場合は、従前から所有していたと同様に当該年度1年分の軽自動車税が賦課
される。
年度途中で所有しなくなった場合(廃車、譲渡など)でも月割の還付はない。
・4月2日以降に軽自動車を取得(所有)した場合は当該年度の軽自動車税は賦課されない。
・4月1日に当該軽自動車の所有者でなくなった場合は当該年度の軽自動車税は賦課されない。
4 標準税率(法第444条)
a 原動機付自転車
ア 総排気量が50㏄以下のもの、又は定格出力が0.6KW以下のもの…………年額1,000円
イ 総排気量が50㏄を越え、90㏄以下のもの、又は定格出力が0.6KWを越え、0.8KW以下のもの……年額1,200円
ウ 総排気量が90㏄を越えるもの、又は定格出力が0.8KWを越えるもの…………年額1,600円
b 軽自動車、及び小型特殊自動車
ア 軽自動車
二輪のもの(側車付のものを含む)……年額2,400円
三輪のもの…………………………………年額3,100円
四輪以上のもの
(乗用) 自家用……………………………年額7,200円
営業用……………………………年額5,500円
(貨物) 自家用……………………………年額4,000円
営業用……………………………年額3,000円
イ 小型特殊自動車
小型特殊自動車…………………………年額4,700円
〃 (電気自動車)…………年額3,900円
〃 (雪上車)………………年額2,400円
c 二輪の小型自動車
二輪の小型自動車…………………………年額4,000円

238
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
5 身体障害者等に対する減免 (自動車税・自動車取得税・軽自動車税)(法第162条、法第699条の17)
⑴ 公益のため直接専用するものと認められる自動車。
⑵ 天災、その他特別の事情により減免の必要があると認められる自動車。
⑶ 身体障害者等に対する減免。(1人の身体障害者等について1台限りであること。)
ア 一定範囲の身体障害者手帳、又は戦傷病者手帳の交付を受けている者が取得し、又は所有する自動車で、もっぱ
ら当該身体障害者が運転する場合。
イ 一定範囲の身体障害者、及び精神薄弱者で療育手帳の交付を受けている者が取得し、又は所有する自動車で、もっ
ぱら当該身体障害者の通学、通院、もしくは生業のために、当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合。
ウ 一定範囲の身体障害者等と生計を一にする者が取得し、又は所有する自動車で、もっぱら年令18才未満の身体障
害者、又は精神薄弱者の通学、通院、もしくは生業のために、当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合。
⑷ 構造上身体障害者等の利用にもっぱら供するための自動車のうち、必要が認められるもの。

239
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
6 商品中古自動車に係る自動車税の軽減 (中古自動車販売業の方が所有する中古商品自動車)
1) 減免を受けられる必要条件
ア 減免申請書を提出すること
イ 自動車について古物商の営業許可を受けていること
ウ 申請期限までに、所有しているすべての自動車に係る自動車税(延滞金を含む)の滞納をしていないこと及び当
該年度分について納付していること
エ 申請期限までに、都税に関して、罰金以上の刑に処せられたり、国税犯則取締法により通告処分を受けた方は、
それらの刑の執行が終り若しくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経
過していること。
オ 申請期限までに、都税について、滞納処分を受けた方は、滞納処分の日から2年を経過していること。
カ 賦課期日現在、自動車登録ファイルに所有者(使用者が登録されている場合は、所有者及び使用者)として販売
業者が登録されている中古商品自動車であること。
2) 減免申請をするときの必要書類
ア 一般財団法人 日本自動車査定協会が発行する「商品中古自動車証明書」
イ 古物商許可証の写し
ウ 運輸支局の発行する4月1日現在の登録名義が明らかとなる登録事項等証明書
3) 減免額
自動車税(年税分)の12分の3に相当する額
ただし、4月中廃車等(1か月相当分)の場合は、1か月に相当する額
4) 減免申請書の提出場所
減免の申請をする自動車の定置場を担当する税事務所又は、支庁
5) 減免申請書の提出期限
申請期限は、納期限まで

240
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
◦自動車重量税及び自動車取得税の特例措置◦1.新エコカー減税・中古車特例の概要(平成24年度改正) 〈適用期間〉 自動車重量税:平成24年5月1日~平成27年4月30日 自動車取得税:平成24年4月1日~平成27年3月31日
〈注〉JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10・15モードによる燃費値により算定する。 その場合、「平成27年度燃費基準+20%達成」を「平成22年度燃費基準+50%達成」と、「平成27年度燃費基準+10%達成」を「平成22年度燃費基準+38%達成」と、「平成27年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+25%達成」と、それぞれ読み替える。
●自動車重量税 ① 適用期間中の新車新規検査の際に納付すべき税額について減免。 ② 新エコカー減税の適用により免税とされた自動車について、新車新規検査による車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までの間に、継続検査等(新車新規検査後、最初に受けるものに限る。)を受ける際(新車新規検査による車検証の記載事項について車両構造等の変更がない場合に限る。)に納付すべき税額について50%軽減。免税対象車(①及び②の適用を受けた自動車等を徐く)については、平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に、継続検査等(この期間内に最初に受ける検査に限る。)を受ける場合は税額について50%軽減。
●自動車取得税 ③ 適用期間中に新車で購入した際に課される税率について軽減。 ④ 適用期間中に中古車で購入した際の取得価額から控除。 ※:ハイブリッド自動車に限る。
自動車重量税 自動車取得税① ② ③ ④新車
新規検査 2回目車検 新車 中古車(控除額)
① 電気自動車(燃料電池自動車を含む) 免税 50%軽減 非課税 45万円控除② 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減) 免税 50%軽減 非課税 45万円控除③ プラグインハイブリッド自動車 免税 50%軽減 非課税 45万円控除④ クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合の乗用車) 免税 50%軽減 非課税 45万円控除⑤ ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む)A 車両総重量2.5t以下(乗用車等)平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+20%達成〈注〉 免税 50%軽減 非課税 45万円控除かつ平成27年度燃費基準+10%達成〈注〉 75%軽減 - 75%軽減 30万円控除かつ平成27年度燃費基準達成〈注〉 50%軽減 - 50%軽減 15万円控除
B 車両総重量2.5t超3.5t以下(中量車)⒜ 平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+10%達成 免税 50%軽減 非課税 45万円控除かつ平成27年度燃費基準+5%達成 75%軽減 - 75%軽減 30万円控除かつ平成27年度燃費基準達成 50%軽減 - 50%軽減 15万円控除
⒝ 平成17年排ガス規制50%低減(☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+10%達成 75%軽減 - 75%軽減 30万円控除かつ平成27年度燃費基準+5%達成 50%軽減 - 50%軽減 15万円控除
⑥ ディーゼル自動車(ハイブリッド自動車を含む)A 車両総重量2.5t超3.5t以下(中量車)⒜ 平成21年排ガス規制NOx及び PM10%以上低減かつ平成27年度燃費基準+10%達成 免税 50%軽減 非課税 -かつ平成27年度燃費基準+5%達成 75%軽減 - 75%軽減 -かつ平成27年度燃費基準達成 50%軽減 - 50%軽減 -
⒝ 平成21年排ガス規制適合かつ平成27年度燃費基準+10%達成 75%軽減 - 75%軽減 -かつ平成27年度燃費基準+5%達成 50%軽減 - 50%軽減 -
B 車両総重量3.5t超(重量車)⒜ 平成21年排ガス規制NOx及び PM10%以上低減かつ平成27年度重量車燃費基準+10%達成 免税 50%軽減 非課税 45万円控除(※)かつ平成27年度重量車燃費基準+5%達成 75%軽減 - 75%軽減 30万円控除(※)かつ平成27年度重量車燃費基準達成 50%軽減 - 50%軽減 15万円控除(※)
⒝ 平成21年排ガス規制適合かつ平成27年度重量車燃費基準+10%達成 75%軽減 - 75%軽減 30万円控除(※)かつ平成27年度重量車燃費基準+5%達成 50%軽減 - 50%軽減 15万円控除(※)
7 平成24年度の税制改正の概要について

241
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
(参考)新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の概要(平成24年度改正)
対象・要件等 軽 減 率電気自動車(燃料電池自動車を含む)天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)プラグインハイブリッド自動車クリーンディーゼル乗用車 (平成21年排ガス規制適合の乗用車)
自動車重量税 免税*1 (2回目の車検:50%軽減)*2
自動車取得税 非課税
燃費性能(注)排ガス性能 達 成 +10%超過 +20%超過
ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む)
平成17年排ガス規制 75%低減(☆☆☆☆) 50%軽減*1 75%軽減*1
免税*1(2回目車検:50%軽減)*2
○乗用車等(乗用車、車両総重量2.5t以下のバス・トラック)
(注)平成27年度燃費基準の超過達成率。 JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10・15モードによる燃費値により算定する。 その場合、「平成27年度燃費基準+20%達成」を「平成22年度燃費基準+50%達成」と、「平成27年度燃費基準+10%達成」を「平
成22年度燃費基準+38%達成」と、「平成27年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+25%達成」と、それぞれ読み替える。
○中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のバス・トラック)
対象・要件等 軽 減 率
電気自動車(燃料電池自動車を含む)天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)プラグインハイブリッド自動車
自動車重量税 免税*1 (2回目の車検:50%軽減)*2
自動車取得税 非課税燃費性能(注)
排ガス性能 達 成 +5%超過 +10%超過
ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む)
平成17年排ガス規制
75%低減(☆☆☆☆) 50%軽減*1 75%軽減*1
免税*1(2回目車検:50%軽減)*2
50%低減(☆☆☆) 50%軽減*1 75%軽減*1
ディーゼル自動車(ハイブリッド自動車を含む)
平成21年排ガス規制
NOx・PM+10%低減 50%軽減*1 75%軽減*1
免税*1(2回目車検:50%軽減)*2
50%軽減*1 75%軽減*1
〈注〉平成27年度燃費基準の超過達成率。
○重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)
対象・要件等 軽 減 率
電気自動車(燃料電池自動車を含む)天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)プラグインハイブリッド自動車
自動車重量税 免税*1 (2回目の車検:50%軽減)*2
自動車取得税 非課税燃費性能(注)
排ガス性能 達 成 +5%超過 +10%超過
ディーゼル自動車(ハイブリッド自動車を含む)
平成21年排ガス規制
NOx・PM+10%低減 50%軽減*1 75%軽減*1
免税*1(2回目車検:50%軽減)*2
50%軽減*1 75%軽減*1
〈注〉平成27年度重量車燃費基準の超過達成率。
*1:自動車重量税については、適用期間中の新車新規検査の際に納付すべき税額について減免。*2:自動車重量税のみ。①新車新規検査(特例期間中)の後に初めて受ける継続検査等、②適用期間中に初めて受ける継続検査
等の際に納付すべき税額について減免。

242
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
(参考)中古車特例(自動車取得税)の概要(平成24年度改正)
対象・要件等 控 除 額電気自動車(燃料電池自動車を含む)天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)プラグインハイブリッド自動車クリーンディーゼル乗用車 (平成21年排ガス規制適合の乗用車)
取得価額から45万円控除
燃費性能(注)排ガス性能 達 成 +10%超過 +20%超過
ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む)
平成17年排ガス規制 75%低減(☆☆☆☆)
取得価額から15万円控除
取得価額から30万円控除
取得価額から45万円控除
○乗用車等(乗用車、車両総重量2.5t以下のバス・トラック)
(注)平成27年度燃費基準の超過達成率。 JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10・15モードによる燃費値により算定する。 その場合、「平成27年度燃費基準+20%達成」を「平成22年度燃費基準+50%達成」と、「平成27年度燃費基準+10%達成」を「平
成22年度燃費基準+38%達成」と、「平成27年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+25%達成」と、それぞれ読み替える。
○中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のバス・トラック)
対象・要件等 控 除 額
電気自動車(燃料電池自動車を含む)天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)プラグインハイブリッド自動車
取得価額から45万円控除
燃費性能(注)排ガス性能 達 成 +5%超過 +10%超過
ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む)
平成17年排ガス規制
75%低減(☆☆☆☆)
取得価額から15万円控除
取得価額から30万円控除
取得価額から45万円控除
50%低減(☆☆☆)
取得価額から15万円控除
取得価額から30万円控除
〈注〉平成27年度燃費基準の超過達成率。
○重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)
対象・要件等 控 除 額
電気自動車(燃料電池自動車を含む)天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)プラグインハイブリッド自動車
取得価額から45万円控除
燃費性能(注)排ガス性能 達 成 +5%超過 +10%超過
ディーゼル自動車(ハイブリッド自動車のみ)
平成21年排ガス規制
NOx・PM+10%低減
取得価額から15万円控除
取得価額から30万円控除
取得価額から45万円控除
取得価額から15万円控除
取得価額から30万円控除
〈注〉平成27年度重量車燃費基準の超過達成率。

243
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
対象・要件等 自動車重量税 自動車取得税
衝突被害軽減ブレーキ搭載車(車両総重量8t超のトラック、車両総重量13t超のトラクタ)
50%軽減
(注)22t超のトラック、13t超のトラクタはH26.10.31まで
(初回(新車新規検査時)のみ)
取得価額から350万円控除
(注)22t超のトラック、13t超のトラクタはH26.10.31まで
(新車新規登録を受けるもののみ)
バリアフリー車両
ノンステップバス(一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するものに限る)
免税(初回(新車新規検査時)のみ)
取得価額から1,000万円控除
(新車新規登録を受けるもののみ)
リフト付きバス(一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するものに限る)
免税(初回(新車新規検査時)のみ)
乗車定員30人以上:取得価額から650万円控除
乗車定員30人未満:取得価額から200万円控除(新車新規登録を受けるもののみ)
ユニバーサルデザインタクシー(一般乗用旅客自動車運送事業者が導入するものに限る)
免税(初回(新車新規検査時)のみ)
取得価額から100万円控除
(新車新規登録を受けるもののみ)
対 象 自動車重量税 自動車取得税
衝突被害軽減ブレーキ搭載車 新エコカー減税を適用 新エコカー減税とASV減税とのいずれかを申告者が選択
バリアフリー車両
新エコカー減税による免税対象車両は新エコカー減税による措置を適用し、その他の車両はバリアフリー車両減税による措置を適用
新エコカー減税とバリアフリー車両減税とのいずれかを申告者が選択
2.ASV・バリアフリー車両減税(自動車重量税・自動車取得税)の概要(平成24年度改正)
〈適用期間〉 自動車重量税:平成24年5月1日~平成27年4月30日 自動車取得税:平成24年4月1日~平成27年3月31日
〈新エコカー減税との適用関係〉 下記車両が新エコカー減税対象車でもある場合。
3.自動車税のグリーン化特例の概要(平成24年度改正)
○軽課(平成24・25年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減)
対象・要件等 軽 減 率
乗用車等(乗用車、車両総重量
2.5t以下のバス・トラック)
電気自動車(燃料電池自動車を含む)天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)プラグインハイブリッド自動車
概ね50%軽減
ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む)
排ガス性能 燃費性能(注)
平成17年排ガス規制75%低減
(☆☆☆☆)
+10%超過 概ね50%軽減
達 成 概ね25%軽減
中量車(車両総重量2.5t超
3.5t以下のバス・トラック)
電気自動車(燃料電池自動車を含む)天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)プラグインハイブリッド自動車
概ね50%軽減重量車
(車両総重量3.5t超のバス・トラック)
電気自動車(燃料電池自動車を含む)天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)プラグインハイブリッド自動車
(注)平成27年度燃費基準の超過達成率。 JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10・15モードによる燃費値により算定する。 その場合、「平成27年度燃費基準+10%達成」を「平成22年度燃費基準+38%達成」と、「平成27年度燃費基準達成」を「平
成22年度燃費基準+25%達成」と、それぞれ読み替える。
○重課(車齢が一定年数を経過したものに対して概ね10%重課)
ガソリン自動車、LPG自動車:13年超 ディーゼル自動車:11年超 ※電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、一般乗合バス及び被けん引車を除く

244
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1.乗用自動車(ガソリン自動車) (単位:㎞ /ℓ)
区 分 燃費基準値 燃費基準+10%値
燃費基準+20%値
1.車両重量が 601㎏未満 22.5 24.8 27.0
2.車両重量が 601㎏以上 741㎏未満 21.8 24.0 26.2
3.車両重量が 741㎏以上 856㎏未満 21.0 23.1 25.2
4.車両重量が 856㎏以上 971㎏未満 20.8 22.9 25.0
5.車両重量が 971㎏以上 1,081㎏未満 20.5 22.6 24.6
6.車両重量が 1,081㎏以上 1,196㎏未満 18.7 20.6 22.5
7.車両重量が 1,196㎏以上 1,311㎏未満 17.2 19.0 20.7
8.車両重量が 1,311㎏以上 1,421㎏未満 15.8 17.4 19.0
9.車両重量が 1,421㎏以上 1,531㎏未満 14.4 15.9 17.3
10.車両重量が 1,531㎏以上 1,651㎏未満 13.2 14.6 15.9
11.車両重量が 1,651㎏以上 1,761㎏未満 12.2 13.5 14.7
12.車両重量が 1,761㎏以上 1,871㎏未満 11.1 12.3 13.4
13.車両重量が 1,871㎏以上 1,991㎏未満 10.2 11.3 12.3
14.車両重量が 1,991㎏以上 2,101㎏未満 9.4 10.4 11.3
15.車両重量が 2,101㎏以上 2,271㎏未満 8.7 9.6 10.5
16.車両重量が 2,271㎏以上 7.4 8.2 8.9
2.軽貨物自動車 (単位:㎞ /ℓ)
区 分 燃費基準値 燃費基準+10%値
燃費基準+20%値
1.車両重量が 741㎏未満
構造AMT 23.2 25.6 27.9
AT 20.9 23.0 25.1
構造BMT 18.2 20.1 21.9
AT 16.4 18.1 19.7
2.車両重量が 741㎏以上 856㎏未満
構造AMT 20.3 22.4 24.4
AT 19.6 21.6 23.6
構造BMT 18.0 19.8 21.6
AT 16.0 17.6 19.2
3.車両重量が 856㎏以上 971㎏未満
構造AMT 20.3 22.4 24.4
AT 18.9 20.8 22.7
構造BMT 17.2 19.0 20.7
AT 15.4 17.0 18.5
4.車両重量が 971㎏以上
構造AMT 20.3 22.4 24.4
AT 18.9 20.8 22.7
構造BMT 16.4 18.1 19.7
AT 14.7 16.2 17.7
(注)軽貨物自動車……………軽自動車である貨物自動車
平成27年度燃費基準値及び減税対象基準値

245
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3.貨物自動車(車両総重量1.7t以下) (単位:㎞/ℓ)
区 分 燃費基準値 燃費基準+10%値
燃費基準+20%値
1.車両重量が 1,081㎏未満MT 18.5 20.4 22.2AT 17.4 19.2 20.9
2.車両重量が 1,081㎏以上 1,196㎏未満MT 17.1 18.9 20.6AT 15.8 17.4 19.0
3.車両重量が 1,196㎏以上MT 17.1 18.9 20.6AT 14.7 16.2 17.7
4.貨物自動車(車両総重量1.7t超3.5t以下)
区 分 燃費基準値 燃費基準+5%値
燃費基準+10%値
燃費基準+20%値
1.車両重量が 1,311㎏未満
構造AMT 14.2 15.0 15.7 17.1AT 13.3 14.0 14.7 16.0
構造B1MT 11.9 12.5 13.1 14.3AT 10.9 11.5 12.0 13.1
構造B2MT 11.2 11.8 12.4 13.5AT 10.5 11.1 11.6 12.6
2.車両重量が 1,311㎏以上 1,421㎏未満
構造AMT 14.2 15.0 15.7 17.1AT 12.7 13.4 14.0 15.3
構造B1MT 10.6 11.2 11.7 12.8AT 9.8 10.3 10.8 11.8
構造B2MT 10.2 10.8 11.3 12.3AT 9.7 10.2 10.7 11.7
3.車両重量が 1,421㎏以上 1,531㎏未満
構造AMT 14.2 15.0 15.7 17.1AT 12.7 13.4 14.0 15.3
構造B1MT 10.3 10.9 11.4 12.4AT 9.6 10.1 10.6 11.6
構造B2MT 9.9 10.4 10.9 11.9AT 8.9 9.4 9.8 10.7
4.車両重量が 1,531㎏以上 1,651㎏未満
構造AMT 14.2 15.0 15.7 17.1AT 12.7 13.3 14.0 15.3
構造B1MT 10.0 10.5 11.0 12.0AT 9.4 9.9 10.4 11.3
構造B2MT 9.7 10.2 10.7 11.7AT 8.6 9.1 9.5 10.4
5.車両重量が 1,651㎏以上 1,761㎏未満
構造AMT 14.2 15.0 15.7 17.1AT 12.7 13.4 14.0 15.3
構造B1MT 9.8 10.3 10.8 11.8AT 9.1 9.6 10.1 11.0
構造B2MT 9.3 9.8 10.3 11.2AT 7.9 8.3 8.7 9.5
6.車両重量が 1,761㎏以上 1,871㎏未満
構造AMT 14.2 15.0 15.7 17.1AT 12.7 13.4 14.0 15.3
構造B1MT 9.7 10.2 10.7 11.7AT 8.8 9.3 9.7 10.6
構造B2MT 8.9 9.4 9.8 10.7AT 7.9 8.3 8.7 9.5
7.車両重量が 1,871㎏以上
構造AMT 14.2 15.0 15.7 17.1AT 12.7 13.4 14.0 15.3
構造B1MT 9.7 10.2 10.7 11.6AT 8.5 9.0 9.4 10.2
構造B2MT 8.9 9.4 9.8 10.7AT 7.9 8.3 8.7 9.5
⑴ ガソリン自動車 (単位:㎞ /ℓ)

246
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
区 分 燃費基準値 燃費基準+5%値
燃費基準+10%値
燃費基準+20%値
1.車両重量が 1,421㎏未満
構造A又は構造B1
MT 14.5 15.3 16.0 17.4
AT 13.1 13.8 14.5 15.8
構造B2MT 14.3 15.1 15.7 17.2
AT 12.5 13.2 13.8 15.0
2.車両重量が 1,421㎏以上 1,531㎏未満
構造A又は構造B1
MT 14.1 14.9 15.6 17.0
AT 12.8 13.5 14.1 15.4
構造B2MT 12.9 13.6 14.2 15.5
AT 11.8 12.4 13.0 14.2
3.車両重量が 1,531㎏以上 1,651㎏未満
構造A又は構造B1
MT 13.8 14.5 15.2 16.6
AT 11.5 12.1 12.7 13.8
構造B2MT 12.6 13.3 13.9 15.2
AT 10.9 11.5 12.0 13.1
4.車両重量が 1,651㎏以上 1,761㎏未満
構造A又は構造B1
MT 13.6 14.3 15.0 16.4
AT 11.3 11.9 12.5 13.6
構造B2MT 12.4 13.1 13.7 14.9
AT 10.6 11.2 11.7 12.8
5.車両重量が 1,761㎏以上 1,871㎏未満
構造A又は構造B1
MT 13.3 14.0 14.7 16.0
AT 11.0 11.6 12.1 13.2
構造B2MT 12.0 12.6 13.2 14.4
AT 9.7 10.2 10.7 11.7
6.車両重量が 1,871㎏以上 1,991㎏未満
構造A又は構造B1
MT 12.8 13.5 14.1 15.4
AT 10.8 11.4 11.9 13.0
構造B2MT 11.3 11.9 12.5 13.6
AT 9.5 10.0 10.5 11.4
7.車両重量が 1,991㎏以上 2,101㎏未満
構造A又は構造B1
MT 12.3 13.0 13.6 14.8
AT 10.3 10.9 11.4 12.4
構造B2MT 11.2 11.8 12.4 13.5
AT 9.0 9.5 9.9 10.8
8.車両重量が 2,101㎏以上
構造A又は構造B1
MT 11.7 12.3 12.9 14.1
AT 9.4 9.9 10.4 11.3
構造B2MT 11.1 11.7 12.3 13.4
AT 8.8 9.3 9.7 10.6
⑵ ディーゼル自動車 (単位:㎞ /ℓ)
5.小型バス(乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t以下) (単位:㎞ /ℓ)
区 分 燃費基準値 燃費基準+5%値
燃費基準+10%値
燃費基準+20%値
1.ガソリン自動車 8.5 9.0 9.4 10.2
2.ディーゼル自動車 9.7 10.2 10.7 11.7

247
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
6.トラック等(車両総重量3.5t超の貨物自動車) (単位:㎞ /ℓ)
区 分燃費基準値 燃費基準
+5%値燃費基準+10%値車両総重量 最大積載量
1.車両総重量が 3.5t超 7.5t以下
1.5t以下 10.83 11.38 11.92
1.5t超2.0t以下 10.35 10.87 11.39
2.0t超3.0t以下 9.51 9.99 10.47
3.0t超 8.12 8.53 8.94
2.車両総重量が 7.5t超 8.0t以下 7.24 7.61 7.97
3.車両総重量が 8.0t超 10.0t以下 6.52 6.85 7.18
4.車両総重量が 10.0t超 12.0t以下 6.00 6.30 6.60
5.車両総重量が 12.0t超 14.0t以下 5.69 5.98 6.26
6.車両総重量が 14.0t超 16.0t以下 4.97 5.22 5.47
7.車両総重量が 16.0t超 20.0t以下 4.15 4.36 4.57
8.車両総重量が 20.0t超 4.04 4.25 4.45
7.トラクタ(車両総重量3.5t超の貨物自動車) (単位:㎞ /ℓ)
区 分 燃費基準値 燃費基準+5%値
燃費基準+10%値
1.車両総重量が 20.0t以下 3.09 3.25 3.40
2.車両総重量が 20.0t超 2.01 2.12 2.22
8.路線バス(乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t超) (単位:㎞ /ℓ)
区 分 燃費基準値 燃費基準+5%値
燃費基準+10%値
1.車両総重量が 3.5t超 8.0t以下 6.97 7.32 7.67
2.車両総重量が 8.0t超 10.0t以下 6.30 6.62 6.93
3.車両総重量が 10.0t超 12.0t以下 5.77 6.06 6.35
4.車両総重量が 12.0t超 14.0t以下 5.14 5.40 5.66
5.車両総重量が 14.0t超 4.23 4.45 4.66
9.一般バス(乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t超) (単位:㎞ /ℓ)
区 分 燃費基準値 燃費基準+5%値
燃費基準+10%値
1.車両総重量が 3.5t超 6.0t以下 9.04 9.50 9.95
2.車両総重量が 6.0t超 8.0t以下 6.52 6.85 7.18
3.車両総重量が 8.0t超 10.0t以下 6.37 6.69 7.01
4.車両総重量が 10.0t超 12.0t以下 5.70 5.99 6.27
5.車両総重量が 12.0t超 14.0t以下 5.21 5.48 5.74
6.車両総重量が 14.0t超 16.0t以下 4.06 4.27 4.47
7.車両総重量が 16.0t超 3.57 3.75 3.93
備 考1.「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第6号に規定する空車状態における自動車の重量をいう。
2.「車両総重量」とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条第9号に規定する積車状態における自動車の重量をいう。3.「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。 イ.最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。 ロ.乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の
隔壁により仕切られるものであること。 ハ.運転者室の前方に原動機を有するものであること。4.「構造B」とは、構造A以外の構造をいう。5.「構造B1」とは、構造Bのうち備考3ロに掲げる要件に該当する構造をいう。6.「構造B2」とは、構造Bのうち構造B1以外の構造をいう。7.「燃費基準+20%(+10%、+5%)値」とは、燃費基準値に120/100(+10%については110/100、+5%については105/100)を掛け少数第2位(車両総重量3.5t超のものは少数第3位)を切り上げしたもの。

248
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1.乗用自動車(ガソリン自動車) (単位:㎞ /ℓ)
区 分 燃費基準値 燃費基準+25%値
燃費基準+38%値
燃費基準+50%値
1.車両重量が 703㎏未満 21.2 26.5 29.3 31.8
2.車両重量が 703㎏以上 828㎏未満 18.8 23.5 25.9 28.2
3.車両重量が 828㎏以上 1,016㎏未満 17.9 22.4 24.7 26.9
4.車両重量が 1,016㎏以上 1,266㎏未満 16.0 20.0 22.1 24.0
5.車両重量が 1,266㎏以上 1,516㎏未満 13.0 16.3 17.9 19.5
6.車両重量が 1,516㎏以上 1,766㎏未満 10.5 13.1 14.5 15.8
7.車両重量が 1,766㎏以上 2,016㎏未満 8.9 11.1 12.3 13.4
8.車両重量が 2,016㎏以上 2,266㎏未満 7.8 9.8 10.8 11.7
9.車両重量が 2,266㎏以上 6.4 8.0 8.8 9.6
平成22年度燃費基準値及び減税対象基準値
区 分燃費基準値 燃費基準
+25%値燃費基準+38%値
燃費基準+50%値自動車の種別 変速装置の方式 車両重量 自動車の構造
1.軽自動車
MT
703㎏未満構造A 20.2 25.3 27.9 30.3
構造B 17.0 21.3 23.5 25.5
703㎏以上828㎏未満
構造A 18.0 22.5 24.8 27.0
構造B 16.7 20.9 23.0 25.1
828㎏以上 15.5 19.4 21.4 23.3
AT
703㎏未満構造A 18.9 23.6 26.1 28.4
構造B 16.2 20.3 22.4 24.3
703㎏以上828㎏未満
構造A 16.5 20.6 22.8 24.8
構造B 15.5 19.4 21.4 23.3
828㎏以上 14.9 18.6 20.6 22.4
2.車両総重量が 1.7t以下のもの
MT1,016㎏未満 17.8 22.3 24.6 26.7
1,016㎏以上 15.7 19.6 21.7 23.6
AT1,016㎏未満 14.9 18.6 20.6 22.4
1,016㎏以上 13.8 17.3 19.0 20.7
3.車両総重量が 1.7t超 2.5t以下のもの
MT
1,266㎏未満構造A 14.5 18.1 20.0 21.8
構造B 12.3 15.4 17.0 18.5
1,266㎏以上1,516㎏未満 10.7 13.4 14.8 16.1
1,516㎏以上 9.3 11.6 12.8 14.0
AT1,266㎏未満
構造A 12.5 15.6 17.3 18.8
構造B 11.2 14.0 15.5 16.8
1,266㎏以上 10.3 12.9 14.2 15.5
2.貨物自動車(ガソリン自動車) (単位:㎞ /ℓ)
備 考1.「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第6号に規定する空車状態における自動車の重量をいう。
2.「車両総重量」とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条第9号に規定する積車状態における自動車の重量をいう。3.「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。 イ.最大積載量を車両総重量で徐した値が0.3以下となるものであること。 ロ.乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の
隔壁により仕切られるものであること。 ハ.運転者室の前方に原動機を有するものであること。4.「構造B」とは、構造A以外の構造をいう。5.「燃費基準+50%(+38%、+25%)値」とは、燃費基準値に150/100(+38%については138/100、+25%については125/100)を掛け少数第2位を四捨五入したもの。

249
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
[注 意 事 項]
1.電気自動車(燃料電池自動車を含む)・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド自動車・ディーゼル乗用車・車両総重量3.5t超のディーゼルトラック・バス(ハイブリッド自動車を含む)については、各メーカーをそれぞれの車種ごとに括り掲載しています。
また、低燃費かつ低排出ガス認定車については、メーカーごとに、登録車(ハイブリッド自動車を含む)と軽自動車(ハイブリッド自動車を含む)に分けて掲載しています。
2.型式指定番号は同一の通称名の中で、類別区分番号は同一の型式指定番号の中で、それぞれ昇順に記載しています。また、同一型式でも類別区分番号によっては燃費基準値を満たしていないものがあり、その場合には掲載されていません。
3.車両型式欄の※印のついている型式は「構造A」(乗用車派生貨物車)を示します。
4.JC08モードの低燃費区分欄「低燃費+0%」は平成27年度燃費基準を達成している自動車を、「低燃費+5%」は平成27年度燃費基準+5%以上達成している自動車を、「低燃費+10%」は平成27年度燃費基準+10%以上達成している自動車を、「低燃費+20%」は平成27年度燃費基準+20%以上達成している自動車を表記しています。
5.10・15モードの低燃費区分欄「低燃費+25%」は平成22年度燃費基準+25%以上達成している自動車を、「低燃費+38%」は平成22年度燃費基準+38%以上達成している自動車を、「低燃費+50%」は平成22年度燃費基準+50%以上達成している自動車を表記しています。
6.燃費基準とは、省エネ法に基づき定められている燃費基準をいいます。
7.排出ガス規制値に対して一定の低減レベルの達成が求められている自動車については、低排出ガス車認定制度に基づき国土交通大臣の認定を受けている必要があります。
8.ガソリン自動車及びディーゼル自動車の燃費基準値は、前頁のとおりです。
9.車両重量・車両総重量欄は、乗用車については「車両重量」を、乗用車以外については「車両総重量」を表記しています。

250
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
[ 参 考 ]
〈自動車税のグリーン化の内容〉
適用対象:⑴ 排出ガス性能及び燃費性能が下記の条件を満たす普通自動車及び小型自動車 ⑵ 電気自動車(燃料電池車を含む。)、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(一定の排出ガス基 準を満たすものに限る。) ※軽自動車は本取扱いの対象とはなりません。軽減期間:新車新規登録した年度の、翌年度分の自動車税が軽減されます。制度期間:平成24年度から平成25年度まで軽減内容 ⑴
No 新車新規登録(初度登録) 軽減される年度
軽 減 基 準軽減率
排出ガス基準 燃費基準
1 平成23年度 平成24年度のみ 低排出ガス車☆☆☆☆
平成22年度 ※1、2
燃費基準+25%達成車 概ね50%
2 平成24年度平成25年度 登録の翌年度1年間 平成17年度
排出ガス基準75%達成平成27年度燃費基準+10%達成 概ね50%
3 平成24年度平成25年度 登録の翌年度1年間 平成17年度
排出ガス基準75%達成平成27年度燃費基準判断できず平成22年度燃費基準+38%達成 概ね50%
4 平成24年度平成25年度 登録の翌年度1年間 平成17年度
排出ガス基準75%達成平成27年度燃費基準達成 概ね25%
5 平成24年度平成25年度 登録の翌年度1年間 平成17年度
排出ガス基準75%達成平成27年度燃費基準判断できず平成22年度燃費基準+25%達成 概ね25%
※1ディーゼル車は、「平成17年度燃費基準」と読み替えます。※2燃費基準を達成している場合、車検証の備考欄にその旨が記載されます。
⑵ 電気自動車(燃料電池車を含む。)、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(一定の排出ガス基準を満たすものに 限る。) →概ね50%軽減
◦自動車税の特例措置◦

251
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
区分
車両重量
3年自家用 2年自家用 1年自家用 1年事業用
エコカー減免適用エコカー減免
適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外
免 税 75%減 50%減 免 税 75%減 50%減 右以外 13年経過18年経過免 税 75%減 50%減 右以外 13年経過18年経過免 税 75%減 50%減 右以外 13年経過18年経過
0.5トン以下
免税
1,800 3,700 12,300
免税
1,200 2,500 5,000 8,200 10,000 12,600
免税
600 1,200 2,500 4,100 5,000 6,300
免税
600 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800
〜1 3,700 7,500 24,600 2,500 5,000 10,000 16,400 20,000 25,200 1,200 2,500 5,000 8,200 10,000 12,600 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
〜1.5 5,600 11,200 36,900 3,700 7,500 15,000 24,600 30,000 37,800 1,800 3,700 7,500 12,300 15,000 18,900 1,800 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400
〜2 7,500 15,000 49,200 5,000 10,000 20,000 32,800 40,000 50,400 2,500 5,000 10,000 16,400 20,000 25,200 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200
〜2.5 9,300 18,700 61,500 6,200 12,500 25,000 41,000 50,000 63,000 3,100 6,200 12,500 20,500 25,000 31,500 3,100 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000
〜3 11,200 22,500 73,800 7,500 15,000 30,000 49,200 60,000 75,600 3,700 7,500 15,000 24,600 30,000 37,800 3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800
◦平成24年度税制改正に伴う自動車重量税の変更について(H24.5.1~)◦
1.乗 用
●平成24年度税制改正に伴う自動車重量税税率の基本的な考え方(フローチャート)
※車両の種別により、13・18年経過の考え方が異なりますので、ご注意願います。 また、以下は13年経過の例ですが、18年経過の考え方についても、同様となります。
①登録自動車及び小型二輪の場合原則として、初度登録年月(小型二輪の場合は初度検査年月)から12年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。※平成11年6月に初度登録(小型二輪の場合は初度検査)を受けた車両の場合の例
H11.6起算日
H12.51年経過する月
H23.512年経過する月
H24.513年経過する月6月〇日 初度登録
(又は初度検査)
H11.6に初度登録(又は初度検査)を受けた車両の適用日は、H24.5.1。
初度登録(小型二輪の場合は初度検査)の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から13年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。
②検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合原則として、初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。※平成11年に初度検査を受けた車両の場合の例
H11起算日
H121年経過した年
H2312年経過した年
H2413年経過した年6月〇日 初度検査
H11初度検査を受けた車両の適用日は、H24.12.1。
初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、「当該交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。
●平成24年5月1日からの新しい自動車重量税税率表
※表中の税額単位はいずれも円
エコカー減税対象車
免税対象車
75%・50%軽減対象車
YES
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
YESNO
NO
NO
平成24年5月1日から
平成27年4月30日までの間の新車新規検査
平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間の新車新規検査で免税とされた後、最初に受ける継続
検査、又は平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間の
最初に受ける継続検査本則税率
(「エコカー」の欄をご覧下さい)
本則税率を免除
本則税率を50%軽減
75%軽減又は
初度登録(初度検査)から
13年経過している
初度登録(初度検査)から18年経過している
本則税率(「エコカー」の欄をご覧下さい)
本則税率を軽減 50%軽減
18年経過車(「18年経過」の欄をご覧下さい)
13年経過車(「13年経過」の欄をご覧下さい)
13年未満車(「右以外」の欄をご覧下さい)
●「初度登録(初度検査)から13・18年経過している」年数の考え方

252
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
区分
車両総重量
2年自家用 1年自家用 2年事業用 1年事業用
エコカー減免適用エコカー減免
適用なし
エコカー減免適用
エコカー減免適用なしエコカー減免適用
エコカー減免
適用なし
エコカー減免適用
エコカー減免適用なし
エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外
免 税75%減50%減 50%減 右以外13年経過18年経過免 税75%減50%減 50%減 右以外13年経過18年経過
1トン以下
免税
1,200 2,500 6,600 1,200 2,500 3,300 3,800 4,400
免税
1,200 2,500 5,200 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800
〜2 2,500 5,000 13,200 2,500 5,000 6,600 7,600 8,800 2,500 5,000 10,400 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
〜2.5 3,700 7,500 19,800 3,700 7,500 9,900 11,400 13,200 3,700 7,500 15,600 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400
〜3 3,700 7,500 24,600 3,700 7,500 12,300 15,000 18,900 3,700 7,500 15,600 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400
〜4 5,000 10,000 32,800 5,000 10,000 16,400 20,000 25,200 5,000 10,000 20,800 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200
〜5 6,200 12,500 41,000 6,200 12,500 20,500 25,000 31,500 6,200 12,500 26,000 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000
〜6 7,500 15,000 49,200 7,500 15,000 24,600 30,000 37,800 7,500 15,000 31,200 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800
〜7 8,700 17,500 57,400 8,700 17,500 28,700 35,000 44,100 8,700 17,500 36,400 8,700 17,500 18,200 18,900 19,600
〜8 10,000 20,000 65,600 10,000 20,000 32,800 40,000 50,400 10,000 20,000 41,600 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400
3.トラック(車両総重量8トン未満)
2.特種用途
区分
車両総重量
2年自家用 1年自家用 2年事業用 1年事業用
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外
免 税75%減50%減 右以外13年経過18年経過免 税75%減50%減 右以外13年経過18年経過免 税75%減50%減 右以外13年経過18年経過免 税75%減50%減 右以外13年経過18年経過
1トン以下
免税
1,200 2,500 5,000 8,200 10,000 12,600
免税
600 1,200 2,500 4,100 5,000 6,300
免税
1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
免税
600 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800
〜2 2,500 5,000 10,000 16,400 20,000 25,200 1,200 2,500 5,000 8,200 10,000 12,600 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
〜3 3,700 7,500 15,000 24,600 30,000 37,800 1,800 3,700 7,500 12,300 15,000 18,900 3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800 1,800 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400
〜4 5,000 10,000 20,000 32,800 40,000 50,400 2,500 5,000 10,000 16,400 20,000 25,200 5,000 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200
〜5 6,200 12,500 25,000 41,000 50,000 63,000 3,100 6,200 12,500 20,500 25,000 31,500 6,200 12,500 25,000 26,000 27,000 28,000 3,100 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000
〜6 7,500 15,000 30,000 49,200 60,000 75,600 3,700 7,500 15,000 24,600 30,000 37,800 7,500 15,000 30,000 31,200 32,400 33,600 3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800
〜7 8,700 17,500 35,000 57,400 70,000 88,200 4,300 8,700 17,500 28,700 35,000 44,100 8,700 17,500 35,000 36,400 37,800 39,200 4,300 8,700 17,500 18,200 18,900 19,600
〜8 10,000 20,000 40,000 65,600 80,000 100,800 5,000 10,000 20,000 32,800 40,000 50,400 10,000 20,000 40,000 41,600 43,200 44,800 5,000 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400
〜9 11,200 22,500 45,000 73,800 90,000 113,400 5,600 11,200 22,500 36,900 45,000 56,700 11,200 22,500 45,000 46,800 48,600 50,400 5,600 11,200 22,500 23,400 24,300 25,200
〜10 12,500 25,000 50,000 82,000 100,000 126,000 6,200 12,500 25,000 41,000 50,000 63,000 12,500 25,000 50,000 52,000 54,000 56,000 6,200 12,500 25,000 26,000 27,000 28,000
〜11 13,700 27,500 55,000 90,200 110,000 138,600 6,800 13,700 27,500 45,100 55,000 69,300 13,700 27,500 55,000 57,200 59,400 61,600 6,800 13,700 27,500 28,600 29,700 30,800
〜12 15,000 30,000 60,000 98,400 120,000 151,200 7,500 15,000 30,000 49,200 60,000 75,600 15,000 30,000 60,000 62,400 64,800 67,200 7,500 15,000 30,000 31,200 32,400 33,600
〜13 16,200 32,500 65,000 106,600 130,000 163,800 8,100 16,200 32,500 53,300 65,000 81,900 16,200 32,500 65,000 67,600 70,200 72,800 8,100 16,200 32,500 33,800 35,100 36,400
〜14 17,500 35,000 70,000 114,800 140,000 176,400 8,700 17,500 35,000 57,400 70,000 88,200 17,500 35,000 70,000 72,800 75,600 78,400 8,700 17,500 35,000 36,400 37,800 39,200
〜15 18,700 37,500 75,000 123,000 150,000 189,000 9,300 18,700 37,500 61,500 75,000 94,500 18,700 37,500 75,000 78,000 81,000 84,000 9,300 18,700 37,500 39,000 40,500 42,000
〜16 20,000 40,000 80,000 131,200 160,000 201,600 10,000 20,000 40,000 65,600 80,000 100,800 20,000 40,000 80,000 83,200 86,400 89,600 10,000 20,000 40,000 41,600 43,200 44,800
〜17 21,200 42,500 85,000 139,400 170,000 214,200 10,600 21,200 42,500 69,700 85,000 107,100 21,200 42,500 85,000 88,400 91,800 95,200 10,600 21,200 42,500 44,200 45,900 47,600
〜18 22,500 45,000 90,000 147,600 180,000 226,800 11,200 22,500 45,000 73,800 90,000 113,400 22,500 45,000 90,000 93,600 97,200 100,800 11,200 22,500 45,000 46,800 48,600 50,400
〜19 23,700 47,500 95,000 155,800 190,000 239,400 11,800 23,700 47,500 77,900 95,000 119,700 23,700 47,500 95,000 98,800 102,600 106,400 11,800 23,700 47,500 49,400 51,300 53,200
〜20 25,000 50,000 100,000 164,000 200,000 252,000 12,500 25,000 50,000 82,000 100,000 126,000 25,000 50,000 100,000 104,000 108,000 112,000 12,500 25,000 50,000 52,000 54,000 56,000
〜21 26,200 52,500 105,000 172,200 210,000 264,600 13,100 26,200 52,500 86,100 105,000 132,300 26,200 52,500 105,000 109,200 113,400 117,600 13,100 26,200 52,500 54,600 56,700 58,800
〜22 27,500 55,000 110,000 180,400 220,000 277,200 13,700 27,500 55,000 90,200 110,000 138,600 27,500 55,000 110,000 114,400 118,800 123,200 13,700 27,500 55,000 57,200 59,400 61,600
〜23 28,700 57,500 115,000 188,600 230,000 289,800 14,300 28,700 57,500 94,300 115,000 144,900 28,700 57,500 115,000 119,600 124,200 128,800 14,300 28,700 57,500 59,800 62,100 64,400
〜24 30,000 60,000 120,000 196,800 240,000 302,400 15,000 30,000 60,000 98,400 120,000 151,200 30,000 60,000 120,000 124,800 129,600 134,400 15,000 30,000 60,000 62,400 64,800 67,200
〜25 31,200 62,500 125,000 205,000 250,000 315,000 15,600 31,200 62,500 102,500 125,000 157,500 31,200 62,500 125,000 130,000 135,000 140,000 15,600 31,200 62,500 65,000 67,500 70,000

253
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3年自家用2年自家用 1年自家用
3年事業用2年事業用
右以外 13年経過18年経過 右以外 13年経過18年経過 右以外 13年経過18年経過
5,700 3,800 4,400 5,000 1,900 2,200 2,500 4,500 3,000 3,200 3,400
3年自家用 2年自家用 2年事業用
エコカー減免適用エコカー減免
適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外
免 税 75%減 50%減 免 税 75%減 50%減 右以外 13年経過18年経過免 税 75%減 50%減 右以外 13年経過18年経過
免 税 1,800 3,700 9,900 免 税 1,200 2,500 5,000 6,600 7,600 8,800 免 税 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
2輪自家用 2輪事業用 その他自家用 その他事業用
4,900 4,100 9,900 7,800
5.小型二輪 ➡エコカー減免対象外
6.検査対象外軽自動車 ➡エコカー減免対象外
7.検査対象軽自動車(二輪を除く)
※ 2回目以降の届出の際に「自動車重量税用軽自動車届出済証返納証明書」の提出がある場合は非課税
区分
車両総重量
1年自家用 1年事業用 区分
車両総重量
1年自家用 1年事業用
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー減免適用エコカー減免適用なし
エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外 エコカー
エコカー以外
免 税75%減50%減 右以外13年経過18年経過免 税75%減50%減 右以外13年経過18年経過 免 税75%減50%減 右以外13年経過18年経過免 税75%減50%減 右以外13年経過18年経過
1トン以下
免税
600 1,200 2,500 4,100 5,000 6,300
免税
600 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800 〜16
免税
10,000 20,000 40,000 65,600 80,000 100,800
免税
10,000 20,000 40,000 41,600 43,200 44,800
〜2 1,200 2,500 5,000 8,200 10,000 12,600 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600 〜17 10,600 21,200 42,500 69,700 85,000 107,100 10,600 21,200 42,500 44,200 45,900 47,600
〜3 1,800 3,700 7,500 12,300 15,000 18,900 1,800 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400 〜18 11,200 22,500 45,000 73,800 90,000 113,400 11,200 22,500 45,000 46,800 48,600 50,400
〜4 2,500 5,000 10,000 16,400 20,000 25,200 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200 〜19 11,800 23,700 47,500 77,900 95,000 119,700 11,800 23,700 47,500 49,400 51,300 53,200
〜5 3,100 6,200 12,500 20,500 25,000 31,500 3,100 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000 〜20 12,500 25,000 50,000 82,000 100,000 126,000 12,500 25,000 50,000 52,000 54,000 56,000
〜6 3,700 7,500 15,000 24,600 30,000 37,800 3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800 〜21 13,100 26,200 52,500 86,100 105,000 132,300 13,100 26,200 52,500 54,600 56,700 58,800
〜7 4,300 8,700 17,500 28,700 35,000 44,100 4,300 8,700 17,500 18,200 18,900 19,600 〜22 13,700 27,500 55,000 90,200 110,000 138,600 13,700 27,500 55,000 57,200 59,400 61,600
〜8 5,000 10,000 20,000 32,800 40,000 50,400 5,000 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400 〜23 14,300 28,700 57,500 94,300 115,000 144,900 14,300 28,700 57,500 59,800 62,100 64,400
〜9 5,600 11,200 22,500 36,900 45,000 56,700 5,600 11,200 22,500 23,400 24,300 25,200 〜24 15,000 30,000 60,000 98,400 120,000 151,200 15,000 30,000 60,000 62,400 64,800 67,200
〜10 6,200 12,500 25,000 41,000 50,000 63,000 6,200 12,500 25,000 26,000 27,000 28,000 〜25 15,600 31,200 62,500 102,500 125,000 157,500 15,600 31,200 62,500 65,000 67,500 70,000
〜11 6,800 13,700 27,500 45,100 55,000 69,300 6,800 13,700 27,500 28,600 29,700 30,800 〜26 16,200 32,500 65,000 106,600 130,000 163,800 16,200 32,500 65,000 67,600 70,200 72,800
〜12 7,500 15,000 30,000 49,200 60,000 75,600 7,500 15,000 30,000 31,200 32,400 33,600 〜27 16,800 33,700 67,500 110,700 135,000 170,100 16,800 33,700 67,500 70,200 72,900 75,600
〜13 8,100 16,200 32,500 53,300 65,000 81,900 8,100 16,200 32,500 33,800 35,100 36,400 〜28 17,500 35,000 70,000 114,800 140,000 176,400 17,500 35,000 70,000 72,800 75,600 78,400
〜14 8,700 17,500 35,000 57,400 70,000 88,200 8,700 17,500 35,000 36,400 37,800 39,200 〜29 18,100 36,200 72,500 118,900 145,000 182,700 18,100 36,200 72,500 75,400 78,300 81,200
〜15 9,300 18,700 37,500 61,500 75,000 94,500 9,300 18,700 37,500 39,000 40,500 42,000 〜30 18,700 37,500 75,000 123,000 150,000 189,000 18,700 37,500 75,000 78,000 81,000 84,000
4.バス、トラック(トラックは車両総重量8トンから適用)

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
Ⅳ 自動車損害賠償責任保険早わかり

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

257
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
自動車損害賠償責任保険
1 契約締結の強制と保険会社の引受義務(自賠法第5条、第86条の3、第7条、第24条)
自動車の運行により他人を死傷させた場合、運転者および保有者は自動車損害賠償保障法(以下、自賠法)により損害
賠償責任を負う。自賠法は自動車事故による被害者の保護・救済を目的とし、かつ加害者の賠償能力を確保するため、一
部の除外自動車を除いたすべての自動車について自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)の契約締結を義務付けて
いる。これに違反すれば1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられる。一方、自賠責保険の引受け手である保
険会社に対しても正当な理由がない限り契約の締結を拒否できないこととしている。
2 自賠責保険契約を締結しなくともよい自動車(自賠法第5条、第10条、同法施行令第1条)
⑴ 適用除外車
① 自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
② 日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の任務の遂行に必要な自動車
③ 日本国内にある国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車
④ 道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車(構内専用車等)
※保険契約の締結の要望があり、保険会社が引受けを了承すれば契約を締結することができる。
⑵ 自賠責共済の契約が締結されている自動車
3 自賠責保険契約を締結できない自動車 ⑴ 農耕作業車
⑵ トロリーバスや軽車両等
⑶ 身体障害者用電動式車椅子(大きさ、構造による)
4 自賠責保険証明書の備付義務(自賠法第8条)
自動車を運行するにあたり車検証の備付、運転免許証の携帯が義務となっているが、これらに加えて自賠責保険を締結
すると発行される自賠責保険証明書の備付を自賠法により義務付けている。
5 車検期間と保険期間のリンク(自賠法第9条)
運輸支局等は、提示された保険証明書に記載された保険期間が自動車検査証、臨時運行許可証または、回送運行許可証
の有効期間を充足しないときは、新規登録、検査対象軽自動車の車両番号の指定、継続車検等の検査および自動車検査証
の使用者の変更記入等を行わないこととなっている。
6 保険標章(保険ステッカー)表示制度(自賠法第9条の2、第9条の3)
登録自動車は、検査標章の表示により自賠責保険の有無が確認できるが、車検対象外自動車(検査対象外軽自動車・原
動機付自転車等)については、登録・車検制度がないため、保険標章(保険ステッカー)により自賠責の有無を確認でき
るようになっている。なお、これらの自動車の自賠責保険を締結する際、保険期間の満了月の表示されている保険標章(保
険ステッカー)が証明書に合わせて交付される。
7 契約解除の制限(自賠法第20条の2、同法施行規則第5条の2)
自賠責保険契約は、契約当事者間の合意によって解約したり契約締結時に解除条件を付すことを禁止し、下記のような
場合に限り契約の解除を認めている。
⑴ 保険契約者が解約できる場合

258
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
① 登録自動車について滅失し、もしくは解体し、または運行の用に供することをやめたことにより抹消登録を受け
た場合、および輸出するために抹消仮登録を受けた場合
② 軽自動車または小型二輪自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動
車検査協会もしくは全国軽自動車協会連合会に提出した場合
③ 小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標識番号標(原動機付自転車に貸与される試運
転番号標を含む。)を市区町村の長に提出した場合
④ 臨時運行の許可を受けた自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
⑤ 回送運行の許可を受けた自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返納した場合
⑥ 臨時運転番号標の貸与を受けた検査対象外軽自動車について、その番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返
還した場合
⑦ 関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
注 自動車が盗難にあったことを理由とする解約は、当該自動車が抹消登録を受けた等、上記の解約条件を満たし
た場合に限り認められる。
⑵ 保険契約者または保険会社のいずれからも解約できる場合
① 自動車が適用除外自動車(構内専用車など)になった場合
② 重複契約の場合
当該自動車について他に終期が当該自賠責保険契約と同一あるいは遅い自賠責保険契約または自賠責共済契約が
締結されている場合
⑶ 保険会社が解約できる場合
保険契約者、保有者、または運転者の悪意または重大な過失により自動車の番号および種別について事実を告げな
かったり、不実のことを告げた場合(告知義務違反)
8 政府の保障事業(自賠法第72条)
ひき逃げされた場合や自賠責保険が付保されていない自動車にひかれた場合などは、被害者は自賠責保険の支払いを受
けられない。このような被害者を保護するために加害者にかわって政府が被害者に自賠責保険に準じた支払いを行ってい
る。この救済制度を政府の保障事業という。なお、損害保険会社が請求の受付窓口となっている。
9 保険金の支払い(自賠法第3条、第14条)
⑴ 保険金の支払いが受けられる場合
自動車の運行によって他人を傷つけたり死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる者、具体的
には保有者または運転者)に損害賠償責任が発生した場合、保険金の支払いが受けられる。(人身事故に限る。)
注 保有者には、レンタカーを借りて運転する人、友人の車を借りて使用する人、陸送業者なども含まれる。
⑵ 保険金の支払いが受けられない場合
① 電柱に衝突したりして被保険者自身が負傷したようないわゆる自損事故の場合
② 保有者がつぎの3つの条件をすべて立証できる場合
a.自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと
b.被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
c.自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
③ 保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
④ 一台の自動車に重複して自賠責保険の契約がついているときは、締結したときがもっとも早い契約で保険金が支
払われ、他の契約からは重複して支払われない。
⑶ 保険金支払いの内容
支払額は下記の表の基準により損害額を調査のうえ、支払い限度額の範囲内で決定される。保険金の支払い内容(平

259
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
成14年4月1日以降発生の事故)
支 払 い 限 度 額 支 払 い 内 容
傷
害
の
場
合
傷害による損害 被害者1人につき最高120万円まで
救助捜索費治療関係費……応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、
処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用など
原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額をお支払いいたします。
休業損害……1日につき5,700円を支払います。ただし、立証資料等により1日につき5,700円を越えることが明らかな場合は、1日につき 19,000円を限度として、実額を支払います。
休業損害の対象日数は実休業日数を基準とし被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して、治療期間の範囲内で決められます。
慰謝料……1日につき4,200円を支払います。 慰謝料の対象日数は被害者の障害の態様、実治療日数その他を考慮し
て、治療期間の範囲内で決められます。
後遺障害による損害後遺障害の程度により 第1級 最高3,000万円まで 〜第14級 最高75万円まで ※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障
害を残して介護が必要な場合、 常時介護のときは最高4,000万円まで 随時介護のときは最高3,000万円まで
逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの収入)慰謝料等●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護が必要なときは1,600万円(被扶養者がいるときは1,800万円)、
随時介護が必要なときは1,163万円(被扶養者がいるときは1,333万円) また、初期費用等として、常時介護が必要なときは500万円、随時介
護が必要なときは205万円が加算されます。●上記以外の場合 障害の程度により、第1級1,100万円〜第14級32万円 (第1級、第2級、第3級該当者で被扶養者がいるときは、第1級
1,300万円、第2級1,128万円、第3級973万円)
死亡の場合
死亡による損害被害者1人につき最高3,000万円まで
葬儀費……60万円(60万円を超える場合は100万円を限度に妥当な実費)逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)死亡本人の慰謝料……350万円遺族の慰謝料……遺族の人数により550万円〜750万円 なお、被害者に被扶養者があるときは、この金額に200万円加算します。
死亡するまでの傷害による損害 被害者1人につき最高120万円まで
傷害による損害の場合と同じです。
注 つぎのような場合には保険金を減額して支払う。 1.被害者に重大な過失があるとき 2.受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難なとき

260
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
請求者
請求方法加 害 者 被 害 者
本 請 求
損害額が確定したり、損害がお支払い限度額を超えるため、自賠責保険を最終的に請求するという方法です。
治療終了などで損害が確定している場合に直接、損害賠償額を直接請求する方法です。(加害者から損害賠償を受けている場合、または内払金・仮渡金をすでにお支払いしている場合は、その分を差し引いてお支払いすることになります。)
内払金請求
治療などが長引くような場合で、その間に被害者や病院などに支払った損害賠償金が被害者1名につき10万円以上に達したと認められるときに請求することができます。(お支払い済みの内払金は後日の総額が確定したときに差し引かれます。)
治療が長引くような場合で、その間の治療費・休業損害などが被害者1名につき10万円以上に達したと認められるときに請求することができます。(お支払い済みの内払金は後日の総額が確定したときに差し引かれます。)
仮渡金請求
請求できません。(被害者だけが請求できます。) 当座の出費をまかなうために、前払い金として請求できます。支払われる金額は、①死亡の場合…290万円②傷害の場合…その程度に応じて40万円、20万円、5万円の3段階があります。
(最終的な確定額がお支払い済みの仮渡金よりも少ない場合は、差額をお返しいただくことになります。また、加害者に損害賠償責任がないと判明した場合は、ただちにお支払い済みの仮渡金全額をお返しいただきます。)
� 保険金の請求(自賠法第15条、第16条、同法施行令第3条、第19条)
⑴ 保険金請求
保険金を請求できる人は加害者と被害者である。なお、保険金の請求には本請求のほか仮渡金と内払金の請求がある。
① 加害者請求
加害者が被害者や病院などに損害賠償金を支払ったときは、その支払った範囲内で保険金の請求ができる。なお、
請求には被害者や病院などからの領収証が必要となる。
実際に支払った金額についてのみ請求できることになっているため、未払部分について保険金の請求はできない。
② 被害者請求
加害者から損害賠償金の支払が速やかに受けられない場合には、被害者は加害者の加入している保険会社に直接、
損害賠償請求を行うことができる。
③ 保険金の請求方法

261
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
加害者請求の場合 必 要 書 類
被害者請求の場合
死亡 傷害 死 亡 傷 害
保
険
金
仮渡金請求の際に提出していただいた書類は、保険金や損害賠償額請求の場合には再提出していただく必要はありません。 発行者・作成者
損害賠償額
仮
渡
金
損害賠償額
仮
渡
金
● ●1.保 険 金・ 内払金第( )回 支払請求書兼支払指図書 損害賠償額・仮 渡 金
請求書 ● ● ● ●
● ● 2.交通事故証明書(人身) 自動車安全運転センター ● ● ● ●
○ ○ 3.加害車両の自動車検査証・軽自動車届出済証・標識交付証明書等 加害車両所有者 ○ ○ ○ ○
● ● 4.事故発生状況報告書 事故当事者等事故状況に詳しい方 ● ● ● ●
● ●5.・診断書(傷害の場合) ・後遺障害診断書(後遺障害の場合) ・死亡診断書または死体検案書(死亡の場合)
治療を受けた医師または病院 ● ● ● ●
● ● 6.診療報酬明細書 治療を受けた医師または病院 ● ●
● ● 7.通院交通費明細書 被害者など ● ●
○ ○
8.休業損害、看護料等の立証書類 休業損害の証明は ①給与所得者…事業主の休業損害証明書(源泉徴収票添付) ②自由業者、自営業者、農林漁業者等…前年分の税務署受付
印のある確定申告書(控)、納税証明書・課税証明書(所得額の記載されたもの)等
休業損害証明書は事業主、納税証明書・課税証明書等は税務署または市区町村役所
○ ○
● ● 9.被害者の領収書等加害者の支払いを証する書類および示談書(示談成立の場合のみご提出ください。) 事故の当事者
● ● 10.印鑑証明(請求者本人のもの) 市区町村役所 ● ● ● ●
○ ○ 11.委任状および(委任者)の印鑑証明(保険金の請求・受領を第三者に委任する場合) 委任者 ○ ○ ○ ○
●
12.①戸籍謄本 ②戸籍抄本または住民票 (被害者が未成年者で親権者が請求する場合) ③念書 (請求権者に未成年者がいる場合で、親が代理で請求する
とき)
市区町村役所市区町村役所
親権者(または後見人)
●
●
●
●
○ ○
⑵ 保険金請求に必要な書類
⑶ 請求の時効
加害者請求の場合は被害者に損害賠償金を支払ったときから、被害者請求(仮渡金を含む)の場合は通常、普通事
故があった日から2年で時効となり、それ以後は請求できなくなる。
※治療が長引いたり後遺障害が確定しないとき、また、加害者と被害者の話合いがつかないなど2年以内に保険金
の請求ができそうにないときには、前もって保険会社の窓口に相談を行う。
(注1)●印は必ず提出し、○印は事故の内容によって提出する。 (注2)内払金請求の2回目以降は2.3.4.の書類は不要となる。 (注3)後遺障害については症状固定後医師の後遺障害診断書により請求する。 (注4)上記以外の書類が必要なときは保険会社または調査事務所から連絡をする場合がある。

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

� 自動車損害賠償責任保険料表
保険期間車 種
乗 合 自 動 車お よ び
け ん 引 旅 客 自 動 車
営業用
自家用
営 業 用 乗 用 自 動 車 A〜D
自 家 用 乗 用 自 動 車けん引普通貨物自動車
および
普通貨物自動車
営業用
最大積載量が2トンをこえるもの
最大積載量が2トン以下のもの
自家用
最大積載量が2トンをこえるもの
最大積載量が2トン以下のもの
小 型 貨 物 自 動 車お よ び
け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車
営業用
自家用
小 型 二 輪 自 動 車
軽 自 動 車検査対象車
検査対象外車
原 動 機 付 自 転 車
大型特殊自動車および小型特殊自動車
緊 急 自 動 車
商品自動車
イ三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
ロ 小 型 二 輪 自 動 車
ハ 軽 自 動 車検査対象車
検査対象外車
特種用途自動車
イ霊 き ゅ う 自 動 車
ロ教 習 用 自 動 車
ハ
そ
の
他
a.三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
b.小 型 二 輪 自 動 車
c.軽自動車検査対象車
検査対象外車
被けん引自動車(被けん引軽自動車を除く)
被 け ん 引 軽 自 動 車検査対象車
検査対象外車
60か月契 約
48か月契 約
37か月契 約
36か月契 約
35か月契 約
34か月契 約
33か月契 約
32か月契 約
31か月契 約
30か月契 約
29か月契 約
28か月契 約
27か月契 約
26か月契 約
25か月契 約
24か月契 約
23か月契 約
22か月契 約
21か月契 約
20か月契 約
19か月契 約
18か月契 約
17か月契 約
16か月契 約
15か月契 約
14か月契 約
13か月契 約
12か月契 約
11か月契 約
10か月契 約
9か月契 約
8か月契 約
7か月契 約
6か月契 約
5か月契 約
4か月契 約
3か月契 約
2か月契 約
1か月契 約
5 日契 約
57,850 53,870 49,800 45,730 41,670 37,600 33,530 29,470 25,400 21,330 17,270 13,200 9,140
14,560 13,840 13,110 12,380 11,650 10,910 10,180 9,450 8,720 7,990 7,260 6,530 5,800
35,390 34,600 33,790 32,990 32,180 31,380 30,580 29,770 28,970 28,170 27,360 26,560 25,750 24,950 24,130 23,310 22,490 21,670 20,850 20,030 19,210 18,390 17,570 16,750 15,930 15,110 14,270 13,430 12,600 11,760 10,930 10,090 9,250 8,420 7,580 6,740 5,910
96,740 93,170 89,540 85,900 82,270 78,630 75,000 71,360 67,730 64,090 60,460 56,820 53,190 49,550 45,850 42,140 38,430 34,730 31,020 27,310 23,600 19,900 16,190 12,480 8,780
65,870 63,500 61,090 58,680 56,270 53,860 51,450 49,040 46,630 44,220 41,810 39,400 36,980 34,570 32,120 29,660 27,200 24,740 22,280 19,820 17,360 14,900 12,440 9,990 7,530
68,020 65,580 63,080 60,580 58,090 55,590 53,090 50,600 48,100 45,610 43,110 40,610 38,120 35,620 33,080 30,530 27,980 25,440 22,890 20,340 17,800 15,250 12,710 10,160 7,610
44,380 42,850 41,290 39,730 38,170 36,610 35,060 33,500 31,940 30,380 28,820 27,260 25,700 24,150 22,560 20,970 19,380 17,790 16,200 14,610 13,020 11,430 9,840 8,250 6,660
42,640 41,180 39,690 38,200 36,710 35,220 33,730 32,240 30,750 29,260 27,770 26,280 24,790 23,300 21,780 20,260 18,740 17,230 15,700 14,190 12,670 11,150 9,630 8,110 6,590
23,860 23,130 22,380 21,640 20,890 20,150 19,400 18,660 17,910 17,170 16,420 15,680 14,930 14,190 13,430 12,670 11,910 11,150 10,390 9,630 8,870 8,110 7,350 6,590 5,830
18,860 18,500 18,140 17,770 17,400 17,040 16,670 16,310 15,940 15,580 15,210 14,840 14,480 14,110 13,740 13,370 12,990 12,620 12,250 11,880 11,500 11,130 10,760 10,380 10,010 9,640 9,260 8,870 8,490 8,110 7,730 7,350 6,970 6,590 6,210 5,830 5,450
30,840 30,170 29,490 28,800 28,120 27,440 26,750 26,070 25,390 24,700 24,020 23,340 22,650 21,970 21,270 20,570 19,880 19,180 18,480 17,790 17,090 16,390 15,690 15,000 14,300 13,600 12,890 12,180 11,470 10,760 10,050 9,340 8,620 7,910 7,200 6,490 5,780
25,130 21,280 17,350 13,350 9,260
15,600 13,580 11,520 9,420 7,280
11,420 11,170 10,920 10,670 10,420 10,170 9,910 9,660 9,410 9,160 8,910 8,660 8,400 8,150 7,890 7,640 7,380 7,120 6,870 6,610 6,350 6,100 5,840 5,580 5,330
10,930 10,770 10,620 10,460 10,310 10,150 10,000 9,840 9,690 9,530 9,380 9,220 9,070 8,910 8,750 8,590 8,440 8,280 8,120 7,960 7,800 7,640 7,480 7,330 7,170 7,010 6,850 6,690 6,520 6,360 6,200 6,040 5,880 5,720 5,550 5,390 5,230
12,950 12,290 11,640 10,980 10,320 9,670 9,010 8,350 7,700 7,040 6,380 5,730 5,180
8,010 7,760 7,520 7,270 7,030 6,780 6,540 6,290 6,050 5,800 5,560 5,310 5,110
8,010 7,760 7,520 7,270 7,030 6,780 6,540 6,290 6,050 5,800 5,560 5,310 5,110
8,000 7,760 7,520 7,270 7,030 6,790 6,550 6,300 6,060 5,820 5,580 5,330 5,130
9,960 9,770 9,570 9,380 9,190 8,990 8,800 8,600 8,410 8,220 8,020 7,830 7,640 7,440 7,240 7,050 6,850 6,650 6,450 6,260 6,060 5,860 5,660 5,470 5,270
9,960 9,770 9,570 9,380 9,190 8,990 8,800 8,600 8,410 8,220 8,020 7,830 7,640 7,440 7,240 7,050 6,850 6,650 6,450 6,260 6,060 5,860 5,660 5,470 5,270
33,200 32,100 30,990 29,870 28,760 27,640 26,530 25,410 24,300 23,180 22,070 20,950 19,830 18,720 17,580 16,440 15,310 14,170 13,030 11,890 10,760 9,620 8,480 7,340 6,210
21,750 21,310 20,870 20,430 19,990 19,540 19,100 18,660 18,220 17,770 17,330 16,890 16,450 16,010 15,560 15,100 14,650 14,200 13,750 13,300 12,850 12,400 11,950 11,490 11,040 10,590 10,130 9,670 9,210 8,750 8,290 7,830 7,370 6,910 6,450 5,990 5,530
16,450 16,010 15,560 15,100 14,650 14,200 13,750 13,300 12,850 12,400 11,950 11,490 11,040 10,590 10,130 9,670 9,210 8,750 8,290 7,830 7,370 6,910 6,450 5,990 5,530
31,580 26,490 21,300 16,000 10,600
5,100 5,100 5,100 5,100 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080
5,100 5,100 5,100 5,100 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080
5,160 5,150 5,140 5,120 5,110
⑴ 営業用乗用自動車以外の保険料表 (保険始期が平成23年4月1日以降の契約に適用)
本 土 用
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

⑵ 営業用乗用自動車保険料表
保険期間車 種
13か月契 約
12か月契 約
11か月契 約
10か月契 約
9か月契 約
8か月契 約
7か月契 約
6か月契 約
5か月契 約
4か月契 約
3か月契 約
2か月契 約
1か月契 約
5 日契 約
営 業 用 乗 用 自 動 車
A 123,430 114,490 105,370 96,250 87,130 78,010 68,890 59,780 50,660 41,540 32,420 23,300 14,190
B 98,040 91,010 83,850 76,690 69,530 62,360 55,200 48,040 40,880 33,720 26,550 19,390 12,230
C 74,560 69,310 63,960 58,600 53,250 47,900 42,540 37,190 31,840 26,480 21,130 15,780 10,420
D 30,570 28,650 26,680 24,710 22,750 20,790 18,820 16,860 14,890 12,930 10,960 9,000 7,030
使 用 の 本 拠 地 自 動 車 の 種 別 適用保険料12か月
都 道 府 県市 区 等 証明書上の表示 ハ イ ヤ ー、
タクシー区分 証明書上の表示 グループ 保険料円
札 幌 運 輸 支 局(除札幌市) 札 幌 区分せず 営乗 B 91,010
函 館 運 輸 支 局 函 館 区分せず 営乗 B 91,010
室 蘭 運 輸 支 局 室 蘭 区分せず 営乗 B 91,010
旭 川 運 輸 支 局 旭 川 区分せず 営乗 B 91,010
帯 広 運 輸 支 局 帯 広 区分せず 営乗 B 91,010
釧 路 運 輸 支 局 釧 路 区分せず 営乗 B 91,010
北 見 運 輸 支 局 北 見 区分せず 営乗 B 91,010
札 幌 市 札 幌 市 区分せず 営乗 A 114,490
東 京 都(除特別区)
東 京 都 区分せず 営乗 (除武蔵野市、三鷹市のハイヤー) B 91,010
武蔵野市・三鷹市 ハイヤー 営乗(ハイヤー) C 69,310
東 京 都 特 別 区 東京都特別区ハイヤー 営乗(ハイヤー) C 69,310
タクシー 営乗(タクシー) A 114,490
神 奈 川 県(除横浜市、川崎市) 神 奈 川 県 区分せず 営乗 B 91,010
横 浜 市 横 浜 市ハイヤー 営乗(ハイヤー) C 69,310
タクシー 営乗(タクシー) A 114,490
川 崎 市 川 崎 市ハイヤー 営乗(ハイヤー) C 69,310
タクシー 営乗(タクシー) A 114,490
愛 知 県(除名古屋市) 愛 知 県 区分せず 営乗 B 91,010
使 用 の 本 拠 地 自 動 車 の 種 別 適用保険料12か月
都 道 府 県市 区 等 証明書上の表示 ハ イ ヤ ー、
タクシー区分 証明書上の表示 グループ 保険料円
名 古 屋 市 名 古 屋 市ハイヤー 営乗(ハイヤー) C 69,310
タクシー 営乗(タクシー) A 114,490
京 都 府(除京都市) 京 都 府 区分せず 営乗 B 91,010
京 都 市 京 都 市ハイヤー 営乗(ハイヤー) C 69,310
タクシー 営乗(タクシー) A 114,490
大 阪 府(除大阪市) 大 阪 府 区分せず 営乗
(除大阪市域のハイヤー) B 91,010
大 阪 府 大 阪 市 域 ハイヤー 営乗(ハイヤー) C 69,310
大 阪 市 大 阪 市 タクシー 営乗(タクシー) A 114,490
兵 庫 県(除神戸市) 兵 庫 県 区分せず 営乗
(除神戸市域のハイヤー) B 91,010
兵 庫 県 神 戸 市 域 ハイヤー 営乗(ハイヤー) C 69,310
神 戸 市 神 戸 市 タクシー 営乗(タクシー) A 114,490
福 岡 県(除北九州市、福岡市) 福 岡 県 区分せず 営乗 B 91,010
北 九 州 市 北 九 州 市 区分せず 営乗 A 114,490
福 岡 市 福 岡 市 区分せず 営乗 A 114,490
上 記 以 外 の 県 ○ ○ 県 区分せず 営乗 B 91,010
「使用の本拠地」および「自動車の種別」の表示は下表のとおり
(単位 円)
営業用乗用自動車の車種欄においてA、B、CおよびDは、それぞれ次の区分による車種を表わすものとする。 ただし、離島を使用の本拠とする営業用乗用自動車は、離島の保険料表を適用する。A………東京都の特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市および川
崎市に使用の本拠を有するタクシーならびに札幌市、北九州市および福岡市に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く。)
B………札幌運輸支局(札幌市を除く。)、函館運輸支局、室蘭運輸支局、帯広運輸支局、釧路運輸支局、北見運輸支局、旭川運輸支局、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、(特別区のタクシーならびに特別区、武蔵野市および三鷹市のハイヤーを除く。)、神奈川県(横浜市のタクシーおよびハイヤー、川崎市のタクシーおよびハイヤーを除く。)、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県(名古屋市のタクシーおよびハイヤーを除く。)、三重県、滋賀県、京都府(京都市のタクシーおよびハイヤーを除く。)、大阪府(大阪市のタクシー、大阪市域のハイヤーを除く。)、兵庫県(神戸市のタクシー、神戸市域のハイヤーを除く。)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県(北九州市、福岡市を除く。)、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県および鹿児島県に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く。)
C………東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、大阪市域、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市域および川崎市に使用の本拠を有するハイヤー
D………個人タクシー
(注) 車種区分の表中、大阪市域とは、大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、柏原市(大和川以北の区域に限る。)、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、三島郡島本町および泉北郡忠岡町をいい、神戸市域とは、神戸市、尼崎市、明石市(瀬戸川以東の区域に限る。)、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市および川辺郡をいう。
営業用乗用自動車のA、B、CおよびDの車種区分は下表のとおり
本 土 用
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
Ⅴ 自動車の保管場所早わかり

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

267
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1 証明書交付の申請手続き(車庫法施行規則第1条)
⑴ 自家用自動車にあっては、当該申請に係る場所を管轄する警察署長に自動車保管場所証明申請書(第1条関係)2
通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)、及び次の各号に掲げる書面を添付して申請し証明書
及び標章の交付を受ける。
ア 保管場所標章交付申請書(第3条関係)2通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)
イ 保管場所の所在図(付近の道路、目標を表示)
・配置図(周囲の建物等を表示、保管場所の寸法等を明記)
ウ 使用に関する権利関係を証する書面 1通
・土地又は建物が自己所有の場合……保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・土地又は建物が他人所有の場合……保管場所使用承諾書、駐車場賃貸契約書、公法人の確認証明書等
※ 必要に応じて上記以外の書面を求められる場合がありますので、詳しくは各提出警察署にお問い合せ下さい。
⑵ 事業用自動車にあっては、適用除外。
〔自動車の保管場所の確保等に関する法律〕(昭和39年法律第145号)
2 法律適用地域一覧表 ⑴ 登録自動車
都道府県名 適 用 地 域
東 京 都神奈川県埼 玉 県群 馬 県千 葉 県茨 城 県栃 木 県山 梨 県
特別区並びに市、町の区域市、町の区域市、町の区域市、町の区域市、町の区域市並びに町、及び那珂郡東海村の区域市、町の区域市、町の区域
都道府県名 適 用 地 域
東 京 都
神奈川県
埼 玉 県
群 馬 県
千 葉 県
茨 城 県
栃 木 県山 梨 県
特別区並びに八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町、旧城山町を除く)、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市さいたま市、川越市、熊谷市(旧大里町、旧妻沼町、旧江南町を除く)、川口市、所沢市、春日部市(旧庄和町を除く)、狭山市、深谷市(旧岡部町、旧川本町、旧花園町を除く)、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町を除く)、三郷市前橋市(旧大胡町、旧宮城村、旧粕川村、旧富士見村を除く)、高崎市(旧倉渕村、旧箕郷町、旧群馬町、旧榛名町、旧新町、旧吉井町を除く)、桐生市(旧新里村、旧黒保根村を除く)、伊勢崎市(旧赤堀町、旧東村、旧境町を除く)、太田市(旧尾島町、旧新田町、旧藪塚本町を除く)千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市(旧関宿町を除く)、佐倉市、習志野市、柏市(旧沼南町を除く)、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市水戸市(旧内原町を除く)、日立市(旧十王町を除く)、土浦市(旧新治村を除く)、つくば市(旧茎崎町を除く)、ひたちなか市宇都宮市(旧上河内町、河内町を除く)、足利市、小山市甲府市(旧中道町、旧上九一色村を除く)
⑵ 軽自動車の保管場所届出適用地域
※ 市町村合併により、行政区画の境界が変更された場合であっても、自動車保管場所証明及び軽自動車の届出の適用地域に変更はありません。
合併前に適用地域でない区域については、市町村合併後も証明や届出は不要です。 (適用地域は、平成12年6月1日における市町村の区域になります。)

268
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3 認 定 条 件 従来の慣例からみて当該申請場所が、保管場所として適当であるかあるいは不適当であるかの判断基準は、おおよそ次
に掲げる内容で処理されているので参考まで掲載した。
ア 当該申請場所が、道路上の場所でないこと。
イ 当該申請場所が、申請書に記載した車名、型式の自動車を保管することができる広さであること。なお、原則とし
て当該自動車の前後左右にそれぞれ50㎝位を加えた広さ以上なければならないとされているが、2台以上の自動車を
収容する場合は、車両相互間の距離をそれぞれ50㎝位でよいとされている。
ウ 当該申請場所に通ずる道路が、申請書記載の車名、型式の自動車が通行できる幅員であること。ただし、車両制限
令(昭和36年7月17日政令第265号)の規定により各都道府県で適用上の相違があるので幅員の狭い道路の場合にお
いては、事前に所轄の警察の指導を受けることを必要とする場合がある。
エ 当該申請場所が、実際に保管場所として使用されること。
a 当該申請場所が、実際に保管場所として使用されるものであることは、法律の目的、保管場所の証明制度の趣
旨からして当然のことである。原則的には、使用の本拠の位置と保管場所との位置が同一であることが好ましいが、
しかし、それが困難であるという現状においては、実際に使用する限りにおいて、使用の本拠の位置と離れていて
もやむを得ない場合(2㎞を越えないもの)であること。
オ 実際に保管場所として使用することが可能かどうかの具体的な判断については、一般通念によるが、保管場所とし
て一応差し支えない場所として次の場合が挙げられる。
a 軒下、庭先などの空地を使用の場合。ただし、道路にはみ出ることは認められない。
b 住家、店舗、工場、作業場など本来は自動車の保管場所でない建物の一部を使用の場合も認められるが、その自
動車を保管したときにその保管した自動車と、その自動車があることによる周囲の状況とがその建物への人の出入
りなどを妨げるような場合は不適当とされている。
※ 所轄警察署に当該証明書の交付の申請をすると実地調査をし、その報告に基づいて当該証明書を発給するかどうかを
決定することになっているので、通常最高1週間程度の日数を必要とする。
実務に際しては都道府県により取扱が多少相違するので、申請は所轄警察署の指示、指導を受けて行うことが好ましい。
なお、当該証明書の有効期間は、発給後おおむね1か月として運輸支局では処理されている。

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
附 録

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製

271
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
1 運輸支局及び自動車検査登録事務所の管轄区域一覧(関東運輸局管内)
運輸支局及び自動車検査登録事務所 表示名 管 轄 区 域
東京運輸支局本庁舎 品 川 中央区、千代田区、港区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、世田谷区、八丈島、大島、三宅島、新島、式根島、神津島、利島、青ヶ島、御蔵島、小笠原
同上 足立自動車検査登録事務所 足 立 足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区
同上 練馬自動車検査登録事務所 練 馬 練馬区、豊島区、北区、文京区、新宿区、中野区、杉並区、板橋区
同上 多摩自動車検査登録事務所 多 摩三鷹市、調布市、府中市、小金井市、立川市、昭島市、町田市、武蔵野市、東村山市、国分寺市、小平市、国立市、西東京市、東大和市、東久留米市、武蔵村山市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市
同上 八王子自動車検査登録事務所 八王子 八王子市、青梅市、日野市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡
神奈川運輸支局 横 浜 横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町)
同上 川崎自動車検査登録事務所 川 崎 川崎市
同上 相模自動車検査登録事務所 相 模 大和市、相模原市、厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡(愛川町、清川村)
同上 湘南自動車検査登録事務所 湘 南平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、開成町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、真鶴町
埼玉運輸支局 大 宮 川口市、さいたま市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、南埼玉郡(白岡町)、北足立郡
同上 熊谷自動車検査登録事務所 熊 谷 熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、比企郡、秩父郡、児玉郡、大里郡
同上 所沢自動車検査登録事務所所 沢 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見
市、ふじみ野市、日高市、入間郡(三芳町)
川 越 川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡(越生町・毛呂山町)
同上 春日部自動車検査登録事務所 春日部 春日部市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、久喜市、幸手市、吉川市、北葛飾郡、南埼玉郡(宮代町)
群馬運輸支局群 馬 伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、館林市、富岡市、沼田市、藤岡市、前橋市、
みどり市、吾妻市、邑楽郡、甘楽郡、北群馬郡、佐波郡、勢多郡、多野郡、利根郡
高 崎 高崎市、安中市
千葉運輸支局本庁舎千 葉 千葉市、銚子市、佐倉市、東金市、旭市、四街道市、八街市、香取市、匝瑳市、
山武郡(九十九里町・大網白里町)、香取郡(東庄町)、印旛郡(酒々井町)
成 田 成田市、富里市、山武市、香取郡(神崎町・多古町)、山武郡(芝山町・横芝光町)
同上 野田自動車検査登録事務所野 田 松戸市、流山市、野田市
柏 柏市、我孫子市
同上 習志野自動車検査登録事務所 習志野 習志野市、八千代市、船橋市、市川市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市、白井市、印旛郡(栄町)
同上 袖ヶ浦自動車検査登録事務所 袖ヶ浦 館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、鴨川市、市原市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、いすみ市、南房総市、長生郡、夷隅郡、安房郡
茨城運輸支局 水 戸水戸市、北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、東茨城郡(茨城町・大洗町・城里町)、那珂郡(東海村)、久慈郡(大子町)
同上 土浦自動車検査登録事務所土 浦 土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、かすみがうら市、稲敷市、北相
馬郡(利根町)、稲敷郡(美浦村・阿見町・河内町)
つくば 古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、猿島郡(五霞町・境町)、結城郡(八千代町)
栃木運輸支局宇都宮
宇都宮市、日光市、矢板市、塩谷町、那珂川町、さくら市、鹿沼市、那須烏山市、高根沢町、茂木町、市貝町、芳賀町、益子町、真岡市、上三川町、下野市、壬生町
那 須 大田原市、那須塩原市、那須町
同上 佐野自動車検査登録事務所 とちぎ 足利市、栃木市、佐野市、小山市、野木町、岩舟町
山梨運輸支局山 梨
甲府市、山梨市、甲州市、笛吹市、大月市、上野原市、都留市、甲斐市、中央市、北杜市、韮崎市、南アルプス市、昭和町、市川三郷町、富士川町、身延町、早川町、南部町、丹波山村、小菅村
富士山 富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、鳴沢村、忍野村、山中湖村、道志村

272
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
2 全国運輸局、運輸支局の所在地及び支局等コード一覧
支局等コード 名 称 〒 住 所 電 話 番 号
関東運輸局 231−8433 神奈川県横浜市中区北仲通 5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
045−211−7253(管理) 211−7255(技術)
411 東京運輸支局 140−0011 東京都品川区東大井1−12−17
03−3458−9231(総務) 9232(企画) 9233(輸送) 9234(監査) 9236(検査)050−5540−2030 ヘルプデスク(登録)
412 東京運輸支局足立自動車検査登録事務所 121−0062 東京都足立区南花畑5−12−1 050−5540−2031 ヘルプデスク(登録)
03−3884−1513(検査)
413 東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所 179−0081 東京都練馬区北町2−8−6 050−5540−2032 ヘルプデスク(登録)
03−3931−1180(検査)
414 東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所 186−0001 東京都国立市北3−30−3 050−5540−2033 ヘルプデスク(登録)
042−523−2456(検査)
415 東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所 192−0011 東京都八王子市滝山町1−270−2 050−5540−2034 ヘルプデスク(登録)
042−691−6362(検査)
421 神奈川運輸支局 224−0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540
045−939−6800(総務・企画) 6801(輸送) 6802(監査) 6803(整備) 6805(検査)050−5540−2035 ヘルプデスク(登録)
423 神奈川運輸支局川崎自動車検査登録事務所 210−0826 神奈川県川崎市川崎区塩浜3−24−1 050−5540−2036 ヘルプデスク(登録)
044−287−7558(検査)
422 神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所 243−0303 神奈川県愛甲郡愛川町
大字中津字桜台7181050−5540−2037 ヘルプデスク(登録)046−285−4560(検査)
424 神奈川運輸支局湘南自動車検査登録事務所 254−0082 神奈川県平塚市東豊田字道下369−10 050−5540−2038 ヘルプデスク(登録)
0463−54−8909(検査)
441 埼玉運輸支局 331−0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154−2
048−624−1835(総務・企画) 1032(輸送) 6981(整備) 1816(検査)050−5540−2026 ヘルプデスク(登録)
442 埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所 360−0844 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字下林701−4 050−5540−2027 ヘルプデスク(登録)
048−532−8122(検査)
443 埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所 359−0026 埼玉県所沢市大字牛沼字下原兀688−1 050−5540−2029 ヘルプデスク(登録)
04−2998−1603(検査)
444 埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所 344−0042 埼玉県春日部市大字増戸723−1 050−5540−2028 ヘルプデスク(登録)
048−763−5512(検査)
461 群馬運輸支局 371−0007 群馬県前橋市上泉町399−1027−263−4440(企画・輸送) 4432(整備・検査)050−5540−2021 ヘルプデスク(登録)
431 千葉運輸支局 261−0002 千葉県千葉市美浜区新港198
043−242−7336(総務・企画) 7335(輸送) 7338(整備) 7339(検査)050−5540−2022 ヘルプデスク(登録)
434 千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所 278−0013 千葉県野田市上三ヶ尾207−22 050−5540−2023 ヘルプデスク(登録)
04−7121−0112(検査)
432 千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所 274−0063 千葉県船橋市習志野台8−57−1 050−5540−2024 ヘルプデスク(登録)
047−462−6571(検査)
433 千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所 299−0265 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号580−77 050−5540−2025 ヘルプデスク(登録)
0438−63−5592(検査)

273
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
支局等コード 名 称 〒 住 所 電 話 番 号
451 茨城運輸支局 310−0844 茨城県水戸市住吉町353029−247−5348(総務・企画) 5244(輸送) 5249(整備・検査)050−5540−2017 ヘルプデスク(登録)
452 茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所 300−0847 茨城県土浦市卸町2−1−3 050−5540−2018 ヘルプデスク(登録)
029−842−8106(検査)
471 栃木運輸支局 321−0169 栃木県宇都宮市八千代1−14−8028−658−7011(企画・輸送) 7013(整備・検査)050−5540−2019 ヘルプデスク(登録)
472 栃木運輸支局佐野自動車検査登録事務所 327−0044 栃木県佐野市下羽田町2001−7 050−5540−2020 ヘルプデスク(登録)
0283−21−3721(検査)
481 山梨運輸支局 406−0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000−9055−261−0880(企画・輸送) 0882(整備・検査)050−5540−2039 ヘルプデスク(登録)
北海道運輸局 060−0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011−290−2711(代)
111 北海道札幌運輸支局 065−0028 北海道札幌市東区北28条東1丁目 050−5540−2001 ヘルプデスク(登録)
121 北海道函館運輸支局 041−0824 北海道函館市西桔梗町555−24 050−5540−2002 ヘルプデスク(登録)
131 北海道室蘭運輸支局 050−0081 北海道室蘭市日の出町3−4−9 050−5540−2004 ヘルプデスク(登録)
141 北海道帯広運輸支局 080−2459 北海道帯広市西19条北1−8−4 050−5540−2006 ヘルプデスク(登録)
151 北海道釧路運輸支局 084−0906 北海道釧路市鳥取大通6−2−13 050−5540−2005 ヘルプデスク(登録)
161 北海道北見運輸支局 090−0836 北海道北見市三輪23−2 050−5540−2007 ヘルプデスク(登録)
171 北海道旭川運輸支局 070−0902 北海道旭川市春光町10 050−5540−2003 ヘルプデスク(登録)
東北運輸局 983−8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎 022−299−8851(代)
211 宮城運輸支局 983−8540 宮城県仙台市宮城野区扇町3−3−15 050−5540−2011 ヘルプデスク(登録)
221 福島運輸支局 960−8165 福島県福島市吉倉字吉田54 050−5540−2015 ヘルプデスク(登録)
222 福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所 973−8403 福島県いわき市内郷綴町舟湯1−135 050−5540−2016 ヘルプデスク(登録)
231 岩手運輸支局 020−0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2−8−5 050−5540−2010 ヘルプデスク(登録)
241 青森運輸支局 030−0843 青森県青森市大字浜田字豊田139−13 050−5540−2008 ヘルプデスク(登録)
242 青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所 039−2246 青森県八戸市桔梗野工業団地2−12−12 050−5540−2009 ヘルプデスク(登録)
331 山形運輸支局 990−2161 山形県山形市大字漆山字行段1422−1 050−5540−2013 ヘルプデスク(登録)
332 山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所 997−1321 山形県東田川郡三川町
大字押切新田3番地 050−5540−2014 ヘルプデスク(登録)
341 秋田運輸支局 010−0816 秋田県秋田市泉字登木74−3 050−5540−2012 ヘルプデスク(登録)
北陸信越運輸局 950−8537 新潟県新潟市中央区美咲町1−2−1 新潟美咲合同庁舎2号館 025−285−9000(代)
311 新潟運輸支局 950−0961 新潟県新潟市中央区東出来島14−26 050−5540−2040 ヘルプデスク(登録)
312 新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所 940−1104 新潟県長岡市摂田屋町2643−1 050−5540−2041 ヘルプデスク(登録)
321 長野運輸支局 381−8503 長野県長野市西和田1−35−4 050−5540−2042 ヘルプデスク(登録)
322 長野運輸支局松本自動車検査登録事務所 399−0014 長野県松本市平田東2−5−10 050−5540−2043 ヘルプデスク(登録)
561 石川運輸支局 921−8011 石川県金沢市入江3−153 050−5540−2045 ヘルプデスク(登録)
571 富山運輸支局 930−0992 富山県富山市新庄町馬場82 050−5540−2044 ヘルプデスク(登録)

274
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
支局等コード 名 称 〒 住 所 電 話 番 号
中部運輸局 460−8528 愛知県名古屋市中区三の丸2−2−1 名古屋合同庁舎第1号館 052−952−8002(代)
511 愛知運輸支局 454−8558 愛知県名古屋市中川区北江町1−1−2 050−5540−2046 ヘルプデスク(登録)
512 愛知運輸支局西三河自動車検査登録事務所 473−0917 愛知県豊田市若林西町西葉山46 050−5540−2047 ヘルプデスク(登録)
513 愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所 485−0074 愛知県小牧市新小木3−32 050−5540−2048 ヘルプデスク(登録)
514 愛知運輸支局豊橋自動車検査登録事務所 441−8077 愛知県豊橋市神野新田町字京の割20−3 050−5540−2049 ヘルプデスク(登録)
521 静岡運輸支局 422−8004 静岡県静岡市駿河区国吉田2−4−25 050−5540−2050 ヘルプデスク(登録)
522 静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所 435−0007 静岡県浜松市東区流通元町11−1 050−5540−2052 ヘルプデスク(登録)
523 静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所 410−0312 静岡県沼津市原字古田2480 050−5540−2051 ヘルプデスク(登録)
531 岐阜運輸支局 501−6133 岐阜県岐阜市日置江2648−1 050−5540−2053 ヘルプデスク(登録)
532 岐阜運輸支局飛騨自動車検査登録事務所 506−0035 岐阜県高山市新宮町830−5 050−5540−2054 ヘルプデスク(登録)
541 三重運輸支局 514−0303 三重県津市雲出長常町字六ノ割1190−9 050−5540−2055 ヘルプデスク(登録)
551 福井運輸支局 918−8023 福井県福井市西谷1−1402 050−5540−2057 ヘルプデスク(登録)
近畿運輸局 540−8558 大阪府大阪市中央区大手前4−1−76 大阪合同庁舎第4号館 06−6949−6404(代)
611 大阪運輸支局 572−0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12−1 050−5540−2058 ヘルプデスク(登録)
612 大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 594−0011 大阪府和泉市上代町官有地 050−5540−2060 ヘルプデスク(登録)
613 大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所 559−0031 大阪府大阪市住之江区南港東3−1−14 050−5540−2059 ヘルプデスク(登録)
621 京都運輸支局 612−8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37 050−5540−2061 ヘルプデスク(登録)
631 神戸運輸監理部兵庫陸運部 658−0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34−2 050−5540−2066 ヘルプデスク(登録)
632 神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所 672−8588 兵庫県姫路市飾磨区中島福路町3322 050−5540−2067 ヘルプデスク(登録)
641 滋賀運輸支局 524−0104 滋賀県守山市木浜町2298−5 050−5540−2064 ヘルプデスク(登録)
651 奈良運輸支局 639−1037 奈良県大和郡山市額田部北町981−2 050−5540−2063 ヘルプデスク(登録)
661 和歌山運輸支局 640−8404 和歌山県和歌山市湊1106−4 050−5540−2065 ヘルプデスク(登録)
中国運輸局 730−8544 広島県広島市中区上八丁堀6−30 広島合同庁舎4号館 082−228−3434(代)
711 広島運輸支局 733−0036 広島県広島市西区観音新町4−13−13−2 050−5540−2068 ヘルプデスク(登録)
712 広島運輸支局福山自動車検査登録事務所 729−0115 広島県福山市南今津町44 050−5540−2069 ヘルプデスク(登録)
721 鳥取運輸支局 680−0006 鳥取県鳥取市丸山町224 050−5540−2070 ヘルプデスク(登録)
731 島根運輸支局 690−0024 島根県松江市馬潟町43−3 050−5540−2071 ヘルプデスク(登録)
741 岡山運輸支局 703−8245 岡山県岡山市藤原24−1 050−5540−2072 ヘルプデスク(登録)
751 山口運輸支局 753−0812 山口県山口市宝町1−8 050−5540−2073 ヘルプデスク(登録)
四国運輸局 760−0068 香川県高松市松島町1−17−33 高松第2地方合同庁舎 087−835−6351(代)
811 香川運輸支局 761−8023 香川県高松市鬼無町字佐藤20−1 050−5540−2075 ヘルプデスク(登録)
821 徳島運輸支局 771−1156 徳島県徳島市応神町応神産業団地1−1 050−5540−2074 ヘルプデスク(登録)

275
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
支局等コード 名 称 〒 住 所 電 話 番 号
831 愛媛運輸支局 791−1113 愛媛県松山市森松町1070 050−5540−2076 ヘルプデスク(登録)
841 高知運輸支局 781−5103 高知県高知市大津乙1879−1 050−5540−2077 ヘルプデスク(登録)
九州運輸局 812−0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2−10−7 福岡第2合同庁舎 092−472−2312(代)
911 福岡運輸支局 813−8577 福岡県福岡市東区千早3−10−40 050−5540−2078 ヘルプデスク(登録)
912 福岡運輸支局北九州自動車検査登録事務所 800−0211 福岡県北九州市小倉南区新曽根4−1 050−5540−2079 ヘルプデスク(登録)
913 福岡運輸支局久留米自動車検査登録事務所 830−0052 福岡県久留米市上津町2203−290 050−5540−2081 ヘルプデスク(登録)
914 福岡運輸支局筑豊自動車検査登録事務所 820−0115 福岡県飯塚市仁保23−39 050−5540−2080 ヘルプデスク(登録)
921 佐賀運輸支局 849−0928 佐賀県佐賀市若楠2−7−8 050−5540−2082 ヘルプデスク(登録)
931 長崎運輸支局 851−0103 長崎県長崎市中里町1368 050−5540−2083 ヘルプデスク(登録)
932 長崎運輸支局佐世保自動車検査登録事務所 857−1171 長崎県佐世保市沖新町5−5 050−5540−2084 ヘルプデスク(登録)
933 長崎運輸支局厳原自動車検査登録事務所 817−0032 長崎県対馬市厳原町久田645−8 050−5540−2085 ヘルプデスク(登録)
941 熊本運輸支局 862−0901 熊本県熊本市東町4−14−35 050−5540−2086 ヘルプデスク(登録)
951 大分運輸支局 870−0906 大分県大分市大洲浜1−1−45 050−5540−2087 ヘルプデスク(登録)
961 宮崎運輸支局 880−0925 宮崎県宮崎市本郷北方2735−3 050−5540−2088 ヘルプデスク(登録)
971 鹿児島運輸支局 891−0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2−4−1 050−5540−2089 ヘルプデスク(登録)
972 鹿児島運輸支局大島自動車検査登録事務所 894−0007 鹿児島県奄美市和光町12−1 050−5540−2090 ヘルプデスク(登録)
沖縄総合事務局 900−8530 沖縄県那覇市前島2−21−7 098−866−0064
991 沖縄総合事務局陸運事務所 901−2134 沖縄県浦添市字港川512−4 050−5540−2091 ヘルプデスク(登録)
992 沖縄総合事務局宮古運輸事務所(陸運部門) 906−0013 沖縄県宮古島市平良字下里1037−1 050−5540−2092 ヘルプデスク(登録)
993 沖縄総合事務局八重山運輸事務所(陸運部門) 907−0002 沖縄県石垣市字真栄里上原863−15 050−5540−2093 ヘルプデスク(登録)

276
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3 サービスコードの見方サービスコードは各階層の数字で構成されています。
申請したい内容とサービスコードをご確認の上、お電話して下さい。
お電話をお掛けになったら、初めに「0」をプッシュした後、サービスコードをプッシュして下さい。また、電話機によ
り「0」で認識しない機種もありますので、「0」で認識しない場合は「#」「*」「PB」のいずれかを押し、「0」を押
してみて下さい。これで認識する機種があります。
№ 1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 サービスコード
1 1 サービスコード取り出し 1 FAX案内 112 2 軽四輪を除く普
通車の登録手続1 名義変更 1 一般的な手続き 1 音声案内 2111
3 2 FAX案内 21124 2 相続・その他 2125 2 住所変更 1 音声案内 2216 1 FAX案内 222
№ 1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 サービスコード 備 考
1 1 サービスコード取り出し 1 FAX案内 112
2 軽四輪を除く普通車の登録手続
1 名義変更 1 一般的な手続き 1 音声案内 21113 2 FAX案内 21124 2 相続・その他 2125 2 住所変更 1 音声案内 2216 2 FAX案内 2227
3 廃 車
1 自動車の使用の一時中止 1 音声案内 23118 2 FAX案内 23129 2 自動車解体で、自動車重量税還付なし
1 音声案内 232110 2 FAX案内 232211 3 自動車解体で、自動車重量税還付あり
1 音声案内 233112 2 FAX案内 233213 4 自動車輸出する 1 音声案内 234114 2 FAX案内 234215
4再交付及びナンバープレート番号変更
1 自動車検査証の再交付 1 音声案内 241116 2 FAX案内 241217 2 ステッカーの再交付 1 音声案内 242118 2 FAX案内 242219 3 ナンバープレート盗難・遺失等の場合の番号変更
1 音声案内 243120 2 FAX案内 243221 4 ナンバープレートき損・破損の場合の番号変更
1 音声案内 244122 2 FAX案内 244223
5 登録証明書1 現在登録証明書の請求手続
1 音声案内 251124 2 FAX案内 2512 №26と同じ
FAX原稿25 2 詳細登録証明書の請求手続 1 音声案内 252126 2 FAX案内 2522 №24と同じ27 6 その他・オペレーター 26
2 1 1 1
※オペレーターによる案内は登録に関することだけになります。
検査関係の案内は、自動音声案内になるため、詳しい内容をお聞きになりたい方は直接、支局事務所の検査担当(整備
課・検査部門)に電話して下さい。
サービスコード一覧表
初めに、「0」をプッシュした後、サービスコードをプッシュしてください。

277
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
№ 1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 サービスコード 備 考
28
3排気量251㏄以上の二輪車の手続
1 名義変更 1 音声案内 31129 2 FAX案内 31230 2 住所変更 1 音声案内 32131 2 FAX案内 32232 3 廃 車 1 音声案内 33133 2 FAX案内 33234
4再交付及びナンバープレート番号変更
1 自動車検査証の再交付 1 音声案内 341135 2 FAX案内 341236 2 ステッカーの再交付 1 音声案内 342137 2 FAX案内 342238 3 ナンバープレート盗難・遺失等の場合の番号変更
1 音声案内 343139 2 FAX案内 343240 4 ナンバープレートき損・破損の場合の番号変更
1 音声案内 344141 2 FAX案内 344242 5 その他・オペレーター 3543
4排気量126㏄以上250㏄以下の二輪車の手続
1 新規の手続1 新 車 1 音声案内 4111
44 2 FAX案内 411245 2 中古車 1 音声案内 412146 2 FAX案内 412247 2 名義変更 1 音声案内 42148 2 FAX案内 42249 3 住所変更 1 音声案内 43150 2 FAX案内 43251 4 廃 車 1 音声案内 44152 2 FAX案内 44253 5 軽自動車届出済証の再交付 1 音声案内 45154 2 FAX案内 45255
6 ナンバープレート番号変更
1 盗難・遺失等の場合の番号変更1 音声案内 4611
56 2 FAX案内 4612 №58と同じFAX原稿
572 き損・破損の場合の番号変更
1 音声案内 462158 2 FAX案内 4622 №56と同じ
FAX原稿59 7 その他・オペレーター 4760
5 検査関係の案内
1 ユーザー車検を受ける方
1 初めて検査を受ける方 1 音声案内 511161 2 FAX案内 511262 2 継続検査の手続 1 音声案内 512163 2 FAX案内 512264 3 新規検査の手続 1 音声案内 513165 2 FAX案内 513266 4 構造等変更検査の手続 1 音声案内 514167 2 FAX案内 514268 5 検査予約の手続 1 音声案内 515169 2 FAX案内 515270 6 手数料・重量税 1 音声案内 516171 2 FAX案内 516272 7 自動車検査証の有効期限が切れた場合 1 音声案内 517173 2 FAX案内 517274 8 検査場の検査項目 1 音声案内 518175 2 FAX案内 518276
2 定期点検整備
1 定期点検整備 1 音声案内 521177 2 FAX案内 521278 2 四輪自動車の点検整備に関する手引き 1 FAX案内 522179 3 二輪自動車の点検整備に関する手引き 1 FAX案内 523180 4 四輪自動車の整備に実施方法 1 FAX案内 524181 5 二輪自動車の整備の実施方法 1 FAX案内 525182 6 定期点検の間隔及び自動車検査証の有効期間に関する整理表
1 FAX案内 5261
83
3 自動車の改造1 改造自動車等の取扱い 1 音声案内 5311
84 2 FAX案内 531285 2 事前に改造届出の必要な範囲 1 音声案内 532186 2 FAX案内 5322

278
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
№ 1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 サービスコード 備 考
87
3 自動車の改造
3 構造装置の軽微な変更 1 音声案内 533188 2 FAX案内 533289 4 ライトトレーラ 1 音声案内 534190 2 FAX案内 534291 5 けん引重量の記入申請 1 音声案内 535192 2 FAX案内 535293 6 けん引車の型式の記入申請 1 音声案内 536194 2 FAX案内 536295
4 自動車の構造装置の基準
1 初めてお聞きになる方 1 音声案内 541196 2 FAX案内 541297 2 最低地上高 1 音声案内 542198 2 FAX案内 542299 3 タイヤ・ホイール 1 音声案内 5431100 2 FAX案内 5432101 4 ヘッドライト等の灯火装置 1 音声案内 5441102 2 FAX案内 5442103 5 窓ガラスの着色フィルム 1 音声案内 5451104 2 FAX案内 5452105 6 消音器・排気管関係 1 音声案内 5461106 2 FAX案内 5462107
5 自動車の 並行輸入
1 輸入自動車の新規検査の手続 1 音声案内 5511108 2 FAX案内 5512109 2 輸入自動車の改善内容 1 音声案内 5521110 2 FAX案内 5522111 3 排気ガスの検査を行う公的機関の案内
1 音声案内 5531112 2 FAX案内 5532113
6自動車Nox・PM法による使用車種規制
1 対策地域 1 音声案内 5611114 2 FAX案内 5612115 2 規制車種 1 音声案内 5621116 2 FAX案内 5622117 3 自分の車の使用期限 1 音声案内 5631118 2 FAX案内 5632119 4 試験機関 1 音声案内 5641120 2 FAX案内 5642121 5 自治体の通行規制 1 音声案内 5651122 2 FAX案内 5652125
7 特種用途自動車の構造基準
1 構造要件 1 FAX案内 5711126 2 冷蔵冷凍車 1 FAX案内 5721127 3 保温車 1 FAX案内 5731128 4 販売車 1 FAX案内 5741129 5 車いす移動車 1 FAX案内 5751130 6 事務室車 1 FAX案内 5761131 7 キャンピング車 1 FAX案内 5771132 8 放送宣伝車 1 FAX案内 5781133 6 軽四輪自動車及び排気量125㏄以下の二輪車の案内 6134
7 窓口受付時間及び所在地の案内 1 北海道エリア
1 札幌運輸支局 1 音声案内 7111135 2 FAX案内 7112136 2 函館運輸支局 1 音声案内 7121137 2 FAX案内 7122138 3 旭川運輸支局 1 音声案内 7131139 2 FAX案内 7132140 4 室蘭運輸支局 1 音声案内 7141141 2 FAX案内 7142142 5 釧路運輸支局 1 音声案内 7151143 2 FAX案内 7152144 6 帯広運輸支局 1 音声案内 7161145 2 FAX案内 7162146 7 北見運輸支局 1 音声案内 7171147 2 FAX案内 7172

279
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
№ 1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 サービスコード 備 考
148
2 東北エリア
1 青森県内エリア1 青森運輸支局 1 音声案内 72111
149 2 FAX案内 72112150 2 八戸自動車検査登録事務所
1 音声案内 72121151 2 FAX案内 72122152 2 岩手運輸支局 1 音声案内 7221153 2 FAX案内 7222154 3 宮城運輸支局 1 音声案内 7231155 2 FAX案内 7232156 4 秋田運輸支局 1 音声案内 7241157 2 FAX案内 7242158
5 山形県内エリア1 山形運輸支局 1 音声案内 72511
159 2 FAX案内 72512160 2 庄内自動車検査登録事務所
1 音声案内 72521161 2 FAX案内 72522162
6 福島県内エリア1 福島運輸支局 1 音声案内 72611
163 2 FAX案内 72612164 2 いわき自動車検査登録事務所
1 音声案内 72621165 2 FAX案内 72622166
3 関東エリア
1 茨城県内エリア1 茨城運輸支局 1 音声案内 73111
167 2 FAX案内 73112168 2 土浦自動車検査登録事務所
1 音声案内 73121169 2 FAX案内 73122170
2 栃木県内エリア1 栃木運輸支局 1 音声案内 73211
171 2 FAX案内 73212172 2 佐野自動車検査登録事務所
1 音声案内 73221173 2 FAX案内 73222174 3 群馬運輸支局 1 音声案内 7331175 2 FAX案内 7332176
4 千葉県内エリア
1 千葉運輸支局 1 音声案内 73411177 2 FAX案内 73412178 2 野田自動車検査登録事務所
1 音声案内 73421179 2 FAX案内 73422180 3 習志野自動車検査登録事務所
1 音声案内 73431181 2 FAX案内 73432182 4 袖ヶ浦自動車検査登録事務所
1 音声案内 73441183 2 FAX案内 73442184
5 埼玉県内エリア
1 埼玉運輸支局 1 音声案内 73511185 2 FAX案内 73512186 2 熊谷自動車検査登録事務所
1 音声案内 73521187 2 FAX案内 73522188 3 春日部自動車検査登録事務所
1 音声案内 73531189 2 FAX案内 73532190 4 所沢自動車検査登録事務所
1 音声案内 73541191 2 FAX案内 73542192
6 東京都内エリア
1 東京運輸支局 1 音声案内 73611193 2 FAX案内 73612194 2 足立自動車検査登録事務所
1 音声案内 73621195 2 FAX案内 73622196 3 練馬自動車検査登録事務所
1 音声案内 73631197 2 FAX案内 73632198 4 多摩自動車検査登録事務所
1 音声案内 73641199 2 FAX案内 73642200 5 八王子自動車検査登録事務所
1 音声案内 73651201 2 FAX案内 73652202
7 神奈川県内エリア
1 神奈川運輸支局 1 音声案内 73711203 2 FAX案内 73712204 2 川崎自動車検査登録事務所
1 音声案内 73721205 2 FAX案内 73722206 3 相模自動車検査登録事務所
1 音声案内 73731207 2 FAX案内 73732208 4 湘南自動車検査登録事務所
1 音声案内 73741209 2 FAX案内 73742

280
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
№ 1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 サービスコード 備 考
210 8 山梨運輸支局 1 音声案内 7381211 2 FAX案内 7382212
4 北陸信越エリア
1 新潟県内エリア1 新潟運輸支局 1 音声案内 74111
213 2 FAX案内 74112214 2 長岡自動車検査登録事務所
1 音声案内 74121215 2 FAX案内 74122216
2 長野県内エリア1 長野運輸支局 1 音声案内 74211
217 2 FAX案内 74212218 2 松本自動車検査登録事務所
1 音声案内 74221219 2 FAX案内 74222220 3 富山運輸支局 1 音声案内 7431221 2 FAX案内 7432222 4 石川運輸支局 1 音声案内 7441223 2 FAX案内 7442224
5 中部エリア
1 愛知県内エリア
1 愛知運輸支局 1 音声案内 75111225 2 FAX案内 75112226 2 西三河自動車検査登録事務所
1 音声案内 75121227 2 FAX案内 75122228 3 小牧自動車検査登録事務所
1 音声案内 75131229 2 FAX案内 75132230 4 豊橋自動車検査登録事務所
1 音声案内 75141231 2 FAX案内 75142232
2 静岡県内エリア
1 静岡運輸支局 1 音声案内 75211233 2 FAX案内 75212234 2 沼津自動車検査登録事務所
1 音声案内 75221235 2 FAX案内 75222236 3 浜松自動車検査登録事務所
1 音声案内 75231237 2 FAX案内 75232238
3 岐阜県内エリア1 岐阜運輸支局 1 音声案内 75311
239 2 FAX案内 75312240 2 飛騨自動車検査登録事務所
1 音声案内 75321241 2 FAX案内 75322242
4 三重県内エリア1 三重運輸支局 1 音声案内 75411
243 2 FAX案内 75412244 2 四日市自動車検査場
1 音声案内 75421245 2 FAX案内 75422246 5 福井運輸支局 1 音声案内 7551247 2 FAX案内 7552248
6 近畿エリア
1 大阪府内エリア
1 大阪運輸支局 1 音声案内 76111249 2 FAX案内 76112250 2 なにわ自動車検査登録事務所
1 音声案内 76121251 2 FAX案内 76122252 3 和泉自動車検査登録事務所
1 音声案内 76131253 2 FAX案内 76132254
2 京都府内エリア1 京都運輸支局 1 音声案内 76211
255 2 FAX案内 76212256 2 京都南自動車検査場
1 音声案内 76221257 2 FAX案内 76222258 3 奈良運輸支局 1 音声案内 7631259 2 FAX案内 7632260 4 滋賀運輸支局 1 音声案内 7641261 2 FAX案内 7642262 5 和歌山運輸支局 1 音声案内 7651263 2 FAX案内 7652264
6 兵庫県内エリア1 神戸運輸監理部兵庫陸運部
1 音声案内 76611265 2 FAX案内 76612266 2 姫路自動車検査登録事務所
1 音声案内 76621267 2 FAX案内 76622

281
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
№ 1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 サービスコード 備 考
268
7 中国エリア
1 広島県内エリア1 広島運輸支局 1 音声案内 77111
269 2 FAX案内 77112270 2 福山自動車検査登録事務所
1 音声案内 77121271 2 FAX案内 77122272 2 鳥取運輸支局 1 音声案内 7721273 2 FAX案内 7722274 3 島根運輸支局 1 音声案内 7731275 2 FAX案内 7732276 4 岡山運輸支局 1 音声案内 7741277 2 FAX案内 7742278 5 山口運輸支局 1 音声案内 7751279 2 FAX案内 7752280
8 四国エリア
1 徳島運輸支局 1 音声案内 7811281 2 FAX案内 7812282 2 香川運輸支局 1 音声案内 7821283 2 FAX案内 7822284 3 愛媛運輸支局 1 音声案内 7831285 2 FAX案内 7832286 4 高知運輸支局 1 音声案内 7841287 2 FAX案内 7842288
9 九州エリア・沖縄エリア
1 福岡県内エリア
1 福岡運輸支局 1 音声案内 79111289 2 FAX案内 79112290 2 北九州自動車検査登録事務所
1 音声案内 79121291 2 FAX案内 79122292 3 筑豊自動車検査登録事務所
1 音声案内 79131293 2 FAX案内 79132294 4 久留米自動車検査登録事務所
1 音声案内 79141295 2 FAX案内 79142296 2 佐賀運輸支局 1 音声案内 7921297 2 FAX案内 7922298
3 長崎県内エリア
1 長崎運輸支局 1 音声案内 79311299 2 FAX案内 79312300 2 佐世保自動車検査登録事務所
1 音声案内 79321301 2 FAX案内 79322302 3 厳原自動車検査登録事務所
1 音声案内 79331303 2 FAX案内 79332304 4 熊本運輸支局 1 音声案内 7941305 2 FAX案内 7942306 5 大分運輸支局 1 音声案内 7951307 2 FAX案内 7952308 6 宮崎運輸支局 1 音声案内 7961309 2 FAX案内 7962310
7 鹿児島県内エリア1 鹿児島運輸支局 1 音声案内 79711
311 2 FAX案内 79712312 2 大島自動車検査登録事務所
1 音声案内 79721313 2 FAX案内 79722314
8 沖縄県内エリア
1 沖縄陸運事務所 1 音声案内 79811315 2 FAX案内 79812316 2 宮古支所 1 音声案内 79821317 2 FAX案内 79822318 3 八重山支所 1 音声案内 79831319 2 FAX案内 79832320
8 様式類取り出し
1 譲渡証明書 1 FAX案内 811321 2 委任状 1 FAX案内 821322 3 同意書 1 FAX案内 831323 4 理由書 1 FAX案内 841324 5 遺産分割協議書 1 FAX案内 851325 6 永久抹消登録と自動車重量税還付申請に関する委任状 1 FAX案内 861326 7 自動車重量税還付申請書(附票2、附票3) 1 FAX案内 871327 8 清算を結了した法人の登録申請にかかる顛末書 1 FAX案内 881

282
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
4 軽自動車検査協会事務所及び所在地一覧
名 称 〒 住 所 検査予約番号 電 話 番 号
軽自動車検査協会 160−0023 東京都新宿区西新宿3−2−11 − 03−5324−6611
札幌主管事務所 001−0925 北海道札幌市北区新川5条20−1−21 050−3101−9113 011−763−0996
函館事務所 041−0824 北海道函館市西桔梗町830−11 050−3101−9114 0138−48−2500
室蘭事務所 050−0081 北海道室蘭市日の出町2−39−2 050−3101−9116 0143−46−1557
帯広事務所 080−2459 北海道帯広市西19条北1−8−11 050−3101−9118 0155−33−3999
釧路事務所 084−0906 北海道釧路市鳥取大通6−2−3 050−3101−9117 0154−51−0881
北見事務所 090−0836 北海道北見市三輪25−17 050−3101−9119 0157−24−1419
旭川事務所 070−0876 北海道旭川市春光六条5−1−23 050−3101−9115 0166−52−3762
宮城主管事務所 983−0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹4−2−20 050−3101−9120 022−284−1368
福島事務所 960−8165 福島県福島市吉倉字谷地18−1 050−3101−9127 024−546−3222
福島事務所いわき支所 972−8338 福島県いわき市中部工業団地4−3 050−3101−9128 0246−44−4660
岩手事務所 020−0842 岩手県盛岡市湯沢16地割15−10 050−3101−9123 019−639−8011
青森事務所 030−0843 青森県青森市大字浜田字豊田129−2 050−3101−9121 017−739−6568
青森事務所八戸支所 039−2245 青森県八戸市北インター工業団地1−9−2 050−3101−9122 0178−21−2135
山形事務所 990−2251 山形県山形市立谷川2−449 050−3101−9125 023−686−6080
山形事務所庄内支所 997−1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字歌枕109−3 050−3101−9126 0235−68−1350
秋田事務所 011−0901 秋田県秋田市寺内字三千刈463−3 050−3101−9124 018−862−3270
新潟主管事務所 950−0868 新潟県新潟市東区紫竹卸新町1927−12 050−3101−9149 025−275−5845
新潟主管事務所長岡支所 940−1163 新潟県長岡市平島1−3 050−3101−9150 0258−22−0555
長野事務所 381−0037 長野県長野市大字西和田1−38−1 050−3101−9153 026−244−4563
長野事務所松本支所 399−0015 長野県松本市平田西1−8−1 050−3101−9154 0263−58−4055
石川事務所 921−8062 石川県金沢市新保本4−65−8 050−3101−9152 076−269−4747
富山事務所 930−0936 富山県富山市藤木520−1 050−3101−9151 076−423−8472
東京主管事務所 108−0075 東京都港区港南3−3−7 050−3101−9129 03−3472−1561
東京主管事務所足立支所 121−0836 東京都足立区入谷8−10−8 050−3101−9130 03−3897−5675
東京主管事務所練馬支所 175−0081 東京都板橋区新河岸1−12−24 050−3101−9200 03−5399−3811
東京主管事務所多摩支所 183−0003 東京都府中市朝日町3−16−22 050−3101−9132 042−358−1411
東京主管事務所八王子支所 190−1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3−6−1 050−3101−9131 042−557−6262
神奈川事務所 224−0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3914 050−3101−9145 045−938−7752
神奈川事務所相模支所 243−0303 神奈川県愛甲郡愛甲町中津字桜台4071−5 050−3101−9147 046−284−4550
神奈川事務所湘南支所 254−0082 神奈川県平塚市東豊田字道下369−13 050−3101−9146 0463−54−8825
埼玉事務所 362−0055 埼玉県上尾市大字平方領領家字前505−1 050−3101−9138 048−725−2626
埼玉事務所熊谷支所 366−0812 埼玉県深谷市折之口1990−8 050−3101−9140 048−574−1662
埼玉事務所所沢支所 354−0044 埼玉県入間郡三芳町大字北永井360−3 050−3101−9139 049−258−8011
埼玉事務所春日部支所 344−0036 埼玉県春日部市下大増新田字東耕地115−1 050−3101−9201 048−745−7733
群馬事務所 379−2166 群馬県前橋市野中町322−1 050−3101−9137 027−261−4621
千葉事務所 261−0002 千葉県千葉市美浜区新港223−8 050−3101−9141 043−245−0163
千葉事務所習志野支所 274−0063 千葉県船橋市習志野台8−56−1 050−3101−9142 047−461−6600
千葉事務所野田支所 278−0013 千葉県野田市上三ヶ尾207−26 050−3101−9144 04−7120−2020

283
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
名 称 〒 住 所 検査予約番号 電 話 番 号
千葉事務所袖ヶ浦支所 299−0265 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号580−101 050−3101−9143 0438−63−2844
茨城事務所 311−3123 茨城県東茨城郡茨城町若宮字広山887−59 050−3101−9133 029−293−9989
茨城事務所土浦支所 300−0847 茨城県土浦市卸町2−2−8 050−3101−9134 029−843−3535
栃木事務所 321−0158 栃木県宇都宮市西川田本町1−2−37 050−3101−9135 028−645−5161
栃木事務所佐野支所 327−0044 栃木県佐野市下羽田町2001−2 050−3101−9136 0283−20−6116
山梨事務所 406−0034 山梨県笛吹市石和町唐柏792−1 050−3101−9148 055−262−7269
愛知主管事務所 455−0052 愛知県名古屋市港区いろは町2−56−1 050−3101−9155 052−659−2311
愛知主管事務所小牧支所 485−0074 愛知県小牧市新小木3−36 050−3101−9158 0568−75−3464
愛知主管事務所三河支所 473−0917 愛知県豊田市若林西町西葉山48−2 050−3101−9157 0565−51−2555
愛知主管事務所豊橋支所 441−8077 愛知県豊橋市神野新田町字京ノ割18 050−3101−9156 0532−34−3311
静岡事務所 422−8004 静岡県静岡市駿河区国吉田1−1−26 050−3101−9161 054−262−0540
静岡事務所沼津支所 411−0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩字鮎壺1069−1 050−3101−9163 055−988−3847
静岡事務所浜松支所 431−3104 静岡県浜松市東区貴平町字沖ノ宮563 050−3101−9162 053−435−3945
岐阜事務所 501−6257 岐阜県羽島市福寿町平方字丸池東9−1 050−3101−9160 058−394−0232
三重事務所 514−0303 三重県津市雲出長常町字六ノ割1190−10 050−3101−9164 059−234−8431
福井事務所 918−8181 福井県福井市浅水町138字11−3 050−3101−9159 0776−38−1509
大阪主管事務所 559−0031 大阪府大阪市住之江区南港東3−4−62 050−3101−9165 06−6612−1565
大阪主管事務所高槻支所 569−0034 大阪府高槻市大塚町4−20−1 050−3101−9166 072−661−5877
大阪主管事務所和泉支所 593−8316 大阪府堺市山田二丁190−3 050−3101−9167 072−273−1561
京都事務所 612−8418 京都府京都市伏見区竹田向代町51−12 050−3101−9169 075−671−0928
兵庫事務所 651−2145 兵庫県神戸市西区玉津町居住字孫田67−1 050−3101−9172 078−927−3648
兵庫事務所姫路支所 672−8035 兵庫県姫路市飾磨区中島字福路町3313 050−3101−9173 079−231−4101
奈良事務所 639−1037 奈良県大和郡山市額田部北町980−3 050−3101−9170 0743−58−3018
滋賀事務所 524−0104 滋賀県守山市木浜町2298−3 050−3101−9168 077−585−7103
和歌山事務所 641−0036 和歌山県和歌山市湊1106−25 050−3101−9171 073−433−4655
広島主管事務所 733−0036 広島県広島市西区観音新町4丁目13−13−4 050−3101−9174 082−503−8475
広島主管事務所福山支所 729−0115 広島県福山市南今津町41 050−3101−9175 084−934−4887
鳥取事務所 680−0913 鳥取県鳥取市安長77−1 050−3101−9176 0857−28−7001
島根事務所 690−0024 島根県松江市馬潟町字帰リ木65−1 050−3101−9177 0852−37−0539
岡山事務所 701−0144 岡山県岡山市久米177−3 050−3101−9178 086−245−3600
山口事務所 753−0821 山口県山口市葵1−5−57 050−3101−9179 083−924−0542
香川主管事務所 769−0103 香川県綾歌郡国分寺町福家甲1258−18 050−3101−9180 087−870−6676
徳島事務所 771−1156 徳島県徳島市応神町 応神産業団地1−3 050−3101−9181 088−641−4848
愛媛事務所 791−1112 愛媛県松山市南高井町1814−2 050−3101−9182 089−975−6730
高知事務所 781−0270 高知県高知市長浜3106−2 050−3101−9183 088−842−5734
福岡主管事務所 812−0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭2−2−49 050−3101−9184 092−641−8926
福岡主管事務所北九州支所 800−0205 福岡県北九州市小倉南区沼南町3−19−1 050−3101−9185 093−474−3301
福岡主管事務所久留米支所 830−0052 福岡県久留米市上津町字中尾山2199−45 050−3101−9186 0942−21−5680
福岡主管事務所筑豊支所 820−0115 福岡県飯塚市仁保23−68 050−3101−9187 0948−82−3508
長崎事務所 851−0103 長崎県長崎市中里町1600−2 050−3101−9189 095−839−1900
長崎事務所佐世保支所 857−1171 長崎県佐世保市沖新町5−1 050−3101−9190 0956−32−5865

284
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
名 称 〒 住 所 検査予約番号 電 話 番 号
長崎事務所厳原分室 817−0032 長崎県対馬市厳原町久田645−8 050−3101−9191 0920−52−3587
大分事務所 870−0108 大分県大分市三佐5−1−27 050−3101−9193 097−523−0646
佐賀事務所 849−0928 佐賀県佐賀市若楠2−10−8 050−3101−9188 0952−30−4078
熊本事務所 862−0902 熊本県熊本市東本町16−3 050−3101−9192 096−369−5979
宮崎事務所 880−0925 宮崎県宮崎市大字本郷北方2729−4 050−3101−9194 0985−51−3050
鹿児島事務所 891−0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2−4−38 050−3101−9195 099−262−0606
鹿児島事務所大島分室 894−0007 鹿児島県奄美市名瀬和光町12−4 050−3101−9196 0997−53−2808
沖縄事務所 901−2134 沖縄県浦添市字港川500−9 050−3101−9197 098−877−6879
沖縄事務所宮古分室 906−0013 沖縄県宮古島市平良字下里1114−1 050−3101−9198 0980−74−3507
沖縄事務所八重山分室 907−0002 沖縄県石垣市字真栄里863−16 050−3101−9199 0980−84−3233

285
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
5 関東運輸局、及び管内運輸支局並びに軽自動車検査場案内図
至大船
至横浜
首都高速横浜公園ランプ
横浜スタジアム
開港記念館
弁天橋
万国橋
海岸通り
横浜税関
新港ふ頭
第二港湾合庁山下公園
シルクセンター
県庁県庁
JR
市営地下鉄
みずほ銀行
大さん橋
至元町・中華街
馬車道
日本大通り
関内
日本大通り 馬車道
桜木町
関東運輸局
横浜第二合同庁舎
旧関東運輸局(横浜庁舎)
みなとみらい線
関東運輸局〒231−8433 神奈川県横浜市中区北仲通5−57 横浜第2合同庁舎電 話 045−211−7204(代表) 045−211−7253(管理課) 045−211−7254(整備課) 045−211−7255(技術課)
旧川越街道
新大宮バイパス
至川越 至池袋川越街道
自衛隊官舎
練馬車検場前自衛隊練馬駐屯地
光が丘消防署(北町出張所)
東武東上線 東武練馬駅至成増
東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所
北町中学校
練馬自衛隊前
高輪口
港南口
品川駅
八ッ山橋
京浜急行
第一京浜国道
山手線
至五反田 京
浜東北線
至横浜
鮫洲公園
コンビニエンスストア
海岸通り
マンション
首都高速1号線東
京運輸支局
青物横丁駅
鮫洲駅
品川シーサイド駅
鮫洲運転免許試験場
東京運輸支局足立自動車検査登録事務所
東武鉄道
つくばエクスプレス
竹ノ塚駅
至草加
至三郷
環状7号線至西新井
加平ランプ
至亀有
青井駅
六町駅
至亀有
綾瀬駅
至北千住
至小菅ランプ
車検場通り
至上野
交番
首都高速
国道4号線
足立車検場前
青井5丁目
保木間
東京運輸支局〒140−0011 東京都品川区東大井1−12−17電 話 050−5540−2030(登録ヘルプデスク) 03−3458−9236(検査・整備・保安部門)
東京運輸支局足立自動車検査登録事務所〒121−0062 東京都足立区南花畑5−12−1電 話 050−5540−2031(登録ヘルプデスク) 03−3884−1513(検査窓口)
東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所〒179−0081 東京都練馬区北町2−8−6電 話 050−5540−2032(登録ヘルプデスク) 03−3931−1180(検査窓口)
日野橋交差点国道20号線
羽衣町二丁目信号
錦町一丁目信号
東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所
立川駅北口 NTT
南口
緑町通り
五日市街道
多摩車検場
砂川九番
西武バス 車庫
自衛隊
至八王子
至五日市
至新宿
立川第二 中学校
㈳東京都自動車 整備振興会 多摩支所
コンビニ
都立北多摩高校
交番至甲府
至甲府
至横浜
至川越
八王子インター
八王子インター
左入町↗↖左入橋
八王子駅
立川駅
日野駅
拝島駅
拝島橋八王子車検場入口↙
多摩川
中央自動車道
中央自動車道
西武拝島線
JR青梅線
JR横浜線
宇津木台
国道16バイパス
JR中央線
国道16号 至東京
至新宿・東京方面
東京運輸支局
八王子自動車検査
登録事務所
八高線
東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所〒186−0001 東京都国立市北3−30−3電 話 050−5540−2033(登録ヘルプデスク) 042−523−2456 (検査窓口)
東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所〒192−0011 東京都八王子市滝山町1−270−2電 話 050−5540−2034(登録ヘルプデスク) 042−691−6362 (検査窓口)

286
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
東京海洋大学
NTTツインズ
みずほ銀行
アレア品川
バス乗場
ファミリーマート
ローソン
コクヨ
中日新聞(東京新聞)
児童館
港南中学校
港南小学校
港南小前歩道橋
港南の郷
シティハイツ港南港南図書館
五色橋
ローソン
スリーエフコスモポリス 品川
バス停(港南中学校前)バス停ポールに軽検協の地図あり フェイバ
リッチタワー品川
都営港南三丁目
アパート芝
浦下水処理
首都高速1号羽田線海岸通り
高
浜
運
河
旧海岸通り
至東京
東京モノレール
至横浜
東口
港南口
高浜橋新幹線引込線
港南2
東京海洋大学前
浜路橋
公園
新港南橋
芝浦出口
御楯橋
都下水道局汚水処理工場
新港南橋
港南3
軽自動車検査協会東京主管事務所
品川駅
至大宮 至鳩ヶ谷
川口駅より4.5㎞
椿1丁目交差点より4㎞
竹ノ塚駅より4㎞
至春日部
至草加
至亀有
流通センタートラックターミナル
滝野川信用金庫
至北千住
川口駅
JR京浜東北線
東武伊勢崎線
赤羽駅
至上野
至川口
日産プリンス
至鹿浜橋環状七号線
首都高速(川口線)
三菱ふそうサービスセンター
入谷町(交差点)
入谷郵便局
GS
鳩ヶ谷街道
入谷北バス停(国際興業)
JR川口駅発舎人団地行バス
金方バス停(東武バス)
竹ノ塚駅
椿1丁目(交差点)
〒
北足立自動車
教習所
東武竹ノ塚駅発入谷循環バス
軽自動車検査協会 足立支所
軽自動車検査協会東京主管事務所〒108−0075 東京都港区港南3−3−7電 話 03−3472−1561 050−3101−9129(検査予約)
軽自動車検査協会東京主管事務所足立支所〒121−0836 東京都足立区入谷8−10−8電 話 03−3897−5675 050−3101−9130(検査予約)
味の素スタジアム
バス停(警察学校東門)
警視庁警察学校
榊原記念病院
調布福祉園
調布アーバンホテル
飛田給内科クリニック
ミニストップ
至新宿
至新宿
至八王子
京王線
甲州街道
旧甲州街道
飛田給駅
軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所 味の素スタジアム前
飛田給駅入口
味の素スタジアム西
調布市子ども発達センター
市立老人ホーム
都立特別支援学校
白糸台3
榊原記念病院入口
朝日保育所入口警 察 大 学 校
軽自動車検査協会 東京主管事務所 八王子支所
日野自動車工業 羽村工場
栄町二丁目
羽村駅東口
羽村団地入口
都立養護学校新羽村街道
松原中央公園入口
瑞穂南地下道
瑞穂西松原
新青梅街道至新宿
至八王子
至川越岩蔵街道
岩蔵街道至青梅 瑞穂二小前交差点
青梅街道
青梅街道
長岡南会館 バス停
東長岡
西武信用金庫
長岡一丁目
郵便局
下師岡公園
箱根ヶ崎西立体交差点 (側道あり)
松原中央公園
羽村四面道富士見小西
至青梅
至立川
栄小学校入口
市役所通り青
梅線
羽村駅
産業道路
国道16号線
八高線
米軍横田基地
〒
羽村市
動物園
三菱ふそう
軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所〒183−0003 東京都府中市朝日町3−16−22電 話 042−358−1411 050−3101−9132(検査予約)
軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所〒190−1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3−6−1電 話 042−557−6262 050−3101−9131(検査予約)
至世田谷
港北I.C
港北インターチェンジ
至世田谷
ららぽーと
横浜
至長津田
至246号
落合橋
都田中学校入口
日産ディーゼル
緑産業道路
鴨池橋 新川向橋 小机大橋至新横浜
至東神奈川
新横浜元石川線
鶴見川
梅田橋
新整橋
池辺バス停
GS
横浜線横浜上麻生線
至瀬谷区方面
中原街道
横浜上麻生線
池辺隧道
中原街道
大日本印刷
マルハン
都筑店
第三京浜入口
信号
鴨居駅
小机駅
神奈川運輸支局軽自動車検査協会
神奈川事務所
第三京浜
神奈川運輸支局〒224−0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540電 話 050−5540−2035(登録ヘルプデスク) 045−939−6805(検査窓口)
西台駅
西台駅前交番
荒川
新河岸川
高島平九
戸田葬祭場東京三菱ふそう
佐川急便
高砂鐵工 ビッグA
熱帯環境植物館徳丸ケ原公園
西台駅高島通り 都営三田線
高島平警察署
板橋新河岸団地内郵便局
高島平駅
舟渡公園舟渡大橋
セブンイレブン板橋西台駅前郵便局
松坂屋ストア
ケーヨーデイツー
軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所
舟渡大橋北
軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所〒175−0081 東京都板橋区新河岸1−12−24電 話 03−5399−3811 050−3101−9200(検査予約)

287
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
神奈川運輸支局
相模自動車検査登録事務所
至上溝
至半原
至上溝
至新宿
至大和
至大和
至座間
原当麻
座架依橋
桜台五差路
国道246号線
至国道16号 町田
北小
リコートヨタ
ドンキホーテ
新昭和橋
高田橋
愛川町役場
バス停(支局入口)
バス停(西2丁目)
三田金田
山際
萩野新宿
至伊勢原
至茅ヶ崎
旧246号
至平塚(東名厚木IC)本厚木
海老名海老名
厚木
内陸工業団地春日台団地
田名
至三増
国道412
号線 厚木バイパス
小田急線
JR相模線
旧129号
中津川
軽自動車検査協会
神奈川事務所相模支所
平塚八幡宮
国道1号線
神奈川運輸支局
湘南自動車
検査登録事務所日産車体
三菱樹脂
三菱樹脂前
渋田大橋
平塚駅
西口
北口
横浜ゴム
平塚総合公園
総合体育館 湘
南車検場前
国道129号線
日産車体
至藤沢
平塚市役所県道大島
・明石線
平塚合同庁舎
至小田原
渋田川
至新横浜
JR東海道本線
東海道・山陽新幹線
至世田谷
港北I.C
港北インターチェンジ
至世田谷
ららぽーと
横浜
至長津田
至246号
落合橋
都田中学校入口
日産ディーゼル
緑産業道路
鴨池橋 新川向橋 小机大橋至新横浜
至東神奈川
新横浜元石川線
鶴見川
梅田橋
新整橋
池辺バス停
GS
横浜線横浜上麻生線
至瀬谷区方面
中原街道
横浜上麻生線
池辺隧道
中原街道
大日本印刷
第三京浜入口
信号
鴨居駅
小机駅
第三京浜
神奈川運輸支局
軽自動車検査協会
神奈川事務所
マルハン
都筑店
神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所〒243−0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津7181電 話 050−5540−2037(登録ヘルプデスク) 046−285−4560 (検査窓口)
神奈川運輸支局湘南自動車検査登録事務所〒254−0082 神奈川県平塚市東豊田369−10電 話 050−5540−2038(登録ヘルプデスク) 0463−54−8909 (検査窓口)
軽自動車検査協会神奈川事務所〒224−0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3914電 話 045−938−7752 050−3101−9145(検査予約)
神奈川運輸支局
相模自動車検査登録事務所
至上溝
至半原
至上溝
至新宿
至大和
至大和
至座間
原当麻
座架依橋
桜台五差路
国道246号線
至国道16号 町田
北小
リコートヨタ
新昭和橋
高田橋
愛川町役場
バス停(支局入口)
バス停(西2丁目)
三田金田
山際
萩野新宿
至伊勢原
至茅ヶ崎
旧246号
至平塚(東名厚木IC)本厚木
海老名海老名
厚木
内陸工業団地春日台団地
田名
至三増
国道412
号線 厚木バイパス
小田急線
JR相模線
旧129号
中津川
軽自動車検査協会
神奈川事務所相模支所 ドンキホーテ
軽自動車検査協会神奈川事務所相模支所〒243−0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津4071−5電 話 046−284−4550 050−3101−9147(検査予約)
平塚八幡宮
国道1号線
軽自動車検査協会
神奈川事務所
湘南支所
日産車体
三菱樹脂
三菱樹脂前
渋田大橋
平塚駅
西口
北口
横浜ゴム
平塚総合公園
総合体育館 湘
南車検場前
国道129号線
日産車体
至藤沢
平塚市役所県道大島
・明石線
平塚合同庁舎
至小田原
渋田川
至新横浜
JR東海道本線
東海道・山陽新幹線
軽自動車検査協会神奈川事務所湘南支所〒254−0082 神奈川県平塚市東豊田369−13電 話 0463−54−8825 050−3101−9146(検査予約)
東海道線
京浜急行線
神奈川運輸支局
川崎自動車検査
登録事務所
川崎市役所
川崎競輪場
浅田ランプ
川崎警察署
川崎競馬場
国道132号線
川崎区役所
至品川至羽田
バス停(塩浜)
至横浜
至横浜
川崎駅
京急川崎駅
NTT東日本
川崎支店
塩浜操車場
夜光交差点
陸橋 千鳥橋
至東扇島塩
浜交差点
産業道路 高
速神奈川1号横羽線
国道15号(第一京浜)
神奈川運輸支局川崎自動車検査登録事務所〒210−0826 神奈川県川崎市川崎区塩浜3−24−1電 話 050−5540−2036(登録ヘルプデスク) 044−287−7558 (検査窓口)

288
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
籠原駅北口
南口
西別府
駅入口自衛隊入口東方
上増田
田中北
武体西
武体
折之口
17号バイパス
国道17号
JR高崎線
自衛隊日立金属 太
平洋
セメント
ニコン日立物流
上越新幹線GS日石
GS(エッソ)
GS(三菱)
ユニー
古河スカイ
140号バイパス
(籠原駅への案内標識あり)
(インターから約5㎞)
(深谷工業団地への 案内標識あり)
花 園インター
関越自動車道
東芝 陸橋
陸橋
←至深谷
←至高崎
紅白煙突
埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会熊谷支所
武蔵野銀行
埼玉運輸支局所沢
自動車検査登録事務所
至関越・所沢インター
若松小学校
至本川越所沢駅至飯能
西武新宿線
安松
長栄橋
弘法橋
至南浦和
東中学校
牛沼小学校
東川
至新宿
至池袋
至西国分寺
西武池袋線
武蔵野線
東所沢駅
国道463号
松郷
埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所〒360−0844 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原701−4電 話 050−5540−2027(登録ヘルプデスク) 048−532−8122 (検査窓口)
埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所〒359−0026 埼玉県所沢市牛沼688−1電 話 050−5540−2029(登録ヘルプデスク) 04−2998−1603 (検査窓口)
増戸北
至大宮
至東京至北千住
国道16号線
至宇都宮
至柏
至野田
国道4号線
東武伊勢崎線
古利根川
至幸手
春日部駅 西口
国道122号線
(下り)
至久喜
東北自動車道
至東京
国道122号線
(上り)
元荒川
料金所
豊春駅
八木崎駅
東武野田線岩槻駅
東岩槻駅
岩槻I・C
埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所
西大宮バイパス
大宮駅
宮原駅
上尾駅
東北本線ニューシャトル高崎線
バス停(埼玉運輸支局前)
愛宕
17号新大宮バイパス
自衛隊
大宮駐屯地
日進南
大成町3
櫛引町2
大宮西警察署前
清河寺
大宮西警察署
上野
上野北
平方領々家 バス停(平方領家南)
軽自動車検査協会
埼玉事務所
埼玉運輸支局
埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所〒344−0042 埼玉県春日部市増戸723−1電 話 050−5540−2028(登録ヘルプデスク) 048−763−5512 (検査窓口)
軽自動車検査協会埼玉事務所〒362−0055 埼玉県上尾市平方領々家505−1電 話 048−725−2626 050−3101−9138(検査予約)
軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所〒366−0812 埼玉県深谷市折之口1990−8電 話 048−574−1662 050−3101−9140(検査予約)
籠原駅北口
南口
西別府
駅入口自衛隊入口東方
上増田
田中北
武体西
武体
折之口
17号バイパス
国道17号
JR高崎線
自衛隊日立金属 太
平洋
セメント
ニコン日立物流
上越新幹線GS日石
GS(エッソ)
GS(三菱)
ユニー
古河スカイ
140号バイパス
(籠原駅への案内標識あり)
(インターから約5㎞)
(深谷工業団への案内標識あり)
花 園インター
関越自動車道
東芝 陸橋
陸橋
←至深谷
←至高崎
紅白煙突
埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会熊谷支所
埼玉運輸支局〒331−0077 埼玉県さいたま市西区中釘2154−2電 話 050−5540−2026(登録ヘルプデスク) 048−624−1816 (検査窓口)
宮原駅 大宮駅そごう西口ソニックシティ
至浦和 上野
至上尾
新大宮バイパス
JR川越線
西大宮バイパス
至上尾
至浦和
至岩槻国道17号線
新大宮バイパス
JR高崎線
至浦和
至指扇駅
至川越至川越
大宮西警察署
宮前IC
自衛隊大宮駐屯地
日産自動車バス停(運輸支局前)
カインズホーム
セブンイレブン
至首都高 5号線
日進駅
指扇駅
西大宮駅
愛宕 吉野西
大谷本郷
高木
日進南
清河寺
日進1
三橋3三橋5三橋町
桜木町 桜木町4櫛引町2
大成町3
自衛隊
埼玉運輸支局

289
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
至市内 至大胡桂萱小・中学校 桂萱小学校前
中 央前橋駅
上泉駅
県道前橋・大間々・桐生線 天神橋
上 毛 電 鉄石関橋
竹橋
至桐生ケンタッキー
椎茸農協
ゴルフ練習場産業人スポーツセンター
桃ノ木川前橋青果市場
夢書房野中町
野中町
両毛線
交通公園
東部環状線
日赤病院
前橋東警察署
前橋駅 前橋大島駅
国道
号
至渋川
17
県庁
利根川
至高崎(前橋インター)
軽自動車検査協会群馬事務所
群馬運輸支局
至市内 至大胡桂萱小・中学校 桂萱小学校前
中 央前橋駅
上泉駅
県道前橋・大間々・桐生線 天神橋
上 毛 電 鉄石関橋
竹橋
至桐生ケンタッキー
椎茸農協
ゴルフ練習場産業人スポーツセンター
桃ノ木川前橋青果市場
夢書房野中町
野中町
両毛線
交通公園
東部環状線
日赤病院
前橋東警察署
前橋駅 前橋大島駅
国道
号
至渋川
17
県庁
利根川
至高崎(前橋インター)
軽自動車検査協会群馬事務所
群馬運輸支局
稲毛海岸駅
稲毛駅稲毛団地
高洲団地高浜団地中央卸売市場
水路交通会館
運輸支局入口
自動車団地
新港クリーンエネルギーセンター
アクアリンクちば
木材団地
西千葉駅
京成稲毛駅
京成稲毛駅
京
葉
線
みどり台駅
幸町団地
国道14号
総
武
線
軽自動車検査協会
千葉事務所
千葉運輸支局
松戸野田道路
運河駅至柏駅
東京理科大理工学部
東京理科大グラウンド
至常磐道
柏IC
野田工業団地
千葉日産
スズキ千葉東
国道16号線
東武野田線
梅郷駅
山崎小学校
流山街道
利根運河
N千葉運輸支局
野田自動車検査登録事務所
群馬運輸支局〒371−0007 群馬県前橋市上泉町399−1電 話 050−5540−2021(登録ヘルプデスク) 027−263−4432 (検査窓口)
軽自動車検査協会群馬事務所〒379−2166 群馬県前橋市野中町322−1電 話 027−261−4621 050−3101−9137(検査予約)
千葉運輸支局〒261−0002 千葉県千葉市美浜区新港198電 話 050−5540−2022(登録ヘルプデスク) 043−242−7339 (検査窓口)
千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所〒278−0013 千葉県野田市上三ヶ尾207−22電 話 050−5540−2023(登録ヘルプデスク) 04−7121−0112 (検査窓口)
所沢検査登録事務所
至川越方面
至練馬・朝霞方面
至所沢方面 至大宮・浦和方面
県道334号線
国道254号線国道463号線(浦所バイパス)
国道254号(川越街道)
県道56号
けやき並木通り
県道334号
軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所
航空管制前
坂の下橋所沢東高校入口
東入間警察入口
三芳中学校前
三芳小学校前
三芳町役場入口
東所沢入口
亀ヶ谷
藤久保
東新井
南永井
英インター
所沢インター
関越自動車道
鶴間下組
安田病院
三芳町役場
三芳郵便局
鶴瀬
三芳中学校
三芳小学校
オカケン上富
〶
文 文
軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所〒354−0044 埼玉県入間郡三芳町北永井360−3電 話 049−258−8011 050−3101−9139(検査予約)
武里駅
一ノ割駅
東武伊勢崎線
国道16号
豊春駅
東武野田線
八木崎駅
至野田・柏
春日部駅西口
駅入口
地方庁舎
大増中
谷原中
増田新田
増戸(北)
南平野セブンイレブン
ウイングハット春日部
春日部共栄高
秀和綜合病院
春日部署
大沼
かすかべ
湯元温泉
アピタ
GS
GS
島忠
至大宮
セブンイレブンみくに 病院
上大増新田(北) 大沼グランド
防災センター
埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所
軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所〒344−0036 埼玉県春日部市下大増新田字東耕地115−1電 話 048−745−7733 050−3101−9201(検査予約)

290
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
稲毛海岸駅
稲毛駅稲毛団地
高洲団地高浜団地
水路交通会館
中央卸売市場
自動車団地
木材団地
西千葉駅
京成稲毛駅
京成稲毛駅
京
葉
線
みどり台駅
幸町団地
国道14号
総
武
線千葉運輸支局
軽自動車検査協会
千葉事務所
新港クリーンエネルギーセンター
アクアリンクちば
松戸野田道路
運河駅至柏駅
東京理科大理工学部
東京理科大グラウンド
至常磐道
柏IC
野田工業団地
千葉日産
スズキ千葉東
国道16号線
東武野田線
梅郷駅
山崎小学校
流山街道
利根運河
N軽自動車検査協会
千葉事務所野田支所
軽自動車検査協会千葉事務所〒261−0002 千葉県千葉市美浜区新港223−8電 話 043−245−0163 050−3101−9141(検査予約)
軽自動車検査協会千葉事務所野田支所〒278−0013 千葉県野田市上三ヶ尾207−26電 話 04−7120−2020 050−3101−9144(検査予約)
軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所〒299−0265 千葉県袖ヶ浦市長浦580−101電 話 0438−63−2844 050−3101−9143(検査予約)
袖ヶ浦検査登録事務所
国道16号 至千葉
信号機表示板
至木更津
消防署
今井バス停
生コン
パチンコ国道287号
長浦駅
駅前
陸
橋
千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所
長浦駅入口
川
今井野球場
ネッツトヨタ
至船橋
至四街道
至成田
至千葉
至千葉
国道14号(千葉街道)
国道16号
至成田
車検場前 下市場
至木下
新京成電鉄至我孫子
習志野自衛隊
駐屯地
国道296号(成田街道)
至船橋
花輪インター
武石インター
穴川インター
京葉道路
長沼船橋線
習志野自衛隊
演習場
中野木
実籾街道
京成津田沼駅
JR津田沼駅
軽自動車検査協会 千葉事務所習志野支所
京成実籾駅
千葉運輸支局 習志野自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所〒274−0063 千葉県船橋市習志野台8−56−1電 話 047−461−6600 050−3101−9142(検査予約)
千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所〒274−0063 千葉県船橋市習志野台8−57−1電 話 050−5540−2024(登録ヘルプデスク) 047−462−6571 (検査窓口)
至船橋
至四街道
至成田
至千葉
至千葉
国道14号(千葉街道)
国道16号
至成田
車検場前 下市場
至木下
新京成電鉄至我孫子
習志野自衛隊
駐屯地
国道296号(成田街道)
至船橋
花輪インター
武石インター
穴川インター
京葉道路
長沼船橋線
習志野自衛隊
演習場
中野木
実籾街道
京成津田沼駅
JR津田沼駅
軽自動車検査協会 千葉事務所習志野支所
京成実籾駅
千葉運輸支局 習志野自動車検査登録事務所
千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所〒299−0265千葉県袖ヶ浦市長浦580−77電 話 050−5540−2025(登録ヘルプデスク) 0438−63−5592 (検査窓口)
袖ヶ浦検査登録事務所
国道16号 至千葉
信号機表示板
至木更津
消防署
今井バス停
生コン
パチンコ国道287号
長浦駅
駅前
陸
橋
千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所
ネッツトヨタ
今井野球場
長浦駅入口
川

291
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
荒川沖駅
至三郷
至取手
JR常磐線
常磐高速自動車道
国道6号線
至谷田部 土浦野田線
至水戸
至土浦
至土浦
至阿見
西口
東口
桜土浦インター
至牛久・取手至土浦・石岡
至筑波学園都市
大角豆
土浦産業学院 茨城県立土浦産業技術専門学校
乙戸沼公園
学園東大通り
陸橋
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所
大角豆
至日光
至栃木
至市街至福島
至浅草
至東武
宇都宮
至羽生田
至市街
滝谷町交差点
宇都宮高校
至宇都宮
栃木県ガンセンター
アピタ宇都宮店
陽南通り
関東バス停
(陽南小学校前)
関東バス停
(八千代町)
陽南小
JR日光線
八千代1丁目
至東北自動車道鹿沼インター
栃木運輸支局
鶴田駅
栃木街道
交通会館
東武宇都宮線
日産プリンス栃木
江曽島駅
国道4号
至東京
至新4号
佐野駅JR両毛線
佐野・藤岡インター
下羽田交差点
県道7号
田島高架線
カインズホーム
ジャスコ
国道50号バイパス
県道67号線
佐野プレミアムアウトレット
栃木日産
交番佐野市駅
田島駅
西濃運輸
日通ターミナル
羽田工業団地入口
東武佐野線
至前橋
至前橋
至水戸
至小山
秋山川
栃木運輸支局佐野自動車検査登録事務所
(佐野古河線)
県道9号線佐
野行田線
東北自動車道
軽自動車検査協会
栃木事務所佐野支所
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所〒300−0847 茨城県土浦市卸町2−2−8電 話 029−843−3535 050−3101−9134(検査予約)
栃木運輸支局〒321−0169 栃木県宇都宮市八千代1−14−8電 話 050−5540−2019(登録ヘルプデスク) 028−658−7013(検査・整備・保安部門)
栃木運輸支局佐野自動車検査登録事務所〒327−0044 栃木県佐野市下羽田町2001−7電 話 050−5540−2020(登録ヘルプデスク) 0283−21−3721 (検査窓口)
N
茨城運輸支局
軽自動車検査協会茨城事務所
国道50号
水戸南IC茨城町東IC
案内看板案内看板
水戸市役所
北関東自動車道
JR常磐線至上野 至いわき
至日立
国道6号
至水戸インター
至土浦運転免許センター
ENEOSスタンド
水戸駅
酒門町
ケーズデンキ
若宮
中山公民館前
警察学校入口 車検場入口
吉沢町南
案内看板
軽自動車検査協会茨城事務所〒311−3123 茨城県東茨城郡茨城町若宮887−59電 話 029−293−9989 050−3101−9133(検査予約)
N
茨城運輸支局
軽自動車検査協会茨城事務所
国道50号
水戸南IC茨城町東IC
案内看板案内看板
水戸市役所
北関東自動車道
JR常磐線至上野 至いわき
至日立
国道6号
至水戸インター
至土浦運転免許センター
ENEOSスタンド
水戸駅
酒門町
ケーズデンキ
若宮
中山公民館前
警察学校入口 車検場入口
吉沢町南
案内看板
茨城運輸支局〒310−0844 茨城県水戸市住吉町353電 話 050−5540−2017(登録ヘルプデスク) 029−247−5249 (検査・整備・保安部門)
荒川沖駅
至三郷
至取手
JR常磐線
常磐高速自動車道
国道6号線
至谷田部 土浦野田線
至水戸
至土浦
至土浦
至阿見
西口
東口
桜土浦インター
至牛久・取手至土浦・石岡
至筑波学園都市
大角豆
大角豆
土浦産業学院 茨城県立土浦産業技術専門学校
乙戸沼公園
学園東大通り
陸橋
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所〒300−0847 茨城県土浦市卸町2−1−3電 話 050−5540−2018(登録ヘルプデスク) 029−842−8106 (検査部門)

292
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
石和共立病院 山梨県自動車税センター
平等川
JRA場外馬券場
甲府方面
カタクラ
園芸センター
ホテル石庭
国道20号線
(甲府バイパス)
国道20号線(勝沼バイパス)
至勝沼笛吹川至河口湖中央道東京方面
笛吹警察署
至甲府
至甲府市街
石和温泉駅
中央線
至東京
山梨中央銀行
笛吹市役所
県食肉 公社
整 備振興会
自動車
総合会館
軽自動車センター
山梨運輸支局
軽自動車検査協会山梨事務所
関東陸運振興センター
広瀬
軽自動車検査協会山梨事務所〒406−0034 山梨県笛吹市石和町唐柏792−1電 話 055−262−7269 050−3101−9148(検査予約)
山梨運輸支局〒406−0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000−9電 話 050−5540−2039(登録ヘルプデスク) 055−261−0882 (検査・整備・保安部門)
石和共立病院 山梨県自動車税センター
平等川
JRA場外馬券場
甲府方面
カタクラ
園芸センター
ホテル石庭
国道20号線
(甲府バイパス)
国道20号線(勝沼バイパス)
至勝沼笛吹川至河口湖中央道東京方面
笛吹警察署
至甲府
至甲府市街
石和温泉駅
中央線
至東京
山梨中央銀行
笛吹市役所
県食肉 公社
整 備振興会
自動車
総合会館
軽自動車センター
関東陸運振興センター
山梨運輸支局
軽自動車検査協会山梨事務所
広瀬
至日光
栃
木街
道
至栃木
旧
道
ゴルフ練習場
関東バス軽車検場入口
至浅草国道121号線(宇都宮環状線)
西川田駅 県総合運動公園
旧宇都宮 競馬場
東武宇都宮線
江曽島駅
至羽生田
至東武宇都宮駅
至国道4号線
宮内交差点西川田駅入口
至東京
至仙台
軽自動車検査協会栃木事務所
栃木運輸支局
N
軽自動車検査協会栃木事務所〒321−0158 栃木県宇都宮市西川田本町1−2−37電 話 028−645−5161 050−3101−9135(検査予約)
軽自動車検査協会栃木事務所佐野支所〒327−0044 栃木県佐野市下羽田町2001−2電 話 0283−20−6116 050−3101−9136(検査予約)
佐野駅JR両毛線
佐野・藤岡インター
下羽田交差点
県道7号
田島高架線
カインズホーム
ジャスコ
国道50号バイパス
県道67号線
佐野プレミアムアウトレット
栃木日産
交番佐野市駅
田島駅
西濃運輸
日通ターミナル
羽田工業団地入口
東武佐野線
至前橋
至前橋
至水戸
至小山
秋山川
(佐野古河線)
県道9号線佐
野行田線
東北自動車道
栃木運輸支局佐野自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会
栃木事務所佐野支所

293
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
6 自動車の種別(車両法第3条、車両法施規第2条別表第1)
種 別 構 造
大きさ及び原動機
長さ 幅 高さエンジンの総排気量(㏄)
自
動
車
自動車
普
通小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車
四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
4.70メートル以下
1.70メートル以下
2.00メートル以下
2000㏄以下◎
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
250㏄超
軽自動車
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
3.40メートル以下
1.48メートル以下
2.00メートル以下
660㏄以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
2.50メートル以下
1.30メートル以下
2.00メートル以下
250㏄以下
大型特殊自動車
一 次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車
一 前項第一号イに掲げる自動車であって、自動車の大きさが右欄に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの
4.70メートル以下
1.70メートル以下
2.80メートル以下
二 前項第一号ロに掲げる自動車であって、最高速度35キロメートル毎時未満のもの
原動機付自転車
第一種
第二種以外の原動機付自転車2.50メートル以下
1.30メートル以下
2.00メートル以下
50㏄以下
第二種
第一種以外の原動機付自転車2.50メートル以下
1.30メートル以下
2.00メートル以下
125㏄以下
(注)◎は(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)

294
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
7 自動車のナンバープレートの見方1.登録自動車
2.小型二輪自動車
運輸支局又はその自動車検査登録事務所を表示する文字
塗 色自家用貸渡(レンタカー)用駐留軍人軍属私有 車両用等
事業用 緑地、白文字
自動車の種別による分類番号
普通 貨物自動車 1、10〜19、100〜199 乗合自動車 2、20〜29、200〜299 乗用自動車 3、30〜39、300〜399小型 貨物自動車 4、6、40〜49、60〜69、400〜499、600〜699 乗用自動車及び乗合自動車 5、7、50〜59、70〜79、500〜599、700〜799特種用途自動車 8、80〜89、800〜899大型特殊自動車(建設機械を除く) 9、90〜99、900〜999大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの 0、00〜09、000〜099
自家用さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ貸渡(レンタカー)用われ事業用あいうえかきくけこを駐留軍人軍属私有車両用等EHKMTYよ
普通自動車で車両総重量8トン以上のもの最大積載量5トン以上のもの又は乗車定員30人以上のものは大型番号標
−連指定番号 …1から99−99 まで
登録規則第13条第1号
品川 500さ 23 -45
登録規則第13条第3号
白地、緑文字
車両法施規第11条第1項
登録規則第13条第2号
登録規則第13条第4号
運輸支局又はその自動車検査登録事務所を表示する文字
塗 色自家用貸渡(レンタカー)用 白地、緑文字駐留軍人軍属私有 車両用等内側に緑色のわくを付す。
自家用⑴あいうえかきくけこさすせそたち つてとなにぬねのはひふほまみむ めもやらるを⑵次に掲げる文字をその順序により 組み合わせたもの イ.CLV ロ.⑴に掲げる文字事業用 ゆりれ貸渡(レンタカー)用 ろわ駐留軍人軍属私有車両用等 ABEHKMTYよ
登録自動車の場合と同じ
−連指定番号 …1から99−99 まで
車両法施規第36条の18第1号
品川 あ
23 -45
車両法施規第45条第1項第7号
車両法施規第36条の18第2号
車両法施規第36条の18第3号

295
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
3.軽自動車(小板)
運輸支局又はその自動車検査登録事務所を表示する文字
塗 色自家用貸渡(レンタカー)用 白地、緑文字駐留軍人軍属私有 車両用等事業用 緑地、白文字
自家用 あいうえかきくけこさすせそたち つてとなにぬねのはひふほまみむ めもやゆよらるろを貸渡(レンタカー)用 わ事業用 りれ駐留軍人軍属私有車両用等 AB
−連指定番号 …1から99−99 まで
88 品川 あ
23 -45
車両法施規第36条の17第3号
車両法施規第36条の17第4号
車両法施規第36条の17第2号
自動車の用途等による区分1 二輪自動車33 三輪自動車及び被牽引自動車66 四輪の貨物自動車88 四輪の乗用自動車00 特殊用途自動車
車両法施規第36条の17第1号
軽自動車(中板)
運輸支局又はその自動車検査登録事務所を表示する文字
塗 色自家用貸渡(レンタカー)用 黄地、黒文字駐留軍人軍属私有 車両用等事業用 黒地、黄文字
自動車の用途等による区分貨物自動車 40〜49、400〜499、600〜699乗用自動車 50〜59、500〜599、700〜799特種用途自動車 80〜89、800〜899
−連指定番号 …1から99−99 まで
品川 50あ23 -45
車両法施規第36条の17第2号
車両法施規第36条の17第4号
車両法施規第45条第1項第5号

296
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
4.臨時運行許可番号標等
市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が許可した場合の当該行政庁の表示
塗 色 白地、黒文字 斜線は赤色
品川
大田23 -45
車両法施規第25条
市区町村臨時運行用
品川23 -45
運輸支局臨時運行用
品川23 -45
車両法施規第26条の6
品川
23 -45
車両法施規第63条の2第4項
運輸支局又はその自動車検査登録事務所を表示する文字
塗 色 自家用 白地、黒文字 斜線は赤色
塗 色 白地、黒文字 内側に赤色のわくを付す。
運輸局長の許可を受けた者の回送運行用
塗 色 白地、黒文字 内側に赤色のわくを付す。
軽二輪臨時運行用
5.臨時運転番号標
6.その他
外-1111
外交団用
青地、白文字○外は大公使館の長
領-1111
領事団用
白地、青文字
代-1111
代表部用
青地、白文字

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
あ と が き
自動車の手続きについては何でも分かるようにという当初の目途からして、でき上がったものをみま
すと、自動車業務の間口の広さをいやという程感ずるような気がしております。
編集委員の方々は或る程度の専門的知識を持ち合わせておりますが、自動車関係法規の複雑な制度に
わたるので、編集技術の不備な点もあると思われますが、何となくしろうとくさい面も見受けられるで
しょう。
本書にお寄せ下さったご意見の中には、文章の不足による表現の不備等の為、誤解を招いたものもあ
り、或いは全体的に内容を更にくわしくとか、一般的事例なども掲載してほしいというものもありまし
た。大変参考にさせて頂きましたので改めて感謝申し上げる次第です。
自動車便覧 (非売品)
平成24年7月 発行
発 行 所 一般財団法人 関東陸運振興センター 東京都新宿区四谷3丁目2番地1 (四谷三菱ビルディング) TEL 03−3357−1711(代)
印 刷 所 森永印刷株式会社 東京都文京区関口1−17−7
(禁無断転載・複製)

平成24年8月現在 禁無断転載・複製
平成24年8月現在 禁無断転載・複製
〒160−0004 本 部 東京都新宿区四谷3−2−1 四谷三菱ビルディング7F 03−3357−1711〒140−0011 品 川 支 部 東京都品川区東大井1−12−14 03−3474−2649〒108−0075 品 川 支 部 東京都港区港南3−3−10 03−3472−5334 軽自動車出張所〒121−0062 足 立 支 部 東京都足立区南花畑5−12−1 03−3850−3881〒121−0836 足 立 支 部 東京都足立区入谷8−10−8 03−3853−1084 軽自動車出張所〒179−0081 練 馬 支 部 東京都練馬区北町2−8−6 03−3934−3070〒175−0081 練 馬 支 部 東京都板橋区新河岸1−12−26 03−5922−6178 軽自動車出張所〒186−0001 多 摩 支 部 東京都国立市北3−30−3 042−527−5454〒183−0003 多 摩 支 部 東京都府中市朝日町3−16−22 042−358−6381 軽自動車出張所〒192−0011 八 王 子 支 部 東京都八王子市滝山町1−270−4 042−691−5891〒190−1232 八 王 子 支 部 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3−6−1 042−557−2881 軽自動車出張所〒331−0077 埼 玉 支 部 埼玉県さいたま市西区中釘2084−2 048−624−9255〒362−0055 埼 玉 支 部 埼玉県上尾市平方領々家511−3 048−726−0916 軽自動車出張所〒360−0844 熊 谷 支 部 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原701−3 048−532−8125〒366−0812 熊 谷 支 部 埼玉県深谷市折之口1990−6 048−574−1860 軽自動車出張所〒359−0026 所 沢 支 部 埼玉県所沢市牛沼700−3 04−2998−2011〒354−0044 所 沢 支 部 埼玉県入間郡三芳町北永井360−14 049−274−3051 軽自動車出張所〒344−0042 春 日 部 支 部 埼玉県春日部市増戸738−3 048−752−6221〒344−0036 春 日 部 支 部 埼玉県春日部市下大増新田131−1 048−731−1178 軽自動車出張所〒261−0002 千 葉 支 部 千葉県千葉市美浜区新港200 043−242−4627〒261−0002 千 葉 支 部 千葉県千葉市美浜区新港223−17 043−242−5684 軽自動車出張所〒274−0063 習 志 野 支 部 千葉県船橋市習志野台8−57−1 047−466−0726〒274−0063 習 志 野 支 部 千葉県船橋市習志野台8−56−1 047−402−5666 軽自動車出張所〒299−0265 袖 ヶ 浦 支 部 千葉県袖ヶ浦市長浦580−221 0438−63−5516〒299−0265 袖 ヶ 浦 支 部 千葉県袖ヶ浦市長浦580−259 0438−63−4962 軽自動車出張所〒278−0013 野 田 支 部 千葉県野田市上三ヶ尾207−25 04−7121−2511〒310−0844 茨 城 支 部 茨城県水戸市住吉町292−10 029−247−5854〒311−3123 茨 城 支 部 茨城県東茨城郡茨城町若宮887−67 029−293−9669 軽自動車出張所〒300−0847 土 浦 支 部 茨城県土浦市卸町2−1−5 029−842−7901〒300−0847 土 浦 支 部 茨城県土浦市卸町2−2−8 029−843−3366 軽自動車出張所〒371−0007 群 馬 支 部 群馬県前橋市上泉町397−6 027−261−0341〒379−2166 群 馬 支 部 群馬県前橋市野中町322−1 027−261−5633 軽自動車出張所〒406−0034 山 梨 支 部 山梨県笛吹市石和町唐柏1000−6 055−262−4777〒406−0034 山 梨 支 部 山梨県笛吹市石和町唐柏791−1 055−262−7549 軽自動車出張所
標板、用紙、印紙、保険自動車番号標交付自動車関係申請用紙自動車賠償責任保険自動車検査登録印紙自動車重量税印紙自動車税取得税証紙自動車関係無料案内
一般財団法人 関東陸運振興センターhttp://www.rikuriku.or.jp