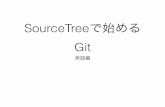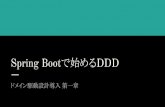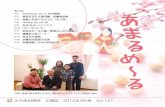案件概要表 - JICA ·...
Transcript of 案件概要表 - JICA ·...

国内機関主管案件
草の根技協(パートナー型)
2017年03月21日現在
本部/国内機関 :東京国際センター
案件概要表
案件名 (和)スリランカ北部地域における就学前教育支援事業
(英)Sustainable Early Childhood Care and Development (ECCD) management project
in Northern Sri Lanka
対象国名 スリランカ
分野課題1 教育-初等教育
分野課題2 平和構築-その他平和構築
分野課題3 市民参加-市民参加
分野分類 その他-その他-その他
プログラム名 プログラム構成外援助重点課題 -開発課題 -
プロジェクトサイト スリランカ北部州ムラティブ県
署名日(実施合意) 2013年11月01日
協力期間 2013年11月01日 ~ 2016年09月30日
相手国機関名 (和)ムラティブ教育局
相手国機関名 (英)Mullativu Zonal Education Office
日本側協力機関名 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン
プロジェクト概要
背景 スリランカでは 、2009年5月まで25年以上にわたり,北・東部の分離独立を目指して活動していた反政府武装勢力と,政府の間で紛争が続いていた。特にムライティブ県は2008年の夏から戦闘終結される2009年5月までの激戦地となり、教育施設を含む社会的インフラが壊滅的な被害を受けた。北部地域での小・中学校の建設・修復、教員研修など教育支援事業は各ドナー、国際機関、NGOが実施しているが就学前のケアへの支援に関しては、国際機関や北部州政府もその必要性を国際社会に対し呼びかけているが、就学前教育のニーズに対し支援が行き届いていないのが現状である。多くの就学前教育(以下ECCD)センターが戦乱の中で崩壊・荒廃したため、仮設テントや近くの建物を借りて授業を行ったり、屋根がなく壁が壊れた施設の中でそのまま授業を行ったりしている状況にある。そのため、当該地域の子どもたちを取り巻く環境は安全や安心とは程遠い。ECCDセンターの教員の質についても政府が定める基準に達してないことも多く、子どもたちは適切な環境下でケアを受けることができていない。本事業では、①子どもにやさしい教育環境を整え、②親・コミュニティ・行政が就学前教育に対する正しい認識を持ち、③適切な補助食が提供されることを通じて、就学前教育の質を高めることで、子どもの健全な発達を促進し、ひいては北部復興の人材育成の礎を作ることを、当事業の実施を通じて目指していく。
上位目標 本事業の経験・成果が活用され、紛争影響地域の就学前の子どもたちが健全に発達する。
プロジェクト目標 子どもにやさしい就学前教育(ECCD)の環境を整えることにより、対象地域の子どもたちの健全な発達を促す。
成果 成果1)ECCDの教育・教員の質が向上する。成果2)ECCD教員および保護者の就学前の子どもたちに関する栄養の知識が向上し、子どもたちの健康が増進される

成果3)対象地域において、行政との連携の元、コミュニティのECCDセンターに対する理解が深まる。
活動 0-1.ベースライン調査及びエンドライン調査が実施される。
1.ECCD教育・教員の質の向上と子どもにやさしい学習環境の整備1-1.ECCD教員への「子どもにやさしい教授法」研修1-2.行政と連携したECCD教員資格コースの実施
2.子どもたちへの補助食提供と教員および保護者への栄養・衛生研修2-1.ECCDセンターに通う子どもの保護者への栄養・衛生講習会2-2.ECCD教員への栄養・衛生研修2-3.ECCDコミュニティガーデンでの野菜/果物/穀物の栽培と収穫物を活用した補助食提供
3.ECCDセンターの運営強化3-1.コミュニティを対象にした就学前教育研修3-2.ECCD運営委員会マネージメント研修3-3.ムライティブ教育局へのモニタリング研修
投入
日本側投入 【人材】•海外事業部マネージャー(日本人)1名•プロジェクトマネージャー(日本人)1名•現地調整員(日本人)1名
【資機材】•講習会実施関係 資機材•コミュニティガーデン用資材•カウンターパート運営強化関係資機材
相手国側投入 ・カウンターパート(ムラティブ教育局)の担当者
外部条件 ・国内における政情・治安が悪化する・事業対象地域の安全状況に問題が発生する
実施体制
(1)現地実施体制 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンとセーブ・ザ・チルドレン・スリランカが協働し、現地のカウンターパート機関(ムライティブ教育局)とともに実施する。
(2)国内支援体制 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの国内調整員が現地とJICAとの調整窓口業務及び会計報告を行う。
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
特になし
(2)他ドナー等の
援助活動
特になし

国内機関主管案件
草の根技協(地域提案型)
2017年11月07日現在
本部/国内機関 :駒ヶ根青年海外協力隊訓練所
案件概要表
案件名 (和)スリランカにおける高齢者ケアー政策プラン・モデル形成プロジェクト
(英)A Health Plan and Model Forming Project of Integrated Health and Welfare
Service for the Elderly in Sri Lanka
対象国名 スリランカ
分野課題1 保健医療-保健医療システム
分野課題2 保健医療-その他保健医療
分野課題3 その他-その他
分野分類 保健・医療-保健・医療-基礎保健
プログラム名 プログラム構成外援助重点課題 -開発課題 -
プロジェクトサイト コロンボ・中央州キャンディ県・ウヴァ州バドゥッラ県
署名日(実施合意) 2015年03月31日
協力期間 2015年02月23日 ~ 2017年03月31日
相手国機関名 (和)スリランカ保健省
相手国機関名 (英)Ministry of Health Srilanka
日本側協力機関名 一般財団法人 農村保健研修センター
プロジェクト概要
背景 スリランカはプライマリーヘルスケアー(PHC)が充実しており、1人あたりGDPの低い途上国としては基本的保健指標がよいことで知られている。その結果平均寿命も延伸し、近年非感染症疾患(NCDs)の増加と対策が課題の一つになっている。政府もその対策に力を入れるようになっている。そのような背景があって、2013年に農村保健研修センターでNCDsと高齢者ケアーの管理運営に関する青年研修事業を実施し、佐久穂町でもこの研修を受け入れた。スリランカ保健省においても、高齢者ケアーの政策プランづくりを進める考えであり、2013年に実施したスリランカ青年研修の研修員は帰国後にアクションプランを作成して保健大臣および高齢者対策委員会(Elderly Steering Committee)に新しい高齢者対策政策づくりを提案した。保健大臣および高齢者対策委員会ではその提案を受け入れた。本事業では、研修員の提案を具体化し、実行に移すために、青年研修の研修員(Sri Lanka YLTP2013)等と協力して、NCDs対策および保健予防活動と連携した高齢者包括的ケアーの政策プランとその具体化のためのモデルづくりを草の根技術協力事業として行う。
上位目標 スリランカにおける高齢者政策プランが全国レベルで認知される。
プロジェクト目標 スリランカにおけるNCD対策と連携した高齢者ケアー政策プランと高齢者ケアーモデルプランを確立する(地区基幹病院モデルおよびコミュニティモデルプラン)
成果 1)国の高齢者対策に関する政策ポリシーと戦略プランが作成される。 2)高齢者対策に必要なプランやガイドラインが整理され、未整備なプランやガイドラインが、必要に応じて作成される。 3)国の高齢者サービスモデル施設プラン(Handalaのケアー施設)が作成される。 4)高齢者サービスモデル病院プラン(Nawalapitiya地域基幹病院)が作成される。 5)高齢者サービスモデルコミュニティプラン(Badulla district)が作成される。

活動 1)高齢者政策を進めるために政策プランナー、高齢者対策関係者などを対象に3回のセミナーを実施する。 2)高齢者サービスのモデルづくりを進めるために6回の現職研修コースを実施する。 3)高齢者政策プランおよびモデルづくりを進めるために3回の日本視察研修を実施する。 4)スリランカにおける政策とモデルづくりのためのベースライン調査を実施する。 5)プロジェクトの進捗状況をモニターして評価を行う。 6)高齢者政策プランづくりに必要な既存の保健政策プランなどの情報を収集整理する。 7)国の高齢者ケアー施設モデルづくりを、スタッフの現職研修等によって支援する 8)高齢者ケアーモデル病院づくりをスタッフの現職研修支援等によって支援する。 9)高齢者ケアーコミュニティモデルづくりをスタッフの現職研修等によって支援する。
投入
日本側投入 1)専門家派遣:保健政策x2、高齢者ケアーx2、保健行政x3、現職研修x2、 2)機材供与(研修用機材、事務機材等)
相手国側投入 1)保健省計画課にプロジェクト事務所スペースを提供する。 2)電気水道通信など、プロジェクトの日常業務に必要な環境を提供する。 3)政策プラン作成(WG)、調査、研修に必要な人材・労力を提供する。 4)プロジェクト活動に必要な情報、資料等を提供する。
外部条件 スリランカ政府および保健省の体制と政策目標が、政治的な変化によって変更されない。
実施体制
(1)現地実施体制 スリランカ保健省(計画課、高齢者協議会、中央州研修センター)ナワラピティヤ地区病院、ウヴァ州バドゥッラ県保健局他
(2)国内支援体制 佐久穂町、千曲病院、農村保健研修センター、佐久総合病院、

本部主管案件
個別案件(国別研修(本邦))
2016年11月15日現在
本部/国内機関 :南アジア部
案件概要表
案件名 (和)保健医療行政・病院管理研修
(英)Training of Senior Registrars in Medical Administration in Japan
対象国名 スリランカ
分野課題1 保健医療-保健医療システム
分野課題2
分野課題3
分野分類 保健・医療-保健・医療-保健・医療
プログラム名 保健医療プログラム援助重点課題 脆弱性の軽減開発課題 脆弱性軽減のための社会基盤整備
協力期間 2012年04月01日 ~ 2015年03月31日
相手国機関名 (和)スリランカ国保健省
相手国機関名 (英)Ministry of Health
プロジェクト概要
背景 スリランカでは少子高齢化及び疾病構造の変化に伴い、国家財政における保健医療分野の公的支出が増加する一方で、限られた財源をどのように有効活用しながら公的保健医療サービスを維持していくかが課題となっており、医療サービス提供者である各病院は限られた予算配分の中で、最大の効果を出せるよう効率化を図ることが求められている。 各病院での医療サービスの向上を図るため、JICAは技術協力プロジェクト「5S/TQMによる保健医療サービス向上プロジェクト」(2009-2011)の実施により、5S/TQMを通じた病院管理体制の効率化への取り組みを実施した。併せて、開発調査「保健医療システム管理強化計画」(2005-2007)で提言された公立病院の会計システム強化を計り、各病院レベルでの保健支出の最適化と経営改善への取り組みが求められている。更には、無償資金協力「アヌラダプラ教育病院整備計画」や「ジャフナ教育病院中央機能改善計画」により3次病院を整備したほか、有償資金協力「地方基礎社会サービス改善計画」による2次医療施設の整備も予定されている。将来的に国家財政における保健支出の適正化と保健医療システムの効率化に貢献していくためには、地域中核病院の効率的・効果的な病院運営の実施が必要となっている。 本案件では、病院運営の改善を図るために、日本の病院経営や財務管理、予算管理、在庫管理を含めた効率的かつ効果的な病院運営の手法を学ぶことを目的として、九州国際センターで実施する集団研修「病院経営・財務管理(A)」(J14-04065)へ、3次病院もしくは2次病院の財務管理担当者及び保健省・州保健局の予算・財務担当官を研修員として派遣することとする。
上位目標 スリランカの地域中核病院(3次病院、2次病院)及び保健省・州保健局において、効率的・効果的な病院運営計画が実施される。
プロジェクト目標 スリランカの地域中核病院(3次病院、2次病院)及び保健省・州保健局において、効率的・効果的な病院運営へ向けての改善計画が策定される。
成果 ア.病院運営・経営の概念及び実践的な知見が習得される。イ.日本で実施される経理業務、各部門の管理体制、資材管理、財務管理、医療情報システム等の仕組み・知見・ノウハウを習得する。ウ.研修を通じて習得した仕組み・知見・ノウハウを活用し、効率的かつ効果的な病院運営のための改善計画案を作成する。エ.帰国後に、研修員所属組織に研修成果が共有されるとともに、病院運営の改善計画案が検討される。

活動 【研修前活動】 病院経営・財務管理にかかるスリランカの現状及び所属組織について課題を分析し、レポートに取りまとめる。【本邦研修】ア. 日本の病院における経理業務及び財務管理、予算管理、医療情報システムを理解する。イ.日本の病院視察及び座学を通して、病院スタッフへの教育体制、人事・労務管理、病院組織論を理解する。ウ.病院のマーケティング、部門別原価計算、病院機能評価、PCM手法、病院の業務改善(5S-TQM)、PFFC(Patient and Family Focused Care)を理解する。エ.所属組織における病院運営改善のためのアクションプランを作成する。【研修後活動】作成したアクションプランの進捗についての、事後モニタリングレポートを作成し、JICAに提出する。
投入
日本側投入 集団研修「病院経営・財務管理(A)」(J14-04065)への上乗せ研修3名。
相手国側投入 N/A
外部条件 N/A
実施体制
(1)現地実施体制 保健省、州保健局、地域中核病院(3次病院及び2次病院)
(2)国内支援体制 厚生労働省、聖マリア病院
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
JICAは、保健医療行政強化を図るため、開発調査「保健医療制度改善計画」(2002年~2003年)及び「保健システム管理強化計画」(2005年~2007年)を実施し、NCD対策強化や病院の業務改善、経営改善への提言を盛り込んだ保健セクター改革のための政策提言を行った。同調査の成果を受け保健省は、10ヵ年計画「保健医療マスタープラン2007-16」を取りまとめ、①疾病負担の削減と健康増進のための統合的保健医療サービス提供、②健康維持のためのコミュニティのエンパワメント、③保健医療システムの効率化等を重点戦略として設定している。保健省の取り組みに対し、JICA はNCD 対策として、技術協力「健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト」及び有償資金協力「地方基礎社会サービス改善事業」を実施し、また保健医療サービスの向上のために5S/TQM 手法を用いた病院管理向上を支援しており、継続的にセクター改革推進に貢献している。
(2)他ドナー等の
援助活動
保健セクターへの協力は、主に世界銀行やWHO、UNICEFが実施している。①世界銀行「保健セクター開発プロジェクト」(2004-2010、72.6百万米ドル)「同追加プロジェクト」(2009-2011、26.7百万ドル)で州保健局の強化及び1次医療施設を中心とした施設整備、保健サービス向上及び保健省の機能強化を図ってきた。併せて2012年対スリランカ中期計画作成後、①NCD管理・予防、②栄養改善の2課題を柱とする後継案件が検討されている。②WHO「WHO国別協力計画」に基づき、保健医療システム強化、感染症・非感染症対策、緊急事態への準備・対応、母子保健・リプロダクティブヘルス等の分野での人材育成及び政策策定支援を実施している。③UNICEFア)母子栄養改善、イ)紛争影響地域の基礎保健サービス改善、ウ)小児科関連の施設・機材の拡充をコンポーネントとする女性と子どもの保健と栄養改善のためのプログラムを実施している。

本部主管案件
有償技術支援-附帯プロ
2019年02月23日現在
本部/国内機関 :人間開発部
案件概要表
案件名 (和)非感染性疾患対策強化プロジェクト(有償勘定技術支援)
(英)Project for Enhancement of Non-communicable Diseases Management
対象国名 スリランカ
分野課題1 保健医療-非感染症
分野課題2
分野課題3
分野分類 保健・医療-保健・医療-保健・医療
プログラム名 保健医療プログラム援助重点課題 脆弱性の軽減開発課題 脆弱性軽減のための社会基盤整備
プロジェクトサイト コロンボ(保健省)及び4 州4 県(北西部州クルネガラ県、中央州キャンディ県、サバラガ
ムワ州ケゴール県、東部州バティカロア県)に存在する対象2次医療施設(基幹病院)の
診療圏
署名日(実施合意) 2013年10月22日
協力期間 2014年02月01日 ~ 2018年01月31日
相手国機関名 (和)保健省、州保健局
相手国機関名 (英)Ministry of Health, Provincial Health Departments of Project sites
日本側協力機関名 未定
プロジェクト概要
背景 (1)当該国における保健セクター/非感染性疾患対策の現状と課題スリランカ民主社会主義共和国(以下、「スリランカ」と記す)は、高齢化や生活習慣の変化に伴い、1980 年代から心血管病などの非感染性疾患(Non-Communicable Disease:NCD)が死亡原因として感染症を上回り、2007 年保健医療統計(Annual Health Statistics)では病院における5大死因1 のすべてがNCD に起因している。心血管疾患や糖尿病の年齢調整死亡率は、経済協力開発機構(OECD)諸国の2 ~ 4 倍高く、特に労働人口である若年層男性の死亡率が高いとされ、経済発展の観点からもNCD 対策は重要な課題になっている。このような背景の下、スリランカ政府は、JICA 技術協力プロジェクト「健康増進予防医療サービス向上プロジェクト」(2008 ~ 2013 年)での経験を基に、血圧、血糖値などの測定による心疾患、糖尿病などの高リスクグループを特定する健診活動及びNCD に関する健康教育を行う「健康生活スタイルセンター(Healthy Lifestyle Centre:HLC)」を全国の医療機関に設置する事業により予防対策・健診の展開を進めている。一方で、健診によりNCD の高リスク者の発見が多くなることが見込まれているものの、NCD の診断や治療を行うことが適している2次医療施設に十分な設備と人材が整備されていないために、わざわざ遠くの検査機材や専門医が存在する3次医療施設へ疑い患者を移送せざるを得ない現状があり、NCD 管理を進めるためには、診断検査機材と専門医が整った2次医療施設の強化が重要となっている。また、健診を行うHLC や健診以外で疑い患者が見つかる1次医療施設と、診断・治療を行う2次医療施設との患者紹介や逆紹介2 のための連携の強化が課題となっている。また、スリランカの保健サービスは公的医療施設にて医薬品を含む医療が無償提供されていることからアクセスが良好である一方で、実際の基礎検査・医薬品は医療施設における在庫がないことにより医療施設近隣の薬局において自費で購入せざるを得ないことが散見され、特にNCD においてその傾向が顕著であり、公立病院におけるNCD に対する継続的な服薬治療の管理という点で脆弱性が指摘されている。このため、必要な医薬品が必要な病院に適正量保管されることがNCD 管理に求められている。これらのことから、今後HLC の本格的な健診活動の進展に従って増加すること

が見込まれるNCD 高リスク者に対して、引き続き診断・治療が円滑に行われることにより、健診・診断・治療及びフォローアップとつながる1次・2次医療施設におけるNCD 管理の質を向上させることが喫緊の課題になっている。(2)当該国における保健政策と本事業の位置づけ国家開発計画「マヒンダ構想(マヒンダ・チンタナ)(2010 ~ 2016 年)3」は、ミレニアム開発目標の指標にみられるような教育や保健医療分野におけるスリランカのこれまでの取り組みと達成度合いを踏まえ、「今後とも途上国の保健医療分野において主導的な役割を継続する。」としており、財政の観点からは、2013 年度予算4 において、教育・保健経費予算額を2011 年の371 億ルピー(開発予算の9.1%)から2013 年は596 億ルピー(同11.3%)への増加を見込むなど、社会開発分野への投資を強化している。このうち、今後の取り組みとして、高齢化や疾病構造の変化に伴い増加傾向にあるNCD 及び女性や子どもといった脆弱集団のニーズへの対応を保健・医療分野の重点課題と位置づけている。NCD対策強化として、集団アプローチ5 による危険因子への介入や、費用対効果の高い高リスクグループへのスクリーニングの実施、医薬品の適切な処方、保健医療施設における生活習慣改善をめざした個別カウンセリングなどを具体例として挙げ、バランスのとれた1次・2次・3次予防6 の必要性が強調されている。本事業は、NCD 対策のなかでも、1次・2次予防の強化改善を進めるものとして位置づけられる。(3)保健セクターに対するわが国及びJICA の援助方針と実績スリランカに対する援助方針を示した国別援助方針(2012 年6 月)は、援助重点分野として、経済成長の促進、後発開発地域の開発支援、脆弱性の軽減の3 点を挙げている。このうち、社会サービス基盤の体制整備の遅れをスリランカの脆弱性とし、保健・医療分野を中心に改善支援を行うとしている。JICA は、開発調査「保健医療制度改善計画」(2002 ~ 2003 年)及び「保健システム管理計画」(2005 ~ 2007 年)を実施し、NCD 対策強化を盛り込んだ保健システム改革のための政策提言を行った。これを踏まえ、スリランカは保健政策である「保健マスタープラン」を策定するに至った。さらに、JICA は技術協力プロジェクト「健康増進予防医療サービス向上プロジェクト」(2008 ~ 2013 年)において住民に対する健診活動や保健指導及び健康増進活動を中心としたNCD 予防モデルを構築し7、円借款事業「地方基礎社会サービス事業」(2012 年3 月28 日貸付契約調印)では、対象州でのNCD 早期発見及び早期治療の強化を通じたNCD 対策強化をめざしている。このような背景からJICA は、スリランカの開発課題を把握・分析した国別分析ペーパーにおいて、脆弱性の軽減のための社会基盤整備の一環として保健医療分野で、「NCD 予防と管理の強化」及び「効率的な病院管理体制の構築」を通じて、「疾病構造の変化に対応した、持続可能な保健医療システムの確立」を協力プログラムとしている。NCD 予防と管理の強化においては、深刻化するNCD 対策を強化すべく、予防、早期発見及び早期治療に対応できる体制を整備する方向性である。(4)他の援助機関の対応世界銀行が保健セクター開発計画(Health Sector Development Project:HSDP)として保健医療セクター全体への支援を行っている。世界保健機関(WHO)はスリランカ国別協力計画においてNCD 対策を優先戦略のひとつと定め、NCD 対策全般に対し、技術的助言を行っている。
上位目標 HLC 並びに1次及び2次医療施設を含む包括的なNCD10 管理が全国で実施される。
プロジェクト目標 対象4 州4 県の対象地域において、全国に応用可能なHLC 並びに1次及び2次医療施設を含むNCD 管理モデルが開発・実施される。
成果 成果1: HLC と対象基幹病院においてトータルリスクアセスメント11 によるNCD 管理が強化される。成果2:対象基幹病院において必須医薬品と医療資材の在庫管理が強化される。成果3:NCD サーベイランスシステムが構築される。成果4:NCD 管理モデル活動を全国展開するための計画がまとめられる。
活動 1.1 1 次医療施設の患者やHCL のスクリーニングで発見された高リスク者のフォローアップシステムが開発される。1.1.1 HLC のスクリーニング後に更なる検査や治療が必要とされた高リスク者及び患者の健康指導に対するコンプライアンスに関する状況分析を行う。1.1.2 HLC のスクリーニングで発見された高リスク者や患者のフォローアップ制度を構築することを目的としたオペレーショナルリサーチの計画を作成する。1.1.3 オペレーショナルリサーチの実施と評価を行う。1.1.4 1.1.3 の結果を基にHLC スクリーニングで発見された高リスク者及び患者のフォローアップのためのガイドラインを作成する。1.1.5 対象地域においてフォローアップ制度を実践する。1.2 対象地域において限定された資源の効率化のための基幹病院、HLC その他の保健医療施設間でネットワークを構築する(例えば検査、情報交換など)。1.2.1 対象地域でネットワークのためのパイロットモデルを作成する。1.2.2 対象地域にてパイロットモデルを実施する。1.2.3 パイロットモデル実施結果を検証する。1.2.4 対象州の他地域へ拡大する計画を策定する。1.2.5 対象州の対象地域におけるネットワークを構築する。1.3 対象県のMO/NCD のモニタリング能力を強化する。1.3.1 MO/NCD によるHLC 等でのNCD 対策モニタリング制度の現状を検証する。1.3.2 1.3.1 の結果を踏まえ、MO/NCD のモニタリング制度をモニタリング試行モデルとして改定する。1.3.3 試行モデルを対象県で実施する。1.3.4 対象県においてMO/NCD のモニタリング活動を評価するための定期会合をもつ。1.3.5 MO/NCD 向けの指針及び研修モジュールを改定する。

1.3.6 対象4 県においてモニタリング制度に関するMO/NCD 研修を実施する。2.1 対象基幹病院における必須医薬品及び医療資材管理の状況分析を実施する。2.2 対象基幹病院における必須医薬品及び医療資材の電子管理システムを開発する。2.2.1 必須医薬品及び医療用品管理の電子管理システム案を作成する。2.2.2 対象基幹病院において2.2.1 案を試行する。2.2.3 2.2.2 の結果に基づき、システムを最終化する。2.2.4 対象基幹病院の全関係職員に対し、電子管理システムに関する研修を実施する。2.2.5 対象基幹病院において最終化した電子管理システムを実施する。3.1 NCD 危険因子サーベイランスシステム試行モデルを策定する。3.2 試行モデルを改善するために対象地域において実施する。3.3 3.2 のサーベイランス結果を基にNCD 予防戦略など必要な対策の改善に資するためのフィードバックの仕組みを開発する。3.4 3.2 及び3.3 の結果を踏まえ、システムの最終化を実施する。4.1 対象地域におけるNCD 管理のためのプロジェクト活動の達成状況を検証する。4.2 医薬品管理システムを含むHLC と基幹病院間におけるNCD 管理モデルが全州で活用されるよう最終化する。4.3 上記システムの指針や研修モジュールを最終化する。4.4 NCD 管理モデルを州全体で強化するための機材や研修等の適切なレベルや必要な資源算定を行う。4.5 NCD 管理モデルを全国展開するための段階、関係者とその役割を特定する。
投入
日本側投入 ・ 専門家(チーフアドバイザー、NCD 管理、疫学、医薬品ロジスティクス、保健情報システム)・ 現地活動費(ワークショップ、研修、会議費、現地専門家)・ 資機材(情報処理機材等)・ 本邦研修(保健省・保健局NCD 対策官:NCD 管理、対象病院管理者:病院管理)
相手国側投入 ・ カウンターパート配置プロジェクトディレクター:保健省次官プロジェクトマネジャー:保健省計画課長その他(保健省・医療局長補、公衆衛生サービス局長補、教育・訓練・研究局長補、非感染性疾患対策課長ほか)・ プロジェクト執務室及び設備・ 執務室運営経費・ 関税・付加価値税、税関措置費用、供与機材に要する保管・輸送費用
外部条件 ・ スリランカ保健政策上、NCD 対策の優先度が維持される。・ 保健省及び州・県保健局が、プロジェクト対象外地域での実施に必要な機材、人材を提供する。
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
・ 技術協力プロジェクト「健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト(2008 ~ 2013 年)」により、住民に対する健診活動、保健指導及び健康増進活動を中心としたNCD 予防モデルの構築・展開が行われた。同プロジェクトで整備されてきたNCD 予防モデルによる健診と、基幹病院における治療への連係及び治療後フォローアップの強化を本事業で取り組むこととなる。・ 円借款事業「地方基礎社会サービス改善事業」(2012 年)において「疾病構造の変化に対応すべく、対象州でのNCD の早期発見及び早期治療(2次予防)の強化を通じて、非感染性疾患対策能力を強化する」ことを目的に、①国立必須医薬品製造センター改善、②2次医療施設(基幹病院)改善、③リファラル体制強化が行われている。本事業では、本円借款により改善される基幹病院を対象として実施されるものである。
(2)他ドナー等の
援助活動
・ 世銀は「第1次保健セクター開発計画(2004 ~ 2010 年)」において、保健省及び各州保健局に対し、約9,600 万ドル予算規模で医療サービスの質の向上や公正なアクセス向上をめざした保健医療セクター全体の改善を支援した。2013 年3 月には約2 億ドルの「第2次保健セクター開発計画(2013 ~ 2018 年)」の実施を承認。HLC でのNCD 健診推進などを図る予定であり、本事業による治療体制構がNCD 対策制度を総体的に強化する相乗効果が見込まれる。・ WHO は、スリランカ保健省に対し技術的助言を行うなど重要な役割を果たしており、現行の国別協力戦略(2012 ~ 2017 年)においてNCD 対策を優先戦略のひとつと定め、最推奨策(Best Buy)の推進、マルチセクターによるNCD 予防・管理アプローチの推進を進めている。また、5 年ごとに危険因子サーベイランス(STEPwise approach to chronicdisease risk factor surveillance)の実施を支援しており、2013 年に2 回目が実施される予定である。本事業における指針づくり、及び、より頻度の高いサーベイランス体制構築に際し、技術的な観点から協力を進める必要がある。

本部主管案件
個別案件(国別研修(本邦))
2017年11月11日現在
本部/国内機関 :南アジア部
案件概要表
案件名 (和)非感染症対策研修
(英)Training on Non-communicable Disease Prevention
対象国名 スリランカ
分野課題1 保健医療-非感染症
分野課題2
分野課題3
分野分類 保健・医療-保健・医療-基礎保健
プログラム名 保健医療プログラム援助重点課題 脆弱性の軽減開発課題 脆弱性軽減のための社会基盤整備
協力期間 2012年04月01日 ~ 2015年03月31日
相手国機関名 (和)スリランカ国保健省
相手国機関名 (英)Ministry of Health
プロジェクト概要
背景 スリランカでは所得水準向上に伴い、感染症罹患や母子保健等の基礎的な保健指標が改善しつつあるが、高齢化及び食生活の変化に伴い疾病構造が転換し、特に慢性疾患等の非感染症の患者数が増加する一方で、公的医療機関の治療体制の整備がなかなか進まない状況であり、貧困層での罹患の深刻化も問題となっている。上記課題に対応していくため、JICAは対スリランカ国支援において、開発課題「脆弱性軽減のための社会基盤整備」の中で「保健医療プログラム」を設定し、疾病構造の変化に対応した保健医療システムの改善を目指していくこととしている。 本プログラムの中では、予防を中心とした非感染症対策能力の強化をめざす技術協力プロジェクト「健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト(NPP技プロ)」(2008-2013)では1次医療施設を中心としたNCD予防モデルの構築・展開が行われた。併せて、有償資金協力「地方基礎社会サービス改善事業(SL-P105)」(39.35億円、2012年~2017年)では、「対象州での非感染症 (NCD)の早期発見及び早期治療の強化を通じて、非感染症対策能力を強化する」ことを事業の目的に、①「国立必須医薬品製造センター」(SPMC)改善、②2次医療施設改善、③リファラル体制強化(救急車整備)を実施することが合意された。併せて、附帯プロジェクトや研修を通じたきめ細やかな能力強化を予定している。 SPMCの強化を図るためには、製造能力の拡大に加えて、製造する医薬品の品質管理や監視指導体制の強化などが重要であり、日本の医薬品製造品質管理行政・体制を学ぶことを目的に、SPMC及び保健省医薬品管理局の担当者を対象として国別研修を実施することとする。なお、実施に当たっては、東京国際センターが実施する課題別研修「薬事行政」(J14-04123)への上乗せによる受け入れを行う。
上位目標 スリランカにおける必須医薬品製造品質管理体制が向上し、非感染症対策能力が強化される。
プロジェクト目標 研修成果を活用した形で、SPMCにおける医薬品の製造品質管理の改善計画が作成される。
成果 ア.日本の医薬品製造品質管理行政が理解される。イ.GMP(Good Manufacturing Practice、製造品質管理基準)の実施体制・監視体制が理解される。ウ.必須医薬品製造品質管理体制の強化に向けての課題が整理される。

活動 【研修前活動】カントリーレポートを作成する。【本邦研修】ア.日本の薬事行政、日本の薬事監視、医薬品規制の国際調和と新しいGMP管理、日本薬局方について理解する。イ.医薬品製造概論を理解するとともに、薬事行政側が実施するGMP調査、日本薬局方について理解する。ウ.医薬品製造所及び試験検査機器メーカー、医薬品製造、製造機器メーカーを視察する。エ.医薬品品質確保、医薬品GMPの監視指導体制、不正医薬品対策を学ぶために、国立医薬品食品衛生研究所を視察する。オ.必須医薬品製造品質管理体制の改善計画をとりまとめる【事後活動】帰国後に、取りまとめた改善計画への取り組み進捗状況を取りまとめたプログレスレポートを作成する。
投入
日本側投入 課題別研修「薬事行政」への上乗せ研修3人分×3年間
相手国側投入 N/A
外部条件 N/A
実施体制
(1)現地実施体制 保健省薬剤管理局国立必須医薬品製造センター(SPMC)
(2)国内支援体制 N/A
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
JICAは、保健医療行政強化を図るため、開発調査「保健医療制度改善計画」(2002年~2003年)及び「保健システム管理強化計画」(2005年~2007年)を実施し、NCD対策強化や病院の業務改善、経営改善への提言を盛り込んだ保健セクター改革のための政策提言を行った。同調査の成果を受け保健省は、10ヵ年計画「保健医療マスタープラン2007-16」を取りまとめ、①疾病負担の削減と健康増進のための統合的保健医療サービス提供、②健康維持のためのコミュニティのエンパワメント、③保健医療システムの効率化等を重点戦略として設定している。保健省の取り組みに対し、JICA はNCD 対策として、技術協力「健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト」及び有償資金協力「地方基礎社会サービス改善事業」を実施し、また保健医療サービスの向上のために5S/TQM 手法を通じて、継続的にセクター改革推進に貢献している。
(2)他ドナー等の
援助活動
保健セクターへの協力は、主に世界銀行やWHO、UNICEFが実施している。①世界銀行「保健セクター開発プロジェクト」(2004-2010、72.6百万米ドル)「同追加プロジェクト」(2009-2011、26.7百万ドル)で州保健局の強化及び1次医療施設を中心とした施設整備、保健サービス向上及び保健省の機能強化を図ってきた。併せて2012年対スリランカ中期計画作成後、①NCD管理・予防、②栄養改善の2課題を柱とする後継案件が検討されている。②WHO「WHO国別協力計画」に基づき、保健医療システム強化、感染症・非感染症対策、緊急事態への準備・対応、母子保健・リプロダクティブヘルス等の分野での人材育成及び政策策定支援を実施している。③UNICEFア)母子栄養改善、イ)紛争影響地域の基礎保健サービス改善、ウ)小児科関連の施設・機材の拡充をコンポーネントとする女性と子どもの保健と栄養改善のためのプログラムを実施している。

在外事務所主管案件
個別案件(第三国研修)
2016年09月15日現在
在外事務所 :スリランカ事務所
案件概要表
案件名 (和)5S-CQI-TQM能力強化
(英)5S-CQI-TQM implementation in Sri Lanka and African Countries
対象国名 スリランカ
分野課題1 保健医療-その他保健医療
分野課題2
分野課題3
分野分類 保健・医療-保健・医療-保健・医療
プログラム名 保健医療プログラム援助重点課題 脆弱性の軽減開発課題 脆弱性軽減のための社会基盤整備
プロジェクトサイト スリランカ国 コロンボ市内および近郊
協力期間 2014年07月15日 ~ 2017年03月31日
相手国機関名 (和)保健省
相手国機関名 (英)Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine
プロジェクト概要
背景 Sri Lanka provides free healthcare services to all the citizens in the country. This has resulted in good health indices in the country when compared to the other countries in the region.
Ministry of Hearth(MOH) of Sri Lanka has concluded "Master Plan for Hearth Sector 2007-2016" in response to policy recommendation by JICA, and set 3 major goals; (i)Comprehensive health and medical service to reduce medical expense and to improve hearth, (ii)Empowerment of communities for health maintenance, and (iii) Efficiency of health and medical services. Hence, the improvement of quality is overall theme in hearth sector since then. However there are common problems related to healthcare quality in relation to the structure (resources and equipment, facilities), processes (service) and outcomes (infection rates, hospital mortality rates etc).
In order to overcome this situation Sri Lankan hospitals introduced the Japanese style of management system, 5S as an entry point to the quality improvement under the technical cooperation project "Quality Improvement of Health Service by 5S-CQI-TQM" by JICA. The guiding principle of this program was to utilize the existing resources effectively to overcome the existing problems.
After several years have passed, Sri Lanka has been able to produce good results with regard to the satisfaction of patients and health staff and improved outcomes. MOH of Sri Lanka has been sharing this experience with the other neighboring countries in Asia with limited resources settings and similar problems as successful show case.
Hence presently, MOH wish to invite health managers of selected countries to share the Sri Lankan experience with them which will enable them to create their own solutions for the existing problems in healthcare of respective countries. It aims to expand their programs to other countries and at the same time it will enhance Sri Lanka to develop their capacities as

a leading country of those programs in Asia and Africa.
上位目標 - Quality management of healthcare institute will be established and utilized within their countries.
プロジェクト目標 -Quality management of healthcare institute will be shared within their countries.
成果 -Participants will acquire the basic knowledge of quality management.
活動 -To provide Begginer-Basic training and implementing programme for the health personnel.
-To provide 3 methods of implementation: Classroom-based lectures, Discussions, and Field study visit.
-To visit 7 hospitals/healthcare institutes in Colombo and other provincial area.投入
日本側投入 Experts in health management (quality and safety), equipments(if nessesary)
相手国側投入 Project Manager, Support staff, Trainer, Office space and runnning expenses
実施体制
(1)現地実施体制 Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicines
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
"The Project on Improvement of Quality and Safety of Healthcare institutions in Sri Lanka"(2009-2011)"Training of Senior Registrars in Medical Administration in Japan"(2012-2015)
(2)他ドナー等の
援助活動
Under World Bank project the Quality and Safety programme will be initiated in 2013. This World Bank Project will be mainly focusing on technical aspects of service quality such as preparing guidelines on quality and safety, clinical guidelines, initiating clinical audit, issues related to patient safety and establishing a hospital accreditation process. WHO will provide technical assistance in improving quality in healthcare especially related to quality and safety.

国内機関主管案件
草の根技協(地域提案型)
2017年08月02日現在
本部/国内機関 :中部国際センター
案件概要表
案件名 (和)配水管施工管理能力強化プロジェクト
(英)Capacity Development Project for Management of Water Supply Pipe Laying
対象国名 スリランカ
分野課題1 水資源・防災-都市給水
分野課題2 都市開発・地域開発-都市開発
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-公益事業-上水道
プログラム名 プログラム構成外援助重点課題 -開発課題 -
プロジェクトサイト コロンボ及び周辺の水道配水管敷設箇所
署名日(実施合意) 2014年01月08日
協力期間 2014年02月04日 ~ 2017年03月31日
相手国機関名 (和)スリランカ上下水道庁
相手国機関名 (英)National Water Supply and Drainage Board of Sri Lanka
日本側協力機関名 名古屋市上下水道局
プロジェクト概要
背景 NWSDBは無収水対策を改善させるため、水道事業を支える人材の育成に精力的に取り組んでいる状況である。本プロジェクトにおいては、「配水管施工管理能力の強化」を主題とし、2013年度実施のプロジェクトにおいて作成された「施工管理チェックリスト」、「管接合マニュアル」の活用を図る。それにより、配管工事の要となる管接合について、施工管理を担う技術者と施工を担う配管工の双方が適切な施工方法を習得し、工事の品質を向上させ、新設管への入れ替えによる無収水率の低減を促進する。また、他工事による毀損事故防止に資するとともに、工事完了後に不可視となる部分の品質確認を目的とした工事記録の作成等についても指導していく。
上位目標 スリランカにおける無収水率を削減する。
プロジェクト目標 NWSDBにおいて、配水管工事の施工管理能力が強化する。
成果 工事において漏水を未然に防ぐ送配水管の施工が実現されるよう、しっかりとした施工を行うことのできる配管工を育成し認定するとともに適切な施工管理が実施されるための知識やノウハウをNWSDBの技術者が習得する。工事記録の作成により工事立会等を実施し他工事での毀損事故が防げる。
活動 ①2013年度に名古屋市上下水道局は、配水管の施工管理を担当する技術職員と本プロジェクトの研修担当の職員をスリランカに調査派遣する。技術職員は、今後の技術指導に必要となる情報を収集する。研修担当職員は本プロジェクトの遂行や今後のスリランカとの協力に必要となる情報を収集する。②2014年度中期にNWSDBの職員に対し、①で収集した情報に基づき日本で研修を実施する。③NWSDBの職員は①及び②を通じて作成されたアクションプランを実施する。④2014年度後期に、アクションプランのフォローアップのため、技術職員をスリランカへ派遣し、必要な技術指導を行う。

⑤2015年度前期に、アクションプランのフォローアップのため、技術職員をスリランカへ派遣し、必要な技術指導を行う。⑥2015年度中期にNWSDBの職員に対し、⑤で収集した情報に基づき日本で研修を実施する。⑦2015年度後期に、アクションプランのフォローアップのため、技術職員をスリランカへ派遣し、必要な技術指導を行う。また、今後のスリランカとの協力に必要となる情報を収集するための調査を行う職員も派遣する。⑧2016年度前期に、アクションプランのフォローアップのため、技術職員をスリランカへ派遣し、必要な技術指導を行う。また、今後のスリランカとの協力に必要となる情報を収集するための調査を行う職員も派遣する。⑨2016年度中期にNWSDB職員に対し、⑧で収集した情報に基づき日本で研修を実施する。⑩2016年度後期に、最終的な評価を行うため、技術職員をスリランカへ派遣する。
投入
日本側投入 名古屋市上下水道局専門家の現地派遣 2013年度 2名×3週間×1回 2014年度 2名×2週間×2回 2015年度 2名×2週間×2回 2016年度 2名×2週間×2回 名古屋市上下水道局研修員受入(本邦研修) 2014年度 6名×3週間×1回 2015年度 6名×3週間×1回 2016年度 3名×1週間×1回、6名×3週間×1回
相手国側投入 スリランカ上下水道庁職員の派遣(本邦研修参加) 2013年度 6名×3週間×1回 2014年度 6名×3週間×1回 2015年度 6名×3週間×1回 2016年度 3名×1週間×1回、6名×3週間×1回
実施体制
(1)現地実施体制 スリランカ上下水道庁
(2)国内支援体制 名古屋市上下水道局

本部主管案件
有償技術支援-附帯プロ
2019年02月01日現在
本部/国内機関 :地球環境部
案件概要表
案件名 (和)土砂災害対策強化プロジェクト
(英)Technical Cooperation for Landslide Mitigation Project
対象国名 スリランカ
分野課題1 水資源・防災-土砂災害対策
分野課題2
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-社会基盤-河川・砂防
プログラム名 気候変動・防災対策プログラム援助重点課題 脆弱性の軽減開発課題 脆弱性軽減のための社会基盤整備
プロジェクトサイト 中部州キャンディ県、マタレ県、ヌワラエリア県及びウバ州バドゥッラ県
協力期間 2014年07月01日 ~ 2018年08月31日
相手国機関名 (和)国家建築研究所
相手国機関名 (英)National Building Research Organization
プロジェクト概要
背景 スリランカ民主社会主義共和国(以下、「スリランカ」)において、土砂災害は最も深刻な自然災害のひとつである。同国の国土の面積の2 割、総人口の3 割を占める中央部の山岳・丘陵地域では、急速な開墾・開発と脆弱な地質特性と急峻な地形条件から、モンスーン期の豪雨の際には、急傾斜地の崩壊や地滑り等の土砂災害が頻発している。特に、本プロジェクトの対象地域である中部州キャンディ県、マタレ県、ヌワラエリア県及びウバ州バドゥッラ県の山岳地域では、潜在的に地すべり、斜面崩壊が起こりやすく、引き金となる豪雨があると、大きな土砂災害が発生している。2003 年、2007 年、2010 年及び2011 年に発生した土砂災害では、全土で300 人近い人命が失われ、これらの土砂災害が及ぼした人々の財産やインフラへの被害と国土開発に対する損害は甚大であった。土砂災害に対する土砂災害対策の実施や早期警報の発出は国家建築研究所(以下、「NBRO」)が担っている。NBROは比較的費用の掛からないハザードマップ整備等の非構造物対策を中心に実施してきたが、社会的要請に基づき、近年では構造物対策も手掛けるようになってきている。一方、NBROの実績は未だ十分ではなく、NBRO職員の対策工の検討に必要となる調査や設計、対策工事の施工監理等の土砂災害対策能力の向上が課題となっている。
上位目標 対象地域の土砂災害が減少する。
プロジェクト目標 パイロットサイトでのスリランカ国に適用可能な日本の技術や他国の技術を活用した土砂災害軽減対策を通じてNBROの土砂災害管理能力が向上する。
成果 成果1:土砂災害対策のための調査および評価の能力が強化される。成果2:地すべり対策のための設計、施工監理およびモニタリングの能力が強化される。成果3:斜面崩壊対策のための設計、施工監理およびモニタリングの能力が強化される。成果4:落石対策のための設計、施工監理およびモニタリングの能力が強化される。成果5:土砂災害軽減対策(非構造物対策を含む)の知識とノウハウが改善される。
活動 1.1 パイロット地域での土砂災害についての予備調査を実施する。1.2 パイロット地域の候補地における地質および地質工学調査を実施する1.3 ピエゾメータ、地盤伸縮計、ピエゾメータ付ひずみ計、孔内傾斜計等の必要機材を設置する。

1.4 パイロット地域での土砂災害対策工の設計思想を検討し、決定する。2.1 パイロット地域での地すべりのモニターリング及び評価を行う。2.2 パイロット地域での地すべり対策のための設計及び工事費の積算を行う。2.3 パイロット地域での地すべり対策のための入札図書を作成する。2.4 パイロット地域での地すべり対策のための入札図書の評価及び施工業者の調達を行う。2.5 パイロット地域での地すべり対策のための施工監理を行う。2.6 パイロット地域での地すべり対策の工事完成報告書を作成する。3.1 パイロット地域での法面崩壊のモニターリング及び評価を行う。3.2 パイロット地域での斜面崩壊対策のための設計及び工事費の積算を行う。3.3 パイロット地域での斜面崩壊対策のための入札図書を作成する。3.4 パイロット地域での斜面崩壊対策のための入札図書の評価及び施工業者の調達を行う。3.5 パイロット地域での斜面崩壊対策のための施工監理を行う。3.6 パイロット地域での斜面崩壊対策の工事完成報告書を作成する。4.1 パイロット地域での落石のモニター及び評価を行う。4.2 パイロット地域での落石対策のための設計及び工事費の積算を行う。4.3 パイロット地域での落石対策のための入札図書を作成する。4.4 パイロット地域での落石対策のための入札図書の評価及び施工業者の調達を行う。4.5 パイロット地域での落石対策のための施工監理を行う。4.6 パイロット地域での落石対策の工事完成報告書を作成する。5.1 土砂災害の構造物対策についての既存ガイドラインと技術マニュアルのレビューおよび改定を行う。5.2 土砂災害の構造物対策についての改定されたガイドラインと技術マニュアルを用いた研修を実施する。5.3 土砂災害の構造物対策及び非構造物対策についてのセミナー及びワークショップを実施する。5.4 土砂災害軽減のための土地利用規制について利害関係者協議を行う。5.5 土砂災害軽減のための土地利用規制の資料を作成する。5.6 日本の経験に基づいた土砂災害軽減のための早期予警報・伝達について利害関係者協議を行う。5.7 日本の経験に基づいた土砂災害軽減のための早期予警報・伝達の資料を作成する。
投入
日本側投入 a)長期専門家(36.0 M/M): 1名(チーフアドバイザー/土砂災害管理)b)短期専門家(全体59.0 M/M): 業務主任/土砂災害解析、土地利用政策、モニタリング機器/地質専門家、地すべり対策(設計/施工監理)、斜面崩壊 対策(設計/施工監理)、落石対策(設計/施工監理)、ボーリング、調達/入札評価、プロジェクト業務調整/ 土砂災害対策補助c)本邦研修/第三国研修d)供与機材: デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、プリンター、ピエゾメータ、地盤伸縮計、ピエゾメータ付 ひずみ計、孔内傾斜計e)パイロット事業:土砂災害対策工(4ヵ所、合計1.0億円程度の規模)
相手国側投入 a) カウンターパートの配置(プロジェクト長:NBRO長官、プロジェクト・ディレクター:土砂研究・リスク管理部長、プロジェクト・マネージャー:キャンディ事務所長、その他のC/Pについてはプロジェクト開始後に確定)b) プロジェクト事務所および設備c) プロジェクトの実施に必要な費用(機材の関税、カウンターパートの給与など)
外部条件 ・プロジェクトを通じて技術を身に付けたカウンターパートが異動しない・壊滅的な災害がプロジェクト期間中に起こらない.・自然条件の急激な変化がない
実施体制
(1)現地実施体制 The project will be implemented by NBRO. Monitoring and Evaluation will be coordinated by Ministry of Disaster Management through District Secretary, Divisional Secrataries and District Disaster Management Coordination Units.
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
RDAが実施機関となって「国道土砂災害対策事業」(円借款事業)が実施予定であり、その中で本事業の対象地域を含む7県において日本の技術を採り入れた先進的な道路法面の土砂災害対策が行われる。本事業と類似性があることと実施時期が重なることから、現場視察の実施などの相互連携の可能性があり、RDAも本事業の研修プログラム等への参加を希望している。
(2)他ドナー等の
援助活動
UNDPの実施するコミュニティ防災は土砂災害対策においては非構造物対策でありJICAの行う構造物対策とともに土砂災害対策として有効となる。世界銀行は学校関連の土砂災害対策支援をおこなうが、技術的なところでJICAのプロジェクトと協力関係を持ちたい意向を持っている。

本部主管案件
技術協力プロジェクト
2018年05月17日現在
本部/国内機関 :地球環境部
案件概要表
案件名 (和)気象観測・予測・伝達能力向上プロジェクト
(英)Project for Improving of Meteorological Observation, Weather Forecasting and
Dissemination
対象国名 スリランカ
分野課題1 水資源・防災-気象
分野課題2
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-運輸交通-気象・地震
プログラム名 気候変動・防災対策プログラム援助重点課題 脆弱性の軽減開発課題 脆弱性軽減のための社会基盤整備
プロジェクトサイト 気象局本部(コロンボ)を核として全土
署名日(実施合意) 2014年05月23日
協力期間 2014年09月01日 ~ 2017年08月31日
相手国機関名 (和)気象局
相手国機関名 (英)Department of Meteorology
プロジェクト概要
背景 In Sri Lana, more than 90% of natural disasters are weather or climate related. Every year flood, droughts, thunder, and lightning activity and strong winds cause disasters in various parts of the islands. Furthermore, the increasing trend of extreme events, natural hazards and disasters are becoming more frequent. Between years 2000 and 2010 more than 13 million people in Sri Lanka have been affected by landslides, floods, droughts and high winds. A recent study to estimate damages and losses as a result of a flood event has resulted in estimating the damages and losses in five districts of Sri Lanka as LKR 5.56 billion. According to published statistics, the total economic damage to the economy of Sri Lanka during the period from 1991-2005 due to natural disasters was a staggering 1.79 billion US dollars. Thus the adverse effect, particularly in terms of absorbing the impact and recovery is very high and is very much linked with all social, economic and development activities due to the increased human activities and more infrastructure facilities associated with modern world. This vulnerability to adversities cannot be handled by the community themselves in isolation. An effective disaster preparedness plan at national level, primarily based on timely and accurate early warning.
上位目標 Early warning system and disaster prevention in Sri Lanka is improved.
プロジェクト目標 to improve the forecasting capability of the Department of Meteorology and thereby effectively improving its capacity to minimize the impact of weather hazards.
成果 1. Identification and incorporation of suitable techniques including equipment to improve weather forecasting/ early warning procedures at all time scales.2. Improvement of meteorological observation network to ensure the timely availability of high quality meteorological information.3. Provision of other essential facilities for seamless service delivery.

活動 1-1. Capacity building in the area of numerical weather prediction in order to enhance the utilization of numerical outputs for routine weather forecasting.1-2. Capacity building in the area of data assimilation (radar, surface observations, radiosonde) to numerical models to fine tune model outputs.1-3 Capacity building in the area of seasonal and long-term forecasting.1-4 Installation of a Doppler Weather Radar at Matale to supplement the coverage of Gongala radar to ensure radar coverage of the entire island.1-5 Capacity development to utilize the radar information as a tool for now-casting and very short range forecasting including heavy rainfall and lighting alerts1-6. Installation of a hi-res satellite cloud receiving /analysis ground station for low earth ororbit meteorological satellites including terra and aqua.2-1. Establishment of four new fully operational surface synoptic stations for round-the-clock observations and several automatic weather stations with real time communication facilities.2-2. Establishment of an radiosonde observation station in strategic location of Pottuvil adjoining bay of Bengal close to Equator where no observation data are available to entire meteorological community world over.2-3. Establishment of a Lightning Detection and Tracking System covering the entire landmass of Sri Lanka.3-1. Establishment of a data archiving system feeding to a central database, for huge amount of daily data that will eventually be used in research by all concerned.3-2. Establishment of a meteorological instrument laboratory for testing, calibration and repair, and procure latest test equipment, a mandatory requirement of WMO to ensure quality of data.3-3. Upgrading of the electronic maintenance division and the media unit.3-4. establishing of a small scale GIS laboratory for meteorological applications.3-5. Upgrading Administrative set up in a new building with up to date infrastructure facilities and transport
投入
日本側投入 要確認
相手国側投入 要確認
外部条件 特になし
実施体制
(1)現地実施体制 要確認
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
特になし

国内機関主管案件
草の根技協(地域提案型)
2014年11月22日現在
本部/国内機関 :関西国際センター
案件概要表
案件名 (和)スリランカ国における持続可能な「トラウマ・カウンセリングと融合した防災教育」活
動推進プロジェクト
(英)Project on Promotion of Sustainable Disaster Mitigation Education and Trauma
Counseling
対象国名 スリランカ
分野課題1 水資源・防災-総合防災
分野課題2
分野課題3
分野分類 人的資源-人的資源-教育
プログラム名 プログラム構成外援助重点課題 -開発課題 -
プロジェクトサイト ウェリガマ県
署名日(実施合意) 2010年07月01日
協力期間 2011年12月10日 ~ 2014年12月09日
相手国機関名 (和)全セイロン教職員組合、スリランカ国教育省
相手国機関名 (英)All Ceylon Teachers' Union, Ministry of Education
日本側協力機関名 兵庫県防災企画局防災企画課
プロジェクト概要
背景 2004年12月26日、インド洋大津波が発生し、スリランカ、インドネシア、タイ、インドなど、多くの国々で甚大な被害が発生した。スリランカでは津波後、トラウマ・カウンセリングと防災教育へのニーズが高まり、諸外国及び国際関係機関やNGOの援助による多くのプロジェクトが実施された。しかし、それらのプロジェクトは一時的で単発的なものであり、時間の経過とともにプロジェクト自体も減少してきている。また、一時的に外部からの援助が集中したため、スリランカ国自身の手による、能動的で持続可能な防災教育のプログラムが発展してきたとは言いがたい現状がある。津波から7年近くが経過した現在、スリランカには心のケアを必要とする子どもたちがまだ多く存在するが、ほとんどの教職員はその専門知識を持っていない。教職員のための研修システムも整備されておらず、被災地域の教職員がもつニーズに応えることができていない。さらに、スリランカは、水害などの自然災害が多発する国であるが、災害のメカニズムを学び、災害にどう備えるかを学ぶ防災教育も、小中高の教育現場で体系的に行われていない。 一方、兵庫県は、阪神・淡路大震災後の教育復興において「子どもの心のケアと防災教育の推進」を中心に実践を蓄積してきた。震災の教訓から、自然現象を学び、備えを実践する防災教育に加えて、命の大切さや助け合いの素晴らしさを学ぶ新たな防災教育を推進してきた。また、被災地域においては、被災者の心のケア(=災害に対する恐怖や大切な人を失った喪失感を軽減し、災害経験を受け入れることができる)のプロセスの中で、防災教育(=災害に対する正しい知識を得て、体験した災害の恐怖を軽減し、次の災害に備えることができる)を行う必要性を実証し、ノウハウを蓄積してきた。その成果は、台風23号(2004年)、台風9号(2009年)の水害時にも発揮され、迅速な教育復興と子どもたちの心のケア、中高生による被災地支援ボランティア活動が展開された。 スリランカの教育関係者の自助努力による、能動的で持続可能な「トラウマ・カウンセリングと融合した防災教育」のプログラム、テキスト、研修プログラムの開発には、兵庫が培ってきたトラウマ・カウンセリングと防災教育を融合させるという視点が必要であり、また、将来的にもこう

した新しい視点は、今後起こり得る災害後の対応に対しても必要と思われる。兵庫県はこれまでにスリランカに対して継続的な支援を行っており、そこで構築した教職員組合の連合体「スリランカ教職員組合連合ツナミ救済委員会」との信頼関係や、同委員会を通してスリランカ国教育省及び地域教育委員会からの支援、協力を受けることができる体制があることを鑑み、このたび事業を実施することとなった。
上位目標 スリランカ国において、今後発生する自然災害からの被害を軽減するために、持続可能な「トラウマ・カウンセリングと融合した防災教育」の体系的なプログラムが開発され普及される。
プロジェクト目標 本事業を通して、南部ウェリガマ県のパイロット地域とその中心となって活動するモデル校の教職員が、防災教育とトラウマ・カウンセリングの知識とノウハウを習得する。さらに、研修を受けた教職員が防災教育とトラウマ・カウンセリングの実践を通して、スリランカで活用可能な防災教育とトラウマ・カウンセリングのカリキュラム、テキスト、研修マニュアルを完成させる。その結果、ウェリガマ県で防災教育とトラウマ・カウンセリングの実践が広がる。
成果 成果1. 教職員、生徒を対象とした津波によるトラウマと防災教育の実態調査報告書が完成する。成果2. スリランカの現状に見合った防災教育とトラウマ・カウンセリングのカリキュラム、テキスト、研修マニュアルが完成する。成果3. ウェリガマ県において教職員による防災教育とトラウマ・カウンセリングが継続的に行われる。成果4. スリランカの教育関係者による防災教育とトラウマ・カウンセリングのセミナーが開かれる。
活動 本事業では、パイロット地域のモデル校の教職員と地域で選抜された教職員が防災教育とトラウマ・カウンセリングの研修を受け、その教職員が地域や自校で他の教職員に知識とノウハウを伝達するTOT(Training of Trainers)手法を用いる。1年目はモデル校(ウェリガマ県ジッダルタカレッジほか、全3校)での実践を中心に行う。2年目はモデル校の実践をパイロット地域(ウェリガマ県)に広げる。3年目は研修を受けた教職員など関係者による自主的実践を支援する活動に重点を移す。3年の事業終了後も、引き続いて防災教育とトラウマ・カウンセリングを実践するための教職員専門チームを組織する。
事業の成果に対する活動の詳細は以下のとおり。1-1. 日本側専門家がモデル校の教職員、生徒を対象に災害後のトラウマとその後の防災教育の実態調査(ヒアリング、アンケート)を行い、報告書にまとめる。1-2. 日本側専門家がパイロット地域の教職員、生徒を対象に災害後のトラウマとその後の防災教育の実態調査(ヒアリング、アンケート)を行い、報告書にまとめる。2-1. 1年目はモデル校での活動(防災教育とトラウマ・カウンセリングのモデル授業、ヒアリング、ワークショップ)を通して、防災教育とトラウマ・カウンセリングのカリキュラム、テキスト、モデル校の教職員を対象とした研修マニュアルの原案を作成する。2-2. 2年目はパイロット地域での活動を通して、防災教育とトラウマ・カウンセリングのカリキュラム、テキスト、パイロット地域の教職員を対象とした研修マニュアルの原案を作成する。2-3. 1年目、2年目の活動を受けて、3年目にパイロット地域の代表教職員と教育委員会関係者で防災教育とトラウマ・カウンセリングのカリキュラム、テキスト、研修マニュアルを完成させる。3-1. 現地の教職員に必要な防災教育とトラウマ・カウンセリングの知識とノウハウを習得させるために、防災教育とトラウマ・カウンセリングのセミナーを開く。3-2.専門家によるスーパービジョンと現地コーディネーターの訪問指導によってモデル校の教職員による継続的実践をモニタリング、支援する。3-3.現地の教職員に必要な防災教育とトラウマ・カウンセリングの知識とノウハウを習得させるために、日本にて防災教育とトラウマ・カウンセリングの専門家から知識・技術を学ぶ(研修員受入)。3-4.専門家によるスーパービジョンと現地コーディネーターの訪問指導によってパイロット地域の教職員による継続的実践を支援する。4-1. パイロット地域で、研修を受けた教職員が講師となる防災教育とトラウマ・カウンセリングの研究集会を開催する。4-2. スリランカ全土に呼びかけた教職員セミナーを開催する。研修を受けた教職員が講師となり、実践発表などを通して、セミナー参加教職員に防災教育とトラウマ・カウンセリングの知識、ノウハウを習得させる。
投入
日本側投入 1)人材・専門家派遣(防災教育専門家、トラウマ・カウンセリング専門家) 実態調査、モデル授業の実施、現地教職員へのセミナー開催、教材作成などを行う。 4人×10日間×2回×3年・研修員受入(現地コーディネーター、モデル校教職員、ウェリガマ県教職員、教育委員会スタッフ) 9人×1週間×1回×3年2)資機材活動実施に必要な資材等
相手国側投入 教育省関係者の人件費等
実施体制
(1)現地実施体制 ACUTおよび教育省が主となって事業を実施する。また、プロジェクト合同調整員会において、案件の進捗や問題点を関係者間で協議する。

(2)国内支援体制 神戸学院大学が実施団体となる。兵庫県立舞子高等学校や兵庫県教育委員会震災・学校支援チームEARTHの協力も得る。
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
スリランカ国南西部主要4河川の流域を中心とする地域(ヌワラエリヤ県、カルタラ県、ラトナプラ県)において、防災省国家防災センターをカウンターパートとする技術協力プロジェクト「気候変動に対応した防災能力強化プロジェクト」を実施している。また、南部州アンバランゴダにおいて、スリランカ国立水産資源調査開発機構をカウンタパートとする草の根技術協力事業(支援型)「スリランカ国南部州アンバランゴダにおける省資源型定置網漁業の導入による漁村活性化支援事業」を実施中である。
(2)他ドナー等の
援助活動
GTZが防災教育プロジェクトを実施しており、教員及び生徒配布用防災教育教材を作成している。

在外事務所主管案件
技術協力プロジェクト
2019年01月24日現在
在外事務所 :スリランカ事務所
案件概要表
案件名 (和)紛争影響地域におけるコミュニティ開発人材育成プロジェクト
(英)The Project for Training of Frontline Officers in Community Development in
Conflict Affected Areas in Sri Lanka
対象国名 スリランカ
分野課題1 ガバナンス-地方行政
分野課題2 平和構築-ガバナンス
分野課題3
分野分類 計画・行政-行政-行政一般
プログラム名 農漁村振興プログラム援助重点課題 後発開発地域の開発支援開発課題 農村地域の社会経済環境の改善
プロジェクトサイト 北部州、東部州、北中部州
署名日(実施合意) 2011年02月21日
協力期間 2011年03月01日 ~ 2016年03月31日
相手国機関名 (和)行政・管理省、北部州政府、東部州政府、北中部政府
相手国機関名 (英)Ministry of Public Administration & Management, Nothern, Eastern and North
Central ProvincialCouncil
プロジェクト概要
背景 スリランカにおいて、30年近く継続した武力紛争は2009年5月に終結した。紛争で最も影響を受けた東部州、及び北部州のうち、2007年に武力紛争が終結した東部州では基幹インフラの復旧が一定程度進み、開発期に移行する一方で、紛争末期に激戦が行われた北部州においては一時28万人に及ぶ国内避難民(IDP)を生み出すなど、東部州以上に甚大な被害を蒙った。その後、2012年後半に公式には全てのIDPが帰還し、2013年前半に人道援助の多くが完了した状況下、北部州においても基幹インフラの復興が進められており、帰還民による生計活動が再開されつつある。しかしながら、同地域には安定的に生計活動を営む基盤が未だに不足していることや、土地なし農民や寡婦世帯などの脆弱層と土地所有世帯等との間で経済格差が生まれつつあるなど、新たな課題が発生している状況にある。更に、紛争中は行政サービスが行き届いていない地域が多く存在し、住民も避難生活を繰り返す中で組織化がなされていない中、行政と住民との関係性が構築されていないといった紛争影響地特有の課題を抱えている状況にある。このため、住民と直接接する機会の多い地方行政官による住民の状況把握力、及び住民に接する能力の強化が課題となっている。 本案件は、要請がなされた当時、まだ紛争中にあっても両州において実施中であった各種コミュニティ開発案件の成果を元に、両州を所管する地方行政官の実践力強化を通じた住民によるコミュニティ開発を推進するため、2007年度に技プロの要請として上げられ、翌2008年度に採択されたものである。その後、紛争終結後の緊急支援を行いつつ、スリランカ政府と本案件のコンセプト及び実施手法に係る協議を進めた結果、2011年2月にR/Dが締結された。同R/Dの締結を受け、JICAは同年7月にローカルコンサルタントによる両州の研修ニーズ調査に着手し、同年10月に「プロジェクト運営管理/研修企画」分野の個別専門家派遣を行い、事業の本格化を図ろうとしたものの、派遣直後の2011年12月に開催された第一回JCCにおいて、当時の北東部の復興の進捗状況等を勘案し、案件の枠組みを見直すようスリランカ側から強い要望が出された。その後、累次に亘りスリランカ政府と枠組みの見直しに係る協議を行った結果、新たに北部州・東部州に隣接し、紛争影響地域を一部抱えている北中部州を加えると共に、プロジェクト目標自体に変更はないものの、地方行政官に対する研修そのものよりも、各州の研修実施機関の機能強化にフォーカスした案件内容に軌道修正することで合意し、

2013年3月に修正R/Dが締結され現在の案件実施基盤が整った状況にある。
上位目標 紛争影響地域(北部州、東部州、北中部州)において行政が提供するサービスの質が改善する。
プロジェクト目標 支援対象3州(北部州、東部州、北中部州)において、地方行政官のコミュニティ開発促進能力を向上させるため、州研修機関の研修実施能力を改善する。
成果 1)コミュニティ開発の推進にとって重要な研修コースを特定し、研修コース内容が開発される。2)十分な数のファシリテーターが育成される。3)優先付された地方行政官に対して研修が実施される。4)州研修所が研修実施過程でPDCAサイクルを経験する。
活動 1-1 支援対象3州(北部州、東部州、北中部州)の研修実施機関が有する研修コースをレビューし、コミュニティ開発の推進にとって重要な優先的な研修コースを特定する。1-2 シンハラ語、タミル語の研修教材を開発する。1-3 支援対象3州(北部州、東部州、北中部州)の研修実施機関が効果的な研修を行うために必要となる機材を供与する。
2-1 北部州MDTU(Management Development Training Unit)、東部州MDTU(Management Development Training Unit)及び北中部州MDTU(Management Development Training Unit)の研修講師の候補者を特定する。2-2 これら研修機関と共にシンハラ語及びタミル語の研修教材を開発する。2-3 シンハラ語或いはタミル語により研修講師へのTOT研修を実施する。2-4 研修実施状況のモニタリングを行い、更に研修講師へのTOT研修が必要な場合においては追加的に研修を実施する。
3-1 関係当局との協議を通して優先的に研修する地方行政官を特定する。3-2 研修実施の計画を策定し、それに沿って実施する。
4-1 研修ファシリテーター、ToT及び地方行政官研修受講者からのフィードバックを得る。4-2 受講者の研修受講後の研修成果を評価する。4-3 研修コースと教材を改善する。4-4 研修コースと教材及び研修による効果について周知を図る。
投入
日本側投入 長期専門家(総括/研修企画)短期専門家(研修計画・教材作成体制強化、教材作成支援・脆弱層支援、コミュニティ開発、参加型開発、組織能力強化等)現地活動費(研修カリキュラム・教材作成費用、ローカルコンサルタント費用、ローカルスタッフ費用、現地調査、研修実施に必要な経費等)供与機材(PC、車両、他研修資機材)
相手国側投入 カウンターパート(プロジェクトコーディネーター、マネージャー、事務スタッフ等)研修施設、プロジェクト事務所事務コスト
外部条件 地方行政官の基本的役割が変更されない。研修を受講した地方行政官が北部州、東部州、北中部州から異動しない。
実施体制
(1)現地実施体制 1.Joint Coordination Committee (JCC):年間活動計画の承認、活動報告(メンバー:行政・管理省、国家政策・経済省、SLIDA、北部州政府、東部州政府、北中部州政府、北部州・東部州・北中部州MDTU、日本人専門家、JICA事務所、日本大使館等)
2.Provincial Coordination Committee (PCC):州レベルの年間活動計画の決定、活動報告(メンバー:北部州政府、東部州政府、北中部州政府、県次官事務所、北部州・東部州・北中部州政府MDTU、SLIDA、日本人専門家等)
3.Working Group/s for Training Module Formulation):研修コース内容(案)の開発、改善、活動報告(メンバー:SLIDA、北部州MDTU長、東部州MDTU長、北中部州MDTU長、JICA専門家、ローカルコンサルタント等)
(2)国内支援体制 国際協力専門員(地方行政/平和構築)並びにJICA本部経済基盤開発部からの技術的支援。
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
2007-2011「南部地域の村落生活向上プロジェクト」(SouthCAP)2005-2009「トリンコマリー県住民参加型農業農村復興開発計画」(TRINCAP)2004-2008「コミュニティアプローチによるマナー県復旧・復興プロジェクト」(MANRECAP)集団研修(「住民主体のコミュニティ開発」、「地方自治体行政強化(参加型地域開発)」)2006-2013「農村経済開発復興事業(円借款)(PEACE)」
(2)他ドナー等の
援助活動
GTZ: PIP (Performance Improvement Project)GTZ: Capacity Enhancement of Field Officers towards Sustainable DevelopmentUSAID: EASR (Economic and Social Transition)WB: NEIAP-II (North East Irrigation and Agriculture Project)ADB: NECORD (North East Community Restoration and Development Project)ADB: NECCDEP (North East Coastal Community Developemnt Project)

各ドナー機関が実施した地域開発プロジェクトにおけるグッドプラクティス及び研修実施の教訓・事例を本プロジェクトに反映する。

在外事務所主管案件
個別案件(専門家)
2018年10月23日現在
在外事務所 :スリランカ事務所
案件概要表
案件名 (和)後発地域における農産物の生産・販売促進による地域開発支援
(英)Long Term Experts(Rural Development)
対象国名 スリランカ
分野課題1 平和構築-経済復興
分野課題2 農村開発-農村生活環境改善
分野課題3
分野分類 農林水産-農業-農業一般
プログラム名 紛争影響地域生産性回復プログラム援助重点課題 後発開発地域の開発支援開発課題 紛争影響地域の開発促進
プロジェクトサイト 北部州及び南部地域(南部州、ウバ州)
署名日(実施合意) 2014年07月18日
協力期間 2014年10月01日 ~ 2017年09月30日
相手国機関名 (和)農業省
相手国機関名 (英)Ministry of Agriculture
プロジェクト概要
背景 スリランカ農業のGDPに占める割合は約11%(2013年)に留まるも、総人口の77.3%(2012年)が農村に居住し、農業部門従事者数は全就業人口の約30%(2012年)を占め、全国に180万人と想定される貧困層も農業部門で最多(44.1%。なお、製造業部門20.8%、サービス部門35.1%。2009/10年)であることから、同国の社会経済発展において農村開発、農業開発は極めて重要な意味を持つ。 加えて同国北東部では、2009年5月まで約30年間続いた内戦によって28万人超の国内避難民(IDP)が発生した。同年10月以降、政府によって幹線道路など基礎インフラの復旧が急速に進められる一方で、IDPの帰還地域の多くは飲み水の確保にも事欠くなど生活基盤が破壊されたままであり、社会サービスや現金収入を得る機会不足など、帰還民を含む当該紛争影響地域の住民は生活再建、生計向上を目指すうえで引き続き多くの困難に直面している。 このような状況に対しJICAは、2012年10月から2014年9月までの計画で派遣中の「紛争影響地域における帰還民を対象とした生計向上」個別専門家を通じて、北部州2県47村(行政村・GN)の帰還民の生計向上を支援してきた。2014年2月末時点で8,000強の世帯に対し、現金収入につながる農作物(ココヤシ、マンゴーなどの果樹、野菜)の栽培や、養鶏の導入を支援しているものの、生活再建を確実なものとし、同地域がより中長期的に持続可能な発展を達成するためには高付加価値な農作物・農産加工品の生産奨励、土地なし農家や寡婦世帯などの脆弱層への配慮、コミュニティーのエンパワーメントに留意した支援が必要である。 こうした背景を受け、2013年8月に農業省より上記専門家の活動拡大を要望する意向が示された。その後スリランカ政府内の調整を経て、北部州同様乾燥気候で、貧困人口が多く州内の経済格差が著しい南部州等も支援対象に含める要請が2014年4月に日本政府に提出され、同年7月に採択された。
上位目標 対象地域住民の生計水準と同国他地域との格差が縮小する。
プロジェクト目標 対象地域において農業収入源が多様化し、住民の生計が向上する。
成果 1.追加的な収入源となる農産物が特定され、対象住民による生産が開始・拡大する。 2.北部紛争影響地の対象行政村(GN)において、紛争により破壊されたヤシ林や畑地が回復

し定住環境が改善する。3.市場性のある農産物加工製品が開発・販売される。
活動 1-1.対象地域毎の農業生産、住民の生活状況を確認し、追加収入源となり得る農産物を選定する。1-2.対象となる行政村と協力して、選定された作物の試験的栽培を行なう。1-3. 住民による小規模灌漑施設(井戸、水路等)の改修を支援する。1-4. 選定作物の普及のため、対象農家向け作物生産技術研修を実施する。
2.紛争で破壊された元ヤシ林にてココヤシの植付を促進する。
3-1.関係地方行政官と協力して、農産物加工品を試作し、改良する。3-2.対象農家向け加工技術研修を実施する。3-3.関係地方行政官等と協力して、住民(グループ)の販路開拓、商業生産に向けた体制強化を支援する。
投入
日本側投入 1) 専門家 - 農業農村開発(短期専門家:シャトル型) - 生計向上支援(北部)(長期専門家) - 生計向上支援(南部)(長期専門家)2) 在外事業強化費ア.ムラティブ県 - 7,000世帯分のヤシおよびマンゴー - 3,000世帯分のパイナップル、パパイヤ、柑橘類等の苗 ※ニーズを見極めたうえで決定 - ヤシの繊維加工製品(玄関マット、箒、帽子)、ココナツ・オイル、ピーナッツ加工、促進のための資機材イ.ワウニア県 - 1,000世帯向け果樹・野菜(玉ねぎ、トウガラシ、豆類等)の種苗ウ.ハンバントータ県、モネラガラ県、バドゥーラ県 - 養蜂農家1,000世帯向け養蜂事業資材 - 2,000世帯分の果樹の苗 - 蜂蜜の貯蔵・販売用資機材 - 小規模灌漑施設改修用資材 ※ニーズを見極めたうえで決定 - 奨励作物の種苗 ※ニーズを見極めたうえで決定エ.現地国内研修(パイナップル栽培、他の果樹や野菜の栽培、農産物加工技術、農産物の販路開拓等)オ.現地アシスタント兼通訳2名(北部および南部担当各1名)、運転手、消耗品等3)携行機材:車両3台4) 本邦C/P研修 ※必要性を見極めたうえで決定
相手国側投入 ・カウンターパートおよびその他支援要員 ・土地、建物、施設の提供 ・プロジェクトに係る活動費・免税措置等
外部条件 ・対象地域における治安環境が悪化しない。・政策に大きな変更が生じない。・大きな気候の変動がない。
実施体制
(1)現地実施体制 Provincial Ministry of Agriculture, Agriculture Instructors, Rural Development Societies
(2)国内支援体制 課題部による助言等
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
・北部東部地域内におけるコミュニティ開発人材育成プロジェクト(技協)2011.3~2014.3・農村経済開発復興事業(PEACE)(有償)2007.3~2013.5・マナー県再定住コミュニティ緊急復旧計画プロジェクト(MANREP)(技協)2010.3~2012.7・ジャフナ県復興開発促進計画プロジェクト(PDP-JAFFNA)(技協)2010.3~2011.10・コミュニティ・アプローチによるマナー県復旧・復興プロジェクト(技術協力プロジェクト)2004.3~2008.3・北東部家畜飼育研修(現地国内研修)2011.3~2013.3・北部州地図更新プロジェクト(緊急開発調査)2010.2~2012.2・貧困緩和マイクロファイナンス事業(円借款)2008.7~2015.6・南部地域村落生活向上プロジェクト(SouthCAP)(技協)2007.3~2011.3
(2)他ドナー等の
援助活動
【世銀】・ENREP(Emergency Northern Recovery Project)2009.12~2013.12、6,500万ドル・Re-Awakening Project 2004.5~2013.12、北部・東部・周辺地域合計7,670万ドル【ADB】・NECORD(North East Community Restoration and Development Project)I&II 2001.10~2013.5、7,630万ドル・Conflict-affected Area Rehabilitation Project 2003.11~2011.12、1億1,650万ドル【UN】・CHAP (Common Humanitarian Action Plan)2010・JPA(Joint Plan of Action)2011及び2012、JNA(Joint Needs Assessment)2013


本部主管案件
個別案件(国別研修(本邦))
2016年11月15日現在
本部/国内機関 :南アジア部
案件概要表
案件名 (和)海上保安強化
(英)Maritime Safety Improvement Training
対象国名 スリランカ
分野課題1 運輸交通-国際交通
分野課題2 ガバナンス-公共安全
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-運輸交通-海運・船舶
プログラム名 プログラム構成外援助重点課題 -開発課題 -
プロジェクトサイト 本邦(国別研修)
協力期間 2012年04月01日 ~ 2016年03月31日
相手国機関名 (和)沿岸警備庁
相手国機関名 (英)Sri Lanka Coast Guard
日本側協力機関名 国土交通省海上保安庁
プロジェクト概要
背景 スリランカは、東南アジアと中東(欧州)を結ぶ重要なシーレーン上に位置する海に囲まれた島国である。現行設置法により文民機関として定義されているスリランカ沿岸警備庁の歴史は浅く2000年に漁業者保護、漁業資源の保護等を目的として、漁業・水産資源省のもと沿岸警備隊が設置され、2007年に法執行機関として改組された。2009年に、沿岸警備法が整備され、沿岸警備隊員は「Peace Officer」と分類される船舶の捕獲等の権限を有する法執行機関としての裏付けが整備され、国防・都市開発省の傘下となった。 2009年に内戦が終結して以降、平和時における海洋救難、海洋資源保護等の観点での強化がこれまで以上に急がれ、防災救難、海賊対策等においてスリランカ海軍、漁業・水産資源省、防災省等の支援を得つつ機能強化に取り組まれている。 また、近年スリランカ漁民の遭難事件、ソマリア海賊のスリランカ付近への侵出に伴うスリランカ漁民人質事件、インド漁民のスリランカ漁業海域での不法操業等のように沿岸警備庁が対応を要する事案が多数発生しており、更なる早急な機能強化が必要とされている。 更には、南アジア地域のコンテナハブ港の役割を果たし多くの船舶の出入りがあるコロンボ港(コンテナ取扱量世界第29位、2010年、横浜港より多い)は、現行の2倍程度の規模への拡張工事が進捗中であり、油流出事故等への対策強化も急がれている。 スリランカは、2004年に我が国主導のもと採択された「アジア海賊対策地域協力協定」のメンバー国(ほかに、ASEAN諸国、中国、韓国、インド、バングラデシュ)であり、同協定は海賊に関する情報共有体制の整備と各国協力網の構築とを通じた海上保安機関間の協力強化を目的としていることから、スリランカは我が国に海上保安能力強化のための人材育成への要請を越した。 なお、ラージャパクサ大統領訪日時(2013年3月)に発表された日本スリランカ共同声明において、日本政府がスリランカの海上保安能力の強化を支援していく旨表明されている。
上位目標 スリランカ沿岸警備庁によりスリランカ周辺海域における安全が確保される。
プロジェクト目標 スリランカ沿岸警備庁における海難救助、海賊対策能力が強化される。
1.海難救助・海上防災を任務とする研修員所属機関において、研修員が作成した行動計画

成果をもとに、救難・防災体制の課題・問題の改善・解決に向けた基本的方向性が整理される。
2.海上犯罪防止のための海上警備や、海上犯罪捜査に関する知識・技術を習得する。
3.周辺国の海上保安ネットワークが強化される。
活動 1.救難・海上防災能力強化 以下(1)~(6)を目的とした研修の実施(1)自国の救難・防災体制の現状及び課題・問題が整理される。(2)海上における捜索救助に関する国際的枠組み、知識及び技術について課題が整理される。(3)防災に関する国際的枠組み、知識、油及び有害危険物質の防除手法について課題が整理される。(4)海上保安担当官庁の取組み、体制について課題が整理される。(5)自国の救難・防災体制の課題・問題を解決するための行動計画が策定される。(6)アクションプランに基づいた活動が実施される。
2.海上犯罪防止 以下(1)~(4)を目的とした研修の実施(1)国際法制度の理解(2)国際組織犯罪の現況と対策の理解(3)海上取締実務に関する知識・技能の習得(4)海上犯罪取締指揮・監督に関する知識・技能の習得
投入
日本側投入 国別研修の実施。(①海上保安実務者のための救難・環境防災コース、②アジア・ソマリア周辺犯罪取り締まり(海賊対策)への国別研修枠による参加)
相手国側投入 特になし。
外部条件 研修参加者が継続的に沿岸警備隊に勤務する。
実施体制
(2)国内支援体制 JICA九州、JICA横浜、海上保安庁
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
1)我が国の援助活動2)他ドナー等の援助活動

本部主管案件
技術協力プロジェクト
2019年02月20日現在
本部/国内機関 :社会基盤・平和構築部
案件概要表
案件名 (和)橋梁維持管理能力向上プロジェクト
(英)The Project for Capacity Development on Bridge Management
対象国名 スリランカ
分野課題1 運輸交通-全国交通
分野課題2
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-運輸交通-道路
プログラム名 運輸ネットワーク強化プログラム援助重点課題 経済成長の促進開発課題 成長のための経済基盤整備
署名日(実施合意) 2014年09月30日
協力期間 2015年02月06日 ~ 2018年02月23日
相手国機関名 (和)道路開発庁 港湾道路省
相手国機関名 (英)Road Development Authority Ministry of Ports and Highways
プロジェクト概要
背景 スリランカには全国の国道に約4,800の橋梁があり、道路開発庁(RDA: Road Development Authority)の道路維持管理部(MM: Maintenance & Management Division)が、技術部(ES: Engineering Services Division)の技術的な支援を受けながら、簡易な点検や清掃、補修工事等、一定の橋梁維持管理業務を行っている。 一方で橋梁の状態に着目すると、RDAによると2010年時点で橋歴50年を超える橋梁が全体の42%を占め経年劣化・損傷が進行しつつあり、さらに2020年には橋歴50年以上の橋梁の占める割合は60%にまで増加する見込みである。我が国をはじめとする先進国のこれまでの知見から、橋梁は建設後50年を経過すると劣化が加速的に進行し維持管理予算が増大する傾向にあることが判明しており、スリランカにおいても効果的な維持管理方法を検討・実施する必要がある。また、橋梁維持管理政策を実施するための枠組みとして、維持管理の組織体制・予算配分計画・技術力の組織的な向上が必要であり、分析を行うための橋梁維持管理データベースの改善、点検・補修工事等の橋梁維持管理実務の手引きとなるマニュアル類の整備、職員の技術力向上が求められている。
上位目標 橋梁維持管理サイクルに則り、スリランカ全土でRDAが橋梁の維持管理業務を計画的に行えるようになる。
プロジェクト目標 RDAの橋梁維持管理組織能力が向上する
成果 1.橋梁維持管理政策が作成される2.RDA本部及び地方事務所(PD、CE、EE)の橋梁維持管理組織体制が再構築される3.橋梁点検及び診断マニュアルが改訂される4.橋梁マネジメントシステム(BMS)が構築される5.セミナーやOJTを通じて、RDA本部及び地方事務所職員(モデル州)の技術的な基礎知識が深まる
活動 活動1-1.既存の橋梁維持管理がレビューされ、分析される活動1-2.橋梁維持管理政策案が起草される活動1-3.橋梁維持管理政策がRDA本部及び地方事務所で共有される活動1-4.橋梁維持管理政策に基づき、モデル州において点検と診断が実施された橋梁を対象

に、橋梁維持管理計画を策定する
活動2-1.RDA本部及び地方事務所の維持管理に関する役割と責任がレビューされ、議論した上で役割・責任案が起案される活動2-2.RDA本部と地方事務所の維持管理手順がレビューされ、議論された上で維持管理手順案が起案される活動2-3.橋梁維持管理に必要な組織図(役割・責任・権限含む)、人員配置計画、その他必要な資機材の見積もりを作成する。
活動3-1.既存の橋梁維持管理マニュアルがレビューされ、課題が整理される活動3-2.橋梁点検及び診断マニュアル改訂案が起草される活動3-3.BM&AUにより、RDA本部及び地方事務所職員に対し、橋梁点検及び診断マニュアルの説明が行われる活動3-4.橋梁点検及び診断マニュアルが最終化され、関係部局に配布される
活動4-1.既存のデータベースがレビューされ、分析される活動4-2.BMSのスペックに関する議論がされた上で、橋梁マネジメントシステムが整備される活動4-3.BM&AUにより、モデル州の橋梁に関する必要なデータがBMSに入力される
活動5-1.RDA本部及び地方事務所(モデル州)の職員に対し、理論セミナーが実施される活動5-2.RDA本部及び地方事務所(モデル州)の職員に対し、実地セミナーが実施される活動5-3.モデル州において、橋梁点検及び診断に関するOJTが実施される活動5-4.全国の人材育成計画が作成される

本部主管案件
有償技術支援-有償専門家
2017年03月29日現在
本部/国内機関 :社会基盤・平和構築部
案件概要表
案件名 (和)コロンボ都市交通改善アドバイザー
(英)Advisor for the Improvement of Metro Colombo Urban Transport Network
対象国名 スリランカ
分野課題1 運輸交通-都市交通
分野課題2
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-運輸交通-都市交通
プログラム名 運輸ネットワーク強化プログラム援助重点課題 経済成長の促進開発課題 成長のための経済基盤整備
プロジェクトサイト コロンボ都市圏およびその近郊
協力期間 2013年02月28日 ~ 2016年02月27日
相手国機関名 (和)運輸省
相手国機関名 (英)Ministry of Transport
プロジェクト概要
背景 スリランカ国(以下、「ス」国)の西部に位置するコロンボ市(面積37.3km2、人口64万人)は、「ス」国の政治経済における中心である。コロンボ市を含む西部州(面積3,709km2、人口540万人)で、コロンボ市を中心としたコロンボ都市圏が形成されている。 JICAは2006年に同都市圏を対象に「大コロンボ圏都市交通開発計画調査」を実施した。これは多くの関係機関が過去に実施した既存の計画を統合した上で再構成や必要な見直しを行い、計画づくりで終わっていたものに対して優先順位を与え、その実施促進に重点を置いた計画づくりが行われた。しかし、実施体制が構築されず事業化も進んでいない。 現地ではダイナミックな都市開発が進み、多岐にわたる都市交通インフラの関係者の調整、長期にわたる膨大な投資の必要性などから、最新の、信頼性の高いデータに基づく、科学的根拠のある計画づくりが必要とされている。その計画が政策決定者の的確な意思決定ツールとして活用され、関係者の合意形成ツールとしても活用されることが重要である。 このような状況を背景に、「ス」国政府は過密するコロンボ都市圏を対象とした公共交通政策を柱とする都市交通計画の策定、及び最も望ましい公共交通計画を策定するため、「コロンボ都市交通調査プロジェクト」(以下、「JICAプロジェクト」)を我が国に対して要請し、日本政府による採択を受けてJICAが2012年8月から同プロジェクトを実施中である。 一方、円滑な公共交通機関の導入を進めていくためには他の交通モード(バス、タクシー、リキシャ―等)との調整、各交通モードを管轄する関係省庁・機関との調整、ひいては関係機関を支援する各ドナーとの援助調整が不可欠である。JICAプロジェクトのカウンターパート(C/P)機関であるスリランカ運輸省(MOT)にはかかる新規公共交通機関の導入にかかる経験が無いため、MOTスタッフの能力向上に資するアドバイザー(専門家)派遣を「ス」国政府は我が国に対して要請した。同アドバイザーには以下の役割が期待されている。・MOTのC/Pメンバーとの協働によるJICAコロンボ都市交通改善プログラムの形成と促進。・MOTのC/Pメンバーの他交通モード関係者との調整能力向上支援。・軌道系公共交通機関整備を実施するためのプロジェクト管理ユニットの設立支援。
上位目標 コロンボ都市圏の新しい公共交通機関の導入が円滑に進む。
プロジェクト目標 1. MOTのC/Pとの協働によるJICA「コロンボ都市交通改善プログラム」の形成と促進。2. 他交通モードを管轄する関係省庁・機関との必要な調整を行うためのMOTのC/Pの能力向上。

3. 軌道系公共交通機関の整備を進めるためのプロジェクト管理ユニットの設立支援。
成果 1. JICAプロジェクトの成果も踏まえたJICA「コロンボ都市交通改善プログラム」が策定される。2. 他交通モードを管轄する関係省庁・機関との必要な調整に一定の役割を果たすためのMOTのC/Pの能力向上が図られる。
活動 1. MOTのC/Pとの協働によるJICA「コロンボ都市交通改善プログラム」への理解促進を図る。2. MOTのC/PとJICAプロジェクトのステアリング・コミッティーおよびテクニカル・コミッティーのメンバーとの関係構築を支援する。3. JICAプロジェクトのコンサルタント・チームとMOTのC/Pとの連携を支援する。4. MOTのC/Pによる市民への啓発を行うワークショップの開催を支援する。5. MOTのC/PがJICAによる「軌道系交通手段導入事業」(円借款)の案件形成のためのファクト・ファインディングおよびアプレイザルミッションの受け入れ準備を支援する。
投入
日本側投入 ・専門家派遣(24か月)・現地活動費
相手国側投入 ・カウンターパート・執務環境
実施体制
(1)現地実施体制 1. 運輸省2. JICA「コロンボ都市交通調査プロジェクト」のステアリング・コミッティーおよびテクニカル・コミッティーを形成する関係省庁・機関
(2)国内支援体制 1. JICA経済基盤開発部2. 国土交通省都市局
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
・「大コロンボ圏都市交通開発計画調査」(2006)(当時存在していた交通問題を解消するための短期改善策提言)・「大コロンボ圏都市交通整備事業」(円借款)(2007- )(コロンボ都市圏内を通過する有料の環状道路)・「大コロンボ圏都市交通整備事業フェーズ2(Ⅰ)」(円借款)(2008- )・「南部ハイウェイ建設事業」(円借款)(2008- )(西部州南部のゴール県からコロンボ県の中央部までを貫通する有料高速道路)
(2)他ドナー等の
援助活動
・【世界銀行】 「Colombo Urban Transport Project」(1999) 「Metro Colombo Urban Development Project」(2012)(運河の改修等の排水関連、被害を受ける道路の改修)・【アジア開発銀行】 「Multimodal Transport」(南部高速道路からコロンボへ向かう国道の拡幅)・【中国】 「コロンボ - カトナヤケ間高速道路建設事業」(2013年完工予定)

本部主管案件
有償技術支援-附帯プロ(開発計画調査型)
2015年04月28日現在
本部/国内機関 :社会基盤・平和構築部
案件概要表
案件名 (和)コロンボ都市交通調査プロジェクト
(英)Urban Transport System Development Project for Colombo Metropolitan Region
and Suburbs
対象国名 スリランカ
分野課題1 運輸交通-都市交通
分野課題2
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-運輸交通-都市交通
プログラム名 運輸ネットワーク強化プログラム援助重点課題 経済成長の促進開発課題 成長のための経済基盤整備
プロジェクトサイト コロンボ圏
協力期間 2012年08月20日 ~ 2014年09月30日
相手国機関名 (和)運輸省
相手国機関名 (英)Ministry of Transport
プロジェクト概要
背景 スリランカ国(以下、「ス」国)の西部に位置するコロンボ市(面積37.3km2、人口64万人)は、「ス」国の政治経済における中心である。コロンボ市を含む西部州(面積3709km2、人口540万人)の中で、コロンボ市を中心をとしたコロンボ都市圏が形成されている。 コロンボ都市圏には交通が集中しており、またコロンボ都市圏内外の交通は道路網への依存が高く、自動車登録台数の急増(2002~2010年の間に倍増)により通行車数も増えているが、西側が海に面しているため陸上交通網の開発に制約があること、植民地時代からコロンボ港を起点として整備されてきた道路網が環状道路未整備のまま放射状に伸びていることなど、都市圏全体のネットワークが十分に整備されていない。そのため、特に朝夕の通勤通学時間帯をピークに激しい交通渋滞が生じている。これを解消するため「ス」国政府はコロンボ都市圏において、大量または中量輸送の公共交通機関の導入を含む、総合的な都市交通政策を必要としている。 かかる総合的な都市交通計画策定にあたっては、確かな交通実態調査に基づく必要があるが、交通実態調査を伴った都市交通計画は1999年に世界銀行の支援で策定されて以降、策定されていない。2000年代に入り、自動車交通量の増加や、人口流入による都市圏拡大、都市機能移転などが進行していることも踏まえ、交通実態調査を再度実施し、新たに都市交通計画を策定することが必要となっている。 このような状況を背景に、「ス」国政府は、過密するコロンボ都市圏を対象とした公共交通政策を柱とする都市交通計画の策定、及びもっとも望ましい公共交通機関にかかる計画を策定するため、「コロンボ都市交通調査プロジェクト」(以下「本プロジェクト」とする)を我が国に要請した。
上位目標 コロンボ都市圏の慢性的な首都圏の交通渋滞解消することにより物流や人の流れを促進し、より一層の経済成長に貢献する。
プロジェクト目標 ・2035年を目標年次とするコロンボ総合都市交通計画が作成される。・最優先プロジェクトにかかるプレ・フィージビリティスタディが実施される。
成果 ・2035年を目標年次とするコロンボ総合都市交通計画の策定・最優先プロジェクトにかかるプレ・フィージビリティスタディの実施

活動 1)現状分析及びレビュー(ア)交通関連法令、政策、既存の計画やプロジェクトのレビュー(イ)既存情報・データの確認、レビュー(ウ)実施機関、組織の分析(エ)道路及び交通サービスのインベントリー調査の実施(オ)経済状況・社会状況・自然状況の確認(カ)環境社会配慮にかかる基礎情報収集(キ)交通実態調査の計画(ク)交通実態調査の実施(ケ)データ解析(コ)都市交通データベースの整備(サ)都市交通に関する問題の特定2)総合都市交通計画の策定(ア)社会経済フレームワークの設定(イ)交通モデル作成と将来交通需要予測(ウ)総合都市交通戦略の設定(エ)総合都市交通政策の作成(オ)戦略的環境アセスメントの考え方に基づく、最優先プロジェクト選定のための環境社会配慮影響も含めた代替案の比較検討(カ)最優先プロジェクトの選定(キ)公共交通計画の策定(ク)交通管理計画の策定(ケ)道路整備計画の策定(コ)総合都市交通計画の策定(サ)事業計画の策定(シ)事業計画の評価(ス)短期アクションプランの策定(セ)優先プロジェクトの選定(ソ)広報用ビデオの作成3)最優先プロジェクトに対するプレ・フィージビリティスタディ調査の実施(ア)概略設計方針の作成(イ)代替案の作成及び比較検討(ウ)補足調査の実施(測量、土質調査、自然条件調査)(エ)SP調査(モード変換に対する意向調査)(オ)概略設計及び概略積算(カ)環境社会配慮調査(最優先プロジェクトの初期環境調査並びに環境社会影響評価及び住民移転計画作成のためのTOR作成)(キ)経済・財務分析(ク)実施計画の作成4)提言のとりまとめ(ア)全体的な結果、留意事項等を含む、必要な提言の取りまとめ(イ)実施のための組織体制の提案
投入
日本側投入 コンサルタント(業務実施契約)1)総括/都市交通2)副総括/公共交通計画3)公共交通政策4)都市計画/社会経済フレーム5)土地利用計画 6)交通需要予測 7)交通調査/解析 8)交通調査29)交通調査310)交通調査411)交通調査512)交通調査補助13)交通調査補助214)画像解析プログラム15)画像解析パラメータ16)ビデオにおる交通量観測17)道路計画 18)交通管理計画/制度計画19)ターミナル交通調査20)ターミナル交通需要予測21)統合交通ターミナル施設計画(鉄道)22)統合交通ターミナル施設計画(バス)23)マルチモーダルセンター24)駅前広場/パークアンドライド計画25)統合交通ターミナル意匠計画26)BRT計画27)経済・財務分析 28)組織制度/能力強化計画 29)環境社会配慮/戦略的環境アセスメント 30)事業実施計画31)土木/施設計画 32)運転/輸送・運行計画 33)信号/通信計画

34)車両計画 35)配電/機械計画 36)事業実施/運営・維持管理計画 37)施工計画/積算 38)交通調査データ整備/業務調整
その他 研修員受入れ・研修員受入れ(国別研修、課題別研修)
相手国側投入 1.ステアリングコミッティ(以下、「S/C」とする)の設置2.業務に関する関連資料および保有資器材の貸与3.カウンターパートの配置4.オフィススペースの提供(予定)
外部条件 ・政変による大統領交代(現大統領の任期は2016年まで)
実施体制
(1)現地実施体制 運輸省(MOT)
(2)国内支援体制 特になし。
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
「大コロンボ圏都市交通開発計画調査」2006(当時存在していた交通問題を解消するための短期改善策提言)「大コロンボ圏都市交通整備計画(円借款)」2007-(コロンボ都市圏内を通過する有料の環状道路)「南部ハイウェイ建設計画(円借款)」2001-(西部州南部のゴール県からコロンボ県の中央部までを貫通する有料高速道路)
(2)他ドナー等の
援助活動
【世界銀行】「Metro Colombo Urban Development Project」2012-2017(運河の改修等の排水関連、被害を受ける道路の改修)【アジア開発銀行】「Multimodal Transport」(南部高速道路からコロンボへ向かう国道の拡幅)【中国】コロンボ‐カトナヤケ間高速道路建設事業(2013年完工予定)

本部主管案件
個別案件(専門家)
2019年03月16日現在
本部/国内機関 :社会基盤・平和構築部
案件概要表
案件名 (和)海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー
(英)Advisor Services for Maritime Disaster Measures and Marine Environment
Protection
対象国名 スリランカ
分野課題1 運輸交通-(旧)その他運輸交通
分野課題2
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-運輸交通-運輸交通一般
プログラム名 気候変動・防災対策プログラム援助重点課題 脆弱性の軽減開発課題 脆弱性軽減のための社会基盤整備
協力期間 2014年09月01日 ~ 2017年03月31日
相手国機関名 (和)スリランカ沿岸警備庁
相手国機関名 (英)Sri Lanka Coast Guard
プロジェクト概要
背景 スリランカはインド洋上の島国であり、マラッカ海峡を経由して中東地域を結ぶ我が国にとっても重要なシーレーン上に位置している。国土面積は6.5万km2と北海道の約8割ほどであるが、1,340kmに及ぶ海岸線と2.1万km2の領海、51.7万km2の排他的経済水域を有しており、海運、漁業、観光等の海洋に関連する産業がGDPの概ね5割を占める。このため、これら海洋産業への負のリスク対策を行うことは、観光促進、水産資源の保護等の観点から海上保安能力の強化は重要である。2013年3月に行われた日・スリランカ首脳会談の共同声明においても海上保安分野の協力の一つとして「沿岸警備庁への研修」が提案され、インド洋海域の治安の安定化の重要性が共有された。その後のスリランカ側との協議で海洋汚染対策、特に油防除に関するニーズがあることが確認された。2014年7月にJICAはスリランカ国に調査団を派遣し、スリランカ沿岸警備庁(Sri Lanka Coast Guard:SLCG)と具体的な計画について協議を行い、油防除に係る短期専門家をスリランカに派遣すること、同専門家の指導によりスリランカにて現地研修を行うこと、研修に必要な機材を調達することなどの基本方針を確認した。本件はこの基本方針を受けて短期専門家の要請があったものである。
上位目標 海上防災対策及び海洋環境保護に係るSLCGの能力が向上する。
プロジェクト目標 海上防災対策及び海洋環境保護に係るSLCGの能力が向上する。
成果 1.SLCG職員が海上における油流出に対する国際的な枠組み及び課題を理解する。2.SLCG職員が海上防災に係る知識を習得し、油などの有害物質に係る対処方法の技術が向上する。3.SLCG職員の海洋環境保護に係る技術が向上する。4.SLCG職員が習得した技術を関連機関に発表し、海上防災及び海洋環境保護に係る関係機関の意識が高まる。
活動 1.海上防災対策及び海洋環境保護に係るSLCGの現在の体制及び運用方法をレビューし、その改善点を推奨する。2.油流出事故や油拡散に係る国際的な枠組み及び課題を紹介し、その対処方法について技

術指導を行う。具体的な内容は以下のとおり。 - 日本の海上保安庁及び機動防除隊組織・業務に係る講義 - 日本の海上防災対策及び海洋環境保護政策に係る講義 - 油防除理論(油の性状、油流出事故対応の流れ、油防除手法など)に係る講義 - 油防除に係る陸上実技訓練(油防除資機材確認、保守管理、オイルフェンス展張、油回収、回収油一時貯油、流出油分散、汚染拡大防止措置など) - 油防除に係る海上実技訓練(流出油拡散防止、流出油回収、回収油一時貯油、汚染拡大防止措置、流出油分散など)3.海上防災対策及び海洋環境保護の啓発活動に係る助言を行う。4.SLCGの運営に係る助言を行う。

本部主管案件
個別案件(国別研修(本邦))
2016年05月24日現在
本部/国内機関 :社会基盤・平和構築部
案件概要表
案件名 (和)海上保安強化
(英)Martime Corporation
対象国名 スリランカ
分野課題1 運輸交通-(旧)その他運輸交通
分野課題2
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-運輸交通-運輸交通一般
プログラム名 プログラム構成外援助重点課題 -開発課題 -
協力期間 2013年11月01日 ~ 2016年03月31日
相手国機関名 (和)スリランカ沿岸警備庁
相手国機関名 (英)Sri LankaCoast Guard
日本側協力機関名 海上保安庁
プロジェクト概要
背景 スリランカは、東南アジアと中東を結ぶ重要なシーレーン上に浮かぶ島国である。スリランカにおける沿岸警備庁整備の歴史は浅く、2000年に漁業者保護を主目的として漁業・水産資源省傘下に設置され、その後文民機関として国防・都市開発省下に移設された。特に内戦終結以降は、インド洋へのソマリア海賊の侵出対策強化、平和時の法執行能力の強化等が強く求められている。加えて、コロンボ港(世界第28位のコンテナ取扱量)拡張や、新設のハンバントゥータ港等の港湾開発・海運分野の発展が進んでおり、現状実施できていない国際基準に基づく外国船籍の船舶検査体制を整えることも急務となっている。 また、排他的経済水域や捜索救難区をカバーするために、スリランカ政府は今後3年間にかけて、5つの地域管区を設け海上保安施設及び研修施設を設立する計画を有しており、人材、装備の能力向上が一層必要となっている。
上位目標 ※詳細は1年目の研修時に決定。(1年目の研修時に幹部クラスの職員を対象として研修を実施し、2年目、3年目の研修内容について、スリランカ沿岸警備庁及び海上保安庁との間で協議する予定のため。)
・スリランカ沿岸警備庁が、自国への外国船籍入港時に国際基準に合致した法執行を実施できるようになる。・排他的経済水域及び捜索所管範囲内において、適切に捜索救難活動を実施できるようになる。
プロジェクト目標 スリランカ沿岸警備庁の遭難救難活動能力及び法執行能力が強化される。
成果 ①外国船籍船舶入港時の検査実施(ポートステートコントロール)を目的とした国際基準での船舶検査の履行及び法執行能力が強化される②捜索救難活動能力が強化される
活動 国別研修(約6人/年 × 3回)の実施。
投入
国別研修 年間約6名×3回

日本側投入
相手国側投入 カウンターパート 18名程度(約6名/年×3年間)
外部条件 なし
実施体制
(2)国内支援体制 海上保安庁
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
課題別研修「アジア・ソマリア周辺海域 海上犯罪取締り」(2012年度)課題別研修「海上保安実務者のための救難・環境防災コース」(2012年度)
(2)他ドナー等の
援助活動
特になし

本部主管案件
有償技術支援-附帯プロ(開発計画調査型)
2018年04月02日現在
本部/国内機関 :産業開発・公共政策部
案件概要表
案件名 (和)ピーク需要対応型電源最適化計画調査【有償勘定技術支援】
(英)The Project for Development Planning on Optimal Power Generation for Peak
Power Demand in Sri Lanka
対象国名 スリランカ
分野課題1 資源・エネルギー-エネルギー供給
分野課題2
分野課題3
分野分類 エネルギー-エネルギー-電力
プログラム名 電力事情改善プログラム援助重点課題 経済成長の促進開発課題 成長のための経済基盤整備
協力期間 2013年03月24日 ~ 2014年11月30日
相手国機関名 (和)セイロン電力庁
相手国機関名 (英)Ceylon Electricity Board (CEB)
プロジェクト概要
背景 (1)現状及び問題点
スリランカ経済は、世界金融危機の影響により2009年のGDP成長率は年率3.5%程度まで減少したものの、2009年後半以降は、紛争終結に伴う復興需要による鉱工業及び運輸・通信業の成長や観光業の回復が見られ8%強の成長を達成し、今後も伸びが見込まれている。 スリランカの人口は主要な港湾や国際空港が位置し、また、政治経済の中心地であるコロンボを含む西部州(大コロンボ圏)に全人口の約30%が集中している。こうした社会・経済構造から、特に大コロンボ圏における電力需要の集中への対応が喫緊の課題となっている。 最近の電力需要は堅調な経済状況を背景に、ピーク需要が年率約6.3%、販売電力量ベースで同約6.5%のペースで増加している。電力需要の伸びを見据えつつ、2010年に策定された開発政策「マヒンダ・チンタナ(2010-2016)」では、今後安定した電力供給の確立を主要な目標としている。 政府の開発政策を踏まえ、電力セクターの主管官庁であるセイロン電力庁(Ceylon Electricity Board、以下、「CEB」)では、長期電源拡張計画(2011-2025)を策定し、電力需要予測と長期電源開発計画を示している。かつてスリランカでは国産エネルギーを有効活用すべく水力中心の電源開発が進められ、1990年代半ばには発電電力量の90%を水力が占めていた。一方、水力発電は降水量に左右されやすくベース電源として不安定であることから、2000年以降は火力を主体とする電源構成への転換が図られてきた。2010年において、水力と火力の発電量の割合は均衡していたものの(水力46%、火力47%、再生可能エネルギー7%)、2011年は極度の雨不足により、水力発電が約20%にまで落ち込み、火力発電が主力となった。CEBは今後、安定した電力供給のため、燃料コストが低く安定的な発電が可能な石炭火力をベース電源とし、水力はピーク対応に移行させるほか、液化天然ガス(LNG)、及び風力や太陽光等の再生可能エネルギーを含むバランスのとれた電源構成を模索している。現在、ベース電源については開発計画の事業化が進みつつある一方、ピーク対応電源の開発計画についてはこれから検討が必要な状況にある。 CEBでは特に大コロンボ圏におけるピーク需要対応型の電源開発の必要性が高まるなか、CEBは既存の水力発電所のみでは将来のピーク需要への対応が不足するものと予想している。本調査では、スリランカにおける電力需要の特性、既存の電源構成等をふまえ、最適なピーク需要対応の観点から、揚水発電の導入や一般水力の運用による対応の可能性等、電源計画並びに最適な運用の検討を行う。さらに検討結果をふまえて、揚水発電等の本邦企業

に優位性のある技術が活用された新規円借款の案件形成につなげることを想定したものである。
(2)相手国政府国家政策上の位置づけ
「マヒンダ・チンタナ(2010-2016)」では、安定した電力供給を国全体に供給することを目標としており、そのために持続可能な電源開発、電力サービスへのアクセスの改善、エネルギーの効率的な活用、電力料金体制の改善に注力するとしている。本調査は、特にエネルギーの安定供給の向上に資する。
上位目標 調査結果を踏まえ、スリランカ国内電力システムにおけるピーク対応電源導入(例えば揚水発電)に係る技術面、経済面、環境社会配慮面を考慮した実施可能性調査等が行われる。
プロジェクト目標 スリランカ国において、ピーク対応型電源最適化計画を作成することにより、適切な電源開発の策定に寄与する。
成果 (a)ピーク対応型電源最適化計画が策定される。 (b)ピーク対応型電源計画候補(揚水発電含む)を選定し、開発優先順位案を提案する。
活動 調査を以下の3段階のステージ分けのうえ実施する。 Stage 1: 初期評価ステージ Stage 2: ピーク対応型電源最適化計画策定ステージ Stage 3: ピーク対応型電源計画候補(揚水発電含む)調査ステージ
<Stage 1> 初期評価ステージ(a) ピーク対応電源の必要性の確認及び代替電源の比較 a 関連情報収集(エネルギー政策、経済政策、電力政策) -エネルギー政策、経済政策、産業開発政策、電力政策 -電力需要予測、系統計画、電力供給計画、電源開発計画の確認 -再生可能エネルギー開発ポテンシャル(水力、風力、ソーラー、バイオマス) -電源開発の課題(中断や遅延事例及びその理由) -既設発電所の運転状況 -水力(揚水)開発計画の基礎データの収集(包蔵水力、水文、地形、地質) -水力開発における環境関係情報(社会環境、自然生態系、地下構造物の環境影響) b ピーク対応電源の代替電源比較(SEAの考え方に基づいた環境社会影響も含めた代替案の比較検討)(b) 系統調査
<Stage 2> ピーク対応型電源最適化計画策定ステージ(a) 長期電力需給計画策定作業の改善 a ピーク対応電源として、揚水発電の導入、揚水発電以外の考慮、及びその運用改善・新規導入による経済性検討 b ピーク対応電源の組合せによるピーク需要対応のための電源開発シナリオの検討(揚水発電導入の妥当性検討) c 候補地点調査(地図調査及び現地踏査)(b) ピーク電力需給のシナリオ設定及び最適化検討 a 系統安定運用のためのシナリオ検討及び最適化検討 b 自然環境や地域社会に配慮したピーク対応型電源開発マスタープランの提案
<Stage 3> ピーク対応型電源計画候補(揚水発電含む)調査ステージ(a) 揚水開発ポテンシャル調査 a ピーク対応型電源のスクリーニングのクライテリアの検討(技術・経済・環境面の評価基準、関連送電線)及び代替電源の比較検討、SEAの実施 b 揚水開発に関する制度、政策面の課題抽出 c 揚水開発の位置づけ整理、整合性確認(b) ピーク対応型電源(揚水発電所)開発計画策定 a 長期電源開発計画、送電計画との整合性の検討 b 有望計画地点の開発優先順位付け並びに開発有望地点の絞込み c 優先プロジェクトの環境社会影響項目のスコーピング
日本側投入 (a)コンサルタント(9分野/11人)(約54M/M) a 総括/電源開発計画 (現地:3.9M/M、国内:1.7M/M) b 水力開発計画(水力土木A)(現地:3.9M/M、国内:1.7M/M) c 水力開発計画(水力土木B)(現地:3.5M/M、国内:1.5M/M) d 地質 (現地:2.6M/M、国内:1.5M/M) e 水文・気象解析 (現地:2.8M/M、国内:1.5M/M) f 系統計画(A) (現地:3.3M/M、国内:1.6M/M) g 系統計画(B) (現地:3.3M/M、国内:1.6M/M) h 電気設備 (現地:2.4M/M、国内:1.5M/M) i 経済財務分析 (現地:3.1M/M、国内:1.6M/M) j 環境社会配慮(自然環境) (現地:3.7M/M、国内:1.7M/M) k 環境社会配慮(社会環境) (現地:3.7M/M、国内:1.7M/M)
(b)その他 研修員受入れ 本邦研修(2週間程度)及び現地セミナー(1日程度)
外部条件 (1)協力相手国内の事情 (a) 政策的要因:スリランカ電力エネルギー省(Ministry of Power and Energy、以下、

「MOPE」)及びCEBによるピーク対応電源導入への方針が継続する。 (b) 経済的要因:持続的経済発展に基づくピーク需要の伸びが継続する。 (c) 社会的要因:治安が悪化しない。 (d) 自然条件:水力発電所(揚水発電所)に適する条件(自然環境、水文、地質等)の候補地を見出すことができる。
(2)関連プロジェクトの遅れ 特に無し
実施体制
(1)現地実施体制 1)セイロン電力庁(CEB) 本調査の実施・総括責任者2)スリランカ電力・エネルギー省(MOPE) 本調査の管理・監督 政策への反映検討3)JICA専門家 本調査に必要な技術的知見をCEBに助言4)合同委員会(JCC) MOPE、CEB、JICAスリランカ事務所、JICA本部の幹部から成る委員会。組織間の協力を促進するために、必要な場合に開催。
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
・開発調査「水力発電最適化計画調査」(2002-2004年)・開発調査「電力セクターマスタープラン調査」(2004-2006年)・開発調査「ヴィクトリア水力発電所増設F/S調査」(2008-2009年)・有償資金協力「電源多様化促進事業(E/S)」(2008-2012年)・有償資金協力「アッパーコトマレ水力発電所建設事業(Ⅱ)」(2002-2013年)・有償資金協力「ワウニア・キリノッチ送電線修復事業(Ⅱ)」(2005-2012年)・有償資金協力「ハバラナ・ヴェヤンゴダ送電線建設事業」(2011-)
(2)他ドナー等の
援助活動
スリランカの電力・エネルギーセクター開発における主なドナーは、アジア開発銀行(ADB)、中国、イラン、JICAであり、これら4ドナーの援助額が、電力・エネルギーセクターへの援助総額に占める割合は約9割と大半を占めている。 中でもADBは、送配電網拡充に積極的である他、発電コスト削減や地方電化、省エネルギーによる電力効率化も重視する等、JICAの関心分野と重複する部分があるが、ピーク対応を目的とした電源開発計画についての支援は特段されていない。 一方、特に石炭火力を中心とする大規模電源開発への新興ドナーの参入が活発である。ノロッチョライ石炭火力(計900MW)については中国(エンジニアリング・サービスは1994年円借款により実施)、トリンコマリー石炭火力(計1,000MW)についてはCEBとインド企業の合弁事業体により実施されている。また、新興ドナーである韓国も電力分野での協力を表明している。

本部主管案件
個別案件(専門家)
2019年02月20日現在
本部/国内機関 :産業開発・公共政策部
案件概要表
案件名 (和)国家計画局能力強化支援アドバイザー
(英)Planning and Implementation Support Advisor for Ministry of Finance and Planning
対象国名 スリランカ
分野課題1 経済政策-その他経済政策
分野課題2
分野課題3
分野分類 計画・行政-行政-財政・金融
プログラム名 プログラム構成外援助重点課題 -開発課題 -
プロジェクトサイト スリランカ コロンボ
協力期間 2014年05月16日 ~ 2016年09月17日
相手国機関名 (和)財務計画省国家計画局及び財務総合学院
相手国機関名 (英)Ministry of Finance and Planning Department of National Planning and Academy of
Financial Studies
プロジェクト概要
背景 (1)スリランカでは、2009年の紛争終結後、急激な経済成長を遂げ、中所得国入りを果たしたところであり、2010年に発表された国家開発政策「マヒンダ構想」によれば、持続的な経済成長の維持、所得倍増、「輸出・観光・環境立国」として産業振興を図ることによって、中所得国からさらに中進国入りを目指すとしている。一方、スリランカ国内には、構造的かつ継続的な巨額の貿易収支赤字や地域内の経済格差等が存在しており、今後もスリランカ国民の生活の安定と国内の均衡を保った形での経済成長を続けるためには、財政の健全化を進めるとともに、諸般の政策課題に的確に応える経済・財政政策を推進していく必要がある。
(2)スリランカ財務計画省は、今後、スリランカが中進国入りを果たす上で、的確な経済・財政政策運営及び国家開発計画と整合性がとれた質の高い開発計画を推進していく為の組織・能力強化が不可欠との問題意識を持っている。同省国家計画局(Department of National Planning、NPD)は、スリランカの開発計画策定・承認に携わる中枢の組織であり、NPD職員の能力向上を通した国家レベルの開発計画・各施策の質の改善、将来事業の企画立案・審査・実施能力強化が求められている。
(3)また、2013年1月、財務計画省は財務総合学院(Academy of Financial Studies、AFS)を設立し、経済政策立案のためのテクノクラートを養成するための重要な研修機関として新たに位置付けると共に、今後南アジアにおける研究拠点として機能することを目指している。今後、質の高い財務官僚育成に向けてAFSの機能強化が求められる中、AFSの中期活動計画の策定等が課題として挙げられている。
(4)こうした状況の下、今般、スリランカ財務計画省より日本に対し、NPDの能力強化及びAFSへの技術支援の要請があり、長期専門家を派遣することとなった。
上位目標 スリランカにおいて、国レベルの開発計画・各施策の質の改善、将来事業の企画立案・審査・実施、人材育成に関する取り組みが強化される。
プロジェクト目標 国レベルの開発計画・各施策の質の改善、将来事業の企画立案・審査・実施、政策策定能力等の観点から質の高い人材の裾野が拡充される。

成果 (1) NPD職員等の以下に関する能力が向上する。・NPDの開発計画・各施策の策定及びレビュー方法・実務・NPD及び関係部局の開発事業の審査及びモニタリング手法
(2) AFSの機能が以下のとおり強化される・AFSの中期活動計画が策定される・シニア・幹部候補向けの研修プログラムが計画される。・AFSの将来に向けたビジョン(AFSが目指す将来像、機能等)が明確化される。
活動 以下に関する助言等を行う。(1) NPDの開発計画・各施策の策定及びレビュー方法・実務(例:日常業務への助言、開発成果の効果的マネジメント手法の提供、開発計画、各種施策の策定プロセスにおける関係機関との調整。)(2) NPD及び関係部局の開発事業の審査及びモニタリング手法。(例:各種開発施策の審査プロセスにおける関連省庁及びドナーとの調整に関する助言。)(3) NPD局長に対する国家計画局能力強化支援アドバイザーとしてNPD職員の能力向上(例:投資計画、予算編成プロセスにおいて、各ライン省庁との調整能力を高める為の能力強化プログラム策定に向けた助言)(4) AFSの機能の強化(含:中期アクション計画策定支援。シニア、幹部候補向け研修プログラムの試行的な取り組みとして日本等のアカデミックスによる現地セミナー開催等に係る各種調整。)
投入
日本側投入 (1) 長期専門家(2) 在外事業強化費(3) 調査団(業務実施)(4) 調査団(直営)
相手国側投入 (1) カウンターパート人材の配置(2) カウンターパート予算の確保(3) オフィススペースの提供等
外部条件 スリランカにおける経済政策分野の高等教育が質量面で改善する。
実施体制
(1)現地実施体制 本アドバイザーは財務計画省次官と連絡を密に採りつつ、法務局長及びAFS院長(CEO)、AFS担当局長代行が直接のカウンターパートとなる。
(2)国内支援体制 業務の難易度・範囲に鑑み、JICAアドバイザリーグループを設置し、経済・財政運営に関連する各分野の専門家からの支援・協力が得られるような支援体制の構築を進める。

在外事務所主管案件
個別案件(専門家)
2016年07月22日現在
在外事務所 :スリランカ事務所
案件概要表
案件名 (和)投資促進アドバイザー
(英)Investment Promotion Advisor
対象国名 スリランカ
分野課題1 民間セクター開発-貿易・投資促進
分野課題2
分野課題3
分野分類 商業・観光-商業・貿易-貿易
プログラム名 プログラム構成外援助重点課題 -開発課題 -
プロジェクトサイト コロンボ
協力期間 2014年03月30日 ~ 2016年03月29日
相手国機関名 (和)投資促進省
相手国機関名 (英)Ministry of Investment Promotion
日本側協力機関名 日本貿易振興機構、経済産業省
プロジェクト概要
背景 スリランカは2009年の内戦終結以降、復興需要により製造業・建設業及びサービス部門(運輸・通信業等)が急速な成長を見せるとともに、観光業も大幅な回復を見せており、年率8%の高水準の成長を続けている。しかしながら、繊維産業や農業等の主要輸出産業が脆弱で相対的に付加価値が低いことから、スリランカは2012年政府予算演説において競争力が低下してきている紅茶、繊維、ゴムといった既存の産業の高付加価値化に加え、特定の分野(医療産業、IT産業)での輸入代替策等を発表し、投資の活発化に重点を置いた。さらに内需頼みの経済では限界があり、スリランカの人口規模が域内各国に比べて相対的に小さく、消費市場としての潜在力が小さいことから、今後はインド等のSAARC域内諸国とのFTAを戦略的に活用して、先進諸国に加え南アジア域内マーケットをターゲットにして、サプライチェーンの一部を構成しうる産業の育成が必要と考えられている。また、政府開発計画(マヒンダ・チンタナ2010)でも、年率8%成長の持続と所得倍増を達成し、中心国入りを目指すとしており、そのための重点取組課題の一つとして海外直接投資(FDI)の促進(対GDP比3.0%まで引き上げること)を掲げている。他方、実際の投資においては投資環境情報へのアクセスが困難、投資に係る許認可取得にかかる手続きが分かりにくい、時間がかかる、といった問題によりその潜在成長性を十分に発揮しているとは言い難い。上記の状況を受け、スリランカ政府は2012年9月に「投資促進アドバイザー」派遣を我が国に対して要請した。同要請で述べられた投資環境の改善と投資の拡大を支援することは、スリランカの経済成長の促進に資することから、2013年11月に本要請が採択された。
上位目標 スリランカへの投資が促進される。
プロジェクト目標 スリランカへの投資促進のために投資促進に関連する機関の人材育成と組織強化が行われる。
成果 1.スリランカのビジネス環境の現状、課題点が把握・分析され、産業構造・貿易投資動向を踏まえた投資ポテンシャルが検証される。2.グローバル市場(特に日本市場を意識した)からの投資促進に向けたマーケティング戦略が策定、実施される。

3.投資促進関連機関の職員の能力が向上する。4.投資関連機関の連携が促進され、BOIが提供するワンストップサービスなど投資家向けサービス機能が強化される。5.スリランカに適した投資促進支援システム、施策が提案される。6.投資優先分野における投資案件の形成が支援される。
活動 1-1BOI等のスリランカ政府関係機関による投資促進に向けた取り組み(ワンストップサービス機能(以下OSS機能)やマーケティング戦略等を含む)や、その実施体制等に関する情報を収集し、整理を行う。1-2産業構造・貿易投資動向を踏まえた、投資ポテンシャルを検証する。1-3企業からのヒアリングを通じて、スリランカに対する投資の阻害要因を把握する。
2-1官民合同による定例協議を開催し、投資ポテンシャルにかかる意見交換の場をファシリテートする。2-2投資促進活動の一環として、投資ポテンシャル実証調査を実施する。2-31-1~1-3および2-1、2-2の活動結果を踏まえ、BOIと共に投資促進に向けたマーケティング戦略を策定する。2-4 2-3で策定したマーケティング戦略に基づき、企業とのビジネスマッチングを支援する。
3-1投資促進関連機関のスタッフの能力向上を目的とした研修を実施する。
4-11-1~1-4の活動結果を踏まえ、BOIの提供するOSS機能の課題を特定し、改善に向けた助言を行う。4-2官民合同の有識者グループによる定例協議を開催し、投資促進省の体制整備に関する助言を行う。
5-1スリランカに適した投資許認可手続きやインセンティブ体系等の施策を検討する。
6-12-4の活動結果を踏まえ、スリランカへの投資に関心をもつ企業を特定し、投資実現に向けたBOIの取り組みを支援する。
投入
日本側投入 個別専門家(投資促進アドバイザー)在外事業強化費国内事業強化費
相手国側投入 カウンターパート(投資促進省、スリランカ投資局)事務スペース
実施体制
(1)現地実施体制 高速道路・高等教育・投資促進省(Ministry of Highways, Higher Education and Investment Promotion)スリランカ投資局(Board of Investmentof Sri Lanka:BOI)
(2)国内支援体制 日本貿易振興機構(JETRO)経済産業省
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
個別専門家「中小企業開発投資促進アドバイザー」(2008-2010)課題別研修「投資環境法整備」「貿易投資促進のためのキャパシティ・デベロップメント」「観光振興とマーケティング」

本部主管案件
技術協力プロジェクト
2018年09月08日現在
本部/国内機関 :地球環境部
案件概要表
案件名 (和)水質管理能力向上プロジェクト
(英)Project for Monitoring of the Water Quality of Major Water Bodies
対象国名 スリランカ
分野課題1 環境管理-水質汚濁
分野課題2
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-公益事業-下水道
プログラム名 上下水道・環境改善プログラム援助重点課題 経済成長の促進開発課題 成長のための経済基盤整備
プロジェクトサイト ケラニ川流域
署名日(実施合意) 2014年11月26日
協力期間 2014年12月01日 ~ 2018年02月28日
相手国機関名 (和)中央環境庁
相手国機関名 (英)Central Environmental Authority
プロジェクト概要
背景 当該国における水環境管理/ケラニ川流域の開発実績(現状)と課題スリランカ民主社会主義共和国(以後「スリランカ」という。)は、2011 年に経済成長率8.3%を達成した。スリランカ政府はこの高い成長率を維持して、2016 年までに国民一人当たりの所得4,000 米ドルを達成し、中進国にランク入りすることを目指している。政府は、水質汚濁の防止を含む環境保全により、生活水準を改善するための持続可能な開発の達成を試みている。しかしながら、コロンボ圏の取水源であるケラニ川の測定地点において、BOD、COD等河川の汚染の程度を示す値や重金属である鉛の濃度が日本の環境基準と比較した際、基準値を超過しており、流域の工場群からの廃水が原因と思われる水質汚染がスリランカ国内の他の河川と比較し、進行している。ケラニ川流域には複数の浄水場も存在するところ、住民の健康や環境に対して深刻な影響を及ぼすことが危惧されている。水質管理は主に環境省 (Ministry of Environmental and Renewable Energy) 傘下の中央環境局 (Central Environmental Authority)が担っている。CEAは工場等の事業者に対し、汚濁発生量に応じてEPL (Environmental Protection License) を発行している。新規EPL発行数は汚染の程度が最も甚だしいとされる業種(カテゴリA)で年間1,000件程度(2012年)である。また、CEAは各種事業者へのインスペクションを実施しているが、排出基準の基準順守率は50%程度に留まっている。更に、CEAは河川の水質モニタリングも実施している。スリランカの主要河川の水質汚染源は工業排水や農業排水、家庭廃水であるものの、採水地点や採水方法は正確に定められておらず、採水頻度も一定でない。加えて、環境基準の類型指定は現時点で実施されていない。類型指定は水環境保全に関する政策策定に際し重要な役割を果たすことから基準策定が必要な状況である。以上から、スリランカの主要な河川における適切な水質モニタリング及び流域工場への適切なインスペクションの実施はスリランカの水環境保全のために国家的課題になっているため、スリランカ政府はJICAに対し、水質モニタリング及びインスペクションに係る技術協力プロジェクトを要請した。
上位目標 【上位目標】主要水域における水質管理がCEAによって適切になされる。【指標】・2020年迄に水質管理システムの役割や機能を規定した施行細則または規則が公布される。

・2020年迄にCEAが行う水質モニタリングモニタリング結果に改善が見られた水域数の割合がプロジェクト開始時(2015年)よりも増加する。・プロジェクトによって作成されたガイドラインに従い、スリランカにおいて2020年迄に水質管理システムが導入された水域数がxxx以上になる。
プロジェクト目標 【プロジェクト目標】水質管理に関するCEAとケラニ川流域の地域事務所の行政執行能力が強化される。
成果 ①スリランカの一般水質環境基準に準拠した水域類型指定導入のための準備がなされる。1-1: 現時点における法制度のレベル、ならびに実施システムについてレビューする。1-2: 一般水質環境基準の管理と遵守状況に関する現状と課題を明らかにする。1-3: ワーキンググループを立ち上げ、キャパシティデベロップメントのニーズを把握し、活動のタスクマトリックスについて合意する。1-4: キャパシティデベロップメント活動を実施し、類型指定や類型区分に関するガイドラインやマテリアルを開発し、選定された河川においてそれらの試行をする。1-5: 試行結果ならびに得られた教訓を基に、水域類型指定導入のためのガイドラインを策定する。②ラボラトリースタッフの水質分析能力が強化される。2-1: 中央ならびに地方のラボラトリーの現状とレベルをレビューする。2-2: ワーキンググループを立ち上げ、水質分析と分析機材の運用と維持管理を含む明確なキャパシティデベロップメント計画について合意する。2-3: キャパシティデベロップメント活動を実施し、標準手順書を開発し、ISO/IEC17025等の公式認証を取得する活動を継続する。
活動 ③対象カウンターパート機関のインスペクションを含む水質モニタリング能力強化、汚染源インベントリの整備及びEPLの取得が促進される。<3-1> インスペクションを含む水質モニタリング3-1-1: インスペクションを含む水質モニタリングの現状をレビューし、キャパシティデベロップメントのニーズを把握する。3-1-2: ワーキンググループを立ち上げ、活動のタスクマトリックスを作成し、明確なキャパシティデベロップメント計画について合意する。3-1-3: 年間計画、採水、報告を含むキャパシティデベロップメント活動を実施し、他のワーキンググループにフィードバックする。3-1-4: インスペクションを含む水質モニタリング結果について解析、評価し、ケラニ川の年間報告書を作成する。3-1-5: スリランカの河川のためのインスペクションを含む水質モニタリングガイドラインを作成する。
<3-2> 汚染源インベントリ (PSI)3-2-1: 汚染源インベントリの現状をレビューし、キャパシティデベロップメントのニーズを把握する。3-2-2: ワーキンググループを立ち上げ、活動のタスクマトリックスを作成し、明確なキャパシティデベロップメント計画について合意する。3-2-3: フォーマット準備、年間計画、報告、他のワーキンググループとの共有、を含むキャパシティデベロップメント活動を実施する。3-2-4: 他の組織と協働して汚染源インベントリデータの管理と活用をする。3-2-5: スリランカの河川のための汚染源インベントリのガイドラインを作成する。
<3-3> ケラニ河流域における工場に対する環境保護ライセンスと排出水質基準制度の促進3-3-1: ケラニ河流域における環境保護ライセンスと排出水質基準制度の現状をレビューし、改善すべき主要な課題を把握する。3-3-2: ワーキンググループを立ち上げ、活動のタスクマトリックスを作成し、明確なキャパシティデベロップメント計画について合意する。3-3-3: 必要なツールと材料の開発を含むキャパシティデベロップメント活動を実施し、ケラニ河流域におけるそれらの適用をパイロットプロジェクトとして実施する。3-3-4: 環境保護ライセンスと排出水質基準制度を促進するためのガイドラインを作成する。
④内陸表面水域におけるインスペクションを含む水質モニタリングデータ、環境保護ライセンスデータ、汚染源インベントリデータの情報管理システムが開発され、有効に活用される。4-1: 内陸表面水域におけるインスペクションを含む水質モニタリングデータ、環境保護ライセンスデータ、汚染源インベントリデータの情報管理の現状をレビューし、改善すべき主要な課題を把握する。4-2: ワーキンググループを立ち上げ、活動のタスクマトリックスを作成し、明確なキャパシティデベロップメント計画について合意する。4-3: データベース構築を含むキャパシティデベロップメント活動を実施し、ケラニ川流域におけるそれらの適用をパイロットプロジェクトとして実施する。4-4: スリランカにおける情報管理システム開発を促進するためのガイドラインを作成する。
投入
日本側投入 専門家(チームリーダー、水質分析、環境モニタリング、汚染源インベントリ(PSI)、インスペクション、データ及び情報管理)、水質分析機器
相手国側投入 カウンターパート(環境再生エネルギー省 (MOER)、中央環境局 (CEA)及びその地方事務所)、オフィススペース
外部条件 CEAが国家環境法で規定される法執行にかかる業務のマンデートを有し続ける。

関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
キャンディ市上下水道整備事業(円借款)(2001~)下水道セクターに係る情報収集・確認調査 (2012)下水セクター案形成調査 (2012)スリランカ国下水道整備事業における案件形成調査 (2)(2013)
(2)他ドナー等の
援助活動
Greater Colombo Wastewater Management Project (ADB) (2009~)Increasing Household Sewerage Connection and Off network Sanitary Solution in Grater Colombo City (WB) (2011~)Greater Colombo Water and Wastewater Management Improvement Project (ADB)( 2013~)

本部主管案件
技術協力プロジェクト-科学技術
2017年04月10日現在
本部/国内機関 :地球環境部
案件概要表
案件名 (和)廃棄物処分場における地域特性を活かした汚染防止と修復技術の構築プロジェク
ト
(英)The project for development of pollution control and environmental restoration
technologies of waste landfill sites taking into account geographical characteristics in
Sri Lanka.
対象国名 スリランカ
分野課題1 環境管理-廃棄物管理
分野課題2
分野課題3
分野分類 計画・行政-行政-環境問題
プログラム名 上下水道・環境改善プログラム援助重点課題 経済成長の促進開発課題 成長のための経済基盤整備
プロジェクトサイト キャンディ、ガンポラ、ハンバントタ
署名日(実施合意) 2011年02月28日
協力期間 2011年04月25日 ~ 2016年03月31日
相手国機関名 (和)ペラデニヤ大学工学部土木工学科
相手国機関名 (英)The Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of
Peradeniya
プロジェクト概要
背景 スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」)では商業活動の活発化、生活の多様化等により廃棄物の排出量が増加し、適切に処分されない廃棄物によって、環境劣化(水質汚濁、悪臭等)や観光国としてのイメージ低下を招いている。このような廃棄物問題を解決するために、スリランカでは「廃棄物管理国家戦略」が2000年に制定され、持続可能な廃棄物管理を目指した取り組みが始まった。2006年に全国廃棄物管理支援センター(以下「NSWMSC」)が設置され、2007年に「廃棄物管理国家政策」が制定され、2008年には自治体が実施する廃棄物管理事業へ総額約57億ルピー(約46億円)の無償資金を供与する環境省によるピリサルプログラムが開始された。 これら廃棄物管理の改善の取り組みを支援するために、JICAは、2002年から2003年に技術協力(開発調査)「地方都市環境衛生改善計画調査」を実施し、中央政府による地方自治体支援の仕組みを構築することを提言した。この提言によって、上述したNSWMSCの設置を促し、2007年にNSWMSCの能力向上のための技術協力プロジェクトを開始した。このNSWMSCは、主に廃棄物管理事業に関する運営体制、行政サービスの向上、廃棄物処分場整備計画等に対する支援を地方自治体に行っているが、処分場の環境改善に係る技術的方策は開発しておらず、現地で適用可能な低コスト・低メンテナンス・低環境負荷の修復技術の研究開発・導入が強く求められている。 一方、スリランカの大学や大学院を卒業し研究職に就いた研究者は、資機材や資金の不足により、国外に移住し、研究を続けるケースが多い。よって、スリランカの研究機関は、複数の研究機関との連携による国際共同研究を通じて、研究者自身の研究開発能力の向上を図るとともに、研究者を引き付けるような国際的な研究開発環境の整備も強く望んでいる。 このような背景から、ペラデニヤ大学を中心とした研究グループより、スリランカの廃棄物処分場における地域特性を活かした汚染防止と修復技術の構築及び持続可能な廃棄物処分場の計画・管理・汚染防止ガイドの作成に係る研究が要請された。

上位目標 ※科学技術協力案件のため、プロジェクト目標と区別して設定せず。
プロジェクト目標 スリランカの持続可能な廃棄物管理に貢献することを目指した、廃棄物処分場における汚染防止及び修復に関する技術の研究開発能力が強化される。
成果 1.スリランカに適応できる廃棄物処分場の計画・管理・汚染防止ガイドのコンセプトが明確にされる。2.新規廃棄物処分場の適地選定手法が定められる。3.既存廃棄物処分場の現状を把握するために、処分場及び周辺域の汚染状況のモニタリングが行われる。4.廃棄物処分場の汚染防止・修復技術が構築される。5.持続的かつ適用可能な廃棄物処分場の計画・管理・汚染防止ガイドが最終化される。
活動 1.スリランカにおける廃棄物管理事業及び廃棄物政策をレビューし、改善すべき課題を把握し、ガンポラ町及びハンバントタ町の廃棄物管理の状況を調査する。その結果を踏まえて、廃棄物処分場の計画・維持管理のためのガイドラインで必要となる項目及び内容等を明確にし、スリランカ廃棄物関係者を対象としたワークショップを開催して意見を聴取する。2.新規廃棄物処分場候補地選定のための技術的・社会的・経済的条件を見出し、ガンポラ町及びハンバントタ町を対象に見出した条件に関するデータを収集する。そのデータを総合的に解析し、適地選定のための総合的評価手法を構築し、選定手順書を作成する。これらの結果は、セミナー、紙面、Webサイト及び学会等を通じて、廃棄物管理の関係者に広く周知する。3.ガンポラ処分場及びハンバントタ処分場、並びにそれら周辺の汚染状況の把握のために、基本情報を収集し、予備的な分析や解析を行ってモニタリング計画を立て、品質保証・品質管理体制を確立し、モニタリングマニュアルを作成した後、モニタリングを実施し、その結果を整理・解析して汚染物質の移動予測及び暴露評価を行う。これらの結果は、セミナー、紙面、Webサイト及び学会等を通じて、廃棄物管理の関係者に広く周知する。4.活動1及び3の結果を活用し、①浸出水処理技術、②遮水ライナー技術、③安全な廃棄物積み上げ層厚及びその傾斜角の決定、④処分場キャッピング技術、⑤反応性浸透壁技術の5項目について、適用・導入可能な汚染防止・修復技術を研究する。その研究結果を基に、ガンポラ処分場及びハンバントタ処分場において野外スケールの実験を行って、汚染防止・修復技術を開発する。これらの結果は、セミナー、紙面、Webサイト及び学会等を通じて、廃棄物管理の関係者に広く周知する。5.活動1から4の結果を活用し、低コスト、低メンテナンス、低環境負荷な廃棄物処分場の汚染防止・修復技術の組み合わせ案を作成するとともに、ガンポラ町及びハンバントタ町における新規廃棄物処分場の適地の可能性を示すマップ、新規廃棄物処分場のモニタリング基準、ガンポラ処分場及びハンバントタ処分場のモニタリング方法及び環境負荷削減方法を提示する。それらの結果は、スリランカ廃棄物管理関係者を対象としたワークショップで共有・検討して、スリランカ国内で適応できる廃棄物処分場の計画・管理・汚染防止ガイドを最終化し、関係省庁に提案する。
投入
日本側投入 ・専門家(長期専門家:1名、短期専門家:16名)・本邦研修(計14名)・機材供与(現場用モニタリング機材、実験室用分析機材、データ解析機材、現場調査用車両等)・在外事業強化費(現地活動費、リサーチアシスタント経費) -リサーチアシスタント:15名×18ヶ月
相手国側投入 ・カウンターパート:31名・カウンターパート旅費・研究機関の施設・設備(専門家執務室、インターネットアクセス、執務室光熱費等)・野外スケール研究用の処分場(ガンポラ処分場、ハンバントタ処分場)
外部条件 1)前提条件・スリランカ国が政治的、社会的に安定している。・同国内の負担分の予算が確保される。2)成果達成のための外部条件・環境モニタリングや野外スケール研究の実施時に地域住民からの理解や協力が得られる。・中間レビュー時に規模・期間が決まる野外スケール研究に必要な資機材がスケジュールどおりに入手できる。
実施体制
(1)現地実施体制 スリランカ側実施体制・ペラデニヤ大学(研究代表機関)・ルフナ大学・キャンディ基礎研究所;IFS・全国廃棄物管理支援センター;NSWMSC・中央環境庁;CEA
JCC委員長:ペラデニヤ大学学長プロジェクトディレクター:ペラデニヤ大学工学部長プロジェクトマネージャー:ペラデニヤ大学工学部シニア講師
(2)国内支援体制 埼玉大学(研究代表機関)、埼玉県環境科学国際センター、独立行政法人産業総合研究所、早稲田大学大学院
関連する援助活動

(1)我が国の
援助活動
・「地方都市環境衛生改善計画調査」:技術協力(開発調査)。2002年度~2003年度。スリランカの環境衛生に関する実態と把握するとともに、パイロットプロジェクトを実施し、地方自治体における廃棄物管理の改善に必要な計画策定及び提言を行った。・「地方都市環境行政」:国別研修。2002年度~2007年度。名古屋市環境局を受入機関として、スリランカの環境行政に従事する地方自治体行政官の人材育成を行った。この研修の帰国研修生らが作る同窓会の会長は、本案件のカウンターパートのひとりであり、帰国研修生らは本案件で行うセミナーやワークショップへの積極的な参加者になると見込まれる。・「全国廃棄物管理支援センター能力向上プロジェクト」:技術協力プロジェクト。2007年3月~2011年2月。2002~2003年に実施した開発調査の提言に基づき、2006年に地方政府・州議会省に新設された全国廃棄物センター(NSWMSC)が地方自治体を支援するための能力強化を行っており、2011年2月に終了した。このNSWMSCは本案件の実施機関のひとつである。・「行政官のための廃棄物管理国別研修」:2009年10月~2011年11月。意思決定レベルにある廃棄物管理にかかわる行政官を対象とした研修を実施した。この研修の帰国研修生らは、本案件のセミナーやワークショップの参加者になることが期待される。
(2)他ドナー等の
援助活動
・UNOPSによるスリランカ東部州のアンパラ地区で廃棄物改善プロジェクトを実施している。アンパラ市を含む12の自治体を対象に、廃棄物管理人材養成や地域住民啓発等が行われ、いくつかの新廃棄物施設が供用開始している。プロジェクトは12.3百万USドルの予算で2011年6月まで続けられる。・オランダのNGOエナジーフォーラムが廃棄物管理能力強化事業を2007年から2010年まで実施した。ハンバントタ町から分離・独立させてタウン清掃協会(TCS)を設立し、ハンバントタ処分場でのコンポスト製造・販売事業等の独立採算を目指してTCSを支援した。

本部主管案件
技術協力プロジェクト
2018年10月06日現在
本部/国内機関 :農村開発部
案件概要表
案件名 (和)認証野菜種子生産システム強化プロジェクト
(英)The Project for Enhancement of Production System of Certified Vegetable Seed
in Sri Lanka
対象国名 スリランカ
分野課題1 農業開発-園芸・工芸作物
分野課題2
分野課題3
分野分類 農林水産-農業-農業一般
プログラム名 農漁村振興プログラム援助重点課題 後発開発地域の開発支援開発課題 農村地域の社会経済環境の改善
プロジェクトサイト キャンディ
署名日(実施合意) 2012年02月29日
協力期間 2012年05月14日 ~ 2017年05月13日
相手国機関名 (和)農業省農業局
相手国機関名 (英)Department of Agriculture, Ministry of Agriculture
プロジェクト概要
背景 スリランカにおいて、国内総生産(GDP)に占める農業セクターのシェアは12%に留まるが、依然として国内労働人口の32%を抱えている。また、貧困層の8割は農村地域に居住しており、貧困層の所得向上のためには農業セクター振興が重要である。 スリランカ政府は、独立以来、主食であるコメの国内自給達成を目標に掲げ、優先的に取り組んだ結果、2008年以後は国内自給を達成するようになっている。その一方で、コメ以外の作物では輸入依存度が高く、食料安全保障の確保及び外貨流出の低減、さらに輸出促進のための生産性の向上が必要とされている。 生産性の向上に向けた一方策として、良質な種子の供給が必要とされているが、国産の野菜種子供給量は需要を大きく下回り、不足分をインド、タイ等からの輸入種子、農民による自家採種で補っている。また、2010年に経済開発省によって生計向上を目的に開始された国家プログラム「家庭菜園推進プログラム(Divi Neguma:Domestic Agriculture Program)」では、栄養価の高い食物供給を目的に、各家庭に野菜種子を150万パッケージ(2011年)配布する全国規模の事業を開始しており、種子の供給不足は更に顕著となっている。 上記の課題に対応すべく、スリランカ政府は、「種子生産農場強化プログラム(Accelerated Seed Farm Development Program)」(政府種子生産農場への予算増額)、「種子生産村落育成プログラム(Seed Village Program)」(潜在的な種子生産農家への支援)など、様々な種子生産プログラムを開始している。 しかし、良質な野菜種子の供給量増加のためには、生産段階だけでなく、需給バランスを考慮した生産計画の策定、質を担保するための政府認証システムの向上、民間企業の参加促進など、更なる取組が必要である。また、生産段階においても、上記の政府プログラムとの連携・役割分担を計りつつ、種子生産技術の向上、種子生産に必要な灌漑設備等の導入への支援が必要となっている。
上位目標 市場に出回る野菜種子のうち、農業局が定める基準を満たしている種子の量が増加する。
プロジェクト目標 対象地域の野菜の認証種子の生産体制が改善される。

成果 成果1 SPMDCの種子生産・配布計画策定能力が向上する。成果2 官民の野菜種子生産技術が向上する。成果3 官民の野菜種子の品質管理技術が向上する。
活動 1-1. 官民が参加する定期的会合及び合同ワークショップを開催する1-2. 対象地域における市場調査と生産・供給の実態調査を行う1-3. 官民双方を対象とした野菜種子の生産、輸入、配布、在庫に関するデータベースを構築する1-4. データベース及び昨期の生産計画のレビューに基づいて、種子の生産計画(マハ期、ヤラ期)を策定する1-5.種子販売サービスの現況評価を行い、改善計画を作成する1-6.DoAモデル販売所において、改善計画(1-5)に基づいたパイロット活動を実施する
2-1. ハイブリッド種子、原種種子及び標準種子の生産に関する現状レビューを行う(ベースライン調査を含む)2-2. 政府種子農場の種子生産、調整、品質管理にかかる機材を導入、更新する2-3. 優良種子の生産に関して、政府及び民間の技術職員、普及員、契約農家向けに実技研修を行う2-4. 優良種子の生産に関して、生産者向けの技術マニュアルを作成する2-5. 研修を受けた普及員が、研修を受けた契約農家による技術の適用を促すため、フォローアップ訪問を行い圃場で指導する
3-1. 種子認証システムの現行手順および施設の評価調査を実施し、改善計画を作成する3-2. 種子検査に関する技術マニュアル及び研修教材を作成する3-3. 政府及び民間の技術職員、普及員に対して、種子の品質管理(圃場検査と種子検査)に関する研修を行う3-4. 種子生産者に対して、優良種子を準備するための研修を行う3-5. 野菜種子マーケットの現状把握のため、種子検査やラベルチェックを含む「市場に出回る種子の品質調査」を実施する
投入
日本側投入 1. 専門家派遣:(1)長期専門家:4名(リーダー/認証種子生産システム、種子検査、種子生産/種子販売、業務調整/研修)(2)短期専門家:種子検査(圃場検査含む)、種子病理、植物病理、農家経済・営農、市場分析、種子の収穫後処理等(必要に応じ)2. 機材供与:プロジェクト活動に必要な資機材(車両2両、種子生産、種子加工、種子検査等に関する機材)3.カウンターパート研修(本邦/第三国)4. ローカルコンサルタント及びローカルスタッフ雇用費
相手国側投入 1. カウンターパートの配置(ア) プロジェクト・ディレクター:農業局(DOA)局長(イ) プロジェクト・マネージャー:SPMDC所長及び種子認証・植物防疫センター(Seed Certification and Plant Protection Center、以下SCPPC)所長(ウ) カウンターパート: (エ) 関係政府機関職員(園芸開発研究所研究員、農民サービス・野生生物省農民サービス部職員等必要に応じて)2. プロジェクトオフィス施設:執務室と室内の電気、家具、インターネット接続等の必要な施設3. 資機材:研修用会場、設備・機材、交換用部品等、プロジェクト実施に必要な項目で、日本側から供与される以外のもの4. ローカルコスト:C/P向け国内研修用日当・旅費、プロジェクトオフィスの光熱費等、プロジェクト実施のための必要経費
外部条件 1. 事業実施のための前提条件 野菜種子産業において、民間セクターの参加が保証され、促進される。2.成果達成のための外部条件 ①大規模な自然災害が起きない ②大規模な病虫害が発生しない ③研修を受けた技術スタッフにより、種子生産技術が継続的に農家に普及される3.プロジェクト目標達成のための外部条件 プロジェクト実施中に、農業省から種子生産に必要な予算および人員が配分される。4.上位目標達成のための外部条件 プロジェクト終了後も、スリランカ政府から種子生産に必要な予算および人員が配分される。
実施体制
(1)現地実施体制 農業省農業局
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
これまで我が国は、スリランカの野菜種子分野に対し、植物遺伝資源センター(PGRC)への無償資金協力および技術協力プロジェクト(1988-1995年)、園芸開発研究所(HORDI)への専門家派遣(1999年)、国別研修「野菜採種」コース(2003-2007年)、政府種子生産農場への機材供与(2KR)等、長年に渡り様々な支援を行っている。プロジェクトの実施において、それら過去の協力成果との相乗効果の発現を十分考慮する。
(2)他ドナー等の 特になし

援助活動

国内機関主管案件
草の根技協(パートナー型)
2017年12月08日現在
本部/国内機関 :東京国際センター
案件概要表
案件名 (和)スリランカ国キリノッチ県における小規模畜産農家の家畜生産性向上プロジェクト
(英)Production Improvement Project for Small-Scale Livestock Farmers in Kilinochchi
District
対象国名 スリランカ
分野課題1 農業開発-家畜衛生・畜産
分野課題2 平和構築-その他平和構築
分野課題3 市民参加-市民参加
分野分類 農林水産-畜産-畜産
プログラム名 プログラム構成外援助重点課題 -開発課題 -
プロジェクトサイト スリランカ国 キリノッチ県
署名日(実施合意) 2013年11月01日
協力期間 2013年11月01日 ~ 2016年02月29日
相手国機関名 (和)キリノッチ県家畜生産者組合
相手国機関名 (英)LIBCO
日本側協力機関名 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
プロジェクト概要
背景 2009年5月の内戦終結後、キリノッチ県では2012年10月末までに127,773人(39,606世帯)が出身地に帰還した。政府や国連機関、NGOなどが帰還民の再定住支援として生計分野においても支援を行ってきたが、未だ安定した収入を得られないまま困窮した状態に置かれている世帯が多い。畜産分野においては家畜・家禽(乳牛、ヤギ、鶏)の頭数自体は内戦前の水準に戻りつつあるものの、家畜の生産性が非常に低く、家畜生産物の販売による収益だけでは充分な収入を得ることが困難で、特に小規模畜産農家の生活状況は厳しい。家畜の生産性が低い原因は第一に、家畜生産衛生局(PDAPH)キリノッチ県事務所や郡獣医局の人材や移動手段の不足のため、農家の家畜の人工授精や治療など専門的な技術サポートを提供することが十分にできていないことが挙げられる。第二に、長年LTTEの支配下にあり外部からの新しい知識や技術がほとんど流入せず、技術指導を受ける機会も無かったため、畜産農家は生産性の低い伝統的な方法で家畜・家禽を飼養していることである。そのため、コミュニティレベルで畜産農家が必要とする基本的な技術サポートの提供や、飼養方法の技術指導を行う普及員(コミュニティ・アニメーター)が求められている。
上位目標 キリノッチ県の畜産農家が安定した収益をあげることができる
プロジェクト目標 畜産農家が飼養する家畜の生産性を向上させ、かつ継続的に家畜生産物を得ることができるようになる
成果 1.畜産農家が必要とする専門的な技術サポートを適切に受けられるようになる2.畜産農家が家畜・家禽の適切な飼養方法を習得する機会を持てるようになる
活動 1-1. 事業開始時関係者会合を実施する1-2. CAを選定する1-3. CAへの研修内容を確定する

1-4. CAの研修を実施する1-5. ベースライン調査を実施する1-6. CAが畜産農家に技術サポートを行う1-7. CAの定例会合を開催する1-8. PDAPHキリノッチ県支部,LIBCO(家畜生産者組合),CAとの定例会合を実施する
2-1. LIBCO事務所を整備する2-2. LIBCO職員に能力強化研修を実施する2-3. CA及びLIBCO職員がモデル事業(JICA技プロ、他)を視察する2-4. CA及びLIBCO職員が既存のモデルファーム(2カ所)の改善計画を作成する2-5. モデルファームの整備を行う2-6. CAがモデルファームやコミュニティで畜産農家に対する研修を開催する2-7. モデルファームやコミュニティでCAが畜産農家の相談に対応する
投入
日本側投入 プロジェクトマネージャー1名、国内調整員2名、コミュニティアニメーター用バイク、人口受精用器材、応急処置用器材、LIBCO事務所建設及び備品一式、モデルファーム用井戸施設整備。
相手国側投入 キリノッチ県家畜生産衛生局責任者及びスタッフ、獣医。
外部条件 ・政策の大幅な変更がない・家畜生産物の販売価格が大幅に下落しない・深刻な災害や家畜伝染病が発生しない・治安が悪化しない
実施体制
(1)現地実施体制 ワールド・ビジョン・ジャパンとワールド・ビジョン・スリランカ事務所がキリノッチ県の畜産農村開発省や家畜生産者組合と協力して、事業を実施する。
(2)国内支援体制 ワールド・ビジョン・ジャパンの国内調整員(事業担当者)、財務担当者等がプロジェクト実施やモニタリング・評価の指導を行う他、JICAとの連絡・協議・報告を行う。

在外事務所主管案件
個別案件(専門家)
2017年12月15日現在
在外事務所 :スリランカ事務所
案件概要表
案件名 (和)紛争影響地域における帰還民を対象とした生計向上専門家
(英)Long-term Expert on Rural Development
対象国名 スリランカ
分野課題1 農村開発-農村生活環境改善
分野課題2 平和構築-経済復興
分野課題3
分野分類 農林水産-農業-農業一般
プログラム名 紛争影響地域生産性回復プログラム援助重点課題 後発開発地域の開発支援開発課題 紛争影響地域の開発促進
プロジェクトサイト 北部州
協力期間 2012年07月05日 ~ 2014年09月19日
相手国機関名 (和)農業省
相手国機関名 (英)Ministry of Agriculture
プロジェクト概要
背景 スリランカ国では、2009年5月に内戦が終結したものの、紛争終結末期に北部州・東部州で激しい戦闘が繰り広げられた結果、住民の多くが元の土地を離れ、28万人超の国内避難民(IDP)が発生した。同年10月以降、「ス」国政府によるIDP帰還事業が進められており、幹線道路などの基礎インフラは急速に復旧されつつある一方で、IDPの帰還地の多くは生活基盤が破壊されており、生計を営むための資本や設備、機材、社会サービス等が不足し、自立的な生計手段を確立するうえで引き続き多くの困難に直面している。特に帰還民の多く住む北部州は、持続的開発フェーズに移行する中にあって、再定住及び帰還民を中心に生計手段の回復及び生活再建への支援が立ち遅れており、必要性が極めて高い地域となっている。このため、土地なし農民や寡婦世帯などの脆弱層を取り込みつつ、個人・コミュニティのエンパワーメントを通じた生計向上手段の安定的確保や持続的な地域開発を進めることが急務となっている。かかる状況を受け、「ス」国政府は、最近帰還した住民の生計向上及び持続的な地域開発を支援する専門家の派遣要請を2012年3月、日本国政府に提出し、本要請内容の緊急性に鑑み、同年4月、年度途中の採択が正式に決定された。
上位目標 紛争影響地域(うち北部州)において、帰還民の経済力が向上し、地域社会が安定的に発展する。
プロジェクト目標 プロジェクト対象地域の帰還民が、地域開発モデルに基づき、生計手段を獲得するための能力が向上する。
成果 1.プロジェクト対象地域の担当行政官が、地域開発モデル(生計向上手段を含む)を計画・実施する能力が向上する2.プロジェクト対象地域以外の北部州の担当行政官の地域開発モデルの理解度が向上する。
活動 <第一年次:2012年7月から2013年3月>1.紛争影響地域におけるIDPの帰還状況及び生活再建状況について確認し、ニーズアセスメントを実施する。2.上記1.の現地調査結果を元に、要請書で記載のある支援対象地域選定クライテリアを基に支援対象地をC/P機関とともに選定するが、基本的にはワウニア県のGN(平均100~200世

帯で構成される最小単位の行政村の名称)から2~3のGNを選定する。3.上記1.の地域に関し、コミュニティを中心とした地域開発の進め方及び具体的な地域開発のオプションを協議する。4.対象GNの置かれている状況を踏まえた生活再建手法を提示し、当該地域を所管する行政官や普及員と共に実践する。5.上記3.及び4.の実践を行う中で得られた課題を整理する。6.上記以外の近隣の地域のうち、置かれている環境から優先的に同様の活動を行う必要性の高い地域を選定し、第二年次からの支援を行うための計画を策定する(基本的にはムラティブ県内のGNを対象とする)。<第ニ年次:2013年4月から2014年3月>1.第一年次で支援対象候補地として選定したGNにおけるIDPの帰還状況及び生活再建状況を確認しつつ、第一年次に策定された第二年次の活動計画に沿った資機材の配布、及び各種生計向上支援事業を運営指導調査の助言等と得つつ、現地を管轄する行政官や被益住民代表と共にパイロット的に実践する。2.第一年次及び上記1.で配布した資機材の適切な使用のために、現地の行政官らと共に資機材配布後の住民による生計向上活動をモニタリングし、地域の活性化に努める。特に加工を伴う支援に関してはスリランカ国内のリソースとの連携を図る。3.運営指導調査団の助言等を得ながら、支援対象地域を所管する行政官とともに、生計向上活動による産品の付加価値を高める取り組みとしてパイロット的に支援する加工場建設を支援する(ココナッツ及び豆(ピーナッツ)加工を想定)。4.上記1.から3.の活動を踏まえ、支援対象地域を所管する行政官とともに、コミュニティを中心とした地域開発の進め方の有効性を検証し、次の農繁期に向けて必要な改善策作成作業を支援する。6.第一年次から実践されている生計向上活動に関し、対象地域ごとの置かれている条件に応じた実践を通じて得られた教訓や課題を整理・分析し(含むマーケットへの出荷を実現する上での課題)、それらの教訓を盛り込んだ地域開発モデル案を関係者と共にとりまとめた上で、近隣の地域住民のみならず、北部州を管轄する行政官や中央政府関係者を対象に紹介する。<第三年次:2014年4月から2014年9月>1.第二年次までに支援した地域住民活動の実態についてインパクト調査を行い、国内支援体制に基づく技術的支援を得つつ、紛争影響地域におけるコミュニティを中心とした複数の生計向上活動にかかる地域開発モデル案の有効性や制約条件について分析を行う。2.上記1.の分析結果を踏まえつつ、第二年次までに支援を実施した地域の活動をモニタリングしつつ、支援対象地域を所管する行政官とともに、コミュニティを中心とした地域開発を継続して実践する。3.第二年次までに支援を実施してきた地域を対象に、上記1.及び2.の分析結果を紹介しつつ、生活再建手法で改善すべき点等について、支援対象地域住民、行政官及び普及員と共に協議する。4.上記3.の議論の結果を踏まえ、改善策にかかる提言をとりまとめる。5.上記1.から4.の結果に関し、近隣の地域住民のみならず北部州を管轄する行政官及び中央政府関係者を対象に紹介する。
投入
日本側投入 長期専門家派遣経費(第一年次6.09MM×1名/第二年次11.35MM×1名/第三年次6.00MM×1名)携行機材およびパイロット事業用資機材購入経費ワークショップ開催費用運営指導調査団派遣経費等
相手国側投入 C/P
外部条件 当国北部地域においては、未だ軍のプレゼンスが強く、軍の介入により活動が影響を受けるリスクがある。また、北部で最近住民が帰還した地域では、未だ地雷が多く埋設されている地域が残されており、細心の注意を払いながら事業に従事する必要がある。また、昨今州政府に対する中央政府の介入が強くなっており、今後州政府の役割に変化が生ずる可能性も排除出来ないところ、特に2015年の大統領選挙に向けた政治的な動きにつき注視していく必要がある。
実施体制
(1)現地実施体制 Ministry of AgricultureNorthern Province財務計画省、JICAスリランカ事務所
(2)国内支援体制 国際協力専門員、運営指導調査団(年間4~8回現地調査派遣予定)、JICA農村開発部、JICA経済基盤開発部からの技術的支援。
関連する援助活動
(1)我が国の
援助活動
・北部東部地域内におけるコミュニティ開発人材育成プロジェクト(技協)2011.3~2014.3・農村経済開発復興事業(PEACE)(有償)2007.3~2013.5・マナー県再定住コミュニティ緊急復旧計画プロジェクト(MANREP)(技協)2010.3~2012.7・ジャフナ県復興開発促進計画プロジェクト(PDP-JAFFNA)(技協)2010.3~2011.10・コミュニティ・アプローチによるマナー県復旧・復興プロジェクト(技術協力プロジェクト)2004.3~2008.3・北東部家畜飼育研修(現地国内研修)2011.3~2013.3・北部州地図更新プロジェクト(緊急開発調査)2010.2~2012.2・貧困緩和マイクロファイナンス事業(円借款)2008.7~2015.6
(2)他ドナー等の ①世銀・ENREP (Emergency Northern Recovery Project) 2009.12, 65百万ドル

援助活動 ・Re-Awakening Project 2002~北部・東部・周辺地域合計141百万ドル②ADB・NECORD (North East Community Restoration and Development Project) 2001~ 北部・東部合計250百万ドル③UN・CHAP (Common Humanitarian Action Plan) 2010 287百万ドル(目標)・JPA(Joint Plan of Action) 2011 289百万ドル(目標)、2011年7月現在ドナーコミット額合計63百万米ドル

本部主管案件
開発計画調査型技術協力
2019年03月16日現在
本部/国内機関 :社会基盤・平和構築部
案件概要表
案件名 (和)防災強化のための数値標高モデル作成能力向上プロジェクト
(英)Capacity Development Project for Creating Digital Elevation Model Enabling
Disaster Resilience
対象国名 スリランカ
分野課題1 防災-その他防災
分野課題2
分野課題3
分野分類 公共・公益事業-社会基盤-測量・地図
プログラム名 気候変動・防災対策プログラム援助重点課題 脆弱性の軽減開発課題 脆弱性軽減のための社会基盤整備
署名日(実施合意) 2014年09月11日
協力期間 2014年12月01日 ~ 2016年12月31日
相手国機関名 (和)測量局
相手国機関名 (英)Survey Department Ministry of Land & Land Developement
プロジェクト概要
背景 (1)スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」)は、国土の地理的条件や昨今の気候変動の影響を受け、様々な自然災害を経験し、多くの人命やインフラの損壊等の経済損失が発生している。 被災者数においては豪雨に伴う洪水による被害が最大であり、毎年数万人から数十万人規模の被災者が出ている。また、脆弱な地質特性、急峻な地形条件、山地・丘陵地の斜面の開墾・開発により、中央地域と南西地域での山岳地では地すべり等の土砂災害が頻発している。この結果、人的被害に加え、多くの家屋の倒壊、国道等基幹道路も含めた道路の損壊が発生している状況である。係る状況を踏まえ、2004 年のスマトラ沖地震・津波を契機としてスリランカ政府は「事後対応」から「事前対策」へシフトするため、国家防災体制強化の方針を打ち出し、2005 年 5 月に事前の防災活動から災害発生後の緊急対応、復興に至るまでの包括的な法的な基礎的枠組みを定めた災害対策法「Sri Lanka Disaster Management Act, 2005」を制定した。これに伴い、防災省(2005 年設置)及び災害管理センター(Disaster Management Center)を設置するなど、災害対策及び防災体制を強化している。事前対策の一環として、洪水及び地すべり等の災害リスクマップの作成整備を通じた早期警戒体制を構築することを目指しており、スリランカ政府に対応が求められる重要な取り組みの一つとなっている。しかし、災害リスクマップの迅速な作成においては正確な標高データを効率的に取得することが求められる一方、スリランカ政府は LiDAR 測量による標高データ取得技術を有していないため、実地測量に基づく作成に頼らざるを得ない状況である。以上のような背景のもと、測量局は土砂災害対策等に活用される標高データを円滑に整備し、スリランカにおける防災能力を向上させるため、LiDAR 測量に係る技術移転を我が国に要請した。(2)相手国政府国家政策上の位置づけ 上記(1)に記載のとおり、洪水や土砂災害に脆弱なスリランカは 2005 年に災害対策法を設け、国家防災体制の強化を目指している。災害リスクマップ作成支援を通じ、早期警戒体制の構築を目指す本プロジェクトは、事前対策の一環として重要な役割を担うものである。(3)他国機関の関連事業との整合性 世界銀行は気候変動に伴う洪水や干ばつ等の災害対策へ向けた投資計画の作成及び優先事業への融資を行っており、本事業で作成される標高データの有効活用が期待される。

(4)我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ日本政府が定めた対スリランカ国国別援助方針(2012 年 6 月)では「後発開発地域に配慮した経済成長の促進」を目指すために、重点分野「脆弱性の軽減」を設定し災害に対する脆弱性への対応を強化するとしている。
上位目標 本事業によって作成された DEM データが防災に係る事業等に活用される。
プロジェクト目標 本事業によって作成された DEM データを活用した防災に係る事業の実施により、災害対策及び防災体制が強化される。
成果 1)オリジナルデータ:7,900km2 2)DEM データ:3,000km 3)オルソフォトマップ:7,900km2 4)SD 職員の人材育成・能力強化
活動 1)既存資料の収集・整理、図式・作業基準・仕様の協議 2)固定点観測 3)航空レーザ計測 4)三次元計測データ作成 5)調整用基準点観測 6)オリジナルデータ作成 7)グラウンドデータ作成 8)DEM データ作成 9)成果品利活用に係る提案及びセミナー・ワークショップの開催 10)DEM 及び主題図作成手法に係る技術移転の実施