Edu sociopsyc2010 08
-
Upload
eiji-tomida -
Category
Documents
-
view
1.017 -
download
0
description
Transcript of Edu sociopsyc2010 08

教育社会心理学第7回
ヴィゴツキーの発達理論
富田英司愛媛大学教育学部
2010/12/21
1

レフ・セミニョヴィチ・ヴィゴツキーLev Semyonovich Vygotsky
•Educational Psychologist
•Born in Belarus (Russian Empire at that time)
•1896 – 1934
•Majored in literature, medicine, law, and psychology
2

ヴィゴツキー理論の3つのテーマ (Wertsch,1985)
(1)発生的方法:発生的方法( Genetic Method )の必要を唱える
(2)認知機能の社会的起源:個人の認知機能は社会的相互作用に由来する
(3)社会的媒介:心的過程は心的道具や記号によって媒介される
3

(1)発生的方法• 前提:人間の心的過程はより原始的な形態からの系統発
生的発達という観点からのみ理解されうる
• 発達を捉える 3 つの領域– a .進化的・系統発生的領域:ヒトが類人猿からいか
にヒトとなりえたか– b .社会・文化的歴史の領域:人類の原始的祖先がい
かに文明化したのか– c .個体発生的領域:人間の個体はいかに発達するの
か
• → 大人の心的機能は以上の 3 つの領域における発達の結果として眼前に現れたものである
4

( 2 )認知機能の社会的起源• 文化的発達の一般発生的法則
– General Gentic Law of Cultural Development
• 「・・・子どもの文化的発達におけるすべての機能は,二度,二つの水準にあらわれる.最初は社会的水準であり,後に心理的水準にあらわれる.すなわち,最初は精神間カテゴリーとして人々の間に,後に精神内カテゴリーとして人々の間にあらわれる.このことは,随意的注意,論理的記憶,概念形成,意志の発達など,いずれにも同じようにあてはまる.」
5

思考力の発達を巡る議論1. 思考力→コミュニケーション力
– 代表的研究者:ピアジェ• 子どもは自分のことに夢中で他者と共同的でな
いが,自分を客観視できるほどの知能を獲得した後に他者と共同することができる
2. コミュニケーション力→思考力– 代表的研究者:ヴィゴツキー
• 人は生まれつき人に向かい,人と交流することで知能を獲得する
6

ピアジェとヴィゴツキーにおける思考と言語の発達の捉え方の違い
ピアジェ
外言的自閉的思考
(=無意識的思考)
(=自閉的な思考が外に
出てしまったもの)
自己中心的言葉
と
自己中心的思考
社会化された言葉
と
論理的思考
(合理的,意識的思考)
ヴィゴツキー
社会的言語
(=最初から誰かに向けられている)
社会的言語
(コミュニケーションのための言語)
内言
(思考のための,自分自身のための言語)
内化
分化
分化
置き換わる
置き換わる
社会的な存在から矯正される
自己中心的言語
(=子どもが発達している証)
=子どもが未熟なことの証
考えていることがつい
口をついて出てしまう

内言および自己中心的言語に対するピアジェとヴィゴツキーの考え方の相違
• Piaget の自己中心語:子どもの思考は物事の特定の面だけに注目して他の面を無視する傾向にある.これを自己中心性と呼ぶが,この特徴が言語面に表れたものを自己中心語という.例えば,幼稚園などでは大勢の子どもがお互いに無関係にしゃべっていることがあり, Piaget はこれを集団的独語と呼び,幼児の自己中心性のあらわれであると考えた.
• Vygotsky の内言:他者とのコミュニケーションの手段として機能していた言語が次第に内面化され,自分自身の中でのコミュニケーション,いわば自己内対話が行われるようになり,思考や自身の行動を統制する機能を担うようになったものを内言という.内言は音声を伴わない自分のための内的言語であり,思考の道具として,自己制御機能をもつ.外言は他者に向かって用いる音声言語であり,伝達の機能を持つ.最初は外言しか持たない子どもが発達に伴って外言と内言に分化させるが,その移行期である幼児期には,内言が音声を伴って現れることがある.
8

( 3 )記号的媒介• 人間の認知機能は,人間の活動が機器など
の技術的道具や言語・記号などの心的道具によって媒介されることで成立している
→技術的道具も心的道具も特定の文化や歴史において徐々に形成されたものであるため,それを媒介とする人間の心的活動も必然的にその文化や歴史に強く規定されたものである

• 第1シリーズ: 15 個の刺激をただ記憶してもらうだけ• 第2シリーズ: 30枚の絵カードが与えられて, 15 の刺激を覚
える際のヒントして利用することができる状況を用意した(高取憲一郎『ヴィゴツキー・ピアジェと活動理論の展開』京都・法政出版 ,
1994 )

媒介による認知機能への影響の例Kearins, J. M. (1981, 1986)• 視覚的空間課題において,アボリジニとヨーロッパ系白
人の子ども(6~17歳)を比較• 西洋文化圏に比べ,言語的コミュニケーションに依存し
ない非西洋文化圏に属するアボリジニの方が優れた成績– 言語方略が有利な課題では言語的コミュニケーションに依存する西洋文化圏の子どもの方が好成績
– 視覚的方略が有利な課題においては,砂漠での道探しなどふだんの生活のなかで視覚的方略をよく使っているアボリジニの方が好成績
• つまり,ヨーロッパ系白人とアボリジニではその媒介手段が異なるため,優れた認知機能を発揮する課題の種類も違う
11

Individual body
Practice
Practice
Community of Practice
Vygotsky’s TheoryIllustrated
12
LanguageLanguage
Language asCommunication tool
Language as
Thinking tool
Personal level
Inter-personal level
Community level
Develo
pm
en
t as
a p
ers
on
Historic
al
Developm
ent
Evolutio
n
As specie
s

相互教授法Reciprocal Teaching
• 4つのストラテジーを獲得させる–予測する–質問をつくる– 要約する– 明確化する
• 話し合いの場面を通して使ってみる →個人に内化し,一人の読みでもできる →読解能力がアップする
これらは読むのが得意な人が頭の中でやっていること
13

足場作りから思考力の獲得へのプロセス
• 「足場づくり」– 生徒が自分でなんとか質問・要約・予想・明確化がで
きるように,言葉を引き出しながら援助– 基本的に生徒と先生が1対1で話す。
• 足場はずし– できるようになれば,徐々に援助を減らしていく– 生徒同士がやりとりするのを援助する。
• 思考力の向上– 自分一人でもできるようになる。
14

中学生の物語理解を対象にした研究Palincsar & Brown, 1984
• 対象– 7年生(中1に相当) 37名( 24 人は読みに問題)
• 方法–4つの群の成績を比較
• 統制群,テストのみ群,相互教授群,情報検索群–実験群のスケジュール
• 事前テスト …最初の成績を測定• 訓練段階 …相互教授法による訓練( 20日間)• 事後テスト …訓練後の成績を測定
15

ThinkTogetherプロジェクト
• Mercer による実験授業
• 3つの会話タイプ
• グラウンド・ルール
16

3つの会話タイプ Mercer, 1996
17
論戦型会話Disputational Talk
意見の相違と個別の意志決定が特徴的。知識資源を互いに提供したり,相手を建設的に批判したりすることがほとんどみられない。また,主張とそれへの反対という著しく短いやりとりが見られる。
累積型会話CumulativeTalk
相手が言ったことに対して賛意を表明するが,無批判的である。会話は共通の知識を事実の蓄積によって構成することを目的としたものである。反復と確証と精緻化がよく見られる。
探索型会話ExploratoryTalk
互いに対して批判的ではあるが,建設的である。互いに挑戦的な意見を出すが,意見には理由や根拠,代替仮説が伴う。上の2つに比べて,他者が分かるようにはっきりと意見が説明され,会話における推論の過程がはっきりと分かる。

グラウンド・ルールWegerif, Mercer, & Dawes, 1999
• 全ての関連ある情報が共有されている• グループは合意に到達することを求める• グループは決定に責任を持つ• 理由が期待される• 反論が受け入れられる• 決定の前に他の選択肢が検討される• グループの全員が他のメンバーから話す
ことを促される
18

日本の小学 1年生が作成したグラウンド・ルール(比留間, 2006 )
1. じゅんばんにはなしていきます。2. おおきなこえではなします。3. みんなのいけんをよくきいてかんがえます。4. わけをききます。5. みんなでちからをあわせてかんがえます。6. しごとのとりあいはしません。7. しっかりとじぶんのかんがえをいいます。8. はなしているのにむししないで,しんけんにき
きます。
19

次回の内容• ブルームの教育学
– 現在の授業作りや評価に関する基盤を形成
• その後,1月 11日からの内容
– 心理学からの教育へのアプローチの変遷を整理 行動主義→認知心理学→状況論,社会文化理論
20

宿題• 宿題
– 内容:この授業にこれまで参加して,印象に残っていることやおもしろいと思ったこと,自分が普段考えていることと大きく違っているなと思ったことなどについて教えてください。
– 提出方法:修学支援システムから課題を出します。それに返信してください。
–締切: 12月 27日 月曜日
21







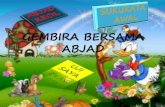










![HNgoztechnika.hu/keszletlista/pdf/572.pdf · 0puphfvwvh nnfrv]dniwovdr +dwwipnun,p2h6 u '1 )7 )7 )7 )7 )7 edu edu edu edu edu edu edu edu edu](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5fc6730ab5393d30f166460f/0puphfvwvh-nnfrvdniwovdr-dwwipnunp2h6-u-1-7-7-7-7-7-edu-edu-edu-edu-edu.jpg)
