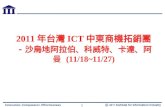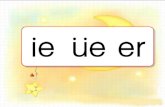三重県伊賀市立 阿山中学校阿 山中学校 静岡県静岡市立 蒲原中学...
Transcript of 三重県伊賀市立 阿山中学校阿 山中学校 静岡県静岡市立 蒲原中学...

中学校での実践例
1110
「生徒たちはすでに、技術科の授業でロボット教材を使ってプログラムを作り、計測・制御について学んでいます。その知識と経験を活かし、探査ロボットのプログラムを作りました」 そう語るのは、JAXAと連携して授業づくりに取り組んだ阿山中学校の藤山秀公先生です。身のまわりの製品の多くに使われている計測・制御技術の学習を重視した藤山先生は、大学と協力してロボット教材を開発するなど、研究を積み重ねてきました。本物の制御ロボットのプログラムを体験できれば、制御の技術が最先端の宇宙開発の現場でも使われていると実感し、興味や知識、技術がさらに深まる――そう考えた先生は、かつてJAXAと宇宙服や宇宙食を活用した連携授業を行った経験も踏まえて準備を重ね、画期的な連携授業を実現させたのです。 迎えた授業当日、生徒たちは、メジャーを使って障害物の位置を計測し、どんなコース取りをすべきか話し合い、プログラムを作りました。自分たちの指令に従って動くロボットを見つめるワクワクした表情が、今回の連携授業の成果の大きさを雄弁に物語っていました。
【連携授業1日目】JAXA講師による、宇宙探査の目的、探査ロボットの役割や現状に関する解説と、プログラミング課題の説明。(2時間)
● 科目/単元 中学校3年生 理科「地球と宇宙」● テーマ 体感! 宇宙開発最前線!!● 授業時間 全28時間のうち連携授業1時間授業計画
砂場には障害物となるブロックなどが置かれ、ゴールまでの道のりは簡単ではない。
班ごとに走行フィールドを計測し、プログラムを作成。(2時間)
2
【連携授業2日目】プログラムに基づいて実際に走行させ、課題をクリアできたか確認(各クラス1時間×3)。JAXA講師による総括。(1時間)
Teacher’s Voice
今回の授業で課題をクリアできた班はゼロです。JAXAの方と話し、あえて難易度を高くしました。宇宙開発の現場でも、難しい課題に挑み、失敗から学んでいると伝えるためです。計測の難しさや大切さも実感してくれたと思います。興味・関心を高めるだけでなく、通常の授業では伝えきれない、そうした点に踏み込めたのも、今回の授業の大きな成果です。(藤山秀公先生)
理科
理科
総合
1回(50分)
エネルギーの現状や課題などと共に未来のエネルギーに関する最新の研究、研究者たちの取り組みなどを知ることで、理科の関連単元で学習した内容を印象づけることをねらいとして連携授業を行った。
2回(200分)
2回(175分)
理科の一環として、宇宙への興味喚起や無重力について知ることを目的とした連携授業を実施。物を落下させて無重力状態にする装置を使い、生徒たちが考えた材料で実験を行い、結果を考察した。
地球環境問題の現状について学習し、他者に科学的に説明できるようにすることなどをねらいとして、総合学習『九段自立プラン:環境』の一環として連携授業を実施。宇宙での生活や地球観測データから環境学習を行った。
学校名科目 テーマ対象 回数(総時間)授業写真 支援内容
月面に見立てた阿山中学校の校庭の砂場をJAXAの月惑星探査ローバの試作機「クアトロ」が走り、周りを取り囲む生徒たちは、その様子を真剣に見つめていました。彼らは、数人の班ごとに、「障害物を避けながらロボットを進め、取り付けられたカメラで目標物の写真を撮影し、ゴールする」という課題をクリアするべく、プログラムを作りました。
三重県伊賀市立 阿山中学校阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿山山山山山山山山山山山山山山山山山中中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校 静岡県静岡市立 蒲原中学校蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲原原原原原原原原原原原原原原原原中中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校
JAXA講師の指導のもと、真剣な表情でプログラムを作る生徒たち。すでに学習用ロボットで経験しているだけに、慣れた様子で取り組んでいた。
中中中中中中中中学学学学学学学学学学学校校校校校校校校
「第2問。国際宇宙ステーションには水をどうやって運んでいるでしょうか。①地球から持っていく。②空気中の水分を集めて使う。③汚水をきれいにして使う」――宇宙や地球への興味・関心を高めるため、JAXA講師が連携授業で取り上げた切り口の1つが、こうした国際宇宙ステーションにまつわるクイズでした。 人類は、長い歴史のなかで「宇宙のなぞを解きたい」という興味を抱き、バトンタッチを繰り返
しながら、少しずつ宇宙に近づいていきました。この日の連携授業では、これまでの人類の宇宙開発の歴史を振り返った後、現在の最前線の現場として、JAXAも運営にかかわっている国際宇宙ステーションの様子を紹介しました。 クイズに続いて、シャワーがないためタオルで体を拭いている宇宙飛行士、ねじを回そうとすると自分も回ってしまう様子、地球ではまっすぐ飛ぶはずが上に上がっていく紙飛行機などの動画も紹介されました。「どうして宇宙ではこんなことが起こるんだろう?」――生徒一人ひとりの胸にふくらんだそんな疑問は、これからの学習を探究的に進める原動力となることでしょう。
宇宙ステーションでの生活の様子を知るため、レトルトカレー、白飯など、さまざまな宇宙食も回覧された。
連携授業には3年生の4クラス約120名が参加。「地上から宇宙まで の 距 離は約100kmで、蒲原から江の島までくらい。意外と近いでしょう?」など、宇宙を身近に感じる話題も。
● 授業時間 全16時間のうち連携授業6時間
中学校3年生技術科の「計測・制御」の単元の連携授業です。生徒たちが、与えられた課題を解決するプログラムを作成し、実際に宇宙開発の現場で活躍中の探査ロボットを動かして確認する、意欲的な試みを行いました。
中学校3年生理科の「地球と宇宙」の単元の連携授業です。JAXA講師が授業を行い、宇宙開発に関するさまざまなトピックスをクイズ形式なども取り入れながら紹介して、生徒たちの探究心を刺激しました。
宇宙開発と「計測・制御」とを関連づけた授業を展開し、宇宙開発の研究を支えている技術が、先人たちの培った技術によって成り立っているものであることについて考えを深める。
連携授業のねらい
単元の導入として、宇宙の不思議や魅力に触れることで、興味・関心を高め、自ら探求しようとする態度を育成する。
連携授業のねらい
【連携授業前】中学の授業用に開発されたプログラミングソフトやロボット教材を用いて、計測・制御についてひと通り学習。
1
【連携授業後】学習を振り返り、授業で学ぶ計測・制御が、宇宙開発の現場で活躍している探査ロボットにつながっていることを確認。
4
連携授業JAXA講師の解説。火星探査ロボット撮影の写真を見せ、「皆さんにもこんな写真を撮ってもらいます」との言葉にどよめきが。
連携連連連連連連連連連連連連連携連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連 授業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業連連連連連連連連連連携授業連携連連連連連連連連連連連連連連連 授業XXXXXXXA講A講A講A講講AA講A講A講A講A講A講AA講A講A講講A講A講講A講講A講A講講A講講講A講A講A講A講A講A講A講A講講A講講講A講A講A講A講A講A講講講A講A講A講AAAAA講講AAA講A講AAAA講AA講AAAAAAAAAAAAXXXXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3
● テーマ 惑星探査ロボットを用いたプログラミング
神奈川県相模原市立旭中学校
東京都千代田区立九段中等教育学校
3年生未来のエネルギーについて
3年生無重力について知ろう岐阜県大垣市立
上石津中学校
1年生
宇宙生活から地球環境を考える
● 科目/単元 中学校3年生 技術科「計測・制御」

中学校での実践例
1110
「生徒たちはすでに、技術科の授業でロボット教材を使ってプログラムを作り、計測・制御について学んでいます。その知識と経験を活かし、探査ロボットのプログラムを作りました」 そう語るのは、JAXAと連携して授業づくりに取り組んだ阿山中学校の藤山秀公先生です。身のまわりの製品の多くに使われている計測・制御技術の学習を重視した藤山先生は、大学と協力してロボット教材を開発するなど、研究を積み重ねてきました。本物の制御ロボットのプログラムを体験できれば、制御の技術が最先端の宇宙開発の現場でも使われていると実感し、興味や知識、技術がさらに深まる――そう考えた先生は、かつてJAXAと宇宙服や宇宙食を活用した連携授業を行った経験も踏まえて準備を重ね、画期的な連携授業を実現させたのです。 迎えた授業当日、生徒たちは、メジャーを使って障害物の位置を計測し、どんなコース取りをすべきか話し合い、プログラムを作りました。自分たちの指令に従って動くロボットを見つめるワクワクした表情が、今回の連携授業の成果の大きさを雄弁に物語っていました。
【連携授業1日目】JAXA講師による、宇宙探査の目的、探査ロボットの役割や現状に関する解説と、プログラミング課題の説明。(2時間)
● 科目/単元 中学校3年生 理科「地球と宇宙」● テーマ 体感! 宇宙開発最前線!!● 授業時間 全28時間のうち連携授業1時間授業計画
砂場には障害物となるブロックなどが置かれ、ゴールまでの道のりは簡単ではない。
班ごとに走行フィールドを計測し、プログラムを作成。(2時間)
2
【連携授業2日目】プログラムに基づいて実際に走行させ、課題をクリアできたか確認(各クラス1時間×3)。JAXA講師による総括。(1時間)
Teacher’s Voice
今回の授業で課題をクリアできた班はゼロです。JAXAの方と話し、あえて難易度を高くしました。宇宙開発の現場でも、難しい課題に挑み、失敗から学んでいると伝えるためです。計測の難しさや大切さも実感してくれたと思います。興味・関心を高めるだけでなく、通常の授業では伝えきれない、そうした点に踏み込めたのも、今回の授業の大きな成果です。(藤山秀公先生)
理科
理科
総合
1回(50分)
エネルギーの現状や課題などと共に未来のエネルギーに関する最新の研究、研究者たちの取り組みなどを知ることで、理科の関連単元で学習した内容を印象づけることをねらいとして連携授業を行った。
2回(200分)
2回(175分)
理科の一環として、宇宙への興味喚起や無重力について知ることを目的とした連携授業を実施。物を落下させて無重力状態にする装置を使い、生徒たちが考えた材料で実験を行い、結果を考察した。
地球環境問題の現状について学習し、他者に科学的に説明できるようにすることなどをねらいとして、総合学習『九段自立プラン:環境』の一環として連携授業を実施。宇宙での生活や地球観測データから環境学習を行った。
学校名科目 テーマ対象 回数(総時間)授業写真 支援内容
月面に見立てた阿山中学校の校庭の砂場をJAXAの月惑星探査ローバの試作機「クアトロ」が走り、周りを取り囲む生徒たちは、その様子を真剣に見つめていました。彼らは、数人の班ごとに、「障害物を避けながらロボットを進め、取り付けられたカメラで目標物の写真を撮影し、ゴールする」という課題をクリアするべく、プログラムを作りました。
三重県伊賀市立 阿山中学校阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿山山山山山山山山山山山山山山山山山中中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校 静岡県静岡市立 蒲原中学校蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲蒲原原原原原原原原原原原原原原原原中中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校
JAXA講師の指導のもと、真剣な表情でプログラムを作る生徒たち。すでに学習用ロボットで経験しているだけに、慣れた様子で取り組んでいた。
中中中中中中中中学学学学学学学学学学学校校校校校校校校
「第2問。国際宇宙ステーションには水をどうやって運んでいるでしょうか。①地球から持っていく。②空気中の水分を集めて使う。③汚水をきれいにして使う」――宇宙や地球への興味・関心を高めるため、JAXA講師が連携授業で取り上げた切り口の1つが、こうした国際宇宙ステーションにまつわるクイズでした。 人類は、長い歴史のなかで「宇宙のなぞを解きたい」という興味を抱き、バトンタッチを繰り返
しながら、少しずつ宇宙に近づいていきました。この日の連携授業では、これまでの人類の宇宙開発の歴史を振り返った後、現在の最前線の現場として、JAXAも運営にかかわっている国際宇宙ステーションの様子を紹介しました。 クイズに続いて、シャワーがないためタオルで体を拭いている宇宙飛行士、ねじを回そうとすると自分も回ってしまう様子、地球ではまっすぐ飛ぶはずが上に上がっていく紙飛行機などの動画も紹介されました。「どうして宇宙ではこんなことが起こるんだろう?」――生徒一人ひとりの胸にふくらんだそんな疑問は、これからの学習を探究的に進める原動力となることでしょう。
宇宙ステーションでの生活の様子を知るため、レトルトカレー、白飯など、さまざまな宇宙食も回覧された。
連携授業には3年生の4クラス約120名が参加。「地上から宇宙まで の 距 離は約100kmで、蒲原から江の島までくらい。意外と近いでしょう?」など、宇宙を身近に感じる話題も。
● 授業時間 全16時間のうち連携授業6時間
中学校3年生技術科の「計測・制御」の単元の連携授業です。生徒たちが、与えられた課題を解決するプログラムを作成し、実際に宇宙開発の現場で活躍中の探査ロボットを動かして確認する、意欲的な試みを行いました。
中学校3年生理科の「地球と宇宙」の単元の連携授業です。JAXA講師が授業を行い、宇宙開発に関するさまざまなトピックスをクイズ形式なども取り入れながら紹介して、生徒たちの探究心を刺激しました。
宇宙開発と「計測・制御」とを関連づけた授業を展開し、宇宙開発の研究を支えている技術が、先人たちの培った技術によって成り立っているものであることについて考えを深める。
連携授業のねらい
単元の導入として、宇宙の不思議や魅力に触れることで、興味・関心を高め、自ら探求しようとする態度を育成する。
連携授業のねらい
【連携授業前】中学の授業用に開発されたプログラミングソフトやロボット教材を用いて、計測・制御についてひと通り学習。
1
【連携授業後】学習を振り返り、授業で学ぶ計測・制御が、宇宙開発の現場で活躍している探査ロボットにつながっていることを確認。
4
連携授業JAXA講師の解説。火星探査ロボット撮影の写真を見せ、「皆さんにもこんな写真を撮ってもらいます」との言葉にどよめきが。
連携連連連連連連連連連連連連連携連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連 授業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業連連連連連連連連連連携授業連携連連連連連連連連連連連連連連連 授業XXXXXXXA講A講A講A講講AA講A講A講A講A講A講AA講A講A講講A講A講講A講講A講A講講A講講講A講A講A講A講A講A講A講A講講A講講講A講A講A講A講A講A講講講A講A講A講AAAAA講講AAA講A講AAAA講AA講AAAAAAAAAAAAXXXXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3
● テーマ 惑星探査ロボットを用いたプログラミング
神奈川県相模原市立旭中学校
東京都千代田区立九段中等教育
学校
3年生未来のエネルギーについて
3年生無重力について知ろう岐阜県大垣市立
上石津中学校
1年生
宇宙生活から地球環境を考える
● 科目/単元 中学校3年生 技術科「計測・制御」