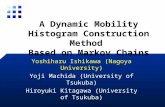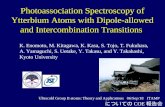薬用作物トウキ(Angelica acutiloba Kitagawa)における 葉 …...Ⅰ 緒 言...
Transcript of 薬用作物トウキ(Angelica acutiloba Kitagawa)における 葉 …...Ⅰ 緒 言...
Ⅰ 緒 言
セリ科の多年生植物トウキ(Angelica acutiloba Kitagawa)(第 1図)は,我が国における主要な薬用作物の 1つである.根を乾燥させたものは「当帰
新近畿中国四国農業研究 38-18,(2020)
2019年 8月 5日受領 2019年 10月 17日受理Correspondence: [email protected]
〔原著論文〕
薬用作物トウキ(Angelica acutiloba Kitagawa)における 葉の収穫が根の収量に及ぼす影響
米田健一・浅尾浩史*奈良県農業研究開発センター 果樹・薬草研究センター 637-0105 奈良県五條市西吉野町湯塩
*現奈良県農業研究開発センター研究開発部 633-0046 奈良県桜井市池之内
Balancing Leaf Harvest and Root Yield of Medical Plant Tōki (Angelica acutiloba Kitagawa)
Kenichi Komeda and Hiroshi Asao*
Fruit and Medical Plant Research Center, Nara Prefecture Agricultural Research and Development Center, Yushio, Nishiyoshino, Gojyo, Nara 637-0105*Present address Research and Development Department, Nara Prefecture Agricultural Research and Development Center, Ikenouchi, Sakurai, Nara 633-0046
Summary
Dried roots of Angelica acutiloba Kitagawa, an important medical plant in Japan, are used as a crude drug called tōki that is used in many traditional Chinese (Kampō) medicines. Being edible and not subject to regulation as a pharmaceutical product, the leaves are attracting attention for consumption. We investigated the effects of leaf harvest on root yield to balance production of both roots and leaves. Harvesting leaves in winter did not affect root yield, but several harvested leaves turned yellow. Harvesting all leaves from each plant in summer dramatically reduced root yield because the mortality rate rose and the root weight decreased. Harvesting a proportion of leaves from summer through autumn avoided plant death. The root yield was decreased in proportion to the total amount of harvested leaves, irrespective of the number of harvests or the amount harvested at one time. However, leaf harvest did not affect the content of dilute-ethanol-soluble root extract isolated. The results suggest that partial leaf harvest allows the production of both roots and leaves from summer through autumn. The total harvest of leaves should be adjusted to meet the respective demands for leaves and roots.
かし,これまでに葉の栽培については,韓国において肥料の配合割合やマルチ資材の種類による収量比較が実施された例があるが 2), 3),ほとんど検討されておらず,効率的な葉の生産方法を検討することが重要である. 葉の栽培方法としては,葉のみを生産する方法も想定されるが,従来の根を生産する栽培方法において同一株で葉を収穫しながら最終的に根も収穫する方法が,栽培管理の大きな変更を伴わないため生産現場の関心が高い.しかし,葉と根の双方を収穫することを想定して,葉の収穫が根に及ぼす影響について検討した調査事例はみられない. そこで本研究では,根の収穫を前提として同一株から葉を収穫する場合において,葉の収穫量や収穫時期が根の収量に及ぼす影響について調査した.また,葉と根の収量の関係および根を薬用利用する際の品質指標の一つである希エタノールエキス含量への影響について調査した.
Ⅱ 材料および方法
1 供試ほ場および栽培管理 奈良県五條市西吉野町の標高約 250 mに位置する奈良県果樹・薬草研究センター内の試験ほ場において実験を実施した.施肥は,元肥として有機配合肥料(くみあい有機 A801,㈱ジェイカムアグリ,N:P:K= 8:8:8)を窒素成分 20 kg/10 aとなるように全層施用し,追肥として上述の肥料を窒素成分が合計 20 kg/10 aとなるように,5月から 9月の間に 4回に分けて株元に施用した.また,抑草と乾燥防止のため苗の定植後に敷きわらを設置した.
(とうき)」と呼ばれ,血行促進などに効果のある生薬として様々な漢方薬に使用されている.トウキは少なくとも江戸時代から奈良県などの産地で生産されてきたといわれるが 5),生産者の高齢化や輸入品の台頭などにより生産量は減少している.しかし,近年漢方薬の効果が見直されたことで医療現場におけるニーズが高まりつつあり 10),トウキについても生産の拡大が求められている. 一般的にトウキは春に播種し,翌春まで 1年間育苗して本圃に定植する.奈良県など積雪が少ない地域では,定植した年の 12月下旬ごろに根を掘り上げ,一次乾燥,温湯を用いたもみ洗い(湯もみ)および二次乾燥を経て,翌年の春に出荷される.また,定植後に抽苔する株が一部みられるが,抽苔株は根が木質化して商品価値が無くなるため発生次第除去される. 一方,2012年の厚生労働省が定める医薬品の範囲に関する基準の改正 7)により,トウキの根は医薬品としての規制を受けるが,葉については医薬品的効能効果を標ぼうしない限り,直ちには医薬品と見なさないとされた.このことから近年,トウキの葉の食利用が注目されつつある.現在,トウキ葉茶,ハーブソルト,ドレッシングまたは葉の粉末を練りこんだ菓子などの商品が開発されている 8).また,中華料理や薬膳料理のメニューに使用される場合もある.現時点では葉の生産量はまだ少なく,市場取引ではなく,加工業者や飲食業者など実需者との相対取引で出荷される場合がほとんどであるが,トウキの生産現場では根を薬用として出荷するだけでなく,葉も食用として出荷することで収益性の向上および生産拡大につながることが期待されている.し
A B
C
第 1図 トウキ(Angelica acutiloba Kitagawa)の外観A:生育盛期,B:葉(葉身部分),C:製品根
米田ら:トウキの葉収穫が根収量に及ぼす影響 9
週間前にあたる 12月 2日に実施した.夏期全収穫区では 8月と 12月にすべての葉を収穫し,夏期 1/2収穫区では 8月には葉の 1/2を,12月にはすべての葉を収穫し,夏期無収穫区では 12月のみに葉をすべて収穫した.収穫した葉は実験室内で直ちに葉身と葉柄に切り分けて生重量を測定した.ただし,黄化葉や枯死している葉は調査対象に含めなかった.なお,抽苔株は発生時点で除去した. また,前述の供試株以外から 12月 1日に生育が揃った 58株を選び,無作為に各 29株の 2試験区に分け,冬期全収穫区と無収穫区とした.冬期全収穫区では 12月 2日に葉を全収穫し,無収穫区では葉を収穫しなかった. 12月 24日に全試験区の根を掘り上げ,直ちに雨よけハウス内で一次乾燥し,2015年 3月 4日に60℃の温湯で湯もみし,再び雨よけハウス内で二次乾燥した.5月 27日に乾燥が完了した根(以下,製品根)の重量を測定した. また,10aあたり定植苗数を 5,300株とし,活着率および抽苔株率より算出した収穫時の株数に,葉または製品根の株あたり収穫量を乗じて,10aあたり収量を計算した .
4 �夏期から秋期における葉の収量が根の収量および希エタノールエキス含量に及ぼす影響(実験2)
実験 1と同様の条件で 2015年 4月 1日にトウキ 1年生苗を定植し,以下の試験区を設定した.葉の収
2 葉の収穫方法 本研究で実施した葉の収穫方法を第 2図に示す.トウキでは株の中央部分にある生長点から葉が発生し,株の外側に広がっていく.そのため,株の内側(生長点付近)には若い葉が多く,外側には成葉や古い葉が多くなる.そこで,本研究では収穫した葉の葉齢が試験区によって偏らないように,株を直上から見て生長点を中心とした円として捉え,試験区により 1/4~4/4(全収穫)の部分円に相当する部分の葉を目測で収穫した.また,複数回収穫する場合は,収穫部分を生長点中心に反時計回りに回転させ(1/4,3/4収穫の場合は 1/4回転,1/2収穫の場合は
1/2回転),未収穫部分を収穫部分に含めるようにした.なお,収穫時にはハサミを用いて株元から葉を刈り取ったが,生長点の損傷を防ぐため,未展開の幼葉は収穫しなかった.
3 �夏期および冬期における葉の収穫が根の収量に及ぼす影響(実験 1)
県内生産者から購入したトウキ 1年生苗を 2014年 4月 17日に畦間 1.3m,株間 25 cmの一条植えで定植し,活着率は約 90%であった.8月初旬に生育が良好に揃っている株を供試株として 180株選定した.また,供試株を無作為に 3試験区に分け,夏期全収穫区,夏期 1/2収穫区および夏期無収穫区とした(60株 /区).葉の収穫は,定植から根の収穫(12月下旬)の中間にあたる 8月 14日と,根の収穫約 3
(実験 2)
無収穫
1/4 収穫
1/2 収穫
全収穫
収穫部分
(例)3/4 収穫
3/4 収穫
略号
C
Q
H
T
第 2図 葉収穫方法の模式図と収穫例円は株を直上から見たときの生長点を中心とする葉の分布範囲を示す黒塗り部分は葉を収穫する範囲を示す
新近畿中国四国農業研究 第 3号(2020)10
実験 1と同様に抽苔株は除去した.また,葉と製品根の 10aあたり収量を実験 1と同じ方法で計算した. 各区の製品根から平均重に近い根をそれぞれ 3株選び,電動ミル(IFM720G,㈱岩谷産業)で粉砕した後に,第 16改正日本薬局方 6)(以下,局方)記載の方法に基づいて希エタノールエキス含量を測定した.
Ⅲ 結 果
1 �夏期および冬期における葉の収穫が根の収量に及ぼす影響(実験 1)
各試験区における葉の収穫後の枯死株および抽苔株の発生状況を第 2表に示す.夏期 1/2収穫区と夏期無収穫区では枯死株は発生しなかったが,夏期全収穫区では供試した 60株中 11株が 8月における葉の収穫後に新たに葉が再生することなく枯死した.
穫方法(第 2図)によって T区(3/4収穫),H区(1/2収穫),Q区(1/4収穫),および C区(収穫なし)の 4区の試験区を設定した.また,収穫回数によって 8月 12日の 1回とする I区,または 8月 12日と10月 15日の 2回とするⅡ区を設定した.ただし,Q区についてのみ収穫回数を 8月 12日,9月 16日および 10月 15日の 3回とするⅢ区を設定し,計 8試験区(T Ⅰ,T Ⅱ,H Ⅰ,H Ⅱ,Q Ⅰ,Q Ⅱ,Q Ⅲおよび C)とした(第 1表).各区の供試株数は12株の 3反復として計画したが,活着不良などで欠株が発生したため(全体の活着率 81%),8月の葉の収穫開始時点で各区 8~12株の 3反復となった(第1表).収穫した葉は,実験 1と同様に収穫日ごとに葉身と葉柄に分けて各区の葉の生重量を測定した.また,12月 25日に根を掘り上げ,直ちに雨よけハウスで一次乾燥し,2016年 3月 8日に湯もみし,二次乾燥後の 5月 27日に製品根重を調査した.なお,
夏期全収穫 60 11 18.3 2 4.1
夏期1/2収穫 60 0 0.0 4 6.7
夏期無収穫 60 0 0.0 6 10.0
(検定結果)z .s.n**
全体 180 11 6.1 12 7.1
試験区 供試株数 枯死株数枯死株率
(%)抽苔株数
生存株あたり
抽苔株率
( %)
第 2表 夏期の葉収穫方法の違いが根収穫時点における枯死株数,枯死株率,抽苔株数および抽苔株率に及ぼす影響
z **,n.s.は試験区間でそれぞれ 1%水準で有意差があること,5%水準で有意差がないことを示す(Fisherの正確確率検定)
8月12日 9月16日 10月15日 反復1 反復2 反復3 合計
C 0 - - - 8 9 11 28
Q I 1 1/4 - - 8 10 12 30
Q II 2 1/4 - 1/4 9 10 11 30
Q III 3 1/4 1/4 1/4 9 10 9 28
H I 1 1/2 - - 10 9 9 28
H II 2 1/2 - 1/2 9 10 11 30
T I 1 3/4 - - 11 9 10 30
T II 2 3/4 - 3/4 8 10 12 30
収穫日ごとの葉収穫方法z
試験区y
供試株数葉の収穫回数
第 1表 実験 2における各試験区の葉収穫方法および供試株数
z葉全葉のうち収穫した葉の割合を示す,-は収穫しなかったことを示すyアルファベットは葉の収穫方法(C:無収穫,Q:1/4収穫,H:1/2収穫,T:3/4収穫)を表し,ローマ数字は収穫回数を表す
米田ら:トウキの葉収穫が根収量に及ぼす影響 11
は夏期全収穫区では 1,426 kg,夏期 1/2収穫区で 1,286 kg,また夏期無収穫区では 636.6 kgと計算され,夏期無収穫区が他区よりも収量が大きく劣る結果となった.一方製品根収量については夏期全収穫区では 249.2 kg,夏期 1/2収穫区で 470.8 kg,また夏期無収穫区では 545.0 kgと試算され,夏期全収穫区が他
なお,枯死株の割合について試験区間で有意差が検出された(Fisherの正確確率検定,p< 0.01).また,抽苔株については試験区間での発生率の差は小さく,有意差は検出されなかった(Fisherの正確確率検定,p< 0.05). 8月と 12月における葉の平均収穫量(株当たり生重量)を第 3図に示す.8月は夏期全収穫区では葉身 117.8 g,葉柄 86.9 gであり,夏期 1/2収穫区では葉身 77.3 g,葉柄 55.4 gであった.一方,枯死株と抽苔株を除いた 12月における葉の平均収穫量は夏期全収穫区では,葉身 60.2 g,葉柄 46.8 g,夏期 1/2収穫区で葉身 71.1 g,葉柄 67.0 g,また夏期無収穫区では葉身 72.7 g,葉柄 71.0 gとなった.なお,12月に収穫した葉では黄化葉や枯死葉が 8月よりも多く発生し,収穫できた葉の葉色も 8月には濃い緑であったのに対して 12月はやや黄緑色に近い葉色のものが多くなった. また,株当たり平均製品根重は,夏期全収穫区では 68.9 g,夏期 1/2収穫区で 106.3 g,夏期無収穫区では 123.0 gとなり,8月の葉の収穫量が多いほど製品根重が有意に小さくなった(第 4図). 以上の結果に基づいて,葉と製品根の 10 a当たり収量を計算したものを第 3表に示す.葉の合計収量
050
100150200250300
050
100150200250300
050
100150200250300
葉収穫量(
g/株)
合計
8 月 14 日収穫 12 月 2 日収穫
夏期全収穫区 夏期 1/2 収穫区 夏期無収穫区 夏期全収穫区 夏期 1/2 収穫区 夏期無収穫区
n=60
n=60 n=47 n=56 n=54
n=60 n=60
n=60
葉収穫量(
g/株)
葉収穫量(
g/株)
:葉柄
:葉身n=60
夏期全収穫区 夏期 1/2 収穫区 夏期無収穫区
試験区
試験区 試験区
第 3図 夏期の葉収穫方法の違いが株あたり葉収穫量に及ぼす影響2014年 8月 14日に各試験区の葉収穫方法(第 2図)に基づき葉を収穫し,12月 2日に全ての葉を収穫した縦棒は標準誤差を示すn:株数
0
50
100
150
321
製品根重(
g/株)
a
c b
夏期全収穫区 夏期 1/2 収穫区 夏期無収穫区
n=47
n=56 n=54
試験区
第 4図 夏期の葉収穫方法の違いが収穫根乾燥後の製品根重に及ぼす影響
根は 2014年 12月 24日に掘り上げ,一次乾燥,湯もみ作業および二次乾燥を経て 2015年 5月 27日に製品根重を測定した縦棒は標準誤差を示すn:株数異なるアルファベット間で有意差があることを示す(Tukey,p< 0.05)
新近畿中国四国農業研究 第 3号(2020)12
区よりも収量が大きく劣る結果となった. また,冬期全収穫区では抽苔株や枯死株は発生せず,無収穫区との製品根重の差はほとんど無く,有意差も検出されなかった(t検定,p< 0.05)(第 5図).
2 �夏期から秋期における葉の収穫量が根の収量および希エタノールエキス含量に及ぼす影響(実験 2)
いずれの試験区についても葉の収穫後に枯死株は発生しなかった(第 4表).抽苔株は,いくつかの試験区で最終の葉収穫の後に発生したが発生数は少なく,試験区間での有意な差はみられなかった(Fisherの正確確率検定,p< 0.05)(第 4表).また,試験区ごとに 10 a当たりの葉と製品根の収量を算出したところ,葉身と葉柄の合計収量はいずれも最大は T Ⅱ区でそれぞれ 421.6 kg,278.6 kgとなり,最小は Q Ⅰ区でそれぞれ 75.7 kg,39.1 kgなった(第5表).また,製品根の収量は葉の合計収量が少ないほど大きくなる傾向がみられ,C区で最大の 348.1 kg,T Ⅱ区で最小の 212.3 kgとなった(第 5表).なお,各試験区における葉身と葉柄の合計収量と製品根の収量を散布図にプロットしたところ,合計収量と製品根の収量の間にはほぼ直線的で有意な負の相関関係(r= -0.967,相関係数,p< 0.01)がみられた(第 6図).
計合
柄葉
身葉
計合
柄葉
身葉
計合
柄葉
身葉
夏期
全収
穫4,
770
624.
341
4.3
1038
.687
427
721
7.7
169.
438
7.1
842.
158
3.7
1425
.724
9.2
夏期
1/2収
穫4,
770
409.
526
4.3
673.
80
339
315.
229
6.8
612.
072
4.7
561.
012
85.8
470.
8
夏期
無収
穫4,
770
0.0
0.0
0.0
033
932
2.2
314.
463
6.6
322.
231
4.4
636.
654
5.0
12月
2日葉
収量
(生
重kg
/10
a)合
計葉
収量
(生
重kg
/10
a)製
品根
収量
kg/1
0 a
試験
区活
着株
数z
(株
/10
a)
8月15
日葉
収量
(生
重kg
/10
a)枯
死株
数(株
/10
a)
抽苔
株数
y
(株
/10
a)
第3表 夏期の葉収穫方法の違いが
10 a当たり葉収量と製品根収量に及ぼす影響
z定植数
5,30
0株
/10
a,活着率
90%として計算した
y生存株あたり抽苔率は一律
7.1%として計算した(第
2表参照)
製品根重(
g/株)
0
50
100
150
21冬期全収穫区 無収穫区
n.s.
n=29 n=29
試験区
第 5図 冬期の葉収穫方法の違いが収穫根乾燥後の製品根重に及ぼす影響
冬期全収穫区では 2014年 12月 2日に全ての葉を収穫した根は 2014年 12月 24日に掘り上げ,一次乾燥,湯もみ作業および二次乾燥を経て2015年 5月 27日に製品根重を測定した縦棒は標準誤差を示すn:株数n.s.:有意差が無いことを示す(t検定,p< 0.05)
米田ら:トウキの葉収穫が根収量に及ぼす影響 13
また,製品根の希エタノールエキス含量には試験区による差はほぼみられず,いずれの供試株においても 50%前後で日本薬局方に定められる品質基準である 35%を上回っていた(第 7図).
3 �葉の収穫方法と収穫時期が葉の収量における葉身収量の割合に及ぼす影響
実験 1および 2の結果に基づき,各試験区における葉の収量における葉身収量が占める割合(葉身収量 /(葉身収量+葉柄収量))を第 6表と第 7表に示す.葉の収穫方法による大きな差はみられなかった.一方,葉の収穫時期については,実験 1の 8月収穫,
0.00082C3.31003IQ7.62003IIQ0.00082IIIQ0.00082IH3.31003IIH3.31003IT0.00003IIT
(検定結果)y n.s.
全体 1.250432
数株死枯区験試 抽苔株数z 抽苔株率
(%)供試株数
第 4表 夏期から秋期の葉収穫方法の違いが根収穫時点における枯死株数,抽苔株数および抽苔株率に及ぼす影響
z抽苔株は全て最終の葉収穫後に発生したy n.s.は試験区間で有意差が無いことを示す(Fisherの正確確率検定,p< 0.05)
葉身 葉柄 葉身 葉柄 葉身 葉柄
C 4,293 90 - - - - - - - - 348.1 a
Q I 4,293 90 75.7 39.1 - - - - 75.7 c 39.1 c 327.3 ab
Q II 4,293 90 89.7 43.5 - - 80.4 69.6 170.1 bc 113.1 bc 314.8 ab
Q III 4,293 90 98.9 51.3 87.7 58.3 62.1 45.9 248.7 b 155.5 ab 272.8 ab
H I 4,293 90 149.7 84.1 - - - - 149.7 bc 84.1 bc 312.7 ab
H II 4,293 90 142.9 79.3 - - 138.4 116.4 281.2 b 195.7 ab 260.7 ab
T I 4,293 90 225.1 127.1 - - - - 225.1 b 127.1 bc 309.8 ab
T II 4,293 90 231.4 125.2 - - 190.2 153.3 421.6 a 278.6 a 212.3 b
試験区 活着株数z
抽苔株数y 製品根収量
x
(kg/10 a)
葉収量(生重kg/10 a)8月15日 9月16日 10月15日
葉身 葉柄
合計x
第 5表 夏期から秋期の葉収穫方法の違いによる 10 a当たり葉収量と製品根収量
z定植数 5,300株 /10 a,活着率 81%として試算したy抽苔率は一律 2.1%として試算した(第 4表参照)x異なるアルファベット間で有意差があることを示す(Tukey,p< 0.05)
0
100
200
300
400
0 200 400 600 800
C Q I
H I
T I
H II
合計葉収量(kg/10 a)
Q II
Q III
T II Y=-0.1938x+356.94 r=-0.967**z
製品根収量(
kg/1
0 a)
第 6図 夏期から秋期の合計葉収量と製品根収量の関係z有意な相関関係があることを示す(p< 0.01)
新近畿中国四国農業研究 第 3号(2020)14
Ⅳ 考 察
実験 1において,8月に株の葉をすべて収穫した区では枯死株が発生したが,12月に葉をすべて収穫した区では枯死株は発生しなかった.このことから,夏期における葉の収穫が株の枯死を誘発すると考えられた.しかし,葉を半分のみ収穫した区では枯死株が発生しなかったことから,葉を部分的に残すことで枯死を回避できることが示唆された.また,実験 2において 8月と 10月に葉の 3/4を収穫した T Ⅱ区でも枯死株が発生しなかったことから,1/4程度の葉を残すことで枯死を回避できる可能性が示唆された.枯死の原因については,葉が全て除去されることによって,生長点付近が直射日光に長期間晒され,何らかの生理障害が引き起こされた可能性などが考えられる.しかし,本研究では詳しく調査しておらず原因は不明であり,今後の課題である.また,実験 1,2の双方において試験区による抽苔株率の差がみられなかった.トウキが定植後に抽苔するかどうかは苗の大きさに影響されることが報告さ
実験 2の 8月収穫および 9月収穫では葉身収量の割合は 60%以上であったが,実験 1の 12月収穫と実験 2の 10月収穫では 50数%となり,収穫時期が遅いと葉身収量の割合が低下する傾向がみられた.
8月15日収穫
12月2日収穫
夏期全収穫 3.651.06
夏期1/2収穫 5.158.06
夏期無収穫 - 50.6
試験区葉身収量の割合(%)
z
第 6表 実験 1における葉収穫方法と収穫日が葉収量に対する葉身収量の割合に及ぼす影響
z第 3表の結果に基づき,葉身収量 /(葉身収量+葉柄収量)として計算した
8月16日収穫
9月16日収穫
10月15日収穫
Q I 66.0 --
Q II 67.3 - 53.6
5.751.068.56IIIQ
H I 64.0 --
H II 64.3 - 54.3
T I 63.9 --
T II 64.9 - 55.4
試験区葉身収量の割合(%)
z
第 7表 実験 2における葉収穫方法と収穫日が葉収量に対する葉身収量の割合に及ぼす影響
z第 5表の結果に基づき,葉身収量 /(葉身収量+葉柄収量)として計算した
0
20
40
60
80
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9希エ
タノ
ール
エキ
ス含
量(
%)
T I T II H I H II Q I Q II Q III C
試験区
第 7図 夏期から秋期の葉収穫方法の違いが製品根の希エタノールエキス含量に及ぼす影響
各試験区それぞれ 3株について第 16改正日本薬局方に基づいて測定した点線は日本薬局方記載の基準である 35%を示す試験区間の有意差なし(Kruskal-Wallis検定,p< 0.05)
米田ら:トウキの葉収穫が根収量に及ぼす影響 15
根の収量との間に直線的な負の相関関係がみられ,収穫時期や一回に収穫する量に関わらずに葉の合計収量に比例して製品根の収量が低下することが示唆された.また,葉の食利用においては,トウキ葉茶に加工する時など,葉身と葉柄の両方を使用する場合があるが,飲食店で生食用として利用する場合などには葉身のみを利用する場合もある.葉の収量に占める葉身収量の割合を比較すると,葉の収穫方法が及ぼす影響は小さかったが,収穫時期が遅いほど葉身収量の割合は低くなる傾向がみられた.さらに詳細な調査が必要であるが,葉身のみを利用する場合は,収穫時期によって葉の収量に対する葉身の歩留まりが変化することに留意する必要があると考えられる. 一方,実験 2において製品根の希エタノールエキス含量について調査したところ,試験区による差は認められず,全調査株について局方で規定されている基準である 35%を上回っていた.このことから,希エタノールエキス含量については,葉を夏から秋に収穫しても根の出荷上問題ないと考えられる.生薬の種類によっては有効成分の含有基準が局方に規定されている場合があるが,トウキでは特定の成分基準は記載されていない.しかし,リグスチリドやフェルラ酸などが血行促進などの効能に関わっていると考えられており 4),今後研究が進展するにつれてさらに多くの薬効成分が見いだされる可能性もある.よって局方に成分基準が記載された場合は,葉の収穫が及ぼす影響について改めて調査・検討する必要がある. 現在トウキの葉は利用が検討され始めてから日が浅く,相対取引がほとんどのため,出荷価格や出荷量は取引先によって大きく異なる.そのため,収益性について考察するのは非常に困難である.ただし,実験 2の結果より,葉を収穫しない C区と葉を最も多く収穫した T Ⅱ区で比較してみると,C区では根の収量が 348.1kg/10a,T Ⅱ区では根の収量が212.3kg/10aで葉身と葉柄を合せた生葉の収量が700.2kg/10aであるから,生葉の単価が根の 19.4%以上あれば,T Ⅱ区の方が C区よりも粗収益が多くなる.筆者の知る範囲では,トウキ葉は生葉 1kg当たり 500円程度で出荷される事例もあれば,少量ながら飲食店での生食用にさらに高い単価で出荷された
れており 1),大きな苗が低温に遭遇することで花芽分化が引き起こされると考えられている.そのため,抽苔の有無は苗の時点でほぼ決定しており,定植後の葉収穫は影響しなかったと推測される. 実験 1において 8月に葉を収穫した区では収穫しない区と比較して製品根重が低下した.一方,12月のみ葉を収穫した区では製品根重の低下はみられなかったことから,葉の収穫は 8月には製品根重に影響するが,根の収穫直前の 12月には影響しないと考えられる.トウキでは 9~10月頃に急速に根が肥大することが報告されている 9).今回の葉を収穫した 12月初旬では転流がほぼ完了しており,根の収穫までの期間も短いため,製品根重に影響を及ぼさないと推察される.このことから冬期における葉の収穫は根に影響を与えない収穫方法として有望であるが,12月に収穫した葉は黄化が進んでいるものが多いため,8月に収穫した葉と比較して収穫後のロスが多く,選別作業も煩雑であった.例えば葉の乾燥粉末を練りこんだ食品への利用など,黄化葉の混入が問題となりにくい用途への使用について検討していく必要がある. また,トウキには形質が遺伝的に固定された育成品種がないため,生育のばらつきが大きくなる.しかし,実験 1では栽培の途中に生育が良好な株を選んで供試しているため,実際の生産現場より葉や根の 10a当たり収量がやや多く見積もられる点については注意する必要があるが,試験区間の比較は可能であると考えられる.夏期全収穫区では葉の収量は他区よりも多いが,1株当たり製品根重が小さくなることに加えて枯死株が発生するため,製品根の収量は夏期無収穫区の約 46% と大きく劣る結果となった.一方,夏期 1/2収穫区では葉の合計収量は夏期全収穫区の約 90%となり,製品根の収量においても夏期無収穫区の約 86%を確保できる結果となった.このことから,葉と根の両方を生産する栽培方法としては,夏期に葉をすべて収穫するのではなく,部分的に収穫する方が実用的であると考えられた. そこで実験 2では夏期から秋期の葉の部分収穫方法を変え,製品根の収量への影響をさらに調査した.その結果,本研究で試行したように,8月から 10月にかけて葉を収穫する場合は,葉の合計収量と製品
新近畿中国四国農業研究 第 3号(2020)16
は無収穫区の約 86%となった.なお,12月における葉の収穫は製品根の収量に影響を及ぼさなかったが,黄化葉も多く発生した.また,2015年 8月から10月に全体の 1/4~3/4の葉を 1~3回収穫したところ,製品根の収量は一度に収穫する量や収穫回数に関わらず,葉の合計収量に比例して低下したが,現状の単価では葉を収穫することで全体の収益が向上する場合もあり得ることが示唆された.なお,葉の収穫が希エタノールエキス含量に及ぼす影響は見られなかった.以上の結果,トウキにおいて葉と製品根の両方を効率的に生産する方法としては,夏期~秋期に部分的に葉を収穫する方法が有望であることが示唆されたが,葉の収穫量は生産者の販売状況に合わせて調節すべきと考えられた.
引 用 文 献
1) 浅尾浩史:ヤマトトウキの発芽と抽苔に及ぼす要因,奈良県農業総合センター研究報告,41,34-35,2010.
2) Choi, S. K.: Effect of Sta-Green on leaf and stem production of Angelica acutiloba. Plant. Res., 8, 13-16, 2005a.
3) Choi, S. K.: Study on leaf and stem production of Angelica acutiloba by mulching materials, Plant.Res., 8, 27-31, 2005b.
4) Fukuda, K., K. Murata, K. Itoh, M. Taniguchi, M. Shibano, K. Baba, M. Shiratori, T. Tani and H. Matsuda: Fibrinolytic activity of ligustilide and pharmaceutical comparison of Angelica acutiloba roots before and after processing in hot water, J. Trad. Med, 26, 210-218, 2009.
5) 福田浩三・村田和也・松田秀秋・谿 忠人:大和当帰の栽培生産の歴史と現状,薬史学雑誌,44,10-17,2009.
6) 厚生労働省,第十六改正日本薬局方,p. 104,2011.
7) 厚生労働省:医薬品の範囲に関する基準の一部改正について(平成 24年 1月 23日,薬食発0123 第 3 号 ),https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7999&dataType=1&pageNo=1.
8) 奈良県:大和当帰 根は薬,葉は食す,http://
事例もある.また,根については薬用作物産地支援協議会が公表している 2016年度の調査結果によると,参考価格帯は製品根 1kg当たり 880円から 1,800円となっている 12).そこで,仮に生葉の 1kg当たり単価を 500円とすると,最も高い製品根単価の 1,800円と比較しても 27.8%となり,T Ⅱ区の方が C区よりも粗収益が多くなる計算となる.このことから,全量出荷できた場合は,葉の収穫によって根の収量が低下しても,根のみ出荷する場合と比べて全体の粗収益は向上する場合があることが示唆される.ただし,現時点では各生産者の取引先によって葉や根の単価や出荷可能量などは大きく異なるため,生産者がそれぞれの取引状況にあわせて,収益が最大となるように葉の収穫量を調整することが重要である.そのため,今後,葉の収量と根の収量の関係についてさらに詳細に調査する必要があると考えられる. 薬用作物は,医薬品原料として出荷する場合は出荷先が限られ,厳しい品質基準も課せられる点が他の農作物と異なることが指摘されている 11).一方,本研究におけるトウキ葉のように,食利用の場合は出荷先の制限も少なく,加工品への利用などによる6次産業的な展開も可能となる.このことから,薬用作物において食利用と薬用利用を組み合わせることにより,安定的な収益が確保され,生産振興につながる可能性があると考えられるため,今後も検討を進めていきたい.
Ⅴ 摘 要
薬用作物トウキ(Angelica acutiloba Kitagawa)は,湯もみを経て乾燥した根(製品根)が生薬として用いられるが,近年は葉を食利用する取り組みが注目されている.そこで,葉の収穫が製品根の収量に及ぼす影響について調査した.夏期全収穫区,夏期1/2収穫区および夏期無収穫区を設定して 2014年 8月に葉を収穫し,さらに 12月に葉を全収穫したところ.夏期全収穫区では葉の 10 a当たり収量は最大となったが枯死株が発生し,根も小型化するため製品根の収量が夏期無収穫区の約 46%と大きく減少した.一方,夏期 1/2収穫区では枯死株は発生せず,葉の収量は夏期全収穫区の約 90%で製品根の収量
米田ら:トウキの葉収穫が根収量に及ぼす影響 17
11,12-16,2014.11) 高橋貴與嗣:薬用作物の生産拡大に向けての課題,農業,1549,40-49,2011.
12) 薬用作物産地支援協議会:(平成 29年度地域相談会,参考資料 3-1)日本産生薬購入価格帯および増産を希望する会社数,http://www.yakusankyo-n.org/document/2017/05.htm.
www3.pref.nara.jp/sangyo/yamatotouki/.9) 頼 宏亮・林 文音・元田義春・玉井富士雄・田辺 猛:トウキ(当帰)の生産ならびに品質向上に関する研究(第 3報),生育時期による品種別トウキの生育,収量およびエキス,Ligustilide含量の変化,生薬学雑誌,46,365-371,1992.
10) 白井正人:薬用作物について,農耕と園芸,
新近畿中国四国農業研究 第 3号(2020)18











![CHUCK Kitagawa kraftmanövrerade chuckar och cylindrar samt … · 2018-11-01 · [ 1-2 ] KITAGAWA CHUCK 1 Trebackig kraftchuck med hög spännkraft Kraftchuck med genomgång B-200](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5e968c75050dff126f6af5c2/chuck-kitagawa-kraftmanvrerade-chuckar-och-cylindrar-samt-2018-11-01-1-2-.jpg)