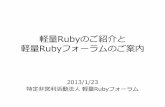渡良瀬川上流の足尾荒廃地における 官民協働による緑化活動の成果 ·...
Transcript of 渡良瀬川上流の足尾荒廃地における 官民協働による緑化活動の成果 ·...

1
渡良瀬川上流の足尾荒廃地における
官民協働による緑化活動の成果
川村 尚子
関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 足尾砂防出張所 (〒321-1513 栃木県日光市足尾町向原5-17)
渡良瀬川河川事務所では20年間にわたり「NPO法人足尾に緑を育てる会」と連携し、砂防
事業の広報の一環として、全国から集まるボランティアの緑化活動を支援している。かつて足
尾は日本一の銅山として栄えた一方で、足尾鉱毒事件や荒廃地の形成などにより「日本の公害
の原点」と呼ばれてきたが、近年、環境を考える聖地として注目され、全国から多くの市民や
学生が訪れており、官民協働の先駆けとして広報と環境学習・防災教育を関連づけた緑化活動
をサポートしている。当初より基本コンセプトを明確化しサポートを継続したことにより、 広報としての高い成果のみならず、砂防事業の効率的な推進や、地域活性化に寄与している。
キーワード 砂防事業,官民協働,環境学習・防災教育の支援,継続は力なり,広報効果
1. はじめに
(1) 渡良瀬川の概要
渡良瀬川は、日本一の大河『利根川』の最も大きな
支流で、日本百名山の皇海山(標高 2,144m)を源流と
し、最上流部では栃木県日光市の足尾地区を流れ、栃木
県・群馬県の山間部及び市街地を流下し、足尾銅山と関
わりの深い渡良瀬遊水地を経て利根川に合流する一級河
川である(図-1)。
図-1 位置図
(2) 日光市足尾地区の概要
日光市足尾地区はかつて日本一の銅山として栄え、明
治の日本の近代化や産業発展に大きく貢献した反面、製
錬所から排出される亜硫酸ガス等の影響により、24㎢以
上の広範囲にわたる荒廃裸地が形成され「日本の公害の
原点」と呼ばれ、土砂災害や洪水発生の大きな原因とな
っていた。
(3) 足尾の直轄砂防事業と現状
足尾地区では1937年より直轄砂防事業が着手されたが、
1947年のカスリーン台風による未曾有の大災害を契機に、
貯砂量が日本最大級の「足尾砂防堰堤」をはじめとした
大規模な砂防堰堤の整備を進めてきた。
写真-1 足尾砂防堰堤と荒廃した周辺状況
スカイサン

2
また、1987年からは「大畑沢緑の砂防ゾーン」におい
て、土砂の発生源となっている荒廃斜面を緑に復元する
山腹工に着手し、現在は足尾砂防堰堤周辺の山腹緑化に
力を入れている。
足尾砂防堰堤の周辺は、1996年に銅親水公園として整
備され、2000年には日光市営の「足尾環境学習センター」
がオープンしている(写真-1)。
(4) 現在の足尾地区
1973年に銅山が閉山されて以降、急激な過疎化が進み
最盛期には約5万人の人口を誇っていたが、現在は1/25
の約2千人まで減少している。一方、全国から環境問題
等に興味を抱く多くの市民や学生が来訪する「環境学習
の聖地」となっている(写真-2)。
写真-2 環境学習のため足尾を訪れる団体の様子
2. NPO法人「足尾に緑を育てる会」
(1) NPO法人の概要
環境問題が大きな社会問題となっている中、住民の間
で足尾の山に緑を取り戻そうという気運が生まれ、既存
の市民活動グループである「わたらせ川協会」など5団
体が集まり、“足尾の山に百万本の木を植えよう”をス
ローガンに掲げ、1996年5月に「足尾に緑を育てる会」
が設立され、2002年にはNPO法人となった(図-2)。
図-2 NPO法人の活動年表
(2) 主な活動内容
年間を通じてボランティア活動の受入や、植樹エリア
の維持管理等を定期的に実施しており、特に4月の第4土
日の2日間に渡り「春の植樹デー」を主催し、全国から
集まる植樹ボランティアによる緑化活動を21年間サポー
トしている(写真-3)。
写真-3 NPO法人の主な活動内容
また、21世紀を担う子供たちへの環境学習の支援とし
て実施している「体験植樹」では、日光へ修学旅行等に
より訪れる、主に首都圏の小学校からの要請に基づき、
年間約150団体、約1万人の子供達に対し効果的な体験型
環境学習の支援を実施している(写真-4)。
写真-4 体験植樹の様子
(3)植樹活動の推移 「春の植樹デー」と「体験植樹」によるボランティア活
動の推移をグラフ化すると、活動の輪が右肩上がりに増
加しており、これまでの参加者を合計すると約15万人、
植樹本数の合計は約19万本となっている(図-3)。
アカガネ

3
図-3 植樹活動の推移
3. 官民協働の基本的な考え方
(1)基本コンセプト
連携当初より「基盤整備(山腹基礎工)は国土交通
省」、「植樹はボランティア活動」と位置づけ、砂防工
事で基盤整備した安全な植樹場所を、全国から集まるボ
ランティアの活動拠点としてNPO法人に提供することに
より、環境問題等に関心のある市民のニーズに応えつつ、
効率的な砂防事業の推進と、確実な緑の復元に寄与して
いる(図-4)。
図-4 足尾の緑化活動基本コンセプト
植樹する樹種の選定や植栽方法なども含めて、全て
NPO法人の主体性に任せ、自由に活動できる環境作りを
実施しており、国土交通省は縁の下の力持ちに徹するこ
とが、リピーターの獲得や口コミによる参加者の増加に
つながっている。
(2)効果的な体験植樹の指導
環境学習及び防災教育の観点から如何に充実した体
験植樹にするかが重要である。そこで植樹の前の30分間
は、「なぜ足尾で木を植えるの?」を理解してもらうた
め、公害の発生原因やその影響、荒廃裸地による災害の
発生や砂防事業の必要性、破壊した自然の復元の困難さ
等を「紙芝居」で説明してから、その後約1時間半程度
かけて植樹を行っている(図-5)。
図-5 効果的な体験植樹の指導
(3)工夫した点 説明者により話の内容やレベルに差があってはならな
いので、一定のサービス水準を確保するために導入した
「紙芝居」が、先生方のアンケート結果では絶賛され、
子供達の作文からも大きな効果が伺える。 また、体験植樹参加者全員が作業に携われるよう、参
加者を穴掘り・苗木設置・水やりの班に分けて作業を分
担させるなど、きめ細やかな配慮を行っている。
4. 20年間に及ぶ官民協働の成果
(1) 緑化活動の成果
植樹への参加者が年々増加することにより、渡良瀬川
河川事務所の山腹工計画箇所35㏊のうち、約74%の範囲
がボランティアの力で緑化された。
その結果、多様な植生により緑が復元し、大雨による
荒廃裸地からの土砂流出が抑制されるとともに、野鳥や
小動物などが生息する生態系豊かな森に回復しつつある。
官民協働の原点である「大畑沢緑の砂防ゾーン」は、
ハゲ山だった面影はなく秋には見事な紅葉を楽しめるま
でになった(写真-5)。
写真-5 緑化活動の成果(大畑沢)

4
(2) 取り組み手法の検証
体験植樹に参加した学校の先生方へのアンケート結果
を解析すると、紙芝居による説明が非常に好評であり、
親切丁寧な対応に多大な感謝の言葉を頂いている。
その結果を裏付けるようにリピーター校が非常に多く、
先生方の口コミにより周辺校の新規申し込みも拡大して
おり、おもてなしの心が伝わっている(図-6)。
図-6 体験植樹のアンケート(先生)
また、体験植樹に参加した子供達の感想文を解析する
と、足尾の環境破壊が自然災害に繋がり、それを防止す
るために木を植えることを学習し、砂防事業や国交省の
事業の重要性を理解し、紙芝居に込めた思いがしっかり
と子供達に伝わっているのが分かる(図-7)。
図-7 体験植樹の感想文(子供)
(3)天皇皇后両陛下のご視察
2014年5月22日(木)両陛下が「官民協働による足尾
の緑化活動」の成果を私的旅行でご視察され、NPO法人
の会長がご説明した。戦時中に足尾荒廃地をご覧になっ
ていた天皇陛下が、ボランティアの活躍で緑が再生した
とお知りになり、ご視察が実現したものである。下野新
聞の見出しには「足尾の緑、再生に感慨」、「植樹活動
の苦労気遣う」と掲載されており、両陛下から頂いた労
いのお言葉が、官民協働の一層の励みに繋がっている。
5. 今後の課題と方針
(1)今後の課題
ボランティア参加者の増加に伴い安全な活動エリアの
確保が年々厳しくなっているとともに、植樹完了エリア
の拡大に伴い、除草などボランティアだけでは維持管理
が困難な状況にある。
また、密植したまま成長した樹木の間伐は良好な森づ
くりには不可欠であるが、一本一本にボランティアの気
持ちがこもっているため、安易に伐採が出来ない。
(2) 今後の方針
これまで植樹をメインに官民協働による緑化活動を実
施してきたが、今後は植えた苗木の維持管理が非常に重
要となる。
たとえば、幼木の手入れ(除草、追肥、補植など)や
鹿による食害防止対策としてのネットの補修など、今後
は安全確実な維持管理について、役割分担を含めた一層
の連携が必要と考えている。
また、危険な作業を伴う間伐については、その範囲や
樹木の剪定について、NPO法人と密接な合意形成を図り
ながら、砂防事業の中で着実に実施する必要がある。
6. おわりに
一度破壊した足尾の山を元に戻すのは数百年単位の年
月が必要であり、NPO法人が掲げる百万本の木を植える
目標達成はまだ先であるが、全国から注目を浴びる官民
協働の緑化活動を更に推進することが期待されている。
これまでの連携により、質の高い環境学習や効果的な広
報活動のみならず、近年話題となっている「防災教育」
の観点からも非常に有益であると言える。
今年で21回目となる「春の植樹デー」も、2日間で全
国から老若男女約1,850人が参加し、約7,000本の苗木が
植栽されている(写真-6)。
写真-6 今年の「春の植樹デー」の様子(2016年4月)
渡良瀬川河川事務所では、砂防事業を通じて地域活性
化にも大きく貢献している官民協働の緑化活動を、今後
も積極的に推進していきたい。