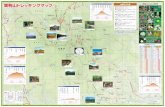身体的虐待の防止及び...
Transcript of 身体的虐待の防止及び...

身体的虐待の防止及び身体拘束・行動制限の廃止
社会福祉法人 豊寿会
障がい者支援施設 妙光園
サービス管理責任者 大館 章子

この資料は、平成30年8月7日、8日に公益社団法人
日本発達障害連盟が行った、「平成30年度障害者虐
待防止・権利擁護指導者養成研修」の資料を基に作
成しています。

身体拘束について・障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を
拘束すること」は身体的虐待とされています。
・身体拘束・行動制限が日常化すると、そのことがきっかけ
となって障害者に対する身体的虐待や心理的虐待に至って
しまう危険があります。
・身体拘束は、行動障害のある障害者への支援技術が十
分でないことが原因の場合が多いので、やむを得ず身体拘
束をする場合であっても、その必要性を慎重に判断するとと
もに、その範囲は最小限にしなければなりません。また、判
断にあたっては適切な手続きを踏むとともに、身体拘束の
解消に向けて道筋を明確にする必要があります。

身体拘束…本当にやむを得ない(条件)
・切迫性
ご本人の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
・非代替性
身体を拘束する以外安全を確保する手段がない
・一時性
身体拘束をする事が一時的な手段
・他の方法や安全など検討したうえで「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たし、さらにご本人や家族の同意を得た場合に認められている。

身体拘束…本当にやむを得ない(判断)
①組織による決定(決定を行う組織体制、緊急の判断の条件を明記)
②個別支援計画への記載(個別支援会議で慎重に議論し詳細に記載)
③本人・家族への十分な説明(承諾書)
④必要な事項の記録(客観的な拘束状態の記録を残す)
★身体拘束の範囲は職場内で、詳細までしっかりと詰めておくこと

身体拘束とは…
①車いすやベッドなどに縛り付ける。
②手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける。
③行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
④支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限
する。
⑤行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させ
る。
⑥自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。

身体的虐待・行動制限がなぜ起きるのか?
・利用者が、興奮して他の利用者を叩く、噛みつくなどの行為がある時や、自分自身の頭や顔を強く叩き続けるなどの行為がある時には、やむを得ず利用者の身体を拘束したり居室に隔離したりするなどの行動制限をしているかもしれません。しかし利用者の問題行動が続くと、このような行動制限が日常化してしまう。問題行動をやめさせることが重要視され暴力や体罰によって止めさせることに必死になる。繰り返されることで、エスカレートし身体に傷や痣、痛みを与える行為、身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制したりするなど・・・エスカレートした際には職員も「誰のための、何のための」という制限当初の気持ちが違ってきている事に気付けなくなる。
身体拘束の定義よりも支援者の意図している事が伝わらない事の要因があるかも??

行動障害が激しい利用者と虐待防止
大きな虐待事件の背景には、言葉によるコミュニケーションが難しい自
傷や他傷などの行動障害が顕著な自閉症の方が存在している。
平成26年の調査から、虐待を受けた障害者の概ね3人に
1人から4人に1人は何らかの行動障害がある。行動障害は
虐待を受けるリスクが「高い」と考えてよい。
(強度行動障害支援者養成研修より)
身体拘束・行動制限も身体的虐待である。

どうして伝わらない?どうしてわかってくれない?
職員から見える行動
・Sさんが、突然大声を出し他者
の目の前を走る。周囲の利用者を叩いてしまう。周囲も落ち着かなくなり、ロッキングしたり声を出し始めたため、Sさん
に居室に入ってもらったがパニックが激しくなったため、一時的に居室に施錠をした。
職員から見えない利用者の要求
・Sさんが、大声を出すには突然
ではなく職員が気づけていない原因があった。原因の訴えについて理解してもらえず、居室に連れて行かれた。訴えが伝わらない事や居室に連れて行かれ、状況が分からなくなり大混乱(意図と違う状況になりパニックになった)

どうして伝わらない?どうしてわかってくれない?
職員から見える行動
・職員が対応に困難な人
・何をしたいのか理解できない
・他の利用者に連鎖してみんな調子が悪くなる
職員から見えない利用者の要求
・困っている人
・適切な表現の仕方を知らない。過去の経験で表出するしかない(合っている、間違っている判断できない)
・どうしたら伝わるのか想像が出来ない。
この考え方の違いは特性からくるもの。職員によって対応が違えば利用者はさらに混乱する。

行動障害の利用者と虐待防止
≪行動障害をどうとらえるか≫
・行動障害は本人の「わからない・伝わらない」の積み重ねからくる訴え
・「問題行動と呼ばれる行為」
自傷・他傷行為、破壊行為、奇声、異食、不潔行為など
やりたくてやっている訳ではない。本人の意思表明と考えられる。
≪なぜ虐待につながるか≫
・自閉症の特性理解の欠如「どう対応したらいいのか分からない」
・支援技術、対応技術の不足。支援方法を教えられていない。
・感情のコントロールが効かない。「自分でどうにかしなくては」等、チー
ム支援の欠如が虐待に繋がる。
・支援の困難さから誤った判断をし、虐待へ・・・ 支援リスクの高さ

解決策として…
・チームで自閉スペクトラムの一人ひとりの特性を
知る
・チームとして共通の言語をもつ
・チームで利用者の置かれている環境を考える
・チームとして統一したかかわり方を心掛ける
・「誰が困っているのか?」チームで認識する

このシートは…
【
問題とされる行動
シート①自閉症の診断基準となる障害 = 行動の違い
【本人の特性】 【環境・状況】
シート②
障害のもとになる認知特性=質的な違い
環境の要因
必要なサポートを書き出す
・支援のアイディアを参考にご本人に合ったもの

シート①自閉症の診断基準となる障害
=行動の違い
シート②障がいのもとになる認知特性
=質的な違い

行動の違いを知ろう・認知の違いを知ろう

支援の開始について
・目的→アセスメント→計画→実施→評価
・目的は氷山の上の内容
最終的に誰が困っているかに気づく
・アセスメントは問題行動を起こす前に
どんな人なのかを知ることで問題行動の
予防的支援の要になる。

シート①の使い方
・日々の生活の中でチェックしていく。
・言語があっても意味が理解できているのか?否か?一人
の視点ではなく複数人がチェックする。
・「(できている)かもしれない」「(自分が見たときは)出来て
いた」は出来ると評価する前にもう一度アセスメントをとる。
・「本人の行動」には根拠となる行動を書き込む。
会議等で根拠となり統一した考えの上での検討を始めや
すい。

シート②の使い方
・生育歴や現在の環境で結び付く
⇒さまざまなところに繋がる
・本人の特性(シート②)は本人の行動の他に前後の本人の
様子や置かれている環境も記入する事が大切。
・支援のアイディアとは、対象者に支援者が困っている事を支
援者の概念や思いに近づけるのではない。
特性(変わらない自閉症の文化)を知った上で、環境を変え
て対象者が困らずに過ごせるように支援していく事。

例えば…想像力、感覚の特性だと…シート①
・標識、ロゴ、数字、テレビのCM、電車、DVDの繰り返しの再生など一部分に執着
・同じ行動・活動、同じ言葉を何度も繰り返す・長時間続ける
・自分のルールを変えられることに抵抗がある/必要があっても変更できない。
シート②
・視覚優位
見て学ぶ事が得意。一度集中すると他に注目する事が難しい。
・焦点化
見た刺激に影響を受けやすい。気になる箇所に強く引きつけられる。一度集中すると他に注目する事が難しい。
・般化
少し違うと動揺したり、分からなくなったりする。

支援のアイディアについて
・シート②に書いてあるアイディアを実践していくための
具体的アイディアを考える上で支援にあたりをつける。
・チームであたりをつけた部分の支援のアイディアをご
本人に合ったものを用意する。
・導入の手立てまで話し合うと実践まで職員も期待でき
る(行動制限以外の支援の手立てを知る事ができる)。

支援に必要な事として
・環境を整える。刺激を減らす。
・利用者にとって想像を働かせる支援ではなく、より具体的に
見通しを知らせる事が大切。
・問題とされる行動の多い時間のデーターや記録をもとに支
援の実施をいつやるのかを絞る。
・同じ支援を2,3回行う事で上手くいく所と行かない所が出てく
るため、上手くいかない所をシートの「支援のアイディア」を
もう一度練り直す。
・再度実施を行う。

支援の開始について
・目的→アセスメント→計画→実施→評価
・どの時間にどんなことを起こすのか。
データを収集して一番多いものが支援
の優先順位が高くなる。
・支援のアイディアと特性に合わせた環境
の設定もチームで考える。

誰が
気になった部分
どのような取り組みか
ゴールをいつにするのか
担当者
中間報告や協力依頼
正解は対象利用者しか解らない(参考資料)
問題取り組みシート ・共通言語で一人一人の気づきを否定し
※金曜日のミーティングで優先順位の高いものから考えましょう。 ない。
・会議での取り組みは決定事項で、全員
が取り組めること。
・経験年数より、「人としてどうなのか」とい
う若手の発言が会議の流れを変えてい
く。
(在籍事業所の経験談)

まとめとして…「特性からもみてもすぐに改善出来ない事もある」
・チームでかかわりを統一する。支援を継続す
る為には、職員一人が頑張っても意味がない。
・チームを作る事は支援が成功する秘訣。
・職員にも仕事の悩み事等話せる環境も必要。
一人で考え込まない環境が必要。
・職員の心のゆとりは支援の視野を広くする。