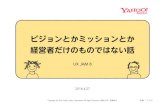視点と日独語の表現 ―...
Transcript of 視点と日独語の表現 ―...
東京外国語大学論集第 79 号(2009) 399
視点と日独語の表現 ― 翻訳の対照を手がかりに1)
成田 節
序論
1. 表現主体と表現客体
2. 知覚・認識の表現
3. 空間関係の表現
4. 身体をめぐる表現
5. 視座/注視点の一貫性
6. 動詞の時制
今後に向けて
序論
言語研究において「視点」(Perspektive)という概念はさまざまな意味で用いられている。
視点は一般に出来事や事態の見方だと言えるので,「誰がみるのか」(視点人物),「どこから見
るのか」(視座),「何を・どこを見るのか」(注視点),「どのように見えるか」(見え)という少
なくとも 4 つの要素が関連してくる。(茂呂 1985,松木 1992)
私は以前の論文(成田 1995)で視点に関して次の2点を主張した。(I) ドイツ語の構文研究
で Perspektive という際,視座と注視点が十分に区別されないことが多いが,実質的には「何・
どこに目を向けて事態を見るか」という意味での視点,つまり注視点を中心にしている。(II) 大
きな傾向として捉えるならば,ドイツ語の構文が注視点と密接に関連しているのに対して,日
本語の構文は視座と密接に関連していると言える。
ドイツ語では注視点が,日本語では視座がより重要だという違いが見られる1つの例として,
ドイツ語と日本語の受動文に見られる意味の違いを挙げることができる。つまり,ドイツ語の
受動文が ― 典型的なケースとして Ein Damm wurde gebaut.「ダムが建てられた。」のような
他動詞の受動文を考えると ― 動作主ではなく被動作者に目を向けてある行為を見る,すなわ
ち注視点に関して能動文と異なるのに対して,日本語の受動文が ― 同じく典型的なケースと
して「私は幼少年時代祖母に育てられた。」のように動作主を「~ニ」で表す「受影受動文」(益
岡 2000: 55ff.)を考えると ― 被影響者(典型的には話者)の立場から他者の行為を見る,す
400 視点と日独語の表現 ― 翻訳の対照を手がかりに:成田 節
なわち視座に関して能動文と異なるというように基本的な意味の違いを捉えることができるの
である。(成田 1996, Narita 2005)
しかし,視座と注視点は両方揃わなければ「視点」も成立しないはずだから,ドイツ語の構
文選択が主に注視点に関わるとしても,視座も当然問題になり得るはずだ。また,日本語の構
文(特に動詞表現)の選択がとりわけ視座に関わるとしても,実際には注視点が問題になるこ
ともあるだろう。たとえば「家の横に自転車がある」と「自転車の横に家がある」の自然さの
違いは,どこにまず目を向けるか,つまり何を注視点として状況を捉えるのが自然かというこ
とに左右されるものと考えられる。(山田 1985)
すると,ドイツ語と日本語の構文の特徴を視点との関連で捉えようとするには,「注視点か視
座か」という対立ばかりを考えるのではなく,視座と注視点の両者を考慮に入れた上で,視座
あるいは注視点に関して,ドイツ語と日本語ではどのように異なるのかと問うことも必要とな
ってくる。本稿では「視座」に目を向けて,どこに視座を定めるのかという観点から両言語の
構文に見られる傾向を考えていく。このような観点は, 近の認知言語学などでもしばしば取
り上げられているようだ。2) 例えば中村編(2004: 33ff.)は「I モード」すなわち「認知のインタラ
クションモード」と「D モード」すなわち「外置の認知モード」(D は desubjectification の頭
文字)という「二つの認知モード」ということに関して次のように述べている。3)
(1) 「日本語は,状況内に視点を置く状況密着型であるが,西洋の言語では視点は状況の外
にある」 ― 中村(2004: 33)
また,池上(2000: 295)にも(2)のような叙述が見られる。
(2) 「ある状況を見たり,あるいはそれについて語るという場合,見たり語ったりする主体
は自分の見たり語ったりする状況の外に自らを措定し,そこからいわば状況を観察する
第三者としてその状況を読み取るという形の演出をすることもできるし,一方また,そ
の状況の内に自らを措定し,状況に臨場する当事者としてその状況を読みとるという形
での演出をすることもできる。」 ― 池上(2000: 295)
さらに,金谷(2004: 31)では「神の視点」と「虫の視点」という対立で英語と日本語のさまざ
まな表現の相違を説明しようとしている。
(3) 「『神の視点』の方は不動である。言語化されようとしている状況から遠く身を引き離し
て,上空から見下ろしている。そしてスナップ写真のように,瞬間的に事態を把握する。
時間の推移はない。(...)『虫の視点』はその反対で,状況そのものの中にある。コンテ
東京外国語大学論集第 79 号(2009) 401
キスト(文脈)が豊かに与えられている。そしてこの視点は時間とともに移動する。」
― 金谷(2004: 31)
これら先行研究を踏まえ,上述の視座と注視点の区別も考慮に入れて定式化しなおすと,本
稿で主張するドイツ語と日本語の表現の違いは(4)のようになる。
(4) ドイツ語では表現主体(話者・語り手)が状況の外側に視座を据えてその状況を表す傾向
があり,日本語では表現主体(話者・語り手)が状況の内側に視座を据えてその状況を表
す傾向がある。
以下本稿では,小説などの翻訳に見られる日独両語の表現パターンの相違を,このような(日
英語対照研究などで既に数多く指摘されている)状況把握の仕方の相違という枠組みに当ては
めて解釈することを試みる。尤も,全く新たな観点から解釈を試みるというのではなく,これ
までにも日本語と英語の対照研究などで指摘されてきていることを,用語をより正確に押さえ
た上で,ドイツ語と日本語の双方向の翻訳テクストによって,実質的に確認するということが
中心になるだろう。
小説などの翻訳をたよりに,ドイツ語と日本語の特徴を対比的に浮き上がらせるという方法
の論考としては,浜崎/乙政/野入編(1985)などすでに多くの先例がある。翻訳には当然のこと
ながら翻訳者による表現の選択という過程が含まれるし,そもそも語彙体系も文法体系も違う
のだから,あるオリジナルの表現が必然的に翻訳における当該部分の表現になるというわけで
はない。しかし,翻訳者がオリジナルの表現内容を翻訳言語においても可能な限り等価かつ自
然な表現として再現しようと努力するという前提に立てば,二つの言語における表現の特徴を
考える材料として翻訳を観察することは有効な手段だと言えるだろう。もちろん,オリジナル
と翻訳の比較が対照研究におけるデータ観察の全てであるということではなく,あくまでもあ
り得るアプローチの一つに過ぎないということは意識した上で,以下の考察を進める。
1. 表現主体と表現客体 まず始めに,表現主体としての話者と表現客体としての話者の区別を確認しておきたい(岸谷
1996)。たとえば Ich sehe ein Flugzeug.(私は・見る・飛行機を)という文を組み立てて発話す
る人物が「表現主体としての話者」であり,この発話で言及されている ich が「表現客体とし
ての話者」である。そして,本稿で「視座」というのは表現主体としての話者の立脚する位置
ということになる。
(5) Ich sehe ein Flugzeug. 私は飛行機を見る。/ 飛行機が見える。
402 視点と日独語の表現 ― 翻訳の対照を手がかりに:成田 節
(5)の Ich sehe ein Flugzeug.は「私は飛行機を見る。」よりは,むしろ「飛行機が見える。」と
いう日本語に相当するというようなことは,初級のドイツ語授業でも指摘されていることであ
ろうが,これも視座が状況の外側に置かれているか,内側に置かれているかの違いから説明で
きる。まず,ドイツ語の Ich sehe ein Flugzeug.では,表現主体である話者が「話者自身が飛行
機を知覚する」という状況を外側から捉えるので,表現客体としての話者を ich として言語化
していると考えられる。このような捉え方は,中村編(2004: 37)の D モード,すなわち「脱主
体化」(desubjectification)による認知モードに相当する。中村によれば,「D モードの特徴は,
認知主体がインタラクティブな認知の場の外に出て,あたかも外から客観的に眺めるような視
点をとる過程にある」ということになる。ここで「インタラクティブ」と言うのは,「認知主体
が対象の事物と不可分に融合してインタラクトしている」(中村編 2004: 33)ということである。
これに対して,日本語の「飛行機が見える。」では表現主体である話者が状況内に位置するため,
客体としての話者と融合し,いわば話者自身が見えないことになり,話者自身は言語化されな
いのだと考えられる。
このような捉え方は,池上(2000: 290ff.)の「主体」と「客体」の融合という考え方にも当
てはまる。池上(2000: 293)は川端康成の「雪国」の冒頭の「国境の長いトンネルを抜けると
雪国であった。」との関連で(6)のように述べている。
(6) 「語り手も自らの語る状況の一部になっているのである。見る,そして語る〈主体〉と見
られる,そして語られる〈客体〉という対立は,そこには存在しない。」
― 池上(2000: 293)
たとえば(7)a の日本語「ここはどこ」なども,(6)の「語り手も自らの語る状況の一部になっ
ている」という説明がまさに当てはまる表現だと言えるだろう。ドイツ語訳(7)b では状況を外
側から捉えて「どこに・いる・私達は・ここで」というように文を組み立てている。
(7) a. 「ここはどこ」と直子がふと気づいたように訊ねた。(村上「ノルウェーの森」)
b. „Wo sind wir hier?“ fragte Naoko. Erst jetzt schien sie die Umgebung wahrzunehmen.
(Ursula Gräfe 訳)
2. 知覚・認識の表現
(7)と平行的な関係が Michael Ende の Momo から取った(8)にも見られる。
(8) a. Es bewegte sich mit majestätischer Langsamkeit dahin und Momo erkannte ein
ungeheures Pendel, (...). (M. Ende, Momo)
東京外国語大学論集第 79 号(2009) 403
b. それはおごそかな,ゆったりした速度で動いているのですが,よく見ると,(...)大
きな大きな振子でした。(大島かおり訳)
ドイツ語(8)a の下線部は「モモは巨大な振子を認識した」というように,語り手がこの状況
を客観的に描いているように感じられる。つまり視座は状況の外側にあると考えられる。これ
に対して,日本語訳(8)b では,振子を認識する主体であるモモが明示されておらず,「よく見
ると...でした」というように,語り手があたかもその場に直接居合わせて,いわば登場人物
であるモモの意識に寄り添うように表現していると読み取れる。視座は状況の内側にあると言
えるだろう。類例として(9)を挙げておく。(9)a の下線部は「モモは...素晴らしい花がしおれ
始めるのを認めた」いう表現になっている。
(9) a. Und während es sich ganz allmählich entfernte, gewahrte Momo zu ihrer Bestürzung,
dass die herrliche Blüte anfing zu verwelken. (M. Ende, Momo)
b. そして振子がわずかずつ遠ざかるにつれて,おどろいたことに,その美しい花はしお
れはじめました。(大島かおり訳)
同じような違いは,日本語の原文とドイツ語の翻訳との間にも見られる。
(10) a. 幸い,側を見ますと,翡翠のような色をした蓮の葉の上に,極楽の蜘蛛が一匹,美し
い銀色の糸をかけて居ります。(芥川「蜘蛛の糸」)
b. Ein glücklicher Zufall wollte es, daß er (=Buddha), als er zur Seite blickte, einen
hübschen silbrigen Faden entdeckte, den eine Spinne des Paradieses auf den
grünschillernden Lotosblättern gesponnen hatte.(Jürgen Berndt 訳)
日本語原文(10)a の下線部では,認識内容だけが表されていて,認識主体は言語化されてい
ない。あたかも語り手がその場に居合わせて,直接認識しているような描き方になっている。
一方,ドイツ語の下線部では,「お釈迦様が...銀色の糸を見出した」というように,認識主体
を主語に据え,状況を外側から客観的に描いていると言える。同じことが(11)にも当てはまる。
(11) a. ところがふと気がつきますと,蜘蛛の糸の下の方には,数限もない罪人たちが,自分
ののぼった後をつけて,まるで蟻の行列のように,やはり上へ上へ一心によじのぼっ
て来るではございませんか。(芥川「蜘蛛の糸」)
b. Doch plötzlich gewahrte er, daß unten am Ende des Fadens unzählige Übeltäter es ihm
nachmachten und wie eine lange Reihe von Ameisen eifrig heraufgeklettert kamen.
(Jürgen Berndt 訳)
404 視点と日独語の表現 ― 翻訳の対照を手がかりに:成田 節
確かにドイツ語訳には点線下線部 heraufgeklettert kamen「こちらへ・攀じ登って・来た」と
いう表現もあるので,ドイツ語訳でも状況内の犍陀多寄りの視座から他の罪人たちを見ている
と考えることができるが,ここで問題にしているのは,そのような犍陀多の認識内容を,日本
語では「...一心によじのぼって来るではございませんか」というように,犍陀多の視座から
見えたままを直接描くような表現となっているのに対して,ドイツ語訳では,「突然彼は...と
いうことに気がついた」というように,やはり一歩外側に視座を置いて描いているということ
である。さらに,次の(12)では,読み手はまるで登場人物と一緒に廊下を進んで行くと扉があ
ることに気がついたというような,臨場性を感じさせるが,ドイツ語訳(再和訳するならば「彼
らは,今度は水色に塗られたドアに着いた」とでもなろう)からはそのような臨場性は感じら
れないのではないだろうか。
(12) a. ずんずん廊下を進んで行きますと,こんどは水いろのペンキ塗りの扉がありました。
(宮沢賢治「注文の多い料理店」)
b. Als sie den Gang entlang weitergingen, kamen sie diesmal an eine hellblau angestrichene
Tür. (Johanna Fischer 訳)
以上,知覚・認識の表現における日本語とドイツ語の傾向の違いを見てきた。もちろん日本
語でも,「私は飛行機を見る/私(に)は飛行機が見える」のように,表現主体である話者が状況
の外側に視座を定め,状況の一部をなす客体としての話者に言及するということは可能だが,
ここで主張しているのは,それぞれの言語でより好んで用いられる表現パターンが異なるとい
った傾向の違いである。
3. 空間関係の表現 日本語では語り手が状況の内部に視座を据える(語り手が登場人物の視座から状況を見る)
のに対して,ドイツ語では語り手の視座が状況の外部にあるということが,直接読み取れるよ
うな例を見てみよう。
(13) a. とうとう芸者に出たのであろうかと,その裾を見てはっとしたけれども,こちらへ歩
いてくるでもない,体のどこかを崩して迎えるしなを作るでもない,じっと動かぬそ
の立ち姿から,彼は遠目にも真面目なものを受け取って,急いで行ったが,...(川端
康成「雪国」)
b. Als Shimamura den langen Saum sah, erschrak er. War sie dann doch eine Geisha
geworden? Sie bewegte sich nicht auf ihn zu, und ihr Körper blieb angespannt stehen,
東京外国語大学論集第 79 号(2009) 405
ohne die geringste einladende Geste erkennen zu lassen. Bereits aus der Ferne nahm er
an ihrer Gestalt eine gewisse Ernsthaftigkeit wahr. Eilig lief er auf sie zu, (...)(Tobias
Cheung 訳)
(13)は主人公の島村が駒子と再会した場面だが,「こちらへ歩いてくる」と「急いで行った」
という表現から,語り手が,登場人物である島村の視座からこの状況を捉えていることは明ら
かだ。一方,ドイツ語訳では,点線下線部 War sie dann doch eine Geisha geworden?という体験
話法のように,語り手が心理的に島村に接近していると読み取れる箇所も確かにあるが,「こち
らへ」が auf ihn zu つまり「彼の方へ」と,また「(向こうへ)行った」が auf sie zu つまり「彼
女の方へ」として表されていることから,空間関係については中立的な位置からの表現である
と言えるだろう。これも,ドイツ語訳では,語り手が状況の外部に視座を据えていると考える
ことで説明が付く。
(14) a. ...プラット・フォウムの寒さに触れると,急に汽車のなかの非礼が恥ずかしくなっ
て,後も見ずに機関車の前を渡った。男が葉子の肩につかまって線路へ下りようとし
た時に,こちらから駅員が手を上げて止めた。(川端「雪国」)
b. ..., doch als er die Kälte auf dem Bahnsteig spürte, schämte er sich plötzlich für sein
ungebührliches Verhalten im Zug und schritt schnell vor der Lokomotive über die Gleise.
Er blickte sich nicht mehr um. Der Mann hielt sich an Yôkos Schulter fest und stieg auf
die Gleise. In diesem Moment hob von der anderen Seite her ein Bahnangestellter die
Hand zum Halt.(Tobias Cheung 訳)
(14)は,主人公の島村が停車した機関車の前を横切って駅舎側に渡った場面だが,日本語の
場面指示表現「こちらから」によって,語り手が島村の視座からこの状況を描いていることが
わかる。一方,ドイツ語訳では, 初の 3 文で er die Kälte ... spürte「(彼は)寒さを感じ」,schämte
er sich und schritt ... über die Gleise「(彼は)恥ずかしくなり...線路を渡り」,Er blickte sich
nicht mehr um.「(彼は)もう振り向かなかった」というように,島村寄りの視座から状況が描
かれているのかと思って読み進むと, 後の一文では ... von der anderen Seite her ein
Bahnangestellter die Hand zum Halt「反対側から駅員が止まるように手を上げた」というよう
に,島村ではなく「男と葉子」を基準にして空間関係が表現されている。これも,この場面全
体を通して,視座は状況の外側に置かれ,注視点が 初の 3 文では「島村」に,次の 2 文では
「男と葉子」にあると考えれば納得がいく。
日本語の「こちら」を使った表現には,(15)a のように,読み手を言わば物語の場面に連れ
406 視点と日独語の表現 ― 翻訳の対照を手がかりに:成田 節
て行き,臨場性を感じさせる働きもあるように思われる。
(15) a. こちらは地獄の底の血の池で,ほかの罪人と一しょに,浮いたり沈んだりしていた犍
陀多でございます。(芥川龍之介「蜘蛛の糸」)
b. Kandata trieb zusammen mit anderen Übeltätern in dem Blutteich in der Hölle.. (Jürgen
Berndt 訳)
ドイツ語訳(15)b を再和訳すれば「犍陀多は他の罪人たちと一緒に,地獄の血の池で漂ってい
ました。」とでもなり,(15)a のように読み手が地獄に一緒に連れて行かれるような効果はない
ように思える。
次にドイツ語の dieser と日本語の「コ・ソ・ア」を見てみよう。日本語の場面指示の「コ・
ソ・ア」については,一般に「話し手の近くにあるものは「こ」系列,聞き手の近くにあるも
のは「そ」系列,どちらからも遠いものは「あ」系列で指す。」(益岡・田窪 1992: 164)と説
明されている。
ドイツ語でこれらに対応する語としては一般に dieser と jener が挙げられている。たとえば,多
くの独和辞典で 初に挙げられる訳語は,dieser は「コノ」,jener は「アノ」となっている。4)
しかし先行研究には,dieser が「コノ」だけではなく,「ソノ」や「アノ」にも対応するとい
う指摘がしばしば見られる。ここでは dieser が「コノ」と「アノ」に対応している例を見てみ
よう。漫画「名探偵コナンの一場面」である。例文は Mikame (2005)から引用させていただい
た。(16)b ではコナン達がいる「この部屋」も diesen Raum,壁の高いところにかけてある「あ
の時計」も dieser Uhr と訳されている。
(16) a.(コマ1)この部屋に入ったとき特に目に付いた矢印があっただろ。
(コマ2)ほら,6 時半で不自然に止まってる,あの時計だよ。(「名探偵コナン」,Mikame
2005 から)
b.(コマ1)Erinnert euch doch mal! Ist euch kein Pfeil aufgefallen, als wir diesen Raum
betreten haben?
(コマ2)Und was ist mit dieser Uhr, die unnatürlicherweise um Punkt halb sieben
stehen geblieben zu sein scheint?(Mikame 2005 から)
Mikame (2005)は,「ドイツ語では対象が直接知覚可能な範囲にある場合は dieser あるいは
der で指示できるが,日本語では直接知覚可能な範囲の対象でも,話し手からの遠近によって
「コ」と「ア」の区別をする」(和訳は成田)と指摘している。このような違いも,表現主体が
取る視座がドイツ語では状況の外にあり,日本語では状況の内側にあるという違いに関連付け
東京外国語大学論集第 79 号(2009) 407
て考えることができる。つまり,日本語では視座,つまり表現主体の立つ位置が状況の内側に
あるとすれば,状況内での表現主体(話者)からの空間的な距離がより大きな意味をもつこと
になるので,話者からの遠近がより明確に指示表現に反映されるのは自然である。一方,ドイ
ツ語では表現主体が状況の外側に立つとすれば,状況の外側にいる表現主体と状況内の対象(相
互)の空間的な位置関係が持つ意味は小さくなり,それに応じて,表現主体との遠近を指示表
現に反映させる必然性は相対的に低くなると考えることができる。
「ア」が dieser と訳されている例をもう 1 つ(17)として挙げておく。
(17) a.「母が来ておりますわ,お判りになります?」かおるに言われて,魚津は改札口の向う
に立っている人々の中から小坂の母の姿を探した。二十歳ぐらいの頬の赤い娘に付き
添われるようにして,こちらに顔を向けている六十年配の女性の姿が,すぐ魚津の眼
に留まった。「あの..
方でしょう?若い娘さんと一緒の ――」(井上靖「氷壁」,野入 1985
から,下線は成田)
b. „Meine Mutter ist da! Erkennen Sie sie?“ Uozu suchte unter den Frauen, die hinter der
Sperre standen, welche Kosakas Mutter sein könnte, und da fiel ihm schon im nächsten
Augenblick eine etwa sechzigjährige Dame auf, die zu ihnen hersah und von einem
ungefähr zwanzigjährigen, rotwangigen Mädchen begleitet war. „Diese Dame ist es doch,
ja? Zusammen mit dem jungen Mädchen......“ (Oskar Benl 訳,野入 1985 から,下線は
成田)
ドイツ語訳(17)b では下線部 zu ihnen hersah「彼らの方を見た」となっている箇所が,日本
語原文(17)a では下線部「こちらに」となっていることから,日本語原文では語り手が登場人
物である魚津の視座からこの状況を捉えていること(つまり内側からこの状況を見ていること)
がわかる。そして,問題の女性が視座(すなわち語り手の位置)から遠くに居るために「あの
方」で指されている。
4. 身体をめぐる表現 野入(1985:135)はドイツ語と日本語の空間表現との関連で,(18)のような例を挙げ,それにつ
いて(19)のように述べている。
(18) Die Luft ist unser Hauptlebenselement, sie umgibt unseren Körper von außen und dringt
durch die Atmung hinein.(空気は我々の主要な生命の基本要素である.空気は我々の身体
を外からとりまいていて,呼吸によって体内に入って来る/行く.)(野入 1985 :135,訳
408 視点と日独語の表現 ― 翻訳の対照を手がかりに:成田 節
も野入,下線は成田)
(19) 「このような場合,話し手の立場は日本語でならば体内・対外のうちの前者にとられ,従
って行クの語は不可で来ルのみが可能である.ドイツ語での hinein の使用を見ると話し
手の立場は体内ではなく対外にとられていることになる.」(野入 1985: 135)
ここで「話し手の立場」と呼んでいるのは本稿の「視座」に当たるとみて差し支えないだろ
う。このような事例も,日本語では視座が状況の内側にあるというだけでなく,さらにその中
でも人物の身体周辺の狭い領域に関しては,文字通り人物の「目」に視座を置き,そのために
「空気は...呼吸によって体内に入って来る」となるのに対して,ドイツ語では視座が状況の
外側にあるので,Die Luft (...) dringt durch die Atmung hinein.「空気は呼吸によって中に入って
いく」となるのだと考えられる。
5. 視座/注視点の一貫性 次の例(20)における日独の表現の違いは,表現主体(語り手)の視座の違いと直接関連付け
るのは難しそうだが,ある登場人物を軸として一貫した表現となっているか否かという点で,
これまでの議論との関連付けが可能かもしれない。まだ考察が十分とは言えないが,観察事例
として挙げ,現時点での解釈を述べておく。
(20) a. Neben dem Wasserhahn standen zwei Eimer, sie griff einen und füllt ihn. (...) Sie holte
weit aus, das Wasser platschte auf den Gehweg und schwemmte das Erbrochene in den
Rinnstein. Sie nahm mir den Eimer aus der Hand und schickte einen weiteren
Wasserschwall über den Gehweg. (B. Schlink, Vorleser)
b. 水道の脇にはバケツが二つ置いてあった。彼女は一方のバケツをつかんで水を満たし
た。(…中略…)彼女は勢いをつけて歩道に水をぶちまけ,ぼくが吐いたものを下水溝
に押し流した。ぼくの手からもバケツをとると,もう一杯,歩道の上に水を流した。(松
永美穂訳)
ドイツ語原文では点線下線部は「彼女は勢いをつけた」だが,それに続く実線下線部は「水
が歩道にはねて,嘔吐物を下水溝に流した」というように,動作を行う登場人物から独立した
出来事のように描かれている。一方,日本語訳では下線部全体にわたって「彼女は勢いをつけ
て歩道に水をぶちまけ,ぼくが吐いたものを下水溝に押し流した」というように,一貫して登
場人物の行為として出来事を描いている。以下の例もこれと同類と見なすことができる。
(21) a. 宿屋の客引きの番頭は火事場の消防のようにものものしい雪装束だった。耳をつつみ,
東京外国語大学論集第 79 号(2009) 409
ゴムの長靴をはいていた。(川端康成「雪国」)
b. Der Angestellte des Gasthofs, der auf Kunden wartete, trug schwere Kleidung und sah
einem Feuerwehrmann ähnlich. Er war bis zu den Ohren eingehüllt, und seine Füße
steckten in hohen Gummistiefeln. (Tobias Cheung 訳)
日本語原文(21)a では「(...)番頭は(...)ものものしい雪装束だった。耳をつつみ,ゴム
の長靴をはいていた。」のように登場人物に軸を定めた表現となっているのに対して,ドイツ語
訳では「旅館の従業員は(...)ものものしい装束で消防士に似ていた。(彼は)耳まで覆われ
て」までは一応登場人物を軸とした表現となっているが,下線部は「彼の足は長いゴムブーツ
に収まっていた」というように登場人物から足だけ切り離したような表現になっている。次の
(22)と(23)にも同様な違いが見られる。
(22) a. 男は窓の方を枕にして,娘の横へ折り曲げた足をあげていた。(川端康成「雪国」)
b. Der Mann hatte sich ein Kissen an die Fensterseite gelegt. Seine angewinkelten Beine
reichten zu der Frau hinüber, die einen Sitz weiter zum Fenster hin saß. (Tobias Cheung
訳)
(23) a. 娘は胸をこころもち傾けて,前に横たわった男を一心に見下ろしていた。(川端「雪国」)
b. Der Oberkörper der Frau war leicht nach vorn gebeugt. Sie schaute aufmerksam auf den
vor ihr liegenden Mann. (Tobias Cheung 訳)
上で登場人物に「軸を定めた」という表現を用いたが,これは「視座が一貫している」と言
うためには語り手の登場人物への接近が不十分なように思え,他方,「注視点が一貫している」
と言うとすると,序論に挙げた「日本語では表現主体(話者・語り手)が状況の内側に視座を
据えてその状況を表す傾向がある」という主張との整合性が問題となるからであった。ただ,
(20)~(23)などの事例から「ドイツ語は日本語よりも注視点の移動が比較的自由である」とい
うことは言えそうであり,このことは「ドイツ語では表現主体(話者・語り手)が状況の外側
に視座を据えてその状況を表す傾向がある」という主張と結び付けられると思われる。いずれ
にしてもさらに考察する必要がある。
6. 動詞の時制
周知のように,ドイツ語の小説では地の文は基本的に過去形をベースとして書かれるが,あ
る場面を,臨場感を持って活き活きと描き出すために現在形に切り替えることがあるというこ
ともよく知られている。たとえば,Weinrich (2003: 217f.)は「物語の直接性,臨場感,緊張感を
410 視点と日独語の表現 ― 翻訳の対照を手がかりに:成田 節
増すために現在形を使用することもある」と述べ,サンプルとして Eichendorff の Aus dem
Tagebuch eines Taugenichts の一節を引用している。以下に(24)a として挙げておく。(24)a で
は, 初の定動詞 ging は過去形だが,umschaue 以下,下線付きの定動詞はすべて現在形とな
っている。
(24) a. In diesem Schloss ging es mir wunderlich. Zuerst, wie ich mich in der weiten, kühlen
Vorhalle umschaue, klopft mir jemand mit dem Stocke auf die Schulter. Ich kehre mich
schnell um, da steht ein großer Herr in Staatskleidern, ... (Eichendorff, Aus dem
Tagebuch eines Taugenichts, Weinrich 2003 より)
b. この城で私は奇妙な目に遭った。まず,広く寒いロビーで周りを見回していると,誰
かがステッキで私の肩を叩いた。とっさに振り向くと,宮廷役人の格好をした大柄な
男が立っていた。(成田試訳)
一方,日本語でも同じような時制の交替が見られる。たとえば庵他(2001: 76)には(25)のよう
な,また工藤(2004: 183)には(26)のような記述が見られる。
(25) 「小説の地の文ではル形とタ形が混在することがよくあります。この現象には厳密な決ま
りはありませんが,(...)ある事物の描写をしている場合はル形が使われやすくなります。
これは,こうした場合のル形がいわばその現場に立ってカメラで映像を撮っているような
臨場感をもたらす効果があるためです。」 ― 庵他(2001: 76)
(26) 「話し手が,過去の特定時において,直接体験した,具体的な(アクチュアルな)出来事
の,発話時における記憶の生々しさを前面化して,非過去形で表現する場合がある。(...)
あえて,非過去形を使用するのは臨場性であるが,また話し手の印象の現在時までの持続
性を前面化させてもいる。」 ― 工藤(2004: 183)
このように,ドイツ語にも日本語にも過去形/タ形で語る文章に現在形/ル形を織り交ぜるこ
とで,その場面を活き活きと描き出す,あるいは臨場感を持たせるという文体的な手法が存在
するわけだが,この可能性は実際にどの程度利用されているのだろうか。
一例として芥川龍之介の「蜘蛛の糸」の地の文の述語とそのドイツ語訳の定動詞を比べてみ
た。サンプルとして冒頭の部分を見てみよう。日本語では従属節内の述語はテンスの対立が相
対化される ― たとえば「手紙を投函する前に,もう一度宛名を確認した」のよう従属節の時
は,発話時ではなく主節の時を基準にして表わされる(益岡・田窪 1992: 213) ― こともある
ので,ここでは文末の述語にだけ注目すると,ル形が「ございます」と「溢れて居ります」の
2 回,タ形が「御歩きになっていらっしゃいました」の 1 回,このほかに「でございましょう」
東京外国語大学論集第 79 号(2009) 411
という推量の形が 1 回でてきている。これに対してドイツ語の定動詞は全て過去形になってい
る。
(27) a. ある日の事でございます。御釈迦様は極楽の蓮池のふちを、独りでぶらぶら御歩きに
なっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花は、みんな玉のようにまっ白
で、そのまん中にある金色の蕊からは、何とも云えない好い匂が、絶間なくあたりへ
溢れて居ります。極楽は丁度朝なのでございましょう。
b. Eines Tages erging sich Buddha im Paradies an den Ufern des Lotosteiches. Die
Lotosblüten auf dem Teich schimmerten weiß wie Perlen, und ihre goldfarbenen
Stempel und Staubfäden erfüllten die Luft ringsum mit einem unaussprechlichen
Wohlgeruch. Es war gerade Morgen im Paradies.
この短編中に現れる地の文の述語 ― 日本語の場合は文末の述語のみ ―および定動詞の時
制と法をまとめると下の表のようになる。
過去/タ形 現在/ル形 接Ⅱ5)/推量など
日本語 19 21 12
独語訳 110 0 7
上述のように,日本語の方は従属節内の述語は除外してあり,また,両言語で同じ内容をそ
れぞれ対応する品詞(Verb と動詞など)で表現できるとは限らないので,このように総数の違
いが大きくなっているが,過去形と現在形およびタ形とル形の使用割合の違いは見てとれる。
表に見られるように,オリジナルの日本語では,ル形とタ形がほぼ半々の割合で混在している
のに対して,ドイツ語訳では,地の文の定動詞が,数例の接続法 2 式以外は全て過去形および
過去完了形となっている。6)
ただ 1 つの,しかも短いテクストの比較に過ぎないが,この事例に限って言えば,日本語が
状況の内側に視座を据え,臨場的に描写する傾向があるのにたいして,ドイツ語では,同じよ
うな表現の可能性は存在するものの,その可能性を必ずしも利用するとは限らないということ
が確認できた。ここにも日本語が状況を内側から見て,主観的な描写を好むのに対して,ドイ
ツ語は状況を外側から見て,客観的な描写を好むという傾向の違いが見て取れるのではないだ
ろうか。
412 視点と日独語の表現 ― 翻訳の対照を手がかりに:成田 節
今後に向けて
以上,主に小説の翻訳を材料として「ドイツ語では表現主体(話者・語り手)が状況の外側
に視座を据えてその状況を表す傾向があり,日本語では表現主体(話者・語り手)が状況の内
側に視座を据えてその状況を表す傾向がある」という違いを示す事例を観察してきたが,これ
に関して問題となり得る観点を本稿ですべて取り上げたわけではない。たとえば日本語の「~
てくれる」「~てやる」 ― およびそれに対応するドイツ語の表現としての Dativ commodi(利
害の与格) ― や「~ていく」「~てくる」,あるいはドイツ語の hin と her などの「視点」と
非常に密接に関わると思われる問題を本稿では取り上げなかった。これらについては稿を改め
て考察したい。
また,本稿では少数の事例を挙げ,それに基づき「~と考えることができる」というような
述べ方が多かったが,今後はより客観的な論証の方法を考えなければならない。たとえば 6「動
詞の時制」で示したような ― もちろんより大規模なものでなければならないが ― 数量的な
調査,あるいはインフォーマントの協力を得て,観察事例に基づく作例の容認性判定などが考
えられる。
なお,序論で触れた成田(1995)の主張の一部,すなわち「大きな傾向として捉えるならば,
ドイツ語の構文が注視点と密接に関連しているのに対して,日本語の構文は視座と密接に関連
している」が,本稿の主張「ドイツ語では表現主体(話者・語り手)が状況の外側に視座を据
えてその状況を表す傾向があり,日本語では表現主体(話者・語り手)が状況の内側に視座を
据えてその状況を表す傾向がある」と十分に整合するということを 後に述べておく。すなわ
ち,表現される状況の外側に視座を据えれば,表現主体は事態参与者に対してより中立的な立
場に立つことになる。したがって,文脈や状況に応じて状況の捉え方を変えるとしたら,事態
参与者のいずれを注視点とするかという選択の方が関与的(relevant)となりやすい。ドイツ語の
諸表現にはこのような特徴が見られる。一方,表現される事態の内側に視座を据えれば,表現
主体は事態参与者に対して中立的な立場を取りにくく,何れかの側に立った表現になりやすい。
つまり,視座が事態参与者のいずれに接近あるいは同一化するかが関与的になる。また,その
分相対的に,注視点の違いが構文に反映される度合いが低くなる。日本語の諸表現にはこのよ
うな特徴が見られる。このような大枠で今後も考察を続けていく予定である。
注
1) 本稿は科学研究費補助金(2008~2010 年度,基盤研究c)の研究成果の一部であり,2008 年度日本独文学
会春季研究発表会(2008 年 6 月 14 日,立教大学)での研究発表および,東京外国語大学語学研究所定例研
究会(2008 年 7 月 2 日,語学研究所)での研究発表をもとにして,研究ノートの形にまとめ直したもので
ある。
東京外国語大学論集第 79 号(2009) 413
2) この点については大薗(2008),Ozono (2008)などから多くの示唆を得ている。 3) 文脈から,中村の「視点」は「視座」の意味であることが読み取れる。 4) 尤も Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache などの辞書には,現代語の特に口語では話
し手から遠くにあるものを指すのに jener ではなく,der…da あるいは dieser が用いられるという記述が見
られる。 5) 接Ⅱは Dann bliebe es ihm erspart, …「そうすれば...な目に合わずに済むだろう」などの接続法第 2 式。 6) なお,ドイツ語訳には次のような体験話法も見られたが,この定動詞も過去形に数え入れてある。Schwebte
da nicht durch die totenstille Finsternis vom fernen, fernen Himmelsrand her ein silbriger Spinnfaden langsam zu ihm herab!(原文は「そのひっそりとした暗の中を、遠い遠い天上から、銀色の蜘蛛の糸が、まるで人目
にかかるのを恐れるように、一すじ細く光りながら、するすると自分の上へ垂れて参るのではございません
か。」)
参考文献 庵功雄他(2001)『中上級を教えるひとのための日本語文法ハンドブック』スリーエーネットワーク. 池上嘉彦(2000)『日本語論への招待』講談社. 大薗正彦(2008)「認知言語学とドイツ語教育」(研究会資料) 金谷武洋(2004)『英語にも主語はなかった』(講談社選書メチエ 288)講談社. 岸谷敞子(1996)「Person(人称)と Subjekt(主語)の関係 ― 言行為の普遍性を求めて―」愛知大学言語学談
話会編『ことばを考える』第 3 集,47-85. 工藤真由美(2004)「第 7 章 現代とのテンス・アスペクト」尾上圭介編『朝倉日本語講座6』朝倉書店,172-192. 中村芳久編(2004)『認知文法論Ⅱ』(シリーズ認知言語学入門)大修館書店. 成田 節(1995)「„Perspektive“の概念について ― 構文研究の観点から ―」大阪市立大学文学部『人文研究』
第 47 巻第 10 分冊,161-177. 成田 節(1996)「ドイツ語と日本語の受動態について ― その意味の相違 ―」日本独文学会『ドイツ文学』第
97 号,122-133. 野入逸彦(1985)「指示・空間の表現」浜崎/乙政/野入編(1985)128-136. 浜崎長寿・乙政潤・野入逸彦編 (1985) 『日独語対照研究』大学書林 益岡隆志 (2000) 『日本語文法の諸相』くろしお出版. 益岡隆志・田窪行則(1992)『基礎日本語文法-改訂版-』くろしお出版. 松木正恵(1992)「『見ること』と文法研究」『日本語学』1992 年 8 月号,57-71. 茂呂雄二(1985)「児童の作文と視点」『日本語学』1985 年 12 月号,51-60. 山田 純(1985)「文における視点」『日本語学』1985 年 12 月号,32-40. Mikame, Hirofumi (2005) „Zur deiktischen und anaphorischen Referenz im Deutschen – Eine kognitiv-
textlinguistische Untersuchung.“ In: Narita/Ogawa/Oya (Hgg.) 185-211. Narita, Takashi (2005) „Ist Passiv eine ‚Leideform’? – Ein deutsch-japanischer Kontrast.“ In: Narita/Ogawa/Oya
(Hgg.) Deutsch aus ferner Nähe. Japanische Einblicke in eine Fremdsprache. Festschrift für Susumu Zaima zum 60. Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg. 41-56.
Ozono, Masahiko (2008) „Sujektive und objektive Auffassung: Zwei Raumauffassungsweisen in kontrastiver Sicht.“ In: Neue Beiträge zur Germanistik, Band 7, Heft 1, 75-90
Weinrich, Harald (2003) Textgrammatik der deutschen Sprache, 2. revidierte Auflage, Olms.
414 視点と日独語の表現 ― 翻訳の対照を手がかりに:成田 節
Perspektive und Ausdrücke im Deutschen und im Japanischen
–– eine kontrastive Untersuchung an Beispielen aus Übersetzungstexten ––
NARITA Takashi In der vorliegenden Arbeit wird unterschiedlichen Charakteristika des deutschen und des
japanischen Satzbaus nachgegangen. Dabei wird zuerst der Begriff der „Perspektive“ überprüft
und genauer bestimmt. Danach wird auf einschlägiger Literatur im Bereich der
deutsch-japanischen und englisch-japanischen kontrastiven Untersuchungen aufbauend die
folgende Hypothese aufgestellt: Zwischen dem deutschen und dem japanischen Satzbau ist ein
tendenzieller Unterschied solcherart zu beobachten, dass sich beim deutschen Satzbau der
Sprecher (als die satzbildende Person) außerhalb der dargestellten Situation befindet und diese
aus dem neutralen Standpunkt eher objektiv darstellt, während sich der Sprecher beim
japanischen Satzbau innerhalb der dargestellten Situation befindet und diese gleichsam direkt
und subjektiv wahrnimmt und darstellt. Dieser Unterschied bekundet sich z.B. im oft
besprochenen Satzpaar wie dt. Ich sehe ein Flugzeug. und jp. Hikôki ga mieru. Im Hauptteil der
Arbeit werden Belege aus den deutsch-japanischen bzw. japanisch-deutschen Übersetzungstexten
einiger moderner Romane und Novellen aufgeführt, anhand derer die aufgestellte Hypothese
überprüft werden soll. Dabei werden vor allem folgende Typen behandelt: (a) Ausdrücke des
Wahrnehmens und Erkennens wie z.B. dt. Momo erkannte ein ungeheures Pendel und jp. Yoku
miruto (...) ôkina ôkina huriko deshita, (b) räumliche Ausdrücke wie z.B. jp. kochira e aruite kuru
demo nai (...) isoide itta und dt. Sie bewegte sich nicht auf ihn zu (...) Eilig lief er auf sie zu, (c)
Ausdrücke um den menschlichen Körper herum wie z. B. dt. Die Luft (...) dringt durch die
Atmung hinein und jp. kûki wa (...) kokyû niyotte tainai ni haitte kuru. Am Schluss des Hauptteils
werden die Formen der finiten Verben in einer japanischen Kurzgeschichte und deren deutscher
Übersetzung klassifiziert, wobei ein deutlicher Unterschied im Gebrauch des „szenischen
Präsens“ festgestellt wird, was auch für die genannte Hypothese spricht.