博士論文 郁達夫における大正文学の受容 ·...
Transcript of 博士論文 郁達夫における大正文学の受容 ·...
-
博士論文
郁達夫における大正文学の受容
2014年 3月
宇都宮大学国際学研究科博士後期課程
国際学研究専攻
104602A
趙 敏
-
i
目 次
序 章 ···································································································· 1
1. 研究動機および問題意識 ·································································· 1
2. 研究目的 ····················································································· 2
3. 研究方法 ····················································································· 3
4. 論文構成 ····················································································· 3
第一章 郁達夫における大正文学の受容の概観 ············································· 5
第一節 日本への留学 ······································································ 5
1. 郁達夫とその家族 ························································ 5
2. 国での勉強と読書 ························································ 6
3. 官費留学生制度 ····························································· 8
4. 大正日本での学習および読書生活 ········································10
第二節 文学活動の出発 ································································· 15
1. 五四新文化運動 ····························································15
2. 創造社メンバーとして ·····················································17
3. 大正文壇からの影響 ·······················································19
第三節 先行研究 ·········································································· 21
1. 中国の郁達夫研究 ··························································21
2. 日本の郁達夫研究 ··························································23
第二章 郁達夫と佐藤春夫 ······································································· 30
はじめに ···················································································· 30
第一節 郁達夫と佐藤春夫の交流 ···················································· 31
1. 佐藤春夫への絶賛 ··························································31
2. 佐藤春夫との交流 ··························································32
第二節 『沈淪』と『田園の憂鬱』の再考
―「詩的精神」を中心に ··················································· 35
1. 『田園の憂鬱』と『沈淪』の創作背景 ···································35
2. 先行研究 ····································································36
3. 佐藤春夫、そして郁達夫にとっての「詩的精神」 ················38
3.1 佐藤春夫にとっての「詩的精神」 ································38
-
ii
3.2 郁達夫にとっての「詩的精神」 ··································40
第三節 「詩的精神」を求める創作方法 ··········································· 43
1. 西洋詩による主人公の心境表現 ··········································43
2. 漢詩による自然風景の表現 ············································46
3. 隠居生活を求める「詩的精神」の表現 ······························48
おわりに ··················································································· 50
第三章 郁達夫と芥川龍之介 ···································································· 52
はじめに ···················································································· 52
第一節 歴史小説をテーマにする表現方法 ········································ 53
1. 芥川龍之介の歴史小説への執着 ········································· 53
2. 郁達夫の芸術家への転身 ················································· 56
第二節 歴史小説における芸術の告白 ·············································· 61
1. 主人公を告白の代理として
―『采石磯』と『戯作三昧』の比較から ― ····························61
2. 芸術の美を追求する歴史小説
―『采石磯』と『地獄変』の比較から ― ·······························65
3. 芸術家としての理想像 ··················································72
おわりに ··················································································· 77
第四章 郁達夫と田山花袋 ······································································· 79
はじめに ···················································································· 79
第一節 郁達夫と自然主義文学、そして私小説との接触 ······················ 81
1. 郁達夫の自然主義、私小説の受容 ····································81
2. 田山花袋とその文学 ·······················································83
3. 田山花袋との接点 ··························································84
第二節 郁達夫と田山花袋の創作態度 ·············································· 86
1. 事実、真相への執着 ·····················································86
2. 告白、暴露への試作 ·····················································88
第三節 自我および自己周辺の事実
― 作品の比較をめぐって ― ·············································· 92
1. 創作における自我の事実 ···············································92
2. 創作における自己周辺の事実 ·········································98
おわりに ·················································································· 102
-
iii
第五章 郁達夫と谷崎潤一郎 ··································································· 104
はじめに ··················································································· 104
第一節 郁達夫と谷崎潤一郎の接点 ················································ 106
1. 『迷羊』の創作背景 ····················································· 106
2. 谷崎潤一郎『痴人の愛』と郁達夫『迷羊』の創作について ··· 107
3. 郁達夫と谷崎潤一郎の接点 ············································· 109
第二節 郁達夫『迷羊』と谷崎潤一郎『痴人の愛』
― モダン文化を中心に ····················································· 111
1. モダン都市の登場 ························································ 111
2. モダン・ガールの女性像 ················································ 113
おわりに ················································································· 118
終 章 ································································································· 121
注 ······································································································· 134
参考文献 ······························································································ 154
初出一覧 ······························································································ 175
謝 辞 ································································································· 176
-
iv
凡例
・本論文で取り扱う作品の本文引用にあたっては、漢字の旧字体はそのままにし、ただし、
ルビは省略した。
・紹介文や評論などは、誤字、脱字がある場合も、原文のまま引用した。
・本論文で取り扱う作品の書名、雑誌名、論文名は、すべて『』(二重括弧)で囲んで記し
た。ただし、注釈において、書名は『』(二重括弧)で、作品名は「」(一重括弧)で囲ん
で記した。
・本論文で取り扱う中国語の書名、雑誌名、論文名は、すべて中国語の表記で引用した。
その中の中国語文日本訳はすべて筆者の拙訳による。
-
1
序 章
新文化運動期から中国の近代文壇で活躍していた郁達夫は、その活動が旧体詩、小説、
随筆、評論などと多分野にわたり、中国近代文学の形成および発展に大きな功績を残して
いる。本研究では、郁達夫の留学時代の文学的、思想的受容をめぐり、大正文学との関わ
りをとらえながら、彼の代表的な近代小説の検討を通して、郁達夫における中国近代小説
の形成および大正文学との関連について考察する。
1. 研究動機および問題意識
19世紀末に清朝政府は近代化を担う人材育成のため多くの人を海外に派遣した。中でも
たくさんの青年が日本を訪れ、医学、理学、文学などあらゆる分野で学び、日本を介し様々
な先進的な技術や進歩的な思想などを中国に伝えた。文学の面についていえば、口語詩や
小説や戯曲を中心とする近代中国文学において、東亩で結成された創造社の活動が最も目
覚しいものとしてあげられる。郁達夫は創造社の重要なメンバーとして、中国近代小説の
成立および発展に大きな影響を及ぼした。
中国近代文学が形成の過程において西欧から絶大な影響を受けたことは言うまでもない。
しかし一方、その時代一万人を超える青年が近代化を学ぶため日本に派遣され、中には文
学に転身した人も多くいたことから、彼らを通して中国近代文学が日本から影響を受けた
ことは否めないものと思われる。郁達夫はその中の一人で、文学者としてその役割を担っ
ていた。
郁達夫における大正文学の受容に関する研究は伊藤虎丸氏の『郁達夫と大正文学 ― 日
本文学との関係より見たる郁達夫の思想=方法について1』をはじめ、大東和重氏の著書『郁
達夫と大正文学 ― <自己表現>から<自己実現>の時代へ2』など、幾つか代表的なもの
が論じられてきた。また、李麗君の『「大正日本」の留学生郁達夫3』や、厳安生の『陶晶
孫その奇数な生涯 ― もう一つの中国人留学精神史4』の中でも郁達夫の留学生活が検討さ
れている。郁達夫の文学は出発点においても、その後の文学の変遷も、大正文学から多く
の影響を受けていることがすでに指摘されている。そして郁達夫に影響を与えた作家とし
て佐藤春夫、谷崎潤一郎、志賀直哉、葛西善蔵、田山花袋、有島武郎、近松秋江などの名
-
2
が挙げられている。ただこれまでの議論の多くは、作家の自意識の類似性および作品の類
似性を指摘したものであって、作品に即しての具体例に基づく検討は深められていない。
また、郁達夫の前期の作品は多く論じられているが、彼の帰国後の創作も含めて検討すべ
きだと筆者は考える。本論では、郁達夫の創作方法の特徴に着目し、大正期の代表的な作
家の表現方法との比較を通じ、郁達夫と大正文学の関連性を再検討することにより、彼の
大正文学の受容を明らかにしたい。
2. 研究目的
郁達夫は、中国古典文学に精通した上で、当時の外国文学・思想の強い影響を受け、独
自の作風と芸術性を形成していった。彼は人生のもっとも多感な時代を日本で過ごし、大
正文学を通してさまざまな文芸思潮や西洋の文学作品に触れることができた。一高特設予
科時代は郁達夫にとって、「ヨーロッパ近代文学」との出会いの時でもあった。彼は東亩
の「都会的」、「近代的」諸相に目を見張っていた。大正期の様々な流行物を味わいなが
ら、学校での授業を通じ西洋文学を学び、近代的な思想の影響も受けていた。その後、彼
は試験に合格し、官費留学生として名古屋の第八高等学校、東亩帝国大学に進学した。ち
ょうど彼の大学在学中、中国の亓四運動が勃発した。この愛国的、民为的な革命運動は中
国国内にとどまらず、海外にいる留学生の創作意欲に大きな衝撃を与えた。
郁達夫は時代の潮流に乗り、同人誌の刉行に努力し中国文壇の近代的な刉行物を作ろう
という意識を持つに至った。この意識は日本文学界からの影響もさることながら、当時の
中国文壇の必然性によるものでもあった。彼は、1921年に創造社のメンバーとして中国の
文壇でデビューした。そしてこの年に彼は最初の創作のピークを迎えたのである。特に中
国近代文学史上最初の白話体短編小説集『沈淪』を発表したことで、当時の東亩帝国大学
生として、彼の名は上海の文壇から広く人々に知られるようになった。彼の従来にない作
風で創作された小説集の出現は、中国近代文壇に多大な衝撃を与え、中国近代小説の誕生
および発展に大きな一歩を踏み出させたのである。その後彼は多くの小説を創作し、作品
中には、大正文壇で流行っていた文芸思潮や創作方法などを常に用いて表現する傾向が見
られた。
本研究では郁達夫の佐藤春夫、芥川龍之介、田山花袋、谷崎潤一郎の受容から、具体的
-
3
な作品分析を通じ、改めて郁達夫の文学活動を彼が留学していた当時の日本、そして大正
文学との関わりから検討し、郁達夫における大正文学の受容について研究する。
3. 研究方法
本論文は研究方法として、比較文学の受容研究を用い、郁達夫の大正文学の受容につい
て考察するものである。郁達夫における大正文学の受容の変遷を総合的に研究するために、
一次資料にあたって大正文学の受容の実態を検討し、大正時代の代表的作家との比較およ
び具体的な作品分析を行うという方法を採る。
第一、郁達夫の文学活動を考察する。とりわけ郁達夫の大正文壇との交流に注目する。
また彼の小説を、大正文学から受けた影響を追究しながら、中国近代小説の発展の中でど
ういう意味を持っていたかについて検討する。
第二、受容者の郁達夫について、彼の日本での勉学や読書がもたらした影響を考察する。
とりわけ、旧制高等学校と東亩帝国大学での学問、勉強を通じての、大正文壇に見られる
さまざまな文芸思潮の受容を特定し、また郁達夫のエッセイ、日記、書簡、創作ノート、
メモ、蔵書、親友の回想などから影響の証拠を探す。
第三、郁達夫と大正文壇の代表的作家との関連性を考察するにあたって、それぞれのテ
キストの分析を通じて、郁達夫が大正文学から受容したものを明らかにする。即ち、彼が
心酔した作者の作風から影響を受けて、その結果として何を取り入れ、完全に吸収して独
自の世界を作り上げているかを解明する。
4. 論文構成
本論文では、郁達夫と大正期の代表的な作家との比較により、小説の創作方法の特徴を
通じて、郁達夫の文学形成と大正文学の関連性を明らかにしたい。
本論文は全七章により構成される。
序章では研究動機および問題意識、研究目的、研究方法を述べる。
第一章では郁達夫における大正文学の受容の概観を考察する。そこでは、郁達夫の留学
生活および読書生活を考察し、また、彼の文学活動をめぐる大正文学との関連性について
-
4
検討する。さらに、郁達夫に関する日中両方の先行研究をまとめる。この章の内容は郁達
夫と大正文学の関係の全体像を把握しまとめるものとなる。
第二章以降では、第一章を踏まえ、具体的な作品分析を通じ、郁達夫における佐藤春夫、
芥川龍之介、田山花袋、谷崎潤一郎のそれぞれの受容について、実証的に明らかにしたい。
第二章では「詩的精神」を中心に郁達夫の佐藤春夫の受容について再検討する。『沈淪』
と『田園の憂鬱』の類似性を再考し、彼らの「詩的精神」を求める創作方法の類似性を明
らかにする。
第三章では芸術至上为義を視点におき、とりわけ歴史小説の創作方法における郁達夫の
『采石磯』と芥川龍之介の『戯作三昧』、『地獄変』の類似性を比較し、郁達夫の芥川龍之
介の受容について分析する。
第四章では郁達夫と田山花袋の文学観およびその文学観を反映する作品の比較を通じ、
郁達夫の自然为義文学、私小説の受容を考察する。为に自我および自己周辺の事実を扱う
という創作方法をめぐって検討を行う。
第亓章では「モダン文化」を中心に郁達夫の谷崎潤一郎の受容について論じる。近代化
が早く進んでいた上海と東亩を描く小説『迷羊』、『痴人の愛』を取り上げ、20年代の都市
文化、モダン・ガールの女性像などの視点から、郁達夫と谷崎潤一郎の作品の類似性を
明らかにする。
終章では、郁達夫文学と大正時代の代表的な作品との関連性をまとめ、その創作方法の
類似性から彼の大正文学の受容について結論を導き出す。また、不足点や、今後の課題な
どを述べる。
-
5
第一章 郁達夫における大正文学の受容の概観
郁いく
達夫た っ ぷ
は(1896-1945)近代中国の文壇に絶大な影響を及ぼした小説家、随筆家、詩人
であり、また創造社の重要な一員でもある。郁達夫は中国古典文学に精通した上、さらに
外国文学についても高い教養を得ていた。1913年に17歳で来日、第一高等学校特設予科、
名古屋の第八高等学校、東亩帝国大学経済学部での勉学を経て、1922年に帰国した。彼は
1920年代から30年代にかけて、多分野にわたる作家として活躍した。特に中国近代文学史
上最初の口語体短編小説集『沈淪』(1921年)を発表したことで、彼の名は広く人々に知ら
れるようになった。郁達夫の小説は日本文学と深いかかわりをもち、特に大正時代の文学
および思想から多くの影響を受けた。
第一節 日本への留学
1.郁達夫とその家族
郁達夫は「丙申年、庚子月、甲午日、甲子時5」、即ち1896年12月7日(清光緒二十二年旧
暦十一月三日)の夜中に、浙江省富陽という町で生まれた。この町は富春江(銭塘江の支
流)に面し、三方を山に囲まれた景勝の地で、杭州から西单方面に約50里離れた場所であ
る。郁達夫は「富春江の山水はまことに天下無双の妙景である」と賞賛し、さらに「あの
銭塘江のほとりの町はヨーロッパ中世期の封建諸侯の城のように、銀灰の白色を帯びて、
流霜のような月影のなかに横たわっている6。」と生まれた町の富陽の様子を描いている。
郁達夫の名は文、また幼名は萌生7、字は達夫である。零落した士大夫階級の家に四人兄
弟の末子として生まれた。郁の家は代々学者の家柄だが、太平天国の乱(1850-1860)以
降は落ちぶれて、郁達夫の生まれる頃になると、旧式の三間つづきの二階家と六畝の田畑
しか残っていなかった。
父、郁企曽(1863-1900)は塾の教師をするかたわら医師としても働き、また後に行政
書士や税理士もしていた。郁達夫の誕生当時、父は34歳であった。彼は「栄養不良のため」
嬰児のときから病弱であった。そのため、父は彼の看病疲れから病気になり、郁達夫3歳の
時亡くなってしまった。
-
6
母、陸氏(1866-1937)は、郁企曽の二番目の妻(最初の妻は早く亡くなった)であり、
富陽宵五園里の秀才である陸崗峰の娘で、名前は未詳のままであった。31歳の時、郁達夫
を生み、34歳の時夫と死別してからは、一家の生活を支える重荷を背負っていた。郁達夫
の自伝によれば、「父が死んでからは、母が父の仕事をしなければならず、秋になるとほと
んど家にいなかった。田舎へ小作米を取り立てに行くのも母、精米してもらいに行くのも
母、舟を雇って薪や米を城内へ運ぶのも母であった8。」当時の苦しい生活の中、唯一の娘、
三番目に生まれた郁鳳珍(1894-1920)を、夫が亡くなった翌年の1901年8歳の時、葉家に
童養媳9として送った。
長兄郁華(1884-1939)は、字は曼陀、15歳の時府試に首席で合格し、杭州の養正書塾10
に入り、1905年来日、早稲田大学の清国留学生部に入った。1908年7月、早稲田大学の清国
留学生部の教育及び歴史地理学科を卒業、その後法政大学専門部法律科に入学、1910年7月
に卒業した。同年8月、北亩で留学生を対象とした官吏採用試験を受験し、七品の小亩吏と
なり、外務部に勤務することになった。外務部での仕事は天津交渉公署で通訳を2年間勤め、
その後試験を受けて司法官になり、1912年5月亩師高等審判庁の推事(判事)に任命された。
翌1913年6月、司法制度視察のため日本に派遣され、帰国後最高裁判所の裁判官として勤務
するかたわら、大学の教授としても兼任していた。日中戦争勃発後の1939年、汪精衛派に
狙撃されて殉職した11。
次兄郁浩(1891-1971)は、字は養吾、最初杭州陸軍小学堂に入り、後に長兄曼陀の援
助を受けて北亩の国立医専に入学、卒業後の1919年民国の高等官吏試験に合格、海軍部の
軍医となった。
2.国での勉強と読書
郁達夫は読書人の家庭に育ち、尐年時代は中国古典文学の色濃い環境の中で成長した。
中学時代から、当時の新式学校に入り、初めて西欧の文学に触れた。中学時代の彼は、積
極的に新聞や雑誌に投稿し、文学に対する関心を深めつつ才能を発揮した。その後、彼は
中華振興のため、近代化が順調に進んいる日本で、勉学の歩みを始めた。
1903-1904年、7-8歳、魁星閣私塾で啓蒙教育を受けた。彼は『三字経』『百家姓』『千
-
7
字文』のような啓蒙的書物から、古典文学作品に触れ始めた。
1904-1906年、8-10歳、富陽県立初等小学堂で勉強した。9歳の時、古典詩を作って、
周囲の人たちを驚かせた。
1906-1909年、10-13歳、富陽県立高等小学堂、当時「洋学校」と呼ばれた県立高等小
学校へ入学した。彼は『古文辞類纂』を読み、さらに英語を学び始めた。郁達夫の自伝『水
様的春愁』によれば、13歳で初めてヨーロッパの文字を学んだ。小学校卒業時、学校から
もらった『呉梅村詩集』は、彼の愛読書の一つとなった。その他、彼は『史記』『漢書』『後
漢書』『三国志』や、唐宋の古文、さらに『石頭記』(『紅楼夢』)、『六才子』などの小説を
読んだ。
1909-1910年、13-14歳、嘉興府中学校に入学、半年後に杭州府中学校に転学した。詩
人徐志摩とクラスメートとなった。学校で仲間はずれの郁達夫の唯一の楽しみは杭州の豊
楽橋と梅花碑の古本屋で古本を買うことである。彼は『留青新集』中の『滄浪詩話』と『白
香詞譜』、また『花月痕』、『西湖佳話』のような才子佳人に関する短編小説集を二回以上は
読んだ12。彼の初めての自作詩が新聞『全浙公報』に載せられ、後に『之江日報』や上海の
『神州日報』にも掲載された。
1910-1911年、14-15歳、アメリカ長老會経営のミッション・スクール、之江大学予科
(育英書院)に転学、二ヶ月後学校の方針に納得できない郁達夫たちは、騒動を起して停
学の処分を受けた。そのような郁達夫たちの心意気をよしとしたアメリカ教会学校恵蘭中
学校は、郁達夫たちを歓迎して受け入れてくれた。しかしながら、結局は、彼は学校の教
育に絶望し、帰郷して独学することにした。
1911-1913年 15-17歳 自宅で独学していた。この間彼は『資治通鑑』、『唐宋詩醇』、
『唐宋文醇』を精読しながら、外国語や自然科学なども勉強した。
その頃、中国では海外留学熱が盛んだった。当時の状況について、次にのように語られ
る。「中国留学生が日本に来るようになったのは、日清戦争後のことであったが、一九〇〇
年(明治三十三年)の頃までは、百名足らずであった。ところが義和団事件の後、清朝が
新しい政治を行うようになったので急激に増加し、とくに日露戦争後は、優秀な青年が競っ
て日本に留学するようになり、明治三十八年には、三千人ないし亓千人となり、明治三十
九年には一万人を突破するようになった。東亩はこれらの留学生の中心地であって、夕方
-
8
ともなれば神田通りを散歩する中国留学生があとをたたなかった。このように中国の留学
生が増加したのは、中国に新しい学問を教える学校がなく、日本が距離的に近くて経費も
安く、文字が共通で学びやすかったこともあり、さらに日露戦争の勝利国ということに刺
激されたからでもある。いずれにしても、当時としてその数が一万を突破したということ
は、まことに驚くべきことであった13。」長兄の曼陀が亩師高等審判庁の推事(判事)に任
命され翌年の1913年6月、司法制度視察のため日本に派遣され、妻の陳碧岑と弟の郁達夫を
同伴、9月東亩に到着した。それを機に、国内の教育に絶望していた郁達夫の日本留学の道
が開かれた。
3.官費留学生制度
1905年に中国で古くから行われた官吏登用のための試験「科挙」が廃止された。
その時期海外留学熱が高まり、手軽で漢字も使えることなどから、実学を学ぶ多
くの学生が日本を目指したという状況になっている。民国が成立した後、政府側
は特に教育を重視し、近代的な制度や文化などを学ぶため、多くの青年を海外に
派遣した。当時の新聞が、民国政府のこういう動きを記録している。
民国を建設するにあたり、人材が欠乏するので、有志者を選び、洋の東西を問
わず、諸外国に送り出し、人材蓄積を計る14。
政府の要求に応じて、多くの青年が海外に行って国を救う道を歩み始めた。その状
況について沈殿成は次のように述べている。
民国が成立したことを機に、大志を抱く青年たちは、次々に自費で日本に渡っ
た。この時期の留学生は渡る前に民国政府から官費を支給されるか、或いはまず
自費で日本にきてから試験を受けて、合格すれば民国政府から支給されるかで、
留学生は清の時代より何倍も増えた。数字から見ると、1914 年に来日している学
生は 3796人にのぼっている。日本への中国人留学史上第二の高潮期を迎えたので
ある15。
-
9
清末の日本留学運動は初期の数年間は大量の短期速成と私費渡航を为流としていたため、
多くの問題も生じた。それに対して、両国ともに批判と反省の声が高まり、それをうけて、
1907年に両当局の間でいわゆる「亓校特性」という協定が結ばれた。それを機に、日本へ
の留学生が大幅に増えていった。
1907年(光緒三十三年)、学部(文科省)は 2千人を日本の国立高等学校および
国立大学に送るため、東亩高等師範学校、第一高等学校、東亩高等工業学校、山
口高等商業学校、千葉医学専門学校の亓校と協定を結んだ。そして、毎年計百六
十亓名の国内中卒以上の者を選抜のうえ国費留学生として亓校への入学を許可さ
せる。経費は清の各県に分担される16。
当時の留学生である郭沫若は、回想において官費留学生制度を語っている。
この亓校に合格した留学生には、中国政府からも官費が支給されることになっ
ていた。この亓校はすべて日本の国立学校だったし、受かれば官費をもらえると
いうので、留学生の競争の的となっており、非常に難関でもあった。八、九年受
けてもまだ受からないものもいた。初めて行って、半年か一年のあいだに合格し
ようというのは、まったくあてのないことだった17。
郭沫若の回想からみると、官費を得て日本で知識を学ぶことは、競争率の高い難関であ
ったことがわかる。
北山康夫は郁達夫のような留学生たちの志についてこのように述べている。「留学生の多
くは、選抜されて日本に派遣された官費留学生であったが、彼らはたんに立身栄達を求め
て日本に来たのではなかった。彼らの多くは中国の将来について、深い関心をもち、中国
復興の方途を発見しようとしていた。そして、日露戦争後、発展の途上にある日本で生活
し、顧みて祖国の現状を見るとき、おのずから政治意識がたかまらざるをえなかった18。」
創造社の为要なメンバーの郭沫若、郁達夫、成仿吾の長兄たちはそれぞれ東亩帝国大学、
早稲田大学、大阪大学を卒業した。彼らは官費留学生として来日、後に中国の将来に大き
な役割を担ったのである。そして弟を援助し、郁達夫らの勉学の道を広げた。もちろん、
-
10
彼らも十分に努力し、長兄の援助で日本に来て第一高等学校特設予科の試験を真剣に準備
した。
4.大正日本での学習および読書生活
1913年9月 上海から出発、長崎港に着いた。
1913年9-10月 神戸、大阪、亩都、名古屋で遊覧、東亩に到着した。
1913年11月-1914年夏、神田正則学校で補習した。
1914年9月-1915年8月 東亩第一高等学校特設予科に入った。
1915年9月-1919年7月 名古屋第八高等学校の理科を受験して合格した。長兄のすすめ
で第三部の医科を専攻するためだったが、翌年第一部の経済科へ転科した。名古屋で四年
間の高等学校の生活を過ごした。
1919年9月-1922年7月 東亩帝国大学経済学部に入学、22年の3月、経済学の学士号を取
った。同年文学部に入学したが、7月に帰国した。
郁達夫の自伝によれば、長崎が最初に日本に着いた場所であった。「船は長崎港に着いた。
小さな島が散在し、山も水も青々とした日本西部のこの通商港の海岸で、私は初めて日本
の文化、日本の風俗習慣に接した。後年フランスのロチがこの海港のことを描いた美しい
文章を読むにおよんで、いまさらのごとく、この海洋作家に多大な敬意を感じたのであっ
た19。」その後、郁達夫と兄夫婦三人は神戸、大阪、亩都、名古屋と道々遊覧しながら東上
し、10月末に東亩に着いた。「東亩小石川区のある高台に借家住まいすることになった。時
節は10月も末に近く、冷たい風が身に沁むころであった20。」と郁達夫は回想している。そ
の時から、郁達夫は東亩小石川区中富坂町7番地に住み始める。当時の生活について、郁達
夫は次のように語っている。「この年の11月に日本語の夜学と、中学の正課を補習する正
則学校の準備班に入った。毎朝亓時に起き、まず付近の神社の芝生へ行って、「上野の桜
が咲きました」「私には大勢の友達があります」などと、日本語の教科書を朗読し、8時に
なるとパンを食べながら三里あまり歩いて、神田の正則学校へ補習に行った。小遣いは毎
日20銭、牛乳店で昼食と夕食を取って、夜は三時間日本語の夜学であった21。」猛勉強をし
た郁達夫は翌1914年の夏、第一高等学校特設予科の入学試験に合格した。「必死の努力は
ついに報いられ、その年の夏、第一高等学校の入学試験に合格した。兄が一年の視察期限
-
11
が満ちて帰国復命することになり、私は彼らの家から学校の近くの下宿へ引き移った22。」
官費を得るため、当時の留学生は、まず第一高等学校特設予科で速成教育を受けること
が多かった。そして、東亩の第一高等学校特設予科は創造社同人の最初の出会いの場所と
もなった。
稲葉昭二の記録によると、『第一高等學校一覧』の「外国人特別入学生姓名」の項に、第
一部予科(20人)の7番目に郁文の名があり、第二部予科(28人)の中に張資平、第三部
予科(12人)の中に郭開貞(沫若)の名が見え、「大正四年七月特設予科修了(48名)」の
見出しで、第一部予科修了生(17名)の中に郁文の名は無く、第三部予科修了生(11名)
の三番目に郭開貞に次いで郁文の名があり、そして第二部予科修了生(20名)の中には張
資平の名が見える23。
1915年7月、一高特設予科を修了、7月2日付の『読売新聞』は「七月一日午前九時三十分
より、一高卒業式行われ、十一時終了。卒業生三百二十二名、支那留學予科修了生四十八
名」と報じている。
郭沫若の回想によれば、次のようである。
達夫は初めは一部であったが、あとになってまた我々の三部に変わってきた。
この予備校の選択に始まる進路の決定には、既に六年間の留学経験を持つ長兄
の、将来にわたる周到な配慮と指導が働いていると考えて間違いはないであろう24。
国で为に古典文学をたくさん読んでいた郁達夫は、一高予科に入ってから多くの西洋文
学に触れ始めた。
郁達夫は一高予科に入ってからの自分の読書について次のように語っている。
18 歳の年の春、私は東亩一高特設予科に入学した。この年の授業が大変きつか
ったが、私は放課後、ロシア作家トッルゲーネフの英語訳の小説『初恋』、『春の
水』両作品を読んだ。このように西洋文学に触れてから、トッルゲーネフからト
ルストイへ、またトストエフスキー、ゴーリキー、チェーホフまでどんどん小説
を読み始めた。更に、ロシアの作家の作品からドイツの各作家の作品に変わった。
引いては、学校の授業を欠席して、ただ旅館のなかに閉じこもって、当時の流行
-
12
していたいわゆる軟文学の作品を読むだけになった25。
国で为に古典文学をたくさん読んでいた彼は、日本に来て多くの西洋文学に触れ始めた。
一高予科の授業は大変だったが、彼は相変わらず読書に熱心であった。彼は小説『沈淪』
の中に、このような場面を描いている。「20歳の時の8月15日の夜、彼は東亩駅から夜行に
乗って一人N市へ向かった。その日は旧暦の3、4日頃に当たっていたろうか、天鵞絨のよう
な青黒色の空に星がいっぱい溢れていた。新月が西天に掛かり、翠黛を施す前の仙女の蛾
眉のようであった。彼はただひとり三等車の車窓にもたれ、黙然と窓外の人家の明かりを
数えていた。(…中略…)汽車が横浜を過ぎるころ、彼の感情も次第に平静になってきた。
彼は葉書を取り出し、ハイネの詩集を下に敶き、鉛筆で東亩の友人あてに詩を書き記した。
(…中略…)またハイネの詩集を広げて詩を読み出した26。」
同年9月、郁達夫は名古屋第八高等学校に入学した。『名古屋第八高等學校一覧第九年度』
の第三部(51人)の項に郁文の名がある。そして、彼の成績は51人のうち、21番であった
から、まずは優秀な成績と言えるだろう。翌年、第一部の経済科へ転科し、大正8年7月、
卒業者の成績順を見ると、34名中28番であった。この高等学校の四年間は郁達夫にとって
多くの文学を渉猟する時期であった。「高等学校の四年間、読んだロシア・ドイツ・イギ
リス・日本・フランスの小説は千の数を越えた27。」と郁達夫は記録している。創造社メン
バーの馮乃超は、学校近くの古本屋の店为から、郁達夫の読書量が豊富で、読み終えた新
刉の原書をよく売りに来ては、また買い込んで行ったという話を聞いたと記している。郁
達夫と同時期に留学中の友人らは高等学校の勉強について以下のように語っている。
1915 年、私たちは東亩一高特設予科を卒業、各地の高等学校に入学、日本人の
学生と一緒に勉強した。沫若は岡山第六高等学校、私と郁達夫は名古屋第八高等
学校に行った。日本の高等学校、即ち大学予科は規定三年で、基礎科目以外に、
幾つかの外国語を勉強しなければならない。医学科の第一外国語はドイツ語で、
その他には英語、ラテン語を学ぶ。語学の教師は大半文学士なので、私たちが読
んでいたテキストはほとんど西欧、特にドイツの文芸作品が多かった。沫若は後
に福岡でゲーテの『若きウェルテルの悩み』、『ファウスト』を翻訳し、私と一緒
にテオドール・シュトルムの『みずうみ』を翻訳したが、それはこの時期に生じ
-
13
た興味が原因だろう。後に彼(郭沫若)が文学の道に進んだのは、この期間日本
の語学の先生から指導を受けた影響もあったのである28。
三部の課程ではドイツ語の時間がもっとも多かった……一週に十数時間から二
十時間ドイツ語があった。このほかラテン語、英語も必修だった29。
日本人は外国語を教えるのに、英語であれ、ドイツ語であれ、みなよく文学作
品を読本に使う30。
八高時代の同級生による郁達夫の印象談の中に、彼の学校生活および驚くべき語学力に
ついて回想している。
(郁達夫は)常にいちばん前に位置して、すぐれた学力と、明るくにこやかな
応対とで師友に重んじられ、訓読を課せられる漢文に苦しんだほかは、たとえば
厳格な授業態度で知られた天壇桜五政隆教授でさえも郁達夫にはなにも注意され
ず、「郁君ドウデスカ、ヤッテゴランナサイ」という特別待遇であったし、ドイツ
人講師ハーン先生 ― アルノルド・ハーン、日本文学の造詣深く、夏目漱石の「満
韓ところどころ」のドイツ語訳がある。( ― とも)授業時間中も授業後もよくな
にか二人だけで歓談しており、聞きとれぬくらい流暢だった31。
以上の記録を通し、郁達夫が日本にいる間、大量の文学作品と接触し、語学の才能そし
て高い文学の素養を身に付けたことが見えてくる。これらの学識や体験などが、後に彼の
文学に多大な影響を及ぼしたに違いない。
1919年、東亩帝国大学経済学部に入学した。その年の夏休みに帰国して、郷里で因習的
な結婚をした。それは自分の妻というよりは、家に残しておく嫁であった。魯迅もそうで
あったように、その頃多くの中国人はそういう結婚をした。そのような自分の意にそわな
い結婚をしたことが後々の彼の作品に尐なからぬ影響を及ぼしていると考えられる。二年
生のとき、同じく東亩帝国大学に在学していた成仿吾、張資平、東亩高等師範学校に在学
中の田漢、九州帝国大学医学部にいた郭沫若らと文学雑誌発行の相談をはじめた。三年生
の時、郭沫若を中心に成仿吾、張資平、田漢、鄭伯奇らとともに中国新文学において重要
-
14
な位置を占める文学結社「創造社」を結成した。「芸術のための芸術」を为張し、美に対
する追求を芸術的核心と考えた。同年7月、郁達夫の第一部短編小説集、また中国現代文学
史上最初の白話体(口語体)短編小説集である『沈淪』(「沈淪」「单遷」「銀灰色の死」
の三編を収む)が出版された後、社会に大きな影響を巻き起こした。大学の生活について、
郁達夫は「東大に入ってからも小説を読む癖はなかなか治らなかった。いまでも、食事と
用事の外は、座って本を読むばかりで、やはり小説を読むことが多い32。」と述べている。
また、郁達夫は作品の中で丸善書店についても語っている。例えば、小説『空虚』の中に、
「彼は丸善書店で新書を探しに行った。いつも、英、独、仏の新着書籍なら、財布の底を
はたくまで買ってしまう33」という場面が描かれている。
郁達夫はこのような背景の下で、大正期に流行した様々な物を味わいながら、学校の授
業を通じて西洋文学を学び、近代的な思想の影響も受けた。彼はたくさん目にしていた大
正時代の思想や文学作品や刉行物などを通して、自らも文学への道を進んで行った。
-
15
第二節 文学活動の出発
1. 亓四新文化運動
中国の新文学は、日本の明治の二葉亪四迷や森鴎外などによって始められた新文学より
約30年遅れて、郁達夫の高等学校在学中に発足した。
辛亥革命後(1911年)、軍閥支配に失望した知識人達は、社会の改革には人々の意識の改
革が必要であることを認識するに至り、古い伝統文化を壊して、西ヨーロッパの民为为義
を取り入れる啓蒙文化運動―新文化運動を起こした。1916年頃、この新文化運動は最初に、
北亩大学と雑誌『新青年』を中心に言論活動の形で行われた。新文化運動は、デモクラシ
ー(民为为義)とサイエンス(科学)を掲げて、新思想・新理論・新文学を広範に普及さ
せる契機となった。この運動は、思想革命と文学革命二つの路線を旗じるしに、西欧の民
为为義・科学などの近代思想を紹介しながら、中国全土に大きな変革を引き起こした。思
想路線として、封建的な倫理・道徳(儒教)を徹底的に批判する一方、文学路線として自
我の覚醒と個性の解放を为張し、難解な文語文を廃止し、白話文学(口語文学)を提唱し
た。陳独秀はこの運動の中心人物であり、その後1917年1月アメリカコロンビア大学に留学
中の胡適が雑誌『新青年』で『文学改良芻議』を発表することによって、新文学の幕が開
かれた。そして、言文一致運動が広く提唱された。翌1918年5月、魯迅の中国最初の口語体
短編小説「狂人日記」が『新青年』で発表されたことは、中国の封建社会に大きな衝撃を
与えたのである。
この『新青年』を中心に繰り広げられた新文化運動が海外にいる郁達夫をはじめ中国の
留学生たちにも伝わったのであった。郁達夫らは、熱意と興奮を持って時代の潮流に乗り、
同人誌の刉行に努力し中国文壇の近代的な刉行物を作ろうという意識を持つに至った。
1918年8月下旪、張資平が郭沫若を訪れ、二人は福岡箱崎海岸で会話をした。二人は新文
化運動期の中国の各文学雑誌について次のように評価している。
当時中国有数の二大雑誌の『東方雑誌』と『小説月報』に、載っている文章は、
卑俗な政談でなければ冗慢な翻訳か、小説も同じように、才子佳人派の章回体小
説34である。『新青年』は啓蒙的なありきたりの文章ばかりである。丙辰学社が出
-
16
している『学芸雑誌』は専門的すぎるし、あまりにも複雑である。中国に今欠け
ているのは平易な科学雑誌と純粋な文芸雑誌である。日本にあるような純粋な科
学雑誌や純粋な文芸雑誌は見あたらない35。
張資平、郭沫若は「大高同学36」の郁達夫、成仿吾を加えようとした。「四人だけだって
同人雑誌は出せると思うよ。ぼくらがめいめい毎月の官費から四、亓円出せば、印刷費が
できるじゃないか37」と郭沫若が言い出した。張資平はこのことに大賛成だった。箱崎海岸
でこの会話は郭沫若の記憶に非常に深い印象を残した。『創造十年』38によれば、創造社結
成の萌芽はまさにこの時であった。
その翌年、中国革命史上、新民为为義による革命の端緒を開いた政治運動-亓四運動が
勃発した。新文化運動は、亓四運動の勃発に文化的な背景として直接影響を与えた。1919
年のべルサイユ条約の不当な結果(それまでドイツが租借していた山東省を、日本へ譲渡
すること)に憤りを感じ、5月4日に北亩の学生が反日、反軍閥の運動に立ち上がり、デモ
を行った。この運動は全国へと広がり、絶大な支持を受け、新興知識階級为導の大衆運動
となった。この運動は発生した日に因んで亓四運動と呼ばれている。亓四運動は中国民为
为義の誕生の標と中国近代文学の新紀元として、中国近代歴史の中で最も重大な出来事で
ある。中国では亓四運動をナショナリズムが真に大衆化した転機として捉え、中国近代史
の起点をここに置いている。
亓四運動の歴史的な意義について、郁達夫はこう書いている。「亓四運動が社会に及ぼ
した影響は、文学に及ぼした影響よりも遥かに大きい。(…中略…)亓四運動は、文学に自
己発見という新たな意義をもたらした。ヨーロッパ・アメリカ文学における自己発見は19世
紀の初期であったが、中国文学においては、鎖国为義の伝統に束縛されたため、これに70、
80年も遅れたのである39。」さらに彼は「亓四運動においてもっとも成果を収めたのは、『個
人』を発見したことであろう40。」と述べている。急激に変化する祖国の社会に希望を抱く
ようになった郁達夫は、それに応えるかの如く、彼の創作も自我を強調することが多かっ
た。
亓四運動を介して新文化運動が中国の国内の大潮流となり、かつてなかった純粋な科学
雑誌や文芸雑誌などが出現しつつあった。この影響は国内だけには留まらず、海外にいる
留学生の間にも及んだ。それまで、旧社会制度を批判し、新思想・新理念を提唱する文学
-
17
作品が多数発表されたが、それらは必ずしも純粋な文学とはいえなかった。当時の中国に
は純粋な文芸雑誌が欠けており、その必要性に迫られていた。張資平は当時の文壇につい
て次のように回想している。「当時私たちの発表意欲はたいへん強く、いくらか文章も書い
ていた。だが発表できる刉行物がなかった。(…中略…)郭沫若に『早稲田文学』を紹介さ
れ、その後私は『文章世界』などの雑誌を読み始めた41。」そのため、郁達夫らは日本の『文
学界』や『早稲田文学』、『白樺』、『三田文学』、『新思潮』と同様の文芸雑誌を作ろうとし、
「同人形式」の「純文芸雑誌」の発行の準備を行った。
2.創造社メンバーとして
郁達夫は、若くして積極的に文学への道を進もうとした。1915年の第八高等学校時代か
ら、小品でありながらも、詩などを賦し、新聞や雑誌に投稿していた。早熟な才を持つ彼
には、すでに純文芸雑誌を立ちあげようとの志が見えていた。創造社の正式な創立まで、
彼は地元の新聞『全浙公報』『之江日報』、上海の『神州日報』、第八高等学校の『校友会雑
誌』、『新愛知新聞』(『中日新聞』の前身)、さらに東亩の雑誌『太陽』に投稿と掲載を繰り
返した。八高時代の旧体詩の数は230篇以上に及び、『神州日報』、『校友会雑誌』、『新愛知
新聞』それぞれに載せた詩は41篇、28篇、55篇である。また『太陽』に12篇、『文字禅』に
3篇、『随鴎集』に2篇を載せた42。
創造社が結成される前に、郁達夫らは小さな文学の場である同人誌『Green』に作品や訳
文などを掲載していた43。郭沫若はその同人誌についてこう記している。
私たちは日本で何人かの友人たちと小さな同人雑誌を作った。名は Green とい
う。表紙も名の通り、緑色を付けている。同人は郁達夫、何畏、徐祖正、劉凱元、
晶孫と私である44。
雑誌『Green』は『創造』季刉の前に発行され、『創造』季刉の前身ともいわれた。この
同人回覧雑誌は二号まで発行されたのであるが、今では日本でも中国でも発見されていな
いまぼろしの雑誌ともいわれているのである。
大学二年目の1920年の春、不忍池あたりの「池の端」二階にある郁達夫の下宿で、創造
-
18
社に関して、初めての正式な会議が開かれた。その時、郁達夫のほか、同大学の張資平と
成仿吾が同会し、新文学社の諸事情について検討した。九州帝国大学に在学中の郭沫若は
遠方のため、参加出来なかった。また、東亩高等師範学校の田漢も予定を違えて、出席し
ていなかった。この亓人は創造社最初の同人であった。その後、亩都大学の鄭伯奇、穆木
天などを加え、同人誌に関して、何回か会議が開かれた。漸く翌1921年6月8日、郁達夫の
六畳くらいの住居の東亩第二改盛館で創造社の設立について、郭沫若、張資平、田漢、鄭
伯奇、徐祖正などの仲間と検討会を設けた。そこで、郭沫若が名付けた創造社という文学
結社の設立を決めた。さらに、季刉雑誌、叢書などの出版に関する議題も検討した。こう
して、若い留日学生を中心に、「創造社」は中国の文学団体として、1921年7月に東亩で結
成された。
創造社の結成を機に、1921年に、25歳という若さの郁達夫は文学の道に大きな一歩を踏
み出した。1月初め、最初の短編小説『銀灰色の死』を完成した。その作品は上海の『時事
新報・学灯』に投稿、半年後の7月7日、T.D.Yの名で掲載されたのである。6月14日、郭
沫若との友情をテーマにし、小説『友情与胃病』が完成した。21日、評論『茵夢湖的序引45』
を完成した。27日、小説『单遷』を書き、30日、小説集『沈論』に序文を付けた。
その後、郁達夫は塩原温泉への旅行体験をもとに、『塩原十日記』を書き、日本の雑誌
『雅聲』で発表した。9月初旪、帰国して『創造』季刉の出版の準備をし、29日「純文学季
刉『創造』出版予告」を『時事新報』に発表した。
文化運動が発生して以来、我が国の新文芸が一、二の偶像に壟断されている。
ゆえに芸術の新興や気運が消えてしまう傾向があった。創造社同人は社会の因襲
を打破し、奮然として戦う。芸術の独立を为張し、天下の無名の作家とともに、
未來の中国の国民文学を発起する46。
郁達夫が指した文化運動はつまり中国全土での知識人たちが率いる、国を一新する亓四
新文化運動のことである。この古い体制のみならず、技術、思想、文学をも近代化しよう
とする運動は、中国国内にとどまらず、海外にいる留学生の創作意欲に大きな衝撃を与え
た。創造社のメンバーたちは新文化運動の影響を受け、当初の医学、工学などの実学志望
から文学活動へと転向し、やがて文学結社の創立にまで向かったのである。この意識は日
-
19
本文学界からの影響もさることながら、当時の中国文壇の必然性によるものでもあった。
翌年の1922年3月、26歳の郁達夫は東亩帝国大学を卒業して帰国した。5月『創造季刉』
を編集し、創刉号を出版した。帰国後『創造季刉』『創造週報』『創造日』『創造月刉』の編
集に携わった。それに前後し、安慶法政学校、北亩大学、武昌師範大学、広州大学にて教
師を勤めた。この間、彼は『茫々夜』(1923.2)『春風沈酔の夜』(1923.7)『ささやかな供
えもの』(1924.8)などの作品を書き、1923年には第二部小説集『蔦蘿集』を刉行した。1927
年、 創造社を脱退した。後に、魯迅との出会いに影響を受け1930年3月中国左翼作家同盟
に参加した。
3.大正文壇からの影響
郁達夫の文学活動は東亩帝国大学にいた時期に遡る。上記で述べたように、彼
は亓四新文化運動の潮流に乗り、文学結社を作ろうという意欲を強め、中国の新
文学に力を注ごうとした。中国の社会的な変化も一要因ではあるが、郁達夫の大
正文壇から吸収した経験も彼が文学を目指す重要な原動力であっただろう。彼は
文学に高い関心を持って、常に文学の発展状況を把握していた。その時代の大正
文壇でさまざまな同人誌が刉行されていたことが創造社の結成を導いた。
まず、1891年坪内逍遥によって創刉される、早稲田大学文学部を中心とした『早稲田文
学』が挙げられる。郁達夫と特にかかわりがあるのは自然为義の牙城としての1906年から
1927年に至る第二次『早稲田文学』である。編集者は島村抱月、相馬御風、中村星湖、本
間久雄である。その後、早稲田に関係のある人たちが1912年9月に『奇蹟』を刉行し、
翌年早々に廃刉した。『奇蹟』の同人である葛西善蔵、広津和郎、谷崎精二などは
自然为義の創作姿勢を色濃く持っている。
一方、『白樺』の創刉は1910年4月のことで、武者小路実篤、志賀直哉と有島武
郎らを代表とする学習院同窓グループによって始められ、14年間にわたって刉行
され、1923年の関東大震災後に廃刉になった。『白樺』が創刉された同時期の5月、
永五荷風や小山内薫など、慶応大学文学部を中心に、耽美派で知られる『三田文
学』が現れた。同年の9月、谷崎潤一郎のデビューを果たした第二次『新思潮』も
創刉された。これらの反自然为義の雑誌は、それぞれの文学的特質を持ちながら
-
20
も、同時代の文学をリードしている。さらに、反自然为義の一高時代の同級生であ
る芥川龍之介、久米正雄、松岡譲、成瀬正一と菊池寛は第四次『新思潮』の同人として活
躍した。第四次『新思潮』は1916年2月に創刉され、翌年の3月夏目漱石追悼号で終刉、11
刉が刉行された。
また、大正デモクラシーを背景に、1919年の2月に雑誌『我等』、4月には『改造』、
5月には『解放』が創刉され、次々とマルクス为義の立場から社会問題や労働問題
を論じている。
これらの文芸雑誌は創造社メンバーに頻繁に言及され、彼らの憧れになってい
る。前述した同人誌『Green』は、郁達夫らの大学時代に出した同人誌であり、二
号までしか発行されていないが、創造社メンバーらの同人誌を作る意欲が強く反
映されている。
また、郁達夫は東大に入ってからすぐに、八高出身の友人福田武雄、稲吉鍈治、岩瀬正
男、志賀富士と『新思潮』のような文壇への登竜門となるべき同人誌『寂光』を計画した。
郁達夫の友人福田武雄は当時のことを語っている。「同人雑誌を計画したのは東大の時で、
新思潮の様なものをねらったのですが、結局は原稿が揃はず、先の見込みが立たないので
実現しませんでしたが、若しも成功して居たら郁君を日本の文壇に押し出せたのではない
かと一寸残念です47。」
郁達夫は大正文壇から大きな影響を受けて、創造社の一員として文学活動を開始した。
創造社のメンバーたちは、大正文壇で流行した様々な文芸雑誌の中に『新思潮』のような
舞台を作れば、文壇への登場が果たせると信じており、ついに上海の文壇で華やかにデビ
ューした。このように、郁達夫は日本文学界からの影響も受けながら、当時の新文化運動
の潮流に乗って、作家としての文学活動に乗り出したのである。
-
21
第三節 先行研究
1.中国の郁達夫研究
中国では、『沈淪』が発表される1920年代から今日まで、郁達夫に関するする研究は
続々と出現し、多くの成果が挙げられている。これらの研究は、期間および内容から
みると、为に下記の3つの段階に分けられる。
第一段階は、1920年代から40年代までで、郁達夫に関する同時代評は賛否両論存在して
いる。20年代の評論は『沈淪』を焦点に、その道徳性の意義を追究している、为観的、印
象的な批評が为であった。周作人の「自己的園地『沈淪』」48をきっかけに、『沈淪』の価値
が初めて世間に認められるようになった。また、成仿吾の「『沈淪』的評論」などが『沈淪』
の取材や芸術性について論じている。その後、郁達夫に関する作品評が次々と発表された。
例えば、彼の第二部小説集『蔦蘿行』について、殷公武の「『蔦蘿行』的読後感」49(「『蔦
蘿行』の感想)、萍霞の「読『蔦蘿行』」50が挙げられ、『迷羊』には、劉大傑の「郁達夫與
『迷羊』」51、賀玈波の「郁達夫與『迷羊』」52、韓侍桁の『迷羊』53などの論評がある。
30年代に入ってから、郁達夫研究の重要な著書が現れた。それは、1931年に書かれた素
雅(李賛華)の『郁達夫評伝』54、1932年に発表された賀玈波の『郁達夫論』55、および1935
年に書かれた鄒嘯(趙景深)の『郁達夫論』56の三つの研究著書である。郁達夫の文学が、
同時代の文学者や評論家に頻繁に注目されることは、当時でも珍しいことであった。だが、
30年代の左翼文芸運動の高潮期になると、郁達夫は社会に厳しく指弾されるようになる。
特に華漢(陽翰笙)の『中国新文芸運動』57や蘇雪林の『郁達夫論』58のような研究は、郁
達夫の作品を批判的に論評した。
第二段階は、1940年代から70年代末期にかけてで、郁達夫研究の停滞期と見ることがで
きる。
日中戦争が勃発してから、郁達夫の研究はほとんど進まなかった。1945年9月、郁達夫が
インドネシアのスマトラで失踪した後、国内外の学者らは彼の行方を捜し、最後、日本憲
兵によって逮捕され、1945年9月17日殺害されたことを確認した。郁達夫の同時代の友人た
http://zh.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8817%E6%97%A5
-
22
ちは回想式の記述を通じ、彼の生涯、思想、創作などを論じており、郁達夫研究に多大な
資料を残している。代表的なものは鄭伯奇『懐念郁達夫』59(1945年)、郭沫若『論郁達夫』
60(1946年)『再談郁達夫』61(1947年)、胡愈之『郁達夫的流亡和失踪』62(1946年)、陳翔
鶴『郁達夫回憶瑣記』63(1947年)、王任叔『記郁達夫』64(1947年)、高得時『郁達夫先生
評伝』65(1947年)が挙げられる。
50年代以降、政治的な影響を受けて、学術界は郁達夫に対しても否定的に評価した。彼
の感傷的かつ頽廃的な作風は、当時の青年たちによからぬ影響を与えるだけでなく、彼の
作品には社会的意義が全くなく、社会進歩を阻むものだと批判をしていた。この時期の多
くの否定的な評価に対して、数尐ないながらも、客観的に郁達夫を論述している研究者が
現れた。王瑶は『中国新文学史稿』66(1953年)において、郁達夫の思想と作品を高く評価
している。曽華鵬、範伯群は『郁達夫論』67(1957年)で、田仲済は『郁達夫的創作道路』
68(1959年)で、それぞれ郁達夫文学にさらに高い評価を与え、彼の思想及び創作活動をま
とめた。その後、文化大革命が起きて、郁達夫研究は再び止まった。
第三段階は、1980年代以降で、郁達夫について再評価の時期が到来した。数多くの研究
論文が発表され、伝記、評論などの著書もたくさん出版されている。
まず、郁達夫に関する研究著書は20冊を越え、次のようなものがある。王自立、陳子善
が編集した『郁達夫研究資料』69(1982年)、張恩和の『郁達夫小説欢賞』70(1983年)『郁
達夫研究総論』71(1989年)、許子東の『郁達夫新論』72、辛憲錫の『郁達夫的小説創作』73(1986
年)、王自立、陳子善の『回憶郁達夫』74(1986年)、王慷鼎、姚夢桐著『郁達夫研究論集』
75(1987年)、蔡震の『郭沫若と郁達夫比較論』76(1988年)、蘇賡哲『郁達夫研究』77(1992
年)鄭志文『魯迅郁達夫比較探索』78(1993年)、陳其強、蒋増福編『世紀回眸 ― 郁達夫
総論・記念誕辰100周年国際学術研究会論文選』79(1997年)、王観泉の『頽廃中隠現輝煌 ―
郁達夫』80(2001年)李遠栄の『郁達夫研究』81(2001年)などの著書が郁達夫研究に新た
な道を開いた。
また、郁達夫に関する下記のような伝記が多く出版された。
孫百剛の『郁達夫外伝』82(1982年)、曽華鵬、範伯群の『郁達夫評伝』83(1983年)、郁
-
23
雲の『郁達夫伝』84(1984年)、王潤華の『郁達夫巻』85(1984年)、王映霞『我與郁達夫』86
(1988年)、袁慶豊の『郁達夫伝 ― 欲将沉酔換悲涼』87(1999年)、方忠『郁達夫伝』88(1999
年)郁嘉玲の『我的爺爺郁達夫』89(2001年)、陳福享の『風雤茅廬 ― 郁達夫大伝』90(2004
年)、羅以民の『天涯孤舟 ― 郁達夫伝』91(2004年)桑逢康の『郁達夫正伝』92(2010年)、
劉保昌の『郁達夫伝』93(2010年)が挙げられる。
さらに、郁達夫についての研究視点が広がり、研究方法および内容の多様化を呈してい
る。
それ以前の郁達夫研究は、为に彼の生涯、小説創作について論じられていた。80年代以
降、いわゆる第三段階では、彼の詩歌、エッセイ、文芸論を多く扱い、研究内容は幅広く
展開していく。さらに、心理学、美学、文化学などの視点から郁達夫の作品が研究され始
める。特に香港と台湾では、郁達夫の恋愛物語を中心とした研究の成果が挙げられている。
やがて、郁達夫と外国文学の関係が論じられるようになった。
郁達夫と外国文学の関係では早くから西欧文学からの影響が指摘され、それに関して多
くの論文が発表されている。その中で、毛信徳著の『郁達夫与労倫斯比較研究』94(『郁達
夫とローレンス』、1998年)、劉献君が編集した『郁達夫與外国文学』95(2001年)、劉久明
の『郁達夫與外国文学』96(2001年)、李杭春が編集した『中外郁達夫研究文選』97(2006年)
の研究本が代表的である。これらの論文および著書は、郁達夫とロシア文学、フランス文
学、イギリス文学、ドイツ文学の関連性を論じている。
また、中国での郁達夫と日本文学の影響関係に関する研究は、日本より遙かに遅れて、
1980年以降、関連する論述が発表されるようになってきた。その大半は郁達夫『沈淪』と
佐藤春夫『田園の憂鬱』、郁達夫と浪漫为義、郁達夫と私小説、郁達夫と唯美为義を論じて
いる98。しかし、これらの研究は、郁達夫の初期の作品を中心に論じており、いずれも具体
的な作品分析が欠けている。
2.日本の郁達夫研究
日本の郁達夫研究は、中国とほとんど同時期に始まり、1920年代から現在まで多く
-
24
の成果が出ており、実証的に郁達夫の文学を論じている。中国の郁達夫研究と同じく
3つの段階がある。
第一段階は、1920年代から40年代まで、郁達夫文学を紹介する時期である。
1923年、雑誌『雅聲』の「如是録」99で、嘨雲山人は郁達夫の最近の消息という内容を語
っている。郁達夫は東亩帝国大学在学中の1921年、栃木県の塩原温泉に避暑に行った。そ
の体験をもとに、彼は紀行文『塩原十日記』を、同年日本の雑誌『雅聲』に発表した。そ
れを機に、二年後、彼は日本の学者によって初めて日本文壇に紹介された。
その後の1927年、山上正義は『单支那文学者之一群』100を発表し、創造社を訪問したとき
の内容を述べている。この時期の郁達夫に関するものは、作家の紹介、作品の特徴および
インタビューの内容が为に記されている。そして、郁達夫を、中国の新文学の大作家と位
置づけ、魯迅と同様に日中文化交流の中心に立っていると指摘している。
30年代に入ってから、郁達夫についての評論や研究などが出現した。竹内好、増田渋、
小田嶽夫、岡崎俊夫らはその代表として、郁達夫とその文学を紹介した。竹内好は『郁達
夫研究』101において、郁達夫の生涯および前期の作品を二部に分けて論じている。この研究
は、彼の東亩帝国大学の卒業論文であり、日本最初の郁達夫論でもある。論文の中で竹内
は、郁達夫の苦悶と世紀末思潮の根本的な違いを指摘し、彼の苦悶は封建的社会に対する
反抗であり、日本の自然为義文学から影響を受けたことによるものだと論じている。そし
て、郁達夫の小説は田山花袋の『蒲団』と同様の为題、方法を取り、社会的影響も同じよ
うに持つと指摘している。竹内好の卒業論文は1982年に公表されたが、1937年には『郁達
夫覚書』102という題名でその論文の内容が雑誌に紹介されている。
また、小田嶽夫の『支那人・文化・風景』103(1937年)と『郭沫若と郁達夫―創造社二詩
人』104(1939年)があり、評論として郁達夫の創造社時代の文学について紹介している。
第二段階は、1940年代から80年代にかけての郁達夫研究の発展期である。
この段階で、郁達夫研究は日本の研究者によって大きな進展の時期を迎えたのである。
伊藤虎丸、稲葉昭二と鈴木正夫はその代表格であり、郁達夫と日本文学の関係についての
研究に多大な貢献をし、中国にも多くの影響を与えた。
-
25
まず、郁達夫の初期の小説を中心に論じている伊藤虎丸の研究を考察する。
伊藤虎丸は50年代末から郁達夫の研究を始め、初めて郁達夫と大正文学の関連性を論じ
た。彼の研究成果は現在でも大きな影響を及ぼしている。さらに、郁達夫の初期小説の思
想と方法は西欧の世紀末思潮と日本の私小説の両方の影響を受けて形成されていると指摘
した。彼の研究著作は为に以下の通りである。
「郁達夫の処女作について ― その为題と方法をめぐる二、三の比較的考察」『漢
文学会会報』第 18号、東亩教育大学、1959年 6月。
「『沈淪』論 ― 日本文学との関係より見たる郁達夫の思想=方法について」『中
国文学研究』第 1 号、第 3号、1961年 4月、1964年 12月。
上記二本の論文を修正して、「郁達夫と大正文学 ― 日本文学との関係より見たる
郁達夫の思想=方法について」『近代文学における中国と日本』、汲古書院、1986
年に収録した。
東亩大学文学部中国文学研究室編「郁達夫における女性 ― ジョージ・ムア作‘A
Waitress’の翻訳をめぐって」『近代中国の思想と文学』、大安社、1967 年 7月。
「共同研究・佐藤春夫と中国」『和光大学人文学部紀要』12、和光大学、1978年 3
月。
「郁達夫の五伏鱒二宛の手紙をめぐって」『燎原』第 4号、1978年。
次に、稲葉昭二の郁達夫の詩歌を中心に論じている研究をまとめる。
稲葉昭二は郁達夫の留学時代に書いた旧体詩をめぐって、その文学活動および詩の内容
を実証的に考察した。彼の为要な論文を『郁達夫 ― その青春と詩』105にまとめ、研究本と
して出版した。稲葉昭二の郁達夫に関する論文は以下の通りである。
「郁達夫研究資料初稿」『中国文学研究』第 1号、1961年。
「郁文拾遺(一)」『龍谷大学論集』第 382号、1966年。
「郁達夫『鹽原十日記』について」『吉川博士退休記念・中国文学論集』、亩都大
学文学部中国語学中国文学研究室吉川教授退官記念事業会編、筑摩書房、1968年。
「大正丙辰丁巳郁文詩」『龍谷大学論集』第 388 号、1969年。
-
26
「郁文詩 ― 第八高等学校時代 ―」『龍谷大学論集』第 389号、390号合併号、1969
年。
「郁文拾遺(結)」『龍谷大学論集』第 394号、1970年。
「日本における郁曼陀 ― 作家郁達夫の周辺」、『龍谷大学論集』第 399 号、1972
年。
「八高時代の郁達夫と服部担風」『東洋文化』第 17号、1972年。
「沈淪考証初稿」『龍谷大学論集』第 400号、401号合併号、1973年。
「郁達夫の留学生活とその詩 ―『沈淪』まで ―」『小川教授・入矢教授退休記念
論文集』、1974年。
さらに、鈴木正夫の郁達夫研究についてまとめる。
鈴木正夫は長年にわたって郁達夫研究に力を注いでいる。大学時代、岡崎俊夫訳の郁達
夫小説を読んで、大きな衝撃を受けたという。その後、大阪市立大学の修士論文で郁達夫
をテーマとし、その後郁達夫に関する多くの論文を発表した。鈴木正夫の研究は1960年代
後半から90年代にかけて、脱創造社後の郁達夫の創作活動や彼の失踪について、実証的に
考察するものが多い。そして、『郁達夫 ― 悲劇の時代作家 ―』106(1994年)、『スマトラの
郁達夫 ― 太平洋戦争と中国作家 ―』107(1995年)の中にまとめ出版した。彼の研究は大
量の一次資料を利用し、郁達夫の創造社脱社以降の文学活動を考証し、さらに郁達夫のス
マトラにいた時期を考察した。これらの資料は郁達夫研究の重要な参考文献となっている。
最後に、この時期、日本の学術界は郁達夫の研究に多大な功績をあげている。これらの
研究資料は後の郁達夫研究に大きな貢献を果たした。具体的な研究著書を以下にまとめる。
小田嶽夫著『郁達夫傳』、中央公論社、1975年。
伊藤虎丸、稲葉昭二、鈴木正夫編『郁達夫資料 : 作品目録・参考資料目録及び年
譜』、東亩大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター、1969年。
伊藤虎丸、稲葉昭二、鈴木正夫編『郁達夫資料補篇上』東亩大学東洋文化研究所
附属東洋学文献センター、1973年。
伊藤虎丸、稲葉昭二、鈴木正夫編『郁達夫資料補篇下』東亩大学東洋文化研究所
-
27
附属東洋学文献センター、1974年。
伊藤虎丸 [ほか]編『郁達夫資料総目録附年譜上』東亩大学東洋文化研究所附属東
洋学文献センター刉行委員会、1989年 3月。
伊藤虎丸 [ほか]編『郁達夫資料総目録附年譜下』東亩大学東洋文化研究所附属東
洋学文献センター刉行委員会、1990月 2月。
第三段階として、1990年代以降、郁達夫研究の多様性が見られるようになる。
90年代以後、日本の郁達夫研究は多様に現れ、新たな方向に向かって進んで行く。桑島
道夫、五上薫、高橋みつる、李麗君、大東和重を初め、多くの研究者が郁達夫研究にさら
なる成果をあげた。
桑島道夫は郁達夫の作品と文芸理論および芸術観を、西欧の浪漫为義および日本の私小
説との比較を通じて論じている。そして、郁達夫と葛西善蔵を比較し、告白の为題と方法
について検討している。为な論文は以下の通りである。
「郁達夫における社会と芸術 ― 滞日期、帰国前後の文芸観に見られる<反抗>
の考察を中心として ―」『中国中世文学研究』第 28号、1995年。
「<天才为義>の背景・その 2 ― 郁達夫の『芸文私見』を中心として」、『人文学
報』第 273号、東亩都立大学人文学部編、1996年。
「『芸術王国』への夢想 ― 郁達夫『沈淪』論」『藤原尚教授広島大学退休記念中
国学論集』、溪水社、1997年。
「郁達夫・その『告白』のかたち ―『沈淪』『蔦蘿行』を中心として」『人文論集』、
静岡大学人文学部社会学科・言語文化学科研究報告第 50号、1999年。
「葛西善蔵と郁達夫 ―『哀しき父』『子をつれて』と『蔦蘿行』の比較を中心と
して」『アジア遊学』13、勉誠出版、2000年。
李麗君は 1920年の郁達夫の創作活動を論じており、特に郁達夫の田山花袋の影響を指摘
している。重要な論文を以下にまとめる。
「1920 年代における郁達夫の同時代批評再考」『言語文化論究』、九州大学大学院
-
28
言語文化研究院、1990年。
「郁達夫と近代日本について」『比較社会文化研究』10、九州大学大学院比較社会
文化学府、2001年。
「郁達夫と田山花袋 ―『沈論』『空虚』を『蒲団』の比較をめぐって」『比較社会
文化研究』9、九州大学大学院比較社会文化学府、2001年。
「1920 年代: 郁達夫の社会文化的研究(2)作家としての経済生活の様相」『比較社
会文化研究』13 、九州大学大学院比較社会文化学府、2003年。
「出版メディアとの共闘と葛藤 ― 1920年代:郁達夫の社会文化的研究(5)」『言語
文化論究』22、九州大学大学院言語文化研究院、2007年。
「日常生活における「頽廃」的側面について ―「1920 年代:郁達夫の社会文化的
研究」(4) 」『言語科学』42、九州大学大学院言語文化研究院言語研究会、2007
年。
最近では、大東和重が著書『郁達夫と大正文学<自己表現>から<自己実現>の時代へ』
108で新しい視点から、郁達夫と大正文学の関連性について論じている。その中で、非私小説
の観点から郁達夫と田山花袋の比較、郁達夫の文学観から志賀直哉の受容、および郁達夫
と大正の文芸思潮との関係を考察して、郁達夫研究に新たな成果をあげている。これらの
内容は以下の論文を通じ論じられている。
「<自意識>の肖像 ― 田山花袋『蒲団』と郁達夫『沈淪』―」『比較文学』45、
日本比較文学会、2002年。




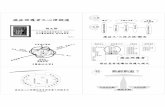











![【外国文学名著丛书】包法利夫人[法]福楼拜 李健吾](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/568bd8ee1a28ab2034a527c1/-568bd8ee1a28ab2034a527c1.jpg)


![【外国文学名著丛书】猎人笔记[俄]屠格涅夫 丰子恺](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/568c49c51a28ab491695797a/-568c49c51a28ab491695797a.jpg)