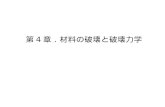解 答 令和2年度図r-10 図r-12 5...
Transcript of 解 答 令和2年度図r-10 図r-12 5...
-
1
理 論
問 1 答 (3)解説
E〔V/m〕の電界中に q〔C〕の電荷を置いたとき、
q〔C〕の電荷に働く力 F〔N〕は、 NF qE= ] gより、E〔V/m〕の電界中の 2〔C〕に働く力 NF C2 ] gは、 NF E E2 2C2 #= = ] g上下方向の移動の仕事は 0〔J〕であるので、2〔C〕
を E〔V/m〕の電界中で 0.7〔m〕移動させるのに要
する仕事W〔J〕が 14〔J〕となる。
力×距離=仕事となるので、この式から、電界の
強さ E〔V/m〕を求めると、
. J
V/m
E
E
2 0 7 14
10
# =
= ]]gg
よって、VBAは、電位=電界の強さ〔V/m〕×距離〔m〕より、
. . VV E 1 0 10 1 0 10BA # #= = = ] g
問 2 答 (2)解説
①は題意から正電荷より、電気力線は正電荷より
出て、負電荷に入るので、電気力線は図のように
なる。図の電気力線の向きより、③と④は-Q、
②は+Qとなり解答は (2)となる。
問 3 答 (3)解説
辺A-B、C-Dの電流は磁界と平行となるので、電磁力が働かない。
辺 D-A、B-Cの電流は、フレミングの左手の法則の電磁力 F 1、F 2〔N〕を生じる。
N
N
F B Ih
F B Ih
1 0
2 0
=
=
]]gg
F 1、F 2によるモーメント T1、T2〔N・m〕は、
解 答 令和 2年度図r-1
B A
E〔V/m〕
1.0〔m〕
0.4〔m〕
C0.3〔m〕
点電荷
0.7〔m〕
図r-2
Q+
Q+
Q− Q−
図r-3
I〔A〕
I〔A〕
h〔m〕
I〔A〕 h〔m〕
A B
CDB0〔T〕
F1 F2
電磁力の向き
m2h〔 〕 m
2h〔 〕
-
2
N m
N m
T FhB Ih
h
T FhB Ih
h
2 2
2 2
1 1 0
2 2 0
# $
# $
= =
= =
]]
gg
T T1 2= より偶力のモーメント (回転力 )は、 N mT2 1 $] gより、 N mB Ih h Ih B2
20
20# # $= ] g
〔参考〕偶力とは、互いに平行で逆向きの二つの対の力をいう。
問 4 答 (4)解説
(1) 磁力線は、磁石の N極から出て S極に入る。 …正しい。
(2) 磁極周囲の物質の透磁率をμ〔H/m〕とすると、m〔Wb〕の磁極から mn〔本〕の磁力線が出入りす
る。 …正しい。
(3) 磁力線の接線の向きは、その点の磁界の向きを表す。…正しい。
(4) 磁力線の密度は、その点の磁束密度を表す。 …誤り。
磁力線の密度は磁界の強さを表すもので、磁束密度とは異なる。
(5) 磁力線同士は、互いに反発し合い、交わらない。 …正しい。
問 5 答 (4)解説
電線の抵抗 R〔X〕は、抵抗率を t〔X・m〕、断面積を S〔m2〕、長さを l〔m〕とすると、 RSlXt= ] gと
表される。与えられた断面積と抵抗率の値を代入し、電線の長さは 1 000〔m〕として、各電線の抵抗
値を求めると次のようになる。
. .
. .
. .
. .
RSl
RSl
RSl
RSl
8 90 109 10
0 99
2 50 105 10
0 5
1 47 101 10
1 47
1 55 102 10
0 78
1 000
1 000
1 000
1 000A
B
C
D
85
85
85
85
##
##
##
##
X
X
X
X
]
]
t
t
t
t
= =
= = =
= = =
= =
--
--
--
--
]]]
]ggg
g
各抵抗値の大きさを比較して大きい順に並べると、R R R RC A D B2 2 2 となる。
-
3
図r-4
VV〔 〕
1I
2I 3I
1 3R = 〔 〕
2 6R = 〔 〕 3 2R = 〔 〕
問 6 答 (2)解説
図において、I 2と I 3の比は抵抗値の比の逆であ
ることから、
I I 2 6 1 32 3 | || = =
I I I1 2 3= + より、
I I I 1 3 1 3 4 1 31 2 3| | | | | |= + =] g
ここで、電力の比を求めると、
P P P 4 3 1 6 3 2 48 6 181 2 3 2 2 2| | # | # | # | |= =] ] ]g g g
したがって、消費電力の大きい順は、P P P1 3 22 2 となる。
問 7 答 (1)解説
図 (a)を描きかえると図 (b)のようになる。
テブナンの定理により、図 (c)の Eab、Rabを求めると、
Sの両端の電圧は 1〔V〕と与えられているので、
VE 1ab = ] gRabは、電源を短絡除去したときの a-b間の合成抵抗となるので、
R1 41 4
2 32 3
2ab# #
X=+
++
= ] gしたがって、Sを閉じたときの 8〔X〕の電流 I〔A〕は、
. AIRE
8 2 81
0 1ab
ab=
+=
+= ] g
図r-5
1 〔 〕
2 〔 〕
3 〔 〕
4 〔 〕5 V〔 〕
8 〔 〕 AI〔 〕
図(a)
図r-6
a
b
1 〔 〕
2 〔 〕 3 〔 〕
4 〔 〕
S
8 〔 〕AI〔 〕
5 V〔 〕
図(b)図r-7
SabR 〔 〕
ab VE〔 〕8 〔 〕
図(c)
AI〔 〕
-
4
問 8 答 (4)解説
2〔nF〕のリアクタンス XCは、
.
.XC1
2 3 14 1 000 2 10
179 6C 6# # # #
X]~
= = - ] g 回路のインピーダンスは、Z =電圧 / 電流〔X〕より、
.
Z0 110
100 X= = ] g抵抗 R〔X〕は、
. .R 100 79 6 60 52 2 X]= - ] g問 9 答 (2)解説
回路 Aにおいて LC 12~ = が成り立つとき、直列共振の状態であり、電流位相に対し V・
Lは 90°進み
位相、V・
Cは 90°遅れ位相となる。電流位相と V・
Rは同位相となるので、下図のベクトル図となる。
回路 Bにおいて LC 12~ = が成り立つとき、並列共振の状態であり、電圧位相 V・
に対し I・
Cは 90°進
み位相、I・
Lは 90°遅れ位相となるので、下図のベクトル図となる。
したがって、解答は (2)となる。
問 10 答 (2)解説
v(t)の最終値は、コンデンサを開放(外す)したと
きの電圧より、分圧の公式により、
. V103 1
12 5#
+= ] g
または、 . AI 10 4 2 5= = ] gなので、1〔X〕の電圧は、 . . V2 5 1 2 5# = ] g
図r-8
0.1 A〔 〕2 μF〔 〕 R 〔 〕
10 V〔 〕1 000 Hz〔 〕
図r-13
3 〔 〕
10 V〔 〕 1 〔 〕 1 F〔 〕
図r-9
VV〔 〕rad/s〔 〕
R 〔 〕 HL〔 〕 FC〔 〕
回路A
図r-11
VV〔 〕rad/s〔 〕
R 〔 〕 HL〔 〕 FC〔 〕
回路B
図r-10
図r-12
-
5
破線から左側にテブナンの定理を適用し、抵抗 Rを求めると、電源は短絡除去し破線から左を見た
合成抵抗なので、
.R3 13 1
0 75#
X=+
= ] g回路の時定数 T〔s〕は、C= 1〔F〕、R = 0.75〔X〕より、
. . sT CR 1 0 75 0 75#= = = ] g
問 11 答 (1)解説
可変容量ダイオードとは、図に示す原理図のように(ア)逆方向 電圧 V〔V〕を加えると静電容量が変化するダイオードである。p形半導体と n形半導体を接合すると、p形半導体のキャリヤ (図
中の●印 )と n形半導体のキャリヤ (図中の○印 )が pn接合面付近で拡散し、互いに結合する
と消滅して(イ)空乏層 と呼ばれるキャリヤがほとんど存在しない領域が生じる。可変容量ダイ
オードに(ア)逆方向 電圧を印加し、その大きさを大きくすると、(イ)空乏層 の領域の幅 dが
(ウ)広く なり、静電容量の値は(エ)小さく なる。この特性を利用して可変容量ダイオードは
(オ)無線通信の同調回路 などに用いられている。
問 12 答 (5)解説
箔検電器の電極に紫外光 (振動数の大きな光 )を照射すると、紫外光のエネルギーを吸収して光電子
を放出する。電子は箔の電荷 Q〔C〕を減少させ箔検電器の箔が閉じる。
したがって、(5)が解答となる。
問 13 答 (5)解説
(1) 演算増幅器には電源が必要である。 …正しい。
(2) 演算増幅器の入力インピーダンスは、非常に大きい。 …正しい。
(3) 演算増幅器は比較器として用いられることがある。 …正しい。
(4) 図 1の回路は正相増幅回路、図 2の回路は逆相増幅回路である。 …正しい。
一般に、正相増幅回路は非反転増幅回路、逆相増幅回路は反転増幅回路という。
図r-14
-
6
(5) 図 1の回路は、抵抗 RSを 0〔X〕に (短絡 )し、抵抗 RFを∞〔X〕に (開放 )すると、ボルテージホロワである。 …誤り。
正しくは、「抵抗 RSを∞〔X〕に (開放 )し、抵抗 RFを 0〔X〕に (短絡 )すると、ボルテージホロワ
である。」となる。
図 1の非反転増幅回路の電圧増幅度は、次式となる。
AVV
RR R
RR
1S
S F
S
F
1
2= =
+= +y
ここで、R 0F X= ] g、RS 3 X= ] gとすると、 A 1 0 1
3= + =y
電圧増幅度は、1となり入力電圧と出力電圧は同じ大きさとなる。
ボルテージホロワは、入力インピーダンスが大きく、出力インピーダンスが小さいバッファ (イ
ンピーダンス変換器 )として用いられる。
問 14 答 (1)解説
電磁誘導に関するファラデーの法則とは、コイルを貫く磁束が変化すると、コイルに起電力が発生す
るというものである。
時間 Dt〔s〕の間に磁束が Dz〔Wb〕だけ変化したとき、巻数 N〔回〕のコイルに発生する起電力 e〔V〕は、
Ve NtzDD
=- ] gこのファラデーの法則をもとに、光を計測することはできない。
図r-15
図1
図r-16
図2
図r’-1
F 0R = 〔 〕
SR = 〔 〕
1 VV〔 〕 2 VV〔 〕
F 0R = 〔 〕
SR = 〔 〕
2 VV〔 〕1 VV〔 〕
図 ボルテージホロワ
-
7
問 15 答 (a)…(2)、(b)…(3)解説
(a) Δ結線となっているR 9 X= ] gを Y変換したときの抵抗値 R'〔X〕は、
R39
3 X= =l ] gY結線で一相を取り出すと図 1のようになり、R 3 X=l ] gとX 4 X= ] gの合成インピーダンスを Z〔X〕とすると、
Z R X 3 4 52 2 2 2 X= + = + =l ] gよって、線電流 I〔A〕は、
AI
53
200
5 3
200= = ] g
求める I ab〔A〕はΔ結線の相電流であるから、
. AII
3 5 3
200
3
115200
13 3ab # ]= = = ] g
(b) 相電圧を E・
a、E・
b、E・
cとし、電圧のベクトル図を描
くと図 3のようになる。単相電力計W1は、線間電圧 V
・
bcと線電流 I・
aを測定
していることから、その指示値 P l〔W〕は、図 2から
sin54
i= より、
W
. kW
cos
sin
P V I2
2005 3
200
2005 3
20054
3 695
3 70
bc a1
# #
# #
]
]
ri
i
= -
=
=
o o d n
]] gg
図r-18
4 ΩX =〔 〕
3 ΩR =〔 〕200 V3〔 〕
AI〔 〕
図1図r-19
3 ΩR =〔 〕
4 ΩX =〔 〕ΩZ〔 〕
rad〔 〕
図2
図r’-2
aE
bE
cE
cE−
aI
2 −
bcV
図3
-
8
問 16 答 (a)…(4)、(b)…(2)解説
(a) 電圧計 V1で 150〔V〕測定したときに流れる電流を I 1〔A〕とすると、
. mAI18 10
1508 331 3#]= ] g
電圧計 V2で 300〔V〕測定したときに流れる電流を I 2〔A〕とすると、
mAI30 10
300102 3#
= = ] gよって、この 2つの電圧計を直列に接続するとき、流すことのできる電流の最大値は 8.33〔mA〕
となる。
このとき、電圧計 V2で測定される電圧は、
8.33〔mA〕× 30〔kX〕≒ 250〔V〕
したがって、2つの電圧計を直列に接続して使用したときに測定できる電圧の最大値〔V〕は、
150+ 250= 400〔V〕
(b) 2つの直流電圧計の指示を最大目盛にして測定するためには、直流電圧計 V1の抵抗を変化させ、10〔mA〕の電流が流れることができるようにする必要がある。 …(ア )
電圧計 V1に 10〔mA〕の電流が流れるとき、V1の抵抗〔kX〕は、
k10 10
150153#
X=- ] g電圧計 V1の内部抵抗は 18〔kX〕であるため、15〔kX〕にするためには、抵抗を並列に接続する必要がある。 …(ウ )
並列に接続する抵抗を r〔kX〕とすると、
rr
1818
15#+
=
∴ r= 90〔kX〕 …(イ )
これに直流電圧計 V2を直列に接続することで、450〔V〕の電圧を測定できる。 …(エ )
問 17 答 (a)…(5)、(b)…(2)解説
(a) 各コンデンサへの印加電圧が等しいため、電界の公式EdV
= より、極板間隔 dが小さいほど、
電界は強くなる。
よって、極板の電界の強さの大きい順は、極板間隔が小さい順の③>②>①となる。
(b) 電界の公式EdV
= より、電圧V Ed= で各コンデンサの絶縁破壊電圧を求めると、
① 10〔kV/mm〕× 4.0〔mm〕= 40〔kV〕
② 20〔kV/mm〕× 1.0〔mm〕= 20〔kV〕
③ 50〔kV/mm〕× 0.5〔mm〕= 25〔kV〕
よって、絶縁破壊電圧の大きさが大きい順は①>③>②となる。
-
9
問 18 答 (a)…(3)、(b)…(3)解説
(a) VV 6CE = ] gのとき、R 2に加わる電圧 VR2〔V〕は、 VV V V 12 6 6CC CER2 = - = - = ] gよって、R 2に流れる電流 I C〔A〕は、
mAIRV
1 10
66C
R
2
2
3#= = = ] g
問題図 2において、 VV 6CE = ] gと mAI 6C = ] gの交点を通るグラフは AI 30B n= ] gであるから、求めるベース電流 I Bは 30〔nA〕となる。
(b) AI 0C = ] gのとき VV V 12CE CC= = ] gであり、VV 0CE = ] gのとき mAI
1 10
1212C 3#
= = ] gとなることから、負荷線を引くと右図のようになる。
AI 30B n= ] gとの交点を Pとすると、問題文において、最大値 10〔nA〕のi Ib B+ がベースに流
れたとあるので、特性曲線の P1から P2の間を
変化することになる。
よって、VCE cey+ は 6〔V〕を中心に± 2〔V〕の
範囲で変化するため、出力交流信号電圧 voの
最大値〔V〕は 2.0〔V〕となる。
図r-21
〔μA〕
〔μA〕
〔μA〕
〔μA〕
〔μA〕
〔μA〕
〔V〕
〔mA〕
P1
P2
P
-
1 0
電 力
問 1 答 (3)解説
水撃作用の発生による影響を緩和する目的で設置される水圧調整用水槽をサージタンクという。サー
ジタンクにはその構造・動作によって、差動式、小孔式、水室式などがあり、いずれも開放構造である。したがって、下線部の密閉構造が誤りで、正しくは開放構造である。
水撃作用の緩和策
① サージタンクの設置: 圧力水路と水圧管との接続部に設け、水撃作用による水圧上昇を水槽内部
の水位の昇降によって、水撃作用を軽減する。
② ガイドベーンあるいは入口弁の緩動動作: 水圧上昇を抑えるため、ガイドベーンあるいは入口弁
の閉鎖時間を遅くする。
③ 制圧機の設置: 水圧管内の水の一部を一時的に放出させ圧力の上昇を抑制する。一時的に水を放
出する装置を制圧機という。
問 2 答 (3)解説
汽力発電所の復水器は蒸気タービン内で仕事を取り出した後の(ア)排気 蒸気を冷却して凝縮させる
装置である。復水器内部の真空度を(イ)高く 保持してタービンの(ア)排気 圧力を(ウ)低下 させる
ことにより、(エ)熱効率の向上を図ることができる。なお、復水器によるエネルギー損失は熱サイ
クルの中で最も(オ)大きい。復水器とは、タービンで仕事を終えた蒸気を復水器内に導き、復水器内部に設置した冷却器で蒸気を
冷却凝縮させて真空を生じさせる装置である。この復水器の真空度を向上させることにより、タービ
ン入口と出口の間に大きな圧力差が生まれて効率的にタービンを動かすことができる。
問 3 答 (1)解説
a) 非常調速機はタービンの回転速度が定格を超える一定値以上に上昇すると、自動的に蒸気止弁を
閉じて、タービンを停止させる装置である。
非常調速機は、調速機構とは独立にタービンを停止する保安装置で、万一、調速機に不具合が生じ
て回転数の上昇を抑えることができないと、大事故になるおそれがある。
したがって、この文章は適切である。
b) 燃料遮断装置とは、ボイラ水の水位低下等、ボイラ水の循環が円滑に行われないとき、自動的に
燃料の供給を遮断する装置である。
したがって、この文章は適切である。
解 答 令和 2年度
-
1 1
c) 題意の役割を果たす弁は「安全弁」で、蒸気加減弁はタービンへ流入する主蒸気の流量を制御し
発電量を制御するための弁である。
したがって、この文章は不適切である。
d) 軸受油圧低下遮断装置は、タービン軸受の保護のため、タービンの軸受油圧が低下したときに、
タービンをトリップさせる装置である。
したがって、この文章は適切である。
e) 比率差動継電器は、発電機固定子巻線や変圧器巻線間の短絡事故を検出・保護するものである。
したがって、この文章は適切である。
問 4 答 (2)解説
核分裂は様々な原子核で起こるが、ウラン 235などのように核分裂を起こし、連鎖反応を持続できる
物質を(ア)核分裂性物質 といい、ウラン 238のように中性子を吸収して(ア)核分裂性物質 になる物
質を(イ)親物質 という。天然ウラン中に含まれるウラン 235は約(ウ)0.7〔%〕で、残りは核分裂を起こしにくいウラン 238である。ここで、ウラン 235の濃度が天然ウランの濃度を超えるものは、濃
縮ウランと呼ばれており、濃縮度 3〔%〕から 5〔%〕程度の(エ)低濃縮ウラン は原子炉の核燃料として使用される。
ウランには、ウラン 235のように核分裂を起こし、連鎖反応を持続できる核分裂性物質と、ウラン
238のように核分裂を起こさないウラン 238とがある。ウラン 238は中性子を吸収して核分裂性物質
になる物質でこれを親 (おや )物質という。
天然ウランの構成は、99〔%〕以上がウラン 238で、約 0.7〔%〕がウラン 235である。現在運用されて
いる商用原子炉の燃料としては、ウラン 235を 3〔%〕から 5〔%〕程度に濃縮した低濃縮ウランが使用
されている。
問 5 答 (3)解説
太陽光発電は、太陽電池の光電効果を利用して太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する。地球
に降り注ぐ太陽光エネルギーは、1〔m2〕当たり 1秒間に約(ア)1〔kJ〕に相当する。太陽電池の基本
単位はセルとよばれ、(イ)1〔V〕程度の直流電圧が発生するため、これを直列に接続して電圧を高
めている。太陽電池を系統に接続する際は、(ウ)パワーコンディショナにより直流電力を交流電力に変換する。
一部の地域では太陽光発電の普及によって(エ)日中 に電力の余剰が発生しており、余剰電力は揚水発電の揚水に使われているほか、大容量蓄電池への電力貯蔵に活用されている。
-
1 2
〔参考〕現在設置されている太陽電池の変換効率は 20〔%〕程度であり、1〔m2〕当たり約 200〔W〕の電力が得ら
れる。セルを直並列に接続して電圧と出力を高めたものがモジュールでおおよそ 200〔W〕、50〔V〕程
度発電する。
問 6 答 (1)解説
(1) 電線に一様な微風が吹くと、電線の背後に空気の渦が生じて電線が上下に振動する微風振動を発生する。振動エネルギーを吸収するダンパを電線に取り付けることで、この振動による電線の
断線防止が図られている。
微風振動による電線の断線防止対策として、下記の 2つが挙げられる。
① ダンパを設置して、電線の振動エネルギーを吸収する。
② アーマロッドを設けてクランプ付近の電線を強化して電線の素線切れや断線を防止する。
したがって、サブスパン振動が誤りで微風振動が正しく、(1)の文章が誤りである。
〔参考〕サブスパン振動とは多導体固有の振動をいい、サブスパンとは、スペーサとスペーサで区切られた区
間のことである。風などが原因となって生じるが、振動防止としてはスペーサの取り付け位置を工夫
することである。
問 7 答 (5)解説
(5) 真空遮断器は経済性に優れるが、空気遮断器に比べて動作時の騒音が大きい。下線部が誤りで、正しくは空気遮断器に比べて動作時の騒音が小さい。
〔参考〕他の遮断器の種類と特徴油遮断器:接点の開閉を油中で行う。
磁気遮断器:電磁力を利用してアークを消弧させる。
空気遮断器:圧縮空気を消弧媒質とする。
ガス遮断器:不活性ガス (SF6ガス )を消弧媒質とする。
d-1
図 太陽光発電システム
d-2
電源
77〔kV〕
変圧器
77 / 6.6〔kV〕
20〔MV·A〕基準
10.6〔%〕
20〔MV·A〕基準
1.1〔%〕
遮断器 A点 負荷
-
1 3
問 8 答 (4)解説
下図は問題文を図示した回路である。短絡点をA点とし、A点において三相短絡事故が発生したと
きの三相短絡電流及び遮断器の定格遮断電流を計算する。
故障点から電源側をみた百分率インピーダンス Z〔%〕は、下記のようになる。
. . . %Z 1 1 10 6 11 7= + = ] g 故障点の基準電流 I n〔A〕は、線間電圧をVn〔kV〕、基準容量をPn〔kV・A〕とすると、下記のようになる。
.
. kAIV
P
3 3 6 6
20 101 75n
n
n3
#
#]= = ] g
よって、故障点に流れる三相短絡電流 I S〔kA〕は、
% .
. . AkIZ
I100
11 7100
1 75 14 96S n# # ]= = ] gしたがって、遮断器の定格電流 I nは、三相短絡電流 I Sの直近の上位の値の 20.0〔kA〕となる。
問 9 答 (2)解説
避雷器は、雷又は回路の開閉などに起因する過電圧の(ア)波高値 がある値を超えた場合、放電によ
り過電圧を抑制して、電気施設の絶縁を保護する装置である。特性要素としては(イ)ZnO が広く
用いられ、その(ウ)非線形 の抵抗特性により、過電圧に伴う電流のみを大地に放電させ、放電後は
(エ)続流 を遮断することができる。発変電所用避雷器では、(イ)ZnO の優れた電圧 -電流特性を利
用し、放電耐量が大きく、放電遅れのない(オ)ギャップレス避雷器 が主に使用されている。
従来型の避雷器は、特性要素と直列ギャップで構成されているが、最近は ZnO(酸化亜鉛素子 )を用
いたギャップレス避雷器が主流である。
酸化亜鉛素子は、非常に大きな非直線性の電圧 -電流特性を持っており、印加電圧が小さな領域では絶縁体として働き、雷サージのような電圧が大きな領域では導体として働く。
続流とは、避雷器が放電した後、引き続き線路電圧によって流れる電流をいう。
d-1
図 太陽光発電システム
d-2
電源
77〔kV〕
変圧器
77 / 6.6〔kV〕
20〔MV·A〕基準
10.6〔%〕
20〔MV·A〕基準
1.1〔%〕
遮断器 A点 負荷
-
1 4
問 10 答 (1)解説
(ア ) 送電線路には、電線の種類・断面積・配置によって定まる抵抗、作用インダクタンス、作用
静電容量、漏れコンダクタンス (省略する場合もある )がある。(イ ) 電線の断面積を A〔m2〕、抵抗率を t〔X・m〕とすると、長さ ,〔m〕の電線 1本の抵抗 R〔X〕は
下記の式で表される。
RA,Xt= ] g
導体に交流が流れると表皮効果により、直流より抵抗値が増加する。この現象は周波数が高いほど、導体断面積が大きいほど顕著である。
(ウ ) 三相送電線路のインダクタンスは、自己インダクタンスと相互インダクタンスを合わせたも
ので、これを作用インダクタンスという。半径 r〔m〕の 3本の電線が線間距離 D〔m〕で配置され
ている場合、電線の比透磁率を nsとすれば作用インダクタンス Lは①式で表される。
. .logLrD
0 4605 0 05 s10 n= + …①
三相送電線路の静電容量は、2線間の線間静電容量と電線 1本と大地間の対地静電容量を合わせ
たもので、これを作用静電容量という。作用静電容量は②式で表される。
.
logC
rD
0 02413
10
= …②
①、②式より Lと Cは D/rの値に影響される。作用静電容量 Cは D/rが大きくなれば分母が
大きくなり Cの値は小さくなる。(エ ) 短距離送電線路ではインダクタンス成分にくらべて静電容量成分が小さいので、静電容量を
無視した回路として取り扱うことができる。
中距離送電線路では、静電容量は無視できないので、作用静電容量によるアドミタンスを 1か
所又は 2か所にまとめる集中定数回路が近似計算に用いられる。(オ ) 送電端側と受電端側の中間の 1ヶ所に集中して取り扱う T形回路または送電端側と受電端側
の 2か所にまとめるπ形回路がある。
問 11 答 (5)解説
(5) 絶縁破壊事故が発生した場合、①架空送電線路では自然に絶縁回復することは稀であるが、 ②地中送電線路では自然に絶縁回復して再送電できる場合が多い。下線部①、②の記述が誤りで、正しくは下記のように訂正される。
① 架空送電線路では雷による1線地絡事故の場合、ある一定時間たてば自然に絶縁回復して再
送電できる場合が多い。
② 地中送電線路では中心導体と遮へい導体との短絡 (送電線路としては地絡状態 )事故が大部分
で永久事故となるので停電時間も長くなる。
-
1 5
問 12 答 (5)解説
高圧カットアウトは、柱上変圧器の一次側に設置して開閉動作や過負荷保護用として使用される。形
状は箱形と円筒形がある。箱形は磁器製のケースに収容されており、需要家の受変電設備や進相コンデンサの開閉に使用される。円筒形は磁器製で円筒状をしており、配電用変圧器の保護や、電鉄用給
電線に使用されている。
したがって、(5)の文章は誤りである。
問 13 答 (5)解説
スポットネットワーク方式の系統構成図を示す。
受電系統構成を特別地中配電系統側から並べると、断路器→ネットワーク変圧器→プロテクタヒュー
ズ→プロテクタ遮断器→ネットワーク母線となる。
d-3
d-4
V
I
誘導体
図 1
-
1 6
問 14 答 (1)解説
(1) 絶縁油の誘電正接は、変圧器、電力ケーブルに使用する場合には小さいものが、コンデンサに使用する場合には大きいものが適している。下線の部分が誤りで、コンデンサにおいても誘電正接の数値の小さいものほど良い。
誘電体に、図 1のように正弦波電圧を加えると、図 2のような有効電流 I Rと無効電流 I Cが流れ、微小な有効電流 I Rによって損失が発生する。図 3は電圧と電流の関係をベクトル図で表したもので、図中のδを誘電損角といい劣化の目安となる。
問 15 答 (a)…(4)、(b)…(4)解説
(a) ある河川の流域面積を A〔km2〕、年降水量を p〔mm〕、1年間の流出水量 V〔m3〕、年間の平均流
量を Q〔m3/s〕、流出係数を kとすると、流域の降水による年間の全水量は下記の式になる。
mA p Ap10 10 106 3 3 3# # # #=- ] gまた、1年間の流出水量 V〔m3〕は、
mV k Ap kAP10 103 3 3# # #= = ] g 上記の式を用いて、年間の平均流量 Q〔m3/s〕を求めると、
..
.m /sQ
kAp365 24 60 60
10365 24 60 60
0 7 15 000 750 10
3 154 10
7 875 10250 3
3 3
7
9
# # #
#
# # ## # #
#
#]= = = ] g
(b) 発電所の出力を P〔kW〕、有効落差を H〔m〕、水車と発電機の総合効率を hgとすると、
. . . kWP QH9 8 9 8 250 100 0 8 196 000g # # #h= = = ] g発電所の設備利用率を hs、年間の発電電力量をW〔kW・h〕とすると、
. . kW hW P 24 365 196 000 24 365 0 6 1 03 10 1 10s 9 9# # # # # # # # $]h= = = ] g
問 16 答 (a)…(3)、(b)…(4)解説
(a) 1回線あたりの送電電力 P〔kW〕とすると、1回線あたりの送電電力 Pは 2 500〔kW〕である。
受電端電圧を V〔V〕、1線を流れる電流を I〔A〕、負荷力率を cos iとすると、
.
. Acos
IV
P
3 3 22 10 0 9
2 500 1072 9
3
3
# # #
#
i= = = ] g
d-3
d-4
V
I
誘導体
図 1
d-5
I
図 2
RI CI 誘電体
d-6
図 3
V RI
CI
d-7
40〔A〕
60〔A〕
1.5〔km〕
1.5〔km〕 2.0〔km〕
1.0〔km〕
30〔A〕
40 + i〔A〕
90-i〔A〕 30-i〔A〕
i〔A〕
d-5
I
図 2
RI CI 誘電体
d-6
図 3
V RI
CI
d-7
40〔A〕
60〔A〕
1.5〔km〕
1.5〔km〕 2.0〔km〕
1.0〔km〕
30〔A〕
40 + i〔A〕
90-i〔A〕 30-i〔A〕
i〔A〕
-
1 7
(b) 送電損失を P ,〔W〕、電線 1〔本〕当たりの電気抵抗を R〔X〕とすると、 I R3=P 2, より、
.
.RI
P
3 3 72 9
125 107 842 2
3
#
#X= = =
, ] g電線の断面積を A〔mm2〕、こう長を ,〔m〕とすると 1線当たりの電気抵抗 R〔X〕は、R
A351 ,
=
で表されるので、
.
. mmAR35
1351
7 8425 10
91 13
2# ##,
]= = ] g送電損失は 5〔%〕以下にするために 91.1〔mm2〕より太い電線の 92〔mm2〕を選択する。
問 17 答 (a)…(4)、(b)…(2)解説
(a) AD間の電流は 90〔A〕で抵抗は 0.4〔X〕、DC間の電流は 30〔A〕で抵抗は 0.3〔X〕であるので、
AC間の線間電圧降下 vACは、
. . . Vv v v 3 90 0 4 3 30 0 3 77 9AC AD DC # # # #= + = + = ] g(b) 開閉器 Sを投入した場合、Bから C方向に流れる電流を i〔A〕とすると、この時の電流分布図
は下図のようになる。
A点からA→ B→ C→ D→Aの順にループを 1巡したときの電圧降下は 0であるので、
. . . .i i i i0 3 40 0 3 0 3 30 0 4 90 0# # # #+ + - - - - =] ] ]g g g
上式を解くと、
.
. Ai1 333
25 4]= ] g
d’-1
40〔A〕
60〔A〕
1.5〔km〕
1.5〔km〕 2.0〔km〕
1.0〔km〕
30〔A〕
40 + i〔A〕
90-i〔A〕 30-i〔A〕
i〔A〕
0.5〔km〕
-
1 8
機 械
問 1 答 (1)解説
直流他励電動機の等価回路は図 1となる。a 他励電動機は、(ア)界磁電流 I fと(イ)電機子電流I a を独立した電源で制御できる。磁束 z〔Wb〕は、
(ア)界磁電流 I fに比例する。
k If1z= (k1:比例定数 )
b 磁束一定の条件で(イ)電機子電流 I aを増減すれば、
(イ)電機子電流 I aに比例するトルク T〔N・m〕を制御できる。
T k Ia2z= (k2:比例定数 )
c 磁束一定の条件で(ウ)電機子電圧 Eを増減すれば、(ウ)電機子電圧 Eに比例する回転数N〔min-1〕
を制御できる。E k N3z= (k3:比例定数 )より、
NkE
3z=
d (ウ)電機子電圧 E一定で磁束を増減すれば、ほぼ磁束に反比例する回転数を制御できる。回転数
の(エ)上昇 のために、(ア)界磁電流 I fを弱める制御がある。 k If1z= (k1:比例定数 )より、
NkE
k k IE
f3 1 3z= =
問 2 答 (3)解説
界磁に永久磁石を用いた小形直流発電機は、図 1の直流他励発電機である。
回転子を固定した場合の等価回路は図 2となり、端子電圧 VV 3= ] g、定格電機子電流 AI 1a = ] gである。起電力 E〔V〕は、固定したため回転数N 0= より、
VE k N 0z= = ] g (k:比例定数 )よって、電機子巻線抵抗r
IV E
13 0
3aa
X=-
=-
= ] g電機子回路を開放した回路は図 3となり、電機子電流は流れず AI 0a = ] gとなる。よって、電機子抵抗 raでの電圧降下がないため、端子電
圧 Vは電機子電圧 Eと等しく、15〔V〕となる。
解 答 令和 2年度
k-1
fr
fI
aI
E M
図 1
V
ar
界磁側 電機子側
k-2
fr
fI aI
E G
図 1 他励発電機
V
ar
k-3
fr〔Ω〕
fI〔A〕 a 1I =〔A〕
0E = 〔V〕 G
図 2 拘束試験
3V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
固定
k-1
fr
fI
aI
E M
図 1
V
ar
界磁側 電機子側
k-2
fr
fI aI
E G
図 1 他励発電機
V
ar
k-3
fr〔Ω〕
fI〔A〕 a 1I =〔A〕
0E = 〔V〕 G
図 2 拘束試験
3V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
固定
k’-1
fr〔Ω〕
fI〔A〕 a 1I =〔A〕
0E = 〔V〕 G
図 2 拘束試験
3V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
固定
k’-2
2
2E
0 0t
0 2Tt + 0
t T+ t
図 2
2E T
k’-3
ゲイン〔dB〕
40
0
100
1 2 20 200
真数
角周波数〔rad/s〕
20− 〔dB/dec〕
図 1 ボード線図
-
1 9
定格運転時の回路は図 4となり、端子電圧 VV E I r 15 1 3 12a a #= - = - = ] gであるから、効率 h〔%〕は、 %
EIVI
1001512
100 80a
a# #h= = = ] g
問 3 答 (4)解説
一次巻線 (三相 Y結線で考える )は、三相電源を加え、これを a、b、c相とすると図 1のように表され、一相等価回路は図 2となる。
(1) 絶縁材料の耐熱クラスは、A種 (105〔°C〕)、B種 (130〔°C〕)、F種 (155〔°C〕)、H種 (180〔°C〕)
等があり、基準巻線温度 T〔°C〕が、A種と B種であれば 75〔°C〕、F種と H種であれば 115〔°C〕
の値が用いられる。
(2) 一次巻線の各端子間抵抗の平均値を R〔X〕とすると、一相抵抗 r〔X〕は、周囲温度を t〔℃〕とす
ると、
r RtT
2 235235$ X=
++ ] g
(3) 無負荷試験では、負荷 ( 図 2における a-b間 )を開放することにより、負荷電流は流れず 0〔A〕となり、励磁回路 (鉄損箇所 )に電流が流れるので、一次側における電圧〔V〕、電流〔A〕及び電力
P i〔W〕を測定する。P iは鉄損〔W〕になる。
定格電圧 Vn〔V〕、無負荷入力 P i〔W〕、無負荷電流 I 0〔A〕とその有効分電流 I 0w〔A〕、無効分 I 0l〔A〕、
コンダクタンス g0〔S〕、サセプタンス b0〔S〕とすると、
A A S SIV
PI I I g
V
Pb
VI
g3
3w
n
il w
n
i
n0 0 0
202
0 2 002
02= = - = = -e o] ] ] ]g g g g、 、 、
k-4
fr 〔Ω〕
fI 〔A〕 a 0I = 〔A〕
15E = 〔V〕 G
図 3 無負荷試験
15V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
k-5
fr 〔Ω〕
fI 〔A〕 a 1I = 〔A〕
15E = 〔V〕 G
図 4 定格運転
12V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
k-6
r〔Ω〕
r〔Ω〕
r〔Ω〕
a
b
c
図 1 一次巻線
k-4
fr 〔Ω〕
fI 〔A〕 a 0I = 〔A〕
15E = 〔V〕 G
図 3 無負荷試験
15V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
k-5
fr 〔Ω〕
fI 〔A〕 a 1I = 〔A〕
15E = 〔V〕 G
図 4 定格運転
12V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
k-6
r〔Ω〕
r〔Ω〕
r〔Ω〕
a
b
c
図 1 一次巻線
k-4
fr 〔Ω〕
fI 〔A〕 a 0I = 〔A〕
15E = 〔V〕 G
図 3 無負荷試験
15V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
k-5
fr 〔Ω〕
fI 〔A〕 a 1I = 〔A〕
15E = 〔V〕 G
図 4 定格運転
12V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
k-6
r〔Ω〕
r〔Ω〕
r〔Ω〕
a
b
c
図 1 一次巻線
k-7
1I
1r 2r
一次巻線 二次巻線
c2p 負荷 一次
銅損
鉄 損 二次
銅損
2I
mP
2P 21 r
ss −
c1p
0g 0b
0wI
0lI
a
b
図 2 一相等価回路
Y
1x 2x 0I
k-8
V
E
SIx
図 1 ベクトル図
k-9
+
N S
図 1
-
I〔A〕
T〔N・m〕
-
2 0
(4) 拘束試験では、回転子を拘束し、一次巻線に定格周波数の定格電流 (In)を流し、一次側における電圧〔V〕、電流〔A〕及び電力 P s〔W〕を測定する。なお、負荷 ( 図 2における a-b間 )の短絡は 0〔X〕であり、励磁回路の電流は微少より省略すると、電力 P sは銅損〔W〕となる。
r rI
Px x
I
Vr r
3 3n
s
n
n1 2 2 1 2
2
1 22X X+ = + = - +l l le ]o g] ]g g、
(5) 励磁回路 (g 0〔S〕、b 0〔S〕)は無負荷試験により、一次二次の合成リアクタンスと二次抵抗は拘束
試験により求められる。
問 4 答 (3)解説
1本の導体の誘導起電力は、 Ve bly= ] gであり、Emを最大値とすると瞬時値は sine t E tm ~=] g と表される。
問題文より、 fv 2x= であり、磁束密度の最大値が Bmであるから、
E fB l2m mx= …① …(ア )
1極の磁束密度の平均値を B〔T〕とすると、 TB B2 mr
= ] gとなる。 …(イ )x lで面積を表すことから、1極の磁束 U〔Wb〕は、
B l2 mr
xU=
Bl2
mxrU
= …②
式①に式②を代入すると、
.
E fB l fll f
Ef f
2 22
2 22 22
m m
m
x xxr
r
r
UU
U U
= = =
= =
1相当たりの誘導起電力の実効値 E〔V〕は、コイルの巻数 Nを 2倍するので、
. .E f N f N2 22 2 4 44#U U= = …③ …(ウ )
式③に巻き方による損失分の巻線係数k k0 1w w1 E] gをかけると、 …(エ )
.E k f N4 44 w U=
問 5 答 (4)解説
端子電圧を V・
、電機子電流を I・
、電動機の逆起電力を E・
とし、
基準ベクトルを V・
としたベクトル図を描くと、図 1となる。ベクトル図より、1相の誘導起電力 E
・
の大きさは、
VE V Ix 200 10 8 215S2 2 2 2# ]= + = +] ]g g ] g
k-7
1I
1r 2r
一次巻線 二次巻線
c2p 負荷 一次
銅損
鉄 損 二次
銅損
2I
mP
2P 21 r
ss −
c1p
0g 0b
0wI
0lI
a
b
図 2 一相等価回路
Y
1x 2x 0I
k-8
V
E
SIx
図 1 ベクトル図
k-9
+
N S
図 1
-
I〔A〕
T〔N・m〕
-
2 1
k-7
1I
1r 2r
一次巻線 二次巻線
c2p 負荷 一次
銅損
鉄 損 二次
銅損
2I
mP
2P 21 r
ss −
c1p
0g 0b
0wI
0lI
a
b
図 2 一相等価回路
Y
1x 2x 0I
k-8
V
E
SIx
図 1 ベクトル図
k-9
+
N S
図 1
-
I〔A〕
T〔N・m〕
k-10
-
S N
図 2
+
I〔A〕
T〔N・m〕
k-11
運転速度 回転速度
交点 C
曲線 A(負荷トルク)
曲線 B(電動機トルク)
0
トルク
図 1 安定運転
k-12
最大トルク
回転速度
安定運転
始動トルク
トルク
T
P P
R1 R2
C C
負荷トルク
図 2 トルクの比例推移
問 6 答 (5)解説
交流整流子モータは、図 1、図 2に示すように直流直巻電動機に類似した構造で、加える直流電圧の極性を逆にしても、磁束 (N-S極 )と電機子電流の向きが共に(ア)逆になる。また、フレミングの左手の法則より、トルクの向き (回転方向 )は変わらない。
交流整流子モータの特徴は、始動トルクが(イ)大きく 、回転速度が(ウ)高速 である。
補償巻線を設けない小容量のものは、交流と直流に使用でき、(エ)ユニバーサルモータ と呼ばれている。
問 7 答 (4)解説
(1) 図 1において、電動機トルク>負荷トルクのときは回転が加速し、負荷トルク>電動機トルクの
ときは回転が減速する。よって、負荷トルク=電
動機トルクで、交点 Cで安定運転ができる。
(2) 図 2において、二次抵抗を大きくすると、グラフは左方向にシフトし、始動トルクが大きくなる。
P点は最大トルクである。この電動機に回転速度
の上昇とともにトルクが増える負荷を接続する
と、両曲線の交点が安定運転の動作点 (C点 )と
なる。
(3) 図 1において、回転速度の上昇とともに電動機トルクが減少し、送風機 (負荷 )トルクは、回転
数の上昇とともにトルクが上昇する。したがって、
交点 Cで安定運転となる。
(4) 定格運転は、図 3に示すように交点が Aと Bの 2点あるが、A点は加速と減速時に通過し、B
点も加速と減速時に通過するので、動作点は変わらない。
(5) 図 2より、安定に送風機 (負荷 )を駆動できる。
k-10
-
S N
図 2
+
I〔A〕
T〔N・m〕
k-11
運転速度 回転速度
交点 C
曲線 A(負荷トルク)
曲線 B(電動機トルク)
0
トルク
図 1 安定運転
k-12
最大トルク
回転速度
安定運転
始動トルク
トルク
T
P P
R1 R2
C C
負荷トルク
図 2 トルクの比例推移
k-10
-
S N
図 2
+
I〔A〕
T〔N・m〕
k-11
運転速度 回転速度
交点 C
曲線 A(負荷トルク)
曲線 B(電動機トルク)
0
トルク
図 1 安定運転
k-12
最大トルク
回転速度
安定運転
始動トルク
トルク
T
P P
R1 R2
C C
負荷トルク
図 2 トルクの比例推移
k-13
図 3 トルクの比例推移
最大トルク(停動トルク)
定トルク
同期 定格運転 の安定点
始動後の 安定点
負荷
速度 始動 トルク
A B
トルク
1 0 滑り
k-14
0
E
-E
0t 0 2
Tt +
0t T+ t
図 1
k-15
2
2E
0 0t
0 2Tt + 0
t T+ t
図 2
図 3 定格運転
-
2 2
問 8 答 (2)解説
(1) 変圧器の巻線には軟銅線が用いられ、鉄心に絶縁を施し、その上に巻線を直接巻く内鉄形と、
円筒巻線や板状巻線を鉄心にはめ込む外鉄形がある。
(2) 変圧器の鉄心には、飽和磁束密度と比透磁率の大きい電磁鋼板が用いられる。この鋼板は、ヒステリシス損を低減するためにケイ素が数〔%〕含有され、さらに渦電流損を低減するために、積層鉄心が用いられたり、表面が絶縁被膜で覆われたりしている。
(3) 変圧器の冷却方法には、絶縁油を用いた油入式、空気による乾式、六フッ化硫黄を用いたガス
冷却式がある。
(4) 変圧器油は、巻線の絶縁耐力向上と温度上昇を防ぐために用いられ、化学的に安定で、引火点
が高く、流動性に富み比熱の大きな性質をもったものが必要である。
(5) コンサベータは、変圧器本体の外に設けたタンクで、油が空気に触れず、油の膨張・収縮を吸
収する。ブリーザ (吸湿呼吸器 )は、大気中の湿気をシリカゲル (乾燥材 )で除去する。
問 9 答 (2)解説
一次、二次、三次側の電圧を V 1、V 2、V 3〔V〕、一次・二次間の巻数比を a 1、二次・三次間の巻数比
を a 2及び二次負荷と三次負荷の皮相電力を S 2、S 3〔kV・A〕とする。
二次巻線における三相誘導性負荷の電流を IL2〔A〕とすると、 kV AS 8 0002 $= ] gより、
.A
S V I
IV
S
3 8 000 10
3 3 6 6 10
8 000 10700
L
L
2 2 23
22
2
3
3
#
# #
#` ]
= =
= = ] gIL2は遅れ電流であり、力率 0.8より、
. . AI j j700 0 8 0 6 560 420L2 = - = -o ] g ] g二次電流 I
・
L2を一次電流に換算したものを I・
L1とすると、.
aVV
II
6 6 10
66 10101
2
1
1
2
3
3
#
#= = = = より、
AIaI
jj
110
560 42056 42L L1
12= =
-= -o o ] g
また、三次巻線における進相コンデンサの電流を I C3〔A〕とすると、 V AkS 4 8003 $= ] gより、
.A
S V I
IV
S
3 4 800 10
3 3 3 3 10
4 800 10840
C
C
3 3 33
33
3
3
3
#
# #
#` ]
= =
= = ] gI C3は 90°進み電流より、
AI j j840 0 840C3 = + =o ] g ] g三次電流 I
・
C3 を二次電流に換算したものを I・
C2 とすると、..
aVV
II
3 3 106 6 10
223
2
2
3
3
3
##
= = = = より、
-
2 3
AIaI
jj
12840
420C C22
3= = =o o ] gさらに、二次電流 I
・
C2 を一次電流に換算したものを I・
C1 とすると、
AIaI
jj
110420
42C C11
2= = =o o ] gよって、求める一次電流 I
・
1〔A〕は、
AI I I j j56 42 42 56L C1 1 1= + = - + =o o o ] g問 10 答 (2)
解説
(2) パワーMOSFETは電圧駆動形であり、キャリア蓄積効果があることからスイッチング損失が大きい。
問 11 答 (3)解説
慣性モーメントを I〔kg・m2〕とする。
回転数 1 500〔min-1〕時の角速度を ~1〔rad/s〕とすると、このときの回転体のエネルギー
E 1〔kJ= kW・s〕は、
J J. kE I21
21
50 260
1 500616 225 616 21 12
2
# # ]~ r= = =d n ] ]g g回転数 1 000〔min-1〕時の角速度を ~2〔rad/s〕とすると、このときの回転体のエネルギー
E 2〔kJ= kW・s〕は、
J J. kE I21
21
50 260
1 000273 878 273 92 22
2
# # ] ]~ r= = d n ] ]g gエネルギー E 1から 2秒間で E 2に変化するので、その間に放出した平均出力 P〔kW〕は、
. . kWP E E2 2
616 2 273 9171
1 2]=
-=
- ] g
問 12 答 (3)解説
光速を F〔lm〕、平均照度を E〔lx〕、照明率を U、保守率をM、床面積を A〔m2〕、光源数を N〔個〕と
すると、
. ..
EA
FNMU
NFMUEA
2 400 0 7 0 6500 15 10
74 4# ## #
` ]
=
= =
よって、75台となる。
-
2 4
問 13 答 (2)解説
電気系と熱系の対応表は下記となる。
電気系の量 熱系の量
電圧 V〔V〕 (ア)温度差 i 〔K〕電気量 Q〔C〕 熱量 Q〔J〕
電流 I〔A〕 (イ)熱流 U 〔W〕導電率 v〔S/m〕 熱伝導率 m 〔W/(m・K)〕
電気抵抗 R〔X〕 熱抵抗 RT(ウ)熱流〔K/W〕静電容量 C〔F〕 熱容量 C(エ)〔J/K〕
問 14 答 (5)解説
真理値表において、出力信号Xが 1の箇所をAND(論理積 )になるようにA、B、Cを組み合わせると、
A BX C X C X C
X C
A B B A
A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $= = = = = = = = =
= $B X1 1 1 1$ $ $= = =A B C 1 1 1 1$ $ $ $= =
この 5つを OR(論理和 )にすればよいので、
B A B
XA C A C C C CB B A A B$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
= + + + +式① 式② 式③ 式④ 式⑤
式①と③より、 B A B B B BA C C C A A C C1$ $ $ $ $ $ $ $ $+ = + = =_ i
式②と⑤より、A B C A B C B C A A B C B C1$ $ $ $ $ $ $ $ $+ = + = =_ i
式④と⑤より、 B C A B C A B C C A B A BA 1$ $ $ $ $ $ $ $ $+ = + = =_ i
以上より、
B BX C B C A B A B C B A B C$ $ $ $ $ $= + + = + + = +_ i
問 15 答 (a)…(4)、(b)…(1)解説
(a) 定格出力を Po〔kW〕、滑りを sとすると、二次入力 (同期ワット )P2〔kW〕は、
.
kW
P s P
Ps
P
1
1 1 0 0245
46
o
o
2
2` ]
= -
=-
=-
] g
] g(b) 定格周波数 Hzf 60= ] g運転時の同期速度を N1〔min-1〕とすると、極数p 4= より、 minN
pf120
4120 60
1 800 11#
= = = -] gこのときの同期角速度を ~1〔rad/s〕とすると、
rad/sN260
260
1 800601
1~ r r r= = = ] g
-
2 5
よって、60〔Hz〕運転時の二次入力 P2〔kW〕は、60〔Hz〕運転時及び 50〔Hz〕運転時の同一出力トル
クを T〔N・m〕とすると、
P T T602 1~ r= = …①
次に、周波数 Hzf 50=l ] g運転時の同期速度を N2〔min-1〕とすると、 minN
pf120
4120 50
1 500 12#
= = = -l ] g
このときの同期角速度を ~2〔rad/s〕とすると、
rad/sN260
260
1 500502
2~ r r r= = = ] g
よって、50〔Hz〕運転時の二次入力 P'2〔kW〕は、
P T T502 2~ r= =l …②
式①よりT P60
2
r= を式②に代入すると、
P P60
5060
5046
22
# #rrr
r= =l
したがって、滑り s'=0.05時の誘導電動機の出力 P'o〔kW〕は、
. kWP s P1 1 0 05 506046
36o 2 # # ]rr
= - = -l l l] ]g g ] g問 16 答 (a)…(4)、(b)…(1)解説
(a) 方形波出力電圧の実効値 V〔V〕は、直流電圧 E〔V〕を
2乗し、図 2に表す 1周期 T (t 0~ t 0+T )の面積 E 2Tを幅 Tで割った平方根となるので、
VV E ETT
2
= = ] gなお、方形波の実効値は、最大値と同じである。
(b) 問題図 1は電圧形インバータで、負荷電流 i0は (ア )、直流電流 idは (エ )である。
なお、各電流の流れは、下記図 4と図 5(a)~ (d)となる。
k-13
図 3 トルクの比例推移
最大トルク(停動トルク)
定トルク
同期 定格運転 の安定点
始動後の 安定点
負荷
速度 始動 トルク
A B
トルク
1 0 滑り
k-14
0
E
-E
0t 0 2
Tt +
0t T+ t
図 1
k-15
2
2E
0 0t
0 2Tt + 0
t T+ t
図 2
k’-1
fr〔Ω〕
fI〔A〕 a 1I =〔A〕
0E = 〔V〕 G
図 2 拘束試験
3V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
固定
k’-2
2
2E
0 0t
0 2Tt + 0
t T+ t
図 2
2E T
k’-3
ゲイン〔dB〕
40
0
100
1 2 20 200
真数
角周波数〔rad/s〕
20− 〔dB/dec〕
図 1 ボード線図
k-16
S1、S4の オンオフ信号
S2、S3の オンオフ信号
オン
オフ
オン
オフ
時間
時間
(ア)
(エ)
時間
時間
2/T 2/T
0i
di
図 3
k-17
0i
0 t
1t 2t 3t 4t
図 4
0i
(負荷電圧)
k-16
S1、S4の オンオフ信号
S2、S3の オンオフ信号
オン
オフ
オン
オフ
時間
時間
(ア)
(エ)
時間
時間
2/T 2/T
0i
di
図 3
k-17
0i
0 t
1t 2t 3t 4t
図 4
0i
(負荷電圧)
-
2 6
k’-1
fr〔Ω〕
fI〔A〕 a 1I =〔A〕
0E = 〔V〕 G
図 2 拘束試験
3V = 〔V〕 a 3r = 〔Ω〕
固定
k’-2
2
2E
0 0t
0 2Tt + 0
t T+ t
図 2
2E T
k’-3
ゲイン〔dB〕
40
0
100
1 2 20 200
真数
角周波数〔rad/s〕
20− 〔dB/dec〕
図 1 ボード線図
問 17 答 (a)…(5)、(b)…(4)解説
(a) 図 1のボード線図から一次遅れであるため、周波数伝達関数の一般式W ( j~)は、kを比例定数、時定数を T〔s〕とすると、
W jj Tk
1~
~=
+] g
なお、CR回路の場合 sT CR= ] g、LR回路の場合TRL
= となる。
40〔dB〕の真数を V1とすると、
dBlog V20 4010 1 = ] g両辺を 20で割ると、
log
log log
V
V
V
2
10
100
10 1
10 1 102
1`
=
=
=
同様に 0〔dB〕の真数 V 2はV 02 = となる。
W (j~)のゲイン g〔dB〕は、
log log
log log log log
gT
kk T
k T k T
201
20 1
20 20 1 20 10 1
102 2
102
21
10 102
21
10 102
~~
~ ~
=+
= +
= + + = - +
-
-
]
]
]
]
g
g
g
g
8 B"
"
",
,
,
k-18
S3
S4
S1
S2
図 5(a) t 1間
E
i
負荷
ON OFF
ON OFF
k-19
S1 S3
S4 S2
図 5(b) t 2間
E
i
負荷
ON
ON OFF
OFF
k-18
S3
S4
S1
S2
図 5(a) t 1間
E
i
負荷
ON OFF
ON OFF
k-19
S1 S3
S4 S2
図 5(b) t 2間
E
i
負荷
ON
ON OFF
OFF
k-20
S3
S4
S1
S2
図 5(c) t 3間
E
i
負荷
k-21
S3
S4
S1
S2
図 5(d) t 4間
E
i
負荷
k-20
S3
S4
S1
S2
図 5(c) t 3間
E
i
負荷
k-21
S3
S4
S1
S2
図 5(d) t 4間
E
i
負荷
-
2 7
図 1のグラフにおいて、 rad/s0~= ] gのとき 40〔dB〕であるから、比例定数 kは、
log log
log log
log
log
g k T
k
k
k
k
20 10 1 0 40
20 10 1 40
20 40
2
100
10 102
10 10
10
10
#
`
= - + =
- =
=
=
=
] g" ,
図 1のグラフにおいて、 rad/s200~= ] gでは 0〔dB〕なので、 log logg k T20 10 1 010 10 2~= - + =] g" ,
T1 2% ~] g より、 T T1 2 2]~ ~+] ]g g とすると、時定数 T〔s〕は、
.
log log
log log
log
T
T
T
T
T
20 100 10 0
20 100 10
20
100
100200100
0 5
10 102
10 102
10
`
~
~
~
~
~
- =
=
=
=
= = =
]
]
g
g
よって、周波数伝達関数W ( j~)は、
.
W jj Tk
j1 1 0 5100
~~ ~
=+
=+
] g
(b) フィードバックの周波数伝達関数の一般式W ( j~)は、伝達関数を G ( j~)、フィードバック関
数を H( j~)、比例定数を kとすると、
W j kG j H jG j
1~
~ ~~
=+
]]
]
]g
g
g
g
選択肢 (1)のブロック線図から表した周波数伝達関数W 1( j~)は、
W j
j
jj
401
11
1
140
1 ##
~
~
~~
=+
=+
] g
選択肢 (2)のブロック線図から表した周波数伝達関数W 2( j~)は、
W j
j
jj
1001
11
1
1100
2
#~
~
~~
=+
=+
] g
選択肢 (3)のブロック線図から表した周波数伝達関数W 3( j~)は、
.
..
W j
j
jj
1001
0 0051
1
0 0051
1 0 005100
3
#~
~
~~
=+
=+
] g
-
2 8
選択肢 (4)のブロック線図から表した周波数伝達関数W 4( j~)は、
.
W j
j
jj j
2001
12
1
2200
1 0 5100
4
#~
~
~~ ~
=+
=+
=+
] g
選択肢 (5)のブロック線図から表した周波数伝達関数W 5( j~)は、
.
.W j
j
jj j
2001
10 5
1
0 5200
1 2400
5
#~
~
~~ ~
=+
=+
=+
] g
よって、解答は (4)となる。
問 18 答 (a)…(5)、(b)…(3)解説
(a) フローチャートの判断記号 ( ア ) a[ i ] < a[ j ]において、YESでは配列の中を入れ替える。NOではなにもせず、jに 1を加算するところに進む。変数mは、置き変えの一次場所とする。
( イ ) a[ i ] ← a[ j ]及び ( ウ ) a[ j ] ← mを繰り返すことで、下記の処理を行う。配列 a[1]を基準に、a[2]~ a[5]と比較し、その最大値を a[1]に格納する。
配列 a[2]を基準に、a[3]~ a[5]と比較し、その最大値を a[2]に格納する。
配列 a[3]を基準に、a[4]~ a[5]と比較し、その最大値を a[3]に格納する。
配列 a[4]を基準に、a[5]と比較し、その最大値を a[4]に格納する。
(b) このフローチャートは、最大値決定法で、以下の手順で進められる。
n= 5であるから、以下の 5つの配列となる。
配列名 a3 1 2 5 4
a[1] a[2] a[3] a[4] a[5]
i=1~ n- 1、j=j+1~ nまで
① i=1、j=i+1=2で、a[i=1]と a[j=2]を比較して、a[1]=3< a[2]=1は正しくないため、
入れ替えは起こらない。
i=1、j=j+1=3とし、a[1]=3< a[3]=2は正しくないため、再び入れ替えは起こらない。
i=1、j=j+1=4とし、a[1]=3< a[4]=5より、入れ替えが起こる (Xを 1回通過 )。
5 1 2 3 4
i=1、j=j+1=5とし、a[1]=5< a[5]=4は正しくないため、入れ替えは起こらない。
② i=i+1=2、j=i+1=3で、a[i=2]と a[j=3]を比較して、a[2]=1< a[3]=2より、入れ替え
が起こる (Xを 2回通過 )。
5 2 1 3 4
-
2 9
i=2、j=j+1=4で、a[2]=2< a[4]=3より、入れ替えが起こる (Xを 3回通過 )。
5 3 1 2 4
i=2、j=j+1=5で、a[2]=3< a[5]=4より、入れ替えが起こる (Xを 4回通過 )。
5 4 1 2 3
③ i=i+1=3、j=j+1=4で、a[3]=1< a[4]=2より、入れ替えが起こる (Xを 5回通過 )。
5 4 2 1 3
i=3、j=j+1=5で、a[3]=2< a[5]=3より、入れ替えが起こる (Xを 6回通過 )。
5 4 3 1 2
④ i=i+1=4、j=j+1=5で、a[4]=1< a[5]=2より、入れ替えが起こる (Xを 7回通過 )。
5 4 3 2 1
i=n- 1=4で終了し、配列内が降順に並べ替えられる。
結果、Xの箇所を 7回通過する。
-
3 0
法 規
問 1 答 (4)解説
電気事業法第 43条「主任技術者」及び電気事業法施行規則第 56条「免状の種類による監督の範囲」の
規定に関する問題である。
a) 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の(ア)監督 の職務を誠実に行わなければならない。
b) 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に(イ)従事 する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
c) 第 3種電気主任技術者免状の交付を受けている者が保安について(ア)監督 をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、一部の水力設備、火力設備等を除き、電圧
(ウ)5 万〔V〕未満の事業用電気工作物 (出力(エ)5 000〔kW〕以上の発電所を除く。)とする。
問 2 答 (4)解説
電気関係報告規則第 3条「事故報告」の規定に関する問題である。
a) 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことに
より人が死傷した事故 (死亡又は病院若しくは診療所(ア)に入院 した場合に限る。)が発生したときは、報告をしなければならない。
b) 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、
(イ)他の物件 に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは、報告をしなければならない。
c) 上記 a)又は b)の報告は、事故の発生を知ったときから(ウ)24 時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して 30日以内に報告書を提出
して行わなければならない。
問 3 答 (5)解説
電気設備技術基準第 5条「電路の絶縁」及び電気設備技術基準の解釈第 15条 (省令第 5条第 2項 )「高
圧又は特別高圧の電路の絶縁性能」の規定に関する問題である。
a) 電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見
される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生し
た際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
電路と大地との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、(ア)絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
解 答 令和 2年度
-
3 1
b) 電路は、絶縁できないことがやむを得ない部分及び機械器具等の電路を除き、次の①及び②のい
ずれかに適合する絶縁性能を有すること。
① (イ)10 350〔V〕の交流試験電圧を電路と大地 (多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間 )との間に連続して 10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
② 電線にケーブルを使用する電路においては、(イ)10 350〔V〕の交流試験電圧の(ウ)2 倍の直流電圧を電路と大地 (多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間 )との間に連
続して 10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
問 4 答 (1)解説
電気設備技術基準第 27条「架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止」の規
定に関する問題である。
a) 特別高圧の架空電線路は、(ア)電磁 誘導作用により弱電流電線路 (電力保安通信設備を除く。)
を通じて(イ)人体 に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
b) 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、(ウ)静電 誘導作用により人による感知の
おそれがないよう、地表上 1〔m〕における電界強度が(エ)3〔kV/m〕以下になるように施設しな
ければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場合において、(イ)人体 に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
問 5 答 (2)解説
電気設備技術基準の解釈第 120条 (省令第 21条第 2項、第 47条 )「地中電線路の施設」の規定に関す
る問題である。
(2) 高圧地中電線路を公道の下に管路式により施設する際、地中電線路の物件の名称、管理者名及
び許容電流を 2〔m〕の間隔で表示した。
上記の文章の下線部に誤りがあり、「許容電流」ではなく、「電圧」が正しい。
問 6 答 (1)解説
電気設備技術基準の解釈第 156条 (省令第 56条第 1項 )「低圧屋内配線の施設場所による工事の種類」
の規定に関する問題である。
低圧屋内配線は、次の表に規定する工事のいずれかにより施設すること。ただし、ショウウィンドー
又はショウケース内、粉じんの多い場所、可燃性ガス等の存在する場所、危険物等の存在する場所及
び火薬庫内に低圧屋内配線を施設する場合を除く。
-
3 2
問 7 答 (3)解説
電気設備技術基準第 1条「用語の定義」及び電気設備技術基準の解釈第 1条 (省令第 1条 )「用語の定
義」の規定に関する問題である。
a) 引込線とは、(ア)架空引込線 及び需要場所の造営物の側面等に施設する電線であって、当該需
要場所の(イ)引込口 に至るもの
b) (ア)架空引込線 とは、架空電線路の支持物から(ウ)他の支持物 を経ずに需要場所の
(エ)取付け点 に至る架空電線
c) (オ)連接引込線 とは、引込線のうち一需要場所の引込線から分岐して、支持物を経ないで他の
需要場所の(イ)引込口 に至る部分の電線
問 8 答 (1)解説
電気設備技術基準の解釈第189条「遊戯用電車の施設」及び198条「電気浴器等の施設」第199条の2「電
気自動車等から電気を供給するための設備等の施設」の規定に関する問題である。
a) 遊戯用電車 (遊園地の構内等において遊戯用のために施設するものであって、人や物を別の場所
図h-1
(ア)金属線ぴ
(イ)金属ダクト
(ウ)バスダクト
-
3 3
へ運送することを主な目的としないものをいう。)に電気を供給するために使用する変圧器は、絶
縁変圧器であるとともに、その 1次側の使用電圧は(ア)300〔V〕以下であること。b) 電気浴器の電源は、電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置内蔵されている電源変圧
器の 2次側電路の使用電圧が(イ)10〔V〕以下のものに限る。)であること。c) 電気自動車等 (カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被
牽引自動車を除く。)から供給設備 (電力変換装置、保護装置等の電気自動車等から電気を供給す
る際に必要な設備を収めた筐体等をいう。)を介して、一般用電気工作物に電気を供給する場合、
当該電気自動車等の出力は、(ウ)10〔kW〕未満であること。
問 9 答 (5)解説
電気設備技術基準の解釈第 150条「配線器具の施設」の規定に関する問題である。
低圧用の配線器具は、次により施設すること。
a) (ア)充電部分が露出しない ように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
b) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。
c) 配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅
ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に(イ)張力 が加わらないようにすること。
d) 屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器その他の器具は、(ウ)損傷を受けるおそれがある場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと。
問 10 答 (5)解説
電気設備技術基準の解釈第 227条「低圧連系時の系統連系用保護装置」の規定に関する問題である。
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合には、次により、異常時に分散型電源を自動的に解列す
るための装置を施設すること。
a) 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
① 分散型電源の異常又は故障
② 連系している電力系統の(ア)短絡事故又は地絡事故③ 分散型電源の単独運転
b) (イ)一般送配電事業者 が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
c) 「逆変換装置を用いて連系する場合」において、「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は、次によ
ること。
表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。
-
3 4
検出する異常 保護リレー等の種類
発電電圧異常上昇 過電圧リレー
発電電圧異常低下 不足電圧リレー
系統側短絡事故 不足電圧リレー
系統側地絡事故 (ウ)地絡過電圧 リレー
単独運転
周波数上昇リレー
周波数低下リレー
転送遮断装置又は単独運転検出装置
問 11 答 (a)…(5)、(b)…(4)解説
(a)
① 電気事業法第 39条 (事業用電気工作物の維持 )において、事業用電気工作物の損壊により
(ア)一般送配電事業 者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。
② 「電気関係報告規則」において、(イ)自家用電気工作物 を設置する者は、(ア)一般送配電事業 の
用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧(ウ)3 000〔V〕以上の(イ)自家用電気工作物
の破損又は(イ)自家用電気工作物 の誤操作若しくは(イ)自家用電気工作物 を操作しないことによ
り(ア)一般送配電事業 者に供給支障を発生させた場合、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。
③ 図 1に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。事故点 1、事故点 2又は事故点 3のいずれかで短絡等により高圧配電系統に供給支障が発した場合、②の報告の対象となるのは
(エ)事故点 2 又は事故点 3 である。
図h-2
図1 高圧配電系統図(概略図)
-
3 5
(b)
① 受電設備を含む配電系統において、過負荷又は短絡あるいは地絡が生じたとき、供給支障の拡大
を防ぐため、事故点直近上位の遮断器のみが動作し、他の遮断器は動作しないとき、これらの遮断
器の間では(ア)保護協調 がとられているという。② 図 2は、図 1の高圧需要家の事故点 2又は事故点 3で短絡が発生した場合の過電流と遮断器 (遮断器A及び遮断器 B)の継電器動作時間の関係を示したものである。(ア)保護協調 がとられてい
る場合、遮断器 Bの継電器動作特性曲線は、(イ)曲線 2 である。③ 図 3は、図 1の高圧需要家の事故点 2で地絡が発生した場合の零相電流と遮断器 (遮断器A及び遮断器 B)の継電器動作時間の関係を示したものである。(ア)保護協調 がとられている場合、
遮断器 Bの継電器動作特性曲線は、(ウ)曲線 4 である。また、地絡の発生箇所が零相変流器より
負荷側か電源側かを判別するため(エ)地絡方向継電器の使用が推奨されている。
図h-3
図2 過電流継電器-連動遮断特性 図3 地絡継電器-連動遮断特性
-
3 6
問 12 答 (a)…(4)、(b)…(1)解説
電気設備技術基準の解釈第 15条「高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能」の規定に関する問題である。
(a)
変圧器の巻線の種類 試験電圧 試験方法
最大使用電圧が(ア)7 000〔V〕以下のもの
最大使用電圧の(イ)1.5倍の電圧 ((ウ)500〔V〕未満となる場合は(ウ)500〔V〕)
試験される巻線と他
の巻線、鉄心及び外
箱との間に試験電圧
を連続して 10分間
加える。最 大 使 用 電 圧 が
(ア)7 000〔V〕を超え、60 000〔V〕以下のもの
最 大 使 用 電 圧 が
15 000〔V〕以下のもの
であって、中性点接
地式電路 (中性点を
有するものであって、
その中性線に多重接
地するものに限る。)
に接続するもの
最大使用電圧の 0.92倍の電
圧
上記以外のもの最大使用電圧の(エ)1.25倍の電圧 (10 500〔V〕未満と
なる場合は 10 500〔V〕)
(b) 公称電圧 22 000〔V〕の最大使用電圧〔V〕は、
..
V22 0001 11 15
23 000# = ] g(a)の表より、求める試験電圧〔V〕は、
. V23 000 1 25 28 750# = ] g
問 13 答 (a)…(5)、(b)…(4)解説
(a) 基本波に対するインピーダンスは、題意より、下記の式となっている。
.Z j Z j Z j4 4 33 545S SR SC1 1 1X X X= = =-o o o] ] ]g g g、 、 第 5次高調波に対するインピーダンスは、周波数が基本波の 5 倍となることから、コイルは基本
波に対するインピーダンスの 5 倍、コンデンサは基本波に対するインピーダンスの 1/5 倍となる。
.Z j j
Z j j
Z j j
4 4 5 22
33 5 165
5545
109
S
SR
SC
5
5
5
#
#
X
X
X
= =
= =
=- =-
o
o
o
]]]
ggg
-
3 7
(b) 第 5次高調波の流出電流上限値は、契約電力 1〔kW〕当たり 3.5〔mA〕需要家の契約電力が 250
〔kW〕より、
. mA . AI 3 5 250 875 0 875S5 #= = =] ]g g第 5次高調波の等価回路より、
. . VV
Z Z Z j j j
22 0 875 19
165 109 56
25
SR SC5 5
#
X
= =
= + = - =o o o
]]
gg
したがって、IC5は、
. . AIZV
5619
0 34425
C5 ]= = ] g高調波発生機器から発生する第 5次高調波電流 I 5の上限値の値〔A〕は、
. . . . AI I I 0 875 0 344 1 21 1 29S C5 5 5 ]= + = + = ] g図h’-1
高調波発生機器
5 AI〔 〕
S5 0.875 AI = 〔 〕 C5 0.344 AI = 〔 〕
S5 22Z j= 〔 〕SR5 165Z j= 〔 〕
SC5 109Z j= − 〔 〕
図 第5次高調波の等価回路
56Z j= 〔 〕
VV〔 〕
図h-4
6.6 kV〔 〕