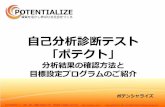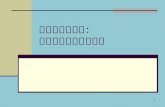資料 B 近年の費用対効果算出結果の分析から · - 1 - 資料b...
Transcript of 資料 B 近年の費用対効果算出結果の分析から · - 1 - 資料b...
- 1 -
資料 B 近年の費用対効果算出結果の分析から
2016/9/25
1.分析の目的
(1)分析対象データ
・林野庁における費用対効果評価は、平成 11 年度から検討され、平成 13 年度から事前評価が実施され公表されている。
・平成 20 年度から現行の事前評価個表、便益集計表の様式に統一されていることから、平成 20 年度から平成 27 年度までの事前評価データ
により分析を行う。
(2)分析の目的
・事前評価における便益項目の選択状況、費用対便益比の傾向について分析し、現行の費用便益分析の課題を検討する。
2.治山事業
(1)直轄治山事業
1)事業評価個表の例
表-1は、平成 23 年度に公開された、直轄治山事業の事前評価個表の例である。
- 7 -
A)事業分類別の便益選択の傾向と費用対便益比
①山腹工・渓間工
山地災害防止便益(被害の軽減額で評価)だけで、費用対便益比が 2.05。
水源涵養便益を全ての事業で選択しているが、便益は非常に小さい。
土砂流出防止便益(砂防ダムで代替的に評価)が 2.19。ほとんどが保全効果区域の便益。
②集水路・水路工
土砂流出防止便益・山地災害防止便益の割合が高い(土砂流出と山地災害防止はダブルカウントになるため、重要度が高い方の
便益で評価)。
森林土壌分の炭素固定便益を選択しているが、便益は非常に小さい。
③海岸林植栽
風害軽減便益(風害防止ネットで代替評価)のみで評価。
④調整伐
山地災害防止便益の費用対便益比の割合が高い。
水源涵養便益は選択されているが、便益は非常に小さい。
B)全体の傾向
・「山腹工・渓間工」、「治山ダム」等の治山事業の典型的施設工事では、水源涵養機能の便益評価が低くなる。
事業費に対して、水源涵養便益が相対的に小さい。
・水源涵養便益、山地保全便益の評価方法について
評価マニュアルにおける治山事業の水源涵養便益評価の考え方
- 8 -
水源涵養便益の事業対象区域の評価法は、森林整備事業と同じである(下記の洪水防止便益)。
森林整備における T 年:新植から T 年目に最大効果
治山事業においても同様に T 年を設定。。
治山事業の事業対象は、無林地に対する新規植栽
水源涵養便益、山地保全便益に関する現行評価式について、
治山事業における評価方法の検討が必要。
・治山事業の土砂崩壊防止便益では、事業完了後10年間は効果ゼロとして
いる。
これは、無林地に植栽した場合に10年目の機能が最低の状態としている
ことによる。
以上から治山事業の事業対象区域森林面積は、全て新規植栽としていると考
えられる。
・保全効果区域の評価について
事業実施箇所周辺の効果であり、評価最終年に効果最大となるとしているが、施設整備が完了すればすぐに効果が発現すると考える
こともできる。
- 14 -
・総じて費用対便益比が高い。
・国有林、民有林森林整備事業とも、水源涵養便益だけで費用対便益比が「1」以上となっている。
・土砂流出防止便益だけで費用対便益比が「1」以上となっている。
・環境保全便益のうち選択されている便益は、「炭素固定便益」が多く、「生物多様性便益」は 1 件であった。
・路網整備事業の便益のうち、費用対便益比が比較的高いのは木材生産等便益である。
木材生産等便益は、新たに林道・作業道が敷設されることにより、将来の素材生産量が確保されたり、生産経費が縮減される便益
一方、森林整備経費縮減便益は総じて費用対便益比は低い
一般交通便益も6件選択されているが、費用対便益比は極めて低い。
- 15 -
5.便益選択の傾向と分析方法に関する検討課題
(1)便益選択の傾向
・治山事業、森林整備事業とも選択される便益は少ない。
・治山事業の場合
直轄治山事業では水源涵養便益を選択している事業もあるが、1件当たりの事業費が大きく、反対に治山関連の森林整備面積が少な
いことから、水源涵養便益の費用対便益比が非常に小さい。
海岸林整備事業では、効果の発現に対応した便益が選択されている。
総じて、山地保全便益か災害防止便益のいずれかの便益だけで、費用対便益比は1以上となっている。
・森林整備事業の場合
水源涵養便益と山地保全便益で、費用対便益比は3以上となっており、事業評価としては十分な結果である。
炭素固定便益の費用対便益比も 0.4 程度と比較的高い割合を示している。木材生産確保便益も比較的高い。
事業評価では、森林整備と路網整備を合わせて評価している。
路網整備関連では、木材生産確保便益が比較的高い費用対便益比を示すが、他の便益は非常に小さい。
民有林森林整備事業では、一般交通便益、森林総合利用便益を選択している事業も見られるが、水源涵養と山地保全便益で1以上と
なるため、他の便益の選択の必要性がないと考えられる。
(2)評価分析方法に関する検討課題
①事業の種類によって、効果の発現度が高い便益が決まるので、その他の便益を選択する必要性が低い。
特に、環境保全便益、路網整備の経費縮減・交通関連便益等は選択されにくい傾向にある。
②路網整備関連の便益が低く、路網整備単独では費用対便益比を確保することが困難であると推定される。
特に民有林森林整備事業では困難。
- 16 -
③現行の事業評価では、森林整備と路網整備の両事業を加算して評価書を作成しているが、評価プログラムでは、別途に評価しており、
国有林、都道府県の事業評価集計作業に多大な負担となっている。
当初の費用効果分析では、治山事業、造林事業、林道事業の3事業別に分析手法を検討してきたが、森林整備事業として造林事業と
林道事業を統合し、次いで森林整備保全事業として治山事業も含めて3事業が統合化されるという経緯を経ている。
現行費用便益分析プログラムを使用した事前評価における費用集計表、便益集計表の整理過程は、下記のとおりである。
- 17 -
④森林整備と路網整備の一体評価による抜本的な評価手法の改正を検討する必要がある。
費用対効果評価が実施されて 17 年程度経過し、森林資源、森林山村等を取り巻く状況は大きく変化している。
・放置森林の増加
平成の市町村合併以後の廃村集落・・中心部への人口流出、
森林山村の高齢化
・森林相続の大量発生
森林山村の団塊世代(昭和 15 年前後、昭和 22 年~25 年)の高齢化
・伐期に達した森林資源量の増加
若返りの推進が森林整備保全事業の当面の課題
以上の変化状況は、今後の森林整備の促進に大きな影響を与えるものと考えられ、森林環境保全直接支援事業における低コスト林業の促
進施策等による対応策が実施されている。流域、団地等の資源集中域に対して森林整備と路網整備を一体とした事業の推進は、これらの施
策を推進する上において重要な施策である。
森林整備と路網整備の一体的事業推進における事業評価の考え方は例えば下記のようなものと考えられる。
・路網整備の効果は、個々の路網効果の積み上げ以上の効果を上げる。
例えば、作業者の配分移動が容易になるため作業効率が向上する。
路網密度が高くなることの効果・・・・・帰着点:整備対象面積の増加、木材生産確保面積の増加
・一般交通便益についても、個々の林道の交通便益では評価しない。
基幹的林道と林道の地域内ネットワーク効果・・・・帰着点:森林空間総合利用自動車台数の増加、交通便益の増加
・水源涵養、山地保全便益についても個々の森林ではなく、路網密度の高低と整備率の関係から便益を評価する。
このように一体的評価は、個別林分の効果評価の積み上げ方式から地域全体の効果評価へと変更することになり、そのためには、評価の
考え方・手法を明確にした上で評価システムを検討する必要があると考えられる。